非公開の医師求人情報を
ご紹介いたします!
マイナビDOCTORでは、医師専任のキャリアパートナーが
あなたの転職活動をサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。

世界の医療ニュースの中から、厳選した記事をギュッと凝縮して紹介します。
1日数本を1分で、サクッと読むことができます。日々の情報収集、話のネタ探しにお役立てください。

お酒の飲み過ぎは、記憶力や思考力の低下につながる可能性があるそうです。ブラジルの研究チームが、死亡時に平均75歳だった高齢者1781人について脳の病理解剖を実施し、研究成果を科学誌Neurologyに発表しました。
チームは、「お酒1杯」の基準をビール350mlまたはワイン150ml程度と定義し、飲酒をしない965人、中程度の飲酒(週に7杯以下)の319人、大量飲酒(週に8杯以上)の129人、過去に大量飲酒をしていた368人を比較しました。
その結果、脳損傷の兆候で血管の壁が硬く厚くなる「硝子(しょうし)様細動脈硬化」の発生リスクが、飲酒をしない人に比べて▽大量飲酒の人は133%▽中程度の飲酒の人は60%▽過去に大量飲酒をしていた人は89%――高くなることが明らかになったそうです。
さらに、アルツハイマー病に関連するとされる「タウタンパク質のもつれ」が発生するリスクについても、飲酒しない人に比べて大量飲酒の人は41%高く、過去に大量飲酒をしていた人は31%高かったといいます。また、過去に大量飲酒をしていた人は、脳の質量が体重と比較して少なく、認知能力も低かったとのことです。

肉や魚、乳製品などの動物性食品を一切食べない「ヴィーガン食」を長年続けると、たとえ必要な量のタンパク質を摂取していたとしても、必須アミノ酸の「リシン」と「ロイシン」が不足する可能性があるそうです。ニュージーランドの研究チームが学術誌PLOS Oneに研究成果を発表しました。
タンパク質は20種類のアミノ酸の組み合わせでできており、そのうち9種類は体内で合成することができない必須アミノ酸です。
チームは、長期にわたりヴィーガン食を続けている健康な成人193人が付けた4日間の食事記録を詳しく分析しました。参加者のうち4分の3が、1日に必要なタンパク質の摂取量を満たしていたといいます。必須アミノ酸の摂取量についても、個々の体重に応じた必要量を超えていました。
しかし、実際に体内に吸収されるアミノ酸消化率を考慮したところ、リシンとロイシンの摂取基準を満たしたのは参加者のわずか50%でした。一般的に植物性タンパク質は、動物性タンパク質に比べて消化吸収される必須アミノ酸の量が少ないためです。
チームは、必須アミノ酸の長期的な不足は、筋肉の維持やその他の生理機能に悪影響を及ぼす可能性があると指摘しています。

パソコンやスマートフォンなどのデジタル機器を最初に使い始めた世代が、認知症リスクが顕在化する年齢になり、デジタル技術の過剰使用が引き起こす「デジタル認知症」の懸念が高まっています。米国の研究チームが、こうしたデジタル技術による悪影響は本当に生じるのかを調査し、科学誌Nature Human Behaviourに論文を発表しました。
チームは、デジタル技術と認知機能に関する136個の研究から50歳以上の成人41万1430人のデータを分析しました。その結果、デジタル技術の使用が、認知機能障害リスクを58%低下させることが明らかになったそうです。日々変化し続けるデジタル技術に適応しようとすることで、脳が鍛えられる可能性があるといいます。
また、デジタル技術によって家族や社会とつながる機会が大幅に増加することや、リマインダーやGPS(衛星利用測位システム)などの機能が高齢の人の自立した生活に役立つことが、認知症と診断されるリスクの低下につながるそうです。
チームは、中高年に対してデジタル技術の健全な使用を促すことが、認知症リスクの抑制に有益であるとしています。

会話やせきをした際に口から飛び散る飛沫(水滴)の大きさや速度は、個人間でばらつきがあるそうです。飛沫は感染症の伝染に関与するため、このばらつきが、他者に病原体を感染させやすい「スーパースプレッダー」が存在する一因の可能性があるといいます。
フランスなどの研究チームが、23人のボランティアについて、「話した時」「せきをした時」「普通に呼吸をした時」の飛沫の大きさと速度を調査しました。
その結果、話したりせきをしたりすると、2〜60μm(1μmは1000分の1mm)の水滴が形成されることが分かったそうです。通常の呼吸では、水滴のサイズは2〜8μmだったといいます。飛沫が排出される速度については、せきをした時が最も速かったといいます。
そして、飛沫の濃度もせきをした時が最も高いことが示されたとのことです。また、マスクを着用することで、74〜86%の飛沫飛散を防ぐことができることが明らかになったといいます。さらに、飛沫の大きさや速度には個人間で大きな差があることも分かったとのことです。
チームは研究成果を科学誌Physical Review Fluidsに発表しました。

新型コロナウイルスワクチンの接種は感染予防に有効であり、その結果として、感染後にさまざまな症状が長引く「コロナ後遺症」の発症リスクが低下することが明らかになりました。米国の研究チームが医学誌eClinicalMedicineに研究成果を発表しました。
チームは、新型コロナウイルスのデルタ株が流行していた2021年7~11月の記録から12~20歳の青年期の若者11万2590人のデータを分析しました。その結果、新型コロナワクチンの接種が、コロナ後遺症を予防するのに95.4%有効であることが示されたそうです。
また、オミクロン株が流行していた22年1~11月に登録された5~11歳の子ども18万8894人と12~20歳の青年期の若者8万4735人を対象に同様の分析を行ったところ、ワクチンによるコロナ後遺症予防効果はそれぞれ 60.2%と75.1%だったといいます。
ただし、さらに詳しい調査を行った結果、ワクチン接種者に新型コロナが感染すると、未接種者と同じくらいの割合でコロナ後遺症を発症することが分かったそうです。こうした結果から、コロナ後遺症のリスクを抑制するためには、ワクチン接種で感染しないようにすることが重要であることが示されました。

騒がしい環境の中で必要な情報を聞き取るのに苦労した時は、指でトントンとリズムを取るといいそうです。フランスの研究チームが、学術誌「英国王立協会紀要(Proceedings of the Royal Society B)」に研究成果を発表しました。
チームは、周囲に雑音がある状態で40個の文章を読み上げた音声を聞いてもらい、聞き取りの正確性とスピードを評価する実験を行いました。
録音を聞き始める前に、自分のペースまたは指定された拍子でトントンと指でリズムを取った場合▽拍子を刻む音を聞いた場合▽静かな環境でただ待っていた場合――を比べたそうです。
その結果、録音を聞き始める前に自分のペースまたは指定された拍子でトントンと指でリズムを取った場合に、音声をうまく聞き取れることが明らかになったといいます。リズミカルな運動刺激によって、騒音下における音声処理能力が向上する可能性が示されました。

皮膚の傷や湿疹が、食物アレルギーの発症リスクを高める可能性があるそうです。米国の研究チームが科学誌Science Immunologyに論文を発表しました。
チームは、マウスの皮膚に損傷を与えると同時に、卵白の主成分で鶏卵アレルギーの主要な原因物質(アレルゲン)である「オボアルブミン」を、栄養チューブを使って腸に直接投与したそうです。その結果、刺し傷や紫外線による炎症などさまざまなタイプの皮膚損傷が、オボアルブミンに対するアレルギーを誘発することが分かったそうです。
皮膚損傷から数時間以内にオボアルブミンを投与しなければ、アレルギーは誘発されなかったそうです。また、皮膚の傷口からアレルゲンが入り込むことでアレルギーが起こるのではなく、腸に直接オボアルブミンを投与されたマウスがアレルギーを発症することも明らかになったとのことです。
これらのことからチームは、皮膚と腸を仲介してアレルギーを引き起こす免疫細胞が存在するとみて、その正体を突き止める研究を進めているそうです。

トランプ米政権は18日、新型コロナウイルスの起源を中国・武漢のウイルス研究所から流出したとする説を強調するコンテンツを、ホワイトハウスのウェブサイト内に新たに公開しました。米国の各メディアが報じました。
米NBC Newsによると、これまでワクチンや検査、治療法など新型コロナ関連のさまざま情報を人々に提供してきた連邦政府のウェブサイト「Covid.gov」にアクセスすると、この新たなページにリダイレクトされます。
新たに公開されたコンテンツは、「LAB LEAK-THE TRUE ORIGINS OF Covid19(研究所からの流出 新型コロナの真の起源)」というタイトルで、主に2024年12月に発表された下院の報告書に基づいています。この報告書は共和党が主導する特別小委員会によって作成され、新型コロナについて「研究所または研究関連の事故が原因で発生した可能性が高い」と結論付けています。
「LAB LEAK」には、ウイルスが自然界にはない生物学的特徴を持っている▽武漢の研究所は安全性が不十分な状態で研究を行ってきた▽研究所の研究者が生鮮市場で新型コロナが発生する数カ月前に症状を呈していた――などの記載があり、流出説を強調しています。
NBC Newsなどは、多くの科学者は研究所からの流出説よりも、動物から人間への自然伝播説が有力であると考えていると報じています。

パーキンソン病に対する幹細胞を使った二つの臨床試験が実施され、それぞれ有望な結果が示されたようです。
パーキンソン病は、脳内の神経伝達物質「ドパミン」を産生する神経細胞が減少することにより、運動機能に障害が生じる神経変性疾患です。
京都大学などの研究チームが科学誌Natureに発表したのは、iPS細胞(人工多能性幹細胞)を使った研究成果です。チームは50~69歳のパーキンソン病患者7人に対し、 iPS細胞から誘導したドパミン神経前駆細胞を脳に移植しました。
24カ月にわたる追跡調査中、重篤な有害事象は認められなかったといいます。また、有効性を検証した6人中4人の運動症状が改善したとのことです。
米国の研究チームが行ったのはES細胞(胚性幹細胞)を用いた臨床試験です。チームは平均年齢67歳のパーキンソン病患者12人の脳に、ES細胞を用いたドパミン神経前駆細胞製品「ベムダネプロセル(bemdaneprocel)」を移植したそうです。
その結果、18カ月にわたる追跡期間中に重篤な有害事象が発生することはありませんでした。また、運動機能に改善がみられた患者もいたとのことです。
米国の研究チームも、この研究成果を科学誌Natureに発表しました。

世界保健機関(WHO)加盟国は、将来起こり得る感染症の世界的大流行(パンデミック)に備える「パンデミック条約」の条文案に合意しました。16日に最終合意に達し、5月のWHO総会で採択される見通しです。
パンデミック条約は、新型コロナウイルスの感染が拡大したことの教訓を踏まえ、感染症への対策を世界的に強化することを目的とした新たな国際ルールです。2022年から3年にわたり加盟国が協議を続けてきました。
条文案には、病原体の情報を共有すること、医薬品製造に関する技術や知識の途上国への移転、世界的な供給網の確立を目指すことなどが盛り込まれています。
また、病原体の情報を共有した国がワクチンや治療薬を入手できるよう保証する条項もあります。そして、パンデミック時にはWHOが医薬品の最大20%を確保し、発展途上国に分配するといいます。
ただ、ワクチン開発などで世界をリードする米国は、今回の協議に参加していません。今年1月にトランプ米大統領がWHOからの脱退を表明しており、AP通信によると、条約にも調印しないとみられています。
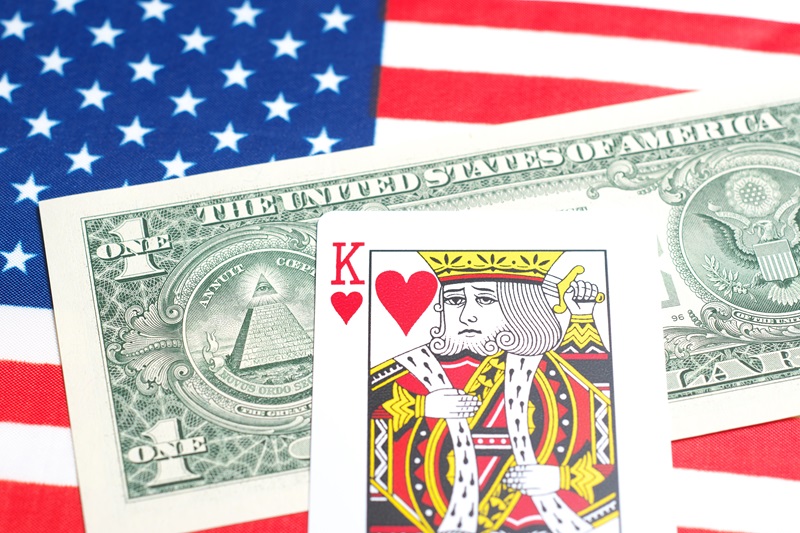
トランプ米政権は、公衆衛生関連の予算の3分の1を削減し、多数の医療プログラムを廃止するほか、研究機関を大幅に縮小する計画を進めているようです。米CNNが報じました。
CNNは、ホワイトハウスの予算担当官から保健福祉省(HHS)に送られた10日付けの暫定版文書を入手したそうです。文書によると、連邦政府の公衆衛生関連支出が年間数百億ドルも削減される可能性があるといいます。
また、複数の医療プログラムや組織が、「米国を再び健康にする」としてトランプ大統領とロバート・ケネディ・ジュニア厚生長官が新設を進めている「健康な米国のための管理機構(AHA)」に統合される予定だとのことです。
特に、疾病対策センター(CDC)は予算の40%以上を削減されることになり、多くの公衆衛生プログラムが完全に廃止されるそうです。CDCは、4月1日に発表された大規模な人員削減で、多くの職員が解雇されました。
国立衛生研究所(NIH)についても、予算を40%以上削減し、27個ある研究機関をわずか八つに減らすことが提案されているといいます。
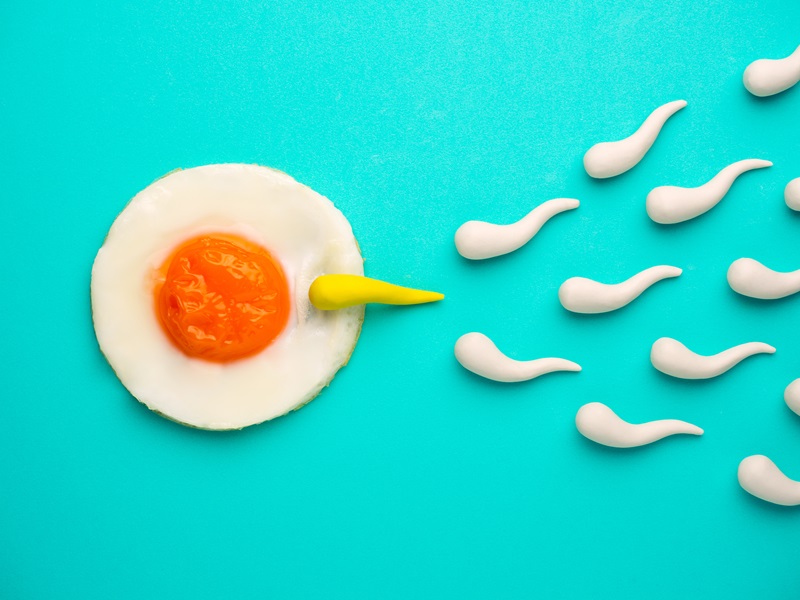
妊娠(受精)した季節が寒い時期だった人は、エネルギー消費量が高いことを発見したと、東北大学などの日本の研究チームが科学誌Nature Metabolismに論文を発表しました。科学メディアScience Alertがこの研究成果を紹介しています。
脂肪組織は、エネルギーを貯蔵する白色脂肪組織とエネルギーを消費して熱を作る褐色脂肪組織の2種類があります。これまでの研究で、褐色脂肪の活性が高い人ほど肥満になりにくく糖尿病などのリスクが低いことが分かっているといいます。
チームが、健康な若い成人男性356人を調査したところ、寒い時期(1月1日~4月15日または10月17日~12月31日)に受精して生まれた人は、暖かい時期(4月16日~10月16日)に受精して生まれた人に比べて褐色脂肪の活性が高いことが分かりました。なお、生まれた時の季節は褐色脂肪に影響を及ぼさなかったといいます。20〜78歳の健康な男女286名を対象とした別の調査でも、寒い時期の受精と褐色脂肪の活性化の有意な関連性が示されたそうです。
また、褐色脂肪の活性化にともないエネルギー消費量が増加し、肥満度の指標となるBMI(体格指数)や内臓脂肪量が低下することも分かりました。さらに、気象データの分析から、受精時期の外気温の低さと日内寒暖差の大きさが、褐色脂肪活性の主な決定要因であることも示されたといいます。
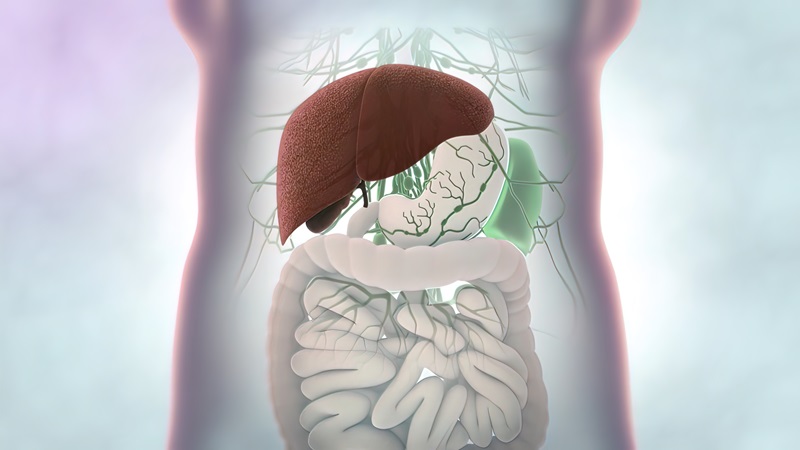
米食品医薬品局(FDA)は、遺伝子操作したブタの肝臓を使って、肝不全患者の血液をろ過する臨床試験の実施を承認したそうです。遺伝子操作したブタの臓器の開発を行っている米国のバイオテクノロジー企業「イー・ジェネシス(eGenesis)」などが15日に発表しました。AP通信が報じました。
今回の試みは、近年研究が進んでいるブタの臓器移植を発展させたものです。ブタの肝臓をヒトに移植する代わりに、特殊な装置を使って体外で患者とつなげるのだそうです。この装置は通常、ドナーから提供された肝臓を保存するために使用されているものだといいます。
肝臓は唯一、再生が可能な臓器です。そこで、ブタの肝臓が数日間血液をろ過する間、患者本人の肝臓を休ませることで、再生の可能性が高まることを期待しているそうです。
治験は今春にも実施される予定で、対象は肝移植の資格がない肝不全患者最大20人とのことです。
米国では、毎年推定3.5万人が急性肝障害で入院しているそうです。治療の選択肢はほとんどなく、死亡率は50%に達するといいます。多くの患者は肝移植の資格がないか、ドナーとのマッチングが間に合わないとのことです。

過剰なCT(コンピューター断層撮影)検査をやめれば、多くの命を救うことができるかもしれません。米国の研究チームが、これまで考えられていたより3~4倍も被ばくが原因でがんを発症している可能性があると、医学誌JAMA Internal Medicineに研究成果を発表しました。
がんをはじめとする体内のさまざまな病巣はCT検査で発見することができますが、X線を用いるため放射線による被ばくを伴います。チームは、2023年に米国内で6151万人に対して行われた9300万回のCT検査について分析を行いました。
その結果、CT検査による被ばくが原因で、将来的に10.3万件のがん症例が発生すると推計されたそうです。このままいけば、ゆくゆくは「CT関連がん」が米国における年間の新規がん症例の約5%を占める可能性があるといいます。
CT関連のがん発生リスクは乳児や子ども、青年期の若者で特に高いことが分かったそうです。ただし、CT検査を受ける割合は成人が最も高いため、症例数は成人で一番多くなると予測されました。成人は腹部と骨盤のCT、子どもは頭部のCTが最もがんの発生につながる可能性が高いとのことです。

MRI検査の造影剤に含まれる金属「ガドリニウム」によって、「腎性全身性線維症」などの重篤な副作用がまれに起こります。米国の研究チームが、多くの食品に含まれ植物のあくの成分である「シュウ酸」が副作用発生の一因の可能性があると、科学誌Magnetic Resonance Imagingに論文を発表しました。
腎性全身性線維症は、皮膚が硬化したり関節が動きにくくなったりするほか、肺や心臓や肝臓などにも症状が出ることがあり、死に至ることもある病気です。
チームは、ほうれん草やナッツ類、ベリー類、チョコレートなどに含まれるシュウ酸が、金属イオンに結合する性質を持っていることから、腎性全身性線維症との関係を調べることにしたそうです。シュウ酸はカルシウムと結合し、尿路結石の原因になることでも知られています。
試験管で実験を行ったところ、シュウ酸が造影剤から微量のガドリニウムを沈殿させ、ナノ粒子の形成を促すことが示されたそうです。そしてこのナノ粒子が、腎臓をはじめとするさまざまな臓器の細胞に侵入することが分かったといいます。こうしたナノ粒子が形成されるかどうかは、個人の代謝環境の違いによると考えられるそうです。
なお、シュウ酸はビタミンCを含む食品やサプリメントを摂取すると体内でも産生されるとのことです。

一般的に、結婚は健康状態の改善や長寿に関連すると考えられています。しかし、結婚していない人の方が認知症を発症するリスクが低くなるとの研究成果が示されたようです。米国とフランスの研究チームが医学誌Alzheimer’s & Dementiaに論文を発表しました。
チームは平均年齢71.79歳の認知症ではない2万4107人を18.44年にわたり追跡しました。その結果、結婚している人と比べた認知症発症リスクは、離婚した人が34%、一度も結婚したことがない人が40%、死別した人が27%、それぞれ低くなることが分かったそうです。
離婚した人と結婚したことがない人においては、健康状態や生活習慣、遺伝などさまざまな要因を調整した後も、こうした関連性は有意なままだったといいます。離婚した人や結婚したことがない人は、軽度認知障害から認知症に進行する可能性も低かったとのことです。
認知症の中でもアルツハイマー病とレビー小体型認知症について、結婚している人に比べて結婚していない人はリスクが低くかったそうです。
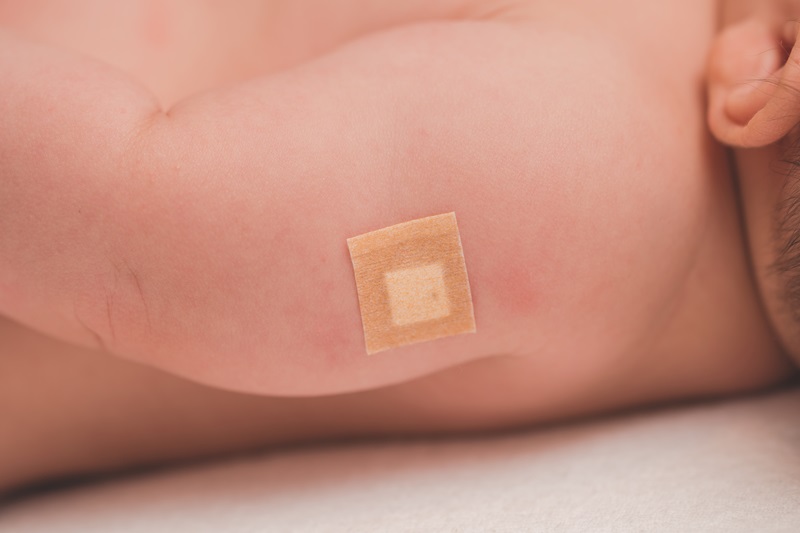
ワクチンで誘導される免疫応答のレベルに個人差があるのはなぜなのでしょうか。オーストラリアの研究チームが、新生児期に使用された抗菌薬が関係している可能性があると科学誌Natureに発表しました。
チームは、経膣分娩で生まれた健康な赤ちゃん191人を生後15カ月まで追跡しました。その結果、新生児期に抗菌薬を投与された赤ちゃんは、13価肺炎球菌(PCV13)ワクチンで誘導される抗体の量が少なく、免疫応答が弱いことが分かったそうです。一方で、分娩中に母親に使用される抗菌薬は、赤ちゃんのワクチン関連の免疫応答に影響しなかったといいます。
また、無菌マウスを使った実験で、新生児期に抗菌薬を投与された赤ちゃんの免疫応答の低さには腸内細菌叢(腸内フローラ)におけるビフィズス菌の減少が関連していることが示されたといいます。そこで、さまざまなビフィズス菌株を含有する乳児用のプロバイオティクスをマウスに投与したところ、抗菌薬による悪影響が解消され、PCV13ワクチン関連の免疫応答が高まったとのことです。
チームは、ワクチン接種前に抗菌薬を使われた乳児は、ビフィズス菌の多い腸内細菌叢を改善させることでワクチンの効果を高めることができるとみているようです。

米国のロバート・ケネディ・ジュニア厚生(保健福祉省:HHS)長官は10日の閣議で、「9月までに自閉症のまん延を引き起こした原因が明らかになる」と述べたそうです。HHSはトランプ大統領の指示の下、自閉症の診断率が「急上昇」している原因を探るため、世界中から数百人の科学者が参加する大規模な調査活動を開始したといいます。米国の各メディアが報じました。
米ABC Newsによると、この20年間で自閉症の診断率が上昇したことは事実ですが、専門家は自閉症への認識の高まりや自閉スペクトラム症(ASD)の定義拡大などの影響を指摘しているそうです。米疾病対策センター(CDC)のデータによると、2000年に自閉症と診断された8歳児は150人に1人でしたが、20年には36人に1人と増加しています。ケネディ長官は、最新のデータではこの割合は31人に1人にまで上昇していると主張しているようです。
ケネディ長官は、これまでにMMR(はしか、おたふくかぜ、風疹)ワクチンと自閉症の関連性について、たびたび問題提起してきました。トランプ大統領の指示の下で行われる大規模調査は食物、水道水、大気汚染などを含むあらゆる可能性について行う予定とのことです。

米ニューヨーク大学ランゴーン医療センターで昨年11月にブタの腎臓の移植手術を受けたアラバマ州の女性が、拒絶反応の兆候が見られたため、4月4日にこの腎臓を摘出する手術を行ったそうです。拒絶反応の原因は現在調査中とのこと。AP通信が報じました。
女性は透析治療が必要になったものの順調に回復し、アラバマ州の自宅に戻ったそうです。女性はブタの腎臓と共に130日間生活しました。これはブタの臓器を移植されたヒトとしては最長記録です。
拒絶反応の兆候が生じる直前、2016年から受けていたという過去の透析治療に関連する感染症を発症していたそうです。この感染症と戦うため、移植後の拒絶反応を抑える免疫抑制薬の量をわずかに減らしたといいます。拒絶反応の兆候に対し医療チームは、高用量の免疫抑制薬を使ってブタ腎臓を温存するよりも、摘出する方が患者にとって安全であると判断したとのことです。
女性がブタの腎臓を移植したのは、異常なほどヒトの腎臓を拒否する体質で、通常の移植手術を受けることができなかったためです。昨年11月25日に同医療センターで10個の遺伝子を改変したブタの腎臓を移植する手術が行われました。術後約3週間の時点でも拒絶反応のわずかな兆候が表れ、治療を受けていました。

医療用大麻は、慢性疾患患者の「健康関連の生活の質(HRQOL)」を改善するのに役立つようです。オーストラリアの研究チームが、 科学誌PLOS One に論文を発表しました。
チームは、2020年11月~21年12月にオーストラリア国内で新たに医療用大麻オイルを処方された18〜97歳の慢性疾患患者2353人を12カ月にわたり追跡調査しました。3カ月の時点で報告された全般的なHRQOLの改善は、12カ月時点まで維持されることが分かったそうです。倦怠(けんたい)感、痛み、睡眠にも改善がみられたといいます。
また、不安、うつ、不眠症、慢性疼痛の診断を受けた患者は、それぞれの疾患に特異的な症状が12カ月にわたり軽減しました。全般性不安障害、慢性疼痛、不眠症、心的外傷後ストレス障害(PTSD)の治療を受けていた患者はみな、HRQOLが向上したそうです。一方、運動障害患者では、HRQOLは向上したものの、運動機能の有意な改善は認められませんでした。
オーストラリアでは16年に医療用大麻が合法化されて以降、新たに100万人以上の患者が医療用大麻を処方されています。

脱毛症の新たな治療につながる可能性のある発見です。シンガポールとオーストラリアの研究チームが、髪の毛の成長に重要な役割を果たすタンパク質を特定したと、科学誌Nature Communicationsに論文を発表しました。
チームが着目したのは、傷ついたり害を及ぼしたりする可能性のある細胞が自殺するプログラム「アポトーシス」から、さまざまな組織を守る役割を持つことで知られる「MCL-1」と呼ばれるタンパク質です。
チームは、このタンパク質の産生が阻害されると、その後マウスの毛が生えなくなることを発見したそうです。毛を産生する皮膚組織の「毛包」は、成長期、退行期、休止期の3ステージを繰り返します。MCL-1には毛包の再生を担う「毛包幹細胞」が休止期から再び目覚める際にストレスやダメージを受けるのを防ぐ役割があるそうです。
そのため、MCL-1がなければ、毛包幹細胞は正常に機能しなくなるといいます。さらにチームは、MCL-1の発現が調整される仕組みも明らかにしたそうです。
脱毛症には複数の種類があり、MCL-1が全ての治療の鍵を握るわけではありませんが、今回の発見は毛包の発毛能力に関して非常に重要とのことです。

胎児期や小児期に汚染された大気に暴露すると、脳に悪影響が及ぶようです。スペインの研究チームが、オランダの都市ロッテルダムに住む子どもの脳を調べた結果を発表しました。
チームが科学誌Environment Internationalに発表した論文は、3626人のデータを分析した結果です。研究対象の子どもたちは、10歳と14歳の時に脳スキャンを受けたといいます。
その結果、生まれてから3歳までの間に、微小粒子状物質「PM2.5」に多く暴露した子どもは、感情の処理や生存に適した行動(情動反応)に関わる「扁桃体」と、注意や運動調整、聴覚機能に関与する「大脳皮質」の接続性が低いことが分かったそうです。
さらに、1回目の脳スキャンが実施される1年前に、粒子状物質「PM10」に多く暴露していた子どもは、刺激の検出や内省、自己認識をつかさどるネットワークの接続性が低かったといいます。
これらは感情処理や認知機能に影響を与える可能性があるとのことです。
また、チームが科学誌Environmental Pollutionに発表した別の研究は、子ども4243人を対象に実施しました。母親が妊娠中にPM2.5や銅などの大気汚染物質に暴露すると、子どもが8歳の時に記憶に関連する「海馬」が小さい傾向にあることが示されたそうです。

植物油などに多く含まれるリノール酸が、悪性度の高いトリプルネガティブ乳がん(TNBC)の増殖を促す可能性があるそうです。米国の研究チームが科学誌Scienceに研究成果を発表しました。
リノール酸は体内で作ることができないため、食物から摂取する必要がある必須脂肪酸「オメガ6脂肪酸」の一種です。不足すると皮膚の障害や免疫機能の低下などが起こるといわれています。
チームは、リノール酸が「FABP5」と呼ばれるタンパク質と結合することで、腫瘍細胞を成長させる「mTORC1シグナル伝達経路」を活性化させることを発見したそうです。FABP5は、他のサブタイプの乳がんに比べてTNBCで特に高レベルで産生されるといいます。
TNBCマウスにリノール酸が豊富なエサを与えたところ、FABP5レベルの上昇とmTORC1経路の活性化が認められ、腫瘍の成長が促進されたそうです。
また、新たにTNBCと診断された患者の腫瘍や血液を調べたところ、FABP5とリノール酸のレベルが上昇していることが明らかになったとのことです。

糖尿病の改善に、持久力の高い一流アスリートの便移植が有効かもしれません。フランスの研究チームがマウスへの便移植の実験で、インスリンに対する感受性の向上と、糖の代謝物であるグリコーゲンの貯蔵が筋肉で増加することを発見したと、科学誌Cell Reportsに論文を発表しました。
チームは、幅広い有酸素運動能力(全身持久力)を持つ標準体重の健康な男性50人から便を採取し、腸内細菌の組成や密度、多様性、代謝機能を分析したそうです。その結果、有酸素運動能力の高いアスリートは、腸内細菌の多様性や密度が低い一方で、善玉菌によって作られる代謝物「短鎖脂肪酸」の濃度が高いことが分かったといいます。
そして、こうしたアスリートは、短鎖脂肪酸の産生に関与する腸内細菌「プレボテラ・コプリ」と「ファスコラークトバクテリウム・スクシナテュテンス」が豊富だったそうです。
腸内細菌の役割を調べるために、チームは有酸素運動能力が高いアスリートの便を無菌マウスに移植する実験を実施しました。すると、マウスのインスリン感受性が向上し、筋肉において運動時のエネルギー源となるグリコーゲンの貯蔵が増加することが明らかになったそうです。ただし、マウスの持久力は改善しなかったとのことです。
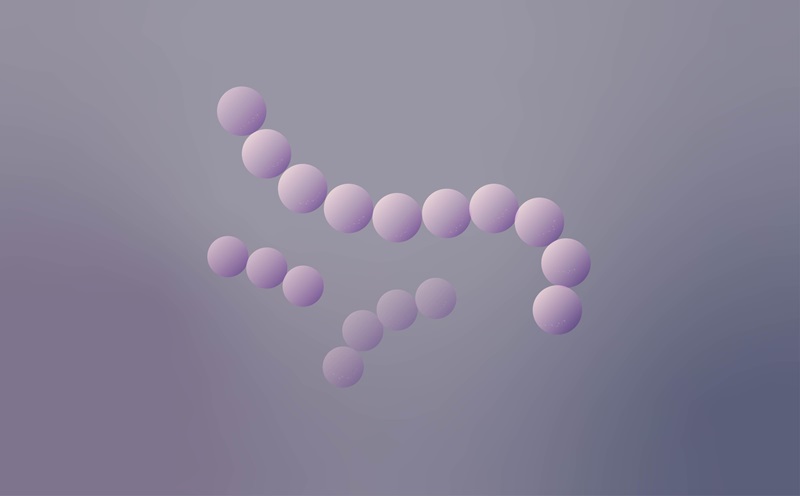
米国で2013~22年に、「侵襲性A群レンサ球菌感染症(iGAS)」の症例数が2倍以上に増加したことが米疾病対策センター(CDC)の調査で明らかになりました。
A群レンサ球菌は一般的には咽頭炎の原因になる細菌ですが、まれに壊死性筋膜炎などの重篤な状態につながる侵襲性の感染症を引き起こします。さらに、劇症化すると手足の壊死や多臓器不全を起こし、「人食いバクテリア」による感染症とも呼ばれる病気につながることがあります。
CDCが米国内の10州に住む3490万人のデータを分析したところ、13年に10万人あたり3.6例だった侵襲性の感染症の発生率が、22年には8.2例に上昇したことが分かりました。9年間で計2万1312人の患者が特定され、このうち1981人が死亡したそうです。こうした増加の原因についてCDCは、糖尿病や肥満の人が増えたことで、一部の人々が細菌感染に脆弱になったことを挙げています。
また、違法薬物を針で注入する際に細菌が血液に侵入する可能性も考えられ、実際に違法薬物を注射している人の侵襲性の感染症が増えているそうです。さらに、65歳以上の高齢者やホームレスなどでも発生率が高かったとのことです。
この研究成果をまとめた論文は医学誌JAMAに掲載されました。

性欲減退を改善するには、長期間の「断続的断食」が有効かもしれません。ドイツと中国の研究チームが、科学誌Cell Metabolismに論文を発表しました。
チームは、長期にわたって断続的断食をした高齢の雄マウスが、異常に多くの子どもを残すことを発見したそうです。この現象は、断食によって生殖器や内分泌の状態が変化したことではなく、断食マウスの交尾の回数が異常に多くなることに起因すると明らかになったといいます。
マウスに行った断食は、24時間エサを自由に食べられるようにした後、次の24時間は水だけを与えるというもので、このサイクルを22カ月間続けました。この期間中は雌マウスとの接触を遮断し、その後、雌マウスと引き合わせました。
6カ月間、同様の断食をした若いマウスでも交尾が増加したそうです。一方で、数週間の断食をさせた場合は、若いマウスも高齢マウスも性欲は増強しなかったといいます。
また、断食による交尾の増加には、性行動に影響を及ぼす神経伝達物質「セロトニン」レベルの低下が関連していることも分かりました。断食によってセロトニンの材料になる必須アミノ酸「トリプトファン」の摂取量が減少することで、脳内のセロトニンレベルが低下し、性欲が高まる可能性があるとのことです。

米テキサス州保健局は6日、麻疹(はしか)に感染した子どもが3日に死亡したと発表しました。死亡したのは学齢期の女児で、はしかの合併症で入院し、治療を受けていたといいます。女児はワクチン未接種で、基礎疾患は確認されていないとのことです。テキサス州では2月に、はしかの感染で6歳の子どもが死亡しており、死者は今年2人目です。
今年1月以降、テキサス州ではしかの感染が急速に広がっており、4月4日時点で州内の感染者は計481人に達したそうです。隣のニューメキシコ州でも、はしかが原因で死亡したとみられる成人の症例が1件確認されています。米国では過去10年、はしかによる死者は報告されていませんでした。
米保健福祉省(HHS)長官のロバート・ケネディ・ジュニア氏はワクチン懐疑派で知られますが、2人目の子どもの死亡を受け、ソーシャルメディアX(旧Twitter)に「はしかの広がりを防ぐために最も有効な方法はワクチンだ」と投稿したそうです。
はしかはワクチンの2回接種で97%の効果が得られます。一方でワクチン未接種の場合、命に関わる病気を引き起こすことがあります。子どもの患者の5人に1人が入院し、20人に1人が肺炎を発症、まれに脳の腫れが起こるとのことです。

脳卒中によって話せなくなった女性が、頭の中で考えた言葉や文章をリアルタイムで音声に変換することができる装置を使い、再び会話をすることができるようになったそうです。米国の研究チームが科学誌Nature Neuroscienceに論文を発表しました。
チームは脳卒中発症後に18年間話すことができなかった47歳の四肢まひの女性の脳に、この装置を埋め込む臨床試験を実施しました。そして、女性が脳内で文章を作っている際の脳活動を電極を使って記録し、かつての女性の声を合成したシンセサイザーで、女性が頭の中で思い浮かべた文章を女性が話しているかのように音声化することに成功したといいます。
これまで開発された同様のブレイン・コンピュータ・インターフェース(BCI)は、脳内で思い浮かべた文章とコンピューターによる音声化の間にわずかな遅れが生じていたそうです。こうした遅れは、自然な会話の流れを阻害し、ミスコミュニケーションやフラストレーションにつながる可能性があります。一方、今回の装置は、文章の終わりまで待たずに、その場ですぐさま処理が行われるとのことです。
AP通信によると、継続的な投資があれば、さらなる研究を行った上で、10年以内にこの装置が実用化される可能性があるそうです。

ホルモンを含まない男性用経口避妊薬の開発が進んでいます。精子の産生を抑制する「YCT-529」と呼ばれる世界初の薬は、既に治験の第1相が終了し、安全性と有効性を評価する第2相が2024年9月からニュージーランドで始まっているそうです。米国の研究チームが、治験を始める根拠となった動物実験の結果を科学誌Nature Communicationsに発表しました。
精子の産生にはビタミンAの代謝物「レチノイン酸」が不可欠です。チームが開発したYCT-529はその受容体「レチノイン酸受容体α(RAR-α)」の作用を阻害することで、精子が生成されるのを防ぐそうです。そして、RAR-αのみを標的にしているため、これまで開発が進められてきた男性ホルモンを抑制する避妊薬と比べて、精神面や性欲減退などの副作用が少ないといいます。
チームが雄マウスにこの避妊薬を投与する実験を行ったところ、パートナーの雌マウスの妊娠が100%近く抑制されたそうです。YCT-529を使い始めてから1カ月以内に、避妊の効果が現れたといいます。サルの実験でも、重篤な副作用に見舞われることなく、精子の数が急減することが確認されたとのことです。マウスもサルも、薬の投与が中止されると、すぐに元の生殖能力が戻ったといいます。
なお、治験の第1相の詳しい結果はまだ公表されていませんが、有望な結果が示されたようです。

立ち上がると心拍数が大きく上昇し、めまいやブレインフォグ(頭の中に霧がかかったようになる状態)などの症状を特徴とする「体位性頻脈症候群(POTS)」は、未解明なことが多く診断や治療の方法が確立されていません。オーストラリアの研究チームが、POTSの根本的な問題は脳の血流悪化の可能性があることを突き止めたと、科学誌Scientific Reportsに論文を発表しました。
POTSは若い女性に多くみられ、自律神経障害が関連すると考えられています。ウイルス感染、脳震とう、手術、妊娠などをきっかけに発症することが多く、まだ認知度の低い疾患です。
チームは、深刻なブレインフォグに苦しむ平均34.8歳のPOTS患者56人に対し、脳の血流を測定するSPECT(スペクト)検査を実施しました。その結果、参加者の61%で、横になっている時でも脳の主要な領域で血流が低下していることが分かったそうです。
特に、実行機能や感覚、運動に関与する領域が影響を受けたといいます。これにより、計画、意思決定、集中、感覚情報処理が困難になり、日常生活や全体的な幸福感に悪影響が及ぶ可能性があるとのことです。
チームは、今後の研究で、脳血流の管理が治療などに果たす役割を調べることの重要性を指摘しています。

帯状疱疹ワクチンの接種が認知症リスクを抑制する可能性があるそうです。米国の研究チームが、28万人以上のデータを分析し、研究成果を科学誌Natureに発表しました。
チームは、2013年に英ウェールズで始まった帯状疱疹ワクチンプログラムに着目。分析の結果、帯状疱疹ワクチン(弱毒生水痘ワクチン)の接種者は、未接種者に比べて、その後7年間で認知症を発症するリスクが20%低くなることが分かったそうです。また、ワクチンによる認知症リスクの予防効果は、男性よりも女性の方がはるかに高いことも明らかになったといいます。
これまでにも、帯状疱疹ワクチンの認知症リスク抑制の効果を示唆する研究結果が報告されていたそうです。しかしチームは、今回の研究の意義を強調しています。
ウェールズのプログラムは、13年9月1日の時点で79歳の人に対して1年間、弱毒生水痘ワクチンを受ける資格が与えられ、80歳になっている人に接種資格は与えられませんでした。このため、健康状態の近い、わずかな年齢差の人のデータを比較することができたとのことです。
帯状疱疹は水痘(水ぼうそう)と同じウイルスが原因で、痛みをともなう発疹が現れる皮膚疾患です。このウイルスは多くの成人の神経細胞に潜伏しており、加齢や免疫機能の低下などによって再活性化して発症します。

コーヒーは健康にさまざまな良い影響をもたらすことが知られています。しかし、コーヒーには血中のLDL(悪玉)コレステロール値を上昇させてしまう成分が含まれており、その成分の濃度はいれ方によって大きく異なるそうです。スウェーデンの研究チームが医学誌Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseasesに論文を発表しました。
LDLコレステロール値を上昇させるのは「ジテルペン」という物質の一種である「カフェストール」と「カーウェオール」です。
チームが、医療施設に設置されているコーヒーマシン14台でいれたコーヒーのジテルペン濃度を分析したところ、中央値はカフェストールが174mg/L、カーウェオールが135mg/Lでした。
一方、ペーパーフィルターを使ってハンドドリップでいれたコーヒーはカフェストールが11.5mg/L、カーウェオールが8.2mg/Lだったといいます。煮出しコーヒーのジテルペン濃度は、コーヒーマシンより高かったといいます。
1日3杯のコーヒーを週5日飲む人が、いれかたをコーヒーマシンからペーパーフィルターに変えると、LDLコレステロールの減少によりアテローム性動脈硬化の相対リスクが5年間で13%、40年間で36%それぞれ低下すると推計されるそうです。

砂糖の代替品として広く使用される低カロリーの甘味料「スクラロース」はダイエットに有効なのでしょうか。米国の研究チームが、スクラロースを摂取すると、甘味に見合うカロリーが取り込まれないことで脳が混乱し、食欲の増加につながってしまう可能性があると、科学誌Nature Metabolismに論文を発表しました。
スクラロースは砂糖から合成され、砂糖の600倍の甘味度を持つといいます。チームは、健康、太り過ぎ、肥満の若年成人を均等に計75人集めました。そして、スクラロース入り飲料、砂糖入り飲料、水の3種類を各300mlずつ別の日に飲んでもらった上で、脳や血液の変化を分析したそうです。
その結果、スクラロースは砂糖に比べて、食欲を調整する脳の視床下部の活動と空腹感を増加させることが分かったといいます。水と比較すると、スクラロースの摂取で視床下部の活動は増えたものの、空腹感に違いは認められなかったそうです。こうした変化は、肥満の人で特に顕著だったといいます。
また、砂糖と違い、スクラロースを摂取しても満腹感を生み出すホルモンの値は上昇しなかったとのことです。

ヒトパピローマウイルス(HPV)は、子宮頸がんをはじめとする複数の種類のがんを引き起こすだけでなく、心血管疾患リスクにも関連するようです。米国の研究チームが、米イリノイ州シカゴで3月29~31日に行われた米国心臓病学会(ACC)で研究成果を発表しました。
チームは、HPV感染と心血管疾患に関するデータが掲載されている七つの研究から、計25万人近くについて3~17年にわたり追跡したそうです。分析の結果、HPV陽性者は、陰性者に比べて心血管疾患を発症するリスクが40%高く、心臓の動脈にプラークが蓄積して心筋の血流が低下する冠動脈疾患を発症するリスクが2倍になることが分かったといいます。
病歴や生活習慣など病気に与えるさまざまな要因(交絡因子)を調整した後でも、HPV陽性者の心血管疾患リスクは33%高かったといいます。一方で、高血圧との有意な関連性は認められなかったそうです。
HPVと心血管疾患の関連のメカニズムは分かっていませんが、チームはHPV感染による慢性炎症が関係しているとみているようです。HPV感染を予防するには、10代のうちにHPVワクチンを接種することが有効であることが知られています。

プラセボ(偽薬)であることを患者に告げたうえで投与するオープンラベルプラセボ(OLP)には、過敏性腸症候群や慢性腰痛などさまざまな症状に効果があることが知られています。スイスの研究チームが、月経前に心や体に不調が生じる「月経前症候群(PMS)」の治療にも有効な可能性があると、医学誌BMJ Evidence-Based Medicineに論文を発表しました。
チームは、中等~重度のPMSか月経前不快気分障害(PMDD)に苦しむ18~45歳の女性150人を3群に分けて調査しました。
普段通りPMS治療薬を服用した群は、症状の強さが33%、日常生活への支障が45.7%抑制されたといいます。一方で、OLPの効果について詳しく説明を受けた上でプラセボを服用した群は、PMS症状の強さが79.3%、日常生活への支障が82.5%減ったそうです。また、OLPの効果については説明されず、服用するものがプラセボであることだけを知っていた群は、症状の強さが50.4%、日常生活への支障が50.3%減少しました。
なお、PMS患者に一般的に処方される選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)や低用量ピルは、めまいや吐き気、体重増加などの副作用があることで知られています。OLPを服用した2群で深刻な副作用はなかったそうです。

マラソン直後にランナーの記憶力が悪くなったり物事に対する反応が遅くなったりすることがあるそうです。スペインの研究チームが、過酷な運動によってエネルギー不足になると、脳が自身の脂肪組織をむしゃむしゃ食べ始めることがその現象を引き起こしている可能性があるとして、科学誌Nature Metabolismに論文を発表しました。
チームは、ランナー10人(男性8人、女性2人)が42kmを走る前と後に撮影した脳のMRI画像を分析しました。すると、マラソンから24~48時間後、体の内外から入って来る情報をまとめて運動や動作につなげる脳領域と、感覚や感情の統合に関与する脳領域において、ミエリン(髄鞘<ずいしょう>)が減少していることが明らかになったといいます。
ミエリンは脂質に富んだ組織で、神経細胞(ニューロン)の情報のやり取りを担う突起(軸索)を包み込んでいます。マラソンから2週間後にミエリンの量は回復に向かい始め、2カ月後にはマラソン前の水準に戻ったそうです。
チームは、マラソン中に脳の主なエネルギー源であるグルコースが減少すると、ミエリンがエネルギーとして代用されるとみています。マウスを使った別の研究でも、脳内のグルコース不足に備えてミエリンがエネルギー貯蔵庫の役割を果たしていることが分かっているとのことです。

麻疹(はしか)が流行している米国のテキサス州とニューメキシコ州で、はしかで入院した患者がビタミンAの過剰摂取によるとみられる中毒症状を引き起こしている症例が報告されているそうです。米保健福祉省(HHS)長官のロバート・ケネディ・ジュニア氏が、ビタミンAがはしかの「予防薬」になり得るという発言をしており、それが影響している可能性があります。米CNNが報じました。
流行の中心地に近いテキサス州ラボックの小児病院では、ビタミンAの過剰摂取が原因とみられる肝機能の異常が複数の患者から見つかったといいます。中毒症状を引き起こしている小児の入院患者は全員がワクチン未接種だったとのことです。
ケネディ氏は、はしか流行の対応としてビタミンAの摂取に重きを置いています。しかし、ビタミンAには免疫機能全般を支える役割はありますが、はしか感染を予防するとの証拠は見つかっていません。逆にビタミンAの過剰摂取は、皮膚や目の乾燥から肝機能障害に至るまで健康にさまざまな悪影響を及ぼすといいます。
はしかを予防できる唯一の手段はワクチンです。2回接種で97%の効果が得られます。
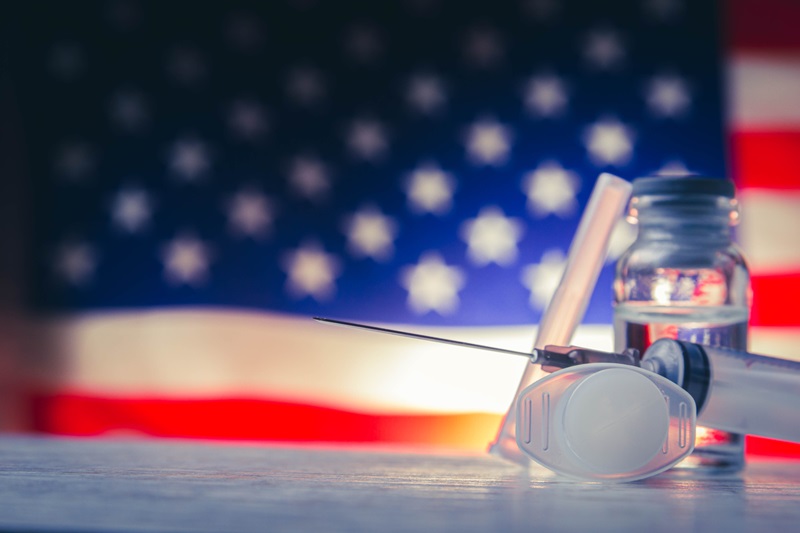
米保健福祉省(HHS)当局者は3月28日、2016年から食品医薬品局(FDA)でワクチン関連部門のトップを務めてきたピーター・マークス氏が辞任したと発表しました。米国の複数のメディアが報じています。米NBC NewsやCNNによると、マークス氏は辞職か解雇かの選択を迫られ、職を追われたそうです。
マークス氏は、FDA長官代行に宛てた辞意を表す書簡で、HHS(厚生)長官のロバート・ケネディ・ジュニア氏について「真実と透明性を望んでいるのではなく、むしろ彼自身の誤った情報や嘘に従順であることを望んでいることが分かった」と指摘したといいます。
新型コロナウイルスワクチンを巡っても二人の立場は真逆でした。マークス氏がワクチンの迅速な開発や承認に重要な役割を果たした一方で、ケネディ氏はコロナワクチンに批判的で、過去には「これまでに作られた中で最も致命的なワクチン」との発言もしているとのことです。また、ケネディ氏は他のワクチンに対する懐疑的な姿勢もたびたび物議を醸してきました。
マークス氏は、ワクチンへの信頼を損なうことは「無責任で、公衆衛生に有害であり、我が国の健康、安全、危機管理にとって明らかに危険である」と書簡に記したといいます。

欧州医薬品庁(EMA)は、米国で昨年7月に承認された米製薬大手イーライリリーの早期アルツハイマー病(AD)治療薬「ケサンラ(一般名ドナネマブ)」について、販売承認を推奨しないことを決めました。AP通信が報じました。
ケサンラはADの原因の一つとされるタンパク質アミロイドβの塊(アミロイドプラーク)を除去する薬で、ADによる軽度認知障害の進行を抑制する効果が確認されています。しかし、脳の出血や腫れなどのリスクが指摘されており、EMAはケサンラを使用するリスクがメリットを上回ると判断しました。
ケサンラはこれまでに米国のほか、日本や中国でも承認されています。イーライリリーは、再審査を通じてEMAとケサンラに関する議論を続けていきたいとコメントしているそうです。
EMAは昨夏、エーザイが開発したAD治療薬「レケンビ(一般名レカネマブ)」についても同様の懸念があるとして販売承認を推奨しない決定を下しましたが、数カ月後にその決定を覆しています。
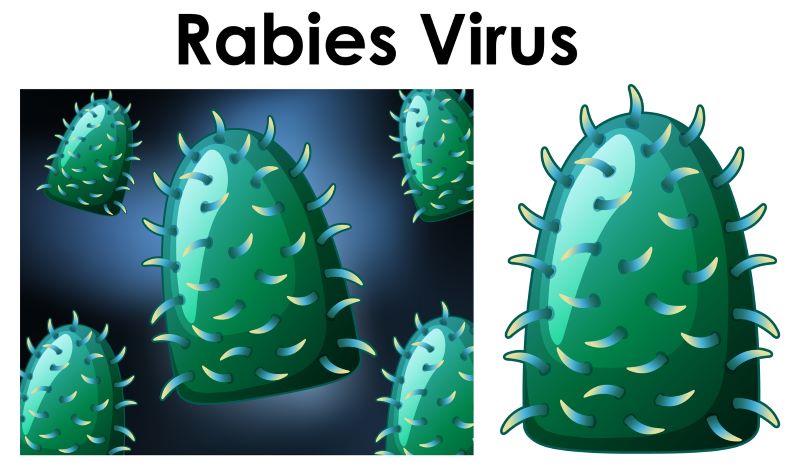
米ミシガン州に住む臓器移植を受けた患者が1月、移植した臓器を通じて狂犬病ウイルスに感染して死亡したそうです。米国などの複数のメディアが報じました。
米NBC Newsによると、3月26日に州保健当局が発表しました。患者は昨年12月にオハイオ州の病院で臓器の移植手術を受けたそうです。公衆衛生調査により、狂犬病ウイルスは移植した臓器から患者に感染したと断定されたといいます。臓器を提供したドナーは、ミシガン州やオハイオ州の住民ではなかったとのことです。
米国ではこれまでにも移植した臓器が原因で狂犬病ウイルスに感染し、患者が死亡した事例があるそうです。2013年に腎臓移植を受けた患者が狂犬病で死亡し、その後にフロリダ州のドナーが狂犬病によって死亡していたことが明らかになったといいます。また、04年には、狂犬病にかかっていたアーカンソー州のドナーから臓器提供を受けた4人が死亡しているそうです。
米国では、臓器提供の候補者にウイルスや細菌が感染していないかを調べるスクリーニング検査を実施しています。しかし、狂犬病は非常にまれである上に、検査に時間がかかりすぎることから通常は対象外だといいます。
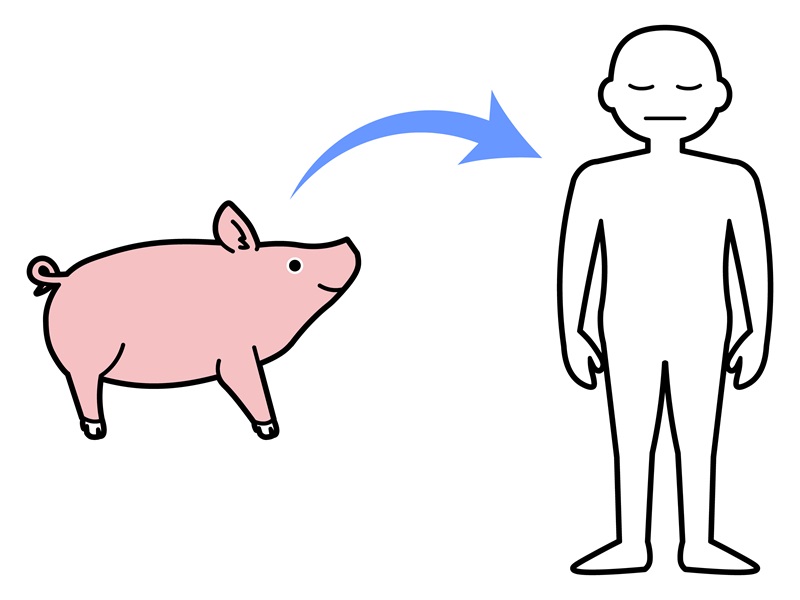
中国の研究チームが、ミニブタの肝臓を成人の脳死患者に移植したと、科学誌Natureに発表しました。米国でブタの心臓や腎臓が移植された例はありますが、ブタの肝臓がヒトに移植されたのは初めてです。
移植手術を行ったのは西安市にある空軍軍医大学(旧:第四軍医大学)で、遺伝子を6カ所改変したミニブタの肝臓を使ったそうです。移植を受けた患者の性別などの詳細は明らかにされていません。手術は2024年3月10日に行われ、家族の要望により試験は10日間で終了したといいます。
患者は自身の肝臓を温存したまま、その機能を補う補助臓器としてブタの肝臓を移植されたとのことです。ブタの肝臓は10日間正常に機能し、十分な量ではないものの、胆汁の分泌や肝臓で作られる主要なタンパク質「アルブミン」の産生も確認されたそうです。
心臓などと違い、肝臓は複数の異なる機能を有するため、移植のハードルは高いと考えられています。ブタの肝臓が、臓器提供者が現れるまでのつなぎの役割を果たすことが期待される一方で、ヒトの肝臓の代替として機能するかどうかは現段階では確認できていないそうです。
次のステップとして、チームは「生きている(脳死ではない)」患者に対してブタの肝臓を移植する計画を進めているとのことです。

心血管疾患リスクが高い患者に対して、悪玉コレステロール(LDLコレステロール:LDL-C)を下げる「スタチン」と「エゼチミブ」の併用を早めに行うと、多くの命を救える可能性があるそうです。ポーランドなどの研究チームが、医学誌Mayo Clinic Proceedingsに論文を発表しました。
スタチンは肝臓でのLDL-Cの生成を抑え、エゼミチブは小腸でのLDL-Cの吸収を阻害する薬です。
チームは、既存の14の研究から、心臓発作や脳卒中のリスクが高い患者またはこれらの既往歴がある患者計10万8373人のデータを分析しました。その結果、スタチンとエゼチミブを併用した人は、スタチンのみを使用した人に比べて全死因死亡リスクが19%低くなることが明らかになったそうです。
また、主要心血管イベント(MACE)を発症するリスクが18%、脳卒中を発症するリスクが17%低下することも分かりました。さらに、この2剤併用療法によってLDL-Cが減少し、LDL-Cの管理目標値である70mg/dL未満を達成する可能性が85%高くなったといいます。

米食品医薬品局(FDA)は25日、英製薬大手グラクソ・スミスクライン(GSK)が開発した尿路感染症(UTI)向け経口抗菌薬「Blujepa」を承認したそうです。米国の複数のメディアが報じました。
米NBC Newsによると、Blujepaは大腸菌などの尿路病原細菌が複製する際に必要な二つの酵素の働きを、新しい方法で阻害することで細菌の増殖を防ぐそうです。UTIに対する新しい作用機序を持つ薬が承認されたのは1996年以来初めてだといいます。
対象となるのは合併症のない単純性UTIを患う12歳以上の女性です。通常、UTIは抗菌薬の短期投与で完治しますが、近年は既存薬に対する耐性の高まりが問題になっています。
UTI患者3千人を対象とした二つの第3相試験では、1日2回Blujepaを5日間服用した群の50~58%で治療が成功したといいます。一方、標準治療薬の抗菌薬「ニトロフラントイン」の治療成功率は43~47%だったとのことです。
UTIは女性の半数以上が生涯で少なくとも1回は経験し、約30%が再発するといわれています。

トランプ米大統領は24日、疾病対策センター(CDC)の次期所長にスーザン・モナレズ氏を指名することを明らかにしました。米国の複数のメディアが報じました。
米CBS Newsによると、モナレズ氏は今年1月からCDCの所長代行を務めています。ある政府高官は、CDC所長代行に就任して以来、モナレズ氏は保健福祉省(HHS)長官のロバート・ケネディ・ジュニア氏と「うまくやってきた」と述べたといいます。
指名を承認するかどうかを決める連邦議会上院の公聴会では、自閉症とワクチンの関連性を調査する計画から人員削減に至るまで、この数カ月間物議を醸してきたCDCのさまざまな決定について、モナレズ氏が果たした役割を追及される可能性があるとのことです。
ホワイトハウスは当初、ワクチン懐疑派のデビッド・ウェルドン元下院議員をCDC所長に充てる予定でしたが、上院で承認を得るのは困難と判断し、3月上旬に同氏の指名を取り下げていました。

宇宙航空研究開発機構(JAXA)の大西卓哉飛行士が日本時間の16日から、国際宇宙ステーション(ISS)で約半年間の長期滞在を始めました。宇宙での生活は人体にどのような影響を及ぼすのでしょうか。英BBCが宇宙の「過酷な環境」での人体の変化について報じました。
ISS内の微小重力状態では、筋力と骨が毎月約1%ずつ衰えていくそうです。そのため地球に帰還後は、失われた機能を取り戻すために激しいトレーニングを行う必要があるといいます。筋肉量を増やすには数カ月、骨量を戻すには数年かかる可能性があるそうです。
また、宇宙空間では体に常在する微生物叢の組成の変化や体液の上半身への移動も起こります。体液の移動は脳の腫れを引き起こし、視力低下や回復不可能な損傷ができてしまう宇宙飛行関連神経眼症候群(SANS)につながる可能性があるといいます。
さらに、平衡感覚をつかさどる内耳の前庭器官の働きが損なわれることで、地球に戻ってから2~3日はめまいやバランス感覚の喪失に見舞われ、普通に歩くことが困難になるそうです。
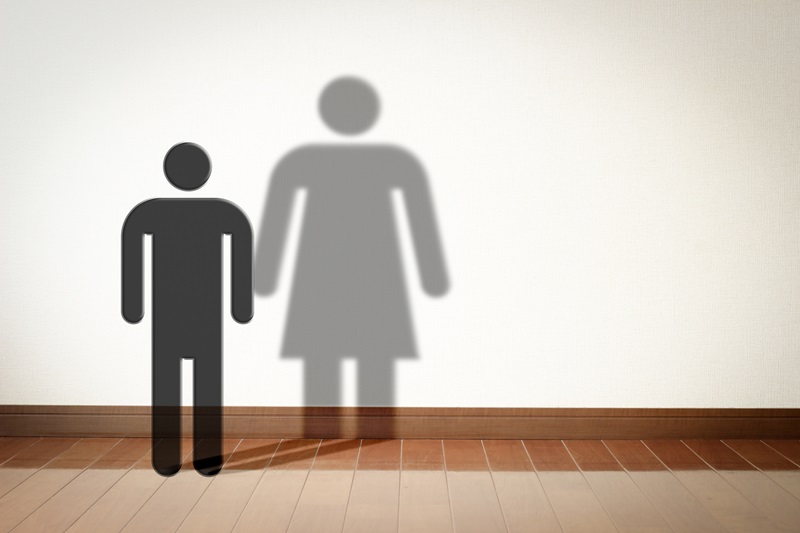
トランスジェンダーなど、出生時に割り当てられた性別を強いられることに苦痛を感じるTGD(Transgender and gender diverse individuals)の人々が「性別適合ホルモン療法」を受けると、体だけでなく心の健康にも好影響があるようです。米国の研究チームが、医学誌JAMA Network Openに論文を発表しました。
チームは、平均年齢28歳のTGD成人3592人を対象に、4年間にわたる追跡調査を行いました。調査を開始した時点で、対象者の15.3%が中等~重度のうつ症状を呈していたといいます。
そして調査の結果、性別適合ホルモン療法を受けた人は、そうでない人に比べて追跡期間中に中等~重度のうつ症状を報告するリスクが15%低くなることが分かったそうです。
米CNNによると、米国の成人の8.3%が大うつ病を少なくとも1回経験していると米国立衛生研究所(NIH)が推計しているといいます。一方で、TGDの人は、約33%がうつ病の兆候を示すことが明らかになっているとのことです。
なお、トランプ大統領は就任直後、19歳未満への性別適合の治療や手術を行うことを制限する大統領令に署名しています。

ハーブの「ローズマリー」や「セージ」に含まれ、抗酸化・抗炎症作用がある「カルノシン酸」が、アルツハイマー病(AD)の治療薬になるかもしれません。カルノシン酸は非常に不安定な物資なのですが、米国の研究チームが、体内で安定した形にしておく方法を発見し、マウスの実験で認知症への効果を確認したと、科学誌Antioxidantsに発表しました。
チームは、カルノシン酸を「ジアセチル化カルノシン酸(diAcCA)」という形に合成すると、脳内で効果を発揮するまで安定していることを突き止めたそうです。マウスに与えると、diAcCAは血流に乗る前に腸でカルノシン酸に変換され、1時間以内に脳内のカルノシン酸レベルが上昇することが分かったといいます。
ADマウスに3カ月にわたりdiAcCAを週3回、経口投与したところ、脳内の炎症が軽減し、神経細胞のつなぎ目であるシナプスの数が増加することが分かったそうです。また、ADに関連するとされる「リン酸化タウ」や「アミロイドβ」などの有害なタンパク質が減少することも明らかになったとのことです。
記憶に関する複数の試験では、diAcCA投与マウスの記憶力がほぼ正常な状態にまで改善することも示されました。なお、diAcCAにマウスへの毒性作用は認められなかったとのことです。

新型コロナウイルスに感染した数週間後に、「小児多系統炎症性症候群(MIS-C)」と呼ばれる重度の炎症性疾患を発症する子どもがいます。不明とされていたMIS-Cの原因について、ドイツの研究チームが、体内で休眠状態にあるヘルペスウイルスの一種「エプスタイン・バーウイルス(EBV)」の再活性化の可能性があることを突き止めたと、科学誌Natureに発表しました。
MIS-Cは発熱や嘔吐(おうと)、腹痛、下痢、目の痛み・充血などが主な症状です。EBVは90%の人が感染する一般的なウイルスで、多感染後に体内に潜伏し、休眠状態に入ります。
チームは、MIS-Cの治療を受けた2~18歳の145人と新型コロナに感染したもののMIS-Cは発症しなかった子ども105人を比較しました。
その結果、MIS-C群の血液から、EBVの痕跡やEBVに対する高レベルの抗体や免疫細胞が見つかったそうです。この免疫細胞は本来、EBVに感染した細胞を殺傷する能力を有していますが、新型コロナ感染によって産生された、細胞の増殖や分化、細胞死を調節するタンパク質(トランスフォーミング増殖因子β:TGFβ)が原因で、その能力が失われることが分かったとのことです。
チームは、EBVが急速に増殖し、極度の炎症につながる可能性が示されたとしています。

アルツハイマー病(AD)の進行を抑える新しい治療薬は、実質的に患者にどのような効果をもたらすのでしょうか。米国の研究チームが、近年承認された「レカネマブ」と「ドナネマブ」についての研究結果を医学誌Alzheimer’s & Dementia: Translational Research & Clinical Interventionsに発表しました。
チームは、軽度のAD型認知症を患う60歳以上の282人(男性159人、女性123人)を対象に平均2.9年間の追跡調査を行ったそうです。請求書の支払い、車の運転、服薬や予約の管理、食事の準備など日常生活に必要な自立の度合いを評価したといいます。
その結果、非常に軽度のADで、日にちや服薬を忘れてしまう可能性のある人が治療を受けなかった場合、その後自立して生活できる期間は平均29カ月と推定されたそうです。一方、同じレベルのADを持つ患者がレカネマブを使用すると10カ月、ドナネマブを使用すると13カ月、自立して生活できる期間がそれぞれ延びることが示されたといいます。
レカネマブとドナネマブは、ADに関連するとされるタンパク質アミロイドβの塊を脳から取り除く薬です。脳の腫れや脳出血のリスクがあるほか、効果について疑問を呈する専門家もいます。

脳内の大麻に対する受容体が、うつ病や不安症などの治療の標的として有望な可能性があるそうです。カナダの研究チームが、科学誌Nature Neuroscienceに研究成果を発表しました。
チームが着目したのは、大麻草に含まれる「カンナビノイド」によって活性化する「1型カンナビノイド受容体(CB1)」です。マウスの実験で、アストロサイトと呼ばれるニューロン(神経細胞)の働きを助けるグリア細胞において、CB1を過剰に発現させて調べたそうです。その結果、攻撃的なマウスからストレスを受けても、不安やうつ症状が少なくなることが分かったといいます。
アストロサイトは、脳組織に有害な物質が入り込むのを防ぐ「血液脳関門」の完全性を維持する働きを持つそうです。ストレスを受けると血液脳関門がダメージを受けて炎症が起きてしまうのですが、CB1を過剰に発現させたマウスではそれが抑制されることが明らかになったとのことです。
さらに死後のヒト脳の分析で、死亡時にうつ病を患っていた人は、アストロサイトのCB1レベルが低いことも判明。チームは、アストロサイトにおけるCB1レベルの上昇が、ストレスからの回復力を高めるとみています。

米トランプ政権が海外援助を一時凍結したことから、世界の医療プログラムに深刻な影響が及んでいます。数カ月以内にHIV(エイズウイルス)の治療薬がなくなる国もあるそうです。WHO(世界保健機関)が17日に発表しました。
米国の海外援助の一時凍結後、HIVについては、50カ国以上で治療や検査、予防に関する事業が即時停止に追い込まれたといいます。英BBCによると、ナイジェリア、ケニア、レソト、南スーダン、ブルキナファソ、マリ、ハイチ、ウクライナの8カ国では、HIVの治療薬(抗レトロウイルス薬)が数カ月以内に底を突く可能性があるそうです。
WHOのテドロス事務局長は、こうした混乱によって20年にわたって積み重ねてきたHIVプログラムの進歩が台無しになりかねないと述べ、このことが1000万人以上のHIV感染者の増加につながり、HIV関連死亡者も昨年の3倍以上の300万人に達する可能性があると警鐘を鳴らしました。
テドロス氏は米国に対し、世界の公衆衛生への支援について再考するよう求めています。

減量薬として注目されているオゼンピックなどの「GLP-1受容体作動薬」よりも、減量効果が期待できるタンパク質が見つかったそうです。米国の研究チームが、科学Natureに研究成果を発表しました。
チームは、AIを使って2600ものタンパク質をスクリーニングしたそうです。その結果、食欲に関わる脳活動を誘発する分子として「BRINP2関連ペプチド(BRP)」を同定したそうです。BRPはわずか12個のアミノ酸で構成される小さな分子だといいます。
痩せた雄マウスやミニブタにBRPを注射で投与したところ、吐き気や便秘などの副作用を引き起こすことなく、その後1時間にわたり食事量が半減したのだそうです。さらに、肥満マウスにBRPを14日間、注射で投与すると、対照群と比較して平均4g体重が減少することも分かったといいます。
この時減少したのは筋肉ではなく、ほとんどが脂肪だったそうです。一方で、GLP-1受容体作動薬による減量は、筋肉や骨の減少を引き起こす可能性があるため、体への長期的な影響が懸念されています。
今後、BPRが人間の肥満治療薬になるかどうか、治験が行われる予定だとのことです。
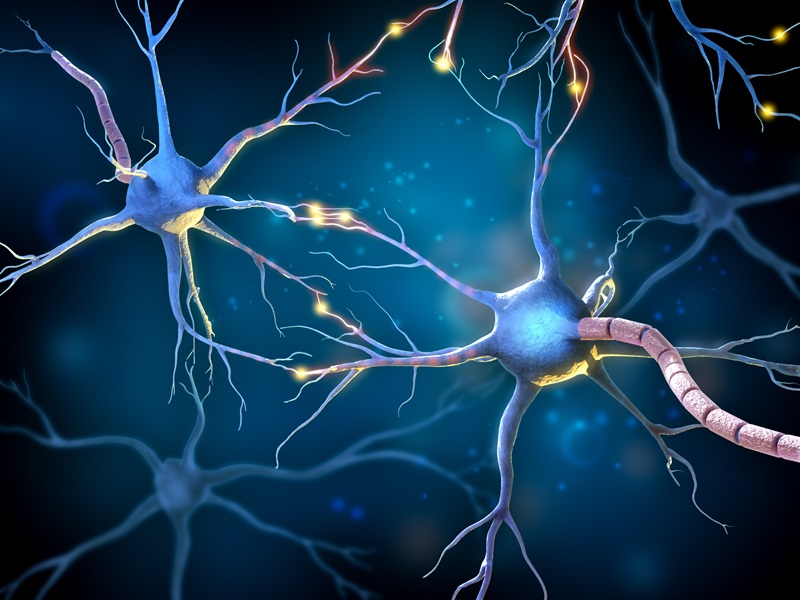
脳の認知機能は何歳から衰え始めるのでしょうか。米国の研究チームが1万9300人の脳スキャンを分析したところ、平均43.7歳で神経ネットワークが不安定になり始めることが分かりました。その後、66.7歳で最も急速に不安定化が進み、89.7歳で横ばいになったといいます。
チームの調べで、こうした脳の衰えには、ニューロン(神経細胞)におけるインスリン抵抗性(インスリンの作用に対して反応しにくくなる状態)が関連していることが明らかになりました。脳が老化するにつれて、インスリンがニューロンに及ぼす影響が小さくなり、エネルギーとして取り込まれるグルコース(ブドウ糖)が減少するそうです。その結果、脳のシグナル伝達が破壊されてしまうといいます。
そこでチームは、インスリン抵抗性の影響を受けることなくニューロンに燃料を供給することができる「ケトン」を参加者101人に投与しました。すると、特に40〜59歳の中年層において脳の老化が抑制されることが判明したといいます。つまり、40代から早期介入することで、加齢に伴う認知機能低下を予防できる可能性があります。
チームは研究成果を科学誌「米科学アカデミー紀要(PNAS)」に発表しました。

潰瘍性大腸炎の患者は腸内細菌由来の「胆汁酸」が不足していることが知られているそうです。スイスの研究チームが、特定の腸内細菌が潰瘍性大腸炎の治癒に重要な役割を果たすことを発見し、新たな治療法につながる可能性があると、医学誌EMBO Molecular Medicineに論文を発表しました。
チームが着目したのは、肝臓で作られた一次胆汁酸を、腸幹細胞の増殖と分化を刺激する二次胆汁酸(7α-脱ヒドロキシル化胆汁酸)に変換する腸内細菌「クロストリジウム・シンデンス」です。
潰瘍性大腸炎マウスにクロストリジウム・シンデンスを投与したところ、投与しない群に比べて腸内の炎症が減少し、腸壁の再生が促進したといいます。そしてその結果、マウスは潰瘍性大腸炎から早く回復することができたそうです。さらに潰瘍性大腸炎患者のデータを分析したところ、7α-脱ヒドロキシル化胆汁酸レベルの低下が、腸管上皮細胞の再生異常と強く相関することが分かったといいます。
潰瘍性大腸炎の従来の治療は炎症を抑えることに重点が置かれているそうです。チームは、有益な腸内細菌を使って胆汁酸のバランスを改善することが、腸の自然治癒力をターゲットにした新しい治療になる可能性あるとしています。

「私に見えている赤」と「あなたに見えている赤」は本当に同じなのでしょうか。色の感じ方は個人の内的体験であるため、この問いに答えることは困難であると考えられてきました。しかし、オーストラリアのモナシュ大学と東京大学の研究チームが、人は同じ赤色を見ている可能性が高いことを証明したと、科学誌iScienceに発表しました。
チームは、「あなたにとって〇〇をするのは、どのような感じがしますか?」と尋ねられたときのような、特定の経験を説明するために作られた用語「クオリア」という概念を活用し、この問いに挑んだそうです。
典型的な色覚(正常色覚)の426人と色覚特性(色覚異常)の257人に対し、93種類の色についてそれぞれの類似性を評価してもらう実験を行ったといいます。こうして集められたデータを分析したところ、正常色覚の人が見ている「赤」は、別の正常色覚の人が見ている「赤」と同じである可能性が高いことが示唆されたそうです。
同じタイプの色覚異常を有する人同士でも、同様の結果が示されたといいます。一方で、正常色覚群の「赤」と色覚異常群の「赤」は、同じではない可能性があるとのことです。

エボラ出血熱の治療が経口薬で可能になるかもしれません。米国の研究チームがサルの実験で有効性を確認したと、科学誌Science Advancesに論文を発表しました。
チームが使用したのは、新型コロナウイルス感染症向けに開発された点滴薬「レムデシビル」の経口タイプの「オベルデシビル」です。オベルデシビルは、ウイルスの複製に不可欠な酵素「ポリメラーゼ」を阻害します。
チームは、計13匹のアカゲザルとカニクイザルを人間の致死量の3万倍に当たる量のエボラウイルス(マコナ株)に暴露させました。そして、10匹に対してウイルス暴露の24時間後から1日1錠のオベルデシビルを10日間投与し、残りの3匹には何も治療をしなかったといいます。
その結果、オベルデシビルを投与したサルのうちカニクイザルの80%、より人間に近いアカゲザルは100%が生き残ったそうです。治療しなかったサルは3匹とも死んだといいます。
オベルデシビルは、サルの血液からエボラウイルスを排除するだけでなく、免疫応答を引き起こし、臓器の損傷を避けつつ抗体の産生を促すことが示されたとのことです。

国連児童基金(UNICEF)と世界保健機関(WHO)が、ヨーロッパと中央アジアの53カ国から成る「欧州地域」における麻疹(はしか)感染に関する報告書を公表しました。この地域では2024年に、はしか感染者が12万7350人と23年から倍増し、1997年以来最多になったそうです。感染者の40%以上が5歳未満の子どもだったといいます。
欧州地域は2024年の世界のはしか感染者の3分の1を占めており、中でも最も多かったのはルーマニアの3万692人、次いでカザフスタンの2万8147人でした。
はしかはワクチンの2回接種で97%の効果が得られます。しかし、新型コロナウイルス流行時にワクチンの接種率が低下し、現在も多くの国でコロナ前の水準には戻っていないといいます。
英BBCによると、2023年の推計で集団免疫を維持するために必要なワクチン接種率95%を達成したのは、ハンガリー、マルタ、ポルトガル、スロバキアの4カ国のみだったことが欧州疾病予防管理センター(ECDC)の調べで明らかになっているとのことです。

英国やアイルランドで、かき氷を溶かしたような「スラッシー」と呼ばれるフローズン飲料を飲んだ子どもが入院する事例が相次いでいるそうです。スラッシーには甘味料や凍結防止剤として「グリセロール(グリセリン)」が使われていることが多く、これが子どもに中毒を引き起こすといいます。
両国の研究チームが、スラッシーを飲んで救急診療を受けた2~7歳の子ども21人のデータを分析し、医学誌Archives of Disease in Childhoodに論文を発表しています。
それによると、調査した子どものほとんどが意識を失っており、血液酸性度の上昇と低血糖が認められたといいます。4人は脳スキャンが必要な状態で、1人はてんかん発作を起こしていました。その後、子どもたちは全員急速に回復したといいます。
高濃度のグリセロールは特に子どもにとって有害で、グリセロール中毒によってショック状態、低血糖、意識喪失が引き起こされる可能性があるそうです。両国の保健当局は、4歳以下の子どもにはグリセロール入りのスラッシーを与えないよう勧告していますが、チームはこの年齢を「8歳未満」に引き上げるべきだと提言しました。

定期的に献血をする人は、血液がんになりにくいかもしれない――。英国とドイツの研究チームが、献血によって造血幹細胞で血液がんリスク抑制につながる遺伝子変異が生じる可能性が示唆されたと、医学誌Bloodに論文を発表しました。
献血を行うと、失われた血液を補うために造血幹細胞が新たな血液細胞に分化します。これにより造血幹細胞に遺伝的多様性が生じる可能性があるのだそうです。
こうした影響を調べるためチームは、生涯の献血回数が100回を超える男性217人と10回未満の男性212人の血液を比較しました。参加者はみな60代で、健康だったといいます。
チームは、遺伝子変異を持つ造血幹細胞が増殖し、血液がんにつながる「クローン性造血(CH)」という現象に着目。分析の結果、両群間でCHの発生率に有意差は見られませんでした。
しかし、CHにおいて最も影響を受けるDNMT3A遺伝子の変異を詳しく調べたところ、定期的に献血を行う群には、血液がんのリスク上昇に関連しない特徴的な変異パターンがあることが明らかになったそうです。そして、この変異を持つ造血幹細胞をマウスに移植したところ、赤血球の産生が促進されたといいます。

重度の心不全を患う40代のオーストラリア人男性が、ドナーからの移植を待つ間、チタン製の人工心臓で100日間生き延びたそうです。チタン製人工心臓を装着した人の生存期間としては、最長記録だといいます。米CNNが報じました。
男性は昨年11月、シドニーのセントビンセント病院でオーストラリアでは初となるこの人工心臓を移植する手術を受け、今年2月に退院しました。チタン製人工心臓を埋め込んだ状態で退院した患者は世界で初めてだといいます。そして今月初め、心臓移植のためのドナーが見つかったため、男性は再び手術を受け、順調に回復しているそうです。
この人工心臓を開発したのは、米豪の医療機器メーカーBiVACOR社。米食品医薬品局(FDA)の早期フィージビリティ試験(実現可能性を分析する試験)では、これまでに5人の患者に対するチタン製人工心臓移植が成功しているといいます。心臓移植が必要なのに、ドナーを待つことができなかったり見つからなかったりする患者にとって、チタン製人工心臓が代替手段となる可能性があるとのことです。

HIV(エイズウイルス)の感染予防が年1回の注射で可能になるかもしれません。米国の研究チームが医学誌The Lancetに治験の結果を発表しました。チームが治験を行ったのは、HIVが細胞内で複製するのを阻害し、年1回の投与で暴露前予防(PrEP)の効果の維持が期待されている「レナカパビル(lenacapavir)」です。
チームはHIVに感染していない18~55歳の成人40人に対し、レナカパビルを筋肉内注射する第1相試験を実施しました。56週間後の参加者の血液を調べたところ、すでに第3相試験で有効性が確認されている年2回のレナカパビルの皮下投与よりも高い濃度のレナカパビルが検出されたといいます。また、深刻な副反応や安全性に対する懸念事項は認められなかったとのことです。
現在、HIV予防薬として使用されているのは、毎日服用する錠剤や8週間に1回投与する注射で、継続が難しいことが指摘されています。レナカパビルの投与が年1回で済めば、利便性が飛躍的に向上し、既存の予防薬以上に広く普及する可能性が期待されています。

風力発電設備からの騒音が原因で生じる不眠や不安、頭痛、めまい、吐き気などの健康被害は「風車症候群」や「風車病」と呼ばれます。ポーランドの研究チームが学術誌Humanities and Social Sciences Communicationsに、風車騒音が人間のメンタルヘルスに悪影響を与えるとの証拠は見つからないとの研究成果を発表しました。
チームは、18~25歳の健康な大学生ボランティア45人に対し、目的を伏せた状態で交通騒音や風車騒音を聞かせ、脳や精神への影響を調査しました。風車騒音を聞いた時、ほとんどの学生がその音を「何らかの雑音」と表現し、騒音の発生源が風車であると特定できた人はいなかったといいます。
調査の結果、交通騒音に比べて風車騒音の方が「煩わしく、ストレスを感じる」と報告した学生は一人もいなかったそうです。また、交通騒音と風車騒音を聞いている時の脳波に違いは見られず、調査中に精神衛生上の問題が認められることもなかったそうです。
これらのことからチームは、風車の騒音がメンタルヘルスの問題を引き起こす可能性は低いと結論付けました。
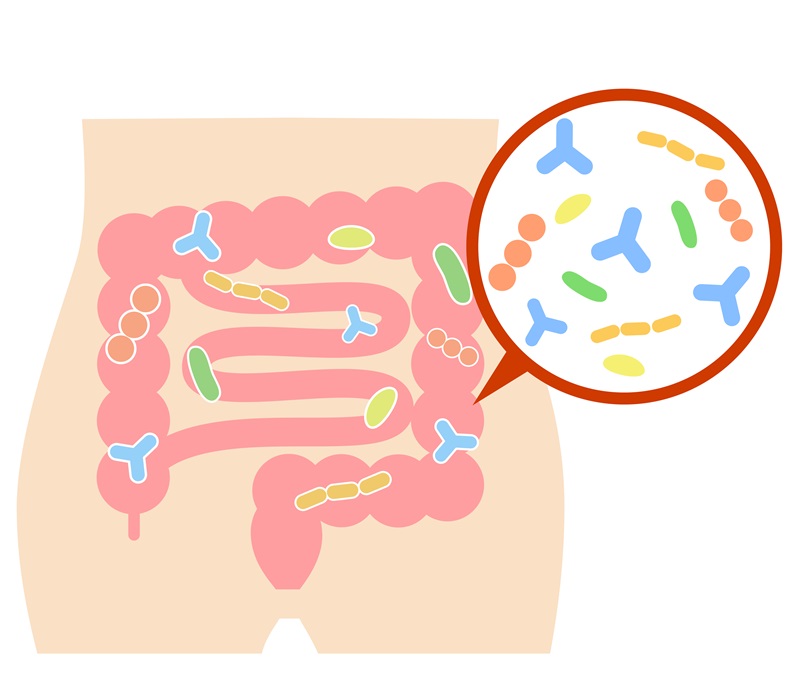
「多発性硬化症(MS)」患者の重症度には2種類の腸内細菌の組成比が深く関わっている可能性があるそうです。The Conversationに米アイオア大学の微生物叢の専門家が報告しました。
MSは免疫系が誤って脳や脊髄を攻撃する神経疾患で、世界で280万人以上の人が罹患しているといいます。MSの専門家は、腸内細菌がMSと深く関わっていると考えているのですが、これまでは一貫した研究結果が出ていなかったそうです。
米国の研究チームが、MS患者の腸内細菌叢(腸内フローラ)の組成を分析したところ、MSでない人に比べて「ブラウティア菌」という細菌が多いことが分かったそうです。また、MSマウスの腸内では、「ビフィズス菌」が少なく「アッカーマンシア菌」が多いことも明らかになったといいます。
そこでチームは、抗菌薬で腸内細菌をすべて除去したMSマウスにブラウティア菌を与えて観察しました。すると、腸の炎症が激しくなり、MS症状が悪化したそうです。
またMSマウスは、MS症状が現れる前から、ビフィズス菌の減少とアッカーマンシア菌の増加が確認され、この組成比率はMS発症後の重症度の上昇に関連していたといいます。こうした腸内細菌叢の不均衡は、MS患者でも認められたとのことです。

ダイエットで人気の食事法である「低炭水化物食(糖質制限食)」には、大腸がんの発生を促進するリスクがあるそうです。カナダの研究チームがそのメカニズムを解明したと、科学誌Nature Microbiologyに研究成果を発表しました。
チームは、大腸がんに関連するとされる腸内細菌をマウスに定着させた上で、通常食、低炭水化物食、脂肪や砂糖を多く含む西洋食のいずれかを与えて観察しました。その結果、DNAに損傷を与える遺伝毒性物質「コリバクチン」を産生する大腸菌と低炭水化物食が組み合わさると、大腸がんにつながるポリープの成長が進むことが明らかになったそうです。
食物繊維不足による腸の炎症で腸内細菌叢(腸内フローラ)の組成が変化し、コリバクチン産生大腸菌が増えやすい環境になるといいます。
また、低炭水化物食マウスは、腸内細菌が腸管上皮細胞に侵入するのを防ぐ粘液層が、他のマウスと比べて薄いことが分かったそうです。粘液層が薄いと、細胞に到達するコリバクチンが増え、腫瘍が成長しやすくなるといいます。低炭水化物食に水溶性食物繊維を加えると、発がん作用を抑制できる可能性があるとのことです。

数多くの研究で「関連性はない」と結論付けられているワクチンと自閉症の関連性について、米疾病対策センター(CDC)が改めて研究を行うそうです。米国の複数のメディアが報じています。
CDCを管轄する米保健福祉省(HHS)の長官に就任したロバート・ケネディ・ジュニア氏は長年、ワクチンの安全性について懐疑的な姿勢を示してきました。米ABC Newsによるとケネディ氏は、かつて1万人に1人だった自閉症児の割合が、現在は34人に1人に急増していると主張しています。ただし、ケネディ氏が「1万人に1人」という数字をどこから引用したのかは不明だそうです。
CDCのデータによると、8歳までに自閉症と診断される割合は2000年に150人に1人だったのに対し、20年には36人に1人に増加しています。しかし、こうした増加は、医師や保護者の間で自閉症に対する認識が高まったことに起因する可能性があるといわれています。
HHSの広報担当官は、ワクチンと自閉症の関連性を調べる取り組みについて、「あらゆる手段を講じる」としているそうです。ただし、具体的な調査方法や、これまでの既存研究との違いに関しては明言を避けているとのことです。

米国南部で麻疹(はしか)の感染者の拡大が止まらないようです。米NBC Newsによると、テキサス州で198人の感染者が明らかになっており、23人が入院し、6歳の子供1人が死亡。隣接するニューメキシコ州で30人の感染者が報告され、そのうち成人1人が死亡した可能性があるとのことです。検査を控える人がかなりおり、実際にはもっと多くの感染者がいる可能性が高いといいます。
はしかはワクチンの2回接種で97%の効果が得られます。一方で、今回感染が確認されている患者の大半がワクチン未接種か、ワクチン接種歴不明だそうです。
多くの感染者が出ているテキサス州ゲインズ郡では、宗教上の理由などでワクチン接種の免除を受けている人の割合が約18%にも上るといいます。
また、ビタミンA欠乏症の人がはしかの症状や合併症が重くなることから、厚生長官のロバート・ケネディ・ジュニア氏がビタミンAを豊富に含むタラの肝油の摂取を勧めているそうです。しかし専門家は、ほとんどの人が十分な量のビタミンAを取っており、さらに摂取しても効果はないと指摘しているとのことです。

嘔吐(おうと)や下痢などの急性胃腸炎症状を起こすノロウイルスに対するワクチンの開発が進んでいるようです。米国の研究チームが治験を行い、高齢の人に安全かつ有効な可能性が示されたと、医学誌Science Translational Medicineに論文を発表しました。
チームが治験を行ったのは、「VXA-G1.1-NN」という錠剤型の経口ワクチンです。55~80歳の健康な参加者65人を対象に第1b相試験を実施しました。その結果、副反応について、ワクチンの用量に関係なく十分に患者が耐えられる程度であることが確認されたといいます。重篤な有害事象や日常生活に支障がある程度(グレード3)の副反応を呈した人はいなかったとのことです。
また、ワクチンの服用によって、ノロウイルスの遺伝情報を取り囲む主要なタンパク質(カプシド)に特異的な抗体(免疫グロブリンG:IgG、免疫グロブリンA:IgA)が血清中で増加することも示されました。こうした血清抗体の増加は、210日間持続したそうです。
さらに、高用量ワクチンを服用した群では、ノロウイルスを中和する可能性がある抗体が有意に増加したといいます。なお、ワクチン服用で、粘膜における強固な免疫応答が誘導されることも明らかになったとのことです。

膣内の細菌叢の乱れで炎症が起こる「細菌性膣症(BV)」の再発の多くが、パートナーとの性行為による再感染が原因で起きているかもしれません。BVは性感染症(STI)ではないとされてきましたが、オーストラリアの研究チームがそれを否定する研究成果を医学誌New England Journal of Medicineに発表しました。
チームは男女のカップル164組を2群に分けて調査を行いました。男女ともに他のパートナーはおらず、女性はみなBVを患っていたといいます。
第一選択薬として推奨されている抗菌薬を女性にのみ投与した群は、12週間以内に63%の女性がBVを再発したそうです。一方、女性を同じ抗菌薬で治療した上で、男性には1日2回、経口抗菌薬と陰茎の皮膚に塗る抗菌薬を7日間使用させたところ、BVの再発率は35%に抑制されたといいます。
BVはSTIの一種であり、パートナーの男性も一緒に治療することで再発リスクが抑えられる可能性が示されました。BVは世界の女性の3分の1が罹患する一般的な疾患で、半数が再発を経験するそうです。

解熱鎮痛薬や抗血小板薬として広く使用される「アスピリン」を常用すると、がんによる死亡リスクが低下するようです。英国の研究チームがそのメカニズムを解明したとして、科学誌Natureに論文を発表しました。がんの転移に対応する免疫システムをアスピリンが強化する可能性があるそうです。
チームがマウスを使って調査したところ、がん細胞が元の腫瘍から離れて別の場所に転移する際に、アスピリンがそれを妨げる重要な役割を果たすことを発見したそうです。
がん細胞の転移が起きそうになると、免疫細胞の一種である「T細胞」が新たな場所に根付こうとする転移細胞をすかさず攻撃します。しかし、血液の凝固を助ける血小板が、こうしたT細胞の働きを妨害してしまうことをチームが突き止めたそうです。そして、アスピリンを投与したマウスにおいては、血小板の凝集が抑制されるため、T細胞の働きが妨害されず、がん細胞を攻撃したといいます。
英BBCによると、早期がんの再発をアスピリンで防げるかどうかを調べる治験が英国で始まっているとのことです。

「中~高強度の身体活動」をほんの少しでも行うと、認知症を発症するリスクを抑制できる可能性があるそうです。米国の研究チームが医学誌Journal of the American Medical Directors Associationに論文を発表しました。
チームは平均年齢63歳の成人8万9667人を4.4年にわたり追跡調査しました。身体活動のレベルを評価するため、参加者は手首に加速度計を装着したといいます。
その結果、運動を全くしない人と比較した認知症発症リスクについて、1週間当たりの中~高強度の身体活動が▽35分未満の人で41%▽35~69.9分の人で60%▽70~139.9分の人で63%▽140分以上の人で69%――それぞれ低下することが分かりました。
また、加齢により心身が老い衰えた状態である「フレイル」を持つ人にも同様の認知症リスク抑制効果が認められたといいます。
チームは、いくつになったとしても、そしてどんなに短い時間だとしても、中~高強度の身体活動を行うことによる恩恵を受けられる可能性があると強調しています。
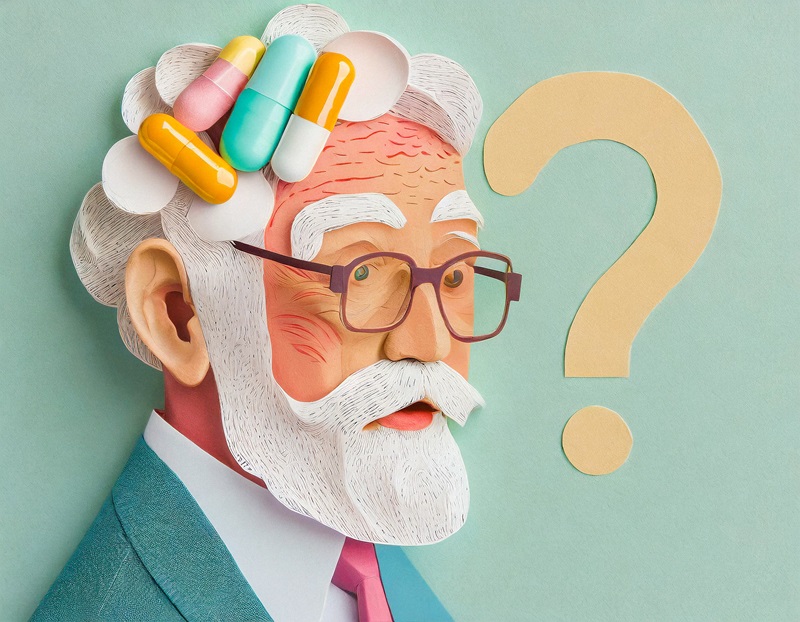
認知症患者に一般的に処方される抗うつ薬が、認知機能の低下を促進させるかもしれません。スウェーデンの研究チームが医学誌BMC Medicineに研究成果を発表しました。
チームは、2007~18年に新たに認知症と診断された患者1万8740人のデータを分析しました。患者の平均年齢は78.2歳で、22.8%が抗うつ薬を少なくとも1回処方されていたといいます。
処方された抗うつ薬のうち、64.8%がSSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)で、2.2%がTCA(三環系抗うつ薬)、2.0%がSNRI (セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)、31.0%がその他の抗うつ薬でした。
分析の結果、抗うつ薬を使用した人は、そうでない人に比べて認知機能の低下が早く進むことが分かったそうです。こうした関連は、特に重度の認知症患者で強く見られたといいます。
さらに、SSRIの使用量が多いほど認知機能の低下率が大きくなり、重度の認知症や骨折、全死因死亡のリスクも高くなることが明らかになったとのことです。

低カロリーの食品や飲料に広く使われる人工甘味料「アスパルテーム」は動脈硬化の一因になり、脳卒中や心臓発作につながる可能性があるそうです。スウェーデンの研究チームが科学誌Cell Metabolismに論文を発表しました。
チームは、アスパルテームを0.15%含有するエサをマウスに12週間与え、その影響を調べました。これは、人間がダイエットソーダを1日に3缶飲むのに相当するといいます。実験の結果、アスパルテームを含むエサを食べたマウスは、そうでないマウスに比べて動脈内の脂質などの塊(プラーク)が増え、高レベルの炎症が起きることが分かりました。
プラークが動脈内に蓄積すると「アテローム性動脈硬化」を引き起こします。また、炎症は動脈硬化に深く関わるとされています。
さらにチームは、アスパルテームが体内に入ると血中インスリン値が急上昇し、その結果、プラークの増大が進むことを確認したそうです。そして、インスリン値の上昇は、炎症を引き起こすタンパク質(ケモカインのCX3CL1)が関連する免疫系を活発にすることを突き止めたといいます。

特殊な抗体の保有者で、60年以上にわたる献血によって240万人もの乳児の命を救ったというオーストラリア人男性が2月17日に88歳で亡くなったそうです。AP通信などが報じました。
亡くなったのはジェームズ・ハリソンさんで、彼の血液の液体成分である血漿(けっしょう)には「抗D」と呼ばれる特殊な抗体が含まれていたそうです。この抗体が、「新生児溶血性疾患」という母親と胎児の血液型不適合などによって、母体の免疫系が胎児の赤血球を攻撃してしまう病気を防ぐための薬剤の製造に使われたといいます。
ハリソンさんは、18歳になった日から81歳で献血から退くまでの間に、計1173回も献血に協力したとのことです。世界で最も多くの血漿を提供したとして2005年に当時のギネス世界記録を更新したといいます。こうした功績から、ハリソンさんは「黄金の腕を持つ男」と呼ばれていました。
オーストラリアには抗D抗体ドナーが200人おり、年間4万5千人の母親とその赤ちゃんを救っているとのことです。

スマートフォンには依存性があることが分かったそうです。ドイツの研究チームが科学誌Computers in Human Behaviorに研究成果を発表しました。
チームは、18~30歳の25人に対し、72時間にわたって必要な連絡と仕事に関連すること以外に、スマホの使用を控えてもらう実験を行いました。神経活動への影響を調査するため、実験の前後にMRIスキャンと心理検査を実施したといいます。
スマホの使用を控えた72時間後に参加者にスマホの画像を見せたところ、報酬に関する情報処理や渇望に関連する脳領域に変化が認められたそうです。この変化はニコチンやアルコールなどの物質の依存につながる脳信号といくつかの点で類似していたといいます。
また、こうした脳の変化は、神経伝達物質のドーパミンやセロトニンに関連していたそうです。これらの神経伝達物質は、気分の調整など多くの脳機能に関わっています。
一方、心理検査では、スマホの使用を制限されていても、参加者の気分の変化や何かに対する激しい欲求は見られなかったとのことです。
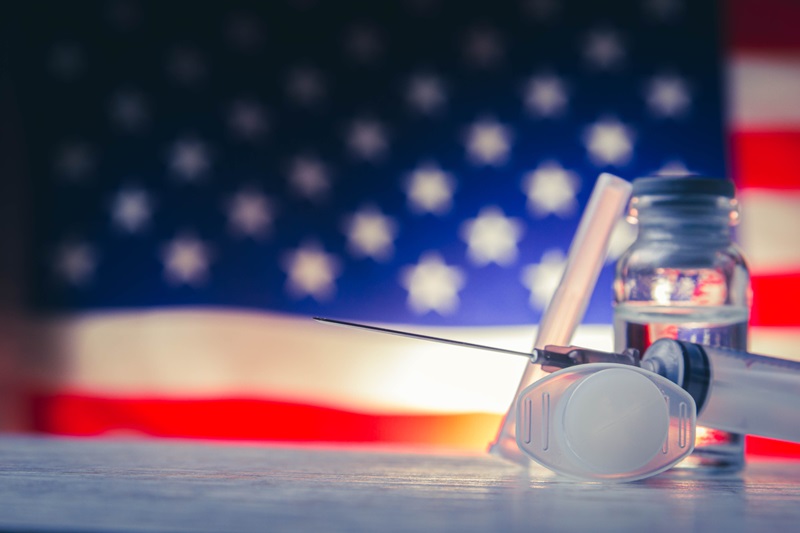
米テキサス州で麻疹(はしか)の感染が広がっています。ワクチン懐疑論者として知られる米厚生(米保健福祉省:HHS)長官のロバート・ケネディ・ジュニア氏が、ワクチン接種を推奨するとも取れる意見を表明する事態になっています。
米CNNによると、テキサス州では1月下旬以降、146人のはしか感染者が確認されており、20人が入院し、学齢期の子ども1人が死亡しました。米国で、はしかによる死者が出たのは2015年以来10年ぶりだといいます。感染者の大半がワクチン未接種か、ワクチン接種歴不明だそうです。
はしかはワクチンの2回接種で97%の効果が得られますが、全米の接種率はHHSが目標とする95%を4年間下回っているとのことです。
今回の流行を受け、ケネディ氏は3月2日、「保護者は子どもたちのために、ワクチンを受けさせるという選択肢を理解するため医療機関に相談するべき」との意見を表明したといいます。
ケネディ氏はワクチン接種を明確に推奨しなかったものの、「子どもをはしかから保護するだけでなく、集団免疫にも寄与するため、医学的な理由でワクチンを接種することができない人々を守ることにもつながる」との考えを示したそうです。

抗うつ薬として一般的な「SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)」が、感染症や敗血症の予防に有効な可能性があるそうです。米国の研究チームが科学誌Science Advancesに研究成果を発表しました。
最近の研究でSSRIの使用者は新型コロナウイルス感染症にかかっても重症化しにくく、コロナ後遺症にもなりにくいことなどが分かっているそうです。
このメカニズムを解明しようとチームはまず、SSRIの「フルオキセチン(商品名:プロザック)」を投与したマウスの群とそうでない群をそれぞれ細菌に感染させる実験を行いました。その結果、フルオキセチン群は敗血症や多臓器障害、死亡から保護されることが分かったそうです。
次にチームは、感染から8時間後の細菌数を測定。フルオキセチン群は細菌数が少なく、重症度が低いことから病原体を殺傷する作用があることが分かったといいます。さらに、フルオキセチン群は抗炎症性サイトカイン(炎症を抑制するタンパク質)の「インターロイキン-10(IL-10)」が多く発現していました。
IL-10が敗血症で起こる症状を予防する可能性があり、フルオキセチンには感染によるダメージから臓器や組織を保護する作用があることも示されました。

アフリカ中部のコンゴ民主共和国(コンゴ)で多数の死者が出ている謎の病気について、WHO(世界保健機関)の緊急対応責任者は2月28日、何らかの中毒が原因の可能性が高いとの見方を示したそうです。地元当局もWHOに対し、村の水源に関連する中毒の疑いが非常に強いと述べたといいます。米CBS Newsなどが報じました。
コンゴ北部では、コウモリを食べた子ども3人がエボラ出血熱やマールブルグ病に似た出血熱の症状を呈して1月下旬に死亡したのを皮切りに、同様の症状で5週間に66人が死亡したそうです。主な症状は発熱、嘔吐(おうと)、内出血で、死亡者のほとんどが発症から48時間以内に死に至ったといいます。
2月13日に発表された検査結果によると、初期患者の検体の半数からマラリアの陽性反応が出たものの、エボラウイルスやマールブルグウイルスは検出されなかったそうです。WHOは髄膜炎が原因である可能性も視野に入れ、患者が発生した地域の食品や水を検査するなど、現地でさらなる調査を行っているとのことです。

きのこがインフルエンザのダメージから体を守ってくれる可能性があるそうです。カナダの研究チームが医学誌Nature Immunologyに論文を発表しました。
きのこには食物繊維の一種「β-グルカン」が多く含まれます。これまでの研究でβ-グルカンは免疫機能を高める効果を持つことが知られているといいます。チームはβ-グルカンがウイルスの攻撃による影響を軽減するのではないかと考えたそうです。
そこで、マウスにβ-グルカンを投与し、その後にA型インフルエンザウイルスに感染させる実験を行ったといいます。その結果、β-グルカンを投与されたマウスは、インフルエンザにかかった際の重症化や死亡のリスクが低くなることが分かったそうです。
また、β-グルカンが免疫細胞の一種である「好中球」を、過剰な炎症を抑制するように再プログラム化し、合併症や肺炎のリスクを低減することも明らかになったといいます。さらに、β-グルカンによるこうした効果は、最大1カ月にわたり持続する可能性も示されたとのことです。

インドの17歳の少年が、腹部に「寄生」していた双子を取り除く手術を受けたそうです。胎内で発育不全になった双子の一方が、もう一方に結合した状態で生まれる「寄生性双生児」と呼ばれる症例で、発生する確率は分娩(ぶんべん)10万件に1件未満だといいます。英BBCが報じました。
少年の体には寄生する双子の脚2本、尻、外性器がくっついており、これらが少年の腹部から飛び出していたそうです。手術を実施したチームがスキャン検査を行ったところ、寄生する双子は少年の胸骨(胸の中央にある縦長の骨)に結合しており、少年の胸部の血管から血液が供給されていることが分かったといいます。
寄生性双生児の症例自体が珍しい上に、この少年のように成長してから手術が行われるのは極めてまれだとのことです。チームの医師によると、双子で共有している血管や神経、組織が網の目のようになっており、それらを切り離さなくてはならなかったそうです。少年の臓器や組織を傷つけないように注意をしながら、約2時間半の手術が行われたそうです。少年は手術後、順調に回復しているといいます。

米国の研究チームが、1990~2021年の世界の自殺に関するデータを分析し、医学誌The Lancet Public Healthに研究成果を発表しました。
2021年の自殺による死者数は世界の死因の第21位で、エイズよりも上位だったといいます。そして、21年の自殺による年齢調整死亡率(年齢構成がそろうように調整した死亡率)は10万人当たり9人で、計74万6千人と推計されるそうです。これは、43秒に1人が自殺によって死亡していることになるとのことです。
1990年は10万人当たり14.9人だったため、約40%減と改善したことになります。しかし、地域や性別、年齢によって差は大きいといいます。
地域別に見ると、自殺死亡率が最も低下したのは東アジアで66%減。自殺死亡率が特に高かったのは、東ヨーロッパやサブサハラ・アフリカの南部や中部だったそうです。
また、男性は女性に比べて自殺で死亡する可能性が2倍以上高い反面、女性は自殺を企てる可能性が男性より49%高いことも分かったといいます。自殺による死亡時の平均年齢は、30年間で男性は43.0歳から47.0歳に、女性は41.9歳から46.9歳にそれぞれ上がったとのことです。

WHO(世界保健機関)はアフリカ中部のコンゴ民主共和国(コンゴ)で、謎の病気による死者が出ていると発表しました。2月15日時点で419人の患者が確認され、53人が死亡しているそうです。主な症状は発熱、嘔吐(おうと)、内出血で、発症から死亡までの間隔はほとんどのケースで48時間以内だといいます。
最初の感染者は1月21日に、コンゴ北西部に位置するボロコで発生したそうです。コウモリを食べた子ども3人が発症し、死亡しました。その後、2月9日にはボロコの北東にあるボマテでも流行が発生したといいます。
ボマテの患者13人から採取した検体はいずれも、エボラ出血熱やデング熱、マールブルグ病、黄熱など既知の病気には陰性反応を示したとのことです。ただ、一部の検体はマラリア検査で陽性が出たといいます。
AP通信によると、コンゴでは昨年も謎の病気が流行し数十人の死者が出ました。しかし、後にマラリアが原因の可能性が高いと判明したそうです。アフリカの野生動物を食べる地域では、動物から人間に感染する病気の発生が10年間で60%超も増加しているとのことです。

ドイツの研究チームが「甘いものは別腹」のメカニズムを突き止めたと、科学誌Scienceに論文を発表しました。
チームは、砂糖に対するマウスの反応を調査したそうです。満腹時にマウスに砂糖を与えたところ、脳内の特定の領域にある神経細胞において、神経伝達物質「β-エンドルフィン」の分泌が促されることが分かったそうです。β-エンドルフィンは、高揚感や鎮痛効果をもたらし、医療用麻薬のモルヒネと同じような作用をすることから「脳内麻薬」とも呼ばれています。
β-エンドルフィンの作用を阻害すると、満腹のマウスは砂糖を取らなくなったそうです。一方で、空腹のマウスのβ-エンドルフィンを阻害しても、こうした影響は見られなかったといいます。
この脳領域の活性化は、マウスが砂糖を食べる前の、砂糖を認識した段階で起こることも判明したそうです。これは、砂糖を食べたことのないマウスの脳でも同様に起こり、砂糖を初めて口にすると即座にβ-エンドルフィンが放出されたといいます。追加で砂糖を取ると、β-エンドルフィンの放出が増強されたとのことです。
ヒトに対する調査でも、マウスと同じ脳領域が砂糖に対して反応することが脳スキャンで示されたそうです。
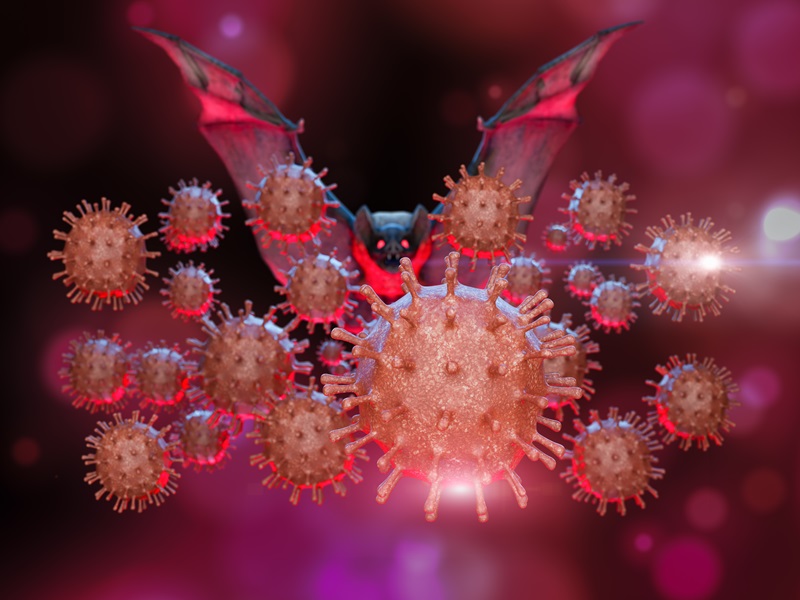
中国の武漢ウイルス研究所などの研究チームが、コウモリから新種のコロナウイルスを発見したと、科学誌Cellに発表(2月18日付)しました。このウイルスはHKU5-CoV-2と呼ばれ、ヒトの細胞に感染する可能性があるそうです。
チームによると、HKU5-CoV-2は、中東呼吸器症候群(MERS)を引き起こすウイルスと同じメルベコウイルスに属しています。実験では、HKU5-CoV-2がヒトの細胞の表面に存在するACE2受容体を介して細胞に侵入する可能性があることが分かったそうです。
これは、新型コロナウイルス感染症を引き起こすウイルス(SARS-CoV-2)がヒトの細胞に感染する経路と同じです。ただし、HKU5-CoV-2はSARS-CoV-2ほど容易にヒト細胞に侵入することはできないことも明らかになったといいます。
米ABC Newsによると、これを受け米疾病対策センター(CDC)は24日、HKU5-CoV-2は今のところ懸念材料にはならないとの見解を出したそうです。ヒトの感染は確認されておらず、現時点ではHKU5-CoV-2が公衆衛生に脅威を与えると考えるべき理由はないといいます。

米疾病対策センター(CDC)は20日に公表した「疫学週報(MMWR:Morbidity and Mortality Weekly Report)」で、鳥インフルエンザウイルス(H5N1型)が飼い主から猫に感染したとみられる2例を報告しました。いずれの症例も2024年5月にミシガン州で発生しました。
一つ目の症例は、室内飼いの5歳のメス猫が食欲不振、毛づくろい頻度の減少、見当識障害、無気力、神経機能の低下などの症状を呈したといいます。緊急治療が行われたものの症状は進行し、4日以内に安楽死させたそうです。そして、死後の検査で鳥インフル感染が判明しました。この家に住む家族の1人は酪農場に勤務していたといいます。ただ、検査を拒否したため、感染の有無は不明とのことです。
二つ目の症例は生後6カ月のオス猫で、食欲不振、無気力、顔のむくみ、活動低下などの症状が現れ、24時間以内に死んだそうです。飼い主は生乳を運ぶ仕事に従事しており、乳牛への鳥インフル感染が確認された農場にも出入りしていたそうです。感染した猫は、生乳に汚染された飼い主の作業着の中に頻繁に潜り込んでいたといいます。猫に症状が現れる前、飼い主は目の炎症を感じていたものの、鳥インフル検査は拒否したとのことです。
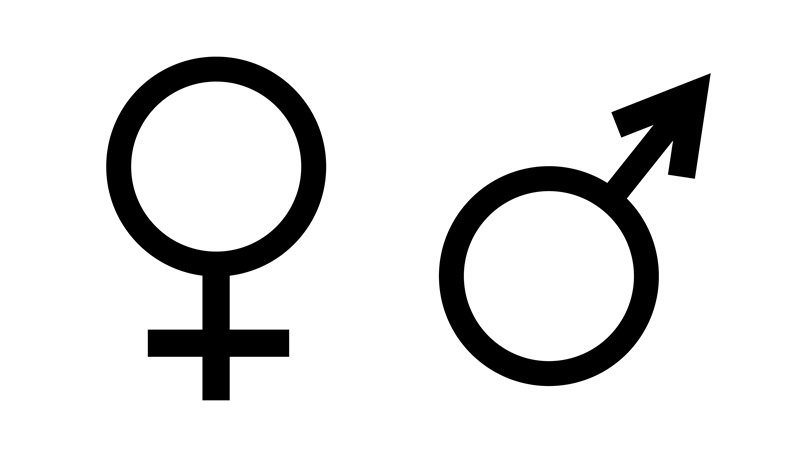
ロバート・ケネディ・ジュニア氏が長官に就任したばかりの米保健福祉省(HHS)は19日、性別に関する定義について新たな指針を明らかにしました。米国の各メディアが報じました。
新指針は、トランプ大統領が1月20日に署名した「ジェンダー・イデオロギーの過激主義から女性を守り、連邦政府に生物学的な真実を取り戻す」と題する大統領令に基づくものです。トランプ氏は「性別は男女の二つのみ」と主張しており、多様性などを重視したバイデン前政権の立場を否定する姿勢を明確にしています。
米CNNによると、HHSが公表した指針では、sex(性別)を「人の不変の生物学的分類で、男または女のいずれか」とした上で、「female(女):卵子を作るという生物学的機能の生殖器系を特徴とする性別の人」と「male(男):精子を作るという生物学的機能の生殖器系を特徴とする性別の人」に分けています。そして、femaleについては成人を「woman(女性)」、未成年を「girl(女子)」と定義。maleの成人を「man(男性)」、未成年を「boy(男子)」とするとしています。
この新たな定義について一部の専門家からは、「科学に基づいていない」などとして厳しい批判の声が上がっているそうです。

膵臓(すいぞう)がんは発見や治療が難しく、致命的ながんの一つといわれています。米国の研究チームが、患者個人に合わせたmRNAワクチンの治験を行い、治療に有効な可能性があると、科学誌Natureに発表しました。
チームは、手術可能な膵管腺がん(PDAC)と診断された患者16人を対象に第1相試験を実施したそうです。まず患者に腫瘍の切除手術を行い、次に個人個人の腫瘍から採取した遺伝物質を利用して、免疫系にがん細胞を攻撃するよう教える「個別化mRNAワクチン」を設計したといいます。患者はワクチンに加えて、標準治療である化学療法と免疫療法を受けたとのことです。
治療の結果、16人のうち8人がワクチンに応答し、腫瘍を標的とする免疫細胞のT細胞が誘導されたそうです。チームの推計によると、このT細胞は平均8年近く生き残るといいます。さらにこれらのT細胞のうち20%は数十年にわたり機能する可能性があるとのことです。
なお3年間の追跡期間中に、ワクチンに応答した患者8人のうち2人、ワクチンに応答しなかった患者8人のうち7人が、それぞれがんを再発したそうです。

フィリピンでデング熱患者が急増しているそうです。そのような中、デング熱対策として、マニラ首都圏に位置するマンダルヨン市のアディションヒルズ地区で、蚊やボウフラ(蚊の幼虫)5匹ごとに1フィリピンペソ(約2.6円)と交換する取り組みが始まったといいます。
AP通信によると、フィリピンでは今年、2月1日時点で2万8234人のデング熱感染者が確認されており、前年同期比で40%増加しているそうです。マンダルヨン市の近隣のケソン市では、デング熱の流行宣言も出されたとのことです。人口10万人を抱えるアディションヒルズ地区では衛生状態の改善などの感染対策が行われてきましたが、今年に入り感染者が42人に急増し、学生2人が死亡したといいます。
こうした状況を受け、アディションヒルズの地区長は、デング熱を媒介する蚊に「懸賞金」をかける異例の試みを開始したそうです。捕獲した蚊やボウフラを住民が役場に持ち込むと、現金と交換される仕組みとのことです。蚊やボウフラの生死は問わないといいます。
しかし、換金目的で蚊を養殖する人が出てくる可能性があるとして、懸念の声も上がっているとのことです。

血液がんの治療に用いられる「CAR-T細胞療法」は小児に発生する固形がんの一種である「神経芽腫」にも効果があるかもしれません。米国の研究チームが、医学誌Nature Medicineに治験の結果を発表しました。
CAR-T細胞療法は、患者自身の免疫細胞(T細胞)を遺伝子改変でがんへの攻撃力を高めて投与する治療法です。
チームは2004~09年に神経芽腫の小児患者19人を対象にCAR-T細胞療法の第1相試験を実施したそうです。この試験でCAR-T細胞療法の安全性は確認されたものの、治療から2カ月~7年の間に12人が神経芽腫の再発が原因で死亡したといいます。
残りの7人のうち5人は、治療から13年以上経過観察が続けられました。そしてこのうちの1人は、18年以上にわたり他の治療を受けることなく寛解状態が続いていることが分かったそうです。さらに、この患者は健康な赤ちゃんを2人出産したことも明らかになりました。
なお、当時のCAR-T細胞技術は第一世代と呼ばれるもので、現在はより改良された技術が使われているとのことです。

妊婦にも広く使われている解熱鎮痛剤「アセトアミノフェン」を母親が妊娠中に使用すると、生まれた子どもの注意欠如・多動症(ADHD)のリスクが高まる可能性があることが分かったそうです。米国の研究チームが科学誌Nature Mental Healthに研究成果を発表しました。
チームは、アフリカ系アメリカ人の母子307組を調査したそうです。その結果、妊娠13~24週のときに採取した母親の血液からアセトアミノフェン代謝物が検出された子どもは、そうでない子どもに比べて8~10歳までにADHDと診断される可能性が3.15倍高いことが明らかになったそうです。こうした関連は、男児より女児に強くみられたといいます。
さらに、チームは307人の母親のうち174人の胎盤組織を分析しました。すると、アセトアミノフェンへの暴露とADHD診断は、胎盤における免疫系やエネルギー代謝に関与する遺伝子発現の変化に関連していることが明らかになったといいます。
アセトアミノフェンによって胎盤における遺伝子発現が変化することで、子どものADHDリスクに影響が及ぶ可能性があるようです。
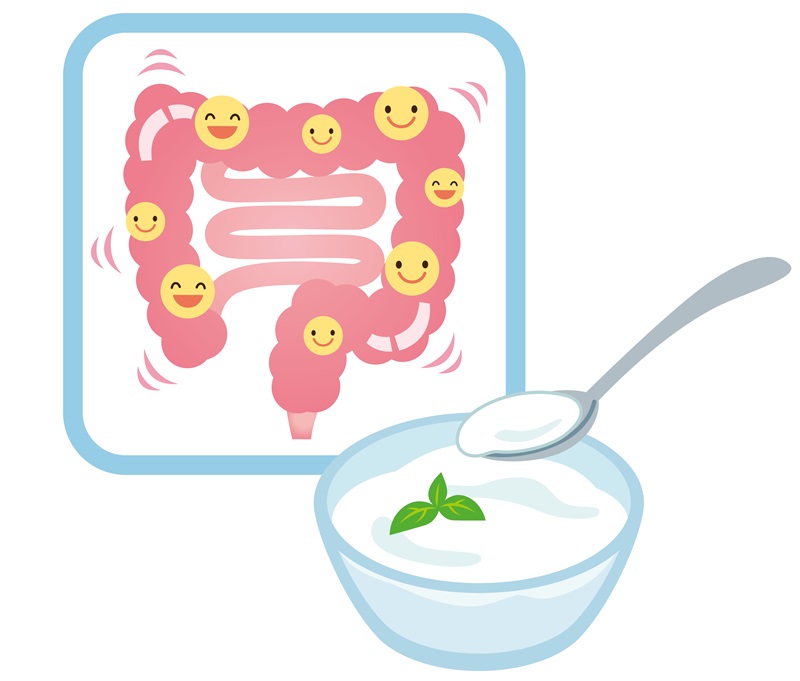
習慣的にヨーグルトを食べると、特定の種類の大腸がんの発症率が低下する可能性があるそうです。米国の研究チームが女性看護師12万1700人と男性医療従事者5万1529人を数十年にわたって追跡したデータを分析し、科学誌Gut Microbesに発表しました。
チームが調べたところ、対象者の中から3079件の大腸がん症例が見つかったそうです。このうち1121例から、腫瘍組織中のビフィズス菌のDNA量に関する情報が入手できたといいます。346例(31%)からはビフィズス菌が検出され、775例(69%)からは検出されなかったとのことです。
そして、大腸がんとヨーグルト摂取量の関連を調べたところ、ヨーグルトを週に2回以上食べる人は、ビフィズス菌陽性の大腸がんを発症するリスクが20%低くなることが分かったそうです。
ビフィズス菌陽性の大腸がんの中でも、生存率が悪いとされる「近位(右側)結腸がん」の発生が特に少なかったといいます。ヨーグルトを長期にわたって食べることでビフィズス菌をはじめとする腸内細菌叢が変化し、がん発症リスクが抑制されるようです。

カリウムを含む塩(減塩しお)を食生活に取り入れることで、脳卒中の再発を予防できる可能性があるそうです。中国などの研究チームが、医学誌JAMA Cardiologyに研究成果を発表しました。
チームは中国北部の農村に住む脳卒中既往歴がある患者1万5249人を平均61.2カ月にわたって追跡したデータを分析しました。その結果、「塩分(塩化ナトリウム)」の25%を「塩化カリウム」に置き換えた「減塩しお(低ナトリウム塩代替品:LSSS)」を使用した群は、普通の塩を使用した群に比べて脳卒中を再発するリスクが14%低くなることが分かったそうです。
特に出血性脳卒中への影響が大きく、普通の塩を使用した群より減塩しおを使用した群は30%リスクが減少したといいます。死亡率についても、減塩しおを使用した群で12%低くなることが明らかになりました。中でも脳卒中関連死については21%減少することが分かったそうです。
一方、カリウムの血中濃度が非常に高くなる「高カリウム血症」を発症するリスクについては、両群間で有意差は認められなかったとのことです。
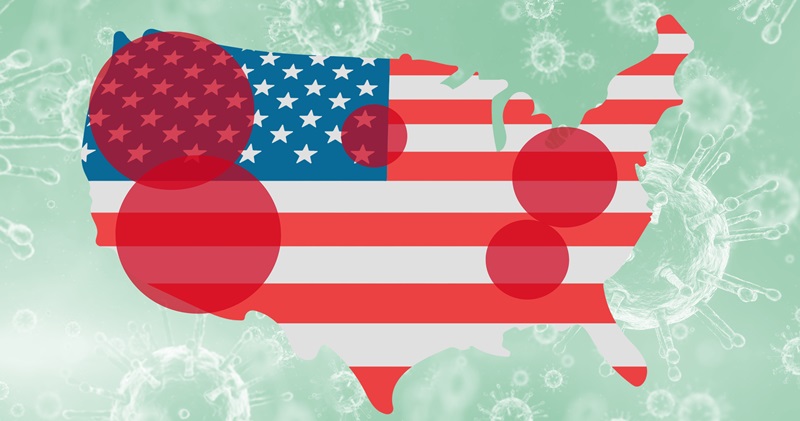
米国には、把握されているより多くの鳥インフル感染者がいる可能性があるそうです。米疾病対策センター(CDC)が公表した研究結果で明らかになりました。
研究者らは昨年9月、牛と接触のある全米の獣医師150人から血液を採取して分析。このうち3人から、最近鳥インフルエンザウイルス(H5N1)が感染したことを示す抗体が検出されたといいます。
3人ともインフルエンザのような症状や結膜炎に心当たりはなく、感染が疑われる牛との接触もありませんでした。ただし、1人は感染した家禽に接触歴があったといいます。そして3人のうち1人は、これまで乳牛の間で鳥インフルが検出されていないジョージア州とサウスカロライナ州でのみ診察を行っているそうです。
米公共ラジオNPRによると専門家は、もし確認されていない患者が多くいるのであれば、ウイルスがヒトの間で感染しやすくなる変化を見逃す危険性があると指摘しています。
この研究成果はCDCが13日に発行した「疫学週報(MMWR:Morbidity and Mortality Weekly Report)」に掲載されました。トランプ政権はCDCなどに対し外部への情報発信を一時的に停止するよう指示していたため、この号が政権発足後初のNMWR発行になります。

トランプ米政権は14日、米疾病対策センター(CDC)で働く職員の約10%にあたる1300人に対し解雇通知を出したようです。国立衛生研究所(NIH)でも同日、1500人が解雇されたといいます。米公共ラジオNPRが報じました。
CDCとNIHで解雇の対象になったのは、最近新たに採用された職員や勤続年数は長いものの最近新たなポジションに異動した職員だそうです。今回の人員削減は、13日にロバート・ケネディ・ジュニア氏が長官に就任した保健福祉省(HHS)の指示によって行われたそうです。
HHSの広報責任者は今回の解雇に関し、「HHSはトランプ政権の方針に従い、連邦政府の再編と効率化に向けた大統領の広範囲な努力をサポートする措置を講じている。HHSがアメリカ国民に対し最も効率的かつ高い水準のサービスを提供するために必要な措置である」とNPRの取材に回答したといいます。
CDCは米国の健康警告システムの役割を担い、病気の予防や対策を行う組織です。NIHは世界最大の医学研究機関です。こうした重要な役割を持つ組織において、急激な人員削減が行われたことについて専門家は、米国の公衆衛生上の脅威になり得るとして懸念を示しています。

「ワクチン懐疑派」として知られるロバート・ケネディ・ジュニア氏が13日、米国の厚生(保健福祉省:HHS)長官に就任しました。トランプ大統領が指名し、米国議会上院が13日に賛成52、反対48で承認しました。
ケネディ氏は計1兆7千億ドルの予算を抱える食品医薬品局(FDA)や疾病対策センター(CDC)、国立衛生研究所(NIH)などを監督下に置くことになります。
AP通信によると、投票では、子どもの頃ポリオに感染した経験を持つ重鎮議員ミッチ・マコネル氏を除く与党・共和党の議員全員が賛成し、野党・民主党の議員全員が反対しました。
13日にホワイトハウスで就任宣誓式を終えたケネディ氏は、米メディアのインタビューで「ワクチンによる副反応をより注意深く監視する強力なプログラムを立ち上げる」と述べたそうです。トランプ氏は、ケネディ氏が肥満などの慢性疾患の研究に焦点を当てた新たな委員会を設立すると発表しました。
ケネディ氏は、NIH、CDC、FDAの職員を大量に解雇する可能性についても言及しているとのことです。

米国で鳥インフルエンザウイルス(H5N1型)の感染によって入院した患者が相次いで報告されました。米CBS Newsによると、ワイオミング州が14日に米国で3人目となる入院患者の発生を公表し、15日にはオハイオ州保健当局の広報担当者が4人目の入院患者についてCBS Newsに明らかにしたそうです。
ワイオミング州の患者は女性で、自宅で飼育していた鳥から感染したとみられています。州の保健当局が公表を拒否しているといい、その後の容体は不明です。
オハイオ州の患者は男性で、感染した家禽と接触し、呼吸器症状があったことが分かっているとのことです。この患者は既に退院したそうです。
2人の入院患者にどの遺伝子型の鳥インフルが感染したかは不明です。ただ、ワイオミング州の患者が住む郡の家禽からは最近「B3.13」が検出されたそうです。B3.13はヒトにはそれほど深刻な症状を引き起こさないと考えられています。
一方、「D1.1」と呼ばれる新たな遺伝子型は、感染したルイジアナ州の高齢者が死亡するなど、重症化する例が確認されています。
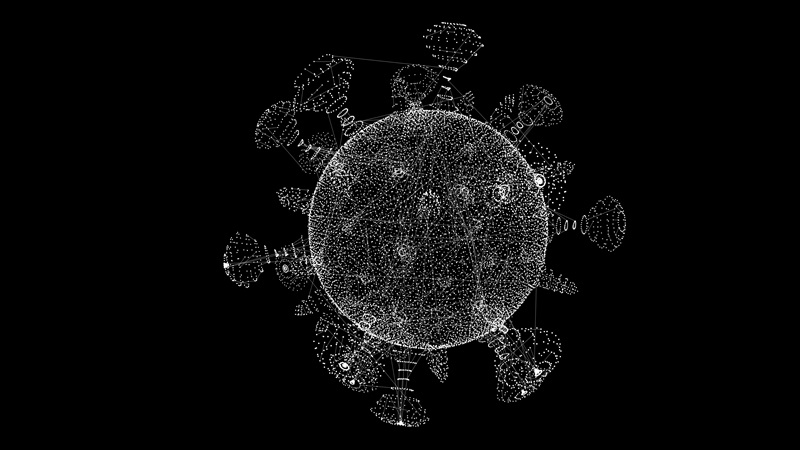
A型インフルエンザウイルスは細胞に感染する能力を高めるため、周囲の環境に応じて球状または大きめのフィラメント(長い線)状に形を変化させるそうです。米国立アレルギー・感染症研究所(NIAID)の研究チームが科学誌Nature Microbiologyに論文を発表しました。
チームは、フィラメントを形成するには多くのエネルギーが必要なのにもかかわらず、A型ウイルスがフィラメント状で存在することが多い理由を調査しました。複数のA型ウイルス株と細胞株を組み合わせ、さまざま感染条件下でウイルスの形状を観察したそうです。
その結果、抗ウイルス抗体の存在や宿主との不適合などが原因で感染効率が低下した環境に置かれると、ウイルスはこれに適応するため形状を迅速に調整することが分かったといいます。ウイルスの形状は動的で、株の種類によって決まっているというよりはむしろ、環境の影響を受けることが明らかになったとのことです。
なお、チームが以前行った研究では、ウイルスのフィラメント状粒子が抗体による不活性化に抵抗できることが分かっているそうです。

米国のトランプ政権は、海外援助を管轄する米国際開発局(USAID)の閉鎖に向け、USAIDからの数百億ドルの資金援助を凍結するなどの措置を講じています。これを受けWHO(世界保健機関)のテドロス事務局長は12日の記者会見で、世界の感染症対策に影響が出ているとして、資金援助の再開を検討するようトランプ政権に訴えたそうです。
英BBCによると、USAIDは年間約400億ドルの海外援助を行っていますが、トランプ大統領は「支出に関して全く説明がつかない」「(職員は)無能で腐敗している」として、ほぼ全ての援助を停止する方針を示しています。
テドロス事務局長は記者会見で、資金援助の一時停止によって世界50カ国でHIV(エイズウイルス)、ポリオ、エムポックス、鳥インフルエンザの治療や予防を目的とした医療プログラムに影響が出ていることを明らかにしたそうです。
世界の公衆衛生に関する専門家は、こうした資金凍結が感染症のまん延やワクチン開発の遅れなどにつながる可能性があるとの懸念を示しています。

1日の中で最も気分が上向きになる時間帯はいつなのでしょうか。英国の研究チームが、2020年3月~22年3月に自身のメンタルヘルスや幸福度に関するアンケートに回答した成人4万9218人のデータを分析し、研究成果を医学誌BMJ Mental Healthに発表しました。
参加者は1人あたり平均18.5回のアンケートに協力し、毎回アンケート入力が完了した時点の日にちや時間を記録したそうです。参加者のうち76.4%が女性、68.1%が大学卒業以上の教育レベル、5.9%が人種的マイノリティーだったといいます。
分析の結果、1日の中で朝の時間帯が最も幸福や満足、やりがいを感じる度合いが高く、うつや不安、孤独を感じる度合いが低いことが分かりました。一方、精神状態が最も悪くなるのは深夜だったそうです。
また、季節による影響も明らかで、夏に全体的な精神状態が最も良くなることが示されました。曜日による精神状態への影響はそれほど明確ではありませんでしたが、平日は週末に比べて時間帯による幸福度や満足度の変動が少なかったとのことです。

脳の健康のためには、ベーコンやソーセージなどの赤肉(牛・豚・羊などの肉)の加工食品を食べ過ぎない方が良いそうです。米国の研究チームが、医学誌Neurologyに論文を発表しました。
チームは、認知症を持たない平均年齢48.9歳の米国人13万3771人を最長で43年にわたり追跡し、食生活と認知症リスクの関連を調査しました。分析の結果、赤肉加工食品の平均摂取量が1日0.25サービング(薄切りベーコン0.5枚分に相当)以上の人は、1日0.1サービング未満の人に比べて認知症を発症するリスクが13%高くなることが分かったそうです。
また、自分では認知機能の低下を自覚しているけれど周りからはそれが認識できない状態の「主観的認知機能低下(SCD)」のリスクは14%上昇することも明らかになったといいます。さらに、赤肉加工食品を1日1サービング(ホットドッグ1個分に相当)多く食べるごとに、認知機能の老化が1.61年早まることが示されました。
加工されていない赤肉の摂取については、認知症リスクとの関連は認められなかったものの、SCDリスクの上昇には関連していたとのことです。

果物や野菜に熱を加えず、強い圧力をかけてすりつぶして作る「コールドプレスジュース」。これを用いた「ジュースクレンズ」と呼ばれる断食方法は、健康に悪影響を及ぼす可能性があるそうです。米国の研究チームが科学誌Nutrientsに論文を発表しました。
研究チームは、平均年齢22.7歳の健康な成人14人を3群に分けて調査しました。参加者は3日間、「コールドプレスジュースのみ」「コールドプレスジュースと通常食」「できるだけ加工精製していない植物性食品(プラントベース・ホールフード)のみ」のいずれかを取り、唾液や頬粘膜、便のサンプルを計3回提出したそうです。
分析の結果、ジュースのみを取った群の口腔内で、有益なファーミキューテス門の細菌が減少し、炎症に関連するプロテオバクテリア門の細菌が増加することが分かったといいます。さらに腸内においても、腸管透過性(不要な物を体内に通さないようにする腸管上皮細胞が持つ機能)や炎症、認知機能低下に関連する細菌の増加が認められたそうです。
「ジュースと通常食」の群は細菌叢の好ましい変化が見られ、プラントベース・ホールフードの群は多少悪化することが分かったとのことです。
コールドプレスジュースは不溶性食物繊維がほとんど残らず糖質が多いため、大量に飲むと口腔内や腸内の細菌組成バランスを崩してしまうのだそうです。
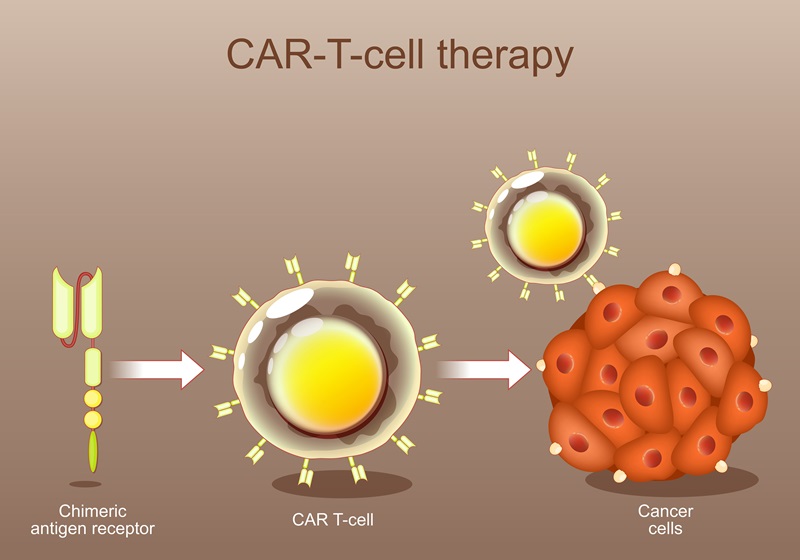
米国の研究チームが、血液がんの治療に用いる「CAR-T細胞療法」について、「二次がん」が発生するリスクは認められないとの研究成果を医学誌Nature Medicineに発表しました。
CAR-T細胞療法は、患者自身のT細胞(がんを攻撃する免疫細胞)を取り出し、遺伝子改変でがんへの攻撃力を高め、その細胞を増やした上で患者に戻す治療法です。二次がんとは、がん治療が原因で元の病気とは異なる種類のがんが生じることです。
米食品医薬品局(FDA)が2023年に、難治性の血液がんに使うCAR-T細胞療法が二次がんのリスクを高めるという警告を出し、問題になっていました。
研究チームは、CAR-T細胞療法の臨床試験を受けた成人と小児の患者計783人を最長で15年にわたり追跡調査したそうです。その結果、18人が二次がんを発症したことが分かりました。
しかし、この18人ついては、CAR-T細胞療法に使ったT細胞の遺伝情報に、誤って新たな腫瘍の発生に関与する「挿入突然変異」が誘発された証拠は見つからなかったといいます。これらの二次がんは、CAR-T細胞療法以前に受けた化学療法や放射線療法による免疫系へのダメージに起因する可能性があるとのことです。

米ネバダ州の酪農従事者1人に、鳥インフルエンザウイルス(H5N1)の新たな遺伝子型「D1.1」が感染したことが明らかになりました。D1.1が乳牛からヒトに感染した例が報告されるのは初めてです。米疾病対策センター(CDC)が10日に公表し、米国の各メディアが報じています。
ヒトのD1.1感染については重症化の危険が指摘されています。実際に2件の重症化例がこれまでに報告されています。米NBC Newsによると、今回の患者の症状は結膜炎のみで、入院することなく回復したそうです。
D1.1は長らく野鳥の間で流行していたもので、先月31日に乳牛への感染がネバダ州で初めて確認されました。今回D1.1陽性が明らかになった患者は、感染した乳牛に接触していたといいます。今のところ濃厚接触者の中に体調不良を訴えている人はおらず、ヒトからヒトへの感染は確認されていないとのことです。
CDCの推計によると、昨年鳥インフルの感染が確認された患者68人のうち、15人がD1.1によるものだそうです。ルイジアナ州以外ではアイオワ州、オレゴン州、ワシントン州、ウィスコンシン州で感染者が見つかっているといいます。なお、ルイジアナ州ではD1.1が感染した高齢の男性が昨年12月に発症し、今年1月に死亡しています。
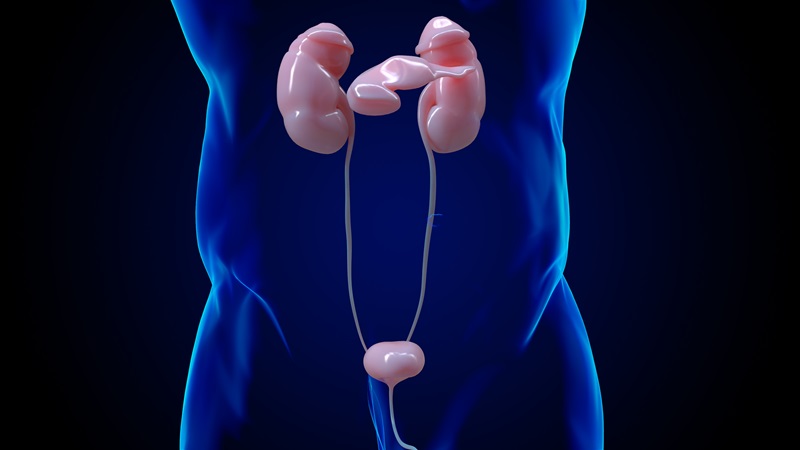
米マサチューセッツ総合病院(MGH)は7日、先月25日にニューハンプシャー州に住む66歳の男性に対し、遺伝子改変したブタの腎臓を移植したと発表しました。MGHはヒトへのブタの腎臓移植を世界で初めて実施しており、今回で2例目です。男性は手術から1週間後には退院し、順調に回復しているそうです。
ブタの臓器移植手術を受けたのは、この男性が世界で6人目です。4人(心臓2人、腎臓2人)は術後2カ月以内に死亡し、腎臓移植を受けた5人目の女性だけが現在も生存しています。
今回移植を受けた男性は、腎不全のために2年前から受け始めた人工透析による疲労感や合併症に苦しんでいました。AP通信によると、男性に適合する腎提供者(ドナー)が見つかるには7年以上かかる可能性があり、男性には心臓発作の既往歴もあったそうです。こうした事情から、男性はブタの腎臓移植を希望したといいます。
今回の移植手術は、米国のバイオテクノロジー企業eGenesis社が米食品医薬品局(FDA)から承認を受けたパイロット試験(本試験の前に予備的に行われる試験)の一環とのこと。同社はさらに2人の患者に対し、同様の試験を行う許可を得ています。

南米アルゼンチンのミレイ大統領は5日、WHO(世界保健機関)からの脱退を発表しました。AP通信によると、ミレイ氏はトランプ米大統領と良好な関係であることが知られており、今回の決定は米国の同様の措置に追随した形だといいます。脱退の次期については明らかにしていません。
大統領府の報道官は脱退の理由として、「新型コロナウイルス流行時の対応に関する考え方の重大な相違」を挙げ、当時のWHOの方針が人類史上最大のロックダウン(都市封鎖)を招いたと批判しているとのことです。さらに、「一部の国からの政治的影響によるWHOの独立性の欠如」などについても言及したそうです。
アルゼンチンは健康管理のための資金をWHOから受け取っていないため、今回の決定が国内の医療サービスの質に影響を及ぼす可能性はないとしています。
なお、2024~25年のWHOの予算69億ドルのうち、アルゼンチンの負担分は約800万ドルと考えられています。資金面での影響は大きくないものの、世界の公衆衛生における協力関係の分断が懸念されています。
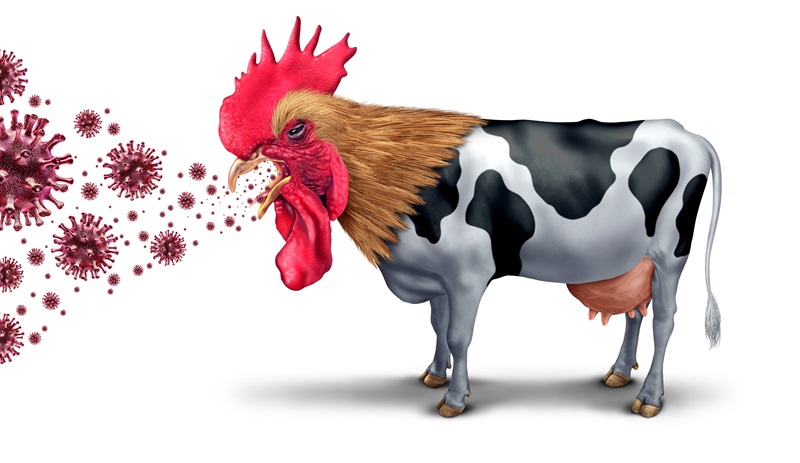
米ネバダ州農業局は、州内の六つの乳牛の群れから鳥インフルエンザウイルス(H5N1)の新たな遺伝子型「D1.1」の陽性反応が出たと発表しました。D1.1はヒトに感染すると重篤な症状を引き起こす危険性があります。
米農務省が全国規模で行っている検査を通じて、先日31日に確認されたといいます。米CNNによると、それぞれの群れが別々に野鳥から感染したとみられており、牛からヒトへの感染は今のところ確認されていないそうです。
D1.1は米国内の乳牛の間で感染が広がっている「B3.13」とは別の遺伝子型で、これまで感染が確認されたのは鳥や感染した鳥に接触したヒトのみでした。
ヒトのD1.1感染については、重症化した症例がこれまでに2件確認されています。昨秋には、カナダのブリティッシュコロンビア州に住む10代の若者1人が重症化し、入院しました。また、今年1月にはD1.1に感染した米ルイジアナ州の高齢者が死亡しています。
一方、D1.1に感染した乳牛の症状は食欲の減退や乳量の減少など比較的軽いもので、B3.13と変わらないそうです。
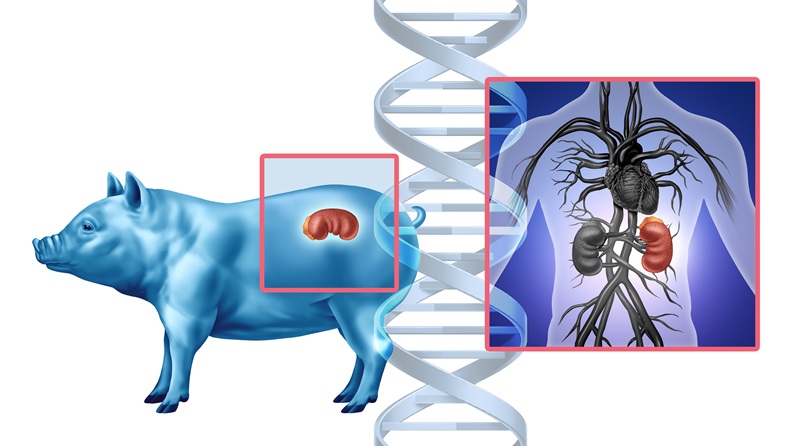
米食品医薬品局(FDA)は米国のバイオテクノロジー企業2社に対し、遺伝子改変したブタの腎臓をヒトに移植する臨床試験の実施を承認したそうです。科学メディアScience Alertによると、承認を受けたのはUnited Therapeutics社とeGenesis社です。
United Therapeutics社は3日、FDAから承認を受けたことを発表しました。今年の半ば以降、まず末期の腎臓病患者6人に対して移植を実施し、その後対象を50人に拡大する予定だといいます。一方、eGenesis社は昨年12月、腎移植のドナーが見つかる可能性が低い腎不全患者3人に対する臨床試験を実施する許可をFDAから得たとのことです。
現在、ブタの臓器移植を受けて生存しているのはアラバマ州の53歳の女性1人のみ。この女性は昨年11月25日にUnited Therapeutics社のブタの腎臓を移植する手術を受け、71日経過した今月4日の時点で順調に回復しているとの報告があります。
これまで、この女性のケースを含めてブタの臓器の移植手術は計5件行われています。これらは正式な臨床試験ではなく、命に関わる患者の救済措置として特別に緊急承認されたものです。
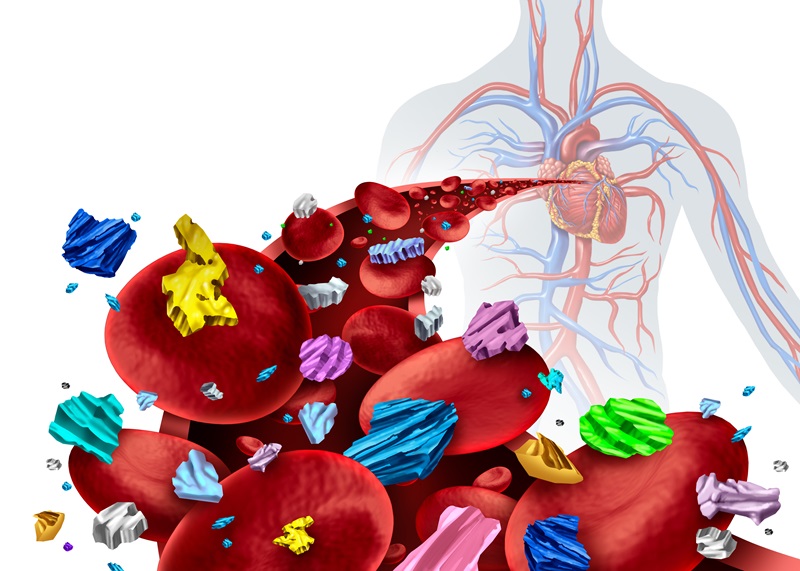
この50年ほどでプラスチックの使用が急増していることに伴い、「マイクロプラスチック」や「ナノプラスチック」と呼ばれるプラスチックの微小な破片(二つを総称してMNP)が人体に深刻な影響を及ぼし始めている可能性があるそうです。米国の研究チームが医学誌Nature Medicineに論文を発表しました。
チームは、2016年と24年の、病死者の遺体を解剖して調査した(剖検)標本を用いて死者計52人の脳、肝臓、腎臓の組織を分析したそうです。その結果、24年の脳と肝臓のサンプルは、16年のものに比べてMNP濃度が高いことが明らかになったといいます。さらに1997~2013年の脳サンプルも調べたところ、年々MNP濃度が上昇する傾向が認められたとのことです。
また、脳のMNP濃度は肝臓や腎臓に比べて7~30倍高いことも分かったといいます。その上、認知症患者の脳からはさらに高濃度のMNPが検出されたそうです。
チームは、MNPが認知症の原因になるということではなく、認知症患者の脳を守る機能の低下によってMNPが多く蓄積する可能性を指摘しています。

WHO(世界保健機関)は家庭で使用する食塩に関する新たなガイドラインを1月27日に公表しました。ガイドラインでは、「塩分(塩化ナトリウム)」の一部を「塩化カリウム」に置き換えた「低ナトリウム塩代替品(LSSS)」に切り替えることを推奨しています。
塩分の過剰摂取は高血圧のリスクを高め、心臓病や脳卒中、腎臓病などを引き起こす可能性があります。WHOによると、世界中で1年間に約190万人がナトリウムの過剰摂取が原因で死亡しているといいます。
WHOは1日あたりのナトリウム摂取量について2g未満を推奨していますが、実際には平均約4.3gが摂取されているそうです。WHO加盟国は2013年に、25年までにナトリウム摂取量を30%削減するとの目標を掲げました。しかし、ほとんどの国で達成されず、この目標は30年まで先送りされたといいます。
目標達成のための戦略として注目されるのがLSSSです。LSSSはナトリウムの含有量が少ないにもかかわらず、通常の塩と同様の風味が楽しめるといいます。さらに、不足しがちなカリウムを補うことができるという利点もあります。
ただし腎機能が低下している人は、カリウムの排泄量が減少して血中のカリウム濃度が高くなるため、注意が必要とのことです。
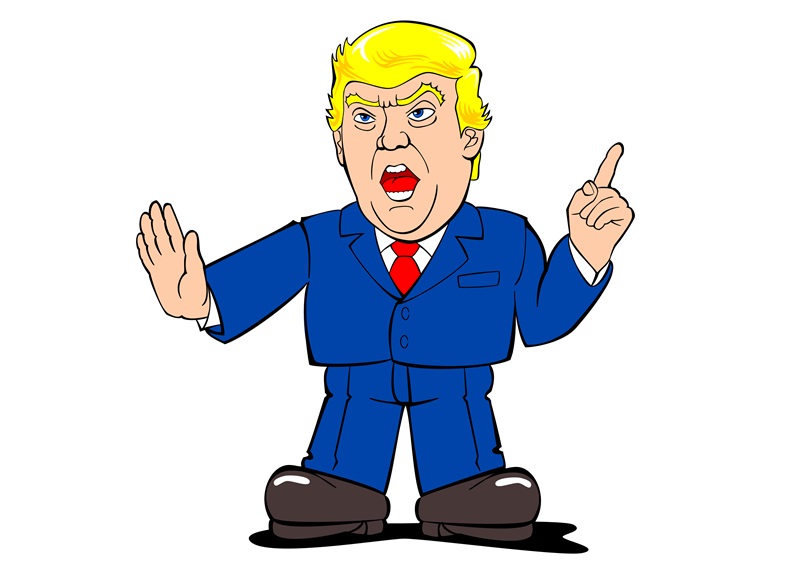
トランプ米大統領がWHO(世界保健機関)からの脱退を表明したことを受けて、WHOのテドロス事務局長は非公開の会議で各国に対し、米国に再考を促すよう協力を求めたようです。AP通信がWHOの内部書類を入手するなどして報じました。
米国の脱退表明については各国も危機感を募らせているようです。先月29日に開かれた予算会議では、最大の資金拠出国である米国の脱退にどのように対処するつもりなのかと、各国がWHOに迫ったそうです。
2024~25年は、WHOの予算69億ドルのうち約14%にあたる9.88億ドルが米国による拠出と推計され、その額は群を抜いています。WHOの大規模な緊急活動、HIVや結核対策、ポリオ撲滅に向けた活動などは米国の資金に大きく依存しているとのことです。
米国脱退による影響を話し合う別の非公開会議では、WHOが現在のペースで支出を続ければ、26年前半にはキャッシュフロー(事業におけるお金の流れ)がその日暮らしのような状態になると財務担当者が述べたそうです。
一方で、国民の健康にとって重要な情報が得られなくなるため、WHOからの脱退は米国にとっても不利益になる可能性があると指摘する専門家もいます。

アルコール依存の人は否定的な感情を軽減するために飲酒する――。米国の研究チームが、この従来の説を覆す研究結果を医学誌American Journal of Psychiatryに発表しました。
チームは21~35歳の参加者221人に対し、日常生活で飲酒した際にアルコールによるどのような影響を自覚したかをリアルタイムで記録してもらう調査を行いました。参加者のうち120人がアルコール使用障害(AUD)の診断基準を満たしており、さらにそのうち64人がうつ病を併発していたといいます。
調査の結果、うつ病の有無にかかわらず、AUDの人は飲酒時に高レベルの刺激や快楽を経験することが明らかになったそうです。一方で、否定的な感情は飲酒によって多少抑制されたものの、こうした効果が認められたのはAUDやうつ病の人に限ったことではなく、それ以外の人も同様だったといいます。
現在、AUD関連の治療はストレスやうつ症状の解消に焦点が当てられており、チームは「コインの一面を扱っているに過ぎない」と指摘しています。
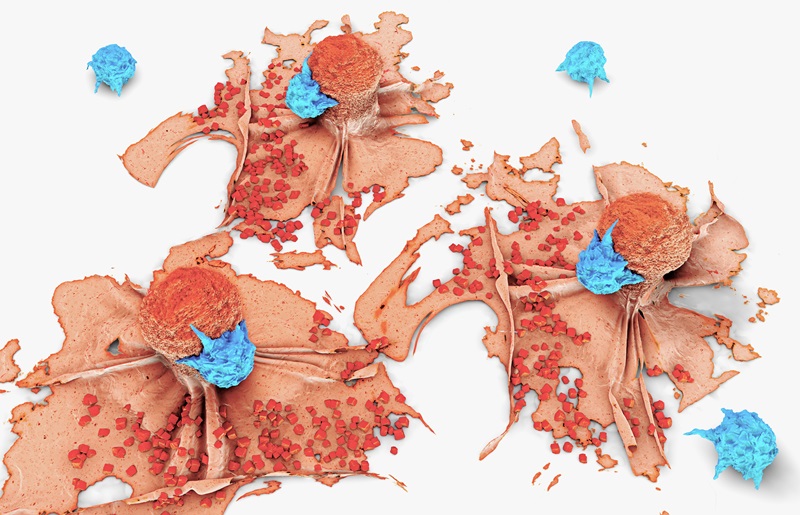
がんや感染との戦いが長引くと免疫系が疲弊し、特にその最前線で防御能力を発揮するT細胞の機能が失われてしまうそうです。オーストラリアなどの研究チームが、こうした免疫疲弊に抵抗し、長期的な免疫応答を維持するためのカギとなる珍しいタイプの免疫細胞「幹細胞様T細胞」を特定したとして、科学誌Science Immunologyに研究成果を発表しました。
チームは、この幹細胞様T細胞の耐久性が、「ID3」と呼ばれるタンパク質によって促進されることを突き止めたそうです。ID3を発現したT細胞は、長期にわたって強力な免疫応答を維持する優れた能力を持つといいます。
そしてID3発現T細胞の増加には、IL(インターロイキン)-36βやIL-18という物質が関与することも明らかになったとのことです。これらは、免疫細胞が分泌し細胞間の情報伝達の役割を持つタンパク質「サイトカイン」の一種です。
チームは、ID3活性を強化することで、がんなどの長引く疾患の治療効果が高まる可能性があるとしています。

米疾病対策センター(CDC)のウェブサイトから、HIV(エイズウイルス)やLGBTQ(性的少数者)に関連するページが削除されたそうです。米国の各メディアが報じています。
米CNNによると、削除されたページの中には、HIVの検査やLGBTの子どもの自殺リスクに関するページをはじめ、高校生の健康上のリスク行動を長期間追跡したデータシステムなどもあるといいます。さらに、HIVなどの感染症に関するCDCのデータにもアクセスできなくなっているそうです。
トランプ大統領は「DEI(多様性・公平性・包括性)推進プログラムの廃止」を指示する大統領令や「性別は男女二つだけ」とする大統領令に署名しています。これを受け、米連邦政府の人事管理局(OPM)は先月29日、「ジェンダー・イデオロギーを植え付ける外部向けのすべての情報」を1月31日午後5時までに削除するよう指示する文書を各政府機関に通知しました。今回のCDCの対応は、この通知に従ったものです。
CDCの関係者は、違反した職員は厳しい処分を受ける可能性があると伝えられたと話しているそうです。そこで、通知が指摘している文言の修正には時間がかかるため、関係する情報を削除したとのことです。

トランプ米政権が米疾病対策センター(CDC)など連邦政府の保健機関に対し、外部への情報発信を停止するよう指示したことで、鳥インフルエンザに関する重要な研究結果の発表が遅れているそうです。
米CNNによると、CDCは1952年以降、「疫学週報(MMWR:Morbidity and Mortality Weekly Report)」を途切れることなく発行してきました。しかし先月21日、保健福祉省(HHS)長官代行がCDCや国立衛生研究所(NIH)、食品医薬品局(FDA)などに対し、大統領が任命した人物が確認・承認するまでどのような情報発信も2月1日まで停止するよう指示。これを受けて、MMWRの発行も止まっているといいます。
その結果、MMWRへの掲載が予定されていた「鳥インフルが感染した牛を治療した獣医師の無自覚感染の有無」に関する研究と「鳥インフル患者から飼い猫に感染した可能性」を示す研究の発表が保留になっているそうです。
CDCに近い関係者によると、MMWRは通常木曜日に発行されるため、少なくとも2月6日(木)までは保留の状態が続く見通しだといいます。なお、MMWR には研究の成果だけでなく、感染症の流行をはじめとする国民の健康に関係する重要な情報が掲載されています。

iPS細胞(人工多能性幹細胞)由来の心臓細胞から作った心筋組織「心臓パッチ」を心臓の表面に移植することで、心不全を安全に治療できる可能性があることを証明したと、ドイツの研究チームが科学誌Natureに論文を発表しました。
チームは、心不全のアカゲザルに対し、アカゲザルiPS細胞由来の心臓パッチを移植したそうです。すると、心臓で新たな心筋が形成され、ポンプ機能が改善することが示されたといいます。また、不整脈や腫瘍増殖などといった深刻な副作用は認められなかったといいます。
こうした結果を受けて、チームはヒトiPS細胞由来の心臓パッチを進行した心不全患者に移植する臨床試験を初めて実施しました。
3カ月後、この患者は心臓移植を受けたため、パッチを移植した心臓は摘出されたそうです。この心臓を分析したところ、パッチを移植したアカゲザルの心臓のように新たな心筋が形成されていることが確認されたといいます。

しゃっくりを止める方法が分かったそうです。米国の研究チームが医学誌Cureusに論文を発表しました。
しゃっくりは、腹部と胸部を仕切る筋肉である横隔膜が自分の意思とは無関係にけいれんすることで起こります。チームが発見したのは、横隔膜の運動を支配する横隔神経、嚥下や声帯の運動などに関わる迷走神経への刺激、一時的な血中二酸化炭素濃度の上昇を組み合わせた対処です。
しゃっくりが出たら、まず最大限に息を吸い込み、喉を開いた状態にしたまま、引き続き30秒間息を吸い続けます。その後、ゆっくりと息を吐き出し、通常の呼吸に戻すのだそうです。
しゃっくりが止まらない17~64歳の21人にこの方法を試してもらったところ、全員がすぐにしゃっくりを止めることができたといいます。このうち1人は、48時間以上しゃっくりが続く持続性しゃっくりに苦しんでいたとのことです。
また途中で息を吸わずにコップの水を一気飲みすることでも、同様の効果が得られる可能性があるとのことです。
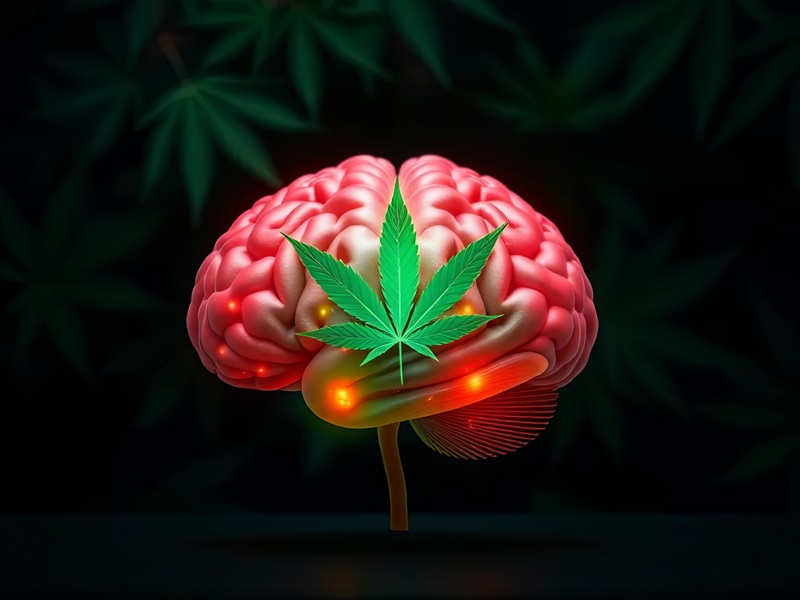
大麻の使用は、必要な情報を一時的に記憶して処理する能力「ワーキングメモリ」に長期的にも短期的にも悪影響を及ぼす可能性があるそうです。米国の研究チームが、医学誌JAMA Network Openに研究成果を発表しました。
チームは、22~36歳の成人1003人を対象に大麻と認知機能の関係を調査しました。その結果、大麻の多用(生涯で1000回以上の使用)は、ワーキングメモリに関わる課題を行う際の脳活動の低下に関連することがMRI検査で明らかになったそうです。
尿検査の結果から最近大麻を使用したと定義された人も、その人たちを除外しても、こうした結果が表れたそうです。このことからチームは、大麻の多用によって脳に長期的な影響が及ぶ可能性が示されたとしています。
また、大麻による脳活動の低下は、特に意思決定や記憶、注意、感情処理などの重要な認知機能に関与する領域(背外側前頭前皮質、背内側前頭前皮質、前島皮質)において顕著だったといいます。
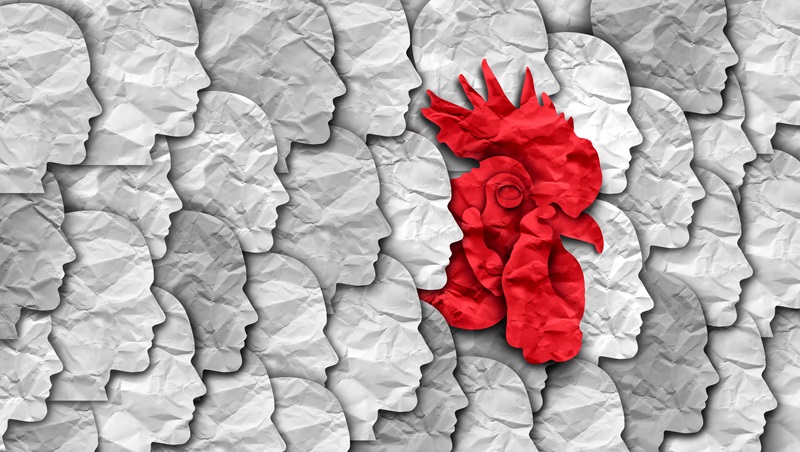
英国の健康安全保障庁(UKHSA)は、イングランド中部のウェスト・ミッドランズの農場労働者に鳥インフルエンザウイルス(H5N1型)が感染したと発表しました。
UKHSAによると、この患者は感染した多数の鳥と長期にわたり密接に接触していたそうです。患者は感染症病棟に入院しましたが、現在の体調は良好だといいます。この患者から周囲の人に鳥インフルがうつったという証拠は見つかっていないとのことです。また、患者に感染したウイルスは、米国で哺乳類や鳥の間で流行しているものとは遺伝子型が違うそうです。
英BBCによると、ウェスト・ミッドランズにあるシュロップシャーの農場で鳥インフルの大流行が発生したことから、この地域は「鳥インフルエンザ防護区域(AIPZ)」に指定されたばかり。AIPZに指定されると、いかなる家禽も屋外に出すことはできないといいます。大流行が起きたシュロップシャーの農場では、100万羽もの採卵鶏の殺処分が続いているとのことです。

米国で、「注意欠如・多動症(ADHD)」と診断される成人が急増しているそうです。そのような中で、診断方法にばらつきがあることが課題になっており、ADHDと関連障害の米国の学会(APSARD:The American Professional Society of ADHD and Related Disorders)が、成人を治療する医療従事者向けの診断および治療のガイドラインを今年後半に公表する予定だそうです。AP通信が報じました。
発達障害の一種であるADHDは男児に多く見られ、成長とともに落ち着くものとこれまで考えられてきました。しかし専門家によると、多くの人が子供の頃に診断されず、実際は大人になっても症状を抱えたまま生活しているといいます。最近の研究で、1500万人以上の米国の成人(17人に1人)がADHDの診断を受けており、成人患者の約半数が18歳以降に診断されていることが分かったそうです。
ADHD急増の背景には、2013年に診断基準が変更され、ADHDの定義が広がったことが挙げられます。しかし、20年に始まった新型コロナウイルス感染対策のためのロックダウン(都市封鎖)で、軽度のADHDを持っていた人が症状を悪化させた可能性もあるそうです。

米疾病対策センター(CDC)は職員に対し、WHO(世界保健機関)と連携して行っている業務を直ちに停止するよう命じたそうです。AP通信がCDCの内部文書を入手して報じました。
AP通信によると、今回の業務停止命令はWHOと協働する全ての職員が対象で、CDCの職員はWHOの事務所に立ち入ることも禁じられたといいます。WHOには現在、CDCから30人近くの職員が派遣されており、感染症や公衆衛生に関するWHOの専門家と日常的に連絡を取り合って、世界中で起きている健康上のリスクやその対応方法について相談しているそうです。
就任直後のトランプ大統領は先週、WHOから脱退する手続きに入るための大統領令に署名しましたが、WHOからの脱退には議会の承認や1年前の通知などが必要になります。そのため、脱退へのプロセスは緩やかなものになると予測されていました。
しかし今回の突然の措置で、世界の公衆衛生に悪影響が及ぶ可能性が懸念されています。米国にとっても、最新の専門的知見を得る機会を失うことになるとの指摘も出ているとのことです。

鳥インフルエンザウイルスH5N1型が感染して、病気になったり死んだりする飼い猫が米国で増えているそうです。ウイルスに汚染された生のペットフードや生乳の摂取が原因のようです。米食品医薬品局(FDA)はペットフード会社に対し、予防措置を講じるよう求めているといいます。
米公共ラジオNPRが、米カリフォルニア大学デービス校の獣医学博士の解説を紹介しています。その獣医学博士によると、鳥類の間でH5N1の感染がまん延し始めた2022年以降、70匹以上の猫が鳥インフルH5N1型に感染しています。その多くが家畜小屋で飼われていた猫で、感染した牛の生乳を飲んでいたそうです。
テキサス州のある酪農場では、鳥インフルが感染した猫の約半数が死んだといいます。また、生の七面鳥を冷凍したペットフードを食べた猫に鳥インフルが感染して死んだ事例なども報告されているとのことです。ウイルスを死滅させる唯一の方法は熱を加えることだそうです。
今のところ、H5N1型が猫からヒトに感染したケースは確認されていないといいます。猫からヒトに感染する可能性は非常に低いのですが、ゼロではないため注意が必要です。

感染によって全身で炎症が起こり、結果として臓器障害が生じる「敗血症」について、そのメカニズムが新たに明らかになったそうです。米国の研究チームが、科学誌Cellに論文を発表しました。チームは、敗血症の炎症の悪循環を引き起こすのは、感染そのものではなく、感染細胞が放出する致命的なタンパク質が原因であることを突き止めたそうです。
細菌などに感染した細胞は、「ガスダーミンD」という細胞膜に穴を開けるタンパク質を自らの表面に送り出すといいます。その穴から細胞内の成分が漏れ出すことで自身を崩壊させ、感染の広がりを防ぐのだそうです。しかし、細胞が感染に対して迅速に反応した場合、穴のあいた部分を切り離すことで、その細胞は生き残ることができるといいます。
一方で、切り離された部分はガスダーミンDを含む小さな袋状の「小胞」になって、周囲を浮遊します。何らかの拍子に小胞が別の細胞の表面にくっつくと、そこから穴が開いて、感染していない健康な細胞が死んでしまうとのことです。チームは、これが広がることで敗血症が悪化するとしています。
WHO(世界保健機関)によると、世界中で毎年1100万人が敗血症で死亡しているそうです。

寝つきをよくするために少量の酒を飲む人は少なからずいるのではないでしょうか。しかし、かなりの量のアルコールを摂取しないと入眠には影響しないそうです。そして、アルコールは少量でも睡眠の質を下げてしまうといいます。英国の睡眠の専門家による記事がThe Conversationに掲載されています。
記事ではアルコール摂取量と睡眠の関係を分析したオーストラリアの研究チームの報告を紹介しています。その研究によると、寝酒による鎮静効果で入眠までの時間が短縮されるのは、寝る前の3時間以内に高用量(グラスワインで3~6杯相当)のアルコールを摂取した場合のみだそうです。
また、アルコール摂取は、記憶や感情調整に重要な役割を果たす「レム睡眠」が最初に出現するタイミングを遅らせる上に、一晩の総レム睡眠時間を減少させてしまうといいます。こうしたレム睡眠の乱れは、低用量(標準的なアルコール飲料2杯相当)のアルコールを飲んだ後にも発生するとのことです。
別の研究では、夜の飲酒を繰り返すと、飲酒を控えた夜にも睡眠が乱れる可能性が示されたといいます。専門家は、禁酒や減酒の重要性を訴えています。
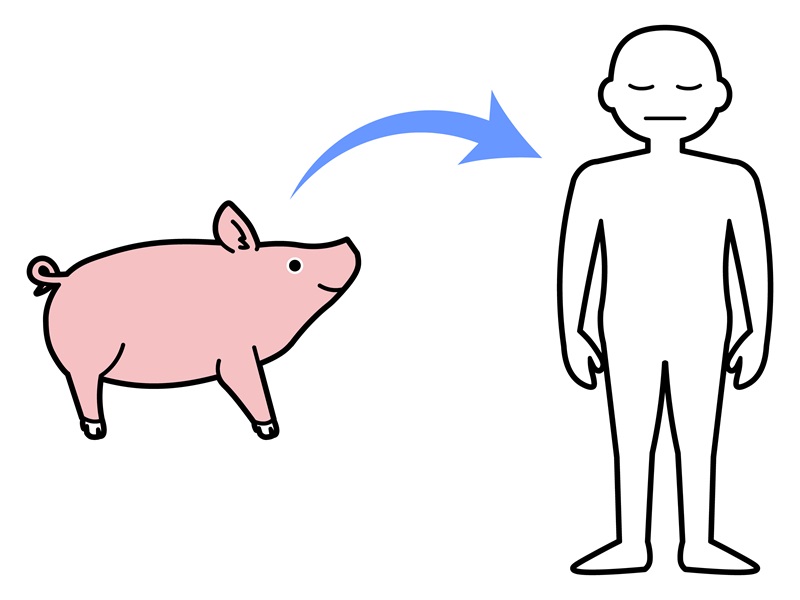
米ニューヨーク大学ランゴーン医療センターで昨年11月25日にブタの腎臓移植を受けた53歳の女性が、節目となる「術後2カ月生存」の記録を達成したそうです。米国ではこの女性の前に、2022年と23年にヒトへのブタの心臓移植手術がそれぞれ1件ずつ、24年にヒトへのブタの腎臓移植手術が2件実施されました。しかし、いずれの患者も術後2カ月以内に死亡しています。
AP通信によると、女性に移植されたブタの腎臓は、拒絶反応を防ぐために10個の遺伝子が改変されているそうです。女性は移植手術から11日後に退院したのですが、術後約3週間の時点で拒絶反応が始まるわずかな兆候が確認されたといいます。
女性は血液検査などの綿密な追跡調査を受けていたために、すぐに拒絶反応に対する治療を受けることができたそうです。この治療が成功して以降、女性に新たな拒絶反応の兆候はないといいます。医師によると女性の腎臓は完全に正常に機能しているとのことです。
現在は移植後の検査のためにニューヨーク市に住んでいますが、あと1カ月ほどで自宅のあるアラバマ州に戻れる見込みだといいます。

クチナシの果実から得られる化合物「ゲニピン」が、病気で損傷を受けたり発育不全になったりした神経細胞(ニューロン)の再生を促す可能性があるそうです。米国の研究チームが医学誌Science Translational Medicineに論文を発表しました。
チームは、さまざまな刺激を脳に伝えるなどの役割を持つ「感覚ニューロン」について、その変性を防ぐ方法を調べていたそうです。そして、640種類の化合物の中からゲニピンが有効であることを発見したといいます。
チームは、感覚ニューロンが集まった感覚神経や自律神経に異常が生じる、まれな遺伝性疾患「家族性自律神経失調症(FD)」の治療にゲニピンが利用できる可能性があるとみています。
培養皿での実験では、ゲニピンによってFD患者の感覚ニューロンが正常に発達するようになり、変性が抑制されることが分かったそうです。また、FDマウス2匹にゲニピンを投与したところ、感覚ニューロンに情報を伝達する末梢神経系の障害が改善することも示されたといいます。
さらに、切断された軸索(ニューロンから延びる突起)がゲニピンによって再生することも試験管内の実験で確認されたとのことです。
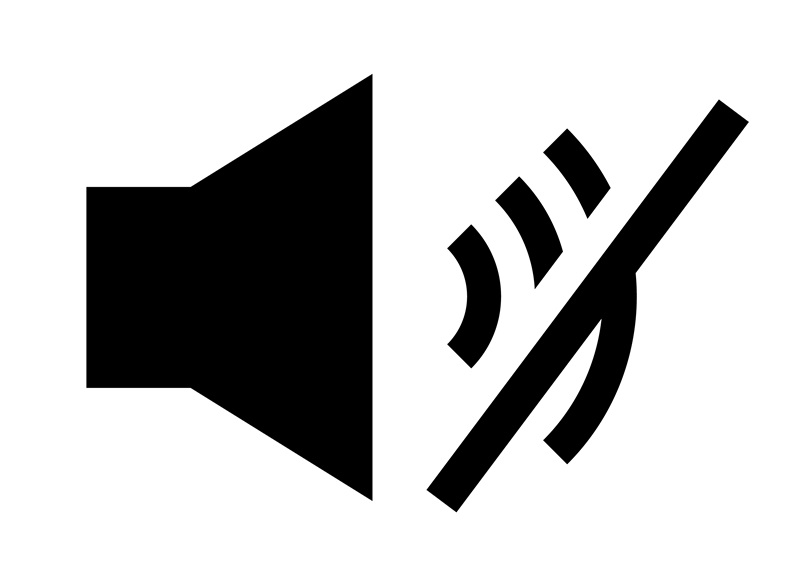
トランプ政権は連邦政府の保健機関に対し、外部への情報発信を一時的に停止するよう指示したそうです。この指令は2月1日まで有効とのことです。米国の各メディアが報じました。
米NBC Newsや米CNNによると、トランプ米政権の保健福祉省(HHS)長官代行が21日、米疾病対策センター(CDC)や国立衛生研究所(NIH)、食品医薬品局(FDA)に、大統領が任命した人物が確認し、承認するまでいかなる発信も控えるよう求めたそうです。
承認なしに公の場で演説をしないことや、公式文書の発行前に大統領任命者と調整することも指示に含まれているといいます。ただし、国民の健康や安全に関係する重要な情報については例外としているとのことです。
NIHは声明で、HHSから情報発信の一時停止の指示があったことを認め、「この停止期間中に、新たなチームが情報の精査や優先順位付けのための流れを整える」と述べたそうです。また、NIHには出張の一時取りやめに関する指示も出されたといいます。
新政権が保健機関に対して、情報の公表を一時停止することはあるそうですが、今回は指示の範囲が異常に広いそうです。

栄養豊富な海の幸のカキが、複数の抗菌薬に耐性のある「スーパーバグ(超多剤耐性菌)」に対抗するための希望の星になるかもしれません。オーストラリアの研究チームが科学誌PLOS ONEに論文を発表しました。
チームは、シドニー周辺に生息する岩ガキの一種「シドニーロックオイスター」の血リンパ(人間の血液に相当)から分離した「抗菌タンパク質」が、肺炎や咽頭・扁桃炎、髄膜炎、皮膚軟部組織感染症などを引き起こすレンサ球菌属の細菌を死滅させるのに有効であることを発見しました。抗菌タンパク質は多細胞生物が細菌と戦うために持つ物質です。カキの血リンパから分離した抗菌タンパク質は、細菌が身を守るために形成するバイオフィルムを通過できることも明らかになったそうです。
さらに、既存の抗菌薬にこの抗菌タンパク質を加えたところ、ほんのわずかな量で抗菌薬の効果が2~32倍に高まったといいます。特に、レンサ球菌属のほか、多剤耐性菌が問題になっている黄色ブドウ球菌や緑膿菌に対する効果が有望なことが分かったとのことです。さらに健康なヒト細胞に対する有害な影響は認められなかったそうです。

解熱鎮痛剤や抗血小板薬として使われるアスピリンは、遺伝性の大腸ポリープの再発や大腸がんのリスクを抑制するという研究結果が出ています。しかし、がん治療を行った後の再発予防には効果がないとの論文をシンガポールの研究チームが医学誌The Lancet Gastroenterology & Hepatologyに発表しました。
チームは、ステージ2~3に相当する大腸がんの切除手術をし、3カ月以上の標準的な術後補助化学療法(体内に残っているがん細胞を抗がん剤によって死滅させる治療)を受けた11カ国・地域の患者1587人を対象に治験(第3相)を実施しました。5年間の追跡調査で、定期的な診察や画像検査、大腸内視鏡検査を行ったそうです。
その結果、追跡期間中に病気をせずに生存した率(無病生存率)は、1日200mgのアスピリンを3年間服用した群で77.0%、プラセボ群で74.8%だったそうです。また、5年生存率については、アスピリン群で91.4%、プラセボ群で88.9%だったといいます。これらの結果は、アスピリン群とプラセボ群の間で大腸がんの再発予防における統計学的な有意差は認められなと結論付けられるとのことです。

肥満や糖尿病の治療薬として承認されている人気の「GLP-1受容体作動薬」について、さらなる効能やリスクがあることが示されました。米国の研究チームが、医学誌Nature Medicineに研究成果を発表しました。
チームは、糖尿病患者200万人のデータをふるいにかけ、オゼンピック、マンジャロ、ウゴービ、ゼップバウンドといったGLP-1受容体作動薬を処方された患者21.6万人と他の種類の糖尿病治療薬を処方された患者の健康状態を平均4年にわたり追跡しました。
その結果、GLP-1受容体作動薬は統合失調症、薬物やアルコールへの依存症、尿路感染症、慢性腎臓病、認知症、脳卒中、誤嚥性肺炎など42の健康上のリスクの低下に関連することが明らかになったそうです。反対に、吐き気、嘔吐(おうと)、腎臓結石、胃食道逆流、睡眠障害、非感染性胃腸炎など19のリスクが高まることも示されましたといいます。
ただ、今回対象になった患者は平均年齢が65歳以上で、白人が70%以上を占め、90%以上が男性でした。そのため、全てのGLP-1受容体作動薬使用者に当てはまらない可能性があるとのことです。
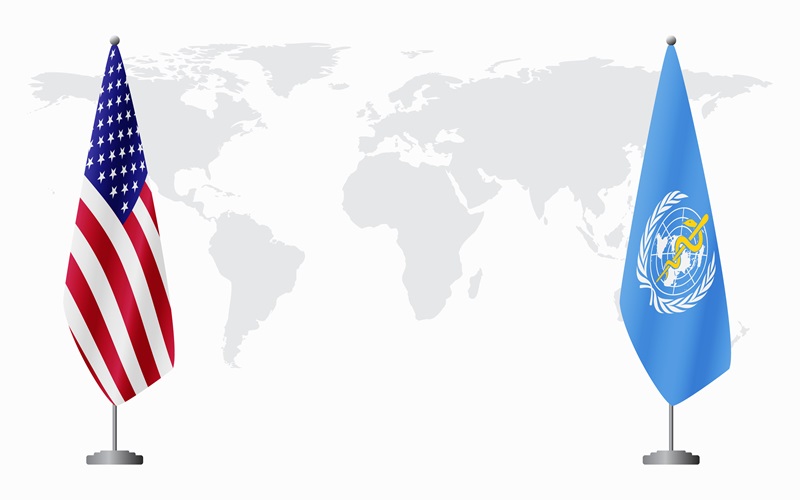
米国のトランプ大統領は就任初日の20日、WHO(世界保健機関)からの脱退を指示する大統領令に署名しました。各国のメディアが報じています。
AP通信によると、トランプ氏は新型コロナウイルスの感染拡大に関するWHOの対応が誤っていたと批判し、これらを脱退の理由として挙げています。トランプ氏は大統領1期目だった2020年7月にもWHOからの脱退を通告しました。しかし、21年1月に大統領に就任したバイデン氏がこの決定を覆したという経緯があります。
これまでWHOにとって米国は、資金や人材の面で最大の支援国の一つでした。23年は予算の18%が米国からの拠出だったそうです。こうした莫大な資金援助が絶たれることで、WHOが長年積み上げてきた公衆衛生をめぐる数多くの世界的戦略が損なわれる可能性が懸念されています。
米国にとっても、WHOのデータベースに迅速にアクセスできないなどの不利益が生じ、ワクチンや医薬品の製造の遅れなどにつながる可能性があるといいます。WHOは21日、今回のトランプ氏の決定について遺憾の意を表明し、再考を求めたとのことです。

希ガス(貴ガス)の一種である「キセノン」が、アルツハイマー病(AD)の治療に有効な可能性があるそうです。米国の研究チームが、医学誌Science Translational Medicineに研究成果を発表しました。
チームは、麻酔作用や神経保護作用を持つことが知られているキセノンをADマウスに吸入させる実験を行ったそうです。その結果、脳萎縮や神経炎症が軽減し、巣作り能力が改善することが分かりました。また、ADに関係するタンパク質アミロイドβの除去や認知機能の改善に関わるミクログリア(脳内の免疫細胞)の神経を保護する反応が、キセノンの吸入によって誘発されることも明らかになったといいます。
こうした治療効果は、アミロイドβの沈着による病変を持つマウスと、神経細胞の中にタンパク質タウが異常に蓄積する病変を持つマウスの両方で観察されたとのことです。
なお、キセノンガスは血液脳関門を通過し、脳内に入っていくことができるそうです。血液脳関門は、脳を保護するために、毛細血管中の物質を脳内に通すか否かを選択する仕組みです。
チームはキセノンがADの治療法に有望であるとして、ヒトでの第1相試験を数カ月以内に開始する予定とのことです。

若者がオリーブオイルや魚、食物繊維を多く摂取する「地中海式食事法」を取り入れると、腸内細菌叢(腸内フローラ)のバランスが変化し、脳に好影響が及ぶ可能性があるようです。米国の研究チームが科学誌Gut Microbes Reportsに研究成果を発表しました。
チームは人間の18歳に相当する若いラットで調査を行いました。その結果、地中海食を14週間与えられた群は、飽和脂肪の多い西洋食を与えられた群に比べてCandidatus Saccharimonas属をはじめとする4種類の腸内細菌が増加する一方で、ビフィドバクテリウム属など別の5種類の腸内細菌が減少することが分かったそうです。
そして、こうした腸内細菌の変化は、ラットの記憶力や学習能力の向上に関連することが、迷路を使った実験で示されたといいます。また地中海食は、新しい情報に適応するための認知の柔軟性や必要な情報を一時的に保存して処理するためのワーキングメモリの向上にも関連していたとのことです。
地中海式食事法は、主な脂肪源としてのオリーブオイル▽豊富な野菜、果物、全粒穀物▽魚と赤身のタンパク質▽赤身肉と飽和脂肪酸の制限▽さまざまな植物から取るたくさんの食物繊維――が重要な要素だそうです。

米国で鳥インフルエンザウイルスのヒトでのパンデミックに対する警戒が高まっています。米保健福祉省(HHS)が、現在家禽や乳牛の間で流行している鳥インフルエンザウイルス株に対応するmRNAワクチンの開発を加速させることを明らかにしたそうです。
米NBC Newsによると、NHSは米製薬のモデルナに5.9億ドルの資金を提供すると発表しました。HHSは昨年7月にも同社に対し、1.76億ドルの支援を行っています。
米政府は、従来の技術を使った2種類の鳥インフルワクチン候補をすでに備蓄していますが、迅速に製造することができるmRNAベースのワクチンの開発が重要だと考えているそうです。モデルナはH5N1型とH7N9型を標的としたワクチンの開発を進めているといいます。
米国では、昨年3月に乳牛の間で鳥インフルが広がり始めました。感染した乳牛や家禽、野鳥などからヒトへの感染例が67件確認されており、最近ではルイジアナ州の高齢者1人が死亡しています。
こうした状況を背景に、政府はワクチンの効果を高める物質「アジュバント」や、あらゆる種類のインフルエンザに対応する「ユニバーサルインフルエンザワクチン(万能ワクチン)」などの開発にも資金提供を行っているそうです。

「ハンチントン病」の患者は、生まれた時から原因となる遺伝子異常を持っています。しかし、ハンチントン病はすぐには発症しません。長らく不明だったその理由を、米国の研究チームが解明したそうです。AP通信が報じました。
ハンチントン病は、自分の意思に関係なく手足や顔面を動かしてしまう不随意運動、不安定な歩行、性格の変化、判断力の低下などの症状を特徴とする遺伝性の神経変性疾患で、通常30~50歳で発症します。特定の遺伝子における塩基C、A、Gの配列の繰り返しが、病気を持たない人では15〜35回なのに対し、ハンチントン病患者では40回以上起きることが分かっています。
研究チームは、ハンチントン病患者53人とハンチントン病ではない50人の脳組織から、この「繰り返し配列(リピート)」に関する詳しい分析を行ったそうです。その結果、CAGリピートが40回以上あるDNA領域は時間の経過とともにリピートし続け、約150回に達した時点で、毒性のタンパク質を生成することが明らかになったといいます。それによって神経細胞(ニューロン)がむしばまれ、死滅しすることが示されたとのことです。
チームはこの発見が、病気の進行を遅らせたり、予防方法を見つけたりすることに役立つと期待しています。

米国の研究チームが、食品包装など多くの製品に使用されている「PFAS(有機フッ素化合物)」とがんリスクの関連性を明らかにしたとして、科学誌Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiologyに論文を発表しました。
PFASは分解されにくく、体内に蓄積していくといい、さまざまな健康問題との関連性が指摘されています。米国の約45%の飲料水からPFASが検出されているそうです。
チームは、2016~21年に米国内で報告された全がん症例と公共水道システムが供給する飲料水中のPFASに関する13~24年の全国データを分析しました。その結果、飲料水から基準値を上回るPFASが検出された郡では、消化器、内分泌、呼吸器、口腔咽頭のがんが発生する割合が2~33%高いことが分かったそうです。
また、飲料水がPFASに汚染された郡に住む男性は、そうでない郡に住む男性に比べて白血病や泌尿器系、脳、軟部組織のがん罹患率が高かったといいます。女性は、甲状腺、口腔咽頭、軟部組織のがんが多くなりました。最新のデータによると、PFASに汚染された飲料水は年間6864件のがん症例に関係すると推計されるそうです。

米食品医薬品局(FDA)は15日、合成着色料「赤色3号(エリスロシン)」の食品や経口薬への使用を禁止すると発表しました。米国の各メディアが報じています。赤色3号は食品などを鮮やかな赤色にする石油由来の合成着色料です。
米NBC Newsによると、FDAは1990年に赤色3号の化粧品への使用を禁止しています。しかし、その後もキャンディーやシリアルなどの食品や経口薬への使用は続いており、2022年には消費者保護団体である公益科学センター(CSPI)が、動物への発がん性や子供の行動障害との関連性への懸念から使用禁止を求める請願書をFDAに提出していました。
こうした動きを背景に、FDAは高レベルの赤色3号に暴露した雄ラットにおいてがんが発生したとの研究結果に基づき、今回の承認取り消しの決定を下したといいます。ただし、ヒトへの発がんリスクは立証されていません。
米国の食品メーカーは27年1月15日までに、薬品メーカーは28年1月18日までに赤色3号の使用を中止する対応が求められるとのことです。なお、日本では赤色3号の使用が認められており、漬物などに使われています。

心臓の神経回路網は、これまで考えられていた以上に高度で複雑な機能を有している可能性があるそうです。スウェーデンと米国の研究チームが科学誌Nature Communicationsに論文を発表しました。
長い間、心臓は脳からの信号を伝達する自律神経によってコントロールされると考えられていたといいます。しかし、人間と同じような心拍数や心機能を持つゼブラフィッシュを使って調査した結果、心臓には、鼓動を調節するために重要な役割を果たす「ミニ脳」のような独自の複雑な神経系があることが分かったそうです。
このミニ脳には、ペースメーカーのような働きをするニューロン(神経細胞)をはじめ、異なる機能を持ついくつかの種類のニューロンが存在することも示されたといいます。
チームは、今回の発見が、心拍のコントールに関する現在の知見に疑問を投げかけるものだとしています。心臓内の神経系について理解を深めることで、不整脈などの心疾患に関する新たな治療法の開発などに役立つ可能性があるとのことです。

カルシウムが豊富な食生活を送る人は、大腸がんを発症するリスクが低くなるようです。イギリスの研究チームが、女性54万2778人を平均16.6年にわたって追跡したデータを分析し、その結果を科学誌Nature Communicationsに発表しました。
チームの調査で、カルシウムを1日300mg(大きめのグラスで牛乳1杯相当)多く取ると、大腸がんリスクが17%低くなることが分かったそうです。朝食用シリアル、果物、全粒粉、炭水化物、食物繊維、ビタミンCも大腸がんリスクの低下に関連していましたが、その影響はわずかでした。
逆に、アルコールを1日20g(大きめのグラスでワイン1杯相当)多く飲むと15%、赤肉や加工肉を1日30g多く食べると8%、大腸がんリスクがそれぞれ上昇することも示されたといいます。
なお、カルシウムは、牛乳のほかにもヨーグルトやチーズなどの乳製品に多く含まれています。カルシウムが腸内の胆汁酸や遊離脂肪酸に結合し、発がん作用を抑制する効果を発揮する可能性があるとのことです。
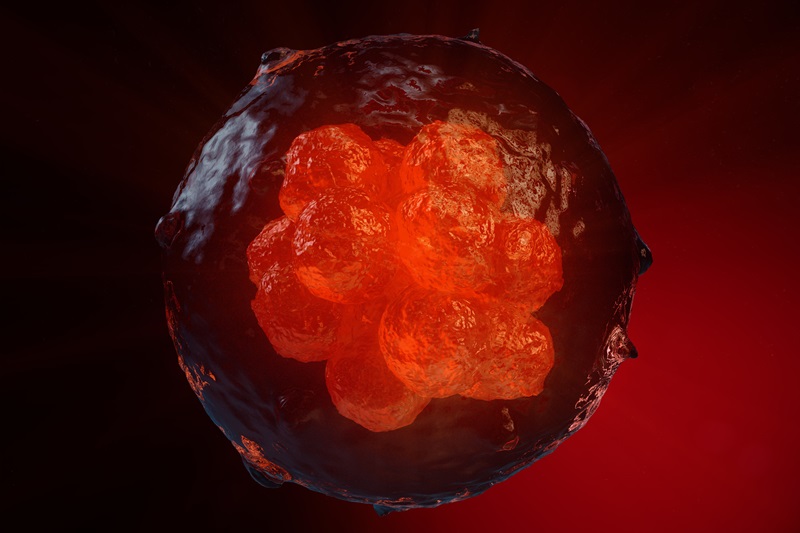
オーストラリアでは最近、人工知能(AI)を導入して生殖補助医療(ART)を行うクリニックが出始めているそうです。オーストラリアの研究チームがARTにAIを活用することの懸念点を明らかにし、医学誌Human Reproductionに発表しました。
チームが調査したのは、移植に適した胚を評価するAI(機械学習ツール)の使用によって生じる倫理的な問題です。調査の結果、機械学習ツールは、ARTの専門家の医師が行うのに比べてより一貫性のある胚評価を行うことができる上に、評価にかかる時間を大幅に短縮できることが示されたそうです。
一方で、こうしたツールを使用することによる「患者の非人間化」「アルゴリズムのバイアス(偏り)」「透明性や公平性の確保」などといった数々の懸念事項が明らかになったといいます。
チームは、これらの倫理的懸念が機械学習による胚評価を排除するものではないとしています。しかし、AIが人間の命に関係する非常に繊細な領域に干渉することになるため、熟慮を重ねたうえで慎重に取り扱う必要があるとのことです。

脳の白質病変は、血流不足によって脳深部の大脳白質に生じた変化で、認知症のリスクに関連するとされています。緑茶をたくさん飲む人は、この白質病変が少ない傾向にあることを金沢大学などの研究チームが突き止めたそうです。チームが科学誌npj Science of Foodに論文を発表し、科学メディアScience Alertが紹介しています。
チームは、認知症を持たない65歳以上の日本人8766人のデータを分析したそうです。その結果、緑茶を1日1杯飲む人と比較して、緑茶を1日3杯飲む人は3%、7~8杯飲む人は6%、それぞれ白質病変が少ないことが分かったそうです。
一方で、緑茶の摂取は記憶をつかさどる海馬や脳全体の大きさには影響しなかったといいます。また、うつ病と診断された人やアルツハイマー病リスクに関連するAPOE4遺伝子を持つ人は、緑茶摂取によるこうした白質病変の減少は見られなかったとのことです。
緑茶には血圧を下げる効果があるとされており、このような心血管への影響が今回の結果に関係している可能性があると、チームは考えているようです。

脳損傷によって、病的なほど「冗談好き」になってしまう「ふざけ症(Witzelsucht)」という感情の障害がまれにあるそうです。科学メディアScience Alertが米国の研究チームが2016年に発表した69歳の男性の症例を紹介しています。
この男性は脳卒中を起こした後、冗談に対する取りつかれたような欲求が生じるようになったといいます。思いついたダジャレや不快なジョークを共有したい欲求を抑えきれず、夜中にたびたび妻を起こすほどだったそうです。
ふざけ症は、ドイツの神経科医ヘルマン・オッペンハイムによって、1890年に初めて発表されたといいます。社会生活を営む上で重要な高次機能をつかさどる右前頭葉に病気やけがで損傷がある人が、過剰にユーモラスになることがあると気付いたことがきっかけだったそうです。
また最近、上機嫌や多幸、軽率な態度で、一人ではしゃぎふざける「モリア(Moria)」と呼ばれる精神症状が、ふざけ症と共存または重複することも分かっています。ふざけ症やモリアには、いずれも前頭葉の下部にある「前頭眼窩野」回路の損傷が関連するとみられています。これらに標準的な治療法はないそうです。

米マクドナルドで昨年、腸管出血性大腸菌O157による集団食中毒が発生した問題で、タマネギを供給した食品会社の不十分な衛生管理が明らかになったようです。米CBS Newsが米食品医薬品局(FDA)の査察報告書を入手し、その内容を報じました。
CBS Newsによると、タマネギを供給したTaylor Farms社のコロラド州の施設内の設備からは、清掃作業終了後にもかかわらず、微生物が形成するバイオフィルムや大量の食品かすが見つかったそうです。また、食品加工を担当する作業員が衛生管理に必要な手順を踏んでいないことも明らかになりました。
作業員が手洗いシンクを使用している様子は見られず、時々、手袋の上から手の消毒剤を使っていただけだといいます。さらに、消毒液に漬けた道具の乾燥作業もきちんと行われておらず、濡れたままになっていたとのことです。
Taylor Farms社は、FDAが査察終了後に発行した指摘事項通知に基づき速やかに是正措置を講じたとの声明を出しているそうです。マクドナルドはFDAの査察前にこの施設からの仕入れを中止しているとのことです。

たくさん歩くことは、うつ病リスクの抑制につながるようです。スペインの研究チームが、日々の歩数とメンタルヘルスに関する33の研究を分析した結果を医学誌JAMA Network Openに発表しました。
対象者は世界13カ国の18歳以上の男女で、合計9万6173人に上ったといいます。分析の結果、1日の歩数が5千歩以上の人は、5千歩未満の人に比べてうつ症状が少ないことが分かりました。また、1日の歩数が7千歩以上の人は、7千歩未満の人に比べてうつ病発症リスクが31%低くなることも示されたそうです。1日7500歩以上歩く人は、うつ病リスクが42%低下することも示されました。
歩数が増えるにつれてうつ病リスクは低下する傾向にありましたが、1日1万歩を超えるとこうしたメンタルヘルスへの恩恵は横ばいになったといいます。
これまでの研究で、ヨガやウェートトレーニング、太極拳などがうつ病リスクを抑制することが分かっていました。今回の研究で、身体活動レベルのより低い「歩くこと」もリスク抑制の効果があることが明らかになりました。

子宮内膜症を正確に検出する血液検査をオーストラリアの医療技術企業(Proteomics International)が世界で初めて開発したそうです。同社がオーストラリアのメルボルン大学などと共同で研究を行い、学術誌Human Reproductionに論文を発表しました。
研究チームは、主にヨーロッパ系の参加者749人から採取した血液データを分析したといいます。その結果、10のタンパク質バイオマーカーが単独で子宮内膜症に関連することが明らかになったそうです。
これらのバイオマーカーを用いると、「重症の子宮内膜症患者」と「子宮内膜症ではないが同様の症状がある患者」を99.7%の割合で識別することができたといいます。また、「微症~中等症の子宮内膜症患者」と「子宮内膜症ではないが同様の症状がある患者」も85%以上の割合で識別できたとのことです。
現在、子宮内膜症の診断は腹腔鏡による侵襲的な方法で行われるため、非侵襲的な診断ツールが求められているといいます。科学メディアScience Alertによると、この血液検査は「PromarkerEndo」という名前で、同社は今年6月までにこの血液検査を実用化することを目指しているそうです。

米国では虫歯予防のために数十年間、水道水にフッ化物を添加しているそうです。そのフッ化物が子どもの知能指数(IQ)に影響を及ぼすという論文を米国の研究チームが医学誌JAMA Pediatricsに発表し、物議を醸しているようです。
チームは、フッ化物と子どものIQに関する既存の74研究を分析。その結果、子どものフッ化物への暴露とIQスコアの低下の間に統計的に有意な関連があることが分かったとしています。ただし、今回対象となった研究は、水道水のフッ化物濃度が高い中国などで実施されたもので、研究の質も低かったそうです。そのため、チームは水道水からのフッ化物の除去を主張しているわけではないといいます。
米NBC Newsによると、歯科医師らは、フッ化物が水道水から除去された地域では虫歯の発生率が劇的に増加しているとし、今回の調査結果に懸念を示しました。トランプ次期米大統領が厚生(保健福祉省:HHS)長官に指名したロバート・ケネディ・ジュニア氏が、水道水のフッ化物添加について批判的な立場を表明していることもあり、ますます議論が加速するとみられています。

コウモリのふん由来の肥料「バットグアノ」に含まれていた真菌によって、米国の男性2人が肺感染症を起こし、死亡したそうです。米国の研究チームが明らかにし、医学誌Open Forum Infectious Diseasesに発表しました。
2人はそれぞれ自宅で大麻を栽培しており、肥料にバットグアノを使用していたといいます。米国では、ニューヨーク州など一部の州で大麻の栽培が合法化されて以降、リン酸や窒素が豊富なバットグアノが最適な肥料として人気を集めているそうです。
男性2人はバットグアノに生息していた真菌(ヒストプラスマ・カプスラーツム)の胞子を知らぬ間に吸い込み、ヒストプラスマ症を発症したとみられています。
症状は2人ともひどい咳、発熱、体重減少で、最終的に呼吸器不全に陥ったとのことです。ヒストプラスマ症はほとんどの場合、抗真菌薬で回復します。しかし今回死亡した2人は、59歳と64歳と比較的高齢だったこと、基礎疾患があったこと、喫煙者だったことなどが原因で、感染に打ち勝つことができなかったといいます。

禁煙をするなら、「今」がベストタイミングだそうです。英国の研究チームが学術誌Addictionに研究結果を発表しました。
チームは英国内の男女の死亡率に関する大規模な追跡調査のデータを分析したそうです。その結果、たばこを1本吸うごとに男性は17分、女性は22分寿命が短くなると推計されたそうです。つまり、たばこを1箱(20本)吸うごとに、寿命を約7時間縮めてしまう可能性があるということです。
また、生涯にわたって喫煙習慣があった人は、喫煙経験がない人に比べて、平均して寿命が約10年短いことも明らかになったそうです。一方、30代前半までに禁煙することができれば、喫煙経験がない人と同程度の寿命になる傾向が認められたといいます。
年を取るにつれて喫煙によって失われた寿命を取り戻すことは難しくなるそうです。ただし、たとえいくつになっても、たばこを吸い続けるよりは禁煙した方が長生きできる可能性があるとのことです。

米国の公衆衛生政策を指揮するビベック・マーシー医務総監は3日、アルコール飲料のラベルに「がんリスクが高まる」との警告を表示するよう勧告しました。米NBC Newsや米CNNなどの各メディアが報じています。
公表された報告書によると、飲酒は乳がん、大腸がん、肝臓がん、口腔がん、咽頭がん、喉頭がん、食道がんの少なくとも7種類のがんに直接的に関連することが分かったそうです。また、乳がん症例の16.4%が飲酒に関連すると推計されるといいます。
米国では毎年、飲酒関連のがん症例が10万件、飲酒関連のがんによる死亡が2万件発生しているそうです。そして、がんの原因として、飲酒がたばこと肥満に次ぐ3番目に挙げられるといいます。マーシー氏は、「国民の多くが飲酒によるがんリスクを認識していない」と指摘しています。
今回公表された報告書は、がんリスクを高める1日当たりの飲酒量の基準も見直すよう求めています。現行の基準では、男性は1日2杯、女性は1日1杯が適量とされていますが、この程度の飲酒であってもがんリスクが高まることが示されたといいます。

中国でヒトメタニューモウイルス(HMPV)の感染者が急増していると報じられています。HMPVとはどのようなものなのでしょうか。
日本ウイルス学会や日本小児感染症学会によると、HMPVは2001年にオランダの研究チームが発見したありふれたウイルスで、今回新たに発生したものではありません。ウイルス性の呼吸器感染症では小児の5~10%、成人の2~4%がHMPVによるものと考えられているそうです。
RSウイルス(RSV)と同じ仲間に属し、主な症状は咳、発熱、鼻づまり、息切れです。乳幼児や高齢者、免疫力が低下している人に感染すると気管支炎や肺炎に進行し、重症化する恐れがあります。ワクチンや治療薬はありません。
米CBS News によると、HMPVは新たなウイルスではないため、専門家は新型コロナウイルスのような脅威になる可能性は低いと考えているそうです。感染を予防するには、他の呼吸器感染症と同様、手洗いや感染者との接触を避けるなどの対策が有効とのことです。
なお、2023年春には米国で患者の報告数が急増しニュースになりました。

米ルイジアナ州保健当局は6日、鳥インフルエンザウイルス(H5N1型)が感染し重篤な呼吸器症状で入院していた州内の患者が死亡したと発表しました。死亡したのは基礎疾患を持つ65歳以上の患者で、裏庭で飼っていたニワトリや野鳥と接触していたといいます。
米疾病対策センター(CDC)は昨年12月26日、この患者から採取したウイルスから、ヒトに感染しやすくなる変異が見つかったと発表しています。患者に感染したのは家禽や野鳥の間でまん延しているD1.1と呼ばれる株で、米国内の乳牛の間で流行しているものとは別のものです。遺伝子解析の結果、ヒトの上気道細胞に付着しやすくなる変異が発見されたというのです。
なお、こうした変異は、カナダのブリティッシュコロンビア州で鳥インフルが感染して入院した若者のサンプルからも確認されているとのことです。米NBC Newsによると、今回見つかった変異は鳥のサンプルからは検出されていないため、患者の体内で起きた可能性が高いそうです。現状では、ヒトからヒトへの感染は確認されていません。

高齢者の日々の脳の機能は、前日の運動と睡眠によって大きな差が出るそうです。英国の研究チームが科学誌International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activityに論文を発表しました。
チームは、認知機能に問題のない50~83歳(平均64.6歳)の中高年76人に防水の加速度計を24時間装着してもらい、8日間の追跡調査を実施しました。これに加え、睡眠の評価と認知機能の測定も毎日行ったそうです。
その結果、散歩やダンスなどに相当する「中~強度の身体活動」を多く行った人は、その後最大24時間にわたりエピソード記憶(個人が経験した出来事に関する記憶)とワーキングメモリ(入ってきた情報を保ちながら、何かを処理する機能)が向上することが分かったそうです。逆に「座りっぱなし」が多かった人は、ワーキングメモリが低くなったといいます。
興味深いことに、前日に中~強度の身体活動をしたかどうかに関係なく、前夜の睡眠時間が長い人はエピソード記憶と精神運動速度(物事を考えたり作業したりする速度)が向上することも明らかになりました。

トレーニングをより効果的に行うためのカギとなる「ディロードウィーク(積極的休養期間)」を知っていますか。The Conversationに英国の生理学の専門家による記事が掲載されています。
激しいトレーニングの期間中、4~8週間ごとに運動強度を抑えるディロードウィークを設けることで、それまでに蓄積した筋肉組織の疲労や損傷が回復しやすくなり、筋肉によい変化が起こるそうです。
また、過剰なトレーニングが原因で倦怠(けんたい)感やパフォーマンスの低下が生じる「オーバートレーニング症候群」のリスクについても知っておくべきだといいます。筋肉の成長に関与する遺伝子の記憶は休養期間中も保持されるため、普段のトレーニングを中断することを恐れる必要はないとのことです。
ディロードウィーク中は、通常の半分ほどのトレーニングを行うか、強度を20%ほど下げるのが一般的だそうです。特にマラソンなどに向けて激しいトレーニングを行っている場合は、運動をしない休息日を週1~2回設けることに加えて、ディロードウィークを設定するとよいとのことです。

歩くことは、さまざまな病気のリスクを下げるなど健康上多くのメリットがあることが知られています。より多くの効果を得るには、どのような点に気を付けて歩けばいいのでしょうか。英国の臨床運動生理学者が五つのポイントをThe Conversationで紹介しています。
<ポイント①>まず、一定の速さで歩くよりも、速く歩いた後にゆっくり歩くというように数分おきに「歩く速さを変える」と心血管の健康がより向上するそうです。
<ポイント②>また、時速5km以上の速さで歩くと、心血管疾患やがんを含め全ての死亡リスクが低下することが5万人以上のデータを分析した研究で明らかになっているといいます。息が少し弾む程度に「速く歩く」と、心臓の健康が改善するだけでなく、体重の管理にも効果的とのことです。
<ポイント③④>歩く時に「重いベストやリュックで負荷をかける」ことや「坂や階段を取り入れる」ことは、筋肉によい効果をもたらすそうです。
<ポイント⑤>そして、自分の動きや呼吸、周囲の環境に意識を向けて歩く「マインドフル散歩」を行うと、メンタルヘルスの向上につながるといいます。

カカオ豆をすりつぶしたカカオマスを多く含むダークチョコレートには、2型糖尿病のリスクを抑制する効果があるようです。米国の研究チームが、医学誌BMJに研究成果を発表しました。
チームは、看護師11万1654人のデータを平均25年にわたり追跡調査したといいます。その結果、ダークチョコレートを1週間に5サービング(1サービングの目安は約28g)以上食べる人は、ダークチョコレートを全くまたはめったに食べない人に比べて2型糖尿病を発症するリスクが21%低いことが分かったそうです。
一方、ダークチョコレートの原料に乳製品や多くの砂糖を加えたミルクチョコレートを食べる人は、こうしたリスク低下は認められなかったといいます。それどころか、ミルクチョコレートの摂取は長期的な体重増加に関連していたとのことです。
ダークチョコレートに多く含まれるポリフェノールの一種「フラバノール」が、2型糖尿病リスクの抑制に関与していると考えられるそうです。

コーヒーを1日に3杯飲むと、健康に長生きできる可能性があるそうです。ポルトガルの研究チームがコーヒー業界から資金提供を受け、さまざまな地域や民族を対象としたコーヒーの摂取量と健康に関する50以上の疫学調査を分析し、科学誌Ageing Research Reviewsに発表しました。
この研究の対象者は、合計300万人近くに上るといいます。分析の結果、適度な量(1日3杯)のコーヒーを定期的に飲む人は全死因死亡率が低く、寿命が長くなることが分かったそうです。
また、心血管疾患や脳卒中、がんといった加齢に関連する疾患の発症リスクも低く、健康寿命が約1.8年延びることも明らかになったといいます。さらに、加齢による記憶力の低下、気分や体調の悪化を緩和することも判明したとのことです。
コーヒーに含まれるカフェインやポリフェノ―ルの一種である「クロロゲン酸」が持つ覚醒作用、抗酸化作用、抗炎症作用が、基本的な生物学的メカニズムを維持するのに役立つ可能性があるそうです。
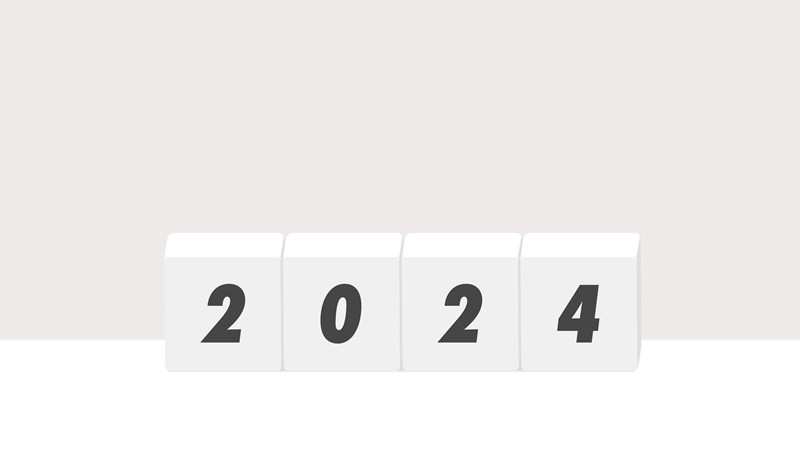
2024年の医療・医学に関する重大ニュースの続きです。新型コロナウイルス感染症の流行発生から5年がたちますが、今もなお「後遺症」に苦しむ人は多く……。後遺症に関して、慢性疲労症候群との関連性、子どもの特徴的な症状、抗ウイルス薬の効果など、世界各国で研究が進められています。
韓国では政府の医学部増員計画に反発する若手医師らが、2月から10カ月以上もストライキを続けています。病院に受け入れられなかった患者が亡くなるなどの実害が出る異常事態です。
ベトナムでは「バインミー」を食べた500人超が、米国ではマクドナルドの「クォーターパウンダー」で104人が食中毒に。韓国から輸入した激辛即席麺に対し、デンマーク政府が回収を指示するなど、食品による健康被害が相次ぎました。
ブタの腎臓移植が3件行われ、うち2人はすでに死亡。3例目の女性は12月に遺伝子改変したブタの腎臓が植えられ、17日現在で経過良好だといいます。
10月には、遺伝子の働きを調節する「マイクロRNA」を見つけた米国の研究者2人が、ノーベル生理学・医学賞を受賞。発表の4カ月前、血中のコレステロールを下げる物質「スタチン」を発見して有力候補とされていた東京農工大学栄誉教授の遠藤章さんが、90歳で亡くなりました。

2024年の医療・医学に関する重大ニュースを振り返ります。今年一番のニュースは、米国での鳥インフルエンザウイルス(H5N1型)の広がりでしょう。3月にテキサス州で感染した乳牛が見つかり、瞬く間に乳牛の間で流行が広がりました。その後、乳牛からヒトへの感染例が報告されただけでなく、感染経路の不明な患者も見つかっています。
そして11月には米大統領選でドナルド・トランプ氏が勝利しました。トランプ氏が公衆衛生分野の要職に指名した人の顔ぶれを見て、米国内外のメディアが危機感をあらわにしています。厚生(HHS)長官に反ワクチン派の政治家、公的医療保険のトップに健康や科学に関して誤解を招く主張を展開する元テレビ司会者、食品医薬品局(FDA)長官にFDAの方針に批判的な外科医、米疾病対策センター(CDC)所長にワクチンと自閉症の関連を主張した医師、国立衛生研究所(NIH)所長に新型コロナ対策のロックダウン(都市封鎖)を批判した大学教授……。
今年もさまざまな感染症が世界中で流行しました。中南米では蚊が媒介するデング熱が過去最多の患者・死者数を記録し、蚊やヌカカが媒介するオロプーシェ熱の感染者の報告も急増しました。麻疹(はしか)の感染が各地域で拡大し、CDCが警報を出したのは3月のことです。アフリカでは致死率の高いエムポックスの感染者が急増。WHO(世界保健機関)が8月に緊急事態を宣言しました。

コーヒーや紅茶は抗がん物質や抗炎症物質を含み、発がんリスクを抑えるといわれています。米国の研究チームが、口腔や咽頭などに生じる「頭頸部がん」の発症リスクに影響があることを明らかにしたそうです。
チームは、既存の14の研究から頭頸部がん患者9548人と対照群1万5783人のデータを分析しました。その結果、1日に4杯超のカフェイン入りコーヒーを飲むと、頭頸部がんリスクが17%、口腔がんリスクが30%、中咽頭がんリスクが22%、それぞれ低くなることが分かったといいます。下咽頭がんについては、1日3~4杯のカフェイン入りコーヒーを飲むと、リスクが41%低下することも示されたそうです。
また、デカフェ(カフェインレス)のコーヒーも効果があり、飲む習慣がある人は口腔がんリスクが25%低かったといいます。
一方、紅茶を飲む習慣がある人は下咽頭がんリスクが29%低かったものの、1日に1杯超の紅茶を飲むと喉頭がんリスクが逆に38%上昇することも明らかになったとのことです。
チームは研究成果を医学誌Cancerに発表しました。
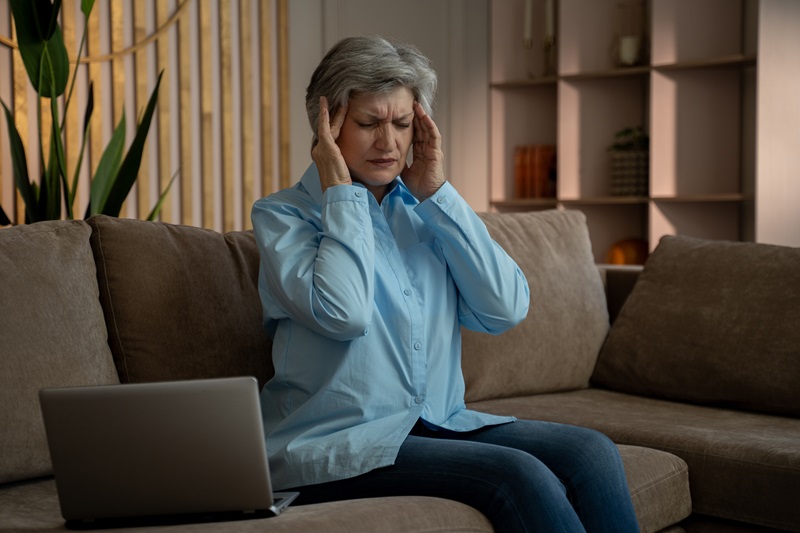
2023年に米食品医薬品局(FDA)と欧州連合(EU)欧州委員会に承認された片頭痛予防薬「Atogepant」の高い効果が明らかになったそうです。米国の研究チームが研究成果を医学誌Neurologyに発表しました。
チームは、Atogepantの有効性と安全性を評価した三つの臨床試験のデータを分析。片頭痛が月に14日以下の頻度で生じる「反復性片頭痛(EM)」患者436人を対象とした一つ目の臨床試験では、Atogepantを服用した群はプラセボ群に比べて、服用初日に片頭痛が生じるリスクが61%低くなることが分かったそうです。
他の経口片頭痛予防薬が効かなかったEM患者305人を対象とした二つ目の臨床試験では同リスクが47%、頭痛が月に15日以上生じる「慢性片頭痛」患者502人を対象とした三つ目の臨床試験では同リスクが37%低くなったといいます。
また、Atogepantを服用した人は、治療開始から4週間で片頭痛に見舞われる日が週に平均1~1.5日減少し、生活の質も向上しました。なお、これらの臨床試験の参加者はほとんどが白人女性だったとのことです。

飲料や超加工食品の甘味料として広く使われ、果物にも多く含まれる「果糖(フルクトース)」は、腫瘍の成長を促すそうです。米国の研究チームが、そのメカニズムを明らかにしたとして、科学誌Natureに研究成果を発表しました。
チームが各種がんの動物モデルで実験したところ、フルクトースを多く含むエサを与えると、体重や空腹時血糖値、空腹時インスリン値が変化することなく、メラノーマ(悪性黒色腫)や乳がん、子宮頸がんが急速に成長したといいます。
さらにチームは、高フルクトース食を与えられた動物の血液で、「リゾホスファチジルコリン(LPC)」などの脂質レベルが上昇することを発見したそうです。そしてこのLPCは、フルクトースを与えられた肝細胞から放出されることが明らかになったといいます。
肝臓がフルクトースをLPCに変換し、血流に乗ったLPCががん細胞の成長を促す栄養素の役割を果たす可能性が示されました。

目的地までの最適なルートを常に考える職業の人は、アルツハイマー病(AD)の発症リスクが低いそうです。米国の研究チームが医学誌BMJに論文を発表しました。
チームは、2020年1月1日~22年12年31日に死亡した成人約900万人のデータを分析したそうです。このうち3.88%に当たる34万8328人がADによる死亡者だったといいます。
443の職業別にみると、ADによる死亡率は救急車の運転手が0.91%と最も低く、次いで1.03%のタクシー運転手だったそうです。つまり、「空間処理能力」や「ナビゲーション処理能力」を頻繁に使う職業です。
一方で、決められたルートを運行する職業にはこうした傾向は見られず、ADによる死亡率はバスの運転手が3.11%で、航空機のパイロットは4.57%だったとのことです。タクシーや救急車の運転手の脳内で起こる神経学的変化が、ADの発症リスクを低下させている可能性があるそうです。

米食品医薬品局(FDA)は20日、米製薬大手イーライリリーの肥満症治療薬「ゼップバウンド(一般名:チルゼパチド)」を閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)の治療薬として承認しました。OSAの治療薬が承認されるのは初めてです。
対象となるのは中等~重度のOSAに苦しむ肥満患者で、薬を使用する際は摂取カロリーを制限し、運動を増やすことが大切だといいます。臨床試験では、ゼップバウンドを使用した患者の半数近くでOSA関連の症状がなくなるほどの改善が見られたそうです。一般的な副作用として軽~中等度の胃腸症状が認められましたが、その多くが投薬開始時や用量増加時に発生しました。
米CNNによると、米国では3千万人もの人がOSAに罹患しており、肥満と密接に関連していることも分かっています。
なお、現在OSAの標準治療として使われているのは「持続陽圧呼吸療法(CPAP)」です。CPAPは睡眠中にマスクで気道に空気を送り、気道の閉塞を防ぐ治療法ですが、その煩わしさから途中で治療をやめてしまう患者もいるといいます。

米カリフォルニア州ロサンゼルスで開催されたグルメイベントでノロウイルスによる集団食中毒が発生し、生ガキを食べた来場者80人以上が体調不良を訴えたそうです。
米NBC Newsによると、このイベントは地元紙ロサンゼルス・タイムズが12月3日にハリウッド地区にある劇場で開催しました。ロサンゼルスの名店を紹介する「101 Best Restaurants list」に関するイベントで、このリストの作成は2014年から続くよく知られたものだといいます。
カキなどの二枚貝は、下水として海に流れ込んだノロウイルスをプランクトンと一緒に摂取することで体内に蓄えます。カキはカナダのブリティッシュコロンビア(BC)州内で収穫したものだといい、米食品医薬品局(FDA)が国内14の州とコロンビア特別区のレストランや小売店に対し、カナダBC州の一部地域産のカキを提供・販売しないよう注意を呼びかけたとのことです。
ノロウイルス感染症の潜伏期間は1~2日で、吐き気や嘔吐(おうと)、下痢、腹痛、発熱などの症状が1~2日間ほど続きます。

水をたくさん飲むことは体に良いといわれています。では、実際にどのような恩恵がもたらされるのでしょうか。米国の研究チームが、医学誌JAMA Network Openに研究成果を発表しました。
チームは、水分摂取量と健康に関する18の既存研究(平均参加人数は48人)を詳しく分析したといいます。その結果、このうち10の研究で、水を多く飲むことによる明確な効果が認められたそうです。なかでも、最も大きなメリットは、腎臓結石のリスクの低下と体重減少でした。
他にも、片頭痛や尿路感染症の予防や、糖尿病や低血圧の管理にも効果的なことが明らかになったといいます。逆に十分な量の水を飲まない場合、短命やさまざまな慢性疾患リスクの上昇に関連することが分かったとのことです。
なお、WHO(世界保健機関)は、温帯気候の下で過ごす場合、男性は1日 3.2L、女性は1日2.7Lの水を飲むことを推奨しています。

更年期の代表的な症状であるホットフラッシュ(のぼせ・ほてり)の治療薬「VEOZAH(ベオーザ)」は、深刻な肝障害を引き起こす可能性があるそうです。米食品医薬品局(FDA)が16日、最も強い警告に当たる「黒枠警告(black box warning)」を添付文書に追加すると発表しました。
まれなケースではあるものの、ベオーザを飲んで倦怠(けんたい)感、異常なかゆみ、吐き気、嘔吐(おうと)、薄色の便、濃色の尿、黄疸などの症状が出た場合は服薬を中止し、医師に相談するべきだとしています。さらにFDAは使用者に対し、服用開始から最初の3カ月間は毎月、それ以降は6カ月目と9カ月目に血液検査で肝臓の数値を調べるよう求めています。
ベオーザは日本のアステラス製薬が開発し、2023年にFDAが承認しました。ホルモン製剤ではなく、体温調節に関連する脳の神経接続を標的にしているそうです。日本でも承認申請に向けて治験が進められているとのことです。
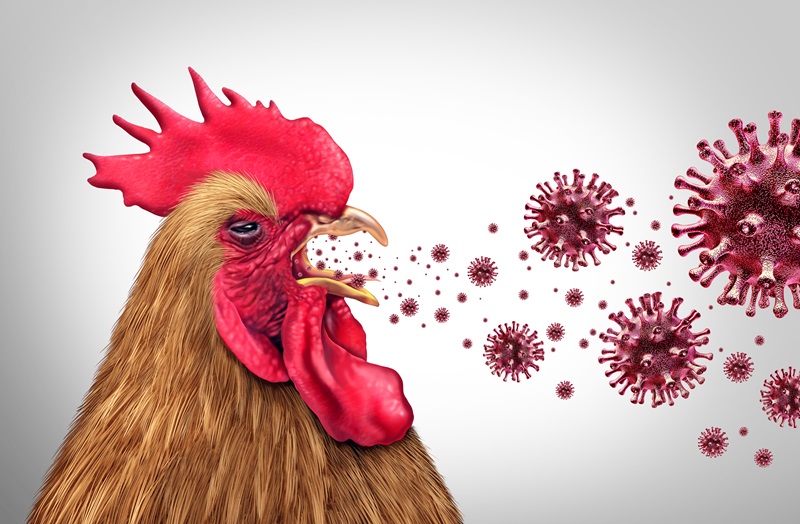
現在流行している鳥インフルエンザウイルス(H5N1)は、遺伝子にたった1カ所の変異が起こるだけで、ヒトの細胞に感染しやすくなる可能性があるようです。米国の研究チームが、科学誌Scienceに研究成果を発表しました。
チームは、最近のヒトへの感染で見つかったウイルス(H5N1 2.3.4.4b株)を詳しく分析したそうです。その結果、ウイルスの主要なタンパク質にたった一つのアミノ酸変異が起こるだけで、ウイルスが感染する際にくっつく標的が「トリ型受容体」から「ヒト型受容体」に切り替わる可能性が明らかになったといいます。
「Q226L」と呼ばれるこの変異は、ウイルスにとって新しい眼鏡のように機能し、ヒト細胞の表面でウイルスが結合できる場所を認識する能力が上がるのだそうです。この変異が起き、ウイルスがヒトの気道の細胞にくっつくことができた場合、飛沫感染でヒトからヒトに感染するリスクが高まります。
このためチームは、ウイルスの変異を監視し続ける重要性を指摘しています。

米ニューヨーク大学ランゴーン医療センターは17日、遺伝子改変したブタの腎臓を53歳の女性に移植することに成功したと発表しました。
女性は1999年に母親に片方の腎臓を提供し、その数年後に妊娠高血圧腎症から腎不全を発症したそうです。2016年に透析療法を始め、17年に腎移植の待機待ちリストに名前が追加されましたが、ドナーは見つかりませんでした。透析のために使える血管が徐々に少なくなるなどの問題が生じたことから、女性は今年の11月25日にブタの腎臓の移植手術を受けたそうです。
ブタの腎臓が生きているヒトに移植されたのは世界で3例目です。ただ、過去の2例の患者は死亡しています。女性の経過は良好で、手術から11日後には退院したそうです。現在は毎日の診察に加えて、人工知能(AI)などを活用し、健康状態のモニタリングが行われているといいます。
今回女性に移植されたブタの腎臓は、拒絶反応を防ぐために初めて10個の遺伝子が改変されたとのことです。

皮膚にクリームを塗るだけのワクチンが実現するかもしれません。米国の研究チームが、科学誌Natureに研究成果を発表しました。
チームが着目したのは、ヒトの皮膚に常在する「表皮ブドウ球菌」です。ヒトは、この細菌が血液に侵入して感染を引き起こす前に、先手を打って抗体を産生しているのだそうです。チームは、通常は表皮ブドウ球菌を持たないマウスの頭にこの菌を塗りました。すると6週間で、表皮ブドウ球菌に対する抗体が一般的なワクチンで誘導される以上の高レベルで産生されることが分かったといいます。
そして、抗体の産生に重要な役割を果たすのは、表皮ブドウ球菌の表面に存在する「Aapタンパク質」であることを発見したそうです。チームは遺伝子操作で、このタンパク質に破傷風毒素の遺伝子を組み込み、その表皮ブドウ球菌をマウスに塗ったといいます。すると、破傷風に対する高レベルの抗体が産生され、致死量の破傷風菌を投与しても、マウスは症状を出さずに生き残ったとのことです。
さらに、チームはこのメカニズムを活用し、ジフテリア菌に対する免疫応答をマウスに誘導させることにも成功しましたそうです。
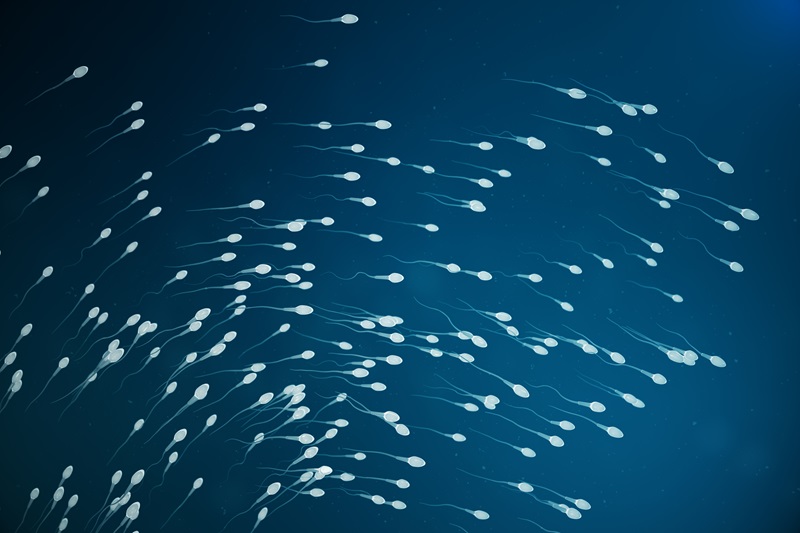
ヒトの精液中に存在し、性行為で感染するウイルスはこれまで考えられていたよりも多いそうです。ドイツの研究チームが、精液中のウイルスに関する373の研究を分析し、医学誌The Lancet Microbeに論文を発表しました。
チームの調査で、22種類のウイルスが急性感染(一過性の感染)後に精液から検出されることが分かったそうです。そして、このうち9種類のウイルス(エボラ、E型肝炎、マールブルグ、ジカ、アデノ、デング、エムポックス、ウエストナイル、アンデス)は性行為で感染することが明らかになったといいます。
一方で、新型コロナウイルスは睾丸(こうがん)や前立腺などの組織から検出されましたが、性的接触では伝染しないことが示されました。エボラ出血熱とジカ熱を引き起こすそれぞれのウイルスは2年以上も精液中で生き続け、ウエストナイル熱とデング熱を引き起こす各ウイルスは3~5週間で精液から検出されなくなるとのことです。
なお、クリミア・コンゴ出血熱とA型肝炎を引き起こすそれぞれのウイルスは、精液中に存在する証拠は見つかっていないものの、性行為で感染する可能性があるといいます。

米科学誌Scienceは2024年の最も重要な成果「ブレークスルー・オブ・ザ・イヤー」に、HIV(エイズウイルス)の感染予防に高い効果を示した「レナカパビル」を選びました。
この薬は米ギリアド・サイエンシズ社の注射剤で、ウイルスの遺伝物質を保護するタンパク質「カプシド」を硬化させて複製の重要な段階を阻止するといいます。Scienceは、この技術が他のウイルス性疾患の治療法開発につながる可能性があるとして高く評価しています。
出生時の性別と性自認が一致する「シスジェンダー」の女性5300人を対象とした治験では、年2回のレナカパビル投与がHIV予防において100%の有効性を示しました。さらに、シスジェンダー男性やトランスジェンダーの男女など3200人を対象とした別の治験でも、HIV感染の予防に96%有効であることが分かったといいます。
HIVの暴露前予防(PrEP)として一般的な錠剤「ツルバダ」は毎日服用する必要がありますが、レナカパビルは年2回の注射で済むというメリットがあります。なお、レナカパビルは22年に米食品医薬品局(FDA)から多剤耐性HIVの治療薬として承認されています。

2023年にカナダで死亡した人の約5%が「ほう助死(自殺ほう助)」によるものだったそうです。カナダ保健省が11日にデータを公表し、英BBCが報じました。カナダでは2016年から終末期患者などに「医師のほう助による死亡(Medically-assisted dying)」が認められているといいます。
カナダでは23年に32万人が死亡しており、そのうち4.7%に当たる1万5300人が医師のほう助による死亡だったそうです。23年のほう助死の割合は前年から16%近く増加しました。過去の平均増加率は31%であり、急激に鈍化したことになります。
ほう助死が適用された人の平均年齢は77歳を超えており、約96%が「死が合理的に予見可能」な状態だったといいます。人種別に見ると、カナダ国民の約70%を構成する白人がほう助死の96%近くを占めたとのことです。州別で見ると、ケベック州でほう助死の利用率が最も高く、全体の37%を占めたそうです。
カナダでは21年に慢性的な身体の苦痛を抱える非終末期患者に対してもほう助死の権利が拡大されています。また、精神疾患患者を対象に加える議論も重ねられているとのことです。

米ルイジアナ州保健当局は13日、鳥インフルエンザウイルスが感染したとみられる州南西部の住人が入院したと発表しました。ルイジアナ州でヒトへの鳥インフル感染が確認されたのは初めてで、鳥インフルの感染者が入院したのは米国で2例目だそうです。米疾病対策センター(CDC)が、地元保健当局と連携して調査を行う予定だといいます。
米国では今年3月以降、乳牛の間で鳥インフル感染が広がっています。米農務省によると、16州で845頭の乳牛の鳥インフル感染が明らかになっています。またCDCによると、少なくとも7州で60人の鳥インフル感染者が確認されており、ほとんどが感染した家禽や乳牛と接触歴のある農場労働者です。今回の患者も、鳥インフルエンザウイルスH5N1型が感染しているとみられる鳥や死んだ鳥に接触していたとのことです。
これまでのところ、感染者の多くが結膜炎などの軽症で済んでいます。ルイジアナ州保健当局は、病気や死んだ動物またはその排泄物に触れたりペットを近づけたりしないこと、低温殺菌されていない生乳を飲んだり、それから作ったチーズを食べたりしないことなどの注意を呼びかけています。

米国のトランプ次期大統領が厚生(保健福祉省:HHS)長官に指名したロバート・ケネディ・ジュニア氏の顧問弁護士であるアロン・シリ氏が、2022年に米食品医薬品局(FDA)に対し、安全性の調査が不十分だとしてポリオワクチンの承認取り消しの申し立てを行っていたことが明らかになりました。米国の各メディアが報じています。
米ABC Newsによると、シリ氏は自身のクライアントの代理人としてこの申し立てに関与したそうです。ポリオはウイルスによる感染症で、重症化すると手足にまひが残ったり、死亡したりします。
米疾病対策センター(CDC)によると、米国では乳幼児に対するポリオワクチンの定期接種が実施されており、3回接種で99%の予防効果が得られます。副反応は通常軽度で、ポリオワクチンが深刻な問題を引き起こすとの報告はありません。
シリ氏はポリオ以外にもB型肝炎ワクチンなどの供給停止を求める請願書の提出にも関与しているそうです。またシリ氏はHHSの幹部選びにも関わっているといい、ケネディ氏に対し、ワクチン問題に関する自身の立場を明らかにするべきとの声が上がっているとのことです。

WHO(世界保健機関)のアメリカ地域事務局である汎米保健機構(PAHO)は10日、中南米における2024年のデング熱患者が昨年の3倍近くに達したと発表しました。今年確認された患者は1260万人、死者は7700人を超え、1980年に統計が開始されて以来、いずれも最多を記録したといいます。
特にブラジル、アルゼンチン、コロンビア、メキシコで感染が拡大しており、これらの国々の患者が全体の90%を占めるそうです。子どもや基礎疾患を持つ人は特に重症化リスクが高いといいます。グアテマラではデング熱による死亡者の70%が子どもで、メキシコ、コスタリカ、パラグアイでは重症患者の3分の1以上が15歳未満だったとのことです。
ブラジルやアルゼンチンなど一部の国ではデング熱ワクチンの接種がすでに行われていますが、ホンジュラスなどでは25年から接種を開始する予定だそうです。
デング熱は蚊に刺されることによって感染するウイルス性熱性疾患です。発熱、激しい頭痛、目の奥の痛み、筋肉痛、関節痛、斑状発疹などの症状がみられます。重症型の場合、激しい腹痛、倦怠(けんたい)感、嘔吐(おうと)、吐血、血便などに見舞われることがあります。
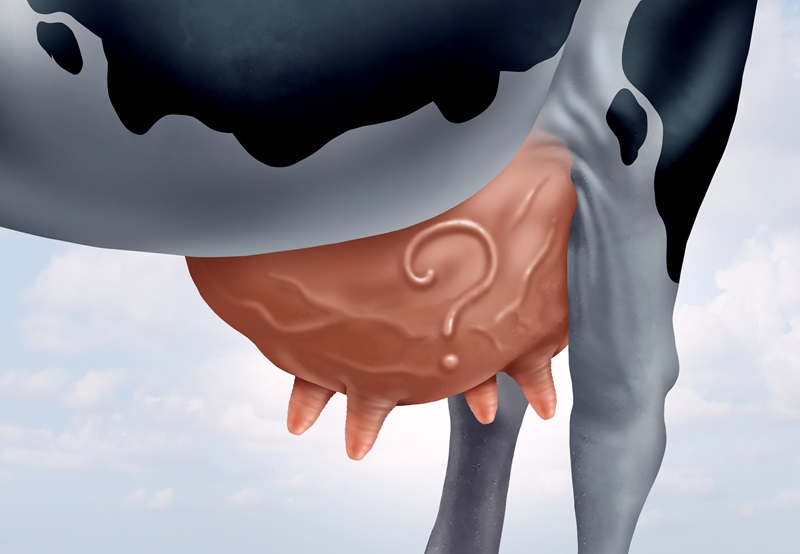
米国で今年3月から鳥インフルエンザウイルスH5N1型が乳牛の間で流行しているのを受け、米農務省は国内の生乳についてウイルスの有無を調べる検査を12月16日から開始するそうです。生乳を取り扱う業者は要請に応じてサンプルの提出が義務付けられます。米CNNや米NBC Newsなどが報じました。
CNNによると、米カリフォルニア州では、低温殺菌処理のされていない生乳を飲んだ後、少なくとも10人が体調を崩したことが分かっているそうです。初期の検査では、これらの人から鳥インフルの陽性反応は確認されていないとのことです。
カリフォルニア州では、マリン郡の保健当局が10日、子ども1人が生乳を飲んで鳥インフルエンザウイルスに感染した可能性があると発表する騒ぎも起きています。結局、米疾病対策センター(CDC)の検査で陰性だったことが12日に明らかになりました。
子どもが飲んだ生乳は、ウイルスが検出されたために11月下旬に一部製品の出荷停止や自主回収の措置が取られた会社が販売したものだそうです。同社の生乳を飲んだ室内飼いの猫2匹に鳥インフルが感染した疑いも報告されているといいます。

主要な男性ホルモンである「テストステロン」の値が上昇すると、男性の性的欲求が高まるといわれています。しかしこの説は、しっかりとした検証に基づいたものではないそうです。米国の研究チームがこの真偽を確かめる実験を行い、科学誌Proceedings of the Royal Society Bに論文を発表しました。
チームは、成人男性41人を対象に31日間の調査を実施しました。参加者は毎日、テストステロン値を測定するために使う唾液を採取し、性的欲求レベルの記録を行ったといいます。テストステロン値は、疲労の度合いや食事内容の影響を受けて変動するため、チームはそれを考慮してデータを分析したそうです。
その結果、日々のテストステロン値と性的欲求レベルに関連は認められないことが分かったといいます。その代わり、パートナーがいないシングル男性においては、テストステロン値が高い日に、交際につなげるための努力が増える傾向があったそうです。テストステロンは、性的欲求よりもむしろパートナー探しの原動力になる可能性が示されました。

自動車などによる交通騒音は精神状態に悪影響を与えるそうです。英国の研究チームが、学生ボランティア68人に行った調査結果を科学誌PLOS ONEに発表しました。
チームが行ったのは、3分間の環境音を3種類聞いてもらう実験です。一つ目は鳥のさえずりなどの自然環境音、二つ目は自然環境音に時速20マイル(約32km)で走る車両の交通音が入ったもの、三つ目は自然環境音に時速40マイル(約64km)の交通音が入ったものです。
その結果、自然環境音を聞くと、自己申告による不安やストレスが軽減し、ストレス要因にさらされた後の気分の回復が促進されることが分かったそうです。しかし、時速20マイルの交通音が混ざると不安やストレスが増加し、時速40マイルの交通音が混ざった場合はさらに強い不安やストレスを報告したとのことです。
この研究で、交通音によって自然環境音による癒し効果が低減することが明らかになりました。チームは、街中を走る車両のスピードを制限することで騒音が減れば、人々の健康や幸福度にプラスの影響があるかもしれないとしています。

米国では、この10年ほどで小児の入院病棟や病床数が大幅に減少しているそうです。米国の研究チームが、国内4800以上の内科・外科病院に関する2008~22年のデータを分析した結果を医学誌JAMA Pediatricsに発表しました。
調査の結果、小児入院病棟を持つ病院はわずか2074(43%)であることが明らかになったといいます。さらに08~22年で、小児用の入院病棟数は30%、病床数は19.5%、それぞれ減少したそうです。一方、同じ期間で成人用の入院病棟数は4.4%、病床数は3%、それぞれ減少するにとどまったとのことです。
チームは、減少傾向が08~18年は緩和していたものの、18~22年は衰えることなく続いたことが最大の発見だとしています。つまり、19年に始まった新型コロナウイルス感染症の流行で、小児用から成人用に変更された病床がそのままになっている可能性があるのだそうです。
ほかにも、成人の病床数を確保した方が収益を上げやすいことや小児科のスタッフが不足していること、小児を入院させるためには専門性を持ったリソースが必要であることなどが小児病棟の閉鎖と関係していると考えられるとのことです。

ぜんそくや慢性閉塞性肺疾患(COPD)の急性増悪(発作)の治療薬が50年ぶりに見つかったかもしれません。The Conversationに英国などの呼吸器内科の専門家による記事が掲載されています。
ぜんそくやCOPDの発作の多くは、白血球の一種である好酸球による炎症が原因で起こるといいます。標準治療はステロイド(プレドニゾロン錠など)を使うものですが、1カ月以内に再発する患者が少なからずおり、高血糖や脂質代謝異常などの副作用の問題もあるそうです。
英国などの研究チームが、好酸球性ぜんそくの長期管理に使われるモノクローナル抗体製剤「ベンラリズマブ」に着目。ぜんそくかCOPDの発作が起きている患者158人を「プレドニゾロン錠の投与」「ベンラリズマブの注射(1回)」「プレドニゾロン錠とベンラリズマブの併用」の3群に分けて治療したそうです。
その結果、90日以内に追加の治療が必要になるか入院または死亡した人は、プレドニゾロン錠群で74%、ベンラリズマブ群で47%、併用群で42%だったといいます。なお、ベンラリズマブを使用した人は症状からの回復が早く、呼吸が楽になり不快感が減ったそうです。

心臓発作や心不全、脳卒中などの主要心血管イベント(MACE)のリスクを抑制するには、「規則正しい睡眠習慣」がカギになるようです。オーストラリアとカナダの研究チームが、医学誌Journal of Epidemiology & Community Healthに研究成果を発表しました。
チームは、MACEの既往歴がない40~79歳の中高年7万2269人を対象に調査を実施しました。参加者の就寝時間や起床時間、睡眠時間、途中で起きた回数を7日間記録し、「規則的な睡眠パターン」「やや不規則な睡眠パターン」「不規則な睡眠パターン」の3群に分け、その後8年間にわたって追跡調査を行いました。
その結果、不規則な睡眠パターン群は、規則的な睡眠パターン群に比べてMACEリスクが26%高くなることが明らかになったそうです。やや不規則な睡眠パターン群は、規則的な睡眠パターン群に比べてリスクが8%上昇したといいます。
さらに、たとえ十分な睡眠時間を取ったとしても、睡眠パターンが不規則な場合は、MACEリスクの上昇を避けられないことも示されました。

米国のトランプ次期大統領は米NBC Newsの報道番組に出演し、自身が厚生(保健福祉省:HHS)長官に指名したロバート・ケネディ・ジュニア氏が小児ワクチンと自閉症の関連を調査する可能性を示唆しました。
ワクチン(おたふくかぜ、麻疹<はしか>、風疹)と自閉症の関連については、1998年に英国の医師が最初に主張したそうです。しかし、後にこの研究に重大な欠陥があることが判明し、論文は撤回されています。そしてこれまでに何百もの研究で、小児ワクチンの安全性が立証されています。
一方で、2000年に自閉症と診断された子どもは150人に1人だったのに対し、今日では36人に1人に増加しているのは事実だそうです。これについてトランプ氏は「ワクチンが原因かどうかは分からないが、何かが起きている。誰かが明らかにしないといけない」と述べ、調査に前向きな姿勢を示しました。
しかし専門家は、自閉症の診断数の急増にはスクリーニングの増加や定義の変更が影響していると指摘しています。

メキシコ保健当局は、首都メキシコシティ郊外にある四つの医療機関で子ども13人が細菌に汚染された輸液バッグが原因で死亡したとみられるとして、詳しい原因の調査を行っているそうです。米NBC Newsが報じました。
感染者が最初に見つかったのは11月のことだといいます。13人はいずれも14歳未満で、血液感染症で死亡したようです。他にも7人が入院しているとのことです。この20人のうち、15人から「Klebsiella oxytoca(クレブシエラ・オキシトカ)」と呼ばれる多剤耐性菌が検出されたといいます。さらに別の4人もこの細菌に感染している可能性が示されたとのことです。ただ、残りの1人についてはその可能性が排除されたそうです。
問題の輸液はメキシコの企業が製造したものだといいます。栄養を補給するための輸液かその関連用品が、今回の感染に関係していると考えられています。保健当局も医師に対し、同社の栄養輸液を使用しないよう命じたとのことです。
ここ数年、メキシコでは医療用品の汚染問題がたびたび起きているといいます。

米カリフォルニア州の中学校教諭の60歳の女性が11月22日に狂犬病で死亡したと、米CNNが報じました。女性は死亡の1カ月ほど前の早朝に、勤務する学校の教室で床にコウモリがいるのを見つけて外に逃がしたと、友人が証言しているそうです。この時、知らない間にコウモリにかまれたか引っかかれた可能性があるといいます。
女性は当初、医師の診察を受けなかったそうです。そして11月半ばに、発熱と手の震えの症状が出始めたといいます。11月18日に入院し、翌日から4日間の昏睡状態を経て22日に死亡しました。
州の保健当局によると、米国における狂犬病の感染者は、ほとんどがコウモリが原因だそうです。女性の事例を受け州保健当局は、コウモリをはじめとする狂犬病の可能性がある動物に接触した場合は、すぐに医療機関を受診するよう呼びかけました。
狂犬病は、狂犬病ウイルスに感染した動物に接触することでヒトにうつります。ウイルスは中枢神経系を攻撃して脳炎を引き起こします。適切な治療を受けずに発症すれば、ほぼ100%死に至ります。

新型コロナウイルス感染症の流行時に、感染対策として多くの医療機関で行われたマスクの着用は本当に効果があったのでしょうか。米国の研究チームが、2020年11月~24年3月に10カ所の医療機関に入院した患者64万1483人のデータを分析した結果を医学誌JAMA Network Openに発表しました。
チームは、入院から4日以内に新型コロナ、インフルエンザ、RSウイルスのいずれかの陽性が確認された場合を「市中感染」、5日目以降に陽性が確認された場合を「院内感染」と定義しました。
市中感染に対する院内感染の比率(週平均)を調べたところ、マスクの着用と入院患者に対する新型コロナのPCR検査といった感染対策をしていた時期は、新型コロナのオミクロン株流行前が2.9%、オミクロン株流行中が7.6%だったそうです。
しかし、23年5月に二つの感染対策が段階的に廃止されて以降、この比率は15.5%に上昇し、24年1月に医療従事者のマスク着用措置が復活すると8.0%に再び低下したといいます。チームはマスクの着用などの対策が院内感染の予防に有効である可能性が示されたとしています。

アフリカ中部のコンゴ民主共和国で、インフルエンザに症状の似た原因不明の病気が広がっているそうです。米NBC Newsや英BBCなどによると、今月3日の時点で79人が死亡し376人が罹患したと、コンゴ民主共和国の保健当局が発表。死者の大半は15~18歳の若者だといいます。一方、地元当局は、死者は143人に上る可能性があると説明しているとのことです。
主な症状は発熱や頭痛、鼻水、せき、呼吸困難、貧血など。被害が拡大している南西部のクワンゴ州は医療資源が乏しく、住民は感染症や栄養失調などさまざまな健康上の問題を抱えているそうです。このため、この謎の病気の診断が難しい状況にある可能性も指摘されています。
コンゴ民衆共和国の保健当局は住民に対し、人が集まるイベントを避け、せっけんを使って手を洗うなどの基本的な感染対策を徹底するよう呼びかけたそうです。また、WHO(世界保健機関)や米疾病対策センター(CDC)が、現地に調査チームを派遣したといいます。

あなたの薬指と人差し指はどちらのほうが長いですか? 薬指の方が長い人は酒飲みの傾向があるそうです。英国とポーランドの研究チームが、科学誌American Journal of Human Biologyに論文を発表しました。
チームは大学生258人(男性89人、女性169人)を対象に薬指と人差し指の長さの比率を計測し、アルコール摂取量との関係を調査しました。その結果、薬指の方が長い人は、アルコール摂取量が多いことが分かったそうです。こうした関連性は、女性より男性に強く見られたといいます。
なお、胎児期に男性ホルモンの一種である「テストステロン」を多く浴びると薬指が長くなり、女性ホルモンの一種である「エストロゲン」を多く浴びると人差し指が長くなるといわれています。また、アルコール依存症患者は薬指の方が長いことが知られているそうです。チームは、胎児期に浴びる性ホルモンが、出生後の飲酒習慣に影響を及ぼす可能性が示されたとしています。

米疾病対策センター(CDC)は3日、大手ハンバーガーチェーンのマクドナルドが販売した「クォーターパウンダー」に関係する集団食中毒について、流行が収束したと発表しました。
今回の集団食中毒は腸管出血性大腸菌O157によるもので、カリフォルニア州の食品メーカーが供給したスライスタマネギが原因とみられます。10月22日に調査が始まって以来、14の州で104人の患者が報告されました。このうち34人が入院し、少なくとも4人が腎不全を引き起こす可能性がある「溶血性尿毒症症候群(HUS)」を発症したといいます。また、コロラド州の高齢者1人が死亡しました。
米NBC Newsによると、食品メーカーが早い段階でタマネギの自主回収に踏み切ったことが、被害の拡大を食い止める結果につながったようです。米食品医薬品局(FDA)も、今回の食中毒に関連する食品安全上の懸念は払拭されたとして、調査の終了を発表しました。

運動後、「氷風呂(アイスバス)」と「温かい風呂」のどちらに入るほうが体の回復に効果的なのでしょうか。立命館大学の研究チームが科学誌Exercise and Sport Sciences Reviewsに発表した研究成果について、米NBC Newsが報じています。
チームは若い男性被験者10人に調査を実施したそうです。被験者は全員、高強度のインターバル走を50分間行った後に、15℃の氷風呂に20分間入る▽40℃の風呂に20分間入る▽風呂に入らずに座って休む──の3パターンを行いました。そして各パターンの後に、ジャンプ力を測定したといいます。
その結果、温かい風呂に入った後の方が、氷風呂に入った後より高くジャンプできることが分かったそうです。お湯の温かさで血流が増加し、激しい運動によって損傷した筋肉が修復・増強されるといいます。
サッカーなどの前半と後半の間にハーフタイムがあるスポーツでは、休憩中に体を温めたほうが、パフォーマンス向上につながる可能性があるようです。ただし、けがをしている場合は、冷やすほうが効果的とのことです。

毎日コーヒーを飲むと特定の腸内細菌が豊富になり、健康によい効果をもたらすかもしれません。米国などの研究チームが、米国と英国に住む2万2867人と別の211の集団の5万4198人から採取した便サンプルのデータを分析し、研究成果を科学誌Nature Microbiologyに発表しました。
チームの調査の結果、コーヒーを1日3杯より多く飲むと報告した人は、ほとんど飲まないと報告した人に比べて「Lawsonibacter asaccharolyticus (L.asaccharolyticus:ローソニバクター・アサッカロリティカス)」と呼ばれる腸内細菌の量が8倍にも上ることが分かったそうです。これは、世界中の人々に共通していたといいます。試験管内で行った実験では、コーヒーがL.asaccharolyticusの成長を促すことも示されたそうです。
この研究により、特定の飲食料が、腸内細菌叢の組成に大きな影響を及ぼす可能性が示されました。現段階ではL.asaccharolyticusの影響は不明ですが、チームはコーヒーを飲むことによる健康上のメリットと関係していると考えているようです。

ビタミンB3の一種である「ニコチンアミドリボシド(NR)」が慢性閉塞性肺疾患(COPD)の治療に有効な可能性があるそうです。デンマークの研究チームが科学誌Nature Agingに論文を発表しました。
COPDは主にたばこの煙を長期にわたって吸うことで発症する肺の炎症性疾患です。チームは、COPD患者40人と健康な人20人を2群に分け、一方にはNRを、もう一方にはプラセボをそれぞれ1日2gずつ6週間飲んでもらいました。
6週間後、NRを飲んだCOPD患者はプラセボ群に比べて、炎症マーカーである「インターロイキン8(IL8)」のレベルが52.6%低下することが分かったそうです。さらに、こうした炎症抑制効果は実験終了から12週間後まで持続したといいます。
また、COPD患者は、老化を遅らせるとされる血中NAD(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド)濃度が低下していたにもかかわらず、NRを取るとNAD濃度が上昇することも示されたとのことです。

私たちの腸内細菌叢(腸内フローラ)の組成は、家族だけでなく友人など社会的なつながりがある人とも類似性が高くなるようです。米国の研究チームが科学誌Natureに研究成果を発表しました。
チームは、中米ホンジュラスの人里離れた18の村に住む成人1787人から腸内細菌叢を採取し、社会的交流の範囲をマッピングしたデータを分析したそうです。その結果、さまざまな関係性を通じて社会的なつながりがある人同士は、腸内細菌叢の組成において偶然を超える類似性を示すことが分かったといいます。
こうした腸内細菌叢の共有は、配偶者や同じ世帯に住む人の間で最も多く確認されましたが、友人や二次的なつながりがある人(友人の友人など)の間でも高い割合で観察されたとのことです。
食事を共にする頻度や、握手、ハグ、キスなどといったあいさつの仕方など、人々が一緒に時間を過ごす頻度も腸内細菌叢の共有率に関連していることが明らかになったそうです。

一般的な心血管系薬を長期間使用すると、認知症を発症するリスクが低下する可能性があるようです。スウェーデンの研究チームが医学誌Alzheimer’s & Dementiaに研究成果を発表しました。
チームは2011~16年に認知症と診断された70歳以上の高齢者8万8065人と年齢や性別を一致させた対照群88万650人のデータを比較したそうです。その結果、心血管系薬として知られる降圧薬、利尿薬、脂質低下薬(LLD)、経口抗凝固薬(OAC)のいずれかを5年以上使用した人は、非使用者に比べて認知症と診断されるリスクが4~25%低くなることが分かったといいます。
また、降圧薬と他の心血管系薬を併用すると、認知症リスクはさらに低下したそうです。一方で、血栓の形成を防止するため脳梗塞(こうそく)の予防に使われる抗血小板薬は、認知症リスク上昇に関連することが示されたとのことです。これは抗血小板薬が、認知機能低下と関連する脳内の微小出血のリスクを高めるためと考えられるそうです。

英BBCによると、英議会下院は11月29日、イングランドとウェールズの終末期患者に対して「ほう助死(Assisted Dying)」(自殺ほう助)の権利を認める法案の1回目の採決を行い、賛成多数で可決しました。2015年には同様の法案が否決されており、法制化への歴史的な一歩を踏み出しました。
1回目の結果は賛成330、反対275だったそうです。今後、さらなる審議や精査を重ね、上下両院の賛成を得て成立する見通しです。法案の内容が修正される可能性もあるとのことです。採決にあたっては、議員は党の方針に従う必要はなく、各自の良心に従って投票したといいます。男性議員よりも女性議員のほうが高い割合で法案を支持したとのこと。法案に賛成の支持者たちは、涙を流して採決の結果を歓迎したそうです。
一方、反対派の議員は、高齢者や障害者などが人生を終わらせるべきだと圧力を感じる可能性があるとの懸念を示し、ほう助死の導入ではなく、終末期ケアの改善に焦点を当てるべきだと主張したといいます。

「お化け屋敷」で恐怖を味わうと、炎症が軽減する可能性がある。そんな研究成果をデンマークの研究チームが科学誌Brain, Behavior, and Immunityに発表しました。
チームは、平均年齢29.7歳の113人に約50分間のお化け屋敷を体験してもらう実験を行ったそうです。参加者が報告した恐怖レベルは、1~9段階で平均5.4だったといいます。
血中の炎症マーカーである「高感度CRP(hs-CRP)値」を調べたところ、お化け屋敷の体験前に軽度の炎症が認められた22人のうち、18人(82%)で、3日後のhs-CRP値が低下したそうです。さらに、10人(45.5%)については、3日後のhs-CRP値が正常になったといいます。
血液中の免疫細胞を調べたところ、元々hs-CRPが正常だった人はリンパ球、単球、好酸球、好塩基球が、軽度の炎症があった人はリンパ球と単球が、お化け屋敷体験から3日後にそれぞれ減少することが分かったとのことです。
娯楽としての恐怖によって血液中のhs-CRP値や免疫細胞数のバランスが調整される可能性が示されました。

米国のトランプ次期大統領は11月26日、国立衛生研究所(NIH)所長にスタンフォード大学教授のジェイ・バタチャリヤ氏を指名する意向であると発表しました。
米NBC Newsによると、バタチャリヤ氏は米国の新型コロナウイルス感染症対策に批判的な立場を取ってきた人物です。トランプ氏は、ワクチン懐疑論者で次期厚生(保健福祉省:HHS)長官に指名されているロバート・ケネディ・ジュニア氏とともに、バタチャリヤ氏が同国の医学研究分野を指揮することに期待を寄せているとしています。
バタチャリヤ氏は新型コロナワクチン普及前の2020年10月、他の2人の学者と共同で、新型コロナ対策のロックダウン(都市封鎖)をやめるよう求める「グレート・バリントン宣言」を発表。「集団免疫」の獲得を目指して、ウイルスに感染しにくい人々は通常の生活に戻るよう呼びかけたといいます。
その直後、公衆衛生の専門家80人がこの宣言について「危険で誤った考え」であるとの共同書簡を医学誌Lancetに公表するなど物議を醸したそうです。

気持ちを落ち着けるために深呼吸をする人は多いと思います。この時に脳ではどのようなことが起きているのでしょうか。米国の研究チームがそのメカニズムを明らかにし、科学誌Nature Neuroscienceに発表しました。
チームがマウスの脳を調査したところ、前頭葉で複雑な思考や感情、血圧や心拍数の調節などをつかさどる「前帯状皮質」のニューロン(神経細胞)が、脳幹の中央の呼吸調節に関わる「橋」を通り、そのすぐ下にある呼吸中枢「延髄」まで接続していることが明らかになったそうです。この三つを通る神経回路を人工的に活性化すると、マウスの呼吸が遅くなり、不安を表すしぐさが減ったそうです。逆にこの回路を阻害すると、呼吸が速まり、不安を表す行動が増えたといいます。
結論として、感情に合わせて呼吸を自発的に調整する際に「前帯状皮質・橋・延髄」回路が重要な役割を果たすことが示されました。こうした知見が、過呼吸の予防や不安やパニックのコントロールに役立つ可能性があります。
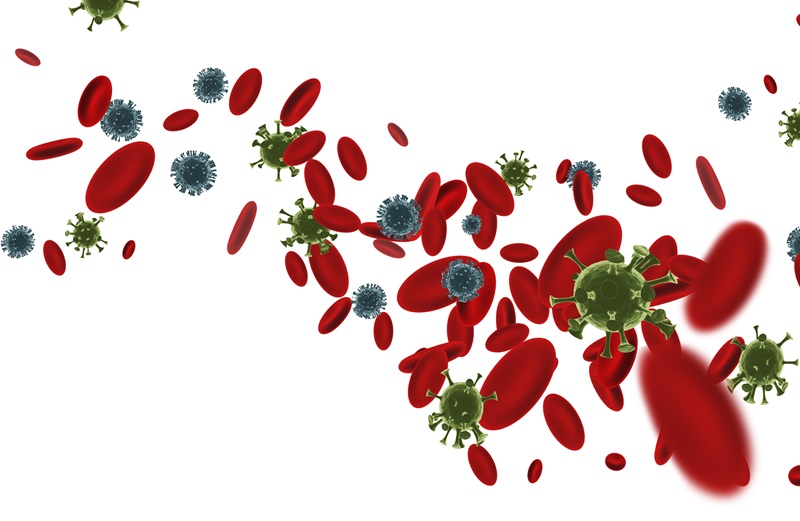
新型コロナウイルス感染後に特定のがんが縮小するケースが報告されているそうです。米国の研究チームがこのメカニズムを解明し、医学誌Journal of Clinical Investigationに発表しました。既存の抗がん剤が効かない患者に対する新たな治療法につながるかもしれません。
チームは、新型コロナウイルスのRNAが免疫系の特別な信号を刺激し、白血球の一種である「単球」が、がんを攻撃する能力を持つ特殊な免疫細胞「誘導性非古典的単球(I-NCM)」に分化することを発見したそうです。がん細胞は、免疫系や抗がん剤から逃れたり成長したりするための細胞や血管に取り囲まれています。新たに形成されたI-NCMは、この腫瘍周辺組織にも侵入できるという、他の免疫細胞にはない強みがあるといいます。
チームは、薬剤を使ってI-NCMを誘導する実験もマウスで行ったそうです。その結果、I-NCMが特にメラノーマ(黒色腫)、肺がん、乳がん、大腸がんと戦うのに有効であることが分かったとのことです。

米国のトランプ次期大統領は22日、感染症対策や予防接種の指針に関して中心的な役割を果たす米疾病対策センター(CDC)の所長に、元下院議員で医師のデーブ・ウェルドン氏を起用すると発表しました。
NBC Newsによると、ウェルドン氏はCDCのワクチンプログラムに対する辛口の批評家として知られ、ワクチンに含まれる防腐剤が自閉症に関連するなどといった誤った主張を展開したこともあるそうです。
上院に承認されれば、同じくワクチン懐疑論者で、次期厚生(保健福祉省:HHS)長官に指名されているロバート・ケネディ・ジュニア氏とともに、米国のワクチン政策に大きな影響力を持つことになります。CDC所長は、外部の諮問委員会によるワクチン使用の可否に関する勧告に従うのが通例ですが、この勧告を拒否する権限も持つそうです。さらに、この諮問委員会のメンバーはHHS長官が任命できるといいます。
鳥インフルエンザや百日ぜき、麻疹(はしか)などさまざまな感染症に対する脅威が高まる中で、両氏がワクチンに関する主導権を握ることになります。

「電子たばこ」は血管の働きに即座に悪影響を及ぼす可能性があるそうです。米国の研究チームがイリノイ州シカゴで開かれた北米放射線学会で研究成果を発表し、米CNNが報じました。
電子たばこは液体(リキッド)を加熱させることで発生する蒸気(ベイパー)を楽しむ製品です。研究チームは、紙巻きたばこか電子たばこを吸う21~49歳の31人を対象に、たばこを吸う前後の血管の様子をMRIで調査し、たばこ類を吸わない10人のデータと比較したそうです。その結果、たばこ類を吸うたびに、下半身全体に酸素を含んだ血液を供給する大腿(だいたい)動脈の安静時の血流速度が低下することが分かったといいます。
また、血管の拡張・収縮などの血管機能は、非喫煙者や紙巻きたばこを吸う人に比べて電子たばこを吸う人の方が低下したそうです。最も血管機能を低下させるのはニコチン入りの電子たばこで、次にニコチンなしの電子たばこだったとのこと。さらに、ニコチンの有無にかかわらず、電子たばこを吸った人は酸素飽和度が低下することも明らかになったといいます。

南米で流行している発熱性疾患「オロプーシェ熱」について、母親から胎児に感染(垂直感染)した例が確認されたそうです。ブラジルの研究チームが医学誌New England Journal of Medicineに発表しました。
WHO(世界保健機関)によると、オロプーシェ熱はヌカカ(ハエ目の微小昆虫)や蚊に刺されることで「オロプーシェウイルス(OROV)」が感染して発症します。2023年12月以降、過去に感染が確認されていない地域でも患者が報告されるようになったといいます。
チームは、過去に流行が起きていない同国北東部セアラ州に住む、妊娠糖尿病の投薬治療を受けていた40歳の患者について報告しています。2024年7月24日、妊娠30週だった女性は発熱や悪寒などを訴えたそうです。27日には膣から軽い出血があり超音波検査で胎児巨人症が判明。その後、胎動が少なくなり、8月5日に子宮内で胎児が死亡していることが確認されました。
女性の血液からOROV感染が明らかになったそうです。さらに死亡した胎児の組織からはOROVのRNAが検出され、現在ブラジルで流行している株と一致したといいます。

米国のトランプ次期大統領は22日、食品医薬品局(FDA)長官にジョンズ・ホプキンス大学の外科医マーティン・マカリー氏を起用すると発表しました。上院に承認されれば、次期保健福祉省(HHS)長官に指名されたロバート・ケネディ・ジュニア氏の管轄下で、医薬品や食品、医療機器、タバコ、化粧品などの規制および監督を行うFDAを率いることになります。
米NBC Newsによると、マカリー氏はワクチン懐疑論などで批判を浴びるケネディ氏を擁護する発言をしています。マカリー氏本人も、新型コロナウイルス感染症の流行時に、ワクチンよりも自然免疫の獲得を推奨するなどし、物議をかもしました。また、「(心臓の筋肉に炎症が起こる)心筋炎は、新型コロナ感染後よりも新型コロナワクチン接種後の方が多く発生する」と、現在は誤りだと証明されている主張をしていたそうです。
トランプ氏はマカリー氏について、「食品に含まれる有害な化学物質や若者に投与されている薬剤を適切に評価し、小児慢性疾患の蔓延に対処するだろう」と述べ、「国民の信頼を失ったFDAの軌道を修正する必要性」を強調したといいます。

慢性の尿路感染症(UTI)は通常、抗菌薬(抗生物質)で治療されます。しかし、抗菌薬の多用は原因菌の薬剤耐性化を加速させてしまいます。この解決策として米国の研究チームが、UTIの原因菌を抑え込むためのバイオマテリアル(生体材料)を開発したそうです。
このバイオマテリアルは、栄養の奪い合いでUTIの原因菌に勝つことができる有益な大腸菌を放出するといいます。通常、細菌をぼうこう内に入れても、ぼうこう壁に付着できずに尿で洗い流されてしまうそうです。しかし、バイオマテリアルは水滴の500分の1ほどの大きさで、最大2週間かけて大腸菌をぼうこう内に放出するよう設計されており、ぼうこう壁に付着しなくても大腸菌が増殖できるといいます。
ペトリ皿を使ってヒトの尿で調査したところ、UTI原因菌とこの大腸菌の比率が50:50のとき、大腸菌が原因菌を打ち負かし、全体の約85%まで増加したとのことです。さらに、原因菌より大腸菌を多く加えると、大腸菌の割合が99%以上になり、原因菌がほぼ一掃されることが明らかになったといいます。
チームは今年5月、研究成果を医学誌Infection and Immunityに発表しました。

バックパッカーに人気のラオス中部の観光地バンビエンで、メタノール中毒の疑いで外国人観光客6人が相次いで死亡したそうです。複数の海外メディアが報じています。米公共ラジオNPRやAP通信によると、死亡したのはオーストラリア人2人、デンマーク人2人、英国人1人、米国人1人で、被害者の多くは19~20歳の若者です。メタノールの混入した飲み物を飲んで、中毒を起こしたとみられています。
メタノールは工業用に使われるアルコールの一種です。税金がかかるエタノール比べてコストが低いため、安価なアルコール飲料の材料として違法に使われることがあるそうです。観光客は知らないうちにこうした密造酒を口にする可能性があり、米国務省はラオスへの観光客に対し、認可を受けた酒屋やバーなどでのみ酒類を購入し、ラベルなどを調べて偽造されていないか調べるよう注意を呼びかけたといいます。
メタノールはわずか25ml摂取するだけで、適切な治療を受けないと死に至る可能性があるそうです。メタノール中毒の初期は典型的なアルコール中毒に似ていますが、12~24時間後には呼吸困難、腹痛、さらには昏睡などのより深刻な症状が現れるとのことです。

血中コレステロール値が高くなると認知症リスクが上昇するといわれています。それでは、コレステロールを多く含む卵を食べると、認知機能に悪影響を及ぼすのでしょうか。米国の研究チームが、科学誌Nutrientsに研究成果を発表しました。
チームは、55歳以上の男女890人(男性357人、女性533人)を4年間にわたり追跡したデータを分析しました。卵を食べる頻度が、全くない(男50人、女88人)▽1カ月間に1~3個(男58人、女136人)▽1週間に1個(男84人、女123人)▽1週間に2~4個(男140人、女166人)▽1週間に5個以上(男25人、女20人)――の群に分けて比較したといいます。
その結果、まず、男女ともに1週間に卵を2~4個食べる群が、血中コレステロール値が最も低いことが分かったそうです。さらに女性に関しては、卵を多く食べる人ほど認知機能を調べるテストで、スコアの低下が抑制されることが判明したといいます。こうした結果から、男女ともに卵が認知機能の維持に有益な可能性が示されました。
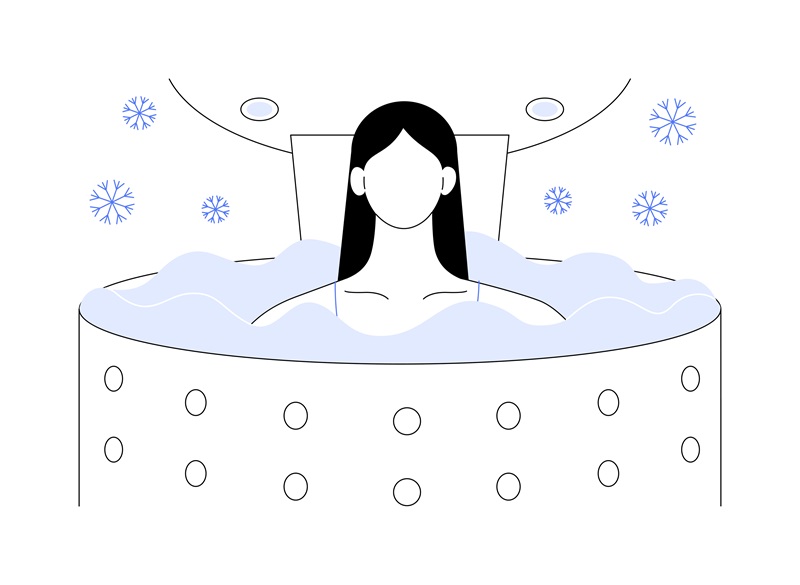
極めて低い温度の刺激を全身に受ける「クライオ刺激」は健康に有益だといわれているそうです。フランスの研究チームが、クライオ刺激が睡眠の質や気分を向上させる可能性があることを明らかにしたと、科学誌Cryobiologyに論文を発表しました。
チームは、平均年齢23歳の健康な男女20人に対し、5日間連続でマイナス90度の部屋で5分間過ごすクライオ刺激を受けてもらったそうです。その結果、徐波睡眠と呼ばれ、身体の回復や修復に効果があるとされる睡眠周期の中で最も深い睡眠が、入眠から2回の睡眠周期の間に平均7.3分増加したといいます。なお、効果を得るには5日間連続でクライオ刺激を受ける必要があったとのことです。
また、男性より女性の方がクライオ刺激の恩恵をより多く受けることも分かりました。女性はアンケートに対し、3日目と4日目の夜に睡眠の質が改善したと報告したそうです。具体的には5段階評価で平均3.4だった睡眠の評価スコアが3.9に上昇したとのことです。さらに女性は、不安の度合いを評価するスコアも改善することが分かったといいます。

米カリフォルニア州公衆衛生局(CDPH)は19日、サンフランシスコ・ベイエリアのアラメダ郡に住む子ども1人に鳥インフルエンザウイルスが感染した可能性があると発表しました。子どもは鳥インフル検査で陽性が出たため、米疾病対策センター(CDC)が確認を進めているといいます。
この子どもには軽度の上気道症状がありましたが、治療を受けて自宅で回復しているそうです。ただし、他の呼吸器感染症ウイルスの検査でも陽性が出たといい、症状が鳥インフルによるものではない可能性もあるといいます。
鳥インフルがどうして感染したのかは不明で、今のところ感染した動物との接触は確認されていないとのことです。専門家が、この子どもが野鳥と接触していないかの調査を進めているといいます。家族は全員、鳥インフル検査で陰性だったそうです。
CDCによると、今年米国では53人(19日現在)の鳥インフル感染が確認されています。1人を除く全員が、感染した家禽または乳牛に接触していたことが分かっています。

米国のトランプ次期大統領は19日、元テレビ司会者として知られるメフメト・オズ氏を公的医療保険「メディケア」や「メディケイド」などを管轄する「メディケア・メディケイド・サービスセンター(CMS)」の所長に指名すると発表しました。
米NBC Newsによると、CMSは保健福祉省(HHS)傘下の機関で、1億6千万人以上の国民に公的医療保険を提供しています。上院に承認されれば、次期HHS長官に指名されたロバート・ケネディ・ジュニア氏と連携し、米国の公衆衛生分野を担うことになります。
オズ氏は心臓外科医でもありますが、ケネディ氏と同様に健康や科学に関する誤解を招く主張を展開し、批判を浴びてきた人物です。2020年には、新型コロナウイルス感染症の治療に抗マラリア薬のヒドロキシクロロキンを推奨して批判を浴びました。
トランプ氏はオズ氏について「国家予算の4分の1を費やすCMSの無駄や不正を減らすだろう」と述べ、疾病予防を推奨するリーダーになることに期待を寄せたといいます。

世界保健機関(WHO)と米疾病対策センター(CDC)は14日、2023年の麻疹(はしか)の症例数が世界で推定1030万件となり、22年から20%以上増加したと発表しました。はしかによって約10万7500人の命が失われ、そのほとんどが幼い子どもだったそうです。
こうした症例数の増加は、特に新型コロナウイルス感染症の流行以降、世界の麻疹ワクチンの接種率が低下していることが原因だといいます。麻疹は 2回のワクチン接種で予防することができ、1回目の接種で93%、2回目の接種で97%の効果があるといわれています。
麻疹は非常に感染力が強く、流行を防ぐには2回のワクチン接種を地域の95%以上の人が受ける必要があるとのことです。しかし昨年は、1 回目の麻疹ワクチン接種を受けた子どもが世界で約83%しかおらず、2回目の接種を受けたのはわずか74 %にとどまったそうです。
なお、米CNNによると、米国における麻疹ワクチンの接種率が下がっており、23年度の幼稚園児の接種率は92.7%だったそうです。

米国のトランプ次期大統領が厚生(保健福祉省:HHS)長官に指名したロバート・ケネディ・ジュニア氏はワクチン懐疑論者として知られています。米ABC Newsがケネディ氏の考え方やそれに対する専門家の反応について報じました。
ケネディ氏は自身のことを「反ワクチンだったことは一度もない」と述べているそうですが、「ワクチンに対するより詳しい調査が必要である」との主張を続けてきたことは周知の事実です。過去には、麻疹・おたふくかぜ・風疹(MMR)ワクチンが自閉症を引き起こす可能性があるとする根拠のない論文に基づく主張を展開。新型コロナウイルスワクチンについても「これまでに作られた中で最も致命的なワクチン」と発言したそうです。
さらに、国立アレルギー感染症研究所長を務めたアンソニー・ファウチ氏やビル&メリンダ・ゲイツ財団がワクチンで利益を得ようとしているなどの誤情報を拡散したこともあるといいます。
専門家は、ケネディ氏のこうした姿勢に子どもを持つ親が影響を受けて、ワクチン接種をためらう可能性を懸念しています。

ナッツには抗炎症作用と抗酸化作用のある栄養素が豊富に含まれ、脳の健康に良いといわれています。スペインの研究チームが、毎日ひとつかみのナッツを食べると認知症リスクを下げられる可能性があると、科学誌GeroScienceに論文を発表しました。
チームは認知症のない成人5万386人(平均年齢56.5歳)のデータを基に7.1年間の追跡調査を実施したそうです。このうち 422人(2.8%)が、後に何らかの原因で認知症を発症したといいます。調査の結果、毎日ナッツを食べる人は、ナッツを食べない人に比べて、全原因認知症(アルツハイマー病や血管性認知症、前頭側頭認知症など)の発症リスクが12%低いことが明らかになったそうです。
ナッツの摂取量は「1日ひとつかみ(30g)まで」で無塩のものが認知症予防に最も効果的である可能性が示されたといいます。なお、ナッツは皮なしでも問題なく、乾燥タイプでもローストタイプでも結果に影響はなかったとのことです。

犬と飼い主の間に作られる愛着には、心拍の間隔の変化である「心拍変動」の同調が関連している可能性があるそうです。フィンランドの研究チームが科学誌Scientific Reportsに論文を発表しました。
心拍変動は自律神経系の状態を反映しており、変動が高いとリラックスした状態、低いとストレスを受けているなどの緊張状態を示します。チームは、犬と飼い主のペア30組を対象に調査を実施。犬は牧羊犬や狩猟犬など人間と協力することができる種類だったといいます。調査の結果、自由な休憩時間を過ごしている間に、飼い主の心拍変動の高まりが犬の心拍変動の高まりにつながることが分かったそうです。
これは、飼い主がリラックスしている時に、犬もリラックスした状態になることを示しています。遊びなどのタスクを実行している時ではなく、休息時に心拍変動の同調が確認されたことで、精神的な状態の同調を反映している可能性が示されました。

腸内細菌叢(腸内フローラ)は、自己免疫疾患の一種である「関節リウマチ(RA)」の進行に影響を与えるそうです。英国の研究チームが、医学誌Annals of the Rheumatic Diseasesに論文を発表しました。
チームは、RAリスクに関連する抗体(抗CCP抗体)が陽性で、関節や骨やじん帯など(筋骨格系)に症状を訴えているけれども関節内の滑膜に炎症を伴わない患者124人の腸内細菌叢を分析したそうです。
その結果、RAに進行した参加者30人とRAに進行しなかった人の間で、プレボテラ属の細菌の豊富さに有意差が認められたそうです。個人が持つRAの危険因子やRAに進行するまでの時間に応じて、プレボテラ属の特定の菌が多くなったり、少なくなったりしたといいます。さらに、参加者19人を15カ月にわたり追跡したところ、RAに進行した5人は発症の約10カ月前から腸内細菌叢が不安定になることが明らかになりました。
チームは、腸内細菌叢の変動の理解がRAの発症予測や診断、治療につながるとしています。また、高リスクの人の腸内細菌叢をターゲットにした予防が可能になるかもしれないと主張しています。

トランプ次期米大統領は、反ワクチン活動などで知られるロバート・ケネディ・ジュニア氏を厚生(HHS:保健福祉省)長官に指名しました。AP通信がその影響について報じています。
HHSは食品医薬品局(FDA)や疾病対策センター(CDC)、国立衛生研究所(NIH)などを所管し、莫大な予算(1兆7千億ドル)を抱える世界最大の公衆衛生機関です。ケネディ氏が厚生長官に承認されれば、これらが彼の監督下に置かれることになります。
ケネディ氏はFDAの腐敗を指摘し、食品栄養などの部門全体を一掃する可能性を示唆。また長年にわたり、FDAのワクチンに関する取り組みについても非難しています。さらに、CDCが市民の虫歯予防のために推奨する水道水中のフッ化物濃度に関するガイドラインを、健康に害があるとして無効にする考えも明らかにしています。
NIHについても、職員600人を解雇する可能性に言及。金銭的な利益相反を持つ研究者に対する資金提供を阻止し、NIHの予算の半分を食事療法などの「健康に対する予防的かつ総合的なアプローチ」の研究に充てる考えを持っているそうです。
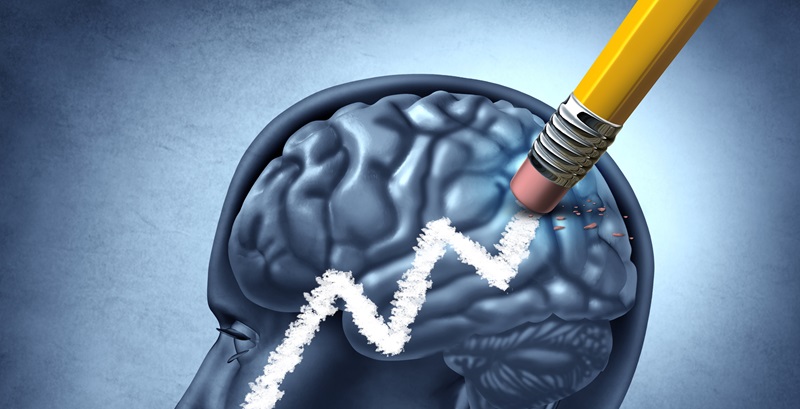
脳内に鉄が過剰に蓄積することが、アルツハイマー病(AD)の病態に深く関わっていると考えられています。オーストラリアなどの研究チームが、鉄を脳内から除去する鉄キレート剤「デフェリプロン」を使い、AD患者の神経変性を遅らせることができるかどうかを調査しました。
チームは、ADに関連するタンパク質・アミロイドβの蓄積がある軽度認知障害患者、または初期AD患者の計81人を対象に治験(第2相試験)を実施したそうです。その結果、1日2回デフェリプロン(15mg/kg)を12カ月服用した群は、プラセボ群に比べて認知機能の低下が進行することが分かったといいます。
MRI画像からはデフェリプロンが、記憶に関わる脳の領域「海馬」に蓄積した鉄の量を減らすことが示されたそうです。しかし予想に反して、鉄の減少によって海馬の萎縮が止まることはなく、代わりに前頭葉の萎縮が進んだといいます。さらに、デフェリプロン群は免疫細胞の好中球が以上に減ってしまう好中球減少症が起きる頻度が高く、安全性にも懸念が生じる結果になったとのことです。
チームは研究成果を医学誌JAMA Neurologyに発表しました。

大手ハンバーガーチェーンのマクドナルドが販売したハンバーガー「クォーターパウンダー」に関連する集団食中毒が発生した問題で、患者数が104人に増加したそうです。米食品医薬品局(FDA)が13日に発表しました。
患者は14州から報告されています。これまでに34人が入院し、コロラド州の高齢者1人が死亡、4人が重篤な腎障害を発症しました。クォーターパウンダーに使われていたスライスタマネギが食中毒の原因とみられています。このタマネギはカリフォルニア州の食品メーカーTaylor Farmsが供給したもので、同社は10月22日にタマネギの自主回収に踏み切りました。
これまでのところ、回収したタマネギのサンプルの一つから大腸菌の陽性反応は出たものの、今回の集団感染の原因となった菌株とは一致しなかったそうです。FDAなどが回収したタマネギの検査を引き続き進めているそうです。
米NBC Newsによると、保健当局は「食品安全上の懸念は払拭されたように思われる」としているといい、マクドナルドは別業者のタマネギを使ってクォーターパウンダーの販売を再開したとのことです。

角膜移植におけるドナー不足や拒絶反応などの問題を解消する新たな治療法が実現するかもしれません。大阪大学の研究チームが、ヒト人工多能性幹細胞(iPS細胞)由来の「角膜上皮細胞シート」を患者に移植する手術を世界で初めて実施し、医学誌Lancetに発表しました。この成果について科学誌Natureがニュースで取り上げています。
角膜は光を屈折させて集める重要な役割を持ちます。チームは、角膜上皮の幹細胞の消失によって角膜が結膜に覆われてしまう角膜上皮幹細胞疲弊症(LSCD)で、角膜混濁のために視力障害がある患者4人にこのシートを移植したといいます。
その結果、移植後すぐに全員の視力が回復し、3人はその状態が1年以上続いたそうです。2年間の経過観察期間で、腫瘍形成などの重篤な有害事象を経験した患者はいなかったとのこと。また、4人のうち2人は免疫抑制剤を使用しなかったにもかかわらず、免疫系による攻撃の兆候は見られなかったそうです。
チームは、3月にも治療法の有効性を評価する臨床試験を開始する予定とのことです。

英国で、イングランドとウェールズの終末期患者に対して「ほう助死(Assisted Dying)」(自殺ほう助)の権利を認める法案が提出されたそうです。英公共放送BBCによると、11月29日に国会議員による1回目の採決が行われる見通しとのことです。
一般的にほう助死とは、医師から処方された致死薬を終末期患者が自らに投与する行為を指します。ほう助死の対象となるのは、かかりつけ医(GP)に1年以上登録をしていて、イングランドかウェールズに住んでいる余命6カ月以内の18歳以上の成人です。
意思決定能力のある患者がほう助死を望む意思を明確に示す必要があり、証人の署名が付いた2通の宣言書の作成が求められます。そして、2人の医師からほう助死に適格であることを認めてもらわなければなりません。裁判官による医師への聴取が行われ、最終的な決定が下されるといいます。
誰かにほう助死を選ぶよう圧力をかけたり、強制したりした場合、懲役14年に処される可能性があるそうです。なお、スコットランドでも同様の法案が審議されているとのことです。

「記憶」は脳に特有の機能だと思っていませんか。米国の研究チームが、他の細胞も記憶機能を持つことを発見したと、科学誌Nature Communicationsに論文を発表しました。
脳細胞が新しい情報を学習する際、あるパターンの神経伝達物質を受け取るといいます。そして、記憶形成の際に活性化する遺伝子があるそうです。チームは神経組織と腎組織から採取した細胞(非脳細胞)に、そのパターンに似た化学信号を伝え、記憶形成の際に活性化する遺伝子の反応を観察したといいます。その結果、非脳細胞の記憶に関する遺伝子が、科学信号に反応して活性化することが分かったそうです。
なお、脳が情報を記憶するには、短時間で集中して学ぶ「集中学習」よりも間隔を空けて繰り返し学ぶ「分散学習」が効果的です。脳細胞以外の細胞も、間隔を空けて信号を伝達したほうが、記憶関連遺伝子が長時間にわたって強力に活性化することが明らかになったとのことです。
チームは、体の細胞は脳細胞と同じように扱うべきであり、病気の治療なども、「記憶がある」ことを前提として行う必要があることが示されたとしています。
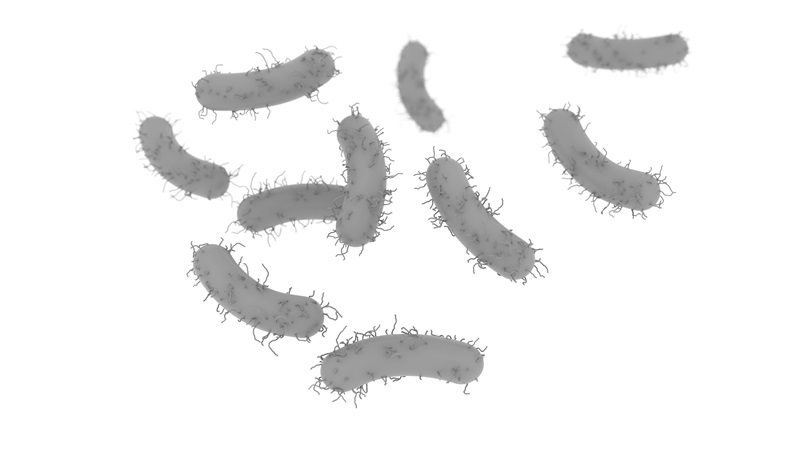
大腸がんのリスクを高める腸内細菌が存在するそうです。ベルギーの研究チームが、これまで謎に包まれていた、ある種の大腸菌ががんを進行させるメカニズムを明らかにしたと、科学誌Natureに論文を発表しました。
これまでの研究で、「pks陽性大腸菌」と呼ばれる腸内細菌が、DNAに結合して損傷を与えるコリバクチンという遺伝毒性物質を産生することでがんのリスクを高めることが分かっています。しかし、この大腸菌がどのようにして腸壁にくっつくのかは不明でした。
チームがマウスで調査を行い、pks陽性大腸菌がFimHやFmlHと呼ばれる分子を使って、腸壁の表面にある腸管上皮細胞に付着することを発見したそうです。この分子は、細菌表面の細長いタンパク質の繊維「線毛」の先端に存在するといいます。付着した大腸菌がコリバクチンを産生することで、DNAが損傷される可能性があるそうです。
なお、FimHの働きを阻害する薬を使ってpks陽性大腸菌が腸管上皮細胞へ付着するのを防いだところ、DNA損傷や腫瘍の成長が大幅に抑制されたといいます。チームは大腸がんの発生と進行を防ぐ有望な治療法の開発につながるとしています。

米国脳卒中協会(ASA)が、10年ぶりに脳卒中予防に関する新たなガイドラインを公表しました。新ガイドラインには、健康的な食生活を送ることで、高コレステロールや高血糖、肥満といった脳卒中のリスクを高める危険因子を抑制できることが明記されています。
具体的には、果物や野菜、全粒穀物、オリーブオイルなどを中心に取る地中海式食事法が有効だといいます。ハムやソーセージ、菓子パン、清涼飲料などの超加工食品や糖分の多い飲食物を控えることも重要だとしています。また、脳卒中の予防には定期的な運動も大切で、1日10分散歩をするだけでも脳卒中リスクが大幅に低下するそうです。
そして、肥満や糖尿病の人に対して、オゼンピックやウゴービなどといった薬の処方を検討することを医師に推奨しています。
なお、毎年50万人以上の米国人が脳卒中を発症するそうですが、このうち最大80%は予防できる可能性があるとのことです。

カナダ西部のブリティッシュコロンビア州で、10代の若者に鳥インフルエンザウイルスH5N1型が感染したことが分かったそうです。同州の保健当局が9日に発表しました。カナダ国内でH5N1型が感染したヒトが見つかるのは初めてとのことです。
この若者は野鳥か動物との接触によってH5N1が感染した可能性が高いとみられており、詳しい感染経路の特定が進められています。患者の症状は明らかにされていませんが、病院で治療を受けているそうです。
同州では、野鳥や家禽、スカンクやキツネなどの小型の野生動物からH5N1が検出されているといいます。今年10月初め以降、少なくとも22カ所の家禽飼育施設でH5N1の感染が確認されているとのことです。
米国では、H5N1型が感染した乳牛からヒトへの感染例が確認されています。ただ、カナダでは今のところ乳牛や牛乳のサンプルから鳥インフルが検出されたことはないそうです。

オーストラリアで百日ぜきの患者が急増しているそうです。オーストラリアの公共放送ABCによると、今年の百日せきの患者数は11月6日までに4万1013人に達し、30年以上前に統計が開始されて以来、初めて4万人を超えたといいます。
百日ぜきは5年ごとに患者が急増することで知られていますが、医師や感染症の専門家は今年の大流行は予想していなかったとのことです。専門家は百日ぜきワクチンの接種率低下に懸念を示しているそうです。特に、追加接種を受ける人の割合が驚くほど低く、2023年は13歳になる子どもの4人に1人が追加接種を受けていないといいます。
百日ぜきは、乳児にとっては致命的になり得る呼吸器感染症です。感染後1〜2週間は症状が現れないことが多いため、感染が広がりやすいそうです。百日咳ワクチンの効果は5年を過ぎると薄れるので、乳幼児期に接種後、学童期に追加接種を受けることが有効だといいます。
なお百日ぜきは米国でも流行が拡大しています。

米疾病対策センター(CDC)は8日付で、鳥インフルエンザウイルス(H5N1型)についての新たな指針を発表しました。感染動物に接触した農場労働者に対し、症状がなくても鳥インフル感染の検査や治療を受けることを推奨しています。
新たな指針は、ミシガン州とコロラド州の酪農従事者115人を対象に6~8月に行われた血液検査の結果に基づくものです。115人は感染が確認された乳牛に接触しており、このうち8人(7%)からH5N1の感染歴を示す抗体が検出されたそうです。
8人は全員、マスクなど呼吸器を保護する個人防護具(PPE)を着けずに酪農場の搾乳室で清掃作業を行っており、感染対策用の眼鏡をかけていたのも3人だけでした。また、4人が無症状だったことも分かっているそうです。
AP通信は今回の指針発表を受け、「動物や人間への感染が増えるごとにウイルスが危険な変異をするリスクが高まる。政府の対応は遅すぎる」というウイルスの専門家の意見を紹介しています。

健康な人の便から採取した腸内細菌叢(腸内フローラ)を患者に移植する「便移植」には、善玉菌のバランスを回復させるだけでなく、腸管壁の修復を促進する効果もあることが分かったそうです。
米食品医薬品局(FDA)は2022年、「再発性クロストリジオイデス・ディフィシル感染症(CDI)」の治療法として、「ふん便微生物叢移植(FMT)」を承認しています。
米国の研究チームが、健康なドナー30人とFMTを受けた患者22人から採取した便を分析。男性ドナーの便を移植された女性患者の33%で、移植から数カ月経過後も男性という性を決める「Y染色体」が大幅に増加していることが確認されました。
このY染色体は、ドナーの便に含まれていた「腸管上皮細胞」に由来すると考えられます。栄養や水分の吸収、異物の侵入を防ぐバリアなどさまざまな役割を担う腸管上皮細胞も、FMTによって患者の腸に根付く可能性が示されました。
チームは研究成果を医学誌Gastro Hep Advancesに発表しました。

オーストラリアのアンソニー・アルバニージー首相は、16歳未満の子どもによるソーシャルメディアの利用を禁じる法案を、今週中にも議会に提出する方針を示しているそうです。英BBCによると、ソーシャルメディアが子どもたちのメンタルヘルスに与える悪影響を軽減することが目的だといいます。
詳細についてはまだ議論されていませんが、すでにソーシャルメディアを利用している子どもも対象で、保護者の同意があっても年齢制限に例外は認めない方針とのことです。アルバニージー首相は、ソーシャルメディアのプラットフォーム側に子どもたちのアクセスを防ぐための合理的な措置を講じていることを示す責任があると述べ、利用者への罰則は設けないそうです。
多くの専門家が、ソーシャルメディアのメンタルヘルスへの悪影響については認めていますが、法律で利用を禁止することの有効性については意見が分かれているといいます。法案が成立した場合は1年後に施行される見込みとのことです。

睡眠不足は精神の健康に悪影響を与えることが知られています。では睡眠時間が増えると、精神面に良い影響が出るのでしょうか。米国の研究チームが、若年成人90人を対象に実施した調査の結果を学術誌Journal of Positive Psychologyに発表しました。
チームは参加者を「遅寝」「早寝」「通常」の三つのグループに分け、1週間にわたって調査を実施したといいます。その結果、いつもより一晩に46分多く寝た人は、困難に直面した時に回復する力、感謝の気持ち、持続的な幸福感が高まったそうです。一方で、睡眠時間が37分少なくなると、こうした精神的な幸福度が下がることが明らかになったといいます。
また、睡眠時間が増えると、個人的な幸福度が高まるだけでなく、社会に恩恵をもたらす行動が増えることも分かったそうです。平均年齢55歳の成人2837人を対象とした別の調査(医学誌Sleep Medicine掲載の論文)では、1日に7~9時間の良い睡眠を取っている人は、寄付に協力する可能性が7~45%高いことが示されたとのことです。

忙しくて時間がない人は、週末だけでも運動をすると脳の健康を維持できるそうです。コロンビアなどの研究チームが、メキシコの首都メキシコシティに住む平均年齢51歳の成人1万33人を16年にわたって追跡して研究し、その成果を医学誌British Journal of Sports Medicineに発表しました。
チームは参加者を、週1~2回(30分以上)運動する人の群▽週3回以上運動する人の群▽週1~2回運動する人と週3回以上運動する人を混ぜた群▽全く運動をしない人の群――の4群に分けて調査。その結果、週1~2回運動する群は全く運動しない群に比べて、軽度認知症を発症するリスクが13%低いことが分かったといいます。また、週3回以上運動をする人、週1~2回運動する人と週3回以上運動する人を混ぜた群は、全く運動をしない群と比べてリスクが12%低かったといいます。
このことから、軽度認知症の発症抑制には、週1~2回の運動で十分である可能性が示されました。なお、男女間で結果に違いは生じなかったとのことです。
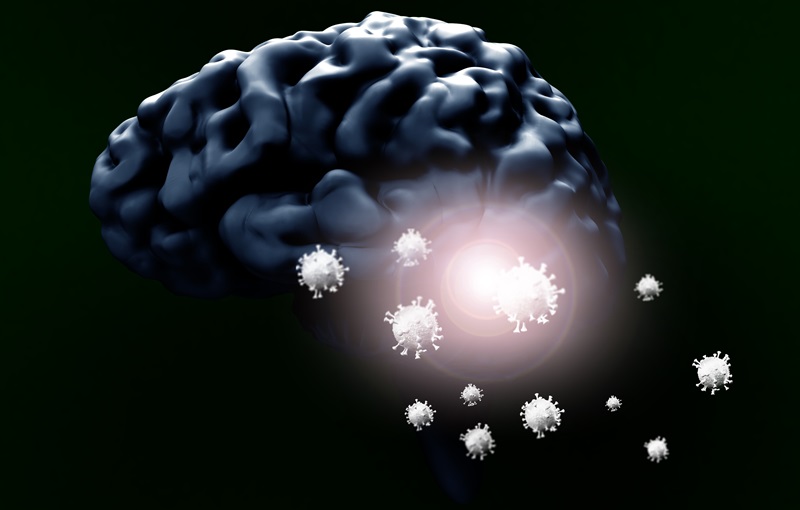
口唇ヘルペスを引き起こすことで知られる単純ヘルペスウイルス1型(HSV-1)は、脳と脊髄からなる中枢神経に侵入することが分かっています。米国とフランスの研究チームが、HSV-1の脳での広がり方を初めて明らかにしたと、科学誌Journal of Virologyに発表しました。
チームがマウスで調査したところ、HSV-1は三叉神経や嗅神経から中枢神経系に侵入した後、生命時に関わる脳幹、内分泌や自律機能をつかさどる視床下部といった重要な領域のいくつかに定着することを発見したそうです。一方で、記憶をつかさどる海馬、思考などの高度な認知機能をつかさどる大脳皮質などの領域はHSV-1の影響を受けなかったといいます。
チームは、HSV-1感染に応答して炎症を引き起こすミクログリア(中枢神経系の免疫細胞)の活動も調査。一部の領域では、ウイルスが消滅した後もミクログリアが活性化しており、炎症が継続していることが示されました。慢性的な炎症はアルツハイマー病やパーキンソン病などの神経変性疾患の引き金になる可能性があるとのことです。

5日投開票の米大統領選に勝利したドナルド・トランプ氏は、「(大統領に返り咲いたら)一部の(小児用)ワクチンを法的に禁止するかどうかを決断する」と明言しているそうです。これに対し多くの小児科医が、米国で何十年もの間発生していない感染症の致命的な大流行につながる恐れがあるとして懸念を示しているといいます。
米NBC Newsによると、トランプ氏の発言は、根拠のない反ワクチン論を唱えることで知られるロバート・ケネディ・ジュニア氏の助言に基づくものだそうです。ケネディ氏は今回の大統領選に無所属で出馬し、トランプ氏支持に転じて選挙活動を中止しました。トランプ氏は選挙前、自身が当選した場合はケネディ氏を「健康問題に取り組むために」公衆衛生分野の要職に起用する可能性を示唆していたといいます。
なお、大統領はワクチンを禁止する権限は持ちませんが、連邦機関の重要な役職の指名権を通じて影響力を行使することがでるとのことです。こうした動きによって、子どもにワクチンを接種させない親が増えることが懸念されています。

胎児期や乳幼児期に砂糖を制限すると、中年期の2型糖尿病や高血圧のリスクが低下する可能性があるそうです。米国などの研究チームが科学誌Scienceに研究成果を発表しました。極端な制限をしなくてもリスクは抑えられるようです。
チームは、第二次世界大戦中に英国の配給プログラムの一環で行われた「砂糖の制限」の影響を受けた子どもと受けなかった子どものデータを比較したそうです。英国では、1942年に砂糖の流通制限が始まり、配給制は53年9月まで続いたといいます。
受胎後1000日間にわたり砂糖の制限を受けた子どもは、約50年後に2型糖尿病を発症するリスクが35%、高血圧を発症するリスクが20%、それぞれ低くなることが明らかになったとのことです。こうしたリスクの抑制には、胎児期に母親が砂糖を制限するだけでも十分だったそうです。
なお、1日の平均砂糖摂取量は配給制下で40g、配給制廃止後で80gでした。WHO(世界保健機関)などがガイドラインで定める成人の添加糖類推奨量は1日50gまでです。

30分間の有酸素運動をたった1回行うだけで、2型糖尿病の予防に重要な糖代謝とインスリン感受性が改善するそうです。イタリアの研究チームが医学誌Journal of Endocrinological Investigationに研究成果を発表しました。
チームは、競技スポーツの経験がなく糖尿病ではない20~35歳の健康な32人を対象に調査を実施。参加者に30分間の軽いジョギングをしてもらい、その「1週間前」と「24時間後」にブドウ糖を含んだ液体を飲んで血糖値の変動を見る「経口ブドウ糖負荷試験」を実施したそうです。
その結果、運動後は、空腹時の血糖値の平均が82.8mg/dLから78.5mg/dLに、ブドウ糖を取った1時間後の血糖値の平均は122.8mg/dLから111.8mg/dLにそれぞれ低下したといいます。
ブドウ糖を取った1時間後のインスリン値の平均についても、57.4µUI/mlから43.5µUI/mlに下がったとのことです。さらに、インスリン感受性の指標(Matsuda indexとQUICKI index)やインスリン抵抗性の指標(HOMA-IR index)も改善したそうです。

座りっぱなしによる健康リスクを軽減できるとして近年人気が高まっている「スタンディングデスク」は、本当に体に良いのでしょうか。オーストラリアの研究チームが、長時間立ちっぱなしでいることは心臓病や脳卒中のリスク減少につながらないことを確認したと、医学誌International Journal of Epidemiologyに発表しました。
チームは平均61歳の成人8万3千人以上を対象に調査を実施しました。参加者は数年にわたり、立ったり座ったりといった身体活動を記録する装置をつけて生活したそうです。こうして得られたデータを分析したところ、1日10時間以上座っていることが心臓病や脳卒中のリスク上昇に関連することが分かったといいます。
一方で、立っている時間を増やすだけでは、それらのリスクは低下しないことも分かりました。実際、立っている時間が長いと脚に血が溜まり、静脈瘤などの循環器系疾患のリスクが高まるそうです。健康のためには、短いウォーキングやストレッチなどの軽い運動を取り入れることが有効だといいます。
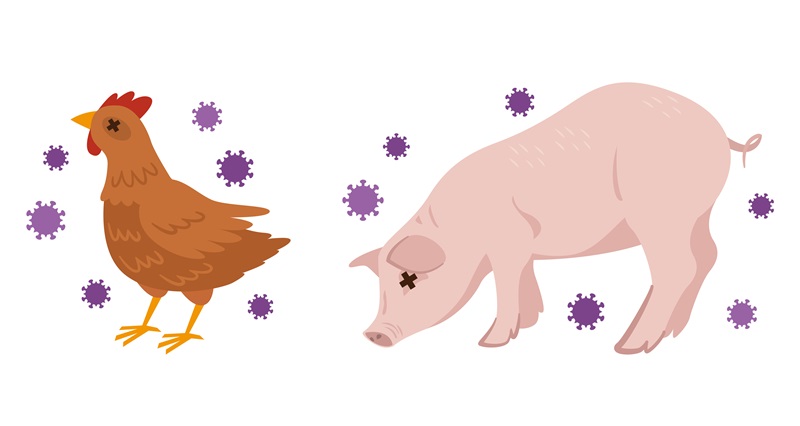
米農務省は10月30日、オレゴン州の家庭農場で飼われていたブタ1匹が、鳥インフルエンザ(H5N1型)の検査で陽性だったと発表しました。米国内でブタへのH5N1型の感染が確認されたのは初めてです。
この農場では家禽や数種類の家畜が飼育されていました。家禽の鳥インフル感染が確認されたことから、水場などの設備を共有していたブタ5匹を安楽死させ検査を行ったところ、1匹の陽性と2匹の陰性が確認されました。残り2匹の結果はまだ出ていないそうです。
米CNNによると、2009年に大流行したH1N1型はブタの中で変異が起き、それがヒトに感染したことが引き金になったと考えられています。そのため、H5N1型がブタに広がることには警戒感が高まっていました。
ただし、ブタはH5N1型感染に対して高い耐性を持つとの研究結果も報告されています。今回のブタについても鼻腔ぬぐい液でウイルスが検出されただけの場合、いわゆる「感染」ではなく単なる鼻腔内のウイルス汚染にとどまる可能性も指摘されています。

猫と暮らすことは、人間の健康にどのような影響を及ぼすのでしょうか。The Conversationにオーストラリアの動物福祉・行動・倫理学の専門家の記事が掲載されています。
猫を飼っている人は、脳卒中や心臓病などといった心血管疾患で死亡するリスクが低いことが複数の研究で示されているといいます。また、社会的孤立が抑制され、精神的な幸福度が高まるとのことです。うつ病患者が飼い猫と触れ合うと、症状が軽減するとの調査結果もあるそうです。
一方、健康上のリスクも存在します。猫はトキソプラズマ原虫の終宿主(成体が寄生する最後の宿主)として知られており、ふんを介してヒトに感染することがあります。妊婦が感染すると流産や死産につながったり、生まれた子どもに失明や脳障害が生じたりする可能性があるそうです。
また、猫アレルギーを持つ人は5人に1人ほどの割合でいるといわれており、その数は増加傾向にあるとのことです。ただし、アレルギーが重度でない限り、衛生面に配慮すれば猫と暮らすことは可能だそうです。

中国の研究チームが、心停止後の虚血による脳損傷の回復に、肝臓の機能が重要な役割を果たすことを突き止めたと、医学誌EMBO Molecular Medicineに発表しました。
チームは、ミニブタ17匹を「脳を30分間虚血(血流を低下)させる群」「脳と肝臓を30分間虚血させる群」「虚血なしの対照群」の三つに分けて調査したそうです。ブタを安楽死させて脳を調べたところ、対象群の次に脳損傷が少なかったのは「脳のみ虚血」の群で、脳と肝臓を虚血させたブタは損傷が多いことが分かったといいます。
次にチームは、取り出した脳を、酵素や栄養分を循環させて臓器を保護する装置(NMP)につなぎ、虚血後の脳活動の回復について観察したそうです。
その結果、NMPだけにつないだ脳は脳の電気活動が現れるものの、時間の経過とともに低下したそうです。しかし、NMP回路に正常に機能している肝臓を組み込むと、虚血から50分後に脳の電気活動が回復し、その状態が6時間継続したといいます。チームは、心停止後の生存率や転帰を改善するヒントがあるとしています。

米国では今年3月以降、鳥インフルエンザウイルスH5N1型の感染が乳牛の間で流行し、乳牛からヒトに感染する症例も相次いで確認されています。米国の研究チームが、乳牛からヒトに感染した株について動物実験を行い、その結果を科学誌Natureに発表しました。
チームが調査に使った株は、今年の春に結膜炎を発症したテキサス州の酪農従事者の目から分離したものです。この株が感染したフェレットを、感染していない6匹のフェレットの近くで飼育したところ、2匹のフェレットへの感染が確認されたといいます。効率的ではないものの、この株が飛沫感染によって広がる可能性が示されました。
また、この株に感染したフェレットの致死率は100%だったそうです。ヒトでは軽症なのに、フェレットで病原性が非常に高くなる理由は不明とのこと。なお、現在乳牛の間で広まっているウイルスは、実験に使った株とは別の変異を持つものに移り変わっているそうです。

米ケンタッキー州で2021年、脳死と判定された男性が、臓器摘出手術のために手術室に向かう途中で目を覚ますという出来事があったそうです。今年9月に開かれた議会公聴会で初めて明らかになったといいます。これを受け、米国で臓器提供のドナー登録を取り消す人が増えているそうです。AP通信が報じています。
21年の出来事の詳細は分かっていませんが、摘出手術は回避され、男性は今も生きているそうです。この件が報道された翌週には、前年同時期の10倍以上に当たる1日平均170人が、国のドナー登録リストから自身の情報を削除したといいます。さらに海を越えたフランスでも、このニュースが報道されて以降、臓器提供拒否の意思を登録する人が1日当たり100人から1000人に急増したそうです。
なお、米国や日本と違い、フランスでは本人が生前に拒否する意思を示しておかない限り、臓器提供するものとみなされるシステムだといいます。

米国などの研究チームが、投薬ミスを未然に防ぐための、小型のアクションカメラを開発したと、医学誌npj Digital Medicineに発表しました。人工知能(AI)を搭載した、頭に装着できるカメラで、手術室や集中治療室などといった慌ただしい医療現場での活用が期待できます。
このカメラは薬瓶や注射器の中身をリアルタイムで解析し、患者に投与する前にミスの可能性を警告することができるといいます。AIの訓練は数カ月かけて実施。13人の麻酔科医が、セットアップや照明の異なる手術室で薬剤を準備する場面を撮影した418個の動画などを使ったそうです。
AIは薬瓶や注射器に表示されている文字を読み取るのではなく、大きさや形状、色などを基に情報を解析します。ミスがあった場合は、薬剤を扱うときにかける眼鏡に映し出すか音で警告するといいます。薬瓶の取り違えや注射器のラベルミスを感度99.6%、特異度98.8%で検出できるとのことです。
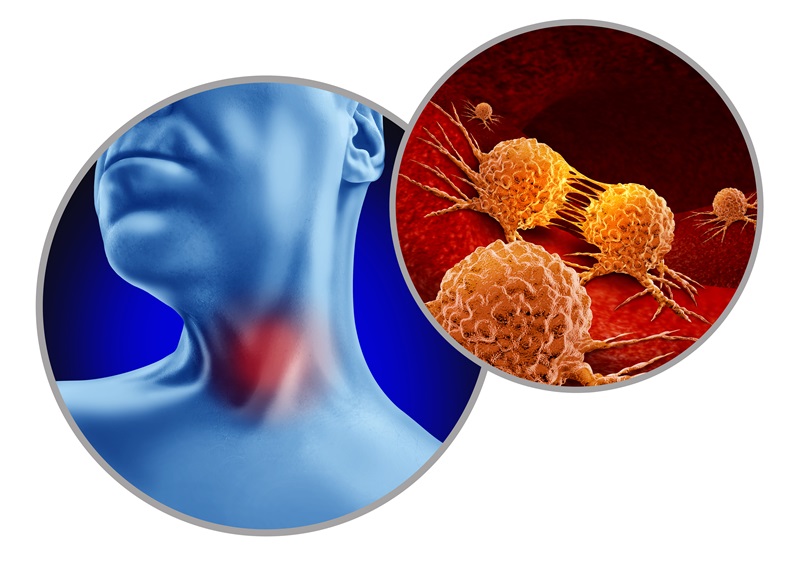
ヒトパピローマウイルス(HPV)は口腔咽頭がんの原因にもなります。米国の研究チームが男性における経口感染について、発生頻度やリスク上昇の要因などに関する新たな調査結果を科学誌Nature Microbiologyに発表しました。
チームは米国、メキシコ、ブラジルの男性計3137人を57カ月(中央値)にわたり追跡調査。発がんリスクのあるHPV経口感染は、1000人月あたり2.4件発生したそうです。リスク上昇の要因は、高学歴の人やアルコール摂取量が多い人、多数の女性パートナーがいる人、頻繁にオーラルセックスをする人、男性パートナーがいる人――であることが明らかになったといいます。また、年齢による感染リスクに違いはなく、生涯にわたりHPVに感染する可能性があるとのことです。
チームは、性別不問のHPVワクチン接種プログラムや中年男性を対象としたキャッチアップ接種の必要性を指摘しています。

歌や演奏で調子が外れ(音程がずれ)ていることを人がどうやって認識するのか、そのメカニズムは分かっていないそうです。米国の研究チームが、二つの要素が手がかりになっていることを明らかにしたと、学術誌Communications Psychologyに発表しました。
チームは、楽器がきちんとチューニングされた曲とされていない曲を参加者に聞かせ、調子が外れていると思うかを尋ねる調査を実施しました。この時、不協和音の認知に影響を与える主な要素として考えられる「ビート(拍)」と「インハーモニシティー(不調和度)」を操作したそうです。インハーモニシティーは音の成分の周波数がわずかに高くなる現象で弦楽器特有のものです。
調査の結果、調子が外れていることを検出する能力に、ビートとインハーモニシティーの両方が重要な役割を果たすことが明らかになったといいます。いずれかの手がかりをなくすと、調子はずれの検出が著しく悪化したとのことです。

米疾病対策センター(CDC)は25日、米ファストフード大手マクドナルドが販売したハンバーガー「クォーターパウンダー」に関係する集団食中毒について、最新の情報を発表しました。感染者は13州で75人が確認されており、22日の公表(10州で49人)から増加しました。
CDCと米食品医薬品局(FDA)は、クォーターパウンダーに使われていた「スライスタマネギ」が原因で腸管出血性大腸菌O157による食中毒が起きたとみているようです。マクドナルドによると、大腸菌に汚染されていたとみられる商品のタマネギはカリフォルニア州の食品メーカーから供給されたものだといいます。食品メーカーは23日、大腸菌汚染の可能性があるとして4種類の生タマネギ商品の回収に踏み切ったとのことです。
感染者のうち22人が入院し、10代の子ども1人と成人1人が溶血性尿毒症症候群(HUS)と呼ばれる重篤な腎障害に陥っており、死者が1人出ています。

高校時代のIQ(知能指数)が高い人ほど成人後に日常的にお酒を飲むようになるそうです。米国の研究チームが、米国人の男女6300人(大部分が白人)のデータを分析した結果を学術誌Alcohol and Alcoholismに発表しました。
チームは1957年に高校を卒業した参加者に対し、2004年に過去1カ月間の飲酒量について聞き取り調査を実施したそうです。男性で月に1~59杯、女性で月に1~29杯の飲酒を「適量」、それを超える飲酒を「多量」と定義したといいます。
その結果、高校時代のIQのスコアが1ポイント上がるごとに、飲酒量が適量または多量に該当する可能性が1.6%上昇することが明らかになりました。一方でIQが高い人は、一度に5杯以上飲む「深酒」はあまりしないことも分かったそうです。
ノルウェーの研究チームが2020年に発表した論文でも、知能テストの点数の高い男性は飲酒頻度が高いとの結果が得られているそうです。

英国の研究チームが、子宮頸がんの標準治療に、婦人科のがん治療で行われる化学療法を加えると生存率が大幅に向上することを確認したそうです。医学誌The Lancetに論文が掲載されました。
チームは、他臓器への転移がない局所進行性子宮頸がん患者500人を2群に分けて調査したそうです。一方の群に、放射線と抗がん剤シスプラチンを併用する標準的な化学放射線療法を実施。もう一方の群には、標準治療の前に6週間、「TC療法」と呼ばれる2種類の抗がん剤(カルボプラチンとパクリタキセル)を組み合わせた化学療法を行ったといいます。
その結果、標準治療群は5年生存率が72%、再発や転移がなかったのは64%だったのに対し、事前にTC療法を行った群は5年生存率が80%に上り、72%ががんの再発や転移を免れたそうです。ただし、重篤または命の危険のある副作用は標準治療群が48%、事前にTC療法を行った群が59%だったとのことです。

他人のそしゃく音など特定の音を聞くと強い不快感や嫌悪感を覚える「ミソフォニア(音嫌悪症)」の人は、うつ病や不安症などの精神疾患に関連する遺伝子を持っていることが明らかになったそうです。オランダの研究チームが科学誌Frontiers in Neuroscienceに論文を発表しました。
遺伝子データの解析により、ミソフォニアを自認する人は、耳鳴り、大うつ病性障害、心的外傷後ストレス障害(PTSD)、全般性不安障害に関連する遺伝子を持つ可能性が高いことが分かったそうです。
また、ミソフォニアは「神経症的傾向/罪悪感」「怒りっぽさ/敏感さ」とも遺伝的な関連が見られたそうです。一方、聴覚に過敏な自閉スペクトラム症(ASD)とは負の相関関係が見られ、ASDの人はミソフォニアではない可能性が高いといいます。
なお、今回の研究に使われたデータはほとんどが欧州人のもので、ミソフォニアに関しては医学的な診断ではなく自己申告に基づくものとのことです。

米疾病対策センター(CDC)は22日、米ファストフード大手マクドナルドが販売したハンバーガー「クォーターパウンダー」に関係する腸管出血性大腸菌O157で集団食中毒が発生したと発表しました。
西部コロラド州や中西部ネブラスカ州など10州で少なくとも49人が症状を訴え、子ども1人を含む10人が入院したといいます。コロラド州では高齢者1人が死亡しました。
CDCの聞き取り調査では、これまでのところ12人が発症前にクォーターパウンダーを食べたと答えているそうです。マクドナルドは、この商品に使われていた「スライスタマネギ」が原因で食中毒が起きた可能性があるとして、一部の州で関連商品の販売を見合わせています。
O157に感染すると、3~4日で高熱、胃けいれん、下痢、嘔吐などの症状が現れます。ほとんどの人は5~7日で回復しますが、中には溶血性尿毒症症候群(HUS)と呼ばれる重篤な腎障害に陥る患者もいるとのことです。

人間の嗅覚はこれまで考えられていた以上に優れているのかもしれません。中国と米国の研究チームが、科学誌Nature Human Behaviourに論文を発表しました。
チームは0.018秒で人間の鼻に匂いを届けることができる装置を開発。この装置を被験者229人に装着し、2種類の匂い物質AとBを立て続けに出し、一嗅ぎで嗅いでもらう実験を行ったそうです。その結果、AとBの間に0.06秒の間隔があれば、「Aの後にBを嗅いだ場合」と「Bの後にAを嗅いだ場合」を識別できることが明らかになったといいます。なお、1回のまばたきにかかる時間は0.18秒ほどです。
チームの研究で、人間の鼻が匂いに対して非常に素早く反応できる可能性が示唆されました。今回の調査で使われた匂い物質は、りんご、甘い花、レモン、玉ねぎの4種類のみだったため、チームはより多くの種類の匂いを試す必要性があるとしています。

米ワシントン州の養鶏場で働く労働者4人に、鳥インフルエンザウイルスが感染したことが確認されたそうです。米NBC Newsによると、4人は鳥インフルに感染した家禽の殺処分を行っていたといいます。
米国では今年、ワシントン州以外に五つの州でヒトへの鳥インフル感染が確認されており、感染者は今回の4人を含めると計31人になります。このうち1人を除く全員が、感染した家禽や乳牛への接触歴がありました。今回感染が疑われている4人は軽度の呼吸器症状と結膜炎があり、抗ウイルス薬が処方されたといいます。
カリフォルニア州とワシントン州は、鳥インフルと季節性インフルの両方が感染するリスクを減らすため、農場労働者への季節性インフルワクチンの接種を検討しているそうです。両方のウイルスが同時に感染するとウイルスに変異が起き、ヒトの間で感染が広がりやすくなるリスクが高まるといいます。

尿酸の結晶が関節にたまることで激しい炎症が起こる「痛風」は、食生活の乱れが大きく関わっているといわれています。しかし、ニュージーランドの研究チームが、これを否定する研究結果を科学誌Nature Geneticsに発表しました。
チームが260万人の遺伝情報を解析した結果、痛風発作を防ぐための標的になり得る多数の免疫関連遺伝子が特定されたそうです。痛風の根本的な原因は「尿酸値の高さ」「尿酸結晶の関節への蓄積」「関節における炎症発作」で、これら全てのプロセスに遺伝子が重要な役割を果たしていたといいます。
特定された遺伝子の一つは、免疫細胞などが産生するタンパク質インターロイキン6(IL-6)に関連するもので、関節リウマチなどの治療に使うIL-6阻害薬「トシリズマブ」が痛風にも有効な可能性があるそうです。
チームは、赤身肉など特定の食事が痛風発作の引き金になる可能性はあるものの、主な原因は遺伝的要因だとしています。

20世紀は、衛生状態の改善や医学の進歩によって高所得国の平均寿命が約30年も延びたといいます。こうした傾向は今世紀も続くのでしょうか。
米国の研究チームが、1990~2019年のオーストラリア、フランス、香港、イタリア、日本、韓国、スペイン、スウェーデン、スイス、米国の人口統計データを分析し、科学誌Nature Agingに論文を発表しました。
その結果、1990年以降、平均寿命の延びが鈍化していることが明らかになったそうです。2019年に生まれた赤ちゃんのうち100歳まで生きるのは、女児で5.1%、男児で1.8%と推定されるとのことです。
論文の著者が米CNNの取材に応じ、生物学的老化のプロセスを著しく遅らせることができない限り、人間の寿命が120歳や150歳まで延びることは現実的ではないと述べています。そして、今後は単なる寿命ではなく「健康寿命」を延ばすことに意識を向ける必要があると指摘しています。

大型ハリケーン「へリーン」と「ミルトン」に相次いで襲われた米フロリダ州で、「人食いバクテリア」と呼ばれる細菌の一つ「ビブリオ・バルニフィカス」の感染者が増加しているそうです。
ビブリオ・バルニフィカスは、沿岸の暖かい海水に生息し、汚染された水や魚介類を摂取したり、傷口が汚染水に触れたりすることでヒトに感染します。また、肝疾患や免疫不全の人が感染しやすいそうです。
米CNNによると、9月26日にヘリーンが上陸するまではフロリダ州の9月の感染者は6人でしたが、月末には24人に増加しました。さらに、二つのハリケーンが直撃して以降これまでに計38人の感染者が確認されており、今年の感染者は76人になったといいます。
米国疾病対策センター(CDC)に報告される感染者は年間150〜200人で、このうち約5人に1人が死亡するそうです。フロリダ州保健局は、ハリケーンによる洪水の水はこの菌が急速に増殖する可能性があるため、触れないよう注意を呼びかけていたといいます。

米国で「百日咳」の流行が拡大しているそうです。米疾病対策センター(CDC)は17日、今年の百日咳(ぜき)の患者が10月12日時点で1万8506件確認されたと発表しました。昨年同時期の報告数は3382件で、その約5倍に上ります。
百日咳は百日咳菌に感染することで起こる気道感染症です。鼻水、微熱、咳などの症状から始まり、1~2週間後には嘔吐や肋骨(ろっこつ)の骨折を伴うことがあるほど咳が悪化し、息を吸う時には「ヒュー」という音がします。
発症の初期には抗菌薬が有効ですが、咳が激しくなる頃に使用してもあまり効き目はなく、その場合は水分補給を十分に行いながら安静にするしかないといいます。1歳未満の乳児の感染は特にリスクが高く、咳が出ずに呼吸困難に陥ることもあるそうです。
予防にはワクチンが有効で、米国では三種混合(ジフテリア、破傷風、百日咳のワクチン)ワクチンの接種が推奨されており、日本ではこれにポリオを加えた四種混合ワクチンが定期接種の対象になっています。

中国の研究チームが、早く寝る子どもの腸は健康であることを明らかにしたと、科学誌Scientific Reportsに発表しました。
チームは、2~14歳の健康な子ども88人を、午後9時半より前に寝る子どもとそれより後に寝る子どもの2グループに分け、その便の分析結果を比較しました。すると、早く寝る子どもは腸内細菌叢(腸内フローラ)の多様性が高く、有益な細菌が多く存在することが分かったといいます。具体的には、腸の健康維持や正常な認知機能に関連する善玉菌「アッカーマンシア・ムシニフィラ」などが豊富だったとのことです。
また、代謝物質の分析では、早く寝る子どもの間でアミノ酸代謝や神経伝達物質調節の活性が高まっていることも明らかになったといいます。これらは脳の機能と発達に重要な役割を果たすそうです。
チームの研究により、睡眠パターンが腸内細菌叢に大きな影響を与えることが分かりました。なお、これまでの研究で、十分な睡眠が成長や学業成績を改善し、BMIを正常に保つことが明らかになっているといいます。

新たな血液検査がアルツハイマー病(AD)の早期発見に有効であることを実証したと、米国の研究チームが科学誌Molecular Neurodegenerationに発表しました。一度の血液検査で、さまざまな側面からADリスクを予測できるそうです。
チームが調査したのは、神経変性疾患に関連する約120種類のタンパク質の変化を解析できるAlamar Biosciences社の「NULISAseq CNS Disease 120 Panel」という血液検査です。
チームは、認知機能が正常な高齢者113人を対象に2年間の追跡調査を実施。まず、参加者の血液検体をNULISAseqで解析しました。それをADの標準的なバイオマーカーであるタンパク質タウやアミロイドβなどの測定結果、脳画像によるADの評価と比較したといいます。
すると、NULISAseqがADに関連する複数のバイオマーカーを検出できることが分かったそうです。これらのバイオマーカーの多くが、脳脊髄液を使わないと測定できない神経細胞の一部や脳血管に関連するタンパク質だったとのことです。
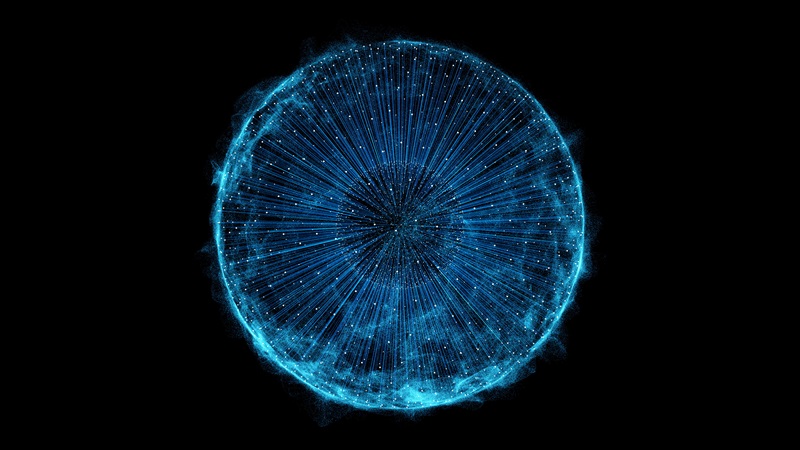
クマやワラビーなど130種類以上の哺乳類が、母体や周囲の環境が子どもにとって適切な状態になるまで胚の成長を一時停止させる「胚休眠」と呼ばれる生殖戦略を持っています。ドイツの研究チームが、ヒトも同じようなメカニズムを持っている可能性があることを突き止めたと、科学誌Cellに発表しました。
チームは、マウスの胚の休眠状態を引き起こすことが分かっているmTORというタンパク質に着目しました。ヒト多能性幹細胞(hPSC)由来の受精から5~7日目の胚(胚盤胞)モデルを、mTORの働きを阻害する薬に暴露させたところ、胚が最長8日間にわたって休眠に似た状態に入ることが明らかになったそうです。mTOR阻害薬への暴露をやめると、胚は再び正常な成長プロセスに戻ったといいます。
チームは、こうしたメカニズムの理解は体外受精(IVF)技術の進歩につながるとしています。
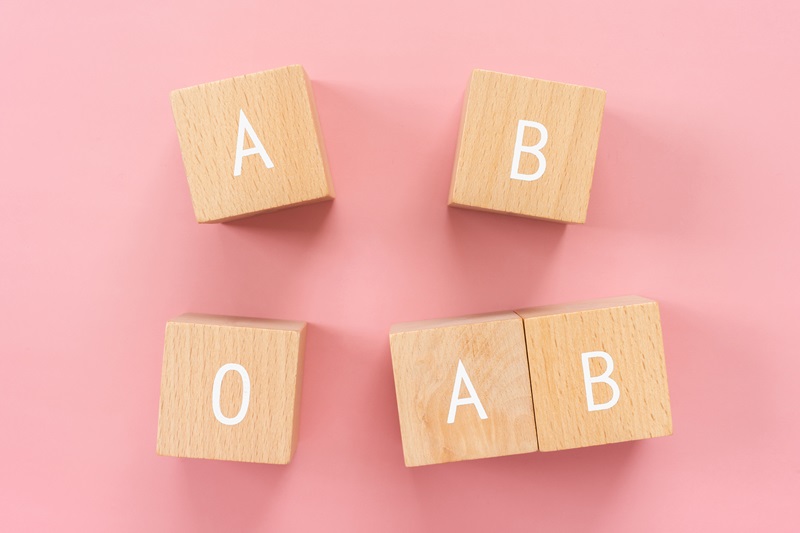
血液型がA、B、AB型の人は、新型コロナウイルス感染後の心血管系の病気(心血管イベント)のリスク上昇に特に注意が必要なようです。米国の研究チームが医学誌Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biologyに論文を発表しました。
チームは、2020年2~12月に新型コロナを発症した人1万5人と感染者ではない21万7730人のデータを分析。コロナ感染歴がある人は、感染から3年以内に心臓発作や脳卒中などの心血管イベントを発症するリスクやそれによって死亡するリスクが倍増することが明らかになったそうです。
特に、新型コロナで入院した患者はこうしたリスクが高かったといいます。さらに詳しい遺伝子解析を行ったところ、血液型がA、B、AB型の人はO型の人に比べてコロナ感染後に有害な心血管イベントを経験する可能性が2倍高くなることも示されたとのことです。

消化器感染症「クロストリジオイデス・ディフィシル(C. ディフィシル)感染症」に対するmRNA技術を使ったワクチンが実現するかもしれません。米国の研究チームが科学誌Scienceに発表しました。
C. ディフィシルはヒトの腸管などに少数生息する細菌です。多くの場合、抗菌薬の使用などによって腸内細菌叢(腸内フローラ)のバランスが乱れることで感染症を発症します。症状はさまざまで、軽度の下痢から、大腸が膨張する中毒性巨大結腸症や腸閉塞を起こして死に至ることもあります。
チームはmRNA技術を用いて、C. ディフィシルが病気を引き起こす際に必要な数種類のタンパク質を標的にするワクチンを開発したそうです。他のmRNAワクチンと同様、このワクチンも感染自体を防ぐのではなく、病原菌と効果的に戦えるよう免疫系を訓練する仕組みだといいます。
マウスを致死量のC. ディフィシル菌に感染させた実験では、このワクチンを投与したマウスが全て回復したのに対し、ワクチンを投与しなかったマウスは全て死んだそうです。

たばこ製品を生涯にわたり購入することができない「たばこフリー世代」を実際に作ることができれば、肺がんによる死亡を大幅に減らせるようです。スペインの研究チームが、世界保健機関(WHO)やその付属機関である国際がん研究機関(IARC)が公表した82カ国のデータを基に、将来の肺がんによる死亡率を予測し、医学誌The Lancet Public Healthに発表しました。
世界では毎年180万人が肺がんで死亡し、その3分の2以上がたばこが原因と推定されているといいます。チームによると、2006~10年生まれの人にたばこの販売を禁止した場合、95年までに185カ国で120万人の肺がんによる死亡を防ぐことができるそうです。現状では肺がんで290万人が死亡すると予想されており、それを40.2%減らせることになります。
また、こうした措置によって恩恵を受ける割合は男性の方が高く、死亡者は女性が30.9%減と推計されるのに対し、男性は推計45.8%減になるといいます。
なお、今回の研究は、電子たばこの使用については考慮されていないとのこと。

新型コロナウイルス感染症後の長引く「後遺症」は、生命維持に関わる「脳幹」の炎症が影響している可能性があるそうです。英国の研究チームが科学誌Brainに論文を発表しました。
新型コロナで死亡した人の脳幹は、感染による免疫応答によって炎症などの変化が生じていることが確認されています。そこでチームは、脳幹のダメージが「コロナ後遺症」の一因であるとの仮説を立て、生きている患者の脳についても観察することにしたそうです。
脳の様子を詳細に画像化することができる超高磁場の「7テスラMRI」を使い、ワクチンが開発される前のパンデミック初期に、重度の新型コロナで入院した患者30人の脳を解析。これらの患者の多くが疲労感や息切れ、胸痛といった症状が長引いていたとのことです。
調査の結果、脳幹の一部(延髄、橋、中脳)に炎症反応と思われる異常が認められたそうです。また、脳幹の変化は精神の健康とも密接な関係があり、うつ症状や不安を生じさせていると考えられるとのことです。

評価や判断を加えずに、今この瞬間に意識を向ける状態を作る「マインドフルネス瞑想(めいそう)」は、プラセボ効果ではなく、本当に痛みを軽減する効果があるそうです。米国の研究チームが科学誌Biological Psychiatryに論文を発表しました。
チームは、健康な115人を▽事前にマインドフルネス瞑想の仕方を学んだ群▽偽の瞑想を学んだ群▽偽の痛み軽減クリームを与えられた群▽瞑想指導の代わりにオーディオブックを聞かされた群――に分けて実験を行いました。
熱刺激による痛みを与え、MRIで脳の反応を分析したところ、事前にマインドフルネス瞑想の仕方を学んだ群は、その他の群に比べて、痛みの強度に関連する神経信号や、痛みに対する否定的な感情に関連する神経信号が大幅に減少することが明らかになったそうです。マインドフルネス瞑想群は、自己申告による痛みの評価スコアも低かったといいます。
なお、プラセボ効果によって痛みの神経信号が減少したのは、偽クリーム群だけだったそうです。

歯磨きで口の中を清潔に保つことで、歯周病だけでなく「頭頸(けい)部扁平上皮がん(HNSCC)」の発症リスクも抑制できる可能性があるそうです。米国の研究チームが、医学誌JAMA Oncologyに研究成果を発表しました。
チームは、健康な男女15万9840人を10~15年にわたり追跡調査しました。このうち、HNSCCを発症した236人と、対照群として無作為に選んだHNSCCではない485人の唾液のサンプルを比較しました。その結果、数百種類ある一般的な口腔内細菌のうち13種類がHNSCC発症リスクの上昇や低下に関連することが明らかになったそうです。
総合すると、こうした細菌はHNSCC発症リスクを30%高める可能性があるといいます。さらに、これらの細菌に9種類の歯周病菌を加えて、合計22種類の細菌に着目したところ、HNSCCリスクを50%上昇させることが明らかになったそうです。
また、チームは口腔内の真菌についても調査を行っています。真菌とHNSCCリスクとの関連性は認められないことが分かったとのことです。

人は不十分な情報しか得ていなくても、自分は正しいと信じ込む傾向にあるようです。米国の研究チームが、平均年齢40歳の1300人を対象に行った研究結果を科学誌Plos Oneに発表しました。
チームは「地域の地下水が枯渇したため学校の水が不足する」という架空の記事を使って実験を行いました。500人には「別の学校と統合する」ことの利点三つと中立的な意見一つが書かれたもの、別の500人には「現状のまま雨が降るのを待つ」ことの利点三つと中立的な意見一つが書かれたもの、残りの300人にはこれら七つの意見が全て書かれたものを与えたといいます。
記事を読んだ後、学校が取るべき対応策について意見を聞いたところ、大部分の人が、自分が読んだ記事に書かれていた意見に賛成し、意見を決めるために十分な情報を得ていると自信を持っていたそうです。
一方で、その自信がもろいことも明らかになりました。参加者に反対側の意見が書かれた記事を読ませて意見を聞くと、多くの人が意見を変えたがり、当初の意見に自信が持てなくなったとのことです。

抗菌薬の使用で乳児期に腸内細菌叢(腸内フローラ)のバランスが乱れることが、将来の攻撃的な行動につながる可能性があるようです。イスラエルの研究チームが科学誌Brain, Behavior, and Immunityに発表しました。
チームは、生まれてから48時間以内に抗菌薬を投与され、腸内細菌叢の多様性が低くなった生後1カ月のヒトの乳児から採取した便を、生後5週間のマウスに移植して調べたそうです。すると、このマウスは抗菌薬を使わなかったヒト乳児の便を移植されたマウスに比べて、移植から4週間後の攻撃性が高くなることが分かったそうです。
また、抗菌薬を使用した乳児の便を移植されたマウスは、脳の五つの領域において攻撃性に関連する遺伝子発現に変化が見られ、同じく攻撃性に関係があるとされる神経伝達物質「セロトニン」の減少やセロトニンの生合成に必要なアミノ酸「トリプトファン」の増加も確認されたといいます。
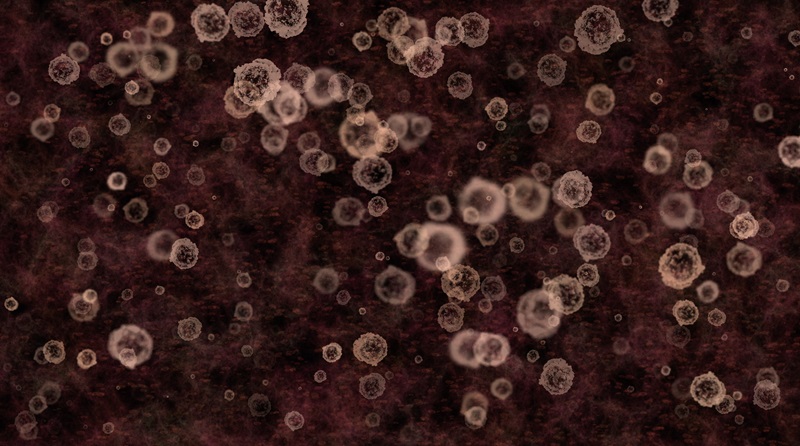
新型コロナウイルス感染後の長引く後遺症は、ウイルスが体内から完全には除去されず感染状態が続く「持続感染」が原因の一つかもしれません。米国の研究チームが、医学誌Clinical Microbiology and Infectionに発表しました。
チームは、スパイクタンパク質をはじめとする新型コロナウイルスの構成成分を高感度で検出できる抗原検査を開発したそうです。そして、この検査を使って新型コロナ感染歴のある706人から採取した1569の血液検体を分析しました。
その結果、新型コロナ感染から1~14カ月後に心肺、脳、筋骨格に関連する後遺症がある人の43%からウイルスのタンパク質が検出されたそうです。一方、後遺症の症状がない人のうち、こうしたタンパク質が検出されたのはわずか21%だったといいます。
ウイルスが体内に残り続けることでコロナ後遺症が起こる場合は、抗ウイルス薬で症状を緩和できる可能性があるとのことです。

生活習慣の乱れによる概日リズム(体内時計)のズレは、大腸がんの進行に影響を及ぼすそうです。米国の研究チームがこのメカニズムを明らかにしたと、科学誌Science Advancesに発表しました。
チームは大腸がんマウスを使って調査を実施。その結果、概日リズムが乱れると、腸内細菌叢(腸内フローラ)の多様性や豊富さが変化することが分かったといいます。さらに、腸内細菌における核酸、アミノ酸、炭水化物(糖)の代謝経路も変化してしまい、そのことが関連して、有害な細菌などから腸を保護する粘液の量が減少することも明らかになったそうです。こうしたことから、概日リズムが腸のバリアの完全性を維持するために不可欠であることが示されました。
腸は本来、必要な物質だけを体内に取り込みますが、バリア機能が崩れると毒素や細菌が血液に流れ込みやすくなり、がんの進行が加速するようです。近年、50歳未満の大腸がん発症が増加しているといい、チームは概日リズムの乱れが影響している可能性があると指摘しています。

米イリノイ州のシカゴ公衆衛生局(CDPH)は、9月12日に行われた野外コンサートの観客が、狂犬病ウイルスを保有するコウモリに接触した可能性があるとして注意を呼びかけました。シカゴ周辺のコウモリの一部が狂犬病にかかっていることが分かっているそうです。
CDPHは、ライブ会場「Salt Shed」で午後5~10時の間にバンドグループ「Goose」に参加した人の中で、コウモリにかまれたり、引っかかれたり、直接接触したりした人がいれば、直ちに医療機関で狂犬病の「暴露後予防(PEP)」について相談するよう求めました。ただし、コウモリのかみ傷は小さいため見つけるのが難しく、かまれたことに気づかない場合もあるといいます。
狂犬病はヒトや哺乳類の神経系に深刻な影響を与える感染症で、狂犬病ウイルスに感染した動物を介してヒトに感染します。潜伏期間は通常1~3カ月ですが、1週間~1年以上と大きな幅があります。感染動物と接触した後、迅速かつ適切にPEPが投与されなければ、ほぼ100%死に至ります。

スウェーデンのカロリンスカ研究所は7日、2024年のノーベル生理学・医学賞を遺伝子の働きを調節する「マイクロRNA」を発見した米マサチューセッツ大学のビクター・アンブロス教授とハーバード大学のゲイリー・ラブカン教授に授与すると発表しました。
アンブロス教授らは長年、体内の全ての細胞は同じ遺伝情報を持つにもかかわらず、それぞれが筋肉や神経など全く異なる種類の細胞に発達する理由を調査してきました。そして線虫を使った実験で、マイクロRNAという分子が遺伝子の働きを制御(タンパク質の合成量を調整)していることを突き止めました。
その後、線虫から見つかったマイクロRNAが、ヒトなどさまざまな生物に存在することが判明。さらに、マイクロRNAによる遺伝子調節がうまくいかなくなると、がんなどの疾患につながる可能性も明らかになりました。
近年は、マイクロRNAを病気の診断や治療に活用する研究も進められています。

ベトナムで9月、トラなどの大型肉食獣が数十頭、鳥インフルエンザウイルス(H5N1型)の感染によって死んだそうです。
AP通信によると、ベトナム南部ドンナイ省ビエンホア市の動物園で、トラ20頭とヒョウ1頭が死にました。トラから採取された検体は、鳥インフルエンザウイルス(H5N1型)に陽性反応を示したといいます。死んだトラやヒョウは、近くの養鶏場から購入した生の鶏肉を餌として与えられていたそうです。
動物園の関係者は「トラは弱り、餌を食べなくなり、病気になって2日後に死んだ」と話しているとのことです。トラの飼育を担当していた職員30人は全員検査で陰性が確認されており、体調の変化もないそうです。
また、近隣のロンアン省の動物園でも、同時期にトラ27頭とライオン3頭が鳥インフルで死んだといいます。鳥インフルH5N1型は近年、犬や猫からアシカやホッキョクグマに至るまで多くの哺乳動物で感染が確認されています。
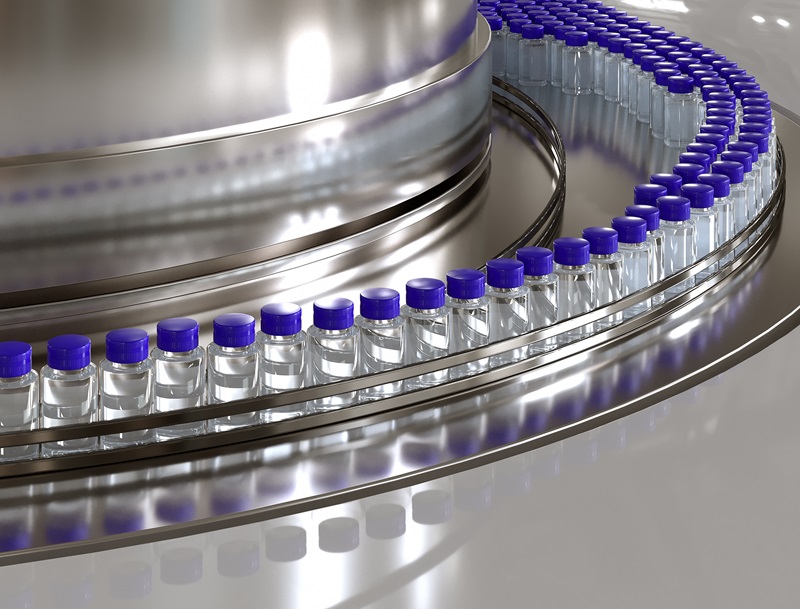
致死率の高い出血熱「マールブルグ病」の流行が発生しているアフリカ中部ルワンダの保健当局は6日、マールブルグ病に対するワクチンの臨床試験を開始すると発表しました。
AP通信によると、米国の非営利組織(NPO)セービンワクチン研究所によって、研究段階のマールブルグ病ワクチン700回分が提供され、感染者に接触した人や医療従事者などに投与されます。現時点ではマールブルグ病に対する承認済みのワクチンはありません。
ルワンダは、9月27日にマールブルグ病の流行を宣言しています。感染拡大を防ぐために通院や通学の制限など厳しい対策が講じられているといいます。これまでに感染者46人、死者12人が確認されているそうです。
マールブルグ病は、マールブルグウイルスが原因の出血熱で、致死率は最大88%と報告されています。患者の血液や体液、排泄物や汚染された寝具などを介してヒトからヒトに感染します。

米疾病対策センター(CDC)は3日、カリフォルニア州で鳥インフルエンザウイルス(H5型)が感染した2人の酪農従事者が確認されたと発表しました。
2人は同州セントラル・バレーの別々の農場で働いており、どちらの農場にも鳥インフルエンザウイルス(H5N1型)が感染した乳牛がいたそうです。2人とも軽症で、主な症状は結膜炎だといいます。
今年3月以降、米国では鳥インフルがヒトに感染する症例が報告されており、今回の2人を含めて計16件になります。そのほとんどが感染した家禽や乳牛に関連したものですが、ミズーリ州では動物への接触歴がない感染者が1人確認されています。
その他、これまでに感染者が確認されたのはテキサス州1人、コロラド州10人、ミシガン州2人です。
CDCは、感染動物に接触した人が鳥インフル陽性になるのは想定内であり、一般市民へのリスクは低いままだとしています。

英国などの研究チームが、アンドラッカブル(創薬不可能)と考えられてきた、がん細胞の標的を「分解」する新薬の開発に成功したと、科学誌Scienceに発表しました。難治がん治療の道が開かれる可能性があるといいます。
チームは、発がんに関与する「KRAS遺伝子変異」のタンパク質を分解へと誘導することができる低分子「タンパク質分解誘導キメラ分子(PROTAC)」をベースに、新薬(ACBI3)を開発したそうです。
KRAS遺伝子には多くの変異サブタイプがあり、現在はこのうちの一つ「G12C」を標的に、その活性を阻害する薬(阻害剤)のみが承認されています。一方、今回新たに開発されたACBI3は一般的なKRAS遺伝子変異17種類のうち13種類を選択的かつ強力に分解できることが分かったそうです。
マウスの実験では、ACBI3による分解がKRAS遺伝子の阻害よりも有効であり、効果的な腫瘍退縮を誘発することが示されたとのことです。

2型糖尿病の治療に使われる「SGLT2阻害薬」が、アルツハイマー病(AD)やパーキンソン病(PD)の発症リスクを抑制する可能性があるそうです。韓国の研究チームが医学誌Neurologyに発表しました。
SGLT2は、腎臓の糸球体で尿から血液中に糖を再吸収する際に働くタンパク質です。SGLT2阻害薬は、この働きを阻害することで、糖を尿として排出して血糖値を下げます。
韓国の研究チームが、2型糖尿病の投薬治療を受ける患者35万8862人(平均年齢58歳)を対象に調査を実施。SGLT2阻害薬を服用していた人は平均2年、それ以外の2型糖尿病治療薬を服用していた人は平均4年、それぞれ追跡調査を行ったそうです。
その結果、SGLT2阻害薬を使用した人は、AD発症リスクとPD発症リスクが共に20%、脳血管障害(脳卒中)によって起こる血管性認知症発症リスクは30%、それぞれ低くなることが分かったといいます。

多発性骨髄腫の治療に使われる「ポマリドミド」が、「遺伝性出血性毛細血管拡張症(HHT、 オスラー病)」に有効な可能性があると、米国の研究チームが医学誌New England Journal of Medicineに発表しました。
オスラー病は全身の血管に異常が生じ、鼻血などの出血症状が起こる遺伝性疾患です。肺や脳、肝臓、消化管などにも動静脈奇形を生じることがあります。
チームは、中等~重度の鼻出血がある成人のオスラー病患者144人を対象に臨床試験を実施。ポマリドミドを投与された人は、鼻出血の重症度が著しく低下し、輸血や鉄補充の量が減ったといいます。中間分析の時点で安全性と有効性が確認されたため、臨床試験は早期に終了しました。
試験終了後、参加者の追跡調査は行われませんでしたが、投薬を中止しても、参加者の一部は最長で6カ月にわたり鼻出血が再発しなかったことが確認されているといいます。ポマリドミドによって異常な血管の成長が阻害される可能性があるようです。

韓国政府が医師不足を解消するために医学部の定員増計画を打ち出し、これに反発した研修医らが今年2月に始めたストライキは、7カ月が経過した今も続いているそうです。
米公共ラジオNPRによると、長引くストに国民の不安は高まっており、世論調査では80%近くの人が「病気になったときに医療を受けられなくなるのではないかと恐れている」と回答したといいます。
政府と医師らの対立が続く中、韓国の医療制度が崩壊する兆しも見えています。今年、韓国内の主要な病院でのがん手術は16%減少しており、救急搬送の拒否や救急診療の業務制限も問題になっているそうです。
一方、政府は「医療システムは円滑に運営されている」と事態の深刻さを否定しており、医師らは政府が定員増計画を完全に中止するまでストを続ける構えだといいます。
どちらも相手側が譲歩しない限り対話さえするつもりはないそうで、患者や国民の医療に対する信頼が損なわれかねない状況だとのことです。

食事中に適切な量のエネルギーを摂取するために、脳ではどのようなことが起きているのでしょうか。
ドイツの研究チームが、マウスの視床下部においてニューロンが電気信号を発するタイミングを詳しく分析。その結果、食事中に順番に活性化するニューロン(神経細胞)の四つの「チーム」を特定したそうです。
これらのチームは、食事中にリレーのようにそれぞれが異なるフェーズで活性化し、適度な量が摂取されるまでグループ間でバトンが引き継がれていくといいます。また、食事に関与するニューロンの全チームが同じようなリズムで振動しているため、チーム間で情報伝達がしやすくなる仕組みになっているのだそうです。
チームは、こうしたニューロンの振動リズムに着目し、例えば外部から電磁波で振動リズムに影響を与えることなどによって、摂食障害の治療につながる可能性があるとしています。
研究チームは論文を科学誌Journal of Neuroscienceに発表しました。
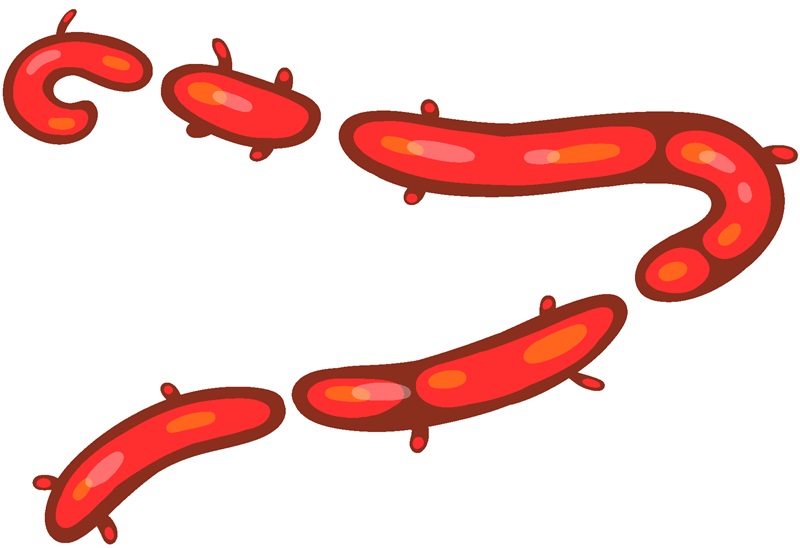
AP通信によると、アフリカ中部ルワンダでエボラ出血熱に似た症状が出るマールブルグ病の流行が発生し、8人が死亡しました。ルワンダの保健当局が9月29日に発表したそうです。
マールブルグ病は、オオコウモリが自然宿主と考えられているマールブルグウイルスが原因の出血熱で、致死率は最大88%と報告されています。患者の血液や体液、排泄物や汚染された寝具などを介してヒトからヒトに感染します。
潜伏期間は3日~3週間と幅があります。症状は発熱、頭痛、筋肉痛、下痢、嘔吐(おうと)などで、激しい出血で死に至ることもあるといいます。ワクチンや治療薬はありません。
ルワンダは9月27日に流行を宣言。これまでに確認された感染者は26人で、感染者に接触したと特定されている人は約300人いるそうです。
世界保健機関(WHO)のテドロス事務局長は28日、「ルワンダ当局と協力して感染拡大を食い止める」とX(旧ツイッター)に投稿したとのことです。

「水をたくさん飲むと二日酔いを防げる」という説は本当なのでしょうか。オランダなどの研究チームが、飲酒や二日酔いに関する13の研究結果から、アルコールの利尿作用によって引き起こされる脱水と二日酔いが関連しているかどうかを分析した結果を科学誌Alcoholに発表しました。
チームの分析の結果、脱水と二日酔いが同時に起こる可能性は否定されませんでしたが、この二つが直接関連しているという証拠は見つからなかったそうです。学生826人を対象とした研究では、水を飲んで二日酔いを和らげようとしても、その効果はほんのわずかだったといいます。
また、18~30歳の参加者29人を対象とした別の研究では、脱水の感覚は、頭痛など他の二日酔いの症状ほど長く続かないことが明らかになったそうです。
チームは、飲酒中や飲酒後に水を飲んでも、翌日の二日酔いを防ぐ効果はほとんど期待できないと結論付けました。さらに、二日酔い中に飲む水の量で、二日酔いの重症度が変わることもなかったといいます。

「Kombucha(コンブチャ)」を飲むと、断食と同じような効果を得られるかもしれません。コンブチャは、紅茶や緑茶に砂糖を加えたものに酢酸菌と酵母菌からなるゲル状の菌株「スコビー」を入れて発酵させたドリンク。日本では「紅茶キノコ」とも呼ばれており、昆布茶とは別物です。
米国の研究チームが、線虫の一種であるC.エレガンスを使ってコンブチャが腸の遺伝子発現に及ぼす影響を調査。コンブチャの微生物が腸に定着すると、脂肪の分解に必要なタンパク質が増加し、トリグリセライド(中性脂肪)の合成に必要なタンパク質が減少することが分かりました。
コンブチャに含まれる微生物からなるエサを与えられたC.エレガンスは、脂肪蓄積や中性脂肪が減少し、脂肪滴(細胞の脂質を貯蔵する細胞小器官)が小さくなったといいます。代謝の変化によって脂肪が減少し、食事制限をせずに断食に似た効果がもたらされる可能性が示されました。チームは人間でも同様の効果が得られると考えているようです。
今年3月に科学誌PLOS Geneticsに掲載された論文です。

さまざまな呼吸器感染症を予防する点鼻スプレーを開発したと、米国の研究チームが科学誌Advanced Materialsに発表しました。チームは、米食品医薬品局(FDA)がすでに承認している点鼻スプレーの成分やFDAの安全基準を満たしている成分を使って、点鼻スプレー「Pathogen Capture and Neutralizing Spray(PCANS)」を開発したそうです。
このスプレーには薬剤は一切含まれていませんが、鼻の内側にジェルが形成され、それがウイルスや細菌を捕らえて無力化する仕組みです。マウスの実験では、スプレーを使ったマウスは、致死量の25倍のインフルエンザウイルス(H1N1型)を投与しても、100%が生き残ったそうです。
さらに、スプレーを使わなかったマウスに比べて、肺のウイルスレベルが99.99%以上少なくなることも分かったといいます。感染防止の効果は少なくとも4時間持続。新型コロナやRSウイルスなど、試験した病原体のほぼ100%をブロックし、無力化したそうです。

米疾病対策センター(CDC)は27日、中西部のミズーリ州で動物との接触歴がない成人1人に鳥インフルエンザウイルス(H5N1型)が感染したことに関連して、この感染者に接触した医療従事者4人が呼吸器症状を呈したことが新たに分かったと発表しました。
このうち1人については、病院がマスク着用などの感染予防対策を講じるよう指示を出す前に感染者に対応した「高リスク接触」に該当したそうです。CDCはこの前週までに、今回とは別の医療従事者2人に呼吸器症状が出たと報告しており、感染者に接触して症状を呈した医療従事者は合計6人になりました。6人とも重篤な症状はなく、すでに回復しているといいます。
最初に症状を報告した医療従事者はインフルエンザ検査で陰性でしたが、残りの5人は検査を受けておらず、これから鳥インフルの抗体の有無を調べる血液検査が行われる予定とのことです。CDCは、一般市民への差し迫ったリスクは低いままだとしています。

血管収縮作用や抗炎症作用によって片頭痛の痛みを和らげる「トリプタン系薬」は、最新の高価な片頭痛治療薬(ラスミジタンやリメゲパント、ユブロゲパント)より効果が高い可能性があるそうです。英国などの研究チームが医学誌BMJに発表しました。
研究チームは、17種類の片頭痛向け経口薬やプラセボの効果を比較した137の臨床試験から、平均年齢40歳の成人8万9445人分(86%が女性)のデータを分析したそうです。その結果、服用から2時間の時点で、痛みの緩和に最も効果があるのはトリプタン系の「エレトリプタン」で、続いて同じくトリプタン系のリザトリプタン、スマトリプタン、ゾルミトリプタンが有効なことが分かったといいます。
また、痛みを24時間にわたって和らげるのに最も有効なのは、エレトリプタンと非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)のイブプロフェンだったとのことです。
チームは、この研究結果から、トリプタン系薬の使用を世界的に促進し、国際的なガイドラインを見直す必要があると指摘しています。
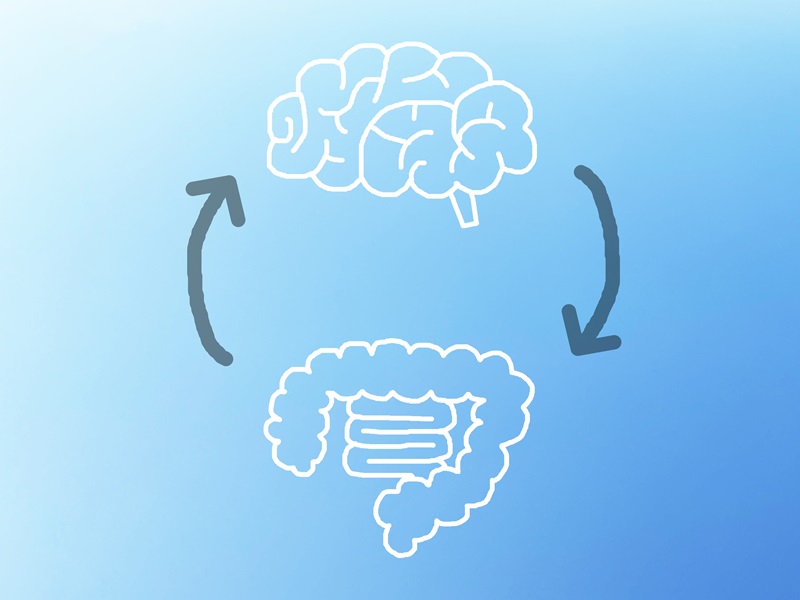
アルツハイマー病(AD)患者は大腸がんを発症する人が少なく、反対に大腸がん患者はADを発症する人が少ないといわれているそうです。中国の研究チームが、マウスの実験で大腸がんとADに逆相関の関係が生じることを明らかにしたとして、米国科学アカデミー紀要(PNAS)に発表しました。
チームはまず、大腸がんを誘発する薬剤をマウスに投与して調査。元々ADの症状があったマウスは、そうでないマウスに比べてがんを発生する可能性が低いことが分かったそうです。次に、ADマウスに健康なマウスの便を移植したうえで大腸がんを誘発したところ、がんが発生する可能性が健康なマウスと同程度になったといいます。
マウスの腸内細菌叢を調べたところ、ADマウスには「プレボテラ属細菌」が多いことが判明。同じことが軽度認知障害と診断された患者でも確認されたといいます。
プレボテラ属細菌の細胞壁の成分であるリポ多糖を健康なマウスに投与したところ、認知機能が低下する一方、大腸がんを発生する可能性は低かったとのことです。

慢性的なストレスは記憶力や社会性を損なう原因になるといいます。モロッコの研究チームが、モロッコ原産の植物「ユーフォルビア・レシニフェラ(白角キリン)」の樹脂から作られた「プロポリス」でそれを改善できる可能性があると、科学誌Neuroscience and Behavioral Physiologyに発表しました。
プロポリスはミツバチが樹脂と唾液を混ぜて作る粘り気のある物質で、ミツバチの巣の材料として使われます。
チームは、雄の成体ラット18匹を3群に分け、このうち二つの群のラットに対し1日2回、6週間にわたって軽度のストレスを与えたといいます。次に、この2群のうち片方の群のラット対し、ユーフォルビア・レシニフェラから抽出したプロポリスを毎日2週間経口投与したそうです。
その結果、マウスの海馬が保護され、記憶力が改善することが明らかになったといいます。さらに、この群のラットは、ストレスを受けた後にプロポリスを投与されなかったラットに比べて、面識のないラットと交流する傾向が強くなったとのことです。

近視の子どもが世界中で増加しているそうです。中国の研究チームが、世界50カ国の子ども540万人以上のデータを分析した結果を医学誌British Journal of Ophthalmologyに発表しました。
チームの調査で、1990年に24.32%だった世界の子どもの近視有病率は、2023年には35.81%に上昇したことが明らかになったといいます。特に、新型コロナウイルス感染症のパンデミック中に子どもたちが長期間外に出られなかったことが関連している可能性があり、50年までに世界の子どもの近視有病率は39.8%に達すると予測されています。
子どもの近視の割合が最も高いのはアジアで、なかでも日本の85.95%は世界1位だといいます。一方、南米のパラグアイや東アフリカのウガンダでは約1%と最も低いとのことです。英国や米国では約15%でした。
英国の専門家によると、近視リスクを抑制するには、7~9歳の間は毎日少なくとも2時間外で過ごすべきだといいます。また、近視は遺伝する可能性が高く、親が近視の場合、子どもの近視リスクは3倍になるとのことです。

肝臓や腎臓は他の臓器に比べて急速に老化するそうです。スイスの研究チームがその理由を解明したと、科学誌Cellに論文を発表しました。
外部との接触が多い皮膚や腸は1週間に1~2回、DNAの複製によって細胞が入れ替わるそうですが、肝臓や腎臓は1年間に数回とその頻度が非常に低いといいます。チームは、若いマウスと高齢マウスの肝臓の3分の2を切除して幹細胞を調査。切除による損傷から回復するためのDNA複製が「非コード領域(ゲノムの中でタンパク質を生成する情報を持たない領域)」で開始することが分かったそうです。
「コード領域」では、遺伝子が活性化している時にDNAの損傷を検出して修復します。一方で、「非コード領域」ではDNAを複製する時にだけそれが行われます。そのため、DNA複製頻度が低い肝細胞では、時間の経過とともにさまざまなDNA損傷が蓄積してしまうそうです。DNA損傷が蓄積すると「警報システム」が作動して、DNAの複製自体が妨げられます。細胞は増殖できなくなり、細胞機能の低下や組織の老化につながるといいます。

抗菌薬は2種類のメカニズムを介して腸管粘膜のバリア機能にダメージを与える可能性があるようです。スウェーデンなどの研究チームが科学誌Science Advancesに論文を発表しました。
チームは6カ月以上前に抗菌薬治療を少なくとも5クール受けたことがある人と10年以上抗菌薬を使用していない人の便のサンプルを比較しました。その結果、度重なる抗菌薬の使用により腸内細菌叢(腸内フローラ)の組成が変化し、さらにその変化が最後の治療から少なくとも6カ月にわたって持続することが明らかになりました。そして、過去に抗菌薬を繰り返し使った人の腸内細菌叢をマウスに移植すると、腸粘液層の機能が損なわれ、細菌の侵入が容易になることも示されたといいます。
一方、無菌マウスに抗菌薬「バンコマイシン」を投与した別の研究では、抗菌薬が腸内細菌叢とは無関係に、粘液層に直接作用することも分かったそうです。抗菌薬の投与からわずか数分以内に腸管を保護する粘液の分泌が阻害されることが確認されたとのことです。

米疾病対策センター(CDC)は20日、中西部のミズーリ州で動物との接触歴がない成人1人に鳥インフルエンザウイルス(H5N1型)が感染したことに関連して、この感染者に接触した医療従事者の1人が呼吸器症状を呈したことが新たに分かったと発表しました。
CDCはこの前週、感染者の同居家族1人にインフルエンザに関連する可能性のある胃腸症状が出て、今回とは別の医療従事者1人に呼吸器症状が出たと報告していました。家族は検査を受けることなく回復し、1人目の医療従事者はインフルエンザの検査で陰性だったといいます。
今回新たに判明した2人目の医療従事者も詳しい調査が始まる前に回復したため、検査は受けておらず、これから鳥インフルの抗体の有無を調べる血液検査が行われる予定とのことです。
CDCによると、発端となった感染者の感染経路についてはまだ明らかになっていないそうです。

新型コロナウイルス感染症の起源を知るための重要な手がかりが見つかったようです。米国などの研究チームが、科学誌Cellに研究成果を発表しました。
チームは、中国武漢市の海鮮市場で採取した遺伝物質を解析しました。武漢市は新型コロナの集団感染が最初に確認された都市です。その結果、この市場で売られていたタヌキ、ジャコウネコ、タケネズミがパンデミックの引き金になった可能性が高いことが判明したそうです。
チームは、新型コロナに感染した動物が2019年11月下旬に初めて市場に持ち込まれ、そこからヒトへの感染拡大につながったと考えているといいます。また、市場にいたタヌキは、中国南部に多く生息する種類であることも分かったといいます。
こうした発見は、新型コロナの自然宿主がどの地域に存在するのかを特定するのに役立つとのことです。

がん細胞が持つ「体内時計(概日リズム)」に合わせて化学療法を行うと、治療効果が大幅に向上する可能性があるそうです。
ドイツとルクセンブルクの研究チームが、細胞の概日リズムや薬剤への反応をモデル化して観察する新たなスクリーニング法を開発。増殖や広がりが早く、治療が難しいとされるトリプルネガティブ乳がん(TNBC)細胞の解析をしたところ、一日の中でいつ化学療法薬を投与するかによって治療の効果が最大30%異なることが明らかになりました。
ある特定の細胞株(HCC1937)については、約24時間の概日リズムの中で「10~12時間」または「18~20時間」の時点で治療をすると、全体的な恩恵が最も高まることが分かったといいます。化学療法薬「フルオロウラシル(5-FU)」は、「8~10時間」の時点での投与が有効であることが、明確に示されたとのことです。
チームは研究成果を科学誌Nature Communicationsに発表しました。

「顔面移植」の結果は長期的に良好であることが明らかになったそうです。フィンランドの研究チームが、世界でこれまでに実施された全ての顔面移植に関するデータを分析し、医学誌JAMA Surgeryに発表しました。
顔面移植は2005年に初めて実施され、それ以降、世界11カ国(北米、欧州、中国、ロシア)で患者48人対して計50件が行われました。このうち52%が顔全体の移植で、48%は部分的な移植だったといいます。
顔面移植を受けた患者の5年生存率は85%、10年生存率は74%だそうです。移植そのものに関連する死亡に限ると、5年生存率は96%、10年生存率は83%に上がるといいます。
肝臓移植の10年生存率が61%、心臓移植の10年生存率が65%であるといい、チームは顔面移植の生存率の高さが浮き彫りになったとしています。失敗したとみられる顔面移植6件のうち4件は、拒絶反応が原因だったとのことです。

遺伝子の異常によって視力低下や視野欠損が起こる「レーベル先天黒内障(GUCY2D遺伝子の変異に起因するレーベル先天黒内障:LCA1)」に対する遺伝子治療が行われ、初期の治験で有望な結果を示したそうです。米国の研究チームが英医学誌The Lancetに論文を発表しました。
チームは、深刻な視力障害があるLCA1患者15人(3人が小児)の網膜下に、遺伝子治療薬「ATSN-101」を三つの異なる用量で投与することで、安全性と有効性を確認する治験を実施しました。その結果、高用量のATSN-101を投与された患者9人の光に対する感度が、平均で100倍向上することが明らかになったそうです。さらにこのうち2人については、光感度が1万倍になったといいます。
こうした効果は、ほとんどの患者で薬の投与から1カ月以内に現れ、少なくとも12カ月は継続しているそうです。なお、重篤な副作用は認められなかったとのことです。

数杯のコーヒーを毎日飲むことで、2型糖尿病、冠状動脈性心疾患、脳卒中のうち二つ以上を持つ「心代謝性疾患の多疾患併存(CM)」のリスクを抑えることができるそうです。中国とスウェーデンの研究チームが、医学誌Journal of Clinical Endocrinology & Metabolismに研究成果を発表しました。
チームは、英国バイオバンクから抽出したCMではない37~73歳の成人36万人のデータを分析しました。12年間追跡したデータを調べたところ、カフェインを1日200~300mg取る人は、カフェイン摂取量が100mg未満の人に比べてCM発症のリスクが低くなることが分かったといいます。
特に、カフェインを1日3杯のコーヒーから取る人はCMリスクが最も低く、CM発症リスクが約50%抑制されたそうです。また、200~300mgのカフェインを紅茶や緑茶から取る人や、コーヒーと紅茶や緑茶の両方から取る人は、リスクが約40%低くなったといいます。

抗菌薬が効かない「薬剤耐性菌」の脅威は、今後25年で一段と増していくようです。米国などの研究チームが、5億2000万件のデータを基に世界204の国と地域における薬剤耐性菌による健康への影響を分析し、英医学誌The Lancetに論文を発表しました。
チームの分析によると、2050年までの25年間で3900万人以上が薬剤耐性菌により死亡し、1億6900万人が薬剤耐性菌が関連する原因で死亡すると推計されます。また、薬剤耐性菌が原因の死亡者は50年に191万人となり、22年と比べた年間の死者数は約70%増加すると考えられるそうです。
ワクチンの予防接種や感染症対策が進んだことにより、1990~2021年で薬剤耐性菌による5歳未満の子どもの死者数は50%以上減少したといいます。しかし、感染した時には治療が難しくなっているとのことです。また、70歳以上の死者数は同期間に80%以上増加しており、これらの傾向は今後も続く見通しだといいます。
チームは、不適切な抗菌薬の使用を最小化することや新しい抗菌薬の開発、感染症の予防対策などで、2025~50年で合計9200万人の命を救うことができるとしています。

新生児の腸に最初に定着する「先駆細菌」は3種類に分類され、そのうちの一つが乳幼児の健康を守るために非常に重要な役割を持つことが明らかになったそうです。英国の研究チームが研究成果を科学誌Nature Microbiologyに発表しました。
チームは、英国内で生まれた生後1カ月未満の健康な乳児1288人とその母親の一部から提供された計2387の便のサンプルについて、全ゲノム解析を行いました。その結果、全ての乳児が、有益なビフィズス菌の一種であるB. longumかB. breve、感染症を引き起こすリスクのあるE. faecalisの三つのうちのいずれかを腸内先駆細菌として保有していることが明らかになったそうです。
また、B. longumは分娩(ぶんべん)時に母親から受け継がれるのですが、B. breveはそうでないことも分かったといいます。そして、B. breveは母乳の栄養を最大限に活用する働きを持っており、病原菌が腸に定着するのを防ぐ役割も果たすそうです。
チームは、B. breveが乳児向けの新たなプロバイオティクスの開発に役立つ可能性があるとしています。

米国の研究チームが、近年アルツハイマー病(AD)の治療薬として開発された複数の「抗アミロイドβ(Aβ)モノクローナル抗体」について、その効果に関する新たな説を科学誌Brainに発表しました。チームは、この薬が認知機能低下の進行を遅らせるのは、ADとの関連が指摘されている脳内のタンパク質Aβを除去するためではなく、あるタンパク質を増加させることが理由だとしています。
チームが発見したのは、脳脊髄中の「アミロイドβ42(Aβ42)」というタンパク質を増加させる作用だといいます。Aβ42はアミロイドβの一種で、構成するアミノ酸の数が通常のAβより多いタンパク質です。
チームは、ADを引き起こすのはAβの蓄積ではなく、可溶性Aβ42の減少であるとの仮説を基に、抗Aβ抗体に関する24の治験に登録されたAD患者2万5966人のデータを分析したそうです。
その結果、抗Aβ抗体の投与後に起こる脳脊髄液中のAβ42レベルの上昇が、認知障害の進行を遅れさせることに単独で関連していることが明らかになったといいます。

米中西部のミズーリ州で8月末、動物との接触歴がない鳥インフルエンザ感染者が確認されました。米疾病対策センター(CDC)は13日、この感染者から検出したウイルスについて、米国内の乳牛の間で流行している株と密接な関係があることが明らかになったと発表しました。
遺伝子解析の結果、ウイルスはH5N1型であることが判明し、感染力や重症化リスクが高まっていることを示す変異は確認されなかったそうです。感染経路は不明です。この感染者は胸の痛みや嘔吐、下痢などの症状で病院を受診。基礎疾患を有していたため入院し、検査で鳥インフル感染が判明したといいます。
感染者の家庭内濃厚接触者の1人が同じ日に同様の症状を呈したものの、回復したそうです。家族は検査を行っていないとのことです。CDCは、2人が同時に発症していることから、ヒトからヒトへの感染を裏付けるものではないとしています。
また、濃厚接触者である医療従事者も軽度の症状が出ましたが、インフルエンザの検査では陰性だったとのことです。

小児向け抗てんかん薬として一般的な「スルチアム」が、「閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA)」の治療に有効な可能性があるようです。スウェーデンの研究チームが、オーストリア・ウイーンで9月7~11日に開かれた欧州呼吸器学会(ERS)で発表し、科学技術メディアNew Atlasが報じました。
チームは、OSA患者298人を対象に12週間の調査を実施。睡眠中の呼吸障害を評価する無呼吸低呼吸指数を調べたところ、呼吸停止の頻度が、スルチアムを毎日300mg服用した群で39.9%、200mg服用した群で34.8%、100mg服用した群で17.8%、それぞれ低くなることが明らかになったそうです。さらに、血中酸素飽和度の改善や日中の倦怠(けんたい)感の軽減も確認されたといいます。
副作用としてしびれや頭痛などがみられたものの、軽~中等度だったそうです。マウスピースやCPAP(持続陽圧呼吸療法)が合わないOSA患者にとって、スルチアムが治療の選択肢になる可能性が示されました。

ゴリラは自己治療のために植物を食べるそうです。その植物から将来の創薬の手がかりが見つかる可能性があるとして、アフリカ中部ガボンの研究チームが国内の国立公園で調査を行い、成果を科学誌PLOS ONEに発表しました。
チームはまず、ニシローランドゴリラが食べる植物を記録しました。そして、地元の伝統治療師への聞き取りを基に、現地の人々のさまざまな症状の治療に使うという「パンヤノキ」「ジャイアントイエロー・マルベリー」「アフリカンチーク」「イチジクの木」の4種類に着目したそうです。詳しく調査した結果、これらの木の樹皮には抗菌・抗酸化作用のある「フェノール類」や「フラボノイド」など薬効のある物質が含まれていることが分かったといいます。
また、これらの樹皮が少なくとも1種類の大腸菌の多剤耐性株に抗菌活性を示すことが確認されたそうです。特にパンヤノキは、調査した全ての多剤耐性株に対して著しい抗菌活性を発揮したとのことです。

自分の体を攻撃する抗体ができてしまう自己免疫疾患「全身性エリテマトーデス(SLE)」の重症患者が、再発または難治性の多発性骨髄腫の治療薬「teclistamab(テクリスタマブ)」で寛解したそうです。ドイツの研究チームが、医学誌New England Journal of Medicineに発表しました。
チームはテクリスタマブに、自己抗体を産生する形質細胞やその前駆細胞を破壊する作用があることに着目。既存の治療法が効かない重度のSLEに苦しむ23歳の女性に対し、5週間にわたり5回投与しました。すると、わずか数週間で女性の腎臓機能や赤血球数が改善し、皮膚や関節の炎症は完全に消失したといいます。
治療開始から6カ月近くが経過した現在も、自己抗体は検出されておらず、女性は寛解状態を保っているそうです。ただし副作用として、免疫系を活性化させるサイトカインの大量放出によって起こる「サイトカイン放出症候群」を発症し、肺炎や副鼻腔炎などが生じたとのことです。

米国の産科医療が深刻な危機に直面しているようです。妊婦と赤ちゃんの健康増進を支援する米非営利団体「マーチ・オブ・ダイムス」が報告書を発表し、米CNNが報じました。
CNNによると、報告書は、米国で分娩を扱う医師の離職や産科病棟の閉鎖が増加していることを指摘しています。その背景には、職員の不足、診療報酬の低さ、出生数の減少などがあるといいます。また、2022年に連邦最高裁判所が中絶を認めた過去の判断を覆したことで、一部の州では中絶に関与する産婦人科医が免許を剥奪されるなどのリスクにさらされているそうです。
なお、南部や中西部の農村地域を中心に、全郡の35%以上(1104郡)で分娩設備または産科医がゼロの状態だといいます。ここには230万人以上の生殖可能年齢の女性が居住していますが、こうした地域に住むことで早産リスクが13%高まるとのことです。
報告書は、産科医療のアクセスを改善するために、助産師の活用を提唱しているそうです。

「乳幼児突然死症候群(SIDS)」のリスクの予測は、現状ではできません。しかし米国の研究チームが、既存の検査(新生児マススクリーニング検査)の項目に含まれる代謝産物を調べることで、そのリスク予想が可能になるかもしれないとの研究成果を、医学誌JAMA Pediatricsに発表しました。
新生児マススクリーニング検査は、新生児のかかとから血液を採取し、先天性疾患の有無を調べるもので、米国では全ての州で実施が義務付けられているといいます。チームは、SIDSで死亡した乳児354人とSIDSを発症しなかった乳児1416人について、この検査のデータを比較したそうです。
その結果、SIDSのリスク上昇に関連する8種類の代謝産物が特定されたそうです。この代謝産物から予測した「SIDS高リスク児」は、「SIDS低リスク児」に比べてSIDSを発症する確率が14倍高くなることが分かったといいます。高リスク児は、糖や脂肪の使用や分解に困難を抱えている可能性があるとのことです。

新型コロナウイルス感染症対策として行われたロックダウン(都市封鎖)による社会的交流の減少が、子どもたちの脳に悪影響を及ぼした可能性があるようです。米国の研究チームが米国科学アカデミー紀要(PNAS)に論文を発表しました。
米国の研究チームが、9~17歳の男女160人を対象に調査を実施。2018年とロックダウン後の21年に、論理的思考や意思決定などの機能を制御する「大脳皮質」の厚さを、MRIの脳画像から測定して比較しました。大脳皮質は年齢を重ねるにつれて自然に薄くなり、慢性的なストレスも脳に同様の変化を引き起こす可能性があるといいます。
子どもたちの大脳皮質は3年間で予想よりもはるかに薄くなっており、男子は1.4年、女子は4.2年、脳の老化がそれぞれ早まったことが示されたそうです。特に女子は、脳の30の領域で厚さが薄くなる現象が確認されたといいます。こうした脳の変化が、うつや不安、行動障害の増加に関連している可能性があるとのことです。

前立腺がんの治療で行う、男性ホルモンのアンドロゲンの分泌を抑える「アンドロゲン除去療法(ADT)」は、アルツハイマー病(AD)リスクの上昇と関連しているといいます。米国の研究チームがそのメカニズムの一端を解明したと、科学誌Science Advancesに論文を発表しました。
チームは、前立腺がんを持つADモデルマウスに8週間のADTを実施し、ADTとAD関連認知障害の関連性を分析しました。その結果、ADTによって、認知機能低下に関連する神経炎症が増進する可能性が示されたそうです。ADTが、脳の毛細血管にあるバリア機能「血液脳関門(BBB)」の完全性を損なわせ、免疫細胞の脳内への侵入が促されることが原因だといいます。
この際、AD関連のタンパク質アミロイドβの蓄積に変化は見られなかったとのこと。なお、免疫細胞の浸潤を阻害する既存薬「ナタリズマブ」をADTと併用すると、神経炎症が抑制され、マウスの認知機能が改善することも分かったそうです。

新型コロナウイルス感染症後の後遺症で認知障害が起こることがあります。米国などの研究チームが、これがアルツハイマー病(AD)による脳の変化と似たメカニズムで発生することを明らかにしたと、医学誌Alzheimer’s & Dementiaに発表しました。
チームは、コロナ感染後に起こる認知障害がADおよび関連認知症(ADRD)のメカニズムと重複するかどうかを調べるため、システマティックレビュー(系統的レビュー)を実施しました。その結果、コロナ後遺症患者に見られる脳波の異常が、ADRDの初期段階で観察されるものと類似していることが明らかになったそうです。
こうした脳波の異常は、脳の働きを助ける細胞であるアストロサイトの過剰な活性、神経炎症、低酸素状態、神経血管損傷などに起因する可能性があるといいます。チームは、認知障害を予防したり進行を緩やかにしたりすることができる可能性があるため、コロナ患者の脳波を測定することの重要性を強調しています。

子宮頸がんなどの原因となる「ヒトパピローマウイルス(HPV)」が、男性の生殖能力に影響を及ぼす可能性があるようです。アルゼンチンの研究チームが、HPVワクチン未接種の18歳以上の男性205人の精液サンプルを分析し、その結果を科学誌Frontiers in Cellular and Infection Microbiologyに発表しました。
参加者の男性のうち19%に当たる39人がHPV検査で陽性となり、20人の男性がHPVの中でも子宮頸がん、肛門がん、中咽頭がんなどの悪性腫瘍を引き起こす可能性が高い「高リスク株」の感染者だったといいます。
これらの男性は、HPVに感染してない男性に比べて、精液中に死んだ精子の割合が高いことが分かったそうです。また、精子の損傷やDNAの変化につながる白血球の減少、活性酸素種の増加も認められたといいます。一方で、「低リスク株」が感染していた男性については、同様の関連は認められなかったとのことです。

米疾病対策センター(CDC)は6日、中西部のミズーリ州で動物との接触歴がない成人1人の鳥インフルエンザ(H5)感染が判明したと発表しました。鳥インフルの感染者は今年14人目で、養鶏や酪農の関係者以外が感染した事例は米国で初めてです。CDCがウイルスの型などを含め詳細の分析を進めているそうです。
米国では今年に入ってから、乳牛や家禽の間で鳥インフルエンザH5が流行しており、感染動物と接触した13人が感染したことが分かっています。今回感染が確認された患者は基礎疾患があり、8月22日に入院して抗ウイルス薬で治療を受けた後、回復したといいます。また、患者との濃厚接触者への感染は確認されていないとのことです。
ミズーリ州では、家禽や野鳥の鳥インフル感染が確認されていますが、乳牛の感染は報告されていません。なおCDCは、今のところ一般市民へのリスクは低いままだとしています。

「塩化ナトリウム(食塩)」が、がんに対する免疫応答の強化に役立つ可能性があるそうです。ドイツの研究チームが論文を科学誌Nature Immunologyに発表しました。
チームは、まず、乳がん患者の腫瘍においてナトリウムイオン濃度が上昇していることを発見。そして、ナトリウムイオン濃度が高い環境では、がん細胞やウイルス感染細胞を殺傷する「CD8陽性T細胞」が腫瘍に対して特に高い攻撃力を発揮することを突き止めたといいます。
ヒトCD8陽性T細胞を使った生体外実験では、塩化ナトリウムが糖やアミノ酸の取り込みを促進し、細胞内のエネルギー産生を増加させることにより、T細胞の代謝機能が向上することが示されました。そしてその結果、CD8陽性T細胞による腫瘍殺傷能力が強化されるといいます。
さらに、塩化ナトリウムで前処理したCD8陽性T細胞を膵臓がんマウスに注入したところ、腫瘍の縮小が確認できたとのこと。ただし、患者が塩分の多い食事を取ればいいということではないそうです。

携帯電話が発する電波は脳腫瘍リスクに関連しない――。WHO(世界保健機関)から委託を受けたオーストラリアなどの研究チームが、科学誌Environment Internationalに論文を発表しました。
問題の発端は、WHOのがん専門研究機関である国際がん研究機関(IARC)が2011年、観察研究から得られた限られた証拠を基に、電波への暴露を「ヒトに対して発がん性の可能性あり」に分類したことです。
これによって世界中で懸念が高まったため、WHOの委託を受けた研究チームが、5000以上の文献のシステマティックレビュー(系統的レビュー)を実施したといいます。そして、1994~2022年に発表された63の研究が最終的な分析の対象になったそうです。
結果的に、携帯電話の使用と、脳腫瘍をはじめとする頭や首のがんに関連性は認められませんでした。さらに、携帯電話を10年以上使用した場合でもがんとの関連性は見つからず、通話回数や携帯電話の使用時間も結果に影響を及ぼさないことが分かったとのことです。

ヒトの体細胞に由来するiPS細胞(人工多能性幹細胞)から分化誘導した「造血幹細胞(HSC)」で、白血病や骨髄不全症を持つ子どもたちの個別化医療が実現するかもしれません。
オーストラリアなどの研究チームが、ヒトiPS細胞からヒト胚のHSCに非常によく似た移植可能なHSCを作製することに成功したそうです。そして、このHSCを免疫不全マウスに投与したところ、臍帯血(さいたいけつ)細胞移植をした場合と同程度に、骨髄の中で血液を作り始める現象(生着)が確認されたといいます。
さらに、このHSCは、ドナーから提供されるHSCと同様に、凍結保存が可能であることも示されたとのことです。患者自身の細胞からHSCを作製できれば、ドナー不足や合併症の問題を解消できる可能性があるといいます。チームは、5年以内にヒトへの第1相試験を実施することを次の目標にしているとのことです。
論文は学術誌Nature Biotechnologyに掲載されました。

体外で受精させた胚(受精卵)の遺伝的異常を子宮に移植する前に調べる「着床前遺伝学的検査(PGT)」について、スウェーデンとオランダの研究チームが1回の検査で全ての既知の異常を調べる技術を開発したそうです。
PGTは、重い病気が子どもに遺伝するリスクや染色体異常による流産のリスクがある人が行います。PGTによるスクリーニングで異常をもつ可能性が低い受精卵を選択し、子宮に戻すことができます。これまでは、染色体と遺伝子を調べるには別々の検査が必要でした。しかし、研究チームが開発したPGTは、全ての染色体と遺伝子を一度の検査で迅速かつ正確に解析することができるそうです。
時間が短縮する上に、99%以上の確実性で異常が分かるといいます。また、ミトコンドリア病のMELAS症候群などで見られる「ミトコンドリアDNA」の異常の検出もできるそうです。
論文は科学誌Nature Communicationsに掲載されました。
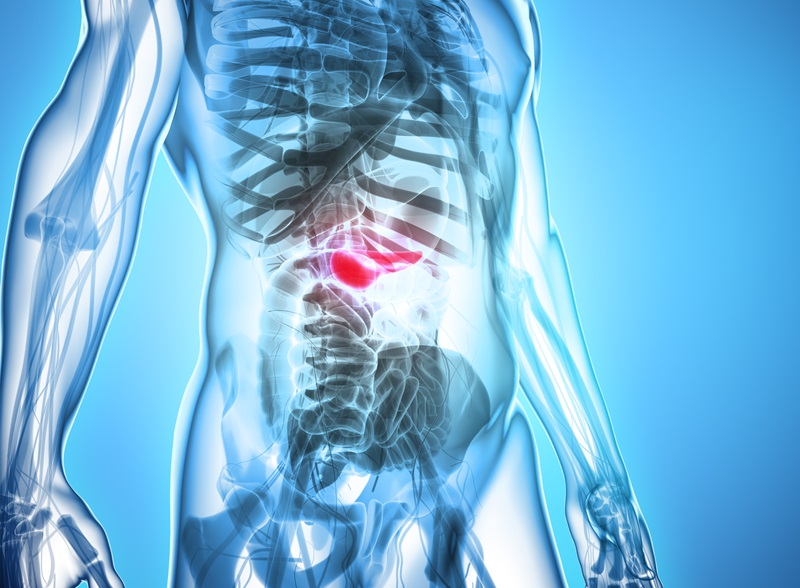
膵臓がんの大半を占める「膵管腺がん(PDAC)」に対する新たな治療法が、マウスの実験で有望な結果を示したそうです。米国の研究チームが、医学誌Science Translational Medicineに論文を発表しました。
PDACの治療を難しくしているのは、腫瘍を取り巻く環境(微小環境)にあるといいます。血管の形成を阻害し、免疫系からの攻撃を防ぐためのバリアを作っているそうです。チームは、ある薬剤を微小環境まで届ける脂質ベースのナノ粒子を開発。薬剤は、免疫系を活性化させるタンパク質インターフェロン(サイトカインの一種)の放出を促すといいます。こうすることで、腫瘍細胞がウイルスに感染していると免疫系に「信じ込ま」せ、攻撃させることができるそうです。
既存のがん治療薬(トラメチニブとパルボシクリブ)を、このナノ粒子と併用したところ、PDACマウス9匹中8匹の腫瘍が壊死または縮小し、そのうち2匹の腫瘍は完全に消滅したとのことです。

米国の研究チームが、うつ病の患者一人一人に合わせた低レベルの電流で脳を刺激する治療法を開発したそうです。チームは研究成果を医学誌American Journal of Psychiatryに発表しました。
うつ病患者は、前頭前野の左右でアルファ波(8Hz以上13Hz未満の電気信号)と呼ばれる脳波のバランスが崩れ、左側ではしばしば過活性の状態が起きるといいます。そこでチームは、患者個人のアルファ波を測定し、その結果を基に低レベルの電流で脳を刺激することで、アルファ波のバランスを取るシステムを開発したそうです。このシステムは、対象者の脳波の情報をリアルタイムで解析し、個人に合った刺激を調整して与える「閉ループ」と呼ばれるものだといいます。
うつ病患者15人に対してこのシステムを1日1時間、5日間連続で使用したところ、80%の人がすぐにうつ症状の改善を経験したそうです。さらに、2週間経過後も症状の改善は継続したとのことです。

米国で承認されている片頭痛薬「ユブロゲパント」は、頭痛が始まる予兆の段階で服用すると、片頭痛に悩まされることなく日常生活を送れるような効果があるそうです。米国の研究チームが、医学誌Neurologyに研究成果を発表しました。
チームは、1年以上片頭痛に悩まされ、直近3カ月は月に2~8回の片頭痛発作に襲われた患者518人を対象に調査しました。患者はみな、頭痛が始まる数時間前から光や音に対する感覚過敏、だるさ、首の痛みや凝り、めまいなどの予兆を経験していたといいます。
片頭痛の予兆を感じてユブロゲパントを服用した人の65%が、24時間後の状態について「日常生活に全く支障がない」または「少しだけ支障がある」と回答したそうです。一方で、予兆後にプラセボを服用した人のうち同様の回答をしたのは、48%だったといいます。
なお、ユブロゲパントを服用した人はプラセボを服用した人と比べ、服用から2時間の時点で「支障なく通常の生活を送れた」と報告する可能性が73%高くなったとのことです。

ニシキヘビが捕食した後に起こる心臓の変化の研究が、ヒトの心臓病の治療法開発に役立つかもしれません。米国の研究チームが米国科学アカデミー紀要(PNAS)に論文を発表しました。
チームは、ニシキヘビを28日間絶食させた後、一方には体重の25%に相当する量の餌を与え、もう一方には餌を与えず、双方を比べました。その結果、餌を食べたヘビは、24時間後に心臓が25%大きくなることが判明。それに伴い、心臓の拡張と収縮に関わる「筋原線維」が柔らかくなり、心臓の収縮力が約50%増強したといいます。
また餌を食べたヘビは、エピジェネティック(DNAの塩基配列の変化なしに遺伝子発現が制御される現象)な変化が生じることも確認されたそうです。そして、遺伝子や代謝物の影響を受けて、ヘビの心臓が糖の代わりに脂肪をエネルギー源にしている可能性も示されました。心不全の心臓はこの切り替えができないといい、メカニズムを解明することで、心臓組織が線維に置き換わって硬くなる心筋線維化などの治療法につながる可能性があるとのこと。

有効成分を含まない偽薬(プラセボ)を飲んで効果が出る「プラセボ効果」は、メンタルヘルスの改善に役立つ可能性があるようです。米国の研究チームが、新型コロナウイルス感染症のパンデミック中に、長期にわたるストレスを経験したという64人を対象に2週間の調査を実施し、明らかになったそうです。
チームは、32人に1日2回のプラセボ(植物繊維の錠剤)を処方し、残りの32人には治療に関わることは何もしなかったといいます。そして、プラセボを処方された群は、自分たちが有効成分を含まない偽薬を飲むことを知らされていたそうです。それにもかかわらず、プラセボを処方された群は何も治療を受けなかった群に比べてストレス、不安、うつのレベルが低下したといいます。
チームは、この結果について、明確な期待だけでなく、暗示的な期待や過去に受けた有効な治療の経験などが、こうしたプラセボ効果につながる可能性があると分析しています。
この研究成果は、学術誌Applied Psychology: Health and Well-Beingに掲載されました。

米国の研究チームが、血中の「LDL(悪玉)コレステロール」に加えて、脂質の一種である「リポ蛋白(a)<Lp(a)>」と炎症の指標である「CRP(C反応性たんぱく)」を測定すると、女性の心血管疾患リスクをより正確に予測できることを発見したそうです。米医学誌New England Journal of Medicineに論文を発表しました。
チームは、平均年齢55歳の健康な女性3万人近くのデータを分析。30年にわたる追跡調査の結果、約3600人(13%)が▽心筋梗塞(こうそく)や脳卒中を発症した▽動脈狭窄や動脈塞栓の手術を受けた▽心血管疾患で死亡した――のいずれかに当てはまったといいます。
調査開始時の血液検査でLDLの値が高かった人は、この値が低かった人に比べてこうした心血管疾患リスクが36%高くなることが分かりました。そしてリスクは、Lp(a)値が高い人で33%、CRP値が高い人で70%上昇することも示されたといいます。三つ全てが高かった人は、脳卒中リスクが1.5倍、冠状動脈性心疾患リスクが3倍超になったとのことです。

細胞内に存在する「ミトコンドリア」は元々「好気性細菌」だったと考えられています。その名残として、ミトコンドリアは独自のDNAを持っています。米国の研究チームが、ミトコンドリアがDNAを細胞核内に送り込む現象が脳細胞で起きており、そのことが人間に害を及ぼしている可能性があると、科学誌PLOS Biologyに発表しました。
チームは、死亡した高齢者1187人の脳組織サンプルを調査。ミトコンドリアDNAの断片が核ゲノム内に挿入される現象が、人の生涯で複数回起きている可能性が示されたそうです。
核ゲノムに挿入されたミトコンドリアDNAの断片は「NUMT」と呼ばれます。前頭前野にNUMTが多い人は、NUMTが少ない人に比べて早死にするリスクが高いことが明らかになったといいます。
さらに、ヒト皮膚組織を使って調査したところ、ストレスによって細胞内のミトコンドリアが機能不全になると、NUMTが4〜5倍の速さで蓄積することが示されたといいます。

週末に「寝だめ」をして平日の睡眠不足を補うと、心臓病リスクを抑制できる可能性があるそうです。中国の研究チームが欧州心臓病学会(ESC2024 Congress)で発表しました。
チームは、英国バイオバンクから抽出した9万903人のデータを分析。このうち5分の1が1日の睡眠時間が7時間未満の「睡眠不足」に分類されたといいます。チームは、睡眠不足を埋め合わせるために週末に取っている余分な睡眠時間を基に参加者を4群に分け、平均14年間の追跡調査を行いました。
その結果、週末の余分な睡眠時間が最も多い(1時間強~)群は、最も少ない(平日よりも少ない)群に比べて心臓病を発症するリスクが19%低くなることが明らかになったそうです。
NBC Newsによると、米調査会社ギャラップによる世論調査では、必要な睡眠時間を確保できている米国成人はわずか42%で、57%が「もう少し睡眠を取ることができれば、すっきりする」と回答したといいます。

尿失禁や骨盤臓器脱の治療の「経膣メッシュ手術」を受けた後、慢性的な痛みに苦しむ人がおり、問題になっています。英BBCによると、英イングランドで、この手術によって痛みや合併症を経験した女性100人以上が集団訴訟を起こし、メッシュを製造した3社から解決金を受け取ったそうです。
経膣メッシュ手術は何年ものあいだ、女性の尿失禁や骨盤臓器脱の代表的な治療法と考えられてきました。しかしメッシュが硬化して組織を傷つけ、一部の女性は永続的な痛みに悩まされたといいます。歩けなくなったり、働けなくなったり、性行為ができなくなったりした人もいるとのことです。
この手術によって約1万人が負傷したといわれていますが、手術を受けた人の10~20%に当たる約4万人が合併症に悩んでいるとの推計もあるそうです。
イングランドでの訴訟は、「メッシュの製造日から10年」が解決金の請求期限で、訴訟の機会を奪われた人が多数いるとの指摘もあるとのことです。

米疾病対策センター(CDC)は27日、キューバから帰国した21人が「オロプーシェ熱」を発症したと発表しました。また、医師らに対し、中南米への渡航歴がある人については、感染の可能性を考慮するよう注意を呼びかけています。
オロプーシェ熱の原因となるオロプーシェウイルスは、ヌカカ(ハエ目の微小昆虫)や蚊を介してヒトに感染します。中南米では今年に入り、既知の流行地だけでなく新たな地域でも感染者が見つかり、ボリビア、ブラジル、コロンビア、キューバ、ペルーで8000人以上の患者が報告されています。
主な症状は発熱や頭痛、筋肉痛で、下痢や嘔吐、発疹がみられることもあるそうです。命にかかわることはまれですが、ブラジルでは最近、健康な若者2人が死亡したといいます。妊婦から胎児に感染したとみられるケースも確認されています。
ワクチンや治療薬はありません。CDCはキューバを訪れる全旅行者に対し、虫除け対策を講じることを推奨しています。

喫煙や太り過ぎなどの「修正可能な危険因子」に注意して健康な生活を送るだけで、がんリスクが半減するかもしれません。
米国の研究チームが、米国における2019年の30歳以上のがん症例178万件を分析しました。その結果、30種類のがんのうち19種類について、死亡や発症の半数以上が修正可能な危険因子に起因することが分かったそうです。
全症例のうち19.3%が喫煙、7.6%が太り過ぎ、5.4%が飲酒、4.6%が紫外線の暴露、3.1%が運動不足に関連していたといいます。また、子宮頸がんについては、症例の100%がワクチンを接種していれば予防でき、修正可能な危険因子に起因することが明らかになったそうです。症例数が最も多かったのは肺がんで、男性は10万4410件、女性は9万7250件が、それぞれ修正可能な危険因子が原因である可能性が示されたとのことです。
チームは、この研究成果を医学誌CA: A Cancer Journal for Cliniciansに発表しました。

健康や寿命、組織再生を改善するといわれる「断食」について、米国の研究チームが腸幹細胞に着目した研究で、メリットとデメリットを明らかにしたそうです。英科学誌Natureに研究成果を発表しました。
チームがマウスを使って調査したところ、腸の損傷や炎症からの回復を助ける腸幹細胞の再生能力が、断食中にいったん低下し、断食明けに食事を好きなだけ取り始めてから24時間経過した時点で最も高いレベルまで上がることが分かったそうです。これは、細胞の成長や分裂に関わる細胞内の物質「ポリアミン」の産生が増大するためだといいます。
一方、断食によって幹細胞の再生能力が高まることによるデメリットも示されました。腸幹細胞について、断食明けに食事を再開したマウスの発がん遺伝子をオンにして調べたところ、断食中または断食を行わなかったマウスの発がん遺伝子をオンにした場合に比べて、前がん状態のポリープが作られるリスクが高くなったとのことです。

人とのつながりが希薄で孤独を感じると、ひどい悪夢を見たり、悪夢を見る頻度が増えたりするそうです。米国の研究チームが学術誌The Journal of Psychologyに論文を発表。認知機能、気分の調節、代謝、その他の健康と深い関係がある睡眠の質に、孤独が悪影響を及ぼす可能性があると指摘しています。
チームは18~81歳の成人1600人以上を調査したそうです。参加者は、孤独感に関するさまざまな感情や悪夢の体験、ストレスに関わる感情などの質問について答えたといいます。分析の結果、孤独が悪夢の頻度や強度に関連していることが明らかになったとのことです。孤独によるストレス、心配や不安がぐるぐる頭の中を巡る「反すう思考」、過度に用心深くなったり集中したりする「過覚醒」が、悪夢の要因として考えられるといいます。
チームは、孤独と睡眠障害はいずれも健康に深刻な影響をもたらす問題であり、心臓病や脳卒中、早死になどのリスク上昇に関連する可能性があるとしています。

アルツハイマー病(AD)の新たな治療薬の候補となる化合物が見つかったそうです。「レカネマブ」などのようにAD関連のタンパク質であるアミロイドβを標的とするのではなく、全く違った経路で作用するといいます。米国の研究チームが、米国科学アカデミー紀要(PNAS)に研究成果を発表しました。
チームは、認知処理やワーキングメモリーの基礎となる脳回路の調整をする「ガンマ振動」という脳波に着目。軽度認知障害がある初期AD患者は、このガンマ振動が減少することが知られています。そしてチームは、このガンマ振動をニューロン(神経細胞)で持続的に発生させる化合物「DDL-920」を発見したそうです。
ADマウスにDDL-920を1日2回、2週間にわたって経口投与したところ、健康なマウスと同程度の認知力と記憶力を取り戻したといいます。DDL-920を投与したマウスに、異常行動や多動をはじめとする目に見える副作用は認められなかったとのことです。

低カロリーでありながら栄養価の高い食事をスープやシェイクの形で取ると、2型糖尿病の寛解につながる可能性があるそうです。
英国民保健サービス(NHS)は、2型糖尿病の寛解を目指す1年間の国民向けプログラムを実施しています。そして今回、2022年1月以前にプログラムに参加した太り過ぎの2型糖尿病患者1740人のデータを分析し、調査結果を公表しました。患者は最初の3カ月間は1日の総摂取カロリーが800~900kcalになるよう全ての食事をスープやシェイクに置き換え、その後の9カ月間で徐々に固形の食事を再開するよう指導を受けたといいます。
プログラムの完遂と2回のヘモグロビンA1c(HbA1c)検査という条件を満たした450人のうち、145人(32%)が血糖降下薬なしで糖尿病が寛解したそうです。寛解を達成した患者は、プログラム期間中に体重が平均15.9kg減少したとのことです。
論文は医学誌Lancet Diabetes and Endocrinologyに掲載されました。

子どもの新型コロナウイルス感染症後の後遺症は、年齢によって主に見られる症状が異なる可能性があるそうです。米国の研究チームが医学誌JAMAに論文を発表しました。
チームはコロナ感染歴のある子ども3800人以上の保護者に対し、感染から90日以上経過した時点の症状について聞き取り調査を実施。そして、コロナ感染歴のない子ども約1500人の保護者へも聞き取り調査を行い、それぞれの結果を比較したところ、子どものコロナ後遺症に関連するとみられる症状が14種類特定されたそうです。
6~11歳の子どもではコロナ後遺症として、頭痛、記憶力や集中力の低下、睡眠障害、腹痛が最も一般的であることが分かったといいます。また、12~17歳の子どもは、大人と同様に倦怠(けんたい)感や頭にもやがかかったようになるブレインフォグなどの症状が多く見られ、幼い子どもに比べて日中の眠気や活力低下、筋肉や関節の痛みが生じる可能性が高かいことが明らかになったとのことです。
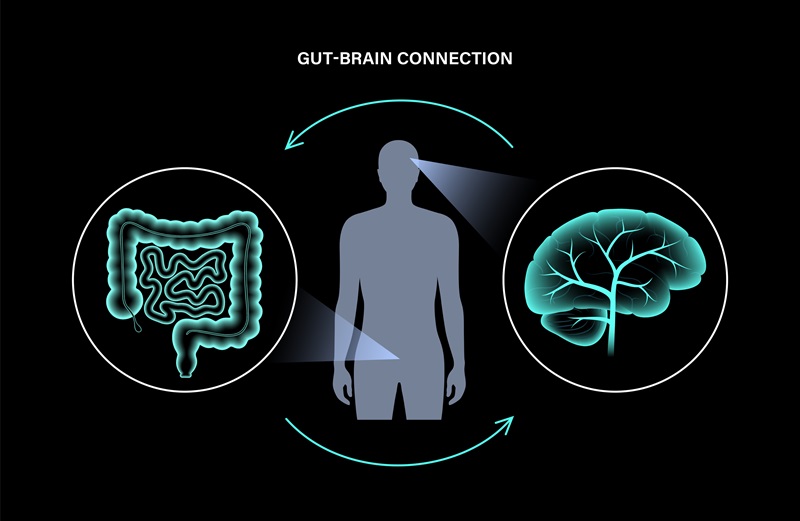
ストレスは有益な腸内細菌を減らしてしまうそうです。米国、中国、ドイツの研究チームが米科学誌Cellに論文を発表しました。
チームは十二指腸の「ブルンネル腺」に着目。腸内の物質の移動を助ける粘液を分泌する役割を持つのですが、神経細胞が多くあることから、それ以外の働きがあると考えたそうです。マウスのブルンネル腺を切除したところ、腸壁から血液に有害物質が漏れ出すのを防ぐ乳酸菌の一種「ラクトバチルス菌」が減少し、炎症や異常な免疫応答が起きることが分かったといいます。
さらにチームは、ブルンネル腺の神経細胞が迷走神経を介してストレス処理に関与する脳の扁桃体につながっていることを発見。健康なマウスにストレスを与えたところ、ブルンネル腺を切除したマウスと同様の状態に陥ることが確認されたそうです。ストレスを受けた扁桃体の影響がブルンネル腺にも波及し、ラクトバチルス菌が減少して炎症や異常な免疫応答につながる可能性が示されました。

パーキンソン病(PD)治療薬「レボドパ」で、アルツハイマー病(AD)に関連するタンパク質「アミロイドβ」の蓄積を減らせる可能性があるようです。理化学研究所などの国際チームが、研究成果を科学誌Science Signalingに発表し、Science Alertが概要を紹介しました。
チームは、脳内神経伝達物質の一つである「ドーパミン」がアミロイドβの分解酵素「ネプリライシン」の産生を増加させることを発見したそうです。レボドパは脳内に入るとドーパミンに変化する薬で、これをADモデルマウスに投与したところ、ネプリライシンの発現が高まり、アミロイドβの蓄積が減少したといいます。さらに、マウスの認知機能が改善することも示されたとのことです。
また、高齢マウスにおいてドーパミンとネプリライシンが減少していることも確認されたといいます。この発見は、加齢が主原因とされるADの発症機序に関する重要な手掛かりになる可能性があるとのことです。

ニュージーランド特産の蜂蜜「マヌカハニー」で、乳がんの70~80%を占める「エストロゲン受容体(ER)陽性乳がん」の増殖を抑制できるかもしれません。
米国の研究チームがER陽性乳がんマウスにマヌカハニーを経口投与したところ、腫瘍の増殖が84%抑制されることが明らかになりました。正常な乳房細胞が影響を受けたり、重大な副作用が起きたりすることはなかったといいます。ヒトの細胞を使った実験でも、マヌカハニーが正常な細胞に影響を与えることなく、ER陽性乳がん細胞の増殖を抑制することが示されました。
マヌカハニーによって、腫瘍の増殖に関与する情報シグナル伝達が阻害され、乳がんの細胞死が誘導されることも分かったそうです。ER陽性乳がん治療に一般的に使われる「タモキシフェン」などの抗エストロゲン薬の効果は、マヌカハニーと併用することで高まる可能性があるとのことです。
チームは科学誌Nutrientsに論文を発表しました。

プラスチックの原料「ビスフェノールA(BPA)」に母親が多く暴露していると、お腹にいる男児の自閉症リスクが高くなる可能性があるそうです。
オーストラリアの研究チームが、母子1074組のデータから、男の胎児の脳発達に特に重要な役割を果たす酵素「アロマターゼ(芳香化酵素)」のレベルが低い男児に着目。妊娠後期に尿中BPAレベルが高かった母親から生まれた低アロマターゼレベル男児は、2歳までに自閉症の症状が出るリスクが3.5倍、11歳までに自閉症と診断されるリスクが6倍になったといいます。
またBPAが、DNAの塩基配列を変えずに遺伝子の働きを制御する「エピジェネティック」な経路を介してアロマターゼの発現を抑制することも示されたそうです。マウス実験では脂肪酸の一種「10-ヒドロキシ-2-デセン酸(10HDA)」でBPAによるこうした有害作用を軽減できる可能性が示されました。
チームは科学誌Nature Communicationsに研究成果を発表しました。

免疫細胞のマクロファージは、呼吸器感染症で肺に損傷を与える可能性があることが指摘されていました。しかし、ベルギーの研究チームが、肺修復に重要な役割を果たすマクロファージが存在することを発見したと、科学誌Science Immunologyに発表しました。
チームはインフルエンザAに感染させたマウスを使って調査。感染による肺損傷からの回復初期に、「単球由来Ly6G発現マクロファージ」が出現することが明らかになりました。このマクロファージは非典型的で短命であり、食作用が強く、再生中の肺胞に動員されるといいます。
Ly6Gマクロファージを欠損したマウスを調べたところ、インフル感染後の上皮再生がうまくいかないことが分かったそうです。また、 Ly6Gマクロファージは、肺の構造維持に必要な成分を出す細胞「2型肺胞上皮細胞」が肺胞を再生する際に不可欠であることも明らかになったといいます。呼吸器感染症の新たな治療標的になる可能性が示されました。

舌の色からさまざまな病気を即時に検出できるAI(画像処理システム)が開発されたそうです。
イラクとオーストラリアの研究チームが5260枚の画像を使い、舌の色から病気を検出できるよう機械学習アルゴリズムを訓練したといいます。そして、このアルゴリズムを組み込んだ画像処理システムでさまざまな健康状態の患者60人の舌の画像を分析したそうです。その結果、96.6%の精度で病気を診断することができたといいます。
このシステムは、患者から20cm離れた所に置いたカメラで舌を写すことで、糖尿病、脳卒中、貧血、ぜんそく、肝臓や胆のうの疾患、新型コロナウイルス感染症、血管や胃腸の問題を予測することができるといいます。将来的には、スマートフォンを使って同様の診断ができるようになる可能性もあるとのことです。
チームは科学誌Technologiesに研究成果を発表しました。

無反応に見える脳損傷患者の中には、頭の中で呼びかけに反応しようしている人が思ったより多くいる可能性があるそうです。米国の研究チームが米医学誌New England Journal of Medicineに論文を発表しました。
チームは、外からは意識がないようにみえる脳損傷患者353人を調査。このうち241人が、「昏睡状態」「植物状態」「最小意識状態」のいずれかであると診断されました。こうした患者に、「手を閉じたり開いたりして」などと口頭で指示をしたところ、241人中60人が頭の中でこの指示を実行しようとしていることが脳波やfMRI(機能的磁気共鳴画像)から立証されたといいます。
脳は反応しているけれど体の反応はみられない状態は、「認知と運動の解離」や「隠れた意識」と呼ばれています。特に若者や事故による外傷性脳損傷患者は、この状態の可能性が高かったとのことです。

視覚処理速度を評価する検査が、認知症リスクの予測に役立つ可能性があるそうです。
英国の研究チームが、48~92歳の健康な8623人を長期にわたり追跡調査しました。このうち537人が調査終了時までに認知症と診断されたといいます。そして、認知症を発症した人は、そうでない人に比べて調査開始時に実施した視覚処理速度の検査のスコアが低いことが明らかになったとのことです。検査は、画面上をドットが動き、そこに三角形ができたらすぐにボタンを押すというテストが用いられました。
研究の結果、視覚処理速度の遅さを調べると、診断の12年も前から認知症を予測できる可能性があることが示されたそうです。視覚に関与する脳領域は、アルツハイマー病に関連する有害な「アミロイドプラーク」の影響を最初に受ける可能性があると考えられています。そのため、記憶より先に視覚の問題が認知機能低下の初期指標になり得るとのことです。
チームは2024年2月、科学誌Scientific Reportsにこの研究成果を発表しました。

スウェーデンの保健当局は15日、アフリカで感染が拡大している「エムポックス(サル痘)」について、国内で感染者が確認されたと発表しました。アフリカ以外では初めての感染例で、WHO(世界保健機関)が14日に「緊急事態宣言」を出したばかりです。
AP通信によると、欧州各国の保健当局は「輸入例」について警戒しているものの、世界的なパンデミックにつながる可能性は非常に低いとみているようです。理由について専門家は、エムポックスは主に肌と肌との接触で感染し新型コロナウイルスのような空気中のエアロゾルによって感染が広がることはない▽エムポックスは目に見える皮膚病変が起こることが多いため感染者との接触を避けやすい▽有効なワクチンや治療薬が存在する――ことなどを挙げています。
また、新型コロナは3カ月で感染者12.6万人、死者4600人を記録したのに対し、エムポックスは2022年以降の世界の感染者が10万人、死者が200人と拡大のスピードが遅いことも明らかになっています。

お酢を毎日取ると、心の健康に意外な効果をもたらす可能性があるそうです。米国の研究チームが、科学誌Nutrientsに研究成果を発表しました。
チームは、太り過ぎていること以外は健康に問題がない成人28人を2群に分けて4週間の調査を実施したそうです。その結果、メンタルヘルスを評価するアンケート調査で得られたうつ症状のスコアが、大さじ2杯の「赤ワインビネガー」を1日2回摂取した群が平均42%、少量のお酢を含有する錠剤を1日1錠摂取した群が平均18%、それぞれ低下したことが分かったといいます。
さらに、赤ワインビネガー群では、抗炎症作用に関連するとされる「ビタミンB3(ニコチン酸アミド)」の血中濃度が86%上昇することも明らかになったといいます。毎日お酢を摂取することでビタミンB3の代謝が変化し、うつ症状が軽減する可能性があるとのことです。

WHO(世界保健機関)は14日、アフリカで感染が急拡大している「エムポックス(サル痘)」について、「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言しました。今回の宣言は、致死率の高い「クレード1b」と呼ばれる型がコンゴ民主共和国やその近隣諸国で急速に広がっていることを受けたものです。
エムポックスに関する緊急事態が宣言されるのは2022年7月に続いて2回目。アフリカ疾病対策センター(CDC)によると、アフリカでは今年、13カ国で計1万7千件以上の症例が報告されています。WHOによると、最も症例数が多いのはコンゴ民主共和国で、感染者は1万5600人以上、死者は537人に上るといいます。
エムポックスは、性行為やキスなどの密接な接触だけでなく、汚染されたシーツや衣類などを介しても広がる可能性があります。発熱やリンパ節の腫れ、痛みを伴う発疹が主な症状です。

米食品医薬品局(FDA)は9日、重篤なアレルギー反応「アナフィラキシー」に対処するためのエピネフリン点鼻スプレーを承認したそうです。
米CNNによると、承認されたのは米ARS Pharmaceuticals社が開発した「Neffy」という薬です。体重30kg以上の成人及び子どもが対象で、片方の鼻孔からスプレーを噴霧して投与するといいます。アナフィラキシーの一般的な補助治療剤である「エピペン(エピネフリン自己注射薬)」などと同じく、必要に応じて2回目の投与もできるそうです。
健康な成人175人を対象とした臨床試験では、Neffyを使用した場合とエピネフリンを注射で投与した場合で、血中のエピネフリン濃度が同等であることが示されたといいます。
注射針を使わずにエピネフリンを投与できるため、注射を怖がる子どもにとって使用のハードルが下がることが期待されます。ARS社は、9月末までに体重15~30kgの小児用Neffyの承認も申請する予定とのことです。

米食品医薬品局(FDA)は9日、米Lykos Therapeutics社による合成麻薬「MDMA」の「心的外傷後ストレス障害(PTSD)」治療薬としての使用について、承認申請を却下したそうです。
AP通信によると、FDAは安全性や有効性を示すデータが不十分であるとして、追加の試験を求めたといいます。今年6月に開かれたFDAの諮問委員会でも、同様の理由で承認は推奨されませんでした。
Lykos社が実施した二つの小規模治験では、MDMAとトークセラピーの併用でPTSDの症状が緩和することが示されていました。しかし、FDAがデータを精査したところ、治験参加者の多くがMDMAとプラセボのどちらを投与されたかを推測できてしまっており、医学研究に不可欠な「盲検化」が維持されていないことが判明したそうです。
さらに、治験にかかわった一部の研究者が、否定的な結果を隠したり肯定的な結果を誇張したりしていたなどの不正疑惑も浮上しているといいます。

蜂蜜はヨーグルトに含まれるプロバイオティクス(人体に有益な生きた微生物)の働きを助けるそうです。
米国の研究チームがビフィズス菌の一種「ビフィドバクテリウム・アニマリス(B.アニマリス)」を含むヨーグルトに4種類の蜂蜜を加え、唾液、胃液、胆汁などを模倣した溶液を混ぜて微生物を培養したといいます。その結果、特に「クローバー蜂蜜」に、B.アニマリスの腸での生存を促進する効果がある可能性が示されたそうです。
また、健康な成人66人に対する調査で、クローバー蜂蜜入りのヨーグルトを2週間食べた上で便を調べると、B.アニマリスの腸内での生存能力が高まることが分かったといいます。さらに、36人を対象にした調査を行い、ヨーグルトに砂糖を加えても蜂蜜のような効果は得られないことを確認したそうです。
チームはこの研究成果を科学誌Journal of Nutritionに発表しました。

人工甘味料の「エリスリトール」は、心臓発作や脳卒中の一因となる血栓のリスクを高めるそうです。米国の研究チームが、研究成果を医学誌Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biologyに発表しました。
エリスリトールはトウモロコシを原料とする糖アルコールで、「ゼロカロリー」や「糖質ゼロ」の商品に使われています。チームは、健康な中年男女20人を対象に調査を実施。参加者は一晩の絶食後、30gのエリスリトールまたは砂糖(グルコース)が入った甘い水を飲んだといいます。
甘い水を飲む前と飲んだ30分後の血液を比較したところ、グルコース入りの水を飲んでも血中グルコースレベル(血糖値)の上昇はわずかだったのに対し、エリスリトール入りの水を飲むと血中エリスリトールレベルが1000倍に上昇したといいます。そして、エリスリトール群でのみ、血栓につながる「血小板凝集」が増加することが分かったそうです。

砂糖の代わりに人工甘味料を使った「ダイエット飲料」は、健康にどのような影響を与えるのでしょうか。長期的なリスクについて懸念を持つ豪州の栄養学などの研究者による記事が、The Conversationに掲載されました。
米国や豪州の当局は、人工甘味料は安全であるとの考えを示しています。しかし、ダイエット飲料を定期的かつ頻繁に飲む人は、糖尿病や心臓病のリスクが高くなることが分かっているといいます。
WHO(世界保健機関)は2023年、多くのダイエット飲料に添加されている人工甘味料「アスパルテーム」について「発がん性の可能性がある」との見解を公表。さらに、人工甘味料が長期的な体重管理に直接的な効果をもたらさない可能性があるとの研究結果も発表しています。
その上、ダイエット飲料の過度な摂取は消化器系や肝臓の炎症、歯が溶けてしまう「酸蝕」につながる恐れもあるといいます。

臓器移植後の免疫抑制剤として広く使用されている「ラパマイシン」で、卵巣の老化を遅らせることができる可能性があるそうです。英大学の生殖生物学の専門家による記事がThe Conversationに掲載されました。
記事では、米国の研究チームによる調査結果を紹介しています。チームは、閉経周辺期に入った35~45歳の女性50人を対象に3カ月間の調査(治験)を実施しました。
その結果、週1回ラパマイシンを投与された人は、卵巣の老化が20%抑制することが示されたそうです。副作用はなかったとのことです。
これは、妊娠可能な期間が5年延長されることを意味する可能性があるといいます。月経周期に合わせて卵巣で育つ卵胞の数をラパマイシンが制限することで、この効果がもたらされると考えられるとのことです。
なお、この結果を受け、治験を1000人規模に拡大して実施する見込みだそうです。

インフルエンザウイルスの感染の広がりを防ぐために換気をしても、環境によってはあまり効果が得られないそうです。米国の研究チームが米国科学アカデミー紀要(PNAS)に論文を発表しました。
チームは、人の子どもと似た動きをするとされるフェレットを使って、保育所を再現した環境で実験を行ったそうです。おもちゃがあるベビーサークル内で、インフルエンザにかかっているフェレット1匹と非感染フェレット4匹を数時間遊ばせ、ウイルスの広がりを調査したといいます。その結果、きちんと換気をしたとしても、ウイルスが感染するフェレットの数はほとんど変わらないことが分かったそうです。
換気をすると空気中のウイルス量がわずかに減るものの、サークル内の物に付着したウイルス量は、換気レベルが低い場合と同程度だったといいます。また、感染リスクに重要な影響を及ぼすのは、一緒に過ごした時間の長さではなく、お互いの距離の近さや物を介した間接的な接触である可能性も示されたとのことです。

植物由来の成分を配合するサプリメントは、過剰に摂取すると肝障害につながる可能性があるそうです。米国の成人の約5%がそういった危険性のあるサプリを使用していることが分かったと、米国の研究チームが医学誌JAMA Network Open に発表しました。
ウコン、緑茶、アシュワガンダ、ガルシニア・カンボジア、紅麹、ブラックコホシュの6種類のサプリが肝臓に負担をかける可能性があるといいます。チームが、米国の成人9685人のデータを分析したところ、4.7%がこのうち一つ以上を摂取していることが判明。
最も多かったのはウコンのサプリで、関節痛などを和らげるために推定1100万人以上が定期的に摂取しているとみられるそうです。同じ目的で非ステロイド性抗炎症薬(NSAID)を使用しているのは1480万人おり、あまり変わらない数だといいます。
薬物性肝障害のうち、こうしたサプリの過剰摂取などによる症例の割合は、2004~05年の7%から13~14年は3倍近い20%に増加しているとのことです。

2型糖尿病や肥満の治療に使われるGLP-1受容体作動薬の一種「リラグルチド」が、アルツハイマー病(AD)に有効な可能性があるそうです。英国の研究チームが米国で開かれたアルツハイマー病協会国際会議(AAIC2024)で発表し、Medical Xpressが報じました。
チームは、軽度AD患者204人を対象に調査を実施。最大1.8mgのリラグルチドを1年間毎日投与した群は、プラセボ群に比べてADの特徴である脳萎縮が50%近く減少したそうです。リラグルチド群は、認知機能の低下が18%遅くなることも分かったといいます。
リラグルチドがどのように脳に作用するかは明らかになっていませんが、炎症やインスリン抵抗性、AD関連のタンパク質であるアミロイドβやタウの毒性などを低減する可能性があるそうです。現在二つの治験が行われており、結果は2025年末に明らかになる予定とのことです。

WHO(世界保健機関)のアメリカ地域事務局である汎米保健機構(PAHO)は2日、ブラジルで「オロプーシェ熱」によって若い女性2人が死亡したとみられることなどを受けて、疫学的警告を出しました。
オロプーシェ熱は、ヌカカ(ハエ目の微小昆虫)や蚊に刺されることで「オロプーシェウイルス」に感染して発症する熱性疾患です。米疾病対策センター(CDC)によると、症状はデング熱に似ており、発熱、頭痛、筋肉痛などが生じます。妊婦が感染すると、ジカウイルス感染症でもみられる胎児の「小頭症」や死産につながる可能性もあるそうです。ワクチンや特効薬はありません。
NBC Newsによると、中南米では今年に入り、少なくとも8078件のオロプーシェ症例が報告されています。このうち約90%(7284件)はブラジルで確認されており、昨年1年間の832件から急増しているそうです。

アルツハイマー病(AD)の遺伝的な危険因子である「APOE4遺伝子」を持つ人は、積極的に魚油を摂取するといいかもしれません。
米国の研究チームが、魚油に多く含まれる「オメガ3脂肪酸」の血中濃度が低い75歳以上の102人を対象に調査を実施しました。参加者は、脳深部の神経線維が集まる大脳白質に、白質病変と呼ばれる虚血状態の部分が比較的高いレベルで見られ、認知症リスクが高めだったそうです。
3年間にわたる調査を行い、魚油を毎日摂取した群とプラセボ群を比較したところ、白質病変の進行抑制については統計的な有意差は認められなかったといいます。しかし、APOE4遺伝子を持つ高齢者だけを調べてみると、魚油の摂取開始からわずか1年で、脳細胞の破壊が劇的に抑制されることが分かったそうです。
チームは医学誌JAMA Network Openに論文を発表しました。

既存の抗菌薬の治療だけでは効果がない「人食いバクテリア」などに広く効果が期待できる化合物を発見したと、米国の研究チームが科学誌Science Advancesに発表しました。
チームは、細菌感染と戦う能力を持つ化合物を使い、「GmPcides」と名付けた新たな抗菌薬を開発したそうです。そして、劇症型溶血性レンサ球菌感染症を引き起こすA群溶血性レンサ球菌をマウスに感染させて軟部組織壊死を発生させ、GmPcidesで治療したといいます。
すると、皮膚潰瘍は小さく、感染からの回復も早かったとのことです。GmPcidesは細菌の病原性を抑え、感染による皮膚損傷の治癒を早めることが示されました。
また、チームは、病気を引き起こすことのある腸球菌やブドウ球菌などにもGmPcidesが効果を発揮することを確認。さらに、GmPcidesに対する薬剤耐性菌は出現しにくいことも分かったそうです。

細胞の核を未分化の状態にリセットする「リプログラミング」の技術で、加齢に関連するアルツハイマー病(AD)をモデル化することに成功したそうです。米国の研究チームが米科学誌Scienceに成果を発表しました。
チームは、患者の皮膚から採取した線維芽細胞を神経細胞(ニューロン)に転換し、脳の環境を模倣した塊(スフェロイド)を作製。AD患者由来のスフェロイドでは、ADに関連するタンパク質であるアミロイドβやタウの蓄積、ニューロン死が確認できたそうです。
一方、健康な高齢者由来のスフェロイドでも少量のアミロイドβ沈着が確認され、この技術が患者自身の加齢の影響を反映できることが明らかになりました。
AD患者由来のスフェロイドを使った実験では、アミロイドβプラークの形成を阻害する薬剤の早期投与や、B型肝炎やエイズの抗ウイルス薬「ラミブジン(3TC)」の投与が治療に有効である可能性が示されたそうです。

大腸がんの発症リスクが高いとされる生活習慣を持つ人は、「アスピリン」を服用するとその発症を予防できるかもしれません。米国の研究チームが研究成果を医学誌JAMA Oncologyに発表しました。
チームは、調査開始時に平均年齢49.4歳だった男女10万7655人を30年以上にわたり追跡。大腸がんの10年累積罹患率は、アスピリンを定期的に服用した人が1.98%だったのに対し、定期的に服用しなかった人は2.95%だったそうです。
特に、BMIや喫煙の有無などから算出した生活習慣スコアが最も低い(不健康な)群においては、アスピリンを服用しなかった人で3.4%だった大腸がん罹患率が、アスピリンを服用した人では2.12%に抑制されたといいます。一方、最も健康な群がアスピリンを服用しても、罹患率は1.6%から1.5%とわずかな低下にとどまりました。
過去の研究によると、アスピリンは毎日低用量(81mg)を服用するといいそうです。

アルツハイマー病(AD)と間違われやすい認知症があるそうです。米国などの研究チームが、この認知症を「LANS(辺縁系優位型健忘性神経変性症候群)」と名付け、ADと区別するための基準を科学誌Brain Communicationsに発表しました。
LANSは、ADと似た記憶障害があるにも関わらず、脳画像やバイオマーカーからは明らかにADではないこと分かるそうです。チームは、ゆっくりとした進行▽高齢(主に80歳以上)であること▽症状が軽度▽海馬の萎縮――などの項目を含む基準を設定しました。
そして、この基準を使って遺体の解剖(剖検)で診断が付いたADまたはLANS患者について、生前のデータを基に分類を行ったといいます。その結果、ADとLANSの患者を70%以上の精度で分類できることが分かったそうです。

血液検査でアルツハイマー病(AD)を高い精度で検出できることを実証したと、スウェーデンの研究チームが医学誌JAMAに成果を発表しました。
「APS2」と呼ばれるこの検査は、ADに関係するタンパク質「アミロイドβ」と「タウ」について、血漿(けっしょう)に含まれる正常なタンパク質と異常なタンパク質の比率の組み合わせを用いて調べるそうです。
チームは、認知症状のためにプライマリケア医や専門の医師の診察を受けた患者1213人を対象に調査を実施しました。その結果、APS2を使うと、プライマリケア医も専門の医師も91%の精度でADを特定できることが分かったそうです。一方で、認知検査や臨床検査を使った標準的な評価方法によるADの検出精度は、プライマリケア医で61%、専門の医師で73%だったといいます。

低用量アスピリンは、インフルエンザの妊婦の血管炎症を治療し、胎盤への血流を改善させる可能性があるそうです。豪州などの研究チームが医学誌Frontiers in Immunologyに、マウスを使った研究の成果を発表しました。
妊娠中にインフルエンザにかかると、大動脈や血管に炎症を引き起こす「妊娠高血圧腎症」に似た状態に陥るリスクがあります。そこでチームは、妊娠高血圧腎症の予防に使われる「低用量アスピリン」に着目し、妊娠マウスを使って調査を行いました。
A型のインフルエンザウイルスに感染したマウスは、そうでないマウスに比べて胎児の血液に供給される酸素が少なく、血管の発達も悪かったそうです。しかし、低用量アスピリンを毎日投与したマウスは炎症が少なく、胎児の発達や生まれた子どもの生存率が向上したといいます。
ヒトでの臨床試験はまだ行われていませんが、妊娠中の低用量アスピリンの服用は安全であるとの認識が一般的です。

ビタミンB2(リボフラビン)とビタミンB7(ビオチン)がパーキンソン病(PD)の治療に役立つ可能性があることを腸内細菌叢(腸内フローラ)の解析から発見したと、名古屋大学の研究チームが医学誌npj Parkinson’s Diseaseに発表しました。
チームは、全ての遺伝物質を解析するショットガンメタゲノムという手法を用いて、日本や米国を含む5カ国のPD患者から採取した便を分析。PDと診断された患者は、ビタミンB2とB7の合成に関与する腸内細菌の遺伝子が減少していたそうです。
ビタミンB2とB7には、PDなどでみられる神経炎症を抑制する抗炎症作用があります。さらにこの二つのビタミンは、炎症を引き起こす毒素が血流に入るのを防ぐ腸管バリア機能を維持する「短鎖脂肪酸(SCFA)」と「ポリアミン」の産生や働きにも関与するといいます。
PD患者の便中代謝産物を調べたところ、SCFAとポリアミンが減少していることも示されたとのことです。

パーキンソン病は、神経伝達物質「ドパミン」を産生するドパミン神経細胞が失われる病気です。米国の研究チームが、ヒト人工多能性幹細胞(ヒトiPS細胞)由来の、ドパミン神経細胞に分化する手前の前駆細胞を使った新たな細胞治療について、サルの実験で安全性と実行可能性を確かめたと、医学誌Journal of Neurosurgeryに発表しました。
チームはカニクイザル6匹の脳に、ヒトiPS細胞由来のドパミン神経前駆細胞を注入したそうです。MRI技術を活用して、特定の領域に正確に細胞を移植したといいます。
Medical Xpressによると、移植から7日後と30日後に組織を採取して分析したところ、5匹の脳で移植細胞が生き続けていたとのこと。さらに、周囲の細胞と接続するために若い神経細胞が放出するタンパク質の存在も確認されたといいます。
この結果を受け、4月から臨床試験が行われているそうです。

米食品医薬品局(FDA)が7月29日、ガーダントヘルス社が開発した血液による大腸がん検査「Shield」を承認したそうです。米NBC Newsなどが報じました。Shieldは腫瘍から血液中に放出される特有のDNAを測定することで大腸がんを検出します。
米国の研究チームが今年3月、米医学誌New England Journal of Medicineに、約8000人を対象に行ったShieldの研究結果を発表しています。それによると、Shieldの大腸がん検出の感度は約83%だそうです。
ただ、腫瘍由来のDNAは進行した大腸がんから多く放出されるため、Shieldが最も効果を発揮するのはその段階のがんの検出だといいます。実際、3月に発表された研究結果でも、初期ポリープは13%しか検出されなかったとのこと。
なお、Shieldの結果だけでは大腸がんの診断はできず、陽性が出た場合は内視鏡による精密検査が推奨されるそうです。

米国の研究チームが、新型コロナウイルス感染症後の後遺症の一つとして知られる「筋肉の疲労」について、そのメカニズムの一端を明らかにしたと、科学誌Science Immunologyに発表しました。
チームはショウジョウバエとマウスを使って、炎症を起こした脳内のニューロン(神経細胞)が、どのようにして筋肉の機能不全を引き起こすのかを調査しました。その結果、まず、脳内でコロナ関連のタンパク質が見つかったショウジョウバエやマウスは、運動機能が低下することが分かったそうです。
そして、炎症によってヒトのニューロンが放出するサイトカイン「インターロイキン-6」に相当するタンパク質が、ショウジョウバエとマウスにも存在することを確認したといいます。
このタンパク質が血流に乗って筋肉に到達すると、「JAK-STAT」と呼ばれるシグナル伝達経路(細胞内に情報を伝える経路)が活性化し、筋肉組織のミトコンドリアが作り出すエネルギーの量が減少して機能不全を起こすとのことです。

動物性食品を一切取らない「ヴィーガン食」は人を若返らせる可能性があるそうです。
米国の研究チームが、成人の一卵性の双子21組を対象に8週間の調査を実施。双子の片方は肉や卵、乳製品を含む食事を、もう片方はヴィーガン食を取ったといいます。チームは、「調査開始時」「4週目」「8週目」の3回、参加者の血液から「DNAメチル化」レベルを測定し、生物学的年齢を予測しました。
DNAメチル化は、メチル基という分子がDNAにくっついて遺伝子がタンパク質を作るのを抑えてしまう現象です。このレベルの上昇が、老化と関連していることが知られています。
調査の結果、ヴィーガン食を取った人だけ生物学的年齢が若返ることが確認されたそうです。心臓、ホルモン、肝臓、炎症、代謝のそれぞれの年齢も若返ったといいます。ただ、ヴィーガン食群は対照群より体重が平均2kg多く減っており、このことが「若返り」に影響している可能性もあるとのこと。論文は医学誌BMC Medicineに掲載さました。

新型の帯状疱疹ワクチンは、認知症のリスクを低下させる可能性があるそうです。英国の研究チームが、医学誌Nature medicineに研究成果を発表しました。
チームは、グラクソ・スミスクライン(GSK)が開発した新型の帯状疱疹用の不活化ワクチン「Shingrix(シングリックス)」を接種した10万人を、旧型の帯状疱疹用の生ワクチン「Zostavax(ゾスタバックス)」を接種した群と比較したそうです。その結果、6年にわたる追跡期間において、シングリックス群はゾスタバックス群に比べて認知症と診断されるのが平均164日遅くなることが示されたそうです。なお、こうした効果は女性の方が顕著にみられたといいます。
英BBCによると、英国では「65歳になる人」「70~79歳の人」「免疫不全がある50歳以上の人」を対象に帯状疱疹ワクチンが無料で提供されており、旧型ワクチンから新型のシングリックスに置き換えが進んでいるそうです。

従来のPSA検査よりも優れた結果が得られる前立腺がんの検査が、世界的に普及するかもしれません。スウェーデンで開発された前立腺がん検出のための血液検査「Stockholm3(ストックホルム3)」について、幅広い人種に有効であることが示されたと、スウェーデンと米国のチームが医学誌journal of clinical oncologyに発表しました。
この検査は血液中のタンパク質と遺伝子マーカーを組み合わせたもので、白人における有効性が示されていました。チームは、前立腺がんの疑いで生体検査が必要と判断された複数の人種の男性2000人を調査。16%がアジア人、24%がアフリカ系アメリカ人、14%がラテン系アメリカ人、46%が白人アメリカ人だったといいます。
その結果、ストックホルム3は、前立腺がんの検出において優れており、不要な生検を45%減らせることが明らかになりました。人種間における有効性の違いも認められなかったとのことです。

シンガポールの研究チームが、自身や他の細胞を興奮させるために細胞が放出するタンパク質「サイトカイン」の一つを阻害すると、寿命や健康寿命が延びることをマウスの実験で明らかにしたそうです。英科学誌Natureに成果を発表しました。
チームは、老化に関わると考えられているサイトカインの一つ「インターロイキン11(IL-11)」に着目。「遺伝子操作でIL-11産生を阻害したマウス」と「抗IL-11薬を投与したマウス」を使って調査を行ったそうです。その結果、両方ともがんや腫瘍による死亡が減少し、慢性的な炎症や代謝の低下などといった老化に関連する疾患が少ないことが分かったといいます。
また、平均寿命は、遺伝子操作マウスで24.9%延長し、生後75週(ヒトの55歳に相当)の時にIL-11を投与したマウスはオスが22.5%、メスは25%、それぞれ延長することが明らかになったとのことです。

DNA(デオキシリボ核酸)の構成要素である「デオキシリボース(糖)」が、「男性型脱毛症(AGA)」の治療に有効な可能性があるそうです。英国などの研究チームが、デオキシリボースを使ったジェルクリームを開発し、マウスの実験で効果を確かめたと、科学誌Frontiers in Pharmacologyに発表しました。
チームは開発したジェルを、背中の毛を除去したオスのAGAモデルマウスに、20日間にわたって毎日塗布したそうです。すると、薬剤を含まないジェルを塗布したマウスに比べて新たな毛包が多く形成され、結果的に80~90%の毛がしっかりと再生したといいます。この発毛効果は、市販の発毛剤「ミノキシジル」を塗布したマウスと同等だったとのことです。
デオキシリボースが発毛を促す理由は分かっていませんが、ジェルによる治療部位の周辺で血管と皮膚細胞が増加していることが確認されたそうです。

何らかの健康問題で業務効率が落ちている状態を「プレゼンティーズム」と呼びます。大阪大学と東京大学の研究チームが、その主な要因を明らかにしたと、医学誌に論文を発表しました。
チームは、健康な労働者56人に対して2週間の調査を実施。就業時間中の心身の状態に関する自覚症状の程度と、その日のパフォーマンスについての終業時の自己評価を分析しました。また、睡眠時間を計測し、日中の作業効率との関連性も調べました。その結果、「日中の抑うつ気分」「肩凝り」「前日の睡眠時間」がプレゼンティーズムに影響を与える主要因であることが分かりました。
論文の筆頭執筆者で、東京大学大学院博士課程の諏訪かおりさんは「気軽かつ日常的にできる『ながら運動』」や「あいさつや立ち話程度の、職場でのちょっとしたコミュニケーション」がプレゼンティーズムの改善に有効だと話しています。(マイナビRESIDENT)

初期アルツハイマー病(AD)における神経細胞(ニューロン)の機能障害に、オリゴデンドロサイトという非神経細胞が重要な役割を果たしていることが分かったそうです。英国の研究チームが科学誌PLoS Biologyに論文を発表しました。
オリゴデンドロサイトは、中枢神経を構成するニューロン以外の細胞「グリア細胞」の一つで、ニューロンの長い突起部分に巻き付くミエリンを形成します。チームは、このオリゴデンドロサイトがADに関連するタンパク質「アミロイドベータ(Aβ)」を産生することを発見したそうです。これは、Aβを産生するのはニューロンだけだとするこれまでの定説を覆す結果です。
ADマウスを使った実験では、オリゴデンドロサイトにおけるAβ産生を阻害することで、ニューロンの異常な過活性が抑制されることが示されたといいます。ADの有望な治療戦略につながる可能性があります。

米国などの研究チームが、減量に有効な食物繊維を明らかにしたとして、科学誌Journal of Nutritionに論文を発表しました。
チームは、高脂肪食摂取マウスに対してさまざまな食物繊維を補給する調査を実施しました。その結果、「ベータグルカン(β-グルカン)」を補給させたマウスだけが、18週間以内に体重と体脂肪が減少することが分かったそうです。また、このマウスでのみ、減量に関連するとされる腸内細菌Ileibacteriumが増加することも示されました。
さらに、β-グルカンを補給させたマウスの腸内では、食物繊維の代謝産物である酪酸の濃度が上昇することも判明。酪酸はインスリン分泌を促すホルモンGLP-1の放出を誘発することで知られています。糖尿病や肥満症の治療に使われる「オゼンピック」などの薬剤はこのGLP-1を模倣して作られており、β-グルカンがオゼンピックと似た効果を持つ可能性が明らかになりました。β-グルカンは、きのこや大麦、オーツ麦などに多く含まれています。

たった1滴の血液から、さまざまな病気のリスクを知ることができるかもしれません。英国などの研究チームが、4万人の血漿タンパク質と健康記録のデータを分析して明らかにした結果を医学誌Nature Medicineに発表しました。
チームは3000種類のタンパク質の中から各疾患を予測するのに最も重要な5~20種類のタンパク質の「シグネチャー(配列特徴)」を突き止めたといいます。そして、こうしたシグネチャーから、多発性骨髄腫、非ホジキンリンパ腫、運動ニューロン疾患、肺線維症、拡張型心筋症などといった67疾患の発症リスクを予測できることを明らかにしました。
タンパク質を使った予測モデルは、血球数やコレステロールなどの標準的な臨床データに基づく予測モデルに比べて高い精度を発揮したとのことです。

米国で5月以降、リステリア菌による集団食中毒が発生しているそうです。米疾病対策センター(CDC)によると、今月19日時点で、12州で合計28人がリステリア菌感染で入院し、イリノイ州とニュージャージー州ではそれぞれ1人が死亡しました。
当局が患者18人に聞き取り調査をしたところ、16人がスーパーマーケットなどのデリカウンターでスライスされた加工肉を食べていました。患者の多くは、デリでスライスされた「ターキー(七面鳥)」や「レバーヴルスト(レバーペーストを詰めたソーセージ)」を食べていたそうです。
軽い症状だけで回復する人がいる一方で、高齢者や免疫系の弱い人は重症化することがあるといいます。また、妊婦が感染すると胎児に全身感染を引き起こし、早流産などの危険があるとのこと。

米疾病対策センター(CDC)は19日、コロラド州の養鶏場で6人目の鳥インフルエンザウイルスH5N1型の感染者を確認したと発表しました。これまでの5人の感染者と同様、鳥インフルエンザの感染が広がった養鶏場で、家禽の殺処分に従事していたそうです。
感染が確認された6人は、結膜炎や呼吸器感染症に関連する症状が出ているものの、いずれも軽症だといいます。患者の1人から採取したウイルスを遺伝子解析した結果、5月に乳牛からの感染が確認されたミシガン州の1例目の症例と密接な関係があることが分かったといいます。
また、抗ウイルス薬耐性に関連する変異は起きていないほか、ヒトに感染しやすくなったりヒトの間で感染が広がったりするような変異も見つかっていないとのことです。CDCは、今のところ一般市民への健康リスクは低いままだとみています。

インド南部ケララ州で14歳の少年がニパウイルス感染症で死亡し、同州保健当局が警戒アラートを出したそうです。
英BBCによると、当局は少年と接触した人を隔離した上で検査を行っています。そのうち60人以上が「感染高リスク」と判断されたとのことです。また、当局は少年の地元住人に、公共の場でのマスク着用や入院患者との面会見合わせなどの対策を講じるよう求めたといいます。
ニパウイルス感染症は、オオコウモリやブタなどからヒトに感染する人獣共通感染症です。汚染された食品や感染者との接触でうつることがあります。初期症状として、発熱、頭痛、筋肉痛、嘔吐、のどの痛みが現れ、その後脳炎や肺炎などを発症する人もいます。治療薬やワクチンはなく、致死率は40~90%といわれています。同州は、ニパのリスクが世界で最も高い地域の一つとされているそうです。

血液の凝固を防ぐために使う「ヘパリン(ヘパリン類似物質)」が、コブラ毒の解毒剤として使える可能性があるそうです。豪州などの研究チームが医学誌Science Translational Medicineに発表しました。
チームは、コブラ毒が組織の壊死を引き起こすのに必要な遺伝子を調査。ヒトや動物の細胞の表面に存在する分子、「ヘパラン硫酸」と「ヘパリン」がコブラ毒による壊死に関連していることを明らかにしました。これらは構造が似ており、コブラ毒はどちらにも結合することができるそうです。そのため、コブラにかまれた部位にヘパリン(類似物質)を「おとり」として投与することで、コブラ毒が結合して毒素が中和されるといいます。マウスの実験では組織損傷が軽減されることが示されたとのこと。
コブラを含めたヘビにかまれることで、世界中で1年間に13.8万人が死亡し、40万人が長期的な傷や障害を負っているそうです。

麻酔薬が人の意識を失わせる仕組みは、はっきりとは分かっていません。米国の研究チームが、全身麻酔などに使われる麻酔薬「プロポフォール」について、そのメカニズムの一端を明らかにしたと、科学誌Neuronに発表しました。
チームは、サルにプロポフォールを1時間投与し、「視覚」「音声処理」「空間認識」「実行機能」に関与する脳の4領域における電子記録を分析。さらに、周囲からの刺激(感覚入力)などに対する脳の反応も数値化したといいます。
通常、神経活動はなんらかの刺激(入力)を受けて急増し、すぐに制御を取り戻して過度の興奮を防ぐそうです。しかし、プロポフォールを投与すると、サルが意識を失うまで過度の興奮状態が増大し続けることが分かったといいます。薬が神経細胞の活動を抑制することで、脳内のネットワークが不安定になり、意識を失ってしまうことが示されたとのことです。

大気汚染が健康に与える影響は、私たちが考えているよりも深刻なようです。
インドなどの研究チームが、デリー首都圏などの10大都市で微小粒子状物質「PM2.5」の濃度を調査し、2008~19年に年間3万3000人以上が死亡した可能性があることが分かったそうです。また、インドの大気汚染について調べた以前の研究では、大都市に住む子どもは、肥満やぜんそくと診断される割合が高いことも明らかになっています。
PM2.5に暴露すると、細胞の成長や増殖に関わるEGFR遺伝子に変異が生じ、肺がんのリスクが高まるという英国の研究チームによる報告もあります。また、PM2.5は大気汚染物質の二酸化窒素(NO2)と連携して、肺深部の細胞に損傷を与える可能性があるそうです。(マイナビRESIDENT)

排便の頻度は健康に長期的な影響を及ぼす可能性があるそうです。米国の研究チームが、医学誌Cell Reports Medicineに論文を発表しました。
チームは、健康な成人1400人の血液や便などの検体から参加者の健康状態を調べたそうです。その結果、排便の頻度は1日1~2回が理想的であることが明らかになったといいます。そして、慢性的な便秘(排便が週2回以下)は腎臓の、下痢(排便が1日4回以上)は肝臓の、それぞれ機能低下に関連することも分かったそうです。
通常、腸内細菌は便中の食物繊維を餌にしています。しかし、なんらかの原因で食物繊維が不足すると、代わりに腸粘液層のタンパク質を食べてしまうそうです。こうしたタンパク質由来の有毒な代謝物が、腎臓や肝臓の機能低下に関連する可能性が指摘されています。

自閉症の兄や姉を持つ子どもは自身も自閉症と診断される可能性が高くなることを明らかにしたと、米国などの研究チームが医学誌Pediatricsに発表しました。
チームは、自閉症の兄か姉のいる幼児1605人のデータを分析しました。その結果、3歳の時点で幼児本人が自閉症と診断される割合は20.2%だったとのことです。また、家族内で最初の自閉症児が女児だった場合は、それが男児だった場合に比べて、もう1人自閉症児が生まれる可能性が50%高くなることが分かったといいます。
下の子が自閉症と診断される可能性は、自閉症の兄姉が複数いる場合は37%で、自閉症の兄姉が1人だけだった場合は21%だったといいます。調査対象の男児は、本人が自閉症と診断される可能性は25%だったのに対し、女児は13%の確率だったとのことです。

国連は11日、『国連世界人口推計2024版』を公表しました。2024年の世界人口は約82億人で、80年代半ばに103億人まで増加してピークを迎え、その後、今世紀の終わりには102億人に減少すると予測しています。
各国で出生率が低下していることなどから、世界人口のピークがこれまでの予想より早まる見通しです。世界の半数以上の国・地域で、女性1人当たりの平均出生児数が2.1(人口を維持するために必要な水準)を下回っているといいます。
また、24年の時点で中国や日本を含む63カ国・地域ですでに人口のピークに達しており、これらの国々の人口は今後30年間で14%減少する見込みとのことです。ブラジルやベトナムなどの48カ国・地域は25~54年、インドやインドネシア、ナイジェリア、米国など126カ国・地域は今世紀後半にそれぞれピークが予測されています。

生物学的な性別「性(sex)」と本人が自認する性別「ジェンダー(gender)」は、それぞれ異なる脳の領域のネットワーク(機能的結合)に影響を与えることが分かったそうです。米国などの研究チームが、国内の子ども4800人のデータを分析した結果を科学誌Science Advancesに発表しました。
研究の結果、「性」の違いは主に運動、視覚、制御、感情などをつかさどる大脳辺縁系のネットワークに関連し、「ジェンダー」が関連するネットワークは脳全体に広く分布していることが分かったといいます。このことから、性やジェンダーによる影響が、脳関連疾患(精神疾患)の発症傾向の違いにつながる可能性が指摘されています。
これまで生物医学の研究は、性に焦点を当てて行われてきたといいます。今回の成果は、ジェンダーについても考慮することの重要性を浮き彫りにしました。

レーザーによる視力矯正手術である「レーシック」や「PRK」を受けた後に、長引く目の痛みを訴える人がいるそうです。米国の研究チームが、痛みが出るリスクがある人を予測する方法を開発したと、科学誌Journal of Proteome Researchに発表しました。
チームは、両目にレーシックかPRKの手術を受ける患者を対象に調査を実施しました。術後3カ月の時点で、10段階で3以上の痛みを訴えた患者16人と痛みを訴えなかった患者32人の涙を分析したそうです。
その結果、涙の中に存在する2748種類のタンパク質のうち、目の痛みを訴えた患者において83種類のタンパク質レベルが変化することが明らかになったといいます。そして、このうち三つまたは四つのタンパク質を解析するコンピューターモデルを作って調べたところ、術後の長引く痛みが出る人を効果的に予測することができたといいます。

米コロラド州保健当局は14日、州北東部の養鶏場の労働者5人に鳥インフルエンザウイルスH5N1型が感染したことを確認したと発表しました。5人はいずれも鳥インフルの感染が広がった養鶏場で家禽の殺処分に従事していたそうです。感染した鳥との接触によってウイルスがうつったとみられます。
米疾病対策センター(CDC)によると、結膜炎のほか、発熱、悪寒、せき、のどの痛み、鼻水といった典型的なインフルエンザの症状が出ているもののいずれも軽症です。CDCは、現状では一般市民への感染リスクは低いとみていますが、リスク評価を変えるような遺伝子変異がないかどうかを調べているそうです。
米国では今年に入ってから、H5N1に感染した乳牛から4人が感染したことが確認されています。CDCは感染動物との接触による感染リスクが浮き彫りになったと注意を呼びかけています。

幅広い腸内微生物に着目することで、子どもの自閉スペクトラム症(ASD)を高い精度で診断できる可能性があるという研究成果を、香港の研究チームが科学誌Nature Microbiologyに発表しました。
これまでASDの研究は、腸内細菌の構成との関連に焦点が当てられてきました。チームは今回、中国に住む1~13歳の男女1627人の糞便サンプルについて、古細菌(アーキア)や真菌、ウイルスといった細菌以外の腸内微生物にも焦点を当てて分析(メタゲノム解析)を行ったそうです。
食事や薬物、併存疾患などの要因(交絡因子)を調整した結果、ASDの子どもにおいて▽古細菌14種類▽細菌51種類▽真菌7種類▽ウイルス18種類▽微生物遺伝子27種類▽代謝経路12種類――が変化していることが明らかになったといいます。これらを基に機械学習モデルを作成したところ、高い精度でASDを特定できたとのことです。

ダイエットには、「断続的断食(IF)」と「タンパク質ペーシング(P)」を組み合わせた「IF-P食事法」が効果的なようです。米国の研究チームが科学誌Nature Communicationsに論文を発表しました。
「IF」は食べ物の摂取を1日の決まった時間枠内に制限する食事法で、「P」はタンパク質の摂取を1日の中で分散する食事法です。チームは、太り過ぎまたは肥満の41人を、IF-P食事法を組み込んだカロリー制限食を摂取した群と地中海式のカロリー制限食を摂取した群に分けて8週間の調査を実施しました。
その結果、IF-P食事法群の方が、痩せやすい体質に関連する腸内細菌が増加し、体重減少に関連する血中タンパク質や脂肪を分解するアミノ酸のレベルが上昇することが明らかになったそうです。また、IF-P食事法群の方が、腸内細菌叢の多様性が増大し、胃腸症状や内臓脂肪が少なくなることも示されたといいます。

「適度な飲酒は健康に良い」「いや、酒は飲まないに越したことはない」。どちらの意見も耳にします。実際のところどうなんでしょう。
「適度な飲酒は認知症リスクを抑制する可能性がある」という研究結果を、韓国の研究チームが報告しています。缶ビール1本程度の酒を1日1杯程度飲む習慣がある人は、飲酒しない人に比べて、7~8年後に認知症を発症するリスクが21%低かったそうです。
一方で、英国の研究チームは「適度な飲酒は健康に良い」との説を覆す研究結果を発表。ビール、シードル(リンゴ酒)、蒸留酒の摂取量が、英国の健康ガイドラインで推奨されている上限より少ない人でも、心血管疾患で入院するリスクが高かったといいます。
そして、禁酒の効果を侮ってはいけないようです。英プリマス大学の専門家によると、脂肪肝は2~3週間禁酒すると正常な状態に戻るといいます。(マイナビRESIDENT)

米ニューヨーク大学(NYU)は、植え込み型補助人工心臓を装着した状態でブタの腎臓移植を受けた女性が7日に死亡したと発表したそうです。
米CNNによると、女性は4月12日に、拒絶反応を防ぐために遺伝子改変したブタの腎臓の移植手術を受けました。女性は心不全と透析が必要な末期の腎臓病を患っていたため、通常の臓器移植については対象外だったそうです。
ブタの腎臓を治療目的で人に移植するのは世界2例目で、人工心臓を装着した患者へのブタの腎臓の移植は初のことです。拒絶反応を抑えるために、女性には免疫細胞が訓練を受ける臓器であるブタの胸腺も一緒に移植されたといいます。
しかし、血流の悪化でブタの腎臓が機能せず、5月29日に摘出手術を受けていました。女性の死亡を受け、移植手術を行ったNYU のチームは「医学や外科、そして異種臓器移植分野への女性の貢献は計り知れない」という声明を発表したとのことです。
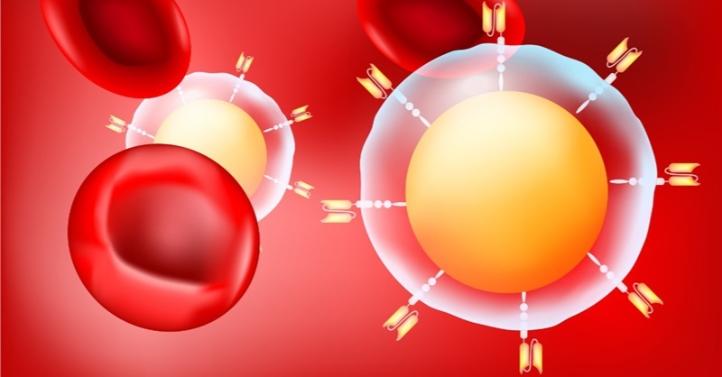
自己免疫疾患の全身性エリテマトーデス(SLE)の患者を世界で初めてCAR-T細胞療法で治療したと、ドイツの研究チームが医学誌The Lancetに発表しました。
患者は当時15歳の少女で、SLEの急激な悪化によって一生入院生活を送らなければならない状態だったそうです。医師があらゆる手を尽くしたにもかかわらず、「ループス腎炎」によって腎臓機能は著しく低下し、人工透析が不可欠だったといいます。
チームは最後の手段として2023年6月、血液がんの治療に使われるCAR-T細胞療法を実施。SLEに関与する自己反応性B細胞を破壊するために、少女自身のT細胞を遺伝子改変したものを投与したそうです。
治療3週間目から改善が認められ、徐々に全ての症状が消えていったといいます。治療によって正常なB細胞も破壊されたため、感染症予防のために毎月1回、抗体の投与を受けていますが、透析の必要もなく、少女は通常の生活を送っているとのことです。

がんになる前の状態(前がん状態)の子宮頸がんを尿から診断する検査法が実現するかもしれません。早稲田大学などの研究チームが、子宮頸がんの原因となる「ヒトパピローマウイルス(HPV)」の極微量のタンパク質を検出する「超高感度タンパク質測定法」を開発したと、学術誌Microorganismsに発表しました。
チームは、感染するとがん発症のリスクが高いHPV16型について、がん発症に関わるE7タンパク質を患者の尿から検出することに成功したそうです。子宮頸がんの前段階にある患者45人のうちHPV16かその関連型が陽性だった人の尿を使ってこの検査を試したところ、軽度異形成(CIN1)患者の80%、中等度異形成(CIN2)患者の71%、高度異形成(CIN3)患者の38%――でそれぞれE7タンパク質が検出されました。
この検査が実用化されれば、検診のハードルが大きく下がり、子宮頸がん撲滅への道が開かれます。

認知機能の維持に最も悪影響を与える生活習慣は喫煙だそうです。英国の研究チームが、欧州14カ国で認知機能に問題のない50歳以上の男女3万2000人を対象に10年にわたる追跡調査を実施し、科学誌Nature Communicationsに論文を発表しました。
チームは、喫煙の有無、週1回以上の運動、週1回以上の家族や友人との関わり、飲酒の有無(男性は1日2杯以上、女性は1日1杯以上)の生活習慣ごとに参加者を分類し、記憶力と言語の流ちょうさのテストで認知機能を評価して分析したといいます。その結果、喫煙が認知機能の低下を速める最も重要な要素であることが明らかになったそうです。
喫煙の習慣がある人は、非喫煙者に比べて認知機能を評価するスコアが最大85%も低くなったといいます。ただし、喫煙者であっても他の三つの生活習慣がすべて健康的だった場合、認知機能の低下は非喫煙者と同程度に抑えられたとのことです。

韓国南西部の南原市で、給食のキムチが原因とみられる集団食中毒が発生したようです。英BBCによると、地元当局は2日、ノロウイルスによる食中毒の症例を確認。その後、6日午後までに患者の数は1024人に達したといいます。
患者は市内24の学校に在籍する生徒や職員で、嘔吐や下痢、腹痛を訴えているそうです。当局によると、これらの学校に給食として納品されていたキムチの一部からノロウイルスが検出されたといいます。このキムチを製造した会社の名前は公表されていませんが、市はこの会社の全製品を対象に、製造・販売を一時的に停止する措置を講じたとのことです。すでに出荷された製品については、自主回収が進んでいるといいます。
ノロウイルスは非常に感染力が強く、感染者がウイルスに汚染された手で触れたトイレの洗浄レバーなどからもうつります。通常は発症から1~2日で回復しますが、人によっては重症化することもあります。

「利き手」や「利き目」は、何かに影響を与えるのでしょうか。英国の研究チームが、さまざまな年代や人種の男女1600人を対象に調査を実施し、その結果を科学誌Scientific Reportsに発表しました。
利き手の「強さ」は人によって偏りがあるといいます。チームは、ペグボードを使って色を合わせる課題を参加者に行ってもらいました。その結果、利き手への偏りが軽度~中程度の人の方が、偏りが強い人よりも正確性が高いことが分かったそうです。利き手への極端な偏りはタスク遂行における柔軟性を制限する可能性が示されました。
また、参加者の53%が「利き手が右、利き目は左」で、逆の組み合わせ(利き手が左、利き目が右)はわずか12%だったといいます。他者と関わるために必要なスキル(ソーシャルスキル)を調べたところ、「逆の組み合わせ」の群は他の群に比べて評価スコアが優位に低かったそうです。さらに、この群は自閉症や注意欠陥多動性障害(ADHD)を自己申告する割合が4倍高かったとのことです。

11月に大統領選を控える米国で、現職バイデン氏の高齢不安が高まっていることをCNNが報じています。
先日行われたトランプ前大統領との大統領選討論会では、バイデン氏が支離滅裂でまとまりのない発言をする様子などが物議を醸したそうです。こうした様子を見た複数の脳の専門家らは、バイデン氏は認知障害と運動障害の詳しい検査を受け、結果を公表するべきだと考えているといいます。
バイデン氏の健康問題を巡っては、2月に主治医らが「職務遂行に適している」と評価した報告書を公表していました。しかし、その報告書には認知検査に関する言及はありませんでした。
ホワイトハウスによると、バイデン氏は討論会当日、風邪などの理由で体調が悪かったそうです。なお主治医らは、バイデン氏が認知検査を受けて結果を公表する必要は「ない」としているといいます。

2型糖尿病治療薬「オゼンピック」や肥満症治療薬「ウゴービ」として知られるGLP-1受容体作動薬「セマグルチド」を使うと、失明につながる「非動脈炎性前部虚血性視神経症(NAION)」の発症リスクが高まる可能性があるそうです。
米国の研究チームが、NAIONではない1万6800人のデータから、糖尿病または肥満(過体重を含む)がある1700人に着目。セマグルチドを処方された糖尿病患者200人のうち17人が36カ月以内にNAIONを発症し、その割合はセマグルチドを処方されなかった群に比べて4倍も高かったそうです。肥満患者については、セマグルチドを処方された361人のうち20人がNAIONを発症。その割合は非セマグルチド群の7倍だったといいます。
ただ、糖尿病や肥満自体がNAIONリスクを高める要素でもあるため、セマグルチドとNAIONの関連を裏付けるためにはさらなる調査が必要とのことです。
チームは論文を医学誌JAMA Ophthalmologyに発表しました。

インドでは、大気汚染によって多くの人が死亡しているそうです。インドなどの研究チームが、ニューデリーやムンバイをはじめとする10大都市で、呼吸器や循環器の病気、がんを引き起こすとされる微小粒子状物質「PM2.5」の濃度を調査。WHO(世界保健機関)が推奨する年平均値(1立方メートル当たり15μg)を超えるPM2.5への曝露が原因で、2008~19年にかけて年間3万3000人以上が死亡した可能性があることが分かりました。これは、同じ期間にこれらの都市で死亡した人の7.2%に当たるといいます。なかでも首都ニューデリーでは、年間1万2000人以上が大気汚染関連で死亡しており、その割合は全死亡の11.5%に相当します。インドは現在、PM2.5の環境基準値をWHOの推奨値の4倍に当たる1立方メートル当たり60μgとしているそうです。医学誌The Lancet Planetary Healthに発表した論文です。

米コロラド州保健当局は3日、乳牛の間で流行している鳥インフルエンザウイルスH5N1型について、州内でヒトへの感染が確認されたと発表しました。同州では初めてで、米国内では4例目です。コロラド州では、乳牛の4分の1以上が鳥インフルに感染していると報告されており、その数は他のどの州よりも多いといいます。今回感染が確認されたのは酪農従事者の男性で、鳥インフルが感染した乳牛に直接接触する機会があったそうです。男性の症状は結膜炎のみだといいます。感染が発覚してすぐに抗インフルエンザウイルス剤「オセルタミビル(タミフル)」を服用し、すでに回復しているとのことです。米疾病対策センター(CDC)は、一般市民の感染リスクは低いものの、感染した動物に接触する機会がある人は個人用保護具(PPE)を着用するなどの対策を講じる必要があるとしています。

健康に良いと思ってやっていることや習慣的に行っていることが、実は健康に悪影響を与えることがあるようです。中国などの研究チームは、多くの人が心臓の健康のために取っている魚油サプリメントが、逆に不整脈や脳卒中のリスクを高めることを明らかにしました。ベルギーの研究チームは、アルコール入りのマウスウオッシュを使うと口腔内細菌叢(口腔内フローラ)のバランスが崩れ、がんの発生に関わる細菌が口の中で増加することを発見。スウェーデンの研究チームは、タトゥー(入れ墨)が血液がんのリンパ腫の危険因子になることを報告しています。また、飛行機内でお酒を飲むと、心臓に大きな負担がかかることが、ドイツの研究チームの調査で明らかになりました。米国の研究チームはジャンクフードが不安を助長することを報告しています。マイナビRESIDENTの記事です。

きちんと準備をしたのに、試験で良い点数が取れなかったことはありませんか。もしかしたら、試験会場のせいかもしれません。豪州の研究チームが、2011~19年に国内の大学に在籍した学生1万5400人のデータを分析したそうです。その結果、天井が高い部屋で試験を受けると、想定よりも点数が低くなることが分かったというのです。具体的には体育館や広いホールなどが当てはまるといいます。なぜこのような結果が出るのかは不明とのこと。豪州では、効率化の観点からこうした広くて天井が高い場所で試験が行われることが多いそうです。試験を実施する側は、物理的な環境が学生の成績に及ぼす潜在的な影響を認識し、すべての学生に平等な機会が与えられるよう調整する必要があるようです。科学誌Journal of Environmental Scienceに発表した論文です。

米イーライリリー社は2日、開発したアルツハイマー病(AD)の治療薬「ドナネマブ(商品名キスンラ)」が米食品医薬品局(FDA)に承認されたと発表しました。ドナネマブは、ADの原因物質とされる脳内のアミロイドプラークを除去するよう設計されたモノクローナル抗体で、早期ADの進行を抑制する効果が期待できるといいます。最終段階の臨床試験では、ドナネマブを使用した群はプラセボ群に比べて1年半後のAD進行リスクが35%抑制されることが示されていました。まれではあるものの、患者の2%で重篤な有害事象が確認されており、3人がアミロイド関連画像異常(ARIA)を発症して死亡しています。AD向けモノクローナル抗体については、日本のエーザイと米バイオジェンが開発した「レカネマブ」がすでにFDAに承認されており、使用が開始されています。

フィンランドの研究チームが、「うつ病」についての不正確な情報が広まっており、患者が自身の本当の苦悩を把握することが難しくなっているという研究結果を医学誌Psychopathologyに発表しました。チームは、WHO(世界保健機関)やアメリカ精神医学会(APA)、イギリスの国民保健サービス(NHS)、有名大学など、英語を使う国際的な保健衛生団体がウェブサイトに公開しているうつ病に関する情報を分析。ほとんどの団体が、うつ病を「精神症状を引き起こす障害」として表現していることが明らかになったそうです。チームは、うつ病は症状を引き起こす「原因」ではなく、気分の落ち込みなどの症状がある状態だと指摘。このような表現が一般的になると、メンタルヘルス問題における本質の理解があいまいになってしまうため、誤った認識を強化することがないよう注意を払う必要があると強調しています。
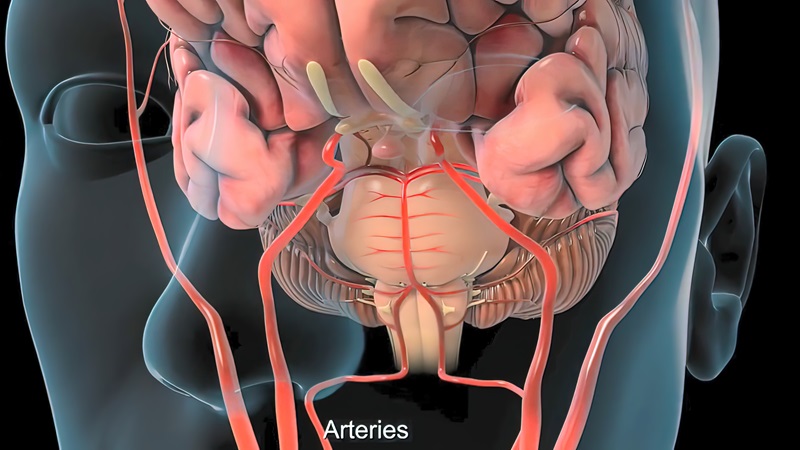
頭蓋骨の底(頭蓋底部)は脳幹や神経や血管が密集しています。その錐体先端部と呼ばれる部位にできる腫瘍の摘出は、工程が煩雑で時間がかかり、脳損傷や術後の合併症のリスクもあるため、脳外科手術の中で最も難しいといわれているそうです。大阪公立大学のチームが、従来の顕微鏡を使った手術法よりも安全で迅速な、内視鏡を使った低侵襲手術法(内視鏡下前経錐体到達法:内視鏡下ATPA)を開発し、医学誌Journal of Neurosurgeryに発表しました。チームは2022~23年に内視鏡下ATPAを用いて患者10人を手術し、2014~21年に従来法で手術を行った患者13人のデータと比較しました。すると、平均手術時間が410.9分から252.9分に短縮し、失血量は193 mlから90 mlに減少したことが判明。腫瘍切除率は従来法と同等で、神経機能の維持率は内視鏡下ATPAのほうが高いか従来法と同程度だったといいます。

先史時代のネアンデルタール人は、障害児を集団で養育していた可能性があるそうです。スペインの研究チームが、1989年にコバ・ネグラ洞窟遺跡で発掘されたネアンデルタール人の子どもの側頭骨を調査し、その結果を科学誌Science Advancesに発表しました。チームがマイクロCTスキャンで側頭骨を調べたところ、この子どもがダウン症で、難聴や平衡感覚の問題を抱えていたことが分かりました。そして、少なくとも6歳まで生きていたことが明らかになったそうです。1900年のダウン症の人の平均寿命が9年なので、この時代にダウン症児が6歳まで生きたのは驚くべきことだといいます。過酷な環境で生きていたネアンデルタール人が母親だけでこのダウン症児をケアしていたとは考えにくく、養育や介助において想定より広範囲に及ぶ集団から継続的なサポートを受けていた可能性があるとのことです。
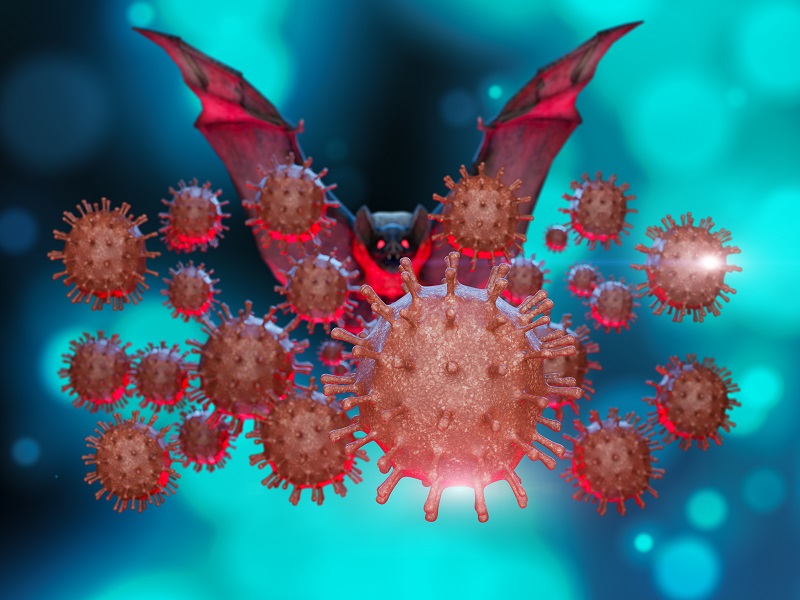
致死率の高い感染症「ニパウイルス(NiV)感染症」について、治療薬の開発が進んでいるようです。NiV感染症はコウモリが媒介する1990年代に現れた新興の人獣共通感染症です。感染動物の唾液や排泄物で汚染された食品などからヒトに感染し、呼吸器障害や脳炎などの症状が出て、40~90%が死に至ります。南アジアや東南アジアのヒトや動物の間で流行が繰り返されているそうです。米国の研究チームがNiVを中和するモノクローナル抗体「hu1F5」を開発し、動物実験で有望な結果が得られたとして、医学誌Science Translational Medicineに発表しました。hu1F5は、感染に関わるF糖タンパク質を標的にしているといいます。感染から1日たったハムスターにこの抗体を投与したところ、100%が生存。さらに感染から5日たったアフリカミドリザル6匹に投与した実験でも、6匹全てが生き残ったとのことです。

幼いころの記憶が大人になってもずっと残っているはなぜでしょうか。米国などの研究チームが、記憶力の良し悪しに関連するタンパク質「KIBRA」と記憶形成に重要な役割を果たす酵素(タンパク質キナーゼ)「Mzeta(PKMzeta)」の相互作用に着目した研究で、その理由を明らかにしたそうです。マウスの実験で、長期記憶が形成されるシナプス(神経細胞間の結合部)において、KIBRAが「接着剤」の役割を担うことが分かったといいます。記憶形成の際に活性化するシナプスにKIBRAが選択的に付着し、それが目印になってPKMzetaがそのシナプスに引き寄せられるそうです。こうして強化されたシナプスにまたKIBRAがくっつくというサイクルが繰り返され、記憶が長期間保持されるといいます。KIBRAとPKMzetaの結合を切ると、古い記憶が消去されることも確認されたとのこと。 論文は科学誌Science Advancesに掲載されました。

麻酔薬として開発され、点滴や経鼻薬などでうつ病治療にも使われている「ケタミン」。ニュージーランドなどの研究チームがケタミンの錠剤の治験(第2相)を行い、薬物治療抵抗性のうつ病患者にも有効な可能性があるとの結果が得られたとして、医学誌Nature Medicineに発表しました。チームは、過去に平均4種類の抗うつ薬を試したことがあるうつ病患者270人に試験を実施。ケタミン錠を服用した人の半数以上で、うつ病が寛解したそうです。一方で、プラセボ群の70%が13週間後に再発したといいます。このケタミン錠は肝臓で分解されるのに10時間もかかるため、極端な高揚感や解離などといったケタミンによくみられる幻覚的な副作用は報告されませんでした。オピオイドのような乱用リスクを懸念して、ケタミンのうつ病への使用に慎重な姿勢を貫く精神科医もいますが、この錠剤が懸念を和らげる可能性があります。

感染症の「迅速検査」は、どのタイミングで行うのが適切なのでしょうか。米国の研究チームが、迅速検査の効果や精度を評価する計算モデルを開発し、新型コロナやインフルエンザ、RSウイルス(RSV)感染症などについて調査を行ったそうです。その結果、新型コロナのオミクロン株については症状が出た直後に迅速検査を使うと、実際は感染しているのに陰性の結果が出る「偽陰性」が92%に上ることが分かりました。症状が出てから2日たつと偽陰性の確率は70%に下がるといいます。さらに3日目に2回目の検査を行えば、偽陰性率は66%にまで低下するそうです。一方、インフルエンザウイルスやRSVは急速に増殖するため、症状が出た後にすぐに検査をしても、きちんと陽性が出ることが多いといいます。科学誌Science Advancesに発表した論文です。

スイスの研究チームが、他者にインフルエンザをうつしやすい人がいる理由を明らかにしたと、科学誌Journal of Virologyに発表しました。チームはまず、くしゃみの飛沫に似た液滴を使って調査を行いました。インフルエンザウイルスのみを含んだ液滴は室内に30分間放置すると、ウイルスが99.9%死滅したそうです。一方、ウイルスに加えて気道に常在する細菌を含んだ液滴では、感染力のあるウイルス量が同時点で100倍も多く、その後何時間もウイルスが生存していたといいます。次に、浮遊微粒子の形態で調査したところ、ウイルスのみの粒子では15分でウイルスの感染力が消滅しました。一方、細菌を含有する粒子では1時間後も感染力のあるウイルスが存在していたとのことです。特に黄色ブドウ球菌と肺炎球菌が、このような「ウイルス保護効果」を発揮したといいます。

アトピー性皮膚炎の一般的な治療方法は、皮膚を清潔にしてうるおいを保つことと、炎症を抑える「ステロイド外用薬」の塗布です。近年、塗り薬以外のアトピー性皮膚炎の新たな治療薬の開発が進んでいます。生物から産生されるタンパク質などの物質を応用して作られる「生物学的製剤」の登場により、既存の治療薬では効果のない患者などにも治療の選択肢が広がりました。生物学的製剤の特徴は、炎症やかゆみが発生する根本的な原因にアプローチできることです。次々と登場している治療薬の中で、最も新しいのは、イーライリリーが2024年5月に発売した生物学的製剤「イブグリース(一般名レブリキズマブ)」です。初めは2週間に1回注射で投与しますが、4週目以降は症状に応じて1カ月に1回に切り替えることもできるため、患者の負担を軽減できるといいます。マイナビRESIDENTの記事です。

欧州連合(EU)当局は、欧州15カ国向けの4000万回分以上の鳥インフルエンザワクチンを確保することを決めたそうです。ロイター通信が25日に報じました。まず最大66.5万回分のワクチンを調達し、最長4年にわたって追加で4000万回分のワクチンを確保する契約を豪CSL Seqirus社と結んだといいます。ワクチンは最初にフィンランドに向けて出荷され、養鶏場の労働者や獣医師など鳥インフル感染のリスクの高い人が接種の対象になるそうです。鳥インフルエンザウイルス(H5N1型)の感染が米国の乳牛の間で広がっており、今年4月以降、乳牛に接触した酪農従事者3人に鳥インフルが感染したことが確認されています。欧州疾病予防管理センター(ECDC)によると、6月初旬時点で、EUではヒトや牛の感染例は確認されていません。

米疾病対策センター(CDC)は25日、蚊が媒介する感染症「デング熱」について、世界の患者数が過去最多を記録したとして警戒を呼びかけました。気候変動の影響もあり、デング熱感染が世界的に急増しています。南北アメリカでは既に6月の時点で、年間のデング熱患者数の最多記録を更新した国もあるといいます。こうした状況を受けて、WHO(世界保健機関)が昨年12月に、カリブ海にある米自治領プエルトリコが今年3月にそれぞれ非常事態を宣言しています。米国本土でも、今年の感染者数が前年の同じ期間に比べて3倍に増加したそうです。そのほとんどが海外を旅行した際に感染したケースだといいます。CDCは医師らに対し、症状をよく把握したうえで、渡航歴を確認し、必要に応じてデング熱検査を検討するよう呼びかけました。

人工知能(AI)を使って、がんを早期に診断できるようになる日が来るかもしれません。英国の研究チームが、がんの発達に深く関わると考えられている「DNAメチル化」に着目しました。メチル基という分子がDNA(の塩基)にくっつくことで、遺伝子がタンパク質を作るのを抑えてしまう現象です。チームは機械学習とディープラーニングを併用し、がん発生の初期にみられるDNAメチル化のパターンを解析するAIモデルを開発したといいます。このAIで組織検体を調べたところ、健康な組織と、乳がんや肝臓がん、肺がん、前立腺がんなど13種類のがんを98.2%の精度で識別することができたそうです。実際の臨床でこのAIを活用するためには、追加の訓練やより多様な検体を使った試験が必要だといいます。科学誌Biology Methods and Protocolsに発表した論文です。

気候変動は脳の健康に悪影響を及ぼすようです。英国の研究チームが、1968~2023年に世界で発表された332の論文を分析し、医学誌The Lancet Neurologyに結果を発表しました。脳卒中、片頭痛、アルツハイマー病、てんかんなど19種類の脳神経疾患と、不安症(不安障害)やうつ病、統合失調症などの精神疾患について気候変動の影響を検討しました。その結果、高温や熱波で、脳卒中による入院や障害、死亡のリスクが上昇することが分かったそうです。また、認知症の人は環境の変化に適応する力が弱いために異常気象の被害を受けやすく、一日の中の気温差が激しい日や高温の日があると、認知症関連の入院や死亡が増加することも明らかになりました。精神疾患の発生やそれによる入院や死亡のリスクについても、高温や気温差などとの関連が認められたといいます。
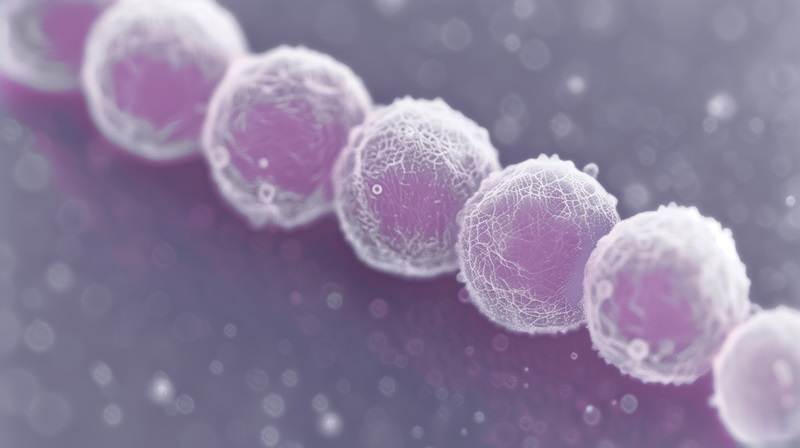
劇症型溶血性レンサ球菌感染症(STSS)の患者が日本で急増しており、このことについて米NBC Newsが報じています。STSSは、「人食いバクテリア」とも呼ばれる特殊な溶血性連鎖球菌(溶連菌)によって組織が破壊される感染症で、患者の3割が死に至るといわれています。国立感染症研究所によると、今年1月以降に確認された日本国内のSTSS患者は1019人で、これまで過去最多だった昨年の941人をすでに上回りました。患者急増の原因は分かっていません。こうした日本の状況が、近年米国でも懸念されているSTSSの感染拡大の原因をめぐる謎に、改めて関心が寄せられるきっかけになっているといいます。

双極性障害を患った人は、心の健康を取り戻すことができるのでしょうか。カナダの研究チームが、双極性障害の既往歴がある555人と双極性障害の既往歴がない2万530人のカナダ人のデータを分析。双極性障害の既往歴がある人のうち、43%が双極性障害の症状が改善したそうです。さらに、23.5%が、過去 1 年間に双極性障害、うつ病、薬物依存症、自殺念慮などの精神疾患にかかっていないなどの条件を満たした「心が完全に健康な状態」であると確認されたそうです。また、信頼できる友人の存在が、心の健康を取り戻す上で最も影響力のある要因だったといいます。双極性障害の既往歴がない人については、4分の3が心が完全に健康な状態だったとのこと。論文は医学誌Journal of Affective Disorders Reportsに掲載されました。

米食品医薬品局(FDA)は20日、米サレプタ・セラピューティクス社が開発したデュシェンヌ型筋ジストロフィー(DMD)における初の遺伝子治療薬「ELEVIDYS(エレビジス)」について、対象範囲を拡大すると発表しました。FDAは昨年6月、対象をDMD遺伝子の変異が確認された4~5歳の小児患者に限り、エレビジスを迅速承認していました。しかし今回、DMD遺伝子変異をもつ歩行可能な4歳以上の患者を対象に通常承認することを決定しました。さらに、同様の遺伝子変異をもつ歩行不能な4歳以上の患者に対する使用についても、迅速承認を出したといいます。エレビジスは、筋肉の構造を保つために必要なタンパク質「ジストロフィン」を作る遺伝子を体内に送り込む薬です。薬の投与は1回で完了します。

2型糖尿病治療薬「マンジャロ」や肥満症治療薬「ゼップバウンド」の商品名で知られる米製薬大手イーライリリーの「チルゼパチド」が、「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」の治療に有効な可能性があるそうです。米国の研究チームが、肥満およびSASと診断された患者469人を対象に調査を実施。鼻に付けたマスクから圧力をかけた空気を送り込んで気道を広げるSASの一般的な治療法「持続陽圧呼吸療法(CPAP)」を行っているかどうかにかかわらず、チルゼパチドを週1回投与された人は、睡眠時の無呼吸や低呼吸が50~60%減ることが分かったそうです。また、チルゼパチドを使った患者は、睡眠の質の向上や睡眠障害の減少を報告しているとのことです。論文は米医学誌New England Journal of Medicineに掲載されました。

前立腺肥大症の治療に一般的に使われる既存薬で、「レビー小体型認知症(DLB)」の発症リスクを抑制できるかもしれません。DLBはアルツハイマー病に次いで2番目に多い認知症で、レビー小体というタンパク質が脳に異常に蓄積して神経細胞が減少する病気です。米国の研究チームが、前立腺肥大症治療薬の「テラゾシン」「ドキサゾシン」「アルフゾシン」が脳細胞のエネルギー産生に必要な酵素を活性化することで細胞死を阻害する可能性があることに着目。3薬のいずれかを使用する男性12万6313人を、別のタイプの薬(タムスロシン、5α還元酵素阻害剤)を使用する人と比較しました。その結果、テラゾシンなどの3薬を使用する群は3年以内のDLB発症リスクが、タムスロシンの群と比べて40%、5α還元酵素阻害剤の群と比べて37%、それぞれ低いことが明らかになったといいます。医学誌Neurologyに発表した論文です。
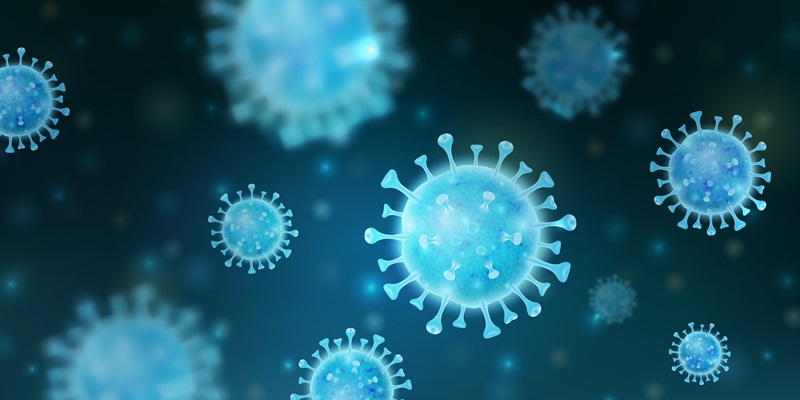
英国の研究チームが、新型コロナウイルスに感染しない人がいる理由を明らかにしたと、英科学誌Natureに発表しました。チームは、新型コロナの感染歴のない健康な成人16人に対して鼻から新型コロナウイルスを入れた上で、臓器の細胞を一個一個分離して解析する「シングルセル(単一細胞)解析」を用いて免疫応答を詳しく調査しました。その結果、ウイルスをすぐに排除できた人は、典型的な広域の免疫応答は示さず、代わりにこれまで知られていなかった自然免疫応答を引き起こすことが分かったそうです。また、ウイルスへの暴露前にHLA-DQA2と呼ばれる遺伝子の活性レベルが高いと、感染が持続しにくくなることも明らかになったといいます。一方で、参加者の中で新型コロナを発症した6人は、血液中の免疫応答は速かったものの、鼻腔内の免疫応答が遅いためにウイルスがそこに感染してしまったとのことです。

英国とドイツの研究チームが、パーキンソン病(PD)の早期診断を可能にする血液検査を開発したそうです。PDは手足がふるえたり思うように体が動かせなくなったりする神経変性疾患です。チームはまず、PD患者とそうでない人から採取した血液を使い、PD発症の予測に有用な八つのタンパク質を特定しました。そして、これを基に人工知能(AI)を使って脳疾患リスクのある患者72人の血液を分析し、10年間の追跡調査を行ったそうです。その結果、16人のPD発症を正確に予測することができたといいます。症状が出る7年も前にPD発症を予測できたケースもあったそうです。さらに、特定されたタンパク質が、PD治療に役立つ可能性もあるとのことです。論文は科学誌Nature Communicationsに掲載されました。

米国の研究チームが、「リンパ球性脈絡髄膜炎ウイルス(LCMV)」を使ったがんのウイルス療法を開発し、免疫不全マウスにも有効なことを確認したそうです。マウスのメラノーマや大腸がんなどを縮小させて生存率を高めただけでなく、がんの予防効果も認められたとのこと。ウイルス療法は、がん細胞のみで増殖するように遺伝子改変したウイルスを使って、がんを破壊する治療法です。免疫細胞が破壊された細胞のタンパク質を「敵」と認識し、がん細胞を攻撃する効果もあります。ただ、免疫抑制剤を使用している患者は、この攻撃力が弱まる可能性があるために使用できないことが課題になっています。現在は単純ヘルペス1型ウイルスなどが使われています。論文は医学誌Journal of Clinical Investigationに掲載されました。

韓国政府の医学部増員計画を巡り政府と医師らの対立が続いている問題で、国内の診療所が抗議行動の一環として18日に一斉に休診したそうです。AP通信によると、保健福祉省は「一斉休診」に参加したのは国内に3万6000ある民間医療施設の約4%だと発表しているとのことです。韓国当局は、一斉休診への参加を当局に通知した医師らに、「職場復帰命令」を出したといいます。韓国の法律では、命令に従わなかった医師は免許停止などの処分を受ける可能性があります。今回の一斉休診は、17日からソウル大学病院の教授ら数百人が無期限の休診に入ったことに続くもの。今後ストがさらに拡大する恐れもあるといいます。韓国の医療現場では多くの手術や治療が中止されるなど混乱が続いているとのことです。

デンマーク食品当局は、韓国から輸入された激辛即席麺について、急性中毒のリスクがあるとして回収を指示したそうです。AP通信によると、対象となる製品はソウルに本社を置く韓国最大の食品メーカー三養食品が製造し、世界中で販売されている3種類。デンマーク当局は、これらの激辛麺にはカプサイシンが過剰に含まれており、これが神経毒や健康上のリスクになりうるとしているそうです。症状は灼熱感や吐き気、嘔吐、高血圧などです。デンマークでは、子どもや若者がSNS上で激辛麺のスープを飲んで競い合っており、こうした背景が今回の規制につながったといいます。昨年9月には、先天性心疾患などを持っていた米国の14歳の少年が、激辛チップスを食べるSNSの企画に参加して死亡しています。

ジャンクフードのような高脂肪食は腸内細菌の組成を変化させ、脳内物質に影響を与えて不安を助長するようです。米国の研究チームが青年期のラットを2群に分けて調査。一方には脂肪を45%含む「高脂肪食」を、もう一方には脂肪分が約11%の「通常食」をそれぞれ9週間与えました。その結果、高脂肪食群は通常食群に比べて腸内細菌の多様性が低いことが分かったそうです。また、高脂肪食群の脳内では、神経伝達物質「セロトニン」の生成などに関連する三つの遺伝子が多く発現することも判明。セロトニンは精神を安定させることで知られていますが、高脂肪食群で多く発現していた遺伝子の影響で特定の領域の神経細胞が活性化すると、不安行動を引き起こすことがあるそうです。科学誌Biological Researchに発表した論文です。

非ホルモン性の男性用避妊薬の開発が進んでいるそうです。米国の研究チームが「CDD-2807」と名付けた避妊薬を開発し、マウスに21日間投与して調べた結果を米科学誌Scienceに発表しました。研究の結果、適切な用量を投与するとマウスが不妊になることが示されたそうです。不妊になったマウスの精巣を調べたところ、精子数が少なく、精子の運動率も低く、受精するために精子の動きが激しく変化する「超活性化」の割合も低かったといいます。なお、薬を止めると、53日ほどでマウスは再び繁殖能力を取り戻し、可逆的であることも分かったとのこと。この薬はSTK33と呼ばれるタンパク質を阻害します。STK33遺伝子は精巣に多く存在し、欠損すると精子に欠陥が生じて不妊につながることがマウスとヒトで確認されているといいます。

2001年9月11日の米同時多発テロ事件で、ニューヨークの世界貿易センター(WTC)が崩壊した際に発生した粉塵が、脳に悪影響を及ぼしている可能性があるようです。米国の研究チームが、WTCやその周辺で対応に当たった、消防士や建築関係者など「レスポンダー」と呼ばれる5010人を調査しました。91.3%が男性で、調査を開始した14年時点の平均年齢は53歳だったそうです。22年までに228人が、65歳未満で認知症(若年性認知症)を発症したといいます。調査の結果、レスポンダーとして15週間以上働いた場合、65歳より前に認知症を発症するリスクが高くなることが分かったそうです。粉塵への暴露レベルが上がるごとに、リスクは42%増加することも明らかになったとのことです。医学誌JAMA Network Openに発表した論文です。

非小細胞肺がん(NSCLC)の中には、既存の免疫チェックポイント阻害薬に反応しないものがあります。米国の研究チームが、そんなNSCLCの治療を可能にするかもしれないナノ粒子を開発したそうです。チームは80人以上の肺がん患者の組織を検査し、がん細胞の表面にあるタンパク質を特定したといいます。そして、抗がん剤に加え、これまで治療の標的としてきたタンパク質PD-L1だけでなくCD47にも結合する抗体を搭載したナノ粒子を開発しました。2種類のタンパク質を標的にしているので、ナノ粒子ががん細胞に結合できる可能性が高まります。マウスを使ってナノ粒子の効果を調べたところ、重篤な副作用なしに肺がん細胞が縮小することが確認されたといいます。論文は科学誌Science Advancesに掲載されました。

米国の研究チームが、アルツハイマー病(AD)患者に使用する一般的な二つの薬の併用で、患者の5年生存率が延びる可能性があるという研究成果を発表しました。チームはADと診断された1万2744人について、アチルコリンエステラーゼ阻害薬「ドネペジル」を使用▽NMDA受容体拮抗薬「メマンチン」を使用▽二つの薬を併用▽薬物未治療――の4群に分けて比較しました。ドネペジル、メマンチン、二つの薬の併用は、AD患者に対する最も一般的な治療法だといいます。分析の結果、「併用」患者に比べて、全ての患者の5年後の死亡率が高いことが判明。特に、薬剤未治療の患者と比較すると、併用患者の5年生存の可能性が6.4%上昇したといいます。論文は医学誌Communications Medicineに掲載されました。

米食品医薬品局(FDA)は2023年11月、主に難治性の血液がん患者に使われる「CAR-T細胞療法(キメラ抗原受容体T細胞療法)」が、逆にがんを発生させる「二次がん」のリスクを高めるという警告を出しました。米国の研究チームが米医学誌New England Journal of Medicineに、これを否定する研究結果を発表しました。チームは、2016~24年にCAR-T細胞療法を受けた患者724人について、平均3年間の追跡調査を実施。その結果、二次血液がんの発生率は6.5%だったことが明らかになったそうです。なお、二次がんで死亡したのは1人だけだったといいます。その症例を詳しく分析したところ、二次がんの原因はCAR-T細胞そのものではなく、CAR-T細胞療法の影響による免疫抑制である可能性が示されたといいます。

近ごろソーシャルメディアを賑わせている「オゼンピック・フェイス」という言葉を知っていますか? これまで2型糖尿病治療に使われていたGLP-1受容体作動薬「オゼンピック(一般名セマグルチド)」などを減量目的で使用することで、頬がこけたり、目がくぼんだり、皮膚がたるんだりすることを指す言葉です。ただし、顔の変化がGLP-1受容体作動薬の副作用なのか、単に急激な減量の影響なのかは現時点では明らかになっていないといいます。専門家はこうした言葉が独り歩きしていることに懸念を示しています。体重が急激に減ると、頬や目、顎、口の周りの余分な皮膚がたるんで、しわができることが知られており、顔が老けて見えることも以前の研究で分かっているそうです。Science Alertが報じました。

血液中のコレステロールを下げる物質「スタチン」を発見した東京農工大学栄誉教授の遠藤章さんが、5日に90歳で亡くなりました。英公共放送BBCが遠藤さんの死を報じています。遠藤さんが1973年に青カビから発見したスタチンは、動脈硬化を治療するスタチン製剤の開発につながりました。BBCはスタチンを抗生物質ペニシリンに並ぶ発見とし、「心臓病や脳卒中のリスクを減らし、英国だけで毎年何千人もの命を救った」とその功績をたたえています。また、「(遠藤さんは)卓越した科学者。ここ数年で、これほど劇的な影響を与えた治療法はない。数百万人もの命を救う発見をした遠藤さんがノーベル賞を受賞できなかったことは残念だ」という英国心臓財団の責任者のコメントを紹介しています。

米国で今年3月から、鳥インフルエンザウイルスA(H5N1型)の感染が乳牛の間で流行しています。CDC(米疾病対策センター)によると6月9日の時点で、10州85の牛の群れで感染が確認され、感染牛と接触していた3人にH5N1が感染しました。2人は目の充血などの症状が出て、1人は上気道感染症の症状がありました。現状ではヒトに感染しやすく変異している様子はないそうです。ただ、米国の研究チームが、感染牛の乳には高濃度のウイルスが含まれており、マウスに飲ませると咽頭から感染が起きて全身感染を引き起こすことを明らかにしました。米国では、動物と人間の両方に対するH5N1用のmRNAワクチン開発が進んでいるそうです。マイナビRESIDENTの記事です。

米食品医薬品局(FDA)の諮問委員会は10日、イーライリリーのアルツハイマー病(AD)治療薬「Donanemab(ドナネマブ)」について、承認を推奨すると全会一致で決定しました。FDAは数週間以内に承認の可否を最終決定する見込みで、承認されればエーザイの「レカネマブ」に続くAD治療の選択肢となります。ドナネマブはAD関連のタンパク質アミロイドβを除去するモノクローナル抗体(抗アミロイド抗体医薬)です。委員会は、初期AD患者1736人を対象とした第3相試験のデータを基に、ドナネマブにADの進行を遅らせる効果があると結論付けました。FDAがこれまでに承認した抗アミロイド抗体医薬は二つです。しかし、バイオジェンのアデュカヌマブは今年1月に市場からの撤退を発表しています。

米モデルナ社は10日、mRNA技術を使って同社が開発した、新型コロナウイルスとインフルエンザウイルスの両方の感染を予防する混合ワクチン(mRNA-1083)について、第3相試験の結果を発表しました。3種類のインフルエンザウイルス株と新型コロナウイルスの変異株に対して、既存のワクチンを接種するよりも高い免疫応答を誘発することが確認されたといいます。同社はまず、65歳以上の高齢者4000人を対象に調査を実施しました。その結果、mRNA-1083を接種した群は、従来のコロナワクチンとインフルワクチンを同時に接種した群に比べてコロナとインフルに対する強力な免疫応答を示すことが分かったそうです。さらに、50~64歳の成人4000人を対象とした調査でも、同様の結果が示されたといいます。

体内に取り込まれたマイクロプラスチックが、近年の世界的な出生率低下に関与している可能性があるようです。中国の研究チームが、東部の済南に住む健康な成人男性36人から採取した精液を分析したところ、全ての検体からマイクロプラスチックが検出されたといいます。済南市は、汚染地域とされている最寄りの海岸線から約180km離れた場所にあり、プラスチック製造施設もないそうです。検出されたマイクロプラスチックは8種類で、なかでも梱包材として使われるポリスチレンが最も多く見つかりました。また、精液中にポリ塩化ビニルが含まれていると、精子の運動率が低くなることも分かったといいます。科学誌Science of the Total Environmentに発表した論文です。

精神科の介助犬を知っていますか? 精神障害のある人に対し、不安を和らげる癒し行動を取るように訓練された犬です。米国の研究チームが、心的外傷後ストレス障害(PTSD)を患う軍人や退役軍人にとって、QOL(生活の質)を改善する大きな助けになることを確認したそうです。チームは、介助犬とのマッチングを希望するPTSD治療中の軍人経験者156人を調査。81人のマッチングが成立し、介助犬と共に3カ月間生活したところ、介助犬待ちの71人に比べてPTSDの症状が軽く、うつや不安の症状も少なくなることが分かったそうです。また、PTSDと診断される確率も66%低くなることが明らかになったといいます。医学誌JAMA Network Openに発表した研究成果です。

勃起不全治療薬「シルデナフィル(商品名バイアグラ)」が、脳の小血管へのダメージによって起こる「血管性認知症」を抑制する可能性があるそうです。英国の研究チームが、軽い脳卒中を起こし、軽~中等度の小血管病の兆候を示した患者75人を対象に3週間の試験(二重盲検プラセボ対照試験)を実施。超音波とMRIの調査で、3週間シルデナフィルを使った人は、脳内の血流が増加し、脳血管の機能が改善することが示されました。脳梗塞の再発抑制のために使う抗血小板剤「シロスタゾール」との比較調査も行っており、両方とも、血液が血管に流れ込むときの抵抗(血管抵抗)を低下させることが判明。ただ、副作用はシルデナフィルの方が少なかったそうです。医学誌Circulation Researchに発表した論文です。

世界保健機関(WHO)は7日、インド旅行から帰国したオーストラリアの2歳の女児が鳥インフルエンザウイルスA(H5N1)に感染していたと発表しました。女児は2月12~29日までインドのコルカタ(旧カルカッタ)に滞在したそうです。2月25日に食欲不振や発熱などの症状が出たといいます。その後、発熱や咳、嘔吐のために2月28日にインドで診療を受け、解熱鎮痛薬のアセトアミノフェンを処方されたとそうで。3月1日にオーストラリアに帰国し、翌日から2週間以上入院して退院しました。症状悪化のために1週間は集中治療室に入ったとのことです。5月22日時点で、症状を訴えている濃厚接触者はいないといいます。女児にはインド滞在中に病人や病気の動物に接触した形跡はなく、感染経路は不明です。

英国の研究チームが、クローン病や潰瘍性大腸炎などの「炎症性腸疾患(IBD)」の原因を明らかにしたと、英科学誌Natureに発表しました。チームは、IBDとの関連が以前から指摘されていたゲノムの「遺伝子砂漠」と呼ばれる領域を調査したそうです。遺伝子砂漠とは遺伝子が存在しない非コード領域のことです。チームは、この領域の特定の部分が免疫細胞のマクロファージの中で活性化することを発見。これが遺伝子「ETS2」に働きかけ、マクロファージが活性化して炎症が促進することが分かったそうです。IBD患者の腸サンプルを使って、ETS2活性を間接的に抑えると思われる既存の薬(MEK阻害薬)の効果を調べたところ、炎症反応を抑制することが示されたといいます。

エナジードリンクは心臓発作を引き起こす可能性があるようです。米国の研究チームが、突然の心停止から生還した患者144人のデータを分析したところ、5%に当たる7人が心停止の直前にエナジードリンクを飲んでいたことが分かったそうです。1人分のエナジードリンクには80~300mgのカフェイン(紙コップ<8オンスカップ>1杯のコーヒーには100mg)のほか、タウリンやガラナエキスなどの刺激物が含まれているといいます。こうした物質は心停止につながる不整脈を誘発する可能性があります。研究者は、特に遺伝性心疾患をもつ人がエナジードリンクを飲む際はリスクを考慮するべきだと注意を呼びかけています。医学誌Heart Rhythmに発表した論文です。

遺伝子治療に関する研究成果が相次いで発表されています。中国、米国、英国からは、遺伝性難聴の子どもが、日常会話ができるレベルにまで聴力が改善したという報告が上がっています。遺伝性網膜疾患の患者14人に治験を実施した米国のチームもあり、11人の視力に改善が見られたそうです。単純ヘルペスウイルス1型(HSV-1)についても、米国のチームが有望な結果を報告。マウスの実験で、口腔感染したHSV-1の90%、性器感染したHSV-1の97%をそれぞれ除去することに成功したそうです。また、英国と米国では遺伝性血液疾患向けの、ゲノム編集技術CRISPRを使った治療法が2023年末に承認されています。マイナビRESIDENTの記事です。

鳥インフルエンザウイルスA(H5N1型)の感染が乳牛の間で広がっている米国で、動物と人間の両方に対するmRNAワクチンの研究が進んでいるそうです。米ペンシルベニア大学は、鳥インフル感染を抑制する牛用のmRNAワクチンを開発したといいます。マウスやフェレットを使った実験では、鳥インフルエンザウイルスに対する高レベルの抗体が産生されたそうです。来月実施予定の牛への試験で同様の結果が得られれば、牛からヒトへの伝染リスクを低減させることで、ヒトからヒトへの感染を抑えることが期待できます。一方、モデルナ社やファイザー社は、ヒト用の鳥インフルmRNAワクチンを開発し、既にヒトに接種する初期治験を実施済みとのことです。AP通信が報じました。

アルコールを含むマウスウオッシュを使うと、消化を助けたり口の健康を維持したりする口腔内細菌叢(口腔内フローラ)のバランスが崩れ、健康に悪影響を与える可能性があるそうです。ベルギーの研究チームが、男性と性行為をする男性の性感染症に関する研究の一環で、59人を調査。一般的なマウスウオッシュ「リステリン」を3カ月間毎日使うと、歯周病や大腸がん、食道がんなどに関連するとされる日和見感染菌「フソバクテリウム・ヌクレアタム」と「ストレプトコッカス・アンギノサス」が口腔内で増加することが分かったそうです。さらに、血圧の調整に重要な役割を果たす「アクチノバクテリア」が減少することも明らかになったといいます。科学誌Journal of Medical Microbiologyに掲載された論文です。
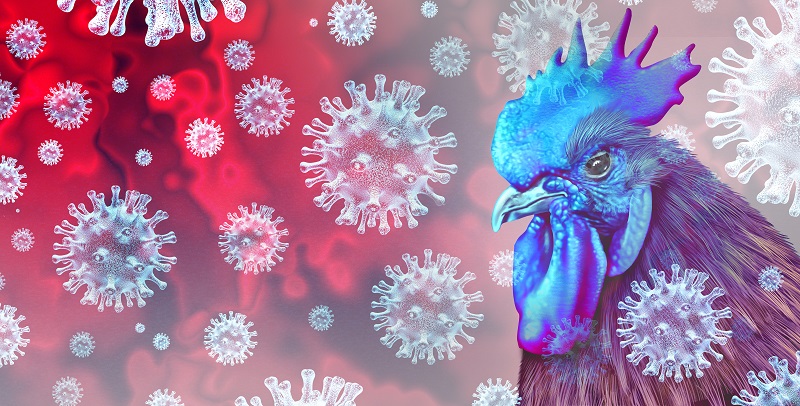
世界保健機関(WHO)は5日、鳥インフルエンザウイルスA(H5N2型)の感染者が世界で初めて確認されたと発表しました。感染者は59歳の男性で、4月24日に発熱や息切れ、下痢、吐き気、全身けん怠感の症状でメキシコシティの病院に入院し、同日死亡したそうです。メキシコでは今年3月、家禽の間でH5N2型の感染が確認されています。しかし、男性は家禽や他の動物との接触歴はなく、感染源は不明だといいます。男性は複数の基礎疾患を抱えており、4月17日に急性の症状が出た時には別の理由で3週間寝たきりの状態だったとのことです。男性と病院で接触した人や近隣住民が検査を受け、全員が陰性だったそうです。

腎移植は拒絶反応の一つである「抗体関連型拒絶反応(AMR)」が大きな課題となっています。オーストリアなどの研究チームがAMR治療薬「felzartamab」の第2相試験を行い、有望な結果を示したと発表しました。チームは、腎移植後にAMRと診断された患者22人に対して、felzartamabまたはプラセボを6カ月間投与して調査。felzartamabはAMRに対して安全かつ非常に有効であることが分かったそうです。felzartamabは細胞表面のタンパク質CD38を標的としたモノクローナル抗体で、当初は多発性骨髄腫の治療薬として開発されたそうです。心臓や肺、さらには遺伝子編集したブタの臓器移植の拒絶反応にも有効な可能性があるそうです。米医学誌New England Journal of Medicineに掲載された論文です。

若くて健康な人であっても、飛行機内での飲酒は控えた方がいいようです。ドイツの研究チームが、18~40歳の健康な成人48人を調査。寝る前に缶ビール2本分に相当するアルコールを摂取してから、飛行中の機内と同程度に気圧を低くした検査室で睡眠を取ると、参加者の酸素飽和度が平均85%に低下することが明らかになったそうです。そして、これを補うために心拍数は1分間に平均88回に上昇したといいます。一方、飲酒をしてから海抜ゼロ地点の気圧に相当する検査室で寝た人の酸素飽和度は平均95%、心拍数は平均77回だったといいます。日本呼吸医学会によると、酸素飽和度は96~99%が標準値。人間ドックでは、心拍数は1分間に45~85回が正常値とされているようです。医学誌Thoraxに発表した論文です。

動画投稿アプリ「TikTok(ティックトック)」に投稿された健康情報は信頼してもいいのでしょうか。米国の研究チームが、2023年11月15~16日にTikTokで視聴され、#sleephacks、 #sleephygiene、#sleeptipsのタグが付いた睡眠に関する人気の動画58本を調査したそうです。その結果、寝つきを良くしたり、睡眠の満足度を上げたり、日中の眠気を軽減させたりといった快眠につながる独自の35個のヒントが見つかったといいます。そして詳細な分析の結果、このうち33個が科学的に立証された根拠に基づいていることが明らかになったそうです。睡眠分野に関しては、コンテンツの制作者が医学的に適切な情報を提供している可能性が高いことが示されました。医学誌SLEEPに発表した論文です。

カナダの研究チームが、体内でアルコールを醸造してしまう珍しい「自動醸造症候群(ABS)」の症例を報告しました。腸内の細菌や真菌が炭水化物をエタノールに変えてしまい、酩酊状態になる病気です。患者はトロントに住む50歳の女性で、飲酒をしていないのに呼気からアルコールの臭いがし、気を失うこともあったといいます。女性は2年間で7回も救急外来を受診しましたが、医師らは女性の飲酒を疑うばかりでした。7回目の受診でようやくABSだと判明。この女性の場合、尿路感染症の治療で使った抗菌薬で善玉菌が死滅し、ABSを引き起こす真菌が腸を乗っ取ったといいます。ABSは抗真菌療法や低炭水化物食などによる長期の治療が必要だそうです。論文は医学誌Canadian Medical Association Journalに掲載されました。

米疾病対策センター(CDC)は5月30日、鳥インフルエンザウイルスH5N1型が乳牛の間で流行して以降、3例目の感染者がミシガン州で確認されたと発表しました。患者は酪農従事者で、咳などの上気道感染症と涙目の症状が報告されているといいます。これまで確認された他の2人(テキサス州で1人、ミシガン州で1人)の患者は、目の症状のみでした。3例に関連性はなく、全員がH5N1型が感染した牛と直接接触していることが分かっています。CDCは鳥インフルエンザウイルスがヒトからヒトへ感染している兆候はないとしています。今回の患者は抗ウイルス薬(タミフル)を投与され、呼吸器症状は改善したそうです。

米ニューヨーク大学は、ブタの腎臓移植を受けた世界で2例目の患者に対し、この腎臓を摘出する手術を行ったと発表しました。患者の女性は人工透析を受け、容体は安定しているといいます。移植したブタの腎臓は拒絶反応を防ぐために遺伝子編集されたものです。女性は4月に人工心臓とブタ腎臓の移植を受け、一時は順調に回復していました。しかし、人工心臓と新たな腎臓の両方を一度に管理するに当たり、特有の課題があったようです。女性の血圧は何度も低くなり過ぎてしまい、腎臓への血流が不十分になったとのことです。移植後わずか47日で腎臓を摘出せざるを得なくなりました。AP通信やCNNが報じました。

5月31日は世界保健機関(WHO)が定める「世界禁煙デー」です。そして、6月6日までの1週間を厚生労働省が「禁煙週間」と定めています。たばこが健康に与える悪影響については今でも新しい発見があり、各国から報告が上がっています。フランスの研究チームは、特定の病原体に対する強力な「適応免疫」の能力が喫煙によって下がり、禁煙してもなかなか回復しないことを明らかにしました。米国の研究チームは日常的に喫煙をしていた人は非喫煙者に比べて、認知機能に関わる部分を中心に脳が小さくなっていることを発見。喫煙は周囲の人にも悪影響を与え、心臓発作や子どもの近視を引き起こすことも明らかになっています。マイナビRESIDENTの記事です。

ザクロやイチゴなどに含まれる物質が、アルツハイマー病(AD)の進行を遅らせる可能性があるそうです。デンマークの研究チームが着目したのは、これらの果物に含まれるエラグ酸の腸内代謝物「ウロリチンA」です。チームがADマウスにウロリチンAを長期にわたって投与したところ、ADマウスの学習能力や記憶力、嗅覚が向上することが明らかになりました。ADなどの神経変性疾患は、損傷したミトコンドリアの蓄積が原因の一つと考えられているといいます。AD患者の脳は、炎症に関連するタンパク質「カテプシンZ」が過剰に活性化しており、これが損傷ミトコンドリアを除去する細胞の機能を妨げているとみられます。ウロリチンAは、カテプシンZの産生を抑制するといいます。医学誌Alzheimer’s & Dementiaに発表した論文です。

アレルギーの発症を恐れて、幼い子どもにピーナツを食べさせないようにすることは、間違っているそうです。英国の研究チームが、ピーナツアレルギーの治験に参加した子ども497人のデータを分析。幼年期から5歳までピーナツを定期的に摂取した群は、同じ期間にピーナツを避けた群に比べて、5歳時点のアレルギーリスクが81%低かったそうです。6歳以降は、子どもたちにピーナツを好きな時に好きな量を食べてもらい、追世紀調査を実施しました。その結果、5歳までピーナツを定期的に摂取していた群は、ピーナツを避けた群に比べて、12歳以降のアレルギーリスクも71%抑制されることが判明。幼い頃にできた耐性が、成長しても持続することが分かったとのこと。論文は医学誌NEJM Evidenceに掲載されました。

米国の研究チームが、早い時期に生命維持装置を外された外傷性脳損傷の患者の中には、装置を維持していれば改善していた人がいる可能性があるとの研究結果を発表しました。チームは、米国内の集中治療室で生命維持装置を付けた外傷性脳損傷患者のデータを分析。生命維持装置を数日で外された80人と外されなかった対照群を比較したといいます。その結果、生命維持装置を外された人の42%は、もし装置を維持していれば、脳損傷を負ってから6~12カ月後に生存または少なくとも部分的に改善した可能性が示されたといいます。負傷後すぐに患者の予後を予測するのは非常に困難であるようです。医学誌Journal of Neurotraumaに発表した論文です。

米疾病対策センター(CDC)は23日、2022年7月にサウスダコタ州で発生した「旋毛虫症」に関する詳細を公表しました。旋毛虫症は線虫の幼虫によって引き起こされる感染症です。狩猟した熊の肉を使ったケバブが原因で、6人が発症したそうです。熊肉は45日間冷凍保存してあったものを解凍し、ケバブは生焼け状態だったといいます。ケバブを食べたのは家族9人で、1週間後に当時29歳の男性が発熱や激しい筋肉痛に見舞われて入院しました。検査の結果、旋毛虫症であることが判明しました。その後、他の5人が発症し、発熱、頭痛、腹痛、下痢、筋肉痛、目の周りの腫れなどの症状が出たといいます。現在は全員回復しているそうです。

話せなくなった男性が、脳インプラントによって2カ国語を話せるようになったそうです。スペイン語を母国語とする男性は20歳の時に脳卒中を起こし、言葉の能力をほとんど失ったといいます。米国の研究チームが、男性に「ブレイン・コンピューター・インターフェース(BCI)」を埋め込み、スペイン語と英語の単語を頭の中で復唱する訓練を3年間実施。埋め込んだ電極が脳波を読み取り、そのデータにAI技術を適用することで、どちらの言語なのかを識別して言葉に変換することに成功したそうです。この装置は、男性が話そうとするのがスペイン語なのか英語なのかを88%の精度で判別でき、単語全体の解読の精度も75%に達したといいます。論文は科学誌Nature Biomedical Engineeringに掲載されました。

心臓の健康を保つために多くの人が取っている「魚油サプリメント」は、逆に心血管疾患のリスクを高める可能性があるそうです。魚油サプリに含まれるオメガ3脂肪酸は心臓保護の効果があるとされ、60歳以上の米国人の20%が摂取しているといいます。中国などの研究チームが、英国バイオバンクから抽出した40~69歳の参加者41万5000人を平均12年間追跡したデータを分析しました。その結果、心臓に問題のない人が魚油サプリを定期的に摂取すると、不整脈の一種である心房細動を発症するリスクが13%、脳卒中を発症するリスクが5%高くなることが分かったそうです。ただし、心臓に既往歴がある人には魚油サプリの効果が期待できる可能性があるといいます。医学誌BMJ Medicineに発表した研究成果です。
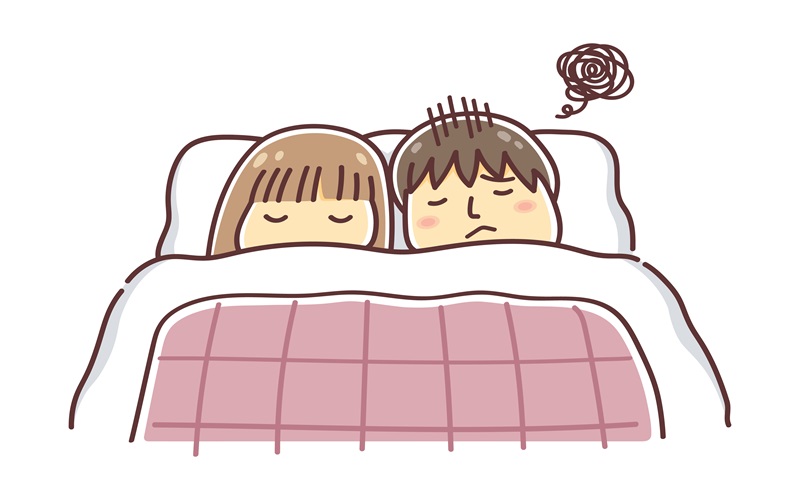
性交中の頭痛は、深刻な病気が原因の可能性があるそうです。性行為によって頭頚部の痛みが起こる「性行為に伴う一次性頭痛(PHASA)」は、1.0~1.6%の人が経験すると推定されているそうです。PHASAが起こる原因は明らかになっていません。ただし、片頭痛持ちの人は起こりやすく、高血圧や頭頸部の静脈の異常、静脈の狭窄なども関連していることがあるといいます。性交中の脳出血が原因で頭痛が起こることもあるそうです。また、特に50歳前後の男性の性交時頭痛は、脳動脈瘤のほか、脳梗塞につながることのある心臓の壁の穴「卵円孔開存」を疑う必要があり、検査を受けた方がいいとのことです。The Conversationの記事です。

タトゥー(入れ墨)は、血液のがん「リンパ腫」の危険因子になる可能性があるそうです。スウェーデンの研究チームが、1万1905人を対象に調査を実施。20~60歳でリンパ腫を患った人は2938人いたそうです。その中で1398人がアンケートに回答し、リンパ腫を患ったことのない対照群4193人と比較したといいます。タトゥーを入れていたのは、リンパ腫群が21%(289人)で、対照群が18%(735人)だったそうです。喫煙や年齢などを考慮した結果、タトゥーがある人のリンパ腫発症リスクは対照群より21%高くなることが示されました。タトゥーの大きさによってリスクが変わることはないとのことです。eClinicalMedicineに掲載された論文です。

鳥インフルエンザウイルス(H5N1型)が感染した牛の乳には高濃度のウイルスが含まれており、殺菌処理をせずに飲むと、ヒトも感染する危険があるそうです。米国の研究チームが、乳牛の間で感染が広がっているH5N1型に汚染された生乳をマウスに飲ませて調査。わずか1日で、マウスは毛の逆立ちや無気力などの典型的な感染の兆候を示したそうです。4日目にマウスを安楽死させて調べたところ、複数の臓器からウイルスが検出され、特に呼吸器でウイルスの量が高レベルでした。咽頭から感染が起きた可能性を示唆しており、所見はH5N1が哺乳類で引き起こす全身感染と一致するとのこと。感染動物の乳からH5N1が感染する危険があり、研究者は注意を呼びかけています。New England Journal of Medicineに発表した研究成果です。

米国では2022年に、毎日大麻を使う人の数が、毎日飲酒する人の数を初めて上回ったそうです。米国の研究チームが、薬物使用と健康に関する全国調査のデータを分析して明らかになりました。22年に「毎日」または「ほぼ毎日」大麻を使用していると報告した人は推定1770万人おり、同様の頻度で飲酒していると報告したのは1470万人だったそうです。一方、1992年に「ほぼ毎日」大麻を使用すると答えたのは100万人未満でした。最近の大麻使用者の40%は、「毎日」または「ほぼ毎日」大麻を使用する習慣があるといいます。論文はAddictionに掲載されました。なお、AP通信によると、米国では現在、半数近くの州で娯楽用大麻の使用が認められているそうです。また、大麻を頻繁に使う人は大麻依存症になりやすいといいます。

米マサチューセッツ州の病院が3月、重い腎臓病の62歳の男性患者にブタの腎臓を移植したと発表しました。男性は4月に退院したのですが、5月に死亡しました。死亡原因は明らかにされていません。どの国でも移植用臓器の提供数が不足しています。解決策として注目されているのが、「異種移植」です。冒頭の男性に加え、2人の患者にブタの心臓が移植され、別の1人の患者にブタの腎臓が移植されています。しかし、心臓を移植した患者は2人とも2カ月以内に死亡しています。異種移植はどうなっていくのでしょうか。ブタの腎臓を移植したサルが2年以上生存したという報告もあるので、「無理な話」ではないようにも思えます。マイナビRESIDENTの記事です。

米疾病対策センター(CDC)とミシガン州保健当局は22日、同州の酪農従事者に鳥インフルエンザウイルスA(H5N1)が感染したと発表しました。米国では乳牛の間で鳥インフルの感染が広がっており、感染した乳牛との接触が原因とみられるヒトへの感染が確認されたのは2例目です。この患者は鼻腔ぬぐい液の検査は陰性でしたが、目のぬぐい液で陽性が出たといいます。患者にみられたのは目の症状のみで、すでに回復しているそうです。テキサス州で4月に確認された1例目の患者も目の症状のみでした。CDCによると、正確なことは不明ですが、ウイルスに汚染された手や液体などから目に感染する可能性があるとのこと。なお、感染した牛の未殺菌の牛乳から、高レベルのウイルスが検出されているそうです。

アルツハイマー病(AD)の進行を抑制する新たな薬が、治験で有望な結果を示したようです。米国の研究チームが開発したこの薬(LM11A-31)は、ADに関連すると考えられているタンパク質のアミロイドβやタウを標的とした既存の薬とはメカニズムが異なるそうです。脳細胞の成長や生存、死といったさまざまなプロセスを制御する「P75神経栄養因子受容体(P75NTR)」を標的にし、脳細胞の生存や成長を促すといいます。治験(第2A相)は、カナダのチームなどの協力の下で、軽~中等度のAD患者242人を対象に26週間にわたって実施したとのこと。その結果、安全性と忍容性が確認されただけでなく、LM11A-31がADの進行を遅らせることも実証されたそうです。論文はNature Medicineに掲載されました。

インフルエンザウイルスの感染を予防する薬が実現するかもしれません。米国の研究チームが、インフルエンザA(H1N1)の感染を阻害する低分子「F0045(S)」を発見。この低分子は、ヘマグルチニンという細胞に侵入する際に必要なウイルス表面のタンパク質に結合するそうです。これにさまざまな調整を加えてスクリーニングを実施した結果、細胞培養実験でF0045(S)の200倍の抗ウイルス能力を示す無害な分子を発見したそうです。チームはこの分子を最適化し、さらに抗ウイルス効果が高い化合物を設計したといいます。次は、動物でこの化合物の効果を調べる予定とのことです。米国科学アカデミー紀要(PNAS)に発表した論文です。

世界保健機関(WHO)は21日、世界の性感染症(STI)に関する報告書を公表しました。世界中でSTIが増加しており、「大きな懸念(major concern)」としています。報告書によると、毎日15~49歳の男女計100万人以上が、クラミジア、淋病、梅毒、トリコモナス症のいずれかに新たに感染しているといいます。特に、2020年に710万人だった世界の新規の梅毒患者は、2022年には800万人に急増。妊娠中に母親から胎児に感染する先天梅毒の割合も増えているそうです。抗菌薬(抗生物質)に対して耐性をもつ淋病の症例が増えていることも深刻な問題の一つです。一方で、エイズウイルス(HIV)の新規感染者は減少傾向とのことです。

スイスの医療機器企業Onwardが開発した電気刺激装置は、脊髄損傷患者のQOL(生活の質)を大きく向上させるようです。脊髄が損傷した付近の皮膚に電極を貼り付け、電流を流す仕組みです。米国の研究チームが、首から下のまひに苦しむ脊髄損傷患者60人を対象に調査を実施。この装置を使用してリハビリを行ったところ、2カ月後には43人の手や腕の機能が改善したそうです。また、この治療を続けることによって、脳と手に新たな接続が生まれるため、装置を付けていないときにも効果が見られるようになるといいます。現在開発中の他の装置は脊髄に埋め込むための手術が必要ですが、この装置は非侵襲的であるために早期の実用化が期待できるとのことです。研究成果はNature Medicineに掲載されました。

米国の研究チームが、完全に機能する「血液脳関門(BBB)」を持つヒトのミニ脳の開発に成功したそうです。ヒトの脳の血管には、血液から脳内に有害な物質が入り込まないようにするためのバリア機能「BBB」があります。このBBBを持つミニ脳の作製は、世界中のどの研究機関も成功していなかったといいます。チームはヒト多能性幹細胞(hPSC)を使い、脳組織を模した「脳オルガノイド」と血管構造を模した「血管オルガノイド」を作製し、この二つを統合させたそうです。このミニ脳ができたことで、脳卒中、脳血管障害、脳腫瘍、アルツハイマー病、ハンチントン病、パーキンソン病など、広範な脳神経疾患の創薬や治療法開発が飛躍的に進歩する可能性があるとのこと。Cell Stem Cellに発表した論文です。

米国小児科学会(AAP)は20日、エイズウイルス(HIV)陽性者による授乳について、母親が処方薬を規定通り服用している限り、赤ちゃんに母乳を与えても差し支えないとする報告書を発表したそうです。APPは1980年代にHIVの流行が確認されて以降、HIV感染者の母乳育児を推奨しない方針を貫いていたとのことです。報告書によると、母親が抗レトロウイルス薬をきちんと服用することで、母乳から赤ちゃんにHIVが伝染するリスクは1%未満に抑制されるといいます。今回のAAPの方針変更で、HIV陽性者が母乳育児の選択を検討できる環境が広がることが期待されています。AP通信の記事です。

微小なプラスチック粒子「マイクロプラスチック」が、生殖機能に悪影響を及ぼしている可能性があるそうです。米国の研究チームが、イヌ47匹と平均35歳の男性23人の精巣組織を調査したところ、全ての検体からマイクロプラスチックが検出されたといいます。検出されたのは計12種類で、イヌもヒトも、ビニール袋やペットボトルに使われる「ポリエチレン(PE)」が最も多かったそうです。イヌについては配管などに使われるポリ塩化ビニル(PVC)が2番目に多く、精子との関係を調べたところ、PVCの濃度が高いと精子の数が少なくなることも明らかになりました。Medical Xpressの記事です。

米マサチューセッツ州に住む当時14歳の少年が昨年9月、激辛のトルティーヤチップスを食べた後に死亡した問題で、州当局は16日、唐辛子の辛み成分「カプサイシン」の過剰摂取による心肺停止が原因と発表したそうです。少年には心肥大と先天性心疾患があったとのこと。少年はこのチップスを食べることに挑戦するSNSの企画に参加したといいます。チップスは菓子メーカーPaqui(パキ)の製品で、世界一辛い唐辛子といわれる「キャロライナ・リーパー」と「ナガ・バイパー」で味付けされているそうです。専門家は、カプサイシンが基礎疾患のある若者などに及ぼす影響を詳しく調べる必要があると指摘しています。NBC Newsの記事です。

最新の新型コロナウイルスワクチンを定期的に接種すると、未知の変異株や新型コロナ以外のコロナウイルスにも有効な広域中和抗体が産生される可能性があるそうです。米国の研究チームが、パンデミック初期の従来株に対応したワクチンを接種した後、オミクロン株に対応したワクチンを追加接種したマウスやヒトの中和抗体を調査。従来株とオミクロン株の両方に交差反応するだけでなく、オミクロン株の亜系統やSARS(重症急性呼吸器症候群)の原因であるSARSコロナウイルスなども中和することができたといいます。MERS(中東呼吸器症候群)を引き起こすMERSコロナウイルスは中和できなかったとのこと。Medical Xpressの記事です。

韓国政府の医学部増員計画に反対する医師ら16人が、計画の差し止めを求めて申し立てを行い、ソウル高等裁判所は16日、この申し立てを却下したそうです。高裁は、この医師らをこの件に関して申し立てを行う資格がない「第三者」と表現。公共の福祉を守るため、増員は必要だと判断したようです。韓国政府は医師不足を解消するため、医学部の定員を2000人増やす計画を進めています。これに反発する研修医ら約1万2000人が、2月からストライキを続けています。政府はこれらの医師に対して免許を停止するとしていましたが、対話を進めるために措置を中止しているとのこと。AP通信の記事です。

手術を担当するチームの3分の1以上を女性医師が占めるような病院で治療を受けると、術後の転帰が良くなる傾向があるそうです。カナダの研究チームが、2009~19年に88カ所の病院で入院を伴う手術を受けた患者70万9899人のデータを分析。外科医や麻酔科医の35%以上を女性が占める病院は、これらの科の女性医師が少ない病院に比べて、手術から90日以内に患者が死亡したり重篤な合併症を発症したりするリスクが3%低くなることが分かったそうです。特に、外科医や麻酔科医として女性医師が直接的に手術に関与すると、こうしたリスクが低減したといいます。CBS Newsの記事です。

米国で鳥インフルエンザウイルスA(H5N1)の感染が乳牛の間で広がり、大きな問題になっています。感染した牛と接触していた酪農家の男性1人にもH5N1が感染したそうです。男性の症状は結膜炎で、呼吸器感染症に関連するものはなかったといいます。ウイルスに汚染された手で目をこすったことで感染した可能性が高いとのことです。男性は抗ウイルス薬(タミフル)を処方されて回復したそうです。H5N1はヒトに感染した場合に重篤な症状を引き起こすものが多いことが分かっています。世界保健機関(WHO)が監視と備えを強化するよう呼びかけています。マイナビRESIDENTの記事です。

ヒトに吸い込まれることで体内に侵入した新型コロナウイルスは、肺などの臓器だけでなく、目にも到達することが明らかになったそうです。米国の研究チームが、コロナウイルスがヒトに感染する際に必要な受容体を持つマウス(ヒト化マウス)で調査。目の網膜は、不要な物質を血管から通さない「血液網膜関門」によって感染などから守られています。しかしコロナウイルスは、血液網膜関門の細胞に感染することでこれを突破し、網膜で過剰な炎症反応を誘発することが分かったといいます。ウイルスの残骸が長期間残ると、網膜や視覚の機能が損なわれるリスクが高まるとのことです。Medical Xpressの記事です。

二日酔いが予防できるようになるかもしれません。スイスなどの研究チームが、乳タンパク質と金ナノ粒子から作ったジェルをマウスに与えて調査。その結果、ジェルを投与されたマウスは、アルコール摂取から30分以内に血中アルコール濃度が40%下がったそうです。5時間後には、アルコール濃度は50%以上低下したといいます。アルコールは胃や小腸から吸収され、肝臓で二日酔いの原因となる有害物質「アセトアルデヒド」に分解されます。その後、肝臓で毒性の弱い「酢酸」に分解され、体外に排出されます。このジェルは、腸内でアルコールを酢酸に分解する触媒として働くそうです。Science Alertの記事です。

新型コロナウイルスが感染しても、子どもは重症化しにくいことが分かっています。英国の研究チームが、その理由を明らかにしたそうです。チームは、12歳未満(子ども)、30~50歳(中年)、70歳超(高齢者)の三つの年齢層で、それぞれ健康な参加者から鼻の粘膜を採取して調査しました。これらに新型コロナウイルスを感染させ、3日後に顕微鏡で観察したといいます。その結果、子どもの上皮細胞はすぐにウイルスからの攻撃に防御反応を示し、ウイルス量が早く減少したそうです。一方で、中年の細胞ではこうした防御反応が顕著に起こらなかったといいます。さらに高齢者の細胞では、ウイルス量が増えてダメージが増大したといいます。BBCの記事です。

口唇ヘルペスや性器ヘルペスを引き起こす「単純ヘルペスウイルス1型(HSV-1)」について、遺伝子療法の開発が進んでいます。HSV-1の感染者は、50歳未満の67%に上るといわれています。米国の研究チームが開発したのは、HSV-1のDNAの2カ所を切断して修復不能にする働きを持つ酵素と、これを体内のHSV-1まで送達するウイルスベクターからなる遺伝子療法薬です。この薬をマウスの血液中に投与したところ、1カ月後には口腔感染したHSV-1の90%、性器感染したHSV-1の97%がそれぞれ除去されたといいます。ウイルスの排出量も大幅に減り、他者に感染させるリスクが抑制される可能性も示されたとのこと。Medical Xpressの記事です。

両手の移植手術を受けた48歳の英国人女性に対して、拒絶反応リスクを減らすための世界で初めての治療が行われたそうです。治療の結果、腫れや器用さの低下、皮膚の色素沈着などの拒絶反応の症状が改善したといいます。女性は敗血症が原因で両手と左腕の4分の3を失い、2018年に両手と両腕の移植手術を受けました。しかし、免疫系が新たな組織を異物と判断して抗体を産生する「抗体関連型拒絶反応(AMR)」が発生。そこで英国民保健サービス(NHS)のチームは、有害な抗体を血液から取り除く「血漿交換療法」を女性に10回行ったそうです。今後は、抗体が再び増加するのを防ぐため、免疫抑制療法を再開する予定とのこと。BBCの記事です。

米国人の成人には、「オゼンピック」や「マンジャロ」といった「GLP-1受容体作動薬」を減量目的で使用している人が多くいるそうです。米カイザー・ファミリー財団(KFF)が、米国の成人1500人に対して4月に行った調査の結果です。GLP-1受容体作動薬を使用したことがあるのは8人に1人だったそうです。ほとんどが糖尿病や心臓病などの慢性疾患を管理するためにこの薬を使っていたとのことです。しかし、使用経験者の5人に2人は減量のためだけに薬を使用していたといいます。また、使用経験者の約半数が現在も薬を使っているそうです。使用者が最も多いのは50~64歳ですが、減量目的で使っているのはより若い層とのことです。CNNの記事です。

米ボストンにあるマサチューセッツ総合病院(MGH)は11日、今年3月に世界で初めてブタの腎臓の移植手術を受けた62歳の男性が死亡したと発表したそうです。MGHは当初、移植した腎臓は少なくとも2年間は機能すると説明していました。男性に移植したブタの腎臓は、拒絶反応が起きないように遺伝子改変されていたといいます。MGHは移植が原因で男性が死亡した兆候は認められないとしているとのことです。男性は2018年に通常(ヒト)の腎臓を移植したものの、昨年再び人工透析が必要になり、ブタの腎臓の移植手術を受けたそうです。AP通信の記事です。

毎日の食事にティースプーン1杯のオリーブオイルを加えるだけで、脳の健康を維持できるかもしれません。米国の研究チームが、心臓病やがんを持たない医療関係者9万2383人のデータを分析。1日7gを超える量のオリーブオイルを定期的に摂取していると答えた人は、「ほとんど」または「全く」摂取しないと答えた人に比べて認知症関連で死亡するリスクが28%低かったそうです。オリーブオイルに含まれる1価不飽和脂肪酸やポリフェノール、ビタミンEなどの成分が、抗炎症作用や神経保護効果を発揮する可能性があるといいます。Science Alertの記事です。

遺伝性難聴を持つ1歳目前の英国人の女児が、遺伝子治療で音を聞き取れるようになったそうです。女児はOTOF(オトフェリン)遺伝子に変異があり、音の振動を電気信号に変換するために必要なタンパク質オトフェリンが作られず、音を感知する内耳(蝸牛)の有毛細胞が損傷を受けているといいます。この女児の右耳に、無害化したウイルスを使って、正常な遺伝子を有毛細胞に送達する遺伝子治療を実施。女児は数週間で拍手などの大きな音を右耳で聞き取ることができるようになったそうです。さらに、半年後にはささやき声も聞こえるほど聴力が改善したといいます。この遺伝子治療法は米リジェネロン社が開発しました。BBCの記事です。
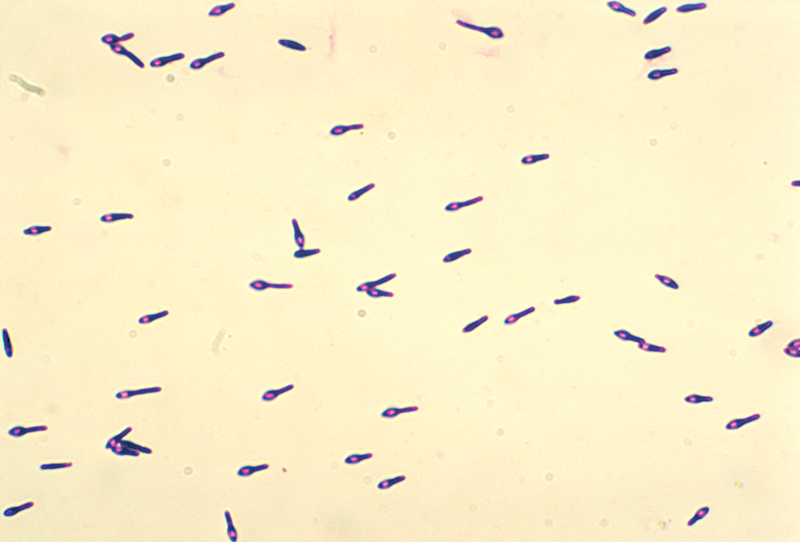
米国で偽の「ボトックス注射」によるものと思われる健康被害が起き、問題になっています。ボトックスの有効成分はボツリヌス菌が産生するボツリヌス毒素です。米疾病対策センター(CDC)は、11州で少なくとも22人がしわ取りのために「ボトックス注射」を受けた後、ボツリヌス毒素によるものとみられる健康被害を訴えたと発表。資格を持たない施術者が注射を行ったり、偽造品のボトックス注射が使われたりした可能性があるといいます。また2023年には、減量のために内視鏡を使って胃壁にボツリヌス毒素を注入する「胃ボトックス」によって欧州で67件の健康被害が報告されていました。マイナビRESIDENTの記事です。

単3電池ほどの大きさの小児向け植込み型補助人工心臓「Jarvik 2015」が、心臓移植を待つ子どもたちの生活を変えるかもしれません。現在、心臓移植を待つ子どもたちは、外付けの大きな装置につながれて病院内で移植待機期間を過ごしているといいます。米国の研究チームが、心臓移植を待つ生後8カ月~7歳の収縮性心不全患者7人にJarvik 2015を移植。このうち6人は無事に心臓移植を受けることができ、残りの1人は心臓が改善したため移植が不要になったそうです。装置を付けていたのは平均149日だといいます。Jarvik 2015の使用が実現すれば、自宅で待機し、多くの通常の活動に参加できるようになるとのこと。Medical Xpressの記事です。

失明の恐れがある遺伝性網膜疾患「レーバー先天性黒内障10型(LCA10)」に対するゲノム編集治療が、初期の治験で有望な結果を示したようです。米国の研究チームが、ゲノム編集技術CRISPRを用いて開発されたLCA10治療薬「EDIT-101」を成人患者12人と小児患者2人の片目に投与。病気の原因は、視力に関わる重要なタンパク質を作るための指示を出すCEP290遺伝子の変異で、この薬はその変異を編集するそうです。治験参加者の11人(79%)が見え方に何らかの改善があったといいます。さらに、4人(29%)は視力が臨床的に意義のある改善を示したとのことです。重篤な有害事象は確認されなかったそうです。ScienceDailyの記事です。

ベトナム南部ドンナイ省で、伝統的なサンドイッチ「バインミー」を食べた560人が体調不良を訴えて病院に搬送されたそうです。このうち、6~7歳の男児2人を含む12人が重体だといいます。患者は下痢や嘔吐、発熱、激しい腹痛といった症状があり、重体患者の血液からは食中毒を引き起こす大腸菌が検出されたとのことです。バインミーはフランス風のバゲットに冷たい肉やパテ、野菜を入れたものです。患者らは、省内のベーカリーで販売されていたバインミーを4月30日に食べた後に体調を崩したそうです。当局は、このところの熱波でバインミーが腐った可能性があるとして、詳しい原因を調べています。BBCの記事です。
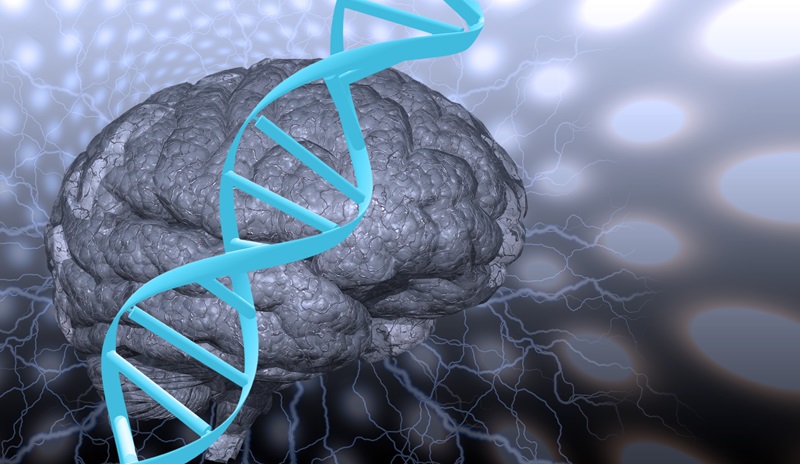
長い間、APOE4遺伝子はアルツハイマー病(AD)の危険因子の一つと考えられてきました。しかし、スペインなどの研究チームによって、この遺伝子のコピーを二つ持っている場合は、危険因子どころではなく、それがAD発症の根本的な原因となる可能性が示されたそうです。チームは、脳ドナー3297人と欧米のAD研究参加者1万人のデータを分析。APOE4の2コピー保持者は、1コピー保持者などに比べて55歳時点で脳にADの原因タンパク質・アミロイドβ(Aβ)が多く蓄積していることが判明しました。さらに、65歳までに2コピー保持者の3/4で著しいAβプラークの蓄積が認められ、その年齢の前後でADの初期症状が出る可能性が高かったといいます。AP通信の記事です。

英医薬品医療製品規制庁(MHRA)は、男性型脱毛症や前立腺肥大症(日本では未承認)の治療薬として知られる「フィナステリド」の副作用について注意を呼びかけたそうです。この薬の製品情報には、うつ症状や自殺念慮、性欲低下や勃起不全などの性機能障害を引き起こす可能性があることがすでに記載されているといいます。しかし、これらのことは、医師や患者にあまり知られていないのが実情だそうです。また、性機能障害については、薬の服用をやめた後も持続することがあるとのことです。こうしたリスクを広く知ってもらうため、MHRAは年内にも使用上の注意や副作用が記載された「警告カード」を薬の箱に入れる措置を開始する予定だといいます。Medical Briefの記事です。

米テキサス州で3月下旬に酪農に従事する男性が牛から鳥インフルエンザH5N1型に感染した症例について、米疾病対策センター(CDC)が詳細を公表したようです。感染者の男性に唯一みられた症状は結膜炎で、発熱や咳などの呼吸器感染症に関連するものはなかったといいます。目と鼻のスワブ検査から、牛の間で広まっているものと同じH5N1型に感染していることが判明したそうです。咳やくしゃみなどの飛沫を介した感染の可能性を排除することはできないものの、男性はウイルスに汚染された手で目をこすったことで感染した可能性が高いといいます。NBC Newsの記事です。

アフリカのコンゴ民主共和国(旧ザイール)では今年1月以来、エムポックス(サル痘)の感染者が急増しているそうです。同国の研究チームが、昨年10月から今年1月に鉱山の町カミトゥガでエムポックスに感染して入院した患者を調査したところ、新たな派生型を発見したといいます。ヒトの間で伝染が継続したことで起きたと考えられる遺伝子変異が見つかり、ヒトからヒトへ感染しやすくなっているとのこと。この新たな派生型は、少なくとも患者240人と死者3人の原因になったとみられるそうです。主な症状は性器の軽い発疹で、死亡率は低いようです。AP通信の記事です。

健康的な生活習慣は「早死に」の遺伝的なリスクを抑え込むことができるようです。英中の研究チームが、英国バイオバンクから抽出した成人35万3742人を平均13年間追跡調査。生活習慣の良し悪しにかかわらず、個人の遺伝的なリスクを表す「多遺伝子リスクスコア(PRS)」で短命と評価された人は、長寿と評価された人に比べて早死にするリスクが21%高かったそうです。また、好ましくない生活習慣の人は、遺伝的素因に関係なく、好ましい生活習慣の人に比べて早死にのリスクが78%高かったといいます。ただし、早死にの遺伝的リスクは、健康的な生活習慣によって約62%相殺される可能性が示されたとのこと。Medical Xpressの記事です。

皮膚に傷を負うと、腸にまで影響が及ぶそうです。米国の研究チームがマウスで調査。皮膚を1.5cm切開された群は、そうでない群に比べて便の中に病原菌が多く、善玉菌が少なかったそうです。皮膚と腸のつながりを正確に探るため、チームは遺伝子改変によって皮膚損傷に似た状態のマウスを作り出したといいます。傷の修復に必要なヒアルロン酸を分解してしまう酵素を多く産生するようにしたのです。すると、遺伝子改変マウスの便は皮膚損傷マウスと同様の状態になったといいます。さらに、マウスに大腸炎を誘発したところ、皮膚損傷マウスと遺伝子改変マウスは、対照群よりはるかに重症度が高くなったとのこと。Science Alertの記事です。

糖質を控え、脂質を増やした「ケトン食」が、重度の精神疾患の改善に有効かもしれません。米国の研究チームが、統合失調症または双極性障害と診断された成人患者21人に対して、カロリーの10%を炭水化物から、30%をタンパク質から、60%を脂質からそれぞれ摂るケトン食療法に従うよう指示。研究開始時は、患者はみな抗精神病薬を服用し、代謝異常が認められていたといいます。4カ月後、精神疾患に対する医学的評価が平均31%改善。気力や睡眠、気分、QOLが良い方向に変化したといいます。また、平均して体重が10%、胴回りが11%減少したそうです。療法に従った人ほど効果が高かったとのこと。Medical Xpressの記事です。

新年度になり、新しい環境に慣れずにつらい思いをしている人はいませんか。そんな人に知ってほしい研究成果が、いくつか発表されています。名古屋大学のチームによると、怒りが生じたときは、その感情を紙にいた上で、ゴミ箱やシュレッダーで処分すると気持ちが収まるそうです。英国の研究チームは、ネガティブなことを考えないようにすると、メンタルヘルスが改善することを発見。少量のお酒を飲むことにはストレス軽減の効果があると、米国のチームが報告しています。また、アイマスクをして寝て、スヌーズ機能を使って起きると、認知機能と目覚めが良くなるといいます。マイナビRESIDENTの記事です。

米ニューヨーク大学が、心不全と末期の腎臓病を患う54歳の女性に対して、補助人工心臓とブタの腎臓を移植したそうです。まず、チームは女性に人工心臓を植え込み、その約1週間後に、遺伝子改変したブタの腎臓を移植したといいます。拒絶反応を抑えるため、免疫細胞が訓練を受ける臓器であるブタの胸腺も腎臓と一緒に移植したとのことです。人工心臓を植え込んだ患者が臓器移植を受けた例は初めてで、ブタの腎臓移植が成功したのは2例目。今回使われたブタの腎臓は、拒絶反応の原因となる糖が作られないように、遺伝子を1カ所だけ改変してあるといいます。女性は順調に回復しているそうです。ABC Newsの記事です。

一般的な病院で使われているものと比較して約10倍も高精細な画像が撮れるMRIが開発されたそうです。「Iseult」と名付けられたこのMRIが、脳疾患治療の突破口を開くかもしれません。フランスの研究チームがIseultを使い、20人の脳画像を取得。通常のMRIであればスキャンに何時間もかかりますが、Iseultはわずか4分で完了するそうです。スキャン画像には、大脳皮質に流れ込む小血管やこれまでほとんど見ることができなかった小脳の細部が写し出されたそうです。こうした高性能MRIを使うと、アルツハイマー病やパーキンソン病などに関連する脳の変化を特定できる可能性があるとのこと。INSIDERの記事です。

医師の性別が患者の予後に影響する可能性があるようです。日米の研究チームが、米国で2016~19年に入院した65歳以上の女性患者45万8108人と男性患者31万8819人のデータを分析。女性医師が担当した患者の方が、入院から30日以内の死亡率と退院から30日以内の再入院率が低かったそうです。特に女性患者への影響が大きく、その死亡率は女性医師で8.15%だったのに対し、男性医師では8.38%だったといいます。この差は入院417件につき1件の死亡に相当するそうです。女性医師は女性患者とコミュニケーションを取りやすいことが、こうした差が生じさせる理由として考えられるようです。Science Alertの記事です。

複雑な思考を必要とする職業に就いている人は、高齢になっても脳の健康を維持できるかもしれません。ノルウェーの研究チームが、同国の男女7000人を30代から60代まで追跡調査しました。30~60代で精神的刺激の少ない定型業務に従事していた人は、複雑な思考を必要とする職業の人に比べて、70歳以降の軽度認知障害リスクが66%、認知症リスクが37%、それぞれ高くなることが分かったそうです。定型業務を行う職種にはハウスキーパーや用務員、建設作業員などが分類されます。複雑な思考を必要とする職業は教師や弁護士、医師、会計士などが該当するそうです。CNNの記事です。

市販の抗菌薬(抗生物質)の軟膏がウイルス性呼吸器感染症の予防または治療に有効な可能性があるようです。米国の研究チームが、一般的に使用される抗菌薬「ネオマイシン(フラジオマイシン)」をマウスの鼻腔内に投与したところ、新型コロナウイルスやA型インフルエンザウイルスに対する強力な防御反応が認められました。皮膚感染症などに使う市販の軟膏薬「ネオスポリン(ネオマイシンを含有)」を健康な人の鼻に塗ることでも、同様の防御反応が確認されたそうです。ハムスターの実験では、ネオマイシンがコロナの接触感染を抑制することも分かったといいます。Medical Xpressの記事です。

人は毎週、クレジットカード1枚分(5g)の微細なプラスチック粒子(マイクロプラスチック)を摂取しており、これがさまざまな臓器に広がっているようです。米国の研究チームが、人の平均的な摂取量に相当するマイクロプラスチックを加えた飲み水を4週間にわたり健康なマウスに与え、消化器系への影響を調査。マイクロプラスチックが腸から体内に侵入し、肝臓や腎臓、脳の組織にまで移動することが明らかになったそうです。さらに、マイクロプラスチックの影響を受けた組織において、代謝に関わる化学反応(代謝経路)の変化が起きてしまう可能性も示されたといいます。Medical Xpressの記事です。

トキソプラズマ原虫とボレリア属の細菌の感染は、人の性格特性に直接的な影響を及ぼすそうです。チェコの研究チームが、女性4942人(平均43歳)と男性2820人(平均40歳)のデータを分析。トキソプラズマは猫のふん便や加熱不十分な肉などを介して感染します。参加者の女性の24%、男性の12%が感染していました。ボレリアはマダニが媒介し、ライム病を引き起こします。感染していたのは参加者の女性の41.6%、男性の30.7%でした。分析の結果、これらの感染が誠実性の低さなどに関連することが判明。また、それは感染による健康状態の悪化が理由で起きたわけではないといいます。PsyPostの記事です。
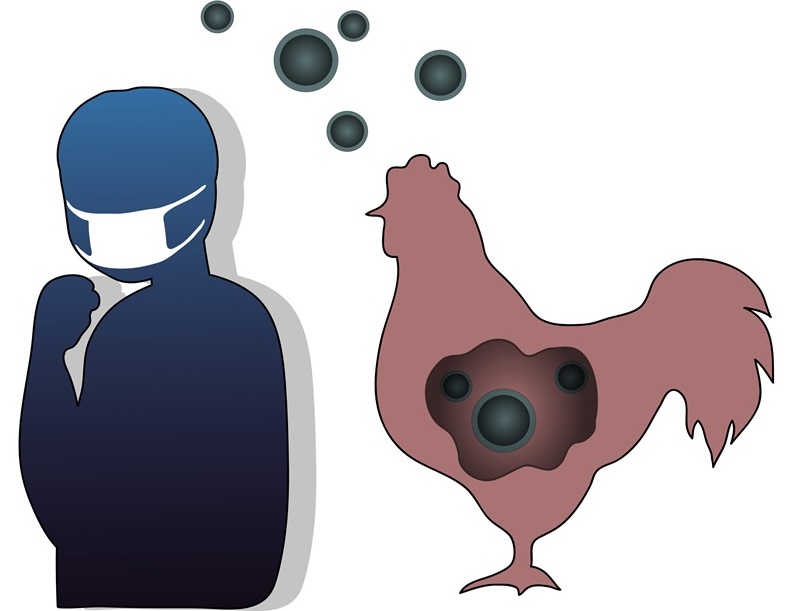
世界保健機関(WHO)は18日、鳥インフルエンザH5N1型に対する監視と備えを強化するよう呼びかけたようです。米国で牛を介してヒトへの感染が起きたことを受けたものです。今のところ、ヒトからヒトへの感染は確認されていません。ただし、過去2年間で鳥インフル陽性になる哺乳類が増加しており、ウイルスがヒトに感染しやすく変異しつつあることが懸念されています。2003年以降、23カ国から889人の感染者が報告され、52%に当たる463人が死亡しているそうです。WHOは「ワクチンや治療薬、診断薬によって、すぐに対応できるようにしなくてはならない」と指摘しているとのこと。CNNの記事です。

米国では、資格を持たない施術者による偽造の「ボトックス注射」に対する警戒感が高まっているそうです。米疾病対策センター(CDC)は19日、11州で少なくとも22人がしわ取りのために偽造のボトックス注射を受け、その後、ボツリヌス毒素によるものとみられる健康被害を訴えたと発表しました。米食品医薬品局(FDA)によると、外箱やビンにロット番号「C3709C3」が含まれる▽外箱に有効成分が「Botulinum Toxin Type A」と書かれている▽外箱やビンに「150 units(単位)」との表示がある▽外箱に英語ではない言語が表記されている――場合は偽物の可能性があるといいます。NBC Newsの記事です。

伝統的な日本食は、女性の認知機能低下を予防する可能性があるそうです。英国の研究チームが、40~89歳の日本人1636人に、口にした全ての物を3日間記録してもらい、その後2年にわたり追跡調査を実施。その結果、米や魚介類、大豆製品、キノコなどを中心とした伝統的な日本食を摂取していた女性は、西洋式の食事を摂取していた女性に比べて脳の萎縮が少ないことがMRIスキャン画像から明らかになったそうです。男性にはこうした違いが認められなかったといいます。日本食の食材に含まれるマグネシウムや植物性エストロゲンなどの栄養素は、女性の脳を特に強く保護する効果があるようです。The Conversationの記事です。

世界各国から奇妙な病気についての報告が上がっています。4カ月間も片頭痛に悩まされていた米国の52歳の男性がおり、脳にサナダムシの幼虫が寄生していることが分かったそうです。原因は、男性が生焼けのベーコンを好んで食べていたことのようです。せきやうつ、物忘れの症状が出た64歳の豪州の女性の脳からは、長さ8cmのニシキヘビに寄生する線虫が見つかったといいます。81歳のブラジル人女性は、56年間も胎児をお腹に持っていたことが判明。腹腔で妊娠したことで胎児が死亡し、石灰化したそうです。59歳の米国人男性は突然、人の顔が悪魔のように見えるようになったといいます。マイナビRESIDENTの記事です。

思春期に脂質や糖質が多い「ジャンクフード」を多く食べると、成人後の記憶力に悪影響があるかもしれません。米国の研究チームが、ラットを使って記憶力のテストを実施したそうです。ジャンクフードを食べて育った群は、対照群に比べて過去に見た物や場所を思い出せない傾向があったといいます。さらに脳の検査で、ジャンクフード群は、記憶に関連する神経伝達物質「アセチルコリン」によるシグナル伝達が低下していることも判明しました。チームは治療方法を探るため、アセチルコリンの放出を促す薬を記憶に関わる脳の海馬に直接投与したところ、ジャンクフード群の記憶障害が改善したといいます。Medical Xpressの記事です。

テトラサイクリン系抗菌薬は免疫系を活発にするそうです。既存の免疫チェックポイント阻害薬などのがん免疫療法は一部の患者にしか効果がないため、大阪大学の研究チームが新たな方法を探していたといいます。チームは、テトラサイクリン系抗菌薬を肺がん患者のがん組織に加えると、組織内の免疫細胞・Tリンパ球(T細胞)の「がん細胞傷害活性」が増強することを突き止めたそうです。この抗菌薬が、がん細胞が産生する免疫抑制物質「ガレクチン-1」の働きを阻害することで、Tリンパ球によるがんへの攻撃が活発になるといいます。Medical Xpressの記事です。

ハグなどの身体的接触は、心身の健康によい影響を及ぼすようです。ドイツとオランダの研究チームが、計1万2966人を対象とした212の先行研究を分析したそうです。その結果、身体的接触が痛みやうつ、不安の軽減に役立つことが示されたとのことです。こうしたプラスの影響は、大人でも子どもでも確認されたといいます。身体的接触の種類については、ハグでもマッサージでも大きな違いは見られませんでしたが、頭や顔への接触がもっとも効果的だったそうです。また、短時間の接触を頻繁に行うと、より効果が高まることも明らかになったとのことです。Science Alertの記事です。

米食品医薬品局(FDA)の「迅速承認プログラム」は、重篤な疾患に対する有望な薬を正式承認前にできるだけ早く患者に届けることを目的として実施されています。米国の研究チームが、こうした薬が実際に患者に恩恵をもたらしているのかどうかを調べたそうです。チームは2013~17年に迅速承認された46個のがん治療薬を5年間にわたって追跡調査。このうち厳密な検証試験で臨床的有益性が示されたのはわずか20個(43%)だったそうです。それにもかかわらず、29個(63%)が通常の承認に切り替えられたといいます。効果不明な薬を、そうとは知らずに投与されている患者が多くいるようです。AP通信の記事です。

米疾病対策センター(CDC)は10日、カンザス州の同じ家で飼われていた猫2匹に「スポロトリクス・シェンキィ」と呼ばれるまれな真菌が感染し、治療に当たった獣医技師も猫に引っかかれて感染したと発表したそうです。獣医技師は8カ月間も抗真菌薬を使って、ようやく回復したといいます。一匹目の猫は治療が遅れて状態が悪化したために安楽死させられ、もう一匹は抗真菌薬で回復したとのこと。この真菌はバラのとげなどから体内に入ることが多く、感染すると長引く皮膚病変を引き起こします。本来は伝染性ではありませんが、猫に感染すると他の動物への伝染リスクが高まるそうです。NBC Newsの記事です。

健康な人の腸内細菌を移植する「ふん便移植(FMT)」で、パーキンソン病(PD)の症状が改善する可能性があるようです。ベルギーの研究チームが初期PD患者を集め、22人には健康なドナーのふん便を、24人にはプラセボをそれぞれ鼻から小腸に移植。1年後、ふん便移植を受けた人は、震えやバランス障害などの運動症状が、緩やかではあるものの有意に改善したといいます。こうした改善が顕著に認められたのはふん便移植から6カ月以降だったとのことです。また、PDの進行とともに現れることが多い便秘の症状についても、ふん便移植で抑制されたそうです。Science Alertの記事です。

腸内環境の悪さは、肝硬変などの深刻な病気につながるといいます。英国の研究チームが、それを改善する画期的な方法を見つけたそうです。チームは、腸内の悪玉菌が産生する毒素や代謝物を吸着することができる微小な「カーボンビーズ」を開発。これをラットやマウスに数週間にわたって毎日経口で与えたところ、肝硬変の進行を抑制するのに有効であることが分かったそうです。また、慢性肝不全の急性増悪(ACLF)による死亡率も低下したといいます。肝硬変患者28人に対する試験も実施し、このビーズが安全であることを確認したとのことです。Medical Xpressの記事です。

米国でボツリヌス毒素を使った「ボトックス注射」による健康被害が起きている問題で、米疾病対策センター(CDC)は15日、ボツリヌス症の症状を訴えた患者は九つの州で計19人に上ると発表したそうです。19人は25~59歳の女性。1人以外は美容目的で、不適格な個人からや非医療施設で注射を受けたといいます。偽造品や誤った処理をされた製品が使われたケースもあったそうです。CDCは、注射を受ける際に▽免許を持っているか▽訓練を受けたか▽承認された製品か▽製品の供給源は信頼できるか――を確認するよう呼び掛けています。CNNの記事です。

米疾病対策センター(CDC)は、ボツリヌス毒素を使った美容医療用「ボトックス注射」の偽造品について、注意喚起を行うそうです。イリノイ州とテネシー州では、偽造品を使ったボトックス注射が原因とみられる「ボツリヌス症」のような症状で、それぞれ2人が入院。患者は目のかすみや顔の垂れ下がり、呼吸困難などの症状を訴えているといいます。これまでに計5州で同様の症例が確認されているそうです。ボトックス注射は通常は安全ですが、米国で承認されていない偽造品が出回り、非医療施設が無許可で行っていることもあるといいます。NBC Newsの記事です。

一般的な性感染症の「クラミジア感染症」に対するワクチンが実現するかもしれません。英国とデンマークの研究チームが、病原菌クラミジア(・トラコマチス)に感染していない平均年齢26歳の健康な男女を対象に、クラミジアワクチンの第1相試験を実施。安全に免疫応答が誘導されることが分かったそうです。クラミジアは女性の不妊の主な原因の一つで、男性は尿道炎や精巣上体炎などが起こります。また、目に感染すると結膜炎を起こし、視力低下の危険もあります。今回の治験では、ワクチンは腕への注射だけでなく、目薬でも投与したといいます。NBC Newsの記事です。

紅茶や緑茶を飲むと、新型コロナウイルスの感染が抑えられるかもしれません。米国の研究チームが市販の茶葉24種類を使って、これらを抽出したものを飲んだ場合のコロナ感染抑制に対する有効性を、実験室でシミュレーションしたそうです。最も効果が高かったのは紅茶で、わずか10秒で唾液中のウイルスを99.9%減少させることが示されたといいます。また、紅茶の他に、緑茶、ラズベリージンジャー、ユーカリミント、ミントメドレーがウイルスを96%以上減少させることが分かったとのこと。お茶の濃度を上げれば、うがいでも同様の効果が期待できるといいます。Medical Xpressの記事です。

怒りを簡単に抑制する方法が見つかったようです。名古屋大学の研究チームが、実験の趣旨を知らない参加者を集め、まず社会問題についての意見を書いてもらったそうです。次に、それに対してわざと低い評価を付けた上で、「学のある人がこんなことを考えるなんて信じられない」などと侮辱したコメントを付けてフィードバックし、怒りを生じさせたといいます。そして参加者に、その時の怒りの感情を紙に書かせたそうです。この紙をゴミ箱に捨てたり、シュレッダーで処分したりした人は、怒りのレベルが侮辱される前の状態に戻ったそうです。一方、怒りの気持ちを書いた紙を捨てずに持ち続けた人は、怒りのレベルがわずかに低下しただけだったといいます。ScienceDailyの記事です。

他人から「魅力的な人だな」と思われたくないですか。各国の研究チームが、「魅力」について科学的に解明しようと研究を続けています。フランスの研究チームによると、小麦粉や白米、砂糖などの精製炭水化物を頻繁に摂取すると、顔の魅力度が下がってしまうそうです。また、米国の研究チームは、低い声の人は、結婚など長期的な関係を築く相手として魅力的に思われることを発見したといいます。なお、これを実践する人はいないと思いますが、トキソプラズマ原虫が感染している人の顔は左右対称である傾向が高く、他人から魅力的だと思われることが多いそうです。マイナビRESIDENTの記事です。

妊娠中に解熱・鎮痛薬のアセトアミノフェンを服用すると、子どもの注意欠如・多動症(ADHD)や自閉症のリスクが上昇するという報告があります。米国の研究チームが、スウェーデンの子ども200万人を26年間追跡したデータを分析し、これを否定する研究成果を発表しました。チームは、兄弟姉妹のペアで、母親が一方の妊娠中にアセトアミノフェンを使用し、もう一方の妊娠中には使用しなかったケースに着目。アセトアミノフェンに関連する神経発達症リスクの上昇はみられなかったそうです。リスクに関連するのは、遺伝など他の要因である可能性が示されたといいます。NBC Newsの記事です。
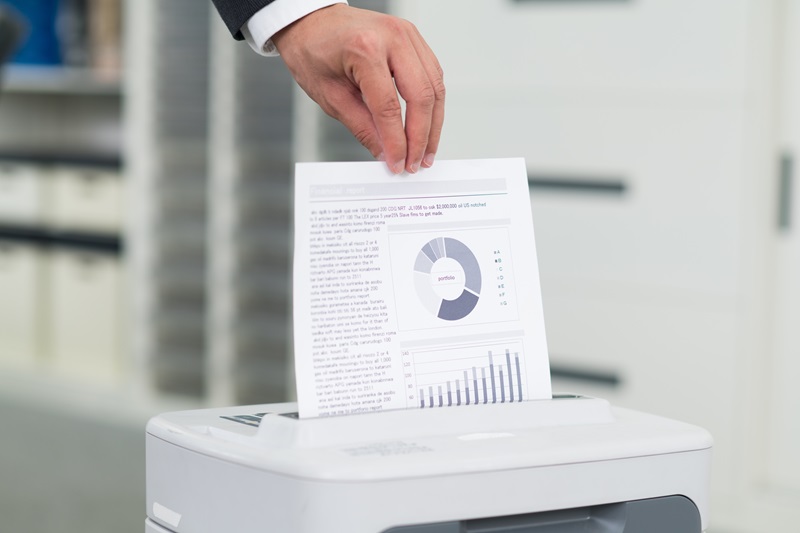
米ハーバード大学の「ダナファーバーがん研究所」の信頼が損なわれる事態が生じているそうです。問題の発端となったのは、英ウェールズの微生物学者が今年1月、自身のブログでダナファーバーの研究者が執筆した数十の論文に使われている画像に誤りや改ざんがある可能性を指摘したことでした。研究所は誤りを認め、この2カ月で医学誌「Journal of Immunology」と「Cancer Research」に掲載された計7本の論文を撤回したそうです。このうち6本の筆頭著者は、骨髄腫分野の第一人者で、この分野に多大な影響力を持つケネス・アンダーソン教授の研究だといいます。NBC Newsの記事です。

米アミリックス・ファーマシューティカルズ社は4日、筋萎縮性側索硬化症(ALS)治療薬「Relyvrio(レリブリオ)」について、販売から撤退すると発表したそうです。第3相試験で有効性を証明できなかったためです。今後は、新規の患者が同薬を使用することはできなくなるといいます。3月に公表された結果では、48週間後の患者の呼吸や嚥下、会話能力を示す指数がプラセボを上回らず、QOL(生活の質)や全生存期間、呼吸機能にも有意な改善はみられなかったそうです。レリブリオは、2022年9月に米食品医薬品局(FDA)が小規模治験の結果をもとに承認しました。CNNの記事です。

新型コロナウイルス感染症の後遺症(コロナ後遺症)に関する治療の鍵は、「炎症」かもしれません。英国の研究チームがコロナ重症患者650人を追跡調査。6カ月後、このうち426人がコロナ後遺症の症状を訴えたそうです。そして、こうした後遺症患者の血液中に、通常はウイルス感染直後にのみ認められる炎症関連タンパク質が継続的に存在していることが分かったそうです。さらに、胃腸症状のある患者で、腸と脳のコミュニケーション障害に関わることで知られるSCG3タンパク質が増加するなど、一部のタンパク質が特定の症状に関連している可能性も示されたといいます。BBCの記事です。

アマゾンの先住民族「ヤノマミ族」が深刻な水銀汚染の被害にあっているようです。ブラジルの保健当局がヤノマミ族300人から採取した毛髪を分析したところ、84%から健康被害につながる可能性のある「1gあたり2μg」以上の水銀が検出されたといいます。周辺地域ではかねてより金の違法採掘が横行しているとのこと。違法採掘では金の抽出処理の過程で水銀が使われることが多く、これが河川などの汚染につながるそうです。この地域の魚からも高濃度の水銀が検出されており、汚染された魚を食べることで水銀が体内に取り込まれてしまうといいます。水銀は主に神経症状を引き起こします。AP通信の記事です。

香港で37歳の男性がマカク属のサルと接触してけがをし、致死率の高い「Bウイルス病」を発症したそうです。Bウイルスはマカク属のサルを自然宿主とし、唾液やふん尿に含まれています。男性は2月下旬に公園で野生のサルと接触し、1カ月後に発熱と意識レベル低下で病院を受診。それ以降、集中治療室で治療を受けているそうです。Bウイルスは1932年に初めてヒトへの感染が確認され、これまでの感染者数は世界でわずか50人。香港では初確認とのことです。治療せずにいると70%以上が死亡するものの、近年は抗ウイルス薬による早期の治療で生存率が向上しているといいます。Science Alertの記事です。

長引く喘息(ぜんそく)発作の詳細な原因が分かったようです。英国の研究チームがマウスとヒト肺組織を使って、喘息発作の際に起こる気管支収縮の過程を詳しく調査したそうです。気管支収縮は筋肉(平滑筋)が収縮することで気道が狭くなる現象です。調査の結果、気管支収縮によって気道の上皮層が損傷されることが明らかになったといいます。そのために、長期的な炎症や感染が起こり、発作が繰り返されるそうです。マウスの実験では、「ガドリニウム」と呼ばれる元素が上皮層の損傷を防ぐのに有効である可能性が判明。ただし、臨床試験の実施までには数年かかるといいます。BBCの記事です。

スペインのImmunotek社が開発した尿路感染症(UTI)の再発を防ぐ舌下ワクチン「MV140」が、抗菌薬(抗生物質)の代替手段になるかもしれません。英国の研究チームが、UTIの再発に苦しむ18歳以上の男女89人を対象にMV140の長期的な安全性と有効性を調査。なお、MV140は3カ月間毎日、舌下にスプレーする薬だそうです。MV140を使い始めてから9年後の時点で、参加者のうち48人(54%)が一度もUTIの再発を報告しなかったといいます。再発した場合でも、水を飲めば治る程度の軽い症状で済むことが多かったそうです。目立った副反応も報告されなかったとのことです。Medical Xpressの記事です。
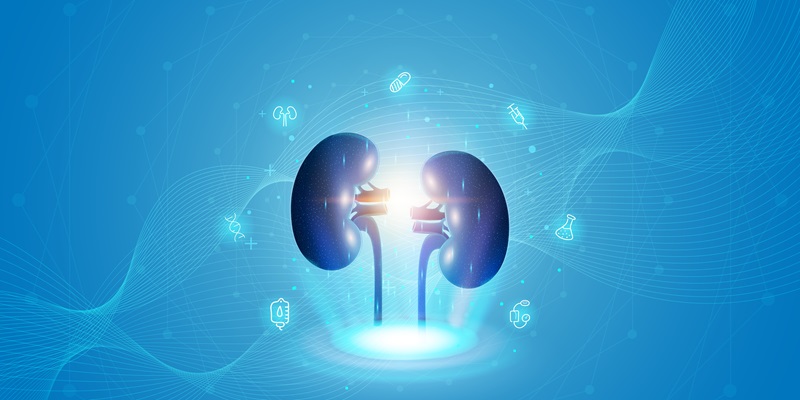
米マサチューセッツ州ボストンの米マサチューセッツ総合病院は3日、ブタの腎臓移植手術を受けた62歳の男性が退院したと発表したそうです。末期の腎臓病を患っていた男性は先月16日、拒絶反応が起きないよう遺伝子改変したブタの腎臓を移植する手術を受けました。治療目的で患者にブタの腎臓が移植されたのは世界初です。新しい腎臓は今のところ正常に機能しており、人工透析も不要になったそうです。男性は2018年に死亡したドナーからの死体腎移植を受けたといいます。しかし昨年から、腎臓がうまく機能しなくなったそうです。BBCの記事です。

アルツハイマー病(AD)を引き起こすとされる脳内の「アミロイドβプラーク(細胞外沈着物)」を除去する新たな方法が見つかったようです。米国の研究チームが、脳内のゴミを除去する免疫細胞「ミクログリア」に着目。AD患者のミクログリアで発現し、ミクログリアの不活性化に関わる受容体「LILRB4」を標的にした自家製抗体をADマウスに投与したそうです。その結果、ミクログリアが活性化してプラークを除去できるようになったといいます。さらに、記憶がなくなることから起こるマウスのリスク行動も減少したといいます。Medical Xpressの記事です。

腸内細菌叢(腸内フローラ)の乱れは、さまざまな病気の発症や治療に影響を与えるようです。ある研究では、抗菌薬(抗生物質)の使用によって免疫チェックポイント阻害薬が効かなくなる可能性が明らかになったといいます。また抗菌薬の使用は、後の認知機能低下を引き起こすかもしれないとの報告も出ています。さらに、腸内細菌叢の不均衡が心筋梗塞などの心疾患を引き起こすことが明らかになったそうです。脳の神経伝達物質が減少することによって起こるパーキンソン病も腸内細菌叢と関係がありそうだという研究成果も発表されています。マイナビRESIDENTの記事です。

コロナウイルス全般に有効なユニバーサル(万能)ワクチンが実現するかもしれません。米国の研究チームがmRNAワクチンの技術を活用し、新型コロナウイルスやコウモリコロナウイルスなどに幅広く効果が期待できる3価ワクチンを開発。このワクチンをハムスターに接種したところ、試した全ての新型コロナオミクロン株系統を中和することができたそうです。さらに、コウモリの間で広がっており、将来ヒトでパンデミックを起こす危険性のあるコロナウイルスにも有効だったといいます。肺からウイルスが検出されない「完全な防御」が確認できたとのこと。Medical Xpressの記事です。

米国の研究チームによると、過去24時間以内にシュガーレスガムをかんだ人は、そうでない人に比べて国が作成した食生活指針に従った食事を取る傾向にあるそうです。その結果、健康全般にも好影響が及ぶ可能性があるといいます。チームが、米国の全国健康栄養調査 (NHANES)から抽出したデータを分析して明らかになりました。シュガーレスガムをかむと、砂糖の摂取量、間食やカロリーの高い食事を取る量が減るといいます。また、口の病気が減ることから、糖尿病や心血管疾患などの慢性疾患、うつ病などの精神疾患にも効果があるかもしれないとのこと。Science Alertの記事です。

鳥インフルエンザウイルス(H5N1型)が感染した乳牛が見つかった米テキサス州で、ヒトへの感染が確認されたそうです。この患者は仕事上、H5N1の感染が疑われる牛と直接接触していたといいます。症状は目の充血だけで、抗ウイルス薬による治療で快方に向かっているとのこと。米疾病対策センター(CDC)は「感染動物との接触でうつることがあるが、ヒトからヒトへの感染は確認されていない」としています。また、感染動物の殺菌処理をしていない乳を飲んだり、生のチーズを食べたりしないよう注意を呼び掛けています。米国でH5N1の感染者が見つかったのは2例目だそうです。ABC Newsの記事です。

81歳のブラジル人女性が、「石児」と呼ばれる石灰化した胎児の摘出を行い、その後に死亡したそうです。腹痛を訴えた女性にCT検査を行ったところ、腹部のスキャン画像に胎児の姿が映し出されたといいます。女性には7人の子どもがいるそう。医師らは、女性が最後に妊娠した56年前から死亡した胎児を体内に持っていた可能性があるとみています。3月14日に胎児を摘出する手術が行われたものの、翌日死亡したそうです。石児は極めてまれな症例で、腹腔で妊娠が起きてしまったことで胎児が死亡し、大き過ぎて体内に吸収されない場合に起こることが多いといいます。Medical Briefの記事です。

韓国の尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領は1日、医学部定員増を巡って政府と医療界が対立している問題で、医師不足を解消するために定員を2000人増やす必要があることを改めて国民に訴える談話を発表したそうです。尹氏は、医療界の対応を「社会に深刻な脅威をもたらす違法な集団行動」と厳しく批判。「この計画が医師の収入減につながることはない」とも述べたといいます。また、ストライキ中の医師らに職場復帰を促し、「対話のドアはオープンである」としたそうです。一方、大韓医師協会は「従来の方針を繰り返しただけ」と、「大きな失望」を表明したといいます。AP通信の記事です。

脂肪から採取した幹細胞で、脊髄損傷による運動機能障害やまひを改善できるかもしれません。米国の研究チームが、18~65歳の脊髄損傷患者10人を対象に実施した幹細胞療法の第1相試験の結果を報告。チームは、患者本人の脂肪から幹細胞を採取し、4週間かけて1億個に増殖させ、患者の腰椎に注入したそうです。その後、患者の状態を5段階の機能障害尺度を使って2年間で10回評価したところ、10人中7人において、尺度が少なくとも1段階改善したといいます。頭痛や筋骨格系の疼痛が副作用として報告されたものの、重篤な有害事象は認められなかったとのこと。Medical Xpressの記事です。

長期記憶を形成するには、関係する神経細胞(ニューロン)のDNAの損傷が不可欠なことが明らかになったそうです。米国の研究チームが、エピソード記憶と呼ばれる個人的な経験に基づく長期記憶を形成するのに十分な衝撃をマウスに与え、記憶に関わる脳の海馬領域の神経細胞を分析。DNAが損傷し、その断片が核から放出されると、炎症に関わる「Toll様受容体9(TLR9)」シグナル伝達経路が強力に活性化されることが分かったそうです。活性化したTLR9経路を介してDNA損傷が修復され、長期記憶の形成につながるといいます。Medical Xpressの記事です。

高齢の人の脳の健康状態を知るには、「話すスピード」に注意を払うといいそうです。カナダの研究チームが、18~90歳の健康な成人125人に、ある場面について詳しく説明してもらい、その音声を人工知能(AI)で分析したといいます。認知機能を評価するテストの結果と照らし合わせたところ、加齢に伴う認知機能低下が日常会話のスピードに密接に関連していることが分かったそうです。「適切な言葉を思い出せない」と認知機能の低下を心配しますが、「話すスピードが遅い」ことの方が正確な指標になる可能性があるといいます。The Conversationの記事です。

ブロッコリーやカリフラワーは、がん予防やコレステロール抑制に効果があることが知られています。それは、これらアブラナ科の野菜に含まれる「スルフォラファン(SFN)」という成分によるものだそうです。豪州の研究チームが新たに、SFNが脳卒中治療にも有効な可能性があることを突き止めたといます。植物に含まれる23の化合物を調査したところ、SFNには血小板の凝集を抑制し、血栓の形成を妨げる効果があることが判明。マウスを使った実験では、脳卒中治療に使われる血栓溶解(tPA)療法にSFNを組み合わせると、脳損傷を回避できる割合が20%から60%に上昇したとのことです。Science Alertの記事です。

腸内細菌叢(腸内フローラ)は、体質に影響を与えるようです。アイルランドの研究チームによると、新型コロナのパンデミック中に生まれた子どもは、食物アレルギーを発症しにくいそうです。ロックダウン(都市封鎖)で感染症にかかる機会が減り、抗菌薬・抗生物質があまり使われなかったのが理由のようです。また、新型コロナの後遺症の出やすさは、腸内細菌叢によって決まる可能性があるといいます。その他、人間の健康状態を反映するとされる「血中代謝物」の組成や脳の視床下部の活動にも腸内細菌叢が関係していることが分かってきたとのことです。マイナビRESIDENTの記事です。

犬の鋭い嗅覚は、心的外傷後ストレス障害(PTSD)によるフラッシュバックを予測できるそうです。人体からは、さまざまなにおいの分子「揮発性有機化合物(VOC)」が発せられています。カナダの研究チームは、人がトラウマを思い出している時の呼気を採取して、2匹の犬を訓練したといいます。2匹は「トラウマを思い出しているときの息」と「落ち着いているときの息」を嗅ぎ分けられるようになったそうです。1匹は74%、もう1匹は81%の精度でトラウマによるストレス関連VOCを検知できたとのこと。早い段階で犬が危険を察知することで、フラッシュバックを防げるようになるかもしれません。EurekAlert!の記事です。
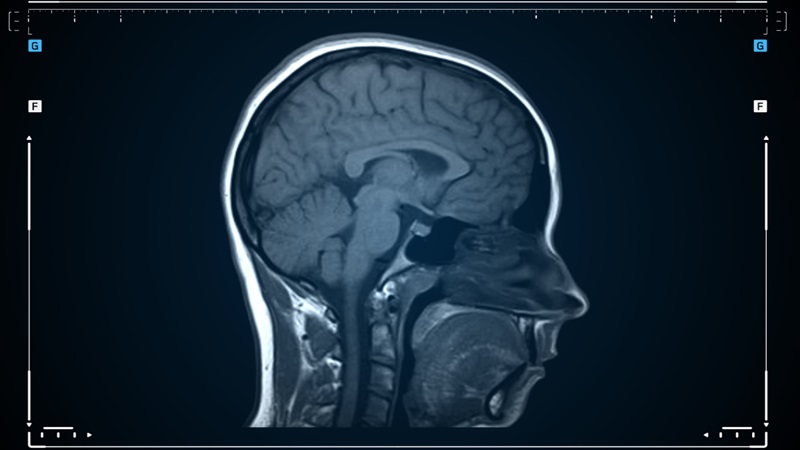
過去30年間で米国と欧州の認知症発生率は10年ごとに13%低下しているそうです。なぜ、世代が進むと認知症リスクが下がるのでしょうか。米国の研究チームが、1930~80年生まれの米国人3000人以上を対象に脳画像を分析。その結果、70年代生まれの人は、30年代生まれの人に比べて脳体積が6.6%大きかったそうです。神経細胞が集まっている灰白質の表面積や、記憶や学習に関わる海馬の大きさが若い世代の方が大きいといいます。研究者は「脳が大きいと加齢に伴う脳の衰えの影響を緩和する可能性がある」としています。Science Alertの記事です。

1人の女性が生涯に産む子どもの平均数を表す「出生率」は、今後も急激に下がり続けるようです。米国の研究チームの推計によると、1950年に4.84人、2021年に2.23人だった世界の出生率は、2100年までに1.59人に急落するそうです。さらに、2100年には世界の国々の97%で、人口を維持できる水準である「合計特殊出生率2.1人」を下回る見込みだといいます。特に高所得国における出生率の低下が顕著だそうです。2100年には世界の出生数に占める低所得国の割合は、21年の18%から35%に倍増する可能性があるとのことです。CNNの記事です。

米テキサス州とカンザス州の農場で採取された殺菌処理前の牛乳から、鳥インフルエンザウイルスが検出されたそうです。25日に米当局が発表しました。テキサス州では、鼻咽頭ぬぐい液の検査でも陽性を確認したとのことです。検出されたウイルスは人にまれに感染し、重篤な症状が出ることで知られる「鳥インフルエンザA(H5N1)」だといいます。テキサス州では、3週間前から乳牛の体調不良が急増。野鳥から乳牛にウイルスが感染した可能性が考えられるそうです。市場に出回る牛乳の安全性は確保されているといいます。専門家によると、これまでに48種の哺乳類で鳥インフルの感染が確認されているとのこと。AP通信の記事です。

突然、人の顔が歪んで見えるようになる「相貌変形視(PMO)」を知っていますか。米国の研究チームが、人の顔を直接見たときだけ歪みが生じるという59歳の患者の例を紹介しています。チームはこの患者に、目の前にいる被験者と、その被験者の顔写真を比較してもらい、顔がどう見えるのかを画像編集ソフトで再現。耳や鼻や口が後方に伸び、額や頬には深いしわが入って、まるで悪魔のように見えることが分かったといいます。PMOは脳の神経学的機能障害が関連しているとみられていますが、詳しい原因は分かっていません。統合失調症などの精神疾患と誤診され、誤った薬を処方されることもあるそうです。NBC Newsの記事です。

米国の研究チームが、アルツハイマー病(AD)の根本的な原因を見つけた可能性があると発表したようです。チームは、細胞小器官(オルガネラ)の一つで、脂質の貯蔵や分解などを担う「脂肪滴」と、脂質の代謝に関与する「APOE遺伝子」に着目。ADで死亡した患者の脳組織を分析したところ、ADの危険因子でAPOE遺伝子の一つの型である「APOE4遺伝子」を有する人の脳には、脂肪滴蓄積の促進に関連する酵素を持つ免疫細胞が多く存在していたそうです。複数の実験結果を勘案すると、AD関連タンパク質・アミロイドβの沈着が脂肪滴蓄積を引き起こし、AD発症につながる可能性があるといいます。Medical Xpressの記事です。
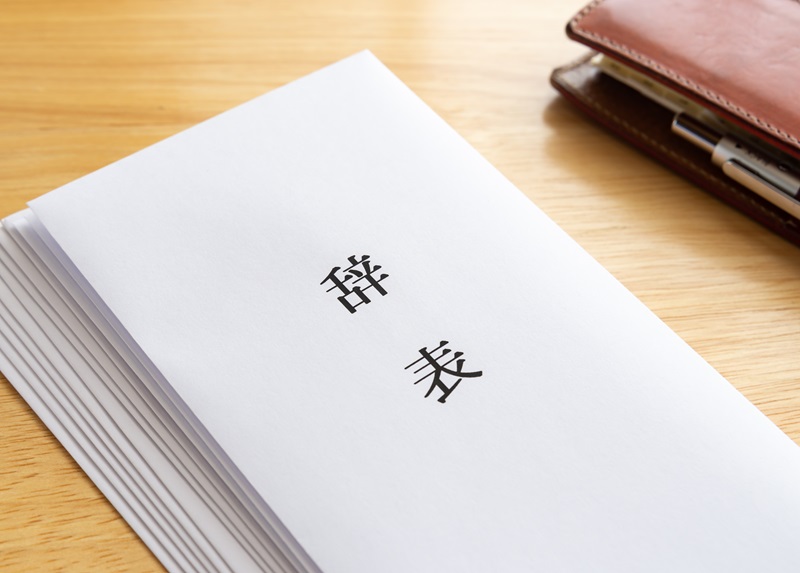
韓国の主要な大学病院の教授らが25日、政府が掲げる医学部定員増計画の撤回を求めて、一斉に辞表を提出したそうです。政府の計画に反発した研修医らがストライキを始めてから、5週間が経過しました。政府はストライキに参加している研修医らの免停手続きを進めていましたが、24日には尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領が医師側と建設的な対話を進めるよう関係者に指示するなど、態度をやや軟化させていたといいます。教授らは、辞表提出後も法定労働時間の週52時間以内で勤務を続ける方針とのこと。医師側の代表者は「政府が計画を撤回、再検討するなら話し合う用意がある」としているそうです。AP通信の記事です。

名古屋大学などの研究チームが、「中年太り」は脳の神経細胞が加齢によって変化することが原因であることを突き止めたそうです。チームは、脳の視床下部に存在し、栄養過多を検知して代謝を促したり食欲を調節したりするタンパク質「4型メラノコルチン受容体 (MC4R)」に着目。ラットを使って調べたところ、MC4Rが視床下部の神経細胞の「一次繊毛」という「アンテナ」に集中していることが分かったそうです。そしてこの繊毛は、加齢に伴って短くなることが判明。それに応じてMC4Rが減少し、結果的に増量につながるといいます。また、高脂肪食が繊毛の短縮を促進することも示されたそうです。Medical Xpressの記事です。

米実業家イーロン・マスク氏が創設したニューラリンクは、同社の小型チップを脳に埋め込む手術を受けた29歳の男性が、考えるだけでコンピューター画面を操作し、チェスを楽しむ様子の動画を配信したそうです。男性は8年前のダイビング中の事故で、肩から下がまひしているといいます。今年1月、脳インプラントの治験に参加。手術翌日には退院し、認知機能にも問題はなかったそうです。カーソルを動かすことを考える訓練からスタートし、そのうちに脳インプラントが意図を反映するようになったといいます。男性はゲームのほか、日本語やフランス語のレッスンも楽しんでいるとのことです。Medical Xpressの記事です。

「におい」というのは不思議です。イスラエルの研究チームは、女性の涙をかぐと、男性の攻撃性が抑えられるという研究結果を発表しています。また、イスラエルの別の研究によると、人は同じような体臭の人と仲良くなりやすいことが分かったそうです。米国の研究チームは、記憶を思い出すことが困難なうつ病の人を対象に調査を実施。においを嗅ぐと、それに関連する過去の具体的な出来事を思い出せることが明らかに。気になる臭いの消臭方法の研究も行われています。ニンニクを食べた直後にヨーグルトを食べると効果が期待できるそうです。マイナビRESIDENTの記事です。
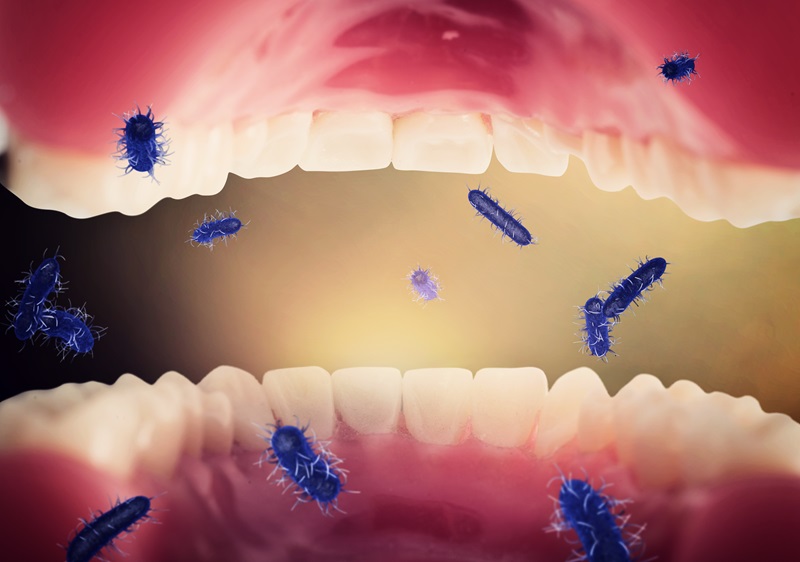
口の中に常在する細菌「フソバクテリウム・ヌクレアタム」の特定のサブタイプが、大腸がんの進行を促進することが分かったそうです。米国の研究チームが、大腸がん患者200人の腫瘍を分析したところ、約半数でサブタイプの「FnaC2」が増殖していることを発見。FnaC2は口から胃を通過して腸に移動し、そこで増殖する特異な形質を持つことも明らかになったそうです。また、腫瘍と健康な組織の比較から、FnaC2が大腸がんの増殖に関与することも示されたとのこと。大腸がん患者は、健康な人に比べて便からFnaC2が多く検出されたといいます。Medical Xpressの記事です。

米マサチューセッツ州ボストンのマサチューセッツ総合病院は21日、重い腎臓病の62歳の男性患者にブタの腎臓を移植したと発表したそうです。ブタの腎臓が治療目的で患者に移植されるのは世界初。16日に行われた手術の後、男性は順調に回復しており、近く退院できる見込みだといいます。手術チームは、ブタの腎臓は少なくとも2年間は機能すると考えているようです。今回移植されたブタの腎臓は人体側の拒絶反応を抑えるため、害のある遺伝子を除去し、人体に適合させるためにヒトの遺伝子を加える処置を施してあるそうです。AP通信の記事です。

世界中ではしかの感染が広がっています。米疾病対策センター(CDC)は春夏の旅行シーズンを前に、はしかに関する警報を出したそうです。現在、アフリカ26カ国、ルーマニアやトルコなどヨーロッパ4カ国、中東8カ国、インドなどアジア7カ国、東南アジアのマレーシアとインドネシア――の計46カ国で多くの感染者が発生。CDCは、海外に行く乳児には、定期接種のスケジュール(通常は1歳)を前倒ししてワクチンを接種させるよう呼び掛けています。また、ワクチンを接種したかどうか不明な人には、旅行の6週間前に医師の診察を受けることを勧めています。CNNの記事です。

ピロリ菌と同じくらい胃がんの発症に影響を及ぼす可能性のある細菌が明らかになったそうです。口の中に一般的に存在する「ストレプトコッカス・アンギノーサス菌(SA菌)」です。シンガポールなどの研究チームが2週間にわたり、マウスの胃にSA菌を入れ続けて調べたそうです。その結果、軽~中等度の胃炎が引き起こされたといいます。そして1年後には、多くの細胞が異常な前がん状態に変化したそうです。また、SA菌が胃粘膜の細胞に感染するためには、細菌の表面に特定のタンパク質が必要なことが分かり、胃がん治療の標的になる可能性も示されたとのこと。Medical Xpressの記事です。

世界各国に駐在している米国の外交官らの中には、原因不明の頭痛やめまいなどに見舞われる「ハバナ症候群」の患者がいるそうです。米国立衛生研究所(NIH)の調査で、患者の脳には損傷を示す証拠がないことが分かったといいます。NIHは患者80人以上を2018年から調査。最新のMRIスキャンを使って、患者と同様の職に就いている健康な対照群と比較したところ、脳の体積、構造、白質に有意差はなかったそうです。ハバナ症候群は16年にキューバで最初に報告されました。現在は否定的な見解が優勢とのことですが、当初は敵国による何らかの攻撃の可能性があると考えられていたようです。AP通信の記事です。

患者自身の免疫細胞・T細胞を遺伝子改変し、がんへの攻撃力を高める「CAR-T細胞療法(キメラ抗原受容体T細胞療法)」で、悪性度の高い脳腫瘍「膠芽腫」を治療できる可能性があるようです。米国の研究チームが、CAR-T療法と抗体分子を組み合わせた治療法を開発。この抗体分子は、がん攻撃に参加させるために周辺のT細胞を引き寄せることができるといいます。また、米国の別のチームは、タンパク質「EGFR」など膠芽腫に関わる二つのタンパク質を標的とするCAR-T療法を生み出したそうです。どちらの治療法も、小規模な治験で腫瘍の縮小が認められたといいます。ABC Newsの記事です。

新型コロナなどの呼吸器感染症対策として推奨されてきた「換気」は、過度に行うと逆効果になるかもしれません。米国の研究チームが、ウイルスを殺す作用があることで知られ、空気中を漂う「過酸化水素(H2O2)」に着目。室内の湿度が15%から50%に上がると空気中の微小水滴のH2O2濃度は3.5倍になり、その後50~95%の濃度は横ばいであることが分かったといいます。米疾病対策センター(CDC)は1時間に5回の換気を推奨しています。しかし研究者は、空気を乾燥させてしまうと指摘。換気だけを意識するのではなく、加湿器で湿度を保った上で行うことを勧めています。Medical Xpressの記事です。

米食品医薬品局(FDA)は、マドリガル・ファーマシューティカルズ社が開発した非アルコール性脂肪肝炎(NASH)向け経口薬「resmetirom(商品名:Rezdiffra)」を迅速承認したそうです。NASHの治療薬の承認は初めてだといいます。NASHは飲酒を原因とせず、肝臓に中性脂肪がたまって炎症が起こる疾患で、肝硬変や肝がんに進行するリスクがあります。同薬には、代謝に関わる甲状腺ホルモンの受容体を活性化し、肝臓内の脂肪を減少させる効果があるそうです。臨床試験では、同薬100mgを毎日服用した人の30%で、炎症による肝線維化が悪化することなくNASH消失が認められたといいます。CNNの記事です。

片頭痛の悪化で受診した52歳の米国人男性が、豚に寄生するサナダムシの幼虫によって脳に嚢(のう)胞が形成される「神経嚢虫症」と診断されたようです。男性は生焼けのベーコンを好んで食べる習慣があったといいます。これによりサナダムシが男性の腸に寄生し、不十分な手洗いで糞便に含まれる卵が口から入り、神経嚢虫症を発症した可能性があるそうです。男性は4カ月にわたる頭痛に悩まされ、薬が効かなくなったといいます。CT画像から脳に多数の嚢胞があることが判明し、嚢虫症の抗体検査で陽性反応が出たとのこと。抗寄生虫薬と抗炎症薬が効き、男性の症状は改善したそうです。NBC Newsの記事です。

タンパク質生成に関わらないため、機能を持たないジャンク(がらくた)と考えられていた「ノンコーディングRNA」が、小児悪性脳腫瘍「髄芽腫」の新治療法の鍵になる可能性があるそうです。米国の研究チームが、長鎖ノンコーディングRNA「lnc-HLX-2-7」が発がん遺伝子の発現に関与することを発見。これを標的とするRNAベースの静脈内投与薬を開発したそうです。最も治療が難しい「グループ3髄芽腫」のマウスにこの薬剤を投与したところ、腫瘍の成長が40~50%抑制されたといいます。既存の化学療法(シスプラチン)と組み合わせると、さらに効果が高まったとのこと。Medical Xpressの記事です。

新型コロナのパンデミック中に生まれた子どもは、腸内細菌の関係でアレルギーを発症しにくいそうです。アイルランドの研究チームが、パンデミック中(開始後3カ月以内)に生まれた乳児351人とパンデミック前に生まれた乳児を比較。1歳までに食物アレルギーを発症したのは、「パンデミック中」が5%だったのに対し、「パンデミック前」は22.8%だったそうです。便を比較したところ、「パンデミック中」の方が、有益な腸内細菌が多いことが分かったといいます。ロックダウン(都市封鎖)で乳児の感染症の発生率が減り、抗菌薬の使用が激減したことが原因と考えられるそうです。Medical Briefの記事です。

韓国で研修医らがストライキを起こし、医療現場に異常な事態が発生しているようです。発端は、医学部の入学者数を増員するという韓国政府の発表でした。これに反対したソウルの5大病院の研修医が、2月19日に一斉に退職届を提出。翌日から職場を離れてストに入ったといいます。全国的に同様の動きが広がり、国内の研修医のほとんどがストに参加しているそうです。この動きを支持する上級医師らが大規模デモを行ったり、政府がスト参加者の医師免許を停止する措置を始めたりして、両社の対立は激化しているとのこと。患者に深刻な影響が出ているようです。マイナビRESIDENTの記事です。

脳と外部のコンピューターをつなぐ「ブレイン・コンピューター・インターフェイス(BCI)」の臨床試験で、筋萎縮性側索硬化症(ALS)で指先の運動機能を失った男性が、体調や痛みに関する情報を画面上で選択して送信するプログラムを使いこなせるようになったそうです。臨床試験は米シンクロン社が行っているものです。男性の脳に埋め込んだBCIは、脳の電気信号を検出することができるステント(金属製の筒)で、開頭せずに頸静脈から挿入できるといいます。男性が画面のある場所をクリックしたいなどと考えると、BCIがその信号を読み取ってコンピューターに伝えるそうです。CNNの記事です。

携帯電話から出る電磁波が、脳腫瘍のリスクを高めるという説があるそうです。本当なのでしょうか。スウェーデンと英国などの研究チームが、2007~13年にかけて世界5カ国(英国、デンマーク、スウェーデン、フィンランド、オランダ)で25万人を対象に携帯電話の使用に関するアンケート調査を実施(COSMOS研究)。その後、参加者を追跡調査したところ、携帯電話による総通話時間が最も長い群であっても、脳腫瘍の発生リスクが高まることはないと分かったそうです。アンケート調査の15年前から携帯電話を使用していた人でも、リスクは上昇しなかったといいます。Medical Xpressの記事です。

韓国政府の医学部増員計画に反発して、研修医がストライキを起こしている問題の続報です。韓国政府は12日、大学病院の教授らが研修医のストライキに合流する可能性を示唆したことを受けて、「大変遺憾」と非難したそうです。現在、ストライキを行っている研修医の数は1万2千人にまで増加。政府は、ストを続ける研修医に対して、医師免許停止手続きを開始しています。こうした状況を受け、教授らは11日、政府が来週初めまでに妥当な打開策を打ち出さなければ、一斉に辞職願を提出すると表明したといいます。AP通信の記事です。
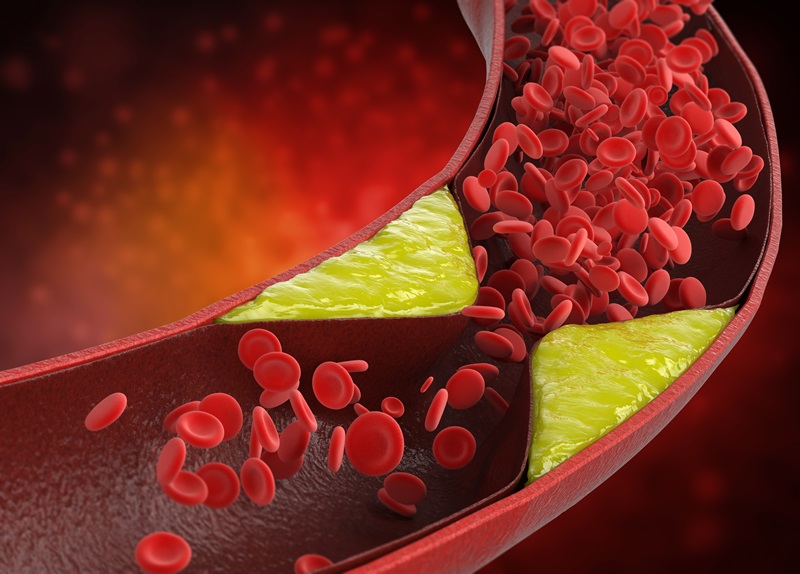
ヒトは食事や呼吸によって、微小なプラスチック片(マイクロプラスチック)を体内に取り込んでいるといいます。このことが、心血管の健康に悪影響を及ぼしているかもしれません。イタリアの研究チームが、動脈血栓症のため血管内から「プラーク」を摘出する手術を受けた患者257人を調査。プラークは、LDLコレステロールが血管の内皮細胞の下にたまってできたかたまりです。摘出したプラークから、ポリエチレン(PE)やポリ塩化ビニル(PVC)が検出された人は、そうでない人に比べて34カ月以内に脳卒中や非致死性の心臓発作を発症するリスクや、全死因死亡リスクが4.5倍高くなったといいます。ScienceAlertの記事です。

悪性度が非常に高い脳腫瘍「膠芽腫」の新たな治療法が開発されるかもしれません。シンガポールの研究チームが、ジカ熱のワクチン用に開発された「ジカウイルス弱毒生ワクチン(ZIKV-LAV)株」に着目。生体外でZIKV-LAV株をヒト膠芽腫細胞に感染させたところ、腫瘍細胞の65~90%が死滅することが明らかになったそうです。ZIKV-LAV株は脳内の血管細胞の9~20%に感染したものの、健康な細胞を殺すことはなかったといいます。また、ZIKV-LAV株は健康な細胞ではうまく増殖できず、がん細胞で良く増殖するそうです。Medical Xpressの記事です。

米アミリックス・ファーマシューティカルズ社は8日、同社が開発した筋萎縮性側索硬化症(ALS)治療薬「Relyvrio(レリブリオ)」の販売を自主的に中止する可能性があると発表したようです。レリブリオは、2022年9月に米食品医薬品局(FDA)が承認しました。しかし、小規模な中間段階の研究結果しかなく、有効性については当時から疑問の声が上がっていたといいます。そして今回、ALS患者600人以上を対象とした追跡調査の結果、レリブリオがALSの進行を遅らせることはなく、筋力を改善することもないことが判明したそうです。AP通信の記事です。

米食品医薬品局(FDA)は8日、人気の肥満症治療薬「ウゴービ(一般名セマグルチド)」について、心血管疾患リスク抑制の治療に対する適応拡大を承認したそうです。心臓発作や脳卒中などのリスクを減らす作用があると認められた肥満症治療薬は、ウゴービが初めてだといいます。この薬を販売するデンマークの製薬大手ノボノルディスクが、心血管疾患既往歴のある1万7000人を対象に行った臨床試験では、ウゴービが心血管イベントを20%抑制するとの結果が示されたとのことです。一方で、既往歴のない人への有効性については、さらなる研究が必要だといいます。CNNの記事です。

出生前にエイズウイルス(HIV)が母子感染した乳児に対して、複数の薬剤を組み合わせる「抗レトロウイルス療法(ART)」が有効かもしれません。米国立衛生研究所(NIH)が資金提供した研究で、研究チームはHIVが感染している乳児に、生後すぐにARTを集中的に行い、日常的な投薬をせずに寛解を保てるのかを調査。参加した子どもたちのうち4人が、治療を休止してから1年以上寛解を維持したといいます。最終的には全員からHIVが再検出されたのですが、将来的に、こうした子どもたちが人生の一時期だけARTを受ければいいようになる可能性が示されました。ABC Newsの記事です。


小麦粉や白米、砂糖などの精製された炭水化物の摂取量が、顔の魅力に影響を及ぼすようです。フランスの研究チームが、成人男女104人に「精製炭水化物を使った血糖値が上がりやすい朝食」か「そうでない朝食」を食べてもらい、2時間後に写真を撮影。そして、別途集めた参加者に撮影した異性の写真を見せ、顔の魅力度を評価させたといいます。その結果、精製炭水化物を使った朝食を取った人は、顔の魅力度が低くなることが男女ともに示されたそうです。食生活に関するアンケートから、精製炭水化物を習慣的に摂取する人も、低評価を受けたといいます。Medical Xpressの記事です。

世界保健機関(WHO)が、昨年から今年にかけて欧州で「オウム病」患者が増えているとして注意を呼びかけたそうです。オウム病は、クラミジア属の細菌が感染することによって発症する呼吸疾患です。感染した鳥の排泄物や分泌物を介してヒトうつります。症状は頭痛、筋肉痛、せき、発熱、悪寒などで、抗菌薬で治療することができ、死に至ることはまれだといいます。欧州では昨年から患者が急増し、スウェーデンで感染者39人、デンマークで23人(うち4人死亡)、オランダで21人(うち1人死亡)、ドイツで19人、オーストリア18人――が確認されているといいます。CNNの記事です。
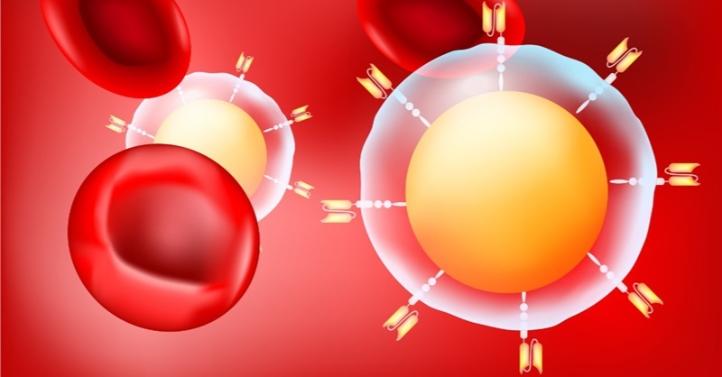
がん治療の新たな選択肢として注目されている「CAR-T細胞療法」。現在は血液がんの治療として使われていますが、固形がんを含むさまざまながんの治療に有効であることが明らかになっています。イタリアの研究チームは、小児神経芽腫の痕跡が消失したことを報告しています。また、米国の研究チームが、がんを直接攻撃しない新しいCAR-T細胞療法を開発し、マウスの実験で、卵巣や肺、すい臓のがんを縮小させることに成功したといいます。さらに、若返りや老化防止に効果があるという驚きの報告も出ています。マイナビRESIDENTの記事です。

神経細胞間のつなぎ目「シナプス」の主要なタンパク質である「PSD-95」が、アルツハイマー病(AD)の早期診断や治療の鍵になる可能性があるようです。米国の研究チームが、培養した神経細胞や、ADの一般的な兆候が現れる前の若いマウスを使って調査。PSD-95の増加が、AD初期の患者に見られる脳内の過剰興奮やてんかん発作を起こりやすくすることが示されたそうです。PSD-95を阻害したマウスは、過剰興奮やてんかん発作の回数が減ったといいます。また、PSD-95の増加が最初期ADのバイオマーカーになるとのことです。Medical Xpressの記事です。
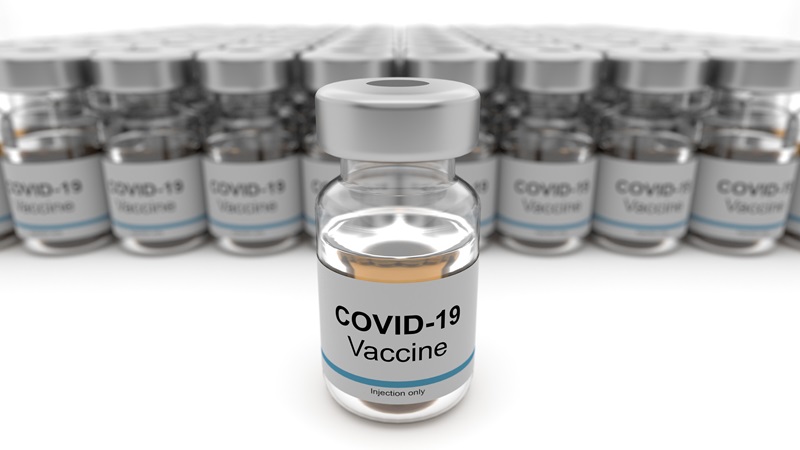
2年5カ月の間に新型コロナウイルスワクチンを217回も接種した人がいるそうです。62歳のドイツ人男性で、個人的に購入して接種したといいます。この男性の存在を知った同国の研究チームが、男性の血液や唾液を分析したそうです。度重なる接種で免疫系が過剰に刺激され、特定の細胞が疲弊することが懸念されますが、男性にはそのような痕跡は見つからなかったそうです。また、男性が新型コロナに感染した形跡もなかったとのことです。言うまでもないことですが、研究者は「過剰接種は推奨されるものではない」としています。BBCの記事です。

心筋症のため17歳の時に心臓移植手術を受けたオランダ人男性が、現在57歳になっているそうです。男性が心臓を移植されたのは1987年6月。当時はオランダで心臓移植手術が行われていなかったため、英国で手術を受けたそうです。それから39年100日生き延びたとして、ギネス記録に認定されたといいます。これまでの世界記録は、カナダ人が持つ34年359日だったといいます。男性の主治医によると、心臓移植を受けた患者の平均余命は16年だそうです。男性は心臓の薬による副作用の影響で近年は動作が緩慢になっているものの、現在も健康に日常生活を送っているとのことです。CNNの記事です。

ウゴービやオゼンピックの商品名で知られ、肥満症治療の効果で注目されている持続性GLP-1受容体作動薬「セマグルチド」が、アルコール依存の低減に有効だとの事例が多数報告されているようです。その中の一人、米バージニア州に住む38歳の女性は、減量のためにセマグルチドを服用し始めたそうです。7カ月で約20kg減量し、アルコール摂取量は75%減ったそうです。女性は、薬を服用している間はアルコールへの欲求が減ったと話しているとのことです。現在米国の研究チームなどが、セマグルチドが飲酒欲求を減らすのに有効かどうかを調べる臨床試験を複数行っているといいます。CBS Newsの記事です。

韓国政府の医学部増員計画に反発して研修医がストライキを起こしている問題で、韓国政府は4日、ストライキ終了を求める命令に従わなかった数千人の医師免許を停止する手続きに入ったそうです。政府は2月、医学部入学者数を現在の3058 人から2000人増員することを発表したといいます。これに反対した約9000人の研修医が、2週間にわたり職場を離脱しているとのことです。政府は繰り返し職場復帰を求めてきましたが、それに応じた研修医はわずかだったそうです。ストを続けた研修医には少なくとも3カ月の免停処分が科される見通しです。免停が実際に発効するまでには数週間かかるといいます。AP通信の記事です。

米疾病対策センター(CDC)は、新型コロナウイルス感染者の隔離に関するガイドラインの見直しを決めたそうです。これまでCDCは、新型コロナ感染者に対して5日間の自宅待機を推奨。しかし今後は、一般的な呼吸器系ウイルスと同様の扱いに変更するといいます。具体的には、症状が改善し、解熱剤なしで24時間以上発熱がなかった場合は日常生活の再開が可能になります。その後5日間は、マスクの着用や手洗い、人との距離の確保、換気をするなどして感染を広げない行動を求めるといいます。この見直しについては、公衆衛生の専門家から「新しいデータに基づいていない」などの批判が上がっているそうです。nprの記事です。

韓国政府による大学医学部の定員拡大方針に反発して、9000人近い研修医が辞表を提出してストライキを起こしている問題で、研修医への支持を表明する医師らが3日、大規模なデモをソウル市内で行ったそうです。政府が、ストを続ける研修医に対する医師免許の停止措置について言及したことがきっかけだといいます。また警察は、研修医のストを扇動・教唆したとして、大韓医師協会の幹部5人を捜査しているとのことです。なお、医師らの行動は国民の支持を得ておらず、国民の多数が「定員拡大」に賛成しているそうです。AP通信の記事です。

米国で昨年承認された60歳以上向けの2種類のRSウイルス(RSV)ワクチンが、「ギラン・バレー症候群(GBS)」をまれに引き起こす可能性があると指摘されているようです。GBSは、免疫システムが自分の末梢神経を障害し、手足のまひなどが起こる疾患です。米国では、すでに950万人がRSVワクチンを接種。その中で、20件以上のGBSが確認されているそうです。割合は非常に低いものの、想定より多い報告数だといいます。これを受けて米保健当局は、RSVワクチンがGBSと関連があるのかを詳しく調査中とのことです。AP通信の記事です。

大麻は摂取の方法に関わらず、心臓病や脳卒中のリスクを高める可能性があるようです。米国の研究チームが、18~74歳の成人43万人分のデータを分析。毎日大麻を使用する人は、全く使用しない人に比べて心臓発作リスクが25%、脳卒中リスクが42%高くなることが分かったといいます。大麻の使用量が多いほど、有害な影響を与えるリスクも上昇したそうです。喫煙による摂取だけでなく、食用大麻や蒸気による摂取も同様とのこと。大麻による心血管への影響は、タバコとそれほど変わらないということも示されたといいます。CBS Newsの記事です。

勃起不全(ED)治療薬として有名な「バイアグラ(一般名シルデナフィル)」は元々、狭心症や高血圧の治療薬として開発が進められていたことが知られています。ED改善は、その中での思わぬ効果だったそうです。今、バイアグラなどのED治療薬について、新たな「思わぬ効果」が報告されています。アルツハイマー病の発症リスクの抑制や、化学療法耐性の食道がんの治療に有効だというのです。一方で、ED治療薬は深刻な眼疾患を招いたり、大動脈瘤悪化の可能性があったりすることが指摘されています。マイナビRESIDENTの記事です。

公立の病院を民営化すると、医療の質は向上するのか――。その問いに対する一つの答えが出たようです。英国の研究チームが、高所得国を対象に公営から私営になった医療機関の質を評価した13の研究を分析。病院の民営化は、概して医療の質を低下させることが分かったといいます。民営化が患者の病状に好影響を及ぼすことを明確に示した研究はなかったといいます。それどころか、民営化した病院では、清掃スタッフの減少や院内感染の増加などがみられたとのこと。Medical Xpressの記事です。

有名投資家の未亡人(93)が、自身が理事長を務める米ニューヨーク市のアルバート・アインシュタイン医科大学に10億ドル(約1500億円)を寄付したそうです。これを受け大学は、全学生の授業料を無償化する予定だといいます。同大は米ニューヨーク市の低所得地域にあるそうです。現在の同大の授業料は年間6万3000ドルで、多くの学生は返済に何十年もかかるような借金を抱えて卒業するとのことです。今回の無償化が、移民など多様な志願者の呼び込みにつながることが期待されるといいます。なお、寄付金の運用により、同大の授業料無償化は永続するとみられています。AP通信の記事です。

1カ月に連続5日間だけ食事を制限して、体を断食時と似た状態にするダイエット法「断食模倣食(FMD)」は、健康に有益なようです。米国の研究チームが、18~70歳の男女を対象に2件の臨床試験を実施。FMDを実践する人、通常の食事を取る人、地中海食を取る人に分けて比較したそうです。FMD実践者は、食事制限の5日間は野菜中心のスープなどを食べ、その生活を3~4カ月継続。その結果、FMD実践者は、その他のグループと比べて、免疫系の加齢や糖尿病、脂肪肝の兆候が低減したそうです。また、生物学的年齢も実年齢より平均2.5歳若くなったといいます。Medical Xpressの記事です。

日本や韓国、中国などに自生する「チョウセンゴミシ(朝鮮五味子)」の果実の成分が、大腸がんに有効なことが分かったそうです。果実に含まれるポリフェノールの一種「シサンドリンB(SchB)」は肝臓がん、乳がん、卵巣がん、胃がん、胆のうがんに対して抗がん作用があることが知られているといいます。チームが大腸がんについて調査したところ、さまざまなステージの大腸がんに抗がん効果を発揮することが判明。特に、末期の大腸がんに高い有効性が確認されたといいます。その上、正常な細胞に対する毒性は非常に低かったとのこと。Medical Xpressの記事です。

アルツハイマー病(AD)患者の脳には、どのような流れで変化が起こるのでしょうか。中国の研究チームが、ADと診断された中高年648人と認知的に健康な中高年648人について、脳脊髄液や脳画像の20年間にわたる定期検査の記録を比較したそうです。AD患者は、診断の18年前の時点で髄液中のAD関連タンパク質アミロイドβのレベルが高かったといいます。それに続いて、神経細胞におけるタウタンパク質の異常な蓄積が起こり、神経細胞の伝達不良が出現したとのことです。その数年後に、脳萎縮と認知機能低下が認められたといいます。AP通信の記事です。

韓国政府は26日、医学部増員計画に反発して研修医約9000人が起こしているストライキについて、4日以内に復職しなければ医師免許停止などの法的措置を講じると警告したようです。29日までに復職すれば、処分は求めない方針。ストの影響で、手術や治療の中止が多発しているそうです。政府は公立医療施設の診療時間を延長するなどして医療の安定を図っていますが、急患がたらい回しの末に死亡する事例も起きているといいます。スト参加者は「計画している数の新入生を大学は受け入れられない」「この計画では慢性的な医師不足を解消できない」と主張しているとのこと。AP通信の記事です。

乳がんのリスクが高い女性に対して、リスク低減乳房切除(RRM)を推奨することを検討するべきかもしれません。カナダの研究チームが、乳がんリスクを高めるとされるBRCA1またはBRCA2遺伝子の変異を持つがん患者ではない1600人を6年にわたり追跡調査したそうです。このうち半数がRRMを受けたといいます。調査終了時点で乳がんを発症したのは、RRMを受けた群が20人、受けなかった群は100人。RRMが乳がん発症リスクを80%抑制することが示されたそうです。また、RRMを受けてから15年以内に乳がんで死亡する確率は1%未満だったとのことです。Medical Xpressの記事です。

ドイツで早ければ4月から、公共の場での大麻の使用が合法化される見込みです。ドイツ連邦議会が23日、娯楽目的での大麻使用・栽培を認める法案を可決。闇市場の取り締まりや汚染された大麻から使用者を守ることが目的だといいます。法案によると、18歳以上の成人は公共の場で25g、自宅では50gまで大麻の所持が可能になります。1世帯あたり3株まで大麻栽培も認められます。大麻の購入に関しては厳しいルールを設ける予定で、非営利の会員制「大麻クラブ」に所属するメンバーのみが入手できるといいます。一方で、医療関係者などは強く反対しているようです。BBCの記事です。

米食品医薬品局(FDA)は、皮膚に刺さずに血糖値を測定するスマートウォッチやスマートリングを使用しないよう警告を発したそうです。こうした機器をFDAは承認しておらず、血糖値の不正確な測定や命を脅かす誤った糖尿病管理につながる恐れがあるとしています。FDAは消費者に対し、「非侵襲的技術」は血糖値を直接検査するものではないため、購入しないよう呼びかけたといいます。また、医療機関に対しては、未承認の機器を使うことのリスクを患者と話すよう求めたそうです。なお、FDAはこうした機器が原因で起きた有害事象の情報収集を行っているといいます。CNNの記事です。

喫煙が健康に与える深刻な影響が、また一つ明らかになりました。フランスの研究チームが、20~69歳の健康な男女1000人の血液検体を細菌やウイルスに暴露させ、免疫応答を評価したそうです。その結果、生活習慣や食生活、遺伝的性質など136の条件のうち、喫煙が免疫応答に最も悪影響を及ぼすことが分かったとのこと。禁煙をすると免疫応答はある程度改善するものの、完全に回復するには数年かかったといいます。特に、リンパ球のT細胞やB細胞が関与し特定の病原体に対する強力な「適応免疫」への影響が長く続いたそうです。CNNの記事です。
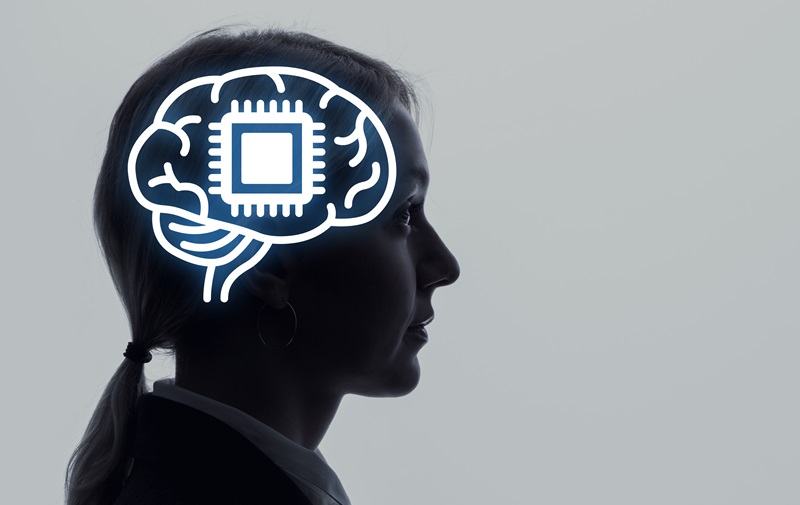
米起業家イーロン・マスク氏のニューラリンク社が1月、脳インプラントの臨床試験を開始したと発表しました。マスク氏はまず、視力回復▽筋肉を動かせない人による電子機器の操作▽首を骨折した人の脳の信号を脊髄に送達――を実現したいと考えているようです。同社が手がけるもの以外にも、脳インプラントの研究は進んでいます。話すことができなくなった人が脳波で文字を入力したり、念ずることでアバターが発話したり。まひの男性が100m歩けるようになったとの研究発表や、強迫性障害とてんかんを改善した女性がいるとの報告もあります。マイナビRESIDENTの記事です。

口唇ヘルペスの原因「単純ヘルペスウイルス1型(HSV-1)」の感染歴が、認知症発症の危険因子である可能性が示されたそうです。スウェーデンの研究チームが、70歳の認知症ではない1002人を15年にわたって追跡調査した結果です。対象者の82%がHSV-1抗体を保有していた(感染歴があった)そうです。そして、HSV-1抗体を持つ人は、そうでない人に比べて追跡期間中に認知症を発症するリスクが2倍高かったといいます。こうした関連性は、認知症の危険因子とされるAPOE4遺伝子や年齢に関係なく認められたとのこと。Science Alertの記事です。

「ナイアシン(ビタミンB3)」は代謝やエネルギー産生、DNAの修復・合成などに関わる重要な物質です。しかし、取り過ぎには注意が必要なようです。米国の研究チームが、心臓病患者 3163人のデータを分析。ナイアシンが過剰な場合に分解産物「4PY」が作られ、血中にこれが見つかると心臓発作や脳卒中のリスクが高まることが明らかになったそうです。マウスに4PYを注入して調べたところ、血管の炎症が増加することも示されたといいます。ナイアシンはシリアルやパン、魚や肉などに多く含まれており、米国人の4人に1人が推奨量より多く摂取しているそうです。NBC Newsの記事です。


血液がんの治療で注目を集めている「キメラ抗原受容体(CAR)-T細胞」が、若さの維持にも有効な可能性があるそうです。米国の研究チームが、体に蓄積して有害な炎症を引き起こす老化細胞に着目。白血球の一種であるT細胞に遺伝子改変を行い、老化細胞を除去できるCAR-T細胞を作製しといいます。これをマウスに投与したところ、肥満や糖尿病など老化に関連する疾患が抑制されたのだそうです。そして、高齢マウスは若返り、若いマウスは老化スピードが遅くなったといいます。CAR-T細胞をたった一回投与するだけで、その効果は生涯にわたって続いたとのことです。Science Dailyの記事です。
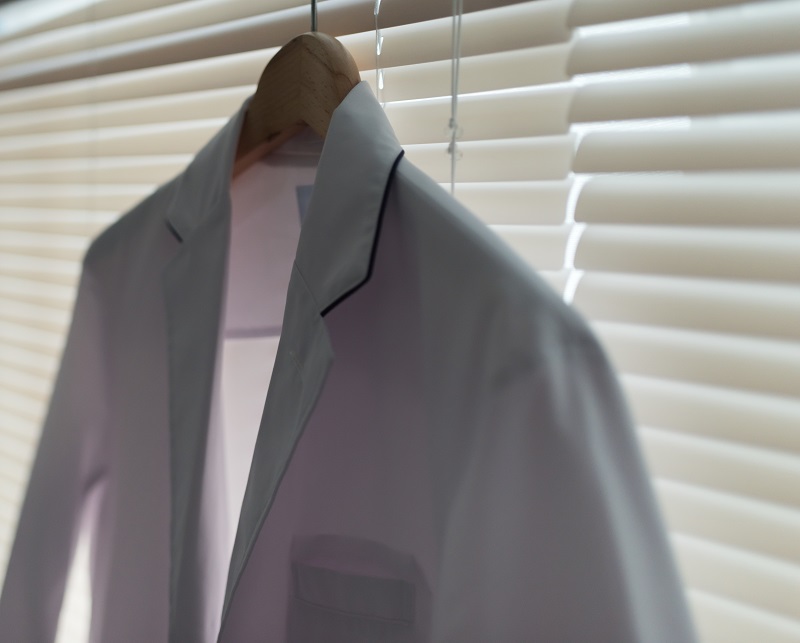
韓国政府が医師不足の対応策として、来年度以降の医学部入学定員を2000人増やすという方針を示し、医師側から医療の質の低下につながるとして大反発が起きているそうです。韓国の5大病院に勤務する研修医らが19日、一斉に退職届を提出したといいます。20日からは、各自の持ち場を離れる予定だとのことです。他の病院でも数百人の研修医が退職届を提出しており、一部で手術や治療に遅れが生じているそうです。政府は研修医に勤務の継続を要求しているといいます。政府は急患に対応するため、状況に応じて軍医を投入する用意をしているとのことです。AP通信の記事です。

うつ病の人は記憶を思い出すのが困難であることが知られています。うつ病の人が過去の具体的な出来事を思い出すのに、「匂い」が役立つかもしれません。米国の研究チームが、成人うつ病患者32人を対象に調査を実施。24種類の匂いを嗅がせ、それらに関連する過去の記憶を呼び起こしてもらったそうです。すると参加者の68%が、匂いに応じて過去の具体的な出来事を思い出すことができたといいます。参加者にそれぞれの匂いを表す言葉を説明してみたところ、52%が過去の出来事を思い出したものの、匂いを嗅いだ場合よりも不鮮明だったとのこと。NBC Newsの記事です。

米食品医薬品局(FDA)が2月16日、米バイオテクノロジー企業Iovance Biotherapeuticsが開発した転移性の悪性黒色腫(メラノーマ)に対する初の細胞療法「Amtagvi」を承認したそうです。AmtagviはTIL(腫瘍浸潤リンパ球)療法と呼ばれるもので、患者自身の免疫細胞・T細胞(TIL)を利用し、がんを破壊します。1回の治療で少なくとも数年間効果が続くといいます。メラノーマ患者73人を対象とした臨床試験では、Amtagviの効果があった人(客観的奏効率)は31.5%だったそうです。このうち43.5%で、12カ月が経過した時点まで腫瘍の進行や死亡が発生することなく効果が持続したといいます。CNNの記事です。

喘息治療薬「ゾレア(一般名:オマリズマブ)」が、食物アレルギー患者のアレルギー反応を減らす目的での使用について、米食品医薬品局(FDA)から2月16日に承認されたそうです。対象は1歳以上の患者で、2~4週間に1回、注射で投与。ピーナッツアレルギー患者を対象とした臨床試験では、ゾレアを投与された群の68%がティースプーン半量のピーナッツタンパク質に耐えられるようになったのに対し、プラセボ群は6%だったといいます。ナッツや牛乳、卵、小麦についても同様の結果が出たそうです。ただし、ゾレアでの治療自体がアナフィラキシーを起こすことがあり注意が必要とのこと。AP通信の記事です。

多くの人がうつ症状に苦しんでいます。症状の抑制に効果がある食品や、逆に症状を進行させる食品の研究が進んでいます。キウイやヨーグルトはうつ治療に効果があり、ビタミンB6サプリメントは気持ちを落ち着かせるそうです。一方で、インスタント食品やスナック菓子、炭酸飲料などの超加工食品は、特に女性のうつ病リスクを高めるといいます。揚げ物もリスクを高め、特にフライドポテトが悪いそうです。そして、うつ予防に効果があると考えられていたオメガ3サプリは、実は効果がないことが分かったといいます。マイナビRESIDENTの記事です。

呼吸器感染症後に長引くせきは、ほとんどの場合、時間がたてば改善するそうです。カナダの研究チームが、感染症後のせきに関する重要ポイントをまとめています。まず、こうしたせきは、呼吸器感染症を患った成人の11~25%が経験するそうです。ただし、8週間を超えて続くせきは注意が必要で、嚥下困難や過度の息切れ、喀血などの症状、肺炎の再発歴や長期にわたる喫煙歴がある場合は追加の検査や評価をしなくてはならないとしています。また、長引くせきに使われている吸入薬や経口薬は、ほとんど効果がなく副作用もあることを知っておくべきだとのこと。EurekAlert!の記事です。

うつ病と体温には奇妙な関連性があるそうです。米国の研究チームが、世界106カ国の2万880人から7カ月にわたって収集したデータを分析。うつ症状(自己申告)が深刻になるほど、平均体温が高くなることが明らかになったそうです。ただし、うつ病が体温を上昇させるのか、体温上昇がうつ病の原因になるのかは不明とのこと。また、サウナなどがうつ症状を軽くするという研究報告があるそうです。これは、発汗による自己冷却で体温が下がることが理由の可能性があるそうです。冷水を浴びるよりもサウナなどの方が体温が下がり、その状態が長く続くといいます。Science Alertの記事です。

雷が頭に落ちたとき、頭皮が雨水で濡れていると生存率が高くなるそうです。ドイツの研究チームが、ヒトの頭皮、頭蓋骨、脳の頭部モデルを作製して実験を行ったといいます。この「頭部」はヒトの組織の電気伝導性(電気の通りやすさ)が再現されているとのこと。チームは、乾燥した状態の「頭部」と人工の雨水で濡らした「頭部」に、雷を模した電流を流したそうです。雨水で濡れている頭部の方が、濡れていない頭部に比べて落雷による傷(穿孔)や深刻な損傷部位が少なかったといいます。さらに、頭部が濡れているほうが、脳に届く電流強度も低かったとのことです。Medical Xpressの記事です。

南アジアの人は、白人に比べて若いうちから心血管疾患を患うリスクが高いそうです。カナダなどの研究チームがその理由を明らかにしたようです。チームは、南アジア系だと自認する成人60人と欧州系の白人60人の血液細胞を比較。参加者はみな、心血管疾患か糖尿病のどちらかを患っている上、心臓病の危険因子を一つ以上持っていました。その結果、南アジア人は、白人に比べて血管の修復や再生に必要な幹細胞が非常に少ないことが示されたといいます。南アジアはインド、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ブータン、モルディブで構成される地域です。CBCの記事です。

11月の米大統領選で再選を目指すバイデン大統領(81)の認知力に、注目が集まっているようです。きっかけは、バイデン氏が機密文書を自宅に持ち出した問題についての報告書です。検察当局は訴追しないと結論付け、「(バイデン氏は)高齢で記憶力が乏しい」と指摘したそうです。ただ、複数の医師によると、過去の日付や時系列を忘れただけでは、認知機能や意思決定などのレベルの判断はできないといいます。その瞬間の記憶力や認知力に影響を与える要因は多岐にわたり、特にプレッシャーがかかる状況ではこうした能力が損なわれることがあるそうです。ABC Newsの記事です。

米オレゴン州デシューツ郡で、8年ぶりにペスト患者が確認されたそうです。ペストは通常、ペスト菌を持つネズミなどからノミを介してヒトに感染します。家庭のペットも同様のルートで感染することがあり、そのペットの飛沫などからヒトに感染することもあるそうです。特に猫はネズミを追いかける習性がある上、体質的にペスト菌を除去するのが難しいといいます。今回の患者については、飼い猫から感染した可能性が指摘されています。患者はリンパ節が腫れる「腺ペスト」から始まり、血液まで感染が拡大したそうです。幸い抗菌薬がよく効いているといいます。NBC Newsの記事です。

アレルギー治療の新たな標的が見つかったかもしれません。カナダとデンマークの研究チームが、新たなタイプの免疫細胞「2型メモリーB細胞(MBC2)」を発見したそうです。チームは、花粉などのアレルゲンから蛍光分子の一種(四量体)を作製したり、舌下免疫療法臨床試験の検体を活用したりすることで、MBC2とアレルギー反応を引き起こすIgE抗体が直接関連することを明らかにしたそうです。MBC2がアレルギーであることを記憶し、アレルゲンに遭遇するとIgE抗体を多く産生するといいます。Medical Xpressの記事です。

低い声で話すと、他人に良い印象を与えられるそうです。米国の研究チームが、男女2人ずつに同じ文章を読んでもらい、その音声記録を編集して、それぞれについて声の高さが「高い」「平均的」「低い」の3パターンを作成したといいます。これを世界22カ国の男女計3100人に聞かせたそうです。そして、長期的な関係を築く相手として魅力に感じる声を尋ねたところ、男女ともに「低い声」と答えたといいます。また、低い声の男性は、他の男性に怖く威厳がある印象を与えることも分かったとのことです。Science Dailyの記事です。

私たちの身の回りには、たくさんの健康リスクが潜んでいるようです。豪州の首都圏では、薪ストーブの影響で年間63人が死亡している可能性があるそうです。また、シンガポールの研究チームが、現在の「たばこ規制」がなければ、副流煙などで2万人以上が心臓発作を起こしていたとの推計を発表しています。健康への影響は今のところ分かってはいませんが、ペットボトル飲料水には大量の微小なプラスチック片が入っているといいます。そして、飲食物に残る殺虫剤は精子濃度を低下させるとの報告もあります。マイナビRESIDENTの記事です。
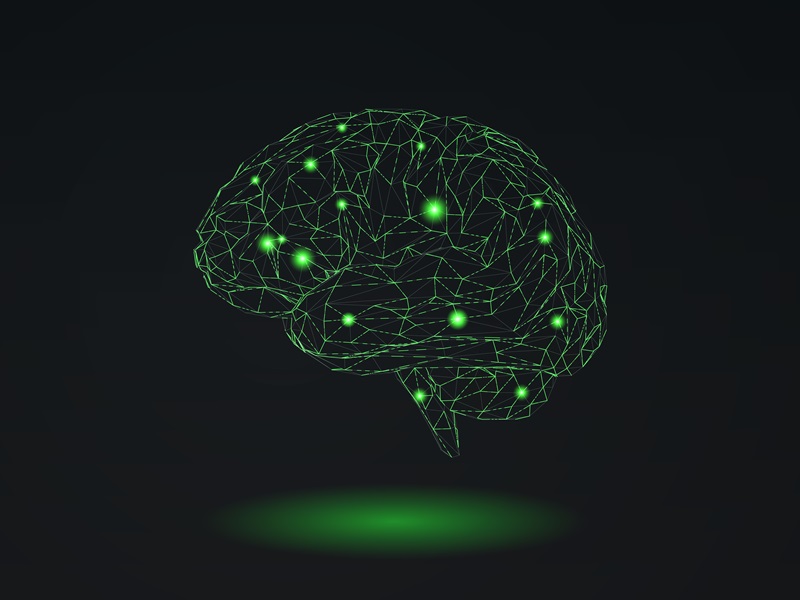
原因不明の脳卒中患者が再度脳卒中を起こすのを防ぐために、抗凝固薬が使われることがよくあるといいます。米国の研究チームが、これを「やめるべき」とする研究結果を発表したようです。チームは、原因不明の脳卒中を起こし「心房心臓病(atrial cardiopathy)」の兆候がある患者1015人を調査しました。標準治療である「アスピリン」を使用した群と、それよりもリスクがある抗凝固薬「アピキサバン」を使用した群との脳卒中再発率は共に4.4%だったそうです。心房心臓病は心房細動(AF)に似ているため、AF向けの抗凝固薬が使われることが多いといいます。Medical Xpressの記事です。

バイアグラなどの勃起不全(ED)治療薬を使用している男性は、アルツハイマー病(AD)を発症するリスクが18%低くなることが分かったそうです。英国の研究チームが、ED患者26万人の処方データを分析し、5年間の追跡調査を実施。その結果、1万人年あたりのAD発生数は、ED治療薬を処方されていた群が8.1人だったのに対し、こうした薬を処方されていない群は9.7人だったそうです。AD発症リスクが一番低かったのは、ED治療薬を最も多く処方されていた群だったといいます。研究者は、血流の増加の影響や、薬が神経細胞に直接作用した可能性があるとみています。BBCの記事です。
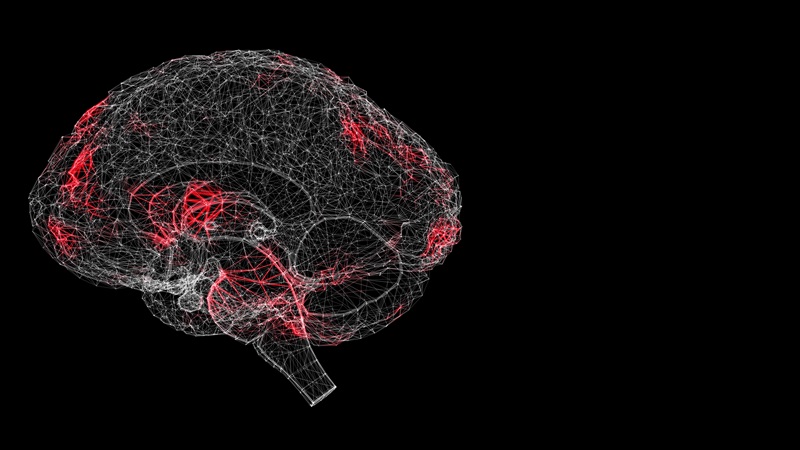
ジカウイルスや新型コロナウイルスなどに感染すると、神経損傷が起きやすいことが知られています。カナダの研究チームが、これはウイルスそのものが原因ではなく、免疫系に問題があることを突き止めたそうです。チームは、ジカウイルスに感染させたマウスを使って調査を実施。その結果、免疫細胞・T細胞の中の「NKG2D+CD8+T細胞」が、ジカウイルスに感染していない細胞を大量に死滅させていることが明らかになったといいます。この攻撃的な免疫応答が脳内で起こると、神経疾患につながる可能性があるとのことです。Medical Xpressの記事です。

楽器の演奏や合唱などの音楽経験は、後の認知機能にどのような影響を及ぼすのでしょうか。英国の研究チームが、主に女性の中高年に音楽経験に関するアンケートと認知テストを実施。楽器の演奏経験がある人は、そうでない人に比べて記憶力と実行機能(計画を立てて目的を達成する能力)が優れていたそうです。特に今も楽器を演奏している人は、最も高い認知能力を示したといいます。合唱の経験者は、実行機能のみ優れていたとのこと。なお、音楽鑑賞と認知機能の間に関連性は見いだせず、「モーツァルト効果」は誤りのようです。The Conversationの記事です。

フランスの研究チームが、北極圏の永久凍土に眠る数十万年前の「ゾンビウイルス」を複数見つけたそうです。これらのウイルスは培養細胞に感染できることが分かり、研究者は次のパンデミックを引き起こすかもしれないと警戒を呼び掛けています。チームは、シベリアの異なる7カ所で採取した永久凍土を調査し、ゾンビウイルスを発見。温暖化や採掘作業の影響で、こうしたウイルスが現代に蘇る可能性があるといいます。北極ではそのような場合に備えて、隔離施設の整備や専門家の派遣が計画されているとのことです。Medical Briefの記事です。

がん細胞の増殖を促すタンパク質「CDK9」を阻害する経口新薬「CDDD11-8」が、予後不良で知られる「トリプルネガティブ乳がん(TNBC)」に対する前臨床試験で有望な結果を示したようです。豪州の研究チームが、TNBC患者から採取した組織を使って調査をしました。その結果、CDDD11-8がTNBCの増殖を効果的に抑制することが示されたそうです。その上、この薬は乳房組織の正常な細胞には影響を及ばさないことも明らかになったといいます。CDDD11-8は当初、急性骨髄性白血病向けに開発されたのだそうです。Medical Xpressの記事です。

てんかんと強迫性障害(OCD)に苦しんでいた34歳の女性が幸せを取り戻したそうです。米国の研究チームが、この女性のてんかん発作を治療するために32mmの小型装置を脳に埋め込む手術を実施。その際、OCDの症状が出た時に起こる、脳内の特定の信号に反応するプログラムもこの装置に追加したそうです。手術から8カ月後、女性が10代から悩まされ続けていたOCDによる1日8~9時間の執拗な手洗いや施錠の確認などの「儀式行為」が徐々に減り始め、現在は通常の生活を送れるようになったといいます。Medical Xpressの記事です。

大気汚染物質の「二酸化窒素(NO2)」や「微小粒子状物質(PM2.5)」が、健康な人の肺にどのようにダメージを与えるかが明らかになったようです。英国の研究チームが、肺の複数の細胞を使い、ガス交換や肺胞の構造維持の役割を担う肺深部の「肺胞上皮」を体外で再現。これをNO2やPM2.5に暴露させ、肺への影響を調査したそうです。NO2とPM2.5に同時に暴露させた場合と別々に暴露させた場合を調べたところ、NO2とPM2.5が連携して肺の深部の重要な細胞に損傷を与える可能性が示されたとのことです。The Conversationの記事です。

2022年にがんと診断された患者は世界に2000万人おり、50年には77%増の3500万人に達する可能性があるそうです。世界保健機関(WHO)が、世界185カ国、36種類のがんを対象にした調査結果を公表しました。22年に最も患者数が多かったのは肺がんで、全体の12.4%に当たる250万人だったそうです。患者数は、女性の乳がん、大腸がん、前立腺がん、胃がんが肺がんに続くといいます。死者数も肺がんが最も多く、全体の19%にあたる180万人だったとのこと。がんの治療や検査について、先進国と発展途上国で深刻な格差が生じていることも指摘されています。CNNの記事です。

距離感がなくなったり物体が認識できなくなったりするなど、視空間認知に支障をきたす「後部皮質萎縮症(PCA)」が、アルツハイマー病(AD)と密接に関連していることが分かったそうです。米国などの研究チームが、PCA患者1092人のデータを分析。患者の94%で明らかにADに関連する脳の変化が確認され、PCAがADの強力な予測因子であることが示されたといいます。PCA患者は、視空間情報の処理に関与する脳の後部に、ADに関連するとされるタンパク質タウの病変が多く存在することも判明。研究者は、これが治療のヒントになる可能性があるとしています。ScienceAlertの記事です。

メンタルヘルスの向上には、ビタミンCが豊富なことで知られるキウイフルーツが有効かもしれません。ビタミンCの不足は、うつ病の増加や認知障害と関連しているそうです。ニュージーランドの研究チームが、ビタミンC不足の成人155人に8週間の調査を実施。キウイフルーツを1日2個ずつ毎日食べると、4日以内に気分や活力が向上することが分かったそうです。この効果は14~16日後にピークに達するといいます。ビタミンCサプリメントの摂取も有効ではあったものの、キウイフルーツの方が効果が高かったとのこと。Neuroscience Newsの記事です。

米製薬大手バイオジェンは、2021年に米食品医薬品局(FDA)の迅速承認を得たアルツハイマー病(AD)治療薬「アデュヘルム(一般名アデュカヌマブ)」の販売を中止するそうです。正式承認のために必要な追加の研究も打ち切るといいます。同薬は有効性を示す証拠に乏しく、商業化に苦戦していたそうです。同社は今後、日本のエーザイと共同開発し、すでにFDAの正式承認を得ているAD治療薬「レケンビ(一般名レカネマブ)」などに注力するといいます。アデュヘルムは世界で約2500人が使用しており、11月までは継続使用できるとのこと。AP通信の記事です。

米国の起業家のイーロン・マスク氏が率いるニューラリンク社が、手術で人の脳に小型の装置を埋め込み、コンピューターに直接つなぐ臨床試験を開始したそうです。マスク氏は詳細を明らかにしていませんが、患者の経過は良好だとしています。同社は、脳卒中などで体が不自由な患者の自律性を回復させることを目標に、「ブレーン・マシン・インターフェース(BMI)」を開発しているそうです。BMIは脳に埋め込んだ装置が神経活動を読み取ることで、患者が頭の中で考えるだけでコンピューターやスマートフォンを操作できる技術です。ABC Newsの記事です。
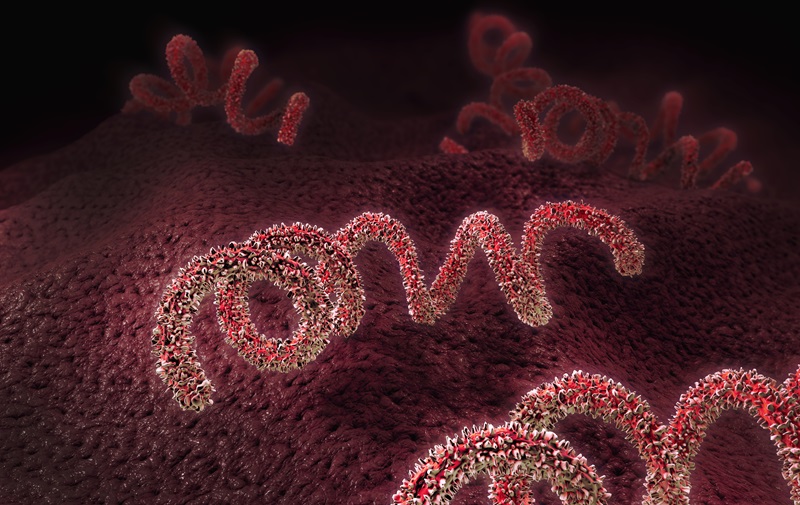
米疾病対策センター(CDC)は、米国における2022年の性感染症に関する報告書を公表しました。22年に報告された梅毒の全患者数は 20万7000人を超え、前年より17%増加したそうです。梅毒患者数は1950年以来最多を記録したとのこと。梅毒は異性愛者の患者も増えているといいます。異性愛者には通常あまり検査が行われないため、気づかないうちに感染が広がっている可能性が指摘されています。胎盤を通して梅毒が母子感染する先天梅毒も増えているとのこと。一方、淋病は前年より9%減少し、クラミジアは横ばいだったそうです。AP通信の記事です。

ペットは高齢者の認知症リスクにどのように影響するのでしょうか。東京都健康長寿医療センターが、 国内の65~84歳(平均年齢74.2歳)の男女1万1194人を対象に4年間にわたる調査を実施したそうです。犬を飼っている人は、そうでない人に比べて認知症を発症するリスクが40%低いことが分かったといいます。犬の散歩で身体活動や社会的交流が増えることが、高齢者に好影響を及ぼす可能性があるとのこと。そのためか、猫を飼っている人については、認知症リスクが低くなるとの結果は示されなかったといいます。Asian Scientist Magazineの記事です。

死亡した人の下垂体から作った「ヒト成長ホルモン(c-hGH)」の投与が原因で、アルツハイマー病(AD)を発症した可能性のある人が見つかったそうです。英国の研究チームが、c-hGH関連とみられるAD患者5人を調査。患者はみな、子どもの時にAD関連タンパク質(アミロイドβ)に汚染されたc-hGHの投与を受けており、38~55歳で神経症状が始まったそうです。c-hGHは1980年代に使用が中止されています。研究者はこの発表について、同じ経路でのAD患者が新たに出ることはなく、ADが感染性であるという意味でもないとしています。BBCの記事です。

妊娠中の新型コロナウイルスワクチンの接種は、生まれたての子どもの呼吸困難リスクを抑制する効果があるようです。米国の研究チームが、妊娠中に新型コロナ陽性になった女性を追跡し、生まれた子ども199人を調査したそうです。チームは、母親が新型コロナに感染すると、胎児が炎症を起こしやすくなることを発見したといいます。ワクチン未接種だった母親の子どもは、母親がコロナ感染前にワクチン接種済みだった子どもに比べて出生時に呼吸困難を起こすリスクが3倍高いことが分かったとのことです。ABC Newsの記事です。

2022年に世界初の部分心臓移植を受けた乳児が順調に成長しているそうです。米国の研究チームが22年、本来二つある心臓出口の血管が一つしかない先天性心疾患「総動脈幹症」を持つ生後18日の乳児に、生体ドナーの乳児の心臓弁と血管を移植。1年以上経過した現在、心臓が大きくなるのに伴い、移植した組織も成長しているそうです。この方法は心臓全体の移植に比べて拒絶反応のリスクが低いだけでなく、子どもが大きくなるにつれて移植組織も成長するため、何度も手術をする必要がなくなるといいます。ScienceAlertの記事です。

新型コロナウイルス感染後に続く「後遺症」は、感染症などを契機に突然激しい倦怠感などに襲われる「筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)」の一つとして捉えることができるようです。ニュージーランドの研究チームが、コロナ感染から1年たった後も後遺症に苦しんでいる患者6人と、平均16年間ME/CFSに苦しんでいる患者9人の免疫細胞のタンパク質を分析したそうです。その結果、両群のデータは非常に似通っており、この2疾患が密接に関連していることが示されたといいます。研究者は、免疫反応や炎症経路を標的にした治療が有効な可能性があるとしています。Medical Xpressの記事です。

豪州の一部で近年、細菌による皮膚感染症「ブルーリ潰瘍」の患者が急増しているそうです。原因菌のM. ulceransが作る毒素によって皮膚に潰瘍ができ、治療が遅れると進行して体が変形してしまう病気です。豪州の研究チームが不明だった感染経路について、蚊の媒介によって感染した有袋類ポッサムからヒトにうつることを明らかにしたといいます。チームは、2016~21年にビクトリア州メルボルンで捕獲した蚊6万5000匹のゲノム解析を実施。その結果、2種類の蚊から見つかった細菌の遺伝子構造が、この地域でブルーリ潰瘍を発症した人のものと完全に一致したとのことです。ABC News(AUS)の記事です。

遺伝子治療で、生まれつき難聴の子どもが聞こえるようになったそうです。中国の研究チームが、オトフェリン遺伝子(OTOF)の変異による遺伝性難聴の子ども6人に遺伝子治療を実施。子どもたちは、内耳の有毛細胞で音の振動を電気信号に変換するために必要なタンパク質オトフェリンが作られない病気を持つそうです。手術は1回で、正常に機能する遺伝子のコピーを内耳に送り込んだといいます。5人は、完全に聞こえない状態から日常会話ができるレベルにまで聴力が改善したとのことです。AP通信の記事です。

欧州で昨年、麻疹(はしか)感染者が前年の45倍近くに急増し、世界保健機関(WHO)が警鐘を鳴らしたそうです。2022年は941人だった欧州の感染者が、23年には4万2200人に増加したといいます。これは、新型コロナ禍ではしかワクチンを受ける子どもが減少したことによるものだとみられています。19年 に96%だった欧州のはしかワクチン初回接種率は、22年には93%に低下。はしかのまん延を防ぐには、社会全体で子どもの95%が2回のワクチン接種を完了する必要があるといいます。BBCの記事です。

米国で、新型コロナウイルスやインフルエンザウイルスのまん延にともない、合併症として心血管疾患が増える可能性があると専門家が警鐘を鳴らしています。米国の心臓を専門とする医師が、呼吸器感染症が心血管に影響を及ぼす二つの経路を指摘。まず、発熱や脱水で心拍数が上昇するうえに、炎症によってできた血栓が心臓発作を引き起こす可能性があるそうです。もう一つの経路は心筋炎で、不整脈や心不全につながることもあるといいます。専門家は、胸痛や息切れがひどくなった場合は、基礎疾患や危険因子に関係なくすぐに受診する必要があるとしています。ABC Newsの記事です。

米食品医薬品局(FDA)は、白血病などの治療に使われる「キメラ抗原受容体T細胞療法(CAR-T療法)」が、逆にがんリスクを高める可能性があるとして、最も強い警告である「枠囲み警告」を製品情報に記載するよう複数の製薬会社に求めたそうです。今回の決定は、過去にCAR-T療法を受けた患者25人が血液がんを発症したとの報告などに基づくもの。ただ総合的には、CAR-T療法によるメリットの方がこうした潜在的リスクを上回るといいます。CAR-T療法は患者自身のT細胞を遺伝子改変して体内に注入するもので、主に血液がんの治療法として注目されています。NBC Newsの記事です。

アフリカ中部のカメルーンで、世界初となるマラリアワクチンの子どもへの定期接種プログラムが始まるそうです。ワクチンは、グラクソ・スミスクライン(GKS)社が開発した「Mosquirix(モスキリックス)」。アフリカでは年間約60万人がマラリアで死亡しており、そのほとんどが幼い子どもだそうです。このワクチンは4回の接種が必要で有効性はわずか30%。効果も数カ月で薄まるとのこと。しかしそれでも、重症化や入院が劇的に減る可能性があるといいます。AP通信の記事です。

禁酒の効果を侮ってはいけないようです。アルコールを飲み過ぎると肝臓に脂肪がたまり、悪化すると肝硬変に進行します。しかし脂肪肝については、2~3週間禁酒すると正常な状態に戻るそうです。また、飲酒量が多く肝臓がひどく損傷している場合でも、数年間禁酒をすれば肝不全の悪化や死を防げる可能性があるといいます。ただし、大量に飲酒していた人が突然禁酒すると、アルコール離脱症状が現れる危険性があるので、注意が必要とのことです。The Conversationの記事です。

韓国で、新型コロナのパンデミック後に自己免疫性の脱毛症が増加しているそうです。韓国の研究チームが、2020年10月~21年9月のデータを使い、コロナ患者25万9369人と同数のコロナ感染歴がない人を比較。その結果、コロナ感染歴がある人は、感染歴がない人に比べて円形脱毛症の発生率が82%高いことが明らかになったといいます。コロナ感染歴がある人の円形脱毛症発生率や有病率は、コロナ以前の数値と比べてもかなり高かったとのことです。研究者は、円形脱毛症とウイルス感染に関連があるとみているようです。Medical Briefの記事です。

患者自身の腫瘍細胞を使ってがんへの免疫を高めるメラノーマ向けがんワクチンが実現するかもしれません。米国のバイオテクノロジー企業が、腫瘍溶解物粒子のみを搭載した個別化ワクチン(TLPOワクチン)を開発。進行性メラノーマ(悪性黒色腫)患者数百人を対象に第2相試験を行ったそうです。その結果、TLPOワクチンのみを接種した患者の3年生存率は95%で、無病生存率は64%だったといいます。主な副反応は接種部位の痛みなどだったとのことです。今年中に500人規模の第3相試験が開始される予定だといいます。ABC Newsの記事です。

安全性が高いとされ、解熱や鎮痛のために妊婦にも使われる「アセトアミノフェン」。米国の研究チームによって、生まれた子どもの注意力に悪影響を及ぼす可能性があることが分かったそうです。チームは、300人以上の子どもを母親の妊娠中から追跡調査。妊娠中に6回、母親にアセトアミノフェンの使用量や時期を確認して記録したそうです。その結果、特に妊娠中期に使用量が増えると、子どもが2~4歳時点で、注意力の問題や注意欠陥・多動症(ADHD)のような行動が多く報告されることが明らかになったといいます。Medical Xpressの記事です。

B細胞性急性リンパ性白血病(B-ALL)に対する免疫療法薬「ブリナツモマブ」は、小児患者にも有効な可能性があるようです。英ロンドンの病院が、化学療法が効かず副作用もひどかった11歳のB-ALLの男児にブリナツモマブを使用。数カ月にわたる治療が完了した現在、がんは消滅しているそうです。同薬の静脈内投与に必要な機器一式はリュックで持ち運びが可能なため、患者は治療期間中も日常生活を送れるといいます。この薬は、がん細胞を免疫細胞のT細胞とくっつけて破壊する仕組みで、健康な細胞は影響を受けないとのこと。BBCの記事です。

米食品医薬品局(FDA)は、ほくろと皮膚がんを見分ける際に医師の助けとなる医療機器を承認したそうです。米医療機器メーカーDermaSensor社が開発した同じく「DermaSensor」という名のこの機器は、4000以上の良性または悪性皮膚病変のデータで訓練した人工知能(AI)アルゴリズムを搭載。医師が疑わしいと判断した皮膚病変にDermaSensorを押し当てると、専門家による検査が必要かどうかが即座に評価されるそうです。悪性黒色腫(メラノーマ)をはじめ、基底細胞がんや扁平上皮がんの検出に有効だといいます。CBS Newsの記事です。

米国で、若いうちに大腸がんと診断される人が増えているようです。米国がん協会(ACS)の調査で判明しました。かつて、大腸がんは50歳未満のがんによる死亡原因の第4位だったそうです。しかし近年は、この順位が男性で1位、女性で2位に上昇しているといいます。若い世代の大腸がんが増えている理由は不確かです。ただ、食事や抗菌薬の使用などの生活習慣の変化が、腸内細菌叢に影響を与えていることが要因として指摘されています。CBS Newsの記事です。

砂糖が加えられていない「果汁100%ジュース」を1日1杯(約240ml)以上飲むと、体重増加につながるようです。カナダの研究チームが、既存の42研究を分析。子どもにおいては、果汁100%ジュースを1日1杯多く飲むごとに、体格指数(BMI)値が0.03高くなることが分かったといいます。大人も、こうしたジュースを毎日飲むと体重増加に関連することが示されたそうです。特に11歳未満の子どもは影響を受けやすいといいます。米国小児科学会(AAP)と米疾病対策センター(CDC)は1歳未満は飲むべきではないとしているそうです。CBS Newsの記事です。

子どもにとっては、新型コロナやインフルエンザよりRSウイルス(RSV)感染症の方が危険かもしれません。スウェーデンの研究チームが、2021年8月~22年9月に同国の救急外来を受診した子ども2596人(新型コロナオミクロン株陽性者: 896人、インフルエンザA/B陽性者:426人、RSV陽性者:1274人)を調査。入院率はRSVが81.7%、オミクロン株が31.5%、インフルエンザが27.7%だったそうです。また、集中治療室(ICU)への入院率はRSVが2.9%で最も高く、インフルエンザは0.9%、オミクロン株は0.7%だったとのこと。ABC Newsの記事です。

寝不足による注意力低下をカフェインで改善したければ、普段はカフェイン摂取を控えめにした方がいいようです。フランスの研究チームが、18~55歳の睡眠障害の既往歴のない健康な参加者37人を調査したそうです。注意力の変化を評価する精神運動覚醒検査(PVT)を行ったところ、徹夜時にカフェインを取ると、みな注意力が改善したといいます。ただし、1日3杯以上のコーヒーに相当する量(300mg)のカフェインを普段から摂取している人は、普段のカフェイン摂取量が少ない人に比べて注意力の改善度合いが鈍かったとのことです。PsyPostの記事です。

豪州で、薪ストーブの使用を早急に禁止するべきとの声が高まっているようです。同国の研究チームが、オーストラリア首都特別地域(ACT)内の三つの研究所で、健康に悪影響を及ぼすことで知られる空気中の微小粒子状物質(PM2.5)量を測定。PM2.5は呼吸器系疾患の悪化や心臓発作、脳卒中、がんなどのリスクを高めるといわれています。分析の結果、厳冬の年にはACT内で年間最大43~63人が、薪ストーブの煙が原因で死亡している可能性が示されたそうです。薪は不完全燃焼を起こしやすく、その煙は特に人体に有害だといいます。ABC News(AUS)の記事です。

RSウイルス(RSV)の感染や重症化を予防するモノクローナル抗体製剤「nirsevimab(ニルセビマブ)」について、乳児に対する有効性が実世界環境でも明らかになったようです。英国などの研究チームが、英国、ドイツ、フランスの生後1歳までの健康な乳児計8058人を、RSV流行期前または流行期中にニルセビマブの筋肉注射を1回受ける群(4037人)と受けない群(4031人)に分けて調査。RSV感染症の重症化で入院したのは、注射を受けた群が11人(0.3%)だったのに対し、受けなかった群が60人(1.5%)だったそうです。ニルセビマブの有効性は83.2%であることが示されたといいます。Medical Briefの記事です。

シンガポールでは2013年に、住居区域の廊下や階段などの共用部分における喫煙が法律で禁止されました。非喫煙者が副流煙にさらされるのを防ぐことを目的としたこの規制は、市民にどのような健康上の恩恵をもたらしたのでしょうか。同国の研究チームが、心臓発作の月間症例数を分析した結果を発表しました。13年の規制以前、心臓発作の発生率は毎月100万人当たり0.9件ずつ増えていたそうです。しかし規制以降は、毎月0.6件と緩やかな増加にとどまったといいます。13年の規制で、2万1000件(93%は65歳以上)の心臓発作が抑制されたと推定されるとのこと。Asian Scientist Magazineの記事です。

新型コロナウイルスの感染は、感染者と過ごした時間の長さが最大の危険因子で、その時間が長くなるほどリスクが高まることが分かったそうです。英国の研究チームが、イングランドとウェールズで2021年4月~22年2月にスマートフォンアプリで追跡した700万件のコロナ関連接触データを分析。ブルートゥース(近距離無線通信)の信号強度からアプリが算出した「近さ」「時間」「感染力」のスコアを基に評価したといいます。最大の危険因子は時間で、感染例の大部分は1時間から数日間の接触があったとのことです。Medical Xpressの記事です。

精神疾患の診断・治療のバイブルともいわれる、米国精神医学会(APA)のガイドライン最新版「DSM-5-TR精神疾患の診断・統計マニュアル」について、その独立性に疑問が投げかけられているようです。米国の研究チームが、DSM-5-TRの刊行に関与した米国を拠点にする医師92人を対象に、企業との金銭的なつながりを調査したそうです。このうち55人(60%)が、業界から飲食や旅行、コンサルティング代などの支払いを受けていたことが明らかになったといいます。その金額は、合計で1424万ドルに上るとのことです。Medical Xpressの記事です。

ペットボトル入り飲料水には、想定されていた以上のプラスチック片(マイクロプラスチックやナノプラスチック)が混入しているようです。米国の研究チームが一般的なペットボトル飲料水を調査したところ、1L当たり平均24万個ものプラスチック片が検出されたそうです。このうち90%は1μm未満のナノプラスチックだったといいます。健康への影響は不明ですが、プラスチック片が血液に入り込んで器官に運ばれたり、プラスチック片に付着する微生物や結合する化学物質が何らかの害を及ぼしたりする可能性があるとの指摘が出ています。CBS Newsの記事です。
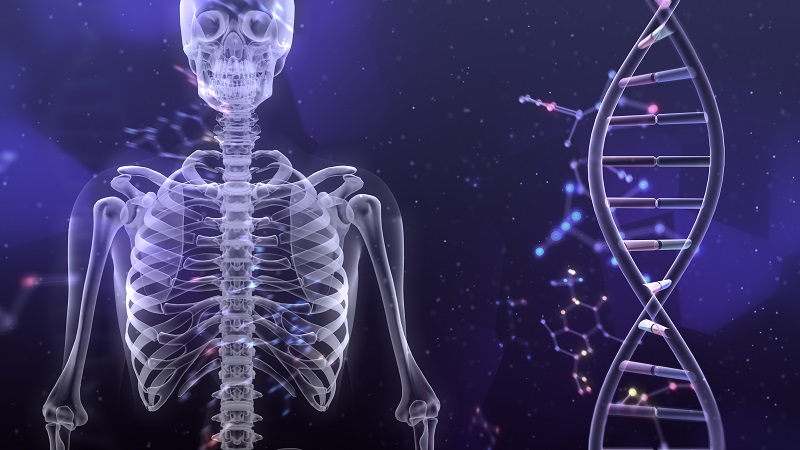
英国や北欧の人は、南欧の人と比べて多発性硬化症(MS)を発症しやすいそうです。人口10万人当たりの症例数は約2倍だといいます。英国などの研究チームが、その理由を解明したそうです。チームは、古代人の歯や骨からDNAを抽出し、現代の英国人のものと比較。約5000年前、遊牧民であるヤムナ文化の人々の大移動によって、MSリスクを高める遺伝子が欧州の西部や北部に流入したことが分かったといいます。この遺伝子は、当時は家畜由来の伝染病から身を守るために有益でしたが、ライフスタイルなどの変化によって役割が変わったとのこと。BBCの記事です。

RSウイルス(RSV)は呼吸器のみに感染すると考えられてきましたが、米国の研究チームが神経細胞にも感染することを発見したそうです。チームは、幹細胞とラットの胚から培養した末梢神経を使って調査し、RSVが感染できることを明らかにしたといいます。また、RSVによって、免疫細胞が仲間を呼び寄せるために使うタンパク質「ケモカイン」の放出が誘発され、激しい炎症が起こることも判明したそうです。これが神経損傷につながることもあるといいます。さらに、末梢神経を介してRSVが中枢神経の脊髄に侵入する可能性も示されたとのことです。EurekAlert!の記事です。

多発性硬化症(MS)の患者がエイズウイルス(HIV)に対する抗レトロウイルス療法(ART)を受けたところ、MSの症状がなくなったり病気の進行が抑制されたりする事例が報告されているそうです。スウェーデンなどの研究チームが、HIV陽性者2万9000人を平均10年にわたって追跡調査し、この真偽を確かめたといいます。追跡期間中にMSを発症したのは14人で、一般集団から予想される人数より47%少なかったそうです。ARTを受けた人に限定すると、MS症例数は予想より45%少なかったといいます。ARTは複数の抗ウイルス薬を併用する治療法です。The Conversationの記事です。

電流で脳を刺激しながら仮想現実(VR)で技術を訓練すると、現実世界でその技術をうまく実践できるようになるそうです。米国の研究チームが、手術支援ロボットを使った実験で明らかにしました。チームは参加者に、手術支援ロボットを使って三つの小さな穴に外科用針を通す操作を行わせました。最初に、参加者全員の小脳を後頭部に付けた電極で刺激。その後のVRの練習は、半数に小脳への電気刺激を与えながら実施させたそうです。実際のロボットを使った操作の実践で、VRでの練習時に電気刺激を受けた参加者の方が技術習得がうまくいっていることが分かったといいます。EurekAlert!の記事です。

1歳以上の小児に起こる原因不明の突然死(SUDC)には「けいれん発作」が関係している可能性があるそうです。米国の研究チームが、睡眠中にSUDCで死亡した小児7人について、寝室に取り付けた「見守りカメラ」の録画映像を分析した結果、明らかになったといいます。死亡した小児のうち5人は、けいれん発作とみられる症状を呈した直後に死亡していたことが判明したそうです。別の1人も、けいれん発作を起こした可能性が認められたといいます。また、複数の子どもに感染症の兆候が見られたといい、研究者はSUDCには熱性けいれんが関連している可能性もあると指摘しています。AP通信の記事です。

糖尿病治療薬「オゼンピック」や肥満症治療薬「ウゴービ」の商品名で知られる「セマグルチド」などのGLP-1受動態作動薬は、自傷行為や自殺念慮のリスクを高める可能性が指摘されています。しかし、米国の研究チームの研究で、これが間違いであることが分かったそうです。チームは、2017~22年に糖尿病または肥満症を治療する薬を処方された患者180万人以上のデータを分析。セマグルチドを使用した人は他の薬を使用した人に比べて、6カ月の追跡期間中に、初発または再発の自殺念慮をもつリスクが49~73%低かったといいます。AP通信の記事です。

米国の研究チームが、世界のICUにおける院内感染の20%を引き起こすグラム陰性菌「カルバペネム耐性アシネトバクター・バウマニ(CRAB)」に有効な抗菌薬を開発したそうです。グラム陰性菌の外膜を構成する分子「リポ多糖(LPS)」は、細胞質で作られて外膜に移動します。チームが開発した抗菌薬「zosurabalpin」は、LPSの移動を阻むことでアシネトバクター・バウマニの増殖を阻害し、殺すという新しいタイプだそうです。臨床検体やマウスの実験では、薬の有効性が示されたそうです。現在、第1相試験が行われているといいます。CNNの記事です。
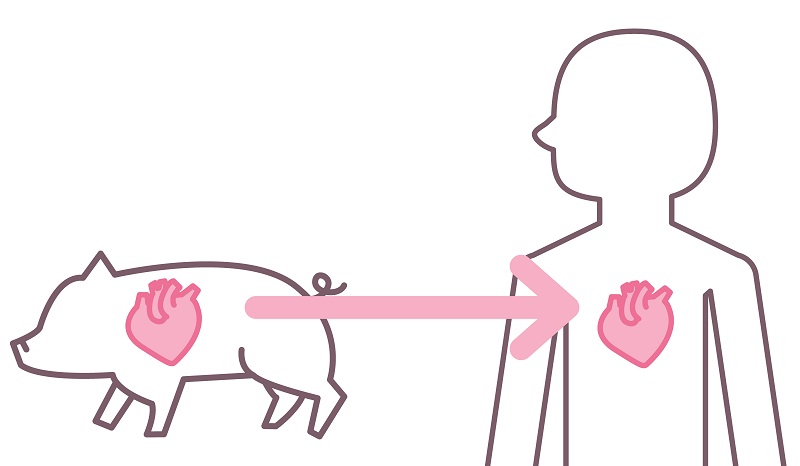
2023年の医療・医学に関する重大ニュースの続きです。米メリーランド大学が9月、世界で2例目となるブタの心臓移植を実施し、移植を受けた男性が6週間後に死亡しました。今年のノーベル生理学・医学賞は、コロナワクチンの開発に貢献したとして、mRNAの研究者2人に授与されました。20年にノーベル化学賞を受賞したゲノム編集技術「CRISPR/Cas9」を使った遺伝子治療が英米で初承認され、話題に。また、肥満症治療薬が大きな注目を集めました。大阪大学のチームによる、両親がオスの赤ちゃんマウスを誕生させたという発表は、衝撃を持って受け止められました。マイナビRESIDENTで詳細な記事が読めます。

2023年も医療・医学に関するさまざまなニュースが配信されました。2回に分けて、重大ニュースを振り返ります。今年5月、WHOが新型コロナの「緊急事態宣言」を解除し、3年以上続いたコロナとの戦いは大きな節目を迎えました。そして、米NIHが7月、「コロナ後遺症」の治療に向けた試験を開始すると発表。米FDAによる、アルツハイマー病治療薬「レカネマブ」や世界初のRSウイルスワクチンの承認も大きな話題になりました。感染症については、米国内で20年ぶりに国内感染が報告されたマラリアや、日米で報告数が急増した先天梅毒などが話題になりました。マイナビRESIDENTで詳細な記事が読めます。

英国の研究チームの報告によると、医師は患者の意見を軽視している傾向があるようです。チームは1000人以上の患者と臨床医を調査したそうです。診断が難しい「全身性エリテマトーデスに伴う神経精神症状」について、診断に使われる13種類の根拠の価値を医師が評価。重要な根拠トップ3の中に「患者の自己評価」を入れた医師は4%にも満たなかったといいます。また、676人(46%)の患者は「自分の病気について一度も、またはほとんど自分の評価を聞かれたことがない」と回答。患者の実体験に基づく見解に医師が耳を傾ければ、診断精度向上など多くの利点につながる可能性があるとのこと。SciTechDailyの記事です。
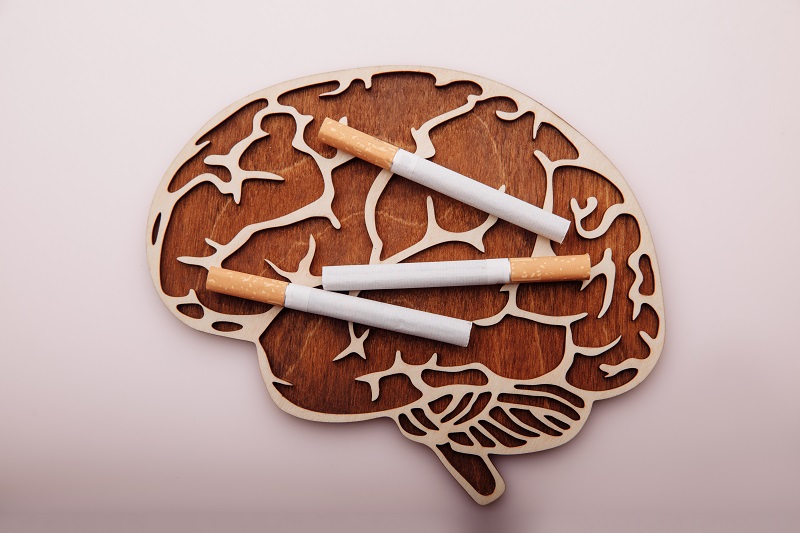
喫煙は心臓や肺の健康に悪影響を与えるだけでなく、脳を小さくしてしまうことが分かったそうです。米国の研究チームが、英国バイオバンクから抽出した神経学的疾患を持たない3万2094人の画像データなどを分析した結果です。日常的に喫煙をしていたことがある人は、非喫煙者に比べて脳の総容量、灰白質量、白質量が有意に少なかったそうです。特に、認知機能に関連する灰白質の減少が顕著だったといいます。また、たばこの消費量が多いほど、脳への影響が大きいことも明らかになったとのことです。これらのことから研究者は、喫煙をやめると認知症発症リスクを抑制できる可能性があるとしています。PsyPostの記事です。

米アラバマ大学バーミンガム病院で、生まれつき子宮が二つある32歳の女性が、それぞれの子宮で妊娠した双子を無事に出産したそうです。二つの子宮をもつ女性の割合は約0.3%とされており、両方の子宮で妊娠する確率は「100万分の1」程度だといいます。双子のうち1人目は、12月19日の現地時間の午後7時45分ごろに経膣分娩で誕生。2人目は、それから10時間後に帝王切開で生まれたそうです。2人は誕生日が別々の「二卵性双生児」に当たるといいます。BBCの記事です。

女性の涙には、男性の攻撃性を抑制する物質が含まれているようです。イスラエルの研究チームが、対戦相手に対して攻撃的になるよう設計された2人用ゲームを男性にやらせて調査をしたそうです。男性はゲーム中に「女性の感情的な涙」か「生理食塩水」のどちらかをかがされたといいます。涙の匂いをかいだ人は、ゲーム中に相手にリベンジを企てる攻撃的な行動が40%減ったそうです。脳画像からも、攻撃性に関連する2領域の活性低下が確認されたとのこと。Medical Xpressの記事です。

フランス南西部に、村全体が大きな介護施設になっている「アルツハイマー村」があるそうです。この村は2020年にオープンし、約120人の住人はみな認知症患者で、それと同数の医療従事者がいるといいます。敷地内にはレストランや店、劇場もあるとのこと。住人には可能な限り自由が与えられ、ゆったりと日常生活を送れるよう設計されているそうです。介護施設に入居すると認知機能の低下が加速することがありますが、この村ではそのような現象は確認されていないといいます。患者の家族の罪悪感や不安も激減するとのことです。BBCの記事です。

デンマークの研究チームが、人生を予測する人工知能(AI)を開発したそうです。チームは、600万人のデンマーク人に関する2008~16年の教育や健康、職業などに関するデータを使い、機械学習アルゴリズムモデル「life2vec」を訓練したといいます。その結果、life2vecは個人がどのように考え、どのように行動するのかをはじめ、数年以内に死亡する可能性があるかどうかも予測できるようになったそうです。さらに、life2vecで10万人のデータを分析したところ、4年後に死亡している可能性を78%の精度で予測できたとのことです。CNNの記事です。

ささいな体の不調に対して、自分が重篤な病気にかかっているのではないかと異常に心配する「病気不安症(心気症)」の皮肉なパラドックスが明らかになったようです。スウェーデンの研究チームが、1997~2020年のデータから、病気不安症を持つ4100人と対照群4万1000人を調査した結果です。1000人年(人年法)当たりの死亡率は、病気不安症群で8.5だったのに対し、対照群は5.5だったそうです。また対照群に比べ、病気不安症群は死亡年齢の中央値が5歳若いだけでなく、自殺率も4倍だったといいます。AP通信の記事です。

皮膚炎に使うステロイド外用薬が、骨の健康に悪影響を及ぼす可能性があるそうです。台湾の研究チームが、骨粗しょう症患者12万9682人と対照群 51万8728人、また、主要骨粗しょう症性骨折(MOF)患者3万4999人と対照群13万9996人を調査。5年後の「骨粗しょう症」と「MOF」のリスクは、ステロイド外用薬の局所使用をしていない人と比べ▽低用量使用群:骨粗しょう症が1.22倍、MOFが1.12倍▽中用量使用群:同1.26倍、同1.19倍▽高用量使用群:同1.34倍、同1.29倍――だったといいます。Medical Xpressの記事です。

殺虫剤への暴露が精子濃度を低下させるそうです。米国などの研究チームが25の研究を分析して明らかにしたといいます。調査対象となったのは世界4大陸(アジア、北米、南米、ヨーロッパ)の成人男性計1774人で、みな殺虫剤として一般的に使われる「リン酸エステル」や「N-メチルカルバメート」に暴露していたとのことです。そして、これらの物質への暴露が増えると、精子濃度が低くなることが示されたそうです。殺虫剤への暴露は、主に汚染された食べ物や水を介して起こり、研究者は「公衆衛生上の懸念」と指摘しています。ScienceAlertの記事です。

ヨーグルトなどの発酵食品に含まれる「ラクトバチルス属」の乳酸菌で、メンタルヘルスを改善できるかもしれません。米国の研究チームが、抗菌薬を使わない特別な方法で腸内にこの乳酸菌を持つマウスと持たないマウスを作製し、調べたそうです。その結果、ラクトバチルスによって、うつを抑制する役割があるサイトカイン「インターフェロン・ガンマ」のレベルが維持されることが分かったそうです。うつ病の新しい治療法として、健康に良い影響を及ぼす微生物「プロバイオティクス」のサプリメントが開発されるかもしれません。Medical Xpressの記事です。

動物性食品を厳しく制限する「ヴィーガン食」は健康に良いのでしょうか。米国の研究チームが、健康な一卵性の双子22組を「ヴィーガン食を摂取する群」と「適量の肉を取り入れた健康食を摂取する群」に分けて調査したそうです。8週間後、両群ともに心血管の健康状態を示すデータが良くなったものの、ヴィーガン群の方がより良くなっていることが明らかになったといいます。ヴィーガン群は減量が進み、空腹時インスリン値や悪玉(LDL)コレステロール値もより大きく低下したとのことです。ScienceAlertの記事です。
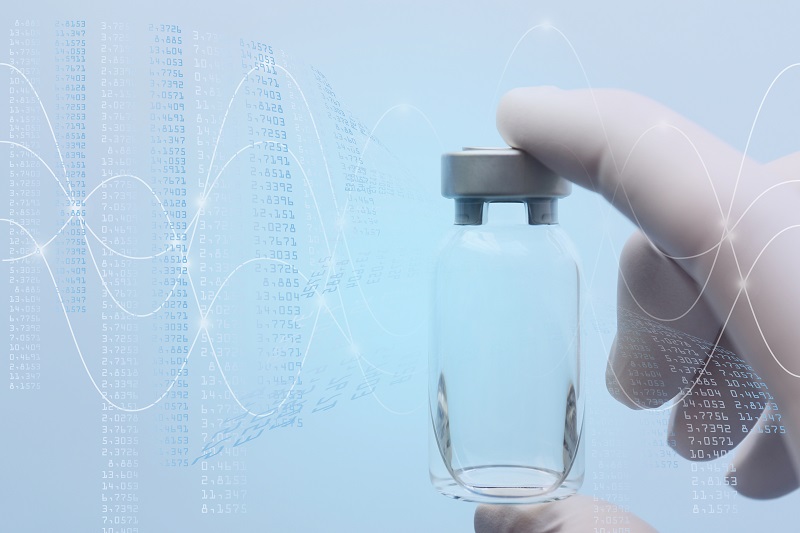
米モデルナと米メルクは、開発中の個別化mRNAワクチン「mRNA-4157/V940」が、「悪性黒色腫(メラノーマ)」患者に対して有望な結果を示していると発表したようです。両社は、ステージ3~4のメラノーマを切除したけれども再発リスクの高い患者を対象に、3年間の追跡調査を実施。メルクのがん免疫治療薬「キイトルーダ」とmRNAワクチンを併用した患者は、キイトルーダのみを使用した患者に比べて再発または死亡のリスクが49%、遠隔転移または死亡のリスクが62%、それぞれ低かったといいます。CNNの記事です。

米国の研究チームが、腎臓病の治療薬「BI690517」について、第2相試験の有望な結果を発表したそうです。この薬は、アルドステロンと呼ばれる腎臓病の進行を早めるホルモンの産生を阻害します。チームは、標準治療の「アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬」か「アンジオテンシン受容体拮抗薬(ARB)」の満量投与を4週間以上受けた慢性腎臓病患者714人を調査。BI690517のみを投与された人の50%、BI690517とSGLT2阻害薬「エンパグリフロジン」を併用した人の70%で、尿中アルブミンがそれぞれ有意に減少したとのことです。Medical Xpressの記事です。

パーキンソン病(PD)の発症リスクを上昇させる二つの危険因子が明らかになったそうです。米国の研究チームが、米国最南部(ディープサウス)出身のPD患者808人と神経学的に健康な対照群415人を調査したといいます。その結果、サッカーなどのスポーツで(無害なようにみえる程度に)繰り返し頭を打っていると、後にPDを発症するリスクが倍増することが分かったそうです。さらに、PD患者の23%が、除草剤や殺虫剤などの有害な化学物質に暴露していたとも判明したとのこと。研究者は、これら二つの危険因子は回避可能だとしています。Medical Xpressの記事です。
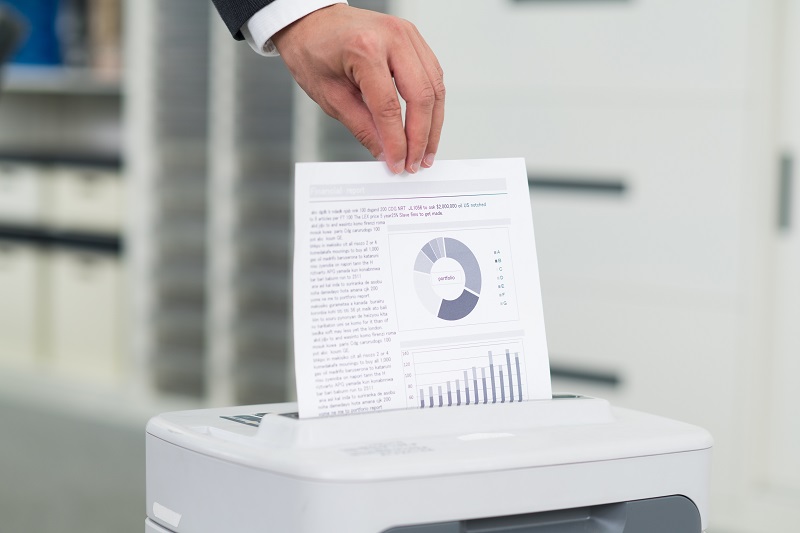
2023年に撤回された論文は1万本を超え、年間記録を更新したそうです。そのうち8000本以上は、ロンドンを拠点とするオープンアクセス出版社「ヒンダウィ」のジャーナルに掲載されたものだといいます。ほとんどが、ゲスト編集者が監修する「特集号」の論文とのことです。また、Nature誌の分析によると、論文撤回率は過去10年で3倍に増加し、22年には0.2%を超えたといいます。過去20年間に10万本以上の論文を発表した国の中では、サウジアラビア、パキスタン、ロシア、中国、エジプトの順に撤回率が高いとのことです。Natureの記事です。

米イーライリリー社の肥満症治療薬「ゼップバウンド(一般名:チルゼパチド)」の減量効果を維持するには、薬を使い続ける必要があるようです。米国の研究チームが、ゼップバウンドを9カ月間使用した肥満または太り過ぎの成人670人を追跡調査。半数には薬を継続させ、残りの半数にはプラセボを投与したそうです。次の1年が経過した時点で、薬を使った群は体重の平均6%が追加で減少したのに対し、プラセボ群はリバウンドがみられたとのこと。プラセボ群で少なくとも減量した体重の80%を維持できたのは17%だったそうです。CNNの記事です。

米アーカンソー州で、「オザークウイルス」と呼ばれる新たなウイルスが発見されたそうです。このウイルスはハンタウイルスの一種です。米国の研究チームが同州オザーク高原で、げっ歯類「アラゲコットンラット」を捕獲し、採取した338検体を調査。26検体がオザークウイルス陽性だったそうです。ハンタウイルスの中にはヒトに感染するものもあり、心肺症候群が起きると致死率は30~40%に上ります。専門家はオザークウイルスに対する警戒を強める必要があるとしています。Medical Xpressの記事です。

米疾病対策センター(CDC)は、「プランB」の名で知られる「モーニングアフターピル(緊急避妊薬)」が2006年に処方箋なしで買えるようになって以降、これを使用する女性が2倍になったと発表しました。性交渉の経験がある15~44歳の女性のうち緊急避妊薬を使用したことがあると答えたのは、06~10年の調査では10.8%だったのに対し、15~19年は26.6%に増加したそうです。一方、性交渉を経験したことがあるティーンエイジャーの割合は、男女共に減少したといいます。CBS Newsの記事です。

喘息患者向けの吸入ステロイド薬は、骨粗しょう症や糖尿病、白内障などの深刻な副作用を伴うことで知られています。英国などの研究チームが、吸入ステロイドの量を減らす方法を見つけたそうです。チームは、高用量の吸入ステロイドを使用する重症喘息患者208人を対象に調査を実施。喘息治療用に開発された生物学的製剤「Benralizumab(ベンラリズマブ)」を使用すると、92%の患者がステロイドの使用量を安全に減らすことができたそうです。さらに、60%以上の患者がステロイドの使用をやめることができたといいます。ScienceDailyの記事です。

乳がんや肺がんが、他の骨よりも脊椎に転移しやすいのはなぜなのでしょうか。米国の研究チームが、腫瘍細胞を引き寄せてしまう新しい幹細胞が脊椎に存在することを発見したそうです。チームは新たに見つかったこの細胞を「脊椎骨格幹細胞(vSSC)」と呼んでいます。vSSCを四肢の骨を形成する幹細胞と比較したところ、vSSCが高レベルで産生するタンパク質が見つかったそうです。このタンパク質を欠損させたマウスは、脊椎へのがん転移が少なくなったとのこと。このタンパク質が、がん細胞を集めてしまうようです。Medical Briefの記事です。

世界保健機関(WHO)が、アフリカのケニア、マラウイ、ウガンダ、ザンビア、ジンバブエで炭疽菌感染が拡大していると発表しました。今年になって確認された死者は計20人。このうち13人はウガンダで報告されているといいます。感染疑いのある患者は計1166人で、684人がザンビアで報告されているとのこと。WHOはザンビアから周辺国へ拡大するリスクが高いと懸念しているそうです。炭疽菌は主に汚染された動物に接触することでヒトに感染します。皮膚や消化器、呼吸器に異常が出て、治療を行わない場合の死亡率は約20%だそうです。AP通信の記事です。

ネコを飼っている家庭は、子どものメンタルヘルスへの長期的な影響の可能性を知ったほうがいいようです。豪州の研究チームが、1980~2023年に11カ国で行われた17の研究を分析。ネコを飼っていると、統合失調症関連障害のリスクが2.24倍になることが推定されたそうです。なお、特に幼い時にネコに接触していると、このリスクに関連することを示す研究もあるといいます。ネコに寄生するトキソプラズマ原虫が、こうしたリスクの原因である可能性が指摘されています。トキソプラズマは猫の糞に含まれていることがあります。Medical Xpressの記事です。

乳がん手術を受けた後は、どのくらいの頻度でマンモグラフィ検査を受けるべきなのでしょうか。英国の研究チームが、乳がん手術を無事に終えた50歳以上の女性5200人を追跡調査。初めの3年間は全員が年1回、マンモグラフィ検査を受けたそうです。その後、半数は毎年検査を受け、残りの半数は乳房切除術を受けた患者が3年に1回、腫瘤摘出術を受けた患者は2年に1回と頻度を減らして、それぞれ受検したといいます。6年後、両群ともに95%の人が再発せず、98%が生存していたそうです。AP通信の記事です。

片頭痛の時にイブプロフェンを使う人は多いと思います。しかし、もっと効果の高い薬があるようです。米国の研究チームが、片頭痛に関する477万7524回分の服薬データを分析した結果を発表しました。27万8006人が6年間にわたってスマホアプリで自己申告したものです。その結果、イブプロフェンに比べて、トリプタン系は4.8倍▽麦角系は3.02倍▽制吐薬は2.67倍――有効であることが判明。特にトリプタンの一種であるエレトリプタンは、イブプロフェンの6.1倍の効果が認められたといいます。Medical Briefの記事です。
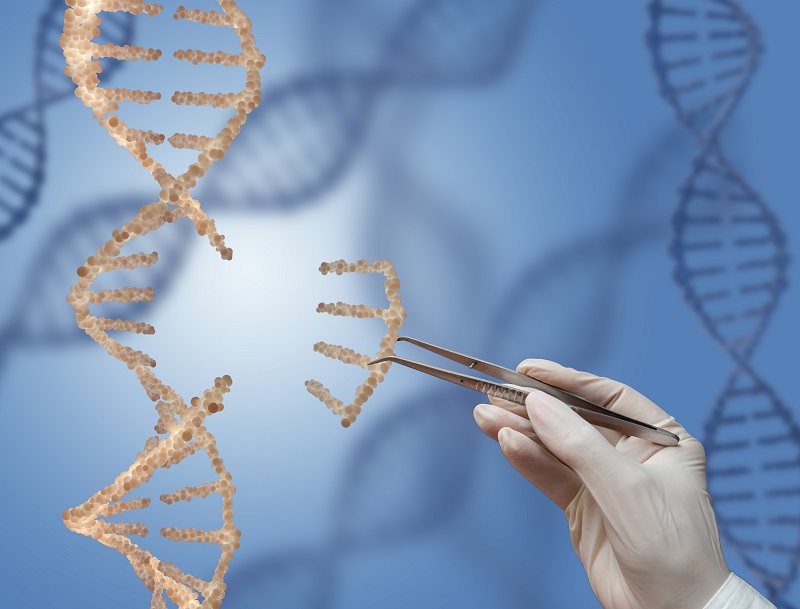
米食品医薬品局(FDA)は8日、遺伝性血液疾患「鎌状赤血球症」に対する2種類の遺伝子療法を承認したそうです。正常な形の赤血球が作られるように血液幹細胞の遺伝子を編集する治療法です。一つは米Vertex Pharmaceuticals社とスイスのCRISPR Therapeutics社が共同開発した「Casgevy(キャスジェビー)」。ゲノム編集技術CRISPRに基づいた治療法で、11月に英国が世界に先駆けて初承認しています。もう一つは、米Bluebird Bio社の遺伝子療法「Lyfgenia(リフジェニア)」です。これらの治療には2回の入院が必要で、1回は4~6週間入院生活が続くといいます。AP通信の記事です。

スマートフォンの使い過ぎは、若者のメンタルヘルスに悪影響を及ぼす可能性があるそうです。韓国の研究チームが、同国の思春期の若者5万人以上を対象に、スマホの使用時間とさまざまな健康状態のデータを分析したといいます。2020年は対象者の85.7%が2時間以上、スマホを使っていたそうです。分析の結果、スマホの使用時間が1日4時間を超える人は、ストレス、自殺念慮、薬物使用のリスクが高いことが分かったといいます。一方で、スマホの使用時間が1日1~2時間の人は、全く使わない人に比べてこうした問題を抱えるリスクが低かったとのことです。Medical Xpressの記事です。

アレルギーや喘息の治療に広く使われている抗インターロイキン(IL)-4受容体抗体「デュピルマブ」が、非小細胞肺がん(NSCLC)の治療に役立つ可能性があるようです。米国の研究チームが、治療抵抗性NSCLC患者6人を対象に調査を実施したといいます。免疫チェックポイント阻害薬での免疫療法にデュピルマブの投与(3回)を組み合わせたところ、免疫チェックポイント阻害薬だけでは増殖を続けていた1人の患者のがんが、ほぼ完全に消滅したそうです。17カ後の現在も、がんはきちんと抑制されているとのことです。Science Dailyの記事です。

米国の研究チームが、数千種類のタンパク質レベルを測定することで、臓器の老化速度や、どの臓器がいつ機能しなくなるのかを知ることができる血液検査を開発したそうです。調べられるのは、脳、心臓、肝臓、肺、腸、腎臓、脂肪、血管(動脈)、免疫組織、筋肉、膵臓の11個だといいます。この検査を主に中高年数千人に実施したところ、50歳以上の18.4%で、老化が平均より有意に早い臓器が一つ以上あることが示されたとのこと。こうした人は、15年以内に病気を発症したり、死亡したりするリスクが高かったといいます。BBCの記事です。

細菌は鼻水などの粘液を利用して、感染力を高めている可能性があるようです。米国の研究チームが、ブタの合成胃粘液やウシから採取した頸管粘液を使って、反すう動物やヒトの胃腸に存在する枯草菌の動きを観察したそうです。そして、その結果を、さまざまな濃度の水溶性ポリマー内における枯草菌の動きと比較したといいます。すると、粘液の粘度が高まれば高まるほど、細菌の集団運動が活発になることが分かったそうです。細菌の感染力は、集団運動が活発になると高まるといいます。EurekAlert!の記事です。

多発性硬化症(MS)の前触れとみられる五つの症状が明らかになったそうです。フランスの研究チームが、MS患者2万174人▽非MS患者5万4790人▽自己免疫疾患のクローン病か全身性エリテマトーデス(SLE)の患者3万7814人――の医療記録を分析。うつ、性機能障害、便秘、ぼうこう炎、ぼうこう炎以外の尿路感染症の五つの症状が、5年後にMSと診断されるリスクに関連していることが分かったそうです。ただし、これらの症状はクローン病やSLEの前駆期にも見られたといいます。Medical Xpressの記事です。

自己免疫性皮膚疾患である乾癬や白斑を治す画期的な方法が見つかったかもしれません。豪州の研究チームが、疾患の原因となる免疫細胞「組織常在性記憶T細胞(TRM)」に着目し、動物モデルで調査。TRMは「敵」と戦った後も、戦う能力を維持したままその場にとどまる免疫細胞です。さまざまな種類がある皮膚のTRMには、それぞれに特有の制御方法があることが判明。現在の自己免疫性皮膚疾患の治療は、全ての免疫細胞に影響を与えてしまうため、長期の治療ができないそうです。特定のTRMを標的にできれば、治療効果が改善する可能性があります。Medical Xpressの記事です。

睡眠中に10秒以上の呼吸停止が起こる「閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA)」は、高血圧や心臓病、2型糖尿病、うつ病、早期死亡のリスクを高めます。その兆候として「いびき」が知られていますが、それだけではないようです。まず、「寝汗」をかく人は注意が必要。そして、就寝中に2回以上トイレに起きる「夜間頻尿」、睡眠中の「歯ぎしり」もOSAの兆候として挙げられるそうです。起床時に、毎朝または頻繁に「頭痛」がする人も多いといいます。うつや倦怠感、不眠症など一見「メンタルヘルス不調」にみえる症状も、実はOSAが原因の可能性もあるとのこと。CNNの記事です。

アフリカ東部ウガンダの首都カンパラにある病院で11月29日、70歳の女性が帝王切開で双子の男女を出産したそうです。女性はこの病院で体外受精(IVF)治療を受けて、双子を妊娠したといいます。女性は2020年にも同じ病院でIVFによって女児を出産したそうです。女性の健康状態は良好で、現在は病院内を歩き回ることもできるといいます。治療技術の飛躍的な進歩によって、近年はIVFの成功率が上昇しています。インドでは2019年、73歳の女性がIVFで授かった双子の女児を出産して話題になったとのことです。AP通信の記事です。

アルゼンチン北西部のカタマルカ州で、フラミンゴ220羽が鳥インフルエンザウイルス(H5N1型)の感染によって死んでいるのが見つかったようです。2022年以降、渡り鳥を介してH5N1型は世界80カ国以上に拡散。継続的な変異も確認されており、専門家は哺乳類への広がりを注視しているといいます。H5N1型はヒトに感染しにくいと考えられているものの、21年12月以降、世界で11人の感染者が見つかっています。また、アザラシや養殖のミンク、猫や犬などさまざまな哺乳類への感染が確認されているとのこと。CNNの記事です。

スウェーデンなどの研究チームが、脳卒中のマウスやラットの実験で、失われた脳機能を改善させることに成功したそうです。チームは、脳神経細胞のネットワークにおいて情報伝達を制御する「代謝型グルタミン酸受容体5(mGluR5)」に着目。脳卒中発症から2日後の動物に、mGluR5を阻害する物質の投与を始めたところ、触覚や位置覚などの体性感覚機能障害が改善したそうです。治療を数週間続けると永続的な改善も認められたといいます。また、数匹を一緒に、遊び道具などがあるケージに入れて「リハビリ」を行うと、治療効果がさらに高まったとのこと。Science Dailyの記事です。

米製薬大手ファイザーは、飲む肥満症治療薬として注目されていた「danuglipron(ダヌグリプロン)」の1日2回服用型の臨床試験を中止すると発表したそうです。この薬は、効果の高さから関心が高まっている注射薬「ウゴービ(一般名セマグルチド)」や「ゼップバウンド(一般名チルゼパチド)」と同じGLP-1受容体作動薬です。ダヌクリプロンは試験の中期段階で、被験者の50%以上が服用を中断。副作用として73%が吐き気、47%が嘔吐を報告したといいます。今後は同薬の1日1回服用型に重点を置く予定で、初期試験の結果は来年初頭に明らかにする見込みとのこと。AP通信の記事です。

大麻の合法化や治療薬としての使用が世界的に進んでいます。オピオイド中毒を抑えるために大麻を利用しようとしている国もあります。しかし豪州のチームが、この流れは早計であるとの研究結果を発表しました。チームは2001~22年、強力なオピオイド「ヘロイン」の中毒者615人を追跡調査。対象者の多くが大麻も使用していたといいます。統計的手法で、経時的な個人の薬物使用の変化を分析したところ、大麻はオピオイドの使用を減らすための長期的な戦略として有効ではないことが示されたそうです。EurekAlert!の記事です。

エイズウイルス(HIV)に対する曝露前予防内服(PrEP)の非常に高い有効性が、実世界においても示されたようです。PrEPは、HIV感染のリスクのある人がHIV治療薬を1日1回、またはリスク行為の前後に飲んで感染を予防する方法です。英保健安全保障庁(UKHSA)が2017年10月~20年7月、イングランドの157のクリニックで調査。計2万4000人がPrEPを服用したといいます。日常生活で起こり得る飲み忘れや飲み間違いを考慮に入れても、PrEPがHIVへの感染を86%抑制することが明らかになったそうです。なお、臨床試験では99%の有効性が示されていたとのこと。BBCの記事です。
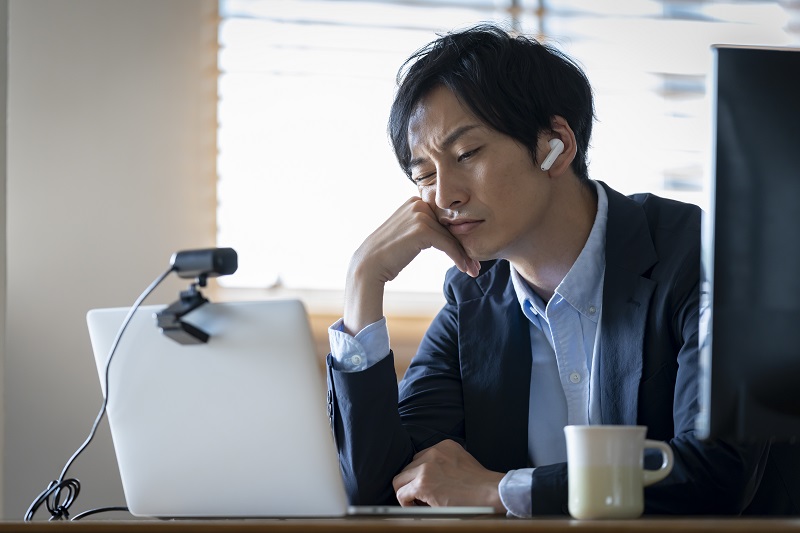
ウェブ会議システム「Zoom」などを使った「オンライン会議」に出席すると心や体が疲れてしまう人はいませんか。米国の研究チームが、体にストレスの兆候が表れる人が多いことを確認したそうです。大学生35人を「オンラインで講義を受ける群」と「対面で講義に参加する群」に分けて、脳波と心臓の状態を調査。オンライン講義を受けた人のほうが、疲れを報告する傾向にあったそうです。実際に脳波計は、オンライン講義中に脳活動が若干鈍くなることを示したといいます。さらに、心拍数も上下することが確認されたとのこと。CBS Newsの記事です。

人の性格は認知症リスクに関連するようです。米国のチームが既存8研究のデータについて、性格特性の主要5因子(開放性、誠実性、外向性、協調性、神経症傾向)や主観的幸福度(肯定的・否定的な感情、生活満足度)などを分析。対象者は4万4000人以上で、1703人が認知症を発症したそうです。後ろ向きの特性(神経症傾向や否定的な感情)のスコアが高く、前向きな特性(誠実さや外向性、肯定的な感情)のスコアが低い人ほど、認知テストで認知症と診断されるリスクが高かったといいます。ただし、特性と実際の脳組織病変との間に関連は認められなかったとのこと。ScienceDailyの記事です。

アルツハイマー病(AD)患者によく見られる怒りっぽさや興奮、不安、抑うつなどの精神神経症状は、脳内の神経炎症に起因するようです。米国の研究チームが高齢者109人について、神経炎症、ADに関連するタンパク質のアミロイドβとタウのレベルを脳画像から測定し、精神神経症状の重症度と比較。その結果、脳の免疫細胞である「ミクログリア」の活性が、さまざまな精神症状に最も強く関連していることが分かったといいます。アミロイドβやタウのレベルも関連がありますが、神経炎症による影響が大きいと考えられるそうです。Medical Xpressの記事です。

卵や乳製品、大豆、肉などに含まれる必須アミノ酸「イソロイシン」の摂取を控えれば、寿命が延びるかもしれません。米国のチームが生後6カ月(ヒトの30歳に相当)のマウスについて、①20種類のアミノ酸を含む餌②20種類のアミノ酸の量を2/3に減らした餌③イソロイシンの量を2/3に減らした餌――を与えた3群で比較したといいます。その結果、①に比べて③のマウスの生存期間はオスが33%、メスが7%、それぞれ延びたそうです。さらに③のマウスは、筋力や持久力、血糖値、脱毛などの健康に関するスコアも良好だったといいます。ScienceAlertの記事です。

胎児がお腹の中で聞いた声や音は、脳の神経発達に影響を与えている可能性があるそうです。イタリアなどの研究チームが、新生児33人とその母親を調査しました。母親はみなフランス語が母語だったそうです。寝ている新生児に、同じ絵本をさまざまな言語で読んだ音声を聞かせ、脳波を測ったといいます。その結果、フランス語で絵本を読んでいる音声を聞かせると、他の言語に比べて言語知覚や言語処理に関連する脳活動が増加したそうです。また、脳の神経反応についても、フランス語を聞いている時がもっとも強かったとのことです。Medical Xpressの記事です。

人工知能(AI)は症例記録まで書けてしまうそうです。米国の研究チームが、生成AI「ChatGPT」に似た機能をもつ「GatorTronGPT」に820億の医学用語を含む2770億語を学習させ、医師が書いたような文章を作成できるよう訓練したといいます。そして、本物の医師が書いた症例記録とこのAIが書いた症例記録を医師2人に評価してもらったそうです。その結果、人間とAIのどちらが書いた文章かを正確に特定できる確率は、たった49%だったといいます。AIが医療従事者の文書作成作業をサポートしてくれる時代が来るかもしれません。Medical Xpressの記事です。

背中や腰の痛みを軽減するには、どのような枕を選ぶといいのでしょうか。英国の専門家がポイントを解説しています。まず、首と背骨の自然なカーブを適切にサポートする枕を選ぶことが重要だそうです。頭の形にフィットする低反発枕や、高さ・硬さを調節できる枕が良いとのこと。特に腰痛がひどい場合には、横向きで寝る時に膝の間に抱き枕を挟むことも有効だといいます。古くなった枕はサポート力がなくなるため、数年に一度、新しいものに交換するのがおすすめだそうです。基本的にうつぶせ寝は避けたほうがいいとのこと。BBC Science Focusの記事です。

米疾病対策センター(CDC)は、梅毒の原因菌である梅毒トレポネーマの新たな変異株が発生している可能性があるとの報告書を発表したそうです。2022年3~5月にかけて40~60歳の女性5人が梅毒の症状が目に現れる珍しい「眼梅毒」を発症し、医療機関を受診。女性たちはみな、同じ1人の男性を性交渉のパートナーとして挙げたといいます。この男性を調べたところ、症状のない潜伏梅毒だったそうです。ある1人と性交渉したことで眼梅毒のクラスター(感染者集団)が起こったという記録はなく、CDCは細菌の突然変異を懸念しているようです。Science Alertの記事です。

中国北部で10月以降、子どもの呼吸器疾患や肺炎が急増しているそうです。世界保健機関(WHO)が中国に詳細なデータの提供を公式に求め、同国当局からは「通常とは異なる、または新規の病原体は検出されていない」との報告があったといいます。中国によると、新型コロナ対策の規制解除を背景に、細菌やRSウイルス、インフルエンザウイルスなどによる感染症の子どもの入院が増加しているとのこと。他国の専門家の反応は分かれており、中国の説明に理解を示す人もいれば、「新たな病気」を疑う人もいるようです。AP通信の記事です。

投与からたった1日で心的外傷後ストレス障害(PTSD)やうつ病の症状が軽減する治療薬があるそうです。米国の研究チームが、中等~重度のPTSD患者259人が参加した六つの研究のデータを分析した結果です。麻酔薬「ケタミン」を注射で投与された人は、1日後と1週間後の両方の時点で症状が25%軽減したことが分かったそうです。ただし、4週間にわたり複数回投与を受けると、症状の軽減は12%にとどまったといいます。うつ症状の緩和にも、わずかながら有意な効果が認められたとのことです。The Conversationの記事です。

薬剤を点滴で静脈内に投与するとき、現在はステンレスやプラスチックなどの硬い素材で出来た針を使っています。そのため、組織損傷や炎症を引き起こすことがあるといいます。韓国の研究チームが、患者の体に刺すと体温で柔らかくなる針を開発。この針は液体金属のガリウムで構成され、超軟性のシリコンで包んでいるそうです。組織を傷つけるリスクも針を刺した部位の痛みも軽減できるといいます。さらに、一度使うと柔らかい状態が維持されるため、針刺し事故や針の再利用を防ぐこともできるとのことです。Science Dailyの記事です。

睡眠周期の中で最も深い段階の「徐波睡眠」が、認知症リスクと関連しているそうです。徐波睡眠は脳波と心拍数、血圧が低下した最もくつろいだ状態で、1サイクル90分の睡眠の中で20~40分続くといいます。豪州などの研究チームが、平均5年の間隔をあけて睡眠検査を受けた非認知症の346人を17年にわたり調査。徐波睡眠は60歳以降に減少する傾向にあり、割合が年間1%減るだけで認知症発症リスクが27%高まる可能性が示されたといいます。アルツハイマー病に限ると、リスクは32%上昇したとのこと。Science Alertの記事です。

文章や画像を自動作成する「生成AI」が医療分野の偽情報を拡散させる危険があるとして、専門科が早急な対応の必要性を訴えています。豪州の研究チームが、米新興企業オープンAI社の生成AI「GPT Playground」を使って、電子たばこやワクチンに関するデマを作成したそうです。その結果、たった65分で、誤解を招くデマのブログ記事が102本も生成されたといいます。さらにAIアバター技術などを使うと、専門家がワクチンに関するデマを広めている「説得力のある」フェイク動画が5分以内に完成したとのことです。Medical Xpressの記事です。

赤ワインを飲むと頭が痛くなりませんか? 米国の研究チームがその理由を解明したかもしれません。チームは赤ぶどうに含まれるポリフェノール(フラバノール)の一種「ケルセチン」に着目。アルコールを摂取すると体内で有害物質のアセトアルデヒドが発生し、頭痛などの原因になります。ケルセチンはアセトアルデヒドを分解する酵素「ALDH2」の働きを間接的に阻害することが明らかになったそうです。日光をたくさん浴びた赤ぶどうほどケルセチンを多く含むといい、高級な赤ワインの方が頭痛が起きやすくなる可能性があるとのこと。BBCの記事です。

細胞から分泌される「細胞外小胞(EV)」と呼ばれるナノ粒子が、母親の腸内細菌叢と胎児をつなぐ鍵になるようです。EVにはタンパク質やDNA、RNAなどが含まれます。フィンランドなどの研究チームが、帝王切開で出産した母親25人を調査。母親の便から検出された腸内細菌由来のEVが、羊水に存在することが分かったそうです。EVは感染症を引き起こさないため、胎児が出生前に母親の腸内細菌に慣れ親しむことができるといいます。EVの羊水への移動が、胎児の免疫系の発達に重要な役割を果たす可能性があるとのこと。Medical Xpressの記事です。

世界保健機関(WHO)と米疾病対策センター(CDC)は、2022年に世界の麻疹(はしか)の症例数や死者が急増したと発表しました。21年にはしかの大流行が起きたのは22カ国だったのに対し、22年は37カ国に増加。22年の感染者は20%近く増の900万人で、死者は40%以上増の13万6000人だったそうです。新型コロナのパンデミック以降、はしかワクチンの接種率が世界的に低下していることが影響したとみられています。特に低所得国のワクチン接種率は66%にとどまっているとのことです。AP通信の記事です。

心身の健康に大きな悪影響を与える孤独や孤立が急増し、世界的に社会問題になっています。世界保健機関(WHO)は15日、この「差し迫った健康上の脅威」に対処するため、「社会的つながりを育む委員会」を新設すると発表しました。委員会は向こう3年間、人々の社会的つながりが深まるよう支援していく予定。社会的なつながりの欠如はメンタルヘルスへの影響はもちろん、早死に、免疫機能の低下、心血管疾患、脳卒中や認知症のリスク上昇との関係が指摘されています。CNNの記事です。
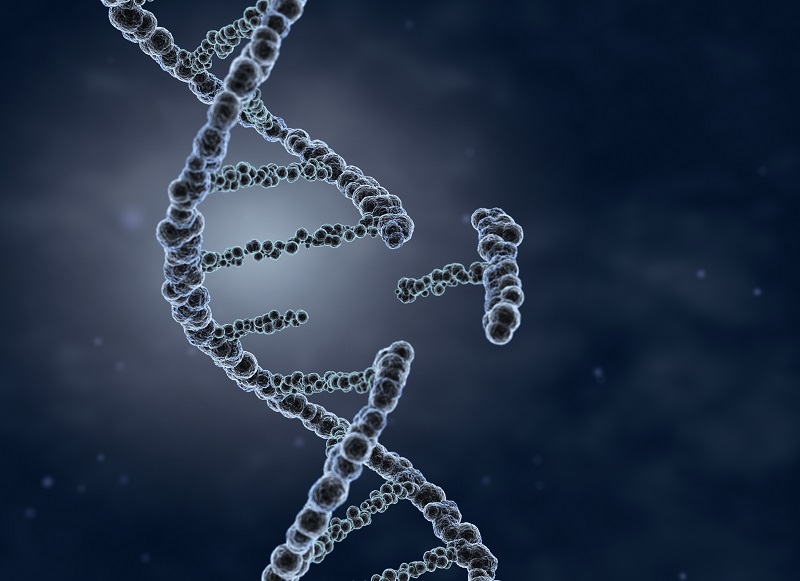
英医薬品医療製品規制庁(MHRA)は、ゲノム編集技術「CRISPR」を使った治療法を世界で初めて承認したそうです。承認された「Casgevy(旧exa-cel)」は遺伝性血液疾患の「鎌状赤血球症」と「サラセミア」向けの治療法です。対象となるのは12歳以上の患者だといいます。患者本人の骨髄から取り出した幹細胞をゲノム編集し、その細胞を体に戻すことで、永久的な治療効果が期待できるそうです。Casgevyは現在、米食品医薬品局(FDA)でも審査されているとのことです。AP通信の記事です。
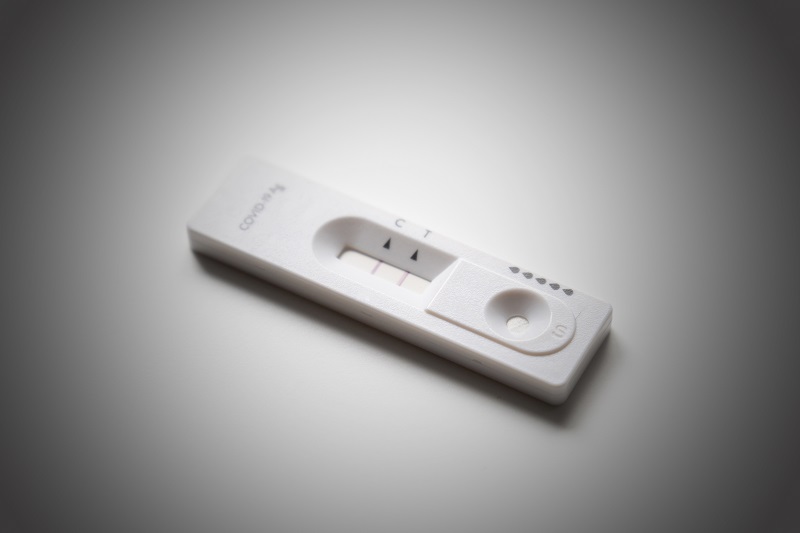
新型コロナウイルス感染症治療薬「パキロビッド」を服用すると、感染後一度陰性になったにもかかわらず、再度陽性になる「リバウンド(再陽性)」現象が起きる可能性が予想以上に高いようです。米国の研究チームが、コロナ患者142人について調査を行ったそうです。その結果、パキロビッドを5日間服用した患者のうち、20.8%がリバウンドを経験したことが分かったといいます。一方、パキロビッドを服用しなかった患者でリバウンドを経験したのはわずか1.8%だったことが明らかになったそうです。ScienceDailyの記事です。

患者自身のT細胞を遺伝子改変して体内に注入する「CAR-T細胞療法(キメラ抗原受容体T細胞療法)」で、子どもの頃に感染して潜伏していた「ヒトヘルペスウイルス6型 (HHV-6)」が再活性化する可能性があるそうです。米国の研究チームが、B細胞リンパ腫や白血病の治療でCAR-T細胞療法を受けた患者のデータを分析。患者の体に注入する前のCAR-T細胞からはHHV-6の転写産物は検出されなかったにもかかわらず、注入後の検体からはHHV-6が増殖したCAR-T細胞が見つかったといいます。Medical Xpressの記事です。

生肉やネコの排泄物などからヒトに感染する寄生虫(原虫)「トキソプラズマ」が、加齢によって心身が衰える状態「フレイル」の一因かもしれません。米国などの研究チームが、65歳を超える高齢者601人の血液を分析したそうです。その結果、トキソプラズマに感染したことがある人の中で、この寄生虫への抗体価が高かった人は、フレイルの兆候を示す傾向が強いことが分かったそうです。トキソプラズマへの激しい免疫応答とフレイルに何らかの関係がある可能性が示されたといいます。Science Alertの記事です。

血圧を測る際に、「両足が床につく椅子に座って背もたれにもたれ、測定する腕を心臓の高さにする」を守っているでしょうか。これは米国心臓協会(AHA)と米国心臓病学会(ACC)のガイドラインが定めた姿勢です。米国の研究チームが成人150人を調査。高さが固定された診察台で血圧を測ると、ガイドラインに従って測定した場合に比べて平均で収縮期血圧が7mmHg、拡張期血圧が4.5mmHg高くなったそうです。不正確な測定値で、高血圧に誤分類される人が多くいる可能性があるとのこと。Medical Xpressの記事です。

ティースプーン1杯分の塩分を控えるだけで、ほとんどの人の血圧が下がるかもしれません。米国の研究チームが、50~70代の中高年213人を調査。1週間にわたって1日のナトリウム摂取量を500mg(米国心臓協会は1500mg未満を推奨)に抑えると、通常の食事を取った場合に比べて収縮期血圧(上の血圧)が6mmHg低くなったそうです。全体として、塩分を控えた人の72%で収縮期血圧の低下がみられたといいます。この効果は、高血圧症の有無や服薬の有無と関係なく認められたとのこと。Medical Xpressの記事です。

薬剤耐性菌が肺に感染して重症化し、肺移植が必要になった男性(34)が、豊胸技術によって死の淵から生還したそうです。男性は重度の感染症のために、すぐには肺移植を受けられませんでした。米国の研究チームは、まず男性の両肺を切除。肺機能は機械で代替できるものの、肺移植が行われるまでの間、胸部に生じた空洞を何かで埋める必要がありました。そこでチームは豊胸に使われるインプラントを一時的にこの空洞に留置。2日後にはインプラントを取り除き、無事にドナーの肺を移植したそうです。ScienceAlertの記事です。

ノボ ノルディスク社の人気の肥満治療薬「Wegovy(ウゴービ)」(一般名セマグルチド)が、重篤な心血管疾患のリスクを下げる可能性があるそうです。米国の研究チームが、41カ国から心血管疾患の既往がある非糖尿病患者1万7500 人を集め、平均3年間の調査を実施。患者はみな45歳以上で、BMIは27以上だったそうです。通常の心血管疾患治療薬に加えてウゴービを週1回投与された人は、プラセボを追加された人に比べて心臓発作や脳卒中、心血管死のリスクが20%低くなったといいます。AP通信の記事です。

ほとんどの人は幼児期のことを覚えていません。この「幼児期健忘」は予防できる可能性があるそうです。母親が妊娠中に感染症にかかったときに起こる免疫応答が、子どもの自閉症に関連することが知られています。アイルランドの研究チームが、妊娠中のマウスでこの免疫応答を誘発したところ、子マウスの記憶細胞がこれに影響を受け、幼児期健忘が防げることが明らかになったそうです。なお、幼児期の記憶は大人になっても保持されている可能性があることも分かったといいます。Medical Xpressの記事です。

米ニューヨーク大学が、高圧電線事故で顔の左半分を大きく損傷した男性に、眼球と顔面の一部を移植していたことを発表したそうです。手術は5月27日に行われました。眼球全体を移植するのは世界初の試みだといいます。手術から5カ月経過した時点では左目に視力はないものの、角膜は正常で、網膜に血液が流れていることも確認されているそうです。神経の成長には時間がかかるため、移植した目の視神経が男性の脳と接続して、視力が戻る可能性も残されているといいます。USA TODAYの記事です。

米食品医薬品局(FDA)は8日、米製薬大手イーライ・リリーの「Zepbound(ゼップバウンド)」(一般名・チルゼパチド)を肥満治療薬として承認したと発表しました。糖尿病治療薬として承認されている「Mounjaro(マンジャロ)」の新バージョンです。近年はマンジャロが肥満治療に適応外使用される例が増えていたそうです。同薬は肥満患者の体重を19~27kg減らす可能性があるといいます。その効果は、ノボノルディスク社の肥満治療薬ウゴービ(一般名・セマグルチド)を上回るとのこと。AP通信の記事です。

ワサビの成分「6-メチルスルフィニルヘキシルイソチオシアネート(6-MSITC)」が、高齢の人の記憶力向上に役立つようです。東北大学などの研究チームが、60歳以上の健康な72人を対象に12週間の調査を実施。1日1回ワサビの錠剤を飲んだ人は、プラセボ群に比べて認知機能テストで、過去の出来事を思い出す「エピソード記憶」と情報を一時的に保つ「ワーキングメモリ」が向上したそうです。論理的思考や注意力、処理速度の分野では有意な改善は見られなかったといいます。Science Alertの記事です。

米疾病対策センター(CDC)が、胎盤を通して梅毒が母子感染する「先天梅毒」が2012~22年で10倍に急増したとして、医療機関に緊急措置を求めたそうです。先天梅毒は死産や乳児死亡、失明や難聴などが生じる可能性があります。22年は3761人の報告があり、200人以上が死亡。妊娠中に陽性だった場合、抗菌薬で治療すれば10人中9人の先天梅毒を防げるそうです。しかし22年は、先天梅毒児の半数以上の母親が検査で陽性だったのに、適切な治療を受けていなかったとのこと。ABC Newsの記事です。

米国の研究チームが成人6500人を対象に、米国心臓協会(AHA)の「健康促進のための8項目(Life’s Essential 8)」を使って、心血管の健康状態を評価したそうです。その結果、心血管の健康状態がよいと評価された人は、生物学的年齢が実年齢より6歳若いことが明らかになったといいます。「健康促進のための8項目」とは、健康な食生活▽適度な身体活動▽禁煙▽よい睡眠▽体重の管理▽コレステロール値の管理▽血糖値の管理▽血圧の管理――が含まれるそうです。CBS Newsの記事です。

パーキンソン病(PD)の影響で歩行困難だった63歳の男性が、6kmの散歩を楽しめるまでに改善したようです。スイスとフランスの研究チームが、脊髄に固定する電気刺激装置を開発したとのことです。この装置で神経を刺激することで脚の筋肉に電気信号が送られ、スムーズな歩行が可能になるといいます。男性はPD患者として初めてこの装置を埋め込む手術を受け、数週間のリハビリで歩けるようになったそうです。次は、別の6人がこの装置を試す予定とのことです。BBCの記事です。
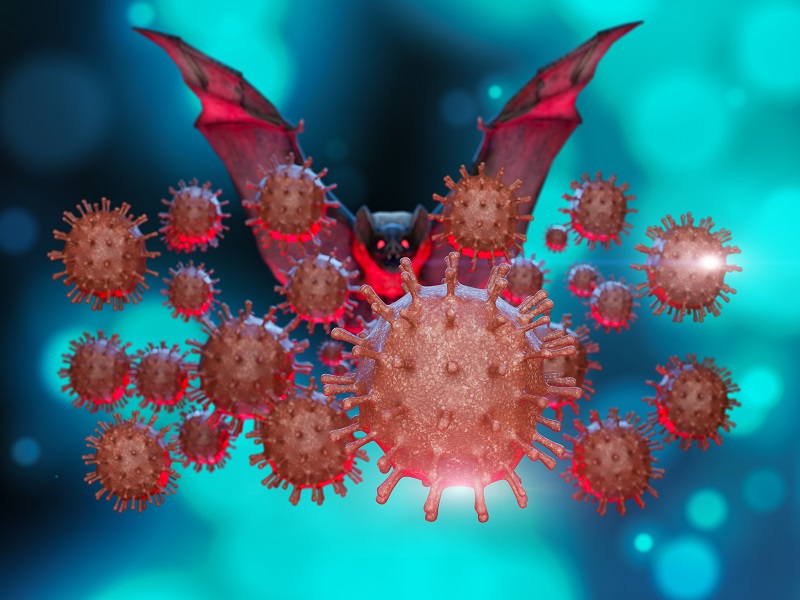
動物からヒトにうつる感染症が、これまで以上に広がる可能性があるようです。米国の研究チームが、1963~2019年に起きた▽フィロウイルス(エボラウイルスやマールブルグウイルス)▽ SARSコロナウイルス(SARS-CoV-1)▽ニパウイルス▽マチュポウイルス――の3150の流行について分析。毎年、動物から人への感染拡大が5%、その死者が9%、それぞれ増えていることが分かったそうです。気候変動や森林伐採の影響で、2050年には死者が20年の12倍になる恐れがあるといいます。Medical Xpressの記事です。

米疾病対策センター(CDC)が、米国における2022年の1歳未満の乳児死亡率が1000人当たり5.6人となり、前年から3%上昇したと発表したそうです。過去20年で最大の上昇率だといいます。白人やネイティブ・アメリカンの子ども▽男児▽妊娠37週以下で生まれた乳児――の死亡率が特に高くなったとのこと。死亡の原因としては、細菌性髄膜炎と母体の合併症が急増したといいます。パンデミック明けの昨秋は、RSウイルス感染症やインフルエンザが大流行し、その影響もあるとのことです。AP通信の記事です。

喫煙が肺がんを引き起こすメカニズムの一端が明らかになったようです。カナダの研究チームが、1万2000以上のがんゲノムを分析した結果です。喫煙によって、特定のタンパク質の産生を止めるよう指示を出す「ストップゲイン変異」が起きてしまう可能性があるのだそうです。異常細胞(がん)の成長は、がん抑制遺伝子が作るタンパク質によって阻害されるといいます。しかし、喫煙はがん抑制遺伝子でストップゲイン変異を引き起こしてしまい、がんが発生しやすくなるとのことです。Medical Xpressの記事です。

ゲノム編集技術「CRISPR」を用いた遺伝子療法が、米食品医薬品局(FDA)に初めて承認されるかもしれません。米 Vertex Pharmaceuticals社とスイス CRISPR Therapeutics社が、鎌状赤血球症に対する遺伝子療法「exa-cel」を開発。慢性貧血を特徴とし死に至ることもある遺伝性疾患です。exa-celは、患者自身の幹細胞を改変したものを一度投与するだけで完了するそうです。FDAは長期的な安全性などに関する独立諮問委員会の見解を参考にしながら、12月8日までに承認の判断をするといいます。CNNの記事です。

米メリーランド大学は1日、遺伝子操作したブタの心臓を移植する手術を受けた58歳の男性が術後6週間で死亡したと発表しました。ブタの心臓のヒトへの移植は世界で2例目で、男性は9月20日に手術を受けました。初めの1カ月は順調に回復しましたが、最近になって拒絶反応の兆候が出始め、10月30日に死亡したそうです。昨年同様の手術を受けた1例目の患者の心臓からは、死後の調査でブタウイルスの痕跡が見つかったため、今回は移植前に念入りな検査が行われていたといいます。NBC Newsの記事です。

慈悲深い人はよく眠るようです。フィンランドの研究チームが、3~18歳の3596人のデータを分析しました。その結果、慈悲深さを調べる評価で高レベルだった人は、睡眠不足や睡眠障害が少ないことが判明。このような人は11年たった後も睡眠問題が少なかったといいます。ただし、慈悲深さが睡眠問題と直接関連しているのではないようです。参加者のうつ症状を考慮に入れて調べたところ、慈悲深さでうつ症状が減り、それによって睡眠問題が抑えられる可能性が示されたといいます。PsyPostの記事です。

聴力低下が認知症リスクに関連することは、これまでの研究で明らかになっています。韓国の研究チームが、耳と認知症の新たな関係を明らかにしたそうです。研究チームは、同国の40~80歳の234万7610人を調査。その結果、平衡感覚をつかさどる内耳の「前庭」の機能低下も認知症に影響を及ぼす可能性があることが分かったそうです。調査した人のうち認知症と診断されたのは、聴力低下も前庭機能低下もない人の5.9%、聴力低下がある人の11.4%、前庭機能低下がある人の12.7%だったそうです。Medical Xpressの記事です。
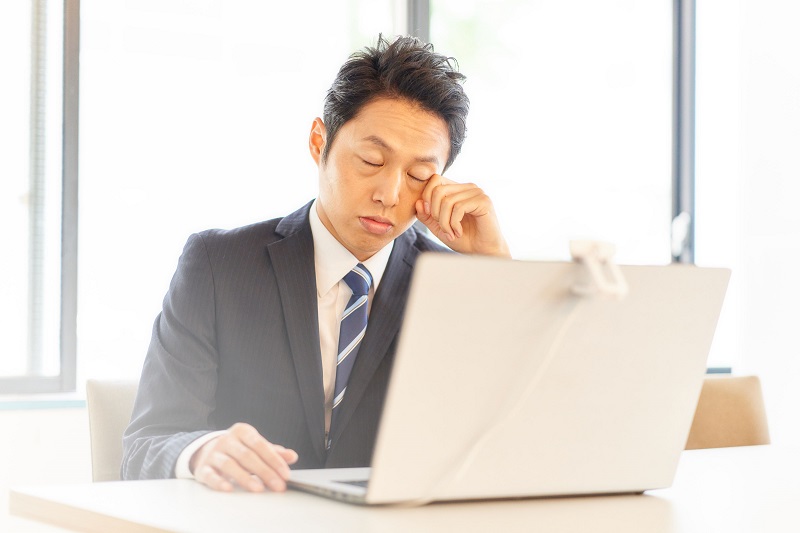
オンラインで行うリモート会議で眠くなることはありませんか。フィンランドの研究チームが、その理由を明らかにしたそうです。チームは、知識労働者44人が400近くの会議に参加した際の心拍変動を分析。仕事に熱心に取り組んでいる人は、対面会議でもリモート会議でも活動的な状態を保っていたといいます。一方、仕事への関与度合いが小さく、あまり熱心ではない人は、リモート会議を退屈に感じていることが判明。特にカメラがオフになっていると、刺激不足になるとのことです。ScienceDailyの記事です。

マスクは新型コロナの感染対策として「非常に役に立つものである」と、米バージニア工科大学の専門家が話しています。マスクはウイルスを運ぶ微小粒子と同じ大きさの物をブロックするため、人が吸い込むウイルス量が抑制されるそうです。この専門家は、マスクの表面に付着したウイルスに触れることで感染するとの説も否定しています。ウイルスを付着させたマスクからヒトの皮膚に、感染力のあるウイルスは移らないことが実験から明らかになっているそうです。CBS Newsの記事です。

合成オピオイド「フェンタニル」を母親が妊娠中に使用すると、生まれた赤ちゃんの顔や筋骨格に共通の異常が出る可能性があるそうです。米国の研究チームが、生後すぐに哺乳困難を起こした赤ちゃんに「小頭症」「低身長」「独特な顔面」などの共通の特徴があることを発見。同じ特徴を持つ赤ちゃん10人を調査したところ、母親は全員妊娠中にフェンタニルを使用していたといいます。フェンタニルは胎盤を通過して先天異常を発生させるリスクがあることが知られています。Medical Xpressの記事です。

中国武術の一つ「太極拳」が、パーキンソン病(PD)の運動症状と非運動症状の両方の進行抑制に有効なようです。中国の研究チームが、PD患者を2群に分けて5年以上追跡調査。143人は1時間の太極拳レッスンを週2回受け、対照群の187人は標準治療のみを継続したそうです。太極拳群は、動きやバランスをはじめとする症状の進行が総じて緩やかで、治療薬の投薬量が増えた人も対照群より少なかったといいます。ジスキネジアやジストニアなどの合併症状も抑制されたとのこと。Medical Xpressの記事です。

プロバイオティクスで、高血圧を治療できるようになるかもしれません。米国の研究チームが注目したのは「ACE2」という、血圧を上昇させるホルモン「アンジオテンシンⅡ」を分解するタンパク質です。遺伝子操作でACE2を産生できる善玉菌「ラクトバチルス・パラカゼイ」を作り、ACE2を産生できなくした高血圧ラットに投与したそうです。その結果、腸内のアンジオテンシンⅡが減少し、血圧が下がったといいます。ただし、血圧降下の効果がみられたのはメスのラットだけだったとのこと。ScienceDailyの記事です。

有酸素運動によって、勃起不全(ED)を克服できるかもしれません。米国の研究チームが、EDと運動に関する11の研究から計1100人のデータを分析。30~60分の有酸素運動を週3~5回行った600人と、500人の対照群を比べたそうです。その結果、有酸素運動はED治療薬であるバイアグラやシアリスと同程度の効果があることが判明。EDの重症度が高いほど、運動による大幅な改善が見られたといいます。また、テストステロンの投与は運動や薬よりも効果がないことも分かったようです。Medical Xpressの記事です。

米国の研究チームが、赤肉(牛・豚・羊などの赤色の肉)を週に2食(未加工の場合は85gが1食分)以上食べると、2型糖尿病のリスクが高まる可能性があるとの研究成果を発表したそうです。チームは、21万6695人を数十年間にわたって追跡して得られた、健康状態や食事内容のデータを分析。赤肉の摂取量が最も多い群は、最も少ない群に比べて2型糖尿病の発症リスクが62%高いことが分かったといいます。赤肉にはインスリンの感受性や生成機能を低下させる成分が含まれているとのこと。CNNの記事です。
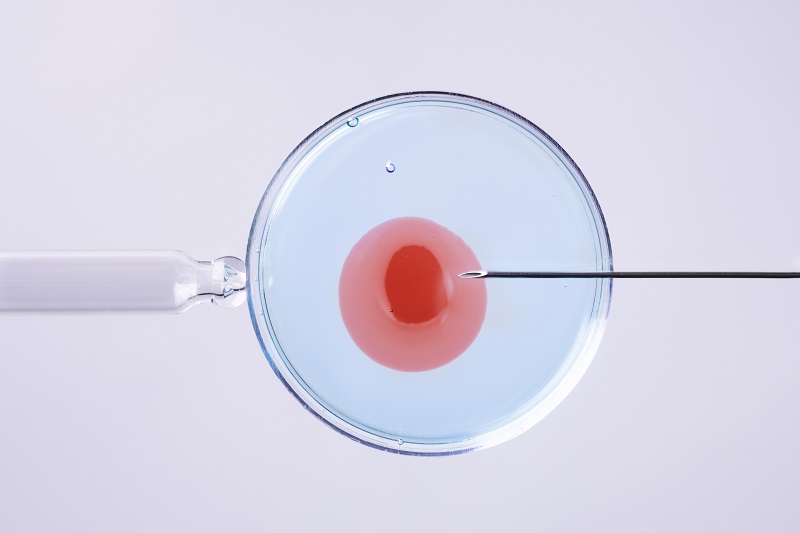
英国の科学者の多くが、ヒト胚を受精後14日以降培養してはならないとする「14日ルール」を「28日」に緩和するよう求めているようです。14日ルールが撤廃されれば、不妊や流産、先天性異常に関する研究の飛躍的進歩につながる可能性があるといいます。現在は研究が許可されていないため14日を過ぎた後に何が起こるのかは正確には分かっていないそうです。しかし、28日目までに心臓が作られて動き始めるといいます。中枢神経は機能していないので痛みは感じないとのこと。BBCの記事です。

10月7日にイスラム組織ハマスがイスラエルを攻撃した後、イスラエルは報復としてパレスチナ自治区ガザ地区への水や電気の供給をストップしているそうです。その結果、ガザでは深刻な水不足が発生。安全な水の確保が難しくなった住民は、飲料水や料理に汚水を使うことを余儀なくされているそうです。こうした環境で、赤痢やコレラなどの腸管感染症のまん延リスクが上昇。コレラの場合、特に子どもは大人よりも脱水症状を早く起こす可能性があり、死亡リスクも高いといいます。NBC Newsの記事です。

40度の環境でヨガを行う「ホットヨガ」が、うつ病の治療に有効かもしれません。米国の研究チームが、中等~重度の成人うつ病患者を対象に8週間の調査を実施。参加者のうち33人が90分間のホットヨガクラスを平均10.3回受講し、別の32人はヨガをしなかったそうです。その結果、うつ症状が50%以上改善したのは、ヨガをした群が59.3%だったのに対し、ヨガをしなかった群は6.3%だったといいます。さらに、ヨガをした群の44%は寛解状態を達成したとのことです。Medical Xpressの記事です。

米生殖医学会(ASRM)の実務委員会は不妊の定義を改訂するそうです。新たな定義には、全ての人が生殖医療に平等にアクセスする権利を持つとの考えを反映。異性カップルに対する定義(治療などをしても1年以内に妊娠できない35歳未満の女性、または半年以内に妊娠できない35歳以上の女性)という従来の定義に加えて、「パートナーの有無にかかわらず、妊娠のために医学的介入が必要な全ての人」も対象になるそうです。シングルの人や同性カップルが念頭に置かれているとのこと。CNNの記事です。
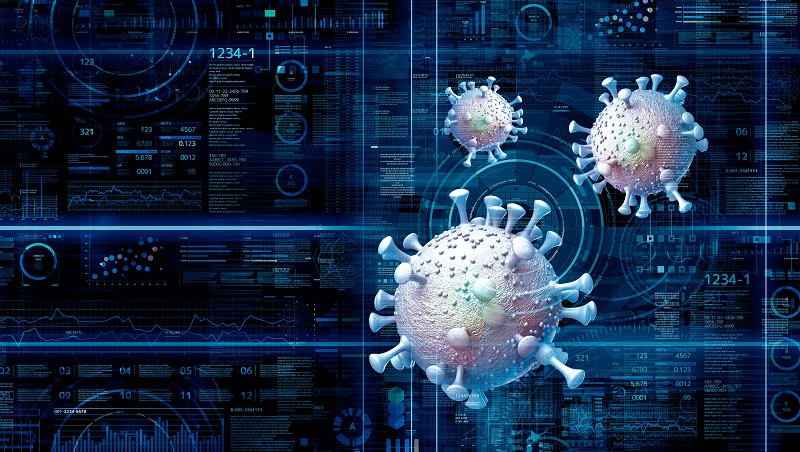
このAIがあれば、新型コロナウイルスの変異も正確に予測できたそうです。英オックスフォード大学と米ハーバード大学が、ウイルスの変異の仕方を予測する人工知能(AI)ツール「EVEscape」を開発したといいます。ウイルスの進化のモデルに、ウイルスの構造的な情報などを組み合わせたとのこと。EVEscapeは、ウイルスの変異が進むに連れてどの抗体治療が効かなくなるかの予見もできるそうです。流行が見込まれる変異株に対する予防策やワクチン開発への活用が期待されています。BBCの記事です。

さまざまな疾患リスクの低減など、コーヒーが健康に良い影響を与えることはよく知られています。では、加齢と共に毎年少しずつ増加する体重の変化も防げるのでしょうか。米国の研究チームが、過去に行われた三つの大規模な研究のデータを分析。コーヒーを1日1杯多く飲んだ人は、コーヒーの摂取量を増やさなかった人に比べて体重の増加が4年間で予想より0.12kg少ないことが判明しました。しかしスプーン1杯分の砂糖を加えると、体重は予想より0.09 kg増えたとのこと。The Conversationの記事です。

数行のフレーズを話してスマートフォンのアプリに記録するだけで、2型糖尿病の診断ができるようになるかもしれません。カナダのKlick Labs社が、糖尿病患者と糖尿病ではない人の計267人に1日6回、2週間にわたってアプリに特定のフレーズを録音してもらったそうです。このうち1万8465の録音データから高低や強弱など14種類の声の特徴を抽出し、2型糖尿病を検出する人工知能(AI)を開発。AIによる2型糖尿病の診断の精度は、女性で89%、男性で86%だったとのことです。ScienceAlertの記事です。

米メリーランド大学が遺伝子操作したブタの心臓を58歳の男性に移植してから1カ月が経過しました。大学は、男性が回復に向けて懸命にリハビリに励む様子を撮影し、その映像を公開しました。今のところ拒絶反応の兆候はなく、心臓は自力で機能しているそうです。男性はすでに立てるようになっており、現在は歩くのに必要な体力の回復に努めているとのことです。ブタの心臓をヒトに移植したのは今回で2例目。1例目の男性は移植から2か月後に死亡しています。AP通信の記事です。

慢性的な睡眠不足は心血管疾患の発症リスクを高めるといわれています。そのメカニズムが明らかになったようです。米国の研究チームが、普段7~8時間の睡眠をとる健康な女性35人を調査。参加者は初めの6週間はいつも通り睡眠を取り、次の6週間は普段より1時間半遅く寝たそうです。血管内皮細胞を取って調べたところ、睡眠が短くなると炎症の原因となる酸化ストレスが増大することが判明。これを除去するための抗酸化応答もうまく機能しなかったとのことです。Medical Xpressの記事です。

寝過ごし防止のために使う、目覚まし時計のスヌーズ機能。これを使っている間の睡眠は、質が低くて健康に悪いような気がしませんか。スウェーデンの研究チームが、スヌーズ機能を習慣的に使っている成人31人を調査したそうです。機能を30分間使うと睡眠が6分ほど減るものの、ストレスホルモンレベルや朝の疲労感、睡眠の質に影響はなかったそうです。むしろスヌーズ機能を使ったほうが、すぐに起きるよりも起床後の認知機能が向上した人もいたといいます。CBS Newsの記事です。

米国の一部地域で、急性疾患にも素早く対応できる医薬品の宅配サービスが導入されるようです。ネット通販大手「アマゾン」は、ドローンを使った処方薬の自宅配送をテキサス州カレッジステーションで開始すると発表したそうです。このサービスを使えば、注文から1時間以内に、ドローンが処方薬を自宅の玄関先まで届けてくれるといいます。対象となる医薬品は500種類以上で、一般的なインフルエンザや肺炎の薬も含まれるそうです。規制薬物は対象外とのこと。AP通信の記事です。

女性の脳卒中には見過ごされやすいサインがあるそうです。一般的に脳卒中の後遺症を防ぐには、「BE FAST」に対する注意が鍵になるといわれています。バランス(Balance)感覚の喪失、目(Eye)の見え方の変化、顔(Face)のゆがみ、腕(Arm)のまひ、言葉(Speech)の障害、発症の時間(Time)――といった症状などの頭文字を取った合言葉です。これに加えて女性の場合は、激しい頭痛▽脱力感▽倦怠感▽息切れや胸痛▽吐き気や嘔吐▽ブレインフォグ(頭の中のもや)▽しゃっくり――もサインになるといいます。CNNの記事です。

歯周病の初期段階である限局性歯肉炎は、口腔内の離れた健康な組織にも炎症を引き起こす可能性があるそうです。米国などの研究チームが、18~35歳の健康な成人21人を調査。一部の歯をアクリル製のカバーで覆い、それ以外の歯は歯磨きで清潔を保ったといいます。しばらくすると、カバーをした部分で歯肉炎が発生し、それと同様の炎症が反対側の歯磨きで清潔にしていた組織でも起きたそうです。炎症の激しさや発生のタイミングには、個人差があったとのこと。Medical Xpressの記事です。

「しこり」以外の乳がんの兆候を知っていますか。まず、乳頭が陥没したり垂れ下がったりする場合は注意が必要だといいます。その他、腕を上げると乳房にしわが寄る▽乳房の一部で感覚がなくなる▽乳房の皮膚が厚くなる▽乳頭から分泌物が出る――が乳がんのサインとして挙げられるそうです。米国で成人1000人以上に対して行った調査では、93%がしこりを乳がんの兆候として認識していた一方で、他の五つの兆候について知っていたのは31~51%だったとのことです。CNNの記事です。

米国の医療技術会社CraniUSが、血液脳関門(BBB:Blood Brain Barrier)の問題を解決する装置「NeuroPASS」を開発したそうです。脳に薬剤を送っても、血液脳関門によってその効果の95%以上が阻害されてしまうといいます。この装置は、頭蓋骨に埋め込むタイプで、カテーテルを通して薬剤を脳組織に直送することができるそうです。充電もワイヤレスで行え、薬剤の注入管理や補充も可能だといいます。ブタを使った実験では、有望な結果が示されているとのこと。Medgadgetの記事です。

米食品医薬品局(FDA)は、髪をストレートにするための縮毛矯正剤やリラクサーを一部禁止するよう提唱することを決めたようです。対象となるのは「ホルムアルデヒド」やホルムアルデヒドを発する「メチレン」などを含むストレートヘアにするための製品だといいます。専門家の間では、以前からこうした製品が子宮がんや卵巣がん、乳がんなどのホルモン関連がんのリスクを上昇させると考えられていたとのことです。実際にそれを裏付ける研究報告も出ているそうです。CNNの記事です。

深刻な臓器提供者(ドナー)不足を動物の臓器で解消しようとする異種移植の取り組みが進んでいます。米eGenesis社が、ブタの腎臓を20匹以上のサルに移植する実験を実施したそうです。ブタには、拒絶反応のリスクを減らすために七つのヒト遺伝子を組み込むなどの遺伝子編集を施したといいます。その結果、サルを長生きさせる3種類の遺伝子編集の組み合せが明らかになったそうです。免疫抑制剤を使用して、移植から2年以上生存したサルもいたとのことです。CNNの記事です。

新型コロナウイルスに感染しても、子どもの方が大人よりも軽症で済みます。その理由が明らかになったようです。米国の研究チームが、乳幼児81人(感染者54人)の鼻腔ぬぐい液と血液を定期的に採取し、母親や大人の感染者と比較。乳幼児がコロナに感染すると鼻腔内の炎症性サイトカインレベルが上昇し、ウイルスが排除されやすくなることが分かったそうです。大人の患者は血液中でこのサイトカインが増加し、重症化や死亡リスクの上昇につながるといいます。USA TODAYの記事です。

オメガ3脂肪酸は、心臓の健康維持や認知症リスクの低下、関節リウマチの改善に効果があることが分かっています。その効果は摂取方法によって異なるのでしょうか。主なオメガ3脂肪酸は魚介由来のDHAとEPA、植物由来のALAの3種類。このうちDHAとEPAについては、魚を食べてもサプリを飲んでも体内で増加するDHAやEPAの量が同じだったという研究報告があるそうです。ただ、関節リウマチに効果のある量を食事から取るのは難しく、サプリメントの使用が勧められています。The Conversationの記事です。

チューインガムを誤って飲み込んでしまうと、7年間胃の中にとどまる――。これは迷信だそうです。英オックスフォード大学の専門家によると、ガムを誤飲してもそのまま排泄されるので心配ないといいます。1日3個以上飲み込まない限り、人体に有害な影響を及ぼすことはないそうです。ただし、クローン病など消化管に異常がある場合や手術で胃が小さくなっている場合などは注意が必要とのこと。消化管が狭くなっていると、ガムが詰まって異常が生じる恐れがあるといいます。CNNの記事です。

甘味、塩味、苦味、酸味、うま味に続く「第6の味覚」が見つかったかもしれません。米国の研究チームが、北欧のお菓子「サルミアッキ」などの味付けに使われ、舌に触れると苦味と塩味と少しの酸味を感じる「塩化アンモニウム」に着目。培養ヒト細胞を塩化アンモニウムにさらしたところ、酸味を感知するOTOP1受容体が反応することが分かったそうです。舌の受容体が反応する新たな経路が特定されたため、これが新しい味覚として加えられる可能性があるといいます。ScienceAlertの記事です。

精神疾患は、自己免疫疾患の一種「多発性硬化症(MS)」の初期兆候の可能性があるそうです。カナダの研究チームが、MS患者6863人とMSではない3万1865人のデータを比較。一般的なMSの症状が医学的に確認されるまでの5年間を対象期間とし、患者のメンタルヘルスの状態を調査したそうです。その結果、うつ病や不安障害などの精神疾患を経験する割合は、MS患者が28.0%、MSではない人が14.9%だったといいます。MSの発症時期に近づくほど精神疾患リスクが高まったとのこと。Medical Xpressの記事です。

カンボジアで今週、鳥インフルエンザH5N1の感染によって2人が死亡したそうです。1人は南東部のプレイベン州に住む2歳の女の子で、咳や高熱などの症状が悪化したため首都の小児病院に運ばれたものの、死亡しました。女の子の村や自宅では9月下旬から、複数のニワトリが死んでいたといいます。女の子は庭で遊んでいた際に感染したようです。もう1人は隣のスバイリエン州に住む50歳の男性とのこと。同国内では今年、計3人が鳥インフルで死亡しています。ABC Newsの記事です。

夜間に光を浴び過ぎると、メンタルヘルスに悪影響があるようです。豪州の研究チームが、英国バイオバンクの8万6772人のデータを分析したといいます。その結果、夜に光を多く浴びる人は、うつ病リスクが30%上昇することが分かったそうです。逆に、昼間に光を多く浴びる人のうつ病リスクは20%低くなったといいます。自傷行為、精神症、双極性障害、全般性不安障害、心的外傷後ストレス障害(PTSD)のリスクについても、同様のパターンが見られたとのこと。Medical Xpressの記事です。

血糖値を下げるホルモン「GLP-1」を補う減量薬(GLP-1受容体作動薬)は、さまざまな消化器障害を起こすようです。カナダの研究チームが、糖尿病でない肥満患者5411人のデータを分析。この薬を使った人は別の減量薬を使った人に比べて、膵炎や胃不全まひ、腸閉塞などの消化器障害を起こすリスクが高かったそうです。例えば腸閉塞の発症率については、GLP-1薬「サクセンダ」使用者が0.8%だったのに対し、非GLP-1薬「コントレイブ」使用者は0.17%だったといいます。Science Alertの記事です。

新型コロナの後遺症と同じように、風邪やインフルエンザ、肺炎などにかかった後に何らかの症状が長引く人がいるそうです。英国の研究チームが、2021年1~2月に同国の成人1万171人から集めたアンケートデータを分析。新型コロナの検査で陰性だった急性呼吸器感染症患者の中には、感染から少なくとも4週間は咳や腹痛、下痢などの症状が長引く人がいることが分かったといいます。以前に同じ感染症にかかったことがあると、症状が重くなる傾向があるとのこと。CBS Newsの記事です。

メントールがアルツハイマー病(AD)の治療に役立つかもしれません。スペインの研究チームがADマウスで調査。メントールの香りを短時間嗅がせる治療を6カ月間行ったところ、認知機能や記憶力の低下が抑制されたそうです。ADの症状には炎症反応が関係していると考えられます。メントールによって、炎症反応に関わるタンパク質「インターロイキン-1β」が正常値まで下がる可能性があるとのこと。同様の実験で、若い健康なマウスの認知機能も改善されたといいます。ScienceAlertの記事です。

善玉コレステロール(HDLコレステロール)の値が高い方が健康状態は良いと思っていませんか? それは間違っているようです。米国の研究チームが、平均年齢70歳の認知症ではない18万4000人を約13年間追跡調査。参加者はHDL値に応じて3群に分けられたそうです。HDL値が最も高い群(65mg/dL以上)は、値が標準的な群に比べて認知症を発症するリスクが15%高くなることが分かったといいます。HDL値が最も低い群(11~41mg/dL)のリスクも標準的な群に比べて7%高くなったとのこと。NBC Newsの記事です。

スイスの研究チームが、ペプチドなどの大きな分子から成る薬剤を、頬内側の粘膜から吸収させることができる吸着カップを開発したそうです。大きな分子の薬剤は、糖尿病や前立腺がんなどの疾患の治療に用いられ、注射以外の投与方法はないといいます。このカップは真空状態を作り出すことで、薬剤が高密度な頬の組織を浸透しやすくするそうです。薬剤の浸透を促す物質の助けも借りるといいます。イヌやヒトの実験では有望な結果が示されているとのこと。Medical Xpressの記事です。

フランスのパリなどの都市で、トコジラミの目撃報告がここ数週間で増加しているそうです。パリは2024年のオリンピックの開催予定地であり、期間中の健康と安全が保たれるのか疑問の声が上がっているようです。トコジラミは人の移動に伴って広がるため、毎年夏の終わりに目撃数が急増するといいます。その数は年々増えており、最近は映画館や電車での目撃情報が、SNSなどで拡散されているそうです。トコジラミにかまれたときの基本的な症状は激しいかゆみです。BBCの記事です。

母親と赤ちゃんの健康リスクを高める恐れがある「妊娠糖尿病」の安全かつ効果的な治療法が見つかったようです。アイルランドの研究チームが、妊娠糖尿病の妊婦535人を対象に調査を実施した結果です。2型糖尿病の治療に使われる「メトホルミン」を投与された群は、プラセボ群に比べてインスリンが必要になる可能性が25%低かったそうです。メトホルミン群の早産リスクが高まることはなかったといいます。また、巨大児が生まれるリスクも低くなったとのことです。Medical Xpressの記事です。

健康に良い影響を与える生きた微生物「プロバイオティクス」の液体製品を与えられた早産児が、敗血症を起こして死亡したそうです。Infinant Health社が病院向けに製造している「Evivo」という製品で、MCTオイルを含有するタイプだそうです。ゲノム解析の結果、敗血症を引き起こした細菌がEvivoに含まれているものと一致することが分かったといいます。これを受けて米食品医薬品局(FDA)は、早産児に対するプロバイオティクスの使用について、医療機関に警告を出したとのことです。CNNの記事です。

2023年のノーベル生理学・医学賞は、ハンガリー出身のカタリン・カリコ氏と米国出身のドリュー・ワイスマン氏が受賞しました。両氏は米ペンシルベニア大学で、遺伝物質「メッセンジャーRNA(mRNA)」に関する技術を研究。mRNAに対する炎症反応がワクチン開発の障壁になっていましたが、2人はmRNAの一部の化学物質を置き換えることでそれが抑制できることを発見したといいます。15年以上前に発表されたこの研究成果が、新型コロナのmRNAワクチンの実現に大きく貢献しました。nprの記事です。

2023年のノーベル生理学・医学賞を受賞した「mRNA技術」は、新型コロナウイルスワクチン以外では何に活用できるのでしょうか。多くの研究者が、季節性インフルエンザや狂犬病、ジカウイルスなどを標的としたmRNAワクチン開発に取り組んでいるといいます。ワクチンが効かないマラリアやAIDS(後天性免疫不全症候群)のmRNAワクチンの研究も進められているそうです。さらに、がん患者の腫瘍から採取したタンパク質を使った個別化mRNA療法の試験も始まっているといいます。Medical Xpressの記事です。

英国の研究チームが脳内の小さな腫瘍や脳深部の重要な構造を正確に示す人工知能(AI)を開発し、これを活用した脳手術が2年以内に実現する可能性があるそうです。脳の手術は、中心部にある下垂体を傷つけないように進めることが極めて重要だといいます。AIに下垂体腫瘍摘出術のビデオを200本以上分析させたところ、たった10カ月で外科医が10年かけて獲得する経験レベルに到達。手術時にこのAIを使うと、次に行うべき手順や何が起きるのかを知ることができるそうです。BBCの記事です。

ニンニクを食べた後の臭いを消すよい方法はあるのでしょうか。米国の研究チームが、ヨーグルトの「乳脂肪」と「乳タンパク質」が有効なことを発見したそうです。スライスした生のニンニクが入った瓶にヨーグルトを加えたところ、臭いの元である硫黄ガスが99%減ったそうです。揚げたニンニクを使った実験でも、硫黄ガスは94%減少。乳タンパク質が特に重要な役割を果たすようです。これまでに、りんごやミントの酸、牛乳の脂肪が有効なことが分かっています。Science Alertの記事です。

米国の研究チームが慢性的なカフェイン摂取の影響を明らかにしたそうです。数週~数カ月間、毎日カフェインを摂取したマウスは昼寝をしなくなり、入眠のタイミングが遅くなったといいます。一方で、ぐっすりと長く眠るようになったとのこと。人間は生活リズムを変えられないために、カフェイン摂取が睡眠不足につながるようです。またカフェイン摂取は睡眠時の脳内血流を増加させ、神経変性疾患に関連する老廃物の排出を助ける可能性があるといいます。Medical Xpressの記事です。

「バナナ・スパイダー」と呼ばれる南米原産の猛毒グモが、「勃起不全(ED)」の治療に役立つかもしれないそうです。ブラジルの研究チームが、このクモにかまれた後に「持続勃起症」が起こることに着目。クモ毒の成分に似た合成分子を使い、ED向け塗り薬を開発したそうです。この分子は、勃起現象に重要な役割を果たす一酸化窒素の放出を促進。薬を男性器に直接塗り込むことで、数分で効果が得られるといいます。現在、第2相試験が行われているとのこと。Medical Xpressの記事です。

ノボノルディスク社の糖尿病治療薬「オゼンピック(一般名セマグルチド)」は使用後に腸閉塞を発症することがあるとして、製品情報に説明が追加されたそうです。米食品医薬品局(FDA)には、オゼンピックなどのセマグルチド製剤使用後の胃腸障害について8571件の報告が寄せられているといいます。また、製剤使用後に腸閉塞が発生した例は33件で、そのうち2人は死亡しているとのこと。オゼンピックはGLP-1受容体作動薬で、その減量効果にも注目が集まっています。CBS Newsの記事です。

重度の治療抵抗性うつ病には、脳内に電極を埋め込んで電気刺激を与える「脳深部刺激療法(DBS)」が有効であることが分かり、治療効果の把握もできるようになったそうです。米国の研究チームが、DBSを受ける患者10人を6カ月間調査。患者の90%に症状の有意な改善が見られ、70%がうつ病の基準を満たさないまでに改善したといいます。また、患者の脳活動の記録を人工知能(AI)で分析したことで、回復過程であることを示す特徴的な脳活動のパターンを特定できたそうです。SciTechDailyの記事です。

新型コロナ罹患後の後遺症(コロナ後遺症)のある人は、血液に特徴があることが分かったそうです。米国の研究チームが268人の血液を調査。後遺症のある人はそうでない人に比べて、免疫抑制や抗炎症作用のあるホルモン「コルチゾール」のレベルが有意に低かったといいます。コルチゾールレベルの低下によって、倦怠感が出る可能性があるとのこと。また、コロナ後遺症の人は、免疫細胞のT細胞やB細胞の動きが通常と異なることも明らかになったといいます。NBC Newsの記事です。

深刻な壊死性筋膜炎を引き起こし、「人食いバクテリア」と知られる細菌ビブリオ・バルニフィカスの感染例が増加しているとして、米疾病対策センター(CDC)が勧告を発表したそうです。この細菌はこれまで、米国ではメキシコ湾岸の暖かい海水に生息していました。しかし地球温暖化の影響で、北東部のコネチカット州でも感染者が出ているといいます。汚染された水や魚介類を介して傷口から体内に侵入し、米国では感染者の5人に1人が死亡しているそうです。CBS Newsの記事です。

胃食道逆流症が食道がんリスクを高めるとの考えは間違っているようです。スウェーデンなどの研究チームが、内視鏡検査で食道炎が見つからなかった胃食道逆流症(非びらん性胃食道逆流症)患者28万5811人を最長で31年間にわたり追跡調査。このうち食道(腺)がんを発症したのは228人で、発症率は一般集団と変わらなかったそうです。一方、びらん性食道炎がある胃食道逆流症(逆流性食道炎)患者は、食道がん発症率が明らかに高くなったといいます。Medical Briefの記事です。

インスタント食品やチップス、炭酸飲料などの「超加工食品」を取りすぎると、心の健康を損なう可能性があるようです。米国の研究チームが、42~62歳の女性3万1000人以上を対象に調査を実施。参加者のほとんどが白人だったそうです。超加工食品の摂取量が最も多い(1日9食分)群は、最も少ない(1日4食分以下)群に比べてうつ病を発症するリスクが50%高かったといいます。特に、人工甘味料がリスクに悪影響を及ぼす可能性が示されたとのことです。NBC Newsの記事です。

「負の感情を抑えるのは心の健康に良くない」との考えは間違っているようです。英国の研究チームが世界16カ国の120人を調査。チームは参加者に、2年以内に実際に起こりそうなさまざまな状況を想像してもらいました。ネガティブな出来事について考えると不安な気持ちになります。しかし、そのようなことを考えるのをやめる訓練を受けることで、出来事に対するイメージを不鮮明にすることができたそうです。その上、メンタルヘルスも改善したといいます。Medical Xpressの記事です。

米メリーランド大学は22日、ブタの心臓を58歳の男性に移植したと発表したそうです。男性は末期の心臓病患者で、末梢血管疾患や内出血をともなう合併症があるため、通常の心臓移植には不適格だったといいます。心臓は拒絶反応を抑えるための遺伝子操作を加えたブタのものです。移植後、男性は自発呼吸をしており、心臓は補助装置なしで正常に機能しているそうです。同大学は2022年に同様の移植を世界で初めて実施。その際は、患者は2カ月後に死亡しています。CNNの記事です。

米食品医薬品局(FDA)の諮問委員会が、早産児を「人工子宮」で育てることの議論を進めているそうです。19、20日に行われた会合では、妊娠28週以前に生まれた早産児の臨床試験の実施に向けて、必要なデータや規制、倫理的配慮などについて話し合ったといいます。人工子宮は人間の子宮のように、酸素や栄養素、ホルモンを赤ちゃんに供給でき、肺や脳の最終段階の発育を助けるそうです。既にヒツジなど複数の動物実験で、良好な結果が示されているとのことです。CNNの記事です。

米国の研究チームが、腫瘍の存在を知らせる細菌を開発したそうです。この細菌は、がんから放出されるDNAのかけらを素早く認識するCRISPRシステムを搭載。ベースとなる細菌には、周囲の環境からDNAを取り込むことに長けている「アシネトバクター・ベイリー」が使用されたそうです。腸に投与した細菌が腫瘍関連DNAを取り込むと、蛍光タンパク質や抗菌薬耐性をもたらす遺伝子が発現。便を抗菌薬を含む培地で培養することで腫瘍の存在が分かる仕組みだといいます。Medgadgetの記事です。

WHO(世界保健機関)が高血圧の世界的な影響について、初の報告書を公表したそうです。血圧が140/90mmHg以上の状態を高血圧と分類。全世界の成人の1/3が影響を受けているといいます。高血圧は脳卒中、心臓発作、心不全、腎臓損傷などを引き起こします。安価で手軽な薬でコントロールできるにもかかわらず、高血圧をきちんと管理できているのは患者の1/5ほどだそうです。適切な治療を受ける患者が増えれば、2023~50年で7600万人の死亡を防げる可能性があるといいます。CNNの記事です。

まれな遺伝子疾患「ミトコンドリア病」に苦しむ英国人の女の子(生後6カ月)について、延命治療を続けるかどうかを裁判所(高等法院)が決めることになるようです。女の子を治療する英ノッティンガムの病院が、高等法院に対して延命治療の中止を申請。病院によると、女の子は瀕死の状態だそうです。これ以上治療法はなく、痛みや苦しみをともなう延命治療は患者の最善の利益ではないといいます。一方、女の子の両親は治療の継続を希望しているとのこと。BBCの記事です。

ストレスフルな職場環境は、特に男性の健康に悪影響を及ぼすようです。カナダの研究チームが、心臓病のない平均45歳の事務系労働者約6500人(男性3118人、女性3347人)を18年間追跡調査。「仕事の重圧」か「労力と報酬の不均衡」のどちらかを経験している男性は、いずれも経験していない男性に比べて心臓病リスクが49%高かったそうです。両方を経験している男性の同リスクは2倍に上昇したといいます。女性に関してはこれらの関係が立証できなかったとのこと。Medical Xpressの記事です。

痩せたい人は午前7~9時に運動するといいかもしれません。香港の研究チームが、20歳以上の5200人について運動、食事、生活習慣のデータを分析。朝に中~高強度の運動をする人は、昼間や夕方に運動をする人に比べて体格指数(BMI)が低いことが示されたそうです。ただし、朝に運動していた人は平均年齢が10歳以上高く、このことが調査結果に影響を及ぼしている可能性があるといいます。さらに人種や生活環境など他の要因も考慮に入れる必要があるとのこと。NBC Newsの記事です。

楽しみより仕事での成功を優先していると、幸せになれないようです。英国の研究チームが、インド、トルコ、英国で計180人を調査。参加者は9日間日記をつけ、さまざまな価値観に従って行動した際の自身への影響を記録したそうです。国籍に関係なく、生きる最大の目的を快楽とする「快楽主義」や自分独自の道を行く「自主独往(どくおう)」に従って行動すると、幸福感が増したといいます。「成功」や「適合・準拠」は幸福感に影響を与えなかったとのこと。Science Dailyの記事です。

臨死体験の謎に迫る研究です。心臓が止まった後も、脳はしばらく静かに活動を続けている可能性があるそうです。米国の研究チームが、病院で心停止に至り心肺蘇生法(CPR)を受けた患者567人を調査。このうち28人は蘇生に成功し、インタビューに答えられるまで回復したそうです。何人かはCPR時の胸部圧迫や皮膚に貼られた電極などを覚えていると報告したとのこと。またCPR時の脳波は、生存者の40%で正常に近い数値が最大で1時間も維持されていたといいます。Science Alertの記事です。

厳しい残暑に対処するよい方法はあるのでしょうか。英国の研究チームが次の四つを推奨しています。暑さを感じた時は、顔ではなくまず手を冷やすとよいそうです。冷たい水に手を15~20分入れると効果的だといいます。シャワーを浴びるなら、冷水は皮膚への血流を遮断してしまうため非効率なので、ぬるま湯がいいそうです。ノンカフェインの温かい飲み物を飲むのも有効。うちわなどで全身に弱い風を当てて、汗を蒸発させるのも効果的とのことです。BBC Science Focusの記事です。

アルツハイマー病や血管性認知症の原因解明につながる新たなヒントが見つかったようです。米国の研究チームが、死亡した認知症患者の脳組織を分析。神経伝達を円滑にするためにニューロン(神経細胞)の軸索に巻き付くミエリン(髄鞘)が加齢などで損傷を受けると、免疫細胞のミクログリアが除去します。この時、そこに含まれる鉄を取り込みすぎることでミクログリアが変性し、細胞死してしまうそうです。これが認知症に関与している可能性があるとのこと。ScienceAlertの記事です。
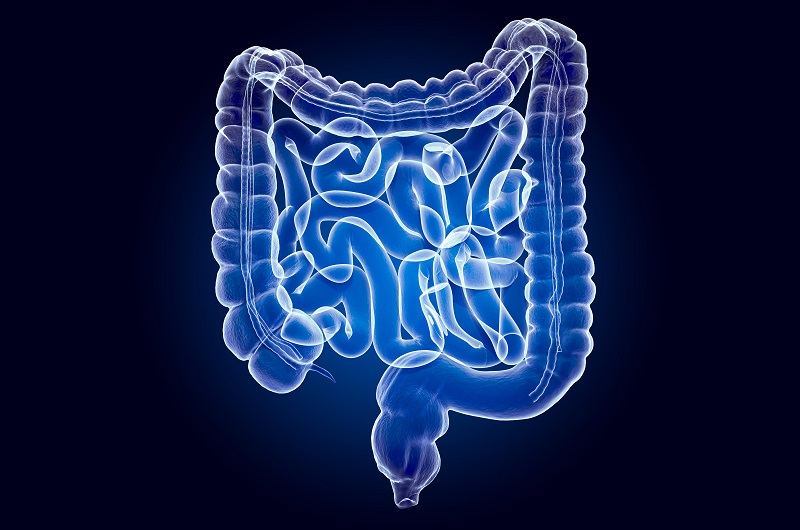
食物繊維を消化する際に腸内細菌によって代謝物として産生される「酪酸」と「プロピオン酸」が、大腸がんに対する免疫応答を促進するようです。カナダの研究チームが、マウスやヒトのがん細胞を使って調査。その結果、この二つの代謝物によってがん細胞の表面にある分子が活性化され、免疫細胞のT細胞が大腸がんを検出しやすくなることが分かったそうです。さらに代謝物はがん細胞の遺伝子発現も変化させ、免疫系の注意を引き付けるといいます。Medical Xpressの記事です。

米食品医薬品局(FDA)の諮問委員会は、風邪やアレルギー性鼻炎の市販薬に含まれる「フェニレフリン」について、錠剤で服用しても効果はないと認めたそうです。同薬は鼻粘膜の血管の腫れを一時的に抑えることで、鼻づまりを改善するとされています。委員会では、16人の委員が満場一致でフェニレフリン錠剤の有効性について「ノー」を投票したそうです。なお、研究で一時的な効果があることが示されている点鼻スプレー薬については、議論されなかったとのこと。CNNの記事です。

インターネットの定期的な利用は、脳の健康を保つのに役立つ可能性があるそうです。米国の研究チームが、調査開始時に50~65歳だった認知症ではない1万8154人を平均8年間追跡したデータを分析しました。その結果、定期的にインターネットを利用すると答えた人の認知症発症リスクは、そうでない人のリスクの57%だったことが分かったといいます。認知症を発症するリスクが最も低かったのは、1日に6分~2時間インターネットを使う人だったとのことです。PsyPostの記事です。

中国の研究チームが、異種動物の体内でヒトの細胞を持つ固形臓器を成長させることに初めて成功したそうです。チームは、ヒトとブタの細胞が混在する「キメラ胚」を作製し、これを雌ブタに移植。25または28日後に五つのキメラ胚を取り出し、腎臓の発達状況を分析したそうです。すると、腎臓は正常に発達しており、ヒト細胞を50~60%含んでいることが明らかになったとのことです。腎臓では尿細管や尿管芽細胞が形成されていたといいます。ScienceDailyに紹介されています。

米マサチューセッツ州の14歳の少年が、世界一辛い唐辛子を使ったチップスを食べた数時間後に死亡したそうです。少年はチップスを食べた直後に胃痛を訴え、その後、意識を失って呼吸が停止したといいます。激辛製品は大脳動脈狭窄や食道損傷など深刻な合併症を引き起こすことがあるそうです。SNSではこのチップスに挑戦する姿を投稿する企画「ワンチップチャレンジ」が行われていました。少年の死因は未特定ですが、製品は自主回収されているとのこと。ScienceAlertの記事です。

2型糖尿病や肥満の治療に使われるノボノルディスク社の「セマグルチド」は、1型糖尿病にも有効かもしれません。米国の研究チームが、3カ月以内に1型糖尿病と診断された患者10人を対象に調査を行いました。患者はみな基礎インスリンと追加インスリンを使用していたといいます。この10人にセマグルチドを週1回、3カ月間投与したところ、全員が追加インスリンをやめられたそうです。6カ月後には、7人が基礎インスリンも不要になったとのことです。CNNの記事です。

液体を熱して蒸気を吸う電子タバコを使うと、免疫系のなかで最初に防御反応を示す免疫細胞の好中球が適切に機能しなくなるようです。英国の研究チームが、タバコや電子タバコ製品を吸ったことがない健康な人の血液から好中球を採取。これを少量のノンフレーバーの電子タバコの蒸気に暴露させたそうです。電子タバコにニコチンが含まれているかどうかに関わらず、好中球はその場に立ち往生してしまい、敵に向かっていくことができなくなったといいます。Medical Xpressの記事です。

豪州の研究チームが、精巣で精子を作る能力が低下した「非閉塞性無精子症(NOA)」の男性不妊患者から素早く健康な精子を見つけ出すAI(SpermSearch)を開発したそうです。NOAの場合、患者の精巣から精細管と呼ばれる組織を取り出し、顕微鏡を使って健康な精子を見つけます。通常、専門家の手で6~7時間かかるそうです。しかしSpermSearchは、コンピューターに組織の画像を読ませると、数秒後には健康な精子を特定できるといいます。チームはSpermSearchの治験の準備を進めているそうです。BBCの記事です。

尿路感染症(UTI)はなぜ再発することが多いのでしょうか。米国の研究チームが、大腸菌によってUTIを発症させたマウスを調査。重度のUTIを患ったマウスの膀胱細胞では、次のUTIの発生に対して積極的に反応するよう免疫系に指示を出してしまう変化が起こるそうです。これは、DNA塩基配列の変化を伴わずに遺伝子発現に影響を及ぼす「エピゲノム」によるものだといいます。衛生状態に関係なくUTIは繰り返されますが、一定期間感染がなければ元に戻る可能性があるそうです。nprの記事です。

米国の研究チームが、生後16~30カ月の子どもの自閉スペクトラム症(ASD)を専門家と同じくらい正確に診断するタブレットツールを開発したそうです。対象者に子ども同士が社会的交流をしている様子のビデオを見せ、このツールがその際の目の動きを追跡して測定します。ビデオからどんな情報を得ているのかを知ることで、ASDを診断できるといいます。ASDの診断は高度な訓練を受けた専門家が何時間もかけて行うそうですが、ツールはわずか30分で結果を出すとのこと。NBC Newsの記事です。

甘い炭酸飲料を飲むと、メンタルヘルスに悪影響が及ぶようです。韓国の研究チームが、同国で平均年齢39.5歳の8万7115人に調査を実施。砂糖入り炭酸飲料の消費量が増えるのに比例して、うつのリスクも上昇することが分かったといいます。砂糖入り炭酸飲料を1日1缶飲むだけで憂うつな気分になる可能性があるそうです。当初、インスリン抵抗性や血糖値などの代謝が関連すると考えられていましたが、それだけでは説明がつかないことが示唆されたとのこと。PsyPostの記事です。

米中英などの研究チームが、50歳未満のがん症例数が過去30年間で急増しているとの研究結果を発表したそうです。チームは世界200カ国以上の情報が集められた疾病データを分析。2019年の50歳未満のがん症例数は326万件で、1990年と比べて79%増加したといいます。消化器系、皮膚、乳房のがんが多かったそうです。若い世代のがんの早期発見や予防に力を入れる必要がありますが、今回の調査には総人口が40%増えたことが考慮されておらず、深読みは禁物とのことです。BBCの記事です。

加齢に伴う病気が少なく長寿な「ハダカデバネズミ」の遺伝子を活用することで、長生きが実現するかもしれません。ハダカデバネズミはヒトやマウスに比べて、体内の高分子量ヒアルロン酸(HMW-HA)の量が多いといいます。米国の研究チームが、HMW-HA産生に関わるハダカデバネズミの遺伝子を移植したマウスを作製。自然発生がんや化学的に誘発した皮膚がんへの防御力が高くなったほか、通常のマウスに比べて健康状態が全般的に改善し、平均寿命が4.4%延びたといいます。Science Dailyの記事です。

中国の養鶏場で流行している鳥インフルエンザウイルス(H3N8型)が、ヒトの間で感染が広がりやすく変異している危険性があるようです。中国と英国の研究チームが、このウイルスに感染した人から分離したウイルス株の特徴を分析。その結果、ヒトの気管支や肺の上皮細胞で効率的に複製されることが分かったそうです。マウスやフェレットを使った実験では、この株が重篤な症状を引き起こすうえ、飛沫を介して空気感染する可能性が示されたといいます。Medical Xpressの記事です。

英国に住むミトコンドリア病を患う女性患者(19)とその家族が、治療方針を巡って英国民保健サービス(NHS)と法廷で闘っているそうです。この女性は、カナダで行われている同疾患のヌクレオシド療法の治験に参加することを希望。しかし担当医は、女性はすでに限りなく死に近い状態であり、終末期医療に進むべきだと考えているようです。裁判所は、女性に医療の継続について自ら決める能力はないと判断。今後の治療については法廷の審理で決まるといいます。BBCの記事です。

化学療法(抗がん剤)が効かない頭頸部がんへの対処法が見つかったかもしれません。英国の研究チームは、「NEK2遺伝子」と「INHBA遺伝子」が原因で頭頸部扁平上皮細胞がん(HNSCC)に化学療法への抵抗性(耐性)が起こることを発見したそうです。そして、これらの遺伝子を標的にする真菌毒素「シロデスミンA」や細菌由来の「カルフィルゾミブ」を使うと、耐性がん細胞に対するシスプラチンなどの抗がん剤の反応が30倍になることを突き止めたといいます。EurekAlert!の記事です。
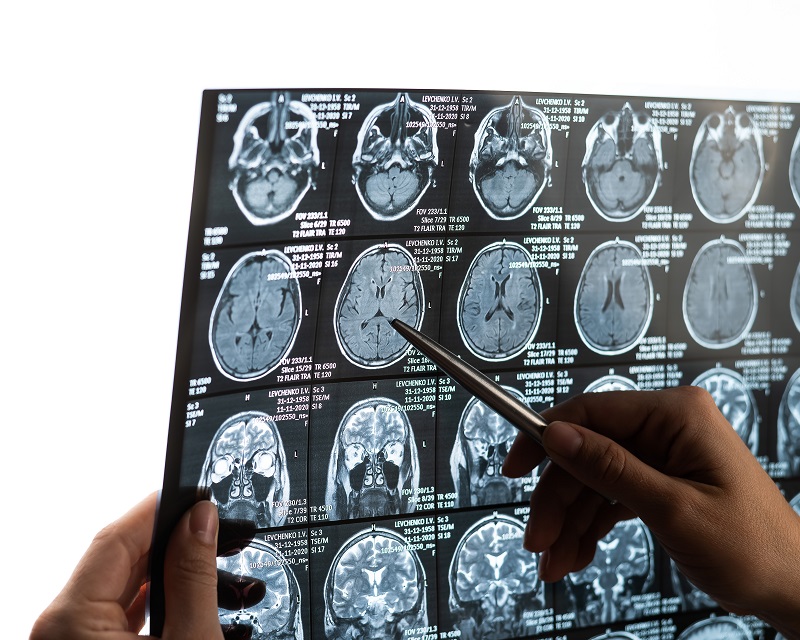
再発型多発性硬化症の治療に使われる経口薬「ponesimod(ポネシモド)」が、アルツハイマー病(AD)の治療に有効な可能性があるそうです。米国の研究チームがADモデルマウスで調査。ポネシモドを投与すると、ADの特徴である神経炎症が抑制されるだけでなく、神経に有害なタンパク質アミロイドが除去される可能性も示唆されたといいます。ADが進行しているマウスの注意力や、一時的な記憶機能「ワーキングメモリー」が改善することも明らかになったとのことです。Medical Xpressの記事です。

大麻草は土壌から重金属をよく吸い取るため、大麻製品を使うとそれらが体内に吸収される危険性があるようです。米国のチームが7200人のデータを分析。過去30日以内に大麻を使用した人は、大麻もタバコも使っていない人に比べて血中の鉛レベルが27%高く、カドミウムレベルは22%高かったといいます。尿の調査でも同様の結果が出たとのこと。鉛は神経系や造血系、腎臓などに障害を与え、カドミウムはイタイイタイ病の原因や発がん性物質として知られます。NBC Newsの記事です。

カナダの研究チームが、大麻に関する100以上の研究を分析し、結果を発表しました。不安やうつなどの症状緩和に大麻は有害で、臨床転機を悪化させるだけでなく、精神疾患発症のリスクを高めるそうです。また、つわりを抑えるための使用は、低出生体重児のリスクを上昇させるようです。さらに、大麻は認知機能に悪影響を及ぼすため、若年層の使用はリスクが高いといいます。けいれん性疾患や慢性疼痛などの分野も、効果があるのは特定の人だけとのこと。CNNの記事です。

頸部に腫れなどの症状がある場合、臨床実践ガイドラインではがんの可能性を疑うことが推奨されているといいます。しかし、実際には抗菌薬が処方されることが多いようです。米国の研究チームが、頭頸部がん(HNC)患者7811人のデータを分析。このうち15.6%がHNCと診断される3カ月以内に抗菌薬を処方されており、結果的に診断までにかかる時間が21.1%長くなっていたそうです。プライマリ・ケアの医師にNHC診断のガイドラインが普及していないことが一因のようです。Medical Xpressの記事です。

がん検診を定期的に受けると、通常より長生きできるのでしょうか。ノルウェーなどの研究チームが、6種類のがん検診を受けた210万人のデータを分析。その結果、寿命の延長に効果があったのは、大腸がんを調べるためのS状結腸鏡検査だけだったそうです。この検査で寿命が3カ月延びる可能性があるといいます。乳がんのマンモ検査、大腸内視鏡検査、便潜血検査、前立腺特異抗原(PSA)検査、喫煙者へのCT検査は、寿命延長の効果はなかったとのことです。CNNの記事です。

医療用大麻は小児がん患者の症状軽減に有効なのでしょうか。カナダの研究チームが19の研究から1927人のデータを分析したのですが、投与量や安全性、効果を示すデータが不足しており、総合的な評価はできなかったそうです。大麻の成分が化学療法による吐き気や嘔吐を抑えるのに有効との研究がある一方で、眠気やめまい、口の渇きなどの有害事象が出るという報告もあったとのこと。研究者は、厳密な調査で効果を評価する必要があると指摘しています。Medical Xpressの記事です。

横紋筋肉腫(RMS)は、体の軟らかい組織の、本来は筋肉になる細胞から悪性腫瘍が発生する小児がんです。米国の研究チームが、RMS細胞を筋肉に変えるという革新的な治療法の可能性を開いたそうです。鍵となるのはタンパク質「NF-Y」。ゲノム編集技術を使ってNF-Yを阻害すると、RMS細胞ががんの性質を完全に失い、筋肉に変化することが分かったそうです。RMS細胞から変化した細胞は全エネルギーを「収縮」に使うようになり、増殖することができなくなるとのこと。Medical Xpressの記事です。

豪州で、64歳の女性の脳から生きた線虫が見つかったそうです。女性は2021年に胃の症状や乾いたせきなどの症状が出て、22年にうつや物忘れの症状が出たために脳の検査(MRI)を受けたといいます。そして、同国のチームが女性の脳から8cmの線虫を除去。豪州原産で、カーペットニシキヘビに寄生するO. robertsiだったそうです。この線虫のヒトへの感染報告は初めてだといいます。女性が食べた野草に、ヘビがふんと一緒に排出した線虫の卵が付いていたようです。ABC News(AUS)の記事です。

5歳未満の子どもの死亡は99%が低中所得国で起きており、その82%が防げるものだったことが分かったそうです。子どもの健康を監視する国際チームが低侵襲な生体組織検査を使って、サハラ以南のアフリカと東南アジアの7カ国で生後1~59カ月の子ども632人の死因を調査。死因は多い順に、栄養失調(16.5%)、HIV(11.9%)、マラリア(11.2%)、先天性の異常(10.1%)、呼吸器感染症(8.4%)、下痢(7.2%)だったといいます。また、死亡者の87%から何らかの感染性病原体が見つかったとのことです。Medical Briefの記事です。
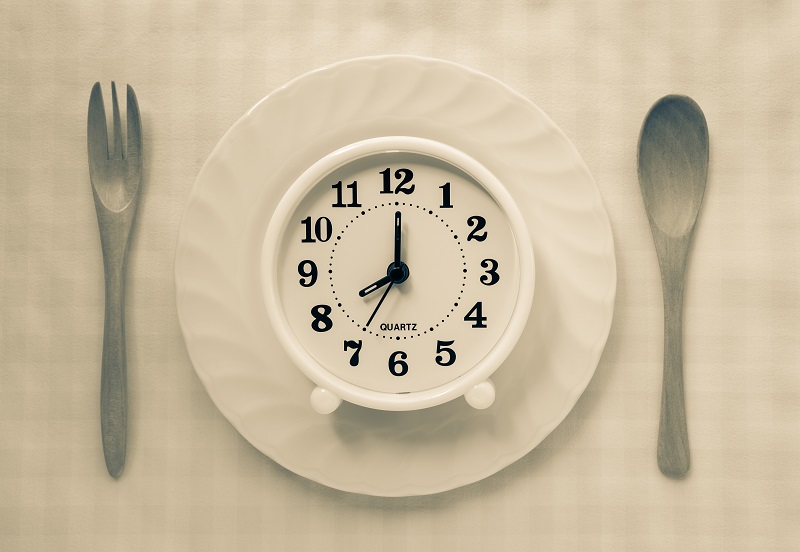
食事法で概日リズムの乱れを改善すれば、アルツハイマー病(AD)の進行を遅らせることができるかもしれません。米国の研究チームがADマウスを使って調査。食べ物を摂取する時間を決める「断続的断食」に基づいて、マウスが餌を食べられる時間を1日6時間に制限すると、記憶力が著しく改善したそうです。食事の時間を制限したマウスは、ADに関連するとされるタンパク質アミロイドβが脳に蓄積しにくいうえ、よい睡眠を取れることも示されたといいます。ScienceAlertの記事です。

脳インプラントを使って言葉を取り戻す技術が進化しているようです。米国の研究チームが、脳卒中でほぼ完全な麻痺状態になった女性の脳に253の電極を移植。人工知能(AI)に「音素」を認識させ、女性が考えている内容をアバターに話させる技術を開発したそうです。女性は周囲の人と同じくらいの速さで会話することが可能になったといいます。また、米国の別のチームが筋萎縮性側索硬化症(ALS)の女性患者に行った同様の研究でも、有望な結果が得られたとのこと。ScienceAlertの記事です。

新型コロナウイルスが脳細胞に与えるダメージの詳細が分かってきたようです。英国の研究チームが、各変異株による4種類の脳細胞への影響を調査。中国の武漢市で最初に広がった従来株は血液脳関門(BBB)を形成する周皮細胞と内皮細胞、免疫応答や脳細胞の各機能を助けるミクログリアにダメージを与え、オミクロン株は周皮細胞と内皮細胞を破壊したといいます。3Dモデルの実験では、この2株が血液脳関門の完全性を損なう可能性が示されたとのことです。Medical Xpressの記事です。

前立腺がんは、採血でPSA値を調べるよりMRI検査の方が正確に検出できる可能性があるそうです。英国の研究チームが、50~75歳の男性303人にMRI検査とPSA検査の両方を実施しました。その結果、48人がMRIで前立腺がん陽性となり、そのうち25人が追加の検査で実際にがんと診断されたそうです。MRIでがんが見つかった人の半数以上が、PSA検査では正常とされる数値だったといいます。PSA検査だけでは見逃される前立腺がんをMRIで発見できる可能性が示されました。BBCの記事です。
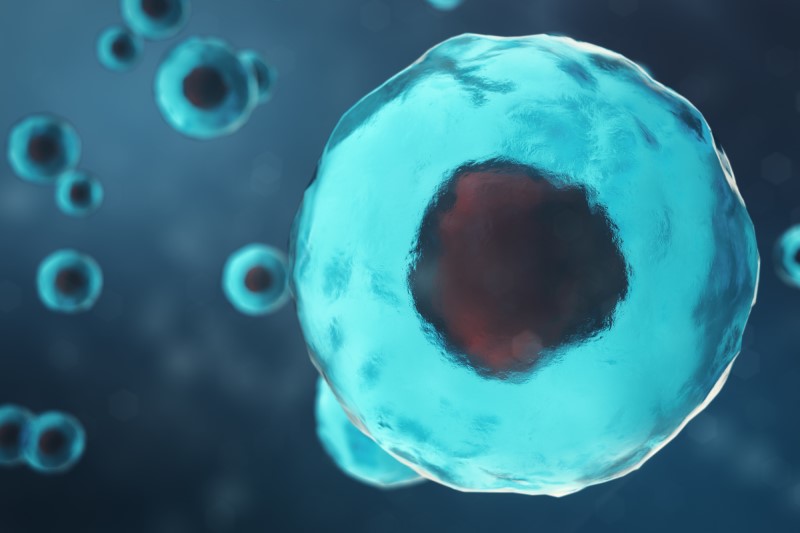
皮膚細胞や血液細胞などの体細胞から作られるiPS細胞(人工多能性幹細胞)はさまざまな種類の細胞に変化することが知られています。しかし、元の細胞の痕跡を「記憶」し続けていることがあるそうです。豪州の研究チームが、胚(受精卵)の発達プロセスを模倣することで、記憶が十分に消去されたiPS細胞を作る方法を発見。胚から作るES細胞(胚性幹細胞)のように機能させることができるといいます。iPS細胞を治療に活用する可能性が高まるとのこと。Medical Xpressの記事です。

胃酸の分泌を抑える効果があり逆流性食道炎の治療などに使われる「プロトンポンプ阻害薬(PPI)」について、新たな注意点が明らかになったようです。米国の研究チームが、非認知症の5712人(45~64歳)のデータを分析。PPIを使用していた人は約1500人(26%)いたそうです。4.4年を超えてPPIを使用した人は、一度も使用したことがない人に比べて認知症の発症リスクが33%高くなることが分かったといいます。使用期間が4.4年以下であればリスクは上昇しなかったとのこと。CNNの記事です。

DNAの塩基配列の変化ではなく、化学反応などで遺伝子の働きが変化する「エピゲノム」が原因で、悪性脳腫瘍「神経膠腫(グリオーマ)」が発生する可能性があるそうです。米国の研究チームがヒトのグリオーマにおいて、エピゲノムによって働きが変化するとみられる二つの遺伝子を特定したとのこと。一つはがん誘発遺伝子で、もう一つはがん抑制遺伝子だそうです。動物実験では、これらの遺伝子のエピゲノムによって脳腫瘍の形成が促進されたといいます。EurekAlert!の記事です。

生きた善玉菌「プロバイオティクス」を使って、自己免疫疾患の一種「多発性硬化症(MS)」を治療できるかもしれません。米国の研究チームが、免疫細胞の応答に関与する「樹状細胞」の活性を調節できる特別なプロバイオティクスを開発したといいます。これをMSマウスの腸に投与したところ、脳の重要な領域で自己免疫応答が抑制されたそうです。人間でも同様の効果が得られれば、既存の治療法より正確で、副作用が少なくなる可能性があるとのことです。ScienceAlertの記事です。

米食品医薬品局(FDA)は21日、ファイザー社が開発した初の妊婦向けRSウイルス(RSV)ワクチン「Abrysvo」を承認したそうです。RSVは下気道感染症を引き起こす一般的なウイルスで、乳児の入院の主な原因の一つ。母親が妊娠後期にワクチンを接種することで、生まれた乳児を生後6カ月までRSV感染から保護できるといいます。18カ国の女性7400人に対する臨床試験では、乳児のRSV感染による重症化を生後3カ月で82%、生後6カ月で70%、それぞれ予防する効果があったとのこと。nprの記事です。

多くの人が大麻を吸うことのリスクを理解していないそうです。米国の研究チームが2017年、20年、21年に平均50歳の5000人に大麻とタバコに対する考え方を調査。大麻への肯定的な認識が年々高まっており、21年には44%以上がタバコより大麻の方が安全と答えたといいます。しかしこれまでの研究で、大麻の煙を吸うことが呼吸器症状を引き起こすほか、肝臓や神経の損傷、貧血、がんなどに関連する血中・尿中の毒素レベルを高めることが分かっているそうです。CNNの記事です。

乳がん患者の中には、放射線治療が不要な人もいるようです。カナダの研究チームが、ステージ1のルミナルA型乳がんを患う55歳以上の女性500人を追跡調査。対象者は、リンパ節や他の場所にがんの転移はなし▽腫瘍の大きさは2cm以下▽がんのグレードは1または2▽がんの増殖能力を示すKi67は13.25%未満(15%超は再発可能性が高い)――だったといいます。こうした条件を満たす患者は、手術とホルモン療法だけで効果的に治療できることが示されたとのことです。CBCの記事です。

豪州の研究チームが、スマートフォンやパソコンのブルーライトを避けるために専用の眼鏡をかけても特に効果はないとの研究結果を発表したそうです。チームはブルーライトに関する17の研究を分析。ブルーライトカット眼鏡を使っても、眼精疲労や睡眠の質に違いは生じないことが分かったそうです。ブルーライト用レンズが網膜を保護するという証拠も示されなかったといいます。ただし、分析した研究の調査期間は1日~5週間と短かったとのこと。BBC Science Focusの記事です。

統合失調症の治療は「ドーパミンD2受容体」を標的にすることが有効とされていますが、この考えは間違っているかもしれません。米国の研究チームが、マウスを使って4種類の抗精神病薬の効果と脳への作用を調査した結果です。効果がある薬には、「ドーパミンD1受容体」を発現する中型有棘神経細胞の過活動を正常化する作用があることが分かったそうです。統合失調症に関連するのは、D2受容体ではなくD1受容体である可能性が示唆されたといいます。ScienceAlertの記事です。

ニュージーランドの研究チームがマウスの実験で、小麦などに含まれるグルテンが脳の視床下部の炎症を引き起こすことを発見したそうです。視床下部は内分泌や自律機能の調節を行う部位です。マウスの標準的な食事にグルテンを加えると、高脂肪食を取るのと同じくらい脳内の免疫細胞ミクログリアや神経細胞の活動を制御するアストロサイトが増加し、炎症状態になったといいます。高脂肪食にグルテンを加えると、これらの細胞はさらに増えたとのこと。Medical Xpressの記事です。

米国の研究チームが、人体に適応しやすいように遺伝子操作したブタの腎臓を脳死状態の男性に移植したところ、1カ月以上にわたって正常に機能し続けているそうです。ブタの臓器が人体内で正常に働いた期間としては過去最長だといいます。またチームは、移植された臓器に対する拒絶反応を抑えるため、免疫抑制剤に加えて新たな方法も試しています。免疫細胞が訓練を受ける臓器であるブタの胸腺を、腎臓に付着させた状態で移植したのだそうです。AP通信の記事です。

健康を維持するためには1日1万歩程度の歩行が必要だといわれています。しかし、この考えは間違っているかもしれません。ポーランドの研究チームが、6カ国で行われた健康と歩数に関する17の研究から計22.7万人のデータを分析。1日4000歩程度歩くだけで、全死因死亡リスクが低下することが明らかになったそうです。1日の歩数が1000歩増えるごとに、死亡リスクは15%下がったといいます。年齢が若いほうが、死亡リスクの下がり幅が大きかったとのこと。NBC Newsの記事です。

ドイツ政府は16日、大麻の規制を緩和する法案を承認したそうです。法案によると、18歳以上の成人は娯楽目的で25gまでの大麻を所持することが可能になり、大麻草を3株まで栽培することも認められます。大麻を購入・栽培するには、「大麻クラブ」と呼ばれる非営利団体に所属する必要があるそうです。議会を通過すれば、法案は年内にも成立する見通しとのことです。政府は、粗悪品の取引や薬物関連犯罪の抑止につながることを期待しているといいます。AP通信の記事です。

高齢者は健康のために毎日の食事にイチゴを加えるといいようです。米国の研究チームが、66~78歳の健康な男女35人を対象に調査を実施。8週間にわたりイチゴのフリーズドライパウダー26gを毎日摂取すると、認知処理スピードが5.2%速くなることが分かったといいます。さらに収縮期血圧は3.6%低下し、総抗酸化能は10.2%上昇したとのこと。以前からイチゴには脳や心血管の健康を促進する効果があると考えられており、今回の研究でそれが実証されたといいます。SciTechDailyの記事です。

炎症性腸疾患の一つ「クローン病」の発症に重要な役割を果たすのは、腸内細菌叢だけではないようです。複数の研究が、クローン病患者と健康な人では口腔内の細菌に違いがあることを示唆しているそうです。クローン病患者の腸内で多く見つかる数種類の細菌が、口腔内にも存在することが分かっているといいます。また、通常は口腔内に住み、歯周病などに関連する細菌「ベイロネラ・パルブラ」が、クローン病患者の腸で数多く確認されているとのこと。The Conversationの記事です。

慢性的な便秘は脳に悪影響を及ぼすようです。米国の研究チームが、成人11.2万人を調査した結果です。今回の研究では、3日以上排便がないことを「便秘」と定義したそうです。慢性的な便秘の人は、1日1回排便がある人に比べて認知機能が衰えており、その程度は3歳老化することに相当するといいます。1日2回以上排便がある人にも同様のリスクが見られたそうです。こうした結果には、腸内細菌叢の善玉菌の減少が関連している可能性があるとのこと。CNNの記事です。

運動の健康への効果は、行うタイミングによって違いがあるのでしょうか。米国の研究チームが、英国の健康な中年9万人を対象に1週間の活動量を記録したデータを分析。ウオーキングなどの中強度運動を週に150分以上行う人は、座りがちな生活を送る人に比べて6年以内に脳卒中や心臓発作などを発症するリスクが低かったそうです。運動の半分以上を週末にまとめて行う人と毎日少しずつ分散して運動する人で、結果に違いは見られなかったといいます。The Conversationの記事です。

困難といわれている心房細動(AFib)の再発予防が可能になるかもしれません。米国の研究チームが、免疫細胞のマクロファージがAFibの発症に関与していることを発見。チームは、AFib患者の心房組織でマクロファージが他の細胞よりも増殖しており、活動的であることを突き止めました。また、マクロファージの SPP1遺伝子がAFibの発生に関係していることも判明。さらにマウスの実験で、マクロファージを阻害するとAFibが抑制されることも示されたといいます。Medical Xpressの記事です。

平日と休日で寝る時間が変わることで心身に不調をきたす「ソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ぼけ)」を知っていますか。英国の研究チームが、参加者1000人を対象に調査を実施。就寝から起床までの中間点が、1週間の中で90分ずれるだけで、腸内で見つかる細菌の種類に違いが生じることが分かったそうです。睡眠の質が悪いと炭水化物や糖分の多い食べ物を強く欲するようになり、これが腸内細菌叢の組成に悪影響を及ぼす可能性があるといいます。BBCの記事です。

毎日オリーブオイルを摂取すると、脳の健康に良い影響があるかもしれません。米国の研究チームが、女性6万600人と男性3万2000人を対象に28年間の調査を実施したそうです。調査開始時、参加者の平均年齢は56歳だったとのことです。食事の全体的な質に関係なく、1日にテーブルスプーン半杯以上のオリーブオイルを摂取する人は、ほとんどまたは全くオリーブオイルを摂取しない人に比べて認知症で死亡するリスクが28%低いことが分かったといいます。CNNの記事です。

英国で48歳の男性が新種の細菌感染症にかかったそうです。男性は野良猫に手をかまれ、8時間後に患部が腫れあがったために救急外来を受診。傷口の手当と破傷風ワクチンの接種を受け、抗菌薬が処方されたそうです。ところが翌日も患部が赤く腫れあがっていたため、傷口周辺の損傷組織の除去手術を受け、複数の抗菌薬が追加されたといいます。その結果、傷は完治したそうです。調査したところ、グロビカテラ属の未知の細菌が原因だと判明したとのこと。ScienceAlertの記事です。

うつや不安が、がん発症リスクに関連するという説は本当なのでしょうか。オランダの研究チームが同国、英国、ノルウェー、カナダの成人30万人以上のデータを分析。26年の追跡調査で、「うつ」「不安」と「全がん」「乳がん」「前立腺がん」「大腸がん」「アルコール関連がん」の間に関連がないこと明らかになったそうです。肺がんや喫煙関連がんはリスクが6%上昇するものの、これには、がん発症につながる不健康な行動が影響しているようです。Medical Xpressの記事です。

米食品医薬品局(FDA)は4日、米セージ・セラピューティクスとバイオジェンが開発した産後うつを緩和する経口の抗うつ薬「zuranolone(ズラノロン)」を承認したそうです。米国で産後うつ向けの経口薬が承認されたのは初。患者は1日1回、2週間続けて薬を飲むそうです。重症の患者に対する治験では、服用後3日以内に効果が表れたといいます。眠気やめまい、下痢などが主な副作用とのこと。これまでの薬は医療施設で60時間の点滴を受ける必要があったといいます。CNNの記事です。

米疾病対策センター(CDC)は3日、RSウイルス(RSV)感染症の予防薬「Nirsevimab(ニルセビマブ)」について、RSVの流行期を初めて迎える生後8カ月未満の全ての乳児が注射を受けることを推奨したそうです。この薬はアストラゼネカとサノフィが開発したヒトモノクローナル抗体製剤で、米食品医薬品局(FDA)の承認を先月得ています。今秋予定の実際の投与開始に当たり、1回495ドルという高い価格や、技術的にワクチンではないことから運用面でハードルが存在するとのこと。nprの記事です。

精神疾患はこれまで考えられてきたよりも身近な存在のようです。オーストラリアと米国の共同研究チームが、世界29カ国の成人15万人を20年にわたり追跡調査。半数の人が、75歳までになんらかの精神疾患を経験していたことが明らかになったといいます。最も多かったのは、うつ病と不安障害。精神疾患を発症した年齢は15歳が最多で、半数以上が19歳までに発症することが分かったそうです。若者のメンタルヘルスケアの重要性が指摘されています。ABC News(AUS)の記事です。
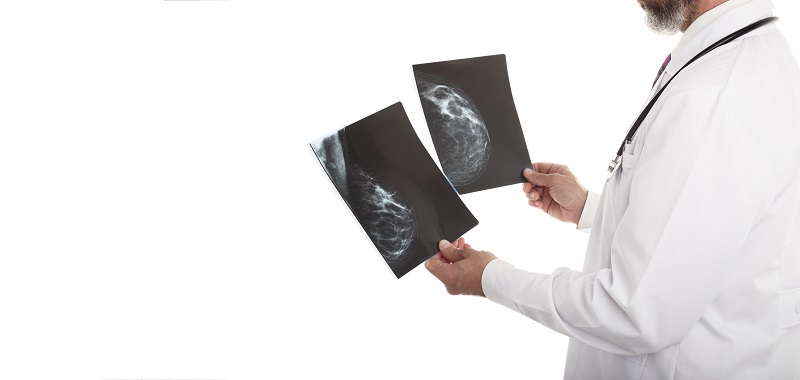
人工知能(AI)が、マンモグラフィ検査の精度と効率を格段に高めるかもしれません。スウェーデンの研究チームの調査で、経験豊富な放射線科医が、マンモグラフィ検査のスキャン画像を基に女性8万人を診断。AIの画像分析を活用した医師は、医師2人で診断に当たった場合に比べて、乳がんを20%多く検出できることが分かったそうです。さらに、AIを使うと、医師の作業負荷が44%減少し、時間短縮を期待できるとのこと。CNNの記事です。

らい菌が感染することで皮膚や神経に病変が生じるハンセン病が、米フロリダ州の風土病になりつつあるそうです。米疾病対策センター(CDC)によると、2020年に新たに確認されたハンセン病患者は全米で159人。その20%が同州中央部のセントラルフロリダ地域からの報告で、それは州全体の報告数の81%を占めます。らい菌は感染力が弱く、90%の人は免疫が抑え込むそうです。発症しても治療薬で治せるのですが、後遺症や合併症を防ぐために早期診断が重要とのこと。CBS Newsの記事です。

DNAの複製に不可欠なタンパク質「増殖細胞核抗原(PCNA)」を標的にした固形がんの治療薬が、前臨床試験で有望な結果を示したようです。米国の研究チームが、がん細胞内のPCNAのみを標的にするよう設計した経口薬「AOH1996」を開発したそうです。70以上のがん細胞株を使って調査したところ、この薬ががん細胞のみを特異的に破壊できることが確認されたといいます。AOH1996を使うと、がん細胞が他の抗がん剤に反応しやすくなることも明らかになったとのことです。Medical Xpressの記事です。

順天堂大学の研究チームが、アルツハイマー病(AD)の進行を抑える可能性のあるワクチンを開発したと米心臓協会(AHA)の会合で発表したそうです。老化細胞に発現するSAGPタンパク質を標的にしたもの。ADの症状を持つマウスに投与したところ、アミロイドプラークの蓄積や炎症関連分子の発現が抑制され、挙動や認知力が改善したそうです。SAGPが脳内の免疫細胞ミクログリアの近くで多く発現することも新たに分かったといい、これも治療法の開発に役立ちそうです。ScienceAlertの記事です。

昼寝は各子どもの認知的ニーズが反映されているため、好きなだけさせた方がいいようです。英国の研究チームが、生後8カ月~3歳の子ども463人を調査。当時は2020年の新型コロナのロックダウン中で子どもたちは家におり、それぞれが必要とするだけの昼寝をしていたといいます。調査の結果、睡眠中に情報整理を効率的に行っている子どもは、昼寝が少ない回数で済むことが判明。反対に、語彙力や認知スキルが未熟な子どもは、標準より昼寝を多くする必要があるとのことです。EurekAlert!の記事です。

米国立衛生研究所(NIH)が、「新型コロナ後遺症」の治療法を探る研究を開始したそうです。コロナ感染後に10~30%の人が、何らかの原因不明の後遺症を経験するといいます。NIHは、知られている200以上の症状別に臨床試験を行う予定。最初は、本来感染初期に使うコロナ治療薬「パキロビッド」を25日間投与した場合の後遺症への有効性を調査するそうです。「ブレインフォグ」や睡眠障害、POTS(体位性頻脈)についての研究開始も決まっているといいます。AP通信の記事です。

筋肉作りに良いとされる「β-ヒドロキシβ-メチル酪酸(HMB)」サプリメントが、認知症に有効な可能性があるようです。米国の研究チームが、アルツハイマー病(AD)モデルマウスにHMBサプリを経口で投与。HMBが学習や記憶に関連する脳領域の健康維持に役立つことが分かったそうです。さらに、ADに関与するとされる脳内のプラーク蓄積が抑制されることも判明。詳細な分析で、脳のシグナル伝達に関与するPPARα受容体にHMBが作用することが示されたといいます。ScienceAlertの記事です。

マジックマッシュルームに含まれる「サイロシビン」で、神経性痩せ症(拒食症)に関連する体重や食への異常なこだわりを軽減できる可能性があるようです。米国の研究チームが、拒食症の部分寛解状態にある女性患者10人を対象に第1相試験を実施しました。サイロシビンによる治療を始めてから3カ月経過時点までに、特に患者の体重に関する不安が有意に軽減することが示されたそうです。この治療法の安全性と良好な忍容性も確認されたといいます。Medical Xpressの記事です。

マダニが原因の「アルファガル(α-gal)症候群(AGS)」に、最大45万人の米国人が罹患していると米疾病対策センター(CDC)が発表したそうです。マダニにかまれ、唾液に含まれる糖分子(糖鎖) α-galが体内に入ることでアレルギー体質になります。α-galは牛や豚の赤身肉、一部の薬剤などにも存在するので、それらを摂取すると2~6時間後にアレルギー反応が現れるといいます。主な症状はじんましんや吐き気などで、アナフィラキシーが起こることもあるそうです。CBS Newsの記事です。

認知症患者に対する鎮痛薬「オピオイド」の使用は慎重に行うべきかもしれません。デンマークの研究チームが、65歳以上の認知症患者7.5万人のデータを分析。180日以内の死亡率は、オピオイドを使用しない患者が6.4%だったのに対し、オピオイドを処方された患者は33%だったそうです。また、強力なオピオイドを使った場合、180日以内の認知症患者の死亡リスクは6倍に上昇。最も深刻なのは14日以内の死亡リスクで、11倍になることが分かったといいます。CNNの記事です。

自己免疫疾患患者はメンタルヘルスに問題を抱えることが非常に多いようです。英国の研究チームが、全身性自己免疫性リウマチ疾患(SARD)患者1853人を調査。その結果、55%がうつ、57%が不安、89%が深刻な倦怠感を経験していたことが明らかになったといいます。これは健康な対照群と比べてかなり高い割合だったとのことです。また、チームは289人の医師の調査も実施しており、医師が患者のメンタル不調に気付いている割合が非常に低いことも分かったそうです。EurekAlert!の記事です。

生理用品を入手しにくい発展途上国の女性の健康を守るために、医療用シリコン製の「月経カップ」が大きな役割を担うかもしれません。米国の研究チームが、ケニアの女子中等学校の生徒436人を追跡調査。月経カップを支給された人は、そうでない人に比べて細菌性膣炎になる可能性が26%低く、膣内細菌叢の組成が最適な状態である可能性が37%高かったそうです。さらに、月経カップを使用すると、性感染症のリスクが低くなることも示唆されたといいます。EurekAlert!の記事です。

表皮と真皮を結合するコラーゲンに異常が生じ、皮膚や角膜に水疱ができるまれな遺伝子疾患「栄養障害型表皮水疱症(DEB)」のキューバの少年(10代)の視力回復に成功したそうです。米国のチームが、角膜病変を除去した上で、DEBの皮膚治療に使われる遺伝子療法の点眼薬を開発して投与。単純ヘルペスウイルス1型(HSV-1)ベクターを用いてコラーゲンの遺伝子を導入する方法です。その結果、病変は再発せず、失明状態だった視力がほぼ完璧に回復したとのこと。AP通信の記事です。

がんサバイバーから、通常より優れた細胞傷害性T細胞(Tc細胞)が見つかったそうです。英国の研究チームが、腫瘍浸潤リンパ球輸注療法(TIL療法)を受ける末期の固形がん患者で、がんが消滅した人を調査。Tc細胞は通常、がん細胞表面の一つの標的を認識して攻撃を仕掛けます。しかし、これらの患者には、複数の異なる標的を同時に認識するTc細胞が存在していたそうです。このTc細胞は、がん治癒後1年以上たっても強いがん攻撃能力があったといいます。Medical Xpressの記事です。

発熱がウイルス感染の重症化を抑制するメカニズムが明らかになったようです。東京大学などのチームが、マウスにインフルエンザや新型コロナのウイルスを感染させて調査。36℃の高い外気温で1週間飼育したマウスは、低い外気温で飼育したマウスに比べて生存率が高かったといいます。体温がより高く(38度以上に)上昇し、腸内細菌叢が活性化して代謝物の二次胆汁酸が増加したためだそうです。二次胆汁酸はウイルス増殖や炎症反応の抑制に関わります。Medical Xpressの記事です。

大麻の使用は遺伝子の発現に変化をもたらすようです。米国の研究チームが発見したのは、遺伝子発現の調節がDNA塩基配列の変化ではなく、メチル化などを通して行われる「エピジェネティクス」と呼ばれるもの。18~30歳の1000人について、15年後と20年後の血液を解析し、大麻使用に関連するDNAメチル化マーカーを調べた結果です。 15年、20年時点の両方で、最近の大麻使用に関連するマーカーと、長期の大麻使用に関連するマーカーが特定されたとのこと。Science Alertの記事です。

アトピー性皮膚炎の治療薬として知られる「デュピルマブ」が、慢性閉塞性肺疾患(COPD)の治療を飛躍的に前進させるかもしれません。米国などの研究チームが、2型炎症が示唆されるCOPD患者939人を対象に調査を実施したといいます。デュピルマブを2週間ごとに皮下投与された人は、プラセボ群に比べて中等~重度の急性増悪の発生が1/3少なくなることが分かったそうです。さらにデュピルマブ群のほとんどで、肺活量が倍増することも明らかになったとのこと。Medical Briefの記事です。

米国では、1年間に79万5000人が誤診によって障害を負ったり、死亡したりするそうです。米国の研究チームの報告によると、脳卒中、敗血症、肺炎、静脈血栓塞栓症、肺がんの5疾患が誤診の38.7%を占めます。誤診のリスクを下げるため、患者は医師に①不調の原因として何が考えられるか②他にどんな可能性があるか③検査結果はいつ出て、自分は何をしたらいいか――を聞くとよいそうです。特に②は、型にはまらない考え方をしてもらうために重要とのこと。INSIDERの記事です。

全身の細胞の表面に存在するタンパク質「ヒト白血球抗原(HLA)」に特別な遺伝子変異があると、新型コロナウイルスに感染しても症状が出ない可能性が高いようです。米国の研究チームが、骨髄ドナーのデータベースから1500人のHLAを分析。参加者はみな白人で、コロナワクチン未接種者だったそうです。HLAに「HLA-B*15:01」と呼ばれる変異を2コピー保有している人は、この変異を持たない人に比べて、コロナ陽性でも無症状である可能性が8倍以上高かったといいます。NBC Newsの記事です。

アルツハイマー病(AD)に関連するとされるタンパク質タウの凝集を防ぐ飲み物があるようです。イタリアの研究チームが、市販のコーヒー豆から抽出したエスプレッソ液やその成分を、ADの原因の一つとされるタウ線維と共に実験室で40時間培養。エスプレッソ抽出液やカフェイン、イソフラボンの一種であるゲニステインの濃度が高くなるほど、タウ線維が短くなり、凝集が抑制されたといいます。中でもエスプレッソ抽出液がもっとも効果的だったとのこと。Medical Xpressの記事です。

母乳に含まれる糖分子「ミオイノシトール」が脳の発達に重要な役割を果たすようです。米国の研究チームが米シンシナティ、メキシコ市、中国・上海市の3都市で母乳サンプルを分析。ミオイノシトールが授乳初期には全ての母乳に高濃度で含まれており、その後徐々に減少することが分かったそうです。そして、培養したヒト神経細胞や脳組織を使った実験で、ミオイノシトールがシナプスを増やし、神経細胞の接続を促進することが判明したといいます。Medical Xpressの記事です。

補聴器を使って耳の聞こえを改善することで、高齢者の認知機能低下を抑えられるかもしれません。米国の研究チームが、平均年齢77歳の高齢者977人に3年間の調査を実施。高血圧や糖尿病の影響で認知症リスクが高いとみなされた人について、専門家による助言とともに補聴器を使用すると、健康に関する講習を受けただけの人に比べて認知機能の低下が48%遅くなることが分かったそうです。一方で、健康な人はこのような違いは認められなかったといいます。CBCの記事です。

世界保健機関(WHO)は、ポーランドで猫29匹がH5N1型鳥インフルエンザに感染したと報告したそうです。一つの国の広いエリアで、これほどの数の猫が鳥インフルに感染したことが確認されたのは初めてとのこと。感染が確認された猫の一部は呼吸困難や血の混じった下痢、神経症状などの重篤な症状を発症し、急速に悪化して死んだといいます。感染の原因は現時点では不明だそうです。感染した猫に接触した人もいますが、症状が出たという報告はないようです。ScienceAlertの記事です。

米イーライリリー社の新たなアルツハイマー病(AD)治療薬「Donanemab(ドナネマブ)」の臨床試験の結果が報告されたそうです。この薬はADに関連するタンパク質アミロイドβを除去するモノクローナル抗体です。1700人を対象に行った臨床試験では、ADの進行を35%遅らせることが判明。米食品医薬品局(FDA)が最近承認した同様のAD新薬レカネマブは、ADの進行を27%抑制するといわれています。AD初期段階でドナネマブを使用すると、より効果が高まることも示されたとのこと。nprの記事です。

米食品医薬品局(FDA)は17日、RSウイルス(RSV)感染を予防する乳幼児向けのヒトモノクローナル抗体製剤「Nirsevimab(ニルセビマブ)」を承認したそうです。開発は英アストラゼネカと仏サノフィ社で、全ての乳幼児が利用可能なRSV抗体薬の承認は初。臨床試験では、同薬がプラセボ群と比べてRSVで受診するリスクを70%、入院するリスクを78%それぞれ抑制することが示されたそうです。対象は生後24カ月までの乳幼児で、注射で1回投与すると4~6カ月効果が持続するとのこと。CNNの記事です。

世界保健機関(WHO)傘下の国際がん研究機関(IARC)は、低カロリーをうたう飲料などに一般的に使われる人工甘味料「アスパルテーム」について、「ヒトに対して発がん性がある可能性がある」との見解を示したそうです。ただし、一般的な量を摂取する分には過度な心配は不要だといいます。アスパルテームは、発がん性があるかどうかの「証拠の強さ」を示す分類で、ガソリンによる排気ガスなどと同じ「2B」(4段階の上から3番目)に指定されたとのことです。CBS Newsの記事です。

米国の女性は近々、目薬と同じくらい簡単に経口避妊薬を購入できるようになるようです。米食品医薬品局(FDA)は13日、経口避妊薬「Opill(オーピル)」を処方箋なしで買える市販薬として承認しました。購入に年齢制限はなく、販売が開始されるのは来年初めになる見通しだそうです。オーピルは黄体ホルモン「プロゲスチン」のみを配合した薬です。エストロゲンとプロゲスチンが配合されている一般的な経口避妊薬に比べて副作用のリスクが低いといいます。AP通信の記事です。

クルミなどに含まれるオメガ3脂肪酸の一種「アルファリノレン酸(ALA)」が、筋萎縮性側索硬化症(ALS)の進行を抑制する可能性があるそうです。米国の研究チームが、ALS患者449人を対象に18カ月の調査を実施。血中ALAレベルが最も高い群に属していた人は、最も低い群の人に比べて調査期間中に死亡するリスクが50%低かったそうです。オメガ3脂肪酸の一種「EPA」とオメガ6脂肪酸の一種「リノール酸」も死亡リスク低下に関連していたといいます。Medical Xpressの記事です。

減量薬として広く使われている「オゼンピック」や「サクセンダ」などのGLP-1受容体作動薬ついて、自傷や自殺念慮のリスクが懸念されているようです。アイスランド当局が、このいずれかの薬を使用した人による自殺念慮や自傷念慮の症例を3件報告したそうです。欧州医薬品庁(EMA)は他のGLP-1受容体作動薬にも範囲を広げ、同じような可能性が考えられる150のケースについて現在調査を進めているといいます。調査は11月まで続く見込みとのことです。CNNの記事です。

新型コロナウイルスが野生のシカとヒトの間で感染を繰り返すことがあるようです。米農務省の動植物検疫局(APHIS)が、米国で2021年11月~22年4月に野生のオジロジカから採取した8830検体を分析。ヒトで流行したコロナ変異株がシカに伝染し、ヒトの間でその変異株の流行が収まった後もシカの間で残っていることが分かったそうです。ヒトからシカに伝染したウイルスが変異し、それがシカからヒトにうつって広がったケースも少なくとも3件確認されたとのこと。CBS Newsの記事です。

米疾病対策センター(CDC)は約70年ぶりに、犬の輸入に関する規定の改定を提言したそうです。狂犬病の再流入を防ぐことが目的。狂犬病は、米国では2007年に根絶していますが、今も世界100カ国以上でまん延しています。毎年約5万9000人が死亡し、ほとんどが犬にかまれた子どもだといいます。提言によると、狂犬病ハイリスク国から犬を持ち込む場合、出発地政府公認の獣医師の署名などがあるワクチン接種証明書が必要で、米国到着後に再接種を求めるとのこと。CNNの記事です。
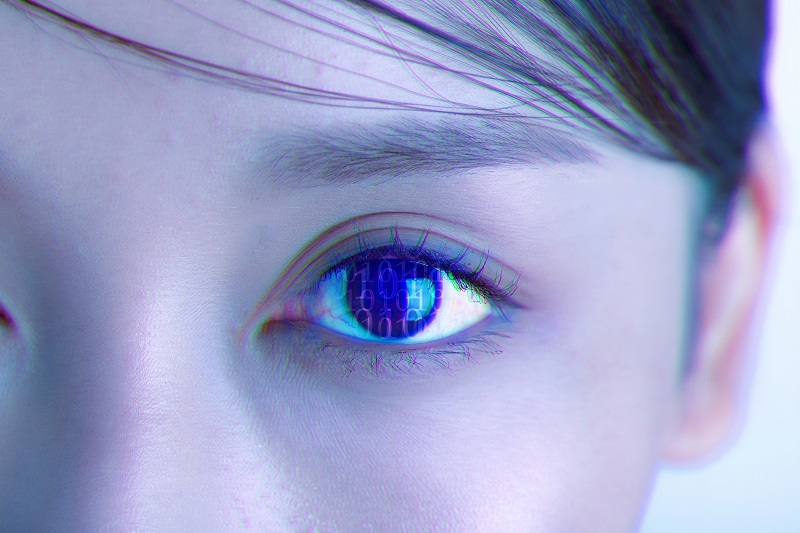
実際には誰もいないのに誰かが近くにいる気配を感じたら、それはパーキンソン病(PD)の症状悪化の予兆かもしれません。スイスの研究チームが、60~70歳のPD患者75人を対象に5年間の調査を実施。PD初期に誰かがいるような錯覚を経験した人は、前頭葉がつかさどる注意力や問題解決、感情調節などに関連する認知機能の低下が速いことが分かったそうです。こうした錯覚がPD初期に起こる人には、特有の脳波パターンがあることも明らかになったといいます。ScienceAlertの記事です。

免疫療法の効果を向上させるには、糞便移植(FMT)で患者の腸内環境を整えると良いそうです。カナダの研究チームが、今回は悪性黒色腫(メラノーマ)患者20人を対象に第1相試験を実施しました。健康なドナーから採取した糞便の経口カプセルを免疫療法開始の1週間前に投与したところ、65%で治療への反応が確認されたそうです。メラノーマ患者で免疫療法の効果が得られるは通常40~50%だといいます。FMTと免疫療法の併用の安全性も示されたとのことです。ScienceDailyの記事です。

米食品医薬品局(FDA)が6日にエーザイのアルツハイマー病(AD)新薬「レカネマブ」を正式承認しました。軽度認知障害(MCI)または初期段階の患者の病気の進行を遅らせる薬です。ただ、有効性に疑問を持つ専門家がいるようです。第3相試験では、同薬がプラセボ群に比べてADの進行を27%遅らせることが判明。しかしこれは、患者や家族が効果に気付かない可能性があるほどわずかな違いだといいます。なお専門家は「ADを治せるわけではない」との指摘もしています。NBC Newsの記事です。

運動には認知機能の低下を抑える効果があるといわれています。しかし6~8時間の十分な睡眠を取らないと逆効果になるようです。英国の研究チームが、認知機能に問題がない50歳以上の中高年9000人に対し10年以上にわたる調査を実施。50、60代のときに身体活動レベルが高く、1日の平均睡眠時間が6時間未満だった人は、10年後に認知機能の低下が速く進むことが分かったそうです。その認知機能レベルは、運動をしなかった人と同程度だったといいます。CNNの記事です。

不健康な状態で歯を残しておくと、認知機能に悪影響があるようです。東北大学の研究チームが、記憶力が正常な55歳以上の日本人172人を4年間調査。アルツハイマー病の初期には記憶をつかさどる脳の海馬の左側(左海馬)が萎縮するといいます。調査の結果、軽度歯周病の人は、残っている歯が少ないほど左海馬の萎縮速度が速いことが分かったそうです。一方で重度歯周病の人は、残っている歯が多いほど左海馬の萎縮速度が速まったとのことです。Science Alertの記事です。

欧州バイオインフォマティクス研究所(EBI)が、研究者や医師、政策立案者などが病原体に関する広範囲の生体分子データにオンラインでアクセスできる「病原体ポータル(Pathogens Portal)」を開設したそうです。将来のパンデミックに備えるのが目的で、20万種類以上の病原体のデータを掲載。塩基配列やゲノムデータはもちろん、世界中のあちこちに散らばっているさまざまな種類のデータを集約し、誰もが迅速かつ容易にアクセスできるようにすることを目指すといいます。EurekAlert!の記事です。

ピロリ菌感染による胃がんリスクは特定の遺伝子変異によって高まるそうです。理化学研究所(理研)などの研究チームが今年3月、胃がん患者1.2万人と非がん患者 4.4万人のDNAサンプルを分析した結果を米医学誌NEJMに発表しています。チームは胃がんリスク上昇に関連する九つの遺伝子変異を発見。胃がん発症リスクは、ピロリ菌感染に加えて、この中の特定の四つの遺伝子変異のいずれかを持つ人が約45%。ピロリ菌感染のみの人のリスクは約14%だったとのこと。SciTechDailyの記事です。

国際的にはBMI(体格指数)25以上を過体重、30以上を肥満と定義するそうです。米国の研究チームが、1999~2018年の同国の成人55万4332人のデータを分析したところ、過体重は死亡リスク上昇にほとんど関連しないことが分かったそうです。高齢者はBMIが22.5~34.9であれば全死因死亡率が有意に上昇することはなく、若者はBMIが22.5~27.4であれば死亡率に影響はなかったそうです。チームは「BMIだけで臨床的な判断をすることへの懸念が高まっている」としています。Medical Xpressの記事です。

睡眠不足がうつ病患者の気分の落ち込みを改善するケースがあるようです。米国の研究チームが、健康な38人と大うつ病性障害(MDD)患者30人に眠らせない(睡眠剥奪)実験を実施。その結果、一晩まったく睡眠を取らなかったMDD患者のうち43%で、気分の落ち込みが改善したことが分かったそうです。機能的磁気共鳴画像(fMRI)を使って脳内を分析したところ、気分が向上した人は、情動や感情の処理に関わる扁桃体と前帯状皮質の接続が有意に増加していたとのこと。Medical Xpressの記事です。

米ファイザー社が開発した円形脱毛症の経口治療薬「リットフーロ(一般名:リトレシチニブ)」が、米食品医薬品局(FDA)に承認されたそうです。対象は12歳以上。頭部の半分以上に脱毛がある患者700人を対象に行った臨床試験では、1日50mgのリットフーロを6カ月間服用した人の23%が脱毛の範囲が20%以下になったといいます。プラセボ群で脱毛の範囲が20%以下になったのは1.6%だったそうです。脱毛の初期段階で薬を服用すると、より効果が高まるとのことです。ScienceAlertの記事です。

パートナーと別々のベッドや寝室で寝る「睡眠離婚」は、本当に睡眠の質を改善するのでしょうか。米国の研究チームが、同国の成人1250人を調査。回答者の1.4%が1年以上パートナーと別々に寝ていることが分かったそうです。パートナーと別々に寝ることで睡眠の質が向上したと答えたのは52.9%だったといいます。一方、睡眠離婚を試した人のうち25.7%が再びパートナーと一緒に寝ることを選択し、それによって睡眠時間が増加したと答えたとのことです。ScienceAlertの記事です。

腸内細菌が目の健康にも影響を及ぼす可能性があるようです。米国の研究チームが、ドライアイマウスの腸内の善玉菌を抗菌薬で一掃して調査。ヒト由来のプロバイオティクス「リモシラクトバチルス・ロイテリ菌DSM17938株」を5日間経口投与されたマウスは、生理食塩水を投与されたマウスに比べて角膜の表面が健康な状態で、損傷も少なかったそうです。また、DSM17938投与群の目の組織には、涙の必須成分であるムチンを作る杯細胞が多く存在していたといいます。EurekAlert!の記事です。

新型コロナウイルスの感染拡大以降、1型糖尿病と診断される子どもや10代の若者が増えているそうです。カナダの研究チームが、世界各国のデータを分析。パンデミック1年目の子どもの1型糖尿病発症率は、パンデミック前に比べて14%上昇したことが分かったそうです。2年目には発症率がパンデミック前より27%高くなったといいます。コロナ感染や、子どもが本来日常生活で感染する細菌に暴露しなかったことなどが原因の可能性があるとのことです。BBCの記事です。

腰や首の痛みに対するオピオイドの使用は有害になるかもしれません。豪州の研究チームが、急性の腰痛や頸部痛で受診した350人を対象に調査を実施。オピオイド系「オキシコドン・ナロキソン錠剤」を短期間服用した人の6週間後の疼痛緩和レベルは、プラセボ群と同等だったそうです。また12カ月後には、プラセボ群の転帰のほうが若干良好だったといいます。オピオイド群は、12カ月後の時点でオピオイド乱用リスクが有意に上昇したとのことです。ABC News(AUS)の記事です。

豪州で7月1日から、うつ病や心的外傷後ストレス障害(PTSD)に苦しむ患者に対して医師が特定の幻覚剤を処方することが許可されたそうです。世界で初めてのことです。豪州の精神科医は「エクスタシー」として知られる合成麻薬「MDMA」をPTSD患者に、マジックマッシュルームに含まれる幻覚成分「サイロシビン」を難治性うつ病患者にそれぞれ処方することが可能になったといいます。価格は患者1人あたり6600米ドル(約95万5000円)に上る見込みとのこと。AP通信の記事です。

米疾病対策センター(CDC)は6月29日、二つの高齢者向けRSウイルス(RSV)ワクチンについて接種を支持することを表明しました。GSK社とファイザー社がそれぞれ開発したワクチンで、CDCの決定は米食品医薬品局(FDA)の承認とCDCの予防接種諮問委員会の勧告を受けたものです。今秋以降、医療従事者と話し合った上で60歳以上のワクチン接種が可能になります。高齢者向けRSVワクチンは、米モデルナやデンマークのババリアン・ノルディックも治験を進めているとのこと。CNNの記事です。

朝コーヒーを飲むと覚醒するのは、カフェインの効果ではないそうです。ポルトガルの研究チームが、1日1杯以上コーヒーを飲む人を対象に機能的磁気共鳴画像法(fMRI)を使って脳の活動を分析。コーヒーを飲んだ後のほうが、カフェインを単独で摂取した後に比べて行動への準備がより整った状態になり、外部刺激にも敏感になることが分かったといいます。コーヒーの匂いや味、心理的期待などが覚醒を引き起こす要因になる可能性があるとのことです。EurekAlert!の記事です。

長年肥満の定義に使われてきたBMI(体格指数)は、健康状態を予測する尺度としては不十分なようです。米国医師会(AMA)が、臨床現場でBMIを重要視するのをやめるよう呼びかける新たな指針を採用したそうです。体重と身長から求めるBMIは、集団レベルでは体脂肪率と関連があることは分かっていますが、個人の体脂肪率を予測するには正確性に欠けるといいます。体重増加の健康リスクを評価する指標として、体脂肪指数や相対脂肪量などが提案されています。The Conversationの記事です。

カロリー制限と同じくらい有効なダイエット法があるようです。米国の研究チームが、18~65歳の肥満患者90人を対象に調査。食事を取る時間を制限する「断続的断食」を行う群と摂取カロリーを制限する群は減量効果が同等で、両群ともに1年後には体重が4%減少したそうです。また、胴囲や脂肪量の減少も同等だったといいます。断続的断食群は、前半の半年間は正午~午後8時、後半の半年間は午前10時~午後8時に食事の時間を制限したとのこと。The Conversationの記事です。

自閉症や知的障害による苦しみを理由に安楽死を選択する人がいるそうです。オランダ政府が、2012~21年に同国で安楽死を選択した6万人のうち900人に関する資料を公表。これを英国の研究チームが分析したといいます。その結果、39人に自閉症や知的障害があり、このうち18人は50歳未満であることが分かったそうです。30人が苦痛の原因として「孤独」を挙げ、8人が苦しみの唯一の原因は自閉症や知的障害から来るものだと答えたとのこと。AP通信の記事です。

米国で、海外滞在歴のない人のマラリア感染が20年ぶりに確認され、米疾病対策センター(CDC)が注意を呼び掛けたそうです。米国内での感染例が最後に報告されたのは2003年だといいます。この2カ月の間にフロリダ州で4例、テキサス州で1例の計5例の国内感染が発生。5人の患者は治療を受け、現在は回復に向かっているとのことです。マラリアは蚊が媒介し、死に至ることもある感染症です。妊婦が感染すると胎児に伝染することがあります。NBC Newsの記事です。

デンマークのノボノルディスク社が開発した肥満症治療剤「Wegovy(ウゴービ:一般名セマグルチド)」の投与が経口でできるようになりそうです。同薬は現在、週1回皮下注射で投与されています。16カ月にわたって実施された二つの臨床試験の結果によると、高用量のウゴービ錠剤を毎日服用することで、皮下注射に匹敵する減量効果が得られることが判明。2型糖尿病の人にも有効だったといいます。副作用として、胃腸関連のトラブルが認められたとのこと。CBS Newsの記事です。
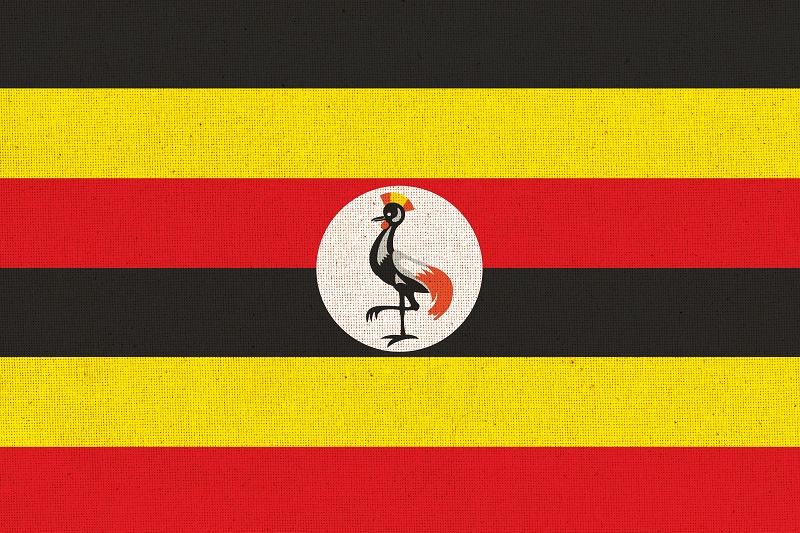
東アフリカのウガンダで、新生児が感染症を患った後に水頭症を発症するケースが多発しており、米国の研究チームが原因の細菌を突き止めたそうです。チームが感染による敗血症や水頭症を発症したウガンダの新生児を調査し、無害とされていた細菌「Paenibacillus thiaminolyticus(パエニバシラス・チアミノリティカス)」が、感染症を引き起こすことが分かったといいます。感染症の治療から数週間後に水頭症が発生した際も、この細菌はまだ体内に残っていたそうです。Medical Xpressの記事です。

認知機能に問題がある大うつ病性障害(MDD)のサブタイプが明らかになったそうです。そして、この患者には一般的な抗うつ薬は効果がない可能性があるといいます。米国などの研究チームが成人MDD患者712人を調査。このうち27%の人が、注意力や自制心を評価する認知課題をうまく処理できないことが分かったそうです。このタイプの人がうつ病の標準的な治療薬である選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)を使用しても、うつ病が寛解する割合は低かったとのこと。ScienceAlertの記事です。

米食品医薬品局(FDA)は、米Sarepta Therapeutics社のデュシェンヌ型筋ジストロフィー(DMD)に対する遺伝子治療薬「Elevidys(エレビジス)」を迅速承認したようです。対象は科学的根拠のある4~5歳の小児患者に限定。同薬の投与は単回で完了するそうです。価格は1回320万ドル(約4億5880万円)の見込みで、世界で2番目に高額な医薬品だといいます。エレビジスの販売を継続するには、現在進行中の治験で同薬が患者の身体機能や運動機能を改善することを示す必要があるとのこと。CNNの記事です。

米イーライリリー社が開発する肥満治療のための経口薬「orforglipron(オルフォルグリプロン)」が、すでに承認済みの他の減量薬(セマグルチド)に匹敵する効果を示したそうです。米国の研究チームが、平均体重108.7kgの太り過ぎか肥満の患者272人を調査。最高用量のオルフォルグリプロンを毎日服用した人は、36週時点で体重が平均14.7%減少したそうです。一方、プラセボ群の体重減少はわずか2.3%だったといいます。副作用として、吐き気や便秘などが認められたとのこと。CNNの記事です。

宇宙飛行士は宇宙滞在中に感染症にかかりやすくなるそうです。カナダの研究チームが、宇宙ステーションに4年半~6年半いた宇宙飛行士14人を調査し、その理由を明らかにしたといいます。宇宙に到着すると数日で、白血球における247の遺伝子発現が通常の1/3に減ることが分かったそうです。こうした変化は、宇宙の無重力によって体液が上半身に集まってしまうことに起因するといいます。ただ、地球に帰還後1カ月ほどで通常の状態に戻るとのこと。ABC News(AUS)の記事です。

昼寝の習慣は、加齢に伴う脳の萎縮を遅らせるかもしれません。米英などの研究チームが、40~69歳の37万8932人のデータを分析。因果関係を検討できるメンデルランダム化解析で遺伝的に昼寝をする素因があるとされた人は、平均で脳全体が15.8㎤大きいことが分かったそうです。これは脳が2.6~6.5歳若いことに相当するといいます。ただし、記憶をつかさどる海馬の大きさ、反応時間、視覚処理という脳の若さを測るその他の指標に違いはなかったとのこと。ScienceAlertの記事です。

不妊治療で授かった赤ちゃんを出産した後に、自然妊娠するのは珍しいことではないようです。英国の研究チームが、11の研究から世界中の5000人を超える女性のデータを分析。データは1980~2021年のものだといいます。分析の結果、少なくとも5人に1人が、体外受精(IVF)などの不妊治療で妊娠した赤ちゃんを出産した後、たいてい3年以内に自然妊娠していたことが分かったそうです。不妊治療の種類の違いなどを考慮しても、結果は同じとのこと。Medical Xpressの記事です。

血栓を防ぐために高齢者にアスピリンを処方する際は、患者の血中ヘモグロビン濃度に注意を払った方がいいようです。豪州などの研究チームが、65歳以上の高齢者1万8000人を対象に5年間、調査を実施したそうです。その結果、低用量(100mg)のアスピリンを毎日服用した人は、プラセボ群に比べて血液検査で貧血と診断されるリスクが20%高かったといいます。また、アスピリン群の24%が5年以内に貧血を発症すると推計されたとのことです。CNNの記事です。

免疫系や脳の発達に重要な役割を果たすとされる補体「C3aペプチド」を含む点鼻薬が、脳卒中の後遺症治療に有効な可能性があるそうです。スウェーデンの研究チームが、虚血性脳卒中を起こさせたマウスで調査。1週間後にC3aの点鼻を始めたマウスは、プラセボ群に比べて速やかに全面的な運動機能が回復したそうです。MRI検査でC3aが神経細胞の接続を増やすことが判明。脳卒中後すぐに治療できなくても、この点鼻薬の使用で回復が期待できるとのことです。ScienceAlertの記事です。

なぜ、減量してもリバウンドしてしまうのでしょうか。米国の研究チームが、痩せている(BMI25以下の)28人と肥満(BMI30以上)の30人の胃にグルコースか脂肪を直接注入し、機能的磁気共鳴画像法(fMRI)を使って脳活動を評価。痩せている人は栄養素の感知に関連する脳活動の変化が起こるのに、肥満の人にはほとんど起きなかったといいます。肥満の人に減量プログラムを行い、10%の減量に成功した人に同じ検査を実施。栄養素を感知する反応は戻らなかったそうです。SciTechDailyの記事です。

南米エクアドルで、6月9日に死亡宣告を受けた76歳の女性が、通夜の最中に棺を叩いて生きていることを知らせ、助け出されるという出来事があったそうです。女性はその後、病院に運ばれて入院していましたが、16日に脳卒中で死亡したといいます。同国保健省は、誤った死亡宣告がされた原因を調査するよう指示したそうです。女性には、体が硬くなったり意識を失ったりする「カタレプシー」(強硬症)があったとのこと。ScienceAlertの記事です。

男性ホルモン「テストステロン」の補充療法は心臓発作や脳卒中の発症リスクを高めるのでしょうか。米国の研究チームが、心臓病リスクが高く、低テストステロンによる症状がある45~80歳の男性5246人に2年間の治療と3年間の追跡調査を実施。心臓発作や脳卒中を発症した割合は、毎日テストステロンジェルを塗布した群とプラセボ群でほぼ同じだったといいます。ただし、注射投与などの場合は結果が異なる可能性を指摘する専門家もいるとのこと。USA TODAYの記事です。

米国で行われている急性骨髄性白血病(AML)と卵巣がんの新たな治療薬の治験が、死亡者が出たために中断したそうです。米2seventy bio社が、AMLに対するCAR-T細胞療法の第1相試験を実施。しかし、高用量の薬剤を投与された最初の子どもが死亡したことを受けて、治験を中断したとのことです。また、米Mersana社が行っている卵巣がん治療の抗体医薬「upifitamab rilsodotin(UpRi)」の第3相試験でも、参加者5人が出血で死亡。米食品医薬品局(FDA)は、この治験への追加登録を保留にしたといいます。CNNの記事です。
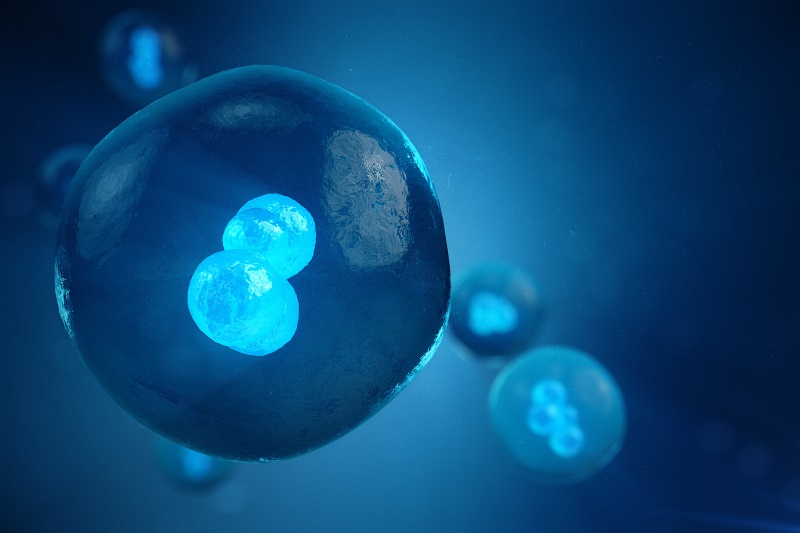
米英の研究チームが、ヒトのES細胞(胚性幹細胞)から胚のような構造体(人工胚)をつくることに初めて成功したそうです。この人工胚を使えば、遺伝性疾患や流産の原因を理解するのに役立つ可能性があるといいます。一方、このような人工胚の取り扱いを巡り、法的そして倫理的な問題が浮上しています。ヒト胚については受精後14日を超えて研究室で培養してはいけないとのルールがあるものの、人工胚に関するルールは多くの国で未整備とのこと。CNNの記事です。

子宮内膜症の発症に、細菌の感染が関与している可能性があるそうです。名古屋大学などの研究チームが、女性155人の子宮内膜組織を分析。子宮内膜症がある女性の64%から、歯周病などに関与するフソバクテリウム属の細菌が検出されたといいます。一方、子宮内膜症がない女性のうち、この細菌が検出されたのはわずか7%だったそうです。フソバクテリウム感染マウスを使った実験では、抗菌薬の投与で子宮内膜症の病変が小さくなることが示されたといいます。natureの記事です。

ポーランドで妊娠5カ月の妊婦が、破水した後に病院で適切な処置を受けられず、敗血症で死亡したそうです。この病院は非常に保守的な地域にあり、中絶は行っていなかったといいます。ポーランドでは現在、レイプや近親相姦、妊婦の命や健康が脅かされる場合にのみ中絶が認められているそうです。女性の死を受け、中絶を規制する法律に対して抗議デモが起こりました。政府は今回のようなケースは女性に中絶の権利があると強調したとのことです。AP通信の記事です。

高い悪玉コレステロール(LDL)値は心筋梗塞や脳卒中の原因になります。植物性食品中心の食生活を送ると、コレステロール低下薬「スタチン」の1/3ほどの効果が得られるようです。デンマークの研究チームが、食生活と心臓の健康に関する1982年以降の30の治験を分析。参加者は合計で2400人に上るそうです。ベジタリアンやビーガンの食事が、LDLを10%▽総コレステロールを7%▽LDLの主なタンパク質であるアポリポタンパク質Bを14%――減らすことが分かったといいます。BBCの記事です。
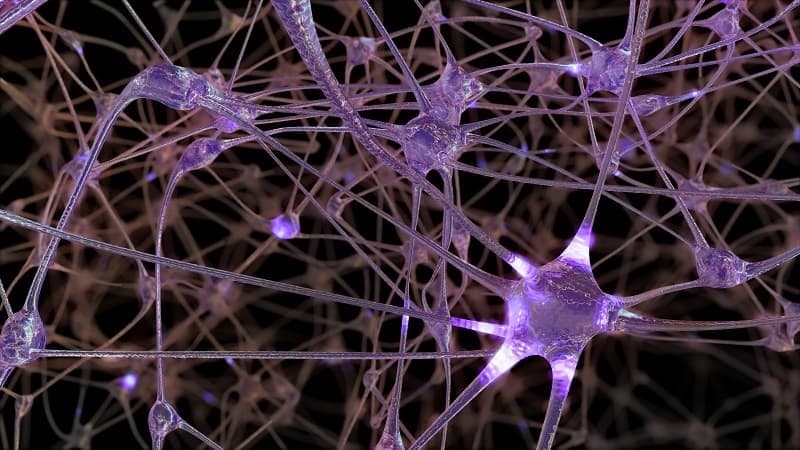
神経細胞の突起(神経線維)を覆う「ミエリン(髄鞘)」の加齢に伴う劣化が、アルツハイマー病(AD)に関連するタンパク質アミロイドβ(Aβ)の蓄積を加速させるようです。ドイツの研究チームがADマウスの調査で、劣化したミエリンによって神経線維にストレスが加わり、Aβの産生が増えることを突き止めたそうです。また、Aβの除去を担う免疫細胞ミクログリアが、劣化したミエリンの除去で手いっぱいになり、適切に働かない可能性があるといいます。SciTechDailyの記事です。

少量のアルコールはストレスを軽減し、心血管疾患リスクの抑制につながる可能性があるようです。米国の研究チームが、数千人分のデータを分析。週に1~14杯アルコールを摂取する人は、アルコール摂取量が週1杯未満の人に比べて心臓発作や脳卒中を発症するリスクが低かったそうです。さらに参加者の脳スキャンを分析したところ、軽~中程度のアルコール摂取が不安や恐怖の感情に関わる偏桃体のストレス応答を減らす可能性が示唆されたといいます。CNNの記事です。

野菜が豊富で加工食品が少なめの食生活を送ると、脳年齢に驚くべき効果がもたらされるようです。イスラエルなどの研究チームが、肥満患者102人を調査。参加者は「地中海式食事」「地中海式食事とポリフェノール」「ガイドラインに基づいた健康的な食事」のいずれかを取り続けたそうです。18カ月後、参加者の体重は平均2.3kg減少。体重が1%減るごとに、スキャン画像から推定する脳年齢が9カ月若く見えることが明らかになったといいます。ScienceAlertの記事です。

2型糖尿病の治療に一般的に使われている安価な経口薬「メトホルミン」で、新型コロナウイルス感染後の後遺症を防ぐことができるかもしれません。米国の研究チームが、太り過ぎまたは肥満の患者1126人を対象に第3相試験を実施。コロナ陽性判定後にメトホルミンを飲んだ人は、プラセボ群に比べて10カ月後にコロナ後遺症と診断されるリスクが40%低かったそうです。すでに発症している後遺症に有効かどうかは未確認だといいます。ScienceAlertの記事です。

母乳育児の期間が、子どの学業成績に影響を及ぼす可能性があるようです。英国の研究チームが、同国の乳児5000人を追跡調査しました。そして、英国で義務教育終了時に受ける全国統一試験「GCSE」の数学と英語の成績を比べたそうです。その結果、乳児期に母乳を1年以上飲んだ子どもは、母乳をまったく飲まなかった子どもに比べて高得点で合格する可能性が39%高かったといいます。また、英語で不合格になる可能性は25%低かったとのとこと。CNNの記事です。

チック症状が1年以上続く「トゥレット症候群」に対する医療用大麻の効果について、初めて厳密な検証が行われたそうです。豪州の研究チームが、重度のトゥレット症候群の成人患者22人を対象に調査を実施。THC(テトラヒドロカンナビノール)とCBD(カンナビジオール)を含有する医療用大麻オイルを6週間経口投与すると、音声チックや運動チックが有意に減少することが分かったそうです。強迫症などの関連する他症状も改善したとのことです。Medical Xpressの記事です。

加齢に伴い体内で減少するアミノ酸に似た物質「タウリン」を補うと、健康寿命を延長できる可能性があるようです。米国などの研究チームが、複数の動物実験を実施。中年マウスにタウリンのサプリメントを摂取させると、寿命の中央値が10~12%延長することが分かったそうです。また、中年のアカゲザルに6カ月間タウリンを摂取させたところ、骨密度や血糖値などに顕著な改善がみられたといいます。タウリンは特に貝類や軟体動物に多く含まれます。ScienceAlertの記事です。

回復不可能な脳損傷がある患者の生命維持装置を止め、心臓が停止した後の「心停止後臓器提供(DCD)」による心臓移植は、従来の脳死ドナーからの心臓移植と同じくらい成功するようです。米国の研究チームが、心臓移植を受けた患者180人を調査。6カ月後生存率は、DCDの心臓を移植された人は94%、脳死患者の心臓を移植された人が90%とほぼ同じだったそうです。DCDでは、ドナーから摘出した心臓は灌流装置につながれ、移植まで保存されるといいます。Medical Xpressの記事です。

5年ほど前に「ゲノム編集ベビー」を誕生させたという中国人科学者の賀建奎氏が研究生活に戻り、ゲノム編集技術CRISPRを使ったデュシェンヌ型筋ジストロフィー(DMD)の治療法開発に取り組んでいるそうです。賀氏は、遺伝子改変技術を使ってHIVに感染しない双子の女の赤ちゃんを誕生させたとして、中国で実刑判決を受けました。賀氏は双子について「平和な生活を送っている」とし、遺伝子編集による悪影響の有無についてはコメントを避けているそうです。nprの記事です。

臨床経験のある看護師のハンドラーとペアで医療チームの一員として病院に常勤し、患者に寄り添い治療のサポートをする犬「ファシリティドッグ(hospital facility dogs:HFDs)」をご存じですか。静岡県立こども病院でHFDsプログラムを手掛けるNPO法人が、病院スタッフにアンケートを実施。回答者431人の73%が、HFDsは終末期の緩和ケアに有益だと「常に感じる」「非常によく感じる」と答えたといいます。また、子どもの表情が豊かになりおしゃべりになることも観察されたそうです。EurekAlert!の記事です。

アフリカから髄膜炎の流行が撲滅できるかもしれません。髄膜炎菌に対する5価ワクチン「NmCV-5」が、第3相試験で有望な結果を示したようです。ガンビアなどの研究チームが、同国とマリで2~29歳の健康な1800人を調査。NmCV-5ワクチンの単回接種で、28日後には既存の4価ワクチンより強力な免疫応答が誘導されたそうです。アフリカで流行の可能性があり、4価ワクチンには含まれない髄膜炎菌X型にもNmCV-5は有効だといいます。安全性も確認されたとのこと。Medical Xpressの記事です。

炭酸飲料やガムなどに広く使われている人工甘味料「スクラロース」について、危険性を指摘する研究結果が報告されたようです。米国の研究チームが、ヒトの血液細胞や腸壁組織を使って調査を実施。スクラロースやスクラロースが体内で代謝された際に産生される「スクラロース-6-アセテート」によって、DNA損傷が生じる可能性があることが明らかになったそうです。これらの物質が腸の内壁にダメージを与えることも確認されたといいます。ScienceAlertの記事です。

加齢によって失われた髪の毛を取り戻すことはできるのでしょうか。米国の研究チームが、年を取ると髪が生えにくくなるのは毛包幹細胞が硬くなるためであることを発見したそうです。さらにチームは、細胞を柔らかくする作用のあるマイクロ(mi)RNA「miR-205」に着目。マウスを遺伝子操作して毛包幹細胞でのmiR-205の産生を増やしたところ、若いマウスと高齢マウスの両方で発毛が促進されたといいます。次は、局所でも同様の効果が得られるか確認する予定とのこと。Medical Xpressの記事です。

米国で昨年の冬、鼻や耳などで起きた細菌感染が脳に回って膿がたまってしまう「脳膿瘍」の子どもが急増したそうです。米疾病対策センター(CDC)が最新のデータを公表。冬にかけて子どものウイルス性呼吸器感染症が急増した後、2022年12月には小児脳膿瘍の症例が102件となり、月間最多記録を更新したそうです。新型コロナのパンデミック前の中間値と比べて200%の増加だといいます。その後は減少傾向にあるものの、コロナ前の最高値より高い水準にあるとのこと。CNNの記事です。
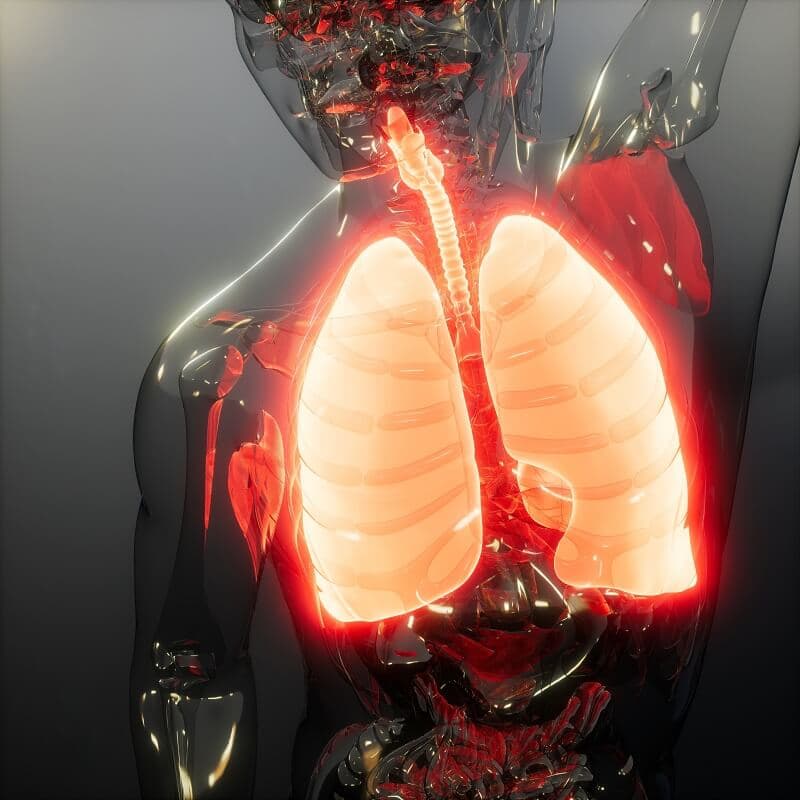
英アストラゼネカ社が開発した非小細胞肺がん切除後の補助療法薬「オシメルチニブ(商品名タグリッソ)」は、患者の全生存期間を延長できるようです。米国の研究チームが、EGFR遺伝子変異のある早期(ステージ1b~3a)非小細胞肺がん患者680人を対象に調査を実施。腫瘍の摘出手術後、オシメルチニブを毎日服用した人はプラセボ群に比べて死亡リスクが51%低下したといいます。5年後に生存していたのは薬の服用患者が88%、プラセボ群が78%だったとのこと。Medical Xpressの記事です。
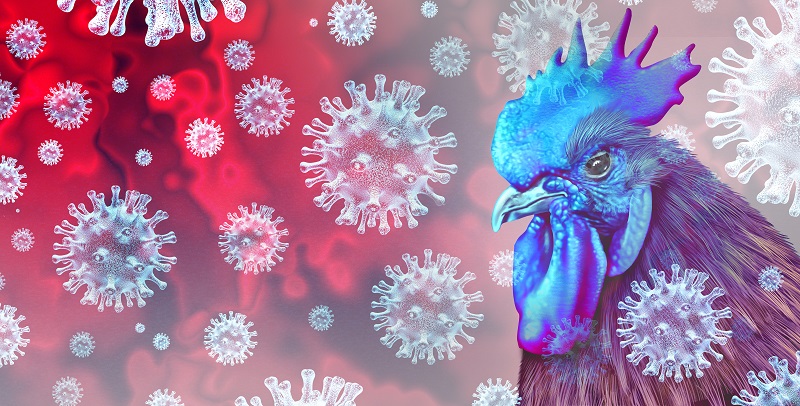
世界中で猛威を振るう鳥インフルエンザが、急速に変異しているようです。米国の研究チームが、鳥インフルが欧州から北米に広がる過程でどのように進化したかを分析。ウイルスが北米に到達した時点で、病原性が高まっていたそうです。フェレットの実験では、新たな変異株が予想以上に脳内で増殖することも判明。ヒトへのリスクはまだ低いものの、哺乳動物間での伝染の可能性も確認されており、家禽へのワクチン接種を求める声が高まっているとのこと。Medical Xpressの記事です。

米グレイル社が開発した50種類以上のがんを検出できる血液検査「Galleri」が、英国で使われるようになるかもしれません。Galleriは、がんから漏れる遺伝コードの断片の変化を調べるものです。英国民保健サービス(NHS)が、がんと疑われる症状があって診療所を受診した5000人を調査。従来の検査でがんと診断された人のうち2/3を検出できたそうです。このうち85%は、がんの発生源も正確に特定できたといいます。NHSは現在、無症状者を対象にした調査を行っているとのこと。BBCの記事です。

デュシェンヌ型筋ジストロフィー(DMD)を対象とする遺伝子治療の初期臨床試験に参加した米国在住の男性(27)が昨年死亡し、調査を行っていた同国の研究チームが結果を公表したそうです。治療は、ゲノム編集技術CRISPRを用いて「ジストロフィン」というタンパク質を増やすもの。CRISPRを体内に送り届けるための「アデノ随伴ウイルス(AAV)ベクター」に対し、男性の免疫系が通常に比べて過剰に反応しすぎたことが死亡の原因とみられるとのことです。AP通信の記事です。

「たばこはがんの原因」「たばこは性的不能の原因」「たばこは臓器にダメージを与える」「一服一服に毒が含まれている」――。たばこ1本1本に、こんな健康被害に関する警告文を表示することが、カナダで義務付けられるそうです。このような取り組みは世界初だといいます。規制は今年8月1日に施行され、その後段階的に警告文付き製品が販売される見通しとのこと。カナダは、2035年までに喫煙率を5%未満に下げることを目指しているそうです。CBCの記事です。

人工知能(AI)を活用することで、スーパーバグと呼ばれる超多剤耐性菌を殺す抗菌薬候補が見つかったそうです。カナダと米国の研究チームがAIを使い、医療施設などで広がる強力な多剤耐性菌「アシネトバクター・バウマニ(AB)」に効く薬剤を6000以上の物質から選別。最終的に「RS102895(abaucinと命名)」と呼ばれる化合物が、ABの増殖を抑える可能性があることが分かったそうです。この薬剤はABにのみ作用し、腸内細菌や皮膚の常在菌などを殺すことはないといいます。CNNの記事です。

ビタミンA、B、Cや亜鉛を含有するマルチビタミンサプリメントに、認知機能の低下を防ぐ効果があるかもしれません。米国の研究チームが、高齢者3562人を対象に調査を実施。米国で一般的に使われるマルチビタミンサプリ「セントラムシルバー」を3年間毎日飲んだ人は、プラセボ群に比べてオンラインで実施した記憶力テストで好成績を残したそうです。サプリを飲んだ人は、記憶力が3.1歳分若くなるとの推計が示されたといいます。NBC Newsの記事です。

新型コロナウイルスの発生源について、昨年まで中国疾病予防コントロールセンターのトップを務めた高福氏がBBCのインタビューに応じたそうです。高氏は、コロナが中国武漢の研究所から漏出したとする説をめぐり「全てのことを疑いの目で見る。それが科学だ。何事も排除すべきではない」として、否定しなかったといいます。一方で、中国政府は研究所漏出説を否定しています。高氏は研究所が「専門家による二重の調査を受けた」とも述べたそうです。BBCの記事です。

米疾病対策センター(CDC)によると、呼吸器感染症を引き起こすヒトメタニューモウイルス(HMPV)の症例が2023年春に急増したそうです。3月半ばのピーク時には、検査検体の11%近くがHMPV陽性だったといいます。これは、新型コロナのパンデミック以前の平均値より36%高い数字とのこと。HMPVはインフルエンザやRSウイルスと同じくらい危険でありふれた呼吸器感染症ウイルスだそうです。ワクチンや治療薬はなく、感染症に弱い人は重症化や死亡のリスクもあるとのこと。CNNの記事です。

がんの診断を受けた後も喫煙を続けると、転帰に悪影響があるようです。米国の研究チームが、がん既往歴のある成人1409人のデータを分析。現在喫煙している人は、過去に喫煙していた人や喫煙経験のない人に比べて倦怠感や痛み、情緒面の問題を抱えるリスクが高かったそうです。紙巻きたばこだけでなく、電子たばこでも同様の結果だったといいます。なお、症状が重い患者は負担から逃れるために喫煙を続ける傾向があるという説は間違いのようです。Medical Xpressの記事です。

子どもの受動喫煙は近視のリスクを高めるそうです。香港の研究チームが、6~8歳の子ども1万2630人を調査。調査対象者の32.4%が受動喫煙の状態だったといいます。分析の結果、副流煙への暴露が、近視の原因となる屈折力の強さや眼軸長(眼球の奥行きの長さ)の伸長に関連することが明らかになったそうです。副流煙に暴露する子どもは近視を発症する可能性が高く、そのオッズ比は中等度近視で1.3、強度近視で2.64だったといいます。Medical Xpressの記事です。
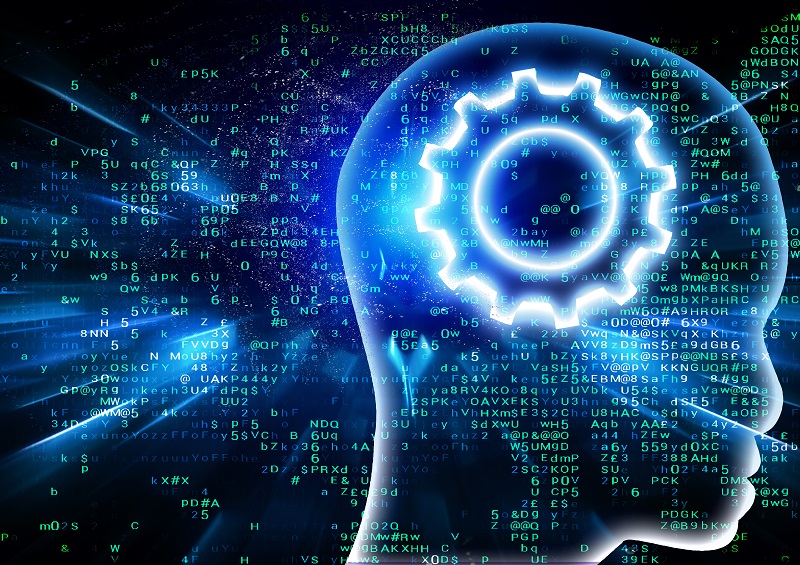
米起業家イーロン・マスク氏らが設立したニューラリンク社は、開発する脳インプラント装置のヒトを対象にした臨床試験が米食品医薬品局(FDA)に許可されたと発表しました。コイン大の物を頭蓋骨に埋め込み、そこから極細の線を脳に入れる装置だといいます。神経系をコンピュータに接続し、脳損傷などが原因で失われた機能を取り戻させるそうです。視力回復や、筋肉を動かせない人が電子機器を操作できるようにすることなどを目指すとのこと。AP通信の記事です。

10年以上前のバイク事故でまひが残り歩けなくなった男性(40)が、スイスの研究チームが開発した脳と脊髄を再接続する装置によって、スムーズに歩けるようになったそうです。脳に埋め込んだ装置が「歩きたい」という信号を受信。次にこの信号が、リュック型の処理装置に無線で伝わるそうです。そして処理装置から脊椎インプラントに命令が伝達され、筋肉が刺激される仕組みだといいます。日によるものの、男性は100m以上の歩行が可能になったとのこと。CNNの記事です。

米国に隣接するメキシコの都市マタモロスで手術を受けた米国人2人が、真菌性髄膜炎の疑いで死亡したそうです。関連するとみられる二つのクリニックが閉鎖され、米疾病対策センター(CDC)はこれらのクリニックで最近手術を受けた224人に連絡を取り、髄膜炎検査を受けるよう呼びかけているとのことです。米国では近年、メキシコをはじめとする他国で医療を受ける「メディカルツーリズム(医療観光)」の人気が高まっているといいます。AP通信の記事です。

乳幼児突然死症候群(SIDS)の危険因子の一つが明らかになったようです。米国の研究チームが、SIDSで死亡した乳児58人と別の原因で死亡した乳児12人の脳組織を比較。SIDSで死亡した乳児は、呼吸などの調節に重要な役割を果たす脳内のセロトニン関連受容体が変異している傾向があったそうです。乳児は通常、睡眠時に酸素が不足すると、呼吸を促す反応を自然に示すといいます。しかしこの変異型をもつ乳児では、この反応が起きない可能性があるとのこと。NBC Newsの記事です。

食欲を抑えたい人は、食べたい物の画像を何度も見るといいようです。デンマークの研究チームが、1000人以上を対象にオンラインで調査を実施。参加者にM&M’s(チョコレート菓子)の画像を複数回見せた後、実際に1~10個の間でいくつM&M’sを食べたいか尋ねたそうです。オレンジ色のM&M’sの画像を30回見た人は、3回見た人に比べて食べたいと申告したM&M’sの個数が少なかったといいます。見せる菓子の色や風味を毎回変えても、結果は同じだったとのこと。Medical Xpressの記事です。

子宮頸がんを予防するヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンについて、複数回接種から単回接種に変更するべきとの声が上がっているそうです。世界保健機関(WHO)は2022年、HPVワクチンについて原則として単回接種を推奨すると決定。接種が1回で済めば手間やコスト面でメリットが大きく、ワクチンのさらなる普及が期待できるためです。最新の研究でも、HPVワクチンの単回接種で少なくとも3年間は高い有効性が持続することが示されたといいます。CNNの記事です。

腸内細菌由来の毒素「エンドトキシン」が、脂肪細胞の代謝機能を低下させて体重増加を促すことが分かったそうです。英国などの研究チームが、肥満の156人の脂肪細胞を分析。エンドトキシンが血中に流出すると、健康的な体重の維持に重要な役割を果たす「白色脂肪細胞の褐色化」が減少することが明らかになったといいます。脂質を貯蓄する白色脂肪細胞は、一定の条件下で褐色化し、脂肪を燃焼する褐色脂肪「様」細胞に転換することが知られています。ScienceAlertの記事です。

米国の研究チームが、閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)と新型コロナウイルス感染後の後遺症の関連を分析する研究を進めているそうです。180万人近くのデータを分析した調査では、成人OSA患者のコロナ後遺症発症リスクが最大で75%高くなることが分かったそうです。また、33万人を対象にした別の調査では、このリスクが12%上昇していたことが判明。OSAは炎症の増加や睡眠の乱れ引き起こし、感染症の発症傾向の増大や免疫機能の低下につながる可能性があるとのこと。CNNの記事です。

慢性閉塞性肺疾患(COPD)の治療法が変わるかもしれません。米国の研究チームが、粘液の塊である「粘液栓」を標的にすれば、死亡率を改善できるかもしれないという研究結果を発表しました。チームは、軽~重度のCOPD患者4000人以上について、初診時に撮影した胸部CT画像を分析したそうです。死亡率は、CT画像で粘液栓が認められなかった患者が34%、粘液栓が存在する肺の区域が1~2カ所だった患者が46.7%、3カ所以上の患者は54.1%だったといいます。Medical Xpressの記事です。

他人をいじめたり、挑発的なメッセージをSNSに投稿したり、創造力を負の方向に使う「悪意のある創造性」。オーストリアの研究チームが、259人を対象に調査を実施し、潜在性うつ症状(軽度のうつ)と悪意のある創造性に関連性があることが明らかになったといいます。うつの程度を示すスコアが高い人ほど、悪意のある創造性を発揮することが多かったとのことです。うつ病と悪意のある創造性は、一方が他方を助長する関係にある可能性があるそうです。PsyPostの記事です。

米食品医薬品局(FDA)の諮問委員会は、米ファイザー社が開発した初の乳児向けRSウイルス(RSV)ワクチンの承認を推奨する立場を示したそうです。FDAは通常、委員会の意見に従うとのことです。このワクチンは、妊婦に接種することで出生後の乳児がRSV感染で重症化するのを防ぎます。専門家14人による投票では、満場一致でワクチンの有効性を支持。一方、ワクチンの安全性については、早産のリスクがあるなどとして14人中4人が「不支持」だったとのことです。nprの記事です。

低カロリーやカロリーゼロの人工甘味料を減量目的で口にするのはやめた方がいいようです。世界保健機関(WHO)が新たなガイドラインを公表。エビデンス(科学的根拠)の系統的レビューを行ったところ、人工甘味料が成人や子どもの体脂肪減少に長期的な効果をもたらすことはないとの結果が示唆されたそうです。それどころか、こうした甘味料を長期間摂取すると、2型糖尿病や心血管疾患、成人における死亡のリスクが上昇する可能性があるといいます。CBS Newsの記事です。
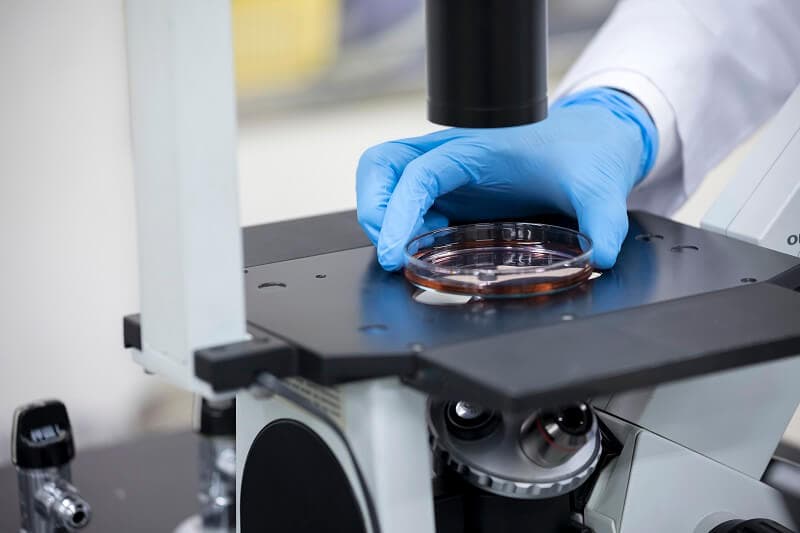
ヘルペスウイルスの一種「エプスタイン・バールウイルス(EBV)」は、多発性硬化症(MS)と関連があることが指摘されています。スウェーデンの研究チームが、メカニズムの一端を明らかにしたそうです。チームはMS患者700人と健康な対照群700人の血液を分析。EBVのタンパク質EBNA1に結合する抗体が、誤って脳や脊髄に存在するタンパク質CRYABにも結合してしまうことが分かったそうです。これにより神経系がダメージを受け、MSの症状が起こる可能性があるとのこと。Medical Xpressの記事です。

米マサチューセッツ工科大学(MIT)が、さまざまな種類のがんの存在や転移の有無を識別する新たな尿検査を開発しているそうです。尿検査に先立ち、患者にはナノ粒子を投与するといいます。このナノ粒子は、腫瘍が過剰に産生する酵素に出くわすと、血液中にその酵素特有のDNA断片を放出するよう設計されているそうです。その後、このDNA断片は尿として体外に排出され、特別な試験紙を使った検査でがんの存在や転移の有無を把握できるといいます。Medgadgetの記事です。

脳腫瘍の一種「膠芽腫」の再発患者に対する新たな治療法が、臨床試験で有望な結果を示したようです。カナダなどの研究チームが膠芽腫再発患者49人に併用療法を実施。チームはまず、がん細胞のみを破壊する「腫瘍溶解性ウイルス」を腫瘍に注入。その後、免疫チェックポイント阻害薬「抗PD-1抗体」を3週間ごとに静脈内投与したそうです。すると、平均生存期間が既存の治療法より半年ほど延長したといいます。腫瘍が完全に消失した患者もいたとのこと。SciTechDailyの記事です。

米国立衛生研究所(NIH)が、mRNA技術を活用したインフルエンザワクチンの初期の治験の参加者登録を開始したそうです。米国立アレルギー感染症研究所(NIAID)が開発した「ユニバーサルワクチン」で、幅広い株に対する長期間の効果が期待されており、ワクチンを毎年打つ必要がなくなる可能性があるといいます。治験には健康な18~49歳が最大50人参加予定で、安全性や免疫反応が起こるかどうかを確認します。既存の4価ワクチンとの比較も行われるとのこと。NBC Newsの記事です。

英医学誌「ブリティッシュ・メディカル・ジャーナル(BMJ)」が、米メルクの非常に高額な抗菌薬「レカルブリオ」について、法的に必要とされる「実質的証拠」がないまま米食品医薬品局(FDA)に承認されたと指摘したそうです。この薬の三つの臨床試験では、いずれも有効性を裏付ける実質的証拠が示されていないといいます。それにもかかわらず、FDAは薬の成分や動物実験の結果などを根拠に「規制の柔軟性」を適用し、承認に踏み切ったとのことです。EurekAlert!の記事です。

対話型人工知能(AI)の「ChatGPT」は、患者への医学的な助言を医師よりも上手に行えるそうです。米国の研究チームが、実際にソーシャルメディアに投稿された健康に関する195の質問について、医師とChatGPTの文書による回答を比較したそうです。その結果、医療分野の専門家は、79%の確率でChatGPTの回答を好んだといいます。「質が高い」または「親身である」と評価された回答は、医師によるものよりもChatGPTによるもののほうが圧倒的に多かったとのことです。Medical Xpressの記事です。

ピーナッツアレルギーを治療する皮膚用パッチ「Viaskin Peanut」が、後期臨床試験で有望な結果を示したようです。仏DBV Technologies社などが、診断を受けた1~3歳の幼児362人を調査しました。ピーナッツタンパク質250㎍(ピーナッツ1粒の1/1000相当)を含有するViaskinを1年間、毎日背中に貼った子どもの2/3が主要目標を達成。プラセボ群は1/3だったといいます。アレルギーの程度が軽い子は3~4個分、重い子は1個分のピーナッツタンパク質を摂取できるようになったとのこと。CNNの記事です。

アステラス製薬が開発した更年期障害治療薬「Veozah」が、米食品医薬品局(FDA)に承認されたそうです。Veozahは、閉経にともなうホットフラッシュ(ほてり)などを改善する経口薬。1日1回の服用で、中~重度の発汗や紅潮などが緩和されるといいます。同薬はホルモン製剤ではなく、体温調節に関連する脳の神経接続を標的にしているそうです。ホルモン製剤による副作用の心配がない一方で、服用に伴い肝臓がダメージを受ける可能性があるとのこと。AP通信の記事です。

仏製薬大手サノフィ社などが開発した抗RSウイルス(RSV)モノクローナル抗体製剤「nirsevimab(ニルセビマブ)」が、臨床試験で有望な結果を示したようです。同社は2022~23年のRSV流行期における実世界データを分析。1歳未満の乳児8000人以上が調査の対象になったといいます。この薬の注射を1回受けた乳児は、そうでない乳児に比べてRSV関連で入院するリスクが83%低かったそうです。この薬はワクチンと同じ目的で使われ、EU、英国、カナダで承認されているとのこと。Medical Xpressの記事です。

最も治療が難しい脳腫瘍の一つである膠芽腫の新たな治療法が見つかったかもしれません。米国の研究チームが、卵巣がんや乳がん、肺がんなどの治療に使われる化学療法薬「パクリタキセル」と免疫療法薬「抗CD47抗体」を組み合わせたハイドロゲルを開発。膠芽腫マウスの腫瘍を切除した後、その部分にこのゲルを注入したといいます。すると腫瘍の痕跡は消え、再発も起きなかったそうです。驚くべきことに、マウスの生存率は100%だったとのこと。ScienceAlertの記事です。

独ビオンテック社が開発する膵臓がん向けのmRNAワクチンが、初期の臨床試験で有望な結果を示したそうです。米国などの研究チームが膵臓がん患者16人から腫瘍を摘出し、その組織と血液を解析して個別にカスタマイズしたmRNAワクチンを作製。患者は投与後に化学療法も受けたといいます。16人中8人で腫瘍に対するT細胞の免疫応答が誘導され、この8人は全員再発しなかったそうです。脾臓を摘出していると、ワクチンの効果が出ない可能性があるとのこと。CNNの記事です。

新型コロナによる死亡原因の多くは、免疫が暴走するサイトカインストームによる臓器不全だと考えられています。しかし、米国のチームが集中治療室(ICU)の患者585人を調査し、それに疑問を呈する報告をしたようです。患者は皆、肺炎や呼吸器不全を患っており、190人がコロナに感染していたといいます。データを分析したところ、コロナ患者は細菌性の人工呼吸器関連肺炎(VAP)を発症することが多く、VAPから回復できない人は死亡リスクが上昇したとのこと。ScienceAlertの記事です。

母から子に難病ミトコンドリア病が遺伝するのを防ぐために「核移植」を行い、遺伝的に3人の親を持つ子どもが英国で初めて誕生していたそうです。まず、異常なミトコンドリアを持つ母親の受精卵や卵子から核を取り出します。それを、正常なミトコンドリアを持つ提供者の受精卵や卵から核を除去した上で移植するのです。提供者から子どもに受け継がれるDNAの割合は1%未満とのこと。英国では2015年に、世界で初めて核移植が合法化されています。Medical Xpressの記事です。

米予防医学専門委員会が、乳がん検診に関する新たな指針を作成したそうです。委員会はこれまで、50~74歳の女性に2年に1回のマンモグラフィ検査を強く推奨してきました。しかし今回、検査開始の推奨年齢を40歳に引き下げることが望ましいとする勧告案を示したそうです。一方で、約半数の女性は「高濃度乳腺」で、マンモ検査だけでは不十分な可能性があるといいます。別種の検査の追加が有効かどうか研究を進める必要があるとのことです。AP通信の記事です。

インターネットを適度に使う人は、認知症になりにくいようです。米国の研究チームが、50~64.9歳の認知症ではない1.8万人を8年にわたり調査。ネットを日常的に使う人はそうでない人に比べて、認知症発症リスクが半減することが分かったそうです。一方で、1日のネット利用時間が長過ぎる人は、逆にリスクが高まる可能性があるといいます。ただし、今回の結果だけではネット利用と認知症の因果関係は立証できず、さらなる研究が必要とのこと。USA TODAYの記事です。

胃がん患者の寿命が延長できるかもしれません。ドイツなどの研究チームが世界20カ国で、膜タンパク質「CLDN18.2」を標的とする抗体医薬「Zolbetuximab(ゾルベツキシマブ)」の臨床試験を実施。CLDN18.2陽性の進行性胃がん患者計565人が参加しました。ゾルベツキシマブと化学療法を併用した患者はプラセボと化学療法を併用した患者に比べて、がんの進行や死亡のリスクが25%低くなったそうです。主な有害事象としては、吐き気や食欲減退などがみられたといいます。Medical Xpressの記事です。

生後すぐに脳損傷や心不全などを引き起こす可能性があるまれな脳血管奇形「ガレン静脈奇形(VOGM)」をもった胎児が、子宮内で手術を受けて元気に生まれたそうです。米国の研究チームが、母親の腹壁から針を挿入しカテーテルを注意深く誘導。金属コイルで胎児の脳内静脈を塞ぎ、激し過ぎる血流を抑える処置を行ったそうです。2日後、母親はこの赤ちゃんを無事に出産。生後約2カ月がたった現在も、赤ちゃんは順調に成長しているといいます。CNNの記事です。

米イーライリリーは、開発しているアルツハイマー病(AD)治療薬「donanemab (ドナネマブ)」について、症状の進行を遅らせる効果が認められたと発表したそうです。同社は早期症候性AD患者1700人に18カ月間の治験を実施。ADに関連する脳内のタンパク質タウのレベルが中程度の患者において、同薬が認知機能の低下を35%遅らせることが確認されたそうです。治験開始から1年時点では、同薬投与群の47%、プラセボ群の29%で認知機能の低下が抑制されたといいます。CNNの記事です。

3年以上続いた世界の新型コロナウイルスとの戦いは、大きな節目を迎えました。世界保健機関(WHO)は5日、2020年1月30日に宣言した新型コロナに関する「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を解除すると発表しました。ただし、パンデミックが完全に収束し、新型コロナが脅威でなくなったというわけではないそうです。WHOは、いまだに毎週数千人の患者が死亡していることに言及。依然として新たな変異株が出現する可能性もあるといいます。AP通信の記事です。

米食品医薬品局(FDA)は3日、世界初のRSウイルス(RSV)ワクチン「Arexvy」を承認しました。英グラクソ・スミスクライン(GSK)製で、対象は60歳以上の高齢者です。2.5万人の高齢者を対象にした臨床試験では、このワクチンによるRSVの肺への感染予防効果が83%であることが示されたといいます。米疾病対策センター(CDC)が推奨をすれば、今秋にも接種が始まる見込みだそうです。FDAは現在、米ファイザー社が開発する同様のRSVワクチンについても審査中とのこと。AP通信の記事です。

揚げ物の摂取が心の健康に悪影響を及ぼす可能性があるようです。中国の研究チームが、参加者14万728人を11.3年間調査。揚げ物を頻繁に食べる人は、揚げ物を食べない人に比べて不安リスクが12%、うつ病リスクが7%それぞれ高かったといいます。特にリスク上昇と関連していたのはフライドポテトだそうです。ゼブラフィッシュの実験で、食品を高温で加熱する際に生じる「アクリルアミド」という物質が不安やうつ病の原因になる可能性が示されたとのこと。CNNの記事です。

米製薬大手イーライリリーの2型糖尿病治療薬「チルゼパチド」が、肥満治療薬として年内に米食品医薬品局(FDA)に承認されるかもしれません。同社は新たな治験結果を公表。それによると、チルゼパチドが肥満と糖尿病の両方を患う患者の体重を最大15.7%減少させることが分かったそうです。以前公表された別の治験では、糖尿病のない肥満患者に高用量のチルゼパチドを投与すると、72週時点で体重が21%減少することも明らかになっているといいます。nprの記事です。

米ネバダ州南部で昨年、子どもの「脳膿瘍」が急増したようです。脳膿瘍とは、細菌などの感染で脳内に膿がたまった状態。初期症状として発熱や頭痛が起こるといいます。同州では例年平均4~5人程度だった子どもの脳膿瘍患者が、2022年は18人に急増。米国の他の地域でも同様の増加が報告されているそうです。急増の原因は分かっていませんが、新型コロナ感染対策で子どもたちが必要な免疫を獲得できなかったことなどが考えられるといいます。CNNの記事です。

2型糖尿病患者がインスリンを使わずに血糖を管理できる方法が見つかったかもしれません。オランダの研究チームが、2型糖尿病患者14人を対象に内視鏡手術で十二指腸に電気パルスを照射。手術は1時間で終了し、患者はその日のうちに退院したそうです。1年後、12人(86%)がインスリンを使わずに糖尿病治療薬「セマグルチド」のみで血糖管理がうまくいっていたといいます。通常、この薬のみで血糖管理できるのは患者のわずか20%ほどとのこと。EurekAlert!の記事です。

境界性パーソナリティ障害(BPD)の患者がうつ病を併発すると、うつ病が重篤で治療が難しいことが多いそうです。抗うつ作用があることで知られる麻酔薬「ケタミン」が、そんな患者の治療に有望な可能性があるといいます。カナダの研究チームが、「BPDとうつ病を併発する患者50人」と「うつ病のみを患う患者50人」に静脈内ケタミンを4回投与。両群ともにうつ症状が有意に同程度改善したそうです。併発群では、BPD症状にも改善がみられたといいます。PsyPostの記事です。

米食品医薬品局(FDA)は、腸炎を引き起こし死に至ることもあるクロストリジウム・ディフィシル感染症(CDI)を繰り返す患者に対して、糞便移植を簡単に実現することができる経口薬「Vowst」を承認したそうです。この種の経口薬が承認されるのは初。米Seres Therapeutics社が健康なドナーの糞便から作ったVowstは、抗菌薬治療を終えた18歳以上の再発性CDI高リスク患者が対象です。この薬を1日4錠3日間連続で服用すると、CDI再発リスクが低下するとのことです。AP通信の記事です。

新型コロナウイルスワクチン接種後に耳鳴りを訴える人がいるようです。副反応の可能性はあるのでしょうか。米疾病対策センター(CDC)には4月14日時点で、ワクチン接種後に耳鳴りが起きたとの報告が1万6500件寄せられているそうです。コロナ後遺症の一つとして耳鳴りを報告する患者もいるといいます。現時点でCDCは耳鳴りについて、ワクチンや後遺症との関連を否定しています。一方、専門家がこの件に関するデータの分析を進めているそうです。USA TODAYの記事です。

ヒトパピローマウイルス(HPV)感染が関連する中咽頭がんが、欧米で男女共に急増しているそうです。このがんの主要な危険因子はオーラルセックス。生涯でオーラルセックスをする相手が6人以上いる人は、オーラルセックスをしない人に比べて中咽頭がん発症リスクが8.5倍になるそうです。英国では成人の80%がオーラルセックス経験者であるとの調査結果も出ており、がん予防のために男子も含めてHPVワクチンを普及させることが重要だといいます。The Conversationの記事です。

代理出産や精子・卵子提供で生まれた子どもには、早いうちにその事実を伝えた方がいいようです。英国の研究チームが、代理出産で生まれた子ども22人▽卵子提供で生まれた子ども17人▽精子提供で生まれた子ども26人――を20年にわたり追跡調査。7歳までに自分の出自について知らされた子どもは、若年成人期に母親と良好な関係にあることが明らかになったそうです。そして、その母親たちも不安やうつ病を抱えるリスクが低かったといいます。CNNの記事です。

薬で睡眠を促すことで、アルツハイマー病に関連するタンパク質であるアミロイドβや異常な(リン酸化した)タウの蓄積を抑えられるかもしれません。米国の研究チームが、認知機能障害と睡眠障害がない中高年38人を調査したそうです。不眠症の一般的な治療薬「スボレキサント」を2日間使用した人はプラセボ群に比べて、脳の周りを循環する脳脊髄液中のアミロイドβ濃度が10~20%低下。薬を高用量服用した人は、リン酸化したタウも減少したとのこと。ScienceAlertの記事です。

英ウェールズでは、新型コロナの重症化リスクが高い人に対して「隔離政策」を取っていました。感染予防のために外部との接触を避けて家にいることを推奨したこの政策が、実は意味がなかった可能性があるそうです。英国の研究チームが、隔離対象になった11.7万人を対象外の一般集団300万人と比較。隔離群は検査を受ける機会が多かった点を考慮する必要がありますが、隔離群の方が死亡や医療機関の利用が多く、感染率も高かったといいます。BBCの記事です。

古くから尿路感染症(UTI)に良いとされてきたクランベリーについて、一部の人で実際の効果が確認されたようです。豪州の研究チームが、クランベリー製品に関する50以上の研究結果を分析。参加者は合わせて9000人近くに上るといいます。クランベリーのジュースやサプリメントを摂取すると、UTIの再発リスクが一部の女性で25%、子どもで50%、それぞれ低下することが分かったそうです。ただし、高齢者や妊婦には同様の効果はみられなかったとのこと。ABC News(AUS)の記事です。

アルゼンチンでは、チリやボリビアとの国境に近い北西部を中心に、蚊が媒介する「デング熱」の記録的な大流行が起きているようです。これまでに約6万人が感染し、40人以上が死亡したといいます。感染拡大を抑えるため、放射線でDNAにダメージを与えて子孫ができないようにしたオスの蚊を準備しており、数千匹を放つ予定だそうです。保健当局は、蚊帳や虫よけ剤の使用、蚊の繁殖場所になる水の容器を取り除くなどの対策を呼び掛けているとのこと。BBCの記事です。

性感染症ウイルスである「ヒトパピローマウイルス(HPV)」は子宮頸部だけでなく、肛門や咽頭、陰茎、膣などのがんを引き起こします。米国の研究チームが年間2000~3000人の成人を対象に行った調査で、この認知度が下がっていることが分かったそうです。HPVについて聞いたことがある人のうち、子宮頸がんとの関連を知っていた人の割合は、2014年(77.6%)から20年(70.2%)の間に7.4%低下。咽頭がんや肛門がんとの関連につい知っていたのはわずか30%だったとのこと。NBC Newsの記事です。

緑内障の主要な危険因子は眼圧上昇です。目の中で血液のような役割をする房水が、静脈への排水口(シュレム管)の目詰まりなどによって流れなくなるために起こります。アイルランドの研究チームが動物モデルや提供されたヒトの目を使って遺伝子治療の実験を実施。タンパク質を分解する酵素「MMP-3」の産生を促す遺伝物質を運ぶウイルスベクターを作り、これを1回投与したところ房水の流れがよくなり、眼圧上昇が改善されたといいます。Medical Xpressの記事です。

白髪が発生するメカニズムが明らかになったようです。米国の研究チームが、色素のメラニンを作るメラノサイト(色素細胞)に着目し、マウスで細胞の老化プロセスを調べました。本来は毛包(毛穴)の周りをあちこち移動しているメラノサイト幹細胞が、年を取るにつれて「立ち往生」して動けなくなり、成熟したメラノサイトに成長できないために色素が作れなくなることが分かったそうです。同じことが人間の毛髪でも起きている可能性があるとのこと。BBCの記事です。

米国の研究チームが、T細胞に焦点を当てた新たな新型コロナウイルスワクチン(T細胞ワクチン)を開発したそうです。このワクチンはT細胞による幅広い免疫応答が誘導されるよう設計されています。これをマウスに投与して致死量のコロナウイルスに感染させたところ、87.5%が生き残ったといいます。T細胞ワクチンは将来の変異株にも有効で、効果が今より長く続く可能性があるとのこと。抗体を誘導するmRNAワクチンよりも高い効果が期待できるそうです。EurekAlert!の記事です。

大気汚染が肺がんの主な原因であることが、英国などのチームの研究で改めて明らかになりました。肺がん患者3万2957人の調査で、多量の大気汚染物質PM2.5に暴露すると、細胞の成長や増殖に関わる上皮成長因子受容体(EGFR)遺伝子に変異のある肺がんの発症リスクが高まることが判明。別の調査では、高レベルのPM2.5に3年間さらされるだけで発症リスクが上昇することも分かったそうです。PM2.5は、がんの原因となる遺伝子変異を持つ細胞を「目覚めさせる」とのこと。ScienceAlertの記事です。

がんには想像を超えた生存能力が備わっているようです。英国の研究チームが、肺がん患者400人を9年間追跡調査。初期の腫瘍において侵攻性の高いがん細胞が最終的に全身に広がることや、遺伝子の「混乱」レベルが高い腫瘍が手術後に別の場所で再発しやすいことなどが分かったといいます。また、がんは進行とともに進化し、高い適応能力を持つことが明らかに。末期がんの治療は極めて困難で、予防や早期発見の重要性が指摘されています。BBCの記事です。

個人がある疾患にかかるリスクを多数の遺伝子変異から評価する「多遺伝子リスクスコア(PRS)」を使って、米国の研究チームがアルツハイマー病(AD)に関連する腸内細菌を特定したそうです。チームは、まずAD患者1278人と対照群1293人を調査した上で、別のAD患者799人と対照群778人にも同様の調査を実施。二つの結果を分析したところ、119の腸内細菌属のうち、コリンセラ属をはじめとする4種類の菌属がAD発症リスクに関連することが示されたといいます。Medical Xpressの記事です。

英国の研究チームがげっ歯類の調査で、ステロイド薬を長期間使用すると記憶障害が起こることを明らかにしたようです。ステロイド薬「メチルプレドニゾロン」を5日間投与するだけで、記憶や学習に関与する脳の海馬の活動が減少し、記憶課題の成績が悪くなったそうです。神経細胞間の接合部であるシナプスは増強される時間帯が決まっており、長期間のステロイド使用によって海馬におけるその概日リズムが乱れる可能性があるとのことです。Medical Xpressの記事です。

米モデルナ社が開発するmRNAがんワクチンと米メルク社の免疫療法薬キイトルーダを併用すると、皮膚がんの一種「悪性黒色腫(メラノーマ)」の再発リスクが低減できるかもしれません。両社が、メラノーマの切除手術を受けた患者157人を2群に分けて行った治験(第2b相)の新たなデータを公表。18カ月後の時点で再発が起きなかったのは、がんワクチンとキイトルーダを併用した人の78.6%、キイトルーダのみを使用した人の62.2%だったといいます。CNNの記事です。

日光を浴びると激痛が走ったり皮膚が腫れ上がったりする難病、赤芽球性プロトポルフィリン症(EPP)やX連鎖性プロトポルフィリン症(XLP)に対する経口薬「dersimelagon」の初期臨床試験の結果が公表されました。米国の研究チームが、EPPまたはXLPの成人患者102人を16週間調査。この薬を毎日飲んだ人はプラセボ群に比べ、日光下で前駆症状(前触れの症状)が現れずに活動できる時間が平均で1日1時間増えたそうです。吐き気や頭痛などの副作用はあったとのこと。Medical Xpressの記事です。

食中毒を引き起こすノロウイルスのワクチンが実現するかもしれません。米国の研究チームが、胃腸炎を引き起こすロタウイルスの生ワクチンを活用して開発。ロタのゲノムにノロの外表面を作るタンパク質遺伝子を挿入し、改変したロタを作製したそうです。これを免疫不全子マウス11匹に投与したところ、全てのマウスの腸で強力な抗体反応がみられたそうです。さらに、この抗体がヒト胃腸オルガノイドの実験でノロとロタの両方を中和したといいます。ScienceDailyの記事です。

経口避妊薬(ピル)のホルモンによる副作用を低減できるかもしれません。フィリピンなどの研究チームが、正常な月経周期を持つ20~34歳の健康な女性23人を対象に下垂体と卵巣のホルモン値を調査。構築した数理モデルを用いて、ピルの最適な用量や服用タイミングを予測したといいます。その結果、ホルモンの用量をエストロゲン単独なら92%、プロゲステロン単独なら43%、それぞれ減らしても避妊効果は十分に得られることが示唆されたとのこと。ScienceAlertの記事です。
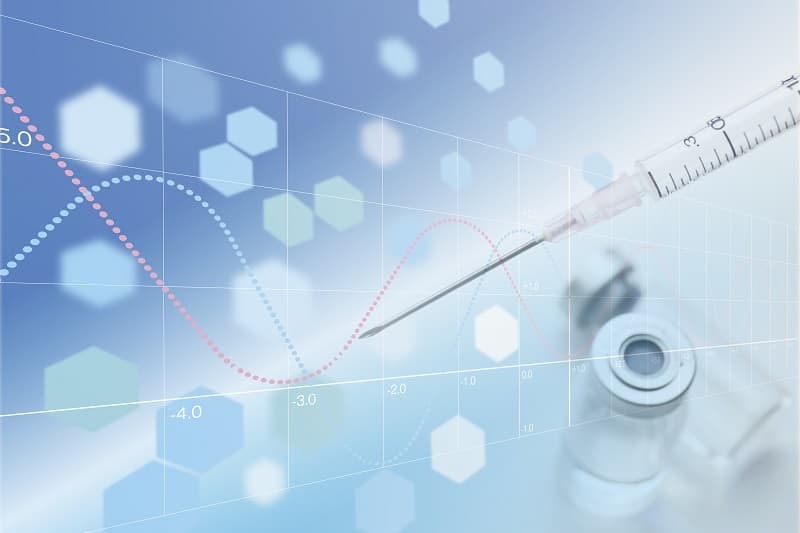
西アフリカのガーナ保健当局は13日、英オックスフォード大学が開発する新たなマラリアワクチンを一足早く承認したそうです。マラリアによる死亡リスクが高い生後5カ月~3歳の乳幼児が対象。ワクチンの治験の最終結果はまだ公表されておらず、世界保健機関(WHO)が現在審査中だといいます。ただ、初期の臨床試験では80%の有効性が示されており、すでにWHOが承認している世界初のマラリアワクチン「Mosquirix」よりはるかに高い効果が期待されています。AP通信の記事です。

米国で性感染症(STD)の増加が問題になっています。そんな中、米疾病対策センター(CDC)が、50年以上前からある安価な抗菌薬「ドキシサイクリン」をSTD予防薬として推奨する見通しだそうです。米国の研究チームが、ゲイやバイセクシャルの男性、トランスジェンダーの女性計500人を調査。避妊具なしの性交後72時間以内にこの薬を服用した人は服用しなかった人に比べて、感染リスクが▽クラミジアは90%▽梅毒は80%▽淋病は50%――それぞれ低くなったといいます。USA TODAYの記事です。

軽度認知障害(MCI)の人が正常な認知機能を取り戻すことがあるそうです。なぜなのでしょうか。米国の研究チームが、65歳以上の高齢者1716人を調査しました。老化に対して肯定的な考えを持つMCI患者は、否定的な考えを持つMCI患者に比べて正常な認知機能を取り戻す可能性が30%高いことが分かったそうです。元々正常な認知機能をもつ高齢者も、老化に肯定的な考えの人は、そうでない人に比べて12年以内にMCIを発症するリスクが低かったといいます。EurekAlert!の記事です。

mRNAの技術は、ピーナッツアレルギーの予防や治療にも使える可能性があるようです。米国の研究チームが、ピーナッツに含まれる複数のタンパク質に関するmRNAを搭載したナノ粒子を開発。肝臓には過剰なアレルギー反応を起こさないように免疫システムを訓練する細胞があり、ナノ粒子はその細胞に結合する糖を持っているといいます。これをマウスに投与したところ、アレルギー反応が減少し、ピーナッツへの耐性を強化する物質の産生が増加したとのこと。ScienceAlertの記事です。
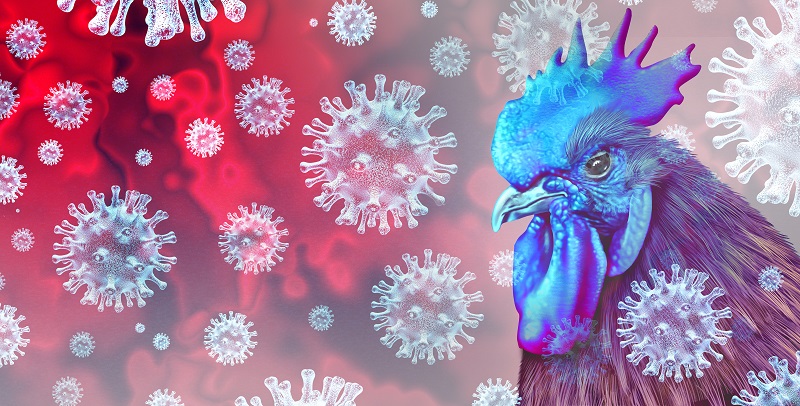
中国広東省に住む56歳の女性がH3N8型鳥インフルエンザウイルスに感染し、死亡したそうです。H3N8のヒトへの感染報告は3例目で、いずれも中国で発生。患者が死亡したのは初めてだといいます。女性は2月22日に体調を崩し、その後重度の肺炎で入院。3月16日に死亡したようです。女性には複数の基礎疾患があり、家禽との接触歴があったといいます。世界保健機関(WHO)は、ヒトからヒトへの感染が拡大するリスクは低いとの見解を示したとのこと。Medical Xpressの記事です。
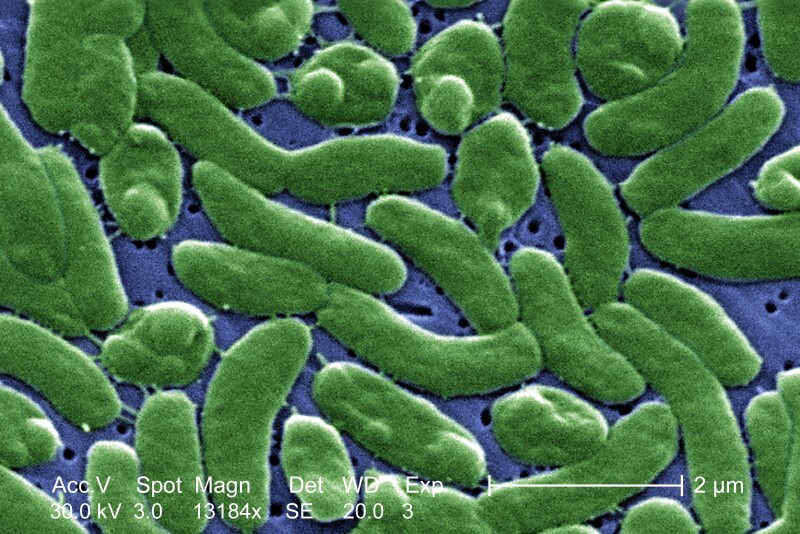
ビブリオ・バルニフィカスは暖かい海に生息し、加熱が不十分な魚介類や傷口から感染する危険な細菌です。この感染者が米東海岸で増加しているようです。英国などの研究チームが、米疾病対策センター(CDC)のデータを使って分析。ここ30年間で年間感染者数が10人から80人に増えたそうです。2100年までに200人に達する可能性があるといいます。さらに温暖化の影響で、感染発生地域は年々北上。数十年以内にニューヨークに到達すると予測されています。ScienceAlertの記事です。(写真:ビブリオ・バルニフィカス=CDC提供)

自殺のリスクが高まる時期や時間帯があるようです。米国の研究チームがインディアナ州にある検視局のデータを使って、2012~16年に起きた自殺について調査。満月の週に自殺による死亡が有意に増加することが分かったそうです。特に55歳以上で顕著に増加したといいます。月明かりによる概日リズム(体内時計)の乱れが自殺の増加に関連している可能性があるようです。午後3~4時の時間帯や夏が終わる9月にも自殺が多かったとのこと。Medical Xpressの記事です。

有益な物質を体内に通し、害をもたらす物をブロックする小腸の細胞は、健康維持に重要な役割を果たします。米国の研究チームが、ブロッコリーに含まれる分子「アリール炭化水素受容体(AHR)リガンド」が、小腸細胞の働きを高める「AHRの活性化」に影響を与えることを発見。ブロッコリーを含まないエサを食べたマウスは、ブロッコリーを15%含むエサを食べたマウスに比べてAHR活性が低く、小腸の不健康につながるさまざまな要素が見られたといいます。EurekAlert!の記事です。

厳しいしつけは子どもの心の健康に悪影響を及ぼすようです。英国の研究チームが、アイルランドの子ども7507人を調査した結果を発表しました。頻繁に大声で怒鳴る、罰として部屋に閉じ込める、親の気分次第で対応が変わるなどは「非友好的な」育児スタイルとされます。そういった育児を3歳時点で受けていた子どもは、精神的な不調に関する評価スコアが9歳まで上昇し続ける「高リスク群」に分類される可能性が1.5倍高かったといいます。ScienceDailyの記事です。

ボツリヌス毒素による麻痺性疾患「ボツリヌス症」が、欧州で今年3月下旬までに67件報告されているそうです。このうち63件の詳細が分かっており、全ての患者がトルコにある二つの個人病院のいずれかで、減量のために胃壁にA型ボツリヌス毒素を注入する「胃ボトックス」を受けていました。トルコ当局によると、治療に使われた製品自体は認可済みですが、胃ボトックスへの使用は承認されていないといいます。今のところ死者はいないとのこと。ScienceAlertの記事です。

インド東部の西ベンガル州で、前例がないほど深刻なアデノウイルスの感染爆発が起きたようです。同州では今年1~3月に1.2万人以上の子どもがアデノウイルスに感染。政府の統計によると死者は19人ですが、実際には150人以上が死亡したとする専門家もいるそうです。患者から検出されたウイルスのほとんどは、3型、7型、組換え型株7/3型のいずれかだったといいます。専門家は「ワクチン開発を真剣に検討する必要がある」と指摘しています。Asian Scientistの記事です。

前夜の睡眠時間が5時間未満のときは、車の運転をしないほうがいいようです。豪州の研究チームが、睡眠と運転に関する61の研究を分析。24時間以内にとった睡眠が4~5時間未満の状態で運転すると、衝突事故を起こすリスクが倍増することが分かったそうです。これは、ほろ酔い状態(血中アルコール濃度0.05%)で運転した場合の衝突事故リスクと同程度だといいます。睡眠が0~4時間の場合、このリスクは最大15倍になる可能性があるとのこと。The Conversationの記事です。

患者本人の免疫細胞T細胞に遺伝子改変を行い、がん細胞への攻撃力を高める「CAR-T細胞療法」が固形がんにも有効かもしれません。イタリアの研究チームが、再発性または難治性神経芽腫の子ども27人を対象にCAR-T細胞療法を実施。6週間後、このうち9人からがんの痕跡が完全に消えたといいます。3年間の調査終了時には、11人が生存していたそうです。CAR-T細胞療法による一般的な副作用は見られたものの、そのほとんどが軽度だったとのこと。AP通信の記事です。

デング熱を引き起こすデングウイルスは、感染するために巧妙な手段を用いているようです。デング熱は蚊が媒介し、世界中で毎年約4億人の患者が出ているといわれてます。米国の研究チームが、デングウイルスに感染した蚊の唾液から「sfRNA」と呼ばれる分子を発見。この分子はデングウイルスによって産生されるもので、ヒトの免疫応答を鈍らせるのだそうです。蚊がヒトを刺した時に唾液と一緒にsfRNAが注入されると、感染が成立しやすくなるとのこと。Medical Xpressの記事です。

米カリフォルニア州に住む4歳の女の子が、コスタリカに旅行中にイグアナにかまれたことが原因で非結核性抗酸菌「マイコバクテリウム・マリヌム」に感染したそうです。米国の研究チームが、イグアナからヒトにこの細菌が感染した初めての症例として報告。女の子はビーチでケーキを食べていた際に、ケーキを狙う野生のイグアナに指をかまれたといいます。5カ月後に痛みのあるこぶ(2cm程度)ができたため、除去して抗菌薬で治療したとのこと。CNNの記事です。
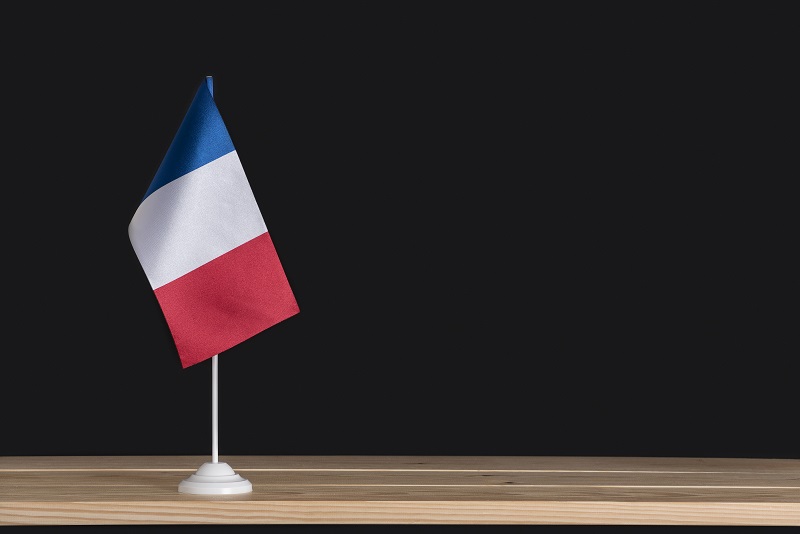
フランスで、安楽死や自殺ほう助といった終末期患者に対する「死への積極的援助」が合法化されるかもしれません。無作為に選ばれた市民184人で構成される委員会で、大多数が「死への積極的援助」を支持したそうです。これを受けてマクロン大統領は4月3日、夏の終わりまでにこの結論を盛り込んだ法案を作成すると表明したとのことです。法案の詳しい内容については明かされなかったものの、子どもへの適用は認めない考えだといいます。AP通信の記事です。
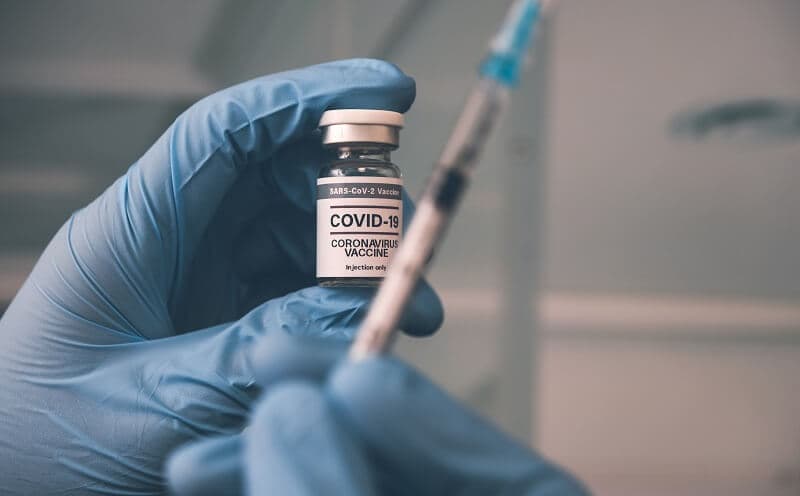
新型コロナウイルスに対する免疫維持のためには定期的な追加接種が必要かもしれません。米国の研究チームが、従来株向けのワクチン接種後にオミクロン株対応ワクチンを追加接種した8人を調査。300種類以上の抗体が検出されたそうです。その中にはオミクロン株に最適化した新しい抗体が六つあり、当時まだ出現していなかったBA.5を中和する抗体も一つ確認されたとのこと。追加接種が未知の変異株を中和する広域抗体を誘導する可能性があるといいます。Medical Xpressの記事です。

子どもの腸内細菌叢の発達は、出産時に母親の産道で受け継がれる細菌に大きな影響を受けるという説は誤りかもしれません。カナダの研究チームが600組以上の母子を調査したそうです。母親から出産前に膣内細菌を、生まれた赤ちゃんからは便をそれぞれ採取したといいます。その結果、経膣分娩か帝王切開かにかかわらず、母親の膣内細菌組成が生後10日や3カ月後の赤ちゃんの腸内細菌組成に大きな影響を与えることはないことが分かったそうです。EurekAlert!の記事です。
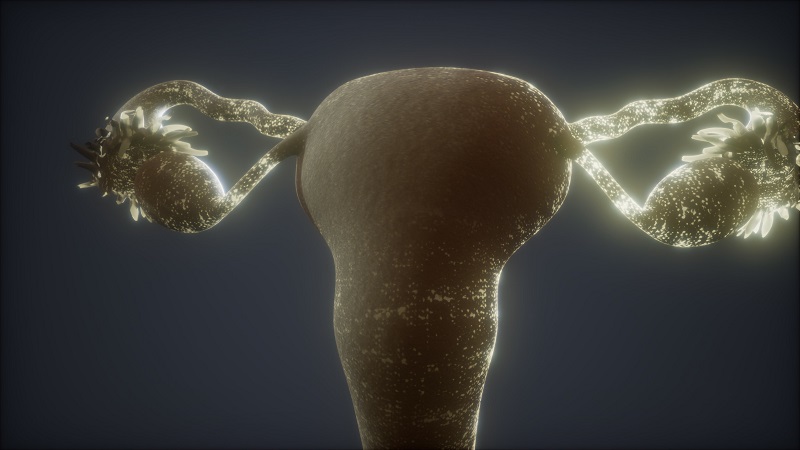
子宮体がんの進行を抑制する方法が見つかったようです。米国の研究チームが、ステージ3または4の子宮体がん患者816人を対象に12カ月間の調査を実施。細胞がDNA複製時のエラーを修復する機能(ミスマッチ修復:MMR)が欠損している患者に対して、化学療法と免疫療法(ペムブロリズマブ:商品名キイトルーダ)を併用すると、化学療法単独の場合に比べてがんが進行するリスクが70%低下したといいます。MMRが正常な患者のリスクは46%低くなったとのこと。Medical Xpressの記事です。

蚊が媒介する感染症で重症化すると半数が死亡する「黄熱」が治せるようになるかもしれません。米国の研究チームが、黄熱ワクチン接種者から取り出した37のモノクローナル抗体のうち2種類に着目。これらの抗体を研究室で作製し、黄熱ウイルスに感染させたアカゲザルとハムスターで調査を行ったといいます。どちらか一つの抗体を投与された動物は、血液からウイルスが検出されなかったそうです。どちらの抗体も安全性が示唆されたとのこと。Medical Xpressの記事です。

ペットの有無が子どもの食物アレルギーリスクに関連しているようです。日本の研究チームが、国内の子ども6万6215人のデータを分析。子どもが胎児期や乳児期のうちに屋内で犬や猫を飼っていた家庭では、子どもの食物アレルギー発症リスクが有意に低かったそうです。屋外犬の飼育では、こうした有意差は見られなかったといいます。屋内で犬を飼う家庭の子どもは、特に卵や牛乳、ナッツへのアレルギーを発症する可能性が低かったとのこと。EurekAlert!の記事です。
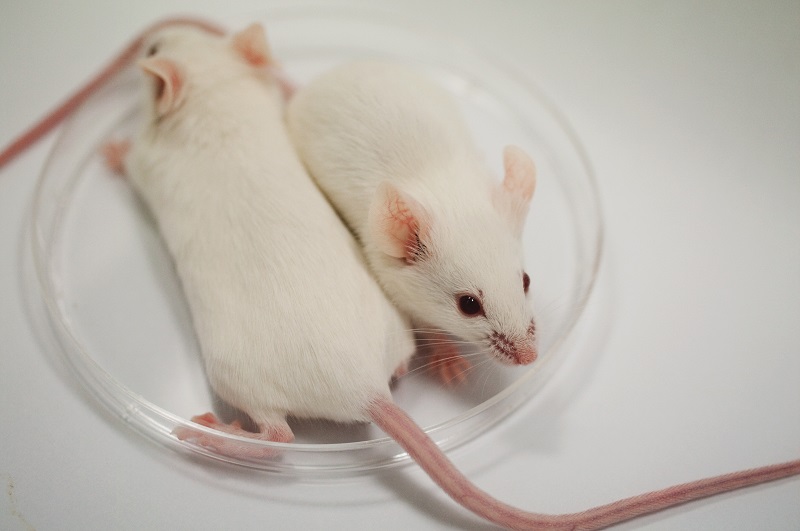
大阪大学の研究チームが、オスの両親を持つ赤ちゃんマウスを誕生させたそうです。チームはオス(XY染色体)のマウスから皮膚細胞を採取してiPS細胞を作製。さらにiPS細胞培養中に起こる細胞分裂のエラーを利用し、卵子(XX染色体)を作り出したそうです。できた卵子と別のオスのマウスの精子を受精させてメスのマウスに移植したところ、赤ちゃんが生まれたといいます。ただし、移植した受精卵が赤ちゃんとして誕生する成功率は約1%だったとのこと。CNNの記事です。

肝細胞にトリグリセリド(中性脂肪)がたまる非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)の人が、食べ物の摂取時間を制限する食事時間制限法(TRE)を実践しても効果は小さい可能性があるそうです。米中の研究チームが、NAFLDをもつ肥満患者88人を「カロリー制限群」と「カロリー制限に加えてTREを行う群(TRE群)」に分けて調査したとのこと。12カ月後に肝内トリグリセリドを調べたところ、カロリー制限群は7.9%減少、TRE群は6.9%の減少で、同程度の効果だったといいます。Medical Xpressの記事です。

目の検査で、認知障害の症状が現れる前にアルツハイマー病(AD)を診断できる可能性があるようです。米国の研究チームが、認知機能低下の度合いが異なる86人から網膜や脳の組織を採取して分析。ADや軽度認知障害を持つ人の網膜からは、正常な人に比べてADと関連があるとされるタンパク質アミロイドβが多く見つかったそうです。網膜周辺の細胞で起きている組織の萎縮や炎症を調べることで、認知機能の状態を予測できる可能性が示唆されたといいます。CNNの記事です。

糖分や脂肪を多く含む高カロリーの西洋式の食事を続けても、太る心配をしなくてよくなるかもしれません。米国の研究チームが、体内にマグネシウムが多く存在すると、ミトコンドリアが糖質や脂肪を使ってエネルギーを生産する速度が遅くなることを発見したそうです。そこで、ミトコンドリアに送られるマグネシウム量を制限する新薬「CPACC」を、西洋式の食事を長期間摂取したマウスに投与したところ、マウスの体重が減ったといいます。Medical Xpressの記事です。

ミトコンドリアを移植することで、心停止後の予後が改善する可能性があるようです。米国の研究チームが、10分間の心停止から蘇生したラット33匹を3群に分けて調査。72時間後生存率は、ドナーのラットから採取した非凍結のミトコンドリアを移植したラットが91%だったのに対し、対照群は55%だったといいます。凍結融解ミトコンドリアの移植では同様の効果は認められず、新鮮なミトコンドリアの機能が生存率改善に関与しているとみられるそうです。Medical Xpressの記事です。

米カリフォルニア州の研究チームが、まれなトキソプラズマ原虫株が原因で2020~22年に同州沿岸のラッコ4匹が死んだと発表したそうです。ヒトへの感染例は確認されていませんが、魚介類や汚染された水を摂取することで感染が広がる可能性があり、専門家が注意を呼び掛けています。この種類のトキソプラズマ原虫が水生動物や同州沿岸で確認されたのは初めてだといいます。死んだ4匹のラッコは、脂肪組織に炎症がみられたそうです。CNNの記事です。

アルツハイマー病(AD)の進行を遅らせるための新たな取り組みです。米Cognito Therapeutics社とマサチューセッツ工科大学(MIT)が、音と光を発する特殊なヘッドセットを開発。脳の免疫細胞ミクログリアを活性化してADと深い関係があるとされるタンパク質アミロイドβの除去を進め、認知機能を改善する可能性が注目されている脳波のガンマ波を刺激するといいます。現在、軽~中等度のAD患者500人への臨床試験が行われており、結果は2025年前半に公表する予定だそうです。INSIDERの記事です。
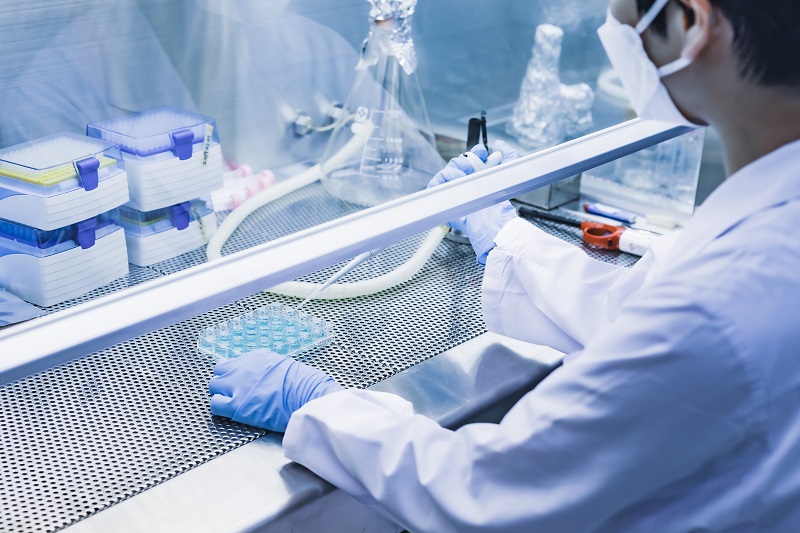
ノルウェーの研究チームが18年の歳月をかけて、がん細胞だけを標的にする末期患者向けの新薬「ATX-101」を開発したそうです。末期がん患者20人に第1相試験を実施したところ、6週間後の時点で患者の70%が、がんの成長が止まる「安定」の状態になったといいます。患者の1人は17カ月間投薬を受け、2年以上安定した状態を保ったそうです。また、ATX-101は健康な細胞には影響を与えないため、がん治療に伴う脱毛の心配をする必要がなくなるとのこと。Medical Xpressの記事です。

作曲家ベートーベン(1770~1827年)の健康上の問題がゲノム解析によって明らかになったそうです。英国などの研究チームが、保管されていたベートーベンの毛髪を使って分析。ベートーベンは肝臓病の遺伝的素因を持っていたといいます。また、B型肝炎ウイルスに感染した形跡も見られたそうです。こうしたリスク因子と大量飲酒が原因で、肝硬変を発症した可能性が指摘されています。今回の解析では、聴力低下の原因は特定できなかったとのこと。BBCの記事です。

原因が特定できない非特異的腰痛に対する鎮痛薬の使用には、慎重になったほうがいいようです。豪州などの研究チームが、1964~2021年に発表された98の臨床試験に関するデータを分析。参加者は計1万5134人、調べた薬の種類や組み合わせは69に上ったといいます。その結果、複数の非ステロイド性抗炎症薬や筋弛緩薬、プレガバリン、アセトアミノフェンなど計17の鎮痛薬について、急性腰痛への効果を示す証拠の信用性が低いことが分かったそうです。Medical Xpressの記事です。
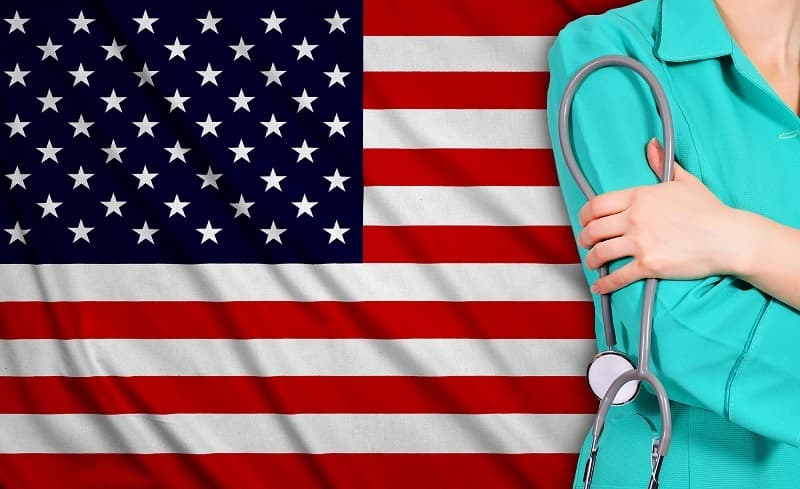
カンジダ・アウリスは、全身感染を起こした場合の致死率が30%という危険な真菌です。米国でこの真菌の症例が、3年間で3倍近くに増加しているそうです。カンジダ・アウリスは健康な人には無害です。しかし、病院や老人施設などでは集団感染や死亡例が発生する危険もあります。一般的に使われる3種類の抗真菌薬すべてに耐性を持つ株も存在するようです。2019年に476例だった米国の症例数は、20年に756例、21年には1471例に急増しているとのこと。AP通信の記事です。

思春期に大麻成分「テトラヒドロカンナビノール(THC)」に暴露すると、卵胞や卵子の枯渇につながる可能性があるようです。米国の研究チームが、発育中のマウスに2週間にわたりTHCを投与して調査。その結果、健康な卵胞数が50%減少することが明らかになったそうです。2019年の調査では、米国の12~17歳の330万人が大麻を使用していると報告されています。女子の大麻使用が生殖機能に及ぼす長期的な影響について周知する必要があるとのこと。Medical Xpressの記事です。

大麻の使用は、心血管へ悪影響を与えることが分かったそうです。米国の研究チームが100万人以上のデータを分析。毎日大麻を使用すると答えた人(4736人)は一度も使ったことがないと答えた人(3万9678人)に比べて、冠動脈疾患(CAD)リスクが34%高かったそうです。大麻の使用頻度が月1回以下の場合、リスクに影響はなかったといいます。研究は、ゲノム情報を利用するメンデルランダム化解析を用いており、大麻とCADの直接的な因果関係が示唆されたとのこと。CNNの記事です。

気候変動の影響で、マラリアを媒介する蚊の分布域が予想以上の速さで広がっているようです。米国の研究チームが、これまでに蓄積されたアフリカにおける蚊の分布域に関するデータを分析。22種類のハマダラカについて、1898~2016年のデータを評価したといいます。この期間内に世界の平均気温は少なくとも1.2度上昇しています。それに伴い、ハマダラカの分布域は1年に4.7kmずつ南方面に拡大し、毎年6.5mずつ標高も高くなっているとのことです。ScienceAlertの記事です。

アイマスクを使って睡眠中の光を遮断することで、翌日の注意力や記憶力が向上する可能性があるようです。英国などの研究チームが、18~35歳の参加者計122人を調査した結果です。睡眠中にアイマスクをすると、記憶力や反応速度を評価するテストでよい成績が出ることが明らかになったそうです。また脳活動の測定から、アイマスクの着用が、記憶力の向上に重要な役割を果たすとされる「徐波睡眠」の増加につながることも示されたといいます。ScienceAlertの記事です。

ノンカロリーのカフェイン飲料を飲んで血中のカフェイン濃度を高めることは健康に良い影響を及ぼすようです。スウェーデンなどの研究チームが、遺伝的証拠から因果関係を明らかにする「メンデルランダム化解析」を用いて、主にヨーロッパ系の参加者1万人を調査。解析はカフェイン代謝に関連する二つの遺伝子変異に着目して行われ、遺伝子的に血中カフェイン濃度が高くなる人は、肥満や2型糖尿病のリスクが低いことが分かったといいます。EurekAlert!の記事です。

コーヒーにミルクを加えると、健康上のメリットが増大するようです。デンマークの研究チームが、炎症時の状態にした免疫細胞のマクロファージを使って効果を調べました。コーヒーに含まれるポリフェノール(カフェ酸:CA、クロロゲン酸:CGA)だけをマクロファージに浴びせた時よりも、ポリフェノールと牛乳のタンパク質に含まれるアミノ酸(システイン:Cys)を組み合せたものを浴びせた時の方が、抗炎症効果が高まることが分かったといいます。ScienceAlertの記事です。

人工甘味料「スクラロース」を自己免疫疾患の治療に活用できるかもしれません。英国の研究チームが、ヒトにおける1日の許容摂取量に相当するスクラロースをマウスに与えて調査したといいます。高用量スクラロース群は、がんや感染に対して免疫細胞のT細胞が活性化しにくかったそうです。T細胞は自己免疫疾患で中心的な役割を果たします。このことからチームは、スクラロースでT細胞の過剰活性を抑制できる可能性があると考えているようです。EurekAlert!の記事です。

モーツァルトの楽曲「ソナタKV448」を聴くとてんかんの症状が緩和するという説があります。本当なのでしょうか。オーストリアの研究チームが、このテーマに関する入手可能な全ての科学文献を調査。KV448がてんかんに有益な影響を及ぼすとの信頼性のある証拠は見つからなかったそうです。いわゆる「モーツァルト効果」神話は、複数の結果の一部だけが選択的に報告されていたり、サンプル数が少なかったりしたことが原因で生まれたものだといいます。Medical Xpressの記事です。

新型コロナにかかった後、人の顔が覚えられない相貌(そうぼう)失認(失顔症)になった女性(28)がいるそうです。カナダの研究チームの調査では、女性は知らない人の顔を覚えるのが困難なだけでなく、家族の顔も分からなかったとのこと。また、場所の位置関係の把握もできなくなっているといいます。こうした症状は視覚処理の障害から起きている可能性が高いそうです。コロナ後遺症患者54人の調査では、多くの人が失顔症の症状を報告したとのこと。Medical Xpressの記事です。

不可能と考えられていた、細菌に有効なmRNAワクチンが実現する可能性があるようです。イスラエルの研究チームが、免疫系に細菌のタンパク質を認識させる画期的な方法を考え出し、細菌用のmRNAワクチンの開発に成功したといいます。致命的な病気を引き起こす細菌に感染させた動物での実験では、ワクチン非接種群は1週間以内に全て死んだ一方、ワクチン接種群は元気に生き残ったそうです。たった1回の接種で100%の有効性が確認されたとのこと。Medical Xpressの記事です。

肺疾患の新たな治療法の開発に道を開く研究成果です。英国の研究チームが、参加者58万869人のゲノム情報を解析したそうです。参加者には世界中のさまざまな人種が含まれ、過去最大規模のゲノム解析だといいます。その結果、肺機能に関係する559の新たな遺伝子が特定されたとのことです。この発見が、慢性閉塞性肺疾患(COPD)や喘息などに対する新たな治療法や有効な既存薬の特定、個々の患者に適した薬剤の選択につながることが期待されています。BBCの記事です。

前立腺がんの手術や治療はほとんどの場合、実施時期を遅らせたり回避したりできるそうです。英国の研究チームが、前立腺のみでがんが確認された患者1600人を3群に分けて調査。15年後の前立腺がんによる死亡率は、血液検査などで積極的に経過観察を行って過剰な治療を防ぐ「監視療法」群が3.1%▽手術群が2.2%▽放射線治療群が2.9%――で有意差は認められなかったといいます。一方で転移率は監視療法群(約9%)の方が他の2群(約5%)より高かったとのこと。AP通信の記事です。

米食品医薬品局(FDA)は、ファイザー社が開発した片頭痛に即効性のある点鼻スプレー薬「Zavegepant(商品名Zavzpret)」を承認したそうです。脳内の炎症に関与するカルシトニン遺伝子関連ペプチド(CGRP)を阻害する薬です。使用からわずか15分で片頭痛の症状を緩和する効果があるといいます。臨床試験では、同薬10mgを使用した片頭痛患者の24%が2時間後には痛みが消えたと報告したそうです。主な副作用として、使用者の5人に1人に味覚の変化が確認されたとのこと。CNNの記事です。

乳がんを検出するにはマンモグラフィ検査だけでは不十分なようです。米食品医薬品局(FDA)は法律を改正し、検査施設がマンモの結果を患者に伝える際に、乳腺密度の情報も一緒に提供することを義務付けるとのこと。マンモ画像ではがんも乳腺も白く写るため、がんを見逃すリスクが高いそうです。検査施設は今後、乳腺密度に関する情報を患者に提供するとともに、高濃度乳腺患者に対して医療機関に相談するよう助言することが求められるといいます。CNNの記事です。

腸内細菌は免疫チェックポイント阻害薬の効果に影響を与えるそうです。米国のチームが、黒色腫(メラノーマ)マウスで調査。免疫チェックポイント阻害薬が消化器系の炎症を誘発し、腸内のリンパ節に変化を起こすことが判明したそうです。この変化によって腸内細菌は、腸以外に存在する腫瘍やその近くのリンパ節に移動し、免疫細胞の活性を促す働きをするといいます。腸内細菌を殺す抗菌薬の使用で、薬が効かなくなる可能性も示唆されたとのこと。Medical Xpressの記事です。

大阪大学の研究チームが、オスのマウスの細胞から卵子を作り出したと発表したそうです。チームはまず、オスマウスの皮膚から幹細胞を作成。この幹細胞はオス由来なのでXY染色体を持ちます。そこで、オスの幹細胞が卵子になるよう調整するため、Y染色体を削除し、X染色体を複製したそうです。この技術がヒトに適用されるまでの道のりは非常に長いといいますが、男性同士のカップルが自分たちの子どもを持つことが可能になる日が来るかもしれません。BBCの記事です。

原発性骨腫瘍患者の生存率が高まる可能性があります。原発性骨腫瘍は子どもに多く発生し、急速に肺に転移するため5年生存率は42%といわれています。英国のチームが開発中の新薬「CADD522」を、人の骨腫瘍を移植したマウスで調査。新薬が腫瘍の転移に関連する遺伝子の働きを阻害することを突き止めました。新薬単独で治療したマウスは、未治療群に比べて無転移生存率が50%上昇。手術や化学療法との併用で、さらに生存率上昇が期待できるとのことです。BBCの記事です。

1週間にグラス1杯分のワイン(純アルコール量12g)でも、妊娠前や妊娠中の母親の飲酒は生まれた子どもの顔の形態に影響を及ぼすそうです。オランダの研究チームが、人工知能(AI)を用いて5000人以上の子どもの3D顔画像を分析。その結果、出生前のアルコールへの暴露が、9歳時点での顔の形態に関連することが分かったそうです。具体的には、鼻が上を向く、鼻が短くなる、あごが突き出る、下まぶたの向きが変わるなどの特徴が見られたといいます。EurekAlert!の記事です。

ストレスが多い人は認知機能の低下が起きやすく、記憶力や集中力、学習能力に影響が出るようです。米国の研究チームが、黒人が多く住み、脳卒中の発症率が高いことで知られる米国南部で、45~98歳の参加者数千人を10年以上にわたり調査。その結果、ストレスが多いと申告した人は認知機能が低下する可能性が37%高いことが分かったそうです。黒人と白人で結果に差はなかったものの、全体的に黒人のほうが高ストレスを報告したといいます。CNNの記事です。
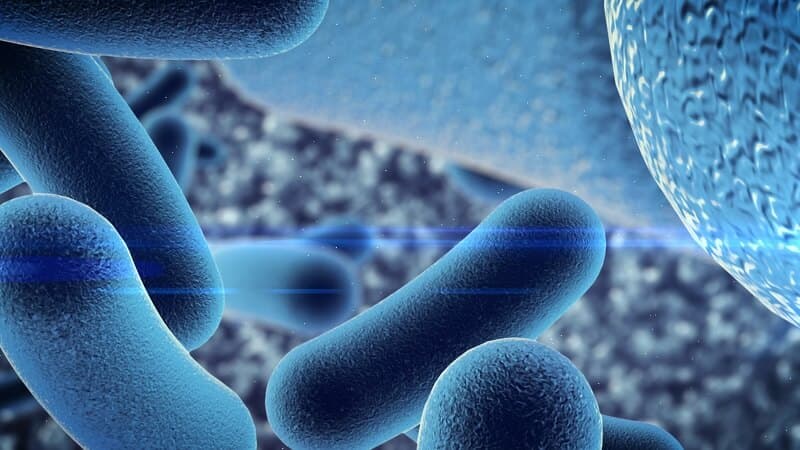
腸内細菌はがん治療に影響を及ぼすそうです。ドイツの研究チームが、化学療法を受ける膵管腺がん患者の血液を分析しました。その結果、化学療法がよく効く人は、3-インドール酢酸(3-IAA)と呼ばれる物質のレベルが高いことが分かったそうです。さらに、この物質は2種類の腸内細菌によって産生されることも明らかになったといいます。がんを持つマウスのエサに3-IAAを加えたところ、化学療法への反応がよくなったとのことです。Medical Xpressに紹介されています。

抗ミュラー管ホルモン(AMH)値は卵巣の中に残っている卵子の数の目安になります。ただ、AMH値が低いからといって、不妊だと決めつけない方がいいようです。複数の研究が、AMH値と妊娠の可能性に関連性はないとの結果を示唆。豪州の専門機関なども「AMH検査は女性の受胎能力について助言するために単独で使われるべきではない」と言及しているそうです。オンラインで簡単に入手できるAMH検査キットが、人々に誤解を与えているとの指摘もあるようです。ABC NEWSの記事です。

筋肉痛などの副作用が理由でコレステロール低下薬「スタチン」を服用できない人がいます。そういった人への新たな選択肢が見つかったそうです。米国の研究チームが、スタチンの副作用に耐えられない高LDL(悪玉)コレステロール患者1万4000人を5年にわたり追跡調査。スタチンと組み合わせて使われるコレステロール低下薬「Nexletol(一般名ベムペド酸)」を単独で毎日服用した人は、プラセボ群に比べて主要な心血管疾患リスクが13%低くなったといいます。AP通信の記事です。

糖質を制限し高脂質な食事をとるケトジェニックダイエットは心臓発作や脳卒中のリスクを上昇させるようです。カナダのチームが、LCHF(低炭水化物・高脂質)を「1日の総カロリーの45%を脂質、25%を炭水化物から摂取する状態」とし、英国でLCHF食をとる305人と標準的な食事をとる1200人を比較。LCHF食群は、LDL(悪玉)コレステロールとアポリポタンパク質の値が高かったそうです。11.8年後には、LCHF食群は動脈閉塞などの心血管イベントリスクが倍増したとのこと。CNNの記事です。

米フロリダ州当局が、水道水で鼻洗浄をした人が「脳を食べるアメーバ」と呼ばれるネグレリア・フォーレリに感染して死亡したと発表したそうです。このアメーバは、汚染された水が鼻から体内に入った場合のみ人に感染します。池や川で泳いで感染することが多く、患者はたいてい死亡します。当局は、煮沸していない水道水を鼻洗浄に使わないよう住民に注意を呼びかけたそうです。胃酸がアメーバを殺すため水道水を飲んでも問題ないとのこと。CNNの記事です。

砂糖の代わりに使われるカロリーゼロの甘味料「エリスリトール」が、心臓発作や脳卒中リスクを高めることが分かったそうです。米国のチームが、糖尿病などの心臓病リスク因子を持つ4000人近くの血液を分析。血中エリスリトールレベルが上位25%の人は、下位25%の人に比べて3年以内に心臓発作や脳卒中を発症するリスクが2倍高かったといいます。動物実験などで、エリスリトールが心臓発作や脳卒中を引き起こす血栓を誘発することも判明したとのこと。CNNの記事です。

米疾病対策センター(CDC)が、米国内で広範囲薬剤耐性(XDR)を持つ赤痢菌への感染が増加しているとして注意を呼びかけたようです。赤痢菌は重度の下痢を引き起こすグラム陰性菌。XDR赤痢菌は、一般的に推奨される抗菌薬すべてに耐性を持つそうです。米国で検査された赤痢菌のうちXDRの占める割合は2019年は1%でしたが、22年は5%にまで上昇したといいます。XDR赤痢菌向け抗菌薬としては、ホスホマイシンやメロペネムが選択肢になる可能性があるとのこと。CBS Newsの記事です。

米食品医薬品局(FDA)の諮問委員会は、グラクソ・スミスクライン(GSK)社が60歳以上向けに開発したRSウイルス(RSV)ワクチンについて、安全かつ有効であると発表したそうです。FDAが高齢者向けRSVワクチン候補に推奨の立場を示したのはファイザー製に次いで2例目。治験ではRSVに関連する下気道疾患の85%以上を予防する効果があったといいます。ただし、一部の治験参加者がギラン・バレー症候群を発症しており、この点を懸念する声も上がっているとのこと。USA TODAYの記事です。

アスピリンを頻繁に使用すると、卵巣がんの遺伝的リスク因子をもつ人の卵巣がん発症リスクが抑制されるそうです。米国などの研究チームが、既存の8研究から非粘液性卵巣がん患者4476人と対照群6659人のデータを分析。 6カ月以上ほぼ毎日アスピリンを使用していると自己申告した人は、卵巣がんリスクが13%低かったそうです。たとえ卵巣がんの発症リスクが高いとされる遺伝子変異を持つ人であっても、この数字に影響はなかったといいます。Medical Xpressの記事です。
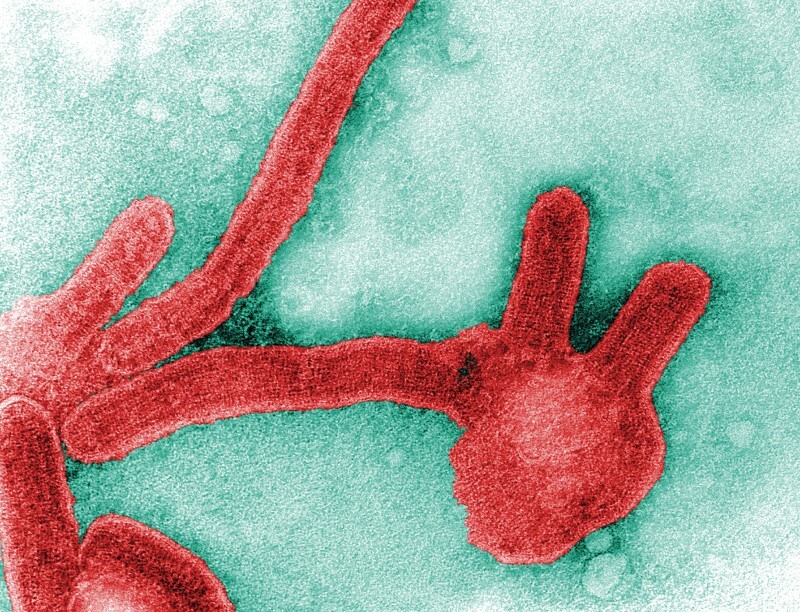
致死率が最大88%というマールブルグ病がアフリカ中部の赤道ギニアで確認されています(隣国ギニアでも疑い例)。エボラウイルスと同じフィロウイルス科のマールブルグウイルスに感染することで発症し、症状はエボラ出血熱に似ています。ワクチンや治療法はありません。世界保健機関(WHO)は緊急会議で28のワクチン候補を特定。二つの第1相試験が始まりましたが、現状では大量生産はできないとのこと。Medical Briefの記事です。最新情報では11人の死者が出ているようです。(写真:マールブルグウイルス=CDC提供)

幹細胞治療で、心不全患者の心臓発作や脳卒中のリスクを低減できる可能性があるようです。米国などの研究チームが、心筋が弱り薬物療法を受ける心不全患者565人を調査。健康なドナーの骨髄から採取した抗炎症作用のある間葉系前駆細胞を心臓に単回投与された人は、プラセボ群に比べて心臓発作や脳卒中のリスクが58%低くなったそうです。この効果は平均2.5年間持続したといいます。体内の炎症レベルが高い患者では、リスクが75%低下したとのこと。CNNの記事です。

米ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)が新型コロナの発生源について、「米エネルギー省が中国の研究所から偶発的に流出した可能性が最も高いと結論付けた」と報じました。同省がホワイトハウスに提出した機密報告書の内容だそうです。新型コロナの発生源をめぐっては、市場で動物から人間に感染したとする説もあり、米国の複数の情報機関の間でも見解が分かれているといいます。しかし、どちらの説も決定的な証拠は見つかっていないとのこと。USA TODAYの記事です。

朝食を抜くと免疫機能が低下するようです。米国の研究チームが、マウスを「朝食をとる群」と「朝食を抜く群(断食群)」に分けて調査。起床から4時間後、白血球の一種「単球」の血液中における数が断食群で大幅に減少したといいます。断食による脳のストレス反応で、血液中の単球が骨髄に移動して「冬眠」してしまうのだそうです。断食後に食事をすると、単球が一気に血液中に戻り、感染を防ぐ代わりに不要な炎症を起こしてしまうとのこと。Medical Xpressの記事です。

英保健当局は、鳥インフルエンザウイルスH5N1型がヒトのあいだで大流行するという最悪の事態を想定し、緊急時の対応計画を作成しているそうです。鳥インフルは感染した鳥に直接接触した場合にヒトにうつり、ヒトからヒトに感染するとの証拠は示されていません。しかしウイルスは絶えず進化します。ヒトにおける感染爆発に備えて、専門家は想定される感染者数や重症化の可能性、検査体制、危険な変異に関する情報を取りまとめているとのこと。BBCの記事です。

カンボジアで、2014年以来初めてとなる鳥インフルエンザウイルスH5N1型のヒトへの感染が確認されたそうです。患者は同国南東部のプレイベン州に住む11歳の少女です。39度の発熱に加えて、咳やのどの痛みの症状があったといいます。少女は首都プノンペンの病院に運ばれましたが、鳥インフルと診断されて間もなく死亡したとのことです。同国の保健当局は、少女の自宅近くで見つかった野鳥の死骸からウイルスを採取したと発表したそうです。AP通信の記事です。

脳の血流が悪くなる可能性があるとして、プソイドエフェドリンを含有する鼻炎薬の安全性に関する再調査が行われるようです。一般的な鼻炎薬や風邪薬に含まれる成分で、鼻の血管に作用することで鼻づまりを改善します。しかし最近、フランスの規制当局がこの薬によるまれな脳への副作用について注意を呼びかけたといいます。英規制当局も、同薬使用に伴う可逆性後頭葉白質脳症(PRES)と可逆性脳血管攣縮症候群(RCVS)について調査を開始するとのこと。BBCの記事です。

多発性硬化症(MS)の原因となる慢性炎症を抑える方法が見つかったそうです。米国の研究チームが、腸などのバリア組織に存在する転写調節因子「芳香族炭化水素受容体(AhR)」に着目。MSマウスの実験で、免疫細胞T細胞のAhRの活性を阻害したところ、腸内細菌叢における胆汁酸などの代謝物産生に大変化が起こり、炎症が抑制されたそうです。その結果、マウスはMSから回復。AhRが腸内細菌の炎症促進作用を調整している可能性が示唆されたとのことです。Medical Xpressの記事です。

白血病治療のために幹細胞移植を受けたドイツの男性(53)が、エイズウイルス(HIV)感染から治癒したそうです。このような症例は世界で3例目。「デュッセルドルフの患者」と呼ばれるこの男性は2008年にHIV感染が判明し、10年に抗レトロウイルス療法を受けたといいます。翌年、男性は白血病と診断され、13年にHIV耐性の遺伝子変異をもつドナーから幹細胞の提供を受けたそうです。9年以上経過した現在も男性のHIV感染は寛解状態にあるとのこと。ScienceAlertの記事です。

65歳以上の乳がん患者は、ホルモン療法を受けていれば術後の放射線治療は不要かもしれません。英国の研究チームが、3cm以下のホルモン受容体陽性乳がんの65歳以上の患者1326人を調査しました。患者はみな手術とホルモン療法を受けていたそうです。術後に放射線治療を受けた人は、受けなかった人に比べて局所再発リスクが低かったといいます。しかし10年後の全生存率は、放射線治療群で80.7%、非放射線治療群で80.8%とほぼ同じだったとのこと。CNNの記事です。

22歳の時に脳卒中を発症し、後遺症で10年近く左半身不随(片麻痺)だった米国人女性が、新たな脊髄刺激療法で左手を動かせるようになったそうです。米国の研究チームが、首の脊髄の表面に金属電極を移植して特定の領域を刺激し、脊髄内の神経細胞を活性化させました。すると弱っていた筋肉の働きが強化され、女性は左の手や腕の動きをコントロールできるようになったそうです。数週間後には、装置がなくても左手が動くようになったとのこと。CNNの記事です。

10代の若者でもアルツハイマー病(AD)を発症することがあるそうです。中国の神経内科医が19歳の男性をADと診断。これまでに世界で報告されたAD患者としては最年少だといいます。この患者は17歳ごろから記憶力の低下がみられ、数年間で認知機能障害が悪化したそうです。この患者には、30歳未満のAD発症者のほとんどに見られる遺伝子変異が認められなかったといいます。また、認知機能低下につながる疾患や頭部外傷、家族のAD既往歴もないとのこと。ScienceAlertの記事です。

新型コロナウイルスの感染によってできる免疫には、予想以上の防御効果があるようです。米国の研究チームが、19カ国で実施された65研究を分析しました。その結果、コロナ感染から少なくとも10カ月間は、どの変異株に対しても良好な感染防御効果が発揮されることが分かったそうです。特に重症化や死亡のリスクについては約90%の抑制効果があるといいます。ただし、今回の調査には現在米国で主流のXBB系統に対するデータは含まれていないとのこと。CNNの記事です。

耐性菌発生の心配がいらない革新的な「抗菌薬」が存在するそうです。それは、米陸軍が兵士の携帯電話充電用に開発した微生物燃料電池用の化合物。米国の研究チームがその化合物をマウスに投与したところ、治療不可能とされる細菌感染症が治ったそうです。また、検証した全ての細菌に有効な上、細菌はこの化合物に耐性を持つことができなかったといいます。この化合物は細菌の細胞膜に作用し、複数の細胞機能を同時に破壊できるとのこと。Medical Xpressの記事です。

より正確に腫瘍のみを攻撃する「次世代」の光免疫療法が実現するかもしれません。英国の研究チームが、特定の波長の紫外線(UV)を照射するとがん細胞と「共有結合」を形成する抗体を開発。共有結合は結合力が強いため、薬剤分子が永久に腫瘍に固定されるそうです。腫瘍近くに埋め込んだライトのスイッチを入れると、抗体ががん細胞に結合し攻撃を始めるといいます。最先端の免疫療法よりも、健康な細胞に治療の影響を与えずに済むとのこと。Medical Xpressの記事です。

2型糖尿病患者にとって、血糖降下薬「ピオグリタゾン」は認知症予防にも有効な可能性があるようです。韓国の研究チームが、同国で新たに2型糖尿病と診断された非認知症患者9万1218人を平均10年間追跡調査。ピオグリタゾンを服用した人は、そうでない人に比べて認知症の発症リスクが16%低いことが明らかに。既往歴がある人ほど効果が高く、虚血性心疾患の人は54%、脳卒中の人は43%、それぞれ服用者の方が認知症リスクが低かったそうです。Medical Xpressの記事です。
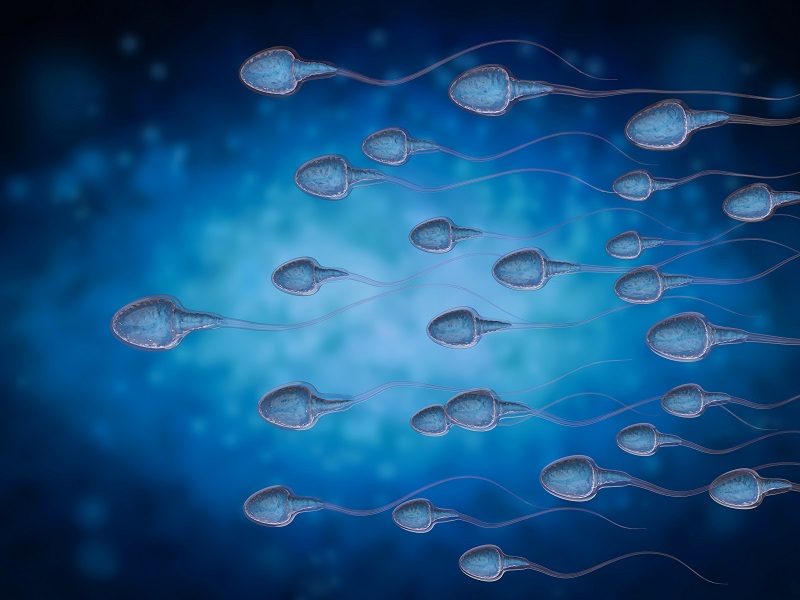
非ホルモン性の男性用経口避妊薬(ピル)ができるかもしれません。米国の研究チームが、酵素「可溶性アデニリルシクラーゼ(sAC)」に着目。sACは、精子の泳ぎを活性化させるスイッチの役割を果たします。sACを阻害する化合物をマウスに投与したところ、30分~1時間で精子の動きが止まったといいます。そして最初の2時間は100%の避妊効果がみられたそうです。24時間後には精子の動きは普段通りに戻り、副作用も認められなかったとのこと。ScienceAlertの記事です。

うつ病治療が変革期を迎えているようです。米セージ・セラピューティクス社が、米バイオジェン社と共同でうつ病を短期間で改善する治療薬「zuranolone」を開発。臨床試験では、大うつ病性障害や産後うつの症状を改善する効果がみられたといいます。既存の抗うつ薬は長期間の服用が必要ですが、zuranoloneは1日1回の服用を2週間だけ続ければいいそうです。米食品医薬品局(FDA)は、同薬を承認するかどうかを今年8月5日までに決める予定とのことです。INSIDERの記事です。

液体を加熱して蒸気を吸う「電子たばこ」は紙巻きたばこより健康被害が小さいとの考えは間違っているようです。米国の研究チームが、健康な成人72人から採取した口腔内の上皮細胞を調査。たばこ類を吸ったことがない人と比べたDNA損傷レベルは、紙巻きたばこを吸ったことがない電子たばこ愛用者が2.6倍、電子たばこを吸ったことがない紙巻きたばこ愛用者は2.2倍だったそうです。口腔上皮細胞のDNA損傷は慢性疾患リスクに関連するといいます。EurekAlert!の記事です。

運動前にビートルート(ビーツ)を摂取すると、良い成績を残せるそうです。ビーツは硝酸塩を多く含有する真っ赤な色をした根菜です。硝酸塩が体内に取り込まれると血管が拡張し、エネルギー燃焼に使われる酸素が筋肉に迅速に運ばれ、疲れにくくなるといいます。大規模な統計的レビューでも、ビーツの摂取で長距離走やサイクリングのパフォーマンスが向上するとの結果が示されたとのこと。ビーツは運動の2~3時間前に取るのがいいようです。ScienceAlertの記事です。

古代人が生き残るために必要だった脳内の反応が、現代のアルツハイマー病(AD)を理解するヒントになる――。米国のチームが、そんな研究成果を発表しました。チームによると、フルクトース(果糖)の働きで一部の脳領域の血流が抑制されると、飢餓に備えるための採食行動が促されるのだそうです。食べ過ぎなどで果糖の過剰生成が起き、脳血流が抑制されて脳代謝の低下が慢性的になると、ADの特徴である脳萎縮やニューロン喪失が生じるといいます。Medical Xpressの記事です。
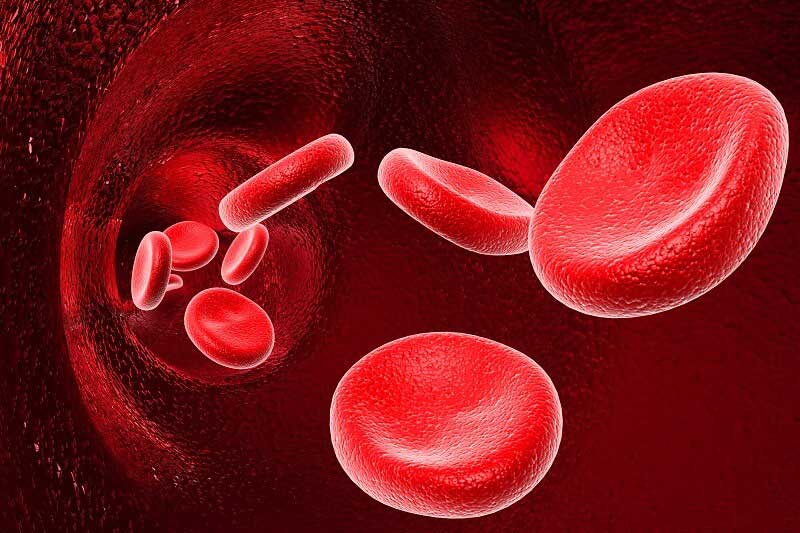
器材を使って血管内で治療を行う「血管内血栓回収療法」は、広範囲な脳梗塞を起こした患者にはリスクが大きいとして避けられてきました。しかし、米国のチームが世界の31医療施設で大動脈閉塞による広範囲脳梗塞を起こした患者352人を2群に分けて調査したところ、「常識」と異なる結果が出たそうです。通常と変わりない日常生活を送れる状態に改善した患者は、血栓回収療法を受けた人の20%、内科的な治療のみを受けた人の7%だったとのこと。Medical Xpressの記事です。

古くから漢方薬として重宝されてきたキノコの「ヤマブシタケ」が、神経細胞の成長を促進するそうです。豪州の研究チームが、培養した脳細胞を用いて前臨床試験を実施。ヤマブシタケの抽出成分が、神経細胞の成長をコントロールする成長円錐を増大させ、神経細胞間の接続を促すことが分かったそうです。これが記憶力の向上につながるといいます。今回の発見は、アルツハイマー病などの認知機能障害の治療や予防に役立つ可能性があるとのこと。Medical Xpressの記事です。

一般的な抗菌薬「ゲンタマイシン」の投与によって、まれに聴力を失う新生児がいることを知っていますか。ゲンタマイシンが、音の振動を電気信号に変換する内耳の有毛細胞が傷つけてしまうのだそうです。英国民保健サービス(NHS)は、新たな遺伝子検査キットを使って薬剤性難聴リスクのある新生児を抗菌薬投与前に素早く特定する試みを開始。このキットで口腔内粘膜を検査すれば、わずか26分で難聴リスクの有無が判明するそうです。BBCの記事です。

薬剤以外の方法で慢性便秘症を改善できるそうです。イスラエルのVibrant Gastro社が、大腸を振動で刺激して排便を促す経口カプセル「Vibrant」を開発。昨年8月に米食品医薬品局(FDA)が承認し、このほど米国で本格的に医師の処方が可能になりました。1日1回寝る前に服用すると、腸内の特殊な神経細胞が刺激され、便を押し出す蠕動(ぜんどう)運動が起こるといいます。Vibrantは便と一緒に体外に排出されるそうです。治験では下痢の副作用も少なかったとのこと。CNNの記事です。
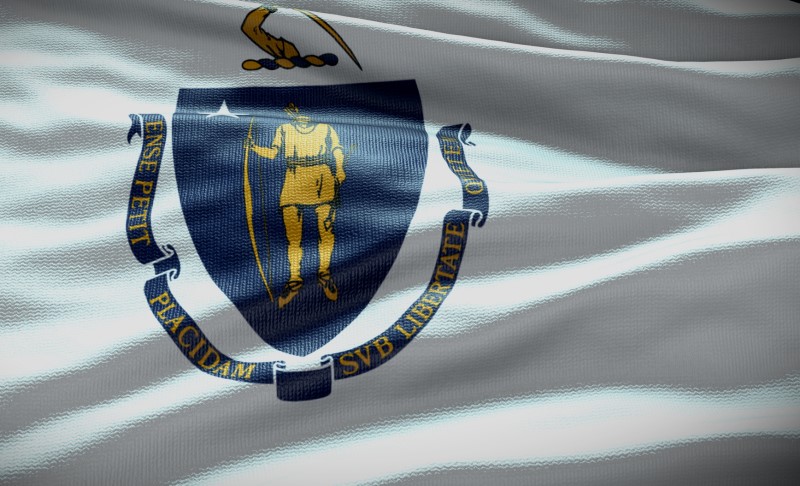
臓器提供に応じた受刑者の刑期短縮を可能にする法案が米マサチューセッツ州議会に提出され、物議を醸しています。法案には、受刑者が骨髄か臓器を提供することを条件に、刑期を60日~1年短縮するのを許可する内容が盛り込まれているといいます。しかしこのような措置は非倫理的であるだけでなく、臓器を売買したり報酬と交換したりすることを禁じる米連邦法に抵触する可能性もあります。なお、この法案は議会で否決される見通しとのこと。AP通信の記事です。
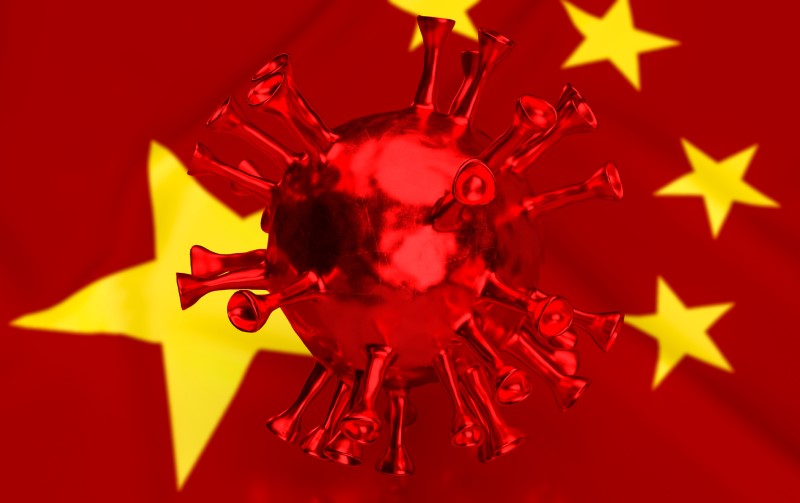
中国の研究チームが、「ゼロコロナ政策」の撤廃から少なくとも最初の数週間は、懸念されていた新型コロナウイルスの新たな変異株は発生しなかったと発表しました。昨年11月14日~12月20日に北京で413の検体を解析。90%以上が既存のオミクロン株の亜型で、新たな変異株発生の証拠はなかったとしています。これに対し、調査の時期が早すぎることや検査数の少なさ、調査地が北京に限定されていることを指摘する専門家もいるようです。Medical Xpressの記事です。

西アフリカのナイジェリアの有力な政治家が臓器の不当な入手を画策したとして、英ロンドンで裁判にかけられているそうです。政治家とその妻は、病気の娘のために腎臓のドナーを探していたとみられます。夫妻はナイジェリアの露天商の男性をロンドンに連れ出し、数千ポンドと引き換えに腎臓を提供させようとしたとされています。男性は仕事のためにロンドンに連れてこられたと信じていたそうです。臓器売買は英国でも犯罪です。AP通信の記事です。

適度な飲酒は認知症リスクを抑制する可能性があるようです。韓国の研究チームが、2009年と11年に同国で集められた40歳以上の400万人のデータを分析。酒を1日1杯 (純アルコール14g、缶ビール1本相当)程度飲む習慣があると答えた人は、飲酒しないと答えた人に比べて7~8年後に認知症を発症するリスクが21%低かったそうです。認知症の発症リスクは、飲酒量が1日2杯の人は17%低下したものの、3杯以上になると逆に上昇したとのこと。CNNの記事です。

アリを使って安価にがんを検出できるようになるかもしれません。フランスの研究チームが、マウスの尿の臭いから腫瘍の有無を識別できるようにアリ70匹を訓練したそうです。すると、アリは尿の臭いを嗅ぎ分けて、ヒトの乳がんを移植されたマウスか否かを正確に特定できるようになったといいます。腫瘍が小さいと尿の臭いはあまり変化しないそうですが、小さな腫瘍を持つマウスも大きな腫瘍を持つものと変わらない精度で検出できたとのこと。ScienceAlertの記事です。

質問を入力すると自然な文章で回答する「ChatGPT」という対話型のAI(人工知能)が話題になっています。米国では、医療分野におけるChatGPTの有益や欠点を調べるため、タスクフォースが発足しているそうです。あるチームが、三つのステップから成る米国の医師免許試験のサンプル問題を解かせたところ、ChatGPTは専門的な訓練を受けることなく全ステップで合格または合格に近い成績を残したとのこと。病期の診断や論文執筆ができるとの報告もあるそうです。CNNの記事です。

シナモンに認知機能の低下を抑える効果があるかもしれません。イランの研究チームが、シナモンと脳の関係を調べた、二つの臨床研究を含む40研究を分析。概してシナモンやその成分が記憶と認知機能に好影響を及ぼす可能性が示されたといいます。ただし、全ての人に効果があるわけではないようです。臨床研究のうち一つは前糖尿病段階にある60歳以下の成人を対象にしたもので、シナモンの効果は確認できなかったと結論づけられているそうです。Medical Xpressの記事です。

豪州は、合成麻薬「MDMA」とマジックマッシュルームに含まれる幻覚成分「シロシビン」を世界で初めて医薬品として正式に認めることを決めたようです。7月から、認可を受けた精神科医が心的外傷後ストレス障害(PTSD)の治療にMDMAを、治療抵抗性うつ病の治療にシロシビンをそれぞれ処方することが許可される予定。これらを使用することの長期的な影響に関するデータが不足しているなどの理由から、この決定に慎重な姿勢を示す専門家もいるといいます。ABC Newsの記事です。

脂質の摂取は、やはり控えた方がいいようです。米国の研究チームが、高脂肪・高カロリーの食事を与え続けたラットを調べたところ、脳と胃腸間のシグナル伝達経路が阻害され、脳が本来持つカロリー摂取量調節能力が損なわれることが分かったそうです。そしてこの調節能力には、脳内のアストロサイト(星状膠細胞)が関与しているといいます。高脂肪食を10~14日間食べ続けたラットは、アストロサイトの反応が鈍くなったとのことです。ScienceAlertの記事です。

米国の研究チームが、脳静脈が血栓で閉塞する「脳静脈洞血栓症(CVST)」を迅速に治療する装置を開発したそうです。この装置は超音波トランスデューサ(変換器)といい、カテーテルに内蔵して血管を通して血栓まで到達させ、そこで超音波のトルネード(らせん状の渦)を作り出して血栓を破壊するといいます。薬剤による血栓の溶解には平均29時間かかるとのことですが、試験管内の実験では、装置を使うと血栓を破壊するのに30分かからなかったそうです。Medgadgetの記事です。

既存の薬で、高齢者の血液を若返らせることができるかもしれません。米国の研究チームが、血液細胞を作り出す造血幹細胞が存在する骨髄を調査。年を取るにつれて骨髄でサイトカインの一種インターロイキン(IL)-1βが関与する炎症が起こり、造血幹細胞の機能が低下することが分かったそうです。そこでIL阻害薬で関節リウマチ治療薬の「アナキンラ」をマウスに投与したところ、加齢の影響を受けた造血幹細胞が若く健康な状態に戻ったといいます。Medical Xpressの記事です。

オランダ政府が、同国の農場で死んだメス牛1頭が牛海綿状脳症(BSE)の検査で陽性だったと発表したそうです。BSEは狂牛病とも呼ばれるまれな牛の伝染病。人が感染牛を食べると、致命的な脳症を発症する可能性があります。今回感染が確認された牛は8歳で、肉骨粉などの飼料を介して感染する「定型BSE」ではなく、孤発的に発生する「非定型BSE」だったそうです。当局が、死んだ牛の子や同じ飼料を食べて育った牛の追跡調査を行っているとのこと。AP通信の記事です。

肥満の人の脳は、アルツハイマー病(AD)患者と同様の変化(神経変性)が起こる可能性があるそうです。カナダの研究チームが1300人の脳を調査。AD患者と健康な人、肥満者と非肥満者をそれぞれ比較し、脳内で情報処理の中心を担う灰白質の萎縮パターンを解析したといいます。その結果、肥満者とAD患者の灰白質が同じようなパターンで薄くなることが明らかになったそうです。ただし、減量によってこのリスクを抑制できる可能性も示唆されたとのこと。Medical Xpressの記事です。

カナダのブリティッシュコロンビア州で、コカインやヘロインなどの中毒性が高い麻薬の所持が部分的に合法化されたそうです。これらの麻薬を成人が所持していた場合、2.5gまでであれば罪には問われず、代わりに薬物中毒治療に関する情報が提供されるといいます。同州ではオピオイドなどの麻薬の過剰摂取が社会問題になっています。今回の政策転換はその対策で、薬物依存が犯罪ではなく「健康問題」であるという認識を広めるためとのこと。CBS Newsの記事です。

高齢者がペットを飼うと、脳の健康を維持できる可能性があるそうです。米国の研究チームが、50歳を超える米国人2万人の2010~16年のデータを分析。ペットを5年超にわたって飼っていると申告した65歳以上の高齢者は、ペットを飼っていない同年代の高齢者に比べて、言葉に関する短期記憶と長期記憶がはるかに優れていることが明らかになったそうです。ただし、65歳未満の参加者では、このような有意差は認められなかったといいます。ScienceAlertの記事です。

米食品医薬品局(FDA)が、英アストラゼネカ製の新型コロナウイルスの抗体薬「エバシェルド」について、緊急使用許可を停止したそうです。この薬はワクチンが効きにくい免疫不全者向けの予防薬です。米国では現在、エバシェルドが効かない変異型「XBB.1.5」「XBB」「BQ.1」「BQ.1.1」の感染者が全体の93%近くを占めているといいます。今後はこの薬が効かない変異型の感染者の占める割合が全体の90%以下になった場合に限り、使用が許可されるとのことです。CNNの記事です。

世界の半数以上の人の胃に存在する「ヘリコバクター・ピロリ(ピロリ菌)」が、悪性黒色腫(メラノーマ)患者における化学療法の治療反応性に影響を及ぼすようです。カナダの研究チームが、化学療法を受けるメラノーマ患者100人を調査。血液によるピロリ菌抗体検査で陽性の人は、陰性の人に比べて免疫チェックポイント阻害薬治療の効果が得られない傾向が強かったそうです。ピロリ菌陽性の患者は、全生存率も有意に低かったといいます。Medical Xpressの記事です。

米国の献血規制が大きく変わるようです。現在米国では、エイズウイルス(HIV)感染のリスクが高いとの理由で、男性と性交渉する男性による献血を「最後の性交渉から3カ月経過している場合」に制限しています。米食品医薬品局(FDA)は1月27日、現在の制限を廃止し、ドナーに性行動などに関する質問票に答えてもらうことでHIV感染リスクを評価するというガイドライン案を公表。男性同性愛者など1600人を対象に行われた研究に基づくものだといいます。AP通信の記事です。

子宮内膜症の発症要因解明や治療につながる研究成果です。米国の研究チームが、腸内細菌叢を除去した子宮内膜症モデルマウスは、腸内細菌叢を持つモデルマウスに比べて子宮内膜症の病変が小さいことを発見。さらに、腸内細菌叢を除去したモデルマウスに子宮内膜症マウスの腸内細菌叢を移したところ、子宮内膜症病変が大きくなったそうです。腸内細菌叢由来の代謝物「キナ酸」が、子宮内膜症の進行に関与する可能性も示唆されたといいます。EurekAlert!の記事です。

映画「アバター」などでは、人間の動きを記録してCGなどで再現するモーションキャプチャー技術が使われています。英国の研究チームがこの技術を使い、運動機能障害を生じる疾患の研究に活用できる人工知能(AI)システムを開発。フリードライヒ運動失調症(FA)やデュシェンヌ型筋ジストロフィー(DMD)の患者を対象にした調査で、専門医より迅速かつ正確に疾患の進行を予測できることが示されたそうです。新薬開発時の治験に利用する計画もあるといいます。BBCの記事です。

筋肉や脂肪、神経などの軟部組織から発生する悪性腫瘍「軟部肉腫」には、微生物叢は存在しないと考えられてきました。しかし、米国の研究チームによる非転移性軟部肉腫の成人患者15人の調査で、それが誤りであることが分かったそうです。また、微生物叢の量が患者の予後に影響を及ぼす可能性も明らかに。軟部肉腫内に呼吸器疾患を引き起こすレスピロウイルスが多いと、腫瘍を攻撃するナチュラルキラー(NK)細胞の数が増えるのだそうです。Medical Xpressの記事です。

新型コロナの最新ワクチンの追加接種には、オミクロン株の派生型「XBB」系統の発症を防ぐ効果があることが分かったそうです。米国ではこの系統の「XBB.1.5」が急拡大しています。米疾病対策センター(CDC)が新たな調査結果を公表しました。それによると、初期のワクチンを接種した上で、従来株とオミクロン株BA.4/BA.5に対応した最新の2価ワクチンを追加接種した場合、XBB系統による発症リスクが抑制されることが明らかになったといいます。USA Todayに紹介されています。

最近新たに「VEXAS症候群」という自己免疫疾患が特定されました。その有病率が想定より高いことが分かり、専門家が懸念を示しています。この症候群はUBA1遺伝子変異によって血液異常が起こり、発疹や発熱、関節の腫れなどさまざまな症状が出ます。米国のチームが16万3096人のデータを分析したところ、50歳超の米国人の有病率(推定)は男性が4269人に1人、女性は2万6238に1人。診断から5年以内に約半数が死亡するといい、治療法は研究中とのこと。Healthlineの記事です。

米ジョンソン・エンド・ジョンソン社が開発中のヒト免疫不全ウイルス(HIV)ワクチンについて、有効性が示されなかったとして後期臨床試験が打ち切られたそうです。この治験は2019年に始まり、PrEP(予防的に抗HIV薬を服用する事)を拒否した男性同性愛者やトランジェンダーの3900人以上が参加したといいます。米国立アレルギー感染症研究所(NIAID)の報告によると、今回の治験でワクチンの安全性は示されたものの、感染予防効果は認められなかったとのこと。ScienceAlertの記事です。

新型コロナウイルスは胎児の健康に深刻な影響を及ぼすようです。英国の研究チームが、2020年7月~22年4月に選択的人工妊娠中絶をされた661人の胎児の脳組織検体を調査。このうち26検体で脳出血が確認されたそうです。そしてこの26検体すべてから、新型コロナウイルスが検出されたといいます。脳出血の兆候がみられた検体のほとんどが、脳の発達にとって重要な時期とされる妊娠初期の終わりや妊娠中期の初めの胎児のものだったとのこと。ScienceAlertの記事です。

米食品医薬品局(FDA)が、新型コロナワクチンの接種方法をインフルエンザワクチンのように原則年1回に簡略化することを検討しているそうです。米国では既に多くの国民がワクチン接種や感染によって既存のウイルスに対して十分な免疫を獲得しており、今後はその年に流行している変異株に対応したワクチンを接種する方法で対応できるといいます。ただし、免疫不全者や乳幼児など一部の人は、2回の接種が必要になる見込みとのことです。AP通信の記事です。

大腸(結腸)がんの再発リスクを抑制する方法が見つかったかもしれません。英国の研究チームが、英国や北欧の結腸がん患者1053人を2群に分けて調査しました。化学療法について、「術前に6週間と術後に18週間」受けた人は、「術後のみ24週間」受けた人に比べて結腸がんが2年以内に再発するリスクが28%低かったそうです。結腸がんの治療は現在、術後に化学療法を行うのが標準的とのことですが、見直しが必要かもしれません。Health Europaの記事です。

米食品医薬品局(FDA)はイーライリリー社のアルツハイマー病(AD)新薬「ドナネマブ(Donanemab)」の迅速承認を見送る判断を下しました。薬を最低12カ月間使用した患者の数が少な過ぎたためだそうです。この薬はADの原因と考えられている脳内のタンパク質アミロイドβ(Aβ)を減らし、認知機能低下を遅らせる効果があるといいます。同社側は「Aβの蓄積が予想より早く消失したケースがあり、12カ月間使用しなくてもいい患者がいたため」と説明しているとのこと。CNNの記事です。
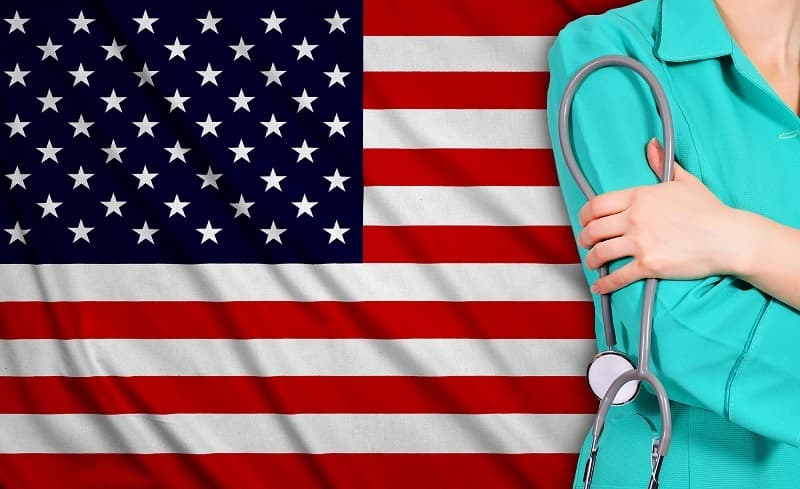
米国で、多くの抗菌薬が効かない淋菌が新たに見つかったそうです。米マサチューセッツ州保健当局がこの新たな菌株に感染した淋病患者2人を特定。2人とも抗菌薬セフトリアキソンの注射で回復したそうです。しかし2人が感染した菌株は、七つ中六つの抗菌薬にある程度の耐性の兆候を示したといいます。患者2人に直接的な関係は認められず、1人は最近の旅行歴がないことから、この菌株が既に州内で広がっている可能性があるとのことです。CBS Newsの記事です。

トゥレット症候群はチックを引き起こす神経疾患です。米国人の少年患者(17)に、パーキンソン病の治療に使われる外科的処置(DBS)が施され、効果があったそうです。少年は3年前から呼吸困難になるほど制御不能なチック症状に苦しんでいたといいます。米マウント・サイナイ・ウェスト病院が少年の脳にワイヤーを挿入し、神経の活動をコントロールするための電気刺激を与えられるようにしました。少年によると、処置以降チックが70%減少したとのこと。CBS Newsの記事です。

有鉛ガソリンを使う小型航空機が離着陸する空港の近くに住む子どもは、健康に悪影響があるようです。米国の研究チームが、カリフォルニア州のリードヒルビュー空港から2.4km以内に住む6歳未満の子ども1万4000人の血液サンプルを分析。住まいが空港に近いほど、血中鉛レベルの基準値として同州が定めている4.5μg/dLを超える可能性が高かったとのこと。空港から 0.5~1.5kmの距離に住む子どもに、鉛リスクの上昇がみられたといいます。NewScientistの記事です。

生きた微生物「プロバイオティクス」を摂取すると、有益な腸内細菌叢に悪影響を与えることなく、さまざまな疾患を引き起こす「黄色ブドウ球菌」のコロニー形成を抑制できるそうです。米国立衛生研究所(NIH)が、体に黄色ブドウ球菌が定着している参加者115人を対象に、タイで第2相試験を実施。プロバイオティクスの「枯草菌」を1日1回、4週間続けて投与された人は、黄色ブドウ球菌が便中で96.8%、鼻腔内で65.4%減少したとのこと。ScienceDailyの記事です。

短時間の激しい運動は、アルツハイマー病など神経変性疾患の発症を抑制するかもしれません。ニュージーランドのチームが、18~56歳の男女計12人を対象に脳由来神経栄養因子(BDNF)を増やす方法を調査。BDNFは、神経細胞の生存や新たなネットワーク作り(神経可塑性)の促進に重要な働きをします。全力で6分間自転車をこぐ高強度の運動は、20時間の断食や90分間ゆっくり自転車をこぐ運動に比べてBDNFが4~5倍増えることが明らかになったそうです。ScienceDailyの記事です。
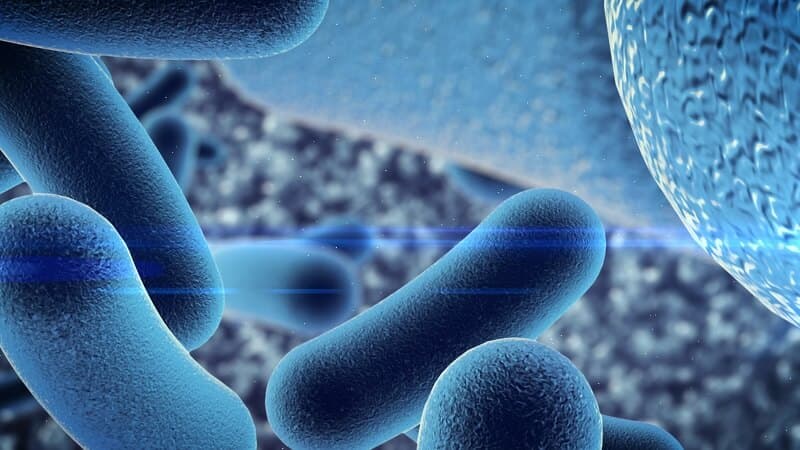
腸内細菌叢は肺の健康にも影響を及ぼすようです。米国の研究チームが新型コロナ患者71人について、集中治療室(ICU)に入院する際に便を採取して腸内細菌叢の組成を分析しました。呼吸不全が進行して死亡した患者はコロナから回復した患者に比べて、プロテオバクテリア門の腸内細菌が多かったそうです。こうした予後不良の患者は、腸内細菌叢由来代謝物質で免疫に関わる二次胆汁酸やデスアミノチロシンが少ないことも分かったといいます。EurekAlert!の記事です。

肥満気味の2型糖尿病患者は、肝臓の健康のためにコーヒーを多く飲んだ方がいいかもしれません。ポルトガルの研究チームが、肥満気味の中年156人のコーヒー摂取量を調査。2型糖尿病を持つ98人については、尿中代謝物も分析して正確な摂取量を調べたそうです。太りすぎの2型糖尿病患者がコーヒーのカフェインやポリフェノールなどを多く摂取すると、非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)の重症化リスクが低下する可能性が示唆されたといいます。EurekAlert!の記事です。

難病の「アラジール症候群」が移植以外の方法で治せるようになるかもしれません。この疾患は遺伝子異常が原因で、胎児期に体を作るための「Notchシグナル伝達」が正常に起こりません。胆管がうまく成長しないことで肝損傷が起こるケースが多いそうです。米国の研究チームが、このNotch経路を標的とした治療薬「NoRA1」を開発。この疾患に似た遺伝子変異をもつゼブラフィッシュにNoRA1を投与したところ、肝損傷が回復し、生存率も3倍向上したといいます。ScienceAlertの記事です。

点鼻薬を毎朝サッとスプレーするだけで、新型コロナを予防できるかもしれません。米国の研究チームが、新型コロナウイルスが細胞に侵入する際、ACE2受容体に結合することに着目。ACE2受容体を持つ「超分子フィラメント」のスプレーを設計しました。おとり役となるこのACE2受容体にウイルスが結合するため、肺細胞への感染が阻止される仕組みです。マウスの実験では、フィラメントは炎症を起こすことなく最大24時間肺の中に存在し続けたといいます。Medical Xpressの記事です。

中国政府は14日、12月8日~1月12日に同国で新型コロナによって6万人近くが死亡したと明らかにしたようです。発表によると、コロナ感染による呼吸不全で5503人が死亡し、基礎疾患との合併症による死者は5万4435人に上るそうです。この発表を受けて世界保健機関(WHO)は、感染状況の把握に役立つとして歓迎し、今後も詳細なデータを共有するよう中国に求めたといいます。なお、今回の発表には自宅で死亡した患者は含まれていないとのこと。AP通信の記事です。

新型コロナの軽症患者が後遺症に1年間以上苦しむことは少ないそうです。イスラエルの研究チームが、同国のコロナ軽症患者30万人と非感染者30万人のデータを比較しました。コロナ後遺症に関連する65の症状について調査したそうです。コロナ軽症患者は感染から30~360日後に、息苦しさや思考力低下をはじめとするいくつかの症状について発症リスクが高まるものの、そのほとんどが感染後1年以内に軽快することが示されたといいます。CNNの記事です。

アフリカ南東部のマラウイで昨年3月以来、コレラが拡大し続けているそうです。これまでに2万2759人の患者が確認され、死者は750人。最近は1日に約15人が死亡しており、過去20年で最悪の状況だといいます。コレラはコレラ菌に汚染された水や食品を通じて伝染します。同国の保健相は、安全な水やトイレ、衛生的なごみ処理場を確保できない施設に閉鎖を命じたそうです。屋台や市場などで調理済みの食品を売ることも禁止されたとのこと。AP通信の記事です。

健康に長生きするには、水分補給が重要なようです。米国立衛生研究所(NIH)が、45~66歳の米国人1万1000人を25年にわたり追跡調査しました。体内の水分量の指標で、数値が高いと水分を十分に摂取していない可能性がある血液中のナトリウム濃度に着目。参加者はみな正常範囲内の135~146mmol/Lでしたが、144mmol/Lを超える人は早期老化リスクが50%、早死リスクが20%高かったそうです。濃度が142mmol/Lを超えると、心不全や脳卒中などの慢性疾患リスクが上昇したとのこと。NBC Newsの記事です。

睡眠不足が原因で失われた記憶が取り戻せるかもしれません。睡眠不足で記憶障害が起こる時は、ある細胞シグナル伝達分子が減少しているそうです。オランダの研究チームが、慢性閉塞性肺疾患(COPD)の一般的な治療薬「ロフルミラスト」が、その分子レベルを上昇させる効果があることに着目。物の置き場所を覚えた後に睡眠不足状態にされ、記憶が失われたマウスにロフルミラストを投与したところ、置き場所の記憶が回復することが示されたそうです。ScienceAlertの記事です。

米国でガスを使ったコンロが使えなくなるかもしれません。米消費者製品安全委員会(CPSC)が、人体に有害な影響を及ぼす可能性があるとして、ガスコンロの使用禁止を検討していることを明言したそうです。昨年12月に発表された研究では、同国における小児喘息症例の13%が屋内でのガスコンロの使用に起因する可能性が示されたといいます。ガスコンロから放出される微小粒子状物質が、認知症やアルツハイマー病の発症率を高める恐れもあるとのこと。CBS Newsの記事です。

英国で、深刻な呼吸器疾患の原因となるウイルスを追跡するための新プロジェクトが始まるようです。同国の研究機関が政府などと協力し、新型コロナの検査で鼻や喉から採取された何百万もの検体の残りを使い、遺伝子情報を詳細に分析するそうです。インフルエンザウイルスやアデノウイルス、RSウイルスなど呼吸器疾患を引き起こす8~9種類のウイルスについて調べ、次の感染症の脅威を早い段階で見つけ出す戦略だといいます。BBCの記事です。

米国小児科学会が15年ぶりに、小児肥満に関する新たなガイドラインを公表したそうです。肥満に苦しむ子どもに対して、早い段階から積極的に治療を行う必要性を指摘。食事制限や運動だけでなく、12歳以上には投薬、13歳以上には減量手術を検討するべきだと明記しているそうです。投薬や手術の対象とするべき年齢が設定されたのは初めてといいます。ガイドラインの著者は「これまでのような経過観察は効果がない」と述べているとのこと。AP通信の記事です。

米食品医薬品局(FDA)は1月6日、製薬大手エーザイと米バイオジェンが開発したアルツハイマー病(AD)治療薬「レカネマブ」を迅速承認しました。この薬は早期AD患者の脳から異常なタンパク質のアミロイドβを除去することで、認知機能の低下を遅らせる可能性があるといいます。一方で、脳の腫れや出血などの深刻な有害事象との関連も指摘されています。なお、米国での卸売価格は患者1人当たり年2万6500ドル(約350万円)とのことです。CNNの記事です。
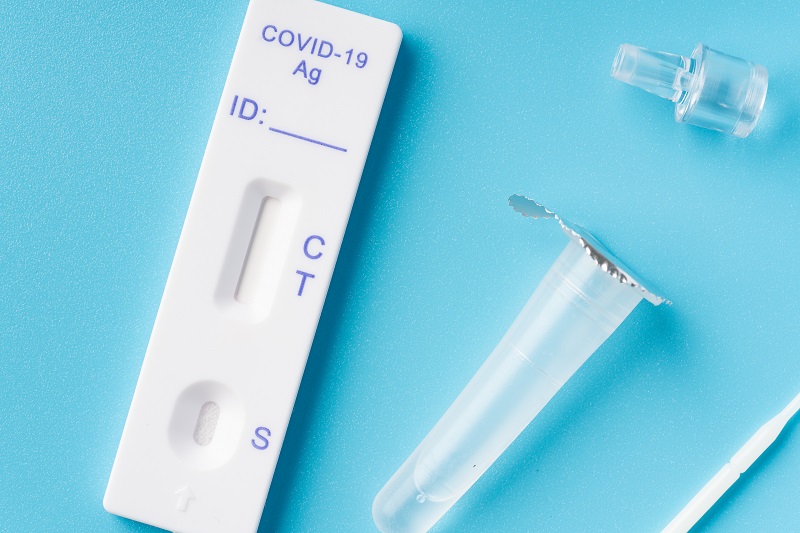
新型コロナの迅速抗原検査キットで、誤った結果が出ることがあるのはなぜなのでしょうか。まず、保管時や使用時の温度が不適切だと、結果が不正確になる可能性があるそうです。そして、検査前にコーヒーやコーラなどの酸性の飲み物を飲むと偽陽性になることがあるといいます。歯磨きなどは口腔のウイルスを一時的に除去するため偽陰性につながるとのこと。また、検査のタイミングはウイルスへの暴露から3~5日は待つ必要があるそうです。INSIDERの記事です。

米国の研究チームがゲノム編集技術「CRISPR-Cas9」を使い、腫瘍細胞を直接殺すだけでなく、免疫系を訓練してがんの再発を防ぐ作用を持つワクチンを開発したそうです。チームは、不活化しない「生きた」腫瘍細胞の遺伝子を改変。改変した腫瘍細胞は、腫瘍を殺す物質を放出し、さらに免疫系が長期的に腫瘍を攻撃するようになる因子を発現するといいます。この改変した腫瘍細胞を膠芽腫マウスに投与したところ、安全性と有効性が確認できたといいます。EurekAlert!の記事です。
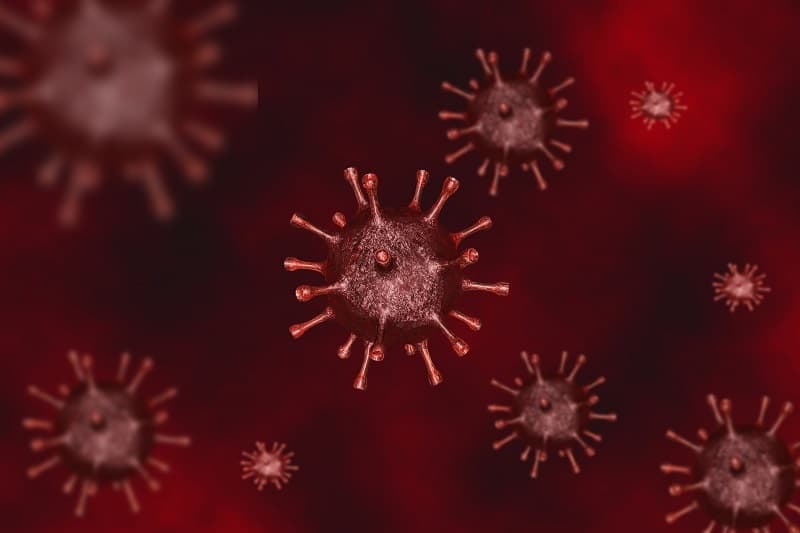
米国で、新型コロナウイルス新規感染者のうち、オミクロン株から派生した「XBB.1.5」感染者の占める割合が昨年12月の1カ月間で4%から41%に急増したそうです。専門家や世界保健機関(WHO)はこの急拡大に懸念を表明。少なくともすでに世界29カ国でXBB.1.5が確認されているといいます。免疫をすり抜ける能力や感染力が強い可能性が指摘されています。XBB.1.5に対するワクチンの効果は調査中で、重症化の割合が高いかどうかは現時点では不明とのこと。CNNの記事です。

中国で新型コロナウイルスの感染が拡大する中、世界保健機関(WHO)は中国当局が公表しているデータについて、実際の状況が反映されていないと考えているようです。中国は先月、呼吸器疾患で死亡した患者のみを「コロナによる死者」として計上するよう基準を変更。12月以降の死者はわずか22人としています。WHOはこの定義が狭すぎると指摘。死者数だけでなく、コロナによる入院者数や集中治療室(ICU)の患者数も過少報告されている可能性があるといいます。BBCの記事です。

USA Todayが2022年医学重大ニュースとして紹介した話題から、新薬に関するものをまとめました。米食品医薬品局(FDA)は10月、筋萎縮性側索硬化症(ALS)の新薬を承認しました。この薬を巡っては、有効性を疑問視する声や高額な薬価への落胆の声が上がりました。1型糖尿病の発症を遅らせる初の薬も11月に承認されました。8歳以上の未発症者が対象です。このほか、RSVなど各ウイルス感染症に対するワクチンの開発も続けられており、23年には朗報がもたらされるかもしれません。

2022年の医学の重大ニュースをUSA Todayがまとめています。サクッと1分!でもほとんどのニュースを紹介しています。再読して1年を振り返ってください。1月、米国の研究チームがブタの心臓を男性患者に移植したことを発表。男性は3月に死亡し、原因はブタのウイルスだった可能性があると判明しましたが、異種移植の可能性が示されました。4月には国際チームが、ヒトゲノムの配列の完全解読を発表。幅広い分野での医学的な進歩につながることが期待されています。<つづく>

米国の研究チームが、ウイルスと細菌のどちらに感染しているかを識別する血液検査を開発したそうです。チームは世界35カ国の感染症患者からの検体を使い、遺伝子発現データを分析。ウイルスと細菌では、感染した際に、免疫に関係する8遺伝子で発現の仕方が異なることが分かったといいます。開発した検査は30~45分でどちらの感染かを識別。感度、特異度ともに90%とのこと。深刻さを増す抗菌薬の乱用を防ぐ手立てになるかもしれません。Medical Xpressの記事です。

米国とトルコの研究チームが、術中迅速病理診断の精度を向上させる人工知能(AI)を開発したそうです。組織をホルマリンで固定する通常の病理診断は正確ですが、時間かかります。そのため手術中は、組織を急速冷凍して観察する術中迅速病理診断が行われます。ただこの方法は、組織が傷つくなどして不正確なことがあるといいます。チームが開発したAIは術中迅速病理診断で使う画像を通常の病理検査で使う高品質な画像に変換できるそうです。Medical Xpressの記事です。

内臓の痛みの管理にオピオイドを使う必要がなくなるかもしれません。米国と豪州の研究チームが、2021年のノーベル医学生理学賞の主題として知られ、触覚や温度の受容体である「Piezo(ピエゾ)2」が腸にも存在することを確認。さらに、腸の痛覚に関連する主なイオンチャネルがピエゾ2の仲間であることも判明したそうです。ピエゾ2を標的にすることで、過敏性腸症候群などの胃腸障害にともなう慢性疼痛を治療できる可能性があるといいます。EurekAlert!の記事です。

新型コロナウイルスの感染拡大が止まらない中国から、新たな変異株が出現する可能性があるとして、専門家が警戒しているようです。中国が公表している同国のワクチン接種率は高いのですが、使用している中国産ワクチンの効果がそもそも低い上に、高齢者の間ではブースター接種率が低いといいます。専門家は「集団免疫が確立していない環境」と指摘し、このような状況は新たな変異株発生の危険性を高めるとの懸念を示しています。AP通信の記事です。
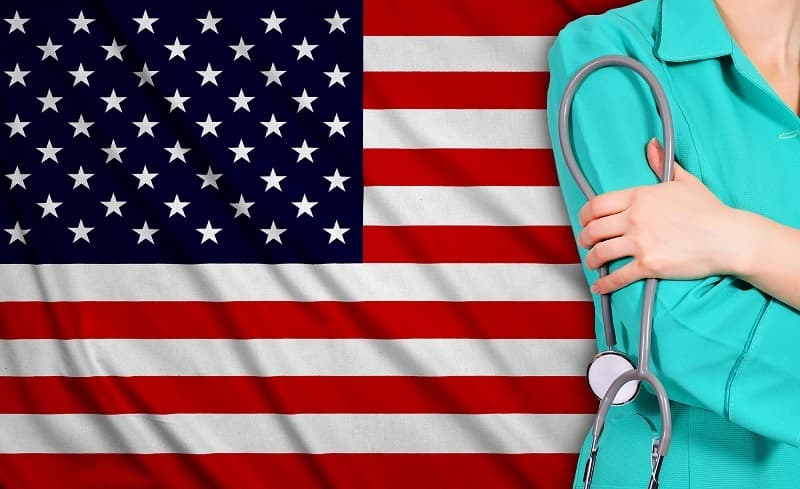
米カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)が、囚人に対して行った非倫理的な実験について謝罪したといいます。1960年代と70年代に、同大学医学部の皮膚科医2人が、刑務所の医療施設で少なくとも2600人の男性囚人に対して、殺虫剤や除草剤を皮膚に塗布したり、静脈に注射したりしたといいます。UCSFはこれを認め謝罪。被害の程度などを把握するために、さらに分析が必要としています。AP通信の記事です。
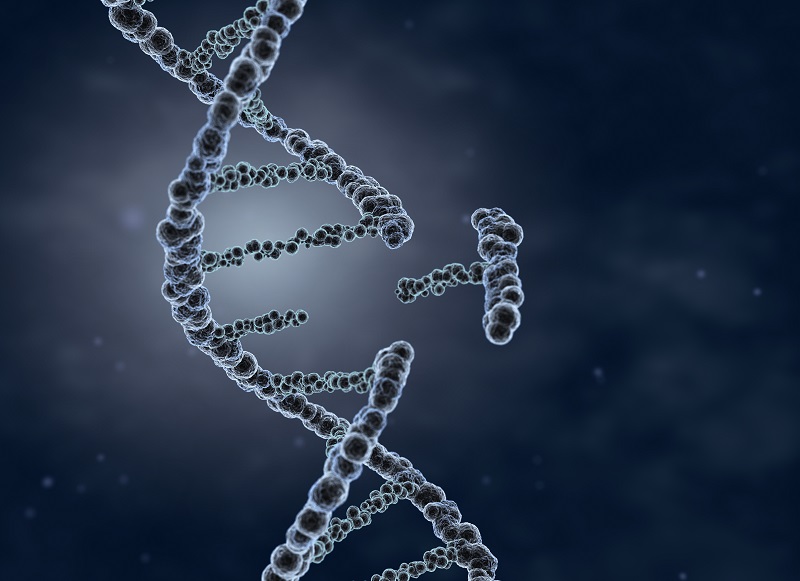
狙った遺伝子を改変するゲノム編集技術「CRISPR-Cas9」を用いて、一般的な遺伝性心疾患「拡張型心筋症(DCM)」を治療できるかもしれません。米国の研究チームが、DCMを引き起こす遺伝子変異を持つヒトの心筋細胞に、CRISPR-Cas9を使用。変異細胞は徐々にDCM固有の特徴を失っていったそうです。同様の遺伝子変異を持つ生後1週間のマウスにもCRISPR-Cas9を用いたところ、発症することなく平均寿命を全うしたといいます。Medical Xpressの記事です。

「新型コロナ後遺症」で頭がぼうっとする「ブレインフォグ」は、注意欠如・多動症(ADHD)や外傷性脳損傷(TBI)に使われる一般的な薬2種の併用で改善するかもしれません。米国の研究チームが、コロナ後遺症に悩む患者12人を対象にN-アセチルシステイン(NAC)600mgとグアンファシン1mgを就寝時に投与。1カ月後、グアンファシンは2mgに変更されたそうです。調査に最後まで参加した8人全員が、ブレインフォグの大幅な改善を報告したといいます。ScienceAlertの記事です。

重症高血圧の人はコーヒーを飲みすぎないほうがいいようです。日本の研究チームが、40~79歳の男女1万8600人を19年近く追跡調査。血圧が160/100mmHg以上の重症高血圧患者について、1日2杯以上コーヒーを飲む人は全く飲まない人に比べて、心血管疾患で死亡するリスクが2倍高くなることが分かったそうです。コーヒー1杯では、リスクが上昇することはなかったといいます。同じくカフェインを含む緑茶の摂取もリスクには関連しなかったとのこと。EurekAlert!の記事です。

鼻水の色で健康状態を把握してみませんか。透明な鼻水は正常ですが、量が急増した場合はアレルギーや風邪の引き始めのサインだそうです。白い鼻水が出る場合はたいてい、感染やアレルギーなどで鼻腔が刺激され、腫れている状態だといいます。黄色や緑色の鼻水は、感染と戦っていることを意味するそうです。通常、赤色や茶色の鼻水は血液が原因とのこと。黒色は喫煙が原因で、ヘビースモーカーや肺疾患の人に多く見られるといいます。ScienceAlertの記事です。

英国で世界初の幹細胞技術を使って、生まれつき心臓の大動脈で逆流が生じる疾患を持つ赤ちゃんの命が救われたようです。この赤ちゃんは生後4日で心臓手術を受けたものの状態は改善せず、心機能が著しく低下。そこで、同国の研究チームがドナーの胎盤から採取した幹細胞を赤ちゃんの心臓に直接注入したところ、損傷した心筋が再生したそうです。この赤ちゃんは現在2歳になり、薬や機械の力を借りることなく元気に生活しているといいます。BBCの記事です。

緑色の光には鎮痛効果があるそうです。中国の研究チームがマウスの実験で、鎮痛に視細胞(錐体細胞と桿体細胞)が深く関わっていることを発見。マウスに緑色の光を浴びせて調べたところ、色を感知する錐体細胞を不活性化したマウスは鎮痛効果が全く得られず、明暗を感知する桿体細胞を不活性化したマウスは部分的な鎮痛効果しか得られなかったそうです。緑色の光を浴びると、視細胞が鎮痛に関わる脳細胞を刺激することも分かったといいます。ScienceAlertの記事です。

中国で新型コロナの感染者が急増しています。中国では今冬、感染拡大の波が3回訪れると予測されており、中国保健当局のトップは「現在第1波が訪れている」との見解を示したそうです。第1波は1月半ばまで続く見込み。第2波は1月21日から始まる旧正月休暇が引き金になり、第3波は人々が仕事に戻る2月末~3月半ばに訪れるとみられています。米国の研究機関によると、中国では2023年に100万人以上がコロナで死亡する可能性があるといいます。BBCの記事です。

アイルランドの研究チームが、これまで免疫応答を鎮める役割があると考えられてきた「インターロイキン37(IL-37)」が、実際には全く逆の働きをすることを確認したそうです。自己免疫疾患の一種で皮膚が炎症を起こす「乾癬」の発症には、皮膚のインターロイキン受容体が重要な役割を果たします。チームは、そこにIL-37が結合することを発見。IL-37が適切な方法で活性化されると、強力な炎症促進作用を発揮することが明らかになったといいます。Medical Xpressの記事です。

米国で年間1.3億人が受診するという救命救急室(ER)で、18人に1人(約6%)に対して誤った診断が下されている可能性があるようです。米政府機関である医療品質研究調査機構(AHRQ)が、2000年1月~21年9月に発表された300近くの研究を分析した結果です。ERでは毎年、740万件の誤診が起きていると推計されるそうです。260万人の患者が回避できたはずの損害を被り、別の37万人は誤診によって回復不能な障害を負ったり、死亡したりしているといいます。CNNの記事です。

世界保健機関(WHO)が、新型コロナウイルス感染症による死者数に関する新たな調査結果を公表したようです。より正確な死者数を推定するため、WHOは「実際に生じた死者数」から「パンデミックが起きなかったと仮定した場合の予測死者数」を引いた「超過死亡数」を分析。2020年と21年の2年間で、コロナによって世界で1480万人の超過死亡が発生したとの結論が出たそうです。この数字は、以前報告されていた世界のコロナ死者数の約3倍に当たるとのこと。Medical Xpressの記事です。

新型コロナウイルスに感染すると、なぜ一部の人だけが嗅覚や味覚に異常を来すのでしょうか。米国の研究チームが、パンデミックの初期にコロナに感染し、回復した患者306人の血液サンプルを調査しました。コロナに対する抗体価が高かった人は、抗体価が平均以下だった人に比べて、嗅覚障害や味覚障害に苦しむ可能性が2倍高かったそうです。患者の免疫応答の強さが、嗅覚や味覚の異常に関連していることが示唆されたといいます。Medical Xpressの記事です。
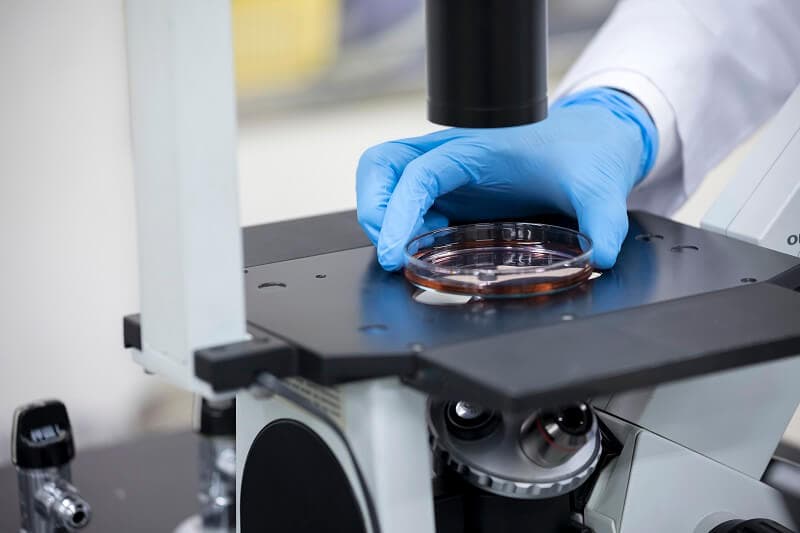
患者自身のT細胞を改変した「CAR-T細胞」で、中枢神経(脳、脊髄)のリンパ腫を安全に治療できるかもしれません。米国の研究チームが、中枢神経系にのみリンパ腫がある患者9人にCAR-T細胞療法薬「アキシカブタゲンシロルユーセル(Axi-Cel)」を投与。腫瘍が、患者の78%で縮小または消失し、67%で完全に消失したといいます。これらの効果は10カ月間続いたそうです。また、脳脊髄液中のCAR-T細胞によって、免疫系が活性化されることも示されたといいます。EurekAlert!の記事です。

低カロリーの食品や飲料に広く使われている人工甘味料「アスパルテーム」が、不安症を引き起こすかもしれません。米国の研究チームが、米食品医薬品局(FDA)が推奨する1日最大摂取量の15%に相当するアスパルテームを含む水を用意。マウスに飲ませたところ、情緒検査で不安を表す行動を多く取り、不安などに関わる脳の偏桃体に著しい変化が見つかったそうです。この影響は、アスパルテームを実際に摂取したマウスの孫の代まで引き継がれたとのこと。ScienceAlertの記事です。

米製薬大手のモデルナとメルクは12月13日、mRNA技術を使った個別化がんワクチンが後期第2相(2b)試験で有望な結果を示したと発表しました。対象はステージ3または4の悪性黒色腫(メラノーマ)で既に手術を受けた患者157人。モデルナ開発のワクチンとメルクのがん免疫治療薬キイトルーダを併用した人は、キイトルーダの単独使用者に比べて再発や死亡のリスクが44%低かったそう。重篤な有害事象の発生率は併用群で14.4%、単独使用群で10%だったとのこと。CNNの記事です。

英国の国民保健サービス(NHS)は2023年から、健康な新生児10万人に全ゲノムシーケンシング(WGS)を提供するプロジェクトを実施するそうです。治療可能な200近い遺伝子疾患のスクリーニングを行うといいます。このプロジェクトによって、これまで新生児の時点では見逃されてきた、疾患を持つ子どもを数百人特定できると推計されています。高齢になってから発症する一部のがんに関わる遺伝子変異も特定できますが、プロジェクトの対象ではないとのこと。BBCの記事です。
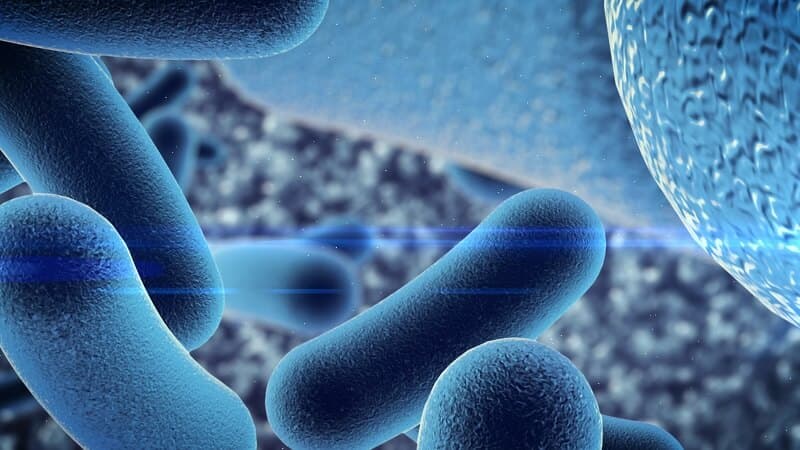
多くの種類の腸内細菌がパーキンソン病(PD)に関与しているそうです。米国の研究チームが、同国最南部に住むPD患者490人と対照群234人の便から直接採取した遺伝物質を調査。調べた257種類の腸内細菌のうち、84種類がPDに関連することが分かったそうです。PD患者では、このうち55種類が異常に増加し、29種類は激減するといいます。こうした広範囲にわたる腸内細菌叢の不均衡が、複数の経路を介してPDを誘発する可能性が示唆されたとのこと。Medical Xpressの記事です。

アトピー性皮膚炎の新薬候補「rocatinlimab」の治験で有望な結果が得られたようです。米国の研究チームが中等~重度の患アトピー性皮膚炎患者274人に対して、後期第2相(2b)試験を実施しました。この薬は、免疫細胞の表面に発現した分子「OX40」を阻害するモノクローナル抗体です。開始から16週時点で、アトピーの重症度を表す評価指標「EASIスコア」が48~61%低下したといいます。症状の改善は、投薬中止から少なくとも20週間後まで維持されたとのこと。EurekAlert!の記事です。

乳房に複数の腫瘍が見つかったからといって、必ずしも全乳房を切除(乳房全摘術)する必要はないようです。米国の研究チームが、片方の乳房に2~3個の腫瘍が見つかり、乳房全摘術の代わりに腫瘍部分の摘出術と放射線照射を受けた40~87歳の女性約200人を追跡調査。腫瘍は全て5cm未満だったそうです。その結果、手術から5年後の再発率はわずか3%で、腫瘍が一つしかない患者が腫瘍摘出術を受けた場合の割合と同等だったといいます。AP通信の記事です。
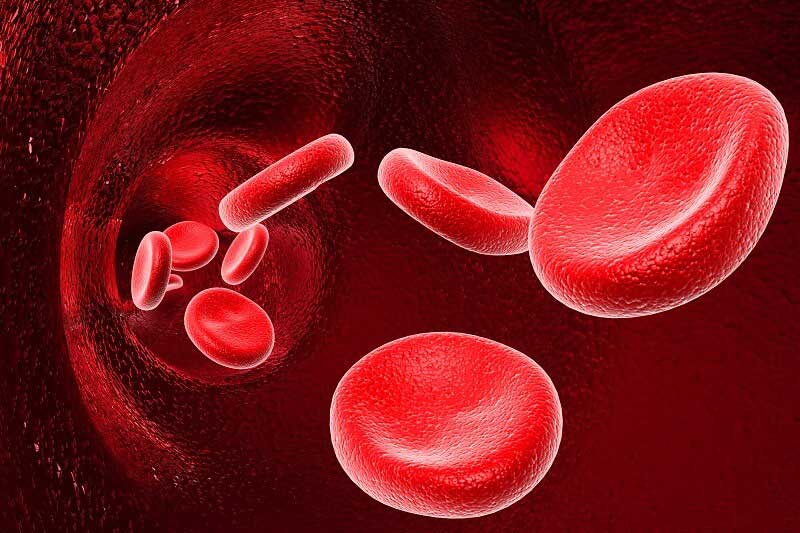
血液がんの一種であるT細胞急性リンパ性白血病の英国の少女(13)に、「塩基編集」を使った治療が初めて実施されたそうです。塩基編集は、DNAを切らずに特定の塩基を編集して遺伝子を改変する新技術です。英国のチームがこの技術を使って、ドナーから提供されたT細胞を、がん化したT細胞を見つけ出して破壊するよう改変。改変T細胞を少女に投与したところ、がんが抑えられたため骨髄移植を実施し、治療から半年後も寛解が保たれているとのこと。BBCの記事です。

子どもの頃から1型糖尿病を持つ人は心血管疾患を発症しやすいことが知られています。米国の研究チームが、これを抑制する方法を見つけたようです。チームは12~21歳の1型糖尿病患者の男女34人を調査。パーキンソン病や2型糖尿病の治療に使われる「ブロモクリプチン」を4週間投与された人はプラセボ群に比べて、収縮期血圧と拡張期血圧が共に低下することが分かったそうです。また、大動脈硬化の改善も確認されたといいます。ScienceDailyの記事です。

脳に膿がたまる「脳膿瘍」の予防策として、口腔ケアが重要かもしれません。英国の研究チームが、脳膿瘍で入院した患者87人の記録を調査。原因が特定できなかった患者が52人おり、それらの患者から採取した膿瘍には、原因が特定できた患者に比べて約3倍高い割合で口腔細菌が存在することが分かったそうです。また、咽頭炎や菌血症を引き起こすことがある口腔細菌「アンギノーサス群レンサ球菌」が見つかる割合も有意に高かったとのこと。Health Europaの記事です。
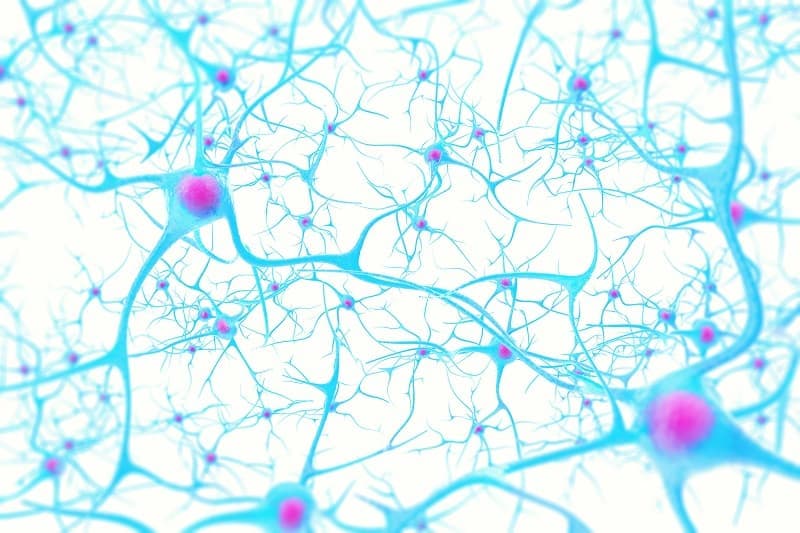
タンパク質のアミロイドβ(Aβ)沈着は、アルツハイマー病(AD)発症に間接的に関与しているのかもしれません。米国の研究チームがマウスの実験で、Aβ沈着周辺の神経細胞の軸索が細胞小器官のリソソームの凝集によって膨張したような状態になっており、それが認知機能の低下につながることを発見したそうです。さらに、タンパク質PLD3がリソソーム凝集に関連することも判明。Aβ沈着付近の膨張軸索で、特に高レベルのPLD3が発現することが分かったといいます。ScienceAlertの記事です。

中国で2017年に発見された「Alongshanウイルス(ALSV)」が、スイスで広まっているようです。 同国のチューリッヒ大学が、国内のマダニからALSVを初めて検出したそうです。ALSVはダニ媒介性脳炎ウイルス(TBEV)と同じフラビウイルス科で、発熱や頭痛といった感染した際の主な症状もTBEVに似ているとのこと。21年と22年にスイスの複数地域で採取された非常に多くのマダニからALSVの遺伝子配列が見つかっており、すでにTBEVよりまん延している可能性もあるといいます。Medical Xpressの記事です。

新型コロナの感染拡大防止のために行われたロックダウンによるストレスで、ティーンエイジャーの脳の加齢プロセスが通常より速いスピードで進んだ可能性があるようです。米国の研究チームが、パンデミック前に撮られた子ども81人のMRI脳画像とロックダウン解除後に撮られた子ども82人のMRI脳画像を分析しました。1年弱のロックダウンを経験したことで、3歳年を取ったのと同等の変化が脳で起きたことが確認されたといいます。ScienceAlertの記事です。

冬に風邪などが流行するのは、冷たい空気によって鼻で起こる免疫応答が半減することが一因のようです。米国の研究チームが、ヒト組織を使ってウイルスや細菌と戦うために鼻孔の細胞が無数に放出する細胞外小胞(EV)の働きを調査。EVはおとりの役割をし、表面にはたくさんの受容体があるといいます。鼻の中の温度が5度下がるだけで、放出されるEVが42%減り、受容体の数は最大70%減少。病原体を攻撃するEV内のマイクロRNAも半減したとのこと。CNNの記事です。

都市部に住むだけで、糖尿病リスクが上昇するかもしれません。中国の研究チームが、中国の成人約10万人のデータを分析。屋外の夜間人工照明が多い地域に住む人は、人工照明が最も少ない地域の人に比べて糖尿病発症リスクが28%高かったそうです。中国の糖尿病症例の900万件以上が、こういった光害に起因するものである可能性が指摘されています。これまでの研究で、薄暗い人工光の中で一晩寝るだけで血糖値が上昇することが分かっているとのこと。CNNの記事です。

慢性閉塞性肺疾患(COPD)患者は、自宅の室内空気汚染対策をしたほうがいいようです。米国の研究チームが、平均65歳のCOPD患者85人を6カ月間調査。高性能なHEPAフィルターとカーボンフィルターを搭載した家庭用空気清浄機を46人の患者に自宅で使ってもらったところ、全員が心血管の健康を示すいくつかの指標が改善したそうです。特に、心拍間の時間の変化を表す心拍変動(HRV)は25%増大したといいます。一般的に、健康な心臓はHRVが大きくなるとのこと。Medical Xpressの記事です。

大麻による鎮痛効果は、「思い込み」が影響している可能性があるそうです。スウェーデンの研究チームが、大麻を疼痛管理に使った20の研究を分析。大麻群とプラセボ群の間で痛みの軽減度合いに差は認められず、両群ともに大幅な痛みの改善が報告されたそうです。これは、効き目があると思い込むことでプラセボ(偽薬)でも効果が出る「プラセボ効果」によるもので、鎮痛作用は本物の大麻成分の効果の67%に相当する可能性があるとのこと。CNNの記事です。

英保健当局は、子どもの間でA群レンサ球菌(A群溶連菌)感染症が重症化する例が増えているとして、注意を呼びかけたようです。イングランドでは今年9月以降、この菌が肺や血液に侵入して重症化する侵襲性A群レンサ球菌感染症で子ども6人が死亡。ウェールズでも女児1人が死亡したそうです。高熱や発疹が出る猩紅(しょうこう)熱の患者数も高い水準で推移しているとのこと。A群レンサ球菌感染症は通常、春先から初夏にかけて流行します。BBCの記事です。

簡単かつ安価な尿検査で、アルツハイマー病を早期に発見できるようになるかもしれません。中国の研究チームが、さまざまな重症度のアルツハイマー病患者と正常な認知機能をもつ健康な人を合わせた計574人の尿や血液を分析。アルツハイマー病患者は健康な人に比べて、尿中のギ酸量が有意に多いことが分かったそうです。ギ酸量の増加は、自分だけが物忘れがあることに気づく段階「主観的認知機能低下(SCD)」の人にも見られたとのこと。Medical Xpressの記事です。

ヒト免疫不全ウイルス(HIV)ワクチンの開発が一歩前進したようです。米国とスウェーデンの研究チームが、18~50歳の健康な成人48人を対象に「eOD-GT8 60mer」と呼ばれるHIVワクチンの第1相試験を実施。このワクチンはウイルスのさまざまな遺伝子変異に応答することができる広域中和抗体の産生を誘導するといいます。8週間間隔で2回接種した36人のうち35人で、広域中和抗体が確認されたそうです。重篤な有害事象は認められず、安全性が示されたとのこと。CNNの記事です。

製薬大手エーザイなどが開発するアルツハイマー病治療薬「レカネマブ」に関する第3相試験の結果が公表されたそうです。治験は早期アルツハイマー病患者1795人に行われました。投与開始から18カ月時点で、レカネマブ群はプラセボ群に比べて認知症状の悪化が27%抑制されたそうです。一方でリスクについても示されています。脳出血はレカネマブ群の17.3%、プラセボ群の9%で発生。脳浮腫はレカネマブ群の12.6%、プラセボ群の1.7%で認められたとのこと。CNNの記事です。

健康な人の便から作られるフェリング・ファーマ社の「Rebyota」が、医薬品グレードの糞便移植製品として初めて米食品医薬品局(FDA)に承認されたようです。Rebyotaの対象は、クロストリジウム・ディフィシルによる腸炎を再発し、抗菌薬治療を受けたことがある成人患者です。直腸から行う投与は、1回で完了するといいます。臨床試験では、Rebyota 群の70%で8週間後に症状が解消したのに対し、プラセボ群で症状が解消したのは58%だったとのことです。AP通信の記事です。
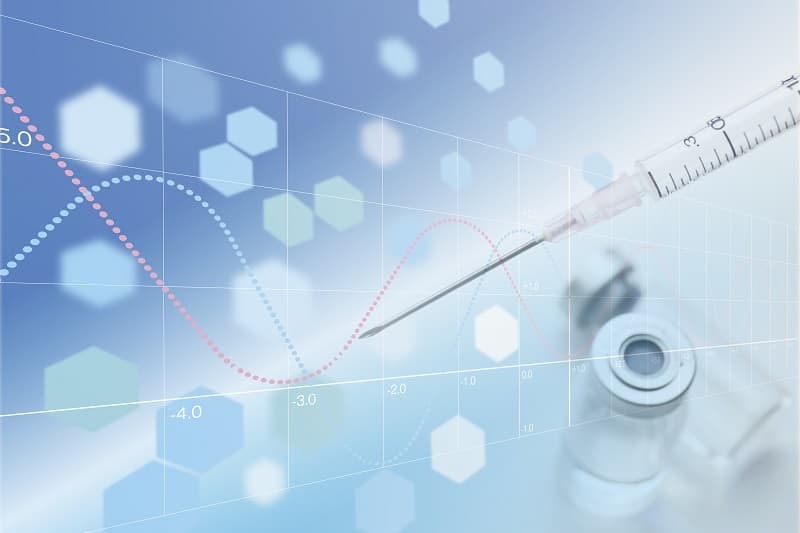
変形性膝関節症(膝OA)の治療によって、かえって状態が悪化する可能性があるようです。米国の研究チームが、X線またはMRIの画像を使って膝OAの進行を2年以上追跡したそうです。コルチコステロイド注射を受けた人は、ヒアルロン酸注射を受けた人や何も治療を受けなかった人に比べて膝軟骨の退行性変化が進んでいることが分かったといいます。ただし、画像上で悪くなっていても、患者が感じる痛みは悪化していない場合もあるとのことです。CNNの記事です。

製薬大手エーザイのアルツハイマー病治療薬「レカネマブ」の治験に参加した65歳の女性が死亡したそうです。脳卒中を発症した女性に血栓溶解薬tPAを投与したところ、脳内で大量出血が起きたといいます。この薬の治験参加者が死亡するのは2例目で、2人ともタンパク質アミロイドβ(Aβ)が血管壁に沈着することによって血管がもろくなる脳アミロイドアンギオパチー(CAA)があったそうです。CAA患者に対するAβ除去の危険性が指摘されています。Medical Xpressの記事です。

尿路感染症(UTI)の治療に抗菌薬が必要なくなるかもしれません。米国の研究チームが、尿路感染症を引き起こす尿路病原性大腸菌(UPEC)に対するワクチンを開発したそうです。舌下錠で、成分が粘膜を透過するよう設計されているといいます。UPECに対する免疫応答が尿路で誘導されることが確認されたとのこと。マウスやウサギの実験では、抗菌薬と同等の有効性が認められたうえ、繰り返し使用しても胃腸障害の副作用は起きなかったといいます。Medical Xpressの記事です。
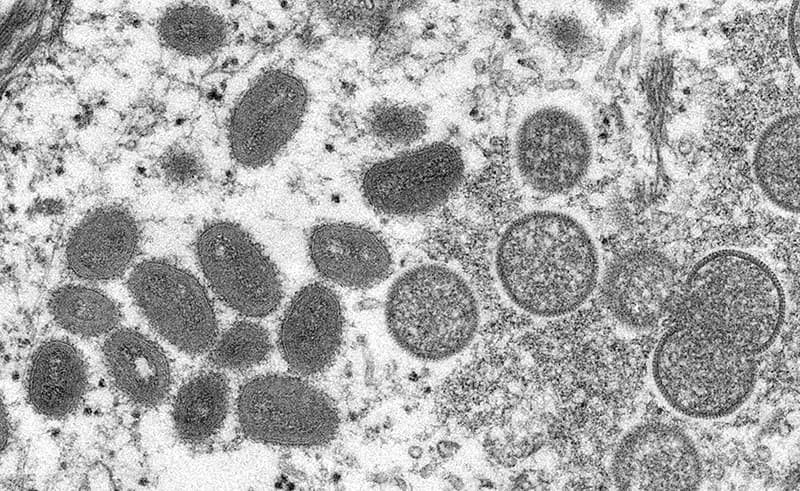
世界保健機関(WHO)は11月28日、今年に入って欧米を中心に感染が拡大した「サル痘(monkeypox)」の名称を「M痘(mpox)」に変更することを推奨すると発表しました。混乱を避けるため、1年間は新旧両方の名称を併用する予定だそうです。サル痘の名称の由来は、このウイルスが最初にサルから見つかったためです。しかし自然宿主はまだ明らかになっていません。サル痘の名称は差別や偏見につながる懸念があることから、WHOが新たな名称を公募していたといいます。CNNの記事です。

CSLベーリング社が開発した血友病Bのための遺伝子治療薬「Hemgenix」が、米食品医薬品局(FDA)に承認されたそうです。この薬は、ウイルスをベースにしたベクター(運び屋)が、血液凝固に関わるDNAを肝臓の標的細胞に送達するといいます。必要な価格は投与1回当たり350万ドル(約4億8600万円)で、医薬品としては世界最高額。しかし、血友病Bの既存薬も非常に高額なうえ定期的な治療が必要なのに対し、Hemgenixはたった1回の静脈点滴ですむそうです。ScienceAlertの記事です。

地域の緑を増やすことで、都市部の人の寿命を延ばすことができるようです。米農務省が率いる研究チームが、オレゴン州ポートランドで1990~2019年に実施された植樹活動のデータを使って分析。街路樹が多く植えられた地区の死亡率は低く、特に男性や65歳以上の高齢者における心血管疾患による死亡や、事故など以外の非偶発的な死亡が減少したといいます。また、樹木の高さが高い地区の人ほど、死亡率が低くなる傾向にあることも明らかになったとのこと。ScienceAlertの記事です。

ゼロコロナ政策が続く中国で11月23日、新型コロナの新規感染者が3万1527人確認されたそうです。2022年4月に記録された2万8000人を上回り、過去最多を更新。同国は数週間前に一部の規制を緩和していたそうです。しかしその後、北京や広州などの大都市を中心に感染が再拡大し、現在一部地域では飲食店や学校が閉鎖されるなど事実上のロックダウンになっているといいます。長引く厳しい規制が、経済や市民生活に大きな打撃を与えているとのこと。BBCの記事です。

流産や中絶後に再び妊娠するまで6カ月間空けることを推奨する世界保健機関(WHO)のガイドラインは、見直される必要があるようです。豪州の研究チームがノルウェーで、流産後の出産4万9058件と中絶後の出産2万3707件を調査。流産から6カ月未満での妊娠は、6~11カ月後の妊娠と比べて胎児発育不全リスクが低いことが明らかに。また、流産や中絶から3カ月未満での妊娠は、有害な妊娠転帰(結果)のリスク上昇に関連しないことも分かったそうです。Medical Xpressの記事です。

日本でも似たような事が起こるかもしれません。米国で、これまで一部地域の風土病とされていた土壌の真菌による感染症が全土で確認されるようになってきたそうです。同国の研究チームが、公的医療保険の請求データから、2007~16年の真菌性肺感染症の症例数を郡ごとに推計。3143郡のうちヒストプラズマ症は1806郡、ブラストミセス症は547郡、コクシジオイデス症は339郡でそれぞれ確認されており、これらの郡は全州に散らばっているといいます。Medical Xpressの記事です。

善玉コレステロールと呼ばれる「HDLコレステロール(HDL-C)」は、これまで考えられていたほど心臓病リスクの予測に有用ではないかもしれません。米国の研究チームが、45歳以上の成人数千人の10年にわたるデータを分析しました。HDL-Cレベルが低い白人は心臓発作リスクが高かったものの、黒人には同じことは当てはまらなったそうです。さらにどちらのグループでも、HDL-Cレベルが高いと心血管疾患リスクが低下するとの結果は見られなかったといいます。CNNの記事です。

1992年4月22日に凍結された胚を使って、米オレゴン州の女性が「双子」の赤ちゃんを出産したそうです。この凍結胚は、別の匿名夫婦(夫は当時50代前半、妻は当時34歳)によって提供されたもの。無事に生まれた凍結胚の保存期間としては今回の30年が世界最長だといいます。2022年2月28日に融解した凍結胚五つのうち三つが移植可能で、3月2日に三つ全てを女性に移植。そして二つの胚が妊娠につながり、10月31日に無事に2人を出産したとのこと。CNNの記事です。

患者本人の免疫細胞(樹状細胞)を取り出し、脳腫瘍を標的にするように設計して作ったワクチン「DCVax-L」が、臨床試験で有望な結果が出たようです。英国などの研究チームが、標準治療を受ける成人の膠芽腫患者331人に第3相試験を実施。初発膠芽腫患者では、追加の化学療法と共にDCVax-L投与を受けた群の平均生存期間は19.3カ月で、対照群の16.5カ月を上回ったそうです。再発患者における平均生存期間は、DCVax-L群が13.2カ月で、対照群は7.8カ月だったとのこと。Medical Xpressの記事です。

英国で2歳の男の子が、カビ(真菌)が原因の呼吸器疾患で死亡したそうです。カビによる健康被害を防ぐにはどうしたらよいのでしょうか。カビは湿った場所で繁殖し、その胞子はいたるところに存在しており、空気中に放出されているそうです。これを吸い込むと、喘息や感染症、アレルギーなどのリスクが高まるといいます。家庭でのカビの主な原因は結露だそうです。「換気をよくして湿度を下げる」「水滴をぬぐう」などの対策が有効とのこと。BBCの記事です。

米食品医薬品局(FDA)が11月17日に、1型糖尿病の発症を遅らせる初の薬「Teplizumab(テプリズマブ)」を承認しました。米Provention Bio社が開発した薬で、インスリンを産生する膵(すい)臓の膵β細胞に対し、免疫細胞が誤って攻撃を与えることを抑制するといいます。膵β細胞を攻撃する自己抗体と血糖値異常が検出された8歳以上の未発症者を対象に静脈内投与するそうです。スクリーニング検査によって発症前段階の患者を早期に特定することが課題とのこと。CNNの記事です。

新型コロナのワクチンや薬が猛スピードで開発された裏側で、米食品医薬品局(FDA)の監督が不十分だったと豪州のジャーナリストが指摘しています。153あったファイザーのワクチン治験施設のうち、FDAが承認前に査察したのは9施設のみ。モデルナ製ワクチンやコロナ治療薬レムデシビルの査察にも同様の少なさだったそうです。データ捏造などの問題が指摘された施設もあったのですが、その施設は調査さえ行われていないとの告発もあるといいます。Medical Xpressの記事です。
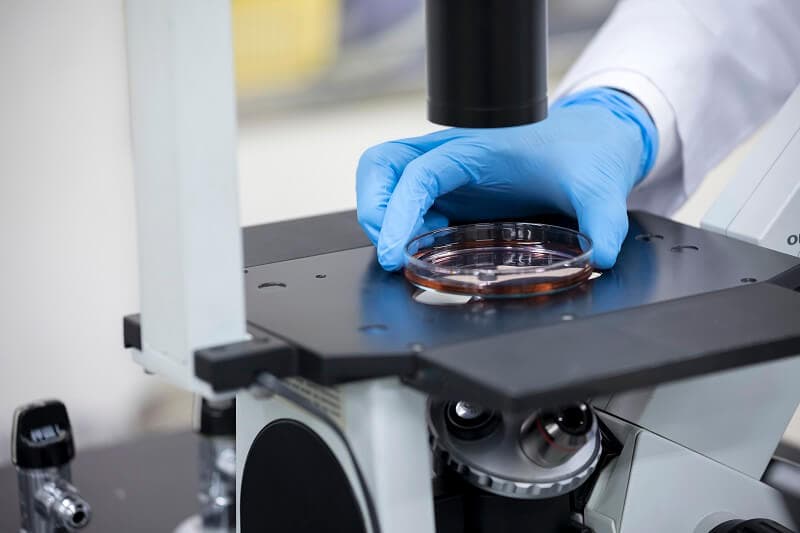
ハンセン病を引き起こす「らい菌」の隠れた能力が、肝臓病の新しい治療法の開発につながるかもしれません。英国の研究チームは、アルマジロがらい菌に感染することに着目し、感染したアルマジロの肝臓を調査しました。すると、らい菌は細胞の健康な成長を促し、肝臓の大きさを2倍にする能力があることが分かったそうです。細胞のDNAを分析したところ、らい菌の作用で肝細胞が発達の初期段階に若返っていることが確認されたといいます。BBCの記事です。

スイス製薬大手ロシュ社が、開発中のアルツハイマー病(AD)治療薬「ガンテネルマブ」について、早期AD患者における記憶障害の悪化などを抑制する効果は認められなかったとする治験(第3相)の結果を公表したそうです。ガンテネルマブは、AD患者の脳内に蓄積することで知られるタンパク質のアミロイドβ(Aβ)を除去するよう設計されています。しかし今回の治験結果によると、Aβの減少レベルは想定より低いものだったといいます。CNNの記事です。

米食品医薬品局(FDA)が承認したアルツハイマー病治療薬「アデュカヌマブ」について、承認をいったん保留にするべきとの声が一部の研究者から上がっているようです。研究者たちは、疾患の原因がタンパク質アミロイドβ(Aβ)の沈着であるとする仮説に疑問を呈し、さらに承認時の証拠としてアミロイドPET検査の結果が使われたことを問題視。PET検査の結果は、Aβの減少ではなく、薬による脳損傷の増加を示している可能性があると指摘しています。Medical Xpressの記事です。

大麻はたばこより安全だという考えは間違っているかもしれません。カナダの研究チームが、「大麻とたばこの両方を吸う人56人」と「25年以上たばこを吸うヘビースモーカー33人」の胸部CT画像を比較。大麻とたばこを吸う人の75%、たばこのみを吸う人の67%にそれぞれ肺気腫が見られたそうです。一見すると小さいように思うこの8%の差には大きな意味があり、大麻の使用がたばこのみの喫煙以上に肺にダメージを与える可能性が指摘されています。CNNの記事です。

産道を通る時に母親の膣内の細菌を受け継ぐことは、赤ちゃんにとってメリットがあるそうです。英スコットランドとオランダの研究チームが、正期産で生まれた健康な赤ちゃん120人の腸内細菌叢を1歳まで追跡調査。経膣分娩児はビフィズス菌や無害な大腸菌を多くもつことが分かったそうです。こうした腸内細菌の影響で、経膣分娩児の肺炎球菌や髄膜炎菌のワクチンによる抗体レベルは、帝王切開児に比べて倍増する可能性が示唆されたとのこと。BBCの記事です。

新型コロナワクチン接種後に発熱のある人は、高い抗体価が得られるのでしょうか。岡山大学が、モデルナ製mRNAワクチンの3回目接種を受けた49人を調査。接種後に発熱した人は、そうでない人に比べてワクチン接種1週間後の抗体価が大幅に高かったそうです。しかし接種1カ月後になると、発熱の有無と高い抗体価の間に関連性は認められなかったといいます。発熱は、20~49歳の若年層やアレルギーの病歴がある人の間で多く見られたとのこと。EurekAlert!の記事です。

前十字靱帯(ACL)損傷が自然に治癒することはないとする「常識」が覆るかもしれません。豪州の研究チームが、ACLを断裂した18~35歳のプロスポーツ選手ではない一般の人のデータを分析。再建術を受けずにリハビリテーションのみを行った人の53%で、損傷から2年後にACLが治癒していることがMRI画像から明らかになったそうです。この人々は再建術を受けた人々に比べて、損傷から2年後の膝の痛みや機能、QOLに関する満足度も高かったとのこと。Medical Xpressの記事です。

症状が現れる前から、脳スキャンでアルツハイマー病(AD)を見つけることができるようです。スウェーデンの研究チームが、認知機能に問題のない1325人を調査。PET検査で、ADに関係すると考えられているタンパク質のアミロイドβ(Aβ)とタウが脳に見つかった人は、その後数年間でADを発症するリスクが20~40倍高かったそうです。チームは、Aβとタウの両方が脳に存在する場合、認知機能の低下がなくてもADと診断するべきだと考えているといいます。Medical Xpressの記事です。

小児悪性脳腫瘍「膠芽腫」の既存の治療法は、子どもの脳の発達を妨げるという後遺症が問題になっています。それを回避する方法が見つかったかもしれません。カナダの研究チームが、最も悪性度の高いMYC遺伝子増幅型の髄芽腫のモデルマウスで調査。「DHODH」と呼ばれる酵素の産生を阻害すると、腫瘍の増殖が止まり、健康な脳細胞や神経細胞は悪影響を受けないことが分かったといいます。臨床試験に到達するまでには数年かかる見込みとのこと。Medical Xpressの記事です。

人間の健康状態を反映するとされる「血中代謝物」の組成が、人によって違うのはなぜでしょうか。米国の研究チームが、1500人以上から検出された930の血中代謝物を分析しました。検出された代謝物の60%以上が、腸内細菌叢または遺伝的要因と関連していることが明らかになったそうです。そしてこのうち69%は、腸内細菌叢が単独で影響を及ぼしていることが分かったといいます。一方、遺伝的要因が単独で代謝物に関与する割合は15%だったとのこと。Medical Xpressの記事です。
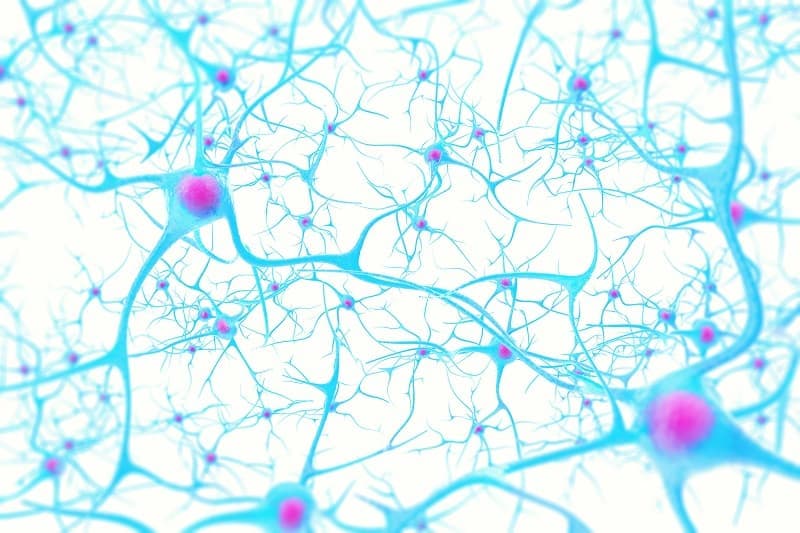
歩行能力の改善に関わる未知のニューロンが特定されたようです。スイスの研究チームが、脊髄損傷による重度または完全麻痺がある患者9人を調査。週4~5回のペースで5カ月間にわたり脊髄硬膜外電気刺激とリハビリテーションを併用した治療を行ったところ、全員が歩行器具を使って歩けるようになったそうです。モデルマウスでこの理由を探ったところ、「SCVsx2::Hoxa10」と呼ばれるニューロンが歩行能力の改善に関与していることが分かったといいます。ScienceAlertの記事です。

米国の研究チームが、脳波を分析して文字に変換する神経機能代替装置を脳卒中で話せなくなった男性の脳に移植し、文字をつづらせることに成功したそうです。各アルファベットに対応する決められた単語があり、例えばアルファベットの「A」をつづりたい時は、男性が「Alpha」と言おうとすると装置が読み取るといいます。これを繰り返すことで単語や文章としてスペリングしたものがモニターに表示でき、1150以上の単語を読み取れたとのことです。ScienceAlertの記事です。

ポンペ病は、必要な酵素が生まれつき不足することで筋力が低下し、ほとんどが生後1年以内で死に至るまれな遺伝性疾患です。米国とカナダの研究チームが女の子の患者に、胎児の段階から酵素を補充する治療を世界で初めて実施したそうです。酵素は、妊娠24週ごろから隔週で6回にわたり、母親の腹部に針を刺してへその緒に送られたといいます。生まれた後も治療は続いていますが、女の子は1歳4カ月現在も順調に成長しているとのこと。AP通信の記事です。

献血協力者に頼らず、輸血用血液を確保できるようになるかもしれません。英国の研究チームが、献血された血液から赤血球になることができる幹細胞を採取し、大量の赤血球を作製したそうです。2人に対して世界初の臨床試験が始まっており、少なくとも4カ月の間隔をあけて5~10mlの「実験室の血液」と「通常の血液」を2回輸血するといいます。実験室で作られた赤血球のほうが、体内で長持ちすることが期待されているそうです。BBCに紹介されています。

目の病気である脈絡膜新生血管の治療薬「ベルテポルフィン」が新型コロナ治療に有効かもしれません。器官の大きさを制御する細胞内の「Hippoシグナル伝達経路」が活性化すると、ウイルスの複製が抑えられることを米国の研究チームが確認。この経路はタンパク質「YAP」の働きで不活性化するため、ヒト培養細胞をYAP阻害薬のベルテポルフィンで処理してコロナに感染させたところ、ウイルスが検出可能レベルを下回ることが分かったといいます。Medical Xpressの記事です。

副作用などが原因で多発性硬化症(MS)の再発予防薬「フィンゴリモド(商品名・イムセラ、ジレニア)」の服用を中止する場合、次にどの薬を選択すればいいのでしょうか。豪州の研究チームが、世界最大のMSデータベースで薬の有効性を調査。再発寛解型MS患者がフィンゴリモドから「オクレリズマブ」か「ナタリズマブ(商品名・タイサブリ)」に切り替えると、再発回数が抑制され、身体の機能障害も安定または改善することが分かったといいます。Medical Xpressの記事です。

新型コロナのmRNAワクチン接種後に起こる心筋炎・心膜炎リスクについての研究結果です。カナダの研究チームが、ブリティッシュコロンビア州でモデルナ製かファイザー製のワクチンを2回接種した18歳以上の人を調査。2回目接種から21日以内に心筋炎や心膜炎を発症した割合は、接種100万回当たりモデルナ製が35.6例、ファイザー製は12.6例だったといいます。モデルナ製のリスクが約3倍高いことが分かりましたが、発症は非常にまれなケースとのこと。EurekAlert!の記事です。

カナダの研究チームが9年間にわたる400万人以上のデータを分析し、インフルエンザワクチンを打つと脳卒中のリスクが低くなることを明らかにしたそうです。ワクチンを受けた人は、その後6カ月間の脳卒中発症リスクが有意に低下することが判明。これは、脳卒中リスクが高い人だけに限らず、全ての成人に当てはまったといいます。これまでの研究で、インフルワクチン接種は心臓病の人の心臓発作リスクを下げることが知られています。Medical Xpressに紹介されています。

国際研究チームが、mRNA技術を使った新たなインフルエンザワクチンを開発したそうです。このワクチンは、ウイルス株間でほとんど変化が起きないとされる▽マトリックスタンパク質2(M2)▽ヘマグルチニン(HA)の茎部分▽核タンパク質▽ノイラミニダーゼ(NA)――の四つのタンパク質を標的としたものだといいます。マウスを使った感染の実験では、このワクチンがさまざまなインフル株に幅広く対応できる可能性が示されたとのことです。Medical Xpressの記事です。
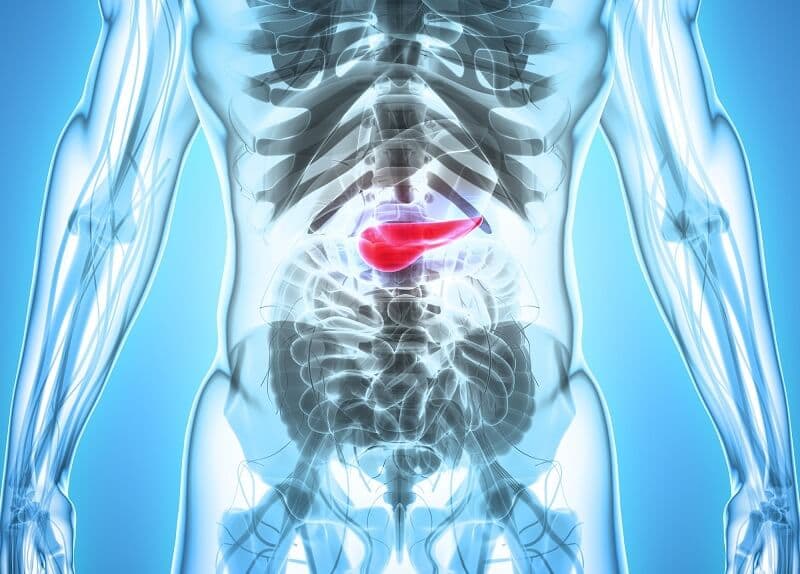
「体格指数(BMI)」と「糖化ヘモグロビン(HbA1c)値」を定期的に測定することで、膵(すい)臓がんを早期に発見できる可能性があるようです。英国の研究チームが、膵臓がん患者8777人と対照群3万4979人のデータを分析しました。膵臓がん患者には、正式な診断を受ける2年前から急激な体重減少が見られたそうです。HbA1c値の上昇は、診断の3年前から認められたといいます。糖尿病をもつ人の体重減少や、原因不明の高血糖症には特に注意が必要とのことです。EurekAlert!の記事です。

マジックマッシュルームの幻覚成分「サイロシビン」が、うつ病の治療薬として使われるようになるかもしれません。英国の研究チームが、欧米10カ国から重度のうつ病患者233人を集め臨床試験を実施。サイロシビン25mgを含んだ錠剤を1錠投与し、心理療法を行うと、3週間後に3分の1の患者が寛解状態になったそうです。12週間経過した時点でも、5分の1の人に有意な改善が見られたといいます。ただし、副作用が認められた患者もいたとのこと。BBCの記事です。

パルスオキシメーターで測定した有色人種の血中の酸素濃度(酸素飽和濃度)が不正確であるとの研究結果が相次ぎ、米当局が調査に乗り出したそうです。肌の色が濃いと実際よりも高い値が出てしまうといいます。米食品医薬品局(FDA)は、この機器への懸念について話し合う専門家会議を招集。患者や医師への提言、精度を担保する方法を協議したとのことです。まずは医療従事者が、測定値が不正確である可能性を知ることが重要だといいます。AP通信の記事です。

ファイザー社が開発中のRSウイルス(RSV)ワクチンの臨床試験で、有望な結果が得られたそうです。同社は年末までに米食品医薬品局(FDA)に承認申請を提出する予定。このワクチンは妊婦向けで、母親の体内で作られた抗体が胎児に渡るよう設計されているそうです。生後間もない乳児をRSVから保護する効果があるといいます。臨床試験では、生後3カ月までのRSVによる重症化を82%、医療機関への受診を50%、それぞれ防ぐ効果が認められたとのこと。CNNの記事です。

安全で即効性のある抗うつ薬ができるかもしれません。中国の研究チームが、うつ症状を改善するためには、セロトニントランスポーター(SERT)と神経型一酸化窒素合成酵素(nNOS)の相互作用の遮断が有効であると考え、その作用を持つ新薬「ZZL-7」を開発。マウスに注入したところ、内側前頭前皮質のセロトニンレベルが上昇するという、うつ症状が軽減する現象が起こったそうです。薬の効果は2~3時間以内に現れ、副作用も少ない可能性があるとのこと。Medical Xpressの記事です。
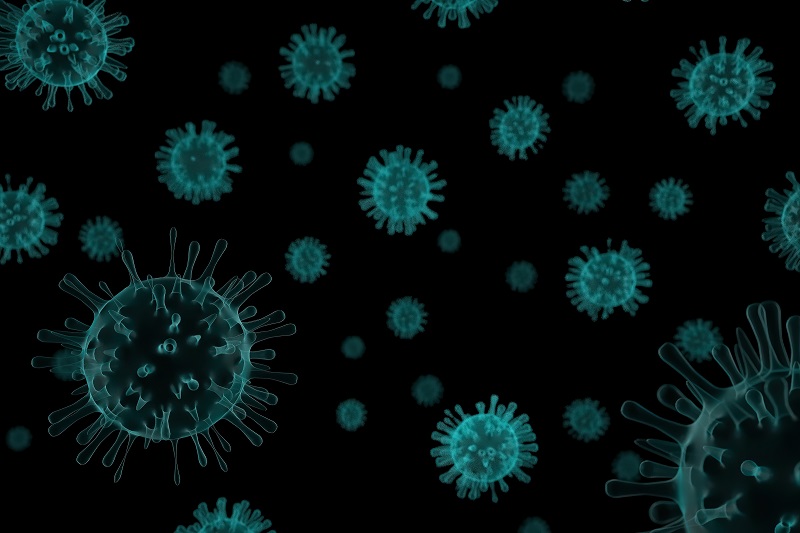
実験室での研究中に、全く異なる二つのウイルスが融合した「ハイブリッドウイルス」が見つかったそうです。英国の研究チームが、A型インフルエンザウイルス(IAV)とRSウイルス(RSV)をヒト肺細胞に同時に感染させる研究を行っていたところ、RSVの表面タンパク質を得たIAVを発見。このハイブリッドウイルスはIAVに対する免疫系を回避し、広範囲のヒト細胞に感染できるそうです。ウイルスが肺深部に到達し、重症化につながる可能性もあるといいます。ScienceAlertの記事です。

認知症リスクを抑えたければ、鼻をほじるなどといった鼻の内側を傷つける行為は極力控えた方がいいかもしれません。豪州の研究チームがマウスの調査で、細菌の肺炎クラミジアが、鼻の嗅神経から脳に直接侵入することを実証したそうです。この細菌の侵入に対し脳細胞は、タンパク質「アミロイドβ」を蓄積させるというアルツハイマー病の特徴となる反応を起こすといいます。チームは、ヒトにも同様の経路が存在するかを確認するとのこと。Medical Xpressの記事です。

製薬大手エーザイが開発中のアルツハイマー病治療薬「レカネマブ」が原因で、治験参加者が死亡した可能性があると医療メディアStatが報じたそうです。同薬については、今年9月に第3相試験で有望な初期結果が得られていました。しかし、被験者の1人が脳出血で死亡していたことが分かったそうです。治験責任医師は、出血がレカネマブに関連するものだと結論付けたといいます。一方エーザイは、他の要因が影響した可能性にも言及したとのこと。CNNの記事です。

ドイツ政府が、娯楽目的の大麻の所持や販売などを条件付きで解禁する計画案を公表したそうです。それによると、最大30gの大麻の購入や所持を合法化。認可を受けた店が、成人に娯楽目的の大麻を販売することも認められるそうです。私的な大麻草栽培も、3株まで許可されるといいます。今回の合法化は、闇市場対策にもなるようです。同国は近く欧州連合(EU)に対し、この計画案がEU法に沿ったものであるか承認を求めるとのことです。AP通信の記事です。

中国上海市が、口から吸うタイプの新型コロナワクチンの接種を開始しました。このワクチンは、同国のカンシノ・バイオロジクスが開発したといいます。既存のコロナワクチンを接種済みの人を対象に、無料で提供されるそうです。短いノズルから霧状のワクチンをゆっくりと吸入し、5秒間息を止めるだけで完了するとのことです。接種した人からは「ミルクティーを飲んでいるようだ」「甘い味がした」との感想が出ていたといいます。AP通信の記事です。

自閉症の人の社会性を高める方法が見つかったかもしれません。イスラエルの研究チームが、気圧を高めた部屋で100%濃度の酸素を吸入させる「高気圧酸素治療」に着目。自閉症の遺伝子変異を持つマウスに対して、1時間の高気圧酸素治療を計40回実施したところ、自閉症に関連する脳内の神経炎症が軽減したそうです。さらに、マウスの社会的関心が高まり、初対面の相手と一緒に過ごすことを好むようになったといいます。Medical Xpressの記事です。

患者の話し声をアプリで分析するだけで、パーキンソン病や新型コロナの重症化リスクを早期に特定できるかもしれません。豪州の研究チームが、人工知能(AI)を使って患者の音声記録を分析することで、この2疾患の特徴を識別するアプリを開発したとのこと。アプリはわずか10秒で音声を評価し、治療の要否を助言してくれるそうです。人間には聞き分けづらい声の震えやこわばり、話すスピードの遅さなどを分析し、疾患を検出するといいます。Medgadgetの記事です。

禁煙は35歳までに成功させたほうがいいようです。米国の研究チームが、1997~2018年にアンケートに答えた25~84歳の成人55万人のデータを分析。このうち 7.5万人が2019年末までに死亡したそうです。そして、35歳までに禁煙をした人の死亡率は、喫煙経験のない人の死亡率とほとんど変わらないことが示されたといいます。全死因死亡率は喫煙経験のない人と比べ、35~44歳で禁煙した人が21%高く、45~54歳で禁煙した人は47%高かったとのこと。ScienceAlertの記事です。

長い間別のものとして考えられてきた複数の精神疾患が、症状だけでなく遺伝的にも共通点があることが分かったようです。米国の研究チームが、「双極性障害」「統合失調症」、それら両方の症状が混在する「統合失調感情障害」に共通する強力な危険因子として「AKAP11遺伝子」を特定したといいます。これら三つの疾患について、研究チームは「互いに境界があいまいなスペクトラム(連続体)の一部と考えられる」としています。AP通信の記事です。

概日リズム(体内時計)における活動期に食事を取ると太りにくいといいます。米国の研究チームがその理由を明らかにしたそうです。チームは、高脂質食を概日リズムの非活動期(昼間)に与えたマウスの方が、活動期(夜間)に与えたマウスよりも体重が増加することを確認。そして、活動期に脂肪細胞内でアミノ酸のクレアチンが増加し、熱産生レベルが高まることを発見しました。これが体重増加の抑制に関係していると考えられるそうです。Medical Xpressの記事です。

米国の研究チームが、がんを直接攻撃するのではない、新たなCAR-T細胞療法を開発したそうです。チームは、免疫細胞のマクロファージが、他の免疫細胞ががんを攻撃するのを妨害してしまうことに着目。マクロファージを破壊するCAR-T細胞を作製し、卵巣や肺、膵臓にがんのあるマウスを治療したところ、がんが縮小したそうです。マクロファージの減少やCAR-T細胞が放出するサイトカインによって、マウスのT細胞ががんを攻撃できるようになったとのこと。ScienceDailyの記事です。

子どもの認知機能を高めたければ、テレビを見せるよりもゲームをさせる方がいいかもしれません。米国の研究チームが、9~10歳の2000人のデータを分析。1日3時間以上ゲームをする子どもは全くゲームをしない子どもに比べて、短期記憶や衝動抑制のテストの成績が良かったそうです。また脳の画像検査から、ゲームをする子どもの脳は、判断・行動に関わるワーキングメモリと注意力に関連する領域が活性化していることも分かったといいます。CNNの記事です。

腸内細菌叢のバランスが乱れている患者は、臓器移植後の死亡率が高いそうです。オランダの研究チームが、腎臓や肝臓の移植手術を受けた患者1087人から採取した1370の糞便サンプルを分析。腸内細菌叢のバランスが乱れている人の移植後3年生存率が77%だったのに対し、多様性に富んだ腸内細菌叢を持つ人の3年生存率は96%だったそうです。また、移植後に使う免疫抑制薬が腸内細菌叢の乱れの主要因であることも明らかになったといいます。Medical Xpressの記事です。
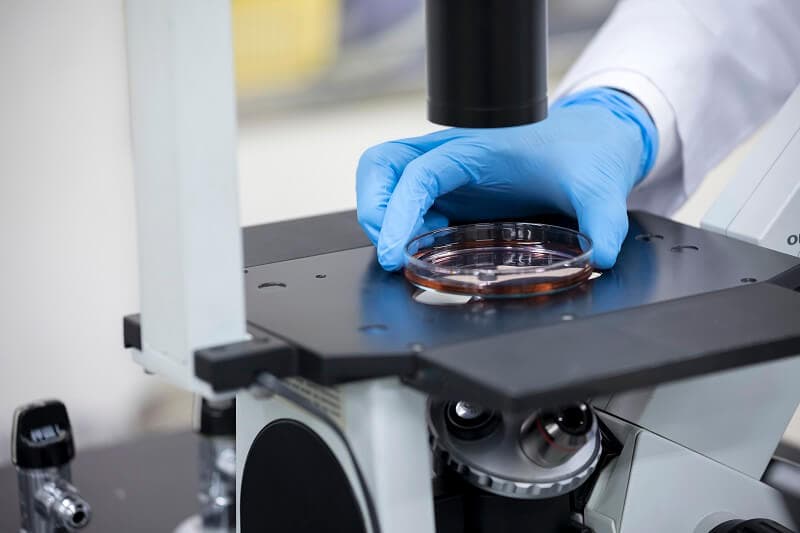
膵臓がんの画期的な治療法が見つかったかもしれません。米国の研究チームが、体内でジェル状になるエラスチン類似ポリペプチド(ELP)で放射性ヨウ素131を包み込んだ、薬効成分を徐々に放出するデポ剤を作製したとのこと。マウスの数種類の膵臓がんに注入したところ、既存の化学療法薬を併用したマウスの80%で、腫瘍が完全に消滅したそうです。ELPデポ剤は他の健康な組織を放射線で破壊せず、最終的には体内に吸収されるといいます。Medical Xpressの記事です。
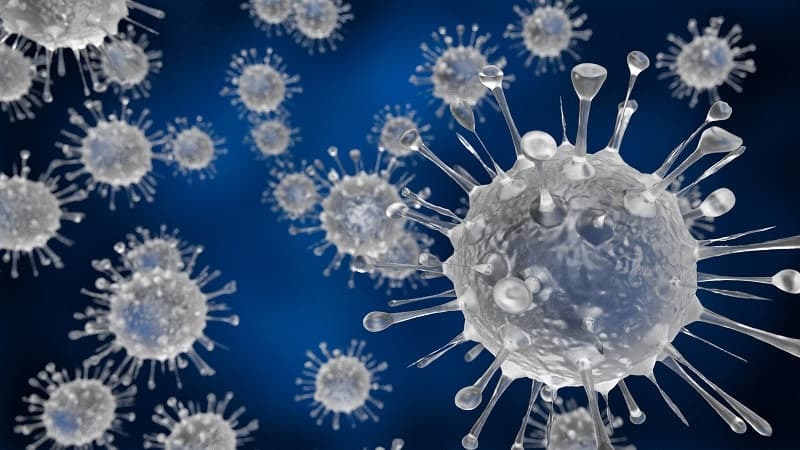
新型コロナウイルスのオミクロン株について、新たな系統が世界で相次いで見つかっているようです。米国では、「BQ.1」「BQ.1.1」「BF.7」「BA.4.6」「BA.2.75」「BA.2.75.2」を確認。シンガポールなどでは「XBB」が急拡大しているそうです。現在、これらの新系統ウイルスは米国の新規感染者の1/3を占め、欧州でも感染者が増加しているといいます。新系統には既存の抗体医薬が効きにくいとの研究結果も出ており、今冬の流行再拡大が懸念されているとのこと。CNNの記事です。

患者一人一人に合わせたがんワクチンが一般的になる日はそう遠くないかもしれません。米ファイザー社と共同で新型コロナウイルスmRNAワクチンを開発した独ビオンテック創業者夫妻は、開発中のがんワクチンが2030年までに広く普及する可能性があると予測。mRNA技術を用いたこのワクチンの狙いは、がんを認識して攻撃するよう体を訓練することだそうです。がんの手術直後に、患者個人に合ったワクチンを提供するのが同社の最終目標だといいます。ScienceAlertの記事です。

14世紀に世界の人口の30~50%の命を奪った「黒死病(腺ペスト)」の大流行が、欧州人のゲノム進化に影響を与えたようです。米国の研究チームが、ロンドンとデンマークで黒死病大流行による死者のDNAを抽出。これを大流行の前と後に死亡した人のDNAと共に分析したところ、大流行を生き延びるのに関与したとみられる四つの遺伝子変異が特定されたそうです。この変異を持つ人は感染症に強い一方、自己免疫疾患リスクが高くなるといいます。nprの記事です。

50代以降も健康に過ごしたければ、夜の睡眠時間を5時間より多く確保する必要があるそうです。英仏の研究チームが、英国の公務員8000人を対象に平日の平均睡眠時間を調査したといいます。さらに20年以上にわたり、糖尿病やがん、心臓病などの慢性疾患に関する追跡調査を行ったそうです。50歳時点で睡眠時間が5時間以下だった人は、7時間睡眠の人に比べて慢性疾患を複数抱えるリスクが30%高くなることが分かったとのことです。BBCに紹介されています。

厳しすぎるしつけが、子どもの遺伝子の働きを変えてしまう可能性があるようです。ベルギーの研究チームが、平均14歳の男女44人を調査。21人が望ましいしつけを受け、23人は厳しすぎるしつけを受けていたそうです。厳しいしつけを受けた子どもは、多くがうつ病の初期兆候を示したうえ、遺伝子の読み取り方を変化させる「DNAメチル化」が多く認められたとのこと。メチル化の増加は、うつ病リスクに関連することで知られているといいます。EurekAlert!の記事です。

縮毛矯正剤を使うと子宮がんリスクが上昇する可能性があるそうです。米国立衛生研究所(NIH)が、35~74歳の女性3万3497人を11年にわたり追跡調査。過去1年間で4回以上縮毛矯正剤を使ったと報告した人のうち、4.05%が70歳までに子宮がんを発症したそうです。一方、縮毛矯正剤を使ったことがないと報告した人の発症割合は1.64%だったといいます。染色剤やブリーチ剤、パーマ剤については子宮がんリスクとの関連性は見られなかったとのことです。EurekAlert!の記事です。

うつ病と認知症発症リスクの関連性についての研究成果です。中国の研究チームが、英国の中高年35万人のデータを分析。このうちうつ病患者は4万6280人で、研究期間中に認知症を発症したのは725人だったそうです。うつ病は認知症リスクを51%増加させることが分かり、うつ病の治療を受けた人は、受けていない人に比べて認知症発症リスクが30%低かったといいます。ただし慢性的な重症患者が治療を受けても、リスクは低下しなかったとのこと。EurekAlert!の記事です。

米疾病対策センター(CDC)によると、新型コロナのmRNAワクチンの追加接種とインフルエンザワクチンは同時に接種しても安全性に問題はないそうです。同時接種をした場合は、倦怠感や頭痛、筋肉痛などの副反応が現れるリスクが8~11%高くなりますが、軽度ですぐに治まるとのことです。なお、臨床試験の結果から、オミクロン株対応のワクチンを追加接種した場合の副反応の発生頻度と症状は、従来のコロナワクチンとほぼ同じとみていいようです。INSIDERの記事です。

大腸内視鏡検査の有効性が過大評価されているかもしれません。ノルウェーの研究チームが、大腸内視鏡検査を受けたことがない55~64歳の男女8万4000人を対象に欧州で調査を実施したそうです。その結果、大腸内視鏡検査を受けるよう案内された人(このうち42%が実際に受検)は、そうでない人に比べて10年後の大腸がん発症リスクが18%低かったといいます。大腸がんによる死亡リスクについては、2群の間で有意差はみられなかったとのことです。CNNの記事です。

新型コロナワクチンは、3回接種すると大きな効果が得られるようです。エストニアの研究チームが、ファイザー製コロナワクチンの3回目接種を受けた健康な成人111人を調査。3回目接種から6カ月後の抗体レベルは、2回目接種から6カ月後の抗体レベルに比べて、平均で6倍高かったそうです。また、3回目接種を受けた人の97%が、コロナ重症化を防ぐのに重要な役割を果たすとされるメモリーT細胞を持つことも明らかになったといいます。Medical Xpressの記事です。

2型糖尿病患者に使われる血糖降下薬「メトホルミン」で、心房細動を治療できるかもしれません。米国の研究チームが、米食品医薬品局(FDA)に承認されている2800の薬剤について、コンピューター計算と、薬剤が標的にする遺伝子の分析などを行ったといいます。その結果、メトホルミンが心房細動に関連する30の遺伝子を標的とし、そのうち八つの遺伝子の発現に直接的な影響を及ぼすことが判明。最も有望な治療薬候補と考えられるそうです。ScienceDailyの記事です。

2型糖尿病の治療に使われる経口血糖降下薬「チアゾリジンジオン系薬剤(TZD)」を認知症予防に転用できる可能性があるようです。米国の研究チームが、60歳以上の2型糖尿病患者55万9106人を平均8年にわたり追跡調査。TZDを1年以上単独で服用した人は、別の血糖降下薬「メトホルミン」を単独で服用した人に比べて認知症発症リスクが22%低かったそうです。具体的には、アルツハイマー病リスクが11%、血管性認知症リスクが57%抑制されたといいます。Medical Xpressの記事です。

米国の研究チームが、ヒトの皮膚組織から作った「ミニ脳(脳オルガノイド)」を生後2~3日のラットの脳に移植することに成功したそうです。脳オルガノイドはラットの神経回路に結合し、行動に影響を及ぼしたとのことです。また、自閉症スペクトラム障害や心臓障害が起こるまれな遺伝性疾患「ティモシー症候群」患者由来の脳オルガノイドを移植したラットから、患者の神経細胞がとても小さく、異常があることが確認されたといいます。AP通信の記事です。

将来身長がどれくらい高くなるかをこれまで以上に正確に予測できるようになるかもしれません。豪州などの研究チームが、540万人の遺伝子データを対象にゲノムワイド関連解析を実施。身長に影響を及ぼす1万2000の遺伝子変異を特定したそうです。この1万2000の変異で、個人間における身長の違いの40%を説明できるといいます。今回の調査は、過去最大規模であることに加え、非欧州系の人が100万人以上含まれている点がポイントとのこと。EurekAlert!の記事です。

鳥のさえずりが聞こえてきたら、立ち止まって耳を傾けるといいかもしれません。ドイツの研究チームが、参加者295人を対象にオンラインで調査を実施したそうです。参加者は鳥のさえずりか交通騒音を6分間聴き、その前後にメンタルヘルスを評価するアンケートに答えたといいます。鳥のさえずりを聴くと、参加者の不安や被害妄想が軽減することが示唆されたそうです。一方、交通騒音は抑うつ状態を悪化させることも分かったといいます。Medical Xpressの記事です。

医師が自己紹介で気軽に使う言葉であっても、患者には意味が伝わらないことがあるようです。米国の研究チームが、医師の専門分野や肩書を表す用語についての知識を調査。調査した14の専門分野のうち六つについて、半数以上の人が意味を正確に定義できなかったそうです。「腎臓専門医(Nephrologist)」の正解率は20%で最も低かったといいます。医学部生、研修医、指導医などの五つの肩書について、正確に序列を付けられたのはわずか12%だったとのこと。ScienceDailyの記事です。

西アフリカのガンビアで子ども66人が急性腎障害で死亡したそうです。世界保健機関(WHO)は、この件に関連する可能性があるとして、インドの製薬会社メイデン・ファーマシューティカルズの咳止めシロップ4製品に対する国際的な警報を出しました。調査の結果、このシロップが許容量を超えるジエチレングリコールとエチレングリコールに汚染されていることが判明。これらの物質は人体に有害で、腎障害を引き起こすことがあるといいます。BBCの記事です。

ブラジルの研究チームによると、ベジタリアンはそうでない人に比べてうつ症状経験のリスクが2倍高いそうです。ただ、その原因は食事の栄養素ではないとのこと。では一体何が原因なのでしょうか。まず、うつ病の人は罪悪感を持ちやすく、食肉処理の需要を生み出していることに苦しんでベジタリアンになることが考えられるそうです。また、ベジタリアン食への固執が社会生活に悪影響を及ぼすことなども要因として指摘されています。ScienceAlertの記事です。

妊婦も使用できるとされている解熱鎮痛剤のアセトアミノフェンが、生まれた子どもの発達に有害な影響を及ぼす可能性があるようです。米国の研究チームが、初産婦2400人と生まれた子どもを妊娠後期から産後3年まで追跡調査。睡眠に問題があると考えられる子どもは、母親が妊娠中にアセトアミノフェンを使用した群が22.7%で、非使用群は18.9%だったそうです。注意力に問題を抱える子どもは、妊娠中の同薬使用群が32.9%、非使用群は28.0%だったといいます。ScienceDailyの記事です。

タンパク質アミロイドβ(Aβ)の塊(プラーク)の蓄積は、アルツハイマー病(AD)の直接的な原因ではないかもしれません。米国などの研究チームが、ADリスクが高いとされる遺伝子変異を持つ患者を調査。Aβには可溶性のものがあり、そのレベルが高い人は、脳内にすでにプラークが蓄積していたとしても3年以内の認知症発症リスクが低かったそうです。脳内の可溶性Aβが270PG/ML以上あれば、プラーク量に関係なく正常な認知機能が維持されるといいます。EurekAlert!の記事です。

ふとした瞬間に「前にもこんなことがあった」と感じる「デジャヴ(既視感)」を経験したことはありますか。米国の研究チームが、バーチャルリアリティー(VR)を使ってデジャヴが起こるメカニズムを調査したそうです。参加者は、VRでさまざまな空間レイアウトの環境を体験したといいます。似たようなレイアウトの景色を見たことがあるにもかかわらず、はっきりと思い出せない場合に、デジャヴが起こりやすいことが分かったとのことです。ScienceAlertの記事です。

動物との触れ合いがもたらす効果が改めて示されたようです。スイスの研究チームが、赤外線神経画像技術を用いて健康な男女19人の社会的・感情的相互作用を調節する前頭前皮質を調査。本物の犬と触れ合うと、同じような重さや温度のライオンのぬいぐるみに触れた時と比べて前頭前皮質の活動が増加したといいます。その効果は犬をなでている時に最も高まり、犬と触れ合うたびにこの脳領域の活動が高まることも分かったといいます。Medical Xpressの記事です。

新型コロナウイルスは脳内で、栄養補給などさまざまな形で神経細胞をサポートする細胞「アストロサイト」を標的にしていることが分かったそうです。ブラジルの研究チームが、新型コロナで死亡した患者26人の脳組織を分析。ウイルスがアストロサイトに感染し、複製していた証拠を見つけました。別の調査では、コロナ感染によってアストロサイトのエネルギー代謝に変化が起こり、神経細胞の生存率が低下することが示唆されたといいます。Medical Xpressの記事です。

老人になっても中年並みの記憶力を持つ「スーパーエイジャー」の脳の秘密が明らかになったようです。米国の研究チームが、80歳以上のスーパーエイジャー6人▽平均的な認知機能の高齢者7人▽スーパーエイジャーより20~30歳若い人6人▽初期アルツハイマー病(AD)患者5人――の死後脳を調査。スーパーエイジャー群は、他の3群に比べて記憶に関わる嗅内皮質の神経細胞が大きく、ADに関連するとされるタンパク質タウの変化がなかったといいます。ScienceDailyの記事です。

「愛情ホルモン」のオキシトシンに思いも寄らない効力があるかもしれません。米国の研究チームが、臓器再生能力が高いゼブラフィッシュの心臓を凍結によって損傷させて調査。オキシトシンが、心筋細胞を再生する心外膜前駆細胞(EpiPC)の生成を促すことが分かったそうです。ヒトiPS細胞を使った実験でも、オキシトシンによる同様の効果が確認されたといいます。オキシトシンを心臓発作後の治療に利用する可能性に期待が寄せられています。EurekAlert!の記事です。
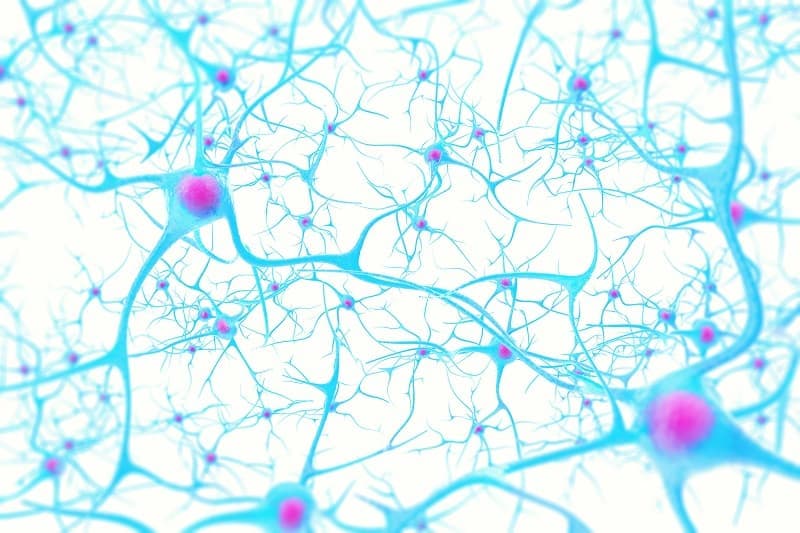
特定の職業環境が、筋萎縮性側索硬化症(ALS)の発症リスクを高める可能性があるようです。米国の研究チームがALS患者381人と対照群272人について、仕事中に暴露する物質のデータを分析。ALS患者は、診断前の金属、粒子状物質、揮発性有機化合物、燃焼汚染物質への暴露レベルが高かったそうです。特に金属への暴露がALSリスクに最も強く関連していたとのこと。製造や溶接などの生産分野で働く人のALSリスクが高いことも分かったといいます。Medical Xpressの記事です。

腫瘍遺伝子変異量(TMB)が高い人は、がん免疫治療薬が効きやすいといいますが、アジア人や黒人は誤って高めに測定される可能性があるようです。多くの医療機関で、腫瘍の遺伝子を分析して、遺伝子データベースと比較する方法が取られているといいます。米国の研究チームが、そこで起こるTMBの過大評価を調整する公式を作り、がん患者2800人を調査。アフリカ系の43.6%、アジア系の37%、ヨーロッパ系の21%がそれぞれ高TMB患者として誤分類されていたそうです。NewScientistの記事です。

米バイオベンチャーのアミリックス・ファーマシューティカルズが開発する筋萎縮性側索硬化症(ALS)の経口治療薬「Relyvrio(レリブリオ)」が、米食品医薬品局(FDA)に承認されたそうです。同社によると、この薬はALSの進行を遅らせるのに有効。ALSの治療法は限られているため、患者らは早期の承認を求めていたようです。しかし今回の承認はわずか137人を対象とした第2相試験のデータに基づくものであることから、薬の有効性を疑問視する声もあるといいます。CNNの記事です。

体外受精した胚をいったん全て凍結する「全胚凍結法」について、注意が必要な研究結果が報告されました。ノルウェーなどの研究チームが、北欧3カ国の妊婦450万人分のデータを分析。妊娠中に高血圧症を発症した人は、自然妊娠が4.3%だったの対し、凍結胚移植が7.4%、凍結しない新鮮胚移植が5.9%だったそうです。ただし、胚の凍結そのものではなく、凍結胚移植に伴う投薬方法が高血圧リスク上昇に影響している可能性も指摘されています。CNNの記事です。

座りっぱなしの生活でも、運動や減量よりも効果的に全身の代謝を上げる方法が見つかったそうです。米国の研究チームが、座った状態でつま先を床に付けたまま、適切な方法でかかとを上げ下げすると、ふくらはぎにある「ヒラメ筋」が数時間にわたりできるだけ多くのエネルギーを消費するようになることを発見。その際、筋肉運動のエネルギー源となるグリコーゲンの代わりに、血糖や脂肪が消費されることが分かったといいます。Medical Xpressの記事です。

カナダの研究チームが、アルツハイマー病(AD)は脳疾患ではなく、脳内の「自己免疫疾患」であるとする新理論を提唱しているそうです。ADの原因については、タンパク質のアミロイドβ(Aβ)が凝集し、脳細胞を殺してしまうためだという説が有力です。しかしチームは、Aβが脳内で細菌などと戦う作用をしている可能性を指摘。Aβが細菌などと脳細胞を見分けることができず、誤って脳細胞を攻撃してしまうことがあると主張しています。Medical Xpressの記事です。
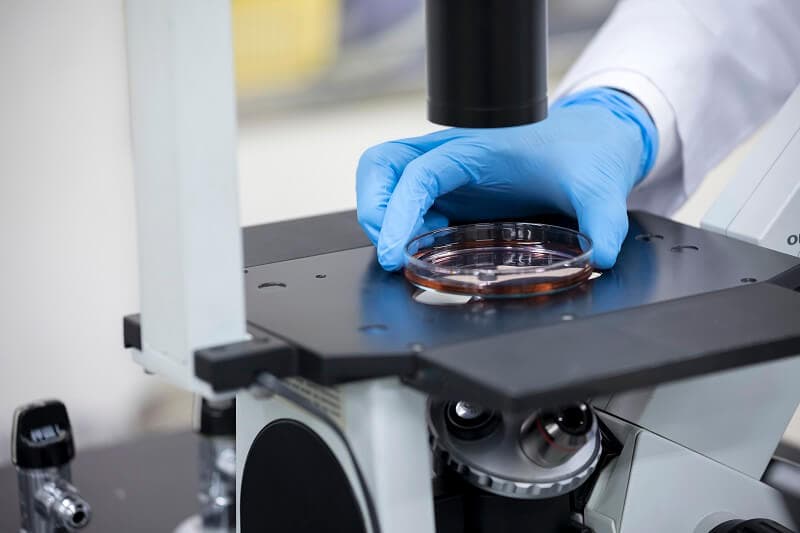
血液がんの治療に使われる「CAR-T細胞療法」が、自己免疫疾患「全身性エリテマトーデス(SLE)」の治療で有望な結果を示したようです。ドイツの研究チームがSLE患者5人に対し、患者自身の免疫細胞を取り出して遺伝子改変し、それを再び本人に戻すCAR-T細胞療法を実施。1回の治療で、SLEを引き起こす「自己抗体を産生するB細胞」が一掃されたそうです。重大な副作用も起きなかったとのこと。その後、5人の患者は5~17カ月間寛解しているといいます。ScienceAlertの記事です。

製薬大手エーザイのアルツハイマー病(AD)新治療薬「レカネマブ」の治験で、認知機能低下を抑制する効果が示されたそうです。治験では、早期AD患者1800人にレカネマブかプラセボを2週間に1回投与して比較。投与18カ月後、レカネマブ群の方が認知症重症度のスコアの悪化が27%抑制されたといいます。ただ、両群間のスコア差が小さいこと、脳浮腫や出血などの副作用の発生率がレカネマブ群の方が高かったことなどに懸念の声も上がっているとのこと。NewScientistの記事です。

ホルモンのエストロゲンの産生を低下させる経口薬「リンザゴリクス」で、子宮筋腫が縮小するようです。米エール大学が、月経時大量出血のある子宮筋腫患者を対象に二つの大規模治験を実施。リンザゴリクス群は、用量や副作用緩和のための治療を受けているかどうかでさらに4群に分けられました。患者の出血は、4群全てで有意に減少したといいます。患者個人に合った用量を選択できる可能性が示されたとのこと。同大学のウェブサイトで紹介されています。

中年期によく悪夢を見るようなら、認知症に気を付けた方がいいかもしれません。英国の研究チームが、米国の35~64歳の男女600人と79歳以上の高齢者2600人のデータを分析しました。調査開始時に認知症だった参加者はいなかったそうです。35~64歳の群で週1回の頻度で悪夢を見ると答えた人は、その後10年で認知機能が低下するリスクが4倍高くなることが分かったといいます。この傾向は、女性より男性のほうが強かったとのことです。Health Europaの記事です。

寝室の壁にルーターのような装置を取り付けるだけで、パーキンソン病の早期診断や進行の追跡ができるようです。米マサチューセッツ工科大学(MIT)が、睡眠中の呼吸パターンからパーキンソン病を診断するAIシステムを開発。この装置は、従来の方法よりはるかに早い段階でパーキンソン病を診断することができるといいます。診断だけでなくパーキンソン病の進行を追跡することもできるため、治療薬を開発する際の臨床試験でも役に立ちそうです。Medgadgetの記事です。

呼吸に使う横隔膜などの筋肉(呼吸筋)のトレーニングが、高血圧の新たな治療法になるかもしれません。米国の研究チームが、運動選手や歌手が呼吸筋を強化するのに使う器具「パワーブリーズ(POWERbreathe)」に着目。口にくわえて息を吸ったり吐いたりする、片手で持つことができる小さな器具です。これを使って1日数分間のトレーニングを6週間続けた人は、収縮期血圧が持続的に、服薬や有酸素運動と同程度の平均9 mmHg低下したそうです。Medical Xpressに紹介されています。

英国の研究チームが、がんを殺す遺伝子組換え単純ヘルペスウイルス「RP2」の第1相試験を実施しました。RP2は、がん細胞内で増殖して腫瘍を破壊したり、免疫系のブレーキを解除したり、免疫系の働きを促進する物質を産生したりするそうです。チームは標準治療の効果が得られなかった数種類の進行がん患者を調査。RP2を単独で使った患者9人のうち3人の腫瘍が縮小し、がん免疫治療薬を併用した患者30人のうち7人に効果が見られたとのこと。Medical Xpressの記事です。
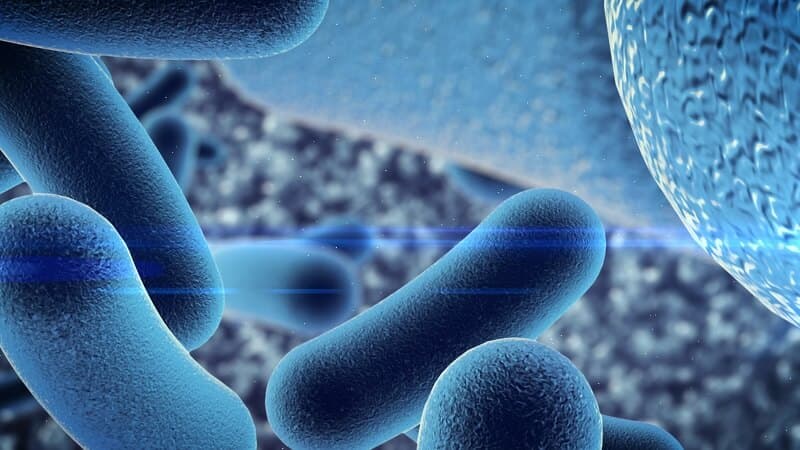
米国などの研究チームが、多発性硬化症(MS)と腸内細菌叢の関連を改めて明らかにしたようです。チームは、世界4カ国のMS患者576人の腸内細菌叢組成を新手法で解析。居住地による環境的な影響を排除するため、患者と一緒に暮らす家族の中で遺伝的には無関係な人を対照群として調査対象に加えたそうです。解析の結果、MSに関連する細菌を新たに数十種類特定。腸内細菌叢の操作や食事療法などの新たな治療につながる可能性があるとのこと。Medical Xpressの記事です。

新たな2型糖尿病治療薬「チルゼパチド」は、有効性だけでなく即効性も優れているそうです。英国の研究チームが、3種類の2型糖尿病治療薬を使ってヘモグロビン値が目標値に下がるまでにかかる期間を調査しました。チルゼパチド群は、「セマグルチド」群に比べて4週間、「インスリンデグルデク(iDeg)」群に比べて12週間早く目標値に到達したそうです。チルゼパチド群は、セマグルチド群に比べて体重の減りも早かったといいます。Health Europaの記事です。

新型コロナにかかった高齢者は、1年以内にアルツハイマー病(AD)と診断されるリスクが高くなるようです。米国の研究チームが、65歳以上の600万人のデータを分析。過去1年以内にコロナの診断を受けた人のうち、新たにADと診断された人の割合は1000人に7人だったそうです。一方で、コロナにかかっていない人のこの割合は1000人に5人だったといいます。コロナ感染で起こる炎症が、既に脳内で起きていた変化を悪化させる可能性があるとのこと。CNNの記事です。

英医学誌「ランセット」のCOVID-19委員会が、新型コロナの死者数について「重大な悲劇かつ世界的大失敗」とする報告書をまとめました。同委員会は、科学に基づく政策や国際協力、国際金融の観点から今回のパンデミックを分析。各国が公衆衛生上の基本対策を軽視し、主要国がパンデミックの制御に協力できなかったことなどを指摘しています。今回の経験を基に、国際的な協力や協調行動に加え、緊急事態への備えが必要であると強調しています。CNNの記事です。

お茶をたくさん飲むと糖尿病リスクを抑制できるかもしれません。中国の研究チームが、お茶の消費量に着目し、8カ国の成人100万人以上を対象とした19の研究を分析。紅茶、緑茶、ウーロン茶のいずれかを1日4杯以上飲む人は、平均10年間で2型糖尿病を発症するリスクが17%低かったといいます。2型糖尿病のない成人5199人の調査では、お茶を飲むか飲まないかでは発症リスクに違いは見られなかったとのこと。飲む量がカギになるようです。CNNの記事です。

安価な関節リウマチ治療薬「リツキシマブ」で、筋力低下などが起こる自己免疫疾患「重症筋無力症」の悪化が防げるようです。スウェーデンの研究チームが、過去1年以内に筋無力症と診断された患者47人を調査。患者は標準治療に加えて、リツキシマブ500mgかプラセボを1回投与されたそうです。4カ月後、リツキシマブ群の71%で疾患がうまくコントロールされていたのに対し、プラセボ群で同様の効果が認められたのはわずか29%だったといいます。Health Europaの記事です。

フランスのマクロン大統領は9月13日、スイスで認められている「自殺ほう助」の合法化の可能性について議論を始めると発表しました。スイスでは、患者が致死量の薬物を自己投与するのを手助けすることが認められています。フランスは2016年、医師が末期患者に死亡時まで鎮静剤を投与することを合法化。世論調査によると、「安楽死」については国民の大多数が賛成しているといいます。政府は来年の法改正を目指し、協議を進める予定とのこと。AP通信の記事です。

乳房インプラントの健康リスクを知っておく必要があるようです。米食品医薬品局(FDA)が、公表済みの文献を調査。乳房インプラントの周りの被膜内にできた扁平上皮がんの症例を20件弱、リンパ腫の症例を30件弱見つけたそうです。FDAに寄せられる医療機器の有害事象報告でも、10件の扁平上皮がんと12件のリンパ腫が確認されたといいます。今回確認されたリンパ腫は、以前から知られている乳房インプラント関連のリンパ腫とは別の種類とのこと。CNNの記事です。

淋病や髄膜炎を引き起こすナイセリア属の細菌が、肺疾患悪化の原因になることが分かったそうです。シンガポールなどの研究チームが、アジア人高齢者で気管支拡張症が悪化しやすい理由を解明するため、アジアと欧州の患者のデータを分析。気管支拡張症が悪化したアジア人には、ナイセリア属の細菌が多く存在していたそうです。特に口中の常在菌であるナイセリア・サブフラバが多い患者は、重症化や反復感染のリスクが高かったといいます。Medical Xpressの記事です。

夜勤勤務のある人は心の健康を損ないやすいといいます。米国の研究チームが、夜間の食事を控えることに、その予防効果があることを確認したそうです。チームは参加者19人に2週間、夜勤に似た生活をさせて調査しました。日中と夜間に食事をした人は、ベースラインと比較してうつ気分が26%増加し、不安な気持ちは16%増加。日中のみ食事をした人に同様の変化は確認されなかったそうです。概日リズムが乱れた人ほど、症状が現れたとのこと。ScienceAlertの記事です。

付着したウイルスを自然に死滅させる医療用ガウンが流通するかもしれません。英国の研究チームが、二酸化チタンのナノ粒子を含むプラスチックシートに着目。この素材は蛍光灯が発するわずかな紫外線に反応し、活性酸素種と呼ばれる分子を放出するといいます。この分子がウイルスのタンパク質と反応し、ウイルスが死滅するそうです。この素材に新型コロナなどのウイルス粒子を100万個付着させたところ、2時間後には全滅したとのこと。BBCの記事です。

予後不良の肺感染症を引き起こす薬剤耐性菌「マイコバクテリウム・アブセッサス(M.アブセッサス)」は、ハチミツの「マヌカハニー」で死滅させられるそうです。英国の研究チームが、嚢胞性線維症または気管支拡張症の患者16人から採取した組織を使って調査し、その効果が明らかになったとのこと。ヒト肺モデルの実験では、抗菌薬アミカシンと共にマヌカハニーを吸入した場合、アミカシンの量を8分の1に減らせることが分かったといいます。ScienceAlertの記事です。

肺機能検査機器のスパイロメーターを使った呼吸機能検査で慢性閉塞性肺疾患(COPD)の基準を満たしていない患者には、気管支拡張剤を処方するべきではないようです。米国の研究チームが、喫煙歴と呼吸器症状があるものの、呼吸機能検査でCOPDの診断基準を満たしていない患者535人を12週間にわたり調査。患者は1日2回、気管支拡張剤かプラセボを吸入しました。調査終了後、投薬群とプラセボ群の間で症状の改善に有意差は見られなかったとのこと。ScienceDailyの記事です。

既存の下痢止め薬で、コミュニケーションや社会的交流の困難さなどといった自閉スペクトラム症(ASD)の中核症状を改善できるかもしれません。ノルウェーの研究チームが、コンピューターモデルを使って既存薬の中からASDの症状改善に有効な薬を調査。下痢止め薬「ロペラミド」が最も有望な候補薬であることが分かったそうです。この薬には、社会的行動にも影響を及ぼすとされる「μオピオイド受容体」を活性化する作用があるといいます。Medical Xpressの記事です。

北半球とは季節が逆の豪州では今年、インフルエンザ患者が平均値の最大3倍に到達し、過去5年間で最悪の大流行を経験したそうです。感染のピークは通常より2カ月も早く訪れたといいます。このことから、米国の感染症の専門家が今冬のインフルエンザ流行に警鐘を鳴らしています。米政府は新型コロナウイルス感染の次の波が12月初めにピークを迎えると予測しており、コロナとインフルの同時流行に対する警戒感も高まっているとのこと。CNNの記事です。

妊娠中に母親が感染症にかかることと、生まれてくる子どもの自閉症リスクには因果関係がないかもしれません。スウェーデンの研究チームが、1987~2010年に生まれた子ども50万人のデータを分析。母親が妊娠中に感染症を患った子どもは自閉症リスクが高いという結果が出たものの、妊娠の前年に感染症にかかった場合も同様にリスクが高かったそうです。遺伝的変異や環境などの要因の方が自閉症リスクに強く影響している可能性があるとのこと。Medical Xpressの記事です。
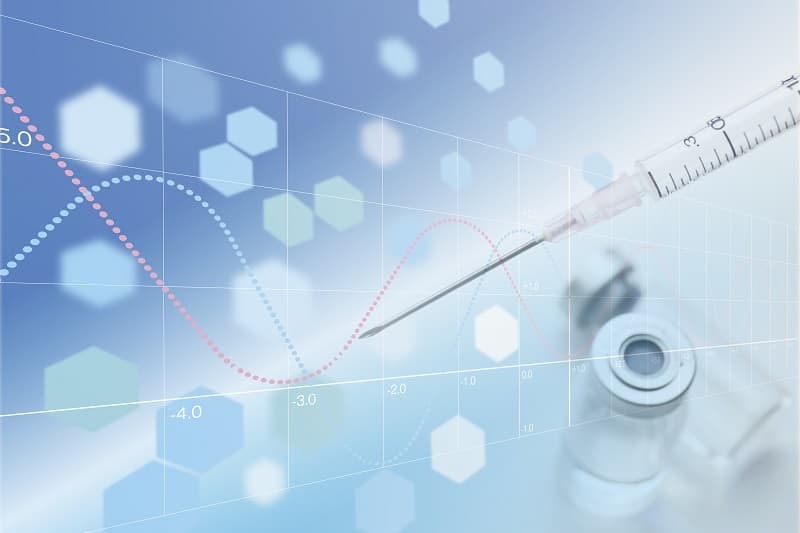
英オックスフォード大学が開発した新たなマラリアワクチン「R21」が、多くの子どもの命を救うかもしれません。チームは西アフリカのブルキナファソの子ども409人を対象に臨床試験を実施。R21に80%の有効性があることが示されたそうです。R21は安価な上、英製薬大手GSK社製の既存のワクチンより効果が高い可能性があるといいます。R21の提供開始は大規模治験終了後の来年になる見込みで、既に年間1億回分を製造する準備が整っているとのこと。BBCの記事です。
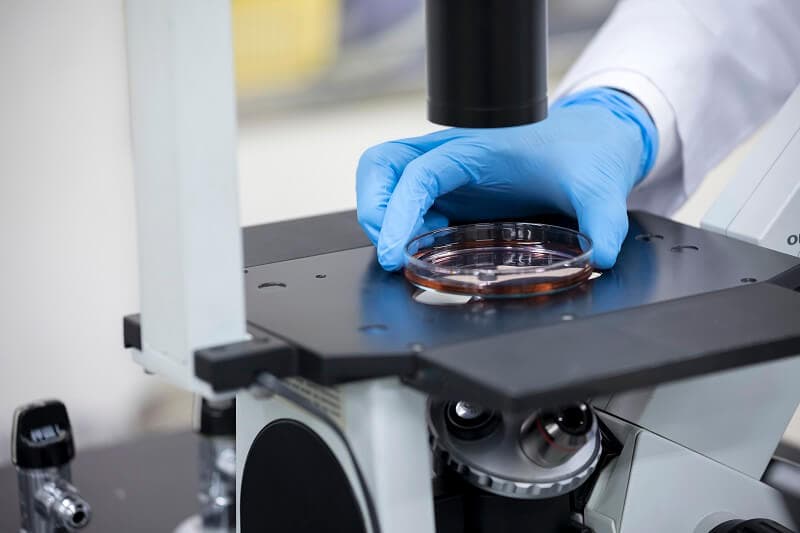
悪性脳腫瘍の一種、膠芽腫(グリオブラストーマ)の治療法につながる可能性があります。イスラエルの研究チームが、膠芽腫の周りに存在する脳細胞「アストロサイト」の役割に着目。動物モデルの実験で膠芽腫周辺のアストロサイトを除去したところ、数日以内に腫瘍が消失し、治療した全ての個体が生き残ったそうです。アストロサイトが腫瘍を免疫系から保護し、腫瘍の成長に必要なエネルギーを供給していることが分かったといいます。Health Europaの記事です。

「魚は水銀を含むので、妊婦は食べる量に注意が必要」は誤りかもしれません。英国の研究チームが、魚を食べる習慣のある島国セーシェルの妊婦と、魚をほとんど食べることがない英国の工業地域の妊婦のデータを分析。母親が魚を食べている場合、妊娠中の水銀レベルが子どもの成長に有害な影響を及ぼすことはないことが分かったそうです。一方で魚を食べていない場合は、母親の水銀レベルが子どもに悪影響を及ぼすことが示されたといいます。Medical Xpressの記事です。

アルゼンチン保健当局は、同国で発生している「謎の肺炎」について、レジオネラ菌感染によるレジオネラ症の可能性があると発表したようです。レジオネラ菌は通常、川や湖などに生息していますが、管理が不適切な給水設備や空調装置で見つかることもあります。菌はエアロゾルとして空気中に漂っており、これを吸い込むと感染して肺炎が起きます。致死率は約10%。今回は、9月5日現在で11人の患者が確認され、このうち4人が死亡したとのこと。BBCの記事です。

中国で、注射針を使わない吸入型の新型コロナワクチンが承認されたようです。このワクチンは、同国のカンシノ・バイオロジクス社が開発しました。同社の注射型コロナワクチンと同様の成分を含んでおり、1回の吸入で望ましい保護効果が得られるといいます。臨床試験では、この吸入型ワクチンは注射型ワクチンを接種済みの人に有効であることが示されたそうです。そのため、今回はブースター接種での使用が承認されたとのことです。BBCの記事です。

アルゼンチン北西部トゥクマン州の医療機関で8月18日以降、9人が原因不明の肺炎を発症し、このうち3人が死亡したそうです。検査の結果、保健当局は新型コロナやインフルエンザの可能性を除外。原因究明のため、他の感染症の検査だけでなく水道水やエアコンも調査しているといいます。症状はコロナに非常に似ており、高熱、体の痛み、呼吸困難が報告されているそうです。今のところ濃厚接触者が発症したケースは確認されていないとのこと。BBCの記事です。

ダウン症候群の人の認知機能は、テストステロンやエストロゲンの分泌を調節する「性腺刺激ホルモン放出ホルモン(GnRH)」を投与することで改善できるかもしれません。スイスなどの研究チームが、20~50歳のダウン症の男性7人に対してGnRHを2時間おきに6カ月間投与。このうち6人で、認知機能に10~30%の改善が見られたそうです。特に視空間認知や立体描写、指示理解などの能力が高まったといいます。重大な副作用は認められなかったとのこと。ScienceAlertの記事です。

糖質コルチコイド(グルココルチコイド)を使った合成ステロイドは、ぜんそくや自己免疫疾患の炎症抑制などの薬です。これを長期間使用すると精神面に影響が出ることがあり、その理由が分かったようです。オランダの研究チームが、ステロイドを使用している人(注射か錠剤:222人、吸入型:557人)と使用していない人(2万4106人)のMRI脳画像を分析。ステロイド使用者は白質構造の完全性が損なわれており、灰白質が縮小していたといいます。Medical Xpressの記事です。

1型糖尿病患者のインスリン注射が不要になるかもしれません。カナダの研究チームが、歯茎と頬の間に入れておくと、頬粘膜からインスリンが吸収される錠剤を開発。ラットの実験では、インスリンは胃にとどまることなく、ほぼ100%が肝臓に直接到達したそうです。錠剤は摂取から30分後には吸収され、効果は2~4時間持続するといいます。これまで開発された飲む錠剤はインスリンの多くが胃に蓄積してしまう上、吸収速度も遅かったとのこと。ScienceDailyの記事です。

米食品医薬品局(FDA)は8月31日、新型コロナウイルスオミクロン株に対応するよう改良されたファイザー社とモデルナ社のワクチンを承認しました。この改良版は、従来株に加えて、感染力が高いとされるオミクロン株「BA.4」や「BA.5」にも対応する2価ワクチンだそうです。追加接種にのみ使用されるといいます。ファイザー製ワクチンは12歳以上、モデルナ製は18歳以上が対象で、前回接種から2カ月以上経過している必要があるとのこと。AP通信の記事です。
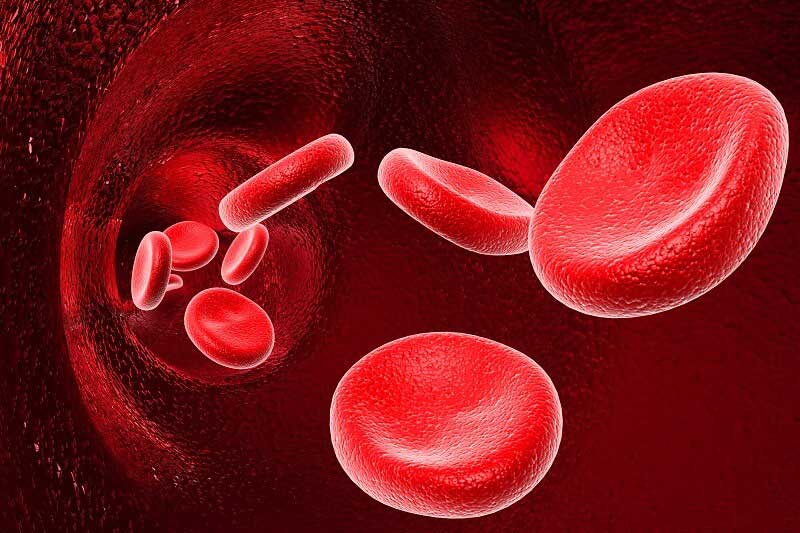
若くして脳卒中を発症するかどうかは、血液型から予測できるかもしれません。米国の研究チームが、遺伝子と虚血性脳卒中に関する48の研究データを分析。対象になったのは、脳卒中患者1万7000人と脳卒中既往歴のない対照群60万人だったといいます。血液型がA型の人は他の血液型の人に比べて、60歳未満で脳卒中を発症するリスクが18%高いことが分かったそうです。一方、O型の人は脳卒中の発症リスクが12%低かったとのこと。Medical Xpressに紹介されています。

ソーセージや炭酸飲料などの超加工食品を摂取することによる健康リスクが、二つの研究から明らかになったようです。米国の研究チームが、男女20万人の食事を最長28年間調査。超加工食品が、男性の大腸がんリスク上昇に関連していたそうです。また、イタリアの研究チームが2万2000人を対象に12年間行った研究では、超加工食品が男女ともに早死にのリスクを上昇させることが示されたといいます。特に心血管疾患による死亡が目立つとのこと。CNNの記事です。

排ガスへの暴露による健康被害は、男性より女性の方が深刻かもしれません。カナダの研究チームが、喫煙をしない健康な男女各5人をディーゼル排ガスに暴露させ、血液サンプルを分析しました。排ガスに暴露すると、男女ともに炎症や感染、心血管疾患に関連する血液成分に変化が確認されました。ただし、その変化は特に女性で顕著だったそうです。血漿中の90ものタンパク質レベルにおいて、男女間で明らかな違いが見られたといいます。Medical Xpressの記事です。

韓国政府は、同国における2021年の15~49歳の女性の年齢別出生率の合計(合計特殊出生率)が0.81だったと公表しました。これは世界最低の値です。韓国では18年に女性1人当たりが出産する子どもの数が1を下回り、6年連続で低下しているそうです。先進諸国の平均出生率は1.6。国が人口を維持するために必要な出生率は2.1だといいます。韓国では経済的圧力やキャリア形成に関連する要因が子どもを持つことの妨げになっていると指摘されています。BBCの記事です。

天然痘の治療薬「テコビリマット」について、サル痘患者への有効性と安全性が示されたようです。米国の研究チームが、皮膚病変のあるサル痘患者25人にこの薬を飲ませました。患者は全員男性で、4人が発症後にサル痘ワクチンを接種していたといいます。投与開始から7日目には患者の40%で皮膚病変が治癒したそうです。そして、21日目までに患者の92%で皮膚病変が治癒し、痛みもなくなったといいます。ひどい副作用もなかったとのこと。Medical Xpressの記事です。

コレステロール値を下げ心血管疾患の予防に使われる薬剤「スタチン」は、副作用で筋肉痛を起こすことがあるといわれています。しかし、英国の研究チームがスタチンに関する23の研究を分析したところ、筋肉痛を報告した人の90%以上はスタチンが原因の筋肉痛ではないことが分かったそうです。服用開始から最初の1年間はスタチンに関連するとみられる筋肉痛や筋力低下が7%増加したものの、その後は有意な増加は確認されなかったといいます。CNNの記事です。
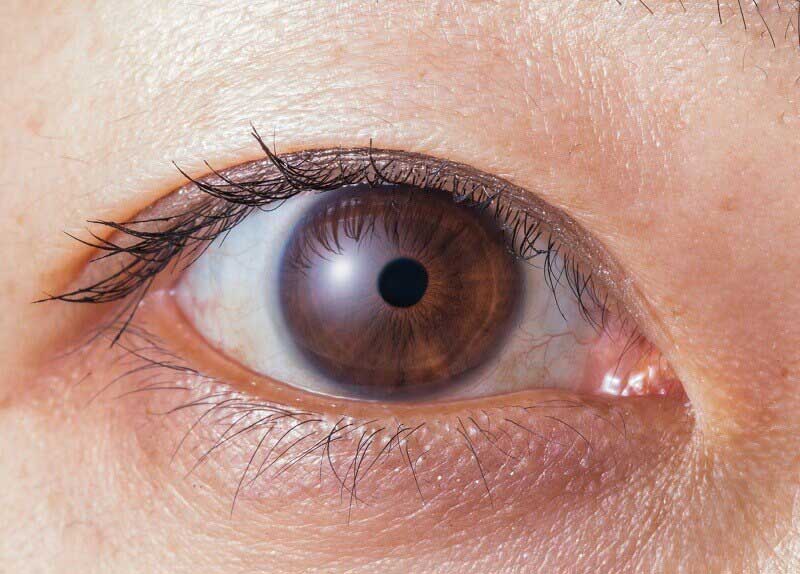
意外な物から作られた組織が、角膜移植におけるドナー不足を解決してくれるかもしれません。スウェーデンの研究チームが、ブタの皮膚から採取したコラーゲンを精製し、角膜の層を作製。これを2mmの切開部から既存の角膜に挿入するそうです。患者自身の組織を摘出する必要がなく、侵襲性が低いといいます。この方法で、角膜疾患のある患者20人が視力を取り戻しました。このうち盲目だった14人全員が、2年後も視力を維持していたとのこと。ScienceAlertの記事です。

ドッペルゲンガーが似ているのは顔だけではないようです。スペインの研究チームが、見た目がそっくりな他人のペア16組を調べたところ、喫煙習慣、体重、教育レベルといった生活様式の特徴まで似ていることが明らかになったそうです。また、DNA解析によって、16組中9組は「超そっくり」とされるペアであることが判明。超そっくりのペアは、 3730の遺伝子において共通の変異が1万9277もあり、多くが体や顔の形質に関係するものだったとのこと。ScienceAlertの記事です。

イスラエルのバイオテクノロジー企業が、人工ヒト胚から移植用臓器を作る研究を進めているそうです。この企業は、まず、マウスの幹細胞から本物そっくりの胚を作製しました。そして、子宮の役割をする機械で胚を数日間育てたところ、心拍や血流などが確認できるまで成長したそうです。精子や卵子、子宮もない状態で、ここまで高度な人工胚が作られたのは初めてだといいます。現在この技術をヒト細胞で試す準備を進めているそうです。MIT Technology Reviewの記事です。

進行した腎臓がんにはロボットによる手術が安全かつ有効であることが示されたようです。米国の研究チームが、がんが下大静脈(IVC)に進展し、腎臓とIVCのがん切除術を受けた患者計1375人を登録した28の研究データを分析。輸血を必要としたのは、ロボット手術を受けた患者が18%で、標準開腹手術を受けた患者は64%だったそうです。また、出血などの合併症を経験したのは、ロボット手術を受けた患者が5%、開腹手術を受けた患者は36.7%だったといいます。ScienceDailyの記事です。

ファイザー社の新型コロナ用経口薬「パキロビッド」は、高齢者にしか効果がないようです。イスラエルの研究チームが同国の患者10万9000人のデータを分析。この薬は40~64歳の患者にはメリットがないことが分かったそうです。一方65歳以上の患者には、入院が75%減少する効果があったといいます。チームはこの結果を米医学誌NEJMに発表しました。パキロビッドが50歳以上に有効だという報告は複数ありますが、専門の医学誌には掲載されていません。AP通信の記事です。
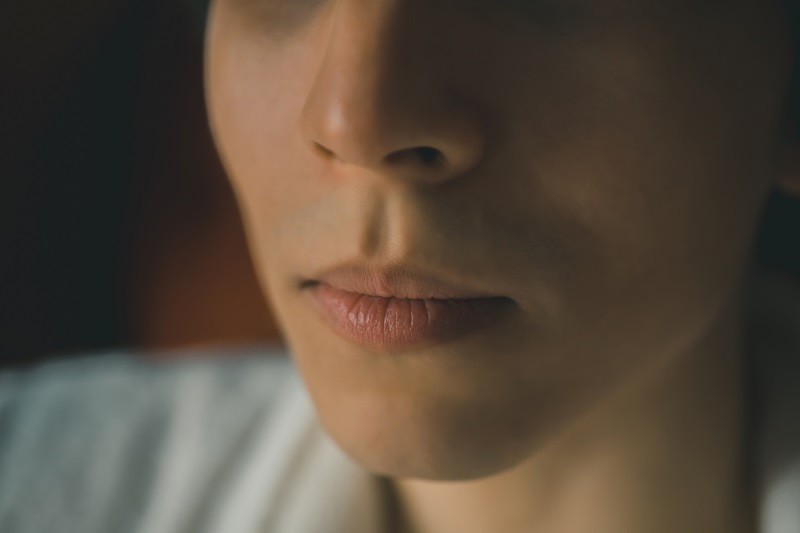
心の健康と口の中の細菌の関係が明らかになったようです。米国の研究チームが、大学生500人の唾液を分析。2週間以内に自殺したいという思い(自殺念慮)を抱いたことがある人は、歯周病などの炎症性疾患に関連する細菌レベルが高かったそう。一方、脳の健康を促進する化合物を産生する細菌Alloprevotella ravaのレベルは低かったといいます。自殺念慮のある人は、この細菌の存在に影響を与える遺伝子変異を持つことも分かったそうです。Medical Xpressの記事です。

米下院議員の61歳の妻が2021年12月、糖尿病や肥満の抑制に効果があるとされる「マグワ(ホワイトマルベリー)の葉」を摂取した後に死亡していたことが分かったそうです。死因は胃腸炎による脱水症で、マグワの葉を摂取したことによる副作用とみられます。この葉を含む栄養補助食品を摂取したのか、葉そのものを食べたりお茶にして飲んだりしたのかは不明だといいます。米国では過去10年間、マグワの葉による死亡例の報告はないとのこと。CBS Newsの記事です。

米中西部のネブラスカ州で、子ども1人が原発性アメーバ性髄膜脳炎で死亡したそうです。この脳炎は「脳食いアメーバ」フォーラーネグレリアを含んだ水が鼻から入ることによって起こる感染症。死亡した子どもは同州のエルクホーン川で泳いでいた際に感染したとみられています。米中西部でこの感染症が原因とみられる死者が確認されたのは今夏2例目。気候変動の影響で、このアメーバの生息地が北上している可能性が指摘されています。AP通信の記事です。

アストラゼネカ社ががん治療薬として開発中の「AZD1390」が、脊髄損傷の治療に有効かもしれません。この薬には、神経細胞のDNAが激しく損傷した際に、細胞分裂を止めたり細胞死を促したりするタンパク質の働きを阻害する効果があることを英国の研究チームが確認。そして、脊髄損傷動物モデルにAZD1390を経口投与したところ、神経の再生が促されたといいます。4週間で、損傷のない動物と見分けがつかないほど感覚や運動の機能が回復したとのこと。Neuroscience Newsの記事です。

ゼロカロリーの人工甘味料を定期的に摂取すると、健康に悪影響があるようです。イスラエルの研究チームが、人工甘味料の摂取を制限している120人を対象に調査。人工甘味料のスクラロースとサッカリンを毎日少量ずつ2週間摂取した人は、プラセボ群に比べて7日後の腸内細菌叢の組成や機能が変化し、血糖値を正常に保つ耐糖能が損なわれたといいます。アスパルテームやステビアなどの甘味料では、耐糖能に影響はみられなかったとのこと。ScienceAlertの記事です。
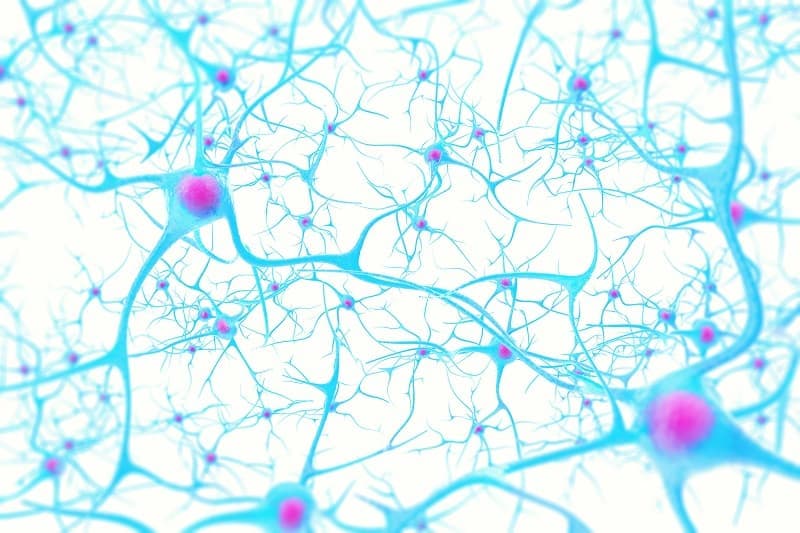
新たなニューロンの生成を促すことで、アルツハイマー病による記憶障害を改善できるかもしれません。米国の研究チームが、アルツハイマー病マウスの神経幹細胞が生き残るよう遺伝子を操作し、ニューロンの新生を促進。マウスの空間認識と、何かと関連した記憶を評価する二つのテストで改善がみられたそうです。新たに形成されたニューロンが記憶を保存する神経回路に組み込まれ、記憶力の回復につながることが分かったといいます。Medical Xpressの記事です。

高齢者の物忘れが改善できるかもしれません。米国の研究チームが、65~88歳の高齢者150人を調査。対象者の中にアルツハイマー病と診断された人はいませんでしたが、ほとんどは年相応に記憶力が低下していたそうです。電極を埋め込んだシャワーキャップを使って20分間の経頭蓋交流電気刺激を4日連続で受けた人は、偽の刺激を受けた人に比べて、覚えた単語を思い出す能力が50~65%向上したといいます。治療の効果は1カ月持続したとのこと。Medical Xpressの記事です。

飲酒や喫煙をはじめとする生活習慣を改善すれば、全世界のがんによる死亡の半数を防ぐことができるようです。米国の研究チームが、世界204カ国のデータから「23種類のがん」と「34のリスク要因」の関係を調査しました。その結果、2019年のがんによる死亡の44.4%が、予防可能なリスク要因に起因していることが分かったそうです。その代表として、気管や肺のがんが挙げられるといいます。予防可能ながんによる死亡は2010~19年で20.4%増加したとのこと。CNNの記事です。

パキスタン北西部のポリオワクチン接種会場で、男2人による銃撃事件が起きたようです。警備の警察官2人が死亡。ワクチン接種の担当者2人にけがはなかったといいます。同国ではポリオワクチン関係者が反ワクチン過激派からたびたび標的にされており、ワクチンはイスラム教徒を不妊にするための欧米の陰謀だと主張する過激派もいるとのこと。野生株ポリオウイルスが常在しているのは、パキスタンとアフガニスタンの2国だけだそうです。BBCの記事です。

サル痘はペットにも感染する可能性があるそうです。フランスの研究チームが、イタリアでグレーハウンドという種類の犬がサル痘に感染した事例を発表しました。飼い主は男性同士のカップルです。2人は別のパートナーと性交渉をした後にサル痘を発症。続いて犬にも症状が現れ、サル痘と診断されたそうです。男性2人はこの犬と一緒に寝ていたといいます。これを受け、米疾病対策センター(CDC)はペットへの感染に注意を呼びかけています。AP通信の記事です。

早産(妊娠37週未満)児は注意欠如・多動症(ADHD)のリスクが高いことが知られています。しかし、出産予定日より少し早めに生まれた子どももリスクが高いことが分かったようです。米国の研究チームが、1998~2000年に生まれた1400人のデータを分析。子どもたちが9歳の時点で、教師にADHDに関連する症状の評価をしてもらいました。妊娠37~38週で生まれた子どもは、39~41週で生まれた子どもに比べて多動や不注意を示すスコアが有意に高かったとのこと。ScienceDailyの記事です。

日曜日の夕方ぐらいから憂鬱になる「サザエさん症候群」を経験したことがある人は多いでしょう。これを防ぐには、週末に入る前にやるべきことをすべて終わらせ、月曜日にやることを残さないようにするといいそうです。また、新しく始まる週に楽しみな予定を入れることも効果的だといいます。なぜサザエさん症候群に襲われるのかが分からなければ、自分の考えや気持ちを書き出す時間を20分とると、その原因が判明するかもしれません。The conversationの記事です。

慢性的な頭痛を軽減するには、はり治療が有効かもしれません。中国の研究チームが、月に15日以上頭痛が起こる「慢性緊張型頭痛」と診断された患者218人に週2~3回、計20回のはり治療を実施しました。そして、全ての治療が終了した後、6カ月にわたる追跡調査を行ったといいます。その結果、通常のはり治療を受けた人の68%、はりを浅めに打つ治療を受けた人の50%が、1カ月のうち頭痛を感じる日数が50%以上減少したと報告したそうです。SciTechDailyの記事です。
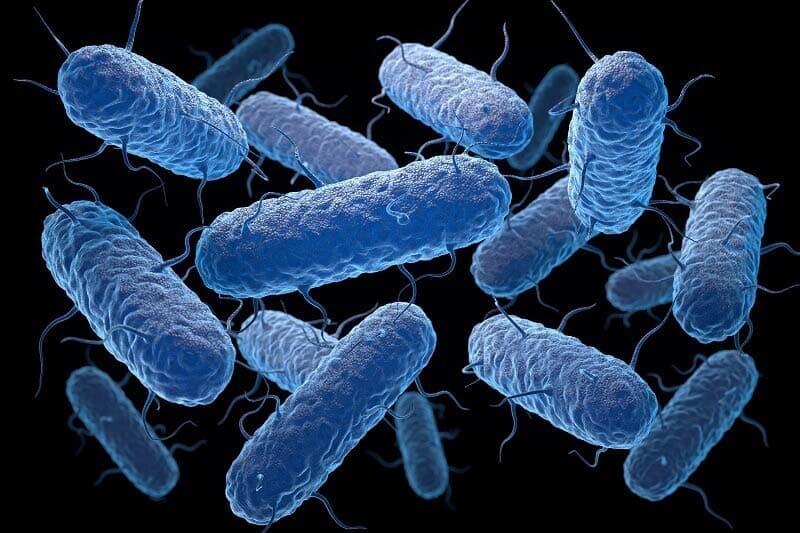
腸内細菌由来の神経毒が、アルツハイマー病(AD)の発症に関与することが明らかになったそうです。米国の研究チームが、ヒトの消化管に多く存在し、通常は病気を起こさない細菌「バクテロイデス・フラジリス」が生成するリポ多糖「BF-LPS」に着目。消化管から流れ出したBF-LPSが、血液脳関門を通過して脳に到達し、ADにつながる神経細胞の萎縮や破壊を引き起こすことが分かったそう。この流れは、食物繊維を多く摂取することで阻害できるといいます。EurekAlert!の記事です。

新型コロナウイルスの従来株とオミクロン株「BA.1」の両方に対応するモデルナ社の2価ワクチンが、英国で承認されました。このワクチンが承認されるのは世界初です。437人を対象にした臨床試験で、その安全性と有効性が確認されたといいます。現在英国で主流のオミクロン株「BA.4」と「BA.5」への有効性も示されたとのことです。このワクチンは、今秋始まる医療従事者や50歳以上の成人などを対象にした追加接種で使用される予定だそうです。BBCの記事です。

中国で、新種のウイルスによる感染症が発生したそうです。このウイルスはトガリネズミが自然宿主とみられ、「ランヤ(狼牙)ヘニパウイルス(LayV)」と名付けられました。これまでのところ35人の患者が確認されており、主な症状として発熱やせき、頭痛などが報告されています。血液細胞の異常、肝臓や腎臓の機能障害を起こした患者もいたようです。現時点ではヒトからヒトへの感染を示す証拠はないものの、結論を出せる段階ではないとのこと。Medical Xpressの記事です。

新型コロナが、子どもの「脳の感染症」に関連しているかもしれません。米国の研究チームが109の小児病院を調査。その結果、43%がパンデミック開始から最初の2年間で脳膿瘍をはじめとする脳の細菌感染症が増加したと報告したそうです。コロナ感染によって免疫能が低下し、口や鼻にいる細菌が脳に侵入する可能性が指摘されています。コロナ禍で、通常診療やワクチンの定期接種が受けられなかったことも原因として考えられるといいます。Medical Xpressの記事です。

新型コロナウイルスへの感染が、中枢神経(脳、脊髄)に長期的な影響を及ぼすことが示唆されたようです。米国の研究チームが、高齢者や基礎疾患のある人がコロナに感染した場合、中枢神経の病気がどのように発生するかなどを調査。抑うつ障害や糖尿病などがある人は、微小脳出血が見つかることが多かったそうです。呼吸器系を調節する脳領域で出血や血栓が起こると、アルツハイマー病や脳卒中などにつながる可能性もあるといいます。Medical Xpressの記事です。

温暖化や山火事、洪水などの気候変動が、感染症の発生や拡大に重大な影響を及ぼすようです。米国の研究チームが、ヒトに病気を引き起こす病原体375種に関する資料を分析。このうち58%が過去に天候の影響で深刻化していたことが分かったそうです。これまでに気候変動が関与していると実証された感染症の流行は 3213件に上るといいます。気候変動がどのようにして感染症の大流行をもたらすかについて、1006もの経路が特定されたそうです。ScienceAlertの記事です。

米ファイザー社と仏ヴァルネヴァ社が、ライム病のワクチン「VLA15」の開発を進めています。ライム病はマダニが媒介する感染症で、インフルエンザ様症状から始まり、心臓や神経などの症状が出て、重症化したり後遺症が残ったりすることがあります。VLA15は小規模治験で良好な結果が出ており、今後の治験では5歳以上の参加者を少なくとも6000人登録するといいます。AP通信の記事です。厚生労働省によると、日本でも1986年以降、計数百人の患者が報告されています。

米政府は7月4日、感染が拡大するサル痘への対応レベルを引き上げる決定を下しました。ワクチンの供給不足に批判の声が上がる中、政府はサル痘に対する公衆衛生上の緊急事態を宣言。宣言が出されたことで、緊急用の基金をはじめとする資源をサル痘対応のために使えるようになるといいます。当局は国民に対し、サル痘を深刻に受け止めるよう呼びかけたそうです。同国で4日までに確認されたサル痘感染者は7100人を超えているとのこと。AP通信の記事です。

ニキビができるメカニズムが明らかになったようです。米国の研究チームが、参加者6人の背中から採取したニキビのある皮膚を分析。ニキビの原因であるアクネ菌を最初に攻撃するのは免疫細胞のマクロファージですが、マクロファージが皮脂成分の「スクワレン」を取り込むと、泡状の「Trem2マクロファージ」になることを発見しました。こうなると、アクネ菌を攻撃する能力を失い、逆にニキビの発生に加担することが分かったといいます。MedicalBriefの記事です。

白血病の遺伝子治療などへの応用が試みられているゲノム編集技術「CRISPR」が、かえってがんの発生を促進してしまうかもしれません。イスラエルの研究チームがCRISPRを用いて、がん細胞を攻撃するように、免疫細胞のT細胞の染色体を改変し、その影響を調査。9%超のT細胞で、改変の際に切断された部分が修復せず、染色体のかなりの部分が失われることが分かったそうです。このことが、長期的にはがんの発生につながる可能性があるといいます。Medical Xpressの記事です。

アルツハイマー病(AD)発症の一つの経路が明らかになったようです。米英の研究チームが、脳に似せたヒト組織の3次元培養モデルで調査。休眠中の単純ヘルペスウイルス1型(HSV-1)を持っている神経細胞が水痘帯状疱疹ウイルス(VZV)に感染すると、初期のADが引き起こされる可能性が示されたそうです。VZV感染によってHSV-1が再活性化し、ADの原因と考えられているタンパク質のタウやアミロイドβの蓄積につながって、神経細胞の機能が失われるといいます。EurekAlert!の記事です。

米ニューヨーク州ロックランド群で7月、約10年ぶりにポリオ患者が確認された件の続報です。米疾病対策センター(CDC)は、ロックランド群で6月上旬に採取した下水から、ポリオウイルスが検出されたと発表しました。このことは、7月に見つかった患者以外にも感染者が存在する可能性を示しているといいます。ただし、現時点ではウイルスが広まっているとする十分な情報はなく、追加の症例も確認されていないといいます。AP通信の記事です。

未熟な青いバナナなどに含まれる「レジスタントスターチ(難消化性でんぷん)」を摂取すると、遺伝性がんの発症リスクが半減するそうです。英国の研究チームが、がんリスクが高いとされる遺伝性疾患「リンチ症候群」患者1000人を対象に調査を実施。2年間、レジスタントスターチの粉末を毎日摂取した人は、10年の追跡期間中に大腸以外のがんを発症するリスクが60%以上低下したといいます。特に上部消化管がんへの効果が顕著だったとのこと。EurekAlert!の記事です。

米エール大学のチームが、死後時間の経過した臓器の機能を一部復活させることに成功したそうです。チームはブタ100頭の心臓を止め、1時間後に「OrganEx」というシステムにつなぎました。全身に酸素を運ぶ人工血液と、細胞死を阻止する13の化合物を投与し、体液を規則正しく循環させるシステムです。6時間後、心臓や肝臓、腎臓などで細胞がよみがえり、機能が部分的に復活。この技術を用いれば、移植できる臓器の数を増やせるかもしれません。BBCの記事です。

栄養ドリンクの成分として知られる「タウリン」には、老化と共に衰える抗酸化防御機構を強化する効果があるようです。ブラジルの研究チームが55〜70歳の女性24人を調査。1日1.5gのタウリンを16週間摂取した人は、抗酸化酵素「スーパーオキシドディスムターゼ(SOD)」レベルが20%上昇したそうです。一方、プラセボ群の同レベルは3.5%低下したといいます。抗酸化力が高まると、心血管疾患や糖尿病などのリスクを抑制できる可能性があります。EurekAlert!の記事です。

インド中央部にあるマディヤ・プラデーシュ州の学校で行われた新型コロナのワクチン接種で、1本の注射器が生徒30人に使い回されていたことが明らかになったそうです。接種を担当した人物はメディアに対し、注射器は保健局から1本しか支給されておらず、その指示に従っただけだと主張したといいます。州保健局はこの人物による過失事件として届出を行い、ワクチン接種に必要な器具を用意する担当者に聞き取り調査を開始したとのこと。BBCの記事です。

米ミシシッピ州の住民2人が、主に熱帯国に生息する類鼻疽(るいびそ)菌に感染したそうです。患者は敗血症で入院しましたが、回復しているとのこと。2人の自宅周辺の土壌から類鼻疽菌が検出されました。米国州内の土壌から見つかるのは初めてだといいます。この菌は汚染された土や水からヒトに感染し、肺炎や敗血症などさまざまな病気を引き起こします。糖尿病や慢性腎臓病などを持つ人は重症化リスクが高く、死亡率も高いとのこと。CBS Newsの記事です。

サル痘による死者の報告が相次いでいます。アフリカ以外で死者が確認されるのは初めてだといいます。最初の報告はブラジルからで、同国保健省が7月29日、感染した41歳の男性が死亡したと発表。男性はリンパ腫と免疫不全を抱えていたそうです。30日にはスペイン保健省が、2人の死亡を報告しました。患者の1人は脳炎を発症したといいます。なお、スペイン保健省によると、詳しいデータがある患者3750人のうち、入院したのは3.2%とのこと。BBCの記事です。

米カリフォルニア州の研究チームが、エイズウイルス(HIV)感染者の66歳の男性が寛解したと発表しました。HIVの寛解が確認されたのは4例目で、これまでの患者の中で最高齢です。男性は1988年にHIV感染の診断を受け、31年間HIVと共に生きてきました。その後、白血病を発症したため、2019年に幹細胞移植を受けました。この時のドナーがHIVに耐性がある遺伝子変異を持っていたそうです。男性は、HIVと白血病のいずれも寛解状態が確認されたとのこと。ScienceAlertの記事です。

米国で子どもへのサル痘感染が初めて確認されたようです。患者は2人で、いずれも家庭内感染の可能性が濃厚といいます。サル痘患者の多くは男性と性交渉する男性です。しかし、皮膚と皮膚の密接な接触があれば、誰もが感染し得るそうです。子どもの場合、抱っこや食べ物を食べさせる行為、日用品の共有で感染する可能性があるといいます。患者は2人とも抗ウイルス薬「テコビリマット」による治療を受けており、容体は良好とのことです。CNNの記事です。

2006年に科学誌Natureに掲載されたアルツハイマー病の重要論文に、改ざんした画像が使われた可能性があるそうです。米ヴァンダービルト大学の研究者が捏造を疑い、科学誌Scienceが調査を実施。いくつかの画像の改ざんを示唆する証拠が見つかったといいます。この論文はタンパク質「アミロイドβ」をアルツハイマー病の原因として挙げた重要な研究で、2200以上の他論文に引用されているそうです。改ざんが事実であれば、これらの論文にも影響は必至とのこと。CNNの記事です。

サル痘に感染する可能性があるのは、男性と性交渉する男性だけではありません。米国で、これまでに報告されているリスク因子に全く該当しない30代男性がサル痘に感染していることが判明。この男性は2回目の受診でサル痘感染が分かったのですが、最初は頭にブツブツができていたことから毛包の感染症と誤診されたそうです。同国では感染者の99%が男性と性交渉する男性であるため、それ以外の人たちの感染が見逃される恐れがあるそうです。CNNの記事です。

血友病Bの患者は、出血を止めるために必要なタンパク質「血液凝固第IX因子(FIX)」を定期的に注射で補充する必要があります。英国の研究チームが、それを不要にするアデノ随伴ウイルス(AAV)遺伝子治療「FLT180a」を開発したそうです。FLT180a は1回の注射でFIXが長期的に発現するよう設計されているとのこと。18歳以上の中等~重度の男性患者10人を対象にした治験では、過剰な出血が抑制され、定期的な補充療法が不要になることが確認されたといいます。Health Europaの記事です。

世界で1000件以上の症例が報告されている謎の小児肝炎について、英国の研究チームが原因を突き止めたようです。チームによると、通常は風邪や胃腸炎の原因となる「アデノウイルス」と、感染しても病気にならない「アデノ随伴ウイルス2型」の二つが深刻な肝炎を引き起こしたと考えられるとのこと。コロナ禍での行動制限により、子どもたちがこれらのウイルスに暴露されず、免疫を作る機会を逃したことが影響している可能性があるそうです。BBCの記事です。

新型コロナウイルス感染の新たな主流となっているオミクロン株の「BA.5」は、再感染を引き起こす可能性が高いそうです。米国の遺伝子解析会社Helix社が、2021年3月以降に検査でコロナ陽性になった30万人分のデータを分析しました。「BA.2」が主流だった今年5月にコロナに再感染した人の割合は3.6%だったのに対し、「BA.5」が主流になった7月のこの割合は6.4%だったといいます。7月現在、前回の感染から再感染までの平均期間は約9カ月とのことです。CNNの記事です。

世界保健機関(WHO)は、世界74カ国で1万6500人以上の感染が確認されているサル痘について「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言しました。現在、ポリオと新型コロナにもこの宣言が出されています。過去には、新型インフル(2009~10年)、エボラ出血熱(14~16年、19~20年)、ジカ熱(16年)の流行時にこの宣言が出されました。サル痘感染者の多くは男性と性交渉する男性で、特に複数のパートナーがいる人に感染が集中しているとのこと。CNNの記事です。

ホルモン剤の避妊薬(低用量ピル)を使用する若い女性は、特定の認知能力が高くなるかもしれません。米国の研究チームが18~27歳の女性59人を調査。低用量ピルを使用している人はそうでない人に比べて、物体の配置を記憶する課題で、新たに現れた物を特定する能力が有意に高かったそうです。一方、空間認識能力を評価する課題では有意差はみられなかったといいます。薬の種類による効果の違いについては比較されていないとのことです。PsyPostの記事です。

世界保健機関(WHO)は7月17日、西アフリカのガーナでマールブルグウイルスによる感染症の患者が初発生したと発表しました。患者2人が確認され、下痢や発熱、嘔吐などの症状が現れ、いずれも死亡。90人以上の濃厚接触者が監視下にあるといいます。このウイルスはエボラウイルスと同じ科に属し、致死率は最大88%に達するそうです。オオコウモリからヒトに感染し、感染者の体液などに触れることでヒトからヒトへうつります。治療薬はありません。CNNの記事です。

高用量のビタミンB6サプリメントが気分障害の予防や治療に有効かもしれません。英国の研究チームが、300人以上の若年成人を対象に調査を実施。推奨摂取量の50倍近い量のビタミンB6サプリを1日1回食事と一緒に1カ月間摂取した人は、不安感やうつ状態が改善したそうです。ビタミンB6には、神経細胞の興奮を抑制する神経伝達物質GABA(γ-アミノ酪酸)の産生を促す役割があり、ビタミンB6サプリを摂取した人はGABAレベルが上昇していたといいます。EurekAlert!の記事です。

食物アレルギーの人は新型コロナ感染に対して、ある利点があるそうです。米国立衛生研究所(NIH)が、4000人以上を対象に調査を実施。その結果、食物アレルギーがある人は、コロナに感染するリスクが50%低いことが明らかになったそうです。食物アレルギーには、免疫反応の一つの型である「2型炎症」が関与しているといいます。この2型炎症が、ウイルスが細胞に侵入する際に取り付く「ACE2受容体」の発現を少なくしている可能性があるそうです。ScienceAlertの記事です。

たった1回の注射でエイズを治療できる日が来るかもしれません。イスラエルと米国の研究チームが、遺伝子改変技術CRISPRを使い、体内にある免疫細胞・B細胞を操作する方法を開発。ウイルス(アデノ随伴ウイルス:AAV)を用いてCRISPRシステムを送り、エイズウイルス(HIV)に対する中和抗体を産生できるようにB細胞の遺伝子を改変するといいます。この治療を受けたすべての動物モデルにおいて、血液からHIVに対する抗体が大量に検出されたとのこと。Medical Xpressの記事です。
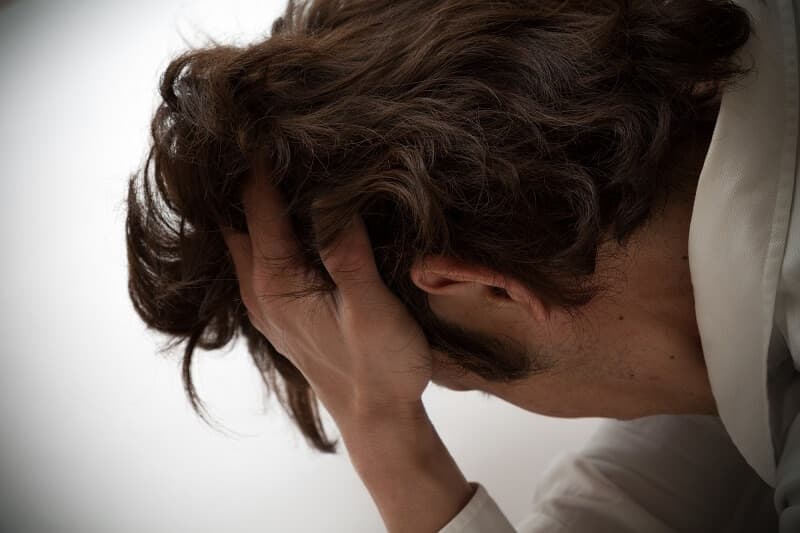
米ニューヨーク州ロックランド群の若年成人がポリオと診断されたようです。この患者はポリオワクチン未接種で、1カ月ほど前に脱力や麻痺の症状が始まったそう。同国でポリオが確認されたのは2013年以来だといいます。ウイルスの型から、米国外で経口生ポリオワクチンの接種を受けた別の誰かに由来することが判明。弱毒化したウイルスが変異し、有害な株が発生することがあります。米国では2000年以降、経口生ワクチンは使用されていません。CNNの記事です。

うつ病の原因に関する定説が覆るかもしれません。英国の研究チームが、セロトニンとうつ病の関連を調査した過去の研究を再検討しました。対象者は数千人に上ったといいます。分析の結果、「セロトニンの働きや濃度の低下がうつ病の原因になる」との仮説を支持する証拠は見つからなかったそうです。抗うつ薬として一般に使われている「選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)」の役割に疑問を投げかける結果になったとのことです。Health Europaの記事です。

オキシトシンは、感情を調整したり他人への信頼感を高めたりし、「愛情ホルモン」などと呼ばれます。オキシトシンの経鼻スプレーは人間関係の改善に役立つとされていますが、本当でしょうか。英国の研究チームが、平均19歳の健康な男性104人を調査。感情を読み取るためのトレーニングを受けた人は、悲しみや怒りの表情を認識する能力が高まったそうです。一方、オキシトシンを経鼻投与した人には、同様の効果は一切なかったといいます。EurekAlert!の記事です。

世界保健機関(WHO)は、エボラ出血熱やサル痘、コロナウイルス感染症など、動物からヒトにうつる感染症がアフリカで急増していることに懸念を示したそうです。2012~22年は、前の10年間に比べて人獣共通感染症が63%増加。特に2019~20年にその数は急増し、アフリカにおける重大な公衆衛生事象の半数を占めました。急速な都市化による野生動物の生息地の減少などが影響しているようです。世界中に人獣共通感染症が広がる危険性があるとのこと。AP通信の記事です。
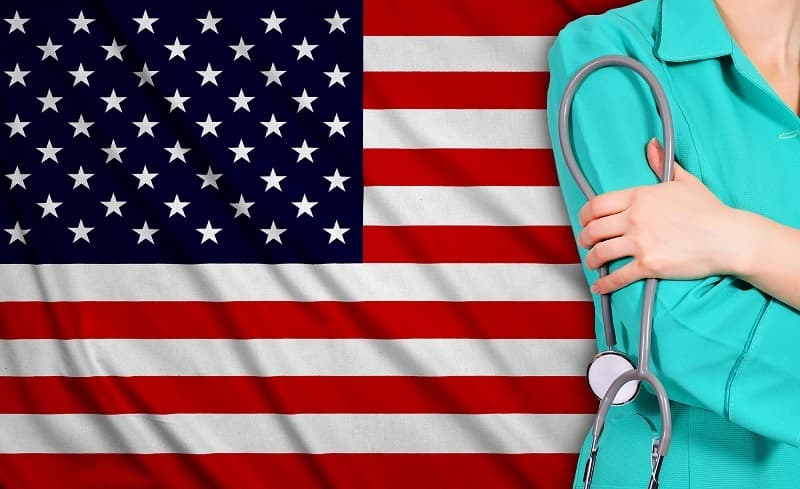
米国では疑い例を含むサル痘患者が7月15日時点で1814人に達しました。米国立アレルギー・感染症研究所長のファウチ氏はこの数値について「過小評価の可能性が高い」とし、サル痘を深刻に受け止める必要性に言及。米食品医薬品局(FDA)元長官のゴットリーブ氏は「封じ込めは手遅れかもしれない」と指摘しています。両氏は検査体制拡大の重要性を強調。米疾病対策センター(CDC)は、1週間の検査能力を6000件から8万件に増やす予定だといいます。CNNの記事です。

骨髄移植のドナーの術中・術後の痛みを緩和する新たな方法が見つかったそうです。米国の研究チームが、「腰方形筋ブロック(QLB)」と呼ばれる局所麻酔技術を骨髄採取の手術に応用したといいます。そして、この技術を使って骨髄を採取したドナー13人と、既存の方法で骨髄を採取したドナー19人のデータを比較しました。その結果、QLBを行うと、疼痛管理のためにオピオイドが必要な人の割合が84%から23%に減少することが明らかになったそうです。Medical Xpressの記事です。

治療方針の判断に重要な役割を果たすパルスオキシメーターは、血液の色から血中の酸素濃度を測定しているため、肌の色の濃い人は実際より高い値が出てしまうという問題があるそうです。米国の研究チームの調査では、実際は血中酸素濃度が88%未満なのに、機器には92~96%と表示されるケースが、黒人患者は白人患者に比べて3倍多かったそうです。皮膚の色素であるメラニンの影響を排除するよう調整することで、誤差を防げるといいます。CNNの記事です。

米国では、ブタの臓器で人間の命を救うための試みが続けられているようです。米ニューヨーク大学ランゴーン医療センターが、遺伝子操作したブタの心臓を脳死患者2人に移植。移植前には、動物特有のウイルスがブタの心臓に存在していることがないよう、特別な方法でチェックしたそうです。また、心臓移植から生命維持装置が外されるまでの3日間、頻繁な生検など、脳死患者に対してだからこそ行える検査が実施されたといいます。AP通信の記事です。
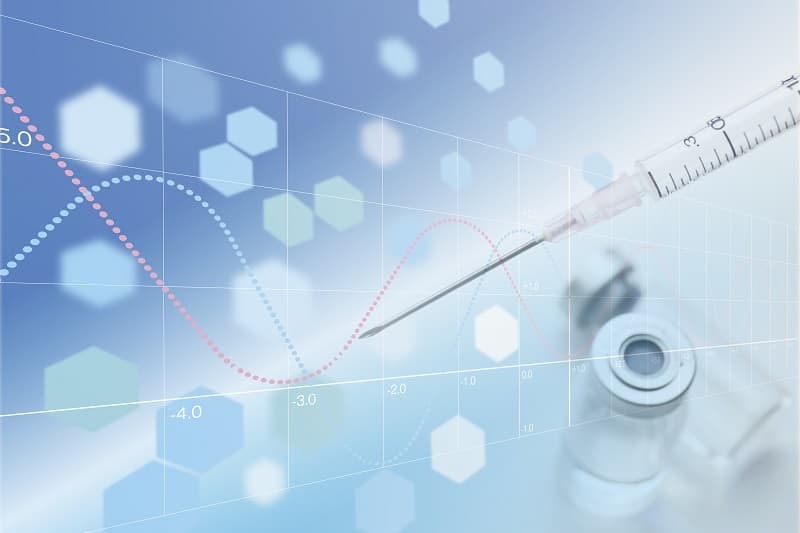
ニパウイルス感染症は、バングラデシュやインドなどを中心に毎年アジアで感染者が報告されています。主に動物を介してヒトにうつり、脳炎症状を引き起こして40~75%を死に至らしめます。米国立衛生研究所(NIH)とモデルナ社がmRNAワクチンを共同開発し、第1相試験を開始したそうです。18~60歳の健康な成人40人が対象で、25、50、100㎍のいずれかの容量のワクチンを原則4週間間隔で2回接種。その後52週間にわたり追跡調査を行うとのこと。EurekAlert!の記事です。

新型コロナウイルス感染拡大の初期に行われた治療法が、深刻な問題を引き起こした可能性があるようです。米疾病対策センター(CDC)は、2020年3~10月に新型コロナ入院患者の80%に抗菌薬が投与され、そのことによって「超多剤耐性菌(スーパーバグ)」の院内感染や死亡が15%増加したと報告しているといいます。メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)やカルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)などのスーパーバグが入院患者から検出されたそうです。AP通信の記事です。

食品包装や化粧品などに使われるフタル酸エステル類への暴露が、早産リスクと関連していることが分かったようです。米国立衛生研究所(NIH)が、1983~2018年に出産した妊婦6045人の尿中フタル酸エステル代謝物濃度と出産時期のデータを分析。11のフタル酸エステルのうち4種類に暴露した妊婦は、早産リスクが14~16%高かったそうです。フタル酸エステル代謝物レベルを50%抑えることで、早産が平均12%減少するとの試算もあるといいます。Medical Xpressの記事です。
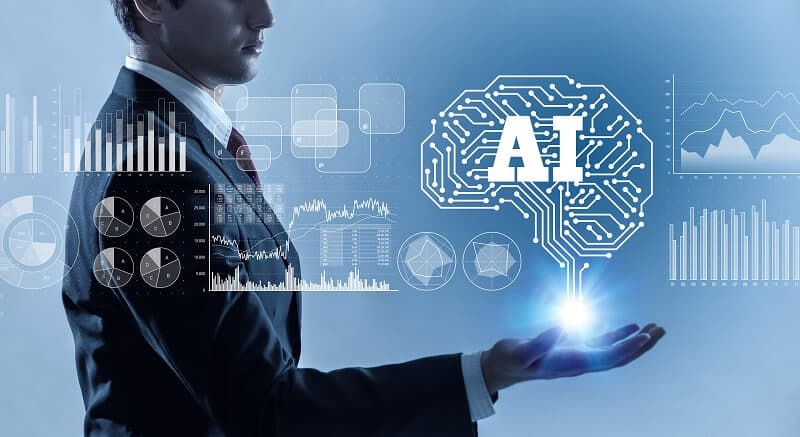
英ディープマインド社が、人間の赤ちゃんと同じように考えることができる人工知能(AI)を開発したそうです。このAIは「PLATO」という名で、物理的概念を習得するといいます。同社はビデオを使って、生後数カ月の赤ちゃんが物体に対して持つような基礎知識をPLATOに学ばせました。その後、PLATOに物理法則上あり得ない現象をみせたところ、驚いたような反応を示したそう。物理法則に反するおかしな現象が起きたことをPLATOが認識したためだといいます。ScienceAlertの記事です。

水だけを飲むという断食を定期的に行っている人は、新型コロナによる重症化リスクが低いとの研究結果が出たようです。米国の研究チームが、ワクチンが普及する前にコロナ陽性になった205人を調査。少なくとも月1回、定期的に断食をすると報告した人が73人おり、その人たちはコロナによる入院や死亡のリスクが低かったといいます。ただ今回の調査は、宗教上の理由から平均40年間も断食を習慣にしている人たちが対象だったそうです。Medical Xpressの記事です。

網膜の病気の治療法として研究が進む経角膜電気刺激(TES)が、神経精神疾患の治療に有効かもしれません。TESは黒目に電極を置いて電気刺激を与える方法です。香港のチームがTESをうつ病モデルのマウスに使ったところ、抗うつ薬と似た効果が現れ、ストレスホルモンが減少。海馬の脳細胞の成長に関与する遺伝子の発現も誘導されました。また、TESがアルツハイマー病マウスの記憶力を大幅に改善し、海馬のアミロイドβ沈着を減少させたといいます。Neuroscience Newsの記事です。

「お腹がすくとイライラする」というのは本当なのでしょうか。英豪の研究チームが、成人64人を対象に21日間にわたる調査を実施。参加者は1日5回、スマホアプリで空腹度や精神状態を報告したといいます。その結果、空腹が怒りやいら立ちなどの負の感情を引き起こし、喜びの感情を低減させることが分かったそうです。「日々の空腹度の変動」だけでなく、「3週間の平均の空腹度」も負の感情を引き起こす原因になるとのことです。Neuroscience Newsの記事です。

注意欠如・多動症(ADHD)の治療に用いるゲームの話題です。米食品医薬品局(FDA)は2020年、米Akilli社が開発した「EndeavorRx」を小児ADHD治療用ゲームとして初承認。EndeavorRxは宇宙人が宇宙を飛び回って物を集めるゲームで、注意機能に重要な役割を果たす脳領域を改善するよう設計されているそうです。使用者の中には、学校に行く準備がスムーズにできるようになったり、成績が上昇したりする子もいるといいます。米国では医師が必要と判断した子どものみ使用できます。BBCの記事です。

対処療法しかないA型肝炎に対する経口治療薬を、米国の研究チームが開発しているそうです。A型肝炎ウイルス(HAV)の複製には、ヒトの細胞が持つ「TENT4」と呼ばれる酵素が使われるといいます。HAVがTENT4を使うためには、HAVのRNAとヒトのタンパク質「ZCCHC14」との結合が必要であることが分かったそうです。チームは、HAVがTENT4を使えなくするために、A型肝炎マウスにTENT4を標的とする経口化合物「RG7834」を投与。すると、HAVの複製が止まったといいます。Medical Xpressの記事です。

生まれつき耳の形が不完全で小さい小耳症。患者の耳を再建するための新方法が見つかったかもしれません。米国の研究チームが、小耳症患者の正常な方の耳を3Dスキャンして設計図を作り、患者から採取した耳軟骨細胞を適切な大きさに成長させて本人に移植したそうです。移植された耳は時間とともに自然な見た目や感触に変化すると考えられています。今回の移植は、患者11人の登録が予定されている臨床試験の一環として実施されたそうです。ScienceAlertの記事です。

新型コロナによって引き起こされる神経症状の原因が明らかになったようです。米国の研究チームが、感染後に突然死亡した患者9人の脳組織を調査。ウイルス自体は脳から検出されなかったそうです。一方で、コロナ感染に応答して作られる抗体が、脳血管内皮細胞を攻撃し、血管に損傷を与えて炎症を引き起こす可能性があることが判明しました。この細胞は、有害物質が血管から脳内に入り込むのを防ぐ血液脳関門の形成に不可欠だといいます。ScienceDailyの記事です。

食品に使われるフリーズドライ(凍結乾燥)技術が、生物多様性の維持に役立つかもしれません。山梨大の研究チームが、マウスから採取した体細胞を凍結乾燥させ、マイナス30度で最長9カ月間保存。この体細胞から取り出した遺伝情報を用いて、クローンを作り出すことに初めて成功したそうです。現時点ではクローンが生まれる成功率は0.02%と非常に低いものの、液体窒素に替わる遺伝資源の保存方法として期待が寄せられているといいます。ScienceAlertの記事です。

ビタミンDサプリメントの過剰摂取による健康被害が増えているようです。英国の研究チームが、5万MGのビタミンD (1日の必要量は600MG)を含む多数のサプリを毎日摂取していた中年男性の症例に着目。サプリを飲み始めて1カ月後、男性に嘔吐やこむら返りなどさまざまな症状が現れ、体重は12.7KGも減少していたそう。症状は3カ月間も続いたといいます。男性の血中ビタミンDレベルは必要量の7倍もあり、カルシウムレベルも極端に高かったとのこと。SciTechDailyの記事です。

スウェーデンのMyrkl社の二日酔いを予防するプロバイオティクスサプリメントの販売が英国で始まったそうです。このサプリは飲酒前に飲む錠剤で、アルコールを分解するとされる腸に有益な「枯草菌」と「有胞子性乳酸菌」を含有。健康で若い白人成人24人を対象に調査を行い14人から得られた結果では、事前にこのサプリを摂取した人は、飲酒から1時間以内の血中アルコール量がプラセボ群より70%少ないことが分かったといいます。ScienceAlertの記事です。

痛みを和らげるためにオピオイドなどの薬を使う必要がなくなるかもしれません。米国の研究チームが、神経を冷却することで麻痺させ、痛みを緩和する埋め込み型の装置を開発。わずか幅5mmほどのこの装置は柔軟性があり、縫合せずに神経に巻き付けることができるそうです。神経が冷えすぎないように監視するセンサーも付いているといいます。使用後は、自然に体内に吸収されるそうです。動物実験で装置の有効性が実証されているとのこと。EurekAlert!の記事です。

娯楽目的の大麻使用が合法化されているカナダで、大麻使用者の健康リスクが明らかになったようです。同国の研究チームが、「1年以内に大麻を使用した」と報告した4800人と、「大麻を使用したことがない」または「1年以上前に1度だけ大麻を使用した」と報告した1万人を比較。1年以内に大麻を使用した人は、対照群に比べて救急外来受診と入院のリスクが22%高かったといいます。受診や入院の主な理由は、外傷と呼吸器関連だったとのこと。ScienceDailyの記事です。

北朝鮮の国営メディアが、新型コロナウイルスの流入は韓国からの飛来物が原因だと示唆する報道をしているそうです。韓国当局は「あり得ない」と強く否定したといいます。国営メディアは、4月上旬に韓国との国境付近で不審物に触れた18歳の兵士と5歳の子どもがコロナ陽性になり、それ以降、北朝鮮でコロナが急速に拡大したと報道。韓国の活動家は何年もの間、国境を越えて風船を飛ばし、ビラ配布や人道支援を行っているそうです。BBCの記事です。

144種類の亜型があるA型インフルエンザウイルスに対する「万能ワクチン」ができるかもしれません。米ジョージア州立大学が、A型ウイルスの比較的変化しにくい二つの部分(タンパク質)に着目。ワクチンは、これらのタンパク質を遺伝子的に結び付けて開発したそうです。成体及び高齢マウスを使った実験では、この新たなワクチンがA型ウイルスの複数の亜型(H1N1、H5N1、H9N2、H3N2、H7N9)に対して有効であることが確認されたといいます。Medical Xpressの記事です。

高齢者がインフルエンザワクチンを1回でも接種すると、その後の4年間のうちにアルツハイマー病(AD)を発症するリスクが40%低下するという研究成果が発表されました。米国の研究チームが、65歳以上の高齢者を4年間追跡。インフルワクチン接種者と非接種者それぞれ93万5887人を調べました。調査期間中にADを発症したのは、ワクチン接種者が5.1%だったのに対し、非接種者は8.5%でした。毎年接種した人が、最も発症リスクが低かったとのことです。Medical Xpressの記事です。

機械学習を使った新技術で、早期のアルツハイマー病(AD)患者を正確に診断できるようになるかもしれません。英国の研究チームが、115の脳領域における660の構造的特徴を評価することで、ADを診断するアルゴリズムを開発。診断には、一般的な装置で撮影されたMRI画像が使われるそうです。このアルゴリズム単独で、ADの有無を98%の確率で予測できるといいます。また、ADの初期と後期については79%の確率で判別することも可能だそうです。SciTechDailyの記事です。
見知らぬ人と友達になれるかどうかは、体臭から予測できるようです。イスラエルの研究チームが、仲のよい友人同士のペアと無作為に選ばれたペアの体臭を、におい測定装置と人の嗅覚によって比較。友人同士の方が、においが互いに似ていることが分かったそうです。また、面識のない人たちに言葉を使わず交流してもらったところ、相手に好感を抱く場合、におい測定装置で互いに「においが似ている」と判定されることが多かったそうです。ScienceDailyの記事です。

断食による腸内細菌の活動の変化が、神経損傷からの回復力を高めるそうです。坐骨神経を損傷したマウスの実験では、1日置きに断食したマウスは毎日好きなだけ食べたマウスに比べて、神経細胞の情報伝達部分である「軸索」が50%長く再生しました。断食したマウスは、腸内細菌の代謝産物である「IPA」の血中濃度が高いことも判明。腸内細菌がIPAを産生しないように遺伝子操作したところ、軸索がうまく再生しなかったとのこと。英大学のICLが発表しました。

革新的な肺のMRI画像から、新型コロナの後遺症が起こる原因が判明したようです。カナダの研究チームが、コロナ感染後に息切れの症状が6週間以上続く患者を調査。MRIを撮る際に患者に偏極キセノンガスを吸い込ませることで、3億個以上存在する肺胞嚢(のう)の機能をリアルタイムで観察できたといいます。肺胞嚢では、赤血球へ酸素が受け渡されます。コロナ後遺症患者は、この受け渡しがうまく行われていないことが分かったそうです。Medical Xpressの記事です。

中高年の健康診断にバランス感覚を調べる検査を含めた方がいいかもしれません。英、米、ブラジルなど5カ国の研究チームが、歩行に問題のない51~75歳の中高年1702人を2008~20年にわたって調査。片足で10秒間立つことができなかった人は、その後10年間の全死因死亡リスクが84%高くなることが分かったそうです。ただし、参加者は全て白人のブラジル人であったため、今回の結果は他の民族や地域には当てはまらない可能性があるとのこと。MedicalBriefの記事です。

米連邦最高裁は6月24日、人工妊娠中絶を憲法が保障する権利として認めた1973年の判例を覆し、州ごとに中絶を禁止・規制することを容認しました。これに対し、世界保健機関(WHO)のテドロス事務局長が「安全で合法的な中絶は医療として理解されるべきだ」と批判しています。また、危険な方法での中絶を選ぶ女性が現れ、命を落とすリスクが生じると指摘。時代の流れを「後戻り」する今回の判断が他国に与える影響にも懸念を示しています。AP通信の記事です。

胃腸炎を引き起こすノロウイルス、ロタウイルス、アストロウイルスのヒト―ヒト感染は、汚染された物に接触して、口からウイルスが入ることで起こると考えられていました。しかし、米国の研究チームによって、唾液を介して感染する可能性が明らかになったそうです。子マウスの実験で、3ウイルスが腸での複製量と同等量、唾液腺でも複製することが判明。さらに、ノロウイルスがヒトの唾液腺細胞で簡単に増殖することも分かったとのこと。NewScientistの記事です。

米疾病対策センター(CDC)とフロリダ州保健当局は、同州で「髄膜炎菌感染症」患者を26例確認したそうです。死者は7人。患者のうち24人は男性と性交渉する男性だといいます。この細菌は唾液などを通じて、密接な接触によって拡散するそうです。高熱、頭痛、肩こり、嘔吐、濃い紫色の発疹が主な症状。初めはインフルエンザのようにみえるものの、急激に悪化することが多いといいます。感染を予防するには、ワクチン接種が最善の方法とのこと。CNNの記事です。

治療しない場合の致死率が最大20%という腸チフス。原因菌であるチフス菌の薬剤耐性化が深刻さを増しているようです。米国の研究チームが、2014~19 年に南アジアで確認された3489 のチフス菌株のゲノム配列を解析。超多剤耐性(XDR)チフス菌が増加し、世界中に急速に広がっていることが明らかになったといいます。現在XDRチフス菌に唯一有効とされる経口抗菌薬「アジスロマイシン」が効かなくなるのも時間の問題だとみられているそうです。ScienceAlertの記事です。

アルツハイマー病を理解するには脳の血流が重要なポイントになるようです。英国の研究チームが、タンパク質「アミロイドβ1-40(Aβ1-40)」に着目。Aβ1-40を多く産生するアルツハイマー病高齢マウスは、健康なマウスに比べて、脳の表面に張り巡らされた小動脈が狭いことが分かったそうです。この動脈が狭まることが、記憶力低下の原因の一つだといいます。そして、Aβ1-40が、血管を広げる役割を持つ「BKタンパク質」の働きを阻害することも判明したそうです。Medical Xpressの記事です。

英保健当局は、サル痘予防のワクチンの提供対象を拡大するようです。これまでは患者に接触する医療従事者などに限定していましたが、男性と性交渉するなど感染リスクが高いと考えらえる男性も対象になるそうです。英国で確認されているサル痘患者の99%以上が男性で、その多くがゲイやバイセクシャルだといいます。ワクチンは元々天然痘のために開発されたものですが、サル痘に対しても85%の有効性があると考えられているとのこと。AP通信の記事です。

乳がんは人が眠っている間に活発になるようです。スイスの研究チームが、乳がん患者30人とモデルマウスを調査。血中を循環して転移を起こす循環腫瘍細胞は、眠っている時の方が腫瘍から多く生み出されることが分かったそうです。さらに、夜間に腫瘍から離れていく循環腫瘍細胞の方が素早く分裂し、転移につながりやすいことも明らかに。昼夜のリズムを司るメラトニンなどのホルモンが、循環腫瘍細胞の遊離をコントロールしているとのこと。ScienceDailyの記事です。

勃起不全(ED)治療に使われるバイアグラなどのPDE5阻害薬が、化学療法耐性の食道がん治療に効果があるかもしれません。英国の研究チームが、食道がんの腫瘍の周辺環境を調査。がんの増殖を助け治療の効果を妨げる「がん関連線維芽細胞(CAF)」の所で、酵素のPDE5レベルが高いことが判明しました。化学療法耐性の食道がんをマウスに移植し、標準的な化学療法とPDE5阻害薬を併用したところ、有害な副作用を起こすことなく、がんが縮小したといいます。News-Medical.Netの記事です。

加齢黄斑変性や糖尿病網膜症の治療では、白目から注射を刺して、眼球内を満たすゼリー状の硝子体に薬剤を注入することがあります。その際、感染症などの合併症の懸念がありますが、韓国などの研究チームがそれを防ぐ、栓の付いた超極微針を開発したそうです。針を刺した時にできる穴は栓で塞がれます。針は眼球内にとどまって薬剤を放出し、最終的に生分解されるといいます。ブタの実験では、薬が安全に眼球内に広がったとのこと。ScienceAlertの記事です。

新型コロナが広がっている北朝鮮で、急性の腸感染症が流行しているようです。流行が確認されたのは、首都平壌から南に120kmほど離れた黄海南道。これまでに少なくとも800世帯が医療支援を受けたといいます。病名は明らかになっていないものの、コレラや腸チフスの可能性が指摘されています。当局は患者の徹底的な隔離の重要性を強調。北朝鮮の労働新聞は、金正恩総書記が準備した医薬品が、患者に届けられる予定だと報道しているそうです。CNNの記事です。

腸内環境を整える「プロバイオティクス」サプリメントが、抗うつ薬の効果を高めるそうです。スイスの研究チームが、うつ病患者47人を31日間調査。抗うつ薬に加えてプロバイオティクスサプリを飲んだ人は、プラセボを使った人に比べてうつ症状が大きく改善したそうです。サプリを使った人の腸内で乳酸菌が増えたといいます。ただ、追跡調査の結果から、この細菌が腸内に定着するには、より長い治療期間が必要なことも分かったそうです。ScienceAlertの記事です。

ラガービールには男性の腸内環境を整える効果があるようです。ポルトガルの研究チームが、健康な男性19人を二つの群に分けて調査。一方の群にはアルコール入りのラガービールを、もう一方にはノンアルコールのラガービールを、それぞれ4週間にわたって夕食時に11液量オンス(約330ml)飲んでもらいました。その結果、両群共に腸内細菌叢の多様性が高まり、腸内環境が改善したそうです。また、体重やBMIなどに変化は見られなかったとのこと。Medical Xpressの記事です。

音に合わせて拍子を取るのが得意な人と苦手な人がいるのはなぜなのでしょうか。米国などの研究チームが60万6825人のボランティアを調査。参加者の遺伝子解析(ゲノムワイド関連解析)を行った結果、拍子を取ることができる人とできない人の間で、69の遺伝子に違いがみられることが明らかになったそうです。これらの遺伝子における変異が、拍子を取る能力にマイナスの影響を与えたりプラスの影響を与えたりすることが示唆されたとのこと。Medical Xpressの記事です。

米スタンフォード大学が、非常にまれな遺伝性の多臓器障害「シムケ免疫性骨形成不全(SIOD)」の小児患者3人に新たな技術を使って腎移植を行ったようです。腎移植に先立ち、チームはドナーの骨髄幹細胞を患者に移植。その際、移植片対宿主病の原因となるアルファ・ベータT細胞とCD19 B細胞を枯渇させる処理を加えたといいます。3人の腎移植は成功し、免疫抑制薬を使わずに少なくとも22~34カ月にわたって良好な経過をたどっているとのこと。ScienceAlertの記事です。

血中のがん由来のDNA(血中循環腫瘍DNA:ctDNA)を調べることで、大腸がんの再発を予測できるそうです。豪州などの研究チームが、ステージ2の大腸がん手術を受けた患者455人を調査。153人は化学療法の標準的な方法で管理され、302人は術後7週間以内に血液検査を受け、ctDNAが検出された患者だけが化学療法で治療されたそうです。化学療法を受けた患者数は血液検査をした群の方が少なく、再発を伴わない2、3年後の生存率は両群で同等だったとのこと。EurekAlert!の記事です。

吸入型の「次世代」新型コロナワクチンが開発されているそうです。カナダのマクマスター大学が、エアロゾルを吸い込むことで肺に直接送り込めるワクチンを開発。現在使われているワクチンの1%程度の量で済み、しかも効果は長続きするといいます。変異が起こりやすいスパイクタンパク質だけでなく、ウイルスの内側にあるタンパク質も標的にしており、新たな変異株にも効果が期待できるとのこと。現在、第1相試験を行っているそうです。The conversationの記事です。

豪州で、馬とコウモリからヘンドラウイルス(HeV)の新たな変異型「HeV-g2」が見つかりました。HeVは感染した馬の体液などを介してヒトにうつります。重篤な肺炎や脳炎を引き起こし、致死率は最大95%。HeV-g2の出現で緊張が高まる中、米国などのチームが、従来のHeVを中和する複数のモノクローナル抗体がHeV-g2にも有効なことを確認。このうち三つを新たに設計した抗体1種と組み合わせ、HeV-g2が新たに変異する能力をも抑える強力な抗体カクテルを作ったとのこと。ScienceDailyの記事です。

女優のジェイダ・ピンケット・スミスが苦しんでいることで知られる重度の円形脱毛症の治療薬として、米食品医薬品局(FDA)が米イーライリリー社のヤヌスキナーゼ阻害剤「バリシチニブ」を承認したそうです。計1200人を対象にした二つの臨床試験の結果に基づくもので、同疾患の経口治療薬の承認は初めて。この薬を1日4mg、36週間摂取した患者の40%が、頭髪の80%を取り戻したそう。主な副作用として、上気道感染症や頭痛などが確認されたとのこと。ScienceAlertの記事です。

新型コロナの経口治療薬「パキロビッド」は、重症化リスクの高い人にのみ効果が期待できるようです。薬を開発したファイザー社が、「重症化リスクが標準的」な患者でのパキロビッドの有効性を調査。コロナ陽性で症状のある18歳以上の患者1100人に対し、半数にはパキロビッドを1日2回、5日間与え、残りの半数にはプラセボを与えて比較しました。その結果、パキロビッドを服用しても症状を軽くする証拠は示されなかったといいます。CNNの記事です。

「ビタミンDレベルが低い(25nmol/L)こと」と「認知症発症」の間に因果関係があることを、豪州の研究チームが明らかにしたそうです。英国バイオバンクから得た29万4514人のデータを使って解析した結果です。全ての人のビタミンDレベルを標準値(50nmol/L)まで増やすことができれば、認知症患者の17%は発症を予防できる可能性も示唆されたそうです。ビタミンDはキノコ類や魚介類に多く含まれるほか、日光を浴びることによって皮膚でも作られます。Medical Xpressの記事です。

タイ政府は禁止麻薬リストから大麻を除外したそうです。大麻の家庭栽培が解禁され、大麻草の販売や飲食店での大麻入り商品の提供も可能に。農業や観光業の促進につながることを期待しています。ただ、向精神作用のあるテトラヒドロカンナビノール(THC)を0.2%以上含む製品の販売や提供は引き続き違法です。また、タイは2018年に医療用大麻の使用を合法化しています。今後は全国のクリニックで、より自由に治療薬として使えるようになるそうです。BBCの記事です。

米食品医薬品局(FDA)に承認されたばかりの2型糖尿病治療薬「チルゼパチド」は、肥満の治療で減量手術と同等の高い効果が期待できるようです。薬を開発した米イーライリリー社が、太り過ぎまたは肥満の2539人を対象に72週にわたる第3相試験を実施。参加者はみな肥満関連の併存疾患があるものの、2型糖尿病ではありませんでした。週1回15mg投与(皮下注射)された人の効果が最も高く、平均して元の体重の22.5%(24kg)の減量につながったといいます。ScienceAlertの記事です。

カナダの人気歌手ジャスティン・ビーバーさんが、「ラムゼイ・ハント症候群」によって顔の一部が麻痺していることを公表しました。この疾患は水痘・帯状疱疹ウイルスによって引き起こされます。小児期などに感染したウイルスが顔面神経に潜伏し、何らかの原因で免疫力が低下した時に再活性化することで発症します。めまいや難聴、耳鳴りなどの症状が出ることもあるといいます。抗ウイルス薬やステロイドを使った治療法があります。CNNの記事です。

IgG抗体は腸内の善玉菌の影響で自然に産生されます。母乳を介してIgGを受け取ることで、乳児が下痢性疾患から守られる可能性があるそうです。米国の研究チームが、母乳からIgGを受け取った赤ちゃんマウスは、下痢を引き起こす細菌の腸への付着が抑えられることを発見しました。一方で、IgG を受け取らなかったマウスは腸内細菌叢の組成に異常をきたし、炎症性疾患に関連のある炎症性サイトカインを産生する免疫細胞が腸内で増加したとのこと。ScienceDailyの記事です。

インターロイキン-12(IL-12)は、免疫細胞を活性化してがん細胞を殺傷させる強い力を持つ物質です。しかし、正常な細胞にも障害を与えてしまうため、治療薬としては使用できませんでした。米国の研究チームが、免疫細胞への結合部分を蓋で覆ったIL-12の作製に成功。腫瘍周辺にある酵素に接触すると蓋が外れてIL-12が活性化し、免疫細胞に腫瘍を攻撃させます。マウスの実験では、懸念された副作用は確認されず、がんの治癒率も非常に高かったとのこと。The conversationの記事です。

神経性やせ症(拒食症)患者に特徴的な脳構造の変化が明らかになったそうです。英国などの研究チームが、2000人近くの脳スキャンを分析。拒食症の人は、「皮質の厚み」「皮質下容積」「皮質の表面積」の三つが大幅に減少することが確認されたそうです。その減少幅は、うつ病やADHDの人にみられる脳縮小の2~4倍にも上るといいます。拒食症に対する適切な治療を早期に行えば、縮小した脳が回復する可能性も示唆されたとのことです。Medical Xpressの記事です。

ルミノコッカス科の腸内細菌が産生する代謝産物「イソアミルアミン(IAA)」が、認知機能の低下を引き起こすようです。米国の研究チームは、IAAが血液脳関門を通過できることに着目。腸から脳に移動したIAAの影響をマウスで調べたところ、神経細胞死につながる作用を起こすことが分かったそうです。若い健康なマウスにIAAを与えると認知機能が低下し、高齢マウスの腸でIAA産生を阻害すると認知能力が改善することも明らかになったといいます。Medical Xpressの記事です。

寝ている間に頻繁に悪夢をみる男性は、パーキンソン病に注意が必要かもしれません。英国の研究チームが、一般的な脳機能をもつ高齢男性3818人を12年にわたり追跡。悪夢を頻繁にみると報告した人は、パーキンソン病を発症するリスクが倍増することが分かったそうです。発症した人のほとんどが、調査開始から5年以内に診断を受けたといいます。悪夢の有無を尋ねることで、パーキンソン病の早期発見につながる可能性が示唆されたとのこと。ScienceAlertの記事です。

子宮内膜がんの治療に使われるがん免疫治療薬「ドスタルリマブ」が、直腸がんにも有効かもしれません。米国の研究チームが、直腸がん(ミスマッチ修復機構欠損:MMRd)患者12人にドスタルリマブを3週間ごとに6カ月間投与。治療から6カ月後もがんの形跡は見当たらず、12人全員が「寛解(臨床的完全奏功)」だったそうです。副作用については、手術や化学放射線療法の影響で起こるような深刻なものは、今のところ報告されていないとのこと。ScienceAlertの記事です。

乳がん治療薬「エンハーツ」は、がんの増殖に関わるタンパク質HER2が多く発現する「HER2陽性」乳がんに使用されます。米国の研究チームが、HER2陰性に分類される「HER2低発現乳がん」を患い、転移性または切除不能な状態と診断された患者500人を調査。がんの進行が抑えられた期間は、標準的な化学療法を受けた人が5.5カ月間、エンハーツを使った人は10カ月間でした。エンハーツによって、生存期間が約6カ月延長することも示されたといいます。AP通信の記事です。

新型コロナ治療薬「パキロビッド」を使用した場合、治療終了後もしばらく注意が必要かもしれません。米国の研究チームが、パキロビッドで治療後にコロナがぶり返す症例を調査。再発後、他の人にコロナをうつした事例が少なくとも2件あり、患者に再度症状が現れる前から感染させる可能性も示唆されたそうです。患者のウイルス量は、パキロビッドの投与によって一旦減少するものの、その後なぜか一部の人で再び増加するとのことです。CNNの記事です。
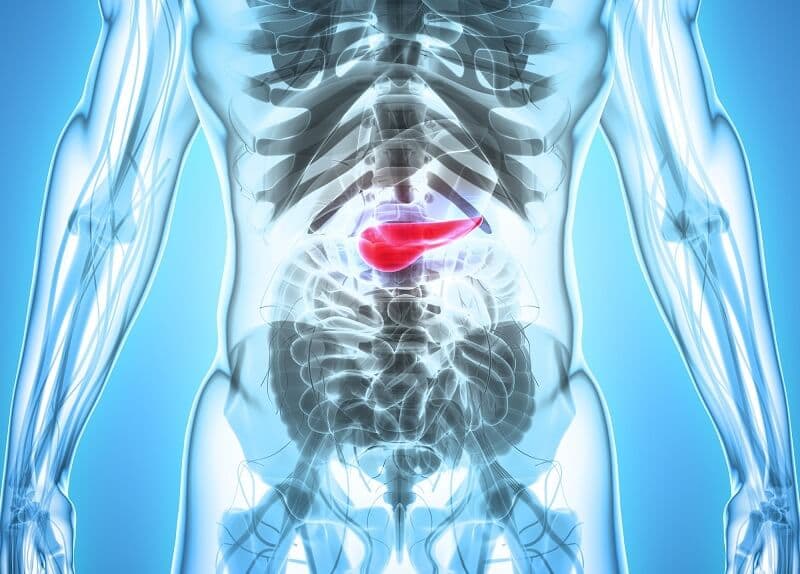
遺伝子改変T細胞療法は、遺伝子改変した免疫細胞のT細胞を使ったがんの治療法です。米国の研究チームが、ある治療困難なすい臓がん患者のT細胞遺伝子を改変。T細胞受容体(TCR)が、腫瘍細胞内に隠れる突然変異タンパク質を発見できるよう操作したといいます。このT細胞を患者に戻したところ、腫瘍が72%縮小したそうです。ただ、同じ療法を受けた別の患者の治療は失敗に終わっており、その理由は明らかになっていないとのこと。AP通信の記事です。

カフェインを含んだコーヒーを毎日適量飲むと、長生きできるかもしれません。中国の研究チームが、心血管疾患やがんを患っていない37~73歳の英国人17万1616人を調査。コーヒーを飲まない人と比べると、7年後(平均値)に死亡しているリスクが、甘いコーヒーを1日1.5~3.5杯飲む人は30%低く、甘くないコーヒーを1日1.5~3.5杯飲む人は16~29%低かったそうです。甘いコーヒーを飲む人は、平均でティースプーン1杯の砂糖を入れていたとのこと。CNNの記事です。

加齢黄斑変性(AMD)の進行を抑えるためのサプリメントがあります。しかし、成分のβカロテンが、喫煙者が摂取した場合に肺がんリスクを上昇させることが分かっていました。そこで、βカロテンを抗酸化物質のルテインとゼアキサンチンに置き換え、安全性と効果を調べる研究が行われたそうです。米国の研究チームが、参加者3883人を10年間追跡したデータを分析。肺がんリスクは上昇せず、AMD進行抑制の効果は高まることが確認されたそうです。Medical Xpressの記事です。

肥満患者が減量手術(肥満外科手術)を受けると、がんのリスクを低減できるかもしれません。米国の研究チームが、2004~17年に肥満治療のために減量手術を受けた患者5053人と手術を受けていない肥満患者2万5265人の10年後を比較。減量手術が、肥満と関連があるとされる13種類のがん発症リスクを32%低下させることが分かったそうです。さらにこの手術によって、がん関連で死亡するリスクが48%低くなることも明らかになったといいます。ScienceDailyの記事です。

膵(すい)臓がんの有望な治療法が見つかったようです。米国の研究チームが、転移性の膵管腺がん(PDAC)患者100人を対象に臨床試験を実施。がん免疫治療薬「ニボルマブ(商品名オプジーボ)」と二つの化学療法薬「ナブパクリタキセル」「ゲムシタビン」を組み合わせて投与された患者は1年生存率が57.7%で、化学療法のみの患者の平均生存率35%を上回ったそうです。ニボルマブの代わりに「ソチガリマブ」を使用した方が有効な患者もいるとのこと。Medical Xpressの記事です。

2021年「世界の医薬品売上高トップ20」は、新型コロナウイルス関連の製品が大きな存在感を示しているようです。コロナ関連製品は4つがランクイン。首位はファイザー・ビオンテック社のコロナワクチン「コミナティ」で、売上高は368億ドルと他を圧倒したそうです。前年まで9年連続首位だった関節リウマチなどに使われるアッヴィ社の「ヒュミラ」は2位、モデルナ社のコロナワクチン「スパイクバックス」が3位だったといいます。 Fierce Pharmaの記事です。

英国では、子宮頸がんのスクリーニング方法が変わりつつあるそうです。イングランド、スコットランド、ウェールズでは、検査方法を従来の細胞診からHPVウイルスの存在を調べる「HPV検査」に変更。これまで3年に1度行われていた検診を5年に1度に減らした地域もあるといいます。同国の研究チームが女性130万人のデータを分析したところ、5年に1度の検診でもHPV検査によって十分にがんを予防できることが分かったそうです。BBCの記事です。

米国で抗菌薬の不適切な使用が続いているようです。同国の研究チームが、プライマリケア医723人を対象に、無症状にもかかわらず尿から細菌が検出される状態の「無症候性細菌尿」患者への対応を調査。回答した551人中392人(71%)が抗菌薬を使うと答えたそうです。無症候性細菌尿への抗菌薬の処方は、下痢や嘔吐、常在菌の感染症などを引き起こしたり、腸内で危険な細菌C.difficileを過剰に増殖させたりする危険があるため、2005年以降推奨されていません。Medical Xpressの記事です。
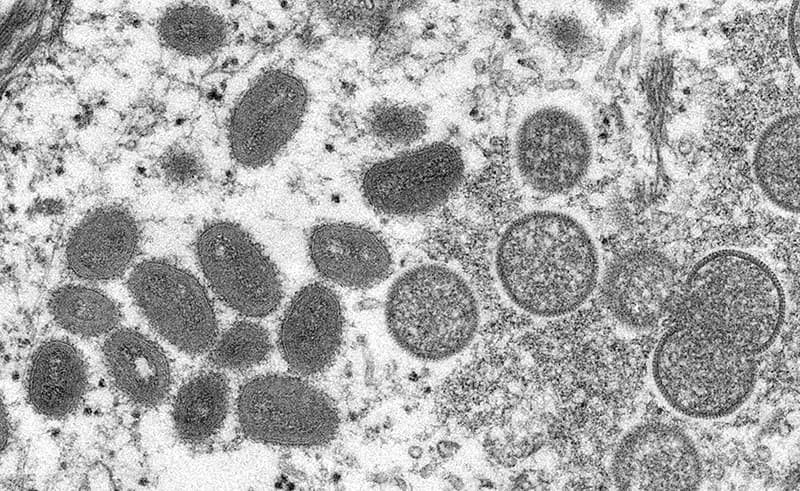
「サル痘」感染が拡大してから、新型コロナウイルスの情報を再利用しているとみられるデマが多く拡散しているようです。インターネット上には、今回のサル痘が研究室から流出したものだとする情報が存在。しかし遺伝子配列を調べると、それはありえないことが分かっています。「ロックダウンが近い」「感染拡大は意図的に計画された」「コロナワクチンが関連している」などの憶測が流れていますが、どれも全く根拠がないといいます。BBCの記事です。(写真:サル痘ウイルスの電子顕微鏡画像=CDC提供)

英国で原因不明の小児肝炎患者の報告が増加しており、5月27日時点で累計222件に達したそうです。原因についてWHO(世界保健機関)は、新たなアデノウイルスの出現▽新型コロナウイルスとの共感染▽子どもがアデノウイルスに感染しやすくなっていること▽コロナ後遺症――など複数の可能性を指摘しています。インターネット上でコロナワクチン原因説も出ていますが、患者の多くは接種対象年齢未満であり、つじつまが合わないとのこと。Forbesの記事です。

環境要因が、炎症性腸疾患の「クローン病」発症リスクに関連しているかもしれません。カナダの研究チームが、患者の第一度近親者(父母、兄弟姉妹、子ども)4289人を調査。2~4歳の時に犬を飼っていた人は、発症リスクが低かったそうです。猫の飼育は発症リスクと関係なかったとのこと。また、生後1年間を3人以上の家族と過ごした人も低リスクだったそう。環境要因による腸内細菌叢組成の変化が関係している可能性があるといいます。Medical News Todayの記事です。

2型糖尿病の脳への影響に、もっと注目するべきかもしれません。米国の研究チームが、英国バイオバンクのデータを使って50~80歳の2万人の脳を調査。2型糖尿病の人はそうでない同年齢の人に比べ、加齢の影響を越えて、実行機能が13.1%、処理速度が6.7%、それぞれ低下したそうです。糖尿病が進行すると、脳の老化が最大で26%加速することも分かったといいます。糖尿病と診断される前から脳が影響を受けている可能性も示唆されています。Neuroscience Newsの記事です。

骨の軟化を引き起こすビタミンD不足は、英国の研究チームが開発した遺伝子組み換えトマトで解消できるかもしれません。ヒトが食べ物から取るべきビタミンD3は、プロビタミンD3(7-DHC)に紫外線(UBV)を当てることで生成されます。プロビタミンD3は本来、葉にしか含まれませんが、チームは実にも含むトマトを作り出すことに成功。スライスした実にUVBを1時間照射したところ、実1個に1日の推奨摂取量に当たるビタミンD3が含まれていたとのこと。SciTechDailyの記事です。

脳卒中後の運動機能の回復に、抗てんかん薬「ガバペンチン」が有効かもしれません。米国の研究チームが、虚血性脳卒中のモデルマウスを使って調査。ガバペンチンを毎日6週間にわたって投与されたマウスは、脳卒中後の前肢運動機能が回復しやすかったそうです。治療終了から2週間後も、機能回復は持続していたといいます。脳卒中が起きてから1時間後に治療を始めても、1日後に始めても、結果に違いはみられなかったとのこと。Medical Xpressの記事です。

米国でまた、新型コロナウイルスの感染が拡大しています。患者の58%はオミクロン株の亜系統「BA.2.12.1」の感染者だといいます。専門家はBA.2.12.1について、以前のオミクロン株に比べて広がりが速く、免疫をうまく回避する能力があると指摘しています。患者が重症化しやすい可能性もあるそうです。BA.2.12.1はオミクロン株だけでなく、デルタ株の特徴も兼ね備えており、従来のオミクロン株に感染した人もBA.2.12.1に再感染するリスクが高いといいます。AP通信の記事です。

ポリオに似た麻痺を起こす「急性弛緩性脊髄炎(AFM)」と「エンテロウイルスD68(EV-D68)」の直接的な因果関係が明らかになったようです。米国の研究チームが、2008年にAFMで死亡した男児の剖検標本を調査。EV-D68が、脊髄ニューロンに直接感染していたことが分かったそうです。EV-D68に感染していたニューロンは、上肢の脱力に関連する領域だったといいます。さらに、感染に伴う強力な免疫反応も確認され、正常なニューロンも破壊された可能性があるようです。Medical Xpressの記事です。
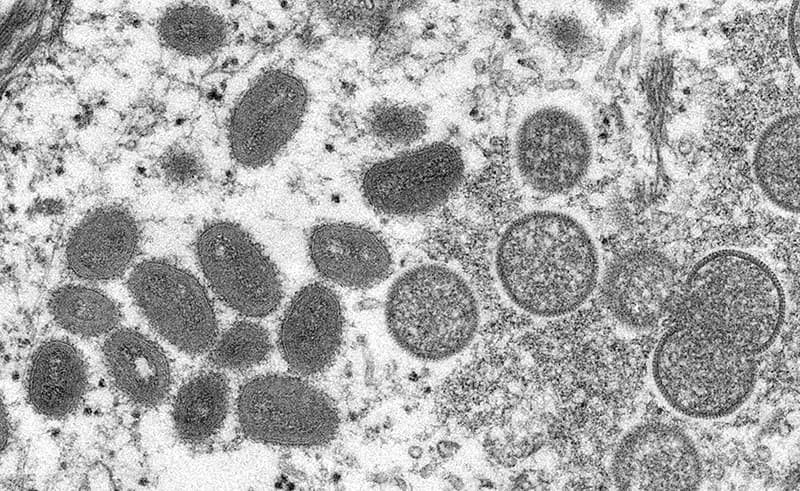
欧米などで報告が相次ぐ「サル痘」は、性交渉によって感染が拡大した可能性があるそうです。WHO(世界保健機関)は、最近欧州内で開かれた二つのダンスパーティー(レイブ)での性的な行為が契機になった可能性に言及。欧州各国の保健当局によると、患者の多くは男性と性交渉をする男性です。ただ、そういった人が他の人より感染リスクが高いわけではなく、たまたまそのコミュニティで最初に感染が起きたことが原因だとみられています。AP通信の記事です。(写真:サル痘ウイルスの電子顕微鏡画像=CDC提供)
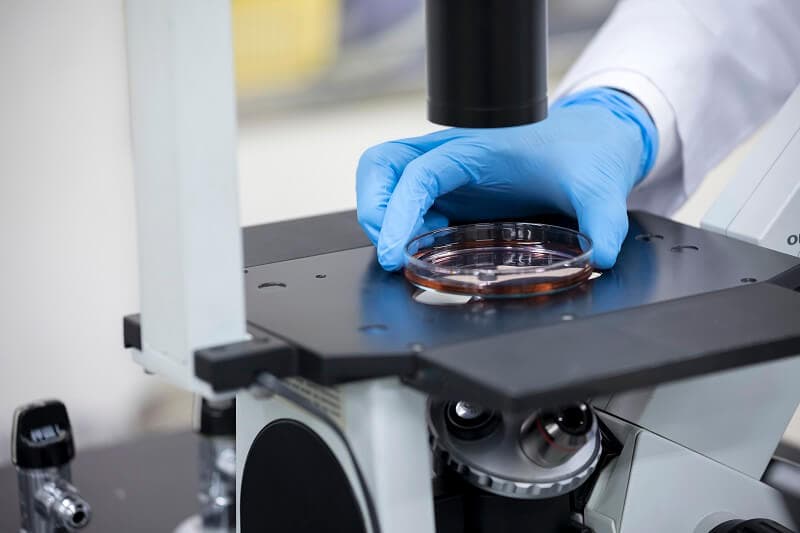
がん細胞のみに感染して増殖し、それを破壊する「腫瘍溶解性ウイルス」をご存じでしょうか。米国と豪州の研究チームが、ポックスウイルスを遺伝子改変した「CF33-hNIS (別称Vaxinia)」を開発。ウイルスが破壊したがん細胞から抗原が放出され、免疫系を刺激する効果もあるそうです。このほど、第1相試験でこの薬を1人目の患者に投与。少なくとも2つの標準治療を受けたことがある転移性または進行性固形がん患者計100人に試験を行う予定とのこと。ScienceAlertの記事です。

新型コロナで入院した患者に生じる長期的な影響が明らかになったようです。英国の研究チームが、2020年5月~21年3月に新型コロナで入院した患者159人を1年間にわたり追跡調査しました。8人に1人が後に心筋炎と診断されたそうです。全身炎症や臓器へのダメージにより、再度治療を受けた患者も多くいたといいます。退院後の体調を左右するのは、基礎疾患の有無ではなく、新型コロナ感染時の重症度だということも判明したそうです。iNewsの記事です。

各国で相次いで感染者が見つかっている「サル痘」は、サル痘ウイルスによる感染症です。潜伏期間は5日~3週間。患者のほとんどは発熱、体の痛み、悪寒、倦怠感といった症状で済むものの、悪化すると顔や手に発疹が現れ、全身に広がるようです。致死率は最高10%。感染者の体液や発疹に触れたり、飛沫を浴びたり、汚染された衣類、寝具に接触したりすることで感染します。性交渉を通じて感染が広がっている可能性が指摘されています。AP通信の記事です。

クランベリーを毎日食べると、記憶力や脳機能にプラスの影響があるようです。英国などの研究チームが、正常な認知機能をもつ50~80歳の参加者60人を調査。生のクランベリー100gに相当する量のフリーズドライクランベリー粉末を毎日12週間にわたって摂取した人は、体験した出来事の詳細な記憶や神経機能、脳の血流が改善することが分かったそうです。さらに、動脈硬化を引き起こすとされる悪玉コレステロールのレベルも低下したといいます。EurekAlert!の記事です。

米疾病対策センター(CDC)などの専門家は、各国で感染報告が相次いでいるサル痘について、「現時点で一般市民が差し迫った危険を心配する必要はない」と考えているようです。専門家は、アフリカ以外の国々で感染が確認されていることは極めて異常だと指摘。一方で、感染例は少なく、大規模な流行が起こる可能性は非常に低いとしています。サル痘には天然痘ワクチンが有効であるため、感染リスクの高い人に接種する用意もできているとのこと。CNNの記事です。

若い世代の急性心筋梗塞(AMI)を予防するためには、男女で戦略を変えた方がいいそうです。米国の研究チームが、55歳以下のAMI患者2264人と対照群2264人のデータを分析。女性において最もAMIに関連する危険因子は糖尿病で、次いで喫煙、うつ病、高血圧、低世帯所得などが続きました。一方男性は、喫煙とAMI家族歴が主な危険因子だったといいます。近年、特に若い女性のAMIが増えており、これらの危険因子を意識する重要性が指摘されています。ScienceDailyの記事です。
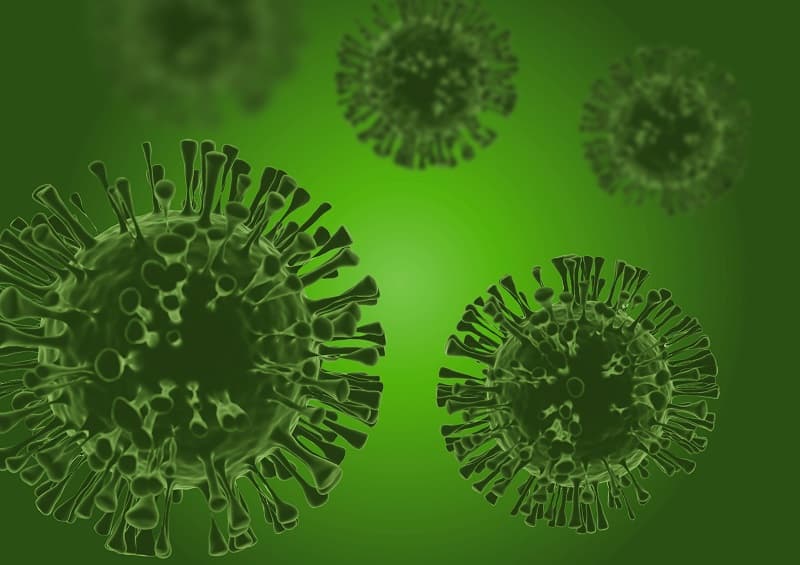
欧米で、中央・西アフリカで流行するサル痘の報告が相次いでいます。このAP通信の記事では、ロンドンで感染したとみられる男性4人について説明。全員がゲイやバイセクシャルで、アフリカへの渡航歴はなかったといいます。サル痘は感染動物の血液や体液に触れることで感染します。症状は発熱や筋肉痛から始まり、ひどくなると顔や性器に発疹が現れます。地域社会で濃厚接触による感染が広がっている可能性があるとのこと。現在、複数の国で感染者の報告が上がっています。

「低タンパク質食」はげっ歯類などの健康や寿命に好影響を及ぼすと考えられています。肝臓から分泌されるホルモン「線維芽細胞増殖因子21(FGF21)」が、この効果には不可欠であることが分かったそうです。米国の研究チームがオスのマウスで調査。FGF21遺伝子ノックアウトマウスに低タンパク質食を与えたところ、同じものを与えられた通常マウスに比べて老化が早く、自然寿命が短くなったといいます。メスのマウスにも当てはまるかは未確認とのこと。ScienceAlertの記事です。

北朝鮮で、新型コロナが原因とみられる発熱者の増加が止まらないようです。同国は5月18日、新たに23万2880人の発熱者と6人の死亡を確認したと発表。4月下旬以降、発熱者は累計で170万人を超え、死者は62人に上るそうです。国外の専門家は、そのほとんどがコロナ感染者で、死者数は少なく報告されている可能性があるとみています。また、同国はワクチンを調達しておらず、WHO(世界保健機関)からの援助の申し出も受け入れていません。AP通信の記事です。

米ノースウェスタン大学が筋萎縮性側索硬化症(ALS)新薬「NU-9」を開発中で、既存薬より有効な可能性があることが分かったそうです。チームは、ALS(SOD1遺伝子変異型)モデルマウスで薬の有効性を調査。NU-9には、異常が生じた上位運動ニューロンの軸索を伸ばす効果があることが判明したといいます。また、既存薬のリルゾールやエダラボンと組み合わせると、NU-9の効果が高まるとのこと。順調にいけば、2023年には第1相試験が行われる予定だそうです。Medical Xpressの記事です。

新型コロナの後遺症に苦しんでいる人は、コロナワクチンを打った方がいいかもしれません。英国の研究チームが、コロナ感染後に少なくとも1回ワクチンを接種した成人2万8356人のデータを分析しました。後遺症に苦しむ人の割合は、感染後にワクチンを1回接種すると13%減り、2回接種するとさらに9%減ることが分かったそうです。生物学的メカニズムを解明することで、後遺症治療薬の開発につながる可能性があるといいます。Medical Xpressの記事です。

トキソプラズマ原虫に感染すると、人の外見が変化する可能性があるようです。フィンランドの研究チームが、トキソプラズマ感染者35人と非感染者178人を比較。感染者は顔が左右対称である傾向が高いことが分かったそうです。別の実験で、同じ感染者と非感染者の顔写真を205人に評価してもらったところ、感染者の方が健康で魅力的に見えるとの結果が出たといいます。感染が内分泌系に与える影響が原因ではないかとの推測があるそうです。ScienceAlertの記事です。

テレビゲームは子どもの知能を高める可能性があるようです。スウェーデンの研究チームが、9~10歳の米国の子ども9855人を調査。子どもたちは1日平均1時間、テレビゲームをしていたそうです。2年後にこのうち5000人について調べたところ、テレビゲームに平均以上の時間を費やしていた子どもは、IQが平均的な上昇値より2.5ポイント高かったそうです。テレビ視聴やソーシャルメディア使用による知能への影響はみられなかったといいます。ScienceAlertの記事です。

インフルエンザによる心臓の合併症は、肺での激しい炎症が原因ではなく、心臓への直接感染で起こるようです。米国の研究チームが、心臓の細胞で複製できないウイルスをゲノム編集で作製。インフルエンザによる心臓の合併症を起こしやすいIFITM3遺伝子欠損マウスと通常マウスに、通常のウイルスとゲノム編集したウイルスを感染させて比較しました。その結果、心臓でウイルスが複製されなければ心臓の合併症は起きないことが分かったとのこと。ScienceDailyの記事です。

バクテリオファージ(ファージ)は細菌を殺すウイルスです。米国の研究チームが、1種類のファージを使い、薬剤耐性菌感染症の治療に成功したそうです。ある関節リウマチ患者が、薬剤耐性を獲得した細菌「マイコバクテリウム・ケロナエ」によって皮膚疾患を起こしていました。チームは「Muddy」と呼ばれるファージがその細菌に有効だということを突き止め、患者に投与しました。すると、感染が8カ月にわたって治まったそうです。Medical Xpressの記事です。

けがによる痛みを和らげるために薬で炎症を抑えると、かえって慢性的な痛みに苦しむことになるかもしれません。カナダの研究チームは、炎症の初期段階に深く関与する白血球の一種「好中球」が、痛みの解消に重要な役割を果たすことを発見。マウスの好中球を阻害したところ、通常の10倍も痛みが長引いたそうです。ジクロフェナクやデキサメタゾンといった抗炎症薬やステロイドの使用も、同様の結果につながったといいます。マギル大学が発表しました。

尿路感染症を抗菌薬で治療するという「常識」を見直す必要があるかもしれません。米国の研究チームが、再発性尿路感染症の女性15人とそうでない女性16人を調査しました。感染を繰り返す女性は健全な腸内細菌の多様性が低く、特に抗炎症作用のある「酪酸」を作り出す菌が少ないことが分かったそうです。尿路感染症治療のために使用した抗菌薬が腸内細菌叢の組成を乱し、再発の機会を増やしてしまう可能性が示唆されたとのことです。Health Europaの記事です。

寄生虫のトキソプラズマが目の網膜や脈絡膜に感染すると、組織が破壊され、著しい視力低下などの症状が出ます。豪州の研究チームが、1946~64年生まれで西オーストラリア州在住だった5000人以上の網膜画像を分析。推定150人に1人がこの疾患を持つことが判明しました。感染源は、感染した猫の糞や加熱不足の肉などで、母親から胎児にうつることもあります。豪州では赤身肉をレアで食べる人が多く、リスクを高める要因になっているそうです。ABC NEWSの記事です。

世界中で報告が上がっている原因不明の小児肝炎について、親はどのようなことに注意すればいいのでしょうか。症状として、まず現れるのは、ウイルス性疾患と同様の胃腸障害や発熱、倦怠感です。濃い色の尿、薄い色の便、皮膚や白目が黄色くなる黄疸が認められた場合は、至急医師に相談するべきだといいます。もし原因がアデノウイルスと関連しているのであれば、手洗いの徹底などの対策が予防につながるとのこと。CNNの専門科へのインタビュー記事です。

若さを保つには、糞便移植が有効かもしれません。英国の研究チームがマウスを使って調査。糞便移植を通じて若いマウスの腸内細菌叢を受け取った高齢マウスは、腸はもちろん、脳や目の老化に関連する有害作用が抑制されたそうです。逆に、高齢マウスの腸内細菌叢を受け取った若いマウスは、加齢による慢性炎症が関連するとされる脳の免疫細胞の過活動状態が起こり、目では網膜変性に関連するタンパク質の増加が認められたといいます。ScienceDailyの記事です。

新型コロナに関連する実際の死者数は、報告されているよりかなり多い可能性があるようです。WHO(世界保健機関)が、「超過死亡数」と呼ばれる指標を使って調査しました。その結果、世界で2020~21年にコロナ関連で死亡した人は1490万人に上ると推計されるそうです。しかし、各国から公式に報告されている同期間のコロナ関連死者数は計540万人だといいます。WHOは、多くの国がコロナ死者数を実際よりも少なく集計しているとみているとのことです。BBCの記事です。

今年1月に世界で初めてブタの心臓をヒトに移植する手術が行われ、移植を受けた男性が2カ月後に死亡しました。手術を担当した米メリーランド大学の教授が、移植された心臓が豚サイトメガロウイルスに感染していたことを発表。このことが患者の死に影響を与えたとみられるようです。臓器提供のために育てられた特別なブタは病原体を持たないと考えられており、事前のウイルス検査が不十分だった可能性を指摘する声もあるといいます。MIT Technology Reviewの記事です。

米疾病対策センター(CDC)は、世界中から報告が上がっている原因不明の小児肝炎について、患者109人の調査を進めているそうです。このうち14%が肝移植を必要とし、5人が死亡。90%以上の子どもが入院したといいます。また、50%以上の患者からアデノウイルスが検出されたそうです。同国や英国の調査から、胃腸炎を引き起こすアデノウイルス「41F型」がこの肝炎に関連している可能性が指摘されていますが、他の要因も含め引き続き調査中とのこと。CNNの記事です。

遺伝的要因が健康や社会的な結果に及ぼす影響は、過大評価されている可能性があるようです。英国やノルウェーなどの研究チームが世界の19の研究から、きょうだい関係にある計17万8076人の遺伝的特徴、学歴、健康に関するデータを分析。学歴、最初の子どもを持つ年齢、うつ病などの社会的特性は、家庭や社会環境に強い影響を受けることが分かったそうです。逆にBMIなどの生物学的な面は、家庭や社会的影響を受けにくいことのこと。Medical Xpressの記事です。

60歳以上の人は心血管イベントを予防する目的で新たにアスピリンを常用し始めるべきではないそうです。米予防医学専門委員会は、60歳以上の人がアスピリンを常用してもメリットはなく、むしろ胃腸や脳における出血リスクが高まると結論付けたことを発表。ただし、心臓発作や脳卒中の既往歴がある人は対象外だそうです。また、既にこの薬を常用している人に服用の中止を求めるものではなく、医師と相談して決めるべきだとしています。nprの記事です。

バイアグラなどの一般的な勃起不全(ED)治療薬を日常的に使っている人は、眼疾患に注意が必要かもしれません。カナダの研究チームが、米国人男性21万3000人の診療報酬明細書を分析。ED治療薬を常用し始める前の年には、深刻な眼疾患を持つ人はいませんでした。調査の結果、ED治療薬の常用者は、深刻な眼疾患である「漿液性網膜剝離」「網膜血管閉塞症」「虚血性視神経症」のうちの一つを発症するリスクが85%高くなることが分かったそうです。Medical Xpressの記事です。

非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)の治療に有効な物質が発見されたそうです。思春期の開始や生殖機能に関わるタンパク質「キスペプチン」です。米英の研究チームが、西洋食を与えて肥満とNAFLDの状態にしたマウスで調査。マウスにキスペプチンを与えると、脂肪肝や非アルコール性脂肪肝炎(NASH)、線維症の発症が抑制されたそうです。肝細胞のキスペプチン受容体「KISS1R」を欠損させた西洋食のマウスは脂肪肝になることも明らかになったといいます。 EurekAlert!の記事です。
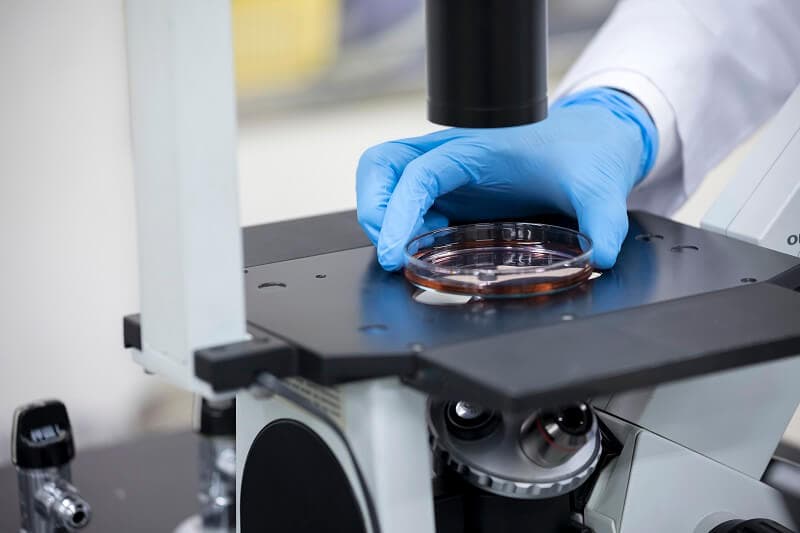
損傷した肝臓を素早く修復させる方法が見つかったようです。米国の研究チームが、四つの細胞リプログラミング因子(Oct-3/4, Sox2, Klf4, c-Myc)の効果をマウスの肝臓で調査。この因子は、iPS細胞を作る際に用いる山中伸弥・京都大学教授らが発見した「山中ファクター」です。この因子を使ってマウスを1日だけ治療したところ、細胞増殖が促され、肝組織の再生につながったとのこと。マウスの寿命の1/3にあたる9カ月間、腫瘍の発生もなかったそうです。Medical Xpressの記事です。

心臓弁膜症の一つである「大動脈弁狭窄症」がある高齢者は、カルシウムサプリメントを控えた方がいいようです。オーストリアの研究チームが、軽~中度の大動脈弁狭窄症患者2657人を平均5.5年以上調査。患者の平均年齢は74歳だったそうです。カルシウムとビタミンDのサプリを摂取していた人は、全死因死亡リスクが31%上昇し、心血管関連死リスクは倍増したといいます。カルシウムだけを摂取した人も全死因死亡リスクが24%上昇したとのこと。Medical Xpressの記事です。

「高用量ビタミンD」「オメガ3」「簡単な運動」の三つを組み合わせることで、高齢者のがんを抑制できるようです。スイスの研究チームが、欧州5カ国から参加した70歳以上の健康な高齢者計2157人を、ビタミンD、オメガ3、運動の組み合わせなどで八つのグループに分けて3年間調査。サプリメントで「ビタミンD3を2000IU」「オメガ3を1g」毎日摂取した上で、簡単な運動を週3回行った人は、浸潤がんのリスクが61%低くなったそうです。EurekAlert!に紹介されています。

喫煙は肺がんの主因とされるのに、喫煙者の一部しか肺がんを発症しないのはなぜなのでしょうか。米国の研究チームが、最新の全ゲノムシーケンシング技術を使って、喫煙経験がない14人と喫煙者19人の肺胞上皮細胞を調査。がんにつながるDNA突然変異の蓄積は、ヘビースモーカーほど多いわけではないことが判明したそうです。一部の人が、突然変異の蓄積を抑制するメカニズムを持ち合わせている可能性が示唆されたといいます。MedicalBriefの記事です。

英国の研究チームが、全ゲノムシーケンシングなど各種の方法を用いて、前立腺がん患者と非前立腺がん患者計600人以上の尿や組織を分析。進行性前立腺がんに関連するとみられる5種類の嫌気性菌を特定することに成功したそうです。Anaerococcus、Peptoniphilus、Porphyromonas、Fenollaria、Fusobacteriumのいずれかの細菌がサンプルから発見された患者は、進行性のがんの可能性があるとのこと。研究者は今回の発見を、前立腺がんの予防や治療につなげたいと考えているようです。Health Europaの記事です。

ジカ熱の大流行が懸念されています。メキシコの研究チームが、ジカ熱の原因であるジカウイルスのアミノ酸がたった一つ変異するだけで、人間や蚊、マウスの細胞においてウイルスの複製が増加し、感染が起こりやすくなることを発見。また、生物学的に似ているデングウイルス(デング熱の原因)に感染するとジカウイルスにも有効な免疫ができますが、この変異株はそれもすり抜ける可能性があることがマウスの実験で分かったといいます。Forbesの記事です。

新型コロナウイルスの「XE」と呼ばれる新たな系統をご存じでしょうか。XEはオミクロン株のBA.1とBA.2が組み合わさったウイルスで、1月中旬に英国で初めて発見されました。今のところ、オミクロン株の一種として扱われています。英国の研究では、感染力はBA.2を5~10%上回ると推計され、オミクロン株の中では最も感染力が高いと考えられています。現時点では、過度に恐れる必要はないとのこと。ScienceAlertの記事です。4月11日に日本でも感染者が初確認されました。

腸内細菌叢が糖尿病治療の鍵を握っているかもしれません。米国とオランダの研究チームが、肥満及び2型糖尿病の状態にしたマウスに抗生物質を投与し、腸内細菌叢を再構成しました。抗生物質を投与したマウスは、そうでないマウスに比べてインスリン感受性が高まり、膵臓の大きさや消化管ホルモンの分泌も正常レベルに戻ったといいます。インスリン感受性については、痩せたマウスでも抗生物質の投与で高まることが確認されたとのこと。EurekAlert!の記事です。

睡眠が不足すると、心疾患や代謝異常の原因となる内臓脂肪が付きやすくなる可能性があるそうです。米国の研究チームが、肥満ではない健康なボランティア12人を調査。2週間にわたって睡眠を1日4時間に制限された人は、腹部脂肪の総面積が9%増え、腹部内臓脂肪は11%増加したそうです。睡眠時間を戻しても、体重は減るのに内臓脂肪は増え続けたといいます。また、睡眠時間が短い人ほど1日の摂取カロリーが多いことも分かったとのこと。ScienceAlertの記事です。

米カリフォルニア州のBionaut Labs社が、脳内に入り込んで患部を直接治療できる小型ロボットを開発したそうです。大きさは数ミリメートルで、頭の外側に設置した磁気コイルをコンピューターにつなぎ、遠隔操作で脳の特定の領域に誘導できます。ヒツジやブタの実験では安全性が確認されているといいます。米食品医薬品局(FDA)は、ダンディー・ウォーカー症候群と悪性神経膠腫に対する臨床試験の実施を認めており、2年以内に開始予定とのこと。Medical Xpressの記事です。

心臓病患者の不眠症には注意が必要なようです。ノルウェーの研究チームが、心臓発作や閉塞した動脈の処置から平均16カ月経過した患者1068人を調査。45%の人が不眠症に苦しんでおり、24%の人が「過去1週間に睡眠薬を使用した」と答えたそうです。平均4.2年の追跡調査期間中に、1068人中225人の患者に計364回の主要有害心血管イベント(MACE)が発生。分析によると、参加者が誰も不眠症を患っていなければ、MACE再発の16%を回避できる可能性があるとのこと。News-Medical.Netの記事です。

言語の理解に関わる左側頭葉がないのに、普通に会話ができる女性がいるそうです。米国の研究チームが、左側頭葉がない50代女性の脳をfMRI で調査したところ、全ての言語処理が右脳で行われていることが判明。女性は幼い頃に脳卒中で左側頭葉を失い、それを補うために右脳で言語機能が発達したようです。女性の女きょうだいも同様に、右側頭葉がないのに脳機能障害はない状態とのことで、遺伝的要素が関係している可能性があるそうです。Medical Xpressの記事です。
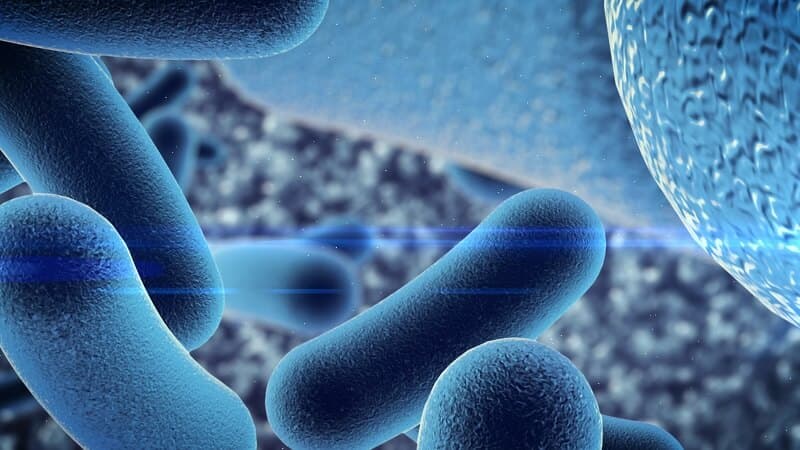
腸内細菌は脳に直接作用するようです。フランスの研究チームが、細菌の細胞壁の主要成分で細菌増殖の指標となる「ムロペプチド」と、それを検出する動物細胞の「NOD2受容体」に着目。マウスの脳を調査したところ、視床下部の神経細胞がNOD2受容体を発現させることが分かりました。視床下部は本能行動の中枢で、自律神経や内分泌と深く関わる領域です。ムロペプチドを視床下部の神経細胞が検出することで食欲や体温が調節されるといいます。ScienceDailyの記事です。

新型コロナウイルスは、呼吸器から排除された後も腸に存在し続ける可能性があるそうです。米国の研究チームが、コロナ軽~中等症と診断された患者110人を追跡調査。肺にはウイルスが残っていないのに便からウイルスのRNAが見つかった人が、診断から4カ月後に13%おり、診断から7カ月後には4%いたそうです。このことが腹痛や吐き気などのコロナ後遺症に関連している可能性もあるといいます。便から他者に感染する可能性は低いとのこと。Medical Xpressの記事です。

太り過ぎが子宮がんリスクを上昇させるようです。英国の研究チームが、世界7カ国の女性計12万人の遺伝子を分析。このうち1万3000人が子宮がんだったといいます。そして、BMIが5増加するごとに、子宮体がんリスクが88%上昇することが分かったそうです。肥満と子宮がんリスクを関連付ける可能性がある14のマーカーについて調べたところ、空腹時インスリンとテストステロンという2種類のホルモンの関与が指摘されたとのことです。Medical Xpressの記事です。

原因不明の小児肝炎が、英国をはじめとする欧州や米国で相次いで報告されているようです。英国では1月以降、4月19日までに74症例を確認。肝臓移植が必要なほど重症化した子どももいたといいます。患者からは肝炎を引き起こす一般的なウイルスは検出されていないそうです。未確定段階ですが、胃腸炎を引き起こす「アデノウイルス41型」が原因として疑われているとのこと。なお、新型コロナワクチンとの関連はないとみられています。AP通信の記事です。

心血管の健康を改善すると、高齢者のうつを抑制できるかもしれません。スペインの研究チームが、太り過ぎの人を対象に地中海式ダイエットの効果を評価した研究のデータを分析。対象者は心血管や内分泌疾患のない6545人で、男性は55~75歳、女性60~75歳でした。心血管リスクとうつの状態を評価したところ、心血管リスクの高さがうつ症状のリスクを高めることが分かったそうです。これは特に女性に顕著だったとのことです。EurekAlert!の記事です。

何かを無性に食べたくなる時は腸内細菌が関与しているかもしれません。米国の研究チームが、腸内細菌を持たないマウス30匹に、食生活が違う3種類の野生げっ歯類から採取した腸内細菌を移植。複数の餌を与えたところ、各グループが異なる栄養素を含む餌を選んだそうです。また餌を与える前の血液検査では、ヒトの必須アミノ酸で腸内細菌からも産生されるトリプトファンの値がグループ間で異なっていたといい、関連性が指摘されています。EurekAlert!の記事です。

米ミシガン大学が超音波を使った非侵襲的がん療法「ヒストトリプシー(histotripsy)」を開発し、ラットの実験で肝臓がんを消滅させることに成功したそうです。チームはラット22匹に肝臓がんを移植。このうち11匹に対して、腫瘍の50~75%を標的としてヒストトリプシーで治療したそうです。治療を受けたラットのうち9匹は腫瘍が完全に退縮し、観察を続けた3カ月間、再発や転移もみられなかったといいます。対照群は全11匹でがんが進行したそうです。ScienceAlertの記事です。

英国の研究チームがiPS細胞技術を応用し、53歳女性の皮膚細胞を30歳も若返らせることに成功したそうです。iPS細胞を作る際、通常は体細胞を特殊な化学物質に50日間浸します。しかし、今回の研究では12日間に短縮。すると皮膚細胞は幹細胞になるのではなく、23歳相当に若返ったといいます。チームは最終的に、人間の健康寿命を延ばすことを目標にしています。ただ、安全性のほか、他組織にも応用可能かどうかなど課題が残されています。BBCの記事です。

マジックマッシュルームに含まれる幻覚成分「サイロシビン」が、脳の領域間の信号伝達(接続性)を長時間にわたって高めるようです。英国の研究チームが、うつ病患者60人の脳画像を分析。サイロシビンを摂取した患者は、標準的な抗うつ薬を摂取した患者と違って脳領域間の接続性が向上することが明らかになりました。効果は摂取した時だけでなく、最大3週間持続。さらにうつ病症状の改善と相関関係があることも分かったといいます。EurekAlert!の記事です。

塩の摂取を控えても、心不全の重症化を防ぐことはできないようです。カナダの研究チームが、心不全患者806人を1年間にわたり調査。減塩食に関する栄養指導を受けた人は、1日のナトリウム摂取量がティースプーン1/4杯ほど減ったといいます。それにもかかわらず、死亡率や入院率については、摂取量を減らさなかった群と比べて有意差はみられなかったそうです。ただし、腫れや疲労感などの症状と生活の質には改善が認められたとのこと。EurekAlert!の記事です。

非ホルモン性の男性用経口避妊薬(ピル)の治験が年内に始まるようです。米ミネソタ大学が、精子の形成などに重要な役割を果たすタンパク質「レチノイン酸受容体アルファ(RAR-α)」に着目。RAR-αのみを標的とする化合物「YCT529」を開発したそうです。これをオスのマウスに4週間経口投与したところ精子数が激減。交配試験での妊娠予防効果は99%に達したといいます。明らかな副作用は認められず、投与中止から4~6週間で生殖能力は回復したとのこと。ScienceAlertの記事です。

新型コロナが流行する中、ムコール症の感染拡大がインドで突出しています。なぜなのでしょうか。米国の研究チームによると、ムコール症を引き起こす真菌は牛の糞(ふん)に豊富に含まれ、それが原因とみられるそうです。インドでは、伝統的な儀式や病気の治療に牛の排泄物が使われるそうです。糞を燃やした煙が真菌を拡散させることが考えられるほか、近年はコロナの治療や予防のために牛の糞が多く使われている可能性があるとのこと。Medical Xpressの記事です。

米国の研究チームが、コーヒーを飲んでから数分後に便意をもよおす理由を分析したようです。過去の研究は、カフェイン以外の成分が突然の便意をもたらす可能性を示唆。コーヒーを飲んでから4分以内に腸の運動が活発になることから、コーヒーの成分が腸ではなく胃の内壁を介して神経系またはホルモンに作用していると考えられるそうです。コーヒーが腸運動の促進につながるホルモン「ガストリン」の分泌を促す可能性もあるといいます。CNNの記事です。

アルツハイマー病の治療や予防のヒントになる可能性がある遺伝子が新たに発見されたそうです。英国の研究チームが、アルツハイマー病と診断された患者111,326人と認知機能が正常な人677,663人の遺伝子を比較。アルツハイマー病リスクを上昇させる75の遺伝子が特定され、このうち42は新たに発見されたものだったといいます。今回見つかった遺伝子は炎症や免疫システムに関連するものが多く、治療の新たな標的になる可能性が示唆されています。CNNの記事です。

グルテンフリー食品などに使われる添加物「キサンタンガム(E415)」は当初、人体では消化されないと考えられていました。しかしノルウェーなどの研究チームが、腸内細菌のルミノコッカス科の一種がE415を消化できるように変化し、またバクテロイデス属の細菌もE415の消化に関与することを発見したそうです。これらの変化は西洋式の食事をする人にのみみられるとのこと。健康影響の有無は不明ですが、腸内細菌叢は変化する可能性があるようです。Medical Xpressの記事です。

米国の首都ワシントンの連邦議会議事堂周辺で9人がキツネにかまれ、そのキツネが狂犬病ウイルスに感染していたことが分かったそうです。アミ・ベラ下院議員が、散歩中に突然キツネに襲われたとの被害を報告。他に少なくとも8人の被害が確認されているといいます。キツネは程なく捕獲され、安楽死させられたそうです。その後の検査で、狂犬病ウイルスの陽性が判明したとのこと。当局は被害者全員と連絡を取っているといいます。INSIDERの記事です。

新型コロナから回復した後も、血栓症や出血に注意が必要なようです。スウェーデンの研究チームが、2020年2月1日~21年5月25日に新型コロナに感染した100万人と感染しなかった400万人のデータを分析。コロナ感染から、60日間は出血▽90日間は深部静脈血栓症▽180日間は肺塞栓症――を起こすリスクが高まることが分かりました。第1波で重症だった患者は、これらのリスクが最も高かったそうです。血栓症のリスクは軽傷者でも高まるとのこと。EurekAlert!の記事です。

女性の7人に1人が悩まされる「産後うつ」の原因解明に一歩近づいたようです。米国の研究チームが、産後6週間以内の女性1500人の血液を調査。このうち482人が産後うつと診断されていたといいます。RNAシーケンシングや遺伝子型判定などを使って血液成分を分析したところ、産後うつ女性のB細胞に著しい「違い」が認められたとのこと。さらなる解析で、B細胞の活性化の変化とインスリン抵抗性が関与していることが示唆されたそうです。Medical Xpressの記事です。
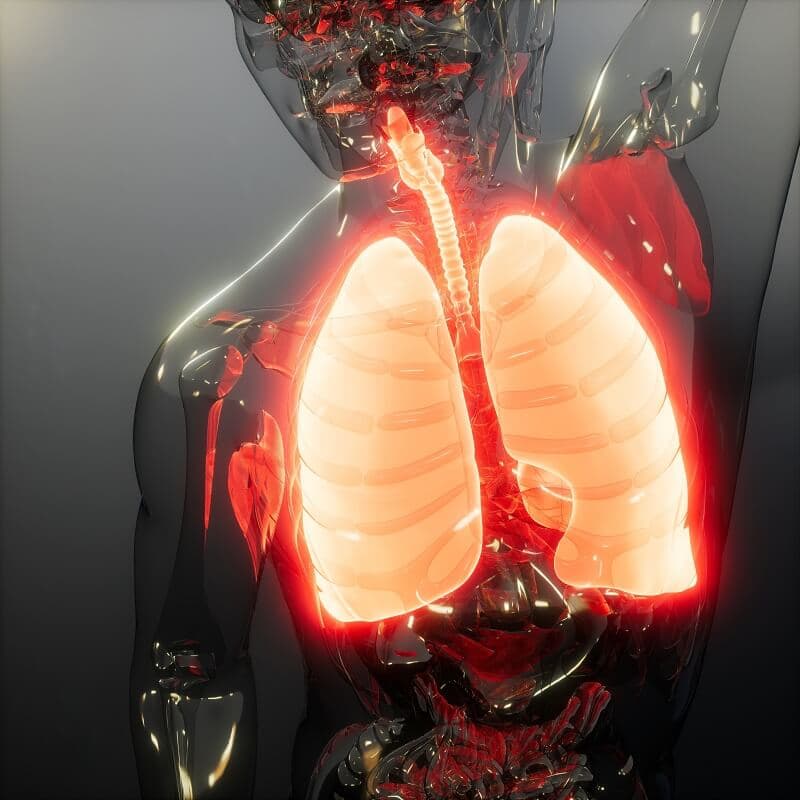
新たな細胞がヒトの肺で発見され、慢性閉塞性肺疾患(COPD)の治療法改善につながる可能性があるそうです。米国の研究チームが、幹細胞に似た性質を持つ「呼吸器気道分泌細胞(RAS細胞)」をヒトの細気管支で発見。RAS細胞には細気管支内の水分を保持する役割があるといいます。また、肺胞2型細胞の前駆細胞として働き、傷ついた肺胞を修復する役目も持つとのこと。喫煙によるRAS細胞の破壊が、COPD発症につながっている可能性があるそうです。ScienceAlertの記事です。
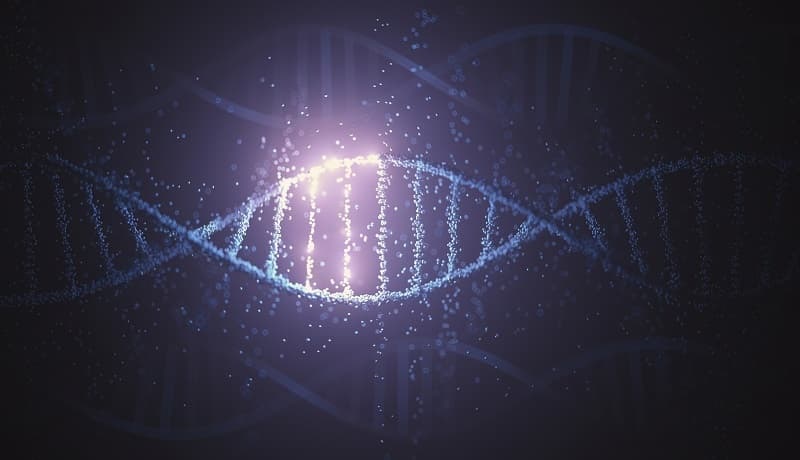
人間の設計図とも言えるヒトゲノム配列の全貌がついに明らかになったようです。各国の研究者で構成される国際チームが、31億塩基対からなるヒトゲノム配列を初めて完全に解読したと発表。これまでに分かっていたゲノム配列は完全なものではなく、約8%が解読できていなかったといいます。今回の完全解読が、老化や神経変性疾患、がんなど様々な分野における医学的進歩への道を開くカギになることが期待されています。AP通信の記事です。

左右の耳で異なる周波数の音を流す「バイノーラルビート」は不安やうつ症状を緩和するという報告があります。これを「デジタルドラッグ」として使用する人がいるようです。豪州と英国の研究チームが、22カ国から参加した計3万人のデータを分析。約5%がバイノーラルビートの経験者だったそうです。その多くは10代後半から20代前半の若者で、禁止薬物を使用した経験があったとのこと。経験者の1割が娯楽目的での使用だったといいます。ScienceAlertの記事です。

米国の研究チームが、膵島の長期凍結保存を可能にする技術を開発したそうです。膵島は糖尿病患者に移植することがありますが、これまでの技術ではドナーから採取した膵島を安全に保存できるのは48~72時間でした。チームは凍結保存する際の余分な液剤を取り除くことで、膵島の急速な冷凍及び解凍に成功。この方法で凍結保存された膵島は9カ月後でも87%が生存しており、齧歯類へ移植したところ正常に機能することが確認されたようです。Medgadgetの記事です。

健康な人に敢えて新型コロナウイルスを感染させるヒューマンチャレンジ試験が世界で初めて行われたそうです。英国の研究チームが、18~30歳でコロナ重症化リスク因子を持たない参加者36人をコロナに感染させ、経過を観察。咳などから生じるわずか10ミクロンの飛沫で、コロナに感染することが分かったといいます。患者は感染から2日後にはウイルスを排出し始め、たとえ無症状だとしても平均6.5日間、最長12日間排出が続いたとのこと。Medical Xpressの記事です。

オフィスや公共空間の照明を変えるだけで、新型コロナウイルスの感染を抑制できるかもしれません。カナダの研究チームが、ある液滴を作製。公共の場で人がコロナウイルスやエイズウイルス(HIV)に暴露する環境に似せたものです。これを紫外線LED(UV-LED)ライトに30秒当てたところ、ウイルスの感染力が93%低下したそうです。UVは人体に無害ではないため、人がいる時は白色光、誰もいない時にはUVライトに自動的に切り替わるUV-LED照明を開発中とのこと。Medical Xpressの記事です。

米国の映画俳優ブルース・ウィリスが引退を表明しました。その理由である「失語症」を知っていますか。失語症は、後天的に言語になんらかの問題が生じる状態を指すそうです。もっとも一般的な原因としては、脳卒中や頭部損傷が挙げられるといいます。「聞く」「話す」「読む」「書く」能力に障害が起こる可能性があるものの、通常は知能には影響を及ぼさないとのこと。2016年の調査では、失語症を知っている人は9%未満だったそうです。ScienceAlertの記事です。

英国では来年にも、医薬品が患者個人の遺伝的性質に合うかどうかを調べる遺伝子検査が、国民保健サービス(NHS)で無料で受けられるようになるかもしれません。医薬品は、個人の体質によって効果が出なかったり、有害事象を引き起こしたりします。英国では、国内で多く処方されている100の医薬品のうち40について、遺伝子検査を提供する技術が既に存在しています。現状では検査は約100ポンドで、血液か唾液のサンプルを使用するといいます。BBCの記事です。
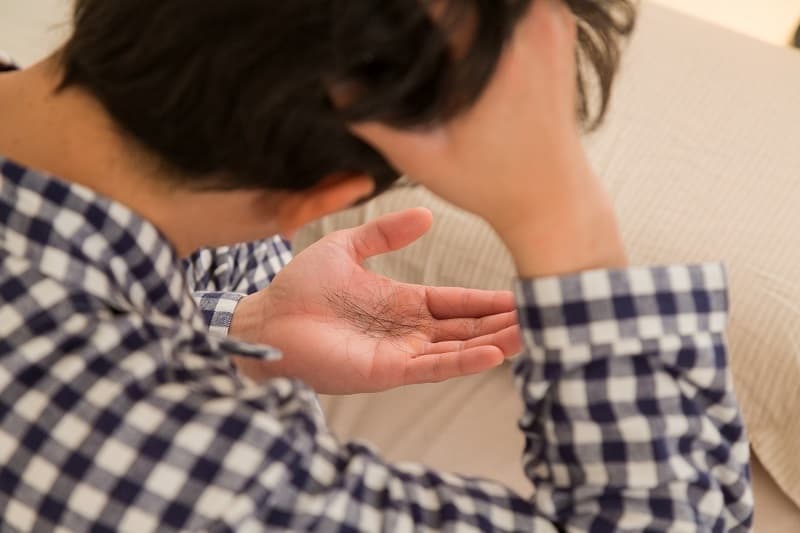
関節炎治療薬「バリシチニブ」の円形脱毛症に対する有効性が明らかになったようです。米エール大学などが、円形脱毛症患者1200人を対象に第3相試験を実施。バリシチニブ4mgを36週間服用した人の35%において、脱毛が有意に改善したといいます。服用量が2mgの場合でも、20%の人に同様の効果が確認されたそうです。吹き出物の悪化、上気道感染症、頭痛などの副作用がみられたものの、そのほとんどが許容できる範囲のものだったとのこと。ScienceAlertの記事です。

新型コロナの後遺症の一つとして、糖尿病を念頭に置くべきかもしれません。米国の研究チームが、感染者18万人と対照群のデータを比較。感染者は、感染から1年後に糖尿病を発症するリスクが40%高かったそうです。感染者の100人に2人が新たに糖尿病と診断されることが見込まれるといいます。コロナ感染時に重症だった人ほど、糖尿病リスクも上昇することが指摘されています。リスクは、糖尿病の危険因子がない人でも上がるそうです。CNNの記事です。

パートナーの妊娠を希望している男性は、2型糖尿病治療薬「メトホルミン」の使用に注意した方がいいかもしれません。デンマークの研究チームが、1997~2016年に同国で生まれた子ども100万人以上のデータを分析しました。出生時に母親が35歳未満、父親が40歳未満の子どもを対象にしたそうです。母親の妊娠直前の3カ月間に父親がメトホルミンを使用していると、生まれた子どもの先天性欠損症リスクが40%高くなることが分かったといいます。CNNの記事です。

人工甘味料の安全性を巡って議論が起きています。フランスの研究チームが、同国に住む10万3000人のデータを分析。人工甘味料を平均量より多く摂取すると報告した人は、全く摂取しないとした人に比べてがん発症リスクが13%高かったとの結果を発表しました。特にソフトドリンクに使われる人工甘味料が高リスクだったとしています。これに対し、「人工甘味料ががんの原因になる」ことを示す証拠としては不十分であるとの指摘が出ています。ScienceAlertの記事です。

米ニューヨーク幹細胞財団(NYSCF)が、Google社と共同でパーキンソン病の特徴を特定する新たなプラットフォームを開発したそうです。NYSCFは、ロボットシステムを使ってパーキンソン病患者91人と健康な人の皮膚から採取した線維芽細胞の画像を100万枚以上作成。人工知能(AI)を使ってこれらの画像を分析することで、パーキンソン病の新たな特徴の特定に成功したそうです。この研究が、パーキンソン病の新薬発見につながることも期待されているといいます。EurekAlert!の記事です。
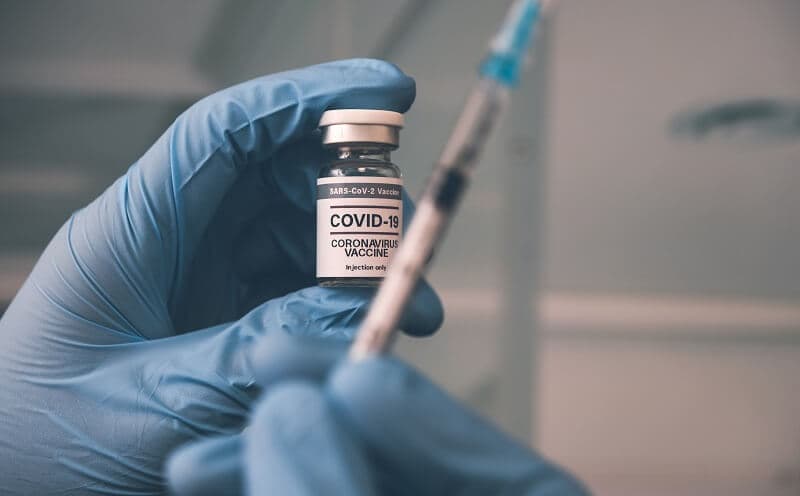
米モデルナ社が新型コロナワクチンについて、6歳未満への有効性に関する中間結果を公表したそうです。結果は生後6カ月~5歳の子ども6900人のデータに基づくもの。この年齢の子どもにワクチン25㎍を2回投与したところ、18~25歳の成人に100㎍を2回投与した場合と同様の免疫反応が確認されたといいます。重篤な副反応はほとんどみられなかったとのこと。同社は近く米食品医薬品局(FDA)にこの年齢に対する緊急使用許可を申請するそうです。CNNの記事です。

米国の研究チームが、治療用の大腸菌(E. coli)を使って、がん細胞を殺すことに成功したそうです。チームは、細菌が一時的に免疫系から感知されないようにする「遮蔽システム」を開発しました。細菌の表面に存在し、免疫系などの攻撃から身を守る莢膜多糖体(CAP)に着目。CAPを制御することで、大腸菌(E. coli)がヒトの血液中で生存できる時間を調節できるようになったそうです。マウスを使った実験では、腫瘍に薬剤を効果的に送達できたといいます。Medical Xpressの記事です。

結核菌に感染したことがあると、新型コロナウイルスに感染しにくくなるかもしれません。米国の研究チームが、2種類の系統のマウスを使って調査した結果です。マウスをまず結核菌に感染させ、次に新型コロナウイルスに暴露させました。その結果、事前に結核菌に感染させたマウスには、コロナ感染の兆候がみられなかったといいます。結核菌に対する免疫反応が、新型コロナウイルスの肺での急速な増殖を防いだ可能性が指摘されています。EurekAlert!の記事です。

腸内細菌叢と脳は深く関係しているとの指摘があります。腸内細菌叢を変えてしまう抗生物質の使用は認知機能に影響を及ぼすかもしれません。米国の研究チームが、平均年齢54.7歳の女性看護師1万5129人のデータを分析。抗生物質を2カ月以上服用していた人は、全く飲んでいない人や服用期間が短い人に比べて、抗生物質の使用から7年後に実施した認知テストのスコアが低かったそうです。約3~4歳老化したのと同等の低さだったといいます。Medical Xpressの記事です。
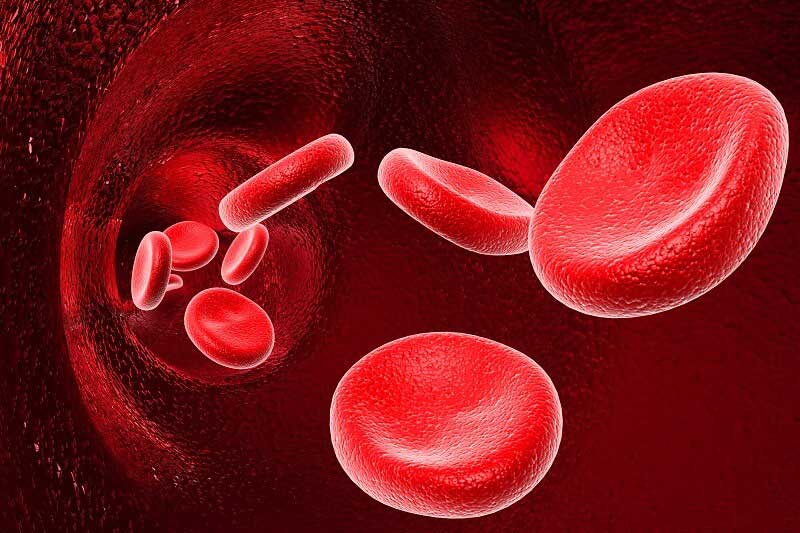
血液脳関門を思い通りに開き、薬剤を脳内に届けることができるようになるかもしれません。米エール大学が、重要な細胞プロセスを調節する「Wntシグナル経路」に着目。成体のマウスを使って、この経路のカギとなる受容体「Unc5B」を阻害したところ、血液脳関門が開いたままになったそうです。Unc5Bは「ネトリン-1」という物質が結合することによって働きが制御されます。最終的に、ネトリン-1をブロックする抗体の開発に成功したといいます。ScienceAlertの記事です。

新型コロナウイルスオミクロン株の影響で中国や香港では患者が急増しています。その中で、感染を厳しく抑え込む「ゼロコロナ政策」はいつまで持ちこたえられるのでしょうか。同国はこれまで、軽症患者でも病院に入院させていました。しかし、最近になって、軽症患者は専用施設に隔離するようルールを緩和。退院の基準も引き下げられました。ゼロコロナに対する国民の理解が得られなくなってきていると指摘する専門家もいるといいます。BBCの記事です。

検査以外に、新型コロナをインフルエンザと見分ける方法はあるのでしょうか。コロナとインフルエンザは両方、発熱、倦怠感、体の痛み、喉の痛み、下痢や嘔吐などの症状が出ます。ただし、頭痛や乾いた咳がある場合はコロナを疑ってもいいかもしれません。味覚や嗅覚の異常も、引き続きコロナの特徴的な症状として挙げることができるといいます。乾いた咳が悪化し、ひどい胸の痛みがある場合は病院を受診した方がいいそうです。CNNの記事です。

エボラウイルス病の原因であるエボラウイルス属は六つの型に分類されます。そのうち、大規模な流行を引き起こし、致死率が高いことで知られるザイール型とスーダン型。この両方に有効な抗体カクテルが開発されたそうです。米国の研究チームが、エボラ生存者のサンプルから、2種類のモノクローナル抗体1C3と1C11を作製。サルにおいて、この二つを組み合わせた抗体療法がザイール型とスーダン型による深刻な症状を改善したといいます。Medical Xpressの記事です。

発高齢者の昼寝の頻度や時間が大幅に増えたら、医師に相談した方がいいかもしれません。米国の研究チームが、74~88歳の高齢者1400人から14年にわたって集めたデータを分析。1日1回以上昼寝をする人や1日1時間以上昼寝をする人は、昼寝が毎日の習慣ではない人や1日の昼寝時間が1時間未満の人に比べてアルツハイマー病を発症するリスクが40%高かったそうです。夜間睡眠の質や量は、この結果に影響を与えなかったといいます。CNNの記事です。

双極性障害やうつ病患者の気分安定薬として使われるリチウムが、認知症の発症を予防する可能性があるようです。英国の研究チームが、メンタルヘルスの問題で受診した50歳以上の患者2万9618人のデータを分析。患者はみな認知症の既往歴はなかったといいます。リチウムを服用していた患者は548人おり、そのうち9.7%が認知症と診断されたそうです。一方、リチウムを服用していなかった2万9070人においては、11.2%が認知症と診断されたとのこと。News-Medical.Netの記事です。
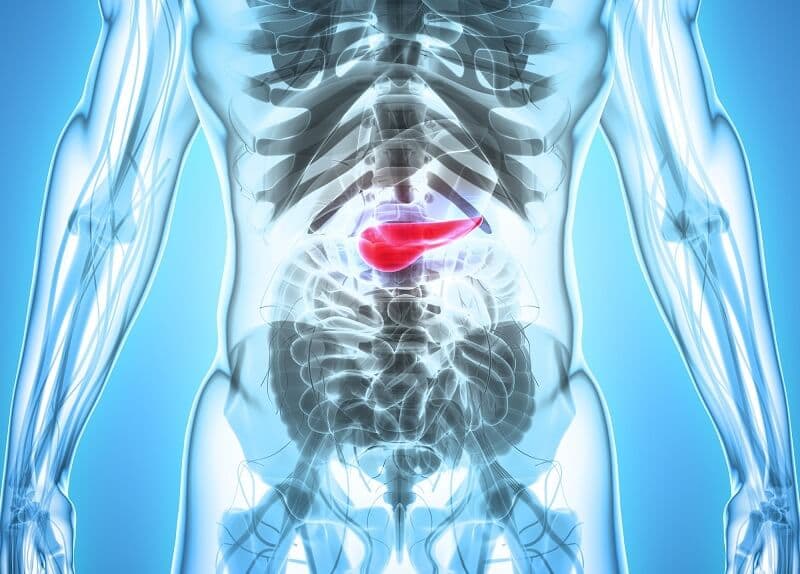
血中アミロイドβ(Aβ)レベルをアルツハイマー病(AD)の診断マーカーとして使う際は、食事の影響に注意が必要かもしれません。大阪市立大学がマウスを使って調査。血中Aβは、グルコースやインスリンの刺激により膵臓や脂肪組織などの末梢組織から分泌されることが分かったそうです。分泌されたAβがインスリン分泌を抑制することも判明したといいます。今回の結果は、2型糖尿病がADのリスク因子となるメカニズムを示唆しているとのこと。Medical Xpressの記事です。

うつ病になりやすい人は、人との関係が良くない状況に陥った際、ふさわしくない行動を取ることが多いようです。英国の研究チームが、うつ病寛解後に薬が不要になった76人と、うつ病既往歴がない44人にアンケートを実施。うつ病が寛解した人は対照群に比べて、自分が親友に対して悪いことをしたと仮定した場合に、隠れたい気持ちや自分自身から距離を置きたい気持ちになる傾向が強かったそうです。その反面、謝ろうとする人は少なかったとのこと。PsyPostの記事です。

大麻草に含まれるカンナビノイドやキノコの抽出物を組み合わせた、大腸がん治療薬の開発が進んでいるようです。この薬はイスラエルのバイオテクノロジー企業であるCannabotech社の製品。大腸がんのモデル細胞を使った研究では、この「組み合わせ製品」は、カンナビノイドを単体で使うより大腸がんの治療に有効なことが分かったそうです。さらに、この製品を使うと大腸がん細胞の90%以上を破壊できることも明らかになったといいます。Health Europaの記事です。

発症すると半年から2年で死に至るクロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)。英国の研究チームが開発している治療薬が、初期研究で有望な結果を示したそうです。この薬は「PRN100」と呼ばれるモノクローナル抗体。CJD患者6人に投与したところ、薬は安全で、脳まで到達することが分かったそうです。最終的に全員が死亡したものの、患者3人においては一時期、病気の進行が安定したようにみえたといいます。副作用を報告した人はいなかったそうです。Medical Xpressの記事です。

豪州の研究チームが開発した自閉症のスクリーニング法「SACS-R」の精度の高さが明らかになったようです。チームは、13,500人以上の子どもを対象に5年にわたる調査を実施。生後12~24カ月時点でSACS-Rで自閉症の可能性を指摘された子どものうち、83%がのちに実際に自閉症と診断されたそうです。豪州の一部の州ではすでに乳幼児健診でSACS-Rが使用されており、日本を含む10カ国で導入に向けた専門家のトレーニングが行われているといいます。Medical Xpressの記事です。

たとえ適度といわれている量でも、飲酒は脳に悪影響を及ぼす可能性があるそうです。米国と欧州の研究チームが、英国バイオバンクのデータから中高年3万6678人の飲酒量と脳の大きさを調査。50歳の人が1日当たり1~2ユニット(1ユニット=純アルコール8g相当)のアルコールを摂取すると、脳の灰白質と白質において2歳老化したのと同等の萎縮がみられたそうです。1日4ユニット飲酒する人は、10歳以上老化したのと同等だったといいます。ScienceAlertの記事です。

夜、電気やテレビをつけっぱなしにしたまま寝ていませんか。米国の研究チームが、100ルクス(中程度の明るさ)の部屋で一晩眠った参加者と3ルクス(ほのかな明るさ)の部屋で眠った参加者を比較。中程度の明るさの部屋で眠った人は覚醒状態に入り、心拍数や心収縮力などが増大したそうです。これでは体が休まらないといいます。明るい部屋で寝ると、次の朝にインスリン感受性が低くなることも明らかになったようです。Medical Xpressの記事です。

インドに住む50代の男性の舌から、黒い毛のようなものが生えてきたそうです。男性は3カ月前に発症した脳卒中の影響で左半身が麻痺しており、ピューレ状の食事を取っていたといいます。医師は男性の舌について、「黒毛舌」と呼ばれる状態だと診断したそうです。黒毛舌の誘因はさまざまですが、ピューレ食を取る人に起こりやすいと指摘されています。この男性は口腔内を適切に洗浄することで、20日後には舌の状態が改善したとのこと。ScienceAlertの記事です。

患者の痛みや不安を和らげるセラピー犬を知っていますか。このセラピー犬が、緊急救命室(ER)でも役に立つ可能性があるそうです。カナダの研究チームが、セラピー犬を大学病院の救急部門に10分間滞在させ、患者への影響を対照群と比較。セラピー犬の介入を受けた患者の48%が、不安が軽減したと報告したそうです。さらに「痛みが軽減した人が43%」「うつが軽減した人が46%」「健康状態が改善した人が41%」いたことも分かったといいます。Medical Xpressの記事です。

アルツハイマー病の新たな治療ターゲットが見つかったようです。米国の研究チームがアルツハイマー病で死亡した患者の脳を調査。健康な人の脳に比べて、学習や記憶に関連する海馬における血管の周皮細胞が34%少ないことが分かったそうです。そして、残っている周皮細胞には高レベルのFli-1タンパク質が存在していたといいます。アルツハイマー病モデルマウスのFli-1タンパク質を阻害したところ、記憶に関するパフォーマンスが向上したとのこと。EurekAlert!の記事です。

米メリーランド大学は、今年1月7日に世界で初めて遺伝子操作したブタの心臓の移植を受けた57歳の男性が死亡したと発表したようです。男性は数日前から容体が悪化。緩和ケアを受け、死の直前の数時間は家族と話をすることができたといいます。男性は通常の心臓移植には不適格で、ブタの心臓移植が生きるための唯一の選択肢だったそうです。移植された心臓は、術後数週間は拒絶反応の兆候を示すことなく正常に機能していたとのこと。CNNの記事です。

便中の腸内細菌を調べることで、早い段階から膵がんの兆候をつかむことができるかもしれません。スペインの研究チームが、膵管腺がん患者と対照群合わせて136人の唾液と便を比較。膵管腺がん患者の便から、腸内細菌叢の独特なパターンが特定されたそうです。このパターンは、がんの進行度と関係なく確認されたことから、膵がんの早期発見に活用できる可能性が示唆されています。現在、日本でもこの検査の臨床試験が行われているとのこと。BBCの記事です。

米国で生後6カ月の乳児に、心臓と胸腺の移植が行われたそうです。乳児は心臓の弁に異常があり、心臓移植が行われました。T細胞の成熟を担う胸腺の機能にも異常があったため、心臓移植から2週間後、同じドナーの胸腺細胞から培養した胸腺が移植されました。これにより、心臓への拒絶反応が抑えられることが期待されています。移植から半年たった今、胸腺は正常に機能しているようです。今後、免疫抑制薬からの離脱を目指すとのこと。CBS Newsの記事です。

米国では1996年まで有鉛ガソリンが使われていました。自動車の排ガスを通じて鉛に暴露したことで、IQが低くなるリスクがあるそうです。同国の研究チームが、現在公表されているデータから有鉛ガソリンへの暴露が脳に与える影響を調査。2015年の時点で米国の人口の半数にあたる1.7億人が、子ども時代に臨床的に懸念されるレベルの鉛に暴露していたそうです。その結果、米国人のIQが累積で8.24億ポイント低下した可能性があるといいます。Medical Xpressの記事です。

ロシアによる侵攻が続くウクライナで、医療用酸素の供給に深刻な影響が及んでいるようです。現在同国では、医療用酸素を工場から病院に運ぶことができなくなっており、大半の病院で今ある酸素を近々使い切ってしまうといいます。このような状況を受けて、WHO(世界保健機関)は酸素が必要な患者に安全に医療用酸素を供給するよう求める声明を発表。ポーランドを経由する安全な輸送ルートの確保に取り組んでいるそうです。WHO Europeの記事です。

ロシアによる侵攻が続くウクライナで、産科病院が通常通りに運営できなくなっているそうです。ロシアの攻撃が激しさを増すなか、沿岸都市マリウポリの産科病院では、薄暗い地下室を防空壕と新生児室として使うことを余儀なくされています。爆撃による犠牲者や遺体がこの病院に運び込まれ、地下室の上階では犠牲者を治療するために医師が奔走している状態だといいます。ハリコフでも同様に、産科病棟が防空壕に移されているとのこと。AP通信の記事です。

関節リウマチの治療に使われる抗炎症薬「バリシチニブ」が、新型コロナの重症患者に有効なことが分かったそうです。英国の研究チームが、2021年2~12月に新型コロナで入院した重症患者8156人を調査。バリシチニブを投与された人は、そうでない人に比べて28日以内に死亡するリスクが13%低かったそうです。抗ウイルス薬やステロイド、モノクローナル抗体など他のコロナ治療を同時に受けていた場合でも、効果は一貫していたといいます。Forbesの記事です。

米ペンシルベニア州の猫が、この地域で流行していた新型コロナウイルスのデルタ株「AY.3」に感染していたことが分かったそうです。飼い主が先に感染し、その後、猫に嘔吐や軟便の症状が出ました。ペンシルベニア大学が、猫のウイルスのゲノムを解析し、10の変異(一塩基バリアント)を確認。ウイルスに深刻な変異をもたらすものは、ほぼなかったとのこと。地域の感染者4200人のうち同じバリアントのウイルスを持っていたのは5%未満でした。ScienceAlertの記事です。

現在米国ではほとんどの地域でマスク着用義務が撤廃されています。しかし実際は、472の郡でマスクの着用が推奨される状況だそうです。米疾病対策センター(CDC)は、新型コロナの感染状況に関する郡ごとの警戒レベルを毎週公表しています。警戒レベルが「高」に分類される地域では、引き続き屋内でのマスク着用が推奨されるといいます。しかし、警戒レベルが「高」の郡を抱えているのに、マスク着用義務を早々に撤廃した州が多くあるとのこと。CNNの記事です。

豪州などの研究チームが、診断が難しい遺伝性神経疾患を迅速かつ正確に特定する遺伝子検査を開発したそうです。遺伝子の一部で塩基の繰り返し配列が異常伸長することによって起きる50以上の疾患を一度に調べられます。ハンチントン病、脆弱X症候群、遺伝性脊髄小脳変性症、筋緊張性ジストロフィーなどが対象です。現在は、症状などから調べるべき遺伝子に当たりを付けて検査をしており、特定までに何年もかかることがあるといいます。Medical Xpressの記事です。

新型コロナウイルスの感染が脳に与える影響が明らかになったようです。英国の研究チームが、コロナ感染から平均4.5カ月経過した患者401人と非感染者384人の脳をMRIで調査。なお、感染者の96%が軽症だったそうです。コロナに感染した人は、脳全体の大きさが0.2~2%縮小したことが分かったといいます。特に、嗅覚や記憶に関連する領域の灰白質が減少していたそうです。この調査は従来株やアルファ株が流行していた時期に行われたとのこと。BBCの記事です。

物を捨てられず必要以上にため込んでしまう「ためこみ症」が、注意欠陥多動性障害(ADHD)と関連しているかもしれません。英国の研究チームが、成人のADHD患者88人と非ADHD患者(対照群)にアンケート調査を実施。ADHD患者の20%にためこみ症の症状が認められたのに対し、対照群で症状が認められたのはわずか2%だったそうです。ADHDの症状が重い人ほど、生活の質の低下、うつや不安といった、ためこみ症の問題を多く抱える傾向にあったといいます。ScienceAlertの記事です。

若い頃に比べて即断ができなくなったと感じることはありますか。ドイツの研究チームが120万人を対象に、課題に対する反応速度を測るテストをオンラインで実施。20歳を超えると反応が遅くなることは事実だったものの、正解を導く情報処理能力は60歳まで衰えないことが分かったそうです。反応速度が低下する理由は、脳が衰えるからではなく、年とともに衝動性が抑えられたり、反射神経が鈍くなったりすることが原因だと指摘しています。Medical Xpressの記事です。

多発性硬化症(MS)を発症する非遺伝的なリスク要因が見つかったかもしれません。スイスなどの研究チームが、遺伝的な要因の影響を排除するため、双子のうち1人がMS、もう1人は健康だという一卵性双生児61組を調査。MSは病原性のT細胞が脳や脊髄に入り込んで神経細胞を破壊することで起こると考えられています。チームが最新鋭の技術を使って参加者の免疫系を分析したところ、病原性T細胞の基になる前駆細胞を発見したそうです。ScienceDailyに紹介されています。

腸内細菌叢の不均衡が心筋梗塞、狭心症、心不全などの心疾患を引き起こすかもしれません。欧州の研究チームが、中年1241人を対象に腸内細菌叢と心疾患の関係を調査。心疾患治療薬の影響ではない「腸内細菌叢の乱れ」の75%は、心疾患の症状が現れる何年も前から発生していたことが判明したそうです。心疾患患者の腸内細菌叢の特徴として、健康によい影響を与える細菌が減り、悪い影響を与える細菌が増えていることが分かったといいます。Medical Xpressの記事です。

全ての乳児をRSウイルス(RSV)から保護する予防薬の開発が進んでいるようです。米国などの研究チームが、アストラゼネカ社とサノフィ社が開発したRSV予防薬「Nirsevimab」の第3相試験を実施。この薬は、人工的に作ったRSVに対する抗体(モノクローナル抗体)薬です。治験では、RSVの流行期を初めて迎える健康な乳児が対象になったそうです。その結果、Nirsevimabを1回投与すると、治療が必要なRSVによる下気道感染症に対して74.5%の有効性を示したといいます。Medical Xpressの記事です。

開発中のデュシェンヌ型筋ジストロフィー(DMD)の治療薬は、既存薬に比べて高い有効性が期待できるようです。カナダの研究チームが、筋肉構造を保つタンパク質が作られるように、六つのエクソン・スキップ分子を組み合わせたカクテル療法治療薬を開発。患者の組織やマウスを使った実験では、患者の約45%において症状が軽減する可能性が示唆されたそうです。さらに、この薬は心筋内にも浸透するため、心臓機能の改善も確認されたといいます。Medical Xpressの記事です。

英国の研究チームが、生殖補助医療(ART)で妊娠した女性の分娩10万6000件を自然妊娠による分娩3400万件と比較した結果を公表したそうです。それによると、ARTで妊娠した女性は高血圧や糖尿病などの既往歴がある人が多く、妊娠合併症のリスクが高いことが判明。さらに心血管関連の既往歴がない場合でも、ARTによる妊娠が合併症リスクの上昇に関連していることも分かったといいます。今回の研究では、ARTの種類については考慮されていないとのこと。CNNの記事です。

死の間際にこれまでの人生が走馬灯のように駆け巡る――。このような現象は本当に起こるのでしょうか。カナダの研究チームが、てんかんの男性患者(87)の脳波を計測していたところ、患者が心臓発作で死亡したそうです。そのため、予期せぬ形で死亡前後の脳波を記録することができたといいます。それによると、心停止の前後ともに30秒間、夢を見たり記憶を呼び起こしたりする時と同じパターンの脳波が確認されたとのことです。BBCの記事です。
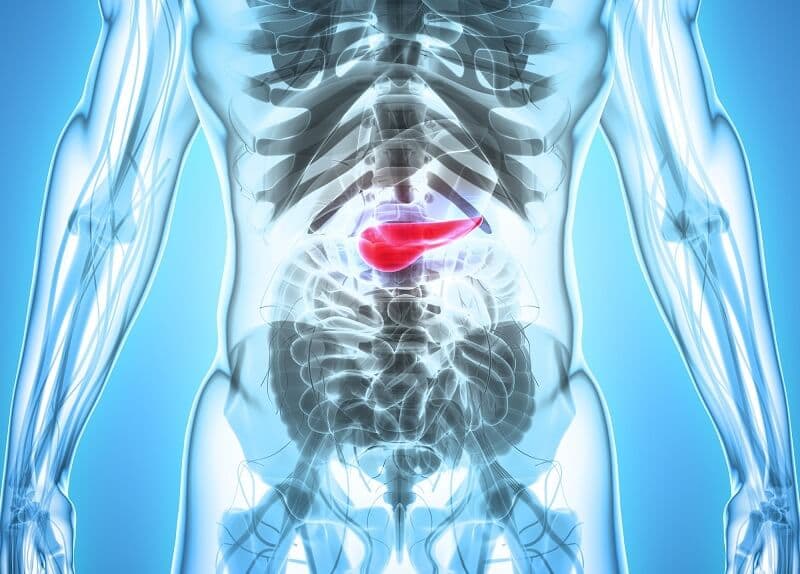
幹細胞由来の膵島細胞移植を受けた64歳の1型糖尿病の男性患者が、薬を使わずにインスリンを産生し、自力で血糖値を制御できるようになったそうです。この結果を受けて、1型糖尿病患者17人を対象とした臨床試験が行われる予定。ただし、米Vertex Pharmaceuticals社が開発したこの治療法は、移植に対する拒絶反応を防ぐため、免疫抑制薬が不可欠だといいます。そこで複数の会社が、免疫抑制薬を使わなくてよい次世代移植療法の研究も進めているとのこと。Medical Xpressの記事です。

英国が「コロナとの共生」に舵を切りました。英政府は、イングランドにおける新型コロナに関する法的規制を2月24日から全面撤廃する方針を表明。陽性者の自主隔離は、推奨(5日間)されますが、法的には不要になります。さらに濃厚接触者の追跡も終了。4月1日からは一般市民向けの無料のPCR検査も終了し、重症化リスクの高い人たちに対象を絞るとのこと。欧州では既に、デンマーク、ノルウェー、スウェーデンが規制を解除しています。BBCの記事です。
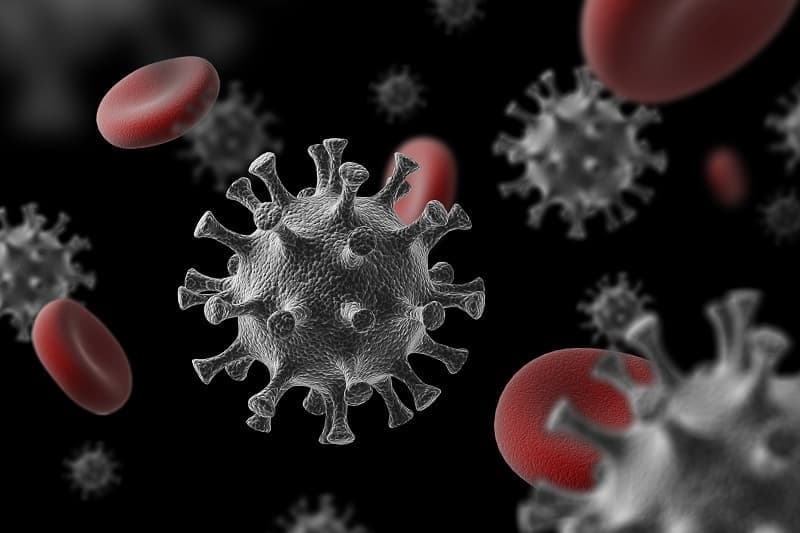
新型コロナウイルスオミクロン株の亜種「BA.2」について、実世界における二つの研究結果が公表されたそうです。南アフリカの研究チームが陽性者9万5000人を調査。従来のオミクロン株(BA.1)感染者とBA.2感染者の間で、入院リスクに差はみられなかったそうです。デンマークの研究チームによると、BA.1に感染した人がBA.2に再感染する割合は非常に低く、再感染者のほとんどがワクチン未接種者だったといいます。再感染で入院した人はいなかったとのこと。CNNの記事です。

アフリカのマラウイで、3歳の女の子が野生株のポリオウイルスに感染していることが分かったそうです。アフリカで野生株ポリオが確認されるのは5年ぶり。2020年にはアフリカで野生株ポリオの根絶宣言が出され、このウイルスが残っているのはアフガニスタンとパキスタンだけになっていました。今回マラウイで確認された野生株は、パキスタン由来のものとみられています。しかし、いつどのようにマラウイに入ってきたのかは不明とのこと。BBCの記事です。

一般的に呼吸器感染症を引き起こすとされる細菌「クラミジア・ニューモニエ」が、アルツハイマー病の発症に影響を及ぼしているかもしれません。豪州の研究チームがマウスを使って調査したところ、クラミジア・ニューモニエが鼻腔の神経を介して脳に侵入できることが判明しました。一旦この細菌が中枢神経系に入ると、数日以内に脳細胞が反応し、アルツハイマー病の特徴であるアミロイドベータペプチドの蓄積が起きるといいます。Medical Xpressの記事です。

インフルエンザの新治療薬「バロキサビルマルボキシル(商品名ゾフルーザ)」と標準的な治療薬「ノイラミニダーゼ阻害薬(NAIs)」を併用しても、効果が高まることはないようです。米国の研究チームが、インフルエンザで入院した患者366人を対象に臨床試験を実施。新治療薬とNAIsを投与された人は、臨床的改善がみられるまでに平均97.5時間かかったそうです。プラセボとNAIsを投与された人もこれとほとんど変わらず、平均100.2時間だったとのこと。Medical Xpressの記事です。

デュシェンヌ型筋ジストロフィーに対する「プレドニゾン」を使ったステロイド治療は、投薬する時間帯によって効果に違いが生じるようです。米国の研究チームがマウスを使って調査しました。週1回のプレドニゾン投薬を午前7時ごろに行うと、筋肉機能の強化が促進されたそうです。夜に投薬を行うと、この反応はみられなかったといいます。マウスは夜行性のため、人間にとっては別の時間帯が効果的である可能性が示唆されています。ScienceDailyの記事です。

新型コロナウイルスオミクロン株の亜種「BA.2」は、感染力が強いだけでなく重症化しやすい可能性があるようです。東京大学などの研究チームが、BA.2は従来のオミクロン株(BA.1)に比べて細胞内で自分のコピーを素早く大量に作れることを発見。BA.2に感染したハムスターは、BA.1に感染したハムスターに比べて重症化しやすく、肺組織の損傷も大きかったといいます。ワクチンやモノクローナル抗体療法の効果が得られない可能性も指摘されています。CNNの記事です。

米エナンタ社が、RSウイルス(RSV)感染症の治療薬の臨床試験を行ったそうです。「EDP-938」と呼ばれる新薬は、RSVが複製するのを妨げる効果が期待されています。RSVに対する抗体レベルが低い18~55歳の178人を対象に、意図的にRSVに感染させて薬の効果を評価する「ヒューマンチャレンジ」試験を実施。感染後に新薬を摂取した人はプラセボ群に比べて、ウイルス量が少なく、症状も抑えられたそうです。副作用はほとんどが軽いものだったとのこと。CNNの記事です。

新型コロナワクチン接種から時間がたつと、抗体の質は変化するのでしょうか。米国の研究チームが、リンパ節などの免疫組織に作られる微小構造「胚中心」に着目。B細胞が強力な抗体を産生できるように生まれ変わる場です。ファイザー製ワクチン2回目接種から半年経過後も、15人中10人のリンパ節の胚中心内にB細胞が存在していたそうです。抗体量の減少と共に、より強力な抗体を産生する仕組みに切り替わることが示唆されています。Medical Xpressの記事です。

妊娠中に母親が新型コロナワクチンを接種すると、生まれた赤ちゃんのコロナによる入院リスクが61%低下するようです。米疾病対策センター(CDC)が、コロナで入院した6カ月未満の乳児176人と、コロナとは関係なく入院した乳児203人を調査した結果から判明しました。母親が2回の接種を妊娠21週以降に受けた場合、乳児のコロナによる入院を抑制する効果は80%だったといいます。妊娠21週より早い段階で接種した場合、同効果は32%だったとのこと。Medical Xpressの記事です。

1889年にロシアで発生し、世界中で猛威を振るった「ロシア風邪」の原因について新たな説が浮上しているようです。これまでロシア風邪は、インフルエンザウイルスが原因と考えられてきました。しかし複数の研究者が、症状や高齢者に死者が多かったことなど、新型コロナとの類似点を指摘。原因はコロナウイルスだった可能性があるといいます。英国や米国の研究者は、当時の肺組織サンプルを探し、証拠を見つけ出そうとしているそうです。ScienceAlertの記事です。

米国の研究チームが、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)感染から治癒したとみられる三つ目の症例を報告しました。患者は人種の異なる両親を持つ女性で、HIV感染に加えて白血病も発症したそうです。白血病治療のため、あるドナーのさい帯血と、血縁者の血液幹細胞が患者に移植されました。さい帯血のドナーはHIVの感染を阻害する遺伝子変異を持っていたといいます。抗HIV薬を中止してから14カ月たった現在も、患者は寛解状態を維持しているとのこと。Medical Xpressの記事です。

女性ホルモンのエストロゲンが新型コロナによる死亡リスクに関連するようです。スウェーデンの研究チームが女性1万4685人のデータを分析。過去に乳がんと診断され、再発を防ぐために抗エストロゲン薬を使用していた人は、エストロゲンによる治療を何も受けていない人に比べてコロナによる死亡リスクが倍増したそうです。更年期障害の改善のためにエストロゲンを増やすホルモン補充療法(HRT)を受けていた人は、同リスクが54%低かったとのこと。iNewsの記事です。

米国の研究チームが、ヒト心筋細胞を使った魚型ロボットを開発したそうです。幹細胞技術によって作製したヒト心筋細胞を左右に配置し、片側の心筋細胞が収縮すると、もう片方が拡張します。この動きを繰り返すことで、魚型ロボットは100日以上にわたり自力で泳ぎ続けることができるそうです。泳ぎ続ける過程で、人間の心臓と同じように細胞が強化されることも分かったといいます。機能不全の心臓の修復に使用できる可能性があるそうです。nprの記事です。

新型コロナやインフルエンザのワクチン接種後に軽~中度の運動を90分間行うと、その後4週間の抗体量が、運動をしなかった場合よりも多くなることが分かったそうです。調査したのは、ファイザー製コロナワクチンと2種類のインフルワクチン。被験者は心拍数が120~140になるように、サイクリングマシンをこいだり、速足で歩いたりしたそうです。45分間の運動では同様の効果はみられなかったといいます。米国の研究チームの成果が、ScienceDailyに紹介されています。

米スタンフォード大学が、うつ病を短時間で効果的に治療する方法を開発したそうです。これは新しいタイプの「反復経頭蓋磁気刺激療法(rTMS療法)」です。従来のrTMS療法は治療に6週間かかっていましたが、新たな治療法はわずか5日間で完了。他の治療法で効果がみられなかったうつ病患者29人を対象に臨床試験を行ったところ、新たなrTMS療法を受けた患者の80%近くが寛解状態になったといいます。プラセボ群で寛解したのは13%だったとのこと。nprの記事です。

電気刺激を使った革新的な技術で、脊髄損傷患者の生活の質を大幅に改善できるかもしれません。スイスの研究チームが、脳の働きに似せて筋肉に信号を送ることができる6cmの脊髄インプラントを開発。これを事故で下半身不随になった患者3人に埋め込んだところ、3人ともすぐに数歩踏み出せるようになったといいます。患者の1人はリハビリを経て、バランスをとる補助器具を使いながら休まず1km歩けるようになるまで回復しているとのこと。ScienceAlertの記事です。

歯と歯茎の間の溝にある歯肉(付着上皮)に発現するタンパク質「SCPPPQ1」に、光が当てられています。カナダの研究チームが、SCPPPQ1に抗菌効果がある可能性を発見。特に口腔細菌ポルフィロモナス・ジンジバリス(Pg菌) に対して抗菌作用があることが示唆されたそうです。Pg菌はアルツハイマー病の主要な危険因子であると考えられており、SCPPPQ1が歯周病だけでなくアルツハイマー病などの神経変性疾患も抑制できる可能性に期待が高まっています。Medical Xpressの記事です。

米カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)の産婦人科医から性的虐待を受けたとして、被害を訴える女性たちが民事裁判を起こし、同大学と女性たちの間で和解が成立したようです。この医師は1983年から30年以上にわたりUCLAの学生保健センターなどに勤務していました。2019年に性的暴行の容疑でこの医師が逮捕されると、多くの女性が被害を訴え出たといいます。同大学は、原告の203人の女性たちに計2億4360万ドルを支払うことで和解したそうです。CNNの記事です。

エボラウイルスの持続感染について、ウイルスの隠れ場所が明らかになったそうです。米国の研究チームが、エボラウイルスに感染したサルを調査。モノクローナル抗体療法を受けて生き延びたサルの20%の脳室系で、ウイルスが生存し続けていたそうです。エボラが再発して死んだサル2匹においては、他の臓器には明らかな異常はみられなかったにもかかわらず、脳室系でエボラウイルスの感染が広がり重度の炎症が起きていたといいます。Medical Xpressの記事です。

新型コロナウイルスに感染すると、重症度や年齢に関係なくその後の心血管疾患リスクが高くなるようです。米国の研究チームが、ワクチン普及前にコロナ陽性になり、最初の30日間を生き延びた患者15万3760人のデータを非感染者群と比較。コロナ患者は、感染から1年以内に主要心血管イベントを発症するリスクが55%高かったそうです。この傾向は、感染前は心臓に問題がなく、心血管疾患リスクが低いと考えられる人にもみられたといいます。Medical Xpressの記事です。

ビタミンDが不足している人は、新型コロナの重症化リスクが高くなるかもしれません。イスラエルの研究チームが、オミクロン株拡大以前のコロナ入院患者253人を調査。コロナにかかる前の血中ビタミンDレベルが不十分だった人のうち、半数が重症化したそうです。一方、レベルが十分だった人の重症化率は10%にも満たなかったとのこと。呼吸器系を狙うウイルスに対しての免疫が、ビタミンDによって強化される可能性が示唆されています。INSIDERの記事です。

新たに開発された「AI聴診器」で、心不全が早期に発見できるようになるかもしれません。英国の研究チームが、心電図の記録が可能な既存の「スマート聴診器」を使い、そのデータをAIが分析することで、心不全の診断をわずか15秒で正確に行う装置を開発。この装置は、人間には見つけることができない心不全の微細な兆候も心電図から検出できるといいます。1000人を対象とした臨床試験では、心不全患者の91%を特定することができたそうです。iNewsの記事です。

前立腺がんはアンドロゲン(男性ホルモン)の刺激によって増殖します。これを効果的にブロックする「第2世代抗アンドロゲン薬」を使ったホルモン療法について、米国の研究チームが前立腺がん患者3万100人のデータを分析。「アビラテロン」や「アパルタミド」などの第2世代抗アンドロゲン薬による治療を受けた人は、従前のホルモン療法を受けた人やホルモン療法を受けなかった人に比べてうつ病を発症するリスクが倍増したといいます。Medical Xpressの記事です。

ヒト免疫不全ウイルス(HIV)の新たな変異型が見つかったようです。英国の研究チームが、オランダなど欧州の国々のデータの中から他とは明らかに違うHIV変異型に感染した人を17例発見。この変異型は「VB変異型」と呼ばれ、欧米や日本で感染者が最も多いHIVの「サブタイプB」に属します。VB変異型に感染しながら治療を受けずにいると、免疫細胞であるCD4陽性リンパ球の数が急激に減少し、平均2~3年以内にエイズを発症すると報告されています。ScienceAlertの記事です。

新型コロナの重症患者で、気管内挿管による人工呼吸を行った人の中には、その際に使用する鎮静剤をやめた後も意識が回復しないケースがあるそうです。米国の研究チームが、「意識障害のあるコロナ患者10人」「健康な人14人」「外傷性脳損傷による意識障害患者18人」の脳をMRIで調査したのですが、意識が戻る時期を予測することはできませんでした。ただ、コロナ患者のほとんどが6カ月以内に意識障害から回復して自宅に戻ったそうです。PsyPostの記事です。

カナダの研究チームが、男性型脱毛症(AGA)治療に使われている3種類の薬について23の研究を分析し、その効果を調べました。効果が最も高かったのは、内服薬「デュタステリド」を1日5mg摂取する方法でした。以下、内服薬「フィナステリド」1日5mg▽内服薬「ミノキシジル」1日5mg▽量を減らしたフィナステリドと1日1mgの経口避妊薬(ピル)――の順で効果が確認されました。1日5mgのミノキシジルを患部に塗布する方法は5番目でした。CNNの記事です。

慢性リンパ性白血病に対するCAR-T細胞療法の効果が、長期にわたって持続することが分かったそうです。米国の研究チームが、2010年に第1相試験の参加者としてCAR-T細胞を投与された慢性リンパ性白血病患者2人を追跡調査しました。投与から10年以上経過した後もCAR-T細胞は体内に存在しているといい、この期間は2人とも寛解状態が続いているそうです。この結果を受けて、チームは「CAR-T細胞療法は白血病の有望な治療法である」と結論付けています。CNNの記事です。

ローズマリーに含まれる「カルノシン酸」が、新型コロナに対して二つの効果を発揮するようです。一つは、感染抑制の効果です。新型コロナウイルスは感染の際に、細胞の「ACE2受容体」に結合します。カルノシン酸は、この結合を阻害するといいます。もう一つは、炎症反応を抑える効果です。コロナ後遺症は強い炎症反応によって起こると考えられており、カルノシン酸がこれを防ぐ可能性があるそうです。日米の研究チームの成果が、Medical Xpressに紹介されています。

子宮頸部細胞診検査(スメア検査)で、卵巣がんや乳がんを早期に検出できるかもしれません。英国の研究チームが、スメア検査のために採取した細胞サンプルを調べました。卵巣がん患者242人と非卵巣がん女性869人、乳がん患者329人と非乳がん女性869人のサンプルを分析。その結果から、卵巣がんや乳がんのリスクの高い女性を特定するのに役立つ特徴が見つかったといいます。高リスク患者が特定されれば、追加のがん検診を行いやすくなります。BBCの記事です。

「適度な飲酒は健康によい」との説が覆されたようです。英国の研究チームが、飲酒習慣のある33万3259人とこれまでに飲酒したことがない2万1710人のデータを分析。健康の問題で飲酒を控えている人のデータを制限するため、「以前飲酒していた人」は調査対象から除外しました。ビール、シードル(リンゴ酒)、蒸留酒の摂取量が同国の健康ガイドラインで推奨されている上限より少ない人でも、心血管疾患で入院するリスクが高かったといいます。ScienceAlertの記事です。

注射をせずに、mRNAワクチンが接種できるようになるかもしれません。米国の研究チームが、mRNAを経口摂取が可能なカプセルに入れて、胃に送達する方法を開発したそうです。50㎍のmRNAが入ったカプセルを三つ、計150㎍のmRNAをブタの胃まで送り届けることに成功したとのこと。これは新型コロナのワクチンに使われているmRNAの量より多いといいます。RNAやDNAを胃に直接送達できることから、消化器疾患治療の改善に寄与することも期待されています。Medical Xpressの記事です。

抗生物質が新型コロナの治療に有効かもしれません。英国などの研究チームがエジプトの病院で、中等~重症のコロナ患者に「セフタジジム」か「セフェピム」をステロイドと一緒に投与。この患者らは、少なくとも7種類の薬を使う「標準的なコロナ治療」を受けた患者と同程度の期間で回復したそうです。抗生物質がウイルスに直接作用するのか、あるいは入院患者によくある他の感染症を防ぐことで回復につながるのかは不明だといいます。News-Medical.Netの記事です。
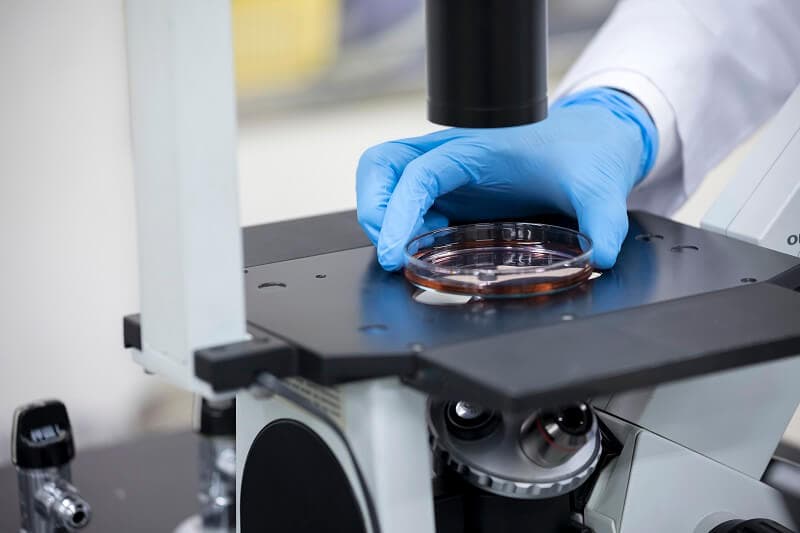
細胞の生存に必須な「スフィンゴ脂質」の合成を阻害することで、筋ジストロフィーを抑制できる可能性があるそうです。スイスなどの研究チームが、デュシェンヌ型筋ジストロフィー(DMD)モデルマウスを調査。スフィンゴ脂質の代謝が異常に高まっていることが分かったそうです。次にミリオシンと呼ばれる化合物を使って、スフィンゴ脂質の合成に重要な役割を果たす酵素を阻害したところ、マウスのDMDによる筋肉機能の喪失が防げたといいます。ScienceDailyの記事です。

米ファイザー社は、18~55歳の成人1420人を対象に新型コロナウイルスのオミクロン株に特化したワクチンの臨床試験を開始したそうです。既存のファイザー製ワクチンを2回接種済みの人に対して、新たなワクチンを1回または2回接種。既存ワクチンを3回接種済みの人には、新たなワクチンか既存ワクチンを1回投与するといいます。ワクチン未接種者に対しては、オミクロン特化ワクチンを3回接種し、安全性や効果を調査するとのこと。CNNの記事です。

結節性硬化症(TSC)には、遺伝的な問題だけでなく人間の脳に特有の発達プロセスが関与しているようです。オーストリアの研究チームが、TSC患者由来の脳オルガノイド(ミニ臓器)を使って原因を調査。神経細胞のもとになる前駆細胞の「CLIP細胞」が過剰に増殖することで、TSCに特徴的な腫瘍や結節と呼ばれる大脳皮質病変が発生することが分かったそうです。この前駆細胞は発達段階の人間の脳で見つかるもので、動物の脳にはみられないといいます。ScienceDailyの記事です。

ロボットが自動で手術を行う日が来るかもしれません。米国の研究チームが、軟部組織を縫合することに特化した手術ロボットを開発したと発表しました。ブタへの腹腔鏡手術で、人の支援を受けることなく、最も複雑で繊細な作業の一つである腸吻合に成功したそうです。その技術は人間よりも優れていたといいます。このロボットは、予測が難しいとされる軟部組織の手術にその場で臨機応変に対応できるよう設計されているとのこと。EurekAlert!の記事です。

他国よりはやく経口避妊薬の普及が進んだ英国で、卵巣がんによる死亡率が大幅に低下することが見込まれるそうです。イタリアの研究チームが、英国における2022年の卵巣がん死亡率は17年に比べて17%低下すると予測。この劇的な低下は、主に経口避妊薬の普及に起因すると考えられるそうです。EU諸国における同死亡率は7%の低下にとどまるそうで、英国との差は経口避妊薬の普及のタイミングの違いから生じている可能性が指摘されています。Health Europaの記事です。

新型コロナ感染後に倦怠感や睡眠障害などの症状が続く「コロナ後遺症」は、腸内細菌叢の組成から発症しやすい人を特定できるかもしれません。研究者らがコロナ患者106人と非コロナ患者68人の便から腸内細菌叢の変化を分析。感染から6カ月後、後遺症がある人は、後遺症がない人やコロナに感染しなかった人に比べて、腸内細菌の種類や数が少なかったそうです。コロナで入院した際に採取した便でも同様の傾向がみられたといいます。Medical Xpressの記事です。

新型コロナの迅速抗原検査はどのくらい正確なのでしょうか。米国の研究チームが、オミクロン株に対する抗原検査の感度を評価。他の変異株に比べて、オミクロン株は検出されにくい可能性があることが分かったそうです。感染して症状が現れているにもかかわらず、初めの数日間は抗原検査で陽性にならない人も多いといいます。研究チームは、現在この現象が起こる理由を調査中で、結果を抗原検査の改善につなげたいとしています。nprの記事です。

新型コロナワクチンを2回接種しただけでは「ワクチン接種完了者」とはいえなくなるかもしれません。米疾病対策センター(CDC)が、オミクロン株が主流になった12月と1月のコロナ入院患者8万8000人を調査。3回目のワクチンを接種している場合、入院予防効果は90%に達したそうです。2回の接種では、入院予防効果は57%だったといいます。CDCによると、3回目接種でオミクロン株による救急外来受診、発症、感染を抑制する効果も高まったとのこと。CNNの記事です。
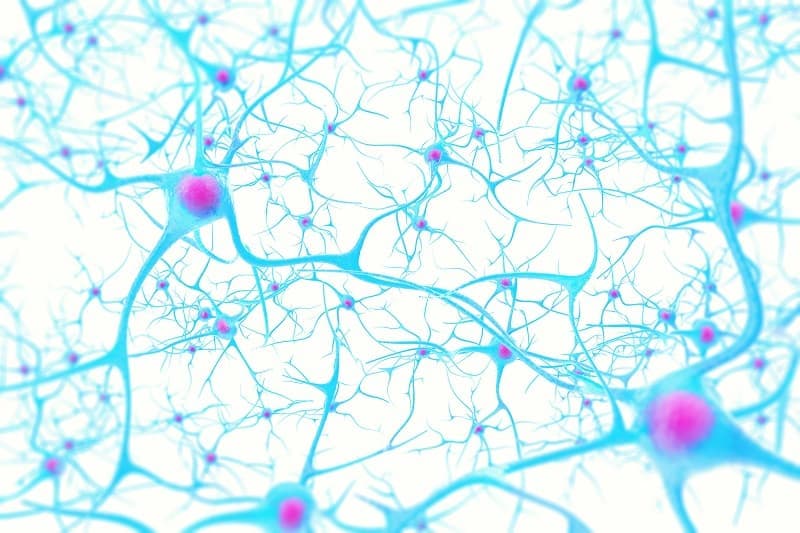
アルツハイマー病には、タンパク質のアミロイドβとタウが関与していると考えられています。治療に向けて、異常なタウがどのように脳内に広がるのかを特定する研究が多く行われています。そんな中、米国の研究チームが、細胞内にタウが取り込まれる経路が複数あることを発見しました。これまでの研究の多くは、この経路は一つだという前提で進められてきました。これが、それぞれの結果に矛盾を生じさせていた可能性があるそうです。Medical Xpressの記事です。

新型コロナウイルスの変異株オミクロン株の亜種「BA.2」について、専門家が動向を注視しているそうです。BA.2は昨年12月にフィリピンで最初に確認された後、デンマーク、英国、シンガポール、インドなどで感染者数が増加。従来のオミクロン株(BA.1)よりも感染力が強い可能性が指摘されています。デンマークではBA.2への置き換わりが進んでおり、今や新規感染者の半数近くを占めているといいます。初期データでは入院数に変化はみられないとのこと。INSIDERの記事です。

幼いうちに治療をすれば、ピーナッツアレルギーを克服できるかもしれません。米国の研究チームが1~3歳の子ども146人を2年半にわたり調査。ピーナッツパウダーを毎日少しずつ食事に混ぜて摂取した子どものうち、71%がピーナッツを16粒食べてもアレルギーを発症しないくらいの耐性を獲得したそうです。治療終了から6カ月後には、21%が同様の耐性を保持していたといいます。プラセボ群で同耐性を獲得したのはわずか2%だったとのこと。AP通信の記事です。
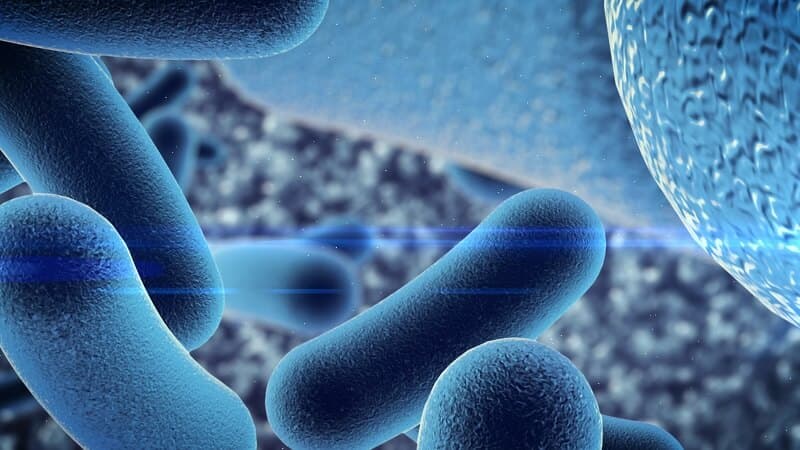
2019年の薬剤耐性菌感染による死者数はHIVやマラリアによる死者数を上回るそうです。米国などの研究チームが、薬剤耐性に関する4億7,100万人分のデータを分析。2019年の世界における「薬剤耐性菌による死者数は少なくとも127万人」「薬剤耐性菌に関連する死者数は495万人」に達すると推計されるそうです。調査した23の病原体のうち、大腸菌(E. coli)をはじめとする6つの菌が薬剤耐性による死亡の原因の73.4%を占めることが分かったといいます。CNNの記事です。

米アラバマ大学が、拒絶反応が起こりにくいよう遺伝子操作したブタの腎臓を脳死の男性に移植する実験を行ったそうです。患者はバイクレースの事故で脳死状態になっていた57歳男性。移植から生命維持装置を外されるまでの3日あまり、拒絶反応の兆候はみられず、尿を作る機能も再開したそうです。患者からブタのウイルスや細胞は見つかっていないとのこと。チームは生きている患者への移植を試みることも視野に入れているといいます。AP通信の記事です。

良質な睡眠の最中に記憶を再活性化させると、記憶力が向上するようです。米国の研究チームが、18~31歳の24人を対象に80人分の顔と名前を記憶する試験を実施。その後、被験者が昼寝で深い眠りに達した際に、先ほどの名前をスピーカーから流して記憶を再活性化させました。すると、目覚めた後に名前を思い出しやすくなったそうです。これには睡眠の質が重要で、睡眠を妨げられた人には、記憶の再活性化の効果は認められなかったとのこと。ScienceDailyの記事です。

イスラエルの研究チームが、新型コロナワクチンの4回目接種に関する初期データを公表したそうです。4回目接種について、ファイザー製ワクチンを打った医療従事者154人の2週間後と、モデルナ製ワクチンを打った医療従事者120人の1週間後の効果を測定。いずれも抗体量は上昇しており、その量は3回目接種後よりもわずかに多かったといいます。しかし、オミクロン株の感染を予防するには不十分な可能性があることが指摘されています。CNNの記事です。

香港当局は、新型コロナウイルスがペットショップのハムスターから人間に感染した可能性があるとして、市内のハムスターなど約2000匹を殺処分する方針を明らかにしたそうです。ペットショップの店員がデルタ株に感染していることが判明し、店内の動物を検査。ハムスター11匹が陽性だったそうです。昨年12月22日以降にこの店から購入されたハムスターも殺処分の対象だといいます。ハムスターを含む小動物の輸入と販売も禁止されるとのこと。BBCの記事です。

ワクチン接種後の副反応を懸念する気持ちから有害事象が生じる「ノセボ効果」の影響はかなり大きいようです。米国の研究チームが、計4万5380人を対象とした新型コロナワクチンに関する12の研究(ランダム化プラセボ対照試験)の結果を分析。プラセボを接種されたにもかかわらず、頭痛や倦怠感をはじめとする副反応を報告する人がいたそうです。分析の結果、報告された副反応の最大64%がノセボ効果によるものだと考えられるといいます。ScienceAlertの記事です。

新たな「人工膵臓」が1型糖尿病の子どもとその家族の生活を一変させるかもしれません。英国の研究チームが、血糖値の監視とインスリン供給の両方を兼ね備えた人工膵臓を開発。食事の時以外は、親がインスリンの量を調整する必要はないそうです。1~7歳の1型糖尿病患者74人を対象に実験を行ったところ、この人工膵臓は、現在普及しているセンサー付きポンプ(SAP)療法に比べ、安全かつ血糖管理に有用だということが分かったといいます。Medical Xpressの記事です。

AIのディープラーニング(深層学習)を用いて算出する「網膜の生物学的年齢」で、死亡リスクを予測できるようです。中国などの研究チームが、英国バイオバンクに登録されている40~69歳の成人4万6969人の眼底画像8万169枚を分析。AIで予測した網膜年齢と実年齢の差に注目したそうです。この差が1歳上がるごとに、11年間の追跡期間における▽全死因死亡リスクが2%▽心血管疾患とがん以外による死亡リスクが3%――上昇したといいます。News-Medical.Netの記事です。

人は退屈を感じると加虐心が増すようです。デンマークの研究チームが、他者を侮辱したり、いじめたりする「サディスティックな行動」に関する九つの研究を分析。このうちの一つの実験では、暇つぶしの手段として「うじ虫をコーヒーグラインダーで押しつぶす行為」を認めたところ、つまらないビデオを見ている人はこの行為を多くしたのだそうです。他の研究でも、退屈がサディスティックな行動に関連することが示唆されたといいます。Medical Xpressの記事です。

ヘルペスウイルスの1種で、成人の95%が感染しているとされるエプスタインバーウイルス(EBV)が、多発性硬化症(MS)に関連しているかもしれません。米国の研究チームが、同国の軍人1000万人分のデータを分析。EBVに感染していない人を特定し、追跡したそうです。その結果、MSを発症するリスクが、EBV感染後に32倍になることが判明したといいます。特定の遺伝子をもつ人が、EBVの影響を受けてMSを発症しやすくなると考えられるとのこと。ScienceAlertの記事です。

妊娠中の新型コロナウイルス感染は死産や早産、胎児の低体重などに関連するようです。米国の研究チームが、妊娠中に新型コロナの検査を受けた女性1万8000人のデータを分析。妊娠中にコロナに感染した人は、重症度に関係なく死産や早産のリスクが高いことが分かったそうです。この傾向は、妊娠初期または中期にコロナに感染した人で顕著だったといいます。胎児の低体重リスクは、主に妊娠後期の感染で高まることが指摘されています。Medical Xpressの記事です。

遺伝子操作したブタの心臓をヒトに移植したニュースが世間をにぎわせています。これについて、いくつかの問題点が指摘されています。まず、異種移植は拒絶反応などの点で医学的にリスクが高すぎるということです。次に、動物を遺伝子操作し、殺して臓器を摘出することが非倫理的だと非難する声もあります。最後は宗教上の問題です。ユダヤ教やイスラム教では豚肉食が禁じられており、移植に関しても物議を醸す可能性があるとのことです。BBCの記事です。

米国がん協会の年次報告書によると、同国のがん死亡率は、ピークを迎えた1991年から2019年の間に32%低下しているそうです。これには、肺がん患者の死亡率低下が寄与している可能性があるといいます。2015~19年をみると、全がん死亡率が毎年2%ずつ低下したのに対し、肺がん死亡率は毎年5%ずつ低下しています。肺がんの早期発見が増えていることや、治療が目覚ましい進歩を遂げていることなどが影響していると考えられるそうです。CNNに紹介されています。
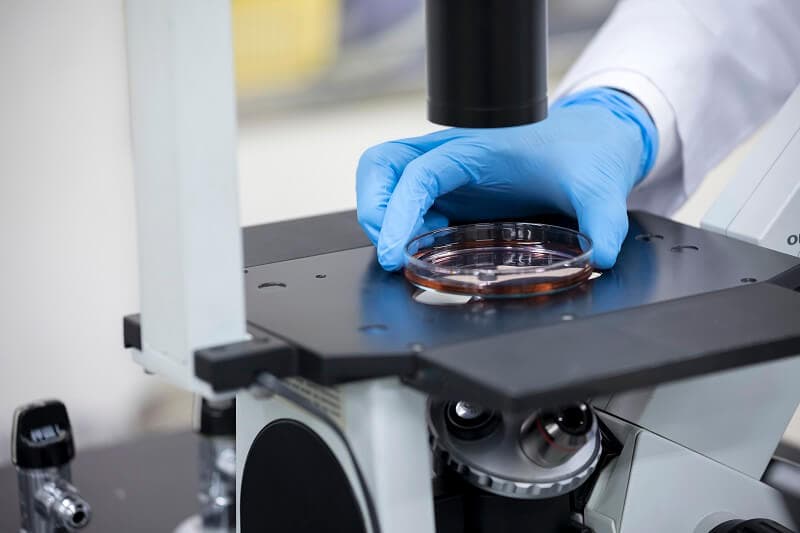
革新的な細胞リプログラミング技術を使って、心不全を治療できる日が来るかもしれません。米国の研究チームが、リプログラミングに耐性があるとされるヒトの線維芽細胞を可塑性のある内皮細胞に似た状態に変換。次に、この細胞を心筋細胞になるようリプログラミングしたところ、リプログラミング効率が向上したそうです。ラットを使った実験では、この方法で瘢痕組織をきちんと機能する心筋によみがえらせることができたといいます。Medical Xpressの記事です。

心疾患患者が向精神薬を服用すると、死亡リスクが上昇するかもしれません。デンマークの研究チームが、心疾患で入院した患者1万2913人を調査。退院後1年以内の全死因死亡率は、入院前6カ月間になんらかの向精神薬を処方されていた人が1.9倍、退院時に不安症状があった人は1.81倍、それぞれ高かったそうです。ただし、高い死亡率が向精神薬の使用と根本にある精神疾患のどちらによるものなのかを評価するには、さらなる調査が必要とのこと。News-Medical.Netの記事です。

ハンチントン病などの遺伝子治療の開発が前進するかもしれません。米国の研究チームが、脳細胞のみを標的にできる新たな遺伝子送達技術を開発したそうです。アデノ随伴ウイルス(AAV)の外殻タンパク質を操作し、血液脳関門を通過して特定の脳細胞に特異的に到達する「AAVベクター」を設計しました。この治療で懸念されていた肝障害の発生も避けられるといいます。霊長類のマーモセットを使った実験でも、脳細胞への到達を確認したとのこと。Medical Xpressの記事です。

米国では2021年、狂犬病による死者が5人確認されました。19年と20年は狂犬病による死者は報告されておらず、ここ10年で最多だそうです。このうち3人はコウモリと接触があったのに、狂犬病の発症を抑えるワクチンを打たなかったといいます。コウモリにかまれてワクチンを接種したものの、免疫系に問題があったためワクチンが効かなかった人も1人いたようです。残りの1人はフィリピン旅行中に犬にかまれ、帰国後に死亡したとのこと。AP通信の記事です。

難治てんかん治療には、大麻成分の中のカンナビジオール(CBD)が有効だとされています。しかし、CBDだけを使った薬剤では不十分かもしれません。英国の研究チームが、大麻草全体の成分を含む薬剤を服用した難治てんかんの子ども10人を調査。発作の頻度が平均86%減少しました。重篤な有害事象はなく、認知機能や行動にも改善がみられたそうです。この10人は過去にCBD製品を使用したこともありましたが、その際は効果が確認できなかったとのこと。ScienceAlertの記事です。

米メリーランド大学は、遺伝子操作したブタの心臓を世界で初めてヒトに移植したと発表しました。患者は重い心臓病をもつ57歳の男性。通常の心臓移植には適さず、異種移植以外の選択肢はなかったそうです。手術から3日後の現在も経過は良好だといいますが、移植が完全に成功したかを判断するには時期尚早とのこと。今回移植されたブタの心臓は、遺伝子操作により拒絶反応の原因となる糖が除去されている点が画期的だといいます。Medical Xpressの記事です。

新型コロナウイルスに感染した医療従事者が軽症または無症状の場合は勤務を許可するという異例の措置が、米国各地で取られ始めているようです。米国はオミクロン株の急拡大にともない深刻な医療従事者不足に直面。患者数の急増だけでなく、コロナ陽性のために出勤できない医療従事者が多数いることが原因だといいます。人員不足を補うための措置とはいえ、感染者のさらなる増加につながる可能性を懸念する声も上がっているとのこと。AP通信の記事です。

新型コロナウイルス「オミクロン株」の起源に関する説が覆るかもしれません。中国の研究チームがオミクロン株の変異スペクトラムを解析。ヒトではなく、ネズミの細胞で起こるウイルス変異に似ていることが分かったそうです。ヒトからネズミに感染した新型コロナウイルスがネズミの細胞内で変異し、再びヒトに感染したと考えられるとのこと。特に研究用マウスでは、自然界に比べて変異のスピードが速まることがあるといいます。Medical Xpressの記事です。

動脈瘤がある男性は、勃起不全治療薬「シルデナフィル(商品名バイアグラ)」の使用に注意が必要かもしれません。米国の研究チームが腹部大動脈瘤モデルマウスを4週間調査。シルデナフィルを毎日投与されたマウスは、そうでないマウスに比べて大動脈瘤が平均37%大きくなり、大動脈瘤の弾力性も大幅に低下していたそうです。シルデナフィルは血管平滑筋細胞の機能調節に関わるPDE5酵素を阻害するため、その影響が指摘されています。EurekAlert!の記事です。

イスラエル保健省は、新型コロナウイルスとインフルエンザウイルスに同時感染した症例を同国で初めて確認したと発表しました。患者はワクチン未接種の30代妊婦で、治療を受け既に退院。今冬はコロナだけでなくインフルへの警戒も高まっており、同時感染を意味する「フルロナ(flurona)」という造語も生まれたといいます。同時感染で重症化リスクが高まるかはまだ判断できないようですが、両ウイルスの流行による医療逼迫が懸念されています。CNNの記事です。

新型コロナウイルス「オミクロン株」が猛威を振るっています。ただ米国では、新規感染者数は急増しているものの、入院者数はそこまで増えていないそうです。一部の専門家は、1日の感染者数より「入院者数」に着目するべきだと主張。感染者数は曜日による偏りがあるほか、自宅で行う検査結果が含まれていないといった問題点を指摘しています。一方で、感染の状況を知るためには、感染者数の追跡も重要だという意見もあるとのこと。AP通信の記事です。

新型コロナウイルス「オミクロン株」に感染しても、入院が必要になる人は少ないようです。スコットランドの研究チームが、オミクロン株にデルタ株と同レベルの重症化リスクがあると仮定して計算。その場合、入院患者は既に47人に達していることになりますが、実際は3分の1の15人だといいます。南アフリカで行われた研究でも、オミクロン株に感染した人は、他の株に感染した人に比べて入院リスクが70~80%低いことが分かったそうです。BBCの記事です。

いたるところに存在するマイクロプラスチックが炎症性腸疾患(IBD)に関連しているかもしれません。中国の研究チームが、同国の健康な50人とIBD患者52人から採取した便を調査。IBD患者の便には、健康な人の便に比べて約1.5倍のマイクロプラスチック粒子が含まれていたそうです。また、IBD患者の便からは50μm未満のより小さな粒子が多く見つかったといいます。IBDの重症患者は、便中のマイクロプラスチックレベルが高い傾向にあったとのこと。Medical Xpressの記事です。

米食品医薬品局(FDA)が緊急使用許可を出した、米メルクの新型コロナの飲み薬「モルヌピラビル」。前日に承認されたファイザーの「パクスロビド」と比べて効果が低く、対象にも制限があるため、米国では第2選択薬になる公算が大きいそうです。モルヌピラビルの対象は、重症化リスクの高い18歳以上の軽症患者。先天性欠損症リスクがあることから、妊婦には使用できない可能性があります。また、効果はパクスロビドの3分の1とのこと。AP通信の記事です。

ヒト免疫不全ウイルス(HIV)に対する暴露前予防(PrEP)のための注射薬が、米食品医薬品局(FDA)に承認されました。ViiV Healthcare社が開発した「Apretude」です。これまでにPrEP薬として承認されたのは「ツルバダ」「デシコビ」の錠剤2種類のみで、注射薬の承認は初。臨床試験の結果、Apretudeは毎日服用が必要な飲み薬に比べてはるかに高い予防効果を示したそうです。2カ月に1回の投与で済むという利便性からも大きな期待が寄せられているといいます。NBC Newsの記事です。

運動で幸福感を得られる「ランナーズハイ」には、内因性オピオイドであるエンドルフィンが関連していると長年考えられてきました。しかし、米国の研究チームが、運動をすると大麻類似物質の内因性カンナビノイドが体内で増加することを発見。エンドルフィンが作用するオピオイド受容体をブロックしても運動後の幸福感を得られますが、カンナビノイド受容体をブロックすると、運動による幸福感や不安軽減などの効果が低下したといいます。ScienceAlertの記事です。

米国では1歳以上の子どもの小児突然死(SUDC)が毎年約400件起こるそうです。しかし関連する研究はほとんど行われていないといいます。そこで同国の研究チームが、SUDCで死亡した子どもとその両親124組のDNAコードを解析。11人(9%)の子どもから、カルシウム調節に関連する遺伝子で変異が見つかったそうです。ほとんどのケースで、両親に同様の変異はみられなかったとのこと。なお、カルシウムは脳や心臓の機能に重要な役割を果たすとされています。News-Medical.Netの記事です。

オメガ3脂肪酸のサプリメントにはうつ病の再発抑制効果があるとされています。本当に発症を予防できるのでしょうか。米国の研究チームが、うつ病のない50歳以上の成人1万8353人を調査。参加者は「ビタミンD」「オメガ3」「プラセボ」のいずれかを5~7年にわたり毎日服用したそうです。ビタミンDとオメガ3の両方を摂取した人もいました。その結果、オメガ3サプリがうつ病発症を予防するという証拠は見つからなかったとのこと。Medical Xpressの記事です。

新型コロナウイルス「オミクロン株」の急拡大を受けて、米国のバイデン大統領は、自宅で使える簡易検査キット5億個を、希望者に無料で配ると発表したそうです。配布は来年1月から開始予定。専用のウェブサイトで申し込むと、自宅まで配送されるといいます。またバイデン氏は、大規模なロックダウンについては慎重な姿勢を示しました。12月18日までの1週間をみると、米国の新規感染者の75%はオミクロン株感染者だそうです。AP通信の記事です。

欧州医薬品庁(EMA)は、米バイオジェンが開発したアルツハイマー病の新薬「アデュカヌマブ」の使用を承認するべきではないと勧告したようです。今回の判断は、初期のアルツハイマー病患者3000人を対象にした二つの臨床試験の結果に基づくもの。試験結果が矛盾していることが問題視され、アデュカヌマブが有効だとはいえないと結論付けられたそうです。何人かの患者の脳スキャン画像から、腫れや出血が疑われるケースも確認されたといいます。BBCの記事です。

ファイザー製の新型コロナワクチンは、2歳以上5歳未満の子どもが接種する場合、2回では十分な効果が期待できないようです。同社は、生後6カ月以上5歳未満の乳幼児に対するワクチン用量を大人の1/10にあたる3㎍に設定。臨床試験の中間データによると、2歳以上5歳未満の子どもでは、期待された免疫反応が確認されなかったそうです。これを受けて、5歳未満の子どもに3回目接種を行うことで、免疫反応が上がるか検証するといいます。CNNの記事です。

新型コロナウイルスmRNAワクチンの接種は心筋炎や心膜炎リスクの上昇と関連があるものの、実際にそれらが起こるのは極めてまれだそうです。デンマークの研究チームが、12歳以上の国民500万人分のデータを分析。ワクチン接種後28日以内に心筋炎または心膜炎を発症したのは、「ファイザー製ワクチンを接種した348万2295人のうち48人(10万人に1.4人)」「モデルナ製ワクチンを接種した49万8814人のうち21人(10万人に4.2人)」だったといいます。Medical Xpressの記事です。

加熱した溶液の蒸気を吸う「電子たばこ」は、男性の性機能に深刻な影響を及ぼすようです。米国の研究チームが、同国における電子たばこの使用に関する研究データを分析。20~65歳の健康な男性で毎日電子たばこでニコチンの蒸気を吸う人は、電子たばこを吸わない人に比べて勃起不全(ED)になるリスクが倍増することが分かったそうです。紙巻たばこの喫煙歴があるかどうかにかかわらず、電子たばこの使用がEDリスクに関連しているようです。CNNの記事です。

ビタミンB群や葉酸の不足はうつ病と関係があるのでしょうか。アイルランドの研究チームが、同国の50歳以上の地域在住中高年のデータを分析。ビタミンB12が不足している人は、4年以内にうつ症状が現れるリスクが51%高かったそうです。一方で、葉酸の不足とうつ病との間に関連は認められませんでした。同国では中高年の8人に1人がB12不足だといいます。Medical Xpressの記事です。健康長寿ネットによると、B12はアサリやシジミ、ノリ、レバーなどに多く含まれます。

新型コロナウイルスワクチンの追加接種後の副反応はどのくらい起こるのでしょうか。米疾病対策センター(CDC)によると、ファイザーまたはモデルナのワクチンの場合、3回目接種後に接種部位の痛みなどの局所反応を経験する人が2回目接種後より増加。一方、その他の副反応については3回目接種後のほうが若干少なくなるようです。ジョンソン・エンド・ジョンソンのワクチンは、他の2種と比べて追加接種後の副反応が少なかったとのこと。Insiderの記事です。
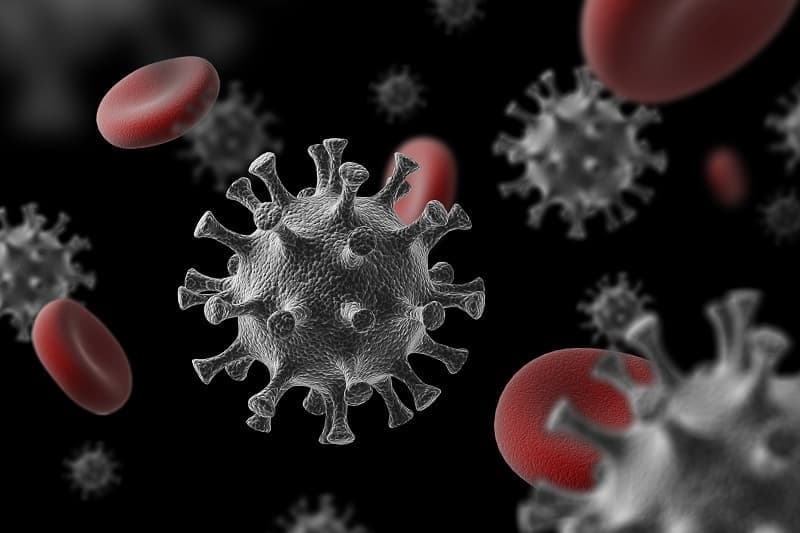
新型コロナウイルス「オミクロン株」の感染は、これまでに世界77カ国で確認されているそうです。しかしWHO(世界保健機関)は、実際にはもっと多くの国・地域に感染が広がっている可能性が高いと警告。WHOの最新データによると、この変異株は既存ワクチンの予防効果を回避する可能性があり、再感染リスクも高いそうです。WHOは、たとえ重症化リスクが低いとしても、多くの感染者が出れば、再び医療体制を圧迫する恐れがあると指摘しています。BBCの記事です。

生殖補助医療(ART)は、生まれた子どもの心の健康に悪影響を及ぼすのでしょうか。スウェーデンの研究チームが、1994~2006年に同国で生まれた子ども120万人のデータを分析。このうち3万1565人がARTで生まれた子どもだったといいます。子どもたちが12~25歳になるまで追跡でき、それを分析した結果、ARTで生まれた子どもは強迫性障害のリスクがわずかに高かったそうです。しかし両親の背景要因を調整すると、このリスク上昇は解消されたとのこと。News-Medical.Netの記事です。

「ロケット科学者や脳外科医は賢い」とのイメージは本当なのでしょうか。英国の研究チームが、航空宇宙エンジニア329人と脳神経外科医72人を、一般集団1万8257人と比較。参加者に6分野の知能レベルを測定するテストを実施したといいます。航空宇宙エンジニアと一般集団の間には、有意な得点差はみられなかったそうです。脳神経外科医は、一般集団より問題を解決するのが速かったものの、記憶を呼び起こすのに時間がかかったとのこと。Medical Xpressの記事です。

白内障手術を受けると、脳の健康に思わぬメリットがあるようです。米国の研究チームが、白内障または緑内障と診断された認知症のない高齢者3038人を調査。白内障手術を受けた人は、10年以内に認知症を発症するリスクが30%低かったそうです。一方、緑内障手術を受けた人と受けていない人の間に認知症発症リスクの違いはみられなかったといいます。認知機能に関連する網膜の細胞が、白内障手術によって再活性化する可能性が指摘されています。ScienceAlertの記事です。

新型コロナウイルスのオミクロン株に対しては、ワクチン2回接種だけでは不十分かもしれません。英国の研究チームが、オミクロン株に感染した581人とデルタ株に感染した数千人のデータを分析。オミクロン株は、デルタ株に比べてワクチンの効果が低くなることが分かったそうです。3回目接種により、オミクロン株感染による発症を75%抑制できるといいます。この研究の対象になったのは、アストラゼネカ製とファイザー製のワクチンとのこと。BBCの記事です。

米モデルナ社が、mRNA技術を使ったインフルエンザに対する4価(A/H1N1、A/H3N3、B/山形、B/ビクトリア)ワクチンの臨床試験データを公表したそうです。180人を対象にした第1相試験で、安全性を確認。若者、高齢者ともに高レベルの抗体が誘導されたそうです。主に若者に、接種部位の痛みや頭痛などの副反応がみられたといいます。同社は500人規模の臨床試験をすでに開始。適切な用量の調査や既存のインフルワクチンとの比較が行われるようです。ScienceAlertの記事です。

禁煙した後に体重が増えるのはなぜなのでしょうか。定期的にたばこの煙にさらしたマウスは、ただ「禁煙」させるよりも、広域抗菌薬で腸内細菌叢を除去して「禁煙」させた方が体重増加が少ないことが判明。たばこの成分による腸内細菌叢の組成の変化が、代謝に影響を及ぼしているとのこと。ジメチルグリシンとアセチルグリシンという代謝産物が、体重増加に関与していることが分かったといいます。イスラエルのチームの成果が、Medical Xpressに紹介されています。

ナノファイバーを使った「超分子薬」で、脊髄を損傷したマウスが歩けるようになったようです。米国の研究チームが、神経再生を促す信号を送るペプチドを何十万も含んだ超極細ナノファイバーを開発。これをゲル状にして、脊椎の損傷から24時間経過したマウスの脊髄周辺組織に注入したところ、4週間後にはほとんど元通りに歩けるようになったそうです。ファイバー内の分子が激しく振動するよう設計されている点がカギだといいます。ScienceAlertの記事です。

ニュージーランドが、若者のたばこ購入を禁止する法律を来年にも成立させる方針を示したそうです。法制化されれば、14歳以下の世代は生涯にわたりたばこを購入できなくなります。世界で最も厳しい水準の規制だといいます。専門家からはこの動きを歓迎する一方、闇市場の拡大を懸念する声も上がっているようです。政府はたばこの販売ができる場所を制限することも発表。たばこ販売の許可を持つ店は、現在の8000から500未満に減るそうです。BBCの記事です。

老眼を一時的に改善する点眼薬「Vuity」が、米国でついに市場に出るそうです。米食品医薬品局(FDA)はこの薬を10月に承認。老眼の人がこの処方薬を1滴ずつ点眼すると、15分後には見えやすくなるといいます。効果は6~10時間持続。40~55歳の人に最も効果がみられ、65歳を超えると有効性が低くなるそうです。価格は30日分で約80ドル。今のところ保険適用外だといいます。臨床試験では、頭痛と目の充血の副作用が確認されたとのこと。CBS Newsの記事です。

ブドウの種に含まれる「プロシアニジンC1(PCC1)」には、マウスの老化を防ぐ効果があるようです。米中の研究チームが、46種類の植物エキスの中からPCC1のアンチエイジング作用に着目。細胞を使った実験では、高用量のPCC1が、老化に関与する細胞のみを破壊することが分かりました。そこで、高齢マウスにPCC1を投与する実験を実施。平均で「寿命が9%」「余命が60%」延びたそうです。若いマウスにPCC1を投与すると、体力の改善がみられたといいます。Medical Xpressの記事です。

オンライン会議でwebカメラをオンにすると、疲労感が増して、会議への貢献度が低くなるかもしれません。米国の研究チームが、リモートで働く103人を対象に調査を実施。オンライン会議中にカメラをオンにすると、疲れを感じやすくなることが分かったそうです。疲れから、会議中のパフォーマンスが低下する可能性も指摘されたといいます。これらの傾向は、他人からの見られ方を気にしやすいと考えられる女性や新入社員に顕著だったとのこと。PsyPostの記事です。

勃起不全の治療薬「バイアグラ」や肺高血圧症の治療薬「レバチオ」で知られる「シルデナフィル」がアルツハイマー病(AD)の予防や治療に有効かもしれません。米国の研究チームが、1600以上の米食品医薬品局(FDA)承認薬の中からADに有効な薬を調査。シルデナフィルが最有力候補に挙がったそうです。次に、同国のデータベースから700万人のデータを分析。この薬を服用していた人は、そうでない人に比べてAD発症のリスクが69%低かったといいます。Medical Xpressの記事です。

赤ちゃんを望む人は体外受精(IVF)を先延ばしにするべきではないそうです。豪州の研究チームが、2016年に同国ビクトリア州でIVFを開始した女性数千人を20年まで追跡調査しました。1サイクルのIVFで無事に出産までたどり着いたのは、IVFを▽40歳で開始した人の13%▽30代半ばで開始した人の40%▽30歳以前に開始した人の43%――だったそうです。男性についても、年齢が1歳上がるごとにIVF成功率が約4%ずつ低下することが分かったといいます。ScienceAlertの記事です。

新型コロナ感染歴のある人が新型コロナに再感染する可能性は、ベータ株やデルタ株に比べてオミクロン株の方が高いようです。南アフリカの研究チームが同国でコロナに感染した270万人のデータを分析。少なくとも2回感染した疑いのある人は3万5670人いました。サンプルの遺伝子解析結果などから、その多くがオミクロン株に再感染したとみられます。オミクロン株には、過去の感染による免疫を回避する能力があることが示唆されたといいます。CNNの記事です。
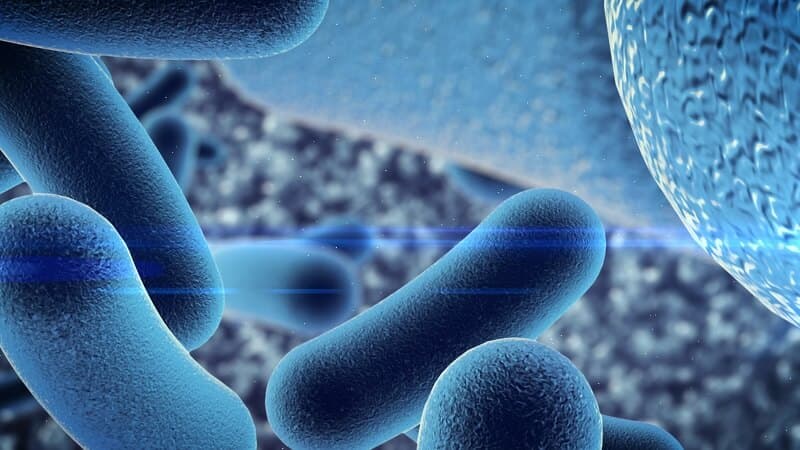
細菌が、膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)をはじめとする膵嚢胞のがん化リスクを高めるそうです。スウェーデンの研究チームが、膵嚢胞性腫瘍の手術を受けた患者29人の嚢胞を調査。嚢胞液内にいる生きた細菌の調査に初めて成功しました。通常は消化管にいるガンマプロテオバクテリア綱やバシラス綱の細菌が多く存在していることが分かったそうです。これらの細菌の一部が、がんにつながるDNA損傷を引き起こす可能性も示唆されたといいます。Medical Xpressの記事です。
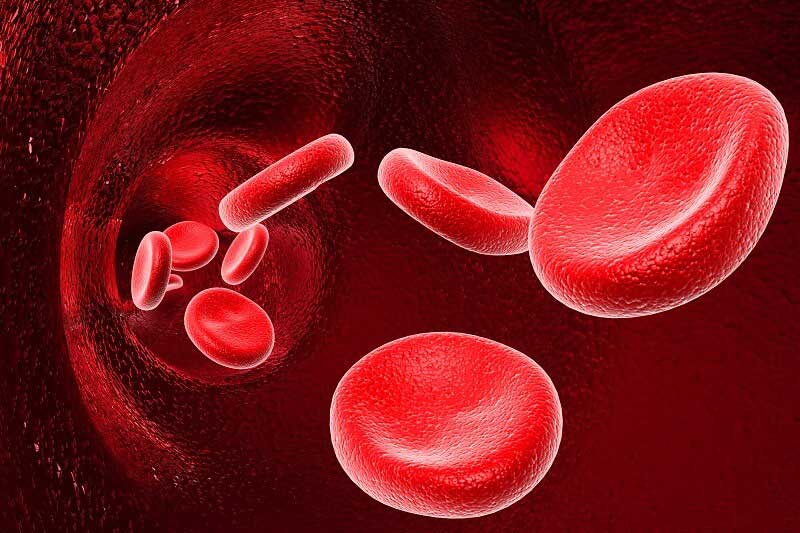
アストラゼネカ製の新型コロナウイルスワクチン接種後にまれにみられる血栓症は、どのようにして起こるのでしょうか。このワクチンはチンパンジーのアデノウイルスをベクターとして使用しています。低温電子顕微鏡でアデノウイルスを詳しく観察したところ、ウイルスの表面が血液中のタンパク質「血小板第4因子」とくっつきやすいことが判明。これが血栓症の「引き金」になると考えられるそうです。英米の研究チームの成果がBBCに紹介されています。

アルツハイマー病治療薬の候補として設計されたBACE1阻害薬「ベルベセスタット(verubecestat)」で、膠芽腫の成長を抑制できるかもしれません。米国の研究チームが、ヒト由来の膠芽腫前臨床モデルをこの薬で治療。腫瘍の成長を「促進する」マクロファージが腫瘍の成長を「抑制する」マクロファージに再プログラミングされることが分かったそうです。結果として、グリオーマ(神経膠腫)幹細胞をはじめとする腫瘍細胞の破壊が進んだといいます。Medical Xpressの記事です。

米食品医薬品局(FDA)の諮問委員会は、メルク社が開発した新型コロナの飲み薬「モルヌピラビル」について、緊急使用許可を出すよう勧告したそうです。諮問委は13対10の僅差で今回の勧告を決定。発症から5日以内の重症化リスクの高い患者が対象で、入院や死亡のリスクを30%下げる可能性があるそうです。妊婦への使用については慎重な姿勢を示す委員もいたとのこと。FDAは勧告に従う義務はないものの、通常は従うことが多いといいます。ScienceAlertの記事です。

米国では2016~19年に早産がわずかに増加したそうです。2013~18年には性感染症の患者も増加していることが分かっています。そこで同国の研究チームが母子1400万組のデータを分析し、この関係性を調査しました。妊娠32~36週で出産するリスクは、「性感染症に感染していない母親」と比べて、妊娠前または妊娠中に母親が▽クラミジアに感染していた場合は1.04倍▽淋病に感染していた場合は1.10倍▽梅毒に感染していた場合は1.17倍――だったそうです。CNNの記事です。

新型コロナウイルス「オミクロン株」に感染するとどのような症状がみられるのでしょうか。最初に新変異株に気づいた南アフリカの医師によると、患者はほとんどが軽症。今のところ多くが40歳以下だそうです。主な症状として1~2日間続く強い倦怠感、その後頭痛や体の痛みがみられるといいます。喉のいがらっぽさや乾いた咳の症状がある患者も。専門家は、これらはあくまでも現時点までの初期症例に基づく情報である点を強調しています。CNNの記事です。

新型コロナウイルス「オミクロン株」は分子的特徴から強い感染力を持つ可能性が指摘されています。実際、最初にこの新変異株が報告された南アフリカでは感染が急拡大。初期のデータでは、デルタ株より速いスピードで広がっている可能性が示されているそうです。しかし同じことが他の地域でも起こるとは限らないといいます。専門家は、オミクロン株がデルタ株を上回る「最強」の変異株になるかは、近いうちに明らかになるとみています。CNNの記事です。

WHO (世界保健機関)はコロナ変異株の名前にギリシャ文字を順番に使ってきました。今回南アフリカで見つかった変異株は、順番からいくと「ニュー(英語表記Nu)」と命名されるはずでした。しかし、2文字飛ばして「オミクロン」に。WHOは、ニューは「new」と混同しやすく、次の「クサイ(英語表記Xi)」は姓として使われているため避けたと説明しているそうです。中国の習近平国家主席の「習」が英語表記で「Xi」だから忖度したとの憶測も……。CNNの記事です。

新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン」の感染拡大を受け、ワクチン各社が対応を始めているようです。モデルナ社は、数週間以内に既存ワクチンの有効性を確認。オミクロン株に特化したワクチンを製造する必要がある場合、提供開始は2022年初めになるとしています。ファイザー社は、2週間以内に既存ワクチンの有効性を調査するといいます。オミクロン株に対応した改良版ワクチンが必要な場合は100日以内に出荷可能だそうです。ScienceAlertの記事です。

3年前、米ボストンに住む38歳の健康な男性が、未明に突然けいれんを起こしたそうです。病院でさまざまな検査を行った結果、脳スキャン画像に3カ所の石灰化病変を発見。寄生虫「有鉤(こう)条虫」の幼虫によって形成される嚢胞で、男性は神経嚢虫症と診断されました。主に幼虫や卵を持つ豚肉を食べることで感染します。男性はこの疾患が多い中南米グアテマラから20年前に移住してきたそうです。米国の研究チームの成果が、ScienceAlertに紹介されています。
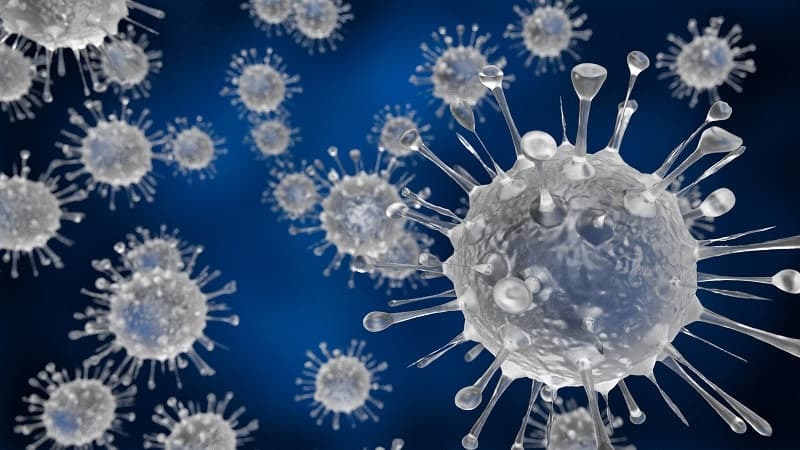
新たに見つかった新型コロナウイルスの変異ウイルス「オミクロン株」。WHO(世界保健機関)が11月26日に「懸念される変異株」に指定しました。全部で50カ所もの変異が確認されており、32カ所はウイルスが細胞に侵入する際に必要な「スパイクタンパク質」で見つかっているそうです。ワクチンはこのタンパク質を標的にしているため、専門家は既存のワクチンの効果が弱まる可能性について懸念を示しています。BBCの記事をマイナビDOCTORで紹介します。

魚やカニの形をしたマイクロロボットが、腫瘍に到達すると口やはさみを開いて薬剤を放出するという新たな技術が開発されたそうです。中国などの研究チームが、ヒドロゲルを使ってpHに反応するマイクロロボットを設計し、これを磁化。体外から磁石を使ってこのロボットを腫瘍まで誘導すると、腫瘍の酸性環境に刺激されて薬剤が放出されるそうです。これまでのところ、ペトリ皿内の人工血管を使った実験で成功が確認されているとのこと。Medgadgetの記事です。

ファイザー製の新型コロナワクチンの2回目接種から90日が経過すると、ワクチン接種済みでも感染する「ブレイクスルー感染」のリスクが徐々に高まるようです。イスラエルの研究チームが、コロナ感染歴がなく、2回目接種から3週間以上経過後にPCR検査を受けた成人8万57人のデータを分析。感染リスクは、「2回目接種~90日未満」と比べて▽90~119日後は2.37倍▽120~149日後は2.66倍▽150~179日後と180日以上経過は2.82倍――だったそうです。Medical Xpressの記事です。

先日米ペンシルバニア州のワクチン研究施設で見つかった「天然痘」と書かれた小瓶に関する続報です。米疾病対策センター(CDC)は、瓶の中に入っていたのは天然痘ワクチンに使われる「ワクシニアウイルス」だったと報告しました。天然痘を引き起こすバリオラウイルスが瓶の中に含まれているという証拠は見つからなかったそうです。ワクシニアウイルスはバリオラウイルスと同属です。天然痘ワクチンはワクシニアウイルスを弱毒化して作ります。CNNの記事です。

2型糖尿病の新たな治療薬候補が見つかったそうです。米国の研究チームが25年にわたる930万人分のデータを分析。慢性骨髄性白血病などの治療に使われる「ダサチニブ」には、2型糖尿病を持つ患者の血糖値を下げる効果があることが確認されたそうです。メトホルミンなどの一般的な糖尿病治療薬を服用した場合に匹敵するそうです。ダサチニブが老化細胞を標的とするセノリティック薬であることが関連している可能性があるといいます。EurekAlert!の記事です。

膵臓がんの早期発見に役立つ初期兆候が明らかになったようです。英国の研究チームが、2000~17年に膵臓がんと診断された患者2万4236人のデータを分析。膵管腺がん(PDAC)の兆候として23の症状、膵神経内分泌腫瘍(PNEN)の兆候として9の症状が特定されたそうです。喉の渇きと暗色尿が、初めてPDACの初期兆候に追加されたといいます。ほとんどの症状は膵臓がんに特異的ではないものの、診断の1年前にはいくつかの症状を経験する可能性が高いとのこと。ScienceDailyの記事です。

がん治療のための薬をアルツハイマー病(AD)治療に転用できるかもしれません。米国の研究チームが、若者や高齢者の病理解剖した脳を使って、ADの危険因子であるAPOE4 遺伝子に関連するタンパク質の変化を特定。既存薬の中で、慢性骨髄性白血病治療薬「ダサチニブ」と肝臓がんの実験薬がこのタンパク質に作用することが分かったそうです。さらに、この二つの薬は細胞培養の実験で、ADの原因とされるタンパク質の分泌や変化を抑えたとのこと。News-Medical.Netの記事です。

栄養成分が強化されたミルクは認知発達に好影響をもたらすのでしょうか。英国の研究チームが、1993~2001年に同国の5カ所の病院で実施された栄養調整乳に関する七つのランダム化試験の結果を分析。対象者は計1763人だったそうです。2018年に、このうち1607人の11歳と16歳時における全国統一テスト(GCSE)の成績を調べたところ、通常のミルクを飲んだ子どもに比べ、栄養成分強化ミルクの子どもの成績が良くなるという証拠は見つからなかったとのこと。Medical Xpressの記事です。

新型コロナによる呼吸不全のリスクを倍増させる遺伝子が特定されたようです。英国の研究チームが、AIなどを使って全身の細胞の遺伝子データを解析し、明らかにしました。「LZTFL1」という遺伝子に「高リスク型」があり、この型を持っていると、新型コロナウイルスに対して肺や気道の細胞が取るべき適切な防御反応が妨げられる可能性があるのだそうです。南アジア系の人の60%、ヨーロッパ系の人の15%がこの遺伝子型を持っているといいます。Medical Xpressの記事です。

コーヒーや紅茶を適度な量飲む人は、脳卒中や認知症のリスクが低くなるそうです。中国の研究チームが、英国バイオバンクのデータを使って50~74歳の健康な中高年36万人を10~14年間調査。1日に「コーヒーを2~3杯」「紅茶を3~5杯」「コーヒーと紅茶を計4~6杯」飲むと報告した人は、脳卒中や認知症を発症するリスクが最も低かったそうです。コーヒーや紅茶の摂取量については自己申告だったという点に注意が必要とのこと。CNNの記事です。

米ペンシルバニア州にあるワクチン研究施設の冷凍庫で、「天然痘」と書かれた小瓶が5本見つかったそうです。冷凍庫を整理していた職員が偶然発見。瓶は冷凍された状態で、誰かが触れた形跡はなかったそうです。極めて危険なウイルスで、既に根絶した天然痘ウイルスのサンプル保管を許されているのは、アトランタにある米疾病対策センター(CDC)の研究所とロシアの研究所の2カ所のみです。米連邦捜査局(FBI)とCDCが詳細を調査中とのこと。Live Scienceの記事です。

アルツハイマー病の予防や進行抑制の効果が期待される経鼻ワクチンの第1相試験が始まるようです。米国のブリガム・アンド・ウィメンズ病院が、アルツハイマー病の初期症状がある60~85歳の高齢者16人を対象に治験を実施。ワクチンは1週間間隔で2回投与されるそうです。ワクチンには免疫系を刺激するプロトリンと呼ばれる物質が使われ、病気の原因と考えられているタンパク質アミロイドβを除去するように設計されているといいます。CBS Newsの記事です。

英国で40~49歳の全ての人が新たに新型コロナワクチン3回目接種の対象になるそうです。英国では50歳以上の人や重症化リスクの高い人、医療従事者などを対象に既に3回目接種を開始。これまでに1260万人が3回目のワクチンを接種したそうです。今回のブースター接種はファイザー製かモデルナ製が対象で、2回目の接種から6カ月以上経過していることが条件だといいます。3回目接種により、コロナへの感染リスクは93%以上減少するとのこと。BBCの記事です。

抗うつ薬を飲んでいる人は、新型コロナで死亡するリスクが低くなるかもしれません。米国の研究チームが、昨年同国で新型コロナに感染した患者8万3584人のデータを分析。選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)を飲んでいた人の死亡率が14.6%だったのに対し、そうでない人は16.3%だったそうです。SSRIは、ウイルスが細胞に感染する際に必要な酸性スフィンゴミエリナーゼ(ASM)という酵素を阻害する作用があり、感染抑制につながる可能性があるとのこと。ScienceAlertの記事です。

HIV感染者の女性が、特別な治療を受けずに治癒したようです。アルゼンチンに住むこの女性は、2013年にHIV-1に感染していることが判明。治療は、妊娠中(2019~20年)に通常の抗レトロウイルス療法を受けたのみ。診断から8年たった現在、体内から複製可能なウイルスは見つからなかったそうです。このようなケースは世界で2例目。HIV感染については他に、幹細胞移植で治癒した人が世界に2人います。ブエノスアイレス大学などによる報告がScienceAlertに紹介されています。

モデルナ社が、同社の新型コロナワクチンを接種した人に心筋炎・心膜炎が起こる割合を調査したようです。同社のデータベースを使って、2億7500万回分の接種データを分析。1400件の心筋炎・心膜炎が確認されたそうです。ほとんどが米国や欧州からの報告で、78%が男性、61%が18~29歳だったといいます。症例が報告された割合は10万人あたり0.95例だったとのことです。ワクチンのメリットが心筋炎・心膜炎のリスクを上回ると結論付けられています。News-Medical.Netの記事です。

個人的に思い入れのある音楽を聞くと、アルツハイマー病患者の脳の性質に有益な効果がもたらされるようです。カナダの研究チームが、認知機能低下の初期段階にある14人を調査。このうち6人は音楽家だったそうです。3週間にわたって、1日1時間それぞれにとってなじみ深い音楽を聞いてもらったところ、特に思考などを担う前頭前野の神経経路に構造的・機能的変化が確認されたといいます。全参加者で認知機能の改善がみられたとのこと。EurekAlert!の記事です。
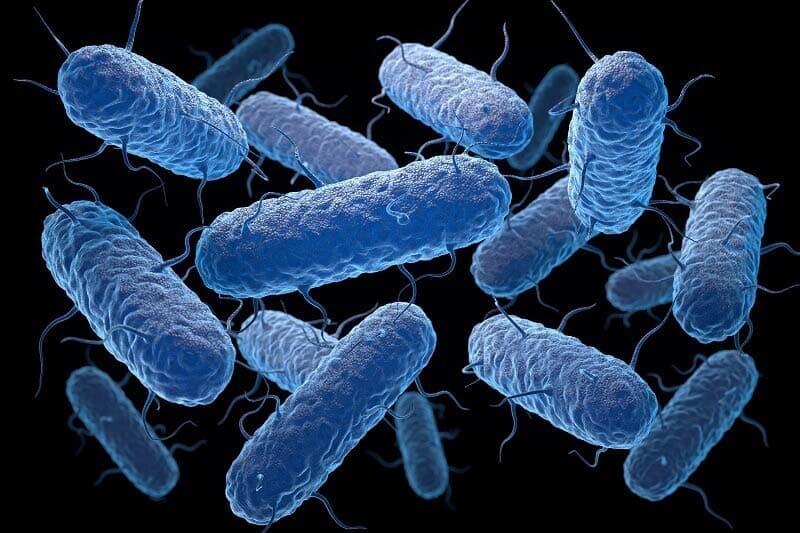
「腸内細菌叢の組成が自閉症を引き起こす」との説が覆されたかもしれません。豪州の研究チームが、自閉スペクトラム症の子ども99人と、その兄弟51人を含む非自閉症児148人の便から微生物のDNAを調査。総じて腸内細菌叢と自閉症の関連を示す証拠は見つからなかったそうです。代わりに、自閉症児は偏食の傾向が強いことが判明したといいます。偏食の結果、腸内細菌の種類が少なくなり、便がゆるくなる可能性も示唆されたとのことです。ScienceAlertの記事です。

母乳から新型コロナウイルスに対する中和抗体が見つかったそうです。米国の研究チームが、コロナの感染歴がある母親47人、mRNAワクチンを接種済みの母親30人を調査。感染歴のある母親の母乳からはIgA抗体、ワクチン接種済みの母親の母乳からはIgG抗体が多く検出されたそうです。抗体は共に新型コロナウイルスを中和する作用があったといいます。ただし研究者は「母乳を飲んだ子どもに保護効果がもたらされるかは未確認」と強調しています。Medical Xpressの記事です。

新型コロナウイルス感染拡大が、海洋環境に深刻な影響を及ぼす懸念があるようです。米中の研究者によると、コロナ下でマスクや手袋などのプラスチックごみが急増。2021年8月半ばまでに193カ国で計920万トンのコロナ関連プラスチックごみが排出されたそうです。その87.4%は病院からのもの。8月23日時点で、すでに2万8550トンが海へ流出したと推定されるといいます。発展途上国における医療プラスチックごみの廃棄方法の改善が必要とのこと。ScienceAlertの記事です。

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、世界的にはしか流行の脅威が高まっているそうです。米疾病対策センター(CDC)は、コロナ下で2200万人以上の乳児が1回目のはしかワクチンを未接種だと指摘しています。2019年と比べて300万人増えたといいます。20年のはしか発生数に増加はみられなかったものの、今後の大流行が懸念されるそうです。コロナの影響でおろそかになっている定期予防接種を強化する対策が必要とのこと。CNNに紹介されています。

男性医師は患者に、女性の外科医を紹介したがらない傾向があるようです。カナダの研究チームが、同国オンタリオ州で1997~2016年に、医師が患者に外科医を紹介した際のデータ4000万件を分析。紹介を受けた外科医は5660人で、このうち男性の割合は77.5%だったそうです。それにも関わらず、患者に男性外科医を紹介した割合は「男性医師で87%」「女性医師で79%」だったといいます。男性医師が女性外科医に偏見を持っている可能性が示唆されたとのこと。EurekAlert!の記事です。

ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンが、子宮頸がんリスクを大幅に減少させることを示す報告です。英国の研究チームが、同国における2006~19年のがん登録データを調査。12~13歳でHPVワクチンを接種した人は、そうでない人に比べて子宮頸がん発症リスクが87%低かったそうです。14~16歳で接種した人は、同リスクが62%低かったとのこと。調査対象になった女性は2価ワクチン「サーバリックス」を接種した世代だといいます。CNNの記事です。

近年、脱リン酸化酵素「SHP2」を標的とした薬の開発が注目されています。しかし、この方法はがん治療においては逆効果になる可能性があるようです。米国の研究チームが、遺伝子操作したマウスを使ってSHP2が肝細胞がんの成長を促進することを確認。ただし、SHP2を肝細胞から除去すると、がん遺伝子「Myc」ががんの成長を劇的に加速させることも分かったそうです。SHP2を阻害することで、予期せぬ複雑な免疫抑制環境が引き起こされたとのこと。News-Medical.Netの記事です。

世界的に注射器が不足し、各種ワクチン接種ができなくなる懸念があるそうです。世界保健機関(WHO)は、2022年に予防接種用の注射器が最大20億本不足する恐れがあると警告。新型コロナワクチンの接種が進むにつれて、注射器の供給が追いつかなくなるといいます。これまでにコロナワクチンは世界で72億5000万回以上接種されており、この数は定期予防接種の2倍に上るそうです。WHOは必要な注射器の量を計画的に確保するよう各国に要請したとのこと。ScienceAlertの記事です。

米ファイザー社の新型コロナ経口薬「パクスロビド」が、高リスク成人患者の入院・死亡リスクを89%減らしたそうです。ウイルスの複製に必要な酵素の働きを阻害する薬です。重症化リスクの高い新型コロナ患者1,219人を対象にした臨床試験の中間結果が公表されました。発症から3日以内にこの薬を投与された患者で入院が必要になったのは0.8%で、死者はいなかったそうです。一方、プラセボを投与された患者は7%が入院し、7人が死亡したとのこと。BBCの記事です。

米国でファイザー製新型コロナワクチンの5~11歳向け接種が始まる中、よくある質問に専門家が答えています。5~11歳の子どもは、通常の1/3の量を大人同様21日以上の間隔をあけて2回接種します。接種部位の痛みや頭痛、倦怠感、発熱などの副反応が起こることもありますが、大人と比べてそのリスクは低いといいます。若者にまれにみられる心筋炎の副反応は、臨床試験では確認されませんでした。感染歴のある子どもも接種すべきだそうです。CNNの記事です。

屋内で新型コロナウイルスのエアロゾル感染を防ぐには、身体的距離の確保だけでは不十分だそうです。米国の研究チームが、コロナウイルスを運ぶことができる、人間の呼吸器から発生する1~10マイクロメートルのエアロゾルの流れを調べました。マスクなしの感染者が屋内で会話をすると、ウイルスを含む粒子が1分以内に2m離れた相手まで届くことが判明。この傾向は換気が不十分な部屋で顕著だったそうです。Medical Xpressの記事です。

血中コレステロール値を下げる薬「スタチン」が潰瘍性大腸炎に有効かもしれません。米国の研究チームが潰瘍性大腸炎に有効な既存薬を調査。スタチンが候補に挙がったそうです。次に同国の電子カルテを分析したところ、スタチンを服用している潰瘍性大腸炎患者は切除手術を受ける割合が50%低かったとのこと。研究者によると、潰瘍性大腸炎患者の3割は抗炎症薬が効かず、大腸の切除手術を受けているといいます。Medical Xpressの記事です。

米国のGrail 社が開発したがんを早期発見する血液検査「Galleri」の臨床試験が英国で始まるようです。Galleriは早期発見が難しい膵臓がんや肺がん、胃がんなどを含む多種のがんの初期兆候を調べる検査です。腫瘍から血液中に漏れ出る遺伝情報の断片があり、その化学変化を見つけるのだそうです。米国ではすでに使用されているといいます。英国では、ランダム化比較試験に参加するボランティア140,000 人を募集する予定とのこと。BBCの記事です。

子どもにおける新型コロナの後遺症は大人ほど長引かないかもしれません。豪州の研究チームが、計19,426人の子どもを対象にしたコロナ後遺症に関する14研究を分析。後遺症の症状が12週間を超えて持続するという証拠はほとんど見つからなかったといいます。感染の4~12週間後に報告された症状は、頭痛、疲労、睡眠障害、集中力低下、腹痛でした。ただ、生活の変化の影響と区別が難しく、さらなる研究が必要だそうです。EurekAlert!の記事です。

強いストレスは、すぐに症状が出なくても、後の高血圧や心血管イベントリスクを高めるようです。京都大学が48~87歳で血圧が正常な多民族の成人412人を10年以上調査。尿中のストレスホルモン(ノルアドレナリン、アドレナリン、ドパミン、コルチゾール)レベルの合計値が倍増すると、高血圧リスクが21~31%高くなることが判明したそうです。また、コルチゾールの倍増で心血管イベントリスクが90%上昇したとのこと。CNNの記事です。

アルツハイマー病の原因とされるアミロイドβが脳に蓄積する経路が判明したそうです。豪州の研究チームは、アミロイドβが脂質とタンパク質の複合体「リポタンパク質」として脳外で作られることに着目。肝臓でヒトアミロイドのリポタンパク質を作るよう遺伝子操作したマウスを調べたところ、脳に炎症が起こり脳細胞が死んだそうです。アミロイドβが血中リポタンパク質から脳内に漏れ出している可能性があるとのこと。EurekAlert!の記事です。

インフルエンザワクチンで新型コロナの感染リスクが低減されるかもしれません。研究者らがオランダのある病院で医療従事者を対象に調査を実施しました。新型コロナ感染拡大の第2波において、4価インフルエンザワクチンを接種した人と、接種しなかった人の新型コロナ感染率を比べたのです。感染率は接種者が2%だったのに対し、未接種者は3.9%。インフルエンザワクチンの接種がリスクを50%下げていたそうです。News-Medicalの記事です。

自由な時間が増えれば増えるほど、人の幸福度は高まるのでしょうか。米国の研究チームが同国で21,736 人分のデータを分析。幸福度は、1日の自由時間が2時間程度までは高まるのですが、そこからは横ばいになり、5時間を超えると低下することが分かったそうです。別の6000人以上を対象にしたオンライン調査では、自由時間が多い環境でテレビを見るなどの非生産的な活動をすると、幸福度が下がる傾向にあったとのこと。EurekAlert!の記事です。

ピーナッツを多く摂取する人は、脳卒中や循環器疾患のリスクが低くなるようです。大阪大学や国立がん研究センターなどの研究チームが、国内に住む45~74歳の成人74,000人を15年間追跡。3,599人が脳卒中を発症し、849人が虚血性心疾患を発症しました。分析の結果、ピーナッツを多く摂取する人は、摂取しない人に比べて▽脳梗塞リスクが20%▽全脳卒中リスクが16%▽循環器疾患リスクが13%――それぞれ低いことが分かったそうです。EurekAlert!の記事です。

タイのバンコクの市場で、脇の下の汗から新型コロナウイルスを検出する携帯型装置の試験が行われたそうです。同国の研究チームが開発したこの装置は、コロナ患者の汗に含まれる細菌が生み出す特殊なにおいを検知。綿棒を脇の下に15分間挟み、その汗を分析装置で調べるといいます。市場の店員を対象に行った試験では、95%の精度だったとのことです。ただし、研究内容の発表や査読はまだ行われていないようです。Medical Xpressの記事です。

「ちゃんと見える」と、子どもの学力はアップするようです。米国の研究チームが、同国の小学3年~中学1年の子ども2,304人を3年間調査。視力検査の結果に基づいて適切な眼鏡を与えられた子どもは、1年後のリーディングや算数の得点が改善されたそうです。特に、成績下位や特別支援教育を受けている子どもで、改善が顕著だったとのこと。研究者は「眼鏡をかけることは2~4カ月の追加教育に相当する」とみています。EurekAlert!の記事です。

米デューク大学が心停止後臓器提供(DCD)による小児心臓移植に成功したそうです。患者は14歳の女性で経過は良好。一般的に心臓は、脳死したドナー(臓器提供者)から摘出され、レシピエント(移植を受ける患者)に移されます。今回は食品医薬品局(FDA)から許可を得て、心停止後のドナーに対し、脳死した成人ドナーの心臓の動きを維持するための技術が活用されたそうです。この技術を使っての小児DCD移植は全米初とのこと。News-Medicalの記事です。

人はなぜ、陰謀論を信じるのでしょうか。オランダの研究チームが英国や米国で5つの調査を実施したそうです。同じ事柄を扱った二つの記事を使い、取り上げ方や文体が読み手に与える印象の違いなどを調査しました。その結果、人は刺激的で注目度抜群の話だと感じるほど、陰謀論を信じやすくなることが分かったそうです。センセーショナルな表現のニュースは、陰謀論を信じる人を増やす危険性があるとのこと。PsyPostの記事です。

眼疾患は認知症リスクを高めるようです。研究者らが英国の55~73歳の12,364人のデータを分析。眼疾患のない人に比べて、加齢黄斑変性の人は26%▽白内障の人は11%▽糖尿病関連眼疾患の人は61%――それぞれ認知症リスクが高かったそうです。緑内障の人は血管性認知症リスクのみ上昇したとのこと。眼疾患に加え、心疾患、脳卒中、糖尿病、うつ病を併発していると、どちらか片方だけを発症しているよりもリスクが高いそうです。EurekAlert!の記事です。

オフィス内の空気の質は、生産性にも影響を与えるのだそうです。米国の研究チームが、世界6カ国で週3回以上内勤のある18~65歳の会社員計300人を1年間調査。アプリを使い、色を識別したり算数の問題を解いたりする認知テストを実施し、オフィス内の空気の質との関係を調べました。その結果、微小粒子状物質PM2.5や二酸化炭素(CO2)レベルが上昇すると、認知テストにおける反応速度や正確性に悪影響がみられたそうです。EurekAlert!の記事です。

高性能な最新のスマート歯科インプラントが紹介されています。このインプラントは、細菌を寄せ付けないようにするためにチタン酸バリウムナノ粒子を使用しています。また、自然な口の動きから電力が生み出され、歯肉組織を健康に保つための光線療法を行う技術も搭載しているそうです。5~10年で交換しなくてはならない既存のインプラントに比べ耐久性にも優れているといいます。米国の研究チームの成果が、Medgadgetに紹介されています。

マインドコントロールを行うカルトにまつわる誤解が挙げられています。記事は、カルト信者は一見普通に見えることが多いため、「マインドコントロールは存在しない」と考える人がいるが、それは誤りだと指摘。マインドコントロールは自律的な意思決定能力を奪ってしまうため、「大人だから干渉すべきでない」というのも間違いだといいます。「知的だからからカルトにはまらない」なども誤った認識とのこと。Psychology Todayの記事です。

シンガポールの研究チームが、人工知能(AI)を使って緑内障の診断を行う新たなシステムを開発したそうです。このシステムは、網膜のさまざまな角度の画像を組み合わせて3次元の「ステレオ眼底画像」作成し、それを分析するアルゴリズムを使用。これによって、緑内障の視神経と正常な視神経を識別するといいます。実験の結果、診断の精度は97%だったそうです。医療アクセスが乏しい地域での活用が期待されるとのこと。News-Medicalの記事です。
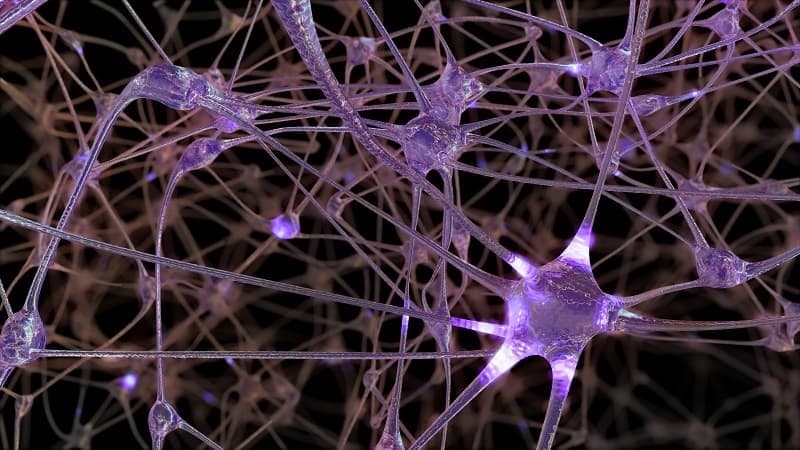
多発性硬化症(MS)の発症リスクは青年期にかかった感染症と関係があるそうです。スウェーデンと英国の研究チームが、青年期に脳や脊髄の感染症を患った人は後のMSリスクが180%高くなることを発見。また、呼吸器感染症で入院したティーンエージャーは、同リスクが51%高かったとのこと。なお、これまでの研究で、思春期に脳しんとうを起こしたり肺炎にかかったりすると、MSリスクが上がることが分かっているといいます。News-Medicalの記事です。

「再利用している布マスク、まだ捨てないで」。米国の研究者がそう呼び掛けています。米国の研究チームが2層構造の綿布を最大52回(週1回洗濯した場合の年間回数に相当)、洗濯・乾燥しました。布の線維がバラバラになりましたが、ろ過効率に影響はみられなかったようです。ただし、サージカルマスクに比べて保護効果が低いことも事実。サージカルマスクの上に布マスクを重ねると高い保護効果が得られるとのこと。EurekAlert!の記事です。
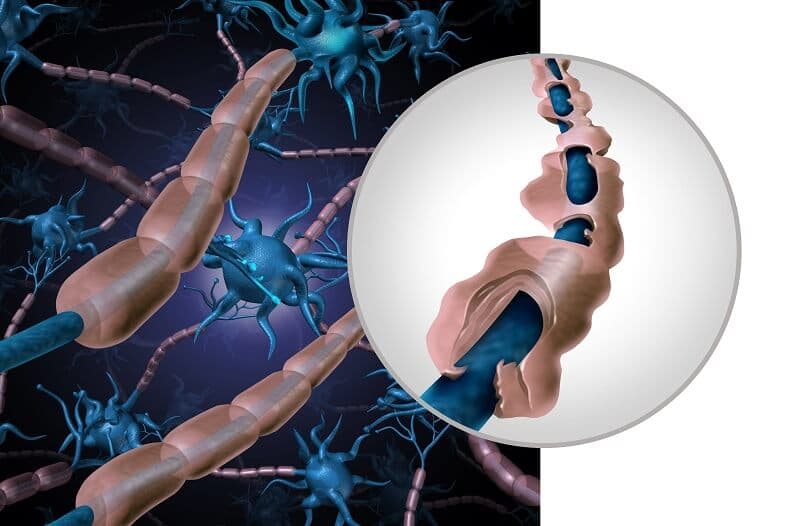
多発性硬化症(MS)とうつ病は併発することが多く、両方を発症した人は早期死亡リスクが高まるようです。英国の研究チームがMS患者12,251人と非MS患者72,572人を調査。研究開始時点で、MS患者の21%、非MS患者の9%がうつ病を発症していたといいます。うつ病のあるMS患者は、MSもうつ病も発症していない人に比べて10年間で死亡するリスクが5倍高かったそうです。うつ病のないMS患者は、同リスクが4倍高かったとのこと。ScienceDailyの記事です。
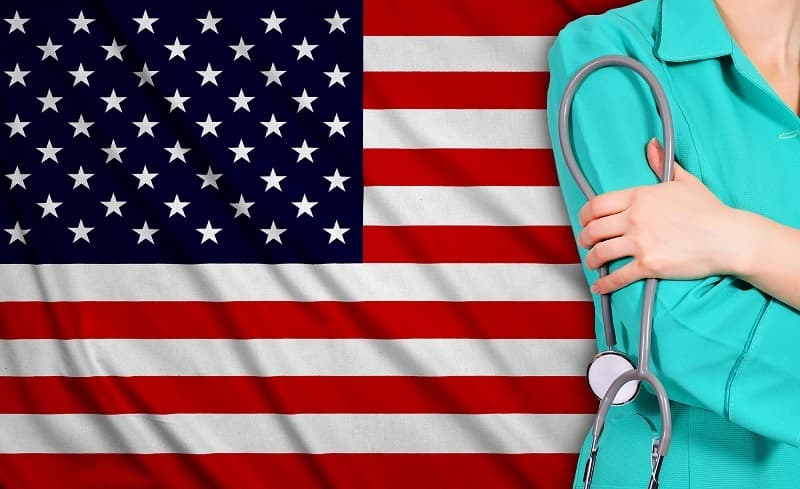
米国で医学部への出願が急増しているそうです。直近の医学部の志願倍率はスタンフォード大学が122倍超、ボストン大学が109倍超。米国全体では、2020年の出願件数が前年比18%増加したといいます。02~20年で出願数は60%近く増加していますが、医学部の新設が進まないため、実際に在籍した学生は35%しか増えていないそうです。こうした状況から、海外、特にカリブ海地域の医学部に目を向ける受験生も多くなっているとのこと。Forbesの記事です。

関節リウマチやクローン病、乾癬などの免疫介在性炎症性疾患(IMID)患者は、新型コロナの重症化リスクが高くなるようです。英国の研究チームが18~110歳の成人17,672,065人のデータを分析。1,163,438人がIMIDを持っており、17%が炎症性関節疾患、17%が炎症性腸疾患、66%が炎症性皮膚疾患でした。IMID患者は一般集団に比べて、コロナによる▽死亡リスクが23%▽集中治療を要するリスクが24%▽入院リスクが32%――それぞれ高かったそうです。News-Medicalの記事です。

ニコチンを含有する電子タバコは、血液や血管に悪影響を及ぼすそうです。スウェーデンの研究チームが18~45歳の健康な喫煙者22人を調査。ニコチン含有電子タバコを吸うと、15分後には血栓が23%増加し、血管も一時的に狭くなったそうです。ニコチン非含有電子タバコでは、同様の影響は確認されなかったとのこと。研究者は「長期的に使用すると心筋梗塞や脳卒中を引き起こす可能性がある」と注意を呼び掛けています。EurekAlert!の記事です。

山火事の煙と流産の関係について、気になる研究結果が報告されています。米国の研究チームが2018年11月にカリフォルニア州で起きた山火事の影響を調査。この時期に妊娠初期だったアカゲザル45匹のうち、無事に出産したのは37匹(82%)だったそうです。通常は86~93%が無事に出産までたどり着くとのこと。アカゲザルはヒトの妊娠に関する有用な動物モデルと考えられています。妊婦はなるべく煙を避けた方がよさそうです。ScienceDailyの記事です。

食物アレルギーの治療として、原因となる食べ物を少しずつ摂取して症状が出ないようにする「経口免疫療法(OIT)」が注目されています。米食品医薬品局(FDA)は2020年、4~17歳のピーナッツアレルギー患者に対する治療薬として、ピーナッツ粉を原料とした薬を承認しました。しかし、米国の研究チームが、全50州から集めた食物アレルギー患者781人を対象に調査を実施したところ、72%がOITのことを知らなかったそうです。ScienceDailyに紹介されています。

他人が無心に手や足をそわそわ動かしているのを見て、強い不快感を持ったり激しい怒りが沸き起こったりする人はいませんか。これは「ミソキネシア」と呼ばれる心理現象だそうです。カナダの研究チームが4,100人を調査したところ、3人に1人が、他人の動きに過敏であると報告したといいます。そういった人は、そわそわ動いている人を見ると無意識に共感し、一緒にネガティブな感情になっている可能性があるとのこと。ScienceAlertの記事です。

大気汚染が子どもの健康に与える悪影響が、また明らかになりました。インドの研究チームが同国の子ども3,157人を調査。比較的空気がきれいな地域に住む子どもの16.4%が太り過ぎだったのに対し、大気汚染が深刻とされるデリーでは太り過ぎの子どもが39.8%に上ったそうです。研究者は、大気中の汚染物質によって内分泌系が異常をきたすことが肥満につながると説明します。また、デリーの子どもは喘息リスクも高かったとのこと。BBCの記事です。
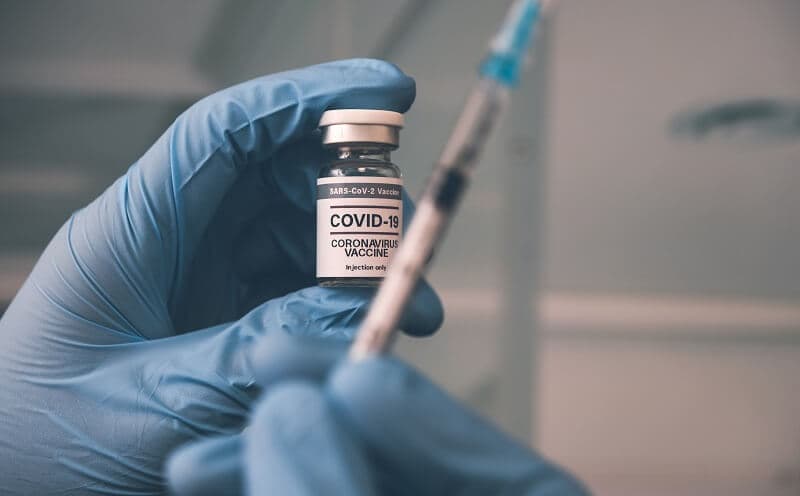
新型コロナウイルスに感染したことがある人は、再感染リスクが低いそうです。研究者らが、新型コロナの再感染に関して言及している全ての研究を対象に系統的レビューを実施。コロナへの感染歴が再感染に対して、ワクチンと同等あるいはそれ以上の保護効果をもたらすとの結論に達したそうです。具体的には、感染歴のある人は再感染のリスクが90%減少し、予防効果は10カ月間持続することが分かったとのことです。News-Medicalの記事です。

脳卒中後の「失読」について、有効なリハビリ方法が見つかるかもしれません。米国の研究チームが、脳卒中既往歴のある人30人とそうでない人37人の読む能力とMRI脳画像を分析。失読には脳の損傷領域に応じて2パターンあることが判明したそうです。左前頭葉を含む脳卒中は単語を発音することに問題が生じ、左側頭葉と頭頂葉を含む場合は単語を発音することに加えて単語全体の認識力にも問題が生じていたとのこと。EurekAlert!の記事です。

過去最大規模の調査で、「自己調整」に関連する遺伝子座が600近く同定されたそうです。米国などの研究チームがヨーロッパ系の150万人分のデータを分析。アルコールやオピオイドへの依存、行動障害などに関連する579の遺伝子座を特定したそうです。これを基に、さまざまな遺伝的リスクを予測するスコアも構築したといいます。リスクを抱えていることが分かれば、早期介入や予防プログラムの実施が可能になるとのこと。Medical Xpressの記事です。

親の喫煙が子どもに与える悪影響が、また一つ明らかになりました。子ども時代に親が喫煙していた女性は、成人後に血清陽性の関節リウマチ(RA)を発症するリスクが高くなるそうです。米国の研究チームが35~52歳の女性90,923人を中央値で27.7年間追跡。子ども時代に親が喫煙者だった人は血清陽性のRA発症リスクが75%高かったといいます。また、後に本人が喫煙者になるとこのリスクはさらに上昇することも分かったそうです。Medical Xpressの記事です。

緑の多い地域に住む人は心血管疾患を発症しにくいようです。米国の研究チームが65歳以上の高齢者243,558人を5年間調査。緑の多い地域に住み続けた人は、緑の少ない地域に住み続けた人に比べて心血管疾患の発症リスクが16%低かったそうです。5年間で周囲の緑が増えた人もリスクが低くなったといいます。要因としては、大気汚染や騒音から守られていること、屋外での運動量が多くなることなどが考えられるようです。News-Medicalの記事です。

米国で新型コロナワクチンの接種に否定的な立場を取る人について、その割合と理由がさまざまな角度から分析されています。カイザー・ファミリー財団の全国調査によると、若者(18~29歳)の21%が「ワクチンを接種しない」と回答。女性より男性、民主党支持者より共和党支持者の方がワクチンに否定的な人が多いそうです。財団は、新型コロナで死亡している人の98%が、ワクチン接種を拒否した人たちだったとの推計も出しています。Forbesの記事です。

料理で使う塩を「低ナトリウム塩」に換えると、脳卒中のリスクを下げるようです。豪州の研究チームが中国の農村で、脳卒中既往歴がある人または60歳以上で高血圧の成人20,995 人を平均4.74年間調査。半数には低ナトリウム塩(塩化ナトリウム75%、塩化カリウム25%)を使ってもらい、別の半数には通常の塩を使ってもらいました。低ナトリウム塩を使った人は通常の塩を使った人に比べて脳卒中を発症するリスクが低かったそうです。ScienceDailyの記事です。

インスタント麺やスナック菓子などの「超加工食品」をたくさん食べる人は、心血管疾患になりやすいようです。ギリシャの研究チームが、平均年齢45歳の心血管疾患のない成人2,020人を10年間調査。超加工食品の摂取が週に1回増えるごとに、10年以内に心血管疾患を発症するリスクが10%増加することが分かったそうです。超加工食品の例としては、再構成肉や甘い炭酸飲料、大量生産のパンなども挙げられています。Medical Xpressに紹介されています。

若い時の飲酒は動脈硬化を促進するようです。英国の研究チームが、若者1,655人を対象に17歳と24歳時点の飲酒・喫煙習慣と動脈硬化の進行を調査。飲酒量が多い人ほど、この期間内に動脈硬化が進行したそうです。喫煙に関しては、1日に10本以上タバコを吸う女性にのみ有意な関連が認められたとのこと。動脈硬化は心臓病や脳卒中につながる可能性があります。研究者は若い時の行動に注意するよう呼び掛けています。EurekAlert!の記事です。

糞便移植療法が、新型コロナの治療に有効かもしれません。新型コロナに感染している19歳と80歳のポーランド人の男性が、クロストリジウム・ディフィシル腸炎を治療するために糞便移植をしました。2人はそれぞれ、コロナの重症化リスクを高める要因である免疫不全と肺炎を患っていましたが、症状が悪化することはなく数日で熱は治まり、再発もしなかったといいます。研究者は、糞便移植がコロナに対する免疫を強化する可能性があるとみています。「ScienceAlert」の記事です。

脂肪が多い魚を食べると片頭痛が和らぐかもしれません。片頭痛を緩和するには、日ごろの食生活で植物油を控え、魚に含まれる脂肪を多く取ると効果的ということが、米国内の研究で分かりました。実験には、複数の頭痛薬を服用していながら、1日に5時間以上の片頭痛が月平均で16日以上ある成人182人が参加。植物油を控え、脂肪の多い魚を多く食べた患者は、他の患者に比べ、頭痛を感じる時間が30~40%減ったといいます。「Medical Xpres」の記事です。

母親が妊娠中に太っていると、子どもの大腸がんリスクが高まるようです。研究者らが米国の母子18,000組を抽出し、子どもを60年にわたり追跡。母親が妊娠中に「太り過ぎ(BMI25~29.9)」「肥満(BMI30以上)」だった子どもは、母親が「正常(BMI18.5~24.9)」「痩せ気味(BMI18.5未満)」だった子どもに比べて成人後の大腸がんリスクが倍増したそうです。胎内で受け取った栄養素やさらされたホルモンの量がリスクと関係している可能性があるとのこと。Medical Xpressの記事です。

1日8時間以上座って過ごしている人は注意が必要です。カナダの研究チームが、40歳以上で脳卒中既往歴のない143,000人を平均9.4年間調査。座っている時間が1日8時間以上で身体活動をあまりしない人は、座っている時間が4時間未満で10分以上運動をする人に比べて脳卒中リスクが7倍高かったそうです。報告された脳卒中は2965件で、動脈が詰まって脳に十分な血液が届かなくなる虚血性脳卒中が9割を占めたとのこと。CNNの記事です。

米国でインフルエンザと新型コロナの同時流行に対する警戒が高まっているようです。昨冬インフルエンザは流行しませんでしたが、今冬は学校が再開していることなどから感染拡大が懸念されています。専門家は、マスクの着用、手指衛生、旅行の制限などでウイルスのまん延を防ぐよう呼び掛けています。また、米疾病対策センター(CDC)は10月末までにインフルエンザワクチンを接種するよう提言しているそうです。CNNの記事です。

新型コロナに対する効果を巡り物議を醸している抗寄生虫薬「イベルメクチン」について、注意点がまとめられています。この薬はヒトや家畜の寄生虫症治療に使われ、コロナへの有効性を示す科学的証拠は不十分です。米疾病対策センター(CDC)によると、過剰摂取によって神経障害やけいれんなどの有害事象が起こることがあり、死亡する危険もあります。米国や豪州はコロナ治療薬としての使用に警鐘を鳴らしているそうです。ScienceAlertの記事です。

妊娠中に抗精神病薬を服用しても、出産や子どもに悪影響はないようです。英国のチームが香港で出産した数十万人を15年以上追跡。妊娠中の抗精神病薬服用と、子どもが自閉症スペクトラム(ASD)や注意欠陥多動性障害(ADHD)などを持つリスクの間に関連性は認められなかったそうです。早産や赤ちゃんの低体重との関連性を示す証拠も得られなかったとのこと。研究者は「抗精神病薬による治療を中止すべきではない」としています。ScienceAlertの記事です。

英国の研究チームが、新型コロナ患者の治療に使う呼吸補助装置を開発したそうです。この装置の製造にかかる費用は150ポンド(約22,700円)と安価。電子機器の冷却ファンを使って空気の流れを作る簡単な仕組みです。酸素ボンベや酸素供給システムの使えない低中所得国での活用が期待されています。10人の健康な人に対する試験では有害事象は報告されず、患者を対象にした治験が9月にウガンダで実施される予定とのこと。EurekAlert!の記事です。

米国の複数州でサルモネラ菌による食中毒が発生したようです。米疾病対策センター(CDC)によると、8月26日現在で患者は合わせて36人。2種類のサルモネラ菌株が検出されたそうです。患者は発症前にサラミや生ハムなどの加工肉製品を食べていたことが分かっています。CDCは「原因が特定されるまで、これらの食品は内部が約74℃になるまで加熱して食べるように」と注意を呼びかけています。CNNの記事です。

世界保健機関(WHO)が「注目すべき変異株」に位置付けた新型コロナウイルス「ミュー株」についての情報です。ミュー株は2021年1月にコロンビアで最初に発見され、8月下旬までに39カ国で確認されているそうです。ウイルスが細胞に侵入する時に使うスパイクタンパク質に変異を起こしている可能性があるといいます。ワクチンはスパイクタンパク質を標的にしているので、ワクチンの効果の低下が懸念されているとのこと。ScienceAlertの記事です。
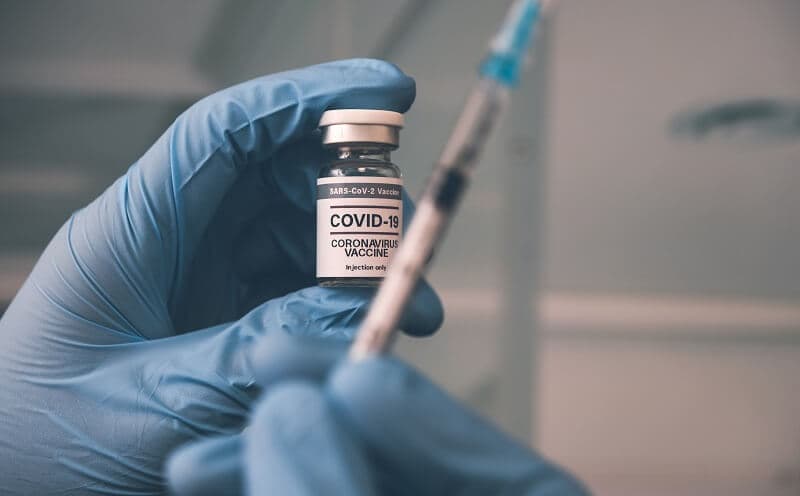
ファイザー製の新型コロナワクチンの安全性を裏付ける研究結果が出たようです。イスラエルなどの研究チームが同国の数百万人分の健康記録を分析。ワクチン接種後の有害事象については、心筋炎、リンパ節の腫れ、虫垂炎、帯状疱疹のリスクが上昇することが分かりました。一方で未接種者がコロナに感染すると、心膜炎や肺塞栓症、脳卒中などのリスクが大幅に上がることが明らかになったそうです。Medical Xpressの記事です。

幼少期を貧困の中で過ごすと、脳の発達が妨げられるようです。米国の研究チームが、3~5歳の子ども216人を17年間調査。未就学時代に貧困状態にあった子どもは、情報伝達に関わる皮質下領域、記憶や学習に関わる海馬、感覚情報の中継点となる視床などの体積が小さく、その後もあまり大きくならなかったそうです。これが認知機能の低さや行動面での問題につながる可能性があるとのこと。News-Medicalの記事です。

母乳中に多く含まれるヒトミルクオリゴ糖(HMO)がB群溶血性連鎖球菌(GBS)感染の抑制に有効かもしれません。GBSは膣などの常在菌で、出産の時に赤ちゃんに感染して重大な病気を引き起こすことがあります。米国の研究チームが、HMOが胎盤免疫細胞などのGBS増殖を阻害することを発見したそうです。また、妊娠中のGBS感染マウスをHMOで治療したところ、生殖器の5カ所でGBS感染が有意に抑制されたとのこと。News-Medicalの記事です。

ジカウイルス(ZIKV)感染症に関連する新生児小頭症の原因が判明したようです。治療法開発につながるかもしれません。中国の研究チームが、ZIKVに感染させたマウスの脳内で、エネルギー産生に関わる物質「ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NAD)」のレベルが劇的に低下していることを発見。子どものZIKV感染マウスにNADを注射で投与したところ、神経細胞死を抑え、脳重量の減少を防ぐことができたそうです。Medical Xpressの記事です。

女性の生殖可能年齢に影響を与える遺伝子が新たに見つかったそうです。国際的な研究チームが何十万人もの女性のデータを分析。これまで、生殖可能年齢に関連する遺伝子変異は56個が知られていました。今回の新発見で計290個が特定されたことになるといいます。さらに、「CHEK2遺伝子を不活性化」または「CHEK1遺伝子を過剰発現」させると、マウスの生殖可能期間が25%延長することも新たに分かったそうです。ScienceDailyの記事です。

脳卒中患者にとって運動は、早期死亡リスクを下げるための有効な手段になるようです。カナダの研究チームが、脳卒中既往歴のある895人(平均72歳)と既往歴のない人97,805人(平均63歳)を平均4.5年間調査。脳卒中後に週3~4時間(1日約30分)のウォーキングに相当する運動を行った人は、そうでない人に比べて全死因死亡リスクが54%低かったそうです。週6~7時間の運動はさらに効果があるとのこと。ScienceDailyの記事です。

がんワクチンで、遺伝性大腸がん「リンチ症候群」のマウスの生存率を改善させることに成功したそうです。米国などの研究チームが、リンチ症候群モデルマウスを使って、ワクチンの標的にすべきネオアンチゲン(がん細胞に発現するタンパク質)4種を同定。この4種のネオアンチゲンを組み入れたワクチンをモデルマウスに投与したところ、強力な免疫反応が誘導され、生存率が改善したそうです。News-Medicalの記事です。

注意欠陥多動性障害(ADHD)の人の約半数は、大人になると症状がなくなると考えられてきました。しかし実態は全く違うようです。米国などの研究チームがADHDの子ども558人を8歳から25歳まで調査。このうち90%が大人になっても何らかのADHD症状を経験していたといいます。ほとんどの場合、症状の断続的な寛解期間があるとのこと。再発時に自分に合った対処法を持っていないと、悪化する可能性があるそうです。News-Medicalの記事です。

新型コロナから回復した人の血漿を使う回復期血漿療法は、軽症の「コロナ外来患者」の症状悪化を防ぐことはできないようです。米国の研究チームがコロナ感染後1週間以内に軽症で外来を受診した患者511人を調査。患者はみな肥満や高血圧、糖尿病、心臓病などがあり、重症化リスクの高い人々です。回復期血漿で治療をした群もそうでない群も、症状が悪化した人の割合は変わらなかったそうです。Medical Xpressの記事です。

新型コロナに有効な化合物が見つかったようです。米国の研究チームが、米食品医薬品局(FDA)の承認済みの化合物1,400種類について調査しました。それらの化合物が、コロナウイルスに感染したヒト細胞にどのような影響を与えるのかをAIを使って画像分析しました。その結果、栄養補助食品「ラクトフェリン」が感染を防ぐのに有効であることが分かったそうです。近く臨床試験を実施予定とのこと。Medical Xpressの記事です。

抗凝固薬「ヘパリン」が新型コロナの中等症患者の治療に有効かもしれません。米国などの研究チームが、新型コロナで入院している中等症患者2,200人を調査。ヘパリンで治療された患者は、通常の治療を受けた患者と比べ、挿管などを行うことなく回復して退院する可能性が4%高かったそうです。ただし別の研究で、重症患者にはヘパリン治療は効果がないことが明らかになっているようです。ScienceDailyに紹介されています。

モデルナ社がヒト免疫不全ウイルス(HIV)ワクチンの第1相臨床試験を開始したようです。この治験はHIVに感染していない18~50歳の健康な成人56人が対象です。10カ月間かけて、安全性と基本的な免疫反応を確認するそうです。このワクチンは、同社の新型コロナワクチンで成功を収めているmRNAの技術を利用しているとのこと。HIVのmRNAワクチンについてヒトで臨床試験を行うのは、世界で初めてです。ScienceAlertの記事です。