非公開の医師求人情報を
ご紹介いたします!
マイナビDOCTORでは、医師専任のキャリアパートナーが
あなたの転職活動をサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。
世界の医療ニュースの中から、厳選した記事をギュッと凝縮して紹介します。
1日数本を1分で、サクッと読むことができます。日々の情報収集、話のネタ探しにお役立てください。
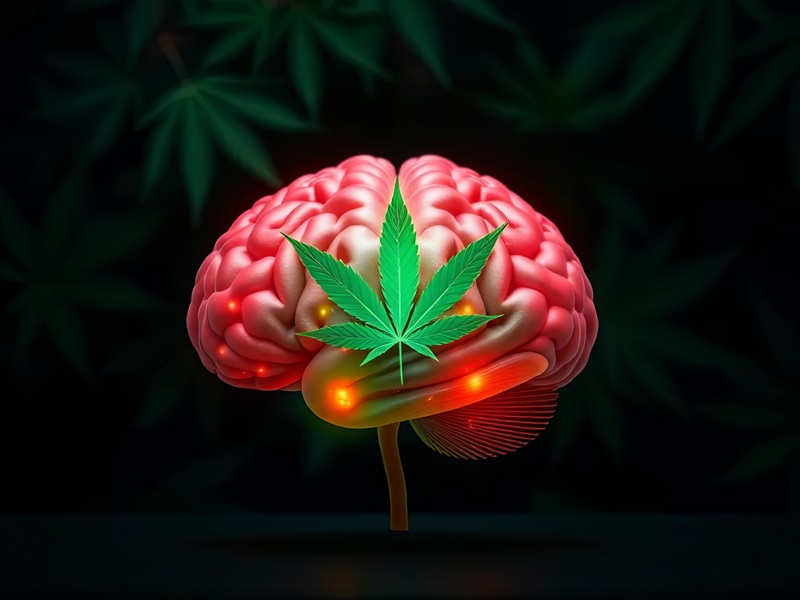
大麻の使用は、必要な情報を一時的に記憶して処理する能力「ワーキングメモリ」に長期的にも短期的にも悪影響を及ぼす可能性があるそうです。米国の研究チームが、医学誌JAMA Network Openに研究成果を発表しました。
チームは、22~36歳の成人1003人を対象に大麻と認知機能の関係を調査しました。その結果、大麻の多用(生涯で1000回以上の使用)は、ワーキングメモリに関わる課題を行う際の脳活動の低下に関連することがMRI検査で明らかになったそうです。
尿検査の結果から最近大麻を使用したと定義された人も、その人たちを除外しても、こうした結果が表れたそうです。このことからチームは、大麻の多用によって脳に長期的な影響が及ぶ可能性が示されたとしています。
また、大麻による脳活動の低下は、特に意思決定や記憶、注意、感情処理などの重要な認知機能に関与する領域(背外側前頭前皮質、背内側前頭前皮質、前島皮質)において顕著だったといいます。
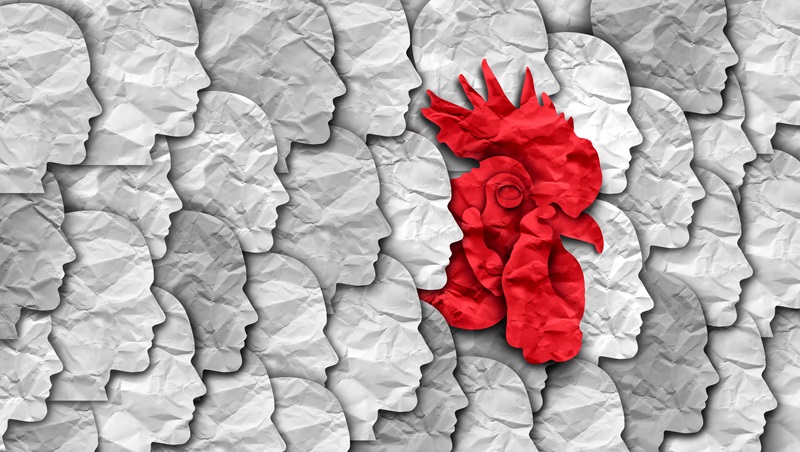
英国の健康安全保障庁(UKHSA)は、イングランド中部のウェスト・ミッドランズの農場労働者に鳥インフルエンザウイルス(H5N1型)が感染したと発表しました。
UKHSAによると、この患者は感染した多数の鳥と長期にわたり密接に接触していたそうです。患者は感染症病棟に入院しましたが、現在の体調は良好だといいます。この患者から周囲の人に鳥インフルがうつったという証拠は見つかっていないとのことです。また、患者に感染したウイルスは、米国で哺乳類や鳥の間で流行しているものとは遺伝子型が違うそうです。
英BBCによると、ウェスト・ミッドランズにあるシュロップシャーの農場で鳥インフルの大流行が発生したことから、この地域は「鳥インフルエンザ防護区域(AIPZ)」に指定されたばかり。AIPZに指定されると、いかなる家禽も屋外に出すことはできないといいます。大流行が起きたシュロップシャーの農場では、100万羽もの採卵鶏の殺処分が続いているとのことです。

米国で、「注意欠如・多動症(ADHD)」と診断される成人が急増しているそうです。そのような中で、診断方法にばらつきがあることが課題になっており、ADHDと関連障害の米国の学会(APSARD:The American Professional Society of ADHD and Related Disorders)が、成人を治療する医療従事者向けの診断および治療のガイドラインを今年後半に公表する予定だそうです。AP通信が報じました。
発達障害の一種であるADHDは男児に多く見られ、成長とともに落ち着くものとこれまで考えられてきました。しかし専門家によると、多くの人が子供の頃に診断されず、実際は大人になっても症状を抱えたまま生活しているといいます。最近の研究で、1500万人以上の米国の成人(17人に1人)がADHDの診断を受けており、成人患者の約半数が18歳以降に診断されていることが分かったそうです。
ADHD急増の背景には、2013年に診断基準が変更され、ADHDの定義が広がったことが挙げられます。しかし、20年に始まった新型コロナウイルス感染対策のためのロックダウン(都市封鎖)で、軽度のADHDを持っていた人が症状を悪化させた可能性もあるそうです。

米疾病対策センター(CDC)は職員に対し、WHO(世界保健機関)と連携して行っている業務を直ちに停止するよう命じたそうです。AP通信がCDCの内部文書を入手して報じました。
AP通信によると、今回の業務停止命令はWHOと協働する全ての職員が対象で、CDCの職員はWHOの事務所に立ち入ることも禁じられたといいます。WHOには現在、CDCから30人近くの職員が派遣されており、感染症や公衆衛生に関するWHOの専門家と日常的に連絡を取り合って、世界中で起きている健康上のリスクやその対応方法について相談しているそうです。
就任直後のトランプ大統領は先週、WHOから脱退する手続きに入るための大統領令に署名しましたが、WHOからの脱退には議会の承認や1年前の通知などが必要になります。そのため、脱退へのプロセスは緩やかなものになると予測されていました。
しかし今回の突然の措置で、世界の公衆衛生に悪影響が及ぶ可能性が懸念されています。米国にとっても、最新の専門的知見を得る機会を失うことになるとの指摘も出ているとのことです。

鳥インフルエンザウイルスH5N1型が感染して、病気になったり死んだりする飼い猫が米国で増えているそうです。ウイルスに汚染された生のペットフードや生乳の摂取が原因のようです。米食品医薬品局(FDA)はペットフード会社に対し、予防措置を講じるよう求めているといいます。
米公共ラジオNPRが、米カリフォルニア大学デービス校の獣医学博士の解説を紹介しています。その獣医学博士によると、鳥類の間でH5N1の感染がまん延し始めた2022年以降、70匹以上の猫が鳥インフルH5N1型に感染しています。その多くが家畜小屋で飼われていた猫で、感染した牛の生乳を飲んでいたそうです。
テキサス州のある酪農場では、鳥インフルが感染した猫の約半数が死んだといいます。また、生の七面鳥を冷凍したペットフードを食べた猫に鳥インフルが感染して死んだ事例なども報告されているとのことです。ウイルスを死滅させる唯一の方法は熱を加えることだそうです。
今のところ、H5N1型が猫からヒトに感染したケースは確認されていないといいます。猫からヒトに感染する可能性は非常に低いのですが、ゼロではないため注意が必要です。

感染によって全身で炎症が起こり、結果として臓器障害が生じる「敗血症」について、そのメカニズムが新たに明らかになったそうです。米国の研究チームが、科学誌Cellに論文を発表しました。チームは、敗血症の炎症の悪循環を引き起こすのは、感染そのものではなく、感染細胞が放出する致命的なタンパク質が原因であることを突き止めたそうです。
細菌などに感染した細胞は、「ガスダーミンD」という細胞膜に穴を開けるタンパク質を自らの表面に送り出すといいます。その穴から細胞内の成分が漏れ出すことで自身を崩壊させ、感染の広がりを防ぐのだそうです。しかし、細胞が感染に対して迅速に反応した場合、穴のあいた部分を切り離すことで、その細胞は生き残ることができるといいます。
一方で、切り離された部分はガスダーミンDを含む小さな袋状の「小胞」になって、周囲を浮遊します。何らかの拍子に小胞が別の細胞の表面にくっつくと、そこから穴が開いて、感染していない健康な細胞が死んでしまうとのことです。チームは、これが広がることで敗血症が悪化するとしています。
WHO(世界保健機関)によると、世界中で毎年1100万人が敗血症で死亡しているそうです。

寝つきをよくするために少量の酒を飲む人は少なからずいるのではないでしょうか。しかし、かなりの量のアルコールを摂取しないと入眠には影響しないそうです。そして、アルコールは少量でも睡眠の質を下げてしまうといいます。英国の睡眠の専門家による記事がThe Conversationに掲載されています。
記事ではアルコール摂取量と睡眠の関係を分析したオーストラリアの研究チームの報告を紹介しています。その研究によると、寝酒による鎮静効果で入眠までの時間が短縮されるのは、寝る前の3時間以内に高用量(グラスワインで3~6杯相当)のアルコールを摂取した場合のみだそうです。
また、アルコール摂取は、記憶や感情調整に重要な役割を果たす「レム睡眠」が最初に出現するタイミングを遅らせる上に、一晩の総レム睡眠時間を減少させてしまうといいます。こうしたレム睡眠の乱れは、低用量(標準的なアルコール飲料2杯相当)のアルコールを飲んだ後にも発生するとのことです。
別の研究では、夜の飲酒を繰り返すと、飲酒を控えた夜にも睡眠が乱れる可能性が示されたといいます。専門家は、禁酒や減酒の重要性を訴えています。
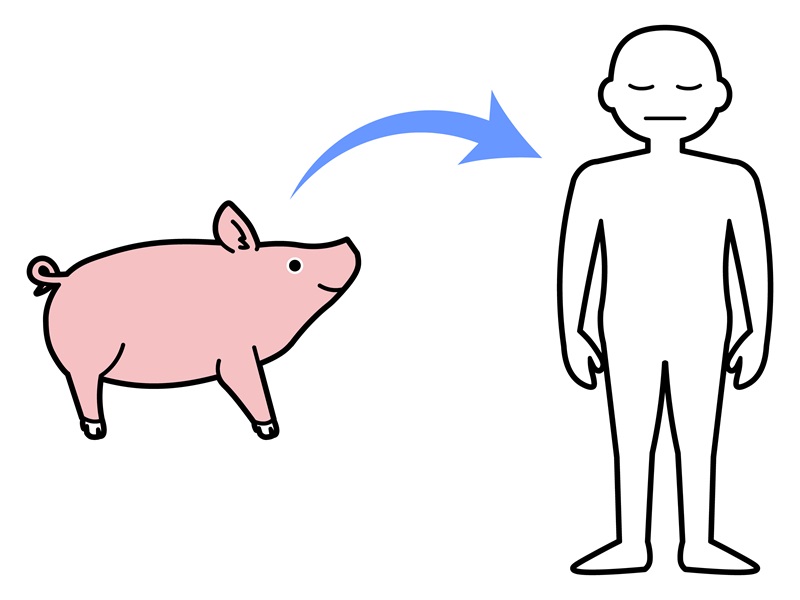
米ニューヨーク大学ランゴーン医療センターで昨年11月25日にブタの腎臓移植を受けた53歳の女性が、節目となる「術後2カ月生存」の記録を達成したそうです。米国ではこの女性の前に、2022年と23年にヒトへのブタの心臓移植手術がそれぞれ1件ずつ、24年にヒトへのブタの腎臓移植手術が2件実施されました。しかし、いずれの患者も術後2カ月以内に死亡しています。
AP通信によると、女性に移植されたブタの腎臓は、拒絶反応を防ぐために10個の遺伝子が改変されているそうです。女性は移植手術から11日後に退院したのですが、術後約3週間の時点で拒絶反応が始まるわずかな兆候が確認されたといいます。
女性は血液検査などの綿密な追跡調査を受けていたために、すぐに拒絶反応に対する治療を受けることができたそうです。この治療が成功して以降、女性に新たな拒絶反応の兆候はないといいます。医師によると女性の腎臓は完全に正常に機能しているとのことです。
現在は移植後の検査のためにニューヨーク市に住んでいますが、あと1カ月ほどで自宅のあるアラバマ州に戻れる見込みだといいます。

クチナシの果実から得られる化合物「ゲニピン」が、病気で損傷を受けたり発育不全になったりした神経細胞(ニューロン)の再生を促す可能性があるそうです。米国の研究チームが医学誌Science Translational Medicineに論文を発表しました。
チームは、さまざまな刺激を脳に伝えるなどの役割を持つ「感覚ニューロン」について、その変性を防ぐ方法を調べていたそうです。そして、640種類の化合物の中からゲニピンが有効であることを発見したといいます。
チームは、感覚ニューロンが集まった感覚神経や自律神経に異常が生じる、まれな遺伝性疾患「家族性自律神経失調症(FD)」の治療にゲニピンが利用できる可能性があるとみています。
培養皿での実験では、ゲニピンによってFD患者の感覚ニューロンが正常に発達するようになり、変性が抑制されることが分かったそうです。また、FDマウス2匹にゲニピンを投与したところ、感覚ニューロンに情報を伝達する末梢神経系の障害が改善することも示されたといいます。
さらに、切断された軸索(ニューロンから延びる突起)がゲニピンによって再生することも試験管内の実験で確認されたとのことです。
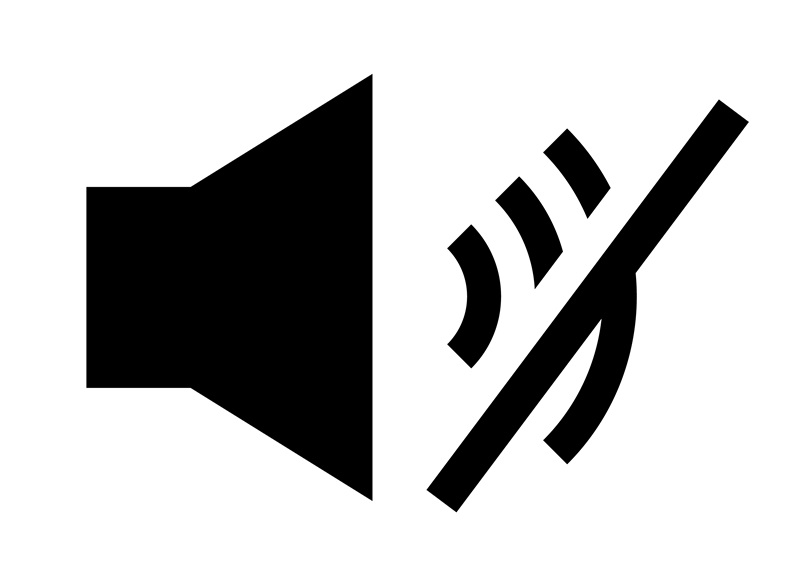
トランプ政権は連邦政府の保健機関に対し、外部への情報発信を一時的に停止するよう指示したそうです。この指令は2月1日まで有効とのことです。米国の各メディアが報じました。
米NBC Newsや米CNNによると、トランプ米政権の保健福祉省(HHS)長官代行が21日、米疾病対策センター(CDC)や国立衛生研究所(NIH)、食品医薬品局(FDA)に、大統領が任命した人物が確認し、承認するまでいかなる発信も控えるよう求めたそうです。
承認なしに公の場で演説をしないことや、公式文書の発行前に大統領任命者と調整することも指示に含まれているといいます。ただし、国民の健康や安全に関係する重要な情報については例外としているとのことです。
NIHは声明で、HHSから情報発信の一時停止の指示があったことを認め、「この停止期間中に、新たなチームが情報の精査や優先順位付けのための流れを整える」と述べたそうです。また、NIHには出張の一時取りやめに関する指示も出されたといいます。
新政権が保健機関に対して、情報の公表を一時停止することはあるそうですが、今回は指示の範囲が異常に広いそうです。

栄養豊富な海の幸のカキが、複数の抗菌薬に耐性のある「スーパーバグ(超多剤耐性菌)」に対抗するための希望の星になるかもしれません。オーストラリアの研究チームが科学誌PLOS ONEに論文を発表しました。
チームは、シドニー周辺に生息する岩ガキの一種「シドニーロックオイスター」の血リンパ(人間の血液に相当)から分離した「抗菌タンパク質」が、肺炎や咽頭・扁桃炎、髄膜炎、皮膚軟部組織感染症などを引き起こすレンサ球菌属の細菌を死滅させるのに有効であることを発見しました。抗菌タンパク質は多細胞生物が細菌と戦うために持つ物質です。カキの血リンパから分離した抗菌タンパク質は、細菌が身を守るために形成するバイオフィルムを通過できることも明らかになったそうです。
さらに、既存の抗菌薬にこの抗菌タンパク質を加えたところ、ほんのわずかな量で抗菌薬の効果が2~32倍に高まったといいます。特に、レンサ球菌属のほか、多剤耐性菌が問題になっている黄色ブドウ球菌や緑膿菌に対する効果が有望なことが分かったとのことです。さらに健康なヒト細胞に対する有害な影響は認められなかったそうです。

解熱鎮痛剤や抗血小板薬として使われるアスピリンは、遺伝性の大腸ポリープの再発や大腸がんのリスクを抑制するという研究結果が出ています。しかし、がん治療を行った後の再発予防には効果がないとの論文をシンガポールの研究チームが医学誌The Lancet Gastroenterology & Hepatologyに発表しました。
チームは、ステージ2~3に相当する大腸がんの切除手術をし、3カ月以上の標準的な術後補助化学療法(体内に残っているがん細胞を抗がん剤によって死滅させる治療)を受けた11カ国・地域の患者1587人を対象に治験(第3相)を実施しました。5年間の追跡調査で、定期的な診察や画像検査、大腸内視鏡検査を行ったそうです。
その結果、追跡期間中に病気をせずに生存した率(無病生存率)は、1日200mgのアスピリンを3年間服用した群で77.0%、プラセボ群で74.8%だったそうです。また、5年生存率については、アスピリン群で91.4%、プラセボ群で88.9%だったといいます。これらの結果は、アスピリン群とプラセボ群の間で大腸がんの再発予防における統計学的な有意差は認められなと結論付けられるとのことです。

肥満や糖尿病の治療薬として承認されている人気の「GLP-1受容体作動薬」について、さらなる効能やリスクがあることが示されました。米国の研究チームが、医学誌Nature Medicineに研究成果を発表しました。
チームは、糖尿病患者200万人のデータをふるいにかけ、オゼンピック、マンジャロ、ウゴービ、ゼップバウンドといったGLP-1受容体作動薬を処方された患者21.6万人と他の種類の糖尿病治療薬を処方された患者の健康状態を平均4年にわたり追跡しました。
その結果、GLP-1受容体作動薬は統合失調症、薬物やアルコールへの依存症、尿路感染症、慢性腎臓病、認知症、脳卒中、誤嚥性肺炎など42の健康上のリスクの低下に関連することが明らかになったそうです。反対に、吐き気、嘔吐(おうと)、腎臓結石、胃食道逆流、睡眠障害、非感染性胃腸炎など19のリスクが高まることも示されましたといいます。
ただ、今回対象になった患者は平均年齢が65歳以上で、白人が70%以上を占め、90%以上が男性でした。そのため、全てのGLP-1受容体作動薬使用者に当てはまらない可能性があるとのことです。
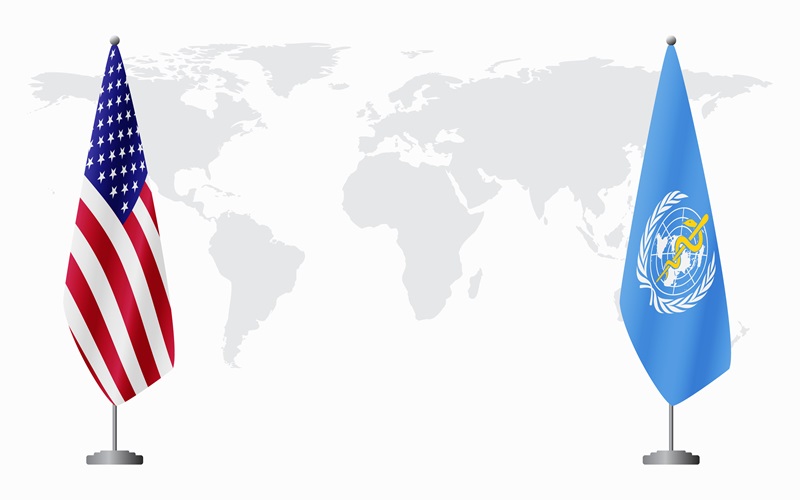
米国のトランプ大統領は就任初日の20日、WHO(世界保健機関)からの脱退を指示する大統領令に署名しました。各国のメディアが報じています。
AP通信によると、トランプ氏は新型コロナウイルスの感染拡大に関するWHOの対応が誤っていたと批判し、これらを脱退の理由として挙げています。トランプ氏は大統領1期目だった2020年7月にもWHOからの脱退を通告しました。しかし、21年1月に大統領に就任したバイデン氏がこの決定を覆したという経緯があります。
これまでWHOにとって米国は、資金や人材の面で最大の支援国の一つでした。23年は予算の18%が米国からの拠出だったそうです。こうした莫大な資金援助が絶たれることで、WHOが長年積み上げてきた公衆衛生をめぐる数多くの世界的戦略が損なわれる可能性が懸念されています。
米国にとっても、WHOのデータベースに迅速にアクセスできないなどの不利益が生じ、ワクチンや医薬品の製造の遅れなどにつながる可能性があるといいます。WHOは21日、今回のトランプ氏の決定について遺憾の意を表明し、再考を求めたとのことです。

希ガス(貴ガス)の一種である「キセノン」が、アルツハイマー病(AD)の治療に有効な可能性があるそうです。米国の研究チームが、医学誌Science Translational Medicineに研究成果を発表しました。
チームは、麻酔作用や神経保護作用を持つことが知られているキセノンをADマウスに吸入させる実験を行ったそうです。その結果、脳萎縮や神経炎症が軽減し、巣作り能力が改善することが分かりました。また、ADに関係するタンパク質アミロイドβの除去や認知機能の改善に関わるミクログリア(脳内の免疫細胞)の神経を保護する反応が、キセノンの吸入によって誘発されることも明らかになったといいます。
こうした治療効果は、アミロイドβの沈着による病変を持つマウスと、神経細胞の中にタンパク質タウが異常に蓄積する病変を持つマウスの両方で観察されたとのことです。
なお、キセノンガスは血液脳関門を通過し、脳内に入っていくことができるそうです。血液脳関門は、脳を保護するために、毛細血管中の物質を脳内に通すか否かを選択する仕組みです。
チームはキセノンがADの治療法に有望であるとして、ヒトでの第1相試験を数カ月以内に開始する予定とのことです。

若者がオリーブオイルや魚、食物繊維を多く摂取する「地中海式食事法」を取り入れると、腸内細菌叢(腸内フローラ)のバランスが変化し、脳に好影響が及ぶ可能性があるようです。米国の研究チームが科学誌Gut Microbes Reportsに研究成果を発表しました。
チームは人間の18歳に相当する若いラットで調査を行いました。その結果、地中海食を14週間与えられた群は、飽和脂肪の多い西洋食を与えられた群に比べてCandidatus Saccharimonas属をはじめとする4種類の腸内細菌が増加する一方で、ビフィドバクテリウム属など別の5種類の腸内細菌が減少することが分かったそうです。
そして、こうした腸内細菌の変化は、ラットの記憶力や学習能力の向上に関連することが、迷路を使った実験で示されたといいます。また地中海食は、新しい情報に適応するための認知の柔軟性や必要な情報を一時的に保存して処理するためのワーキングメモリの向上にも関連していたとのことです。
地中海式食事法は、主な脂肪源としてのオリーブオイル▽豊富な野菜、果物、全粒穀物▽魚と赤身のタンパク質▽赤身肉と飽和脂肪酸の制限▽さまざまな植物から取るたくさんの食物繊維――が重要な要素だそうです。

米国で鳥インフルエンザウイルスのヒトでのパンデミックに対する警戒が高まっています。米保健福祉省(HHS)が、現在家禽や乳牛の間で流行している鳥インフルエンザウイルス株に対応するmRNAワクチンの開発を加速させることを明らかにしたそうです。
米NBC Newsによると、NHSは米製薬のモデルナに5.9億ドルの資金を提供すると発表しました。HHSは昨年7月にも同社に対し、1.76億ドルの支援を行っています。
米政府は、従来の技術を使った2種類の鳥インフルワクチン候補をすでに備蓄していますが、迅速に製造することができるmRNAベースのワクチンの開発が重要だと考えているそうです。モデルナはH5N1型とH7N9型を標的としたワクチンの開発を進めているといいます。
米国では、昨年3月に乳牛の間で鳥インフルが広がり始めました。感染した乳牛や家禽、野鳥などからヒトへの感染例が67件確認されており、最近ではルイジアナ州の高齢者1人が死亡しています。
こうした状況を背景に、政府はワクチンの効果を高める物質「アジュバント」や、あらゆる種類のインフルエンザに対応する「ユニバーサルインフルエンザワクチン(万能ワクチン)」などの開発にも資金提供を行っているそうです。

「ハンチントン病」の患者は、生まれた時から原因となる遺伝子異常を持っています。しかし、ハンチントン病はすぐには発症しません。長らく不明だったその理由を、米国の研究チームが解明したそうです。AP通信が報じました。
ハンチントン病は、自分の意思に関係なく手足や顔面を動かしてしまう不随意運動、不安定な歩行、性格の変化、判断力の低下などの症状を特徴とする遺伝性の神経変性疾患で、通常30~50歳で発症します。特定の遺伝子における塩基C、A、Gの配列の繰り返しが、病気を持たない人では15〜35回なのに対し、ハンチントン病患者では40回以上起きることが分かっています。
研究チームは、ハンチントン病患者53人とハンチントン病ではない50人の脳組織から、この「繰り返し配列(リピート)」に関する詳しい分析を行ったそうです。その結果、CAGリピートが40回以上あるDNA領域は時間の経過とともにリピートし続け、約150回に達した時点で、毒性のタンパク質を生成することが明らかになったといいます。それによって神経細胞(ニューロン)がむしばまれ、死滅しすることが示されたとのことです。
チームはこの発見が、病気の進行を遅らせたり、予防方法を見つけたりすることに役立つと期待しています。

米国の研究チームが、食品包装など多くの製品に使用されている「PFAS(有機フッ素化合物)」とがんリスクの関連性を明らかにしたとして、科学誌Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiologyに論文を発表しました。
PFASは分解されにくく、体内に蓄積していくといい、さまざまな健康問題との関連性が指摘されています。米国の約45%の飲料水からPFASが検出されているそうです。
チームは、2016~21年に米国内で報告された全がん症例と公共水道システムが供給する飲料水中のPFASに関する13~24年の全国データを分析しました。その結果、飲料水から基準値を上回るPFASが検出された郡では、消化器、内分泌、呼吸器、口腔咽頭のがんが発生する割合が2~33%高いことが分かったそうです。
また、飲料水がPFASに汚染された郡に住む男性は、そうでない郡に住む男性に比べて白血病や泌尿器系、脳、軟部組織のがん罹患率が高かったといいます。女性は、甲状腺、口腔咽頭、軟部組織のがんが多くなりました。最新のデータによると、PFASに汚染された飲料水は年間6864件のがん症例に関係すると推計されるそうです。

米食品医薬品局(FDA)は15日、合成着色料「赤色3号(エリスロシン)」の食品や経口薬への使用を禁止すると発表しました。米国の各メディアが報じています。赤色3号は食品などを鮮やかな赤色にする石油由来の合成着色料です。
米NBC Newsによると、FDAは1990年に赤色3号の化粧品への使用を禁止しています。しかし、その後もキャンディーやシリアルなどの食品や経口薬への使用は続いており、2022年には消費者保護団体である公益科学センター(CSPI)が、動物への発がん性や子供の行動障害との関連性への懸念から使用禁止を求める請願書をFDAに提出していました。
こうした動きを背景に、FDAは高レベルの赤色3号に暴露した雄ラットにおいてがんが発生したとの研究結果に基づき、今回の承認取り消しの決定を下したといいます。ただし、ヒトへの発がんリスクは立証されていません。
米国の食品メーカーは27年1月15日までに、薬品メーカーは28年1月18日までに赤色3号の使用を中止する対応が求められるとのことです。なお、日本では赤色3号の使用が認められており、漬物などに使われています。

心臓の神経回路網は、これまで考えられていた以上に高度で複雑な機能を有している可能性があるそうです。スウェーデンと米国の研究チームが科学誌Nature Communicationsに論文を発表しました。
長い間、心臓は脳からの信号を伝達する自律神経によってコントロールされると考えられていたといいます。しかし、人間と同じような心拍数や心機能を持つゼブラフィッシュを使って調査した結果、心臓には、鼓動を調節するために重要な役割を果たす「ミニ脳」のような独自の複雑な神経系があることが分かったそうです。
このミニ脳には、ペースメーカーのような働きをするニューロン(神経細胞)をはじめ、異なる機能を持ついくつかの種類のニューロンが存在することも示されたといいます。
チームは、今回の発見が、心拍のコントールに関する現在の知見に疑問を投げかけるものだとしています。心臓内の神経系について理解を深めることで、不整脈などの心疾患に関する新たな治療法の開発などに役立つ可能性があるとのことです。

カルシウムが豊富な食生活を送る人は、大腸がんを発症するリスクが低くなるようです。イギリスの研究チームが、女性54万2778人を平均16.6年にわたって追跡したデータを分析し、その結果を科学誌Nature Communicationsに発表しました。
チームの調査で、カルシウムを1日300mg(大きめのグラスで牛乳1杯相当)多く取ると、大腸がんリスクが17%低くなることが分かったそうです。朝食用シリアル、果物、全粒粉、炭水化物、食物繊維、ビタミンCも大腸がんリスクの低下に関連していましたが、その影響はわずかでした。
逆に、アルコールを1日20g(大きめのグラスでワイン1杯相当)多く飲むと15%、赤肉や加工肉を1日30g多く食べると8%、大腸がんリスクがそれぞれ上昇することも示されたといいます。
なお、カルシウムは、牛乳のほかにもヨーグルトやチーズなどの乳製品に多く含まれています。カルシウムが腸内の胆汁酸や遊離脂肪酸に結合し、発がん作用を抑制する効果を発揮する可能性があるとのことです。
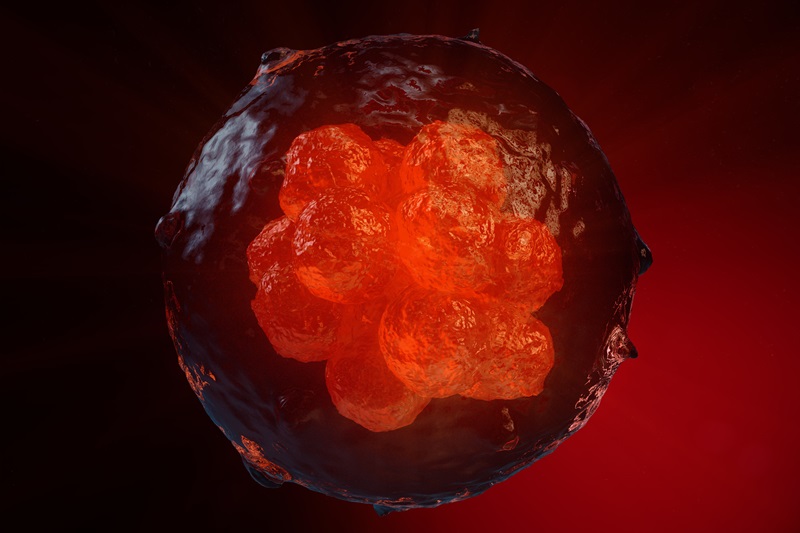
オーストラリアでは最近、人工知能(AI)を導入して生殖補助医療(ART)を行うクリニックが出始めているそうです。オーストラリアの研究チームがARTにAIを活用することの懸念点を明らかにし、医学誌Human Reproductionに発表しました。
チームが調査したのは、移植に適した胚を評価するAI(機械学習ツール)の使用によって生じる倫理的な問題です。調査の結果、機械学習ツールは、ARTの専門家の医師が行うのに比べてより一貫性のある胚評価を行うことができる上に、評価にかかる時間を大幅に短縮できることが示されたそうです。
一方で、こうしたツールを使用することによる「患者の非人間化」「アルゴリズムのバイアス(偏り)」「透明性や公平性の確保」などといった数々の懸念事項が明らかになったといいます。
チームは、これらの倫理的懸念が機械学習による胚評価を排除するものではないとしています。しかし、AIが人間の命に関係する非常に繊細な領域に干渉することになるため、熟慮を重ねたうえで慎重に取り扱う必要があるとのことです。

脳の白質病変は、血流不足によって脳深部の大脳白質に生じた変化で、認知症のリスクに関連するとされています。緑茶をたくさん飲む人は、この白質病変が少ない傾向にあることを金沢大学などの研究チームが突き止めたそうです。チームが科学誌npj Science of Foodに論文を発表し、科学メディアScience Alertが紹介しています。
チームは、認知症を持たない65歳以上の日本人8766人のデータを分析したそうです。その結果、緑茶を1日1杯飲む人と比較して、緑茶を1日3杯飲む人は3%、7~8杯飲む人は6%、それぞれ白質病変が少ないことが分かったそうです。
一方で、緑茶の摂取は記憶をつかさどる海馬や脳全体の大きさには影響しなかったといいます。また、うつ病と診断された人やアルツハイマー病リスクに関連するAPOE4遺伝子を持つ人は、緑茶摂取によるこうした白質病変の減少は見られなかったとのことです。
緑茶には血圧を下げる効果があるとされており、このような心血管への影響が今回の結果に関係している可能性があると、チームは考えているようです。

脳損傷によって、病的なほど「冗談好き」になってしまう「ふざけ症(Witzelsucht)」という感情の障害がまれにあるそうです。科学メディアScience Alertが米国の研究チームが2016年に発表した69歳の男性の症例を紹介しています。
この男性は脳卒中を起こした後、冗談に対する取りつかれたような欲求が生じるようになったといいます。思いついたダジャレや不快なジョークを共有したい欲求を抑えきれず、夜中にたびたび妻を起こすほどだったそうです。
ふざけ症は、ドイツの神経科医ヘルマン・オッペンハイムによって、1890年に初めて発表されたといいます。社会生活を営む上で重要な高次機能をつかさどる右前頭葉に病気やけがで損傷がある人が、過剰にユーモラスになることがあると気付いたことがきっかけだったそうです。
また最近、上機嫌や多幸、軽率な態度で、一人ではしゃぎふざける「モリア(Moria)」と呼ばれる精神症状が、ふざけ症と共存または重複することも分かっています。ふざけ症やモリアには、いずれも前頭葉の下部にある「前頭眼窩野」回路の損傷が関連するとみられています。これらに標準的な治療法はないそうです。

米マクドナルドで昨年、腸管出血性大腸菌O157による集団食中毒が発生した問題で、タマネギを供給した食品会社の不十分な衛生管理が明らかになったようです。米CBS Newsが米食品医薬品局(FDA)の査察報告書を入手し、その内容を報じました。
CBS Newsによると、タマネギを供給したTaylor Farms社のコロラド州の施設内の設備からは、清掃作業終了後にもかかわらず、微生物が形成するバイオフィルムや大量の食品かすが見つかったそうです。また、食品加工を担当する作業員が衛生管理に必要な手順を踏んでいないことも明らかになりました。
作業員が手洗いシンクを使用している様子は見られず、時々、手袋の上から手の消毒剤を使っていただけだといいます。さらに、消毒液に漬けた道具の乾燥作業もきちんと行われておらず、濡れたままになっていたとのことです。
Taylor Farms社は、FDAが査察終了後に発行した指摘事項通知に基づき速やかに是正措置を講じたとの声明を出しているそうです。マクドナルドはFDAの査察前にこの施設からの仕入れを中止しているとのことです。

たくさん歩くことは、うつ病リスクの抑制につながるようです。スペインの研究チームが、日々の歩数とメンタルヘルスに関する33の研究を分析した結果を医学誌JAMA Network Openに発表しました。
対象者は世界13カ国の18歳以上の男女で、合計9万6173人に上ったといいます。分析の結果、1日の歩数が5千歩以上の人は、5千歩未満の人に比べてうつ症状が少ないことが分かりました。また、1日の歩数が7千歩以上の人は、7千歩未満の人に比べてうつ病発症リスクが31%低くなることも示されたそうです。1日7500歩以上歩く人は、うつ病リスクが42%低下することも示されました。
歩数が増えるにつれてうつ病リスクは低下する傾向にありましたが、1日1万歩を超えるとこうしたメンタルヘルスへの恩恵は横ばいになったといいます。
これまでの研究で、ヨガやウェートトレーニング、太極拳などがうつ病リスクを抑制することが分かっていました。今回の研究で、身体活動レベルのより低い「歩くこと」もリスク抑制の効果があることが明らかになりました。

子宮内膜症を正確に検出する血液検査をオーストラリアの医療技術企業(Proteomics International)が世界で初めて開発したそうです。同社がオーストラリアのメルボルン大学などと共同で研究を行い、学術誌Human Reproductionに論文を発表しました。
研究チームは、主にヨーロッパ系の参加者749人から採取した血液データを分析したといいます。その結果、10のタンパク質バイオマーカーが単独で子宮内膜症に関連することが明らかになったそうです。
これらのバイオマーカーを用いると、「重症の子宮内膜症患者」と「子宮内膜症ではないが同様の症状がある患者」を99.7%の割合で識別することができたといいます。また、「微症~中等症の子宮内膜症患者」と「子宮内膜症ではないが同様の症状がある患者」も85%以上の割合で識別できたとのことです。
現在、子宮内膜症の診断は腹腔鏡による侵襲的な方法で行われるため、非侵襲的な診断ツールが求められているといいます。科学メディアScience Alertによると、この血液検査は「PromarkerEndo」という名前で、同社は今年6月までにこの血液検査を実用化することを目指しているそうです。

米国では虫歯予防のために数十年間、水道水にフッ化物を添加しているそうです。そのフッ化物が子どもの知能指数(IQ)に影響を及ぼすという論文を米国の研究チームが医学誌JAMA Pediatricsに発表し、物議を醸しているようです。
チームは、フッ化物と子どものIQに関する既存の74研究を分析。その結果、子どものフッ化物への暴露とIQスコアの低下の間に統計的に有意な関連があることが分かったとしています。ただし、今回対象となった研究は、水道水のフッ化物濃度が高い中国などで実施されたもので、研究の質も低かったそうです。そのため、チームは水道水からのフッ化物の除去を主張しているわけではないといいます。
米NBC Newsによると、歯科医師らは、フッ化物が水道水から除去された地域では虫歯の発生率が劇的に増加しているとし、今回の調査結果に懸念を示しました。トランプ次期米大統領が厚生(保健福祉省:HHS)長官に指名したロバート・ケネディ・ジュニア氏が、水道水のフッ化物添加について批判的な立場を表明していることもあり、ますます議論が加速するとみられています。

コウモリのふん由来の肥料「バットグアノ」に含まれていた真菌によって、米国の男性2人が肺感染症を起こし、死亡したそうです。米国の研究チームが明らかにし、医学誌Open Forum Infectious Diseasesに発表しました。
2人はそれぞれ自宅で大麻を栽培しており、肥料にバットグアノを使用していたといいます。米国では、ニューヨーク州など一部の州で大麻の栽培が合法化されて以降、リン酸や窒素が豊富なバットグアノが最適な肥料として人気を集めているそうです。
男性2人はバットグアノに生息していた真菌(ヒストプラスマ・カプスラーツム)の胞子を知らぬ間に吸い込み、ヒストプラスマ症を発症したとみられています。
症状は2人ともひどい咳、発熱、体重減少で、最終的に呼吸器不全に陥ったとのことです。ヒストプラスマ症はほとんどの場合、抗真菌薬で回復します。しかし今回死亡した2人は、59歳と64歳と比較的高齢だったこと、基礎疾患があったこと、喫煙者だったことなどが原因で、感染に打ち勝つことができなかったといいます。

禁煙をするなら、「今」がベストタイミングだそうです。英国の研究チームが学術誌Addictionに研究結果を発表しました。
チームは英国内の男女の死亡率に関する大規模な追跡調査のデータを分析したそうです。その結果、たばこを1本吸うごとに男性は17分、女性は22分寿命が短くなると推計されたそうです。つまり、たばこを1箱(20本)吸うごとに、寿命を約7時間縮めてしまう可能性があるということです。
また、生涯にわたって喫煙習慣があった人は、喫煙経験がない人に比べて、平均して寿命が約10年短いことも明らかになったそうです。一方、30代前半までに禁煙することができれば、喫煙経験がない人と同程度の寿命になる傾向が認められたといいます。
年を取るにつれて喫煙によって失われた寿命を取り戻すことは難しくなるそうです。ただし、たとえいくつになっても、たばこを吸い続けるよりは禁煙した方が長生きできる可能性があるとのことです。

米国の公衆衛生政策を指揮するビベック・マーシー医務総監は3日、アルコール飲料のラベルに「がんリスクが高まる」との警告を表示するよう勧告しました。米NBC Newsや米CNNなどの各メディアが報じています。
公表された報告書によると、飲酒は乳がん、大腸がん、肝臓がん、口腔がん、咽頭がん、喉頭がん、食道がんの少なくとも7種類のがんに直接的に関連することが分かったそうです。また、乳がん症例の16.4%が飲酒に関連すると推計されるといいます。
米国では毎年、飲酒関連のがん症例が10万件、飲酒関連のがんによる死亡が2万件発生しているそうです。そして、がんの原因として、飲酒がたばこと肥満に次ぐ3番目に挙げられるといいます。マーシー氏は、「国民の多くが飲酒によるがんリスクを認識していない」と指摘しています。
今回公表された報告書は、がんリスクを高める1日当たりの飲酒量の基準も見直すよう求めています。現行の基準では、男性は1日2杯、女性は1日1杯が適量とされていますが、この程度の飲酒であってもがんリスクが高まることが示されたといいます。

中国でヒトメタニューモウイルス(HMPV)の感染者が急増していると報じられています。HMPVとはどのようなものなのでしょうか。
日本ウイルス学会や日本小児感染症学会によると、HMPVは2001年にオランダの研究チームが発見したありふれたウイルスで、今回新たに発生したものではありません。ウイルス性の呼吸器感染症では小児の5~10%、成人の2~4%がHMPVによるものと考えられているそうです。
RSウイルス(RSV)と同じ仲間に属し、主な症状は咳、発熱、鼻づまり、息切れです。乳幼児や高齢者、免疫力が低下している人に感染すると気管支炎や肺炎に進行し、重症化する恐れがあります。ワクチンや治療薬はありません。
米CBS News によると、HMPVは新たなウイルスではないため、専門家は新型コロナウイルスのような脅威になる可能性は低いと考えているそうです。感染を予防するには、他の呼吸器感染症と同様、手洗いや感染者との接触を避けるなどの対策が有効とのことです。
なお、2023年春には米国で患者の報告数が急増しニュースになりました。

米ルイジアナ州保健当局は6日、鳥インフルエンザウイルス(H5N1型)が感染し重篤な呼吸器症状で入院していた州内の患者が死亡したと発表しました。死亡したのは基礎疾患を持つ65歳以上の患者で、裏庭で飼っていたニワトリや野鳥と接触していたといいます。
米疾病対策センター(CDC)は昨年12月26日、この患者から採取したウイルスから、ヒトに感染しやすくなる変異が見つかったと発表しています。患者に感染したのは家禽や野鳥の間でまん延しているD1.1と呼ばれる株で、米国内の乳牛の間で流行しているものとは別のものです。遺伝子解析の結果、ヒトの上気道細胞に付着しやすくなる変異が発見されたというのです。
なお、こうした変異は、カナダのブリティッシュコロンビア州で鳥インフルが感染して入院した若者のサンプルからも確認されているとのことです。米NBC Newsによると、今回見つかった変異は鳥のサンプルからは検出されていないため、患者の体内で起きた可能性が高いそうです。現状では、ヒトからヒトへの感染は確認されていません。

高齢者の日々の脳の機能は、前日の運動と睡眠によって大きな差が出るそうです。英国の研究チームが科学誌International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activityに論文を発表しました。
チームは、認知機能に問題のない50~83歳(平均64.6歳)の中高年76人に防水の加速度計を24時間装着してもらい、8日間の追跡調査を実施しました。これに加え、睡眠の評価と認知機能の測定も毎日行ったそうです。
その結果、散歩やダンスなどに相当する「中~強度の身体活動」を多く行った人は、その後最大24時間にわたりエピソード記憶(個人が経験した出来事に関する記憶)とワーキングメモリ(入ってきた情報を保ちながら、何かを処理する機能)が向上することが分かったそうです。逆に「座りっぱなし」が多かった人は、ワーキングメモリが低くなったといいます。
興味深いことに、前日に中~強度の身体活動をしたかどうかに関係なく、前夜の睡眠時間が長い人はエピソード記憶と精神運動速度(物事を考えたり作業したりする速度)が向上することも明らかになりました。

トレーニングをより効果的に行うためのカギとなる「ディロードウィーク(積極的休養期間)」を知っていますか。The Conversationに英国の生理学の専門家による記事が掲載されています。
激しいトレーニングの期間中、4~8週間ごとに運動強度を抑えるディロードウィークを設けることで、それまでに蓄積した筋肉組織の疲労や損傷が回復しやすくなり、筋肉によい変化が起こるそうです。
また、過剰なトレーニングが原因で倦怠(けんたい)感やパフォーマンスの低下が生じる「オーバートレーニング症候群」のリスクについても知っておくべきだといいます。筋肉の成長に関与する遺伝子の記憶は休養期間中も保持されるため、普段のトレーニングを中断することを恐れる必要はないとのことです。
ディロードウィーク中は、通常の半分ほどのトレーニングを行うか、強度を20%ほど下げるのが一般的だそうです。特にマラソンなどに向けて激しいトレーニングを行っている場合は、運動をしない休息日を週1~2回設けることに加えて、ディロードウィークを設定するとよいとのことです。

歩くことは、さまざまな病気のリスクを下げるなど健康上多くのメリットがあることが知られています。より多くの効果を得るには、どのような点に気を付けて歩けばいいのでしょうか。英国の臨床運動生理学者が五つのポイントをThe Conversationで紹介しています。
<ポイント①>まず、一定の速さで歩くよりも、速く歩いた後にゆっくり歩くというように数分おきに「歩く速さを変える」と心血管の健康がより向上するそうです。
<ポイント②>また、時速5km以上の速さで歩くと、心血管疾患やがんを含め全ての死亡リスクが低下することが5万人以上のデータを分析した研究で明らかになっているといいます。息が少し弾む程度に「速く歩く」と、心臓の健康が改善するだけでなく、体重の管理にも効果的とのことです。
<ポイント③④>歩く時に「重いベストやリュックで負荷をかける」ことや「坂や階段を取り入れる」ことは、筋肉によい効果をもたらすそうです。
<ポイント⑤>そして、自分の動きや呼吸、周囲の環境に意識を向けて歩く「マインドフル散歩」を行うと、メンタルヘルスの向上につながるといいます。

カカオ豆をすりつぶしたカカオマスを多く含むダークチョコレートには、2型糖尿病のリスクを抑制する効果があるようです。米国の研究チームが、医学誌BMJに研究成果を発表しました。
チームは、看護師11万1654人のデータを平均25年にわたり追跡調査したといいます。その結果、ダークチョコレートを1週間に5サービング(1サービングの目安は約28g)以上食べる人は、ダークチョコレートを全くまたはめったに食べない人に比べて2型糖尿病を発症するリスクが21%低いことが分かったそうです。
一方、ダークチョコレートの原料に乳製品や多くの砂糖を加えたミルクチョコレートを食べる人は、こうしたリスク低下は認められなかったといいます。それどころか、ミルクチョコレートの摂取は長期的な体重増加に関連していたとのことです。
ダークチョコレートに多く含まれるポリフェノールの一種「フラバノール」が、2型糖尿病リスクの抑制に関与していると考えられるそうです。

コーヒーを1日に3杯飲むと、健康に長生きできる可能性があるそうです。ポルトガルの研究チームがコーヒー業界から資金提供を受け、さまざまな地域や民族を対象としたコーヒーの摂取量と健康に関する50以上の疫学調査を分析し、科学誌Ageing Research Reviewsに発表しました。
この研究の対象者は、合計300万人近くに上るといいます。分析の結果、適度な量(1日3杯)のコーヒーを定期的に飲む人は全死因死亡率が低く、寿命が長くなることが分かったそうです。
また、心血管疾患や脳卒中、がんといった加齢に関連する疾患の発症リスクも低く、健康寿命が約1.8年延びることも明らかになったといいます。さらに、加齢による記憶力の低下、気分や体調の悪化を緩和することも判明したとのことです。
コーヒーに含まれるカフェインやポリフェノ―ルの一種である「クロロゲン酸」が持つ覚醒作用、抗酸化作用、抗炎症作用が、基本的な生物学的メカニズムを維持するのに役立つ可能性があるそうです。