非公開の医師求人情報を
ご紹介いたします!
マイナビDOCTORでは、医師専任のキャリアパートナーが
あなたの転職活動をサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。
世界の医療ニュースの中から、厳選した記事をギュッと凝縮して紹介します。
1日数本を1分で、サクッと読むことができます。日々の情報収集、話のネタ探しにお役立てください。
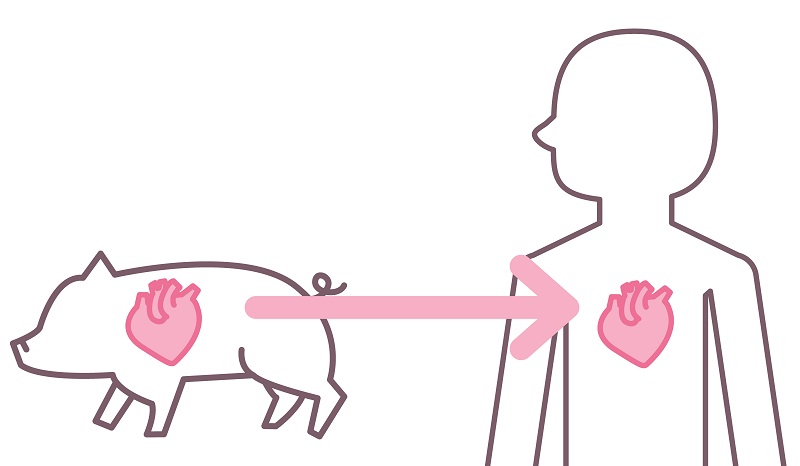
2023年の医療・医学に関する重大ニュースの続きです。米メリーランド大学が9月、世界で2例目となるブタの心臓移植を実施し、移植を受けた男性が6週間後に死亡しました。今年のノーベル生理学・医学賞は、コロナワクチンの開発に貢献したとして、mRNAの研究者2人に授与されました。20年にノーベル化学賞を受賞したゲノム編集技術「CRISPR/Cas9」を使った遺伝子治療が英米で初承認され、話題に。また、肥満症治療薬が大きな注目を集めました。大阪大学のチームによる、両親がオスの赤ちゃんマウスを誕生させたという発表は、衝撃を持って受け止められました。マイナビRESIDENTで詳細な記事が読めます。

2023年も医療・医学に関するさまざまなニュースが配信されました。2回に分けて、重大ニュースを振り返ります。今年5月、WHOが新型コロナの「緊急事態宣言」を解除し、3年以上続いたコロナとの戦いは大きな節目を迎えました。そして、米NIHが7月、「コロナ後遺症」の治療に向けた試験を開始すると発表。米FDAによる、アルツハイマー病治療薬「レカネマブ」や世界初のRSウイルスワクチンの承認も大きな話題になりました。感染症については、米国内で20年ぶりに国内感染が報告されたマラリアや、日米で報告数が急増した先天梅毒などが話題になりました。マイナビRESIDENTで詳細な記事が読めます。

英国の研究チームの報告によると、医師は患者の意見を軽視している傾向があるようです。チームは1000人以上の患者と臨床医を調査したそうです。診断が難しい「全身性エリテマトーデスに伴う神経精神症状」について、診断に使われる13種類の根拠の価値を医師が評価。重要な根拠トップ3の中に「患者の自己評価」を入れた医師は4%にも満たなかったといいます。また、676人(46%)の患者は「自分の病気について一度も、またはほとんど自分の評価を聞かれたことがない」と回答。患者の実体験に基づく見解に医師が耳を傾ければ、診断精度向上など多くの利点につながる可能性があるとのこと。SciTechDailyの記事です。
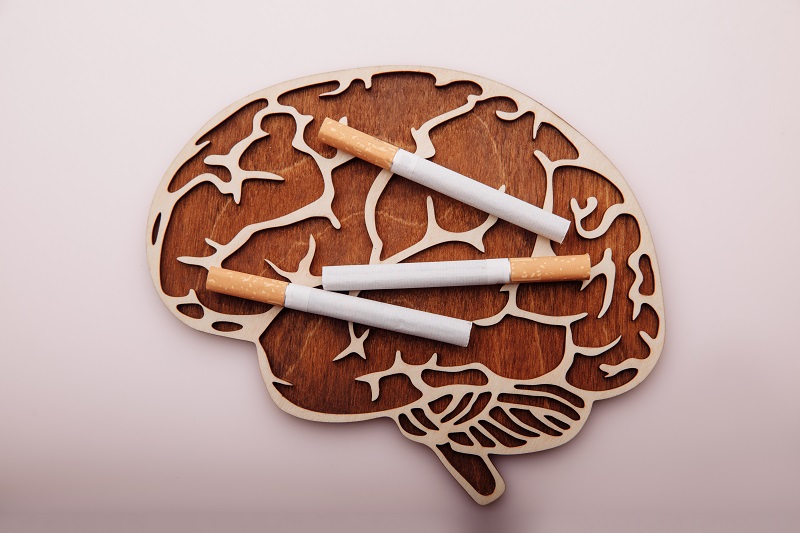
喫煙は心臓や肺の健康に悪影響を与えるだけでなく、脳を小さくしてしまうことが分かったそうです。米国の研究チームが、英国バイオバンクから抽出した神経学的疾患を持たない3万2094人の画像データなどを分析した結果です。日常的に喫煙をしていたことがある人は、非喫煙者に比べて脳の総容量、灰白質量、白質量が有意に少なかったそうです。特に、認知機能に関連する灰白質の減少が顕著だったといいます。また、たばこの消費量が多いほど、脳への影響が大きいことも明らかになったとのことです。これらのことから研究者は、喫煙をやめると認知症発症リスクを抑制できる可能性があるとしています。PsyPostの記事です。

米アラバマ大学バーミンガム病院で、生まれつき子宮が二つある32歳の女性が、それぞれの子宮で妊娠した双子を無事に出産したそうです。二つの子宮をもつ女性の割合は約0.3%とされており、両方の子宮で妊娠する確率は「100万分の1」程度だといいます。双子のうち1人目は、12月19日の現地時間の午後7時45分ごろに経膣分娩で誕生。2人目は、それから10時間後に帝王切開で生まれたそうです。2人は誕生日が別々の「二卵性双生児」に当たるといいます。BBCの記事です。

女性の涙には、男性の攻撃性を抑制する物質が含まれているようです。イスラエルの研究チームが、対戦相手に対して攻撃的になるよう設計された2人用ゲームを男性にやらせて調査をしたそうです。男性はゲーム中に「女性の感情的な涙」か「生理食塩水」のどちらかをかがされたといいます。涙の匂いをかいだ人は、ゲーム中に相手にリベンジを企てる攻撃的な行動が40%減ったそうです。脳画像からも、攻撃性に関連する2領域の活性低下が確認されたとのこと。Medical Xpressの記事です。

フランス南西部に、村全体が大きな介護施設になっている「アルツハイマー村」があるそうです。この村は2020年にオープンし、約120人の住人はみな認知症患者で、それと同数の医療従事者がいるといいます。敷地内にはレストランや店、劇場もあるとのこと。住人には可能な限り自由が与えられ、ゆったりと日常生活を送れるよう設計されているそうです。介護施設に入居すると認知機能の低下が加速することがありますが、この村ではそのような現象は確認されていないといいます。患者の家族の罪悪感や不安も激減するとのことです。BBCの記事です。

デンマークの研究チームが、人生を予測する人工知能(AI)を開発したそうです。チームは、600万人のデンマーク人に関する2008~16年の教育や健康、職業などに関するデータを使い、機械学習アルゴリズムモデル「life2vec」を訓練したといいます。その結果、life2vecは個人がどのように考え、どのように行動するのかをはじめ、数年以内に死亡する可能性があるかどうかも予測できるようになったそうです。さらに、life2vecで10万人のデータを分析したところ、4年後に死亡している可能性を78%の精度で予測できたとのことです。CNNの記事です。

ささいな体の不調に対して、自分が重篤な病気にかかっているのではないかと異常に心配する「病気不安症(心気症)」の皮肉なパラドックスが明らかになったようです。スウェーデンの研究チームが、1997~2020年のデータから、病気不安症を持つ4100人と対照群4万1000人を調査した結果です。1000人年(人年法)当たりの死亡率は、病気不安症群で8.5だったのに対し、対照群は5.5だったそうです。また対照群に比べ、病気不安症群は死亡年齢の中央値が5歳若いだけでなく、自殺率も4倍だったといいます。AP通信の記事です。

皮膚炎に使うステロイド外用薬が、骨の健康に悪影響を及ぼす可能性があるそうです。台湾の研究チームが、骨粗しょう症患者12万9682人と対照群 51万8728人、また、主要骨粗しょう症性骨折(MOF)患者3万4999人と対照群13万9996人を調査。5年後の「骨粗しょう症」と「MOF」のリスクは、ステロイド外用薬の局所使用をしていない人と比べ▽低用量使用群:骨粗しょう症が1.22倍、MOFが1.12倍▽中用量使用群:同1.26倍、同1.19倍▽高用量使用群:同1.34倍、同1.29倍――だったといいます。Medical Xpressの記事です。

殺虫剤への暴露が精子濃度を低下させるそうです。米国などの研究チームが25の研究を分析して明らかにしたといいます。調査対象となったのは世界4大陸(アジア、北米、南米、ヨーロッパ)の成人男性計1774人で、みな殺虫剤として一般的に使われる「リン酸エステル」や「N-メチルカルバメート」に暴露していたとのことです。そして、これらの物質への暴露が増えると、精子濃度が低くなることが示されたそうです。殺虫剤への暴露は、主に汚染された食べ物や水を介して起こり、研究者は「公衆衛生上の懸念」と指摘しています。ScienceAlertの記事です。

ヨーグルトなどの発酵食品に含まれる「ラクトバチルス属」の乳酸菌で、メンタルヘルスを改善できるかもしれません。米国の研究チームが、抗菌薬を使わない特別な方法で腸内にこの乳酸菌を持つマウスと持たないマウスを作製し、調べたそうです。その結果、ラクトバチルスによって、うつを抑制する役割があるサイトカイン「インターフェロン・ガンマ」のレベルが維持されることが分かったそうです。うつ病の新しい治療法として、健康に良い影響を及ぼす微生物「プロバイオティクス」のサプリメントが開発されるかもしれません。Medical Xpressの記事です。

動物性食品を厳しく制限する「ヴィーガン食」は健康に良いのでしょうか。米国の研究チームが、健康な一卵性の双子22組を「ヴィーガン食を摂取する群」と「適量の肉を取り入れた健康食を摂取する群」に分けて調査したそうです。8週間後、両群ともに心血管の健康状態を示すデータが良くなったものの、ヴィーガン群の方がより良くなっていることが明らかになったといいます。ヴィーガン群は減量が進み、空腹時インスリン値や悪玉(LDL)コレステロール値もより大きく低下したとのことです。ScienceAlertの記事です。
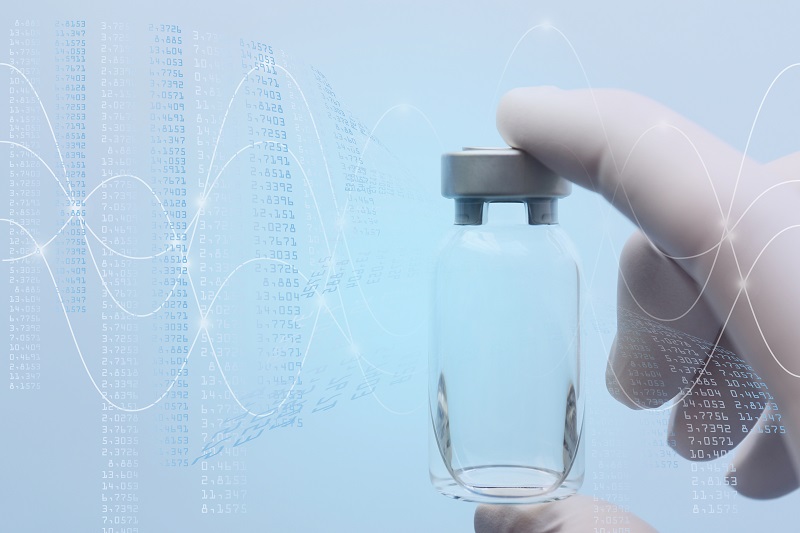
米モデルナと米メルクは、開発中の個別化mRNAワクチン「mRNA-4157/V940」が、「悪性黒色腫(メラノーマ)」患者に対して有望な結果を示していると発表したようです。両社は、ステージ3~4のメラノーマを切除したけれども再発リスクの高い患者を対象に、3年間の追跡調査を実施。メルクのがん免疫治療薬「キイトルーダ」とmRNAワクチンを併用した患者は、キイトルーダのみを使用した患者に比べて再発または死亡のリスクが49%、遠隔転移または死亡のリスクが62%、それぞれ低かったといいます。CNNの記事です。

米国の研究チームが、腎臓病の治療薬「BI690517」について、第2相試験の有望な結果を発表したそうです。この薬は、アルドステロンと呼ばれる腎臓病の進行を早めるホルモンの産生を阻害します。チームは、標準治療の「アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬」か「アンジオテンシン受容体拮抗薬(ARB)」の満量投与を4週間以上受けた慢性腎臓病患者714人を調査。BI690517のみを投与された人の50%、BI690517とSGLT2阻害薬「エンパグリフロジン」を併用した人の70%で、尿中アルブミンがそれぞれ有意に減少したとのことです。Medical Xpressの記事です。

パーキンソン病(PD)の発症リスクを上昇させる二つの危険因子が明らかになったそうです。米国の研究チームが、米国最南部(ディープサウス)出身のPD患者808人と神経学的に健康な対照群415人を調査したといいます。その結果、サッカーなどのスポーツで(無害なようにみえる程度に)繰り返し頭を打っていると、後にPDを発症するリスクが倍増することが分かったそうです。さらに、PD患者の23%が、除草剤や殺虫剤などの有害な化学物質に暴露していたとも判明したとのこと。研究者は、これら二つの危険因子は回避可能だとしています。Medical Xpressの記事です。
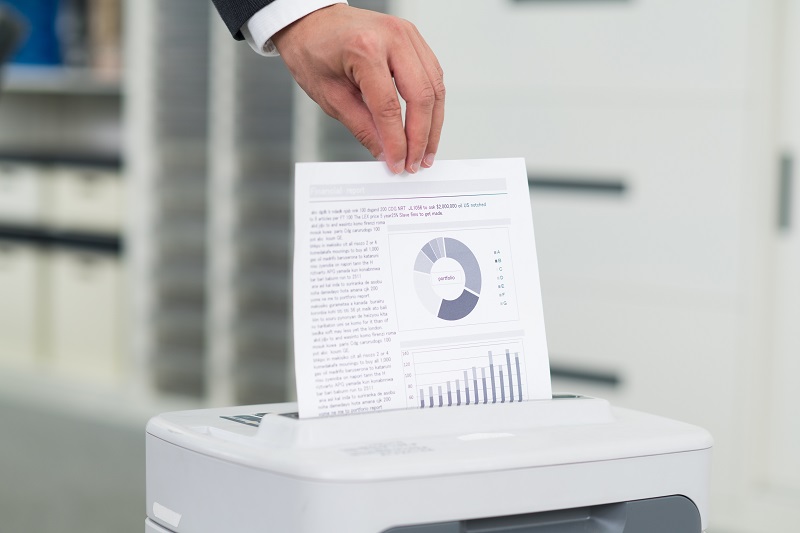
2023年に撤回された論文は1万本を超え、年間記録を更新したそうです。そのうち8000本以上は、ロンドンを拠点とするオープンアクセス出版社「ヒンダウィ」のジャーナルに掲載されたものだといいます。ほとんどが、ゲスト編集者が監修する「特集号」の論文とのことです。また、Nature誌の分析によると、論文撤回率は過去10年で3倍に増加し、22年には0.2%を超えたといいます。過去20年間に10万本以上の論文を発表した国の中では、サウジアラビア、パキスタン、ロシア、中国、エジプトの順に撤回率が高いとのことです。Natureの記事です。

米イーライリリー社の肥満症治療薬「ゼップバウンド(一般名:チルゼパチド)」の減量効果を維持するには、薬を使い続ける必要があるようです。米国の研究チームが、ゼップバウンドを9カ月間使用した肥満または太り過ぎの成人670人を追跡調査。半数には薬を継続させ、残りの半数にはプラセボを投与したそうです。次の1年が経過した時点で、薬を使った群は体重の平均6%が追加で減少したのに対し、プラセボ群はリバウンドがみられたとのこと。プラセボ群で少なくとも減量した体重の80%を維持できたのは17%だったそうです。CNNの記事です。

米アーカンソー州で、「オザークウイルス」と呼ばれる新たなウイルスが発見されたそうです。このウイルスはハンタウイルスの一種です。米国の研究チームが同州オザーク高原で、げっ歯類「アラゲコットンラット」を捕獲し、採取した338検体を調査。26検体がオザークウイルス陽性だったそうです。ハンタウイルスの中にはヒトに感染するものもあり、心肺症候群が起きると致死率は30~40%に上ります。専門家はオザークウイルスに対する警戒を強める必要があるとしています。Medical Xpressの記事です。

米疾病対策センター(CDC)は、「プランB」の名で知られる「モーニングアフターピル(緊急避妊薬)」が2006年に処方箋なしで買えるようになって以降、これを使用する女性が2倍になったと発表しました。性交渉の経験がある15~44歳の女性のうち緊急避妊薬を使用したことがあると答えたのは、06~10年の調査では10.8%だったのに対し、15~19年は26.6%に増加したそうです。一方、性交渉を経験したことがあるティーンエイジャーの割合は、男女共に減少したといいます。CBS Newsの記事です。

喘息患者向けの吸入ステロイド薬は、骨粗しょう症や糖尿病、白内障などの深刻な副作用を伴うことで知られています。英国などの研究チームが、吸入ステロイドの量を減らす方法を見つけたそうです。チームは、高用量の吸入ステロイドを使用する重症喘息患者208人を対象に調査を実施。喘息治療用に開発された生物学的製剤「Benralizumab(ベンラリズマブ)」を使用すると、92%の患者がステロイドの使用量を安全に減らすことができたそうです。さらに、60%以上の患者がステロイドの使用をやめることができたといいます。ScienceDailyの記事です。

乳がんや肺がんが、他の骨よりも脊椎に転移しやすいのはなぜなのでしょうか。米国の研究チームが、腫瘍細胞を引き寄せてしまう新しい幹細胞が脊椎に存在することを発見したそうです。チームは新たに見つかったこの細胞を「脊椎骨格幹細胞(vSSC)」と呼んでいます。vSSCを四肢の骨を形成する幹細胞と比較したところ、vSSCが高レベルで産生するタンパク質が見つかったそうです。このタンパク質を欠損させたマウスは、脊椎へのがん転移が少なくなったとのこと。このタンパク質が、がん細胞を集めてしまうようです。Medical Briefの記事です。

世界保健機関(WHO)が、アフリカのケニア、マラウイ、ウガンダ、ザンビア、ジンバブエで炭疽菌感染が拡大していると発表しました。今年になって確認された死者は計20人。このうち13人はウガンダで報告されているといいます。感染疑いのある患者は計1166人で、684人がザンビアで報告されているとのこと。WHOはザンビアから周辺国へ拡大するリスクが高いと懸念しているそうです。炭疽菌は主に汚染された動物に接触することでヒトに感染します。皮膚や消化器、呼吸器に異常が出て、治療を行わない場合の死亡率は約20%だそうです。AP通信の記事です。

ネコを飼っている家庭は、子どものメンタルヘルスへの長期的な影響の可能性を知ったほうがいいようです。豪州の研究チームが、1980~2023年に11カ国で行われた17の研究を分析。ネコを飼っていると、統合失調症関連障害のリスクが2.24倍になることが推定されたそうです。なお、特に幼い時にネコに接触していると、このリスクに関連することを示す研究もあるといいます。ネコに寄生するトキソプラズマ原虫が、こうしたリスクの原因である可能性が指摘されています。トキソプラズマは猫の糞に含まれていることがあります。Medical Xpressの記事です。

乳がん手術を受けた後は、どのくらいの頻度でマンモグラフィ検査を受けるべきなのでしょうか。英国の研究チームが、乳がん手術を無事に終えた50歳以上の女性5200人を追跡調査。初めの3年間は全員が年1回、マンモグラフィ検査を受けたそうです。その後、半数は毎年検査を受け、残りの半数は乳房切除術を受けた患者が3年に1回、腫瘤摘出術を受けた患者は2年に1回と頻度を減らして、それぞれ受検したといいます。6年後、両群ともに95%の人が再発せず、98%が生存していたそうです。AP通信の記事です。

片頭痛の時にイブプロフェンを使う人は多いと思います。しかし、もっと効果の高い薬があるようです。米国の研究チームが、片頭痛に関する477万7524回分の服薬データを分析した結果を発表しました。27万8006人が6年間にわたってスマホアプリで自己申告したものです。その結果、イブプロフェンに比べて、トリプタン系は4.8倍▽麦角系は3.02倍▽制吐薬は2.67倍――有効であることが判明。特にトリプタンの一種であるエレトリプタンは、イブプロフェンの6.1倍の効果が認められたといいます。Medical Briefの記事です。
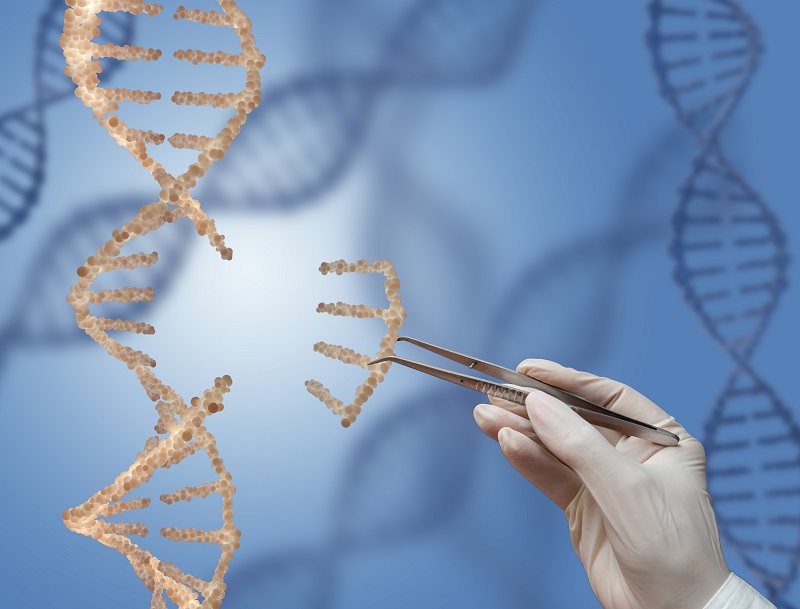
米食品医薬品局(FDA)は8日、遺伝性血液疾患「鎌状赤血球症」に対する2種類の遺伝子療法を承認したそうです。正常な形の赤血球が作られるように血液幹細胞の遺伝子を編集する治療法です。一つは米Vertex Pharmaceuticals社とスイスのCRISPR Therapeutics社が共同開発した「Casgevy(キャスジェビー)」。ゲノム編集技術CRISPRに基づいた治療法で、11月に英国が世界に先駆けて初承認しています。もう一つは、米Bluebird Bio社の遺伝子療法「Lyfgenia(リフジェニア)」です。これらの治療には2回の入院が必要で、1回は4~6週間入院生活が続くといいます。AP通信の記事です。

スマートフォンの使い過ぎは、若者のメンタルヘルスに悪影響を及ぼす可能性があるそうです。韓国の研究チームが、同国の思春期の若者5万人以上を対象に、スマホの使用時間とさまざまな健康状態のデータを分析したといいます。2020年は対象者の85.7%が2時間以上、スマホを使っていたそうです。分析の結果、スマホの使用時間が1日4時間を超える人は、ストレス、自殺念慮、薬物使用のリスクが高いことが分かったといいます。一方で、スマホの使用時間が1日1~2時間の人は、全く使わない人に比べてこうした問題を抱えるリスクが低かったとのことです。Medical Xpressの記事です。

アレルギーや喘息の治療に広く使われている抗インターロイキン(IL)-4受容体抗体「デュピルマブ」が、非小細胞肺がん(NSCLC)の治療に役立つ可能性があるようです。米国の研究チームが、治療抵抗性NSCLC患者6人を対象に調査を実施したといいます。免疫チェックポイント阻害薬での免疫療法にデュピルマブの投与(3回)を組み合わせたところ、免疫チェックポイント阻害薬だけでは増殖を続けていた1人の患者のがんが、ほぼ完全に消滅したそうです。17カ後の現在も、がんはきちんと抑制されているとのことです。Science Dailyの記事です。

米国の研究チームが、数千種類のタンパク質レベルを測定することで、臓器の老化速度や、どの臓器がいつ機能しなくなるのかを知ることができる血液検査を開発したそうです。調べられるのは、脳、心臓、肝臓、肺、腸、腎臓、脂肪、血管(動脈)、免疫組織、筋肉、膵臓の11個だといいます。この検査を主に中高年数千人に実施したところ、50歳以上の18.4%で、老化が平均より有意に早い臓器が一つ以上あることが示されたとのこと。こうした人は、15年以内に病気を発症したり、死亡したりするリスクが高かったといいます。BBCの記事です。

細菌は鼻水などの粘液を利用して、感染力を高めている可能性があるようです。米国の研究チームが、ブタの合成胃粘液やウシから採取した頸管粘液を使って、反すう動物やヒトの胃腸に存在する枯草菌の動きを観察したそうです。そして、その結果を、さまざまな濃度の水溶性ポリマー内における枯草菌の動きと比較したといいます。すると、粘液の粘度が高まれば高まるほど、細菌の集団運動が活発になることが分かったそうです。細菌の感染力は、集団運動が活発になると高まるといいます。EurekAlert!の記事です。

多発性硬化症(MS)の前触れとみられる五つの症状が明らかになったそうです。フランスの研究チームが、MS患者2万174人▽非MS患者5万4790人▽自己免疫疾患のクローン病か全身性エリテマトーデス(SLE)の患者3万7814人――の医療記録を分析。うつ、性機能障害、便秘、ぼうこう炎、ぼうこう炎以外の尿路感染症の五つの症状が、5年後にMSと診断されるリスクに関連していることが分かったそうです。ただし、これらの症状はクローン病やSLEの前駆期にも見られたといいます。Medical Xpressの記事です。

自己免疫性皮膚疾患である乾癬や白斑を治す画期的な方法が見つかったかもしれません。豪州の研究チームが、疾患の原因となる免疫細胞「組織常在性記憶T細胞(TRM)」に着目し、動物モデルで調査。TRMは「敵」と戦った後も、戦う能力を維持したままその場にとどまる免疫細胞です。さまざまな種類がある皮膚のTRMには、それぞれに特有の制御方法があることが判明。現在の自己免疫性皮膚疾患の治療は、全ての免疫細胞に影響を与えてしまうため、長期の治療ができないそうです。特定のTRMを標的にできれば、治療効果が改善する可能性があります。Medical Xpressの記事です。

睡眠中に10秒以上の呼吸停止が起こる「閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA)」は、高血圧や心臓病、2型糖尿病、うつ病、早期死亡のリスクを高めます。その兆候として「いびき」が知られていますが、それだけではないようです。まず、「寝汗」をかく人は注意が必要。そして、就寝中に2回以上トイレに起きる「夜間頻尿」、睡眠中の「歯ぎしり」もOSAの兆候として挙げられるそうです。起床時に、毎朝または頻繁に「頭痛」がする人も多いといいます。うつや倦怠感、不眠症など一見「メンタルヘルス不調」にみえる症状も、実はOSAが原因の可能性もあるとのこと。CNNの記事です。

アフリカ東部ウガンダの首都カンパラにある病院で11月29日、70歳の女性が帝王切開で双子の男女を出産したそうです。女性はこの病院で体外受精(IVF)治療を受けて、双子を妊娠したといいます。女性は2020年にも同じ病院でIVFによって女児を出産したそうです。女性の健康状態は良好で、現在は病院内を歩き回ることもできるといいます。治療技術の飛躍的な進歩によって、近年はIVFの成功率が上昇しています。インドでは2019年、73歳の女性がIVFで授かった双子の女児を出産して話題になったとのことです。AP通信の記事です。

アルゼンチン北西部のカタマルカ州で、フラミンゴ220羽が鳥インフルエンザウイルス(H5N1型)の感染によって死んでいるのが見つかったようです。2022年以降、渡り鳥を介してH5N1型は世界80カ国以上に拡散。継続的な変異も確認されており、専門家は哺乳類への広がりを注視しているといいます。H5N1型はヒトに感染しにくいと考えられているものの、21年12月以降、世界で11人の感染者が見つかっています。また、アザラシや養殖のミンク、猫や犬などさまざまな哺乳類への感染が確認されているとのこと。CNNの記事です。

スウェーデンなどの研究チームが、脳卒中のマウスやラットの実験で、失われた脳機能を改善させることに成功したそうです。チームは、脳神経細胞のネットワークにおいて情報伝達を制御する「代謝型グルタミン酸受容体5(mGluR5)」に着目。脳卒中発症から2日後の動物に、mGluR5を阻害する物質の投与を始めたところ、触覚や位置覚などの体性感覚機能障害が改善したそうです。治療を数週間続けると永続的な改善も認められたといいます。また、数匹を一緒に、遊び道具などがあるケージに入れて「リハビリ」を行うと、治療効果がさらに高まったとのこと。Science Dailyの記事です。

米製薬大手ファイザーは、飲む肥満症治療薬として注目されていた「danuglipron(ダヌグリプロン)」の1日2回服用型の臨床試験を中止すると発表したそうです。この薬は、効果の高さから関心が高まっている注射薬「ウゴービ(一般名セマグルチド)」や「ゼップバウンド(一般名チルゼパチド)」と同じGLP-1受容体作動薬です。ダヌクリプロンは試験の中期段階で、被験者の50%以上が服用を中断。副作用として73%が吐き気、47%が嘔吐を報告したといいます。今後は同薬の1日1回服用型に重点を置く予定で、初期試験の結果は来年初頭に明らかにする見込みとのこと。AP通信の記事です。

大麻の合法化や治療薬としての使用が世界的に進んでいます。オピオイド中毒を抑えるために大麻を利用しようとしている国もあります。しかし豪州のチームが、この流れは早計であるとの研究結果を発表しました。チームは2001~22年、強力なオピオイド「ヘロイン」の中毒者615人を追跡調査。対象者の多くが大麻も使用していたといいます。統計的手法で、経時的な個人の薬物使用の変化を分析したところ、大麻はオピオイドの使用を減らすための長期的な戦略として有効ではないことが示されたそうです。EurekAlert!の記事です。

エイズウイルス(HIV)に対する曝露前予防内服(PrEP)の非常に高い有効性が、実世界においても示されたようです。PrEPは、HIV感染のリスクのある人がHIV治療薬を1日1回、またはリスク行為の前後に飲んで感染を予防する方法です。英保健安全保障庁(UKHSA)が2017年10月~20年7月、イングランドの157のクリニックで調査。計2万4000人がPrEPを服用したといいます。日常生活で起こり得る飲み忘れや飲み間違いを考慮に入れても、PrEPがHIVへの感染を86%抑制することが明らかになったそうです。なお、臨床試験では99%の有効性が示されていたとのこと。BBCの記事です。
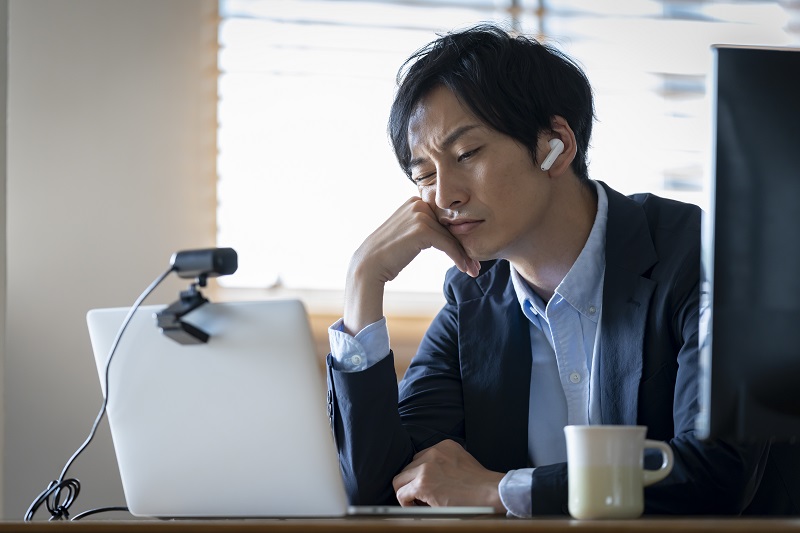
ウェブ会議システム「Zoom」などを使った「オンライン会議」に出席すると心や体が疲れてしまう人はいませんか。米国の研究チームが、体にストレスの兆候が表れる人が多いことを確認したそうです。大学生35人を「オンラインで講義を受ける群」と「対面で講義に参加する群」に分けて、脳波と心臓の状態を調査。オンライン講義を受けた人のほうが、疲れを報告する傾向にあったそうです。実際に脳波計は、オンライン講義中に脳活動が若干鈍くなることを示したといいます。さらに、心拍数も上下することが確認されたとのこと。CBS Newsの記事です。

人の性格は認知症リスクに関連するようです。米国のチームが既存8研究のデータについて、性格特性の主要5因子(開放性、誠実性、外向性、協調性、神経症傾向)や主観的幸福度(肯定的・否定的な感情、生活満足度)などを分析。対象者は4万4000人以上で、1703人が認知症を発症したそうです。後ろ向きの特性(神経症傾向や否定的な感情)のスコアが高く、前向きな特性(誠実さや外向性、肯定的な感情)のスコアが低い人ほど、認知テストで認知症と診断されるリスクが高かったといいます。ただし、特性と実際の脳組織病変との間に関連は認められなかったとのこと。ScienceDailyの記事です。