非公開の医師求人情報を
ご紹介いたします!
マイナビDOCTORでは、医師専任のキャリアパートナーが
あなたの転職活動をサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。
世界の医療ニュースの中から、厳選した記事をギュッと凝縮して紹介します。
1日数本を1分で、サクッと読むことができます。日々の情報収集、話のネタ探しにお役立てください。

アトピー性皮膚炎の一般的な治療方法は、皮膚を清潔にしてうるおいを保つことと、炎症を抑える「ステロイド外用薬」の塗布です。近年、塗り薬以外のアトピー性皮膚炎の新たな治療薬の開発が進んでいます。生物から産生されるタンパク質などの物質を応用して作られる「生物学的製剤」の登場により、既存の治療薬では効果のない患者などにも治療の選択肢が広がりました。生物学的製剤の特徴は、炎症やかゆみが発生する根本的な原因にアプローチできることです。次々と登場している治療薬の中で、最も新しいのは、イーライリリーが2024年5月に発売した生物学的製剤「イブグリース(一般名レブリキズマブ)」です。初めは2週間に1回注射で投与しますが、4週目以降は症状に応じて1カ月に1回に切り替えることもできるため、患者の負担を軽減できるといいます。マイナビRESIDENTの記事です。

欧州連合(EU)当局は、欧州15カ国向けの4000万回分以上の鳥インフルエンザワクチンを確保することを決めたそうです。ロイター通信が25日に報じました。まず最大66.5万回分のワクチンを調達し、最長4年にわたって追加で4000万回分のワクチンを確保する契約を豪CSL Seqirus社と結んだといいます。ワクチンは最初にフィンランドに向けて出荷され、養鶏場の労働者や獣医師など鳥インフル感染のリスクの高い人が接種の対象になるそうです。鳥インフルエンザウイルス(H5N1型)の感染が米国の乳牛の間で広がっており、今年4月以降、乳牛に接触した酪農従事者3人に鳥インフルが感染したことが確認されています。欧州疾病予防管理センター(ECDC)によると、6月初旬時点で、EUではヒトや牛の感染例は確認されていません。

米疾病対策センター(CDC)は25日、蚊が媒介する感染症「デング熱」について、世界の患者数が過去最多を記録したとして警戒を呼びかけました。気候変動の影響もあり、デング熱感染が世界的に急増しています。南北アメリカでは既に6月の時点で、年間のデング熱患者数の最多記録を更新した国もあるといいます。こうした状況を受けて、WHO(世界保健機関)が昨年12月に、カリブ海にある米自治領プエルトリコが今年3月にそれぞれ非常事態を宣言しています。米国本土でも、今年の感染者数が前年の同じ期間に比べて3倍に増加したそうです。そのほとんどが海外を旅行した際に感染したケースだといいます。CDCは医師らに対し、症状をよく把握したうえで、渡航歴を確認し、必要に応じてデング熱検査を検討するよう呼びかけました。

人工知能(AI)を使って、がんを早期に診断できるようになる日が来るかもしれません。英国の研究チームが、がんの発達に深く関わると考えられている「DNAメチル化」に着目しました。メチル基という分子がDNA(の塩基)にくっつくことで、遺伝子がタンパク質を作るのを抑えてしまう現象です。チームは機械学習とディープラーニングを併用し、がん発生の初期にみられるDNAメチル化のパターンを解析するAIモデルを開発したといいます。このAIで組織検体を調べたところ、健康な組織と、乳がんや肝臓がん、肺がん、前立腺がんなど13種類のがんを98.2%の精度で識別することができたそうです。実際の臨床でこのAIを活用するためには、追加の訓練やより多様な検体を使った試験が必要だといいます。科学誌Biology Methods and Protocolsに発表した論文です。

気候変動は脳の健康に悪影響を及ぼすようです。英国の研究チームが、1968~2023年に世界で発表された332の論文を分析し、医学誌The Lancet Neurologyに結果を発表しました。脳卒中、片頭痛、アルツハイマー病、てんかんなど19種類の脳神経疾患と、不安症(不安障害)やうつ病、統合失調症などの精神疾患について気候変動の影響を検討しました。その結果、高温や熱波で、脳卒中による入院や障害、死亡のリスクが上昇することが分かったそうです。また、認知症の人は環境の変化に適応する力が弱いために異常気象の被害を受けやすく、一日の中の気温差が激しい日や高温の日があると、認知症関連の入院や死亡が増加することも明らかになりました。精神疾患の発生やそれによる入院や死亡のリスクについても、高温や気温差などとの関連が認められたといいます。
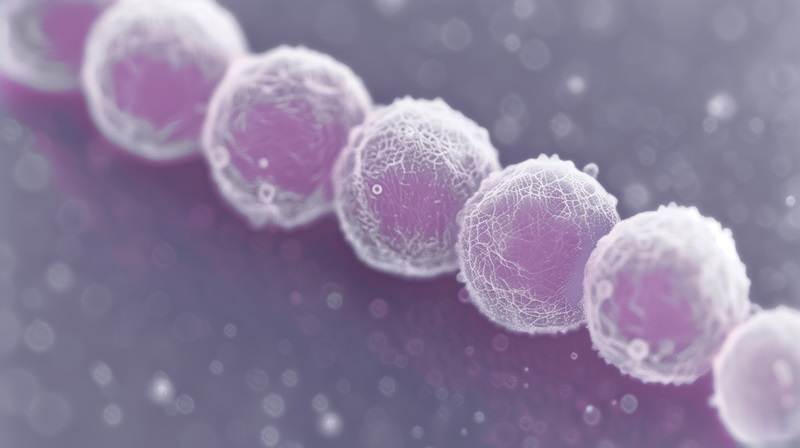
劇症型溶血性レンサ球菌感染症(STSS)の患者が日本で急増しており、このことについて米NBC Newsが報じています。STSSは、「人食いバクテリア」とも呼ばれる特殊な溶血性連鎖球菌(溶連菌)によって組織が破壊される感染症で、患者の3割が死に至るといわれています。国立感染症研究所によると、今年1月以降に確認された日本国内のSTSS患者は1019人で、これまで過去最多だった昨年の941人をすでに上回りました。患者急増の原因は分かっていません。こうした日本の状況が、近年米国でも懸念されているSTSSの感染拡大の原因をめぐる謎に、改めて関心が寄せられるきっかけになっているといいます。

双極性障害を患った人は、心の健康を取り戻すことができるのでしょうか。カナダの研究チームが、双極性障害の既往歴がある555人と双極性障害の既往歴がない2万530人のカナダ人のデータを分析。双極性障害の既往歴がある人のうち、43%が双極性障害の症状が改善したそうです。さらに、23.5%が、過去 1 年間に双極性障害、うつ病、薬物依存症、自殺念慮などの精神疾患にかかっていないなどの条件を満たした「心が完全に健康な状態」であると確認されたそうです。また、信頼できる友人の存在が、心の健康を取り戻す上で最も影響力のある要因だったといいます。双極性障害の既往歴がない人については、4分の3が心が完全に健康な状態だったとのこと。論文は医学誌Journal of Affective Disorders Reportsに掲載されました。

米食品医薬品局(FDA)は20日、米サレプタ・セラピューティクス社が開発したデュシェンヌ型筋ジストロフィー(DMD)における初の遺伝子治療薬「ELEVIDYS(エレビジス)」について、対象範囲を拡大すると発表しました。FDAは昨年6月、対象をDMD遺伝子の変異が確認された4~5歳の小児患者に限り、エレビジスを迅速承認していました。しかし今回、DMD遺伝子変異をもつ歩行可能な4歳以上の患者を対象に通常承認することを決定しました。さらに、同様の遺伝子変異をもつ歩行不能な4歳以上の患者に対する使用についても、迅速承認を出したといいます。エレビジスは、筋肉の構造を保つために必要なタンパク質「ジストロフィン」を作る遺伝子を体内に送り込む薬です。薬の投与は1回で完了します。

2型糖尿病治療薬「マンジャロ」や肥満症治療薬「ゼップバウンド」の商品名で知られる米製薬大手イーライリリーの「チルゼパチド」が、「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」の治療に有効な可能性があるそうです。米国の研究チームが、肥満およびSASと診断された患者469人を対象に調査を実施。鼻に付けたマスクから圧力をかけた空気を送り込んで気道を広げるSASの一般的な治療法「持続陽圧呼吸療法(CPAP)」を行っているかどうかにかかわらず、チルゼパチドを週1回投与された人は、睡眠時の無呼吸や低呼吸が50~60%減ることが分かったそうです。また、チルゼパチドを使った患者は、睡眠の質の向上や睡眠障害の減少を報告しているとのことです。論文は米医学誌New England Journal of Medicineに掲載されました。

前立腺肥大症の治療に一般的に使われる既存薬で、「レビー小体型認知症(DLB)」の発症リスクを抑制できるかもしれません。DLBはアルツハイマー病に次いで2番目に多い認知症で、レビー小体というタンパク質が脳に異常に蓄積して神経細胞が減少する病気です。米国の研究チームが、前立腺肥大症治療薬の「テラゾシン」「ドキサゾシン」「アルフゾシン」が脳細胞のエネルギー産生に必要な酵素を活性化することで細胞死を阻害する可能性があることに着目。3薬のいずれかを使用する男性12万6313人を、別のタイプの薬(タムスロシン、5α還元酵素阻害剤)を使用する人と比較しました。その結果、テラゾシンなどの3薬を使用する群は3年以内のDLB発症リスクが、タムスロシンの群と比べて40%、5α還元酵素阻害剤の群と比べて37%、それぞれ低いことが明らかになったといいます。医学誌Neurologyに発表した論文です。
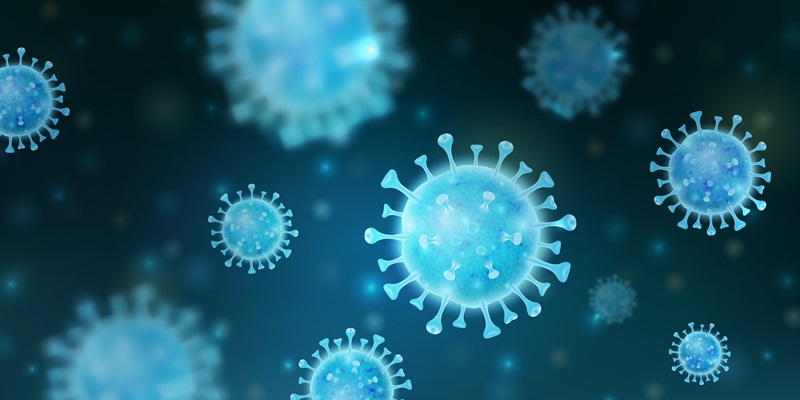
英国の研究チームが、新型コロナウイルスに感染しない人がいる理由を明らかにしたと、英科学誌Natureに発表しました。チームは、新型コロナの感染歴のない健康な成人16人に対して鼻から新型コロナウイルスを入れた上で、臓器の細胞を一個一個分離して解析する「シングルセル(単一細胞)解析」を用いて免疫応答を詳しく調査しました。その結果、ウイルスをすぐに排除できた人は、典型的な広域の免疫応答は示さず、代わりにこれまで知られていなかった自然免疫応答を引き起こすことが分かったそうです。また、ウイルスへの暴露前にHLA-DQA2と呼ばれる遺伝子の活性レベルが高いと、感染が持続しにくくなることも明らかになったといいます。一方で、参加者の中で新型コロナを発症した6人は、血液中の免疫応答は速かったものの、鼻腔内の免疫応答が遅いためにウイルスがそこに感染してしまったとのことです。

英国とドイツの研究チームが、パーキンソン病(PD)の早期診断を可能にする血液検査を開発したそうです。PDは手足がふるえたり思うように体が動かせなくなったりする神経変性疾患です。チームはまず、PD患者とそうでない人から採取した血液を使い、PD発症の予測に有用な八つのタンパク質を特定しました。そして、これを基に人工知能(AI)を使って脳疾患リスクのある患者72人の血液を分析し、10年間の追跡調査を行ったそうです。その結果、16人のPD発症を正確に予測することができたといいます。症状が出る7年も前にPD発症を予測できたケースもあったそうです。さらに、特定されたタンパク質が、PD治療に役立つ可能性もあるとのことです。論文は科学誌Nature Communicationsに掲載されました。

米国の研究チームが、「リンパ球性脈絡髄膜炎ウイルス(LCMV)」を使ったがんのウイルス療法を開発し、免疫不全マウスにも有効なことを確認したそうです。マウスのメラノーマや大腸がんなどを縮小させて生存率を高めただけでなく、がんの予防効果も認められたとのこと。ウイルス療法は、がん細胞のみで増殖するように遺伝子改変したウイルスを使って、がんを破壊する治療法です。免疫細胞が破壊された細胞のタンパク質を「敵」と認識し、がん細胞を攻撃する効果もあります。ただ、免疫抑制剤を使用している患者は、この攻撃力が弱まる可能性があるために使用できないことが課題になっています。現在は単純ヘルペス1型ウイルスなどが使われています。論文は医学誌Journal of Clinical Investigationに掲載されました。

韓国政府の医学部増員計画を巡り政府と医師らの対立が続いている問題で、国内の診療所が抗議行動の一環として18日に一斉に休診したそうです。AP通信によると、保健福祉省は「一斉休診」に参加したのは国内に3万6000ある民間医療施設の約4%だと発表しているとのことです。韓国当局は、一斉休診への参加を当局に通知した医師らに、「職場復帰命令」を出したといいます。韓国の法律では、命令に従わなかった医師は免許停止などの処分を受ける可能性があります。今回の一斉休診は、17日からソウル大学病院の教授ら数百人が無期限の休診に入ったことに続くもの。今後ストがさらに拡大する恐れもあるといいます。韓国の医療現場では多くの手術や治療が中止されるなど混乱が続いているとのことです。

デンマーク食品当局は、韓国から輸入された激辛即席麺について、急性中毒のリスクがあるとして回収を指示したそうです。AP通信によると、対象となる製品はソウルに本社を置く韓国最大の食品メーカー三養食品が製造し、世界中で販売されている3種類。デンマーク当局は、これらの激辛麺にはカプサイシンが過剰に含まれており、これが神経毒や健康上のリスクになりうるとしているそうです。症状は灼熱感や吐き気、嘔吐、高血圧などです。デンマークでは、子どもや若者がSNS上で激辛麺のスープを飲んで競い合っており、こうした背景が今回の規制につながったといいます。昨年9月には、先天性心疾患などを持っていた米国の14歳の少年が、激辛チップスを食べるSNSの企画に参加して死亡しています。

ジャンクフードのような高脂肪食は腸内細菌の組成を変化させ、脳内物質に影響を与えて不安を助長するようです。米国の研究チームが青年期のラットを2群に分けて調査。一方には脂肪を45%含む「高脂肪食」を、もう一方には脂肪分が約11%の「通常食」をそれぞれ9週間与えました。その結果、高脂肪食群は通常食群に比べて腸内細菌の多様性が低いことが分かったそうです。また、高脂肪食群の脳内では、神経伝達物質「セロトニン」の生成などに関連する三つの遺伝子が多く発現することも判明。セロトニンは精神を安定させることで知られていますが、高脂肪食群で多く発現していた遺伝子の影響で特定の領域の神経細胞が活性化すると、不安行動を引き起こすことがあるそうです。科学誌Biological Researchに発表した論文です。

非ホルモン性の男性用避妊薬の開発が進んでいるそうです。米国の研究チームが「CDD-2807」と名付けた避妊薬を開発し、マウスに21日間投与して調べた結果を米科学誌Scienceに発表しました。研究の結果、適切な用量を投与するとマウスが不妊になることが示されたそうです。不妊になったマウスの精巣を調べたところ、精子数が少なく、精子の運動率も低く、受精するために精子の動きが激しく変化する「超活性化」の割合も低かったといいます。なお、薬を止めると、53日ほどでマウスは再び繁殖能力を取り戻し、可逆的であることも分かったとのこと。この薬はSTK33と呼ばれるタンパク質を阻害します。STK33遺伝子は精巣に多く存在し、欠損すると精子に欠陥が生じて不妊につながることがマウスとヒトで確認されているといいます。

2001年9月11日の米同時多発テロ事件で、ニューヨークの世界貿易センター(WTC)が崩壊した際に発生した粉塵が、脳に悪影響を及ぼしている可能性があるようです。米国の研究チームが、WTCやその周辺で対応に当たった、消防士や建築関係者など「レスポンダー」と呼ばれる5010人を調査しました。91.3%が男性で、調査を開始した14年時点の平均年齢は53歳だったそうです。22年までに228人が、65歳未満で認知症(若年性認知症)を発症したといいます。調査の結果、レスポンダーとして15週間以上働いた場合、65歳より前に認知症を発症するリスクが高くなることが分かったそうです。粉塵への暴露レベルが上がるごとに、リスクは42%増加することも明らかになったとのことです。医学誌JAMA Network Openに発表した論文です。

非小細胞肺がん(NSCLC)の中には、既存の免疫チェックポイント阻害薬に反応しないものがあります。米国の研究チームが、そんなNSCLCの治療を可能にするかもしれないナノ粒子を開発したそうです。チームは80人以上の肺がん患者の組織を検査し、がん細胞の表面にあるタンパク質を特定したといいます。そして、抗がん剤に加え、これまで治療の標的としてきたタンパク質PD-L1だけでなくCD47にも結合する抗体を搭載したナノ粒子を開発しました。2種類のタンパク質を標的にしているので、ナノ粒子ががん細胞に結合できる可能性が高まります。マウスを使ってナノ粒子の効果を調べたところ、重篤な副作用なしに肺がん細胞が縮小することが確認されたといいます。論文は科学誌Science Advancesに掲載されました。

米国の研究チームが、アルツハイマー病(AD)患者に使用する一般的な二つの薬の併用で、患者の5年生存率が延びる可能性があるという研究成果を発表しました。チームはADと診断された1万2744人について、アチルコリンエステラーゼ阻害薬「ドネペジル」を使用▽NMDA受容体拮抗薬「メマンチン」を使用▽二つの薬を併用▽薬物未治療――の4群に分けて比較しました。ドネペジル、メマンチン、二つの薬の併用は、AD患者に対する最も一般的な治療法だといいます。分析の結果、「併用」患者に比べて、全ての患者の5年後の死亡率が高いことが判明。特に、薬剤未治療の患者と比較すると、併用患者の5年生存の可能性が6.4%上昇したといいます。論文は医学誌Communications Medicineに掲載されました。

米食品医薬品局(FDA)は2023年11月、主に難治性の血液がん患者に使われる「CAR-T細胞療法(キメラ抗原受容体T細胞療法)」が、逆にがんを発生させる「二次がん」のリスクを高めるという警告を出しました。米国の研究チームが米医学誌New England Journal of Medicineに、これを否定する研究結果を発表しました。チームは、2016~24年にCAR-T細胞療法を受けた患者724人について、平均3年間の追跡調査を実施。その結果、二次血液がんの発生率は6.5%だったことが明らかになったそうです。なお、二次がんで死亡したのは1人だけだったといいます。その症例を詳しく分析したところ、二次がんの原因はCAR-T細胞そのものではなく、CAR-T細胞療法の影響による免疫抑制である可能性が示されたといいます。

近ごろソーシャルメディアを賑わせている「オゼンピック・フェイス」という言葉を知っていますか? これまで2型糖尿病治療に使われていたGLP-1受容体作動薬「オゼンピック(一般名セマグルチド)」などを減量目的で使用することで、頬がこけたり、目がくぼんだり、皮膚がたるんだりすることを指す言葉です。ただし、顔の変化がGLP-1受容体作動薬の副作用なのか、単に急激な減量の影響なのかは現時点では明らかになっていないといいます。専門家はこうした言葉が独り歩きしていることに懸念を示しています。体重が急激に減ると、頬や目、顎、口の周りの余分な皮膚がたるんで、しわができることが知られており、顔が老けて見えることも以前の研究で分かっているそうです。Science Alertが報じました。

血液中のコレステロールを下げる物質「スタチン」を発見した東京農工大学栄誉教授の遠藤章さんが、5日に90歳で亡くなりました。英公共放送BBCが遠藤さんの死を報じています。遠藤さんが1973年に青カビから発見したスタチンは、動脈硬化を治療するスタチン製剤の開発につながりました。BBCはスタチンを抗生物質ペニシリンに並ぶ発見とし、「心臓病や脳卒中のリスクを減らし、英国だけで毎年何千人もの命を救った」とその功績をたたえています。また、「(遠藤さんは)卓越した科学者。ここ数年で、これほど劇的な影響を与えた治療法はない。数百万人もの命を救う発見をした遠藤さんがノーベル賞を受賞できなかったことは残念だ」という英国心臓財団の責任者のコメントを紹介しています。

米国で今年3月から、鳥インフルエンザウイルスA(H5N1型)の感染が乳牛の間で流行しています。CDC(米疾病対策センター)によると6月9日の時点で、10州85の牛の群れで感染が確認され、感染牛と接触していた3人にH5N1が感染しました。2人は目の充血などの症状が出て、1人は上気道感染症の症状がありました。現状ではヒトに感染しやすく変異している様子はないそうです。ただ、米国の研究チームが、感染牛の乳には高濃度のウイルスが含まれており、マウスに飲ませると咽頭から感染が起きて全身感染を引き起こすことを明らかにしました。米国では、動物と人間の両方に対するH5N1用のmRNAワクチン開発が進んでいるそうです。マイナビRESIDENTの記事です。

米食品医薬品局(FDA)の諮問委員会は10日、イーライリリーのアルツハイマー病(AD)治療薬「Donanemab(ドナネマブ)」について、承認を推奨すると全会一致で決定しました。FDAは数週間以内に承認の可否を最終決定する見込みで、承認されればエーザイの「レカネマブ」に続くAD治療の選択肢となります。ドナネマブはAD関連のタンパク質アミロイドβを除去するモノクローナル抗体(抗アミロイド抗体医薬)です。委員会は、初期AD患者1736人を対象とした第3相試験のデータを基に、ドナネマブにADの進行を遅らせる効果があると結論付けました。FDAがこれまでに承認した抗アミロイド抗体医薬は二つです。しかし、バイオジェンのアデュカヌマブは今年1月に市場からの撤退を発表しています。

米モデルナ社は10日、mRNA技術を使って同社が開発した、新型コロナウイルスとインフルエンザウイルスの両方の感染を予防する混合ワクチン(mRNA-1083)について、第3相試験の結果を発表しました。3種類のインフルエンザウイルス株と新型コロナウイルスの変異株に対して、既存のワクチンを接種するよりも高い免疫応答を誘発することが確認されたといいます。同社はまず、65歳以上の高齢者4000人を対象に調査を実施しました。その結果、mRNA-1083を接種した群は、従来のコロナワクチンとインフルワクチンを同時に接種した群に比べてコロナとインフルに対する強力な免疫応答を示すことが分かったそうです。さらに、50~64歳の成人4000人を対象とした調査でも、同様の結果が示されたといいます。

体内に取り込まれたマイクロプラスチックが、近年の世界的な出生率低下に関与している可能性があるようです。中国の研究チームが、東部の済南に住む健康な成人男性36人から採取した精液を分析したところ、全ての検体からマイクロプラスチックが検出されたといいます。済南市は、汚染地域とされている最寄りの海岸線から約180km離れた場所にあり、プラスチック製造施設もないそうです。検出されたマイクロプラスチックは8種類で、なかでも梱包材として使われるポリスチレンが最も多く見つかりました。また、精液中にポリ塩化ビニルが含まれていると、精子の運動率が低くなることも分かったといいます。科学誌Science of the Total Environmentに発表した論文です。

精神科の介助犬を知っていますか? 精神障害のある人に対し、不安を和らげる癒し行動を取るように訓練された犬です。米国の研究チームが、心的外傷後ストレス障害(PTSD)を患う軍人や退役軍人にとって、QOL(生活の質)を改善する大きな助けになることを確認したそうです。チームは、介助犬とのマッチングを希望するPTSD治療中の軍人経験者156人を調査。81人のマッチングが成立し、介助犬と共に3カ月間生活したところ、介助犬待ちの71人に比べてPTSDの症状が軽く、うつや不安の症状も少なくなることが分かったそうです。また、PTSDと診断される確率も66%低くなることが明らかになったといいます。医学誌JAMA Network Openに発表した研究成果です。

勃起不全治療薬「シルデナフィル(商品名バイアグラ)」が、脳の小血管へのダメージによって起こる「血管性認知症」を抑制する可能性があるそうです。英国の研究チームが、軽い脳卒中を起こし、軽~中等度の小血管病の兆候を示した患者75人を対象に3週間の試験(二重盲検プラセボ対照試験)を実施。超音波とMRIの調査で、3週間シルデナフィルを使った人は、脳内の血流が増加し、脳血管の機能が改善することが示されました。脳梗塞の再発抑制のために使う抗血小板剤「シロスタゾール」との比較調査も行っており、両方とも、血液が血管に流れ込むときの抵抗(血管抵抗)を低下させることが判明。ただ、副作用はシルデナフィルの方が少なかったそうです。医学誌Circulation Researchに発表した論文です。

世界保健機関(WHO)は7日、インド旅行から帰国したオーストラリアの2歳の女児が鳥インフルエンザウイルスA(H5N1)に感染していたと発表しました。女児は2月12~29日までインドのコルカタ(旧カルカッタ)に滞在したそうです。2月25日に食欲不振や発熱などの症状が出たといいます。その後、発熱や咳、嘔吐のために2月28日にインドで診療を受け、解熱鎮痛薬のアセトアミノフェンを処方されたとそうで。3月1日にオーストラリアに帰国し、翌日から2週間以上入院して退院しました。症状悪化のために1週間は集中治療室に入ったとのことです。5月22日時点で、症状を訴えている濃厚接触者はいないといいます。女児にはインド滞在中に病人や病気の動物に接触した形跡はなく、感染経路は不明です。

英国の研究チームが、クローン病や潰瘍性大腸炎などの「炎症性腸疾患(IBD)」の原因を明らかにしたと、英科学誌Natureに発表しました。チームは、IBDとの関連が以前から指摘されていたゲノムの「遺伝子砂漠」と呼ばれる領域を調査したそうです。遺伝子砂漠とは遺伝子が存在しない非コード領域のことです。チームは、この領域の特定の部分が免疫細胞のマクロファージの中で活性化することを発見。これが遺伝子「ETS2」に働きかけ、マクロファージが活性化して炎症が促進することが分かったそうです。IBD患者の腸サンプルを使って、ETS2活性を間接的に抑えると思われる既存の薬(MEK阻害薬)の効果を調べたところ、炎症反応を抑制することが示されたといいます。

エナジードリンクは心臓発作を引き起こす可能性があるようです。米国の研究チームが、突然の心停止から生還した患者144人のデータを分析したところ、5%に当たる7人が心停止の直前にエナジードリンクを飲んでいたことが分かったそうです。1人分のエナジードリンクには80~300mgのカフェイン(紙コップ<8オンスカップ>1杯のコーヒーには100mg)のほか、タウリンやガラナエキスなどの刺激物が含まれているといいます。こうした物質は心停止につながる不整脈を誘発する可能性があります。研究者は、特に遺伝性心疾患をもつ人がエナジードリンクを飲む際はリスクを考慮するべきだと注意を呼びかけています。医学誌Heart Rhythmに発表した論文です。

遺伝子治療に関する研究成果が相次いで発表されています。中国、米国、英国からは、遺伝性難聴の子どもが、日常会話ができるレベルにまで聴力が改善したという報告が上がっています。遺伝性網膜疾患の患者14人に治験を実施した米国のチームもあり、11人の視力に改善が見られたそうです。単純ヘルペスウイルス1型(HSV-1)についても、米国のチームが有望な結果を報告。マウスの実験で、口腔感染したHSV-1の90%、性器感染したHSV-1の97%をそれぞれ除去することに成功したそうです。また、英国と米国では遺伝性血液疾患向けの、ゲノム編集技術CRISPRを使った治療法が2023年末に承認されています。マイナビRESIDENTの記事です。

鳥インフルエンザウイルスA(H5N1型)の感染が乳牛の間で広がっている米国で、動物と人間の両方に対するmRNAワクチンの研究が進んでいるそうです。米ペンシルベニア大学は、鳥インフル感染を抑制する牛用のmRNAワクチンを開発したといいます。マウスやフェレットを使った実験では、鳥インフルエンザウイルスに対する高レベルの抗体が産生されたそうです。来月実施予定の牛への試験で同様の結果が得られれば、牛からヒトへの伝染リスクを低減させることで、ヒトからヒトへの感染を抑えることが期待できます。一方、モデルナ社やファイザー社は、ヒト用の鳥インフルmRNAワクチンを開発し、既にヒトに接種する初期治験を実施済みとのことです。AP通信が報じました。

アルコールを含むマウスウオッシュを使うと、消化を助けたり口の健康を維持したりする口腔内細菌叢(口腔内フローラ)のバランスが崩れ、健康に悪影響を与える可能性があるそうです。ベルギーの研究チームが、男性と性行為をする男性の性感染症に関する研究の一環で、59人を調査。一般的なマウスウオッシュ「リステリン」を3カ月間毎日使うと、歯周病や大腸がん、食道がんなどに関連するとされる日和見感染菌「フソバクテリウム・ヌクレアタム」と「ストレプトコッカス・アンギノサス」が口腔内で増加することが分かったそうです。さらに、血圧の調整に重要な役割を果たす「アクチノバクテリア」が減少することも明らかになったといいます。科学誌Journal of Medical Microbiologyに掲載された論文です。
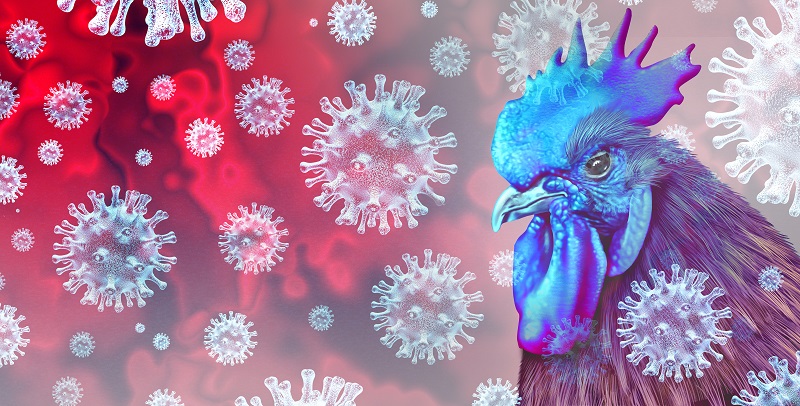
世界保健機関(WHO)は5日、鳥インフルエンザウイルスA(H5N2型)の感染者が世界で初めて確認されたと発表しました。感染者は59歳の男性で、4月24日に発熱や息切れ、下痢、吐き気、全身けん怠感の症状でメキシコシティの病院に入院し、同日死亡したそうです。メキシコでは今年3月、家禽の間でH5N2型の感染が確認されています。しかし、男性は家禽や他の動物との接触歴はなく、感染源は不明だといいます。男性は複数の基礎疾患を抱えており、4月17日に急性の症状が出た時には別の理由で3週間寝たきりの状態だったとのことです。男性と病院で接触した人や近隣住民が検査を受け、全員が陰性だったそうです。

腎移植は拒絶反応の一つである「抗体関連型拒絶反応(AMR)」が大きな課題となっています。オーストリアなどの研究チームがAMR治療薬「felzartamab」の第2相試験を行い、有望な結果を示したと発表しました。チームは、腎移植後にAMRと診断された患者22人に対して、felzartamabまたはプラセボを6カ月間投与して調査。felzartamabはAMRに対して安全かつ非常に有効であることが分かったそうです。felzartamabは細胞表面のタンパク質CD38を標的としたモノクローナル抗体で、当初は多発性骨髄腫の治療薬として開発されたそうです。心臓や肺、さらには遺伝子編集したブタの臓器移植の拒絶反応にも有効な可能性があるそうです。米医学誌New England Journal of Medicineに掲載された論文です。

若くて健康な人であっても、飛行機内での飲酒は控えた方がいいようです。ドイツの研究チームが、18~40歳の健康な成人48人を調査。寝る前に缶ビール2本分に相当するアルコールを摂取してから、飛行中の機内と同程度に気圧を低くした検査室で睡眠を取ると、参加者の酸素飽和度が平均85%に低下することが明らかになったそうです。そして、これを補うために心拍数は1分間に平均88回に上昇したといいます。一方、飲酒をしてから海抜ゼロ地点の気圧に相当する検査室で寝た人の酸素飽和度は平均95%、心拍数は平均77回だったといいます。日本呼吸医学会によると、酸素飽和度は96~99%が標準値。人間ドックでは、心拍数は1分間に45~85回が正常値とされているようです。医学誌Thoraxに発表した論文です。

動画投稿アプリ「TikTok(ティックトック)」に投稿された健康情報は信頼してもいいのでしょうか。米国の研究チームが、2023年11月15~16日にTikTokで視聴され、#sleephacks、 #sleephygiene、#sleeptipsのタグが付いた睡眠に関する人気の動画58本を調査したそうです。その結果、寝つきを良くしたり、睡眠の満足度を上げたり、日中の眠気を軽減させたりといった快眠につながる独自の35個のヒントが見つかったといいます。そして詳細な分析の結果、このうち33個が科学的に立証された根拠に基づいていることが明らかになったそうです。睡眠分野に関しては、コンテンツの制作者が医学的に適切な情報を提供している可能性が高いことが示されました。医学誌SLEEPに発表した論文です。

カナダの研究チームが、体内でアルコールを醸造してしまう珍しい「自動醸造症候群(ABS)」の症例を報告しました。腸内の細菌や真菌が炭水化物をエタノールに変えてしまい、酩酊状態になる病気です。患者はトロントに住む50歳の女性で、飲酒をしていないのに呼気からアルコールの臭いがし、気を失うこともあったといいます。女性は2年間で7回も救急外来を受診しましたが、医師らは女性の飲酒を疑うばかりでした。7回目の受診でようやくABSだと判明。この女性の場合、尿路感染症の治療で使った抗菌薬で善玉菌が死滅し、ABSを引き起こす真菌が腸を乗っ取ったといいます。ABSは抗真菌療法や低炭水化物食などによる長期の治療が必要だそうです。論文は医学誌Canadian Medical Association Journalに掲載されました。

米疾病対策センター(CDC)は5月30日、鳥インフルエンザウイルスH5N1型が乳牛の間で流行して以降、3例目の感染者がミシガン州で確認されたと発表しました。患者は酪農従事者で、咳などの上気道感染症と涙目の症状が報告されているといいます。これまで確認された他の2人(テキサス州で1人、ミシガン州で1人)の患者は、目の症状のみでした。3例に関連性はなく、全員がH5N1型が感染した牛と直接接触していることが分かっています。CDCは鳥インフルエンザウイルスがヒトからヒトへ感染している兆候はないとしています。今回の患者は抗ウイルス薬(タミフル)を投与され、呼吸器症状は改善したそうです。

米ニューヨーク大学は、ブタの腎臓移植を受けた世界で2例目の患者に対し、この腎臓を摘出する手術を行ったと発表しました。患者の女性は人工透析を受け、容体は安定しているといいます。移植したブタの腎臓は拒絶反応を防ぐために遺伝子編集されたものです。女性は4月に人工心臓とブタ腎臓の移植を受け、一時は順調に回復していました。しかし、人工心臓と新たな腎臓の両方を一度に管理するに当たり、特有の課題があったようです。女性の血圧は何度も低くなり過ぎてしまい、腎臓への血流が不十分になったとのことです。移植後わずか47日で腎臓を摘出せざるを得なくなりました。AP通信やCNNが報じました。