非公開の医師求人情報を
ご紹介いたします!
マイナビDOCTORでは、医師専任のキャリアパートナーが
あなたの転職活動をサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。
世界の医療ニュースの中から、厳選した記事をギュッと凝縮して紹介します。
1日数本を1分で、サクッと読むことができます。日々の情報収集、話のネタ探しにお役立てください。

米国では今年3月以降、鳥インフルエンザウイルスH5N1型の感染が乳牛の間で流行し、乳牛からヒトに感染する症例も相次いで確認されています。米国の研究チームが、乳牛からヒトに感染した株について動物実験を行い、その結果を科学誌Natureに発表しました。
チームが調査に使った株は、今年の春に結膜炎を発症したテキサス州の酪農従事者の目から分離したものです。この株が感染したフェレットを、感染していない6匹のフェレットの近くで飼育したところ、2匹のフェレットへの感染が確認されたといいます。効率的ではないものの、この株が飛沫感染によって広がる可能性が示されました。
また、この株に感染したフェレットの致死率は100%だったそうです。ヒトでは軽症なのに、フェレットで病原性が非常に高くなる理由は不明とのこと。なお、現在乳牛の間で広まっているウイルスは、実験に使った株とは別の変異を持つものに移り変わっているそうです。

米ケンタッキー州で2021年、脳死と判定された男性が、臓器摘出手術のために手術室に向かう途中で目を覚ますという出来事があったそうです。今年9月に開かれた議会公聴会で初めて明らかになったといいます。これを受け、米国で臓器提供のドナー登録を取り消す人が増えているそうです。AP通信が報じています。
21年の出来事の詳細は分かっていませんが、摘出手術は回避され、男性は今も生きているそうです。この件が報道された翌週には、前年同時期の10倍以上に当たる1日平均170人が、国のドナー登録リストから自身の情報を削除したといいます。さらに海を越えたフランスでも、このニュースが報道されて以降、臓器提供拒否の意思を登録する人が1日当たり100人から1000人に急増したそうです。
なお、米国や日本と違い、フランスでは本人が生前に拒否する意思を示しておかない限り、臓器提供するものとみなされるシステムだといいます。

米国などの研究チームが、投薬ミスを未然に防ぐための、小型のアクションカメラを開発したと、医学誌npj Digital Medicineに発表しました。人工知能(AI)を搭載した、頭に装着できるカメラで、手術室や集中治療室などといった慌ただしい医療現場での活用が期待できます。
このカメラは薬瓶や注射器の中身をリアルタイムで解析し、患者に投与する前にミスの可能性を警告することができるといいます。AIの訓練は数カ月かけて実施。13人の麻酔科医が、セットアップや照明の異なる手術室で薬剤を準備する場面を撮影した418個の動画などを使ったそうです。
AIは薬瓶や注射器に表示されている文字を読み取るのではなく、大きさや形状、色などを基に情報を解析します。ミスがあった場合は、薬剤を扱うときにかける眼鏡に映し出すか音で警告するといいます。薬瓶の取り違えや注射器のラベルミスを感度99.6%、特異度98.8%で検出できるとのことです。
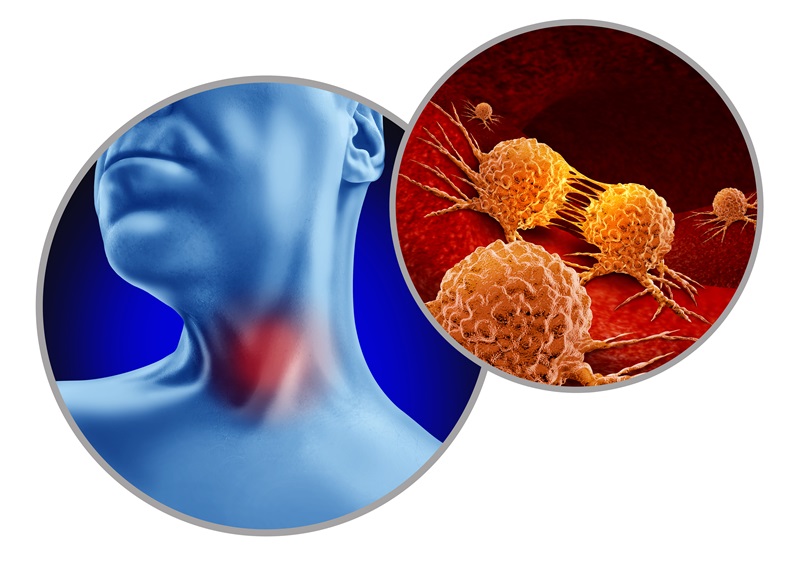
ヒトパピローマウイルス(HPV)は口腔咽頭がんの原因にもなります。米国の研究チームが男性における経口感染について、発生頻度やリスク上昇の要因などに関する新たな調査結果を科学誌Nature Microbiologyに発表しました。
チームは米国、メキシコ、ブラジルの男性計3137人を57カ月(中央値)にわたり追跡調査。発がんリスクのあるHPV経口感染は、1000人月あたり2.4件発生したそうです。リスク上昇の要因は、高学歴の人やアルコール摂取量が多い人、多数の女性パートナーがいる人、頻繁にオーラルセックスをする人、男性パートナーがいる人――であることが明らかになったといいます。また、年齢による感染リスクに違いはなく、生涯にわたりHPVに感染する可能性があるとのことです。
チームは、性別不問のHPVワクチン接種プログラムや中年男性を対象としたキャッチアップ接種の必要性を指摘しています。

歌や演奏で調子が外れ(音程がずれ)ていることを人がどうやって認識するのか、そのメカニズムは分かっていないそうです。米国の研究チームが、二つの要素が手がかりになっていることを明らかにしたと、学術誌Communications Psychologyに発表しました。
チームは、楽器がきちんとチューニングされた曲とされていない曲を参加者に聞かせ、調子が外れていると思うかを尋ねる調査を実施しました。この時、不協和音の認知に影響を与える主な要素として考えられる「ビート(拍)」と「インハーモニシティー(不調和度)」を操作したそうです。インハーモニシティーは音の成分の周波数がわずかに高くなる現象で弦楽器特有のものです。
調査の結果、調子が外れていることを検出する能力に、ビートとインハーモニシティーの両方が重要な役割を果たすことが明らかになったといいます。いずれかの手がかりをなくすと、調子はずれの検出が著しく悪化したとのことです。

米疾病対策センター(CDC)は25日、米ファストフード大手マクドナルドが販売したハンバーガー「クォーターパウンダー」に関係する集団食中毒について、最新の情報を発表しました。感染者は13州で75人が確認されており、22日の公表(10州で49人)から増加しました。
CDCと米食品医薬品局(FDA)は、クォーターパウンダーに使われていた「スライスタマネギ」が原因で腸管出血性大腸菌O157による食中毒が起きたとみているようです。マクドナルドによると、大腸菌に汚染されていたとみられる商品のタマネギはカリフォルニア州の食品メーカーから供給されたものだといいます。食品メーカーは23日、大腸菌汚染の可能性があるとして4種類の生タマネギ商品の回収に踏み切ったとのことです。
感染者のうち22人が入院し、10代の子ども1人と成人1人が溶血性尿毒症症候群(HUS)と呼ばれる重篤な腎障害に陥っており、死者が1人出ています。

高校時代のIQ(知能指数)が高い人ほど成人後に日常的にお酒を飲むようになるそうです。米国の研究チームが、米国人の男女6300人(大部分が白人)のデータを分析した結果を学術誌Alcohol and Alcoholismに発表しました。
チームは1957年に高校を卒業した参加者に対し、2004年に過去1カ月間の飲酒量について聞き取り調査を実施したそうです。男性で月に1~59杯、女性で月に1~29杯の飲酒を「適量」、それを超える飲酒を「多量」と定義したといいます。
その結果、高校時代のIQのスコアが1ポイント上がるごとに、飲酒量が適量または多量に該当する可能性が1.6%上昇することが明らかになりました。一方でIQが高い人は、一度に5杯以上飲む「深酒」はあまりしないことも分かったそうです。
ノルウェーの研究チームが2020年に発表した論文でも、知能テストの点数の高い男性は飲酒頻度が高いとの結果が得られているそうです。

英国の研究チームが、子宮頸がんの標準治療に、婦人科のがん治療で行われる化学療法を加えると生存率が大幅に向上することを確認したそうです。医学誌The Lancetに論文が掲載されました。
チームは、他臓器への転移がない局所進行性子宮頸がん患者500人を2群に分けて調査したそうです。一方の群に、放射線と抗がん剤シスプラチンを併用する標準的な化学放射線療法を実施。もう一方の群には、標準治療の前に6週間、「TC療法」と呼ばれる2種類の抗がん剤(カルボプラチンとパクリタキセル)を組み合わせた化学療法を行ったといいます。
その結果、標準治療群は5年生存率が72%、再発や転移がなかったのは64%だったのに対し、事前にTC療法を行った群は5年生存率が80%に上り、72%ががんの再発や転移を免れたそうです。ただし、重篤または命の危険のある副作用は標準治療群が48%、事前にTC療法を行った群が59%だったとのことです。

他人のそしゃく音など特定の音を聞くと強い不快感や嫌悪感を覚える「ミソフォニア(音嫌悪症)」の人は、うつ病や不安症などの精神疾患に関連する遺伝子を持っていることが明らかになったそうです。オランダの研究チームが科学誌Frontiers in Neuroscienceに論文を発表しました。
遺伝子データの解析により、ミソフォニアを自認する人は、耳鳴り、大うつ病性障害、心的外傷後ストレス障害(PTSD)、全般性不安障害に関連する遺伝子を持つ可能性が高いことが分かったそうです。
また、ミソフォニアは「神経症的傾向/罪悪感」「怒りっぽさ/敏感さ」とも遺伝的な関連が見られたそうです。一方、聴覚に過敏な自閉スペクトラム症(ASD)とは負の相関関係が見られ、ASDの人はミソフォニアではない可能性が高いといいます。
なお、今回の研究に使われたデータはほとんどが欧州人のもので、ミソフォニアに関しては医学的な診断ではなく自己申告に基づくものとのことです。

米疾病対策センター(CDC)は22日、米ファストフード大手マクドナルドが販売したハンバーガー「クォーターパウンダー」に関係する腸管出血性大腸菌O157で集団食中毒が発生したと発表しました。
西部コロラド州や中西部ネブラスカ州など10州で少なくとも49人が症状を訴え、子ども1人を含む10人が入院したといいます。コロラド州では高齢者1人が死亡しました。
CDCの聞き取り調査では、これまでのところ12人が発症前にクォーターパウンダーを食べたと答えているそうです。マクドナルドは、この商品に使われていた「スライスタマネギ」が原因で食中毒が起きた可能性があるとして、一部の州で関連商品の販売を見合わせています。
O157に感染すると、3~4日で高熱、胃けいれん、下痢、嘔吐などの症状が現れます。ほとんどの人は5~7日で回復しますが、中には溶血性尿毒症症候群(HUS)と呼ばれる重篤な腎障害に陥る患者もいるとのことです。

人間の嗅覚はこれまで考えられていた以上に優れているのかもしれません。中国と米国の研究チームが、科学誌Nature Human Behaviourに論文を発表しました。
チームは0.018秒で人間の鼻に匂いを届けることができる装置を開発。この装置を被験者229人に装着し、2種類の匂い物質AとBを立て続けに出し、一嗅ぎで嗅いでもらう実験を行ったそうです。その結果、AとBの間に0.06秒の間隔があれば、「Aの後にBを嗅いだ場合」と「Bの後にAを嗅いだ場合」を識別できることが明らかになったといいます。なお、1回のまばたきにかかる時間は0.18秒ほどです。
チームの研究で、人間の鼻が匂いに対して非常に素早く反応できる可能性が示唆されました。今回の調査で使われた匂い物質は、りんご、甘い花、レモン、玉ねぎの4種類のみだったため、チームはより多くの種類の匂いを試す必要性があるとしています。

米ワシントン州の養鶏場で働く労働者4人に、鳥インフルエンザウイルスが感染したことが確認されたそうです。米NBC Newsによると、4人は鳥インフルに感染した家禽の殺処分を行っていたといいます。
米国では今年、ワシントン州以外に五つの州でヒトへの鳥インフル感染が確認されており、感染者は今回の4人を含めると計31人になります。このうち1人を除く全員が、感染した家禽や乳牛への接触歴がありました。今回感染が疑われている4人は軽度の呼吸器症状と結膜炎があり、抗ウイルス薬が処方されたといいます。
カリフォルニア州とワシントン州は、鳥インフルと季節性インフルの両方が感染するリスクを減らすため、農場労働者への季節性インフルワクチンの接種を検討しているそうです。両方のウイルスが同時に感染するとウイルスに変異が起き、ヒトの間で感染が広がりやすくなるリスクが高まるといいます。

尿酸の結晶が関節にたまることで激しい炎症が起こる「痛風」は、食生活の乱れが大きく関わっているといわれています。しかし、ニュージーランドの研究チームが、これを否定する研究結果を科学誌Nature Geneticsに発表しました。
チームが260万人の遺伝情報を解析した結果、痛風発作を防ぐための標的になり得る多数の免疫関連遺伝子が特定されたそうです。痛風の根本的な原因は「尿酸値の高さ」「尿酸結晶の関節への蓄積」「関節における炎症発作」で、これら全てのプロセスに遺伝子が重要な役割を果たしていたといいます。
特定された遺伝子の一つは、免疫細胞などが産生するタンパク質インターロイキン6(IL-6)に関連するもので、関節リウマチなどの治療に使うIL-6阻害薬「トシリズマブ」が痛風にも有効な可能性があるそうです。
チームは、赤身肉など特定の食事が痛風発作の引き金になる可能性はあるものの、主な原因は遺伝的要因だとしています。

20世紀は、衛生状態の改善や医学の進歩によって高所得国の平均寿命が約30年も延びたといいます。こうした傾向は今世紀も続くのでしょうか。
米国の研究チームが、1990~2019年のオーストラリア、フランス、香港、イタリア、日本、韓国、スペイン、スウェーデン、スイス、米国の人口統計データを分析し、科学誌Nature Agingに論文を発表しました。
その結果、1990年以降、平均寿命の延びが鈍化していることが明らかになったそうです。2019年に生まれた赤ちゃんのうち100歳まで生きるのは、女児で5.1%、男児で1.8%と推定されるとのことです。
論文の著者が米CNNの取材に応じ、生物学的老化のプロセスを著しく遅らせることができない限り、人間の寿命が120歳や150歳まで延びることは現実的ではないと述べています。そして、今後は単なる寿命ではなく「健康寿命」を延ばすことに意識を向ける必要があると指摘しています。

大型ハリケーン「へリーン」と「ミルトン」に相次いで襲われた米フロリダ州で、「人食いバクテリア」と呼ばれる細菌の一つ「ビブリオ・バルニフィカス」の感染者が増加しているそうです。
ビブリオ・バルニフィカスは、沿岸の暖かい海水に生息し、汚染された水や魚介類を摂取したり、傷口が汚染水に触れたりすることでヒトに感染します。また、肝疾患や免疫不全の人が感染しやすいそうです。
米CNNによると、9月26日にヘリーンが上陸するまではフロリダ州の9月の感染者は6人でしたが、月末には24人に増加しました。さらに、二つのハリケーンが直撃して以降これまでに計38人の感染者が確認されており、今年の感染者は76人になったといいます。
米国疾病対策センター(CDC)に報告される感染者は年間150〜200人で、このうち約5人に1人が死亡するそうです。フロリダ州保健局は、ハリケーンによる洪水の水はこの菌が急速に増殖する可能性があるため、触れないよう注意を呼びかけていたといいます。

米国で「百日咳」の流行が拡大しているそうです。米疾病対策センター(CDC)は17日、今年の百日咳(ぜき)の患者が10月12日時点で1万8506件確認されたと発表しました。昨年同時期の報告数は3382件で、その約5倍に上ります。
百日咳は百日咳菌に感染することで起こる気道感染症です。鼻水、微熱、咳などの症状から始まり、1~2週間後には嘔吐や肋骨(ろっこつ)の骨折を伴うことがあるほど咳が悪化し、息を吸う時には「ヒュー」という音がします。
発症の初期には抗菌薬が有効ですが、咳が激しくなる頃に使用してもあまり効き目はなく、その場合は水分補給を十分に行いながら安静にするしかないといいます。1歳未満の乳児の感染は特にリスクが高く、咳が出ずに呼吸困難に陥ることもあるそうです。
予防にはワクチンが有効で、米国では三種混合(ジフテリア、破傷風、百日咳のワクチン)ワクチンの接種が推奨されており、日本ではこれにポリオを加えた四種混合ワクチンが定期接種の対象になっています。

中国の研究チームが、早く寝る子どもの腸は健康であることを明らかにしたと、科学誌Scientific Reportsに発表しました。
チームは、2~14歳の健康な子ども88人を、午後9時半より前に寝る子どもとそれより後に寝る子どもの2グループに分け、その便の分析結果を比較しました。すると、早く寝る子どもは腸内細菌叢(腸内フローラ)の多様性が高く、有益な細菌が多く存在することが分かったといいます。具体的には、腸の健康維持や正常な認知機能に関連する善玉菌「アッカーマンシア・ムシニフィラ」などが豊富だったとのことです。
また、代謝物質の分析では、早く寝る子どもの間でアミノ酸代謝や神経伝達物質調節の活性が高まっていることも明らかになったといいます。これらは脳の機能と発達に重要な役割を果たすそうです。
チームの研究により、睡眠パターンが腸内細菌叢に大きな影響を与えることが分かりました。なお、これまでの研究で、十分な睡眠が成長や学業成績を改善し、BMIを正常に保つことが明らかになっているといいます。

新たな血液検査がアルツハイマー病(AD)の早期発見に有効であることを実証したと、米国の研究チームが科学誌Molecular Neurodegenerationに発表しました。一度の血液検査で、さまざまな側面からADリスクを予測できるそうです。
チームが調査したのは、神経変性疾患に関連する約120種類のタンパク質の変化を解析できるAlamar Biosciences社の「NULISAseq CNS Disease 120 Panel」という血液検査です。
チームは、認知機能が正常な高齢者113人を対象に2年間の追跡調査を実施。まず、参加者の血液検体をNULISAseqで解析しました。それをADの標準的なバイオマーカーであるタンパク質タウやアミロイドβなどの測定結果、脳画像によるADの評価と比較したといいます。
すると、NULISAseqがADに関連する複数のバイオマーカーを検出できることが分かったそうです。これらのバイオマーカーの多くが、脳脊髄液を使わないと測定できない神経細胞の一部や脳血管に関連するタンパク質だったとのことです。
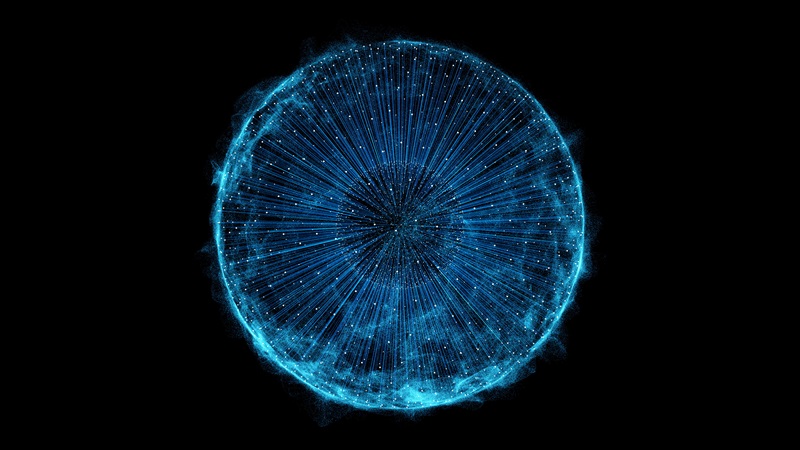
クマやワラビーなど130種類以上の哺乳類が、母体や周囲の環境が子どもにとって適切な状態になるまで胚の成長を一時停止させる「胚休眠」と呼ばれる生殖戦略を持っています。ドイツの研究チームが、ヒトも同じようなメカニズムを持っている可能性があることを突き止めたと、科学誌Cellに発表しました。
チームは、マウスの胚の休眠状態を引き起こすことが分かっているmTORというタンパク質に着目しました。ヒト多能性幹細胞(hPSC)由来の受精から5~7日目の胚(胚盤胞)モデルを、mTORの働きを阻害する薬に暴露させたところ、胚が最長8日間にわたって休眠に似た状態に入ることが明らかになったそうです。mTOR阻害薬への暴露をやめると、胚は再び正常な成長プロセスに戻ったといいます。
チームは、こうしたメカニズムの理解は体外受精(IVF)技術の進歩につながるとしています。
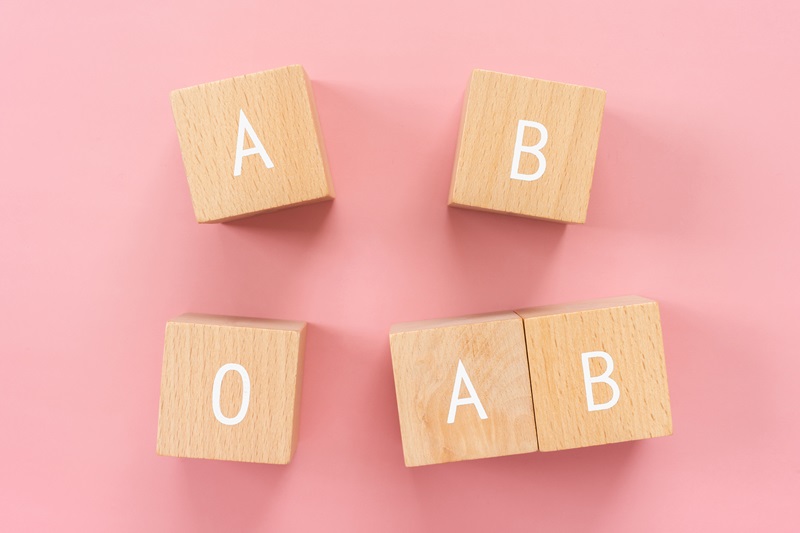
血液型がA、B、AB型の人は、新型コロナウイルス感染後の心血管系の病気(心血管イベント)のリスク上昇に特に注意が必要なようです。米国の研究チームが医学誌Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biologyに論文を発表しました。
チームは、2020年2~12月に新型コロナを発症した人1万5人と感染者ではない21万7730人のデータを分析。コロナ感染歴がある人は、感染から3年以内に心臓発作や脳卒中などの心血管イベントを発症するリスクやそれによって死亡するリスクが倍増することが明らかになったそうです。
特に、新型コロナで入院した患者はこうしたリスクが高かったといいます。さらに詳しい遺伝子解析を行ったところ、血液型がA、B、AB型の人はO型の人に比べてコロナ感染後に有害な心血管イベントを経験する可能性が2倍高くなることも示されたとのことです。

消化器感染症「クロストリジオイデス・ディフィシル(C. ディフィシル)感染症」に対するmRNA技術を使ったワクチンが実現するかもしれません。米国の研究チームが科学誌Scienceに発表しました。
C. ディフィシルはヒトの腸管などに少数生息する細菌です。多くの場合、抗菌薬の使用などによって腸内細菌叢(腸内フローラ)のバランスが乱れることで感染症を発症します。症状はさまざまで、軽度の下痢から、大腸が膨張する中毒性巨大結腸症や腸閉塞を起こして死に至ることもあります。
チームはmRNA技術を用いて、C. ディフィシルが病気を引き起こす際に必要な数種類のタンパク質を標的にするワクチンを開発したそうです。他のmRNAワクチンと同様、このワクチンも感染自体を防ぐのではなく、病原菌と効果的に戦えるよう免疫系を訓練する仕組みだといいます。
マウスを致死量のC. ディフィシル菌に感染させた実験では、このワクチンを投与したマウスが全て回復したのに対し、ワクチンを投与しなかったマウスは全て死んだそうです。

たばこ製品を生涯にわたり購入することができない「たばこフリー世代」を実際に作ることができれば、肺がんによる死亡を大幅に減らせるようです。スペインの研究チームが、世界保健機関(WHO)やその付属機関である国際がん研究機関(IARC)が公表した82カ国のデータを基に、将来の肺がんによる死亡率を予測し、医学誌The Lancet Public Healthに発表しました。
世界では毎年180万人が肺がんで死亡し、その3分の2以上がたばこが原因と推定されているといいます。チームによると、2006~10年生まれの人にたばこの販売を禁止した場合、95年までに185カ国で120万人の肺がんによる死亡を防ぐことができるそうです。現状では肺がんで290万人が死亡すると予想されており、それを40.2%減らせることになります。
また、こうした措置によって恩恵を受ける割合は男性の方が高く、死亡者は女性が30.9%減と推計されるのに対し、男性は推計45.8%減になるといいます。
なお、今回の研究は、電子たばこの使用については考慮されていないとのこと。

新型コロナウイルス感染症後の長引く「後遺症」は、生命維持に関わる「脳幹」の炎症が影響している可能性があるそうです。英国の研究チームが科学誌Brainに論文を発表しました。
新型コロナで死亡した人の脳幹は、感染による免疫応答によって炎症などの変化が生じていることが確認されています。そこでチームは、脳幹のダメージが「コロナ後遺症」の一因であるとの仮説を立て、生きている患者の脳についても観察することにしたそうです。
脳の様子を詳細に画像化することができる超高磁場の「7テスラMRI」を使い、ワクチンが開発される前のパンデミック初期に、重度の新型コロナで入院した患者30人の脳を解析。これらの患者の多くが疲労感や息切れ、胸痛といった症状が長引いていたとのことです。
調査の結果、脳幹の一部(延髄、橋、中脳)に炎症反応と思われる異常が認められたそうです。また、脳幹の変化は精神の健康とも密接な関係があり、うつ症状や不安を生じさせていると考えられるとのことです。

評価や判断を加えずに、今この瞬間に意識を向ける状態を作る「マインドフルネス瞑想(めいそう)」は、プラセボ効果ではなく、本当に痛みを軽減する効果があるそうです。米国の研究チームが科学誌Biological Psychiatryに論文を発表しました。
チームは、健康な115人を▽事前にマインドフルネス瞑想の仕方を学んだ群▽偽の瞑想を学んだ群▽偽の痛み軽減クリームを与えられた群▽瞑想指導の代わりにオーディオブックを聞かされた群――に分けて実験を行いました。
熱刺激による痛みを与え、MRIで脳の反応を分析したところ、事前にマインドフルネス瞑想の仕方を学んだ群は、その他の群に比べて、痛みの強度に関連する神経信号や、痛みに対する否定的な感情に関連する神経信号が大幅に減少することが明らかになったそうです。マインドフルネス瞑想群は、自己申告による痛みの評価スコアも低かったといいます。
なお、プラセボ効果によって痛みの神経信号が減少したのは、偽クリーム群だけだったそうです。

歯磨きで口の中を清潔に保つことで、歯周病だけでなく「頭頸(けい)部扁平上皮がん(HNSCC)」の発症リスクも抑制できる可能性があるそうです。米国の研究チームが、医学誌JAMA Oncologyに研究成果を発表しました。
チームは、健康な男女15万9840人を10~15年にわたり追跡調査しました。このうち、HNSCCを発症した236人と、対照群として無作為に選んだHNSCCではない485人の唾液のサンプルを比較しました。その結果、数百種類ある一般的な口腔内細菌のうち13種類がHNSCC発症リスクの上昇や低下に関連することが明らかになったそうです。
総合すると、こうした細菌はHNSCC発症リスクを30%高める可能性があるといいます。さらに、これらの細菌に9種類の歯周病菌を加えて、合計22種類の細菌に着目したところ、HNSCCリスクを50%上昇させることが明らかになったそうです。
また、チームは口腔内の真菌についても調査を行っています。真菌とHNSCCリスクとの関連性は認められないことが分かったとのことです。

人は不十分な情報しか得ていなくても、自分は正しいと信じ込む傾向にあるようです。米国の研究チームが、平均年齢40歳の1300人を対象に行った研究結果を科学誌Plos Oneに発表しました。
チームは「地域の地下水が枯渇したため学校の水が不足する」という架空の記事を使って実験を行いました。500人には「別の学校と統合する」ことの利点三つと中立的な意見一つが書かれたもの、別の500人には「現状のまま雨が降るのを待つ」ことの利点三つと中立的な意見一つが書かれたもの、残りの300人にはこれら七つの意見が全て書かれたものを与えたといいます。
記事を読んだ後、学校が取るべき対応策について意見を聞いたところ、大部分の人が、自分が読んだ記事に書かれていた意見に賛成し、意見を決めるために十分な情報を得ていると自信を持っていたそうです。
一方で、その自信がもろいことも明らかになりました。参加者に反対側の意見が書かれた記事を読ませて意見を聞くと、多くの人が意見を変えたがり、当初の意見に自信が持てなくなったとのことです。

抗菌薬の使用で乳児期に腸内細菌叢(腸内フローラ)のバランスが乱れることが、将来の攻撃的な行動につながる可能性があるようです。イスラエルの研究チームが科学誌Brain, Behavior, and Immunityに発表しました。
チームは、生まれてから48時間以内に抗菌薬を投与され、腸内細菌叢の多様性が低くなった生後1カ月のヒトの乳児から採取した便を、生後5週間のマウスに移植して調べたそうです。すると、このマウスは抗菌薬を使わなかったヒト乳児の便を移植されたマウスに比べて、移植から4週間後の攻撃性が高くなることが分かったそうです。
また、抗菌薬を使用した乳児の便を移植されたマウスは、脳の五つの領域において攻撃性に関連する遺伝子発現に変化が見られ、同じく攻撃性に関係があるとされる神経伝達物質「セロトニン」の減少やセロトニンの生合成に必要なアミノ酸「トリプトファン」の増加も確認されたといいます。
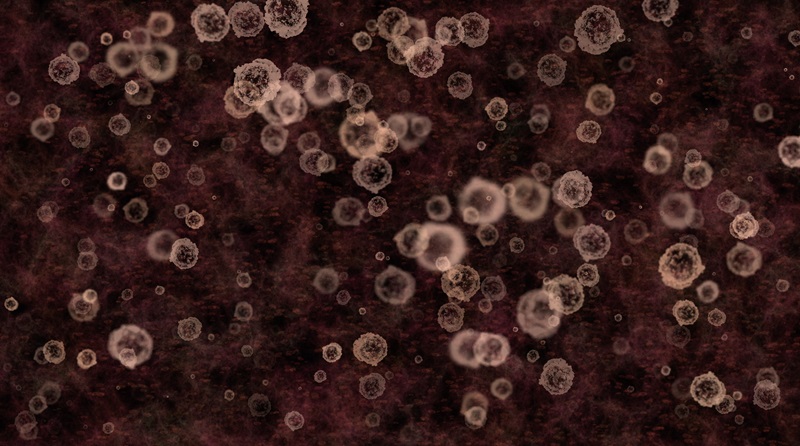
新型コロナウイルス感染後の長引く後遺症は、ウイルスが体内から完全には除去されず感染状態が続く「持続感染」が原因の一つかもしれません。米国の研究チームが、医学誌Clinical Microbiology and Infectionに発表しました。
チームは、スパイクタンパク質をはじめとする新型コロナウイルスの構成成分を高感度で検出できる抗原検査を開発したそうです。そして、この検査を使って新型コロナ感染歴のある706人から採取した1569の血液検体を分析しました。
その結果、新型コロナ感染から1~14カ月後に心肺、脳、筋骨格に関連する後遺症がある人の43%からウイルスのタンパク質が検出されたそうです。一方、後遺症の症状がない人のうち、こうしたタンパク質が検出されたのはわずか21%だったといいます。
ウイルスが体内に残り続けることでコロナ後遺症が起こる場合は、抗ウイルス薬で症状を緩和できる可能性があるとのことです。

生活習慣の乱れによる概日リズム(体内時計)のズレは、大腸がんの進行に影響を及ぼすそうです。米国の研究チームがこのメカニズムを明らかにしたと、科学誌Science Advancesに発表しました。
チームは大腸がんマウスを使って調査を実施。その結果、概日リズムが乱れると、腸内細菌叢(腸内フローラ)の多様性や豊富さが変化することが分かったといいます。さらに、腸内細菌における核酸、アミノ酸、炭水化物(糖)の代謝経路も変化してしまい、そのことが関連して、有害な細菌などから腸を保護する粘液の量が減少することも明らかになったそうです。こうしたことから、概日リズムが腸のバリアの完全性を維持するために不可欠であることが示されました。
腸は本来、必要な物質だけを体内に取り込みますが、バリア機能が崩れると毒素や細菌が血液に流れ込みやすくなり、がんの進行が加速するようです。近年、50歳未満の大腸がん発症が増加しているといい、チームは概日リズムの乱れが影響している可能性があると指摘しています。

米イリノイ州のシカゴ公衆衛生局(CDPH)は、9月12日に行われた野外コンサートの観客が、狂犬病ウイルスを保有するコウモリに接触した可能性があるとして注意を呼びかけました。シカゴ周辺のコウモリの一部が狂犬病にかかっていることが分かっているそうです。
CDPHは、ライブ会場「Salt Shed」で午後5~10時の間にバンドグループ「Goose」に参加した人の中で、コウモリにかまれたり、引っかかれたり、直接接触したりした人がいれば、直ちに医療機関で狂犬病の「暴露後予防(PEP)」について相談するよう求めました。ただし、コウモリのかみ傷は小さいため見つけるのが難しく、かまれたことに気づかない場合もあるといいます。
狂犬病はヒトや哺乳類の神経系に深刻な影響を与える感染症で、狂犬病ウイルスに感染した動物を介してヒトに感染します。潜伏期間は通常1~3カ月ですが、1週間~1年以上と大きな幅があります。感染動物と接触した後、迅速かつ適切にPEPが投与されなければ、ほぼ100%死に至ります。

スウェーデンのカロリンスカ研究所は7日、2024年のノーベル生理学・医学賞を遺伝子の働きを調節する「マイクロRNA」を発見した米マサチューセッツ大学のビクター・アンブロス教授とハーバード大学のゲイリー・ラブカン教授に授与すると発表しました。
アンブロス教授らは長年、体内の全ての細胞は同じ遺伝情報を持つにもかかわらず、それぞれが筋肉や神経など全く異なる種類の細胞に発達する理由を調査してきました。そして線虫を使った実験で、マイクロRNAという分子が遺伝子の働きを制御(タンパク質の合成量を調整)していることを突き止めました。
その後、線虫から見つかったマイクロRNAが、ヒトなどさまざまな生物に存在することが判明。さらに、マイクロRNAによる遺伝子調節がうまくいかなくなると、がんなどの疾患につながる可能性も明らかになりました。
近年は、マイクロRNAを病気の診断や治療に活用する研究も進められています。

ベトナムで9月、トラなどの大型肉食獣が数十頭、鳥インフルエンザウイルス(H5N1型)の感染によって死んだそうです。
AP通信によると、ベトナム南部ドンナイ省ビエンホア市の動物園で、トラ20頭とヒョウ1頭が死にました。トラから採取された検体は、鳥インフルエンザウイルス(H5N1型)に陽性反応を示したといいます。死んだトラやヒョウは、近くの養鶏場から購入した生の鶏肉を餌として与えられていたそうです。
動物園の関係者は「トラは弱り、餌を食べなくなり、病気になって2日後に死んだ」と話しているとのことです。トラの飼育を担当していた職員30人は全員検査で陰性が確認されており、体調の変化もないそうです。
また、近隣のロンアン省の動物園でも、同時期にトラ27頭とライオン3頭が鳥インフルで死んだといいます。鳥インフルH5N1型は近年、犬や猫からアシカやホッキョクグマに至るまで多くの哺乳動物で感染が確認されています。
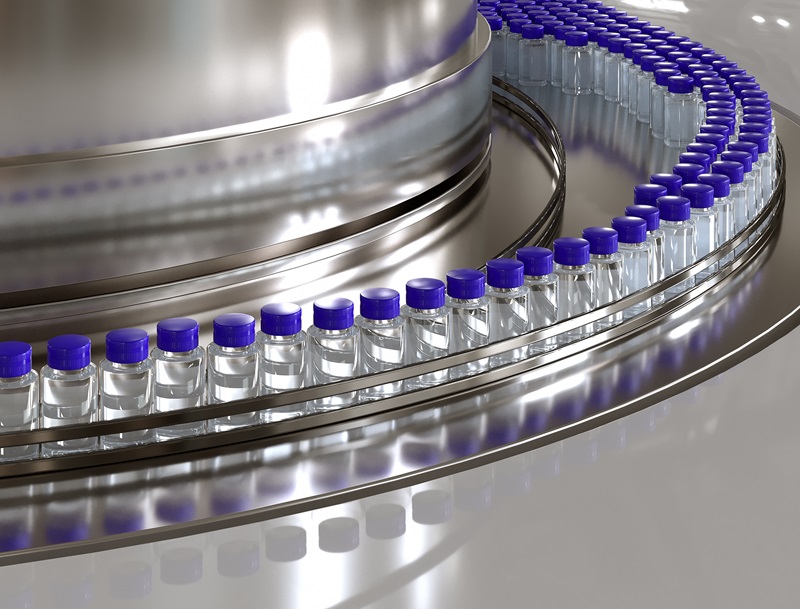
致死率の高い出血熱「マールブルグ病」の流行が発生しているアフリカ中部ルワンダの保健当局は6日、マールブルグ病に対するワクチンの臨床試験を開始すると発表しました。
AP通信によると、米国の非営利組織(NPO)セービンワクチン研究所によって、研究段階のマールブルグ病ワクチン700回分が提供され、感染者に接触した人や医療従事者などに投与されます。現時点ではマールブルグ病に対する承認済みのワクチンはありません。
ルワンダは、9月27日にマールブルグ病の流行を宣言しています。感染拡大を防ぐために通院や通学の制限など厳しい対策が講じられているといいます。これまでに感染者46人、死者12人が確認されているそうです。
マールブルグ病は、マールブルグウイルスが原因の出血熱で、致死率は最大88%と報告されています。患者の血液や体液、排泄物や汚染された寝具などを介してヒトからヒトに感染します。

米疾病対策センター(CDC)は3日、カリフォルニア州で鳥インフルエンザウイルス(H5型)が感染した2人の酪農従事者が確認されたと発表しました。
2人は同州セントラル・バレーの別々の農場で働いており、どちらの農場にも鳥インフルエンザウイルス(H5N1型)が感染した乳牛がいたそうです。2人とも軽症で、主な症状は結膜炎だといいます。
今年3月以降、米国では鳥インフルがヒトに感染する症例が報告されており、今回の2人を含めて計16件になります。そのほとんどが感染した家禽や乳牛に関連したものですが、ミズーリ州では動物への接触歴がない感染者が1人確認されています。
その他、これまでに感染者が確認されたのはテキサス州1人、コロラド州10人、ミシガン州2人です。
CDCは、感染動物に接触した人が鳥インフル陽性になるのは想定内であり、一般市民へのリスクは低いままだとしています。

英国などの研究チームが、アンドラッカブル(創薬不可能)と考えられてきた、がん細胞の標的を「分解」する新薬の開発に成功したと、科学誌Scienceに発表しました。難治がん治療の道が開かれる可能性があるといいます。
チームは、発がんに関与する「KRAS遺伝子変異」のタンパク質を分解へと誘導することができる低分子「タンパク質分解誘導キメラ分子(PROTAC)」をベースに、新薬(ACBI3)を開発したそうです。
KRAS遺伝子には多くの変異サブタイプがあり、現在はこのうちの一つ「G12C」を標的に、その活性を阻害する薬(阻害剤)のみが承認されています。一方、今回新たに開発されたACBI3は一般的なKRAS遺伝子変異17種類のうち13種類を選択的かつ強力に分解できることが分かったそうです。
マウスの実験では、ACBI3による分解がKRAS遺伝子の阻害よりも有効であり、効果的な腫瘍退縮を誘発することが示されたとのことです。

2型糖尿病の治療に使われる「SGLT2阻害薬」が、アルツハイマー病(AD)やパーキンソン病(PD)の発症リスクを抑制する可能性があるそうです。韓国の研究チームが医学誌Neurologyに発表しました。
SGLT2は、腎臓の糸球体で尿から血液中に糖を再吸収する際に働くタンパク質です。SGLT2阻害薬は、この働きを阻害することで、糖を尿として排出して血糖値を下げます。
韓国の研究チームが、2型糖尿病の投薬治療を受ける患者35万8862人(平均年齢58歳)を対象に調査を実施。SGLT2阻害薬を服用していた人は平均2年、それ以外の2型糖尿病治療薬を服用していた人は平均4年、それぞれ追跡調査を行ったそうです。
その結果、SGLT2阻害薬を使用した人は、AD発症リスクとPD発症リスクが共に20%、脳血管障害(脳卒中)によって起こる血管性認知症発症リスクは30%、それぞれ低くなることが分かったといいます。

多発性骨髄腫の治療に使われる「ポマリドミド」が、「遺伝性出血性毛細血管拡張症(HHT、 オスラー病)」に有効な可能性があると、米国の研究チームが医学誌New England Journal of Medicineに発表しました。
オスラー病は全身の血管に異常が生じ、鼻血などの出血症状が起こる遺伝性疾患です。肺や脳、肝臓、消化管などにも動静脈奇形を生じることがあります。
チームは、中等~重度の鼻出血がある成人のオスラー病患者144人を対象に臨床試験を実施。ポマリドミドを投与された人は、鼻出血の重症度が著しく低下し、輸血や鉄補充の量が減ったといいます。中間分析の時点で安全性と有効性が確認されたため、臨床試験は早期に終了しました。
試験終了後、参加者の追跡調査は行われませんでしたが、投薬を中止しても、参加者の一部は最長で6カ月にわたり鼻出血が再発しなかったことが確認されているといいます。ポマリドミドによって異常な血管の成長が阻害される可能性があるようです。

韓国政府が医師不足を解消するために医学部の定員増計画を打ち出し、これに反発した研修医らが今年2月に始めたストライキは、7カ月が経過した今も続いているそうです。
米公共ラジオNPRによると、長引くストに国民の不安は高まっており、世論調査では80%近くの人が「病気になったときに医療を受けられなくなるのではないかと恐れている」と回答したといいます。
政府と医師らの対立が続く中、韓国の医療制度が崩壊する兆しも見えています。今年、韓国内の主要な病院でのがん手術は16%減少しており、救急搬送の拒否や救急診療の業務制限も問題になっているそうです。
一方、政府は「医療システムは円滑に運営されている」と事態の深刻さを否定しており、医師らは政府が定員増計画を完全に中止するまでストを続ける構えだといいます。
どちらも相手側が譲歩しない限り対話さえするつもりはないそうで、患者や国民の医療に対する信頼が損なわれかねない状況だとのことです。

食事中に適切な量のエネルギーを摂取するために、脳ではどのようなことが起きているのでしょうか。
ドイツの研究チームが、マウスの視床下部においてニューロンが電気信号を発するタイミングを詳しく分析。その結果、食事中に順番に活性化するニューロン(神経細胞)の四つの「チーム」を特定したそうです。
これらのチームは、食事中にリレーのようにそれぞれが異なるフェーズで活性化し、適度な量が摂取されるまでグループ間でバトンが引き継がれていくといいます。また、食事に関与するニューロンの全チームが同じようなリズムで振動しているため、チーム間で情報伝達がしやすくなる仕組みになっているのだそうです。
チームは、こうしたニューロンの振動リズムに着目し、例えば外部から電磁波で振動リズムに影響を与えることなどによって、摂食障害の治療につながる可能性があるとしています。
研究チームは論文を科学誌Journal of Neuroscienceに発表しました。
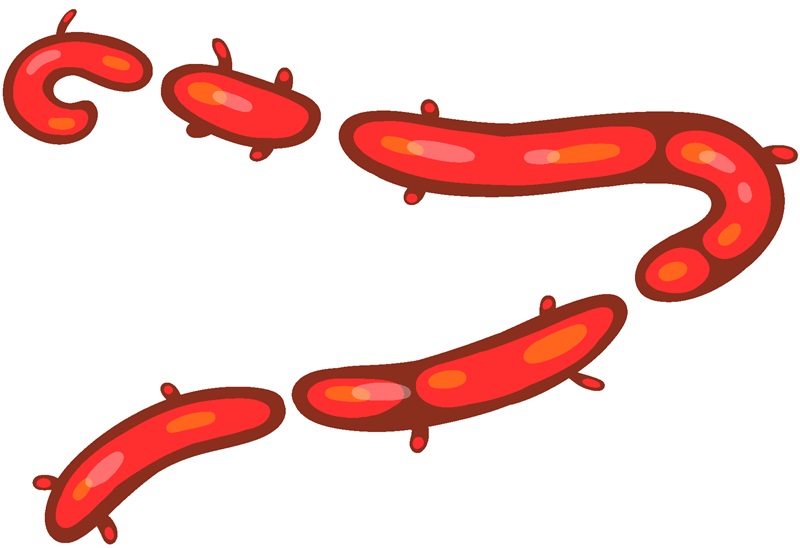
AP通信によると、アフリカ中部ルワンダでエボラ出血熱に似た症状が出るマールブルグ病の流行が発生し、8人が死亡しました。ルワンダの保健当局が9月29日に発表したそうです。
マールブルグ病は、オオコウモリが自然宿主と考えられているマールブルグウイルスが原因の出血熱で、致死率は最大88%と報告されています。患者の血液や体液、排泄物や汚染された寝具などを介してヒトからヒトに感染します。
潜伏期間は3日~3週間と幅があります。症状は発熱、頭痛、筋肉痛、下痢、嘔吐(おうと)などで、激しい出血で死に至ることもあるといいます。ワクチンや治療薬はありません。
ルワンダは9月27日に流行を宣言。これまでに確認された感染者は26人で、感染者に接触したと特定されている人は約300人いるそうです。
世界保健機関(WHO)のテドロス事務局長は28日、「ルワンダ当局と協力して感染拡大を食い止める」とX(旧ツイッター)に投稿したとのことです。

「水をたくさん飲むと二日酔いを防げる」という説は本当なのでしょうか。オランダなどの研究チームが、飲酒や二日酔いに関する13の研究結果から、アルコールの利尿作用によって引き起こされる脱水と二日酔いが関連しているかどうかを分析した結果を科学誌Alcoholに発表しました。
チームの分析の結果、脱水と二日酔いが同時に起こる可能性は否定されませんでしたが、この二つが直接関連しているという証拠は見つからなかったそうです。学生826人を対象とした研究では、水を飲んで二日酔いを和らげようとしても、その効果はほんのわずかだったといいます。
また、18~30歳の参加者29人を対象とした別の研究では、脱水の感覚は、頭痛など他の二日酔いの症状ほど長く続かないことが明らかになったそうです。
チームは、飲酒中や飲酒後に水を飲んでも、翌日の二日酔いを防ぐ効果はほとんど期待できないと結論付けました。さらに、二日酔い中に飲む水の量で、二日酔いの重症度が変わることもなかったといいます。

「Kombucha(コンブチャ)」を飲むと、断食と同じような効果を得られるかもしれません。コンブチャは、紅茶や緑茶に砂糖を加えたものに酢酸菌と酵母菌からなるゲル状の菌株「スコビー」を入れて発酵させたドリンク。日本では「紅茶キノコ」とも呼ばれており、昆布茶とは別物です。
米国の研究チームが、線虫の一種であるC.エレガンスを使ってコンブチャが腸の遺伝子発現に及ぼす影響を調査。コンブチャの微生物が腸に定着すると、脂肪の分解に必要なタンパク質が増加し、トリグリセライド(中性脂肪)の合成に必要なタンパク質が減少することが分かりました。
コンブチャに含まれる微生物からなるエサを与えられたC.エレガンスは、脂肪蓄積や中性脂肪が減少し、脂肪滴(細胞の脂質を貯蔵する細胞小器官)が小さくなったといいます。代謝の変化によって脂肪が減少し、食事制限をせずに断食に似た効果がもたらされる可能性が示されました。チームは人間でも同様の効果が得られると考えているようです。
今年3月に科学誌PLOS Geneticsに掲載された論文です。

さまざまな呼吸器感染症を予防する点鼻スプレーを開発したと、米国の研究チームが科学誌Advanced Materialsに発表しました。チームは、米食品医薬品局(FDA)がすでに承認している点鼻スプレーの成分やFDAの安全基準を満たしている成分を使って、点鼻スプレー「Pathogen Capture and Neutralizing Spray(PCANS)」を開発したそうです。
このスプレーには薬剤は一切含まれていませんが、鼻の内側にジェルが形成され、それがウイルスや細菌を捕らえて無力化する仕組みです。マウスの実験では、スプレーを使ったマウスは、致死量の25倍のインフルエンザウイルス(H1N1型)を投与しても、100%が生き残ったそうです。
さらに、スプレーを使わなかったマウスに比べて、肺のウイルスレベルが99.99%以上少なくなることも分かったといいます。感染防止の効果は少なくとも4時間持続。新型コロナやRSウイルスなど、試験した病原体のほぼ100%をブロックし、無力化したそうです。

米疾病対策センター(CDC)は27日、中西部のミズーリ州で動物との接触歴がない成人1人に鳥インフルエンザウイルス(H5N1型)が感染したことに関連して、この感染者に接触した医療従事者4人が呼吸器症状を呈したことが新たに分かったと発表しました。
このうち1人については、病院がマスク着用などの感染予防対策を講じるよう指示を出す前に感染者に対応した「高リスク接触」に該当したそうです。CDCはこの前週までに、今回とは別の医療従事者2人に呼吸器症状が出たと報告しており、感染者に接触して症状を呈した医療従事者は合計6人になりました。6人とも重篤な症状はなく、すでに回復しているといいます。
最初に症状を報告した医療従事者はインフルエンザ検査で陰性でしたが、残りの5人は検査を受けておらず、これから鳥インフルの抗体の有無を調べる血液検査が行われる予定とのことです。CDCは、一般市民への差し迫ったリスクは低いままだとしています。