非公開の医師求人情報を
ご紹介いたします!
マイナビDOCTORでは、医師専任のキャリアパートナーが
あなたの転職活動をサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。
世界の医療ニュースの中から、厳選した記事をギュッと凝縮して紹介します。
1日数本を1分で、サクッと読むことができます。日々の情報収集、話のネタ探しにお役立てください。

米国の研究チームが、新型コロナウイルス感染症後の後遺症の一つとして知られる「筋肉の疲労」について、そのメカニズムの一端を明らかにしたと、科学誌Science Immunologyに発表しました。
チームはショウジョウバエとマウスを使って、炎症を起こした脳内のニューロン(神経細胞)が、どのようにして筋肉の機能不全を引き起こすのかを調査しました。その結果、まず、脳内でコロナ関連のタンパク質が見つかったショウジョウバエやマウスは、運動機能が低下することが分かったそうです。
そして、炎症によってヒトのニューロンが放出するサイトカイン「インターロイキン-6」に相当するタンパク質が、ショウジョウバエとマウスにも存在することを確認したといいます。
このタンパク質が血流に乗って筋肉に到達すると、「JAK-STAT」と呼ばれるシグナル伝達経路(細胞内に情報を伝える経路)が活性化し、筋肉組織のミトコンドリアが作り出すエネルギーの量が減少して機能不全を起こすとのことです。

動物性食品を一切取らない「ヴィーガン食」は人を若返らせる可能性があるそうです。
米国の研究チームが、成人の一卵性の双子21組を対象に8週間の調査を実施。双子の片方は肉や卵、乳製品を含む食事を、もう片方はヴィーガン食を取ったといいます。チームは、「調査開始時」「4週目」「8週目」の3回、参加者の血液から「DNAメチル化」レベルを測定し、生物学的年齢を予測しました。
DNAメチル化は、メチル基という分子がDNAにくっついて遺伝子がタンパク質を作るのを抑えてしまう現象です。このレベルの上昇が、老化と関連していることが知られています。
調査の結果、ヴィーガン食を取った人だけ生物学的年齢が若返ることが確認されたそうです。心臓、ホルモン、肝臓、炎症、代謝のそれぞれの年齢も若返ったといいます。ただ、ヴィーガン食群は対照群より体重が平均2kg多く減っており、このことが「若返り」に影響している可能性もあるとのこと。論文は医学誌BMC Medicineに掲載さました。

新型の帯状疱疹ワクチンは、認知症のリスクを低下させる可能性があるそうです。英国の研究チームが、医学誌Nature medicineに研究成果を発表しました。
チームは、グラクソ・スミスクライン(GSK)が開発した新型の帯状疱疹用の不活化ワクチン「Shingrix(シングリックス)」を接種した10万人を、旧型の帯状疱疹用の生ワクチン「Zostavax(ゾスタバックス)」を接種した群と比較したそうです。その結果、6年にわたる追跡期間において、シングリックス群はゾスタバックス群に比べて認知症と診断されるのが平均164日遅くなることが示されたそうです。なお、こうした効果は女性の方が顕著にみられたといいます。
英BBCによると、英国では「65歳になる人」「70~79歳の人」「免疫不全がある50歳以上の人」を対象に帯状疱疹ワクチンが無料で提供されており、旧型ワクチンから新型のシングリックスに置き換えが進んでいるそうです。

従来のPSA検査よりも優れた結果が得られる前立腺がんの検査が、世界的に普及するかもしれません。スウェーデンで開発された前立腺がん検出のための血液検査「Stockholm3(ストックホルム3)」について、幅広い人種に有効であることが示されたと、スウェーデンと米国のチームが医学誌journal of clinical oncologyに発表しました。
この検査は血液中のタンパク質と遺伝子マーカーを組み合わせたもので、白人における有効性が示されていました。チームは、前立腺がんの疑いで生体検査が必要と判断された複数の人種の男性2000人を調査。16%がアジア人、24%がアフリカ系アメリカ人、14%がラテン系アメリカ人、46%が白人アメリカ人だったといいます。
その結果、ストックホルム3は、前立腺がんの検出において優れており、不要な生検を45%減らせることが明らかになりました。人種間における有効性の違いも認められなかったとのことです。

シンガポールの研究チームが、自身や他の細胞を興奮させるために細胞が放出するタンパク質「サイトカイン」の一つを阻害すると、寿命や健康寿命が延びることをマウスの実験で明らかにしたそうです。英科学誌Natureに成果を発表しました。
チームは、老化に関わると考えられているサイトカインの一つ「インターロイキン11(IL-11)」に着目。「遺伝子操作でIL-11産生を阻害したマウス」と「抗IL-11薬を投与したマウス」を使って調査を行ったそうです。その結果、両方ともがんや腫瘍による死亡が減少し、慢性的な炎症や代謝の低下などといった老化に関連する疾患が少ないことが分かったといいます。
また、平均寿命は、遺伝子操作マウスで24.9%延長し、生後75週(ヒトの55歳に相当)の時にIL-11を投与したマウスはオスが22.5%、メスは25%、それぞれ延長することが明らかになったとのことです。

DNA(デオキシリボ核酸)の構成要素である「デオキシリボース(糖)」が、「男性型脱毛症(AGA)」の治療に有効な可能性があるそうです。英国などの研究チームが、デオキシリボースを使ったジェルクリームを開発し、マウスの実験で効果を確かめたと、科学誌Frontiers in Pharmacologyに発表しました。
チームは開発したジェルを、背中の毛を除去したオスのAGAモデルマウスに、20日間にわたって毎日塗布したそうです。すると、薬剤を含まないジェルを塗布したマウスに比べて新たな毛包が多く形成され、結果的に80~90%の毛がしっかりと再生したといいます。この発毛効果は、市販の発毛剤「ミノキシジル」を塗布したマウスと同等だったとのことです。
デオキシリボースが発毛を促す理由は分かっていませんが、ジェルによる治療部位の周辺で血管と皮膚細胞が増加していることが確認されたそうです。

何らかの健康問題で業務効率が落ちている状態を「プレゼンティーズム」と呼びます。大阪大学と東京大学の研究チームが、その主な要因を明らかにしたと、医学誌に論文を発表しました。
チームは、健康な労働者56人に対して2週間の調査を実施。就業時間中の心身の状態に関する自覚症状の程度と、その日のパフォーマンスについての終業時の自己評価を分析しました。また、睡眠時間を計測し、日中の作業効率との関連性も調べました。その結果、「日中の抑うつ気分」「肩凝り」「前日の睡眠時間」がプレゼンティーズムに影響を与える主要因であることが分かりました。
論文の筆頭執筆者で、東京大学大学院博士課程の諏訪かおりさんは「気軽かつ日常的にできる『ながら運動』」や「あいさつや立ち話程度の、職場でのちょっとしたコミュニケーション」がプレゼンティーズムの改善に有効だと話しています。(マイナビRESIDENT)

初期アルツハイマー病(AD)における神経細胞(ニューロン)の機能障害に、オリゴデンドロサイトという非神経細胞が重要な役割を果たしていることが分かったそうです。英国の研究チームが科学誌PLoS Biologyに論文を発表しました。
オリゴデンドロサイトは、中枢神経を構成するニューロン以外の細胞「グリア細胞」の一つで、ニューロンの長い突起部分に巻き付くミエリンを形成します。チームは、このオリゴデンドロサイトがADに関連するタンパク質「アミロイドベータ(Aβ)」を産生することを発見したそうです。これは、Aβを産生するのはニューロンだけだとするこれまでの定説を覆す結果です。
ADマウスを使った実験では、オリゴデンドロサイトにおけるAβ産生を阻害することで、ニューロンの異常な過活性が抑制されることが示されたといいます。ADの有望な治療戦略につながる可能性があります。

米国などの研究チームが、減量に有効な食物繊維を明らかにしたとして、科学誌Journal of Nutritionに論文を発表しました。
チームは、高脂肪食摂取マウスに対してさまざまな食物繊維を補給する調査を実施しました。その結果、「ベータグルカン(β-グルカン)」を補給させたマウスだけが、18週間以内に体重と体脂肪が減少することが分かったそうです。また、このマウスでのみ、減量に関連するとされる腸内細菌Ileibacteriumが増加することも示されました。
さらに、β-グルカンを補給させたマウスの腸内では、食物繊維の代謝産物である酪酸の濃度が上昇することも判明。酪酸はインスリン分泌を促すホルモンGLP-1の放出を誘発することで知られています。糖尿病や肥満症の治療に使われる「オゼンピック」などの薬剤はこのGLP-1を模倣して作られており、β-グルカンがオゼンピックと似た効果を持つ可能性が明らかになりました。β-グルカンは、きのこや大麦、オーツ麦などに多く含まれています。

たった1滴の血液から、さまざまな病気のリスクを知ることができるかもしれません。英国などの研究チームが、4万人の血漿タンパク質と健康記録のデータを分析して明らかにした結果を医学誌Nature Medicineに発表しました。
チームは3000種類のタンパク質の中から各疾患を予測するのに最も重要な5~20種類のタンパク質の「シグネチャー(配列特徴)」を突き止めたといいます。そして、こうしたシグネチャーから、多発性骨髄腫、非ホジキンリンパ腫、運動ニューロン疾患、肺線維症、拡張型心筋症などといった67疾患の発症リスクを予測できることを明らかにしました。
タンパク質を使った予測モデルは、血球数やコレステロールなどの標準的な臨床データに基づく予測モデルに比べて高い精度を発揮したとのことです。

米国で5月以降、リステリア菌による集団食中毒が発生しているそうです。米疾病対策センター(CDC)によると、今月19日時点で、12州で合計28人がリステリア菌感染で入院し、イリノイ州とニュージャージー州ではそれぞれ1人が死亡しました。
当局が患者18人に聞き取り調査をしたところ、16人がスーパーマーケットなどのデリカウンターでスライスされた加工肉を食べていました。患者の多くは、デリでスライスされた「ターキー(七面鳥)」や「レバーヴルスト(レバーペーストを詰めたソーセージ)」を食べていたそうです。
軽い症状だけで回復する人がいる一方で、高齢者や免疫系の弱い人は重症化することがあるといいます。また、妊婦が感染すると胎児に全身感染を引き起こし、早流産などの危険があるとのこと。

米疾病対策センター(CDC)は19日、コロラド州の養鶏場で6人目の鳥インフルエンザウイルスH5N1型の感染者を確認したと発表しました。これまでの5人の感染者と同様、鳥インフルエンザの感染が広がった養鶏場で、家禽の殺処分に従事していたそうです。
感染が確認された6人は、結膜炎や呼吸器感染症に関連する症状が出ているものの、いずれも軽症だといいます。患者の1人から採取したウイルスを遺伝子解析した結果、5月に乳牛からの感染が確認されたミシガン州の1例目の症例と密接な関係があることが分かったといいます。
また、抗ウイルス薬耐性に関連する変異は起きていないほか、ヒトに感染しやすくなったりヒトの間で感染が広がったりするような変異も見つかっていないとのことです。CDCは、今のところ一般市民への健康リスクは低いままだとみています。

インド南部ケララ州で14歳の少年がニパウイルス感染症で死亡し、同州保健当局が警戒アラートを出したそうです。
英BBCによると、当局は少年と接触した人を隔離した上で検査を行っています。そのうち60人以上が「感染高リスク」と判断されたとのことです。また、当局は少年の地元住人に、公共の場でのマスク着用や入院患者との面会見合わせなどの対策を講じるよう求めたといいます。
ニパウイルス感染症は、オオコウモリやブタなどからヒトに感染する人獣共通感染症です。汚染された食品や感染者との接触でうつることがあります。初期症状として、発熱、頭痛、筋肉痛、嘔吐、のどの痛みが現れ、その後脳炎や肺炎などを発症する人もいます。治療薬やワクチンはなく、致死率は40~90%といわれています。同州は、ニパのリスクが世界で最も高い地域の一つとされているそうです。

血液の凝固を防ぐために使う「ヘパリン(ヘパリン類似物質)」が、コブラ毒の解毒剤として使える可能性があるそうです。豪州などの研究チームが医学誌Science Translational Medicineに発表しました。
チームは、コブラ毒が組織の壊死を引き起こすのに必要な遺伝子を調査。ヒトや動物の細胞の表面に存在する分子、「ヘパラン硫酸」と「ヘパリン」がコブラ毒による壊死に関連していることを明らかにしました。これらは構造が似ており、コブラ毒はどちらにも結合することができるそうです。そのため、コブラにかまれた部位にヘパリン(類似物質)を「おとり」として投与することで、コブラ毒が結合して毒素が中和されるといいます。マウスの実験では組織損傷が軽減されることが示されたとのこと。
コブラを含めたヘビにかまれることで、世界中で1年間に13.8万人が死亡し、40万人が長期的な傷や障害を負っているそうです。

麻酔薬が人の意識を失わせる仕組みは、はっきりとは分かっていません。米国の研究チームが、全身麻酔などに使われる麻酔薬「プロポフォール」について、そのメカニズムの一端を明らかにしたと、科学誌Neuronに発表しました。
チームは、サルにプロポフォールを1時間投与し、「視覚」「音声処理」「空間認識」「実行機能」に関与する脳の4領域における電子記録を分析。さらに、周囲からの刺激(感覚入力)などに対する脳の反応も数値化したといいます。
通常、神経活動はなんらかの刺激(入力)を受けて急増し、すぐに制御を取り戻して過度の興奮を防ぐそうです。しかし、プロポフォールを投与すると、サルが意識を失うまで過度の興奮状態が増大し続けることが分かったといいます。薬が神経細胞の活動を抑制することで、脳内のネットワークが不安定になり、意識を失ってしまうことが示されたとのことです。

大気汚染が健康に与える影響は、私たちが考えているよりも深刻なようです。
インドなどの研究チームが、デリー首都圏などの10大都市で微小粒子状物質「PM2.5」の濃度を調査し、2008~19年に年間3万3000人以上が死亡した可能性があることが分かったそうです。また、インドの大気汚染について調べた以前の研究では、大都市に住む子どもは、肥満やぜんそくと診断される割合が高いことも明らかになっています。
PM2.5に暴露すると、細胞の成長や増殖に関わるEGFR遺伝子に変異が生じ、肺がんのリスクが高まるという英国の研究チームによる報告もあります。また、PM2.5は大気汚染物質の二酸化窒素(NO2)と連携して、肺深部の細胞に損傷を与える可能性があるそうです。(マイナビRESIDENT)

排便の頻度は健康に長期的な影響を及ぼす可能性があるそうです。米国の研究チームが、医学誌Cell Reports Medicineに論文を発表しました。
チームは、健康な成人1400人の血液や便などの検体から参加者の健康状態を調べたそうです。その結果、排便の頻度は1日1~2回が理想的であることが明らかになったといいます。そして、慢性的な便秘(排便が週2回以下)は腎臓の、下痢(排便が1日4回以上)は肝臓の、それぞれ機能低下に関連することも分かったそうです。
通常、腸内細菌は便中の食物繊維を餌にしています。しかし、なんらかの原因で食物繊維が不足すると、代わりに腸粘液層のタンパク質を食べてしまうそうです。こうしたタンパク質由来の有毒な代謝物が、腎臓や肝臓の機能低下に関連する可能性が指摘されています。

自閉症の兄や姉を持つ子どもは自身も自閉症と診断される可能性が高くなることを明らかにしたと、米国などの研究チームが医学誌Pediatricsに発表しました。
チームは、自閉症の兄か姉のいる幼児1605人のデータを分析しました。その結果、3歳の時点で幼児本人が自閉症と診断される割合は20.2%だったとのことです。また、家族内で最初の自閉症児が女児だった場合は、それが男児だった場合に比べて、もう1人自閉症児が生まれる可能性が50%高くなることが分かったといいます。
下の子が自閉症と診断される可能性は、自閉症の兄姉が複数いる場合は37%で、自閉症の兄姉が1人だけだった場合は21%だったといいます。調査対象の男児は、本人が自閉症と診断される可能性は25%だったのに対し、女児は13%の確率だったとのことです。

国連は11日、『国連世界人口推計2024版』を公表しました。2024年の世界人口は約82億人で、80年代半ばに103億人まで増加してピークを迎え、その後、今世紀の終わりには102億人に減少すると予測しています。
各国で出生率が低下していることなどから、世界人口のピークがこれまでの予想より早まる見通しです。世界の半数以上の国・地域で、女性1人当たりの平均出生児数が2.1(人口を維持するために必要な水準)を下回っているといいます。
また、24年の時点で中国や日本を含む63カ国・地域ですでに人口のピークに達しており、これらの国々の人口は今後30年間で14%減少する見込みとのことです。ブラジルやベトナムなどの48カ国・地域は25~54年、インドやインドネシア、ナイジェリア、米国など126カ国・地域は今世紀後半にそれぞれピークが予測されています。

生物学的な性別「性(sex)」と本人が自認する性別「ジェンダー(gender)」は、それぞれ異なる脳の領域のネットワーク(機能的結合)に影響を与えることが分かったそうです。米国などの研究チームが、国内の子ども4800人のデータを分析した結果を科学誌Science Advancesに発表しました。
研究の結果、「性」の違いは主に運動、視覚、制御、感情などをつかさどる大脳辺縁系のネットワークに関連し、「ジェンダー」が関連するネットワークは脳全体に広く分布していることが分かったといいます。このことから、性やジェンダーによる影響が、脳関連疾患(精神疾患)の発症傾向の違いにつながる可能性が指摘されています。
これまで生物医学の研究は、性に焦点を当てて行われてきたといいます。今回の成果は、ジェンダーについても考慮することの重要性を浮き彫りにしました。

レーザーによる視力矯正手術である「レーシック」や「PRK」を受けた後に、長引く目の痛みを訴える人がいるそうです。米国の研究チームが、痛みが出るリスクがある人を予測する方法を開発したと、科学誌Journal of Proteome Researchに発表しました。
チームは、両目にレーシックかPRKの手術を受ける患者を対象に調査を実施しました。術後3カ月の時点で、10段階で3以上の痛みを訴えた患者16人と痛みを訴えなかった患者32人の涙を分析したそうです。
その結果、涙の中に存在する2748種類のタンパク質のうち、目の痛みを訴えた患者において83種類のタンパク質レベルが変化することが明らかになったといいます。そして、このうち三つまたは四つのタンパク質を解析するコンピューターモデルを作って調べたところ、術後の長引く痛みが出る人を効果的に予測することができたといいます。

米コロラド州保健当局は14日、州北東部の養鶏場の労働者5人に鳥インフルエンザウイルスH5N1型が感染したことを確認したと発表しました。5人はいずれも鳥インフルの感染が広がった養鶏場で家禽の殺処分に従事していたそうです。感染した鳥との接触によってウイルスがうつったとみられます。
米疾病対策センター(CDC)によると、結膜炎のほか、発熱、悪寒、せき、のどの痛み、鼻水といった典型的なインフルエンザの症状が出ているもののいずれも軽症です。CDCは、現状では一般市民への感染リスクは低いとみていますが、リスク評価を変えるような遺伝子変異がないかどうかを調べているそうです。
米国では今年に入ってから、H5N1に感染した乳牛から4人が感染したことが確認されています。CDCは感染動物との接触による感染リスクが浮き彫りになったと注意を呼びかけています。

幅広い腸内微生物に着目することで、子どもの自閉スペクトラム症(ASD)を高い精度で診断できる可能性があるという研究成果を、香港の研究チームが科学誌Nature Microbiologyに発表しました。
これまでASDの研究は、腸内細菌の構成との関連に焦点が当てられてきました。チームは今回、中国に住む1~13歳の男女1627人の糞便サンプルについて、古細菌(アーキア)や真菌、ウイルスといった細菌以外の腸内微生物にも焦点を当てて分析(メタゲノム解析)を行ったそうです。
食事や薬物、併存疾患などの要因(交絡因子)を調整した結果、ASDの子どもにおいて▽古細菌14種類▽細菌51種類▽真菌7種類▽ウイルス18種類▽微生物遺伝子27種類▽代謝経路12種類――が変化していることが明らかになったといいます。これらを基に機械学習モデルを作成したところ、高い精度でASDを特定できたとのことです。

ダイエットには、「断続的断食(IF)」と「タンパク質ペーシング(P)」を組み合わせた「IF-P食事法」が効果的なようです。米国の研究チームが科学誌Nature Communicationsに論文を発表しました。
「IF」は食べ物の摂取を1日の決まった時間枠内に制限する食事法で、「P」はタンパク質の摂取を1日の中で分散する食事法です。チームは、太り過ぎまたは肥満の41人を、IF-P食事法を組み込んだカロリー制限食を摂取した群と地中海式のカロリー制限食を摂取した群に分けて8週間の調査を実施しました。
その結果、IF-P食事法群の方が、痩せやすい体質に関連する腸内細菌が増加し、体重減少に関連する血中タンパク質や脂肪を分解するアミノ酸のレベルが上昇することが明らかになったそうです。また、IF-P食事法群の方が、腸内細菌叢の多様性が増大し、胃腸症状や内臓脂肪が少なくなることも示されたといいます。

「適度な飲酒は健康に良い」「いや、酒は飲まないに越したことはない」。どちらの意見も耳にします。実際のところどうなんでしょう。
「適度な飲酒は認知症リスクを抑制する可能性がある」という研究結果を、韓国の研究チームが報告しています。缶ビール1本程度の酒を1日1杯程度飲む習慣がある人は、飲酒しない人に比べて、7~8年後に認知症を発症するリスクが21%低かったそうです。
一方で、英国の研究チームは「適度な飲酒は健康に良い」との説を覆す研究結果を発表。ビール、シードル(リンゴ酒)、蒸留酒の摂取量が、英国の健康ガイドラインで推奨されている上限より少ない人でも、心血管疾患で入院するリスクが高かったといいます。
そして、禁酒の効果を侮ってはいけないようです。英プリマス大学の専門家によると、脂肪肝は2~3週間禁酒すると正常な状態に戻るといいます。(マイナビRESIDENT)

米ニューヨーク大学(NYU)は、植え込み型補助人工心臓を装着した状態でブタの腎臓移植を受けた女性が7日に死亡したと発表したそうです。
米CNNによると、女性は4月12日に、拒絶反応を防ぐために遺伝子改変したブタの腎臓の移植手術を受けました。女性は心不全と透析が必要な末期の腎臓病を患っていたため、通常の臓器移植については対象外だったそうです。
ブタの腎臓を治療目的で人に移植するのは世界2例目で、人工心臓を装着した患者へのブタの腎臓の移植は初のことです。拒絶反応を抑えるために、女性には免疫細胞が訓練を受ける臓器であるブタの胸腺も一緒に移植されたといいます。
しかし、血流の悪化でブタの腎臓が機能せず、5月29日に摘出手術を受けていました。女性の死亡を受け、移植手術を行ったNYU のチームは「医学や外科、そして異種臓器移植分野への女性の貢献は計り知れない」という声明を発表したとのことです。
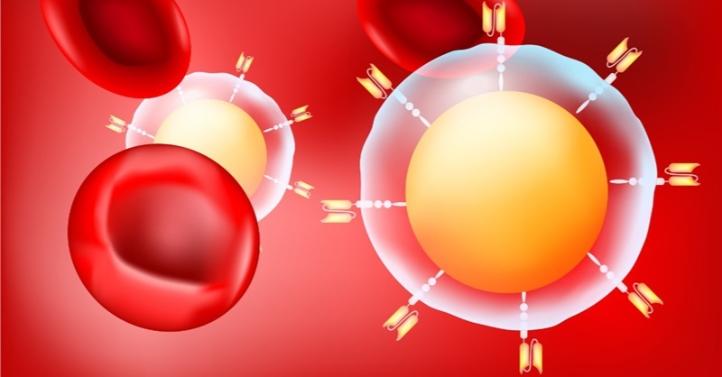
自己免疫疾患の全身性エリテマトーデス(SLE)の患者を世界で初めてCAR-T細胞療法で治療したと、ドイツの研究チームが医学誌The Lancetに発表しました。
患者は当時15歳の少女で、SLEの急激な悪化によって一生入院生活を送らなければならない状態だったそうです。医師があらゆる手を尽くしたにもかかわらず、「ループス腎炎」によって腎臓機能は著しく低下し、人工透析が不可欠だったといいます。
チームは最後の手段として2023年6月、血液がんの治療に使われるCAR-T細胞療法を実施。SLEに関与する自己反応性B細胞を破壊するために、少女自身のT細胞を遺伝子改変したものを投与したそうです。
治療3週間目から改善が認められ、徐々に全ての症状が消えていったといいます。治療によって正常なB細胞も破壊されたため、感染症予防のために毎月1回、抗体の投与を受けていますが、透析の必要もなく、少女は通常の生活を送っているとのことです。

がんになる前の状態(前がん状態)の子宮頸がんを尿から診断する検査法が実現するかもしれません。早稲田大学などの研究チームが、子宮頸がんの原因となる「ヒトパピローマウイルス(HPV)」の極微量のタンパク質を検出する「超高感度タンパク質測定法」を開発したと、学術誌Microorganismsに発表しました。
チームは、感染するとがん発症のリスクが高いHPV16型について、がん発症に関わるE7タンパク質を患者の尿から検出することに成功したそうです。子宮頸がんの前段階にある患者45人のうちHPV16かその関連型が陽性だった人の尿を使ってこの検査を試したところ、軽度異形成(CIN1)患者の80%、中等度異形成(CIN2)患者の71%、高度異形成(CIN3)患者の38%――でそれぞれE7タンパク質が検出されました。
この検査が実用化されれば、検診のハードルが大きく下がり、子宮頸がん撲滅への道が開かれます。

認知機能の維持に最も悪影響を与える生活習慣は喫煙だそうです。英国の研究チームが、欧州14カ国で認知機能に問題のない50歳以上の男女3万2000人を対象に10年にわたる追跡調査を実施し、科学誌Nature Communicationsに論文を発表しました。
チームは、喫煙の有無、週1回以上の運動、週1回以上の家族や友人との関わり、飲酒の有無(男性は1日2杯以上、女性は1日1杯以上)の生活習慣ごとに参加者を分類し、記憶力と言語の流ちょうさのテストで認知機能を評価して分析したといいます。その結果、喫煙が認知機能の低下を速める最も重要な要素であることが明らかになったそうです。
喫煙の習慣がある人は、非喫煙者に比べて認知機能を評価するスコアが最大85%も低くなったといいます。ただし、喫煙者であっても他の三つの生活習慣がすべて健康的だった場合、認知機能の低下は非喫煙者と同程度に抑えられたとのことです。

韓国南西部の南原市で、給食のキムチが原因とみられる集団食中毒が発生したようです。英BBCによると、地元当局は2日、ノロウイルスによる食中毒の症例を確認。その後、6日午後までに患者の数は1024人に達したといいます。
患者は市内24の学校に在籍する生徒や職員で、嘔吐や下痢、腹痛を訴えているそうです。当局によると、これらの学校に給食として納品されていたキムチの一部からノロウイルスが検出されたといいます。このキムチを製造した会社の名前は公表されていませんが、市はこの会社の全製品を対象に、製造・販売を一時的に停止する措置を講じたとのことです。すでに出荷された製品については、自主回収が進んでいるといいます。
ノロウイルスは非常に感染力が強く、感染者がウイルスに汚染された手で触れたトイレの洗浄レバーなどからもうつります。通常は発症から1~2日で回復しますが、人によっては重症化することもあります。

「利き手」や「利き目」は、何かに影響を与えるのでしょうか。英国の研究チームが、さまざまな年代や人種の男女1600人を対象に調査を実施し、その結果を科学誌Scientific Reportsに発表しました。
利き手の「強さ」は人によって偏りがあるといいます。チームは、ペグボードを使って色を合わせる課題を参加者に行ってもらいました。その結果、利き手への偏りが軽度~中程度の人の方が、偏りが強い人よりも正確性が高いことが分かったそうです。利き手への極端な偏りはタスク遂行における柔軟性を制限する可能性が示されました。
また、参加者の53%が「利き手が右、利き目は左」で、逆の組み合わせ(利き手が左、利き目が右)はわずか12%だったといいます。他者と関わるために必要なスキル(ソーシャルスキル)を調べたところ、「逆の組み合わせ」の群は他の群に比べて評価スコアが優位に低かったそうです。さらに、この群は自閉症や注意欠陥多動性障害(ADHD)を自己申告する割合が4倍高かったとのことです。

11月に大統領選を控える米国で、現職バイデン氏の高齢不安が高まっていることをCNNが報じています。
先日行われたトランプ前大統領との大統領選討論会では、バイデン氏が支離滅裂でまとまりのない発言をする様子などが物議を醸したそうです。こうした様子を見た複数の脳の専門家らは、バイデン氏は認知障害と運動障害の詳しい検査を受け、結果を公表するべきだと考えているといいます。
バイデン氏の健康問題を巡っては、2月に主治医らが「職務遂行に適している」と評価した報告書を公表していました。しかし、その報告書には認知検査に関する言及はありませんでした。
ホワイトハウスによると、バイデン氏は討論会当日、風邪などの理由で体調が悪かったそうです。なお主治医らは、バイデン氏が認知検査を受けて結果を公表する必要は「ない」としているといいます。

2型糖尿病治療薬「オゼンピック」や肥満症治療薬「ウゴービ」として知られるGLP-1受容体作動薬「セマグルチド」を使うと、失明につながる「非動脈炎性前部虚血性視神経症(NAION)」の発症リスクが高まる可能性があるそうです。
米国の研究チームが、NAIONではない1万6800人のデータから、糖尿病または肥満(過体重を含む)がある1700人に着目。セマグルチドを処方された糖尿病患者200人のうち17人が36カ月以内にNAIONを発症し、その割合はセマグルチドを処方されなかった群に比べて4倍も高かったそうです。肥満患者については、セマグルチドを処方された361人のうち20人がNAIONを発症。その割合は非セマグルチド群の7倍だったといいます。
ただ、糖尿病や肥満自体がNAIONリスクを高める要素でもあるため、セマグルチドとNAIONの関連を裏付けるためにはさらなる調査が必要とのことです。
チームは論文を医学誌JAMA Ophthalmologyに発表しました。

インドでは、大気汚染によって多くの人が死亡しているそうです。インドなどの研究チームが、ニューデリーやムンバイをはじめとする10大都市で、呼吸器や循環器の病気、がんを引き起こすとされる微小粒子状物質「PM2.5」の濃度を調査。WHO(世界保健機関)が推奨する年平均値(1立方メートル当たり15μg)を超えるPM2.5への曝露が原因で、2008~19年にかけて年間3万3000人以上が死亡した可能性があることが分かりました。これは、同じ期間にこれらの都市で死亡した人の7.2%に当たるといいます。なかでも首都ニューデリーでは、年間1万2000人以上が大気汚染関連で死亡しており、その割合は全死亡の11.5%に相当します。インドは現在、PM2.5の環境基準値をWHOの推奨値の4倍に当たる1立方メートル当たり60μgとしているそうです。医学誌The Lancet Planetary Healthに発表した論文です。

米コロラド州保健当局は3日、乳牛の間で流行している鳥インフルエンザウイルスH5N1型について、州内でヒトへの感染が確認されたと発表しました。同州では初めてで、米国内では4例目です。コロラド州では、乳牛の4分の1以上が鳥インフルに感染していると報告されており、その数は他のどの州よりも多いといいます。今回感染が確認されたのは酪農従事者の男性で、鳥インフルが感染した乳牛に直接接触する機会があったそうです。男性の症状は結膜炎のみだといいます。感染が発覚してすぐに抗インフルエンザウイルス剤「オセルタミビル(タミフル)」を服用し、すでに回復しているとのことです。米疾病対策センター(CDC)は、一般市民の感染リスクは低いものの、感染した動物に接触する機会がある人は個人用保護具(PPE)を着用するなどの対策を講じる必要があるとしています。

健康に良いと思ってやっていることや習慣的に行っていることが、実は健康に悪影響を与えることがあるようです。中国などの研究チームは、多くの人が心臓の健康のために取っている魚油サプリメントが、逆に不整脈や脳卒中のリスクを高めることを明らかにしました。ベルギーの研究チームは、アルコール入りのマウスウオッシュを使うと口腔内細菌叢(口腔内フローラ)のバランスが崩れ、がんの発生に関わる細菌が口の中で増加することを発見。スウェーデンの研究チームは、タトゥー(入れ墨)が血液がんのリンパ腫の危険因子になることを報告しています。また、飛行機内でお酒を飲むと、心臓に大きな負担がかかることが、ドイツの研究チームの調査で明らかになりました。米国の研究チームはジャンクフードが不安を助長することを報告しています。マイナビRESIDENTの記事です。

きちんと準備をしたのに、試験で良い点数が取れなかったことはありませんか。もしかしたら、試験会場のせいかもしれません。豪州の研究チームが、2011~19年に国内の大学に在籍した学生1万5400人のデータを分析したそうです。その結果、天井が高い部屋で試験を受けると、想定よりも点数が低くなることが分かったというのです。具体的には体育館や広いホールなどが当てはまるといいます。なぜこのような結果が出るのかは不明とのこと。豪州では、効率化の観点からこうした広くて天井が高い場所で試験が行われることが多いそうです。試験を実施する側は、物理的な環境が学生の成績に及ぼす潜在的な影響を認識し、すべての学生に平等な機会が与えられるよう調整する必要があるようです。科学誌Journal of Environmental Scienceに発表した論文です。

米イーライリリー社は2日、開発したアルツハイマー病(AD)の治療薬「ドナネマブ(商品名キスンラ)」が米食品医薬品局(FDA)に承認されたと発表しました。ドナネマブは、ADの原因物質とされる脳内のアミロイドプラークを除去するよう設計されたモノクローナル抗体で、早期ADの進行を抑制する効果が期待できるといいます。最終段階の臨床試験では、ドナネマブを使用した群はプラセボ群に比べて1年半後のAD進行リスクが35%抑制されることが示されていました。まれではあるものの、患者の2%で重篤な有害事象が確認されており、3人がアミロイド関連画像異常(ARIA)を発症して死亡しています。AD向けモノクローナル抗体については、日本のエーザイと米バイオジェンが開発した「レカネマブ」がすでにFDAに承認されており、使用が開始されています。

フィンランドの研究チームが、「うつ病」についての不正確な情報が広まっており、患者が自身の本当の苦悩を把握することが難しくなっているという研究結果を医学誌Psychopathologyに発表しました。チームは、WHO(世界保健機関)やアメリカ精神医学会(APA)、イギリスの国民保健サービス(NHS)、有名大学など、英語を使う国際的な保健衛生団体がウェブサイトに公開しているうつ病に関する情報を分析。ほとんどの団体が、うつ病を「精神症状を引き起こす障害」として表現していることが明らかになったそうです。チームは、うつ病は症状を引き起こす「原因」ではなく、気分の落ち込みなどの症状がある状態だと指摘。このような表現が一般的になると、メンタルヘルス問題における本質の理解があいまいになってしまうため、誤った認識を強化することがないよう注意を払う必要があると強調しています。
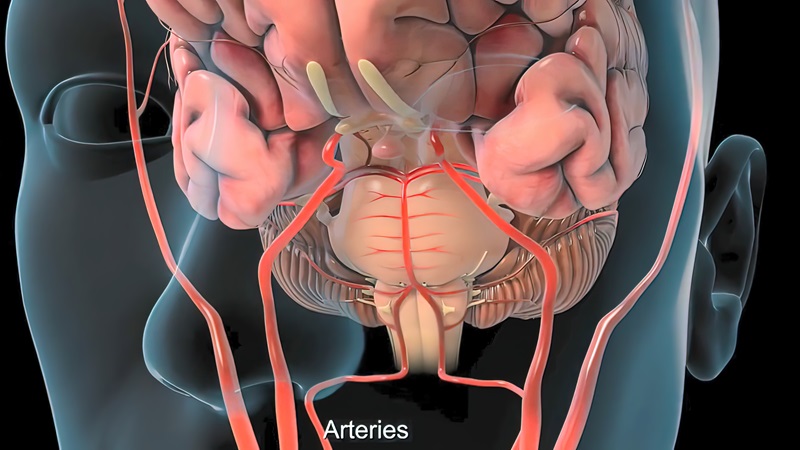
頭蓋骨の底(頭蓋底部)は脳幹や神経や血管が密集しています。その錐体先端部と呼ばれる部位にできる腫瘍の摘出は、工程が煩雑で時間がかかり、脳損傷や術後の合併症のリスクもあるため、脳外科手術の中で最も難しいといわれているそうです。大阪公立大学のチームが、従来の顕微鏡を使った手術法よりも安全で迅速な、内視鏡を使った低侵襲手術法(内視鏡下前経錐体到達法:内視鏡下ATPA)を開発し、医学誌Journal of Neurosurgeryに発表しました。チームは2022~23年に内視鏡下ATPAを用いて患者10人を手術し、2014~21年に従来法で手術を行った患者13人のデータと比較しました。すると、平均手術時間が410.9分から252.9分に短縮し、失血量は193 mlから90 mlに減少したことが判明。腫瘍切除率は従来法と同等で、神経機能の維持率は内視鏡下ATPAのほうが高いか従来法と同程度だったといいます。

先史時代のネアンデルタール人は、障害児を集団で養育していた可能性があるそうです。スペインの研究チームが、1989年にコバ・ネグラ洞窟遺跡で発掘されたネアンデルタール人の子どもの側頭骨を調査し、その結果を科学誌Science Advancesに発表しました。チームがマイクロCTスキャンで側頭骨を調べたところ、この子どもがダウン症で、難聴や平衡感覚の問題を抱えていたことが分かりました。そして、少なくとも6歳まで生きていたことが明らかになったそうです。1900年のダウン症の人の平均寿命が9年なので、この時代にダウン症児が6歳まで生きたのは驚くべきことだといいます。過酷な環境で生きていたネアンデルタール人が母親だけでこのダウン症児をケアしていたとは考えにくく、養育や介助において想定より広範囲に及ぶ集団から継続的なサポートを受けていた可能性があるとのことです。
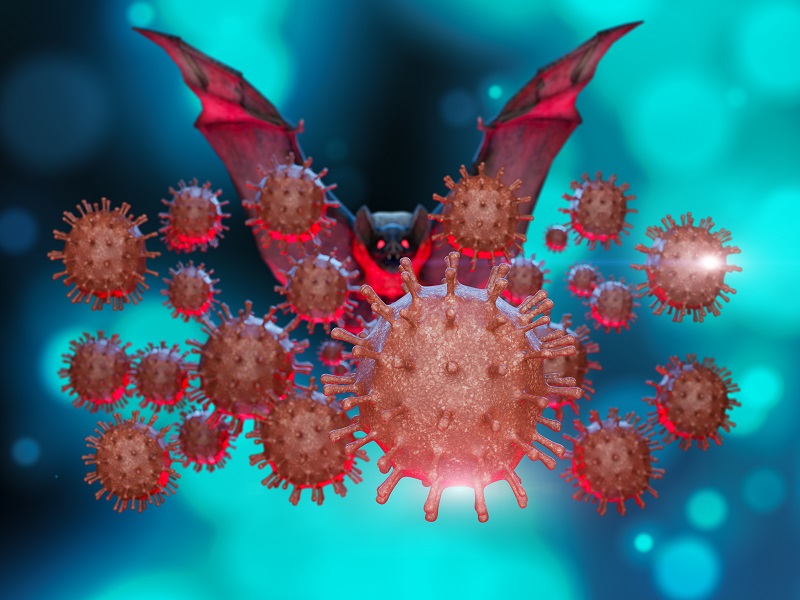
致死率の高い感染症「ニパウイルス(NiV)感染症」について、治療薬の開発が進んでいるようです。NiV感染症はコウモリが媒介する1990年代に現れた新興の人獣共通感染症です。感染動物の唾液や排泄物で汚染された食品などからヒトに感染し、呼吸器障害や脳炎などの症状が出て、40~90%が死に至ります。南アジアや東南アジアのヒトや動物の間で流行が繰り返されているそうです。米国の研究チームがNiVを中和するモノクローナル抗体「hu1F5」を開発し、動物実験で有望な結果が得られたとして、医学誌Science Translational Medicineに発表しました。hu1F5は、感染に関わるF糖タンパク質を標的にしているといいます。感染から1日たったハムスターにこの抗体を投与したところ、100%が生存。さらに感染から5日たったアフリカミドリザル6匹に投与した実験でも、6匹全てが生き残ったとのことです。

幼いころの記憶が大人になってもずっと残っているはなぜでしょうか。米国などの研究チームが、記憶力の良し悪しに関連するタンパク質「KIBRA」と記憶形成に重要な役割を果たす酵素(タンパク質キナーゼ)「Mzeta(PKMzeta)」の相互作用に着目した研究で、その理由を明らかにしたそうです。マウスの実験で、長期記憶が形成されるシナプス(神経細胞間の結合部)において、KIBRAが「接着剤」の役割を担うことが分かったといいます。記憶形成の際に活性化するシナプスにKIBRAが選択的に付着し、それが目印になってPKMzetaがそのシナプスに引き寄せられるそうです。こうして強化されたシナプスにまたKIBRAがくっつくというサイクルが繰り返され、記憶が長期間保持されるといいます。KIBRAとPKMzetaの結合を切ると、古い記憶が消去されることも確認されたとのこと。 論文は科学誌Science Advancesに掲載されました。

麻酔薬として開発され、点滴や経鼻薬などでうつ病治療にも使われている「ケタミン」。ニュージーランドなどの研究チームがケタミンの錠剤の治験(第2相)を行い、薬物治療抵抗性のうつ病患者にも有効な可能性があるとの結果が得られたとして、医学誌Nature Medicineに発表しました。チームは、過去に平均4種類の抗うつ薬を試したことがあるうつ病患者270人に試験を実施。ケタミン錠を服用した人の半数以上で、うつ病が寛解したそうです。一方で、プラセボ群の70%が13週間後に再発したといいます。このケタミン錠は肝臓で分解されるのに10時間もかかるため、極端な高揚感や解離などといったケタミンによくみられる幻覚的な副作用は報告されませんでした。オピオイドのような乱用リスクを懸念して、ケタミンのうつ病への使用に慎重な姿勢を貫く精神科医もいますが、この錠剤が懸念を和らげる可能性があります。

感染症の「迅速検査」は、どのタイミングで行うのが適切なのでしょうか。米国の研究チームが、迅速検査の効果や精度を評価する計算モデルを開発し、新型コロナやインフルエンザ、RSウイルス(RSV)感染症などについて調査を行ったそうです。その結果、新型コロナのオミクロン株については症状が出た直後に迅速検査を使うと、実際は感染しているのに陰性の結果が出る「偽陰性」が92%に上ることが分かりました。症状が出てから2日たつと偽陰性の確率は70%に下がるといいます。さらに3日目に2回目の検査を行えば、偽陰性率は66%にまで低下するそうです。一方、インフルエンザウイルスやRSVは急速に増殖するため、症状が出た後にすぐに検査をしても、きちんと陽性が出ることが多いといいます。科学誌Science Advancesに発表した論文です。

スイスの研究チームが、他者にインフルエンザをうつしやすい人がいる理由を明らかにしたと、科学誌Journal of Virologyに発表しました。チームはまず、くしゃみの飛沫に似た液滴を使って調査を行いました。インフルエンザウイルスのみを含んだ液滴は室内に30分間放置すると、ウイルスが99.9%死滅したそうです。一方、ウイルスに加えて気道に常在する細菌を含んだ液滴では、感染力のあるウイルス量が同時点で100倍も多く、その後何時間もウイルスが生存していたといいます。次に、浮遊微粒子の形態で調査したところ、ウイルスのみの粒子では15分でウイルスの感染力が消滅しました。一方、細菌を含有する粒子では1時間後も感染力のあるウイルスが存在していたとのことです。特に黄色ブドウ球菌と肺炎球菌が、このような「ウイルス保護効果」を発揮したといいます。