非公開の医師求人情報を
ご紹介いたします!
マイナビDOCTORでは、医師専任のキャリアパートナーが
あなたの転職活動をサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。
世界の医療ニュースの中から、厳選した記事をギュッと凝縮して紹介します。
1日数本を1分で、サクッと読むことができます。日々の情報収集、話のネタ探しにお役立てください。

気持ちを落ち着けるために深呼吸をする人は多いと思います。この時に脳ではどのようなことが起きているのでしょうか。米国の研究チームがそのメカニズムを明らかにし、科学誌Nature Neuroscienceに発表しました。
チームがマウスの脳を調査したところ、前頭葉で複雑な思考や感情、血圧や心拍数の調節などをつかさどる「前帯状皮質」のニューロン(神経細胞)が、脳幹の中央の呼吸調節に関わる「橋」を通り、そのすぐ下にある呼吸中枢「延髄」まで接続していることが明らかになったそうです。この三つを通る神経回路を人工的に活性化すると、マウスの呼吸が遅くなり、不安を表すしぐさが減ったそうです。逆にこの回路を阻害すると、呼吸が速まり、不安を表す行動が増えたといいます。
結論として、感情に合わせて呼吸を自発的に調整する際に「前帯状皮質・橋・延髄」回路が重要な役割を果たすことが示されました。こうした知見が、過呼吸の予防や不安やパニックのコントロールに役立つ可能性があります。
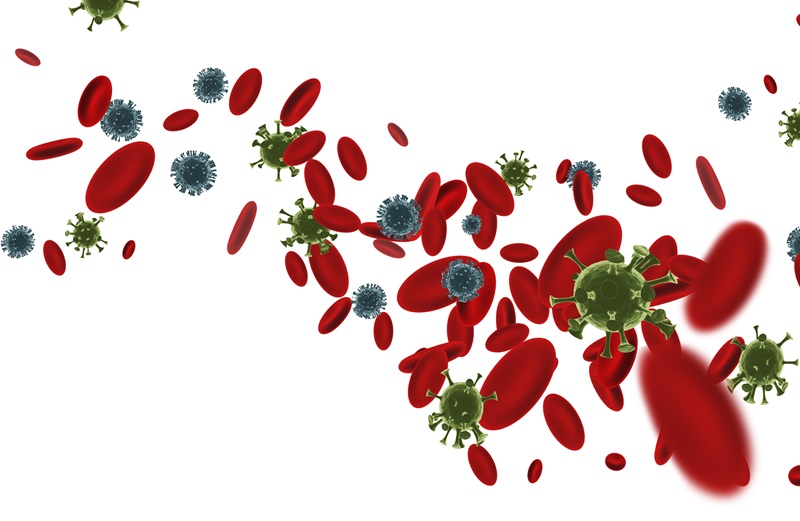
新型コロナウイルス感染後に特定のがんが縮小するケースが報告されているそうです。米国の研究チームがこのメカニズムを解明し、医学誌Journal of Clinical Investigationに発表しました。既存の抗がん剤が効かない患者に対する新たな治療法につながるかもしれません。
チームは、新型コロナウイルスのRNAが免疫系の特別な信号を刺激し、白血球の一種である「単球」が、がんを攻撃する能力を持つ特殊な免疫細胞「誘導性非古典的単球(I-NCM)」に分化することを発見したそうです。がん細胞は、免疫系や抗がん剤から逃れたり成長したりするための細胞や血管に取り囲まれています。新たに形成されたI-NCMは、この腫瘍周辺組織にも侵入できるという、他の免疫細胞にはない強みがあるといいます。
チームは、薬剤を使ってI-NCMを誘導する実験もマウスで行ったそうです。その結果、I-NCMが特にメラノーマ(黒色腫)、肺がん、乳がん、大腸がんと戦うのに有効であることが分かったとのことです。

米国のトランプ次期大統領は22日、感染症対策や予防接種の指針に関して中心的な役割を果たす米疾病対策センター(CDC)の所長に、元下院議員で医師のデーブ・ウェルドン氏を起用すると発表しました。
NBC Newsによると、ウェルドン氏はCDCのワクチンプログラムに対する辛口の批評家として知られ、ワクチンに含まれる防腐剤が自閉症に関連するなどといった誤った主張を展開したこともあるそうです。
上院に承認されれば、同じくワクチン懐疑論者で、次期厚生(保健福祉省:HHS)長官に指名されているロバート・ケネディ・ジュニア氏とともに、米国のワクチン政策に大きな影響力を持つことになります。CDC所長は、外部の諮問委員会によるワクチン使用の可否に関する勧告に従うのが通例ですが、この勧告を拒否する権限も持つそうです。さらに、この諮問委員会のメンバーはHHS長官が任命できるといいます。
鳥インフルエンザや百日ぜき、麻疹(はしか)などさまざまな感染症に対する脅威が高まる中で、両氏がワクチンに関する主導権を握ることになります。

「電子たばこ」は血管の働きに即座に悪影響を及ぼす可能性があるそうです。米国の研究チームがイリノイ州シカゴで開かれた北米放射線学会で研究成果を発表し、米CNNが報じました。
電子たばこは液体(リキッド)を加熱させることで発生する蒸気(ベイパー)を楽しむ製品です。研究チームは、紙巻きたばこか電子たばこを吸う21~49歳の31人を対象に、たばこを吸う前後の血管の様子をMRIで調査し、たばこ類を吸わない10人のデータと比較したそうです。その結果、たばこ類を吸うたびに、下半身全体に酸素を含んだ血液を供給する大腿(だいたい)動脈の安静時の血流速度が低下することが分かったといいます。
また、血管の拡張・収縮などの血管機能は、非喫煙者や紙巻きたばこを吸う人に比べて電子たばこを吸う人の方が低下したそうです。最も血管機能を低下させるのはニコチン入りの電子たばこで、次にニコチンなしの電子たばこだったとのこと。さらに、ニコチンの有無にかかわらず、電子たばこを吸った人は酸素飽和度が低下することも明らかになったといいます。

南米で流行している発熱性疾患「オロプーシェ熱」について、母親から胎児に感染(垂直感染)した例が確認されたそうです。ブラジルの研究チームが医学誌New England Journal of Medicineに発表しました。
WHO(世界保健機関)によると、オロプーシェ熱はヌカカ(ハエ目の微小昆虫)や蚊に刺されることで「オロプーシェウイルス(OROV)」が感染して発症します。2023年12月以降、過去に感染が確認されていない地域でも患者が報告されるようになったといいます。
チームは、過去に流行が起きていない同国北東部セアラ州に住む、妊娠糖尿病の投薬治療を受けていた40歳の患者について報告しています。2024年7月24日、妊娠30週だった女性は発熱や悪寒などを訴えたそうです。27日には膣から軽い出血があり超音波検査で胎児巨人症が判明。その後、胎動が少なくなり、8月5日に子宮内で胎児が死亡していることが確認されました。
女性の血液からOROV感染が明らかになったそうです。さらに死亡した胎児の組織からはOROVのRNAが検出され、現在ブラジルで流行している株と一致したといいます。

米国のトランプ次期大統領は22日、食品医薬品局(FDA)長官にジョンズ・ホプキンス大学の外科医マーティン・マカリー氏を起用すると発表しました。上院に承認されれば、次期保健福祉省(HHS)長官に指名されたロバート・ケネディ・ジュニア氏の管轄下で、医薬品や食品、医療機器、タバコ、化粧品などの規制および監督を行うFDAを率いることになります。
米NBC Newsによると、マカリー氏はワクチン懐疑論などで批判を浴びるケネディ氏を擁護する発言をしています。マカリー氏本人も、新型コロナウイルス感染症の流行時に、ワクチンよりも自然免疫の獲得を推奨するなどし、物議をかもしました。また、「(心臓の筋肉に炎症が起こる)心筋炎は、新型コロナ感染後よりも新型コロナワクチン接種後の方が多く発生する」と、現在は誤りだと証明されている主張をしていたそうです。
トランプ氏はマカリー氏について、「食品に含まれる有害な化学物質や若者に投与されている薬剤を適切に評価し、小児慢性疾患の蔓延に対処するだろう」と述べ、「国民の信頼を失ったFDAの軌道を修正する必要性」を強調したといいます。

慢性の尿路感染症(UTI)は通常、抗菌薬(抗生物質)で治療されます。しかし、抗菌薬の多用は原因菌の薬剤耐性化を加速させてしまいます。この解決策として米国の研究チームが、UTIの原因菌を抑え込むためのバイオマテリアル(生体材料)を開発したそうです。
このバイオマテリアルは、栄養の奪い合いでUTIの原因菌に勝つことができる有益な大腸菌を放出するといいます。通常、細菌をぼうこう内に入れても、ぼうこう壁に付着できずに尿で洗い流されてしまうそうです。しかし、バイオマテリアルは水滴の500分の1ほどの大きさで、最大2週間かけて大腸菌をぼうこう内に放出するよう設計されており、ぼうこう壁に付着しなくても大腸菌が増殖できるといいます。
ペトリ皿を使ってヒトの尿で調査したところ、UTI原因菌とこの大腸菌の比率が50:50のとき、大腸菌が原因菌を打ち負かし、全体の約85%まで増加したとのことです。さらに、原因菌より大腸菌を多く加えると、大腸菌の割合が99%以上になり、原因菌がほぼ一掃されることが明らかになったといいます。
チームは今年5月、研究成果を医学誌Infection and Immunityに発表しました。

バックパッカーに人気のラオス中部の観光地バンビエンで、メタノール中毒の疑いで外国人観光客6人が相次いで死亡したそうです。複数の海外メディアが報じています。米公共ラジオNPRやAP通信によると、死亡したのはオーストラリア人2人、デンマーク人2人、英国人1人、米国人1人で、被害者の多くは19~20歳の若者です。メタノールの混入した飲み物を飲んで、中毒を起こしたとみられています。
メタノールは工業用に使われるアルコールの一種です。税金がかかるエタノール比べてコストが低いため、安価なアルコール飲料の材料として違法に使われることがあるそうです。観光客は知らないうちにこうした密造酒を口にする可能性があり、米国務省はラオスへの観光客に対し、認可を受けた酒屋やバーなどでのみ酒類を購入し、ラベルなどを調べて偽造されていないか調べるよう注意を呼びかけたといいます。
メタノールはわずか25ml摂取するだけで、適切な治療を受けないと死に至る可能性があるそうです。メタノール中毒の初期は典型的なアルコール中毒に似ていますが、12~24時間後には呼吸困難、腹痛、さらには昏睡などのより深刻な症状が現れるとのことです。

血中コレステロール値が高くなると認知症リスクが上昇するといわれています。それでは、コレステロールを多く含む卵を食べると、認知機能に悪影響を及ぼすのでしょうか。米国の研究チームが、科学誌Nutrientsに研究成果を発表しました。
チームは、55歳以上の男女890人(男性357人、女性533人)を4年間にわたり追跡したデータを分析しました。卵を食べる頻度が、全くない(男50人、女88人)▽1カ月間に1~3個(男58人、女136人)▽1週間に1個(男84人、女123人)▽1週間に2~4個(男140人、女166人)▽1週間に5個以上(男25人、女20人)――の群に分けて比較したといいます。
その結果、まず、男女ともに1週間に卵を2~4個食べる群が、血中コレステロール値が最も低いことが分かったそうです。さらに女性に関しては、卵を多く食べる人ほど認知機能を調べるテストで、スコアの低下が抑制されることが判明したといいます。こうした結果から、男女ともに卵が認知機能の維持に有益な可能性が示されました。
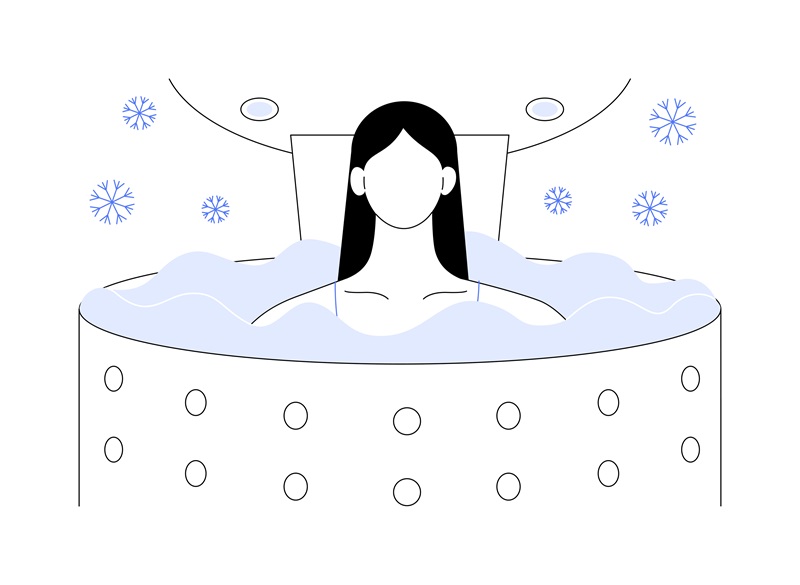
極めて低い温度の刺激を全身に受ける「クライオ刺激」は健康に有益だといわれているそうです。フランスの研究チームが、クライオ刺激が睡眠の質や気分を向上させる可能性があることを明らかにしたと、科学誌Cryobiologyに論文を発表しました。
チームは、平均年齢23歳の健康な男女20人に対し、5日間連続でマイナス90度の部屋で5分間過ごすクライオ刺激を受けてもらったそうです。その結果、徐波睡眠と呼ばれ、身体の回復や修復に効果があるとされる睡眠周期の中で最も深い睡眠が、入眠から2回の睡眠周期の間に平均7.3分増加したといいます。なお、効果を得るには5日間連続でクライオ刺激を受ける必要があったとのことです。
また、男性より女性の方がクライオ刺激の恩恵をより多く受けることも分かりました。女性はアンケートに対し、3日目と4日目の夜に睡眠の質が改善したと報告したそうです。具体的には5段階評価で平均3.4だった睡眠の評価スコアが3.9に上昇したとのことです。さらに女性は、不安の度合いを評価するスコアも改善することが分かったといいます。

米カリフォルニア州公衆衛生局(CDPH)は19日、サンフランシスコ・ベイエリアのアラメダ郡に住む子ども1人に鳥インフルエンザウイルスが感染した可能性があると発表しました。子どもは鳥インフル検査で陽性が出たため、米疾病対策センター(CDC)が確認を進めているといいます。
この子どもには軽度の上気道症状がありましたが、治療を受けて自宅で回復しているそうです。ただし、他の呼吸器感染症ウイルスの検査でも陽性が出たといい、症状が鳥インフルによるものではない可能性もあるといいます。
鳥インフルがどうして感染したのかは不明で、今のところ感染した動物との接触は確認されていないとのことです。専門家が、この子どもが野鳥と接触していないかの調査を進めているといいます。家族は全員、鳥インフル検査で陰性だったそうです。
CDCによると、今年米国では53人(19日現在)の鳥インフル感染が確認されています。1人を除く全員が、感染した家禽または乳牛に接触していたことが分かっています。

米国のトランプ次期大統領は19日、元テレビ司会者として知られるメフメト・オズ氏を公的医療保険「メディケア」や「メディケイド」などを管轄する「メディケア・メディケイド・サービスセンター(CMS)」の所長に指名すると発表しました。
米NBC Newsによると、CMSは保健福祉省(HHS)傘下の機関で、1億6千万人以上の国民に公的医療保険を提供しています。上院に承認されれば、次期HHS長官に指名されたロバート・ケネディ・ジュニア氏と連携し、米国の公衆衛生分野を担うことになります。
オズ氏は心臓外科医でもありますが、ケネディ氏と同様に健康や科学に関する誤解を招く主張を展開し、批判を浴びてきた人物です。2020年には、新型コロナウイルス感染症の治療に抗マラリア薬のヒドロキシクロロキンを推奨して批判を浴びました。
トランプ氏はオズ氏について「国家予算の4分の1を費やすCMSの無駄や不正を減らすだろう」と述べ、疾病予防を推奨するリーダーになることに期待を寄せたといいます。

世界保健機関(WHO)と米疾病対策センター(CDC)は14日、2023年の麻疹(はしか)の症例数が世界で推定1030万件となり、22年から20%以上増加したと発表しました。はしかによって約10万7500人の命が失われ、そのほとんどが幼い子どもだったそうです。
こうした症例数の増加は、特に新型コロナウイルス感染症の流行以降、世界の麻疹ワクチンの接種率が低下していることが原因だといいます。麻疹は 2回のワクチン接種で予防することができ、1回目の接種で93%、2回目の接種で97%の効果があるといわれています。
麻疹は非常に感染力が強く、流行を防ぐには2回のワクチン接種を地域の95%以上の人が受ける必要があるとのことです。しかし昨年は、1 回目の麻疹ワクチン接種を受けた子どもが世界で約83%しかおらず、2回目の接種を受けたのはわずか74 %にとどまったそうです。
なお、米CNNによると、米国における麻疹ワクチンの接種率が下がっており、23年度の幼稚園児の接種率は92.7%だったそうです。

米国のトランプ次期大統領が厚生(保健福祉省:HHS)長官に指名したロバート・ケネディ・ジュニア氏はワクチン懐疑論者として知られています。米ABC Newsがケネディ氏の考え方やそれに対する専門家の反応について報じました。
ケネディ氏は自身のことを「反ワクチンだったことは一度もない」と述べているそうですが、「ワクチンに対するより詳しい調査が必要である」との主張を続けてきたことは周知の事実です。過去には、麻疹・おたふくかぜ・風疹(MMR)ワクチンが自閉症を引き起こす可能性があるとする根拠のない論文に基づく主張を展開。新型コロナウイルスワクチンについても「これまでに作られた中で最も致命的なワクチン」と発言したそうです。
さらに、国立アレルギー感染症研究所長を務めたアンソニー・ファウチ氏やビル&メリンダ・ゲイツ財団がワクチンで利益を得ようとしているなどの誤情報を拡散したこともあるといいます。
専門家は、ケネディ氏のこうした姿勢に子どもを持つ親が影響を受けて、ワクチン接種をためらう可能性を懸念しています。

ナッツには抗炎症作用と抗酸化作用のある栄養素が豊富に含まれ、脳の健康に良いといわれています。スペインの研究チームが、毎日ひとつかみのナッツを食べると認知症リスクを下げられる可能性があると、科学誌GeroScienceに論文を発表しました。
チームは認知症のない成人5万386人(平均年齢56.5歳)のデータを基に7.1年間の追跡調査を実施したそうです。このうち 422人(2.8%)が、後に何らかの原因で認知症を発症したといいます。調査の結果、毎日ナッツを食べる人は、ナッツを食べない人に比べて、全原因認知症(アルツハイマー病や血管性認知症、前頭側頭認知症など)の発症リスクが12%低いことが明らかになったそうです。
ナッツの摂取量は「1日ひとつかみ(30g)まで」で無塩のものが認知症予防に最も効果的である可能性が示されたといいます。なお、ナッツは皮なしでも問題なく、乾燥タイプでもローストタイプでも結果に影響はなかったとのことです。

犬と飼い主の間に作られる愛着には、心拍の間隔の変化である「心拍変動」の同調が関連している可能性があるそうです。フィンランドの研究チームが科学誌Scientific Reportsに論文を発表しました。
心拍変動は自律神経系の状態を反映しており、変動が高いとリラックスした状態、低いとストレスを受けているなどの緊張状態を示します。チームは、犬と飼い主のペア30組を対象に調査を実施。犬は牧羊犬や狩猟犬など人間と協力することができる種類だったといいます。調査の結果、自由な休憩時間を過ごしている間に、飼い主の心拍変動の高まりが犬の心拍変動の高まりにつながることが分かったそうです。
これは、飼い主がリラックスしている時に、犬もリラックスした状態になることを示しています。遊びなどのタスクを実行している時ではなく、休息時に心拍変動の同調が確認されたことで、精神的な状態の同調を反映している可能性が示されました。

腸内細菌叢(腸内フローラ)は、自己免疫疾患の一種である「関節リウマチ(RA)」の進行に影響を与えるそうです。英国の研究チームが、医学誌Annals of the Rheumatic Diseasesに論文を発表しました。
チームは、RAリスクに関連する抗体(抗CCP抗体)が陽性で、関節や骨やじん帯など(筋骨格系)に症状を訴えているけれども関節内の滑膜に炎症を伴わない患者124人の腸内細菌叢を分析したそうです。
その結果、RAに進行した参加者30人とRAに進行しなかった人の間で、プレボテラ属の細菌の豊富さに有意差が認められたそうです。個人が持つRAの危険因子やRAに進行するまでの時間に応じて、プレボテラ属の特定の菌が多くなったり、少なくなったりしたといいます。さらに、参加者19人を15カ月にわたり追跡したところ、RAに進行した5人は発症の約10カ月前から腸内細菌叢が不安定になることが明らかになりました。
チームは、腸内細菌叢の変動の理解がRAの発症予測や診断、治療につながるとしています。また、高リスクの人の腸内細菌叢をターゲットにした予防が可能になるかもしれないと主張しています。

トランプ次期米大統領は、反ワクチン活動などで知られるロバート・ケネディ・ジュニア氏を厚生(HHS:保健福祉省)長官に指名しました。AP通信がその影響について報じています。
HHSは食品医薬品局(FDA)や疾病対策センター(CDC)、国立衛生研究所(NIH)などを所管し、莫大な予算(1兆7千億ドル)を抱える世界最大の公衆衛生機関です。ケネディ氏が厚生長官に承認されれば、これらが彼の監督下に置かれることになります。
ケネディ氏はFDAの腐敗を指摘し、食品栄養などの部門全体を一掃する可能性を示唆。また長年にわたり、FDAのワクチンに関する取り組みについても非難しています。さらに、CDCが市民の虫歯予防のために推奨する水道水中のフッ化物濃度に関するガイドラインを、健康に害があるとして無効にする考えも明らかにしています。
NIHについても、職員600人を解雇する可能性に言及。金銭的な利益相反を持つ研究者に対する資金提供を阻止し、NIHの予算の半分を食事療法などの「健康に対する予防的かつ総合的なアプローチ」の研究に充てる考えを持っているそうです。
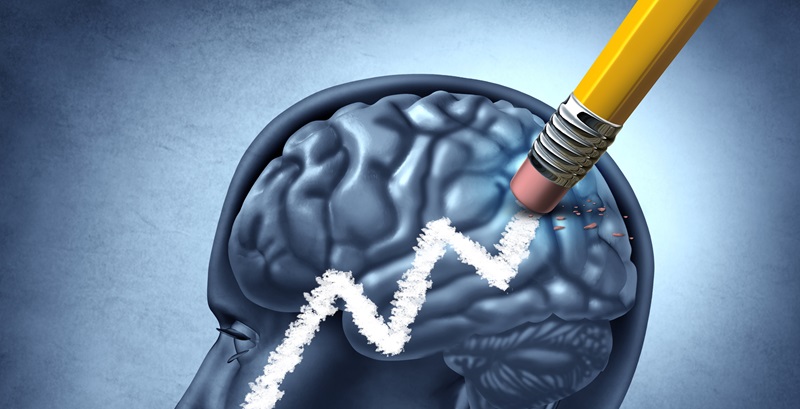
脳内に鉄が過剰に蓄積することが、アルツハイマー病(AD)の病態に深く関わっていると考えられています。オーストラリアなどの研究チームが、鉄を脳内から除去する鉄キレート剤「デフェリプロン」を使い、AD患者の神経変性を遅らせることができるかどうかを調査しました。
チームは、ADに関連するタンパク質・アミロイドβの蓄積がある軽度認知障害患者、または初期AD患者の計81人を対象に治験(第2相試験)を実施したそうです。その結果、1日2回デフェリプロン(15mg/kg)を12カ月服用した群は、プラセボ群に比べて認知機能の低下が進行することが分かったといいます。
MRI画像からはデフェリプロンが、記憶に関わる脳の領域「海馬」に蓄積した鉄の量を減らすことが示されたそうです。しかし予想に反して、鉄の減少によって海馬の萎縮が止まることはなく、代わりに前頭葉の萎縮が進んだといいます。さらに、デフェリプロン群は免疫細胞の好中球が以上に減ってしまう好中球減少症が起きる頻度が高く、安全性にも懸念が生じる結果になったとのことです。
チームは研究成果を医学誌JAMA Neurologyに発表しました。

大手ハンバーガーチェーンのマクドナルドが販売したハンバーガー「クォーターパウンダー」に関連する集団食中毒が発生した問題で、患者数が104人に増加したそうです。米食品医薬品局(FDA)が13日に発表しました。
患者は14州から報告されています。これまでに34人が入院し、コロラド州の高齢者1人が死亡、4人が重篤な腎障害を発症しました。クォーターパウンダーに使われていたスライスタマネギが食中毒の原因とみられています。このタマネギはカリフォルニア州の食品メーカーTaylor Farmsが供給したもので、同社は10月22日にタマネギの自主回収に踏み切りました。
これまでのところ、回収したタマネギのサンプルの一つから大腸菌の陽性反応は出たものの、今回の集団感染の原因となった菌株とは一致しなかったそうです。FDAなどが回収したタマネギの検査を引き続き進めているそうです。
米NBC Newsによると、保健当局は「食品安全上の懸念は払拭されたように思われる」としているといい、マクドナルドは別業者のタマネギを使ってクォーターパウンダーの販売を再開したとのことです。

角膜移植におけるドナー不足や拒絶反応などの問題を解消する新たな治療法が実現するかもしれません。大阪大学の研究チームが、ヒト人工多能性幹細胞(iPS細胞)由来の「角膜上皮細胞シート」を患者に移植する手術を世界で初めて実施し、医学誌Lancetに発表しました。この成果について科学誌Natureがニュースで取り上げています。
角膜は光を屈折させて集める重要な役割を持ちます。チームは、角膜上皮の幹細胞の消失によって角膜が結膜に覆われてしまう角膜上皮幹細胞疲弊症(LSCD)で、角膜混濁のために視力障害がある患者4人にこのシートを移植したといいます。
その結果、移植後すぐに全員の視力が回復し、3人はその状態が1年以上続いたそうです。2年間の経過観察期間で、腫瘍形成などの重篤な有害事象を経験した患者はいなかったとのこと。また、4人のうち2人は免疫抑制剤を使用しなかったにもかかわらず、免疫系による攻撃の兆候は見られなかったそうです。
チームは、3月にも治療法の有効性を評価する臨床試験を開始する予定とのことです。

英国で、イングランドとウェールズの終末期患者に対して「ほう助死(Assisted Dying)」(自殺ほう助)の権利を認める法案が提出されたそうです。英公共放送BBCによると、11月29日に国会議員による1回目の採決が行われる見通しとのことです。
一般的にほう助死とは、医師から処方された致死薬を終末期患者が自らに投与する行為を指します。ほう助死の対象となるのは、かかりつけ医(GP)に1年以上登録をしていて、イングランドかウェールズに住んでいる余命6カ月以内の18歳以上の成人です。
意思決定能力のある患者がほう助死を望む意思を明確に示す必要があり、証人の署名が付いた2通の宣言書の作成が求められます。そして、2人の医師からほう助死に適格であることを認めてもらわなければなりません。裁判官による医師への聴取が行われ、最終的な決定が下されるといいます。
誰かにほう助死を選ぶよう圧力をかけたり、強制したりした場合、懲役14年に処される可能性があるそうです。なお、スコットランドでも同様の法案が審議されているとのことです。

「記憶」は脳に特有の機能だと思っていませんか。米国の研究チームが、他の細胞も記憶機能を持つことを発見したと、科学誌Nature Communicationsに論文を発表しました。
脳細胞が新しい情報を学習する際、あるパターンの神経伝達物質を受け取るといいます。そして、記憶形成の際に活性化する遺伝子があるそうです。チームは神経組織と腎組織から採取した細胞(非脳細胞)に、そのパターンに似た化学信号を伝え、記憶形成の際に活性化する遺伝子の反応を観察したといいます。その結果、非脳細胞の記憶に関する遺伝子が、科学信号に反応して活性化することが分かったそうです。
なお、脳が情報を記憶するには、短時間で集中して学ぶ「集中学習」よりも間隔を空けて繰り返し学ぶ「分散学習」が効果的です。脳細胞以外の細胞も、間隔を空けて信号を伝達したほうが、記憶関連遺伝子が長時間にわたって強力に活性化することが明らかになったとのことです。
チームは、体の細胞は脳細胞と同じように扱うべきであり、病気の治療なども、「記憶がある」ことを前提として行う必要があることが示されたとしています。
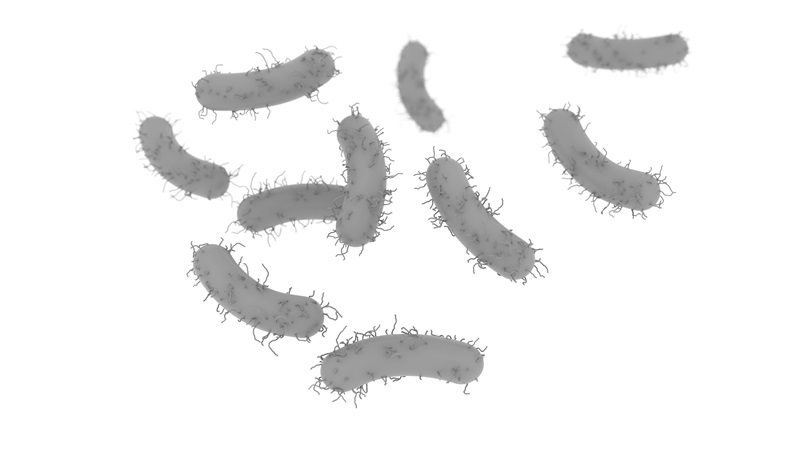
大腸がんのリスクを高める腸内細菌が存在するそうです。ベルギーの研究チームが、これまで謎に包まれていた、ある種の大腸菌ががんを進行させるメカニズムを明らかにしたと、科学誌Natureに論文を発表しました。
これまでの研究で、「pks陽性大腸菌」と呼ばれる腸内細菌が、DNAに結合して損傷を与えるコリバクチンという遺伝毒性物質を産生することでがんのリスクを高めることが分かっています。しかし、この大腸菌がどのようにして腸壁にくっつくのかは不明でした。
チームがマウスで調査を行い、pks陽性大腸菌がFimHやFmlHと呼ばれる分子を使って、腸壁の表面にある腸管上皮細胞に付着することを発見したそうです。この分子は、細菌表面の細長いタンパク質の繊維「線毛」の先端に存在するといいます。付着した大腸菌がコリバクチンを産生することで、DNAが損傷される可能性があるそうです。
なお、FimHの働きを阻害する薬を使ってpks陽性大腸菌が腸管上皮細胞へ付着するのを防いだところ、DNA損傷や腫瘍の成長が大幅に抑制されたといいます。チームは大腸がんの発生と進行を防ぐ有望な治療法の開発につながるとしています。

米国脳卒中協会(ASA)が、10年ぶりに脳卒中予防に関する新たなガイドラインを公表しました。新ガイドラインには、健康的な食生活を送ることで、高コレステロールや高血糖、肥満といった脳卒中のリスクを高める危険因子を抑制できることが明記されています。
具体的には、果物や野菜、全粒穀物、オリーブオイルなどを中心に取る地中海式食事法が有効だといいます。ハムやソーセージ、菓子パン、清涼飲料などの超加工食品や糖分の多い飲食物を控えることも重要だとしています。また、脳卒中の予防には定期的な運動も大切で、1日10分散歩をするだけでも脳卒中リスクが大幅に低下するそうです。
そして、肥満や糖尿病の人に対して、オゼンピックやウゴービなどといった薬の処方を検討することを医師に推奨しています。
なお、毎年50万人以上の米国人が脳卒中を発症するそうですが、このうち最大80%は予防できる可能性があるとのことです。

カナダ西部のブリティッシュコロンビア州で、10代の若者に鳥インフルエンザウイルスH5N1型が感染したことが分かったそうです。同州の保健当局が9日に発表しました。カナダ国内でH5N1型が感染したヒトが見つかるのは初めてとのことです。
この若者は野鳥か動物との接触によってH5N1が感染した可能性が高いとみられており、詳しい感染経路の特定が進められています。患者の症状は明らかにされていませんが、病院で治療を受けているそうです。
同州では、野鳥や家禽、スカンクやキツネなどの小型の野生動物からH5N1が検出されているといいます。今年10月初め以降、少なくとも22カ所の家禽飼育施設でH5N1の感染が確認されているとのことです。
米国では、H5N1型が感染した乳牛からヒトへの感染例が確認されています。ただ、カナダでは今のところ乳牛や牛乳のサンプルから鳥インフルが検出されたことはないそうです。

オーストラリアで百日ぜきの患者が急増しているそうです。オーストラリアの公共放送ABCによると、今年の百日せきの患者数は11月6日までに4万1013人に達し、30年以上前に統計が開始されて以来、初めて4万人を超えたといいます。
百日ぜきは5年ごとに患者が急増することで知られていますが、医師や感染症の専門家は今年の大流行は予想していなかったとのことです。専門家は百日ぜきワクチンの接種率低下に懸念を示しているそうです。特に、追加接種を受ける人の割合が驚くほど低く、2023年は13歳になる子どもの4人に1人が追加接種を受けていないといいます。
百日ぜきは、乳児にとっては致命的になり得る呼吸器感染症です。感染後1〜2週間は症状が現れないことが多いため、感染が広がりやすいそうです。百日咳ワクチンの効果は5年を過ぎると薄れるので、乳幼児期に接種後、学童期に追加接種を受けることが有効だといいます。
なお百日ぜきは米国でも流行が拡大しています。

米疾病対策センター(CDC)は8日付で、鳥インフルエンザウイルス(H5N1型)についての新たな指針を発表しました。感染動物に接触した農場労働者に対し、症状がなくても鳥インフル感染の検査や治療を受けることを推奨しています。
新たな指針は、ミシガン州とコロラド州の酪農従事者115人を対象に6~8月に行われた血液検査の結果に基づくものです。115人は感染が確認された乳牛に接触しており、このうち8人(7%)からH5N1の感染歴を示す抗体が検出されたそうです。
8人は全員、マスクなど呼吸器を保護する個人防護具(PPE)を着けずに酪農場の搾乳室で清掃作業を行っており、感染対策用の眼鏡をかけていたのも3人だけでした。また、4人が無症状だったことも分かっているそうです。
AP通信は今回の指針発表を受け、「動物や人間への感染が増えるごとにウイルスが危険な変異をするリスクが高まる。政府の対応は遅すぎる」というウイルスの専門家の意見を紹介しています。

健康な人の便から採取した腸内細菌叢(腸内フローラ)を患者に移植する「便移植」には、善玉菌のバランスを回復させるだけでなく、腸管壁の修復を促進する効果もあることが分かったそうです。
米食品医薬品局(FDA)は2022年、「再発性クロストリジオイデス・ディフィシル感染症(CDI)」の治療法として、「ふん便微生物叢移植(FMT)」を承認しています。
米国の研究チームが、健康なドナー30人とFMTを受けた患者22人から採取した便を分析。男性ドナーの便を移植された女性患者の33%で、移植から数カ月経過後も男性という性を決める「Y染色体」が大幅に増加していることが確認されました。
このY染色体は、ドナーの便に含まれていた「腸管上皮細胞」に由来すると考えられます。栄養や水分の吸収、異物の侵入を防ぐバリアなどさまざまな役割を担う腸管上皮細胞も、FMTによって患者の腸に根付く可能性が示されました。
チームは研究成果を医学誌Gastro Hep Advancesに発表しました。

オーストラリアのアンソニー・アルバニージー首相は、16歳未満の子どもによるソーシャルメディアの利用を禁じる法案を、今週中にも議会に提出する方針を示しているそうです。英BBCによると、ソーシャルメディアが子どもたちのメンタルヘルスに与える悪影響を軽減することが目的だといいます。
詳細についてはまだ議論されていませんが、すでにソーシャルメディアを利用している子どもも対象で、保護者の同意があっても年齢制限に例外は認めない方針とのことです。アルバニージー首相は、ソーシャルメディアのプラットフォーム側に子どもたちのアクセスを防ぐための合理的な措置を講じていることを示す責任があると述べ、利用者への罰則は設けないそうです。
多くの専門家が、ソーシャルメディアのメンタルヘルスへの悪影響については認めていますが、法律で利用を禁止することの有効性については意見が分かれているといいます。法案が成立した場合は1年後に施行される見込みとのことです。

睡眠不足は精神の健康に悪影響を与えることが知られています。では睡眠時間が増えると、精神面に良い影響が出るのでしょうか。米国の研究チームが、若年成人90人を対象に実施した調査の結果を学術誌Journal of Positive Psychologyに発表しました。
チームは参加者を「遅寝」「早寝」「通常」の三つのグループに分け、1週間にわたって調査を実施したといいます。その結果、いつもより一晩に46分多く寝た人は、困難に直面した時に回復する力、感謝の気持ち、持続的な幸福感が高まったそうです。一方で、睡眠時間が37分少なくなると、こうした精神的な幸福度が下がることが明らかになったといいます。
また、睡眠時間が増えると、個人的な幸福度が高まるだけでなく、社会に恩恵をもたらす行動が増えることも分かったそうです。平均年齢55歳の成人2837人を対象とした別の調査(医学誌Sleep Medicine掲載の論文)では、1日に7~9時間の良い睡眠を取っている人は、寄付に協力する可能性が7~45%高いことが示されたとのことです。

忙しくて時間がない人は、週末だけでも運動をすると脳の健康を維持できるそうです。コロンビアなどの研究チームが、メキシコの首都メキシコシティに住む平均年齢51歳の成人1万33人を16年にわたって追跡して研究し、その成果を医学誌British Journal of Sports Medicineに発表しました。
チームは参加者を、週1~2回(30分以上)運動する人の群▽週3回以上運動する人の群▽週1~2回運動する人と週3回以上運動する人を混ぜた群▽全く運動をしない人の群――の4群に分けて調査。その結果、週1~2回運動する群は全く運動しない群に比べて、軽度認知症を発症するリスクが13%低いことが分かったといいます。また、週3回以上運動をする人、週1~2回運動する人と週3回以上運動する人を混ぜた群は、全く運動をしない群と比べてリスクが12%低かったといいます。
このことから、軽度認知症の発症抑制には、週1~2回の運動で十分である可能性が示されました。なお、男女間で結果に違いは生じなかったとのことです。
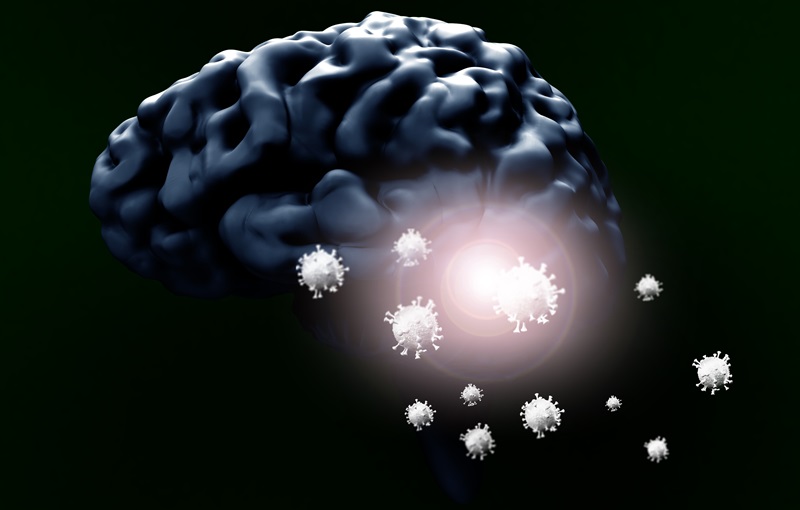
口唇ヘルペスを引き起こすことで知られる単純ヘルペスウイルス1型(HSV-1)は、脳と脊髄からなる中枢神経に侵入することが分かっています。米国とフランスの研究チームが、HSV-1の脳での広がり方を初めて明らかにしたと、科学誌Journal of Virologyに発表しました。
チームがマウスで調査したところ、HSV-1は三叉神経や嗅神経から中枢神経系に侵入した後、生命時に関わる脳幹、内分泌や自律機能をつかさどる視床下部といった重要な領域のいくつかに定着することを発見したそうです。一方で、記憶をつかさどる海馬、思考などの高度な認知機能をつかさどる大脳皮質などの領域はHSV-1の影響を受けなかったといいます。
チームは、HSV-1感染に応答して炎症を引き起こすミクログリア(中枢神経系の免疫細胞)の活動も調査。一部の領域では、ウイルスが消滅した後もミクログリアが活性化しており、炎症が継続していることが示されました。慢性的な炎症はアルツハイマー病やパーキンソン病などの神経変性疾患の引き金になる可能性があるとのことです。

5日投開票の米大統領選に勝利したドナルド・トランプ氏は、「(大統領に返り咲いたら)一部の(小児用)ワクチンを法的に禁止するかどうかを決断する」と明言しているそうです。これに対し多くの小児科医が、米国で何十年もの間発生していない感染症の致命的な大流行につながる恐れがあるとして懸念を示しているといいます。
米NBC Newsによると、トランプ氏の発言は、根拠のない反ワクチン論を唱えることで知られるロバート・ケネディ・ジュニア氏の助言に基づくものだそうです。ケネディ氏は今回の大統領選に無所属で出馬し、トランプ氏支持に転じて選挙活動を中止しました。トランプ氏は選挙前、自身が当選した場合はケネディ氏を「健康問題に取り組むために」公衆衛生分野の要職に起用する可能性を示唆していたといいます。
なお、大統領はワクチンを禁止する権限は持ちませんが、連邦機関の重要な役職の指名権を通じて影響力を行使することがでるとのことです。こうした動きによって、子どもにワクチンを接種させない親が増えることが懸念されています。

胎児期や乳幼児期に砂糖を制限すると、中年期の2型糖尿病や高血圧のリスクが低下する可能性があるそうです。米国などの研究チームが科学誌Scienceに研究成果を発表しました。極端な制限をしなくてもリスクは抑えられるようです。
チームは、第二次世界大戦中に英国の配給プログラムの一環で行われた「砂糖の制限」の影響を受けた子どもと受けなかった子どものデータを比較したそうです。英国では、1942年に砂糖の流通制限が始まり、配給制は53年9月まで続いたといいます。
受胎後1000日間にわたり砂糖の制限を受けた子どもは、約50年後に2型糖尿病を発症するリスクが35%、高血圧を発症するリスクが20%、それぞれ低くなることが明らかになったとのことです。こうしたリスクの抑制には、胎児期に母親が砂糖を制限するだけでも十分だったそうです。
なお、1日の平均砂糖摂取量は配給制下で40g、配給制廃止後で80gでした。WHO(世界保健機関)などがガイドラインで定める成人の添加糖類推奨量は1日50gまでです。

30分間の有酸素運動をたった1回行うだけで、2型糖尿病の予防に重要な糖代謝とインスリン感受性が改善するそうです。イタリアの研究チームが医学誌Journal of Endocrinological Investigationに研究成果を発表しました。
チームは、競技スポーツの経験がなく糖尿病ではない20~35歳の健康な32人を対象に調査を実施。参加者に30分間の軽いジョギングをしてもらい、その「1週間前」と「24時間後」にブドウ糖を含んだ液体を飲んで血糖値の変動を見る「経口ブドウ糖負荷試験」を実施したそうです。
その結果、運動後は、空腹時の血糖値の平均が82.8mg/dLから78.5mg/dLに、ブドウ糖を取った1時間後の血糖値の平均は122.8mg/dLから111.8mg/dLにそれぞれ低下したといいます。
ブドウ糖を取った1時間後のインスリン値の平均についても、57.4µUI/mlから43.5µUI/mlに下がったとのことです。さらに、インスリン感受性の指標(Matsuda indexとQUICKI index)やインスリン抵抗性の指標(HOMA-IR index)も改善したそうです。

座りっぱなしによる健康リスクを軽減できるとして近年人気が高まっている「スタンディングデスク」は、本当に体に良いのでしょうか。オーストラリアの研究チームが、長時間立ちっぱなしでいることは心臓病や脳卒中のリスク減少につながらないことを確認したと、医学誌International Journal of Epidemiologyに発表しました。
チームは平均61歳の成人8万3千人以上を対象に調査を実施しました。参加者は数年にわたり、立ったり座ったりといった身体活動を記録する装置をつけて生活したそうです。こうして得られたデータを分析したところ、1日10時間以上座っていることが心臓病や脳卒中のリスク上昇に関連することが分かったといいます。
一方で、立っている時間を増やすだけでは、それらのリスクは低下しないことも分かりました。実際、立っている時間が長いと脚に血が溜まり、静脈瘤などの循環器系疾患のリスクが高まるそうです。健康のためには、短いウォーキングやストレッチなどの軽い運動を取り入れることが有効だといいます。
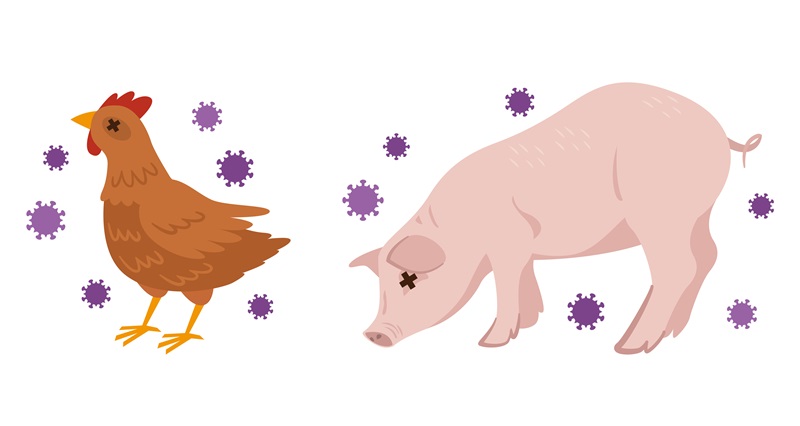
米農務省は10月30日、オレゴン州の家庭農場で飼われていたブタ1匹が、鳥インフルエンザ(H5N1型)の検査で陽性だったと発表しました。米国内でブタへのH5N1型の感染が確認されたのは初めてです。
この農場では家禽や数種類の家畜が飼育されていました。家禽の鳥インフル感染が確認されたことから、水場などの設備を共有していたブタ5匹を安楽死させ検査を行ったところ、1匹の陽性と2匹の陰性が確認されました。残り2匹の結果はまだ出ていないそうです。
米CNNによると、2009年に大流行したH1N1型はブタの中で変異が起き、それがヒトに感染したことが引き金になったと考えられています。そのため、H5N1型がブタに広がることには警戒感が高まっていました。
ただし、ブタはH5N1型感染に対して高い耐性を持つとの研究結果も報告されています。今回のブタについても鼻腔ぬぐい液でウイルスが検出されただけの場合、いわゆる「感染」ではなく単なる鼻腔内のウイルス汚染にとどまる可能性も指摘されています。

猫と暮らすことは、人間の健康にどのような影響を及ぼすのでしょうか。The Conversationにオーストラリアの動物福祉・行動・倫理学の専門家の記事が掲載されています。
猫を飼っている人は、脳卒中や心臓病などといった心血管疾患で死亡するリスクが低いことが複数の研究で示されているといいます。また、社会的孤立が抑制され、精神的な幸福度が高まるとのことです。うつ病患者が飼い猫と触れ合うと、症状が軽減するとの調査結果もあるそうです。
一方、健康上のリスクも存在します。猫はトキソプラズマ原虫の終宿主(成体が寄生する最後の宿主)として知られており、ふんを介してヒトに感染することがあります。妊婦が感染すると流産や死産につながったり、生まれた子どもに失明や脳障害が生じたりする可能性があるそうです。
また、猫アレルギーを持つ人は5人に1人ほどの割合でいるといわれており、その数は増加傾向にあるとのことです。ただし、アレルギーが重度でない限り、衛生面に配慮すれば猫と暮らすことは可能だそうです。

中国の研究チームが、心停止後の虚血による脳損傷の回復に、肝臓の機能が重要な役割を果たすことを突き止めたと、医学誌EMBO Molecular Medicineに発表しました。
チームは、ミニブタ17匹を「脳を30分間虚血(血流を低下)させる群」「脳と肝臓を30分間虚血させる群」「虚血なしの対照群」の三つに分けて調査したそうです。ブタを安楽死させて脳を調べたところ、対象群の次に脳損傷が少なかったのは「脳のみ虚血」の群で、脳と肝臓を虚血させたブタは損傷が多いことが分かったといいます。
次にチームは、取り出した脳を、酵素や栄養分を循環させて臓器を保護する装置(NMP)につなぎ、虚血後の脳活動の回復について観察したそうです。
その結果、NMPだけにつないだ脳は脳の電気活動が現れるものの、時間の経過とともに低下したそうです。しかし、NMP回路に正常に機能している肝臓を組み込むと、虚血から50分後に脳の電気活動が回復し、その状態が6時間継続したといいます。チームは、心停止後の生存率や転帰を改善するヒントがあるとしています。