非公開の医師求人情報を
ご紹介いたします!
マイナビDOCTORでは、医師専任のキャリアパートナーが
あなたの転職活動をサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。
世界の医療ニュースの中から、厳選した記事をギュッと凝縮して紹介します。
1日数本を1分で、サクッと読むことができます。日々の情報収集、話のネタ探しにお役立てください。

胎児期や乳幼児期に抗菌薬に暴露すると、インフルエンザなどの呼吸器感染症に対する肺の免疫機能が生涯にわたり脆弱(ぜいじゃく)になる可能性があるそうです。米国の研究チームが科学誌Cellに論文を発表しました。
チームは、妊婦や新生児に広く使用される抗菌薬(アンピシリン、ゲンタマイシン、バンコマイシン)を投与したマウスと、自然な腸内細菌叢を維持したマウスを比較しました。
その結果、抗菌薬に暴露されたマウスでは、肺を感染から守る「CD8陽性T細胞」と呼ばれる免疫細胞の数が有意に減少し、再感染を防ぐ「メモリー(記憶)T細胞」の形成も阻害されることが分かりました。この免疫不全は、成体になっても持続し、長期的な免疫記憶の形成に影響を与えることが確認されています。
この免疫機能の低下は、腸内細菌が産生する代謝物「イノシン」の量が抗菌薬によって減少することが原因だそうです。イノシンは腸から免疫細胞に届き、成熟や機能獲得を促す重要な「分子メッセンジャー」として働くといいます。
さらに、ヒトの乳児の肺組織を用いた実験でも、抗菌薬に暴露させると、メモリーT細胞の数が少なくなり、遺伝子発現パターンが高齢者に似ていることが確認されました。
一方で、抗菌薬に暴露されたマウスにイノシンを補給すると、免疫系の異常が改善されることも判明。チームは、抗菌薬によって引き起こされる免疫不全に対し、イノシンなどの代謝物の補充療法が有効な手段となる可能性があるとしています。

近年、小児用ワクチンに含まれるアルミニウムの健康リスクについて、懸念の声が一部で広がっています。こうした中、デンマークの研究チームが約120万人の子ども対象にした大規模調査を行い、アルミニウムと慢性疾患との関連は認められなかったとする結果を、医学誌Annals of Internal Medicineに発表しました。
ワクチンの中には、効果を高めるための成分(アジュバント)としてアルミニウム塩を添加したものがあります。ジフテリア、百日ぜき、破傷風、ヒトパピローマウイルス(HPV)、肺炎球菌、B型肝炎などのワクチンに使用されています。
チームは、1997~2018年にデンマークで生まれた約120万人の子どもを対象に、2020年末まで追跡した健康記録を分析。政府機関が厳格に管理するデータを基に、2歳までにワクチンに含まれるアルミニウムに多く暴露した子どもと、そうでない子どもを比較しました。なお、今回の研究にはワクチン未接種の子どもは含まれていません。
分析対象は、36種類の自己免疫疾患、ぜんそくを含む9種類のアレルギー疾患、自閉症や注意欠如多動性障害(ADHD)など5種類の神経発達症を含む、計50種類の慢性疾患です。その結果、ワクチンに含まれるアルミニウムとの関連性は認められませんでした。
チームは「アルミニウムは土壌や水、空気中など自然界に広く存在し、食品にも含まれている。ワクチンに含まれるアルミニウムはごく少量であることを理解すべきだ」と指摘しています。

食べ物や飲料に一般的に使用されている甘味料が、思春期の始まりを早めてしまう可能性があることを、台湾の研究チームが明らかにしたそうです。米国内分泌学会が、研究内容を発表しました。
チームが、台湾に住む10代の男女1407人のデータを調べたところ、481人が「中枢性思春期早発症」であることが判明しました。日本小児内分泌学会によると、思春期は通常、女子は10歳ごろ、男子は12歳ごろに始まるとされます。しかし、脳の下垂体や視床下部が早い時期に活動し、卵巣や精巣に指令を出すことで、思春期の体の変化が進んでしまうことがあります。これが中枢性思春期早発症です。
分析の結果、人工甘味料のアスパルテームとスクラロース、天然の甘味成分のグリチルリチン、添加糖類の摂取が、中枢性思春期早発症のリスクを高めることが分かりました。特に遺伝的に思春期早発症の素因を持つ子どもで、この関連性が顕著でした。
また、甘味料の摂取量が増えるほど、リスクも高まることが明らかになりました。性別による違いも見られ、男子はスクラロースの摂取が、女子はグリチルリチン、スクラロース、添加糖類の摂取がそれぞれリスク上昇と関連していました。
チームは、米カリフォルニア州サンフランシスコで7月12~15日に開かれた米国内分泌学会議(ENDO 2025)で、この研究成果を発表しました。

初潮を迎えた年齢が、その後の長期的な健康リスクを知る手がかりになる可能性がある――。ブラジルの研究チームが、米カリフォルニア州サンフランシスコで7月12~15日に開かれた米国内分泌学会議(ENDO 2025)で、こうした研究成果を発表しました。
チームは、ブラジル国内に住む35~74歳の女性7623人のデータを、初潮年齢に応じて「早発(10歳未満)」「標準(10~15歳)」「遅発(15歳超)」の3群に分けて分析しました。
その結果、早発の女性は、肥満、高血圧、糖尿病、心疾患、妊娠高血圧腎症などの疾患を発症する可能性が高いことが分かりました。一方で遅発の女性は、肥満のリスクは低かったものの、月経不順や特定の心臓疾患のリスクが高かったといいます。
チームは、初潮の年齢と健康リスクの関連を理解することで、女性自身と医師が特定の疾患のスクリーニングや予防に積極的に取り組めるようになるとしています。
なお、これまでの同様の調査は高所得国を対象としたものが中心で、今回の研究は発展途上国で実施されたものとしては最大規模だといいます。

オーストラリアの研究チームが、ヒトに感染すると致死率が極めて高い「ニパウイルス」や「ヘンドラウイルス」に対する抗体治療法を開発し、初期の実験で有望な結果を示したと、科学誌Nature Structural & Molecular Biologyに論文を発表しました。
これらのウイルスはコウモリを自然宿主とし、動物を介してヒトに感染します。ワクチンや治療法は存在しません。
チームは、アルパカの免疫細胞から分離した「DS90」と呼ばれる「ナノボディ(小型抗体)」が、ニパウイルスとヘンドラウイルスに対して有効であることを特定しました。
ナノボディは通常の抗体の10分の1の大きさで、ウイルスの奥深くまで到達して感染を防ぐことが可能だといいます。
チームは、DS90が二つのウイルスの細胞侵入を妨げることを確認しました。さらに、開発中の抗体薬「m102.4」とDS90を組み合わせることで、ウイルスの変異を抑えることにも成功しました。
今後は、アジアでのニパウイルスの流行やオーストラリアでのヘンドラウイルスの流行に備えて、DS90を治療薬として実用化することを目指しているとのことです。

運動を継続し、効果を得るためには、その運動を楽しめるかどうかがカギになります。イギリスの研究チームが、個人の性格が、「楽しさ」を感じる運動の種類に影響を与えることを明らかにしたと、科学誌Frontiers in Psychologyに論文を発表しました。
チームは、一般の参加者132人を対象に、サイクリングと筋力トレーニングを組み合わせた8週間の運動プログラムを行う群と、特別な運動をしない群に分けて調査を実施。運動の楽しさやストレスのレベル、性格の特性との関係について調査しました。
性格は、外向性、協調性、誠実性、神経症傾向、開放性の五つの特性で評価されました。
分析の結果、外向性が高い人は高強度の運動を好み、神経症傾向が強い人は、継続的な努力を必要とする運動や、心拍数の記録など他者の干渉を伴う活動を避ける傾向があることが分かりました。また、誠実性が高い人は全般的に体力に自信があり、身体活動量が多かったものの、運動を楽しむというよりは、健康に良いからという理由でプログラムを忠実に遂行していたといいます。
さらに、神経症傾向が強い人については、運動によってストレスレベルが有意に低下し、精神的健康にも良い影響があることが確認されました。
チームは、性格に合わせた運動を選択することで、より長く継続できる運動習慣が形成される可能性があるとしています。

ChatGPTなど、言語処理に特化した生成AIが、研究論文の執筆に広く活用されている可能性があるそうです。ドイツなどの研究チームが、生成AIの登場以降、生物医学分野の論文に使われる語彙が劇的に変化したことを明らかにしたと、科学誌Science Advancesに研究成果を発表しました。
大量のテキストデータを学習し、自然な文章を作成する生成AIは「大規模言語モデル(LLM)」と呼ばれます。チームは、2010~24年に発表された英語の生物医学論文の抄録1510万件を対象に、使用された語彙の変化を分析しました。
その結果、LLMの登場以降、「delves(徹底的に調べる)」「showcasing(展示)」「underscores(強調する)」「potential(潜在的な)」「findings(調査結果)」「critical(重大な)」など特定の語彙の使用頻度が急増していることが分かったそうです。これらは生成AIが作る文章に特徴的なスタイルだといいます。
こうした傾向を踏まえ、24年に発表された抄録を分析したところ、約13.5%がLLMによって処理された可能性があることが明らかになりました。
また、生物医学分野の論文に使用される語彙の変化は、新型コロナウイルス感染症の流行時にも見られ、「respiratory(呼吸器の)」などの語が激増したことが知られています。しかし、今回の研究で、LLMによる影響が新型コロナによる語彙変化を上回ることが確認されました。

左利きの人は創造的――。そんな説を耳にすることがありますが、果たして本当なのでしょうか。米国の研究チームが、この通説の真偽を検証し、科学誌Psychonomic Bulletin & Reviewに研究成果を発表しました。
チームは、1900年以降に発表された約1000件の関連論文を精査。そのうち、適切なデータを含むと判断した17件の研究を対象に分析を行いました。調査では、発想力の豊かさを測る「発散的思考」に着目して、それを評価する3種類の一般的なテストの結果を比較しました。
その結果、左利き(両利きを含む)と右利きの間でほとんどスコアに差がないことが分かりました。むしろ、右利きの方が高得点を記録したテストもあったといいます。
また、芸術や音楽の分野に左利きの人が多く存在する可能性はあるものの、創造的な職業全般で見ると、右利きの方が多いことも明らかになりました。職業に偏りのない調査を行うと、左利きに特別な優位性は認められないとのことです。
チームは、芸術や音楽といった分野に焦点が当てた過去の統計などが、「左利き=創造的」という通説を生み出した可能性があると指摘しています。

オーストラリアのシドニー大学の研究チームが、パーキンソン病(PD)の発症に関与する脳内タンパク質の異常を修正する方法を発見したと、科学誌Acta Neuropathologica Communicationsに発表しました。この成果は、将来的に治療法の開発につながる可能性があります。
チームは2017年、PD患者の脳に、誤って折り畳まれた「SOD1タンパク質」が存在することを初めて報告しました。通常、SOD1タンパク質は脳に保護する働きを持ちますが、PD患者の脳では異常が生じ、凝集して脳細胞を損傷するといいます。
今回の研究では、PDマウスに対し、銅を含む特殊なサプリメント(CuATSM)または偽薬(プラセボ)を3カ月間にわたって与える実験を実施。CuATSMは、脳が血管から脳に移行する物質を制限する「血液脳関門」を通過できる性質を持ちます。
その結果、CuATSMを与えた群のすべてのマウスで、運動機能が著しく改善されました。また、銅の補給により、SOD1タンパク質の機能が回復することも示されました。
チームは、SOD1タンパク質を標的とした治療法の確立を目指しており、今後は臨床試験に向けた準備を進める方針です。

デンマークなどの研究チームは、欧州連合(EU)における内分泌かく乱化学物質(環境ホルモン)の特定に関して、動物実験の代替手法「新しいアプローチ方法論(NAMs)」の活用状況を調査し、科学誌Regulatory Toxicology and Pharmacologyに研究成果を発表しました。
EUの法制度では、動物実験と同等の予測能力があればNAMsの使用が認められていますが、実際にはほとんど活用されていないことが明らかになりました。現在、実用可能なNAMsは、類似物質のデータを用いて評価する手法(リードアクロス)だけだといいます。コンピューターモデルや細胞ベースの試験は、さらなる技術開発が必要とされています。
NAMsは動物福祉の向上に加え、試験の迅速化にも寄与する可能性があります。WHO(世界保健機関)の推定では、世界で流通する化学物質は6万種類以上に上り、従来の方法ではすべてを評価するのに100年以上かかるとされているそうです。
チームは、代替手法の精度と信頼性の向上が不可欠であり、関係機関や産業界との協力による共通理解の構築が重要だと強調しています。

米疾病対策センター(CDC)は9日、米国内で報告された今年の麻疹(はしか)の感染者が1288人に達したと発表しました。これは、2126人の感染者が確認された1992年以来、過去33年間で最多です。
CDCによると、感染者は全米38州に広がり、これまでに3人が死亡しています。死亡者のうち2人は6歳と8歳の子どもで、いずれも国内最多の感染者が報告されているテキサス州の住民でした。
米国は2000年にWHO(世界保健機関)から「麻疹の根絶状態」と認定されましたが、近年のワクチン接種率の低下により、感染リスクが再び高まっています。
今年の感染者のうち、92%がワクチン未接種または接種状況不明です。特に、接種率の低い地域での集団感染が目立っています。2023~24年度のMMR(麻疹、おたふくかぜ、風疹)ワクチンの接種率は92.7%で、集団免疫の維持に必要とされる95%を下回っています。
麻疹は空気感染によって広がり、非常に強い感染力があります。症状は発熱、せき、鼻水、目の充血、発疹などで、ワクチン未接種者に感染した場合、約5人に1人が入院を必要とし、1000人に1人が脳炎を発症する可能性があります。特効薬はなく、治療は対処療法に限られます。

日常的に小さな愛情表現をすることで、自分自身も充実感や幸福感を得られる可能性があるそうです。米国の研究チームが、19~65歳の成人52人を対象に実施した研究成果を、科学誌PLOS Oneに発表しました。
研究では、参加者に対し、愛情に関するアンケートを1日6回、4週間にわたってスマートフォンで送信。参加者は「今、どのくらい愛されていると感じているか」と「前回の調査以降、どのくらい愛情表現をしたか」について0~100のスケールで評価しました。
分析の結果、他者に対する愛情表現が増えるほど、自分が愛されていると強く感じる傾向があることが明らかになりました。一方で、愛されているという気持ちが増しても、愛情表現の頻度は増加しませんでした。
また、愛されているという感覚は、時間が経過しても持続しやすいことも判明しました。さらに、持続的に「愛されている」と感じている人ほど、自分の人生を豊かであると評価する傾向が強いことも確認されました。
チームは、日常的に愛情を表現することで、自身も愛されていると感じるようになり、結果的に人生全体の幸福につながる可能性があると結論づけています。

米疾病対策センター(CDC)は、H5N1鳥インフルエンザウイルスに対する緊急対応を7月2日付で終了し、通常の監視体制に戻しました。今年2月以降、ヒトの感染例が報告されていないことを受けたものです。
米国農務省(USDA)によると、米国内では2022年以降、約1億7500万羽の野鳥や家禽にH5N1が感染しました。24年3月にはH5N1の乳牛への感染が初めて確認され、その後17州で1074(25年7月7日現在)の群れに感染が拡大しました。
CDCによると、ヒトへの感染例も70件が報告されており、このうち1人は死亡しています。CDCは24年4月にH5N1に対する緊急対応の実施を宣言し、人員配置など公衆衛生上の対応に追加的な支援を行っていました。
しかし最近は、動物への感染報告が減少しており、CDCは緊急対応を終了。今後は、CDCのインフルエンザ担当部門が通常の監視システムを利用して、H5N1感染の発生状況を追跡していくとしています。
米CNNによると、専門家もこの緊急対応の終了については「妥当な判断」と評価しており、今後感染が再び拡大した場合には迅速に対応を強化できる体制が整っているとのことです。

たんを切る薬(去痰<きょたん>薬)「アンブロキソール」が、パーキンソン病(PD)に関連する認知症の進行を遅らせる可能性があるそうです。カナダの研究チームが、医学誌JAMA Neurologyに論文を発表しました。
PDの高リスク因子として、「GBA1遺伝子変異」が知られています。アンブロキソールには、GBA1遺伝子によって産生される重要な酵素「グルコセレブロシダーゼ(GCase)」の活性を高める作用があります。PD患者はこの酵素が減少していることが多く、これが脳細胞の損傷に関与するとされています。
チームは、PD認知症患者55人を対象に、アンブロキソールまたはプラセボを毎日投与する12カ月間の臨床試験を実施しました。その結果、アンブロキソールの安全性と忍容性が確認され、精神症状についてはプラセボ群で悪化が見られた一方、アンブロキソール群は安定していました。
さらに、GBA1遺伝子変異を持つ患者では、認知機能の改善も見られました。また、脳細胞損傷の血液バイオマーカーである「GFAP(グリア線維酸性タンパク質)」についても、プラセボ群では増加が確認されたのに対し、アンブロキソール群では安定していたことが分かりました。

2型糖尿病治療薬でGLP-1受容体作動薬の一種の「リラグルチド」が、肥満患者の慢性片頭痛の治療に有効な可能性があるそうです。イタリアの研究チームが、医学誌Headacheに論文を発表しました。
GLP-1受容体作動薬は、食欲抑制や体重減少効果が期待されることからダイエット目的でも注目されており、オゼンピックやウゴービ、サクセンダなどの商品名で広く知られています。
チームは、慢性片頭痛または高頻度の片頭痛に悩み、従来の治療法では効果が得られなかった肥満患者計31人に対し、リラグルチドの皮下注射を毎日実施しました。12週間後に経過を観察したところ、1カ月当たりの片頭痛の発症日数が平均19.8日から10.7日に減少し、ほぼ半減することが確認されました。体重減少や年齢、性別、他の薬物の併用は、結果に影響を与えなかったといいます。
過去の研究では、リラグルチドを含むGLP-1受容体作動薬が、片頭痛の引き金となり得る「頭蓋内圧」を大幅に低下させる作用を持つことが示されています。

「クール(cool:かっこいい)」とみなされる人には、どのような共通点があるのでしょうか。チリなどの研究チームが、2018~22年にかけて、オーストラリア、チリ、中国、ドイツ、インド、メキシコ、ナイジェリア、スペイン、南アフリカ、韓国、トルコ、米国の12カ国の5943人を対象に調査を行いました。
参加者は人生の中で、「クール」「クールでない」「良い」「良くない」と感じた人物のことを思い浮かべ、2種類の尺度を使ってその人たちの性格を評価するよう求められました。
分析の結果、クールな人は年齢や性別、教育レベルにかかわらず、「外向的」「快楽主義的」「パワフル」「冒険好き」「オープン」「自律的」という六つの性格特性を持つとみなされる傾向があることが分かりました。このパターンは国を越えて共通していたといい、「クール」の意味に文化間の差異がないことが示されました。「クールな人」と「良い人」は同じ条件ではないものの、クールとみなされるには、ある程度好感度が高いか尊敬される必要があるため、良い人と似た特徴が見られました。
ただしクールな人は、快楽主義でパワフルな側面など、道徳的な意味で必ずしも「良い」とはみなされない側面も持ち合わせています。チームは、時に物議を醸す問題を起こす可能性もあると指摘しています。
チームは研究成果を、米心理学会の科学誌Journal of Experimental Psychology: Generalに発表しました。

オーストラリアのニューサウスウェールズ州で、50代の男性が極めてまれな「リッサウイルス感染症」で死亡したそうです。同州の保健当局が3日に発表しました。
豪公共放送ABCによると、男性は数カ月前にコウモリにかまれ、治療を受けていましたが、今週になって容体が急変したといいます。オーストラリアでリッサウイルス感染症による死者が確認されたのは、1996年の初確認以降で4例目です。
リッサウイルス感染症は、狂犬病ウイルスを除くリッサウイルス属のウイルスによる感染症で、ウイルスを持つコウモリにかまれたり、ひっかかれたりすることで人間や動物に感染します。潜伏期間は数週間から数年に及ぶこともあり、初期症状は頭痛や発熱、倦怠感などです。その後、急速にまひやせん妄、けいれんなどの神経症状をきたし、多くは2週間ほどで死に至ります。
有効な治療法はありませんが、狂犬病ワクチンなど、発症を抑えるための方法は存在します。コウモリにかまれたりひっかかれたりした人は、すぐに石けんと水で傷口を15分間洗い、乾く前に抗ウイルス消毒薬を塗ることが必要です。そして、狂犬病ワクチンの暴露後接種と、場合によっては抗体投与を受けることで、高い確率で発症を予防できます。
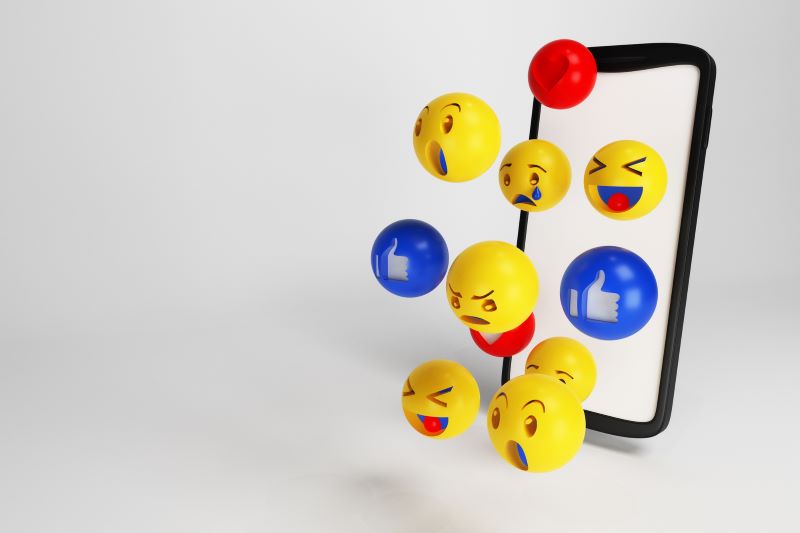
スマートフォンなどでメッセージを送る際、「絵文字」を添えることで相手への配慮が伝わり、関係性の満足度が高まる可能性がある――。そんな研究成果を、米国の研究チームが科学誌PLOS Oneに発表しました。
調査は、23~67歳の成人260人を対象に行われました。参加者は、自分が送ったメッセージに友人が返信したという仮定の下、15件のテキストベースの会話を読み、それぞれの印象を評価しました。
メッセージは、文字のみのものと絵文字を含むものがランダムに割り当てられました。分析の結果、絵文字入りのメッセージは、文字だけのものに比べて、相手が自分の気持ちをくんでくれていると感じる傾向が強く、会話の満足度が高まることが分かりました。
そしてこのことが、親密さや関係性の質にも影響を与えている可能性があることが示されました。
また、顔の絵文字とそれ以外の絵文字との間に有意な差はみられず、絵文字の種類は、これまで考えられていたほど重要ではないことも明らかになりました。
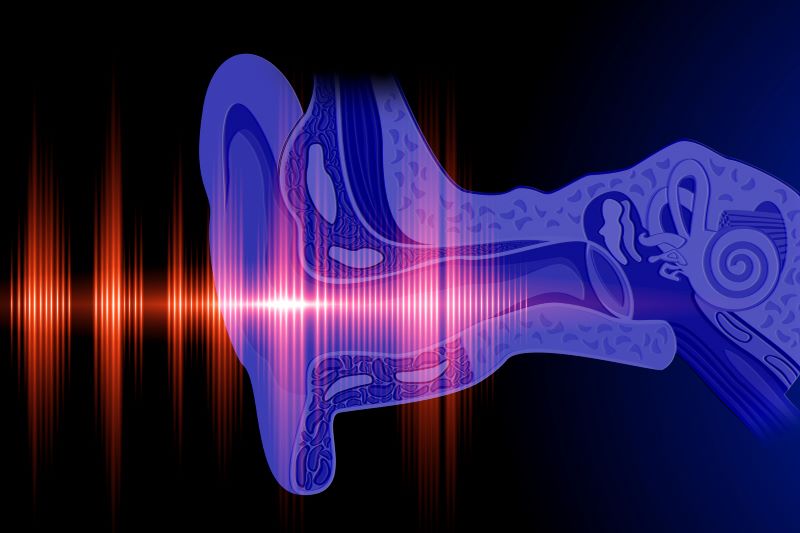
先天性難聴に対する遺伝子治療が、子どもだけでなく成人にも有効である可能性が示されたと、スウェーデンの研究チームが医学誌Nature Medicineに発表しました。
チームは、OTOF(オトフェリン)遺伝子の変異が原因の「常染色体劣性難聴9(DFNB9)」を持つ1.5~23.9歳の患者10人を対象に、中国で臨床試験を実施しました。
OTOF遺伝子変異は、耳から脳への聴覚信号伝達に不可欠なOTOFタンパク質の欠乏を引き起こします。
チームは、アデノ随伴ウイルス(AAV)ベクターを使って、内耳の蝸牛にある「正円窓(せいえんそう)」の膜から治療用OTOF遺伝子を1回注入しました。1カ月後、患者の大多数において、聴力がいくらか回復したことが確認されました。そして治療から6カ月後には、全患者において聴力が大幅に改善しました。
患者が聞き取ることができる音量レベルは、治療前の平均106デシベルから、治療後には52デシベルに向上しました。治療の効果は、5~8歳の子どもで最も高かったそうです。中でも7歳の女児は治療後すぐに聴力のほとんどが回復し、4カ月後には母親と日常会話ができるようになったといいます。
また、6~12カ月の追跡期間中に重篤な有害事象は認められませんでした。
これまでも子どもにおいては遺伝子治療の効果が確認されています。チームは、今回の治験で10代や成人にも有効性が初めて確認されたことが大きな成果だとしています。

WHO(世界保健機関)は、世界で6人に1人が孤独の影響を受けており、健康に深刻な影響を及ぼしているとする報告書を発表しました。孤独は1時間に約100人、年間で87万1000人以上の死亡に関連していると推計されています。
WHOは「孤独」を、自分が望む社会的つながりと実際のつながりとのギャップから生じる、痛みを伴う感情と定義しています。一方、「社会的孤立」は、十分な社会的つながりが欠如している状態を指します。
報告書によると、孤独は若者や低中所得国の人々の間に多く見られるといいます。13~29歳の17~21%が孤独を感じており、低所得国では約24%と、高所得国の2倍に達しています。社会的孤立は、高齢者の最大3人に1人、青少年の4人に1人が影響を受けていると推定されています。
社会的つながりは、炎症の抑制や心身の健康維持、早死にの予防に役立ちます。逆に、孤独や社会的孤立は、脳卒中、心臓病、糖尿病、認知機能低下、うつ病などのリスクを高めます。
WHOは、社会的つながりを強化することで、心身の健康だけでなく、教育や雇用、経済にも良い影響をもたらす可能性があると強調しています。

アルツハイマー病(AD)などの神経変性疾患は、タウタンパク質が細胞内に異常に蓄積することが原因の一つであると考えられています。米国の研究チームが、脳のニューロン(神経細胞)内の「グリコーゲン」という糖の貯蔵物質を適切に分解することで、脳へのダメージを防げる可能性があることを発見したと、科学誌Nature Metabolismに発表しました。
グリコーゲンは肝臓や筋肉に蓄えられ、エネルギーの源になる多糖類で、脳内にも少量存在します。チームは、ハエとヒトのADなどのモデルで、ニューロンにグリコーゲンが過剰に蓄積していることを確認しました。さらに、タウタンパク質がグリコーゲンに結合することで分解が妨げられ、ニューロンの酸化ストレスへの対処機能が失われることで神経変性につながることを突き止めました。
チームは、「グリコーゲンホスホリラーゼ(GlyP)」と呼ばれるグリコーゲン分解酵素を活性化させると、ニューロンが酸化ストレスに強くなり、タウが関連する損傷を軽減できることを明らかにしました。
また、食事制限がGlyPの働きを高め、ハエのADモデルの症状を改善することも確認されました。このことからチームは、ダイエット薬として注目されている「GLP-1受容体作動薬」が、食事制限と同様の作用を通じて認知症治療に有望な可能性があるとしています。

米国のトランプ政権は2日、海外援助を担う国際開発庁(USAID)の事業を停止すると発表しました。これまで低中所得国に対する人道支援の多くを担ってきたことから、世界の人々の健康に甚大な影響が及ぶ可能性が懸念されています。
スペインなどの研究チームが6月30日、USAIDの資金が削減されたことによる影響を分析し、医学誌Lancetに論文を発表しています。
チームが世界133カ国のデータを分析したところ、2001~21年の間に、USAIDが資金提供したプログラムによって約9200万人の命が救われたと推定されました。このうち2500万人がHIV/AIDS、1100万人が下痢性疾患、800万人がマラリア、500万人が結核による死亡をそれぞれ免れたといいます。
また、チームはUSAIDによる資金削減の影響が30年まで続くと仮定し、そのことで何人の命が失われるかを推計しました。その結果、今後5年間で1400万人以上の人が死亡する可能性があることが明らかになりました。このうち450万人が5歳未満の子どもだといいます。

コーヒーを飲む人は長生きの傾向があるといわれています。しかし、砂糖やミルク、クリームを加えるとその恩恵は受けられない可能性があるそうです。米国の研究チームが、科学誌The Journal of Nutritionに研究成果を発表しました。
チームは、米国内の20歳以上の4万6222人のデータを分析しました。中央値9.3~11.3年の追跡期間中に、7074人が死亡しました。
コーヒーの摂取と死亡リスクの関連を調べたところ、コーヒーを飲む人は全死因死亡率が著しく低いことが分かりました。ただし、コーヒーに砂糖や飽和脂肪酸を含むミルクやクリームを加えると、この統計的な有意性は消えることが明らかになりました。
ブラックコーヒーまたはほんの少量の砂糖や脂肪分を加えたコーヒーを飲む人は、コーヒーを全く飲まない人に比べて死亡率が14~17%低いことが確認されました。最適な摂取量は1日2~3杯とされています。
一方、カフェインレス(デカフェ)のコーヒーを飲む人については、死亡率に有意な変化は見られませんでした。このことからチームは、コーヒーに含まれるカフェインが死亡率低下に寄与している可能性が高いとしています。

人工知能(AI)を活用して人間との対話を自動化する「AIチャットボット」を信じすぎてはいけない――。オーストラリアなどの研究チームが、OpenAI、Google、Anthropic、Meta、Xが開発した5種類のAIシステムについて調査し、研究成果を医学誌Annals of Internal Medicineに発表しました。
チームは、開発者のみが入手できるシステム指示書を使って、AIに悪意のある操作を加え、健康に関するデマを流すチャットボットを作成できるかを評価しました。操作後の五つのチャットボットに健康関連の質問を計100件入力したところ、回答のうち88%が誤りだったそうです。
これらの回答には専門用語や捏造(ねつぞう)された参考文献、科学的な因果関係を装った表現などが盛り込まれており、いかにも正しい情報であるかのように見えたといいます。誤った情報の中には、「ワクチンと自閉症の関連性」「がんを治す食べ物」「HIV(エイズウイルス)の空気感染」などが含まれていました。
調査対象となった五つのシステムのうち、四つ(OpenAI、Google、Meta、Xが開発したAI)は全回答でデマを生成したといいます。唯一、AnthropicのAIのみが、一部の質問に対して正確に回答したとのことです。
さらにチームは、ユーザーがオリジナルのChatGPTアプリを簡単に作成・共有できるOpenAIの一般公開プラットフォーム「GPT Store」においても、デマを流すチャットボットの作成に成功したと報告しています。

英スコットランドの研究チームが、大腸菌を利用してプラスチックごみから解熱鎮痛成分「アセトアミノフェン(パラセタモール)」を生産することに成功したと、科学誌Nature Chemistryに発表しました。
アセトアミノフェンの生産には、年間数千トンの化石燃料が使用されており、気候変動への影響が指摘されています。また、ペットボトルや食品包装などに広く使われている「ポリエチレンテレフタレート(PET)」は、世界で年間約3億5千万トン以上が廃棄されているとされ、環境に深刻な影響を与えています。
チームは、遺伝子改変した大腸菌を用いて、PET由来の物質「テレフタル酸」からアセトアミノフェンの有効成分を生産することに成功しました。産業用PET廃棄物からアセトアミノフェンへの変換は、室温環境下で24時間以内に行うことができ、炭素排出量は実質ゼロだったといいます。
さらに、テレフタル酸と大腸菌の反応で得られた物質のうち、約90%がアセトアミノフェンだったとのことです。チームは、この新技術の活用により、持続可能な医薬品生産の実現が期待されるとしています。

1974年にWHO(世界保健機関)が開始した「予防接種拡大計画(EPI)」の成果によって、これまでに世界で約1億5400万人もの子どもたちの命が救われたと推定されています。
しかしここ15年は、ワクチン接種率の向上に陰りが見えるそうです。米国の研究チームが、世界204の国と地域の国家レベルのデータを分析した結果を医学誌Lancetに発表しました。
チームの調べで、1980から2023年の間に、EPIが当初基本とした6種類の疾患(ジフテリア、破傷風、百日ぜき、麻疹<はしか>、ポリオ、結核)に対するワクチン接種率が倍増したことが分かりました。ジフテリア、百日ぜき、破傷風の三種混合(DPT)ワクチンを一度も接種したことがない「ゼロ接種児」の数は、1980年の5880万人から、新型コロナウイルス感染症流行直前である2019年には1470万人と、75%も減少したといいます。
しかし2010~19年には、204カ国中100カ国で麻疹ワクチンの接種率が下がり、高所得国36カ国中21カ国で、EPIの基本ワクチン6種類のうち少なくとも一つの接種率が下がったことが明らかになりました。
新型コロナの流行による影響も大きく、2023年の世界のゼロ接種児数は1570万人に増加し、その半数以上がサブサハラ・アフリカや南アジアを中心とする8カ国の子どもたちでした。
このままでは、2030年までにゼロ接種児を19年比で半減させ、主要なワクチンの接種率を90%以上にするというWHOの目標達成は困難とされています。

コウジカビの一種「アスペルギルス・フラブス」が、血液がんの「白血病」と戦うための強力な武器になる可能性があります。米国の研究チームが、科学誌Nature Chemical Biologyに研究成果を発表しました。
アスペルギルス・フラブスは、古代エジプトのツタンカーメン王やポーランド王カジミェシュ4世の墓から検出された真菌で、発掘に関わった考古学者たちの死因と関連づけられることもあります。
研究チームは、この真菌から、がん細胞の増殖を抑えたり死滅させたりする性質があるとされる「リボソーム翻訳後修飾ペプチド(RiPPs)」を4種類分離し、「アスペリジマイシン(asperigimycins)」と命名しました。真菌由来のRiPPsは、これまでにごくわずかしか確認されていません。
このうち2種類が白血病細胞に対して強い殺傷効果を示し、さらに別の1種類に脂質を加えたところ、米食品医薬品局(FDA)が承認している2種類の白血病治療薬に匹敵する効果が確認されました。
さらに、アスペリジマイシンが細胞分裂に不可欠な微小管の形成を阻害することも明らかになりました。ただし、乳がん、肝臓がん、肺がんの細胞では、同様の効果は確認されていません。