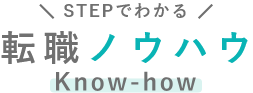STEP.4 円満退職・内定準備
退職願・退職届の書き方のマナーと退職までの流れ【完全保存版】
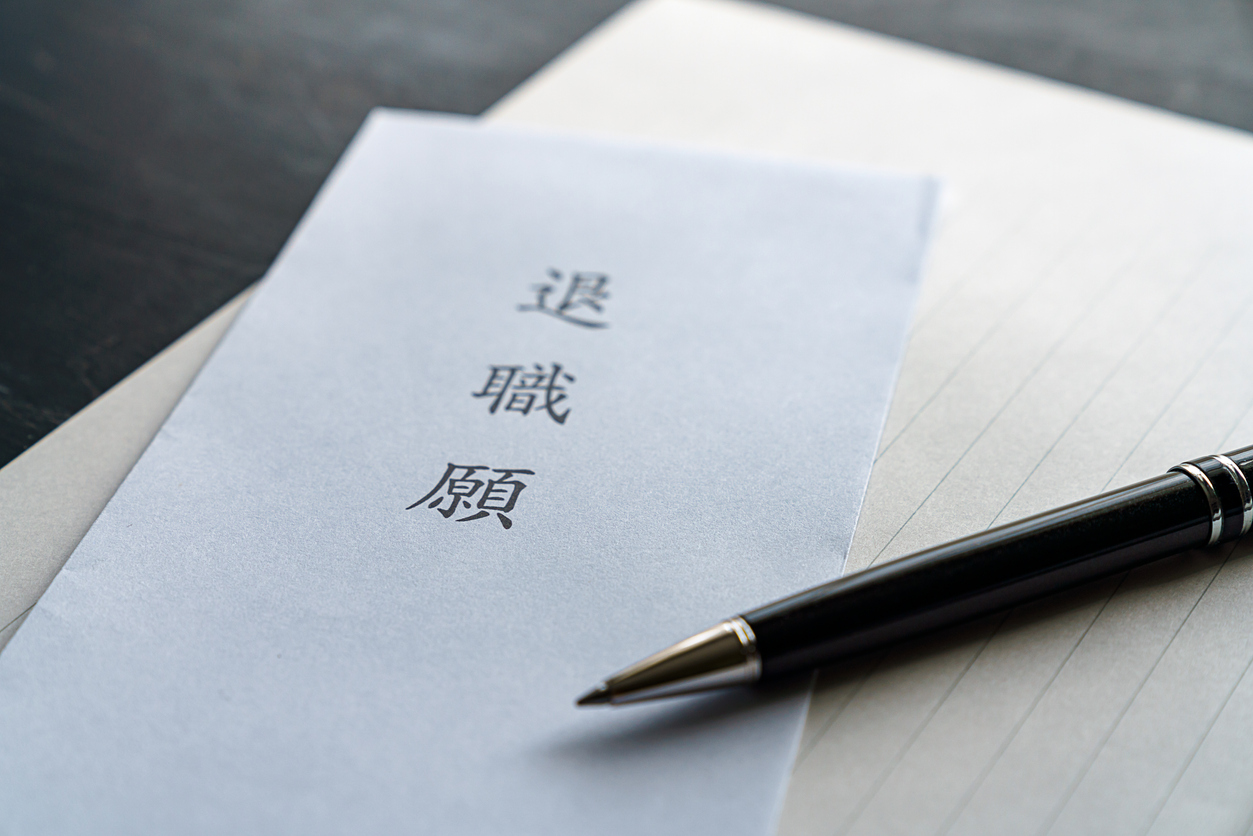
この記事は約 13 分で読むことができます。
転職後も同業者との付き合いが継続する医師にとって、円満に退職することは非常に重要です。病院やクリニックへ退職の申し出をする際に必要となる退職願・退職届のマナーを確認しておきましょう。退職願と退職届の違いといった基本知識から具体的な書き方、また書類を封入する封筒の選び方まで、徹底解説します。
この記事のまとめ
- 「退職願」は退職を願い出る書類で、「退職届」は退職が確定したのちに作成する書類。必ずしも作成する必要はなく、口頭でも同じ意味合いとなる。
- 欠員補充や引き継ぎの期間を考慮して、医師の場合は退職する半年前に相談をしておくことが望ましい。
- 記載方法は手書きでもパソコンでもOK。パソコンで作成する場合も、所属先・署名・日付は手書きにする。
- 民法上の退職届を出すタイミングは、「時給制、日給制の給与形態」であれば「2週間前まで」に出せばOK。
\求人探し・書類作成・面接対策までサポート/
この記事の目次
1.退職願・退職届・辞表の違いとは
「退職願」と「退職届」と「辞表」の違いを知っていますか?どちらも勤務先を退職するときに提出するものですが、実は微妙に用途や役割が異なります。あらためてその違いを確認しておきましょう。
・退職願
退職願は「退職をしてもいいでしょうか」と願い出る書類です。なお、退職の申し出は必ずしも書面で提出する必要はなく、口頭で「退職を希望しております。退職してもいいでしょうか」と相談するのと同じ意味合いを持ちます。
・退職届
退職届は退職することが確定したのちに、退職日を明記して勤務先に対して提出するものです。勤務先によっては規定の書面を使用するケースがあるので確認しましょう。
・辞表
辞表は病院の理事長などの役職者、会社の代表取締役や役員、公務員などが用いる書類です。一般的な医師が辞表を提出することはありません。
退職願・退職届・辞表にはそれぞれ上記のような違いがあります。退職の意思を伝えることを決めたら、「退職願」を用意して上司に相談しましょう。場合によっては、受け入れられない可能性もありますし、「考え直してくれないか」と慰留されるケースもあります。
なお退職が勤務先に承諾されるまでの間は、撤回の申し出をすることも可能です。ただし撤回できるからといって、退職願を提出した後に一方的に撤回することはおすすめできません。少なからず何らかの理由で退職の意思があったことを示すことになるので、戻った後に居心地の悪さを感じる可能性があります。「退職願」は退職のお伺いを立てる書類ですが、退職の意思をしっかりと固めてから提出することをおすすめします。
また勤務先の都合によって退職をする場合は退職届を出す必要はありません。退職届を提出してしまうと、失業保険給付の際に不利になってしまう可能性がありますので留意しましょう。
2. 病院・クリニックに退職願・退職届を出し、退職するまでの流れ

退職の意思を固めたら、まず就業規則を確認しましょう。職場によっては、「●カ月前までに退職願(もしくは退職届)を提出すること」など、期日に関する規定が設けられています。一般的には、退職希望日から1~2カ月前までの申し出を規定されていることが多いでしょう。ただし、規定はあっても、暗黙の了解で3カ月前までに申し出た方がよい場合もあります。タイミングを誤ってしまうと、希望日に退職できなくなる可能性もあるでしょう。状況にもよりますが、可能であれば、できるだけ早い段階で退職の意思を伝えておくのがおすすめです。
\求人探し・書類作成・面接対策までサポート/
退職までの詳しい流れを確認しておきましょう。
■退職までの流れ

▶はじめて転職活動をする医師の方は必見!転職活動全体の流れをチェック
退職願・退職届を提出した後は、退職日までに「引き継ぎ」と「挨拶回り」を行いましょう。
2-1. 引き継ぎ
退職日から逆算して、計画的に引き継ぎ書を行う必要があります。医師の引き継ぎは、おおむねカルテに情報がまとまっているため、詳しく引き継ぎ書をまとめるといった作業はほとんどありません。ただし、特別な配慮が必要な患者さんがいる場合は、個別の引き継ぎ書を作成し、後任となる医師や看護スタッフなどに留意点について説明しておくとよいでしょう。
担当患者さんを引き継ぐ後任の医師がいない場合は、別の医療機関に患者さんを紹介する場合もあります。その際には、患者さんやその家族が不安にならないように、次の施設に引き継ぎが済むまできちんと対応しましょう。
また、管理職として何らかの業務で経営に携わっていた場合は、「外部との交渉案件」「経営上の課題」などについて後継者が状況を理解できるように「引き継ぎ書」を作成しておくとよいでしょう。その他、院内の研修や委員会などに携わっていた場合には、関連する資料をまとめて、後任に引き継ぐ必要があります。
2-2. 挨拶回り
挨拶回りは、退職日が近づいてから行います。医療機関では、シフト制で勤務していることが多く、退職日当日だけで全員への挨拶回りを済ませることは難しいでしょう。お世話になったスタッフや職員など、挨拶をしたい人の勤務状況を確認した上で、計画的に余裕を持って行うことが大切です。手土産などについては、必ずしも持参する必要はありませんが、持参した方が感謝の気持ちを伝えやすく、好印象を残しやすいといったメリットがあります。菓子折りを持参する際には、挨拶相手の人数に合った数を用意し、個包装で賞味期限が長めのものを選ぶとよいでしょう。
患者さんへの挨拶は、状況によって異なります。入院患者さんの主治医を担っていた場合は、後任に引き継ぐ旨をきちんと説明する時間を設けるなど、状況や相手に合わせて対応を検討しましょう。
3.退職願の提出時のマナー

退職願は、自身が退職を希望していることを勤務先に伝える最初のステップといえます。退職願を出すタイミングや、退職願の書き方についてマナーを確認しておきましょう。
3-1.退職願はいつまでに出せばいい?
退職願は手渡しで提出することが基本です。直属の上司に直接話をする時間をもらい、退職を申し出て退職願を渡しましょう。手渡しをすることが難しい場合、郵送するという方法もありますが、突然送り付けるのは勤務先の心証を悪くするため、その場合も事前に電話などで話をしておくようにしましょう。
一般的な会社員の場合「1カ月前までが目安」といわれている退職の申し出は、医師の場合、いつまでに行うのが望ましいのでしょうか?
実は民法(第627条第1項)上の規定では、雇用期間の定めのない従業員の場合、14日前までに退職願を提出していれば退職できることとなっています。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
(民法第627条第1項より)
しかし、これはやむを得ないケースであり、一般的には勤務先の就業規則に記載されている期間に従いましょう。また、医師の場合は全国的に慢性的な医師不足に陥っていることから、1~2カ月前に申し出たとしてもスムーズに退職できないケースがあります。勤務先が自身の代わりとなる人員を確保するための期間や、業務引き継ぎの期間などが必要となることを考慮に入れて、半年ほど前に申し出ることをおすすめします。
3-2.手書きかパソコンか?
退職願を提出する際、手書きが望ましいのかパソコンでもOKなのかというのも気になる点です。やはり手書きだと多少面倒ですし、書き損じをしたときに最初からやり直しになってしまいます。
現在は、パソコンで退職願を作成しても問題ないでしょう。一方で、長年退職願は「手書き」で作成されてきたため、「手書きの方が丁寧」という考え方は確かに根強くあります。結論としては、パソコンでも手書きでも問題ありませんので、自身の作成しやすい方で作成しましょう。
なお、パソコンで作成をした場合、本人が書いたという証明のために、日付、部署名、名前を自筆にすることが求められる場合もありますので、これらの欄のみ、あらかじめ手書きにしておくとスムーズでしょう。
退職届も、基本的には手書きでもパソコンでも問題ありません。勤務先に規定があれば従いましょう。
4. 退職願の書き方のポイント【例文付き】
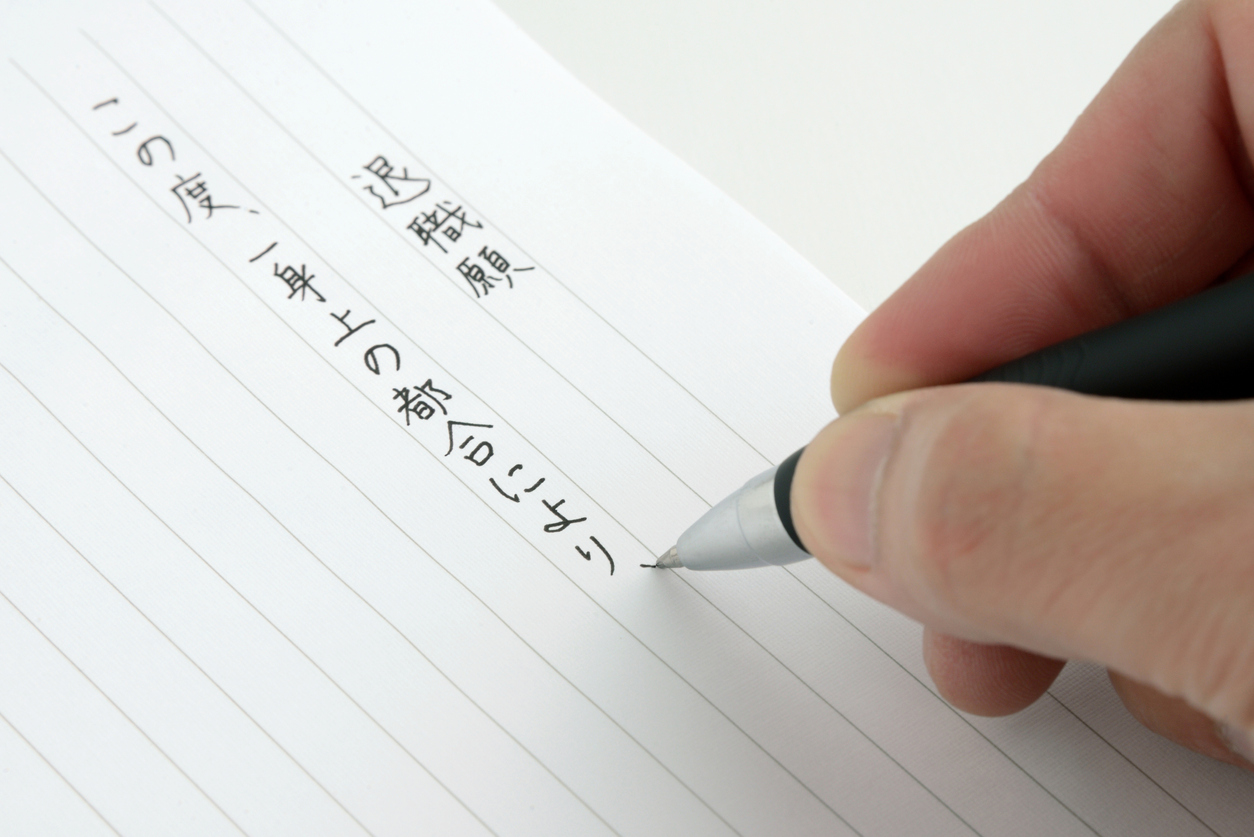
退職願を具体的な記載内容を確認しましょう。実際のところ、退職時の書類に関して、法律上の決まりがあるわけではありません。ビジネスマナー上必要な内容を盛り込んだ内容となっておりますので、記載内容に困った際は以下の見本を参考にしてみてください。なお、退職願、退職届ともに縦書きが基本です。
■退職届の書き方見本
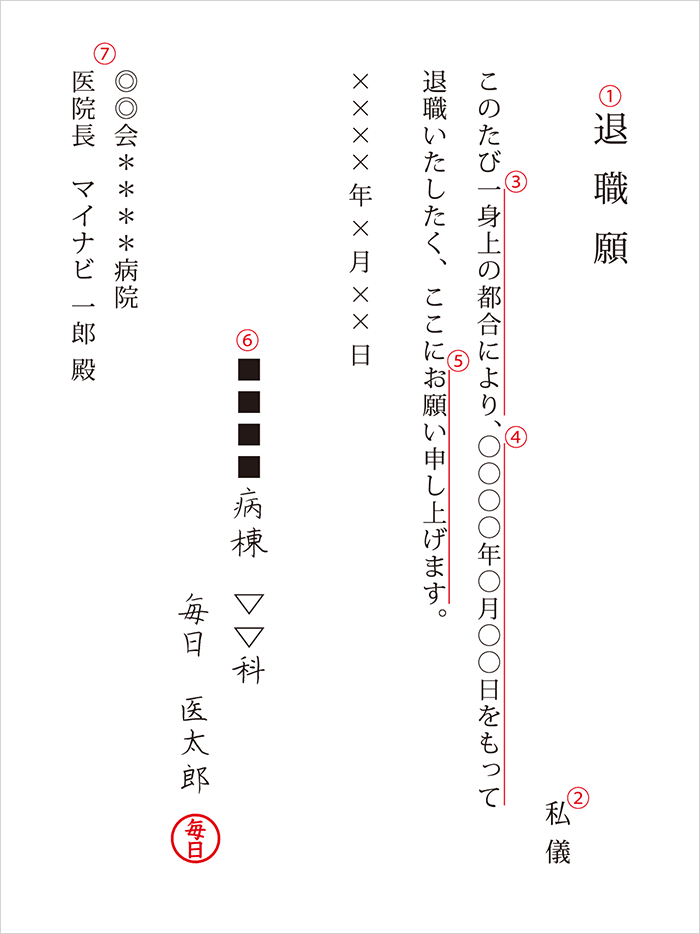
■医師の退職届の記述例
①冒頭行
「退職願」と書きます。すでに口頭で退職の申し入れを行い承諾され、退職が確定している場合は「退職届」となります。
②書き出し
2行目の下部には「私儀」もしくは「私事」と書きます。私事ではありますが、という意味です。
③退職理由
具体的に退職理由を書く必要はなく「一身上の都合により」で問題ありません。
④退職の年月日
退職願の場合は、希望の退職日を記載します。退職届の場合は、上長などと合意した退職の年月日を記載しましょう。
⑤文末の表現
退職願の場合は、「退職をしたく~お願い申し上げます」、退職届の場合は、「退職いたします」という表現にします。
⑥所属先と氏名
略称を使わず正式名称を記載します。氏名の下には捺印をします。パソコンで作成する場合もこの部分は手書きにしましょう。
⑦宛名
略称を用いず正式名称を記載します。
退職願・退職届は正式な書類のため、書類のみを渡すのはマナー違反となります。封筒に入れて渡しましょう。封筒は白無地のものが無難です。また郵便用に郵便番号枠がある封筒は避けるようにしましょう。封筒の表側には「退職願」または「退職届」と、裏側には左下に所属先と氏名を記載します。
5.退職届の提出時のマナー

退職願が承認された後、正式に退職届を提出することになります。続けて、退職届を提出する際のマナーを紹介しましょう。
退職届はいつまでに提出すべきなのでしょうか。
前述の通り、民法(第627条第1項)上の規定では、雇用期間の定めのない従業員の場合、「14日前までに退職願を提出」していれば退職できることとなっています。しかし、民法(第627条第2項)では、「期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。」とされています。
また、民法(第627条第3項)では、「六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。」と定められています。
そのため、原則では「2週間前まで」に退職届けを出せば十分と考えられます。しかし、6ヵ月以上の期間によって報酬を定められた形態(年俸制など)で給与をもらっている場合は、例外として「3カ月前まで」に退職届を出す必要があります。
また、期間によって報酬を定めた場合(月給制など)では、当月15日までに退職届を提出しなければ、翌月末日までは解約(退職)できないことが規定されています。
つまり、民法上の規定であれば、年俸制以外、月給制以外の「時給制、日給制の給与形態」である場合は、「2週間前まで」に退職届を出せば問題ありません。
しかし、入職した際の個別の雇用契約に「退職の申し入れは△前まで」という規定がある場合は、その規定が有効となるため、再確認しておきましょう。
6. 退職届の書き方のポイント【例文付き】
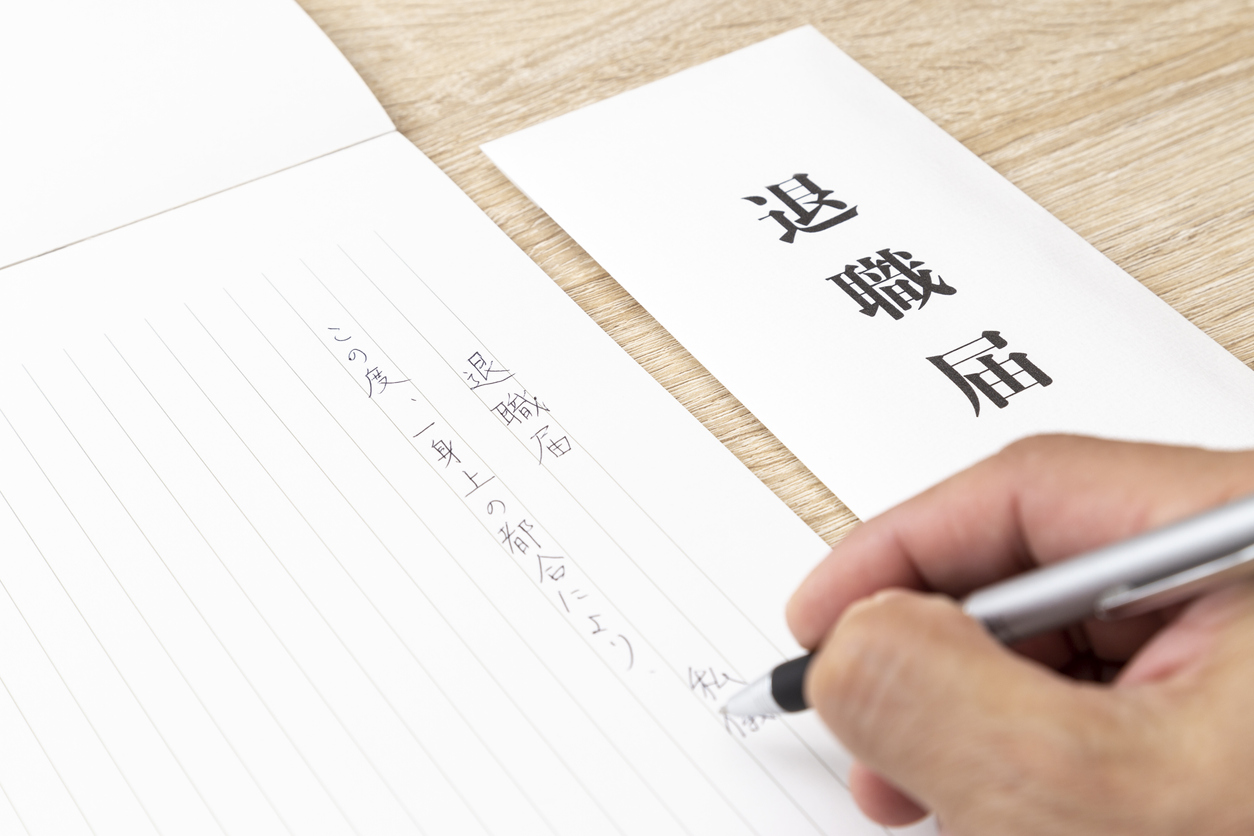
ここからは、退職届の書き方のポイントを例文とともに解説しましょう。
6-1.退職理由を明記しない場合
自己都合退職のため、退職理由を明記しない場合の例文は以下の通りです。
例文1)
「このたび、一身上の都合により、勝手ながら、二〇××年(または令和△年)□月×日をもって退職いたします。」
6-2.退職理由を明記する場合
例文1)
「このたび、早期退職のため、二〇××年(または令和△年)□月×日をもって退職いたします。」
例文2)
「このたび、△クリニック閉鎖のため、二〇××年(または令和△年)□月×日をもって退職いたします。」
6-3.退職届の書き方のポイント
宛名を記入する際は、病院の院長の名前や施設ごとの最高責任者の役職と名前を記入します。敬称は殿とし、自分の名前よりも上に記載することがポイントです。
①冒頭行
「退職届」と書きます。
②書き出し
退職願と同様に、2行目の下部には「私儀」もしくは「私事」と書きます。私事ではありますが、という意味です。
③退職理由
具体的に退職理由を書く必要はなく「一身上の都合により」で問題ありません。
④退職の年月日
退職願とは異なり、退職届の場合は、上長などと合意した退職の年月日を記載します。
⑤文末の表現
退職届は、「退職いたします」と記載します。
⑥所属先と氏名
略称を使わず正式名称を記載します。氏名の下には捺印をします。パソコンで作成する場合もこの部分は手書きにしましょう。
⑦宛名
略称を用いず正式名称を記載します。
■退職願・封筒の書き方
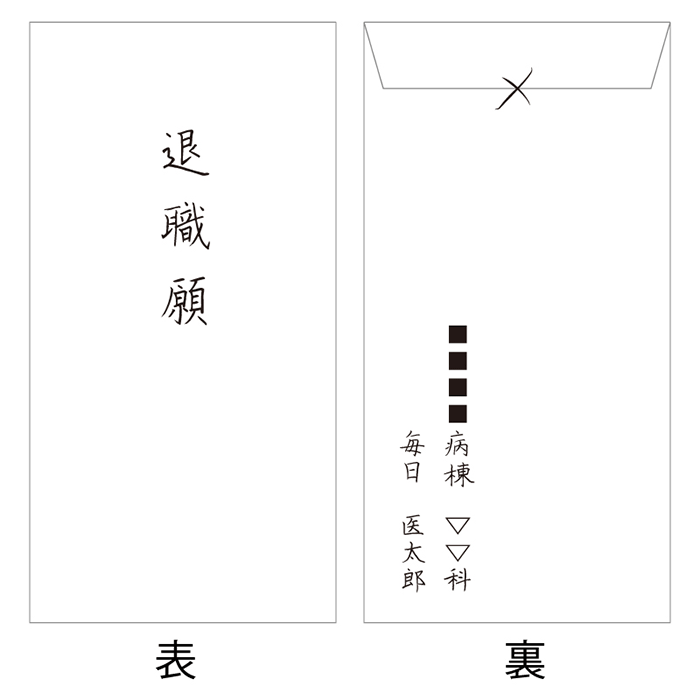
退職願・退職届を三つ折りにして封入します。まず用紙の下部三分の一を文字が隠れるように折り、次に上部三分の一を長方形になるように折り重ねましょう。本文の書き出し部(右上)が封筒の裏の上部にくるような向きで封入します。のりで封をして、封入口に締めマークを書いて封じるのが一般的です。
■退職願・封入の仕方
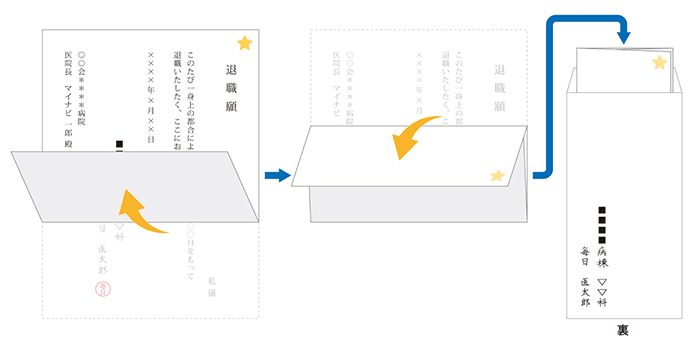
7.病院や施設の退職届に退職理由を書くケース・書かないケース

退職理由を書くケース・書かないケースについて、判断方法と書き方を紹介しましょう。
7-1.退職理由を書かないケース
退職が「自己都合」の場合では、理由は全て「一身上の都合」と記載します。次のような理由に該当するときは「一身上の都合」と記載しましょう。
- ・結婚、出産、育児などのライフイベントに伴う変化
- ・自分の体調不良や罹患による療養、家族の介護
- ・キャリアアップを目指した転職
- ・職場や人間関係によるトラブルや不満
退職届を提出する際に、退職理由を問われた場合には、「結婚、出産、介護など」の家庭やライフスタイルの変化といった個人的な都合であれば正直に伝えても問題ないでしょう。しかし、職場や人間関係によるトラブルや不満をきっかけとした退職の場合、あえて明言する必要はありません。退職理由を確認された場合は、「スキルアップのため」などの前向きな理由に置き換えて表現することが大切です。
7-2.病院や施設の退職届に退職理由を書くケース
退職理由が現在就労している施設など下記のような職場(会社)都合による場合は、具体的な理由を明記します。
- ・施設の倒産
- ・リストラ
- ・早期退職制度を利用した退職
上記に該当する場合は就労している施設などと合意した理由を明記します。退職理由により、退職後に受給する失業保険の期間や金額が変化するため、注意が必要です。
8.病院の退職交渉に悩んだときは専門のエージェントに相談してみよう
退職願・退職届のマナーを知っていれば、いざ退職交渉を始める際にもスムーズです。医師の場合は退職交渉に時間がかかりますので、余裕を持って準備を進められるようにしましょう。
家庭の事情やスキルアップなどを理由に退職を検討していても、退職交渉や手続きに自信が持てないという人もいるかもしれません。そんなときは、医師専門の転職エージェントに相談してみるのもおすすめです。アドバイスを受けながら、スムーズに退職手続きが行えるように、準備を進めましょう。
\求人探し・書類作成・面接対策までサポート/
参考URL
民法 | e-Gov法令検索 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ)第六百二十七条