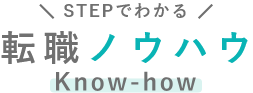STEP.4 円満退職・内定準備
医師が退職する際の手続きと流れ【完全保存版】

この記事は約 11 分で読むことができます。
希望する転職先から内定をもらったらひと安心……そう思うのは実はまだ早いかもしれません。転職活動では内定をもらうのと並行して、現在の勤務先で行っておくべきことがあります。本記事では、内定を得てから新しい職場に出勤するまでに、現職ではどのような手続きを行う必要があるのかについて解説していきます。
この記事のまとめ
- 退職時には、退職の意思表示や退職届の提出、引き継ぎや荷物の整理などさまざまな手続きがある。
- 勤務先への負担を配慮して、退職日まで少なくとも3カ月間の余裕をもって退職交渉を進めることが望ましい。
- 退職時には、お世話になった看護師やコメディカルに直接会ってあいさつするとよい。
- 入院患者さんを担当している場合は、後任の医師に引き継ぐ旨を事前に説明しておくことで安心してもらえる。
- 貸与されていた備品や健康保険証の返却と、年金手帳などの重要書類の受け取りを忘れずに。
この記事の目次
1.退職時の手続き①就業規則の確認

医師が転職を決めたら、現在の勤務先に退職の意思を伝えなければなりません。注意したいのは、職場によって退職の意思を伝える時期が定められていることがある点です。
1-1.退職を伝える期限を確認する
民法上は、職場に退職を伝えるのは退職希望日の14日前までと決まっています(民法第627条第1項より)。しかし病院によっては就業規則で「〇カ月前までに申し出ること」などと規定されている場合があります。一般的には「1カ月前」と規定されていることが多いと思います。民法で決まっているからといって、ぎりぎりの14日前に退職の意思を伝えると、現職の業務が混乱したり人間関係に禍根を残したりする恐れがあります。転職後もつながりのあることが多い医師の世界ですから、退職時もスムーズな引き継ぎを心がけたいものです。
1-2.退職金の規定なども併せて確認
退職を決めたらまずは就業規則を確認しましょう。また退職の申し出に対する規則だけではなく、退職金の規定なども確認しておくとよいでしょう。ある程度の年数の勤務をしていることが前提となりますが、退職金をもらえる可能性があります。
2.退職時の手続き②退職の意思表示

たとえ民法や就業規則で規定されていても、規定ぎりぎりのタイミングで退職の意思を伝えると混乱させてしまう恐れがあります。
2-1.退職の3カ月前までに意思表示する
ほとんどの病院では医師数に余裕がありません。突然14日後の退職となってしまうと、病院の業務が回らなくなってしまいます。できるかぎり余裕をもった対応が望ましく、少なくとも退職の3カ月前までに意思表示を行うことをおすすめします。
現職の病院に不満があったとしても、余裕をもって退職した方が人間関係を悪化させずに済みます。転職後に、新しい業務に取り組む中で現職の病院とやり取りをする可能性がありますので、良好な人間関係を維持しておくことも大切です。
2-2.退職の意思を伝える順番に留意する
退職の意思を伝える相手はまず直属の上司です。例えば、診療科のチームリーダーなどに退職したい旨を相談してみてはいかがでしょうか。特別な事情がないかぎり、いきなり役職が高い人に退職の意思を伝えるのは、好ましくありません。まずは、直属の上司に相談しましょう。また退職の意思の申し出は、「△△といった事情で退職しようと考えているのですが……」と相談から始めることをおすすめします。
退職交渉を円滑に進めるためのポイントの記事を合わせて確認してみてください。
2-3.クリニックに勤務している場合の注意点
ドクターが複数人いる大病院とは異なり、少人数の医師で運営されているクリニックは、1人の退職が勤務体系に大きな影響を及ぼすことがあります。退職する半年~3カ月前では、すぐに代わりの医師を雇用することは難しい可能性があるため、勤務期間の延長を打診されるかもしれません。退職を決めた段階で、できるだけ早く勤務先のクリニックにその旨を伝えることが大切です。
\求人探し・書類作成・面接対策まで全面サポート/
3.退職時の手続き③退職日の決定

直属の上司に退職の相談をして承認されれば、さらに上の役職や総務・人事に話が伝わります。この時点で退職日を決定します。内定先の都合にもよりますが、できるだけ相応の期間を空けた退職日を決定するように心がけましょう。少なくとも退職するまでの間に3カ月ほどの期間があると、病院側も代わりの医師を採用する準備を進めることができます。
4.退職時の手続き④退職届の作成・提出
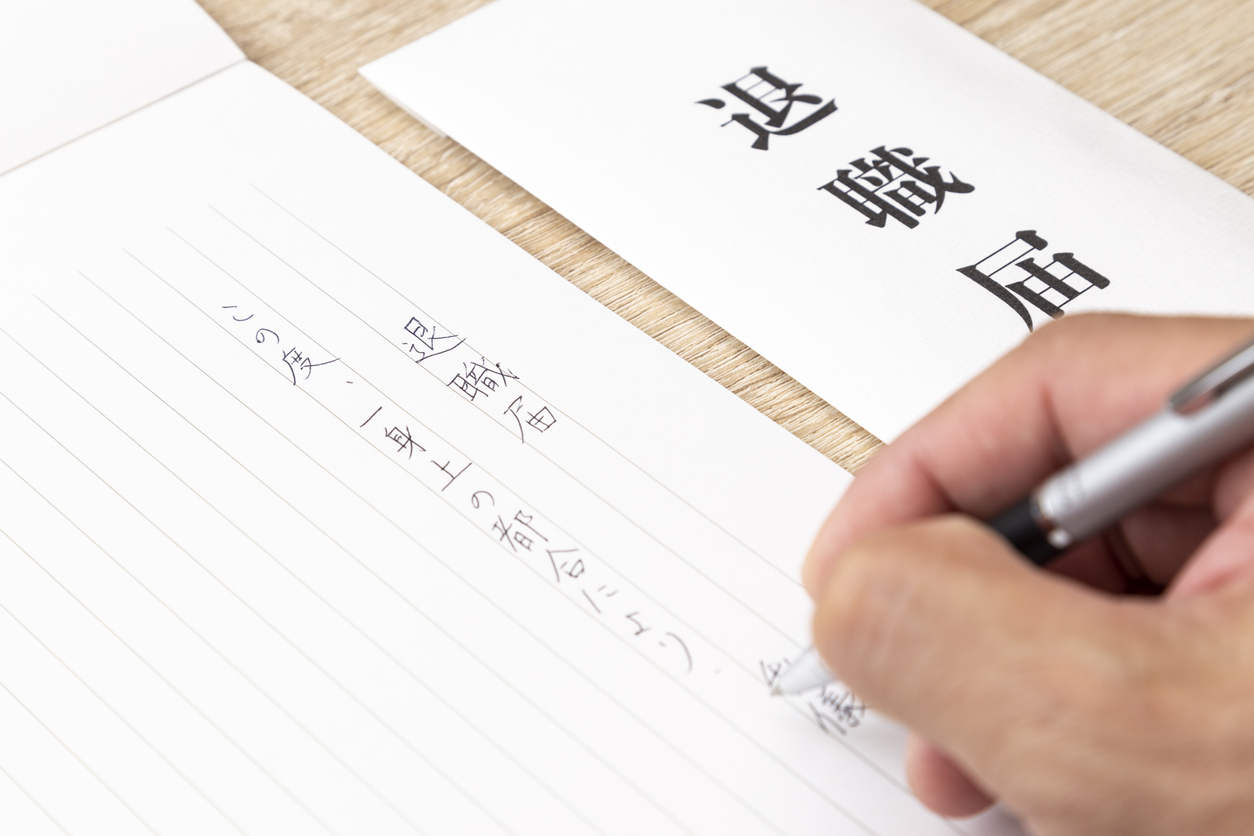
退職日が決定したら「退職届」を提出します。「退職願」は退職を願い出るための書類なのでこの段階では必要ありません。
4-1.「退職届」と「退職願」の違い
「退職届」と「退職願」はよく似ていますが、実は役割が少し違います。「退職願」は「退職をしてもいいでしょうか」と願い出るための書類で、「退職届」は退職確定後に勤務先に対して提出する書類です。退職願・退職届の書き方について詳しく知りたい場合はこちらの記事を確認してみてください。
4-2.「退職届」の提出先
退職届を渡す相手は病院によって異なるため、分からない場合は上司に確認しましょう。退職届は正式な書類であるため、書き方はもちろん、渡し方も重要です。トラブルを避けるためにも、机の上に置いたりするのではなく、手渡しをするように心がけましょう。やむを得ない事情がある場合や病院から許可が出ている場合は、事前に連絡をした上で郵送をすることも可能です。
▶転職活動をまるごとサポートしてもらえるマイナビDOCTORの医師転職支援サービスとは?
\求人探し・書類作成・面接対策まで全面サポート/
5.退職時の手続き⑤引き継ぎ

こちらでは、退職時の引き継ぎのポイントをご紹介します。
5-1.引き継ぎ方法は上司に相談する
医師の場合、カルテがあるので「業務の引き継ぎ」はほとんどありません。とくに気になる患者さんがいる場合にかぎり、個別に引き継ぎ書を作成するくらいでしょう。どのようなものを用意しておいたらいいのかが分からない場合は、上司に相談しましょう。
5-2.退職後の問い合わせの可否や連絡先も伝える
万が一のケースとして、病院側から退職後に問い合わせをされるような事態が生じる可能性もあります。そのため、退職後に問い合わせを受けるかどうか、また問い合わせOKの場合は連絡先をあらかじめ伝えておくとスムーズです。
6.退職時の手続き⑥荷物の整理・備品の返却

今まで働いていた職場を退職するときはなるべく元の状態に戻しましょう。必要な荷物は自宅へ送り、不必要なものは捨てるようにします。また病院から借り受けていた備品は返却する必要があります。どのようなものを借り受けていたか一度整理しましょう。退職時に返却するものの例として、以下が挙げられます。なお、常勤医として働いていた場合は、健康保険証も病院に返却する必要があります。
<退職時に返却する病院の備品>
・病院のIDカード、名札
職員であることを証明するものは、すべて退職時に返却する必要があります。
・支給された名刺
勤務先名が記載された名刺で残っているものを返却します。また、仕事を通じて受け取った名刺も原則として勤務先の所有物とされます。返却が求められる可能性があるため、整理しておきましょう。
・PHSやポケベルなどの通信機器
施設内で使用していたPHSや待機中に使用していたポケベルなどの通信機器類を返却します。
・病院から貸与されていた制服類
制服の貸与を受けていた場合は返却します。クリーニングしてから返却するなど、勤務先のルールに合わせて返却準備をしましょう。
・施設を開ける鍵や棚などのカギ
預かっていた鍵類はすべて返却します。返却を忘れるとトラブルに発展する可能性があります。返却時に漏れがないように、事前にチェックしておきましょう。
・書籍、参考資料、事務用品などの備品
施設側で購入し、提供されたものは、小さな事務用品でも勤務先の所有物となります。消耗品の返却については確認するとよいでしょう。
・業務用の関係書類など
企画書や資料をはじめ、プログラムなどのデータ、業務上の資料や書類、作成物は自分で制作したものであっても、原則として勤務先の資産となるため返却しましょう。
<退職時に返却するもの>
・健康保険被保険者証
それまで加入していた健康保険は、退職とともに脱退となります。無効になった保険証は返却する必要があります。
・通勤定期券
医療施設から定期券が提供されていた場合、返却します。そのた、タクシーチケットなどの預かりがあれば、一緒に返却しましょう。
一方、退職時には勤務先から受け取るものもあります。以下のようなものは忘れず受け取るようにしましょう。
<退職時に受け取るもの>
・雇用保険被保険者証
雇用保険の手続きに必要な書類の一つです。転職先の医療機関に提出します。
・源泉徴収票
年末調整の際に必要になる書類です。年内に新しい会社へ転職した場合は、転職先に提出します。年内に転職しなかった場合も確定申告を行う際に必要です。ただし、施設によっては即日の発行が難しく、年末に送付される場合もあります。
・年金手帳
厚生年金保険の加入を証明する手帳です。雇用先が保管している場合には、忘れずに必ず受け取りましょう。 受け取った後は、転職先に提出します。また国民年金への種別変更をする際にも必要です。
・離職票(次の勤務先が決まっている場合は不要)など
通常、退職後10日以内に交付されます。失業給付の受給手続きの際に必要になります。そのため、退職時にすでに転職先が決まっている場合は必要ありません。10日を過ぎても交付されない場合は、退職先に問い合わせるか、ハローワークに申し出るとよいでしょう。
・保険医登録票や専門医資格証など
勤務先に、保険医登録票や専門医資格証などを預けてある場合には、必ず返却してもらいましょう。県外の施設や、厚生労働省の管轄エリアが異なる場所にある施設に転職する場合には、転出先にて保険医の申請手続きが必要です。転職後、スムーズに申請できるよう、早めに返却してもらえるよう相談するのも一案です。
退職前に勤務先で受け取る場合や、退職後に自宅に送付される場合など、受け取りの時期は書類によってさまざまです。具体的な受け取り時期は勤務先の総務・人事に確認しましょう。
\求人探し・書類作成・面接対策まで全面サポート/
7.退職時の手続き⑦ 退職時のあいさつ

「あいさつは、退職日当日で十分では?」と考える人もいるかもしれません。しかし、医療機関での仕事は基本的に交代制であり、当日に会えない人もいるでしょう。事前に余裕をもって、行動しましょう。
7-1.スタッフへのあいさつ
メールなどであいさつを済ませることもできますが、お世話になった看護師やコメディカルなどのスタッフには、直接会ってあいさつするのがおすすめです。勤務表で事前に各スタッフの出勤日を確認し、誰にいつあいさつすべきか確認し、漏れのないように計画的にあいさつするとよいでしょう。
7-2.患者さんへのあいさつ
患者さんへのあいさつは、それぞれの状況によって異なります。入院患者さんを担当している場合は、後任の医師に引き継ぐ旨を事前に説明しておくと、患者さんやその家族に安心してもらえるでしょう。その際、可能であれば、後任の医師と一緒にあいさつができるとよいでしょう。また、医療機関や役職によっては、直接のあいさつに加えて、公式サイトやSNSであいさつ文を掲載することもあります。
8.退局・退職の意思を伝えてからの過ごし方のポイント

退局・退職の意思を伝えてから、実際に退局・退職するまでの間の過ごし方も大切です。仕事の手を抜いたり、周囲に不満を漏らしたりすることは避けましょう。近隣の地域で転職が決まっている場合には、今後も地域連携として関わる可能性があります。できるだけ円満な人間関係を継続できるように、声かけをしておくのも一案です。引き継ぎを行う時間にも余裕をもって退職日を決めておきましょう。
9.退職準備を進める際の注意点
退職を申し出てから退職日までに行うべき手続きについて紹介してきました。
退職時に一番気をつけたいのは「退職した病院に戻ることがあるかもしれない」ことです。退職時には不満が大きく、戻ることは考えられないかもしれませんが、勤務環境や人間関係、キャリアの変化によって、どのように立場が変わるかは分かりません。また、今の病院で一緒に働いていた同僚と、別の病院で再び一緒に働くこともあるかもしれません。
そのため、退職時にはなるべく同僚の医師や看護師、コメディカルの同僚たちと良好な関係を保ったまま退職することが重要となります。退職に際して、迷惑をかけるようなふるまいを避けて、今まで一緒に働いていた感謝をしっかりと伝えて退職するように心がけましょう。
転職エージェントの支援サービスを利用すると、応募から退職までトータルでサポートしてもらえます。一度利用を検討してみてはいかがでしょうか。
\求人探し・書類作成・面接対策まで全面サポート/
PROFILE

医師。こいけ診療所院長。1994年、東海大学医学部卒業。日本医学放射線学会・放射線診断専門医・検診マンモグラフィ読影認定医・漢方専門医。放射線の読影を元にした望診術および漢方を中心に、栄養、食事の指導を重視した診療を行っている。女性特有の疾患や小児・児童に対する具体的な実践方法をアドバイスし、多くの医療関係者や患者さんから人気を集めている。