浪人、留年……エリートドクターの意外な半生
◆同級生との運命的な出会いから医師を志す

小堀さんの母は森鷗外の次女で、随筆家として活躍した小堀杏奴(あんぬ)。父は画家の小堀四郎だ。鷗外は陸軍の軍医総監まで務めた医師だった。当然、小堀さんの人生の選択にも、鷗外の影響があったのではないか、と思ってしまう。
「よく聞かれることですが、医者になったことと、森鷗外の存在は全く関係ありません。確かに自宅には『鷗外全集』があり、子どものころからよく読んでいました。しかし私の父親は画家、母親は文筆家。将来に関して、医者と言う選択肢を示唆されたことは一度もありません。親はむしろ、僕を自分たちの仕事である絵描きか文筆家にしたかったのではないかと思います」
岐路は中学時代に訪れた。友人、塚原己成(つかはら・きせい)さんとの出会いだ。後にも先にも「人生の大きな転機はこの出会いだけ」と小堀さんは断言する。それほど運命的だった。
当時、小堀さんは成城学園中学校(東京都世田谷区)に通っていた。「塚原君のご両親はともに医師でした。塚原君は幼稚園から成城学園に在籍していて、小学校から入学した私とは中学校で初めて同じクラスになりました。当時の成城学園はとても自由な校風で、試験もなければ宿題も通信簿もなく、大学までエスカレーター式。非常にのんびりした環境だったのですが、そんな中でも彼は自宅できちんと勉強を教えられていたのでしょう。中学の時には独自に仏教の研究をしたり、『無の境地とは』という論文を書いたりと天才肌で、我々同級生の教科書とでも言うべき存在でした。そんな彼に中学3年生の時に呼び出されました。卒業間近だったと思います。そして『君は将来、何になるのか』と聞かれました」
大学まで内部進学ができる学校にいて、進路について家族で話したこともまだなく、小堀さん自身考えたこともなかった。「そう答えると、彼は厳かに『自分は医者になる。医者ほど尊い仕事ない』と滔々と述べ、結論として僕に『君も医者になるべきだ』と言ったのです」
折しも、小堀さんは父親に連れて行かれた講演会で、結核治療薬ストレプトマイシンの発見者でノーベル賞受賞者、セルマン・ワックスマン博士の話を聞いた直後だった。強い印象を残した博士の講演にも後押しされ、小堀さんは成城学園を退学してしまう。
◆「規格外に劣悪な成績」で落第続く
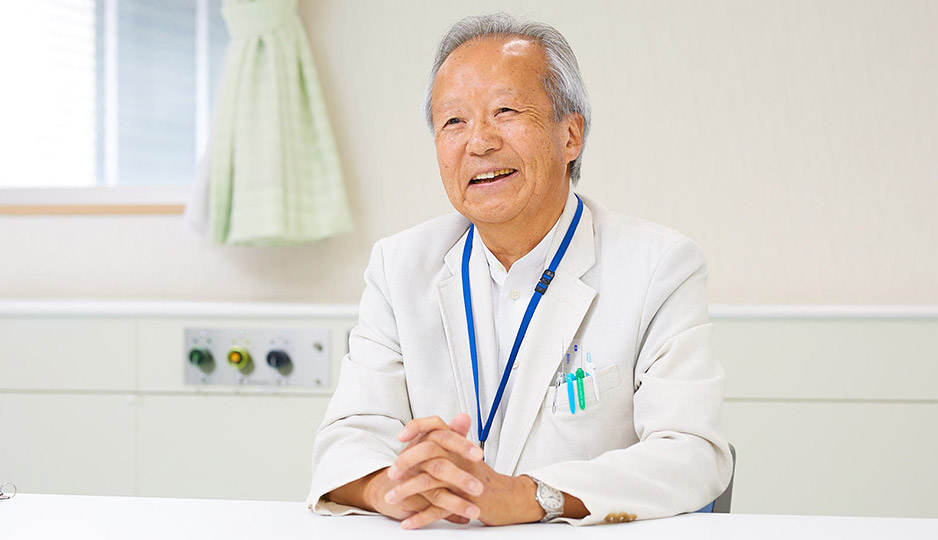
「親にもほとんど相談なく辞めてしまったんですよ。当時、医学部に進学するためには、都立高校の進学校から受験するのが既定路線だったので、塚原君は『成城にいたら医者になれない。都立高校に行かなければ』と。僕の親はよく言えば放任主義、見方を変えれば自分たちの世界に没頭していたので、子どもが何になろうが、あまり興味はなかったのでしょうが、さすがに非常に驚いたと思います。つまり僕は、塚原君に出会わなければ医者になっていない。それは確かです」
ただ、当時の小堀少年は「ひたすら遊びとサッカーに熱中していて、全く勉強をしていなかった」。“放任”の両親に代わり、都立高校受験の段取りは塚原さんの両親が代行してくれた。「彼のお母様が、僕の親の代わりに成城学園中学の担任の先生に面談に行ってくれたんですが、僕の規格外に劣悪な成績に驚かれてね。難関校の都立戸山高校、新宿高校を目指したかったが、それは避けて、ほかの都立3校を受験したんだけど、それも全部落ちてしまった。そこで塚原君の父方のご親族が校長をされていた私立高校に入れてもらいました。当時は都立高校に編入試験がありまして、その私立高校に通いながら戸山高校への編入を目指すことになったわけです」
「元が規格外に低い学力ですから、それからもそれはそれは、大変な思いをしました。最初の高校入学後も、塚原君のご両親が家庭教師を世話してくれて、特訓を受けたのですが、高校1年夏の編入試験はまた落第。結局、2回目の編入試験でやっと合格し、高校2年生から戸山高校への入学が叶いました」
しかし苦労はこれで終わりではなかった。当時は学制改革後の過渡期で、医学部・歯学部進学過程は今とは違い、理学部などの理系学部を2年修了した者の中からさらに選抜された者だけが医学部に進むことができた。東大でも理科三類の設置は1962年まで待たねばならず、医学部志望者は通常まず理科二類に入り、2年修了時に医学部試験を受けて合格しなければならない。3回の試験を経て戸山高校に入った小堀さんは、さらに2年浪人をして理科二類に合格。「なのに教養学部1年の時はまたサッカーに夢中になり、入学と同時に『東京大学ア式蹴球部』に春合宿から参加してしまいました。当時、東大は長らく関東大学1部リーグの強豪だったんですが、僕が入る2年前に2部に転落してましてね。部一丸となって1部復帰を目指していたころです。中学の対抗試合で顔を合わせた部員が何人もいて、それは楽しかった。これがたたって学業成績は理科二類の400名中363番。2年夏の合宿直前、主将から『このままでは東大の1部復帰も、小堀の医学部進学もあぶはち取らずになる』と退部を勧められ、サッカーを辞めました」
結局、2年次を終えた後の医学部入学試験にも落ち、予備校の医学部受験コースに1年通い、ようやく合格できた。「教養学部に入るのに2年、医学部に入るのに1年、都合3年遅れているのです。まともに行けば昭和37年卒だったのが、それが40年卒になりました。そういう意味では知人、友人のレンジが広い」と笑う。エリートそのものといった感の、後の小堀さんのキャリアからは想像できない学歴だが、“寄り道”の多さは、自ら独立独歩で切り開いてきた道のりであることの裏返しなのだろう。
◆治療が難しいから選んだスペシャリティ

医学部卒業後、入局した東大第1外科(石川浩一教授)では悪性腫瘍、消化管、血管、肝臓などの専門外来が開かれ、いくつかの研究グループが作られていた。小堀さんが選んだのは悪性腫瘍のチーム。食道がんを中心に胃がん、乳がんを専門にしていた。
「当時は専門を複数持つべしと言われていました。その後、特に食道がんに力を入れるようになったんですが、それは死亡率が高く、治療が難しいがんだったからです。以来、特に困難な手術や他の医師があきらめた患者の手術を引き受けて、いかに予後をよくするか、ということに傾注していました」。当時、食道がんの患者は手術後30日以上生存させることができれば医師の不名誉ではなくなる、と言われるほど、治療が難しかった。「必然的に外科医同士の競争も激しかったですね。僕は負けず嫌いだからライバル医師の手術を見学に行くこともよくありました」
一方で「僕は、犬猫と子供と若い人が苦手。学生の教育にもあまり興味がありません」と言う。助教授としての講義も「やりたい人はたくさんいたから、代わってもらいました。僕はその間に手術がしたかったから」。時折、「先生に素晴らしい手技を教わりました」と後輩に言われることもあるが、「教えたつもりはないし、教える気もないし、若い人に期待する気もないし、僕の跡を継いでほしいとも思わない」から、さらりと流してしまう。だが、そういう職人気質が、腕一本をたのみとする外科医には憧れを抱かせるのかもしれない。
小堀さんの「手術第一」の生活は延々と続き、国立国際医療センターの病院長時代も新病棟構想に注力しつつ、年に数回は手術場に立った。それだけ現場が好きだった。そんな小堀さんが退職後に選んだ職場は、大学時代からの親友で医局でも同期生であった小島武さんが院長を務める堀ノ内病院だった。今思えば、それが新たな、そして予期せぬ人生のスタートラインだった。







