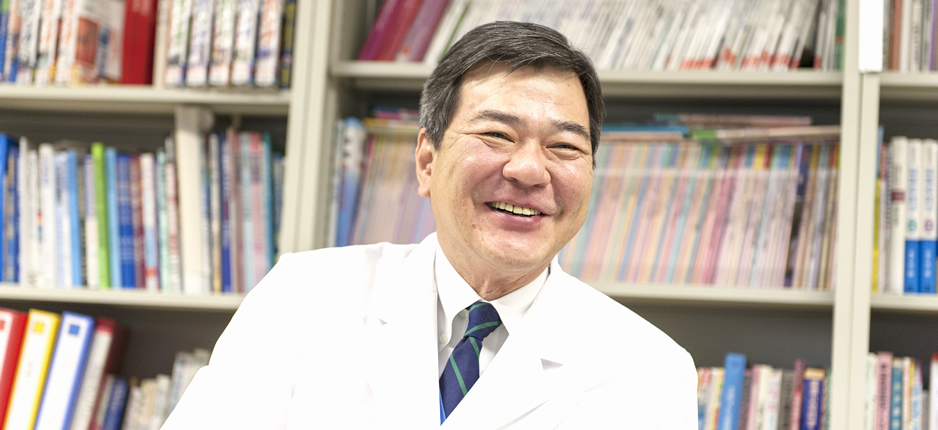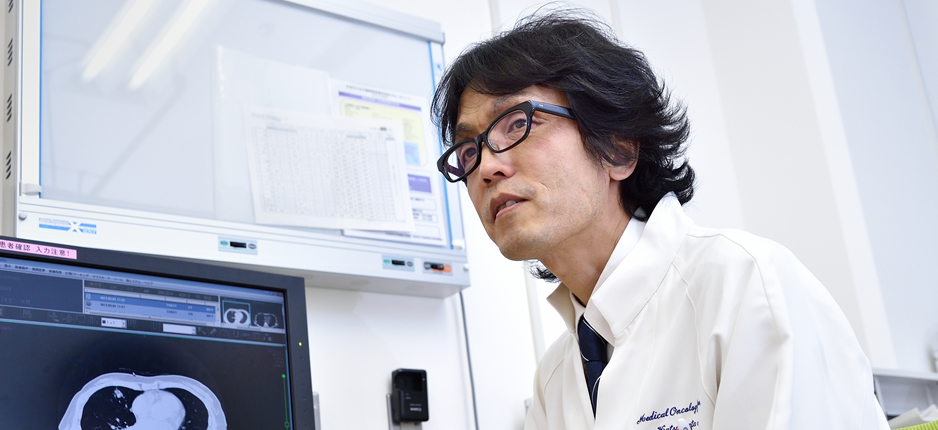試行錯誤を繰り返し、患者・家族を謙虚に支える
◆在宅看取り率75%以上 でも臨終には立ち会わない
話を現在に戻そう。
小堀さんは「在宅での看取り」が多い。前述の著書によれば、在宅医療に取り組み始めて13年後の時点で、臨終にかかわった患者は355人。このうち自宅での死亡者数(在宅看取り数)が271人、病院が84人。約4分の3を在宅で看取っている。
「在宅医療を始めたころは、僕自身に経験がないので、急変時に救急搬送をするか、自宅で看取るかという判断は、ほとんど本人と家族の意向に従っていました。結果、3年目までは在宅死と入院死がほぼ同数でした。ところが、あることがきっかけで、患者や家族の意向に全面的に従うことが必ずしも患者本人の最期の希望を代弁することにはならないと確信しました。以来、私の看取りに対する方針を、患者、家族に話すようにしたのです。そうし始めた2008年を境に、入院死と在宅死の数が逆転し、次第に在宅死が増え始めました」

その“きっかけ”とは、長男夫婦と暮らす101歳の女性患者の看取りだった。ある日、突然ベッドに上がることができなくなり、小堀さんが訪問診療を依頼された。女性は食事量が低下し、3日目に目を覚まさなくなった。当初は在宅で看取る方針だったが、女性が息を吐くときに発するかすかな息づかいを、長男が「母がかわいそうで耐えられない」と、急きょ入院を要請し、堀ノ内病院に救急搬送した。
入院後は中心静脈栄養による栄養管理を行い、併発した肺炎に対して気管切開をし、人工呼吸器を装着した。女性は命を長らえたが、家族は入院の約1カ月後から見舞いに来なくなった。女性は集中治療室で10カ月あまり独り生き続け、その死は宿直の看護師によって確認された。
もう一つ、末期の膵臓がんだった80代女性の例もある。肝臓に転移が見つかり、入院。小堀さんは病状を見て、息子の理解を得てから「自宅に戻って夫婦2人の時間を過ごしてはどうか」と提案した。しかし女性は「こんなにだるいのに、家に帰っても主人のごはんを作れません。元気になってから帰ります」と退院を断った。そして1週間後に亡くなった。
「それぞれ、患者さんが迎えることができたはずの死と、現実に迎えることになった死の差を強く感じます。誰もが自宅で亡くなった時代のように、死を身近に体験できる時代ではないですし、個人の死の受け止め方が異なるのも当然ですが、患者さんや家族の意向はしばしば医学的根拠を無視し、誤解を含んでいます。膵臓がんの患者さんのように、死期が近いのにそのことを自覚しないまま亡くなる人も珍しくありません」
今、小堀さんは、やがて訪れる死について患者や家族に早い時期から説明をすることで、現実を受け入れてもらう土台作りをしている。死が近づくと起こる体の変化や、胃瘻や点滴による栄養補給のデメリットも話す。患者はその話から現実を少しずつ受け入れ、残された時間の過ごし方を考えていく。
そんなかかわりをしながら、小堀さんは患者の臨終には基本的に立ち会わない。「看取るのは家族だから」だ。「患者の死に至る過程に医師がかかわらなくてよい、という意味じゃありません。医師は患者の死に至る過程に常にかかわり、最後の瞬間は“席を外す”ということです。看取りは患者と家族の大事な時間ですから。死ぬ時に医者はいらない」。死が間際にある患者の家族には、夜間に息を引き取っても電話はしてこなくていい、と伝える。「僕を呼ぶより、翌朝まで手を握っていてあげる方がいい。朝、電話をくれたら行って死亡診断書を書くから、と」
◆「人間、負けを知らないと人生を完結させたとは言えない」

もちろん、在宅での看取りがベストとは限らず、病院で最期を迎える方がいいこともある。どちらがいいか、ではなく、患者や家族が最後の希望を叶えられるように力を尽くしたい、と小堀さんは言う。「でも現実にはいい形で死を迎えられる例はごく一部ですよ。家に帰してあげたいと思っても、家族が許さない、気兼ねして帰れないなど、あらゆる状況がありますから」
定年までの外科医としてのキャリアと比較して、こうも言う。「東大や国立国際医療センターは、個々の医師の力が優先で、手術は結果、つまり勝ち負けが明確で、勝ちもあれば負けもある。僕自身、他の医者の手術の失敗をリカバーしたとか、合併症をこれくらいの率に抑えられたとか、まずまずの結果、勝ちを残せたとは思う。しかし、在宅医療の世界では、医者だからと、感謝されることもほとんどないし、尊敬もされない。よかれと思ってやってもなんでそんなことをするのかと、家族から激怒されることもある。そして皆、亡くなっていく。この世界では僕は負けてばかり。常に『負け戦』なんですよ。でも人は皆、そうして死んでいくわけで、死と向き合うのが医者の使命、宿命であるなら、在宅医療、訪問診療の世界を知らなければ、医者の仕事を全うしたとは言えないんじゃないか」
また一つの例を挙げてくれた。「同僚である若い医師の素晴らしい緩和ケアで、希望がかなって帰宅した終末期の女性が予想以上に元気になり、彼女の高齢の旦那さんは妻のために、毎晩一生懸命夕食を作った。1カ月後、旦那さんが過労で倒れ、奥さんは結局、病院に戻って亡くなった。『ごはんなんてどうでもいいよ』と言っても旦那さんは聞かなくて。最後は『俺はもうダメだ』と精根尽きてしまいました」
現代の在宅医療に緩和ケアの知識、技術は必須だ。でも現実には、優れたケアが結果的に患者の希望を摘むことすらある。「正解のない世界」での試行錯誤を小堀さんは「負け」と表現するのだろうか。ただその言葉からは、敗者の悲哀や悔しさより、謙虚に患者と家族を支える優しさがにじみ出る。
「負けるのは好きではないけれど、人間、勝ちばかりで負けを知らないままでは、人生を全うしたとも言えないんじゃないか。この世界で13年間以上やってきたことは、僕自身にとっても意味があると思っています」
◆止められぬ流れに流される最後の日々を共に過ごしたい

2006年、在宅療養支援診療所制度が創設され、多くの診療所が訪問診療を手掛けるようになった。しかし仕組みが整うほど、現場は効率化が進み、個々の患者に合わせて付き合い方を変える小堀さんのようなやり方は難しくなる面もある。
「制度ができ、在宅医療をビジネスチャンスととらえる医師もいます。そうした人は私たちのやり方には踏み込んできません。看取りは医師にとってもきついですから。精神的にも、肉体的にも。それに口幅ったい言い方ですが、正解がないからこそ、医師の人間力がものを言う世界です。人生経験も必要で、僕が患者と一緒に酒を飲む、などというつきあい方ができたのも、この年齢になっていたからで、同じことを若い医師に望むのは無理があります。だから、効率化が進むことも仕方がない面がありますね」
そして最後にこう言葉を重ねた。「僕は若い人に自分のやり方を継いでほしいという気持ちが、残念ながらないのですよ。ほら、犬猫と子供と若者が苦手だからね」
ニヤリと笑う小堀さんを見ると、その言葉は虚実相半ばするものではないか、と思う。1人で走り始めた堀ノ内病院の訪問診療も、今は5人体制だ。小堀さんが望むと望まざるとにかかわらず、その背中を見る若い医師はいる。
小堀さんの著書の最終ページは、次のように結ばれている。
――「死を怖れず、死にあこがれずに」だれにもとどめることができない流れに流されてゆく患者と、その一人一人に心を寄せつつ最後の日々をともに過ごす医師、そのような患者と医師の関係があってもよいのではないか。それは私の見果てぬ夢でもある――
その夢は、小堀さん自身からも離れて、次の世代の誰かに引き継がれていくのだろう。