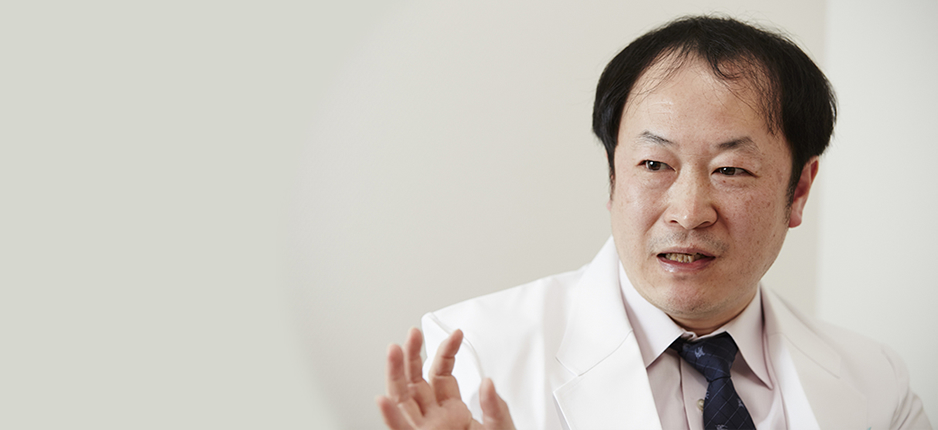1998年当時、総合内科医をめざす医師の選択肢は

動機と熱源を理解するために、プロフィールを読み返してみた。
1998年、順天堂大学医学部卒業。同年、東京都立広尾病院(以下、広尾病院)に入職し、初期研修医となる。
「当初から大学医局に残る気はなく、スーパーローテートで総合内科が目ざせるプログラムを探しました。当時の卒業生の中では、そういう選択をする者は全体の1割もいなかったと記憶しています。試験を受けてまで医局の外で学ぼうなんて発想自体がなかったのです」
現在施行されている初期臨床研修制度が導入されたのは、2004年。皿谷氏の卒業年次はその6年前だが、ジェネラルな研修プログラムがなかったわけではない。実質的に卒業と同時に専門科を決めなければならないストレート研修に疑問を持ったいくつもの医療機関で、内科全般を効率的に学ぶためのプログラム作りの試行錯誤が重ねられていた。
「内科医としての総合力を身につけたい」と目標を定めた皿谷氏は、文字どおり脇目もふらずに広尾病院で初期研修医としての2年を過ごし、次いで東京都立駒込病院(以下、駒込病院)で後期研修医としての3年を過ごした。
努力があれば出会いも幸運も必然と思えるようになる
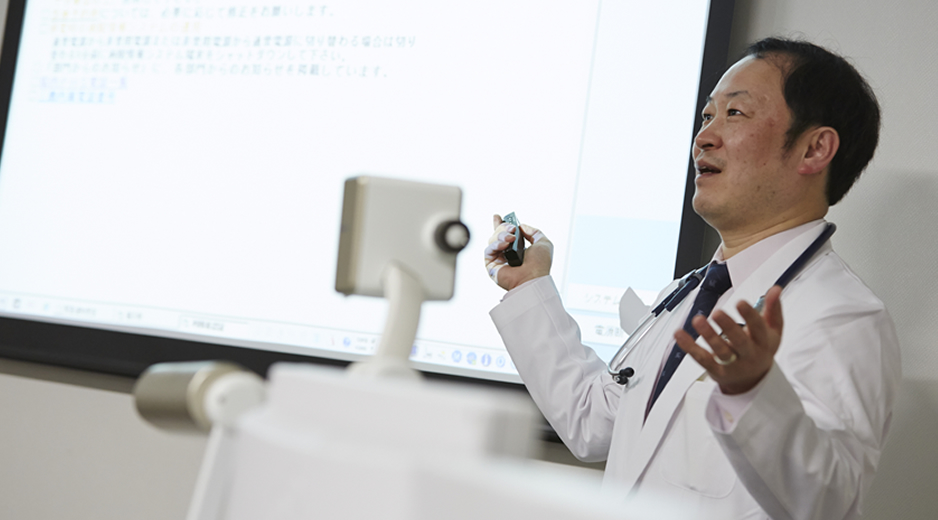
皿谷氏は、インタビューの中で、繰り返しこの5年間への感謝、出会った人々への感謝を口にした。 「卒業時に漠然と循環器への興味、救急への興味を持っていたのですが、広尾病院で仲里信彦先生、駒込病院では青木眞先生といった、今となっては夢のようなそうそうたる先生方にご指導いただき、呼吸器内科と感染症科へ導いていただきました。
また、当時、杏林大学病院呼吸器内科教授であった後藤元先生に引き合わせてくださった駒込病院OBで現杏林大学准教授の石井晴之先生や、実験の指導を受けた新潟大学の中田光教授、中垣和英教授には公私ともに10年来お世話になっています。思い返すと後藤先生は、一言も『うちへきなさい』とおっしゃっていないのですが、いつの間にか自分自身がその気になっていたのが不思議でなりません(笑)」
何たる幸運な出会いの積み重ねであろう。これは単なる出会いではなく、“出会いを呼び寄せている”ように思える。
「私にそんな力があるとは、思いませんね。一つひとつの出会いが、本当に幸運だったような気がしています。
ただ、自分で呼び寄せたとは思いませんが、すべての出会いが必然だったような気がします。あえていうなら、出会いが無駄にならないよう努力したことだけは確かです」
なるほど、努力があれば、出会いも幸運も必然と思えるようになるということか。
正月に課題を書き出す習慣の成果は

皿谷氏の生き方に触れて、浮かんだ言葉は「無欲という名の貪欲」。出会いに翻弄される人生など御免だと考えれば、ライフプランを描きたくなる。どうあってもこうしたいと自分に念じ、こうなるのだけはいやだと行く末を恐怖するものだ。
しかし、この人物にはそこに徒労を重ねた痕跡が見えない。出会った後に努力するそのスタイルが、出会う前の自然体を形成しているのだろう。
一見、無欲だ。しかし、形成されているのは貪欲さきわだつアウトプットの数々。そのコントラストが、あまりにも強烈だ。
「こう見えても、毎年お正月には、前年にできなかったことを洗い出し、今年の目標として掲げる習慣はあるのですよ。毎年、同じ目標が残っているのが難点なのですが(笑)」
肩透かしを食わせるような冗談で一刻、場を煙にまいた後、引きしまった顔で話を継いでくれた。
「でも、2012年に、項目群のうちの一つを、強い決意のもとで消し去りました。それは、論文執筆です。今書かないと、書けなくなった時に後悔すると気づき、同年のゴールデンウィークから猛然と書いています。今も書き続けています」
無欲で、静かなる邁進が今日も続く
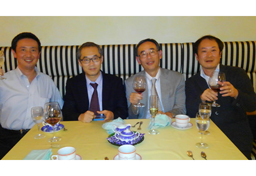
10年後、20年後の理想像などはあるのだろうか。
「まったく考えたことがないですね。突っ走るだけです。前述の論文のペースに関しては、そろそろ蓄積したものを発信しなければという認識があっての自己改革ですが、それ以外の部分は10数年前に医学部を卒業してからまったく変わりません。もうしばらくは、このままでしょう」
振り返って、後悔はないのか。
「一つだけあるとしたら、留学の機を逸したことでしょうか。海の向こうでの見聞には、確かに、強い憧れがありましたから。しかし、よく考えると、今の時代、ネットなどを駆使してそれに近い経験はできてしまっているのかもしれない。事実、欧米に心のつながった仲間は得ていますから。となるとやはり、前を向いて突っ走るだけでしょうか。私のすべきことは」
無欲という名の貪欲をまとった傑物が、最後に独り言のようにつぶやいた。
「突っ走るとか、つながるとか、どうしても自動詞で語りがちですが、後藤先生や、滝澤始先生(現杏林大学病院呼吸器内科教授)が敷いてくださったレールがなければ一歩も前進できなった部分もあるんです。先達への感謝を忘れず、その恩を後進にリレーする意識は持たなくちゃならない」
この、静かなる邁進が大きな業績を世に示す日は、そう遠くない未来にやってくるはずだ。