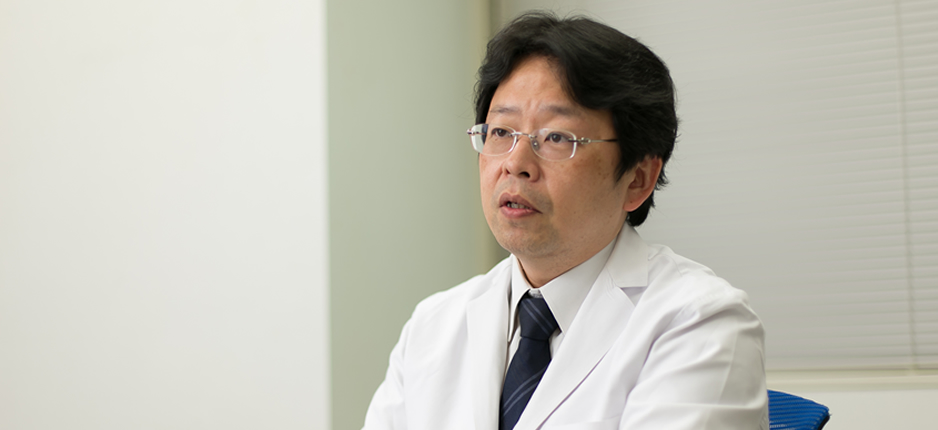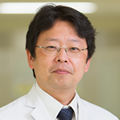かかわった患者さんがよくなると、認めてもらえる
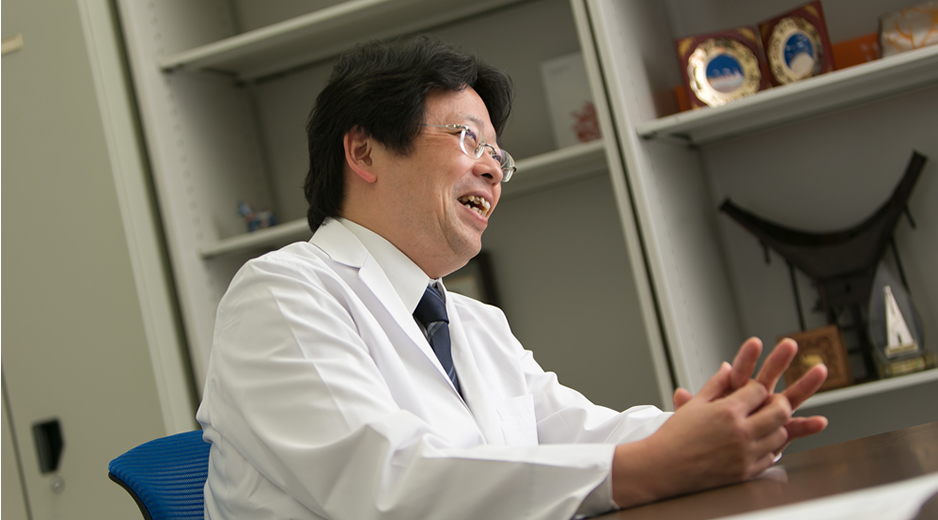
米国での過酷な修業を2年で終え、着任したのが静岡県立静岡がんセンター(以下、静岡がんセンター)だ。
「当時日本に数あるがんセンターのなかでも、感染症科をつくろうとしていたのは静岡がんセンターだけでした。そこへ招聘されたのは非常に名誉なことだと感じました。
同院は感染症への問題意識も理解も深く、チーム医療を駆使して患者本位を貫いています。
総長以下全員が治療のために粉骨砕身しており、尊敬に値する病院でした。
意気に感じた私は日曜日にもべったりと在院するようなスタイルで、学びながら仕事をしていました」
同院にはいい思い出が多くあるとのこと。
「米国への留学後、一本立ちして最初の勤務地で診療科の立ち上げを任されたので、大変なことも多くありました。しかしとにかく学ばせていただきました。理想的な先輩や上司ばかりで、今も感謝に堪えません。現在も多くの方と交流があり、有益な助言をいただいています」
ただし新しい診療科の立ち上げには、当然のように逆風もあった。何といっても、日本ではまだ馴染みのない診療科である。しかも、すべきことの筆頭に抗菌薬制限などの改革、改善があるのだから。

「もちろん反発はありました。居心地の悪さを感じることもありました。『若僧が何を言っている』と怒られたことも数限りありません。ただ静岡がんセンターでは、かかわった患者さんがよくなると認めてもらえるんです。明快でした。感染症科が患者さんのためになる診療科だとわかると、感染症を疑う兆候があればすぐに感染症科を呼ぶ、検体の提出や抗菌薬の変更等は感染科に任せるなど、さっさと必要なところに分業体制までつくり始めました。多くのがん専門医が『感染症科がかかわると患者さんの予後がいい』とシンプルに評価してくれるようになりました。
優秀な臨床医というのは、こういうものなのかと感銘を受けたことを覚えています」
「感染症は誰にでも診られる疾患」という認識を払拭すべき
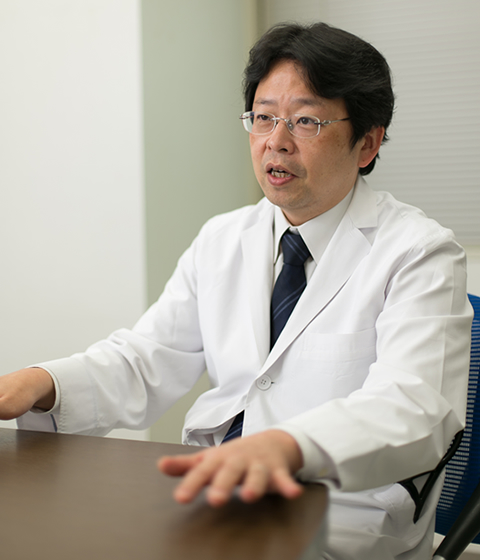
日本における、感染症科の一般的な認知について。
「臨床経験への自負を背景に、『感染症は誰にでも診られる疾患』と考える医師がまだ多いようです。専門家の立場からいわせてもらえば、現代の、最先端の感染症学は専門とする私たちでさえキャッチアップするのが容易でないほど難易度が上がっており、あまつさえ院内感染の難しさを考えると、度を超した楽観には警鐘を鳴らさざるを得ません。
診療科それぞれに他科にはない技術背景を持ち、その上に成立した独特の感染症対策があるのも知っていますが、そろそろ標準化への意識も高めるべき時期かと思います。医師の技量の差が感染症対策の差となり、患者さんの予後に違いをみせてはいけないと思います。標準化の仕組みづくりに、感染症専門医がもっと力を発揮すべきだと考えています」
抗菌薬は人類の資源である。だから、耐性菌をつくってはならない

米国とくらべると、日本の病院の感染症医の数は少ないといわれる。大曲氏も「まだまだ少ない」と感じている。サイエンスとしても地味で、がんや難病のように研究費が落ちる領域ではない。しかし、ここ数年で徐々に問題意識が共有されるようになり、病院での院内感染対策が加算の対象になったり、感染症科を新設する病院が増えたりと追い風が吹き始めている。
「追い風は追い風として喜ばしく思いつつ、気になることはいくつもあります。たとえば、高齢者を多数収容している長期療養型施設の院内感染対策はどうか。現在、専門家の目がまったく届いておらず、インフルエンザ、ノロウイルスなどのアウトブレイクが起こっている可能性が高いでしょう。
そういった、いわば死角にも専門家の目が届き、しかるべき施策が届くような仕組みづくりをするのも私たちの仕事だと考えています」
専門家への取材で、目から鱗が落ちる瞬間がある。大曲氏へのインタビューでも、そんな場面があった。耐性菌をつくってはならない理由について。
「抗菌薬が、人類が細菌から身を守るための貴重な資源だからです。もちろん、無尽蔵ではなく、限りある資源。特に最近は新薬開発のペースが鈍っていますから、希少性は日々増しています。そんな抗菌薬を使い放題に使い、耐性菌をつくってしまうともう使えない。つまり、資源損失です。医療関係者にも、一般市民にもそんな視点でこの問題をとらえてほしいと思うのです」
もちろん、専門家の間ではその認識が定着している。2016年4月には、厚労省から薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン――National Action Plan on Antimicrobial Resistance 2016-2020――も発表された。
「この分野では、関係者が長く努力を続けています。特に農水分野では抗菌薬低減の取り組みがかなり進んでいて、成果もあらわれています。抗菌薬を減らす努力が最も遅れているのは、実は医療界なのです」
闘うべきときは闘う。ファイティングポーズは、まだ解かない

感染症の専門家として、DCCの統括者として、今後の課題は?
「医療現場での感染症対策の実践の底上げです。感染症に関する医師の力の底上げが一つ。もう一つは、その医師の能力だけでは届かない部分を補う仕組みづくり。この2点に注力していきたいと考えています。現場を強くすることが最も重要です。
そういった活動を通して『DCCが世界でも有数の感染症対策のセンターである』と認知されるようになれば、これ以上の喜びはありません。
ただ本当に目指しているのは、こうした活動を通じて安全・安心な社会づくりに貢献していくことです。そこにこそ感染症の専門家の存在意義があると思っています」
帰国した今も、あのファイティングポーズはとり続けているのだろうか。
「もちろん日本では米国と同じ闘い方はしませんが、ファイティングポーズは解いていません。職は、いつ辞してもいい覚悟で務めています。闘うべきところで闘わないと信じる理想は達成できませんし、組織の長として部下も守れませんから」
構えた両拳の間から前方を見据える大曲氏の眼には、感染症医療のあるべき姿がしっかりと像を結んでいるようだった。