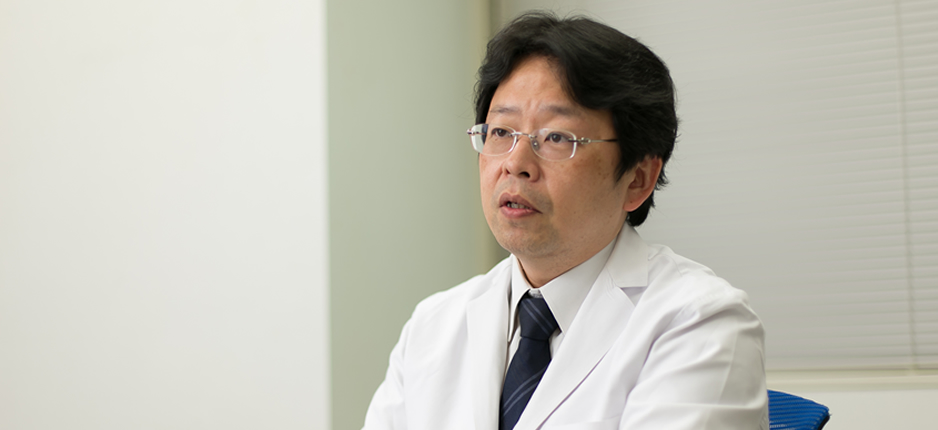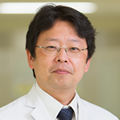臨床の現場には不可欠との認知が進んではいるが、「誰にでも診られる疾患」との誤った認識がぬぐい去れていない感染症。米国で最先端の臨床感染症学を学んだ大曲貴夫は、まだまだ遅れの目立つこの分野で、日本にとってより良い、ひいては世界をリードする「誇れる感染症対策の体制」をつくり上げようと日夜努力している。逆風や無理解が残る日本の医療界で、力強いファイティングポーズをとり続ける医師の決意を聞いた。
国内に4ヵ所ある、厚労省指定の特定感染症指定医療機関のひとつ
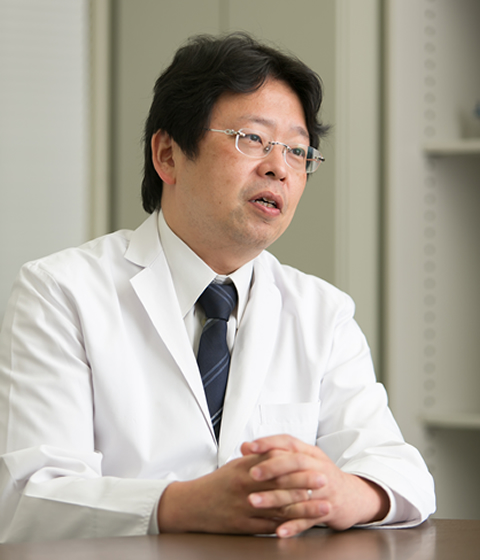
大曲貴夫氏が統括する国立国際医療研究センター病院 国際感染症センター(以下、DCC)は傘下に感染症内科、トラベルクリニック、国際感染症対策室の3部門を持ち、
1)臨床感染症のclinical referral centerとして機能する
2)感染症領域の人材育成/トレーニングへの注力
3)情報の発信源となりネットワーキングに努める
4)国内外の感染症の研究拠点となる
5)実地疫学を実践する
を5つの柱に据え、国内外の感染症に関する包括的、多面的、先進的な取り組みを行う。国内に4ヵ所ある、厚労省指定の特定感染症指定医療機関の一つでもある。
「DCCのもっとも特徴的な側面としてあげられるのが、特定感染症指定医療機関としての活動でしょう。最近メディアなどでもとりあげられることが多くなった国際感染症においては、海外で感染症に罹患した患者さん、あるいは疑い症例を受け入れ診断し、治療しています。その過程で得た重要な知見は研究のかたちで還元します。
診療に関する知見を積み上げつつ、感染防止対策、感染が起こった場合の対策への支援をも担うのが私たちの一番大事なミッションだと考えています」
また大曲氏は政府の各種委員会、検討会にも複数参加し、日本の感染症政策に深くコミットしている。
国際感染症――島国ならではの低リスクに安心しきってはならない

この数年でもMERS、エボラ出血熱、ジカ熱と海外で発生した恐ろしい感染症の話題が報じられたが、四方を海に囲まれた島国である点が奏功するのか、これまでのところ、いずれの騒動も日本でのアウトブレイクには至っていない。
「他の先進国と比べて、島国である点は明らかに有利と思います。また、同じ島国のイギリス/ロンドンとくらべても、国際的な人の出入りが低いレベルと言えますので、国際感染症のリスクは低く納まっていると思います。
ただ、感染症対策に従事する立場の者としては、そういった優位性が国民や医療従事者の危機感の低さにもつながっていて、忸怩たる思いをすることが多々あります。他国と比べる際の明確な指標のないのが難しいところなのですが、いずれにしろ私たちは現在の日本で、『誇れる感染症対策の体制』をつくろうとがんばっています。
そういった考えのもと、DCCではIRS(国内の医療対策支援)としてEメールや電話での問い合わせ窓口を設けました。国内外の感染症危機管理について医療機関や行政、学校等からの相談への対応や情報・技術支援、ときには専門家の派遣を行っています」
海を渡り、日本が学ぶべき臨床感染学を持ち帰る

臨床感染症学は、日本が欧米諸国に大きく後れをとる領域といわれる。そんな状況に憂いをいだいた若手医師が積極的に海を渡り、同領域の先進国である米国で学び、さまざまな知見とノウハウを持ち帰り、国内での活動を広げている。「永い眠りの中にあった臨床感染症学を、徐々に目覚めさせている局面」と表現する識者もいる。
大曲氏も2年間、クリニカルフェローとして米国で学んでいる。
「正直、それほど高邁な理想を掲げて留学したタイプではありません。指導医に『感染症を学ぶなら、米国がいい』とアドバイスされたので海を渡ることにしただけですし、感染症を選んだのも、お世話になった先生が感染症専門医だったから。有り体に説明すると、質問した方にがっかりされるようないきさつです(笑)」
きっかけにドラマはなくとも、渡航先には最先端の臨床感染学の壁と、厳しい臨床研修が待っている。無自覚で乗り越えられるほど甘い日々ではなかったはずだ。
「事前に留学経験のある先輩から『とにかく3ヵ月だけは我慢しろ。そこを乗り切れば、なんとかなる』とアドバイスされていなかったら、ドロップアウトしていたかもしれませんね。とにかく過酷でした。
まず、英会話が拙いので仕事にならない。その上、短時間で膨大な仕事をこなすよう指示される。日本の臨床研修では一人の研修医がどれくらい追い込まれているかは必ず誰かが見ていてくれるもので、何がしかのフォローが期待できます。しかしあちらにはそんなものはありません。実体験があるので明言しますが、人種差別をする指導医だっている。とにかく、すごいところでした(笑)。
先輩のアドバイスどおり、3ヵ月を死にものぐるいで乗り切ったころにやっと、やっていける自信が芽生えました」
ギリシャ人の先輩に学んだファイティングポーズで身を守る
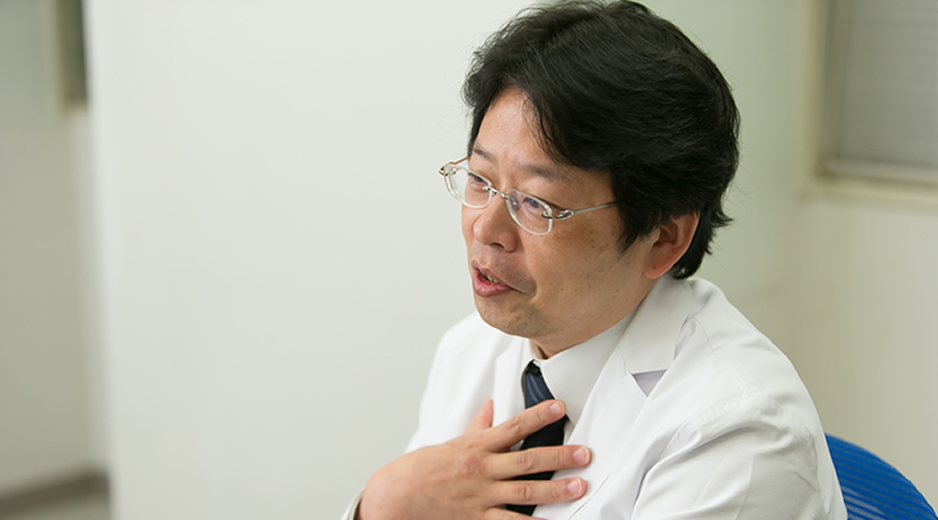
人種差別まである、過酷なだけの日々だったのか。
「いえ、あのプログラムには感謝していますし、あそこで鍛えられたことに自負を持っています。日本にいては絶対に無理だろうと思える数の患者と症例の経験は、今も大きな財産です。
何より、米国の臨床感染学はやはり日本の一歩も二歩も先を行っていました。現在の立場で私がすべきことは、あれに『追いつけ追い越せ』です。追いかけるべき背中を見せてくれている先駆者への敬意は尽きません」
過酷な日々を乗り切った秘訣について、語ってくれた。やはり、ただただ我慢していたわけではないようだ。
「早い段階で、『自分の身は自分で守るしかない』とわかったのが大きかったかもしれません。ファイティングポーズのとり方が身についた。

ギリシャ人の先輩がいました。彼は私の『やわ』な部分を見るに見かねたらしく、自分の苦労談をまじえながらいろいろと助言してくれました。実質的に彼がファイティングポーズの師匠です。闘い方は目前の敵にパンチを見舞うだけが道ではない。ときには敵の頭越しに彼らの上司と交渉する方法論だってある。そういうことを、親身になって伝授してくれた仲間がいたのは幸運だったと思います。
そんな仲間に恵まれ、いい指導医にも出会え、苦手だったプレゼンテーションもこなせるようになって、2年目の終盤には何をしても気持ち悪いくらい褒められるようになりました。ウラがあるような気がしますが(笑)」