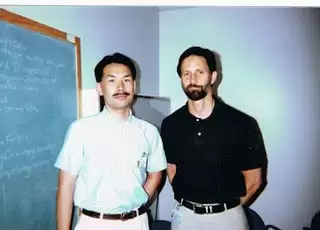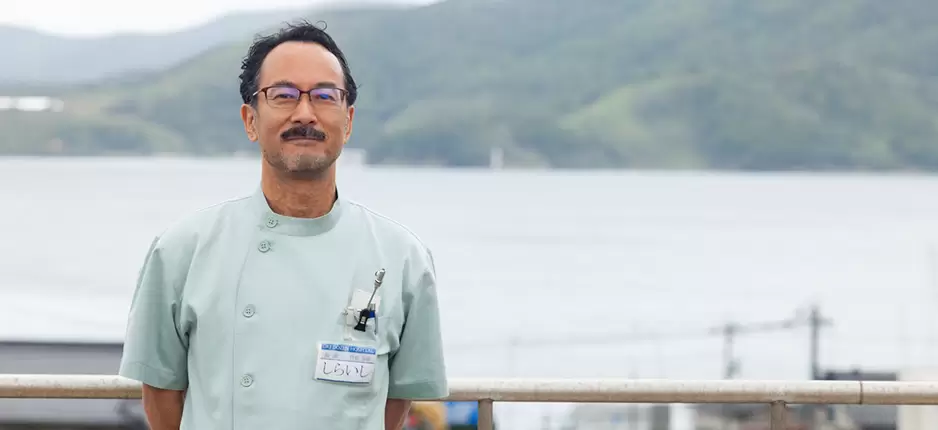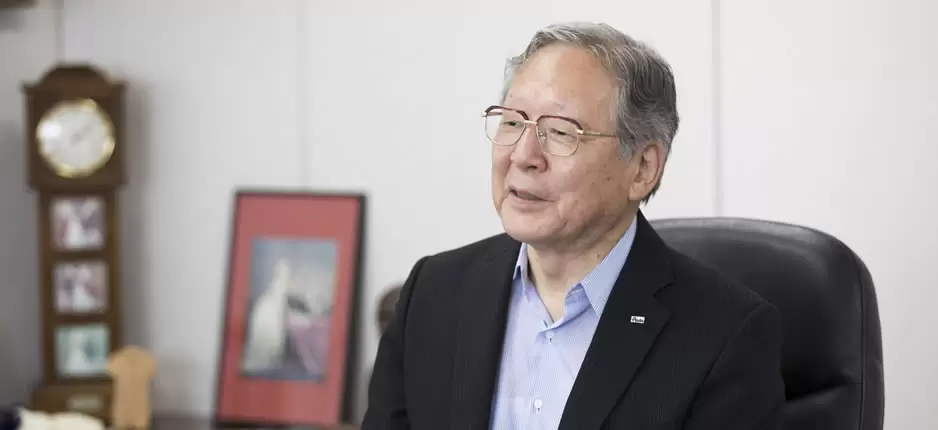日本のこどもたちはけっこう良くない目に
遭っているのではないかと危機感を覚えました
◆小児救命救急・集中治療における日米の格差
米国の小児救命救急・集中治療は、日本と比較にならないほど進んでいた。
小児救命救急・集中治療という分野が小児循環器や小児神経などと同列にサブスペシャリティとして確立され、専門医もいた。そして、チーム医療を徹底している点も日本の医療との大きな違いだった。日本のように主治医が一人で患者を診て、周囲は口を出さないというやり方とは真逆だ。
重症の患者はPICUに入れ、気道や呼吸や循環のことを集中治療医が診ながら、主治医と共同して治療を行う。それぞれの専門知識を生かして一人の命を救うという医療が当たり前のように行われていた。
◆EBMも集約化も実践されていた米国

科学的根拠に基づいた医療(EBM:evidence based medicine)も既に実践されていた。指導医たちからは常に「そのやり方ではダメだ。こうやってみろ。論文にもこう書いてあるから」と根拠が提示された。日本で行ってきた方法とは違うことが多く、初めは半信半疑だった。しかし、指示通りにやると必ず患者の状態が良くなった。繰り返し教えられるうち、「自分の『手癖』ではなく、ちゃんと論文を読んで、そこで結果が出ている治療をすることが患者のためになることを実感しました」。
日本では今ようやく、成人も含めた医療の中に、チーム医療とEBMが定着してきた段階だ。主治医が自分の思った通りに一人で進める医療から、ガイドラインに沿い、医療安全に配慮し、チームで行う医療へ。主治医は家族に対応する窓口としての機能を持ち、バックでは各分野の専門家の医師がチームになって高度医療を展開することが一般的になってきた。
また、患者の集約化も徹底されていた。地方の病院で重篤になり、一般の救急外来で対応できないこどもが医療用ヘリコプターでPICUにどんどん運ばれてくる。この体制により、患者の救命率が上がる。日本では、いわゆるドクターヘリの導入など影も形もないころのことだ。
◆小児科医になった理由は「開発途上国のこどもを救いたい」
米国での研修が4年目に入ったころ、植田さんはその先の道として、日本へ戻ることを決意する。
実は、植田さんはずっと、開発途上国のこどもを救う医師になることを目標にしてきた。将来のことを漠然と考えていた高校生の時、なんとなくテレビを見ていた植田さんの目に飛び込んできたのが、アフリカで飢餓に苦しむこどもの映像だった。顔に何匹ものハエが止まっているのに、それを振り払う力すらないやせ細ったこども。その映像を見て、「自分は何不自由なく暮らしているのに、この違いは何なんだ。小児科医になって開発途上国であの子たちを助けよう」と思い立ったのだ。
それ以降はずっとその目標に向けて進んできた。医学部に進学すると、海外で医師として従事するために英語を身につけようと、教科書は全て英語で書かれたものを購入。日本語で講義を聞いて、それを英語に直して理解するという勉強法を続けた。そして、在学中に米国医師国家試験(USMLE)にも合格した。

◆「まずは日本のこどもたちを救う」
しかし、米国での研修が植田さんの志を大きく変えた。「米国の目線で日本を見ると、日本は小児救命救急・集中治療の体制ができていない。そのせいで、日本のこどもたちはけっこう良くない目に遭っているのではないかと危機感を覚えました。開発途上国のこどもたちを助ける前に、まずは日本のこどもたちを救わなければならないと思い始めたのです」
植田さんは、小児救急の診療科を持っていたり、重症の小児患者を多く診ていたりする日本の病院を探して再び手紙を書いた。自分は米国のPICUで小児集中治療医の研修を受けて専門医になったこと、日本で同様のPICUの開設に携わりたいこと――。今度は米国から日本へ、思いを込めて30通ほど手紙を送った。