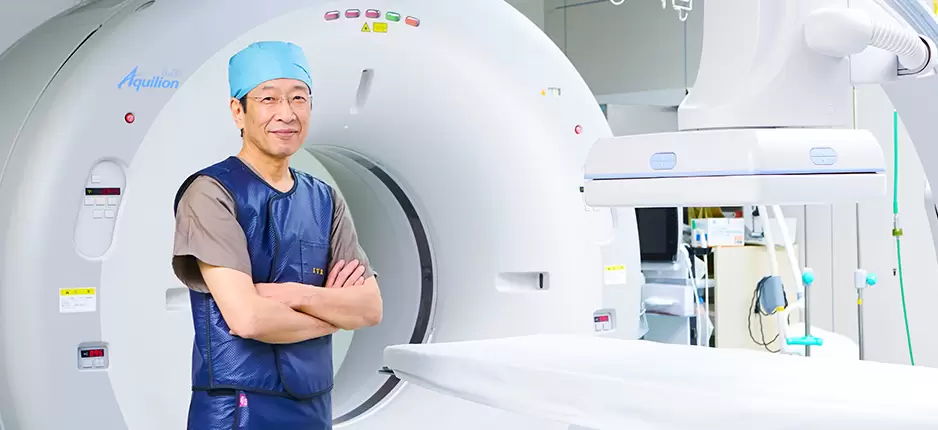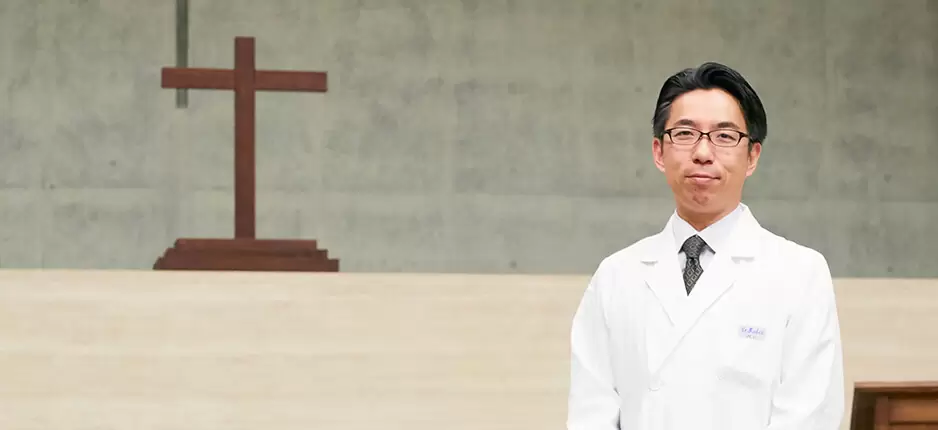日本は2000年代前半まで、1~4歳の小児の死亡率が先進国の中では高いと指摘されていた。現在は大幅に改善しているものの、世界トップレベルの低値の死亡率を久しく維持している新生児の状況とは、大きく異なる。当時からその原因の1つと考えられてきたのが、重篤な小児患者を集中的に治療するPICU(小児集中治療室)の普及率の低さだ。埼玉県立小児医療センター(さいたま市)で小児救命救急センターのトップを務める植田育也さんは約20年前、医師になって4年目の時に米国に渡り、小児救命救急・集中治療のあり方を学んだ。帰国後はPICUの普及と、PICUを核にした地域連携体制の構築に尽力してきた。植田さんの努力が徐々に実を結び、日本の小児医療が変わろうとしている。
指導医の先生方は専門外の患者さんの対応に困っていました
「道が見えていないな」と感じました
◆ロードマップを作って進む
さいたまスーパーアリーナ、官公庁の出先機関が入る合同庁舎、高層のオフィスビルが集まる「さいたま新都心」(さいたま市中央区新都心)に埼玉県立小児医療センターはある。地下1階、地上12階建ての小児専門の総合医療施設で、重篤な疾患を持つ患者に先進的で高度な医療を提供している。
医療センター4階のPICU(小児集中治療室)で、1人の医師が患者の様子を見回っている。ある患者の胸に聴診器を当てた後、その子の顔を見ながらジッと何かを考えている。
「PICUでは、全ての処置は行き当たりばったりではなく、目の前にいる患者に、今何をしたら状態が改善するのかを見極めることが重要なんです。まずゴールを設定し、自分の中の引き出しに詰まっている、これまで診てきた患者さん一人一人の経験データベースから類似のケースの『地図』を探し出します。それを基にロードマップを作って、後はその道をひたすら進むんです」。同センター小児救命救急センター救急診療科長の植田育也さん。小児救命救急・集中治療の第一人者だ。

植田さんが思い描くロードマップは、目の前の患者のものだけにとどまらない。日本の小児救命救急・集中治療のあり方に関して設定したゴールがある。ロードマップの段階は一歩一歩進んでおり、救われるこどもの命が着実に増えている。
◆普及が遅れた日本のPICU
PICUは0〜15歳までの小児を対象にした集中治療室だ。生まれてすぐの新生児が対象のNICUや成人のICUと同様、呼吸や循環、中枢神経、代謝など生命維持に関わる重要な臓器の障害に対して、集中的に管理とケアを行う。
PICUは1950年代に北欧で誕生し、その後、米国で発展した。小児の重症患者をPICUに集約し、そこで治療に当たる専門家(小児集中治療医)を配置して管理とケアを行ったところ、治療成績が向上したのがきっかけだ。
日本では90年代にPICUが登場したが、院内で手術を受けた患者や入院患者のための「箱」としての機能が主だった。小児救命救急・集中治療を専門にする医師はおらず、各科の小児科医が試行錯誤しながら処置を行っていた。専門家のいる本格的なPICUが日本で増えてきたのは2000年代に入ってからだ。植田さんはPICUを国内に広めた立役者の一人として知られている。
きちんとしたPICUが普及していなかった00年代前半までは、日本における1~4歳の死亡率は世界20位台の水準で、先進国の中で最悪のレベルだった。現在、日本を含めた先進国では、00年代前半までと比べて1~4歳の死亡率が3~5割減少した。数値は大きく改善しているのだが、順位をみると、実は日本は今も変わらず世界20位台のままだ。
植田さんは「まだまだ改善途上」と考えている。
◆渡米を決意。送った200通の手紙

植田さんはPICUと小児救命救急・集中治療についての知識やスキルを米国で学んだ。渡米を決意したのは、卒業後に大学病院で小児科の研修医として働いていた時に、当時の日本の小児救命救急・集中治療のあり方に疑問を抱いたためだ。
「大学病院には3次救急の患者さんがたくさんやってきます。指導医の先生方は自身の専門についてのスキルは完璧なのですが、専門外の患者さんの対応には困っていました。失礼ながら、診療していて『道が見えていないな』と研修医として不安を感じることがたびたびあったのです。考えてみれば、指導医の先生方は小児救命救急・集中治療の専門家ではありませんから当然のことなのです。それが当時の日本の状況でした」
米国で研修を受けることを決めたが、米国内から優秀な医師たちが集まってくる中で、そう簡単に受け入れ先が見つかるはずはない。そこで、小児医療の研修プログラムを実施している米国の病院のリストを入手し、片端から抱負を記した手紙(カバーレター)と履歴書を送った。その数は約200通。
「当時は印字の機器といえばタイプライターしかなかったので、手紙を書き始めたころは手紙を1通ずつ打っていかなくてはならなかったんです。それは大変でしたよ。途中でワープロが発売されてだいぶ楽になりましたが」。植田さんは、笑いながら当時を振り返る。
◆シンシナティ小児病院から「採用通知」
約200通の手紙を送り、「面接可」の返事が届いたのはわずか3施設。渡米して各施設の面接を受け、そのうちの1施設から「採用通知」をもらうことができた。オハイオ州にあるシンシナティ小児病院だ。小児科医になって4年目に家族と共に米国に渡った。
現在、シンシナティ小児病院といえば世界有数の小児病院として知られている。しかし当時は、小児救命救急・集中治療の研修制度に実績があったわけでなく、植田さんが採用されたのが自院で研修制度を開始した最初の年だった。そのため、「外国人でも何とか潜り込めた」のだという。
4年間の研修で、植田さんは本場の小児救命救急・集中治療のノウハウを身に着けていく。