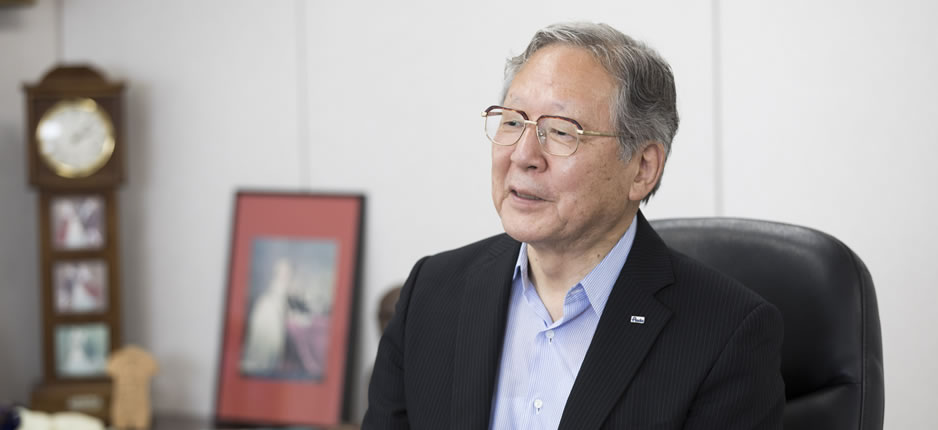心臓病の疑いのはずが、お尻に壊死。辛い体験をとおして、「医療を見た」

驚きの告白を聞いた。岸田氏は、医療過誤の実体験者なのだそうだ。
「小学1年生の健康診断で、心電図検査でひっかかりました。心室中隔欠損の可能性があるとのことで、病院に行ったのですが診断の結果は『よくわからない』でした。エコー検査の精度が現在ほどでない時代だったため、結局10以上の循環器系の病院の門を叩きましたが、やはり検査で結論が出ない。そこで心カテーテルでの検査を勧められました。
問題は、麻酔の注射でした。たぶん、投与する薬剤を間違ったのだと思います。注射のせいで、お尻にぽっこりと穴が空くほどの壊死にみまわれました。
すごく痛かったですよ。しかもかなり筋肉をやられてしまい、計10回ほどの手術が必要でした。その手術も、局所麻酔でとても痛かった。結局その年は、半年ほど学校を休むことになりました。心臓は幸い問題なしでしたが……」
小学1年生の身に起こったこととしては、かなり過酷だ。
「心臓の病気のはずが、お尻の治療で半年休学ですからね(笑)。やっと学校にいけるとなった初日に算数のテストがあって結果は0点でした。嘘ではなく……。“なんだこりゃ”と答案用紙に書かれたのを今でも鮮明に覚えています。なんだこりゃって言われても全然わかりませんでしたので(笑)。ただ、おかげでたくさんの医療を見る機会ができたのです」
医療を「見る」とは?
「半年間病院にかよってわかったのは、『彼は子どもだから』と私には話しかけることなく親とばかり会話する医師と、ちゃんと子どもに向かって説明してくれる医師がいること。もちろん、後者の方が好きでしたし、その診察に小学生ながら勇気づけられ安心感をもらいました。小学校1年生でもちゃんと医師の言葉は伝わってきました。同じお医者さんでも、こうも違うものかと感銘を受けました。検査結果や薬がどうかではなく、患者さんに伝わる話し方のできるお医者さんって素晴らしいと思い、そのような医師に憧れを持つようになりました」
小学校1年生が「医療を見る」とは恐れ入るばかりだ。しかも、痛い思いをして、辛い思いをした経験を夢に代えてしまうとは。視野の広さなのか、克己心なのか、いずれにしろ資質のきらめきが尋常ではない。

学生時代にバックパッカーの旅で訪れた、カンボジアのアンコールワット

米国病院実習のステイ先にて、ホームステイのお礼に和食をごちそうしている風景
総合診療の揺籃期に医学生時代を過ごし、現在を彷彿とさせる行動力を見せる

青年期、岸田氏はここでもきらめきを発してみせる。高校卒業後に、理学部に進学したのだ。
「米国では通常の4年生大学を卒業してから医学部に進む人が多いと聞いたので、私もそんな道のりを歩こうかと考えました。素直に物理学者の夢も捨てきれなかったですので(笑)。高校の時にホーキング博士に感銘を受けた気持ちを優先して、まずは物理学の世界に入りました。物理学がまったく医学に役立たないはずはないとも思いましたから」
この軽やかさは、明らかに新しい時代のものだ。ダブルディグリー、トリプルディグリーを、悲壮感や極度の意気込みのない普通の感覚で目指している。
結局、物理学は2年で諦め、中退。旭川医科大学に入学した。当初の専攻志望は、循環器内科だったそうだ。
「投薬計画などにたくさんの数値が登場するので、数学・物理学が役立つかな、程度の着想でした。しかし、思いのほか患者さんの投与計画は計算どおりにはいきませんでした。
同時に、子供の時の経験から患者さんの全体を診て語りかけてくれる総合診療にも進みたいと思いました。『なんでも診たい』という思いというよりは、『どんな症状であれ自分の目の前に来た患者さんに不都合なことなく対応できるようになりたい』という思いでした。結局後者を選ぶことになりました」
時は総合診療の揺籃期。この分野の泰斗/葛西龍樹氏が北海道家庭医療学センターを立ち上げたのが、岸田氏の医学部4年生の年だった。上記思いから、家庭医療という領域にもとても興味を持った。
「医学部4年時に、米国の教科書を使って診断学の勉強会を立ち上げました。この勉強会は、後に3年間の集大成として、アメリカへの自費留学まで行いました。
医学部6年時には、北海道家庭医療学センターに1週間のエクスターンシップにも行きました」
行動力が光る。後に、思いにしたがって法人を立ち上げる成り行きは容易に想像できる立ち居振る舞いと言えまいか。

多くを学んだ米国病院実習先の病院前にて
多くを学んだ米国病院実習先の病院前にて
「そして、医学部卒業後に手稲渓仁会病院に入職し、初期臨床研修。ここで感染症学と出会った。
「病院が総合内科を開設するのに立ち会えたのが幸運でした。病院は、研修のために沖縄県立中部病院の先生方を招聘したのです。まずは、あの高名な成田雅先生が、専属の指導医ということでいらっしゃいました。初めて学ぶ感染症学は、目から鱗の落ちる思いの連続でした。抗菌薬の使い方から効果判定など他科の先生方と全然違いました。感覚的にやっている感染症診療ではなく極めて論理的でした。身につける喜びと同時に、“日本の感染症診療はまずいのでは?”とも感じ、広めなければならないという使命感も育ったのだと思います」
「感染症をしっかり体系的に学びたいと思い、現国際医療研究センター副院長の大曲貴夫先生がいらした静岡がんセンター感染症科で研修を受けた。そして、総合内科・感染症科を立ち上げ、感染症科チーフ兼感染対策室室長まで務めた後に、転身。
「医師免許を持ち、しかし勤務医でも開業医でもない人物――現在の、岸田氏。今後は、こういった属性を持つ人物が増えて行くのだろうか。
「増えるのではないでしょうか。医学部で学んだことを臨床や研究以外にも活かす道は実際に多くあるのですから。医学知識を活かして医療だけではなく社会に、特に公衆衛生学的な視点をもって横串を入れるような働きで、貢献する人がもっと増えていくように感じていますし、増えていくことがこの変化の社会ではとても重要だと思います。その思いもあり、現在は北海道大学医学院公衆衛生修士課程(MPH)で社会人大学生として学びの場を持っています。医師のひとつのキャリアとしてこのようなニーズがあると感じます。特に日本では先ほども述べたように人口学の側面から社会の変化を考えることは極めて重要です。未曽有の人口減少の背後には少子高齢化という、特に医療に大きな影響があるコンポーネントがあります。この社会変化に対して医師に期待されていることはとても多いと思います。公衆衛生学的な視点をすべての医師が持つことが、これほど重要な時代はないと感じます。そしてなにより、この難局を良い形で子供たちの世代になんとかつないでいきたいという思い、ただそれだけでやっています」
「医師免許を持ち、「医療界のエンパワメント」に邁進する岸田氏。その究極の目標は――。
「SMAの究極の目標ということで言えば、それは国民一人一人の適切な医学知識、特にセルフケアです」
なるほど、視線の先に患者を見据えていたのか。
「義務教育の、たとえば道徳の時間などを使って風邪かどうかの判断や、鼻血の止め方とか、病院へ受診するか否かの判断基準を学ぶカリキュラムを入れる。そうすればフリーアクセスによる外来の飽和の問題が改善されるひとつになるはずです。カリキュラムには、かかりつけ薬剤師の活用法もあるべきですね。『風邪をひいたら薬局で薬剤師に相談する』という行動規範が定着すれば、有名無実になりかかっている医薬分業だって息を吹き返すのではないでしょうか。
『総合診療医が教える よくある気になるその症状 レッドフラッグサインを見逃すな!』(発売元:じほう)というテキストを使って、近々、本格的にセルフケア教育に進めればと思っています」
医療界のエンパワメントの最終目的地が、患者教育。理論と実践を伴う思想家にしか提示できない、瞠目の視点だ。
「心がけているのは、時代の空気を早く察知し、変化をサポートすること。医療には、そんな役割を担うプレイヤーが必要なのだと信じています」

米国病院の臨床実習にて、共に学んだメンバーたちと

米国病院で臨床実習を行ったときのようす
資格・役職
北海道薬科大学 客員教授
日本感染症学会専門医・指導医
日本内科学会総合内科専門医
日本化学療法学会抗菌化学療法指導医
インフェクションコントロールドクター
東京女子医科大学女性医師再教育一般内科プロジェクトメンバー
東京都病院薬剤師会 特別委員
横浜市中区薬剤師会 特別顧問
感染症総合誌「J-IDEO(ジェイ・イデオ)」編集委員
日本感染症教育委員会(IDATEN)世話人
IDATEN北海道 代表世話人