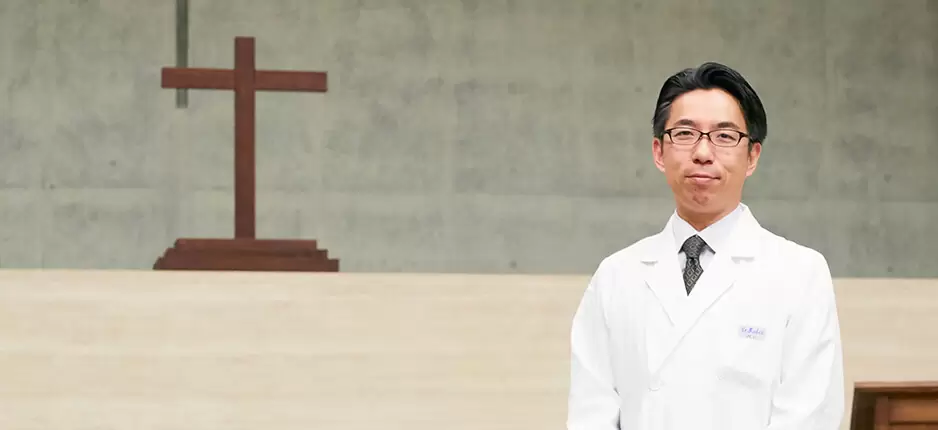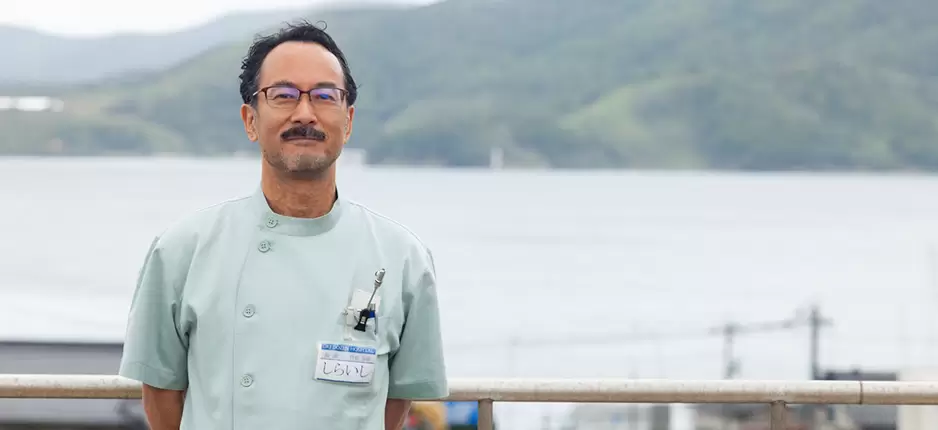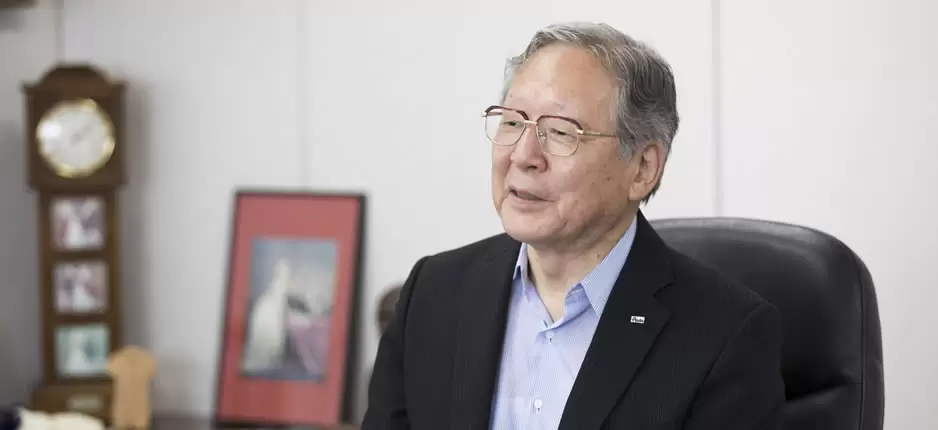4人の恩師。それぞれに違うスタイルのすべてに影響を受けた。
時折、志水氏の口から「そうしん(総診)」という言葉が発せられる。初めて耳にした者は、それが「総合診療科」を意味するとわかるまでに時間を要するが、飲み込んだ後は、その音に、誇りと自負を感じ取るようになる。
尊敬する青木氏に総合診療科という選択肢を指し示された志水氏は、青木氏の紹介で大阪・市立堺病院総合内科部長の藤本卓司氏と知り合うことになり、幸運なことに翌春から藤本氏に師事するチャンスを手にする。

徳田安春先生(写真左から2番目)、
皿谷健先生(写真右)とパーティで
徳田安春先生(写真左から2番目)、
皿谷健先生(写真右)とパーティで
「僕には4人の恩師がいます。いずれの先生にも初期研修医中に出会いました。師の青木先生、そして兄と慕う徳田先生、ベッドサイドでの勝負に執着することを濃厚に叩き込んでくださった恩師である藤本先生、そして米国の父と慕うローレンス・ティアニー先生。4人から学んだこととして共通しているのはベッドサイドへの愛情です。4方それぞれにスタイルは違いますが、大きな影響を受けています。僕にとって、何ものにも代えがたい財産です」
青木氏との交流の中で知り合うことになったティアニー氏には、渡米後エモリー大学の大学院を修了し、ハワイ大学への入職が決まるまでの1年を中心に弟子として間近でその診察技術とベッドサイドでの振舞い、プリンシプルを濃密に学んだ。
「ティアニー先生の偉大さはどこにあるかといえば、『患者さんはもとより、すべてのことに敬意と興味を持つ』という姿勢です。患者さんとの出会いにしてもそうです。口癖は『すべてのcaseはgreat caseだ“Every case is great!”』です。彼は、興味深い症例か否かなどという視点を持ちません。すべての患者さんが興味深いし、敬意を払うべきと思っていらっしゃるし、そして彼らとの交流から彼自身学び、また後輩たちに常に何か重要な学びを教えてくれる教育者です。僕はその姿勢を受け継ぎ、次の世代に伝える教育者になりたいと願って日々行動しています」


患者さんに目を向ける-日常の診療で大切なこと

話題は、医療はアートかサイエンスかに及んだ。
「臨床はサイエンスに基づいたアートであるべき」が、志水氏の論だ。
「僕が“傭兵時代”と呼ぶ米国と日本を往復した2009年~2011年の3年間で、数多くの非常勤(アルバイト)の仕事を経験しました。あるとき、アルバイト先のある病院でひとりの高齢のご婦人を診察する機会を得ました。その患者さんがとても難しい疾患をわずらっていることは直観できました。そんな彼女が風邪をひいて薬をもらいにきたということのようでした。歯はぼろぼろで、着の身着のまま。生活がかなり困難な環境であることは、外観から容易にうかがえました。
ふと、ティアニー先生が必ず患者さんにするように手を握ってあげたくなりました。そのワンポイントの診療の機会でできることもそう多くなく、診察の最後に『おうちを暖かくして休んでくださいね』という言葉を添えて、そっと手をとりました。すると、そのご婦人はポロポロと涙を落したのです。『数十年で、お医者さんに手を握ってもらったのは、初めてだ』と仰ったのです。意外に感じたと同時に、僕自身何かハッとすることがありました。」
医は仁であるということか。
「これは、医学生の前で講演する際に、よく話題に出す個人的な体験談です。手を握ると患者満足度が上がるというエビデンスはありません。必ずしもサイエンスともいい難いですし、そもそもこのエピソードにどんな感想を持つかは人それぞれだと思います。
ただ、少なくともそのとき直感的に、僕は多くの学びを得たと思いました。医学的・科学的に病態にアプローチするというロジカルなアプローチが現代医学では必須であり、それをサイエンスというと思いますが、それだけを提供しても患者さんは十分に癒されるとはいい切れないかもしれません。サイエンスに、少なくとも現時点で裏付けられないものも数多く医療現場には存在します。手を握りたくなった僕、感激したご婦人、『手を握ってくれてありがとう』と言われ切なく思った僕。ティアニー先生の臨床の姿勢を追認した出来事でもありますし、日本の臨床の現場にどこか足りない点に気づかされた出来事といえるかもしれません」
アートの必要性について。
「少なくとも内科の臨床医学領域では、いかに先端分野であっても、医師が患者さんの思いに目を向けることができるか否かが臨床の質を左右すると信じます。このことは、臨床研究にも当てはまると思います。技術者、医学者である以前に、人間としての感受性を磨くことはとても大事です。アートは中核に位置するファクターだと思います」
失敗し、克服しながらも、同時進行で取り組んでいたもうひとつのテーマ。

経歴を紐解き、事実を確認するにつれ背筋に信号が走った。
「僕は数々の失敗をしました。毎回毎回つらい体験ではありましたが、何とか乗り越えました。今となってはすべての失敗に意味があったのだと思えます」
前述した受験の失敗、研修病院選びの失敗に加え、勇躍渡米するも医師免許取得に何度も失敗し、海外での就職にも挫折した人生談まで聴取した。強い克己心とバイタリティは、十分に理解できた。
しかしこの人物にまつわるエピソードは、そこで幕を引かないのだ。そんな挫折と克服の繰り返しと同時進行で、もうひとつの取り組みも遂行していた。
それは、医学教育への興味。
「医学部時代、解剖実習にティーチングアシスタント制度がありました。それに参加し、後輩に教えているうちにわかったのは、実習が大切な理由を自分の経験を踏まえて説明すると、その学生のモチベーションがアップするということです。教育には力があると感じました」
そんな体験を踏まえて、独自に生み出した取り組みが「全国どこでも自分のTeachingをdeliverする」という教育活動/Teaching delivery Project(TdP)だ。招聘に応じて足を運び、惜しげもなく体験値を伝授する同プログラムは、若手医師や医学生の間でたいへんな評判となり、志水氏に指導を仰ぎたいと門を叩く者が年とともに増えて行った。
自身が修業しながら、アメリカでの活動に苦心惨憺しながら、併行して教育への興味と情熱を発露する活動を続けたということである。驚異的という言葉で感想を述べても、決して大げさではないと思う。


12年で――それが高密度な時間であれば、切り開ける出会いがある。

2017年は、志水氏は卒後12年目。本インタビュー前、「卒後まだ若い年数で、これほどの大任を得て大丈夫なのだろうか」と感じたのが正直なところだ。
だが、志水氏のこれまでの期間は、尋常ではない密度を持っていた。診療科を任され、指導、育成を託されるにまったく不足のない蓄積があると、信頼を寄せる大学が現れてもまったく不思議はないとわかった。
獨協医科大学を舞台に果たすべき教育のミッションとは?
「総合診療科開設となると、研修医教育、医学生教育に話題が集まることと思います。もちろんそれはとても重要ですが、僕は今回もうひとつ重要なテーマとして『総合診療の指導医育成』に重きを置いた取り組みをしています。総合診療が全国的に爆発するには、スタッフレベルの育成と増加が必須で、さらにその拠点を守り、率いるリーダーの育成が急務です。
そのため「総合診療スタッフレベルの登竜門」を掲げる獨協総診としては、スタッフレベルにフォーカスを当てた独自の教育プログラムを発展させ、各地から志ある若手の将来のリーダー候補を鋭意募集しています。彼らがここで学び、成長して地元に戻り全国各地でトップを張り、そこをまた教育の牙城にしていく。そのための中心となる訓練の場にこの獨協総診を確立、成長させたいと考えています。そして、獨協医科大学はそのアンビションをサポートしてくださる強力な場所です」

(写真左から3番目)、院長補佐 下田和孝氏(写真右から4番目)と、
総合診療科のメンバーたち
(写真左から3番目)、院長補佐 下田和孝氏(写真右から4番目)と、
総合診療科のメンバーたち
学生時代からの遠い将来的な夢は、「新しいコンセプトの医学教育システムを作って、世界をリードする医学教育を展開すること」だそうだ。 まったく大言壮語には聞こえない。端緒はすでに手にしているように見える。
見たこともないスタイルで疾走する人物が、ここから数年後、あるいは10数年後に見せてくれるはずの見たこともない成果に期待していようではないか。