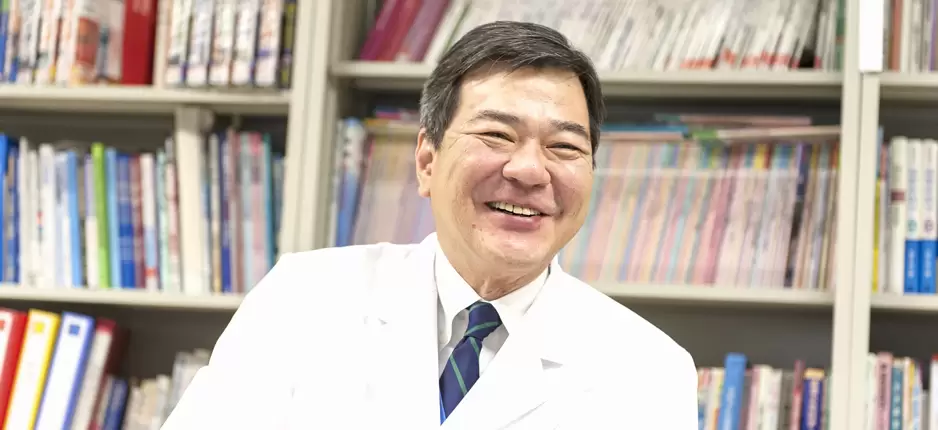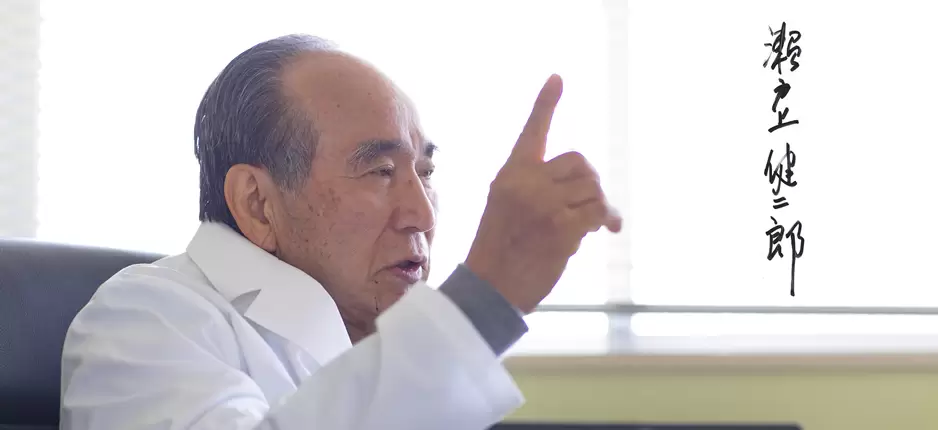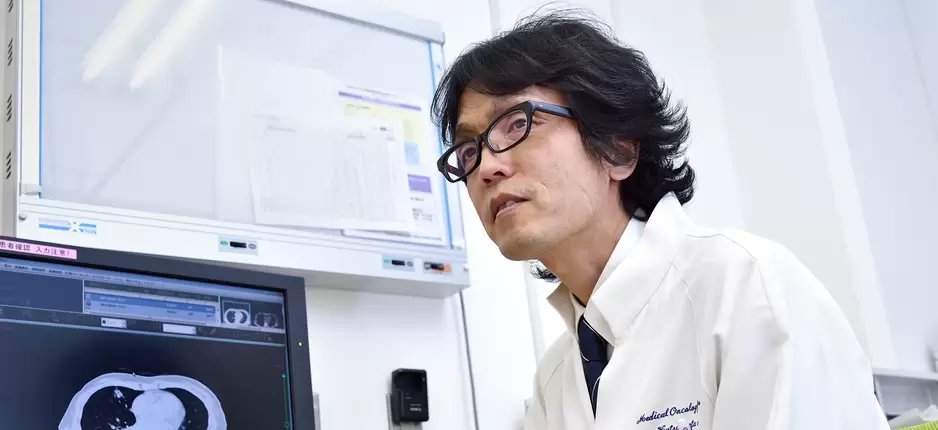まずは主治医と丁寧に話し合おう
少しでも私たちの専門性を理解してもらうように努めよう
◆長野県立こども病院でPICU開設

送り先の1つ、長野県立こども病院から返事が来た。
長野県の中部、わさびやそばの産地で知られる安曇野市に位置する病院だ。地域医療の拠点となっている同病院は、全国でもまれな本格的なPICU開設の計画を立てていた。この実現に向けて協力を依頼されたのだ。植田さんは快諾した。
帰国した植田さんは1998年、同病院の新生児科の医師として従事しながら、PICU開設の準備にとりかかった。2001年、植田さんを含め計4人の小児集中治療医によって、PICUがスタートした。
もちろん、最初から順風満帆とはいかなかった。新しい事を始める場合の常として、周囲からの反発は大きく、理解を得るのに苦労した。当初のPICUは院内の患者を診ることが中心だった。状態が悪化し集中治療が必要な患者を各科の主治医がPICUに連れてくる。しかし、彼らは患者を植田さんたち小児集中治療医に任せようとはしなかった。従来の日本のスタイルで、主治医が患者を囲って一人で治療を始めてしまうのだ。
植田さんらが、「その方法では良くないと思います。こうやった方が……」と指摘しても、「そんなことはない。こちらが正しい」と言って耳を貸してくれない。しかし、小児集中治療医たちも譲れない。最後は「そのやり方では救命できません。専門分野は私たちに任せてください」と強く言い返す。どちらが患者を引き受けるか、どちらのやり方が正しいかを巡って、小児集中治療医と主治医はしょっちゅう怒鳴り合いのけんかをしていたという。
◆1年かけて得た信頼関係
そのような日々が続く中で、植田さんはふと冷静になって考えた。「患者さんに良くなってほしいと思っているのは、どちらも同じ。怒鳴り合うのではなく、まずは主治医と丁寧に話し合おう。少しでも私たちの専門性を理解してもらうように努めよう」
そうしているうちに、植田さんらの思いが通じ始め、「じゃあ、この処置はそちらに頼むよ」と言ってくる主治医が現れ始めた。植田さんたちの治療で患者が回復するのを目にし、主治医は小児集中治療医の技量を認めるようになった。同じことが繰り返され、次第に感謝の言葉を言われる機会も増えた。
「信頼を得るまで1年間かかりました。でも、このプロセスを経て、他科との連携だけでなくPICUのスタッフの連帯感が深まり、チーム医療も熟成されていきました」

◆県全土の医療機関と連携
次に植田さんが取り組んだのが、PICUと地域の病院やクリニックとの連携だった。長野県全土の医療機関と連携し、集中治療の必要な小児患者を長野県立こども病院のPICUで引き受ける計画だ。
長野県は南北約212キロメートル、東西約120キロメートルで、全国4番目の面積を持つ。山に囲まれた地形で、点在する盆地に人が住み、そこに医療圏が形成されている。長野県中部にある県立こども病院からは車で片道2時間ぐらいかかる場所もある。
PICU開設前の3年間、植田さんは新生児科の医師として、重症の赤ちゃんの集約化に取り組んでいた。県内各地の医療圏で重症の赤ちゃんが生まれると、保育器を積んだドクターカーに乗り込んで現地に赴き、その場で救命処置を施す。その後、ドクターカーに患者を乗せて県立こども病院まで連れて帰る。地域の医療機関でも診られる程度にまで回復したら、再度ドクターカーで送り届けるのだ。
当時、スタッフの中で一番若かった植田さんは、ドクターカーによるほぼ全ての搬送に出動していた。そのことで県内各地のさまざまな医療機関の医師と信頼関係が築けていた。
「『これからは赤ちゃんだけでなく、もっと大きなこどもたちも重症になったら、同じように迎えに来て引き受けます』と伝えて回ったら、スムーズに進みました。そして、それが長野県内のシステムとして広まったんです」
約5年が経過し、PICUにおける集中治療と集約化が軌道に乗った頃、植田さんは静岡県立こども病院(静岡市)からPICUの開設を依頼される。
◆静岡県立こども病院へ
静岡県立こども病院に赴任した植田さんは、すぐにPICUを中心とした地域連携に向けて動き始める。
なじみのない土地で、顔見知りの医師も全くいない。そこで、まず、県内の病院の小児科や救命救急センター全てにPICU開設を知らせる手紙を送った。その上で、PICU直通電話「ホットライン」の番号をラミネート加工したものを持参し、あいさつに出向いた。
「重い患者さんがいたら、こちらにご連絡ください」と頭を下げて回った。反応はさまざまで、「なんで来たの? うちでやっているから、そんなのいらないよ」とそっけない対応をされることもあれば、「それはいいですね。ぜひお願いします」と喜んでもらえることもあった。

◆ドクターヘリを持つ2病院と連携
静岡県の小児救命救急・集中治療の体制を大きく前進させたのは、ドクターヘリを導入していた聖隷三方原病院(浜松市)と順天堂大医学部附属静岡病院(伊豆の国市)との連携だった。どちらの病院も多くの重症患者が集まる。しかし、小さなこどもの状態が悪くなった時に、「このままここで診療し続けていいのか」と悩みながらも、適切な搬送先がないためにどうすることもできず、非常に困っていたというのだ。
初めて聖隷三方原病院の救命救急センターにあいさつに訪れた日のことを、植田さんは今でもよく覚えている。腕利きの救急医から厳しい対応をされるかもしれないと不安を抱え緊張していたが、いざ行ってみると、救命救急センターのトップ3人が和やかに迎えてくれた。「よく来たね、待っていたんだよ。協力するから、どんどん引き受けてほしい」と連携を約束してくれた。
静岡県立こども病院は、県西部に位置する聖隷三方原病院と県東部に位置する順天堂大学医学部附属静岡病院の中間にある。
連携を開始すると、県の東西から患者がドクターヘリで次々と搬送されてきた。こうして、ドクターヘリを活用した小児救命救急・集中治療の地域連携のモデルケースが、静岡県でできあがった。