肩痛などの関節痛は、経験者以外には苦しさを理解しがたいものだ。正直者は、「命に別状なければいいじゃないか」とさえ言うかもしれない。そんな意見を持つ人には、千葉県船橋市にある船橋整形外科病院で、早朝玄関前にできる患者の列を見て何を感じるかを問うてみたい。少なくとも、菅谷啓之氏はその苦しみを取り去ってさしあげたいと願った医師のひとりだ。自身が野球による肩痛を味わった立場であったため、迷うことなくこの分野の開拓にエネルギーを注いだ。そして今、その注いだエネルギーが開花の時を迎えようとしている。
1日に100人の患者でも断らない。
肩・肘痛の4つのパターンを見抜く整形外科医
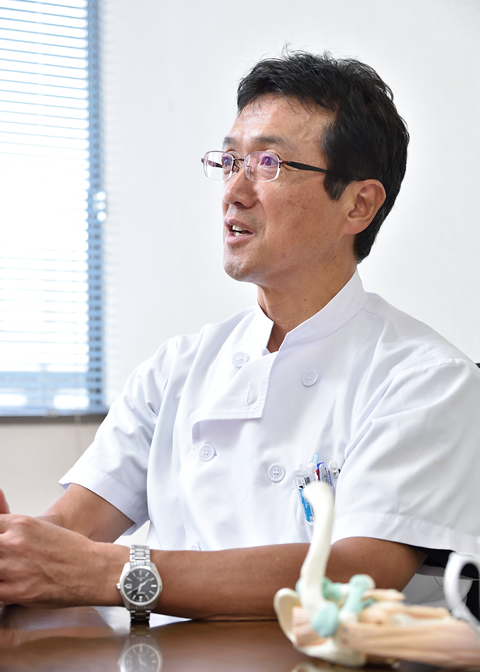
診察方針への質問に、目から鼻に抜けるような返答が返ってきた。「肩・肘痛には、4種類の原因が考えられ、それが構造に起因する場合、手術を実施します。機能に問題がある場合はリハビリテーションへ、炎症が起こっていれば薬剤を処方し、心が関わっていると判断すれば整形外科に心身医療をとり入れている専門家に紹介します」
年間1,000例近い肩肘手術を実施する船橋整形外科病院/スポーツ医学・関節センターのセンター長を務めながら、多い日で150人の外来患者を引き受けている。
「飛び込みの患者さんもまったく断りません。私を頼って来院した方を、追い返すようなことはしない方針です。私は、ひとりでも多くの患者さんを治してさしあげたいのです」とはいえ、150人の患者を診察するとなればひとりあたりの診察時間は……。
「ほとんどの患者さんが2~3分で済みます。少々難解なケースで5分,詳しい説明を要するケースで10分かかるでしょうか。
私の診察には、電子カルテ入力担当のサポートスタッフが2名いて、私の診察所見、診断、処方、再診日などの指示を適確に入力してくれます。初診患者さんの病歴聴取は、研修中のフェロードクターが担当してくれますし、手術のオーダーが必要な場合も手続きはサポートスタッフがする体制になっています。このチーム体制がなければ、これほどの数の患者さんを診ることは不可能でしょう」
サポート体制だけで解決するものなのかという、心中の疑問を察したかのように言葉をつないでくれた。
「肩や肘に愁訴(しゅうそ)のある患者さんには、前述の4つのパターンがあります。フェロードクターがとった問診内容とレントゲンや持参画像を併せて見て、患者さんに何が困っているかを聞けばパターンがわかり、患者さんの性格もわかる。その上で可動域制限テストをしながら夜間痛、安静時痛などの有無を質問するうちに、治療方針はほぼ固まります。必要があると判断すれば、あらためてMRI撮影を決めます」
「ストーリーづくり」の修練を積み、瞬時に診断できる知見とした
続いて何をどう聞こうかと頭を整理しているうちに、さらなる解説が。
「私は、研修医時代にスポーツ医学で高名な元昭和大学藤が丘リハビリテーション病院の筒井廣明先生の外来を見学させて頂いた際に、『ストーリーづくり』の大切さを学びました」
ストーリーとは、要約すれば「患者さんそれぞれの、損傷や障害に至った物語」。痛みの生じた原因を探り、機能改善の道を見つけるメソッドが「ストーリーづくり」なのだそうだ。
「『ストーリーづくり』には、ていねいさが求められ、当初はとても時間がかかります。しかし、ていねいにやってさえいれば、誰にでも身につきます。私の場合はその蓄積が20年以上分あり、パターンの分類ができています。ほとんどの症例がそのどれかに当てはまるので、2~3分の診察であっても、確実にポイントをつかむことができるのです」
立て板に水のごとき解説を聞きながら、「ああ、今、名医と話している」と実感した。
さらに話が進むと、菅谷氏が診断のみならず、治療の名医でもあるのをつくづく理解させられた。1日150人という患者は無為に集まってくるのではなく、「治る」との評判を頼り、こぞって門を叩いているのだ。
東医体の準優勝投手が、自身の経験則から見定めた肩痛という目標

日本のスポーツ医学は、多くの、競技経験のある医師たちの参画によって発展してきた。菅谷氏もその一例といえるだろう。投手として東医体(東日本医科学生総合体育大会)準優勝を獲得した経験のあるアスリートだ。ポジションの宿命か、肩を痛めた経験もある。
「今でもスポーツは大好きですが、医学部在学中の最優先は野球、空いた時間にアルバイトといった生活をしていました(笑)。専門を整形外科と決めて以降は、自然にスポーツ医学に目を向けるようになりましたし、多くの投手が悩む肩痛に興味を持つのも不思議はなかったように思います」
研修医時代に、「ピッチャーの肩痛は、どう治すのか」と先輩医師に聞いてみたところ、はっきりとした返答がなかったそうだ。
「しっかりとした技術が確立していない分野なのだとわかりました。ならば、自分で切り拓いてみようと、俄然やる気が出たのをよく憶えています。
知見を重ねた結果、肩痛治療のためには手術と保存療法の2系統を学ぶ必要があると、明確な目標を立てることができました。特に前者は、低侵襲な関節鏡を学ぶべきだともわかってきました」
そこで立てた志に従って、1996年から今日まで、アメリカ整形外科学会には毎年参加している。
「当時、スポーツ整形でアメリカが抜きん出た存在であったことに加え、最先端情報を得るには英語圏での情報収集が必要だとの判断で、アメリカとの接点を重視しました」
1996年に学び始め、2000年には情報発信の使命を自覚する
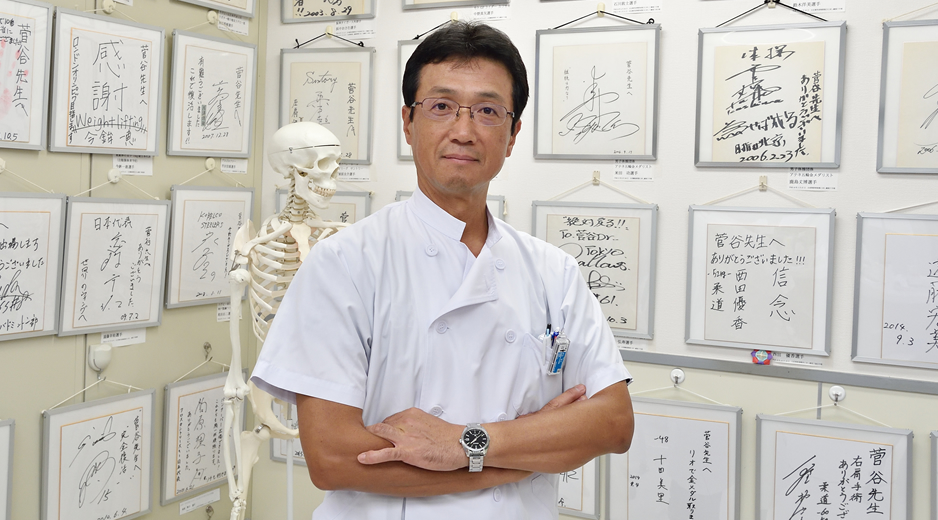
もちろん、関節鏡もアメリカがとても進んでおり、菅谷氏は熱心に学んでいった。関節鏡技術に関する映像教材なども積極的に閲覧した。
「今でも、時折、海外で、『君の関節鏡の師匠は誰だ』と聞かれるのですが、『独学だよ』と答え、驚かれます。入手した映像で学びながら、自分なりの工夫を加えているうち、他から学ぶことがどんどん少なくなっていきました。
1996年からアメリカ整形外科学会に参加し始めましたが、比較的新しい分野であったこともあり、2000年頃には、同学会での講演を聞いても『なんだ、こんなレベルか』と思うようになっていました。これ以降はもう、参考にするのではなく、こちらから情報を発信すべき時期だと確信しました。肩関節鏡が内包する可能性を、より良く引き出すようなコンセプトを見出し、提示する作業に注力していきました」
大旱慈雨(たいかんじう)といったところだろうか。たった数年で、独学でのキャッチアップが完了してしまうとは。持って生まれた素養が分野の求めるものに合致していたのだろう。時代にも恵まれたのかもしれない。事実、1998年には、それまで関節鏡手術の適応外とされていた肩関節不安定症、肩腱板損傷をすべて関節鏡で治療すると学会で宣言し、見事に実現してみせている。

「教科書に従うだけでは進歩はないと考え、許される範囲でのトライ&エラーを繰り返したことは成功の要因と言えると思います。適応外とされている病態に対して関節鏡を有効利用するために、いかに徹底的に考え、『ひらめき』を大切にしたのかが奏功したと感じています」
関節鏡運用の可能性を追求した結果、臨床研究の成果も手にするようになった。肩の脱臼癖の患者の骨がどんな状態か、どんな形かをリサーチしてみると……
「肩の外傷性不安定症には、関節の皿の形がノーマルなもの、削れているもの、欠けているものの3タイプがあると判明しました。レントゲン技師の協力を得て、現在のマルチスライスCTレベルの立体的な画像を撮る作業を積み重ね、100例を収集、解析しました」
その解析結果は、2003年に論文発表。世界中の専門家が新たなスタンダードとして受け入れた。そして2005年頃には、海外から講演依頼が舞い込むようになっていた。







