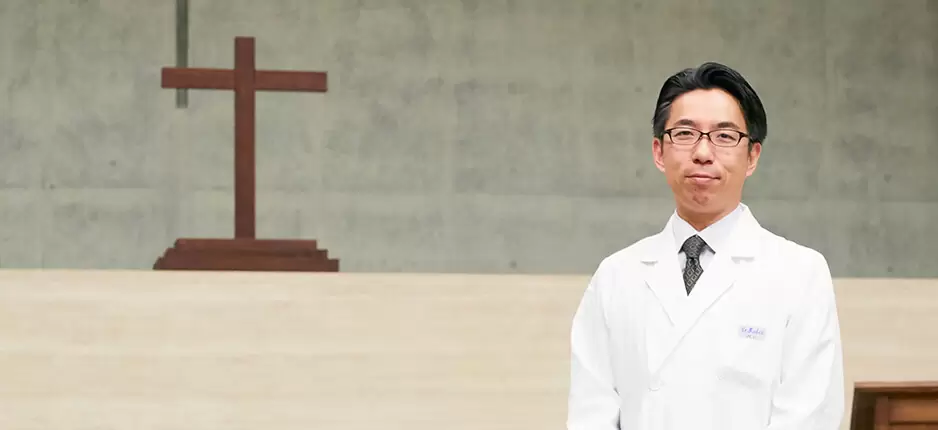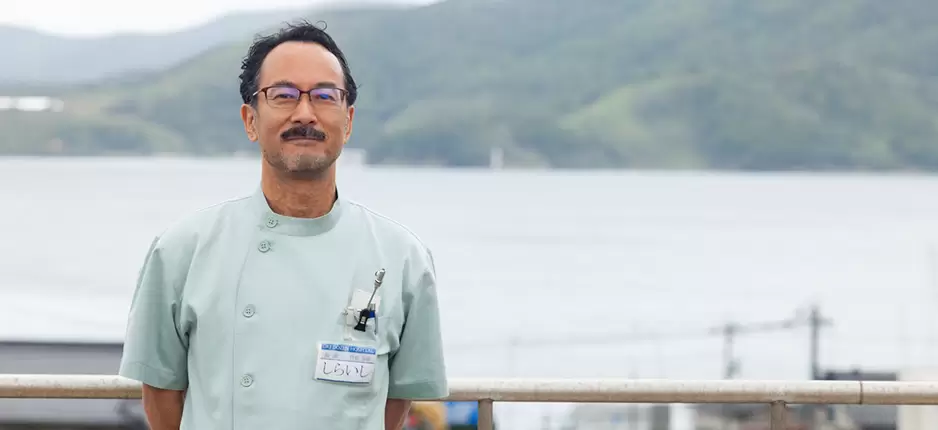憧れの先生が手渡してくれた18年分のカルテ

小西氏は、小学生の頃にはすでに医師となることを心に決めていたという。
「私は0歳児の時から高校3年生まで、18年間、何かあれば近所で開業していた北村芳太郎先生に診てもらっていました。私だけでなく家族全員がお世話になっていたのですが、横浜伊勢佐木町・福富町という繁華街の一角で医療を展開するその先生があまりに素敵な人で、いつの間にか自然に、『ああなりたい』と思うようになっていたのです。
後で知ったのですが、先生は地域医療で有名な長野県の佐久総合病院で、伝説的な院長である若月俊一先生から直接、医療を学んでいます。今で言う、総合内科医の精神がほとばしっていたのでしょうね。私が総合内科医をめざすことになったのは、たぶんそのせいです」

このエピソードには、さらなる挿話が2つある。1つは患者と家庭医の関係が終わった高校3年生の時。
「引退による廃院でした。そして先生は、私が医師をめざしているのを知り『勉強になれば』と、保管してあった私の全カルテを譲ってくださいました。0歳から18歳まで、すべて残してあったのです。感動しました。
ただ、いざ勉強しようと思っても、言語がドイツ語で、記述が見事過ぎる筆記体のせいで、読み解くのに大変苦労させられました(笑)」
もう1つは、その先生は今も移住した大分県で健在。齢92にしてまだまだ元気で、家族ぐるみで定期的に交流しているとのこと。
幸運な出会いに恵まれたようだ。そして、その幸運を無駄にせずに紡いだ動機の豊かさが、必ず結果の豊かさを呼び寄せることだろう。
北へ南へ。自分を信じて進む、アウトサイダーの自覚。

夢を追いかけ北海道大学医学部に進み、もちろんめざすは総合内科医。卒業を目前にしても大学医局には目もくれず、国内でプライマリケアを学べる研修先を探した。卒業年は、初期臨床研修必修化の2年前で小西氏のような志望を持つ医師を受け入れる施設も、それにまつわる情報も少なかったという。
「九州の民間病院に臨床実習に行った際、受け入れ担当医師から『そういう目標があるなら、卒後研修は沖縄県立中部病院(以下、中部病院)がいいのでは』とアドバイスをいただき、すぐに臨床研修責任者の徳田安春先生にメールを出しました。6年生時の7月に1ヵ月間の臨床実習を体験し、『まさに、ここだ』と、翌年からの入職を即決しました」
行動原理について聞いた。シンプルな答えが返ってきた。
「アウトサイダーと言えるのではないでしょうか。結果的に、多数派の人たちと同じ歩みを選択することはほぼありません。大学をわざわざ北海道にしたのも、臨床研修を沖縄にしたのも、『面白そうだから』の一点でした。
周囲の人たちがどう振る舞い、何を選んでいるか、さらに言えば彼らの目に自分がどう映っているのかにも興味はないんです。自分で選び進んだ先に、後悔のない未来が待っていることだけは信じて疑っていませんでした。今も、そうです」
中部病院、南部医療センターで研鑽を積み、生まれてきた興味。

中部病院のとても厳しく、しかしずば抜けてレベルの高い臨床研修プログラムのもと、逞しく育つ。研修は院内プログラムならではの自由度があり、小西氏は3年でローテーション研修を終了して、4年目はチーフレジデントとして研修運営を牽引する立場となった。
「同院の研修には先輩レジデントが後輩の相談に乗ったり、組織の問題点を改善したりといった慣習がありましたが、私の目には『やり方を工夫すれば、もっと良くなるのに』というポイントがいくつか見えていました。病院に進言してみると、『では、やってみなさい』となったのです。研修をしないで中部病院に残る研修医は初めてだったそうです。
臨床研修に身を投じてはみたものの、うまく嵌まることができず思い悩む研修医が各年次に必ずいます。彼らを手助けし、導く仕事に大いにやり甲斐を感じました」
早朝に救急に出向き、研修医が行った診療のチェックと受け入れ患者の診療科への振り分けをする。その後は、朝のカンファレンスの司会を務める。日中は緊急入院の対応、研修医からの相談、医療安全セクションからの研修医に関する苦言を処理しつつ、翌朝のカンファレンスの資料を作る。そして、研修医の教育には何が必要か、何が足りないかを考えながら、次の方策を練る。
そんな1年を過ごす中、病院から「新設される沖縄県立南部医療センター(以下、南部医療センター)の立ち上げを行ってください」との指示があり、翌年赴任した。

左端:一から指導してくれた仲里信彦先生
左端:一から指導してくれた仲里信彦先生
南部医療センターには2年在籍した。
「南部医療センターは県内の4つの医療機関からスタッフを集めてできあがった『寄り合い所帯』。私の主たるミッションは総合内科の立ち上げでしたが、ぎくしゃくした院内の仕組みを改善するにはどうすればいいかが気になって仕方なかったのです」
ここで胸の中にあったモヤモヤが晴れた。
「自分は、病院経営に興味があるのだと合点が行ったのです。中部病院時代からモヤモヤし続けていた感覚の正体は、これでした。『何がわからないか、わかっていない』がクリアになった。書店に駆け込み、経営理論の本を購入して読むと、目から鱗が、音をたてて落ちました」
『あれが理想だ』と言ってくれるような病院作りに参加したい

ついに顕在化した「病院経営への興味」を満たす次のステップは、「医療マネジメントフェロー」なる、国内でも稀なトレーニングプログラムを持つ関東労災病院。小西氏は2008年に、医療マネジメントフェロー兼総合内科医員となった。臨床をこなしながら、院長や事務長レベルの出席する経営会議に同席し、電子カルテシステム構築といったプロジェクトにも参加し、病院経営のスキルを磨いていった。
そして、留学、帰還。卒後15年目にして3つの肩書きを持ち、奮闘する日々だ。
「まだまだ、修業のまっただ中、ですね。疑問や難問と闘いながら突っ走るのみです。走りつづければ、いつか、何かが見えてくるでしょう」
具体的な目標は、まだ見えていないのか。

「ひとつ、間違いなくあるのは、多くの人が、『あれが理想だ』と言ってくれるような病院作りに参加したいという思いです。そこにたどり着くプロセスがどうなっているのかを、今、必死で探しているということになるのでしょうね」
「前史」という言葉がある。「先史」とも言う。ある歴史的出来事の成因となった、それ以前の歴史のこと。通常それは、歴史的出来事成立後の振り返りと分析で突き止められるものだが、時折、目の前で起こっている事象に「これは必ず、何かの前史になるはずだ」と確信に近い感触を得ることがある。
小西氏の奮闘を取材して、それを感じた。これは、何かのエポックの前史の現在進行形なのだと。