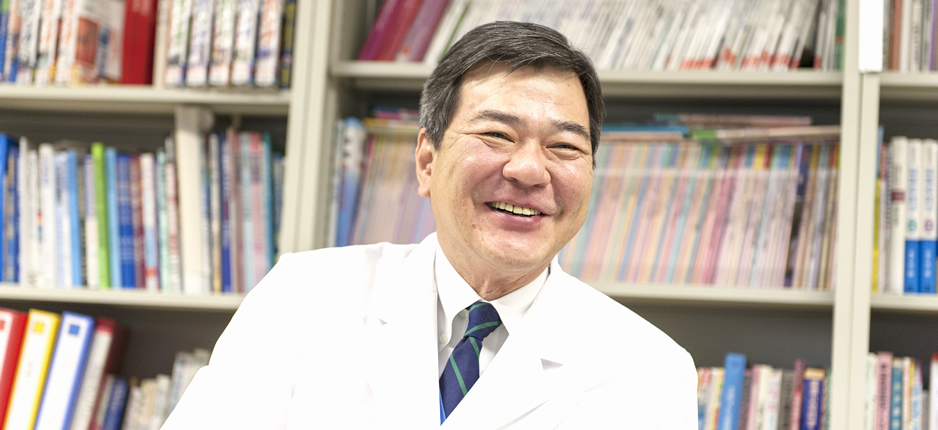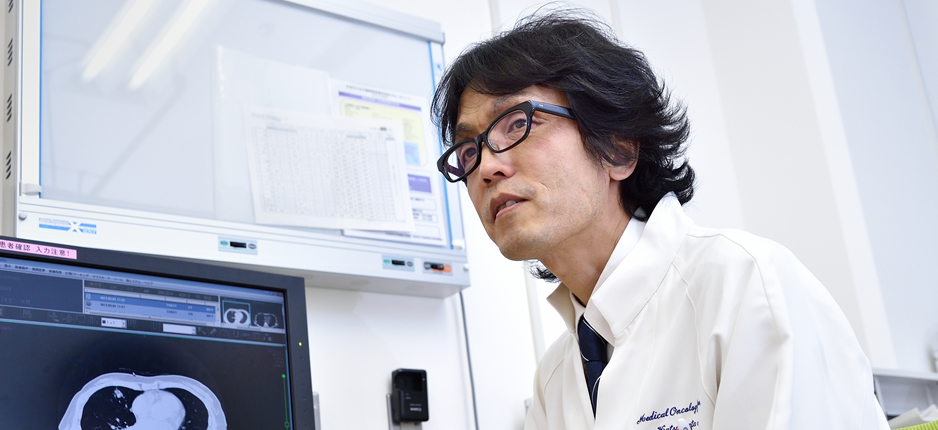認定医制度を発足し、「総合診療産婦人科医」として
全国の病院でお産に関わる仕組みを創りたいと考えています
◆新たな挑戦の先に
恵那病院の産婦人科開設とともに始まった総合診療産婦人科養成センターの挑戦は、まだ緒に就いたばかりだ。
伊藤さんは「母体である地域医療振興協会の中で、地域限定あるいは組織内のプログラム限定でもいいので『認定医制度』を発足させたい。一定の研修期間を条件に、『総合診療産婦人科医』として全国のグループ病院でお産に関わる仕組みを作り、同じような志を持った人たちとその制度を共有していきたいと考えています」と中長期的な展望を語る。

自治医大の卒業生を中心に1986年に設立された同協会は現在、全国各地の70カ所以上の病院・施設を運営。多くが離島や山間地域で、名実ともに日本のへき地医療を支えている。産婦人科医療に関わることができる総合診療医を育てることは、単に産婦人科医の負担を取り除くことではなく、これらの地域のお産を守っていくことに直結するのだ。
◆ALSO普及にも尽力
伊藤さんが参考にしているのが、米国やオーストラリアの研修制度だ。米国では、家庭医の認定取得には産婦人科医療の習得が必要だ。産婦人科が必修でない日本の初期研修制度とは考え方が大きく異なる。またオーストラリアでは、へき地医療を担う総合診療医に対するサブスペシャリティの研修・認証制度がある。実際にGP Obstetrician(総合診療産婦人科医)として働く多くの医師がいる。
伊藤さんは「他の科を希望している医師に産婦人科研修で何を教えるべきなのか、受け入れる側も戸惑うことがあります。でも、少し発想を変えると、産婦人科を学ぶことの意義はとても大きいことに気づくわけです。どんな科の医師でも、診る患者さんの半分は女性。ウィメンズヘルスを学ぶという目的をもって産婦人科での研修を捉えれば、多くの若手医師たちも、意欲をもって取り組んでくれます」と強調する。
伊藤さんが今、自ら講師となって普及に取り組んでいるのが、米国で生まれた教育コース「ALSO(Advanced Life Support in Obstetrics)」だ。
産婦人科専門医だけでなく、助産師、総合診療医、救急医らを対象にしたトレーニングプログラムで、妊産婦の救急医療に関する知識や技術を実践的に学ぶものだ。米国では現在、ほとんどの分娩に関わる医療従事者に対してALSOの受講が義務付けられている。
2008年に日本で初めて開催されたコースを受講した伊藤さんはその後、講師として後進の育成に努めている。「助産師もいれば総合診療医もいて、救急医もいる。その中で、みんながお互いの立場を尊重しながら、お産に関わるあらゆるケースに対処するためのトレーニングを積んでいきます。非常に意義深い教育制度です」
◆軌道に乗ってきた恵那の産婦人科医療
分娩開始から2年がたち、恵那病院での産婦人科医療は軌道に乗ってきた。住民の信頼も得ることができているようで、分娩数、外来数、腹腔鏡を含めた手術件数も増えている。

研修の受け入れを積極的に行うことで、産婦人科の体制も充実しつつある。恵那病院が新専門医制度の産婦人科研修プログラム連携施設になったことによって、今後は産婦人科の常勤医、専攻医ともに人数が増える見込みだ。また恵那病院には総合診療専門医のプログラムがあり、将来そのプログラムで研修予定の専攻医1人が現在、研修の一環として継続的に産婦人科の外来見学・研修を行っている。2019年度は、恵那病院産婦人科が独自に実施している家庭医の研修(期間は3カ月間)に1人が参加した。過去の研修参加者には、恵那病院の外来に関わり続けてくれる医師もいる。
◆恵那から全国へ
足元が固まりつつある一方で、伊藤さんは日本全体の産婦人科医療の先行きには不安も感じている。早くから専門に特化した医師を作る新専門医制度、日本産科婦人科学会が進める分娩施設の重点・大規模化といった流れは、確かに産婦人科医の労働環境改善という視点からは必要かもしれないが、地域の産婦人科医療・ウィメンズヘルスを守るという視点からは伊藤さんの構想とは逆向きともいえるからだ。伊藤さんは「今の流れは、分娩の安全性を高め、産婦人科医の労働環境は改善するかもしれません。しかし、地域のウィメンズヘルスがおろそかになったり、妊婦健診へのアクセスが悪くなったり、妊婦の救急搬送が増えたりするリスクがあります。その中で、セーフティネットとして、総合診療医の産婦人科に関するトレーニング、助産師を中心とした多職種連携、緊急時のシミュレーショントレーニングは絶対に必要です」と強調する。
伊藤さんによって、「地方の産声を守る医療」が恵那で芽生えようとしている。「変わりつつある産婦人科医療の大きな流れの中で、いったい自分に何ができるのかは、まだ模索中です。でも、まずは教育の場を整えたいと思っています。そこで学んだ若手医師たちがそれぞれの地域に戻り、地域の分娩を守るコアになっていってもらうために。今後5~10年の間にそれを実現させることが、僕の使命だと考えています」