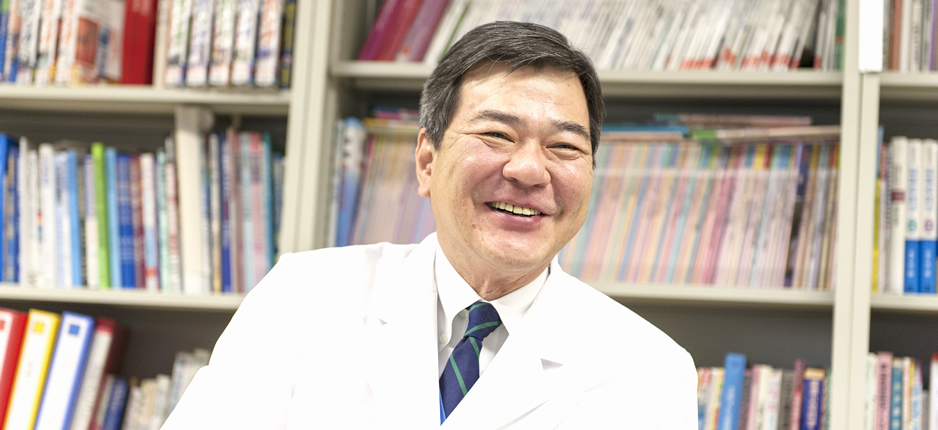新生児の後遺症なき救命救急をめざし、1000g未満で生まれた未熟児に対して、昼夜を問わず不眠不休で向き合っている医療者たちがいる。茨聡医師は、1981年に鹿児島大学卒業と同時にその道に進むと、つねに最前線にあって、タフな仕事の陣頭指揮を執ってきた。
ダイナミックに状況が変化する出生後数時間の救命を使命に

第一人者である茨氏は新生児と向き合う難しさの中に、醍醐味を感じている。
「新生児には独特の疾患があります。母胎内では胎盤で呼吸していたのが、肺で呼吸するようになるので、出生後数時間は、人生で死亡率の高い時でダイナミックにいろいろなことが起こってきます。赤ちゃんは生まれてくるだけで奇跡なんです」
胎児期からの子どもの安全を見守る周産期医療という概念が、日本で初めて産声を上げたのが、実は鹿児島市立病院である。かつて全国でも最下位近くを低迷していた鹿児島県の新生児死亡率は、同院の熱心な取り組みで、1990年代半ばには1000人中1.1人と大幅に改善され、なお低水準を保ち続けている。「赤ちゃんの後遺症なき生存」を基本方針として、チーム一丸となって新生児の安全を守り続けてきたのだ。
「新生児を絶対に助けるとなったら、それを“憲法”として、その方向に向かっていきます。患者は断らない。この子たちを助けるのは私たちしかいないという使命感、誇りがあります」
大学医局に属さず、その道一筋に歩んできた異端の産婦人科医の人生を遡ってみよう。

1956年、茨氏は長崎市で生を受けた。地元の進学校・長崎東高等学校に進み、早稲田大学の理工学部応用物理学科に合格して入学を決めた。75年のことだ。
ところが、一方で“賭け”をしていた。当時、国立大学には、3月初旬に入試行う一期校と、下旬の二期校があり、2校を受験できた。二期校の鹿児島大学医学部に出願。父の親しい知人に医師がいたことに多少影響を受けていた。
大都会・東京で大学生活をスタートさせた後、4月末になって鹿児島大の合格通知が届いたのだ。
「田舎者だから、山手線の満員電車にはうんざりしていました。これを逃れられるならば、別の道の進んでもいいとさえ思えました」
一転、九州に舞い戻った。“消去法”で入った医学部であり、そうまじめとは言えない学生だったが、それなりの成績を収めていた。
日本で初めての五つ子の分娩成功で新生児センターを拡充
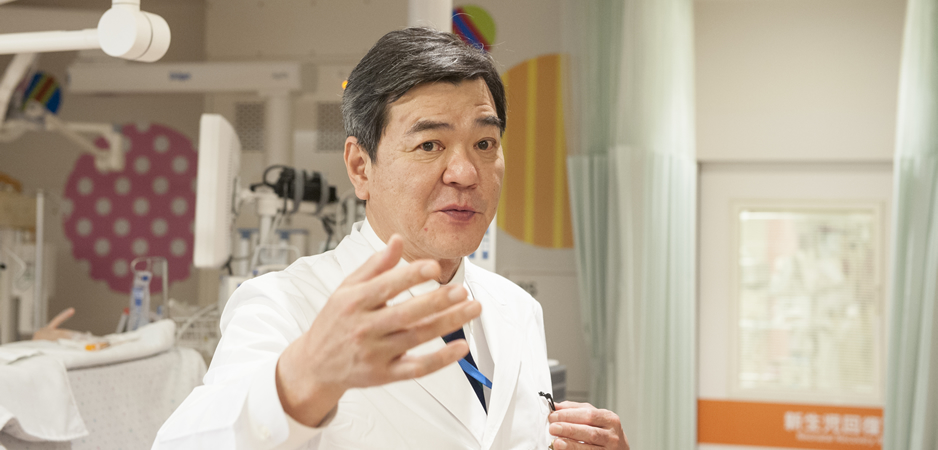
76年1月になって、地元の鹿児島市立病院で5つ子が誕生し、全員揃って生育しているというビッグニュースが飛び込んできた。名実共に地域でナンバーワンの病院といえば大学病院のはずだが、大仕事を成し遂げたのは、市民病院だ。取り上げた池ノ上克氏(後に宮崎大学学長)は、留学先の米国南カリフォルニア大学から帰国した直後の精鋭だった。
市立病院は、周産期医療に重きを置いていた。外西寿彦氏(故人)が、鹿児島大学産婦人科の助教授から70年に同院の産婦人科部長として赴任した当時、県の周産期死亡率は、日本でワースト3に入るほどだった。周産期を専門とする医師は少なく、未熟児の分娩への取り組みは遅れていた。
そこで、「太陽の子」事業と名付けた母子保健事業が展開され、外西氏は、周産期死亡を減らそうと、保健所を回るなどしていた。一方、長崎県には、国立長崎中央病院(現・国立病院機構長崎医療センター)に田崎啓介氏という新生児医療の大家がいて、九州で初となる未熟児医療センターを立ち上げていた。外西の部下たちが、そこに行って技術を磨いていたことが、五つ子の分娩というチャレンジにつながった。
日本ではそれまで、五つ子が生きて誕生したことはなかったため、日々のミルク量や体重がテレビニュースでも報道されるなど、大きく世間の耳目を大きく集めた。これが契機になって、周産期医療をさらに強化するため、県や市、国の助成も受けて78年、最新鋭の設備を備えた、新生児部門(新生児センター)40床(うち9床がNICU=新生児治療室=)を新設し、産科部門(分娩センター)、および母子保健指導室から成る周産期母子医療センターが開設された。

翌80年に茨氏が見学に訪れると、新生児センター内は機械だらけ、「まるで工場だ」。工学部をめざしていた頃の思いが、むくむくと頭をもたげた。案内してくれた池ノ上氏は、実に長崎東高校と鹿児島大学の先輩にあたるという。話が盛り上がり、寿司をごちそうしてもらうなどするうちに、スカウトを断り切れなくなった。故郷の長崎に戻って外科医をめざすはずが、抜き差しならならなくなって、鹿児島市立病院の産婦人科に入職を決めた。
茨氏の関心は、もっぱら新生児医療にあった。
「NICUは大好きな機械に囲まれていたし、何といっても、新生児医療がとても論理的であることに魅せられました」
実は、新生児の治療を、産婦人科が手掛ける医療機関は減りつつあった。日本では戦前、新生児医療を産婦人科が担っていたが、戦後はアメリカ流に小児科が行うことが主流となった。しかし、鹿児島のような地方では、まだ産婦人科が行っていた。これが幸いして、異端の医師人生が幕を開けた。