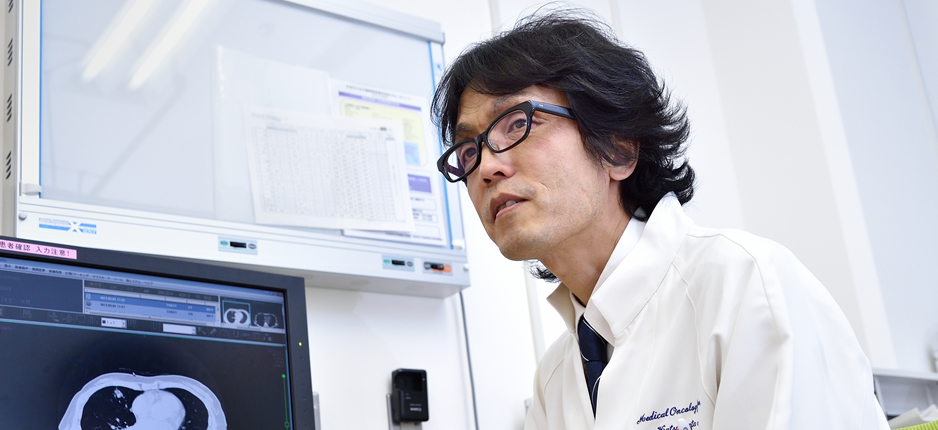「がんとの共存」、「患者はがんサバイバー」といった用語は耳にしたことはある。しかし、その本質的な意味にまで思いが至っていないのが、日本社会におけるがん医療の問題なのかもしれない。外来投与がスタンダードになり、発症後も、治療中も普通に仕事を続けている「がんサバイバー」たちが普通に暮らす欧米と、いまだそうなっていない日本。社会通念の違いは、つまりは医療の質の違い。そんな、かなり強いテーゼが込められたがん医療の昨今を、柔らかな語り口で教えてくれるのが日本医科大学武蔵小杉病院腫瘍内科教授の勝俣範之氏なのである。
腫瘍内科医は、がん医療の総合内科医
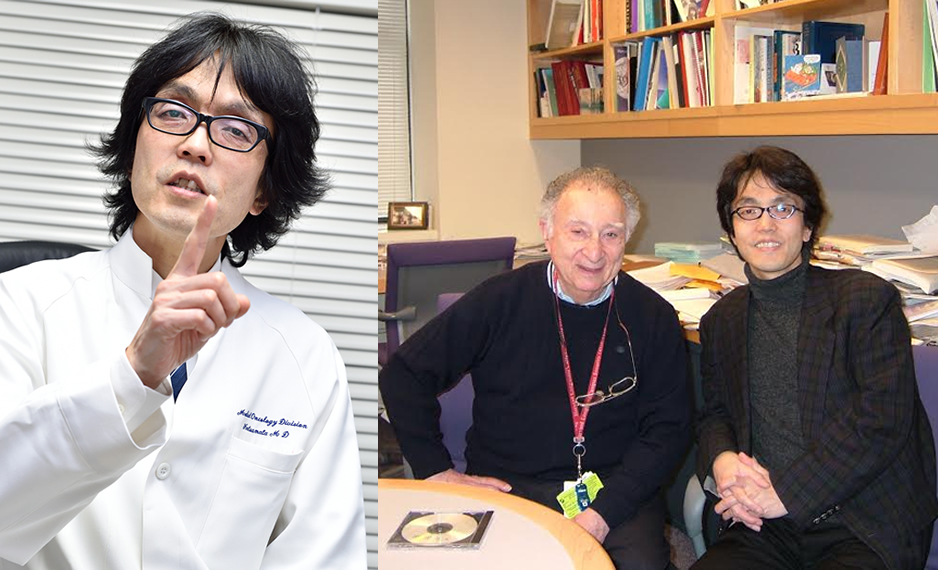
腫瘍内科学は日本の医学界が世界に後れをとっている、いくつかの分野のうちのひとつ。
勝俣氏による後れの見積もりは――
「米国でも、日本でも腫瘍内科学の活性化を後押ししたのは法律。米国の米国がん法(National Cancer Act)制定が1971年で、日本のがん対策基本法制定が2006年であることから、約30年の後れだと考えています。
がん対策基本法制定を受けて、日本の多くの大学医局に臨床腫瘍学の講座ができましたが、10年経った現在も充実しているとは言い難い状況です」
腫瘍内科医の数も、いまだ不足しているとのこと。
「10年で約1000名の専門医が育っていますが、日本で必要と算定されている5000名にはまだ遠く及びません。単純比較すると、約15,000名の腫瘍内科医が活躍する米国の15分の1です。2016年の米国の人口が約3.2億人、日本の人口が約1.3億人なので、人口比で考えても専門医数が米国並みになるには6000人弱の腫瘍内科医がいないといけないことになります」
腫瘍内科医とは?
「私はよく、がんの総合内科医だと説明します。欧米では、がんの疑いのある患者さんはまず、腫瘍内科医に受診します。手術の適応判断も、そこで腫瘍内科医が下します。もっとも重要なのは、患者さんを見捨てないこと。初診から最後まで、患者さんをサポートするのが腫瘍内科医の務めです」
そういったがん医療のあるべき姿や、腫瘍内科医の役割は――
「日本ではまだ、医師でも正しい認識を持てずにいる方が多いですね。
がん医療の黎明期に臓器別の、外科医がこの世界を牽引する図式ができ、今も続いています。この図式は明らかに時代遅れと言えます」
抗がん剤治療を受けながら、仕事を続ける患者が増える
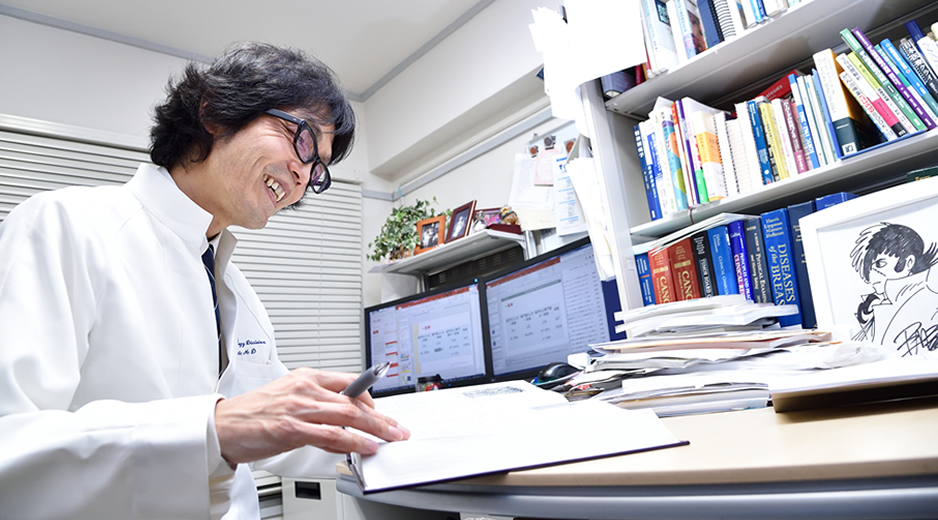
腫瘍内科医に受診すると、患者にとってどんなメリットがあるのだろう。
「端的に言えば、抗がん剤治療です。世界的ながん治療の潮流は、すでに抗がん剤がその中心にあります。大変良く効き、副作用も少ない薬剤が開発実用化され、今も多く誕生している。
それらを駆使して薬物療法を中心とした治療計画を立てるには、豊富な専門知識を有した腫瘍内科医が欠かせません。
いまだ過渡期を抜け出せない日本では、抗がん剤への正しい知識を有した腫瘍内科医が少ない分を、外科医が担っている。残念ながら薬剤および、副作用対策に対する知識や経験が不足した医師が薬物療法の適応判断から処方までを行っているケースが多いため、使いこなせているとは言い難い状況が多々あります。
患者さん側に、『抗がん剤は副作用が怖い』という先入観がいまだ強いのも、そのためです。副作用に対して、最も簡単な対応策は、薬を減量することですが、安易に減量してしまっては、効果も減弱してしまう。減量は最後の手段であり、まずは、副作用を減らすための色々な対応策を講じることが大切なのです。十分な副作用対策も講じないうちから減量してしまうことはよく見られます。」
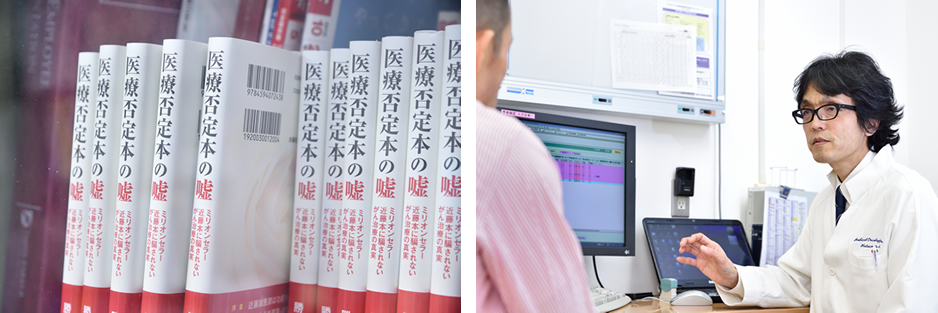
たしかに一般には、「抗がん剤投与で、身も心もボロボロになる」といったイメージがある。
「副作用でボロボロになってしまうのかというと、確かに20年くらい前にはそういった患者さんもいたかもしれません。現代では、副作用に対する薬剤や対応が相当すすんでいて、ボロボロになり、寝たきりになるような患者さんはいません。明らかに前時代のイメージを引きずっていますね。
欧米では、患者さんが抗がん剤投与を受けながら普通に仕事を続けるのは一般的なこと。日本では、外来でできる抗がん剤を、いまだに入院させるといった決定をする医療機関があるようですが、最新の世界的ながん医療の常識に照らせば考えられないことです。入院で抗がん剤をやると、患者さんの生活の質(QOL)が下がってしまいますので、そういった意味でも通院のほうがよい。当院にも、仕事を続けながら抗がん剤治療を受けている患者さんが多くいます。ステージ4で、仕事を続けている方も実在します」
ところで、日本にはがん手術の名医とされる医師が多く存在する。
「確かに、日本のがん専門外科医の技術は、世界のトップレベルです。素晴らしい手技を持った医師は日本の誇りと言っていいでしょう。ただし、ここ最近のがんの治療成績向上への貢献度は、放射線治療と抗がん剤治療によります。外科医も、最先端を行く先生ほどアジュバント療法(術後補助化学療法)の有効性を認識しているはずです」
腫瘍内科医と外科医とのパートナーシップについては。
「必須です。安心して手術を任せることのできる外科医と、いつでも相談できる体制でなければなりません。プロとして尊敬しあい、切磋琢磨し、患者さんのために最善を尽くすパートナーです。
時折、腫瘍内科医とがん専門外科医が患者さんを取り合う敵対関係にあるかのように理解する方がいらっしゃいますが、それは違います。さらに言えば、現在の世界のがん医療は、患者さんを中心にしたチーム医療がスタンダードです。外科医の協力も必須ですし、薬剤師、看護師の力量もQOLを大きく左右します」
見捨てない医療。そして、共存とサバイバー



腫瘍内科医が中心になって展開するがん医療の理想の姿とは?
「ひとつは、前述したように最後まで見捨てない医療であること。緩和ケアへの転換なども、シームレスにしなければなりませんし、腫瘍内科医ならばそれができます。
もうひとつは、がんとの共存という概念。サバイバーという考え方の定着です。がんを克服(?)することがよくメディアでも話題になりますが、がんと診断された時から、すべての患者さんはがんサバイバーとなり、がんとの『共存』を模索していきます。再発の可能性はどんな患者さんでもあり、がんを克服というよりは、がんサバイバーと呼んだほうがよい。進行もしくは再発した患者さんでも、抗がん剤をうまく使うことにより、『共存』が可能な時代になっています。腫瘍内科医はそれを徹底的にサポートするために存在する。そんな、欧米ではもう当たり前の価値観を、早く日本にも根づかせたいと願っています」
がんに対して国民がいだくイメージを、いろいろと変えていく必要があるようだ。
「がんを告白したら仕事を失う社会など、もっての他です。しかし、日本ではまだそれさえ克服できていない。がん闘病記を発信しているブロガーのほとんどが匿名なのも、大きな偏見があることを示しています。がん患者が、あまりにも住みづらい社会ですね。
繰り返しになりますが、抗がん剤治療を受けていても仕事は続けられます。日本では、抗がん剤治療に専念するためにと、仕事を辞めるように勧める医師もいる。
欧米ではもう普通になっているように、仕事をしていても堂々とがんを告白し、社会から差別することなく、自分らしい生活を続けられる社会になるよう診療の現場から患者さんをサポートし、エールを送り続けたいと思います」