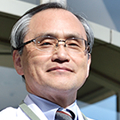静岡県立静岡がんセンター(以下、静岡がんセンター)の肝胆膵外科に、上坂克彦あり。マスメディアでの露出が増えるに従って膵臓がんの権威たる名声も膨らんでいるが、露出の真意はそこにはない。上坂氏は伝えたいことがあり、伝えなければならないという使命感を帯びた肝胆膵外科医だった。
「治る」と「治らない」の境界線を、大きく「治る」側に動かす

「治る」と「治らない」の境界線を数㎝でも「治る」方へ動かしたい。そんな思いを胸に医療人は日々努力し、医学は少しずつ進歩している。
上坂克彦氏も現在、境界線を動かす取り組みのまっただ中にいる。膵癌補助化学療法研究グループ(Japan Adjuvant Study Group of Pancreatic Center)の「膵がん切除後の補助化学療法における塩酸ゲムシタビン療法とS-1療法の第Ⅲ相比較試験」(JASPAC 01試験)は、2013年に「術後補助化学療法に抗がん剤S-1を使用することで、2年生存率が塩酸ゲムシタビン群53%に対し、S-1群は70%、死亡のリスクを44%減らす」と報告し世界中をあっと言わせた。研究代表としてプロジェクトを牽引した立場から、感慨深そうに語ってくれた。
「中間解析が出て統計の責任者がS-1の驚くべき効果に目を疑ったと、後で聞かされました。データセンターに再確認を要請し、解析に間違いがないとわかると、次に参加全33病院に再確認の指示を出したそうです。当院にも、効果安全性評価委員会から再確認指示が来ましたから、『何か起こっているのか?』と訝しがったのをよく憶えています。そのとき、当院のデータをみると、S-1群の長期生存者はゲムシタビン群の2倍いることに気付いたので、もしかするとこの効果が全国でおきているのか? と思いました。そして、次に来た指示は『すぐに発表しなさい』でした。死亡リスクを44%減らすという報告を出す際には、得も言われぬ誇らしさを感じました」
JASPAC 01試験の最終結果は、2016年6月にLancetに発表され、ゲムシタビン群の5年生存率が24.4%であったのに対し、S-1群の5年生存率は、なんと44.1%であることが明らかにされたのだ。
膵臓がん治療の進歩を国民に知らせたい
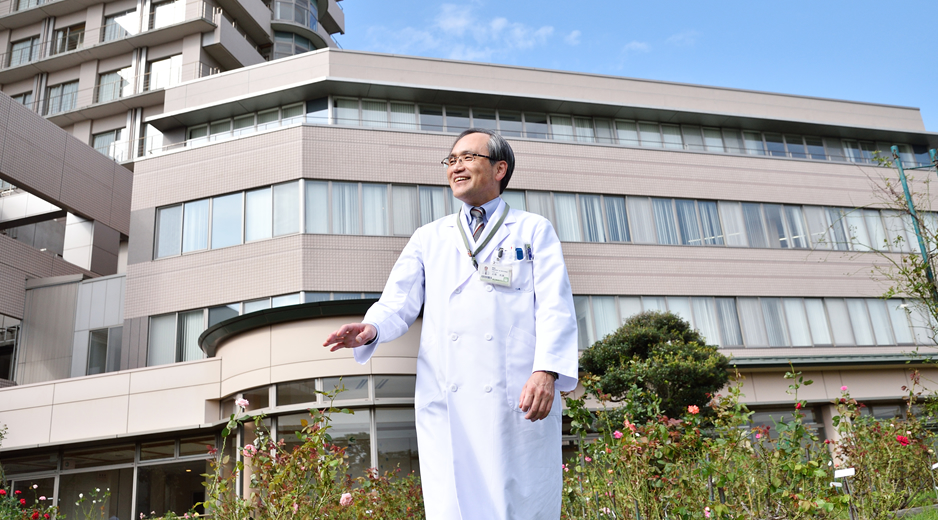
「膵癌診療ガイドライン2013」の術後補助化学療法の項では、すぐに「術後補助療法のレジメンはS-1単独療法が推奨され(グレードA)、S-1に対する忍容性が低い症例などではゲムシタビン塩酸塩単独療法が勧められる(グレードB)」と記載が改訂され、S-1が新たな術後補助化学療法の標準治療として位置付けられた。
「現在は、JASPAC 01試験をさらに進めるとともに、JASPAC 05試験では、手術の前に化学放射線療法を行い、従来は切除できなかった膵臓がんがどの程度切除できるようになるかの研究を進行中です」
肝臓とともに「沈黙の臓器」と呼ばれる膵臓は、そのためにがんの発見が難しく、しかも難治。発見されても手術可能なケースは3割程度で、発症した患者さんに絶望を与える疾患だった。
「膵臓がんの治療は、この10年、明らかに進歩し、救える患者さんの数が増えています。医療関係者は10年の進歩を認知していますが、一般国民にはまだ充分には伝わっていませんね。ですから、膵臓がんの現状を速やかに、正しく伝えなければという思いがあります」
講演会依頼があればふたつ返事で引き受け、最近はテレビ取材や番組出演に応えることも多い。
「肩こりなどの軽い病気をとりあげていた番組に、私が呼ばれるなんて驚きですね。少なくともメディア関係者は、膵臓がんの進歩に気づき始めてくれているようです」
名声を高める快感を追ってメディアに露出しているわけではないのが、よくわかる。そのとき、上坂氏のシノプシスを刺激しているのは、患者さんの笑顔ではないだろうか。
「冷静に考えれば、講演依頼があること事態がすごいのですよ。以前は、膵臓がんをテーマに講演などできませんでした。講演でお伝えできるような明るい話題がない世界でしたから(笑)」
職員を食わせていけるのだろうかと心配した

上坂氏は、2002年に静岡がんセンターが開設された当初から参加する、いわばオリジナルメンバーだ。
「このセンターは静岡県民の願いを受けて、国立がん研究センターゆかりの先生方が集って誕生した医療機関です。縁あって私にもお声がけがあり、肝胆膵部長として参加しました。がんセンターを一から作り上げる機会を得た喜びを知る同志が集い、それぞれの理想を持ち寄り、がむしゃらにがんばって今日を迎えています」
徐々に業績を積み、評価を上げ、現在では県外からも多数の患者さんが集まる状況を前に、感慨深く振り返る。
「畑と野山を切り拓き、病院を建ててスタートしたものの、本当に患者さんは来るのだろうか、職員を食わせていけるのだろうかという不安に苛まれていたのが昨日のことのようです」
いわゆる口コミサイトで静岡がんセンターの評判を確認すると、よい評判が多いのはもちろんだが、それぞれのコメントがどれも長文なのに驚かされる。喜びや感謝の要因を具体的に、適確に記した文章の数々。たぶん、ほかの医療機関で落胆や不信を経験した分、静岡がんセンターの「患者さん本位」を強く認識したのだろう。
「あそこを頼れば、治してもらえる、よりよい医療を提供してくれる。そんな思いを抱いた患者さんが来院してくれるとしたら、私たちの本望と言っていいでしょう。当院に寄せてくださる患者さんの期待に応えられるよう、120%の力を発揮し続けるつもりです」
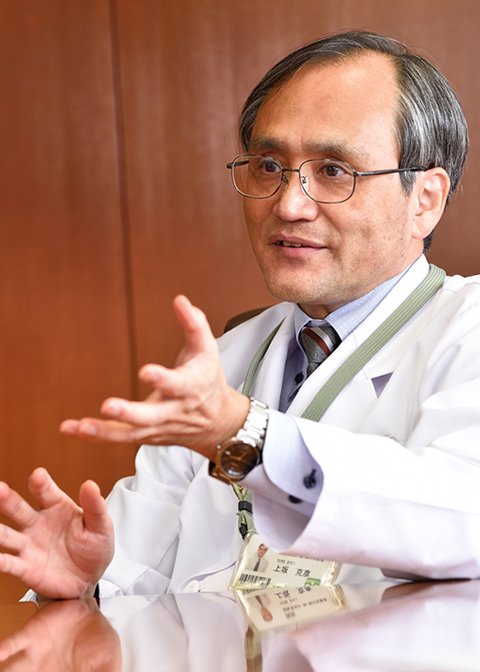
自信の裏付けは、いずこに?
「すべてが患者さん本位に動く院内カルチャーに自信を持っています。具体的には、たとえば、当院の医師は診療科の垣根なく考え、行動します。いわゆる縄張り争いのようなものは、皆無。患者さんのためと思えば、診療科を越えたコラボレーションなど朝飯前です。
ちなみに、前出のJASPAC 01試験のおおもとのアイデアは、消化器内科部長のものです。消化器内科が発案し、肝胆膵外科に声をかけて始まったプロジェクト。行きがかり上、私が研究代表になったに過ぎません」
結果、形となった「患者さん本位」は。
「当院では、たとえば肝がんでは、患者さんに示す第一選択は常に3つ以上あります。それぞれのメリットとリスクを丁寧に説明し、納得して選んでいただく。
3つの選択肢を提示した折、担当チームは『入り口がどれになっても、結果は同じにできる』との自負と使命感をもって考え、準備しています」