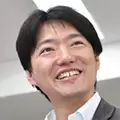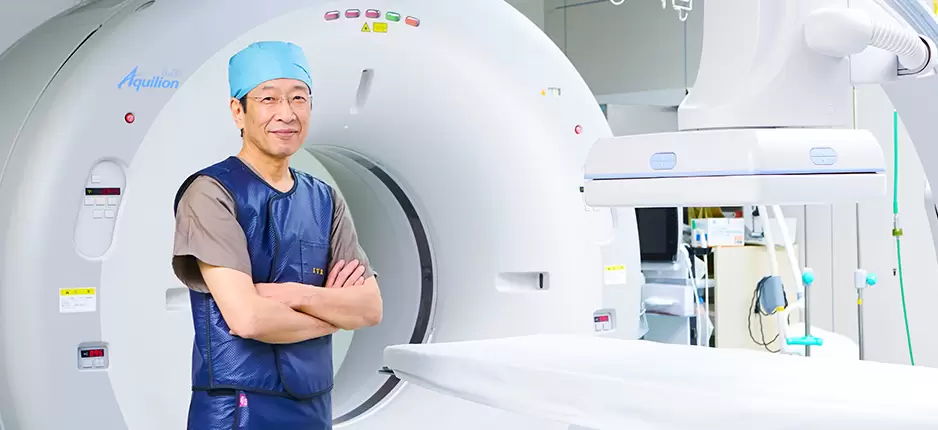研究という言葉が基礎研究を意味していた頃、研究者は白衣と薬品の匂いにまみれて患者に背を向けている姿がパブリックイメージだった。臨床医であり、糖尿病の疫学研究者である後藤温氏は、そんな旧態依然のイメージとはかけ離れた佇まいで仕事の解説をしてくれる。もちろん医師を選んだ若者は、いつの時代もすべからく人の役に立ちたいとの志が共通している点に疑いはないが、アウトプットの違いに時代性を帯びるもの。後藤氏を通じて、新しい時代の新しいスタイルの医師像を、垣間見ることができる。
疫学研究に魅せられ、突き進む若手研究者。
彼は、臨床医でもある。

一般市民の認識が及ばない医学と医療の真実のひとつに、臨床医による臨床研究がある。ほとんどの患者にとって、診察室で相対する医師は「診る人」。しかも「診る」は、問診、触診や診断、処置、処方せん確定といった、目に見える作業がすべてという認識。
日々の臨床の中にみつけた疑問を研究デザインに結びつけ、解析デザインを構築し、研究成果で多くの患者を救うリサーチマインド。つまり、臨床研究。実はこれも、りっぱな「診る」であると言っていいが、多くの患者が、臨床医の、このもうひとつの横顔を知らない。少々医療の知識をかじった者ほどむしろ、「臨床と研究は対極の医師の道」と信じこんでもいる。研究とはすなわち基礎研究だと、旧態依然の図式で考えがちだ。
ただ、致し方ない側面もある。実は、当の医師たちが、つい最近まで、臨床と研究を二者択一の俎上に載せていたのだから。日本の医学界が基礎研究にこれまでどおりの存在意義を残しつつ、臨床研究にもそれに劣らぬ意義と重要性を認めるようになって、日はまだ浅い。臨床医を続けながらできる研究、いやむしろ臨床医にしかできない研究があるという新しい認識はいまだ定着の過程と言っていいだろう。
2016年に卒後12年目を迎えた後藤温氏は、そんな新しい時代を象徴する臨床医のひとり。同年4月に国立国際医療研究センター糖尿病研究センター糖尿病研究部から国立がん研究センター社会と健康研究センター疫学研究部代謝疫学研究室長へと転籍し、一貫して取り組んできた臨床研究、疫学研究への取り組みを加速させている。
「国立がん研究センターの社会と健康研究センターは、がん予防・健診研究センターとして活動していた組織を改組し2016年1月に誕生しました。それまでのがんの予防・早期発見(検診)に加え、がん患者・サバイバーへの支援、支持療法やがん対策などを組入れ、社会的、経済的、倫理的な諸問題などに関する研究を実施することにより、国民生活の質の向上、格差の解消と健康の維持・増進に資することを使命としています。
私は、同センター予防研究グループに属する疫学研究部と予防研究部のうち、疫学研究部長の岩崎基先生の下で代謝疫学研究室長を拝命しました」
国立がん研究センターに糖尿病研究者が採用された意味
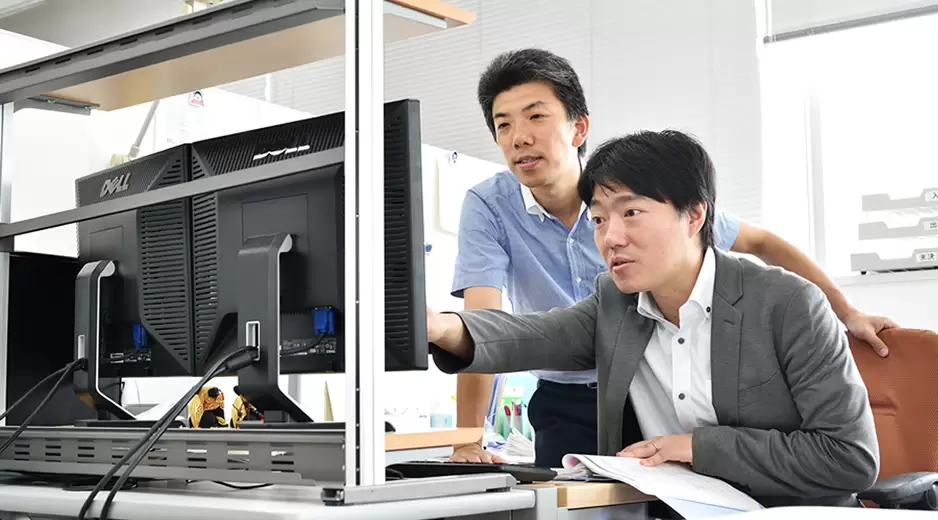
がん予防・健診研究センターが社会と健康研究センターに衣替えした意図は、名称の変更からもうかがい知れる。
「代謝疫学研究室が設置され、専門分野が糖尿病である私が採用されたことでも、改組の意図はよくわかると思います。近視眼的ながんの予防・早期発見からさらに視野を広げ、これまで以上の貢献を目指します。
これは、日本のがん医療と研究を強力にリードし続けた歴史を背景に、2014年には、『大学又は民間企業が取り組みがたい課題に取り組む』法人として国立研究開発法人にも指定された国立がん研究センターが、課せられた使命をより適確に果たすために打ち出した新方針のひとつです」
『がん研に行くということは、糖尿病の研究を止めるのか?』と早のみこみした心配の声をかけられたこともありますが(笑)、もちろん違います。ライフワークである糖尿病の疫学研究を、がん予防に役立て、国民の健康増進に寄与したいと思い、ここに異動しました。1990年から始まっている国立がん研究センターによる大規模コホート研究であるJPHC Studyにおいて糖尿病の疫学研究に携わって、津金昌一郎先生や岩崎基先生とご一緒させていただいたことがきっかけとなりました」
糖尿病とがんの間に関係があろうことは、すでに一般市民でさえ気づいている。
「糖尿病の予防はもちろん大事ですが、糖尿病を発症したらどんな合併症に気をつけるかという点も大切な疾患です。欧米では、それは心疾患。糖尿病に起因する心臓病の患者さんが多いのです。一方、日本ではそれががんになります。糖尿病の合併症での死亡者数をみると、圧倒的にがんが多い。国民的な関心事になるのは当然と言えますし、私も糖尿病の研究の過程でがんへの関心は年とともに強くなっていました。
医学界もその点は注視しており、2013年7月には、日本糖尿病学会と日本癌学会による合同委員会が糖尿病とがん罹患リスクや予後などに関する検討を行い委員会報告を発表しています。報告のとりまとめには私も参加し、現在取り組んでいる研究につながっています」
すべてのがんで1.2倍、
肝臓がん、膵臓がんでは2倍のがん発症リスク

ところで、肝心の糖尿病とがんの因果関係だが、実際にはあるのだろうか。
「研究結果は、相関関係があることを示しています。すべてのがんでみると、糖尿病罹患者はそうでない人の約1.2倍。肝臓がん、膵臓がんでは約2倍にまで発症リスクが高まることがわかっています。しかし、因果関係があるかどうかはまだわかっていません」
そこで、後藤氏はどんな研究に取り組むのか。
「疫学研究は2000年代に入って複数の研究結果を統合して解析するメタ解析の手法が確立し、飛躍的に進歩しました。2013年の合同委員会報告もその成果のひとつですが、糖尿病とがんとの関係の整理がついたに過ぎません。まずは、その詳細な分析、解析をさらに前進させるのが私の仕事と認識しています。
JPHC Studyを基盤に活用し、がんの原因を明らかにし、がん予防法の開発につながるエビデンスの構築を目指します」