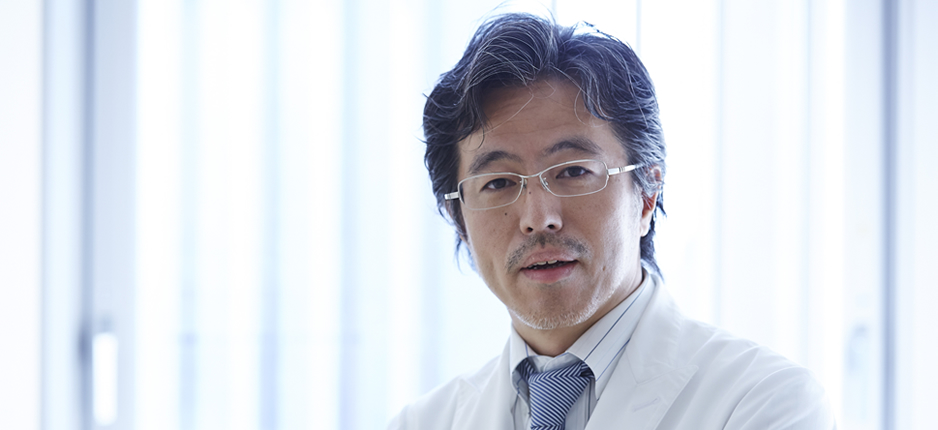脳神経外科領域には様々な疾患があり、様々な技術が投入され、数多くの名医の名が知られている。しかし、同じ頭部領域ながら頭蓋底を境にした向こう側にある頭頸部外科領域に関する話題は、脳神経外科領域に比べて極めて少ない。今回登場願うのは、国立大学医学部で唯一の頭頸部外科学教室である東京医科歯科大学頭頸部外科教授・朝蔭孝宏氏。単に命を長らえるだけでなく、嚥下や発声といった機能の維持までも求められ、症例によっては形成外科を巻き込んだ再建術の適応も必要となる。そんな、知られざる最先端領域で、最先端の技術と知見を振るう若き教授の原風景を追ってみた。
頭頸部外科、脳神経外科はもとより多彩な診療科が協働する究極のチーム医療

従来から難病治療に積極的に取り組んできた東京医科歯科大学医学部附属病院では、2012年4月に5つの先端治療センターからなる難病治療部を新設し、高度な診療技術で数多くの患者さんを救っている。
2016年4月、5つの先端治療センターの1つである頭頸部・頭蓋底腫瘍先端治療センターセンター長に就任したのが朝蔭孝宏氏だ。前年4月に就任した、東京医科歯科大学頭頸部外科の第2代教授との兼任だ。
「頭頸部外科は首から上のうち、眼球と脳以外を対象とした医学領域です。口腔がん、咽頭がん、喉頭がんなどが典型的な対象疾患です。一方、頭蓋底領域に腫瘍が浸潤する場合もあり、そのようなケースでは脳神経外科の協力が必要不可欠となります。
たとえば、悪性腫瘍が鼻の奥にできたとなると頭頸部外科と脳神経外科の領域を隔てている骨は厚さ1㎜にも満ちません。腫瘍が頭蓋底を突き破って脳領域へ、あるいは頭蓋底付近にできた悪性腫瘍が頭頸部領域へと侵出すると技術的にとても難しい症例となります。そんな難易度の極めて高い症例を頭頸部外科・耳鼻咽喉科、脳神経外科、放射線科などがチーム医療で治療に当たる体制を有するのが頭頸部・頭蓋底腫瘍先端治療センターの大きな特徴です」
手術を選択した場合、外科系各科のエキスパートがそれぞれの分野の豊富な経験と高度な技術を活かした合同手術を実施できる。その体制のもと、症例個々の病態に応じた、より有効かつ侵襲の少ない治療を行うため、治療方針を立てる段階から多くの診療科が緊密に連絡をとりあう。
「カンファレンスでの議論の結果、支持療法を選択するケースもあります。その場合は、チームに内科系の専門家を加え、徹底的に集学的に、患者さんのQOLを最優先に治療にあたります」
多くの場合、合同手術には形成外科も参加する。
「首から上は服をまとえない部位ですから、喪失部分の再建までもがQOLに関わってきます。そんな場合の合同手術は10時間を超えることも稀ではなく、手術中のライトが消えるのは日付が変わってからということもあります」
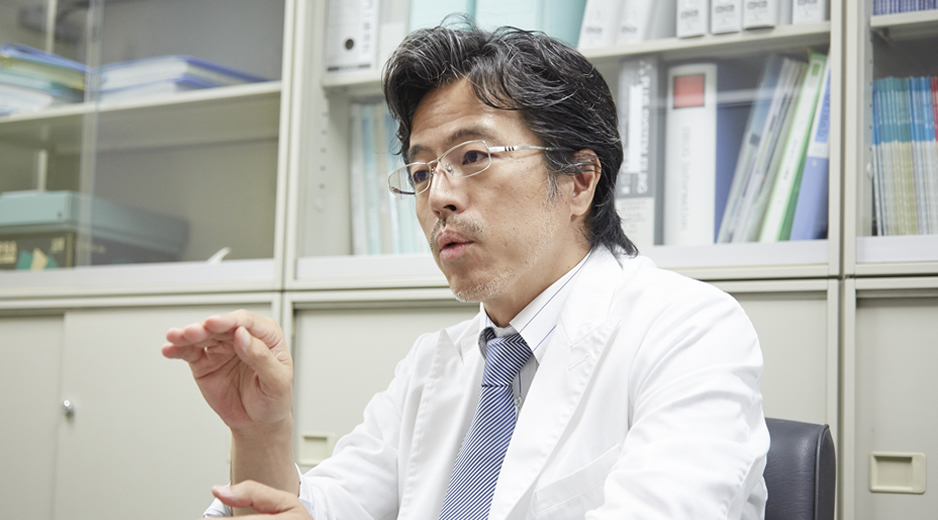
国内でも稀有な診療体制を頼って、超進行がんや頭蓋顔面深部の頭蓋底腫瘍など難治症例の患者さんが全国から集まっている。同センターにおける医療の質の秘訣について質問した。
「カンファレンスで導き出される治療方針には、手術、放射線治療、抗がん剤治療の3つの可能性があり、参加したスタッフが徹底的に議論し、最終的に1つを選択します。
たとえば結論が手術であった場合でも、そういったプロセスで治療方針が決まり、治療計画が策定されると治療の半分は終わったと言っていいでしょう。当センターの医療は、診療科横断で集った専門家が共に考え、共に決断する点が常に最大の武器なのだと考えています」
頭頸部外科が切り拓いた患者中心、QOL重視の価値観を引き継ぎ、育てる

頭頸部外科は耳鼻咽喉科のサブスペシャリティのひとつで、比較的歴史が浅い。朝蔭氏が教授職を引き継いだ東京医科歯科大学頭頸部外科は1999年に日本初の頭頸部外科講座として誕生したもので、現在でも国立大学医学部としては唯一の講座。日本の頭頸部外科学を牽引する存在と言っていい。頭頸部外科医には聴覚、嗅覚、味覚、平衡感覚を扱うエキスパートであると同時に、呼吸、摂食嚥下、音声言語などの機能と、それに必要な鼻腔、口腔、咽頭、喉頭の専門的診察を担うことが求められる。大学病院や基幹病院では、頭頸部がんが症例の大多数を占めている。朝蔭氏も、頭頸部がん専門医資格を有する医師である。
「頭頸部がんは切除し、命を繋ぐことだけではなく、嚥下や発声といった複雑なメカニズムの維持にまで心を砕いて治療をしなければなりません。そこがまさに、この分野の難しさであり、やり甲斐でもあります」
この分野には、頭頸部がんの第一人者で寛仁親王の主治医として高名な海老原敏氏という巨星がある。朝蔭氏は国立がんセンター(現:国立がん研究センター)東病院(以下、東病院=千葉県柏市)で、海老原氏から直接薫陶を受けている。
「海老原先生が確立した温存療法に関する技術を学んだのはもちろん、常に患者さんオリエンテッドな姿勢に、強い影響を受けました。現在の私の礎は、東病院時代に確立されたと言っていいと思います」
がん領域が生存率至上だった時代から、機能温存、つまりQOLの重要性を説き、実践してきた海老原氏の医療の理念。それを引き継ぐ朝蔭氏には、『患者さん中心かつ最先端』という現代医療の理想の具現化が期待されているといっていいだろう。
外科医志望の諸君! 現役のうちに教授を超えるのが、君たちの使命だ

昨今の「外科離れ」が、話題にのぼった。
「世にそういった風潮があるのは認識していますが、正直、私の実感値としては、特段の危機感はありません。前職(東京大学医学部耳鼻咽喉科医局)時代も、現在も、やる気と見込みある若者は集まってきてくれていますので」
自信の根拠は?
「なんといってもこの分野には、『自分の腕一本で患者さんを救える』という魅力があります。私たちがその魅力を適確に伝えることができていれば、命脈が途絶えることはないはずです」
技術の継承について、信念を示してくれた。
「私は、外科の世界に『神の手』は不要だと思っています。神の手にしかできない技術より、学べば修得できる再現性の確立の方が数段重要。私が教える若手には、なるべく早く私と同じ技術を習得してもらわなければ困ります。そして、できるならば私が現役のうちに、最低でも私が死ぬときには(笑)、私を超えていてもらいたい。そうでなければ、技術の進歩は見込めませんよね」