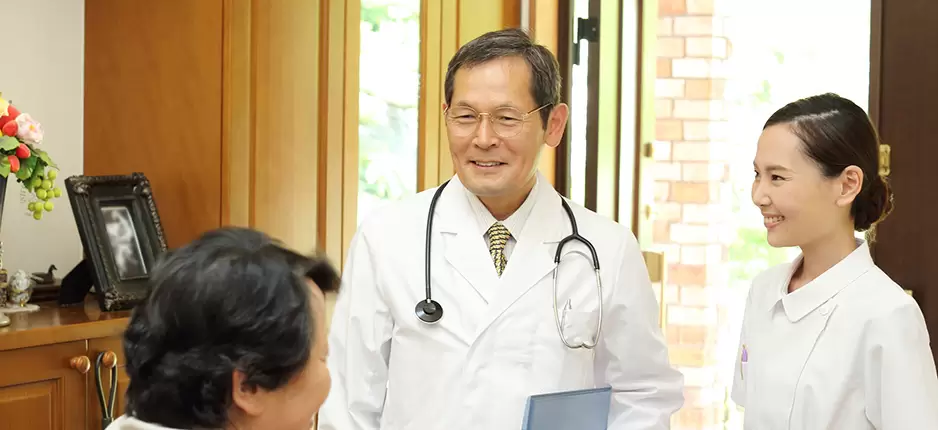医師の働き方は、大きく臨床医と研究医の2つに分けられます。そのうち、医学の発展を支えるために日々研究を行うのが研究医です。今回は、研究医について、その仕事内容や役割、臨床医との違いなどを詳しく紹介します。
- 治療法が確立されていない疾患の研究に興味がある方。
- 研究に専念しながら臨床も行う医師を目指している方。
- 最新医療の知見を活かして患者さんのQOL向上に貢献したい方。
目次
研究医とは

まずは、研究医の主な仕事内容や役割などについて見てみましょう。
1-1.研究医の仕事内容や役割
日々データを収集し、研究するのが研究医の主な仕事です。現時点で治療法が確立されていない疾患の原因解明を行ったり、患者さんにより良い医療を提供するために、薬学や生化学などの分野で専門的な研究を行ったりします。論文を作成し、発見したことを学会などで発表するのも大切な仕事の一つです。
企業に勤務している場合は、製薬の開発に関わったり、医療技術を研究したりするなど、最先端の医療に触れるケースが多いでしょう。医学の進歩に貢献できるよう、日々研究に携わるのが研究医の役割だといえます。
1-2.携わる研究の種類は大きく分けて2つ
研究医が携わる研究内容は「基礎研究」と「臨床研究」の大きく2つに分けられます。基礎研究とは「病気の原因などを解き明かす研究」で、臨床研究は「実際に診察などに携わりながら治療法の確立などを進める研究」です。
基礎研究においては、医学部だけでなく薬学部や理学部出身者が携わるケースも見られますが、臨床研究では実際に診療を行うため医師免許が必要です。
1-3.研究医の活躍の場
研究医が属する職場は、医療系企業の他、大学などが挙げられます。また、公務員として研究施設に属するケースもあります。
研究医と臨床医の違い

臨床医は、患者さんと直接関わり、診断や治療などを行いながら研究を進めます。一方で、研究医は研究を専門に行うため、患者さんを直接診察することがほとんどない点が大きな違いです。
ただし、大学病院で働く臨床医の場合は、研究を義務付けられている場合もあり、研究・臨床のいずれかのみに専念できるとは限りません。また、研究を主として、大学で講義を担うこともあるでしょう。研究と臨床を両立する医師もいるため、明確に区分するのが難しい場合もあります。研究医になるには、臨床医同様に、2年間の初期研修を受ける必要があり、その後のキャリア選択によって道が分かれるのが一般的です。
研究医の魅力・やりがいと、向いている人
続けて、研究医の魅力・やりがいと向いている人について見てみましょう。
3-1.研究医の魅力・やりがい
研究医の魅力として「今まで見たことのない現象や最新医療の知見を得られること」や「臨床を大きく変え、患者さんに還元できること」などが挙げられます。さまざまな研究により新薬の開発に貢献したり、治療法の進化によって患者さんのQOL向上につながったりすることは、研究医ならではのやりがいといえるでしょう。
研究医は、日進月歩で変化する医療現場により良い治療技術を提供する、なくてはならない存在です。裏方として医療を支えたい人にとって、研究医の働き方は大きな魅力があるといえます。
3-2.研究医に向いている人
研究を続けていく中で、すぐに成果が得られないこともあります。そのため、研究医には「成果が出るまで諦めずに研究を継続できる人」や「物事を広く多角的な視点から柔軟に考察できる人」などが向いているでしょう。また「好奇心があり、興味のある分野に特化して新たな発見を楽しめる人」も、研究医に向いているといえます。

研究医と臨床医は両立できる?
先述したように、大学病院や大学院などに所属する医師は、研究と臨床との両立が義務付けられているケースもあります。
とはいえ、研究医としてさまざまな症例やデータを集め、仮説を立て、実験・検証し、新たな治療法や医療技術を確立していくためには、多くの時間が必要です。そのため、研究に集中するための環境が必要でしょう。両立するとなると、肉体的にも精神的にも大きな負担がかかる可能性があります。
臨床医から研究医に転向できる?

臨床医として働いているものの、今後、研究医に転向したいと考えるケースもあるでしょう。実際、臨床医としての経験を十分に積んだ後、大学院に入り、研究医としてキャリアを形成する医師もいます。年齢を重ねてもチャレンジできる環境はあるため、臨床医から研究医への転向は可能です。
また、近年では、研究医の増加を目的として、研究医としてのキャリアに進むためのさまざまな取り組みが見られます。今後のキャリアを考えながら、どのような方法があるのか検討してみましょう。
5-1.「基礎研究医プログラム」
厚生労働省は、近年、国内での基礎医学論文数が低下傾向にあることから、2022年度より「基礎研究医プログラム」の募集を開始しました。基礎研究医の養成を目的として、基礎医学に興味を持つ医師・学生を対象に、臨床研修と基礎研究を両立しやすい環境を提供するものです。
このプログラムは、大学院や大学病院などが実施するもので、研究医へのキャリアにつながる「MD-PhDコース」を設定したり、研究医を志す学生のために特別な入学選抜を行ったりするといった取り組みを組み合わせながら、研究医の養成を図ります。また、研究医としてのキャリア支援を行っているケースもあるようです。現在、臨床医として働いている人であっても、こうしたプログラムを利用することで、研究医への転向を検討するのも一案です。
5-2.新専門医制度「臨床研究医コース」
一般社団法人日本専門医機構は、2023年4月より、これまでの専門研修制度に加え「臨床研究医コース」の設置を予定しています。将来の臨床研究医を養成する目的であり、研修期間は7年となっています。
■臨床研究医コースの研修期間

コース採用後、最初の2年は臨床研鑽を行い、その後5年間はエフォートの50%以上を研究に充てるといった内容で、コース在席中は、責任医療機関の規定に従い、給与なども保証されるとしています。しかし、2021年度、2022年度と採用者数は目標を下回っており、今後コース内容が見直される可能性もあります。興味がある場合には、最新情報を確認しながら、応募を考えてみてはいかがでしょうか。
研究医に関心がある人は医師専門のエージェントに相談してみよう!

研究医の仕事に関心があるものの、臨床医からの転向に悩んでいる人もいるでしょう。また、現在、研究医と臨床医を両立している場合、日々の負担を軽減したいと考えるケースもあるかもしれません。臨床医から研究医への完全な転向を考えるなら、大学院に行く他、企業への転職などを検討することになります。どんな働き方ができるのか、また、どのような職場があるのかなど、お悩みの場合には、医師専門のエージェントに相談してみてはいかがでしょうか。

臨床医とは?研究医との違いや臨床医のやりがい・魅力を解説
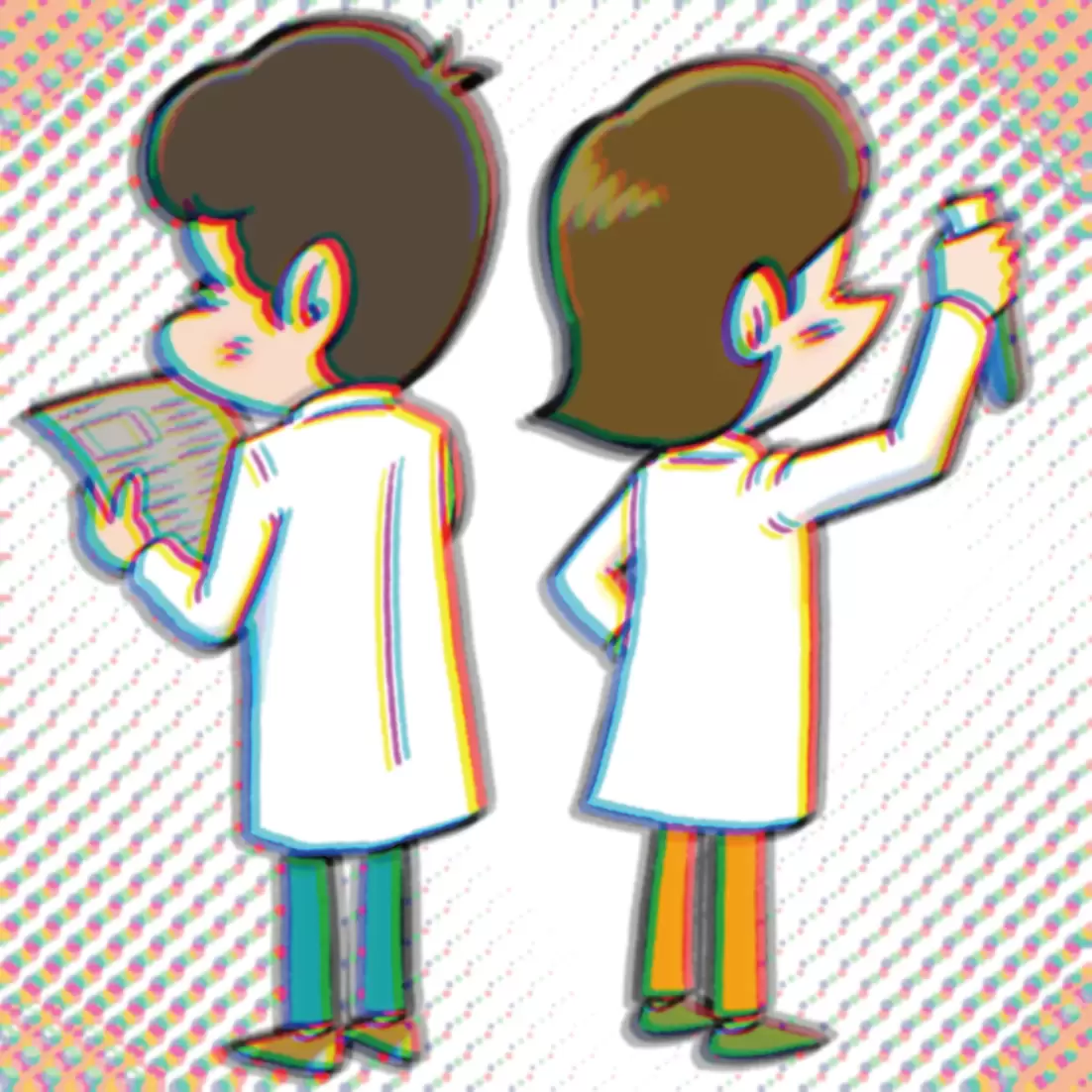
「臨床検査」のリアル 現役の専門医に直撃!
[キャリアの情報収集におすすめ]
医師のキャリアに関する記事一覧はこちら