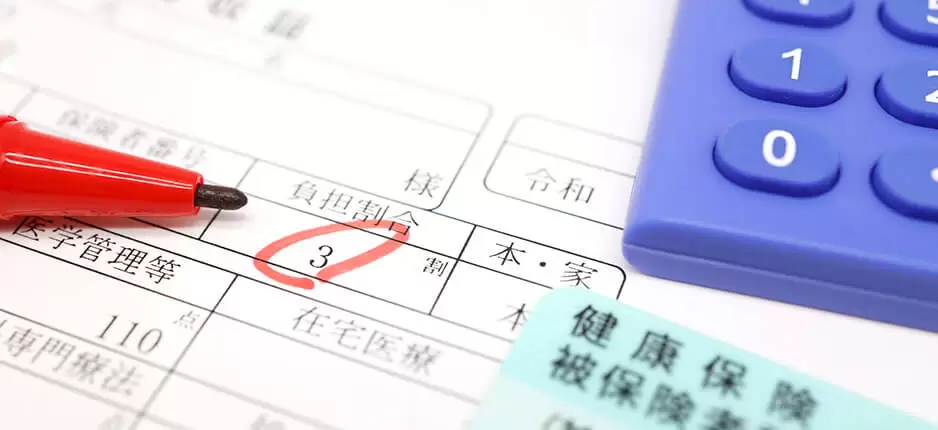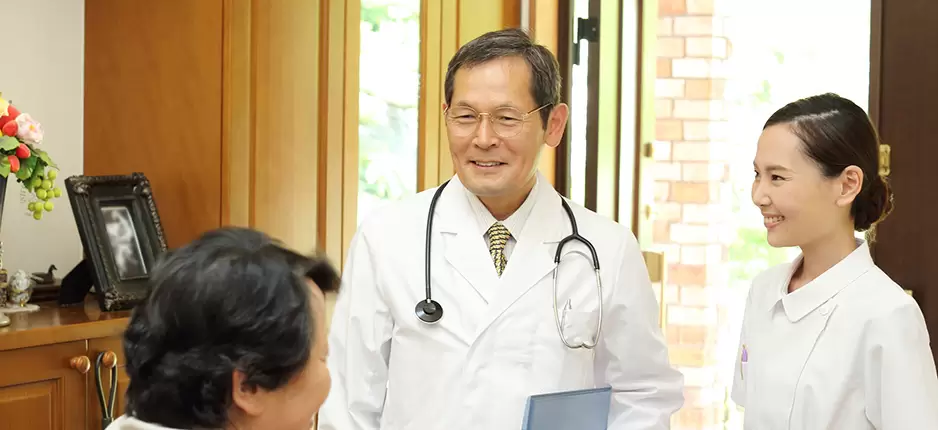超高齢社会を迎え医療費の増大が懸念される中、政府が進めているのが「医療費適正化計画」です。どのような計画・目標が設定され、どのように進められているかご存じでしょうか。今回は、医療費適正化計画の立案背景や経緯をはじめ、医師が理解しておきたいポイントを分かりやすく解説します。
- 医療費適正化計画の概要や仕組みに興味を持っている方。
- 入院や外来医療費の適正化の具体的な取り組みに関心のある方。
- 高齢者保健事業と介護予防の最新動向を知りたいと思っている方。
目次
医療費適正化計画とは

日本では高齢化率の増加に伴い、医療費が増加傾向にあります。そうした中、国民皆保険制度を持続的に運営していくためには、国や都道府県だけでなく、保険者および医療従事者が協力しながら、限りある医療資源を効果的に活用する必要があります。
そのために、地域住民の健康維持と効率的な医療提供体制の構築に向けた指針、目標設定などをまとめたものが「医療費適正化計画」です。
1-1.医療費適正化計画における目標
医療費適正化計画は、第1期(2008〜2012年度)、第2期(2013〜2017年度)に続き、第3期(2018〜2023年度)は6年間を1期間として実施されています。過去の取り組みや、その結果を基に、期間ごとに実績の評価と見直しが行われ、主に以下の3つを主軸として計画が立てられています。
1.国民の健康の保持の推進に関する達成目標
2.医療の効率的な提供の推進に関する達成目標
3.計画期間における医療に要する費用の見込み
1-2.医療費適正化計画が立案された背景
医療費適正化計画が立案された背景には、医療費の増大が大きく影響しています。医療の需要が高い高齢者が増えたことで医療費が増加し、少子化の影響で財源の確保が難しくなっています。従来の医療制度を維持するためには、生活習慣病の予防・早期発見、早期治療に向けた取り組みなどを推進し、国民の健康維持・増進を促すことで、医療費を適正化する必要があるのです。
第1期~第3期の医療費適正化計画のまとめ

続いて、医療費適正化計画における第1期~第2期の成果と、第3期の状況を見てみましょう。
2-1.第1期(2008~2012年度)のまとめ
国民の健康保持の推進として、主に以下の目標が設定されました。
・「特定保健指導」が必要と判断された対象者への実施率45%以上
・メタボリックシンドローム該当者および予備群の減少(2012年度において、2008年度比-10%以上)
・平均在院日数の短縮(2012年度の全国平均在院日数目標29.8日)
「特定健康診査」と「特定保健指導」の実施率に関しては、残念ながら第1期では目標値を達成することはできませんでした。しかし、両者ともに都道府県で着実な実施率の向上が確認されました。
■特定保健指導の実施状況
| 対象者数(人) | 対象者割合 | 終了者数(人) | 実施率 | |
| 2008年度 | 4,010,717 | 19.9% | 308,222 | 7.7% |
| 2009年度 | 4,086,952 | 18.9% | 503,712 | 12.3% |
| 2010年度 | 4,125,690 | 18.3% | 540,942 | 13.1% |
| 2011年度 | 4,271,235 | 18.2% | 642,819 | 15.0% |
| 2012年度 | 4,317,834 | 17.7% | 707,558 | 16.4% |
また「メタボリックシンドローム該当者および予備群の減少」については、-12%の減少を達成しました。しかし、増加に転じた地域も見られ、地域差が表れる結果となりました。
また、医療機関の機能分化と連携の推進、在宅医療・地域ケアの推進、療養病床の再編成を各地域で実践することにより「入院期間(平均在院日数)の短縮」を図った結果、2012年度の全国平均在院日数の目標値29.8日に対し、29.7日を達成しました。しかし、療養病床から介護保険施設などへの転換は進まず、介護療養病床の転換期限を2017度末まで延長しました。
■都道府県別平均在院日数(介護療養病床を除く )
| 2006年(全国) | 2012年(全国) | |
| 平均在院日数 | 32.2日 | 29.7日 |
第1期医療費適正化計画では、2008年度の医療費見通し34.5兆円に対して実績は34.1兆円(0.4兆円減)、2012年度は医療費見通し38.6兆円に対して実績は38.4兆円(0.2兆円減)と、それぞれ医療費を削減できました。
2-2.第2期(2013~2017年度)のまとめ
第2期医療費適正化計画では、生活習慣病の発症予防のために「たばこ対策」の普及啓発に取り組むことが掲げられましたが、具体的な数値目標は設定されませんでした。しかし、2012年~2017年の間に「習慣的に喫煙している者の割合」が減少してきている傾向を確認できました。
■習慣的に喫煙している人の割合
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
| 20.7% | 19.3% | 19.6% | 18.2% | 18.3% | 17.7% |
また、第2期医療費適正化計画には、限られた財源の有効活用と、国民医療を守ることなどを目的に「後発医薬品の使用促進」も盛り込まれました。こちらも、具体的な目標値は設定されませんでしたが、毎年度着実に、後発医薬品の使用割合が増加していることを把握できたことが報告されています。

第2期医療費適正化計画では、2017年度の医療費見通し(適正化に向けた取り組みを行わない場合)は約47.0兆円と推計されていましたが、適正化計画に沿って取り組みを行った結果、2017年度の医療費(実績見込み)は約43.1 兆円となりました。
2-3.第3期(2018~2023年度)の状況
現在の第3期医療費適正化計画では、以下の2点に重点を置いて実践が進められています。
都道府県の医療計画(地域医療構想)に基づく病床機能の分化・連携の推進
・外来医療費の適正化
糖尿病の重症化予防、特定健診・保健指導の推進、後発医薬品の使用促進(80%目標)、医薬品の適正使用(この結果、2023年度には0.6兆円程度の適正化効果額が見込まれる)
外来医療費の適正化により、40歳以上の糖尿病患者1人当たり医療費の平均との差が半分になった場合、2023年度には約1,000億円の医療費削減につながることが見込まれます。また、重複投薬(3医療機関以上)と、多剤投与(65歳以上で15種類以上)されている人が半分になった場合、約600億円の医療費削減が見込まれています。
なお、2021年6月に「経済財政運営と改革の基本方針2021(骨太方針2021)」が閣議決定され、医療費適正化計画の見直しが進められることになりました。今後、状況の変化に応じて医療費適正化計画が変更される可能性もあるため、新しい情報を確認する必要があるでしょう。
医療費適正化計画を受けて医師が理解しておきたいポイント

医療費適正化計画は、医療体制の見直しなど、現場への影響が少なからずあります。医師として理解しておきたいポイントをまとめました。
3-1.都道府県の地域医療構想との連携
第3期医療費適正化計画に挙げられた「入院医療費の適正化」は、上述したとおり、都道府県の医療計画(地域医療構想)に基づくものです。高齢化の状況は地域によって大きく異なるため、地域ごとに将来の医療需要を推計し、必要な病床数を予測した上で、将来の地域医療体制が計画されています。ただし、地域医療構想は、2025年に必要となる病床数を推計したものであるため、今後を見越した試算が求められている状況です。医療費適正化計画は政府主導で行われていますが、都道府県の動向も確認しておく必要があるでしょう。
3-2.医療と介護の一体的な計画はこれから
現状、医療に関しては、都道府県の地域医療構想に基づいた計画が進んでいますが、介護については市町村が計画を立てている状況です。そのため、今後の高齢者医療に向けて、医療と介護にまたがるアプローチを盛り込んだ計画を進めるべきであるといわれています。今後は、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施を推進する流れになっていくと考えられます。
3-3.未来に備え、今後の動きに関する情報収集を
進行中の第3期医療費適正化計画は、いま医療現場で活躍する医師にとって、現実的に関わっていく内容です。例えば、病床機能の分化・連携の推進によって、働き方にも変化が起きるかもしれません。2024年以降は、第4期の計画が進む予定です。今後の動きに注意しながら、常に知識のアップデートを心がけ、時代に合った対応を行いましょう。
医療費適正化計画を正しく理解して自分の役割を全うしよう
医療費適正化計画は、長期入院や重複投薬・多剤投与などを適正化することで、医療費を削減することを大きな目的としています。目的の達成には、さまざまな立場の医療関係者がそれぞれの役割を果たしながら、連携を進める必要があります。最新の情報を確認しながら、地域医療を担う医師として、どのような変化があり、どう対応すべきなのかを考える必要があるでしょう。
[働く環境について情報収集したい方におすすめ]
医師の勤務事情に関する記事一覧はこちら