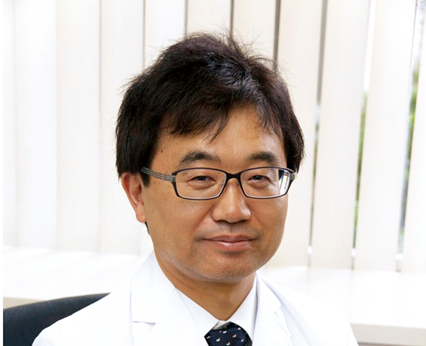経済のグローバル化が進む中、自らの活躍の場を海外へと広げる医師も増加しています。日本人医師による国際協力活動にはどのような意義があるのでしょうか。ミャンマーの無医村で医療活動などを進める「ミャンマーファミリー・クリニックと菜園の会」代表の名知仁子氏へのインタビューをWeb医事新報よりお届けします。
自らの健康を守る 地域健康推進員を育成
ミャンマーで、どのような活動をしているのですか。

国際医療協力は聴診器1本で幅広い経験が試される医の原点
保健衛生活動と菜園支援、巡回診療で
ミャンマー人が自ら健康と幸せを築く支援を目指す
1つは、無医村の巡回診療です。ミャンマー南部の町ミャウンミャを拠点に15の無医村をミャンマー人の医師や看護師と一緒に車で巡回しています。
ミャンマーでは人口5300万人の約7割が農村部に住み、十分な医療を受けられないばかりか、電気や清潔な水のない生活をしています。町の病院まで行くには日当(平均160円程度)の3倍もの交通費がかかるため、具合が悪くても受診が遅れがちです。
もう1つの活動の柱は、病気にならないための保健衛生指導です。巡回診療を行っている村で、手洗いや歯磨き指導、ふたのついたトイレの設置の必要性など、感染症や熱中症の予防などを目的とした啓発活動を行っています。
また、自分たちで健康を守れるように、トーイ村、ガヤジ村、コピン村とガンコーズ村という4つの村で地域健康推進員の育成もしています。ガンコーズ村では、地域健康推進員の説得で、村長に協力を求めたこともあり、全124世帯にトイレが設置されました。対策を進めたらデング熱による死者や入院者も出なくなっています。
3つ目の活動の柱が、栄養不良を根本的に防ぐ目的で行っている無農薬の有機家庭菜園支援です。有機栽培の指導は、佐賀県の認定NPO法人「地球市民の会」にお願いしています。
活動地の農村のミャンマー人の食事は、質の悪い米飯と、ガピと呼ばれる塩辛のような魚の発酵食品が中心で、野菜をほとんど食べないため栄養不足による病気も少なくありません。ミャンマーでは5歳未満の子の約3割が栄養不良で亡くなっています。有機家庭菜園で作った野菜を食べて栄養状態が改善し、脚気などの病気の予防が期待できるだけではなく、収入増大につながった人もいます。
愛を与えれば自分が豊かに
国際医療協力を始めようと思ったきっかけは?
大学病院での出身大学差別や派閥争い、女医蔑視に限界を感じていた時に読んだマザー・テレサの本の「もし、あなたの愛を誰かに与えたら、それは、あなたを豊かにする」という言葉に感銘を受けました。それまで海外に興味もなかったのですが、インドでのマザー・テレサの活動を知って、国際医療協力をしたいと思い英語を勉強し始めました。
ところが、国際医療協力をする決意を固めて大学を辞めた後、反射性交感神経性萎縮症で動けなくなり、4カ月の入院と7カ月のリハビリ生活を強いられました。国際医療は健康でないとできないので希望を失いました。
最初は国境なき医師団の活動で海外へ行ったのですね。
そうです。39歳のときに国境なき医師団に入団して、フランスのプロジェクトでタイへ行き、ミャンマーから逃れて来たカレン族の医療支援を行いました。当時は40歳までにファーストミッションを得ないと国際医療活動ができなかったので、ギリギリの年齢でした。
だけど、いざ現場に行ったら聴診器1本しかなくて、血液検査さえできない現実に愕然としました。その時日本へ電話するチャンスが1度だけあり、日本人で初めて国境なき医師団に参加した貫戸朋子先生に電話して、「何もできない、帰りたい」と訴えたことをよく覚えています。貫戸先生には、「あなたは学ぶために行ったのではなく教えるために行っている。教えなさい」と励まされました。この言葉が今の活動につながっています。
ミャンマーで今の活動を始めたのはなぜですか。
2004年から05年にかけて9カ月間、国境なき医師団のオランダプロジェクトでミャンマーを訪れ、ロヒンギャ族に対する医療援助をしました。衛生状態が悪く食べ物も少ない過酷な現場でしたが、ある日夕陽を見ていて、ミャンマーは第2の故郷、ここで何かしたいという思いが沸き上がりました。
現在の活動を始めたのは2008年に乳がんになったのがきっかけです。抗がん剤で髪の毛もなくなった時に自分が本当に進みたい道を考え、聴診器1本で患者さんを診ることを教えてくれたミャンマーに貢献したいと決意しました。
すぐに「ミャンマーファミリー・クリニックと菜園の会開設基金」という任意団体を立ち上げ寄付を募り、12年にNPO法人化しました。ミャンマー保健省の許可を取るのは大変でしたが、活動が継続できているのは支援してくださる方々の寄付のお陰です。
最終的には支援が不要になるのが理想
日本人医師が国際協力活動を行う意義は大きいと考えますか。
医学生や日本で活躍する医師がミャンマーなど発展途上国での医療活動に参加して、聴診器1本で患者を診る体験をする意義は大きいと思います。私たちの会でもスタディツアーを実施しています。
日本に帰国中に体調不良で救急外来を受診したことがあるのですが、担当医が私の顔を見もせず、CT、採血、尿検査をオーダーしたのに驚きました。国際医療協力の現場では、全人的に人を診るとは何なのか、医の原点に戻れます。患者さんや他のスタッフとのコミュニケーションの仕方や本当の意味でのチーム医療を学ぶ機会にもなり、日本での診療や災害医療の現場でも役立つのではないでしょうか。
今後の目標は。
前述のトーイ村をモデル地域として、自分たちで健康づくりができるコミュニティを増やしていきたいです。トーイ村では住民が主体になって進める簡易診療所設置やコミュニティガーデン作りを支援中です。また、NPO法人オアシスと連携して、安全な飲み水を得られる井戸を掘っています。
最終的には、村の人たちが夢を持ち、それを達成して、私たちの会の支援がいらなくなるのが理想です。日本だったらスピーディに進むことに時間がかかるジレンマはありますが、これからも全力でミャンマーの農村部の健康作りと自立を支えたいです。
(聞き手・福島安紀)
出典:Web医事新報
※本記事は株式会社日本医事新報社の提供により掲載しています。
<この記事を読んだ方におすすめ>
・外国人診療で医師が注意するべきポイントとは?【小林米幸先生インタビュー】
・「やさしい日本語」を用いた外国人診療のメリット