2019年9月29日(日)、JR新宿ミライナタワーにて医師を対象としたセミナー「心不全を防ぐための“弁膜症再発見”」(株式会社マイナビ・主催、エドワーズライフサイエンス株式会社・共催)が開催されました。東京ベイ・浦安市川医療センターの渡辺弘之先生が登壇し、高齢化にともない増加している心臓弁膜症の早期発見について解説。セミナーの様子をレポートします。
高齢者の心臓弁膜症に警鐘を鳴らす
マイナビDOCTORが主催する医師のためのイベントは、7月に開催された「離島発 とって隠岐(おき)のエコーで変わる外来診療」(白石吉彦先生登壇)に続き2回目となります。この日登壇したのは東京ベイ・浦安市川医療センターでハートセンター長を務める渡辺弘之先生。弘前大学医学部を卒業してから現在にいたるまで、長年にわたって循環器疾患についてキャリアを積み、特に心エコー図を用いた心疾患治療のプロフェッショナルとして医療関係者を中心に広く知られる存在です。
今回のセミナーのテーマは「心臓弁膜症」。高齢化にともない患者さんが増加しているにもかかわらず、正しく診断されずに見逃されている実情を渡辺先生は問題視しています。循環器を専門にする医師のみならず、地域のかかりつけ医として多くの患者さんと関わる一般内科や総合診療科の医師、そして若手の研修医にこそこの実情を知ってもらい、患者さんを注意深く見て心臓弁膜症を発見してほしい、と渡辺先生はいいます。
かつて弁膜症といえば、リウマチ性によるものが大多数を占めていました。抗菌薬の普及によりリウマチ熱が減ったことで、弁膜症は「いつかなくなる病気」だと考えられていた時期もあったそうです。しかし、超高齢社会を迎えた日本では、心不全の患者さんが増加しています。心不全の原因のひとつとされる心臓弁膜症も増加傾向にあり、推計患者数は200~300万人ともいわれています。高齢者の心臓弁膜症にはその年代だからこそ気を付けるべき点があると渡辺先生は指摘します。
「活動量が落ちることによって、予見される自覚症状がないことも多い。だからといって、症状が顕在化するまで待っていれば、患者さんのリスクを高めるだけ。すでに症状が出ている人はもちろん、疑いがある人を見極めることが大切です」(渡辺先生、以下同)
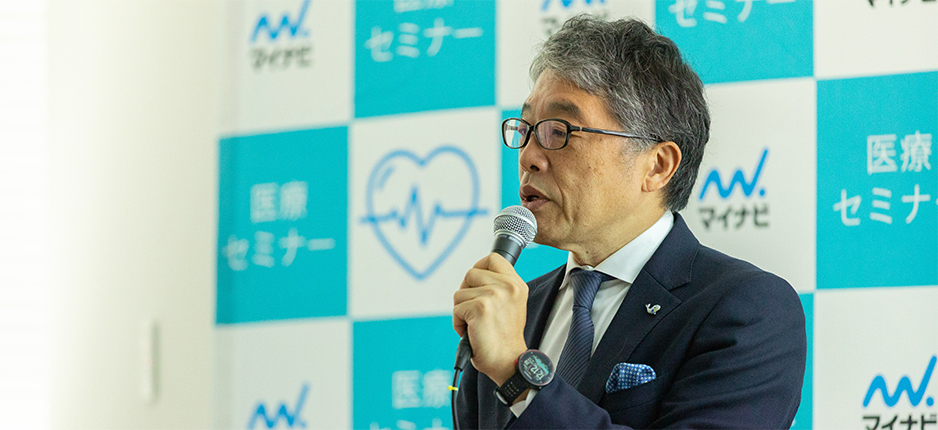
弁膜症の診断に用いられる「NYHA心機能分類」では、日常的な身体機能に関する自覚症状を確認することで、Ⅰ~Ⅳ度のレベルに分けて心機能の状態を表します。しかし、患者さん本人はⅣ度(非常に悪い:安静にしていても症状がある状態)になってから初めて自覚症状を訴えることが多く、また家族もⅣ度程度にならないと患者さんの異変に気が付くことができないというのが現状です。弁膜症の代表的な症状は、動悸、激しい息切れ、極度の疲れやすさですが、加齢による体力の低下と似ていることも、異常を自覚しにくい一因だと渡辺先生は指摘します。また高齢の患者さんは他の疾患をすでに発症しているケースも少なくありません。
「多くの場合、弁膜症は単独ではやってきません。実際、弁膜症手術を行うとき、およそ44%の事例で他の治療を同時に行っているのです」
他に発症している病気がないかを問診で確認することも重要ですが、問診や病歴だけに頼らず、身体所見を通して多角的に評価しなければならないと渡辺先生は強調しました。
身体所見&心エコーにより総合的な判断を
では、高齢の患者さんをどのように診察すればいいのでしょうか。渡辺先生は、「身体所見は1分でとる」ことを推奨しています。具体的な身体所見とは、視診、触診、聴診の3つ。例えば患者さんの脈を測る時は、脈の強弱や左右差、不整脈の有無などはもちろん、手の温度にも注目するべきだといいます。そして身体所見を通して違和感のあった患者さんはすぐに心エコーで確認するという流れです。
「手がいつも冷たい人の中には、低拍出の人が一定数いるので、少なくとも高齢の患者さんに対しては、こういった身体所見を必ずとるよう習慣付けることが大切。弁膜症の所見があれば、すぐに専門医につなげてほしい。スピーディーな身体診察と手軽な心エコーなら、日々の診療でも無理なく実施できるはずです」
またアメリカの心臓弁膜症治療ガイドライン(米国心臓病学会)の改訂内容(2017年)にも触れながら、弁膜症治療の今後についての解説もされました。
「生体弁か機械弁か、開胸手術が可能かといった点の判断材料として、新たな指針が出てきています。特に、これまで手術が難しかった患者さんにTAVI(経カテーテル大動脈弁治療)を適用するケースが増えており、予後も良好というデータが少なくありません」
体格も体質も異なる日本人にそのまま適合させる可能性は低いでしょうが、アメリカのガイドライン改訂を受けて、日本でもTAVIの適用範囲が変わっていくのか、その動向にも注目が集まります。

チーム医療実現のために、職種を越えた学びを
心臓弁膜症の例からもわかるように、今後専門分野の垣根を超えた医師同士の連携が重要となります。高齢患者さんは複数の疾患を併発するケースが多いため、自身の専門分野のみならず他科の疾患や最新治療についての知識のアップデートが求められるのです。そして、チーム医療の重要性を肌で実感している渡辺先生は医師同士が連携できる場を積極的に提供しています。
「多様な課題を抱えた患者さんが多いからこそ、内科が外科を理解し、外科は内科を生かして手術に臨まないといけない。異なる診療科の医師やコメディカルからの質問に対して、『そんな基礎的なことを』と上から目線で答えるのはご法度です。東京ベイ・浦安市川医療センターのように専門性が高い医療機関では、チームで動く意識が非常に高くなっています」
渡辺先生が代表幹事を務める「東京ハートラボ」は、まさにチーム医療を推進する団体です。ここでは診療科や職種の壁を越え心臓疾患について学び合う機会がたくさんあります。教材やコンテンツが提供されるだけでなく、テーマを変えたイベントも定期的に開催されています。11月23日(土)、24日(日)に開催される東京・品川で「東京ハートラボ2019」では「感染性心内膜炎」をテーマに多種多様なプログラムが組まれています。興味のある方は東京ハートラボのホームページをチェックし参加してみてはいかがでしょうか?
わずか1時間というコンパクトな時間でありながら、心臓弁膜症・早期発見のポイントが凝縮された今回のセミナー。医師向けセミナー初の試みとして、医師のための臨床互助ツール「ヒポクラ✕マイナビ」におけるオンライン上での同時中継が行われました。セミナー会場とオンライン上で視聴した計50名ほどの医師からは「身体所見のとり方が参考になった」「マイナビの医師向けイベントには2回目の参加ですが、興味深い内容で非常によかった」などの感想が聞かれました。
今後日本においてますます増加が予測される心臓弁膜症。循環器専門の医師はもちろん、日ごろから多くの患者さんと接する内科や総合診療医の医師は積極的に知識をアップデートし、業務に役立てましょう。
<講演者プロフィール>
渡辺弘之先生[循環器内科/東京ベイ・浦安市川医療センター ハートセンター長]
1987年弘前大学医学部卒業。千葉大学にて研修。神戸市立医療センター、大阪市立大学、榊原記念病院を経て2012年より現職。日本心臓病学会、日本循環器学会に所属し、日本心臓病学会特別正会員。Fellow of American College of Cardiology、日本心エコー図学会評議員。一貫して心エコー図を通じた臨床的心臓病学を学び、かつ実践している。「エコーこそが共通言語」という思いのもと、心エコー図を広めることを自らのミッションと考える。
撮影/櫻井健司 取材・文/ナレッジリング






