新型コロナウイルス感染症の拡大にともない、オンライン診療のニーズが高まっています。今回は、オンライン診療の導入の背景やメリット・デメリット、オンライン診療を実施するにあたり知っておくべき注意点などについて詳しく解説します。
※本記事は2022年2月時点の情報にもとづいています。オンライン診療の最新情報は厚生労働省「オンライン診療に関するホームページ」でご確認ください。
- オンライン診療の拡大背景や仕組みに関心がある方。
- 感染リスクを減らしつつ医療アクセスを確保したい方。
- オンライン診療の実施条件やガイドラインを確認したい方。
目次
オンライン診療とは

新型コロナウイルス感染症の拡大にともないニーズが高まっているオンライン診療ですが、どのように導入が検討されてきたのでしょうか。オンライン診療の定義と導入の背景について見てみましょう。
1-1.「オンライン診療」の定義
オンライン診療とは、そもそもどのような診療を指すのでしょうか。
厚生労働省の「オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月)」では、オンライン診療の定義を「遠隔医療のうち、医師-患者間において、情報通信機器を通して、患者の診察及び診断を行い診断結果の伝達や処方等の診療行為を、リアルタイムにより行う行為」としています。
遠隔医療において、「情報通信機器」を用いながら「リアルタイム」で診療を行うという点が重要な特徴といえそうです。
1-2.導入の背景と現状
少子高齢化が進むなか、医師の需要が高まり現在も深刻な医師不足が続いています。とくに離島やへき地などにおける継続的な診療へのニーズは高く、そうした事情を背景として、2003年の「『情報通信機器を用いた診療(いわゆる[遠隔診療])について』の一部改正について」で、対面診療と適切に組み合わせて実施する場合は遠隔診療も差し支えないことが確認されました。
その後、2015年に「情報通信機器を用いた診療(いわゆる[遠隔診療])について」の事務連絡が発出され、それまでオンライン診療の対象とされていた「対面診療を受けることが困難である場合」の「離島、へき地の患者」があくまで例示であることが示されました。それにより、制度の上では地域によらずオンライン診療の実施が可能となりました。
しかし、2015年当時はオンライン診療による診療報酬を得るためのハードルが高く、2018年診療報酬改定によってさらに要件が厳しくなりました。そうした背景もあり、導入する施設が少ないままでした。
しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大にともない、「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」により、時限的・特例的にオンライン診療の規制も緩和されたことから、各医療機関での導入が急速に進んでいます。
「第15回オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」(令和3年5月31日開催)で使用された資料によると、電話や情報通信機器を用いた診療を実施できるとして登録した医療機関の数は、令和3年4月末の時点で16,843機関、そのうち初診から実施できるとして登録した医療機関数は7,156機関でした。また実施件数では、初診からの電話及びオンライン診療が、多い月では月間1万件近く実施されている(対象期間:令和2年4月~令和3年1月)と報告されています。
オンライン診療の時限的・特例的措置や診療報酬改定をめぐっては現在も議論が続いています。厚生労働省のホームページなどで最新情報をしながら、動向をつかんでおくことをおすすめします。
オンライン診療のメリット

オンライン診療には、どのようなメリットがあるのでしょうか。患者さん側、医師側それぞれの視点で見てみましょう。
2-1.【患者さん側のメリット】医療を受けられる機会が増える
オンライン診療は、医療を必要とする人へのアクセシビリティが確保され、最適な医療を受けられる機会が増えるのが大きなメリットです。特に、遠隔地に住んでいる慢性疾患の患者さんや特殊な疾患のために遠くの病院まで通院している患者さん、高齢者や妊婦さんなど感染リスクを避けるために外出を控えたい患者さんにとっては、移動にかかる肉体的・精神的負担が軽減されるというメリットがあります。
また、待ち時間や通院のための時間がかからなくなるため、多忙な患者さんが医療にアクセスしやすくなったり、転勤・転居の多い患者さんが継続的に医療機関に受診しやすくなったりするため、アドヒアランス向上や、治療継続率の向上が期待できます。
2-2.【医師側のメリット】患者さんの治療環境を把握しやすい
オンライン診療の場合、基本的に患者さんは自宅などのリラックスした場所からアクセスしているケースが多いでしょう。そのため、患者さんの生活環境を把握しやすいという利点があります。予約によって診療時間が設定されているため、長引くことは少なく、落ち着いた状況で診療できるのも利点です。患者さんとより深い人間関係を構築できる可能性も高まります。
2-3.【双方のメリット】感染症対策をしながら診療を進められる
医療スタッフと患者さんがともに、感染症への罹患のリスクを低減しながら診療できるのも大きな利点です。事前問診で得られた情報からスムーズに診療方針が立てられるようになり、事務的な手続きの負担が軽減されるといったメリットもあります。
オンライン診療のデメリット

一方で、デメリットもあります。ここでは、医師側のデメリットのみを紹介します。
3-1.患者さんから得られる情報が制限される
オンライン診療では、患者さんを直接見ることはできず、触診も不可能です。顔色が明確にわからないなど、得られる情報に限界があるのはデメリットといえるでしょう。また、電波状態が悪かったり、音声の不具合が生じたりすると、詳しく診察することができません。
3-2.情報通信機器、通信環境に課題が残る
オンライン診療を行うためには、医療施設と患者さんがともに、情報通信機器を準備する必要があります。さまざまな通信機器が普及したとはいえ、利用しにくいと感じる患者さんもいます。
医療施設側が通信機器に慣れていないケースもあり、特殊なアプリなどを使用すると、うまく起動できず、診察時間に影響することもあります。事前に設定した時間帯に接続ができなかった場合、再度スケジューリングを行わなければならないなど、情報通信機器の取り扱いや通信環境の面で課題があるのが現状です。
3-3.オンライン診療で対応できない疾患がある
オンライン診療ができる疾患や患者さんはまだ限定的です。診療科によっては、対面での診療が必須な場合もあります。厚生労働省は対象疾患の見直しや拡充を進めているものの、検査を必須とするケースや緊急のケースなど、まだまだ対面との組み合わせによって進めることが望ましいこともあるため、適切なバランスでの運用が望まれます。
3-4.施設によって診療システムが異なる
オンライン診療を導入する医療機関は、それぞれの方針により希望に合った診療システムを自由に導入できます。そのため、オンライン診療の非常勤を複数行う場合などは、それぞれの医療機関のシステムに慣れる必要があり、操作方法を学ぶ時間が必要かもしれません。設定や事前練習に時間がかかる場合、かえって業務負担が増える可能性も考えられます。
3-5.対面診療よりも診療報酬が低い
対面診療とオンライン診療では2割から3割前後の診療報酬の差が見られます(令和2年度の診療報酬改定時点)。例えば、初診料を見ると、対面診療では288点ですが、オンライン診療(特別措置)は214点(大和総研資料より)です。慢性疾患等で再診する場合の合計点を比較すると、対面診療では合計419点ですが、オンライン診療では合計289 点と3 割ほど低くなってしまいます。
再診料や処方箋料(院外処方)は同点ですが、オンライン診療への切り替えが進み、件数が増えるほど、病院経営に影響してしまうリスクがあります。
オンライン診療実施の条件

現状、オンラインでの初診や服薬指導は「新型コロナウイルス感染症が収束するまでの間」と時限的・特例的措置がとられています。基本的には、日頃から直接の対面診療を重ねているなどの「かかりつけ医」であることや、多職種間で患者さんの情報を共有でき、医師と患者さんともにオンライン診療が可能と合意した場合に限り診療できます。
また初診からオンライン診療を行う場合には、診療前相談を実施し、医師と患者さんの双方がオンライン診療が可能であると判断して合意した場合に実施できるとされています(厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針[平成30年3月、令和4年1月一部改訂]」より)。
オンライン診療に関する指針は定期的に見直されているため、厚生労働省の案内を常に確認しておく必要があるでしょう。
オンライン診療の研修について
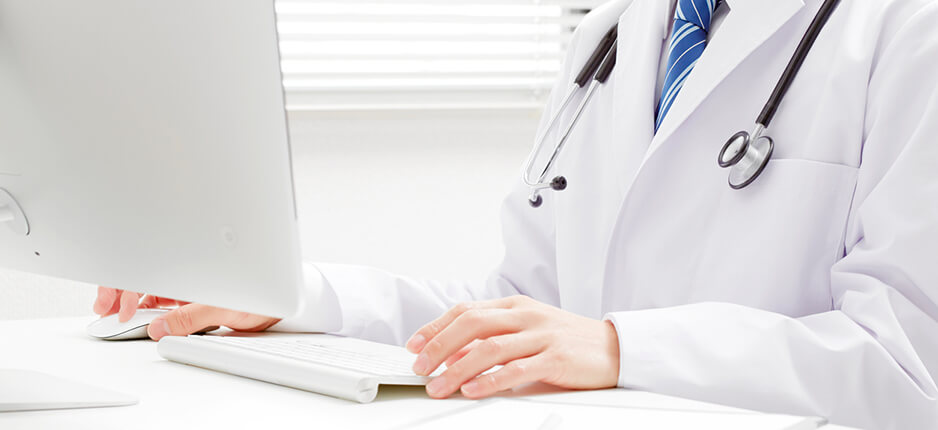
2020年4月以降、オンライン診療を実施する医師には、厚生労働省の指定する研修の受講が義務化されています。具体的な内容を見てみましょう。
研修はe-learning形式で、無料受講が可能です。厚生労働省が運営する指定のWEBサイトから申し込みます。サイト内には、「オンライン診療を行う医師向けの研修」と「緊急避妊薬の処方に関する研修」の2つがあります。令和元年7月の改定で、例外的に初診からのオンライン診療による緊急避妊薬の処方が可能となったことで、緊急避妊薬の研修も合わせて案内されていると考えられます。
それぞれのプログラムで提示される演習問題10問。全問正解で研修内容を理解したものとみなされ、合格となります。研修の具体的なプログラムは以下の内容です。
・オンライン診療の基本的理解とオンライン診療に関する諸制度
・オンライン診療の提供に当たって遵守すべき事項
・オンライン診療の提供体制
・オンライン診療とセキュリティ
・実臨床におけるオンライン診療の事例■緊急避妊薬の処方に関する研修
・経口避妊薬(OC)について理解すべき事項-各種避妊法とOC全般
・緊急避妊(Emergency Contraception:EC)
厚生労働省「オンライン診療研修・緊急避妊薬の処方に対する研修」より
オンライン診療の非常勤のニーズ拡大中

オンライン診療の普及に伴い、オンライン診療に対応する非常勤医師のニーズが拡大しています。特に保険適用のない自由診療を担う医療施設を中心に求人が増加する傾向が見られます。非常勤としてオンライン診療を希望する際に知っておきたいポイントをお伝えします。
6-1.オンライン診療の非常勤の業務内容
オンライン診療対応を主とする働き方を選択する場合、「自宅で対応」、「医療機関に出勤して対応」、「医療機関に出勤し、通常外来とオンライン診療両方に対応」の3つの方法があります。
いずれの場合も、予約を受けて、患者さんの端末に医師の側から接続することからはじめます。医師免許証などを提示して自身が診療を担う医師本人であることを証明し、患者さんの本人確認と被保険者証などの確認を済ませてから診察。必要な場合は薬を処方します。最後にオンライン診療の記録を残して業務完了です。
6-2.オンライン診療の非常勤をするメリット
ネットワーク環境が整った環境であれば、どこでもオンライン診療ができるため、働きやすさにつながります。育児や介護などと両立しながら働きたい場合や、フリーランスとして複数の業務に対応する場合など、すき間時間を上手に活用した効率よい働き方ができるでしょう。
オンライン診療は、時給単位の契約となるケースがほとんどです。対面診療と比べるとやや時給が低い傾向がありますが、複数の医療施設と契約したり、副業を兼ねたりすれば、ワークライフバランスを重視しながら、無理なく収入が確保できるのではないでしょうか。
オンライン診療の求人探しはエージェントに相談しよう
オンライン診療のニーズの拡大に伴い、診療を担う非常勤医師の求人も増加しています。非常勤としてオンライン診療に携わりたい場合は、医師専門のエージェントに相談すると好条件の求人を効率よく探せます。オンライン診療に関心のある方は、お気軽にご相談ください。
※本記事は2022年2月時点の情報にもとづいています。オンライン診療の最新情報は厚生労働省「オンライン診療に関するホームページ」でご確認ください。
参考URL
オンライン診療に関するホームページ|厚生労働省
新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関するQ&Aについて|厚生労働省
第15回オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会 資料1-2|厚生労働省
オンライン診療についての現状整理|日本医師会総合政策研究機構
オンライン診療の適切な実施に関する指針|厚生労働省
「情報通信機器を用いた診療(いわゆる『遠隔診療』)について」の一部改正について|厚生労働省医政局長通知
情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について 事務連絡(平成27年8月10日)|厚生労働省
初診からのオンライン診療が恒久化へ|大和総研
オンライン診療研修実施概要|厚生労働省
第15回検討会の議論のまとめと今後の方針|厚生労働省 資料











