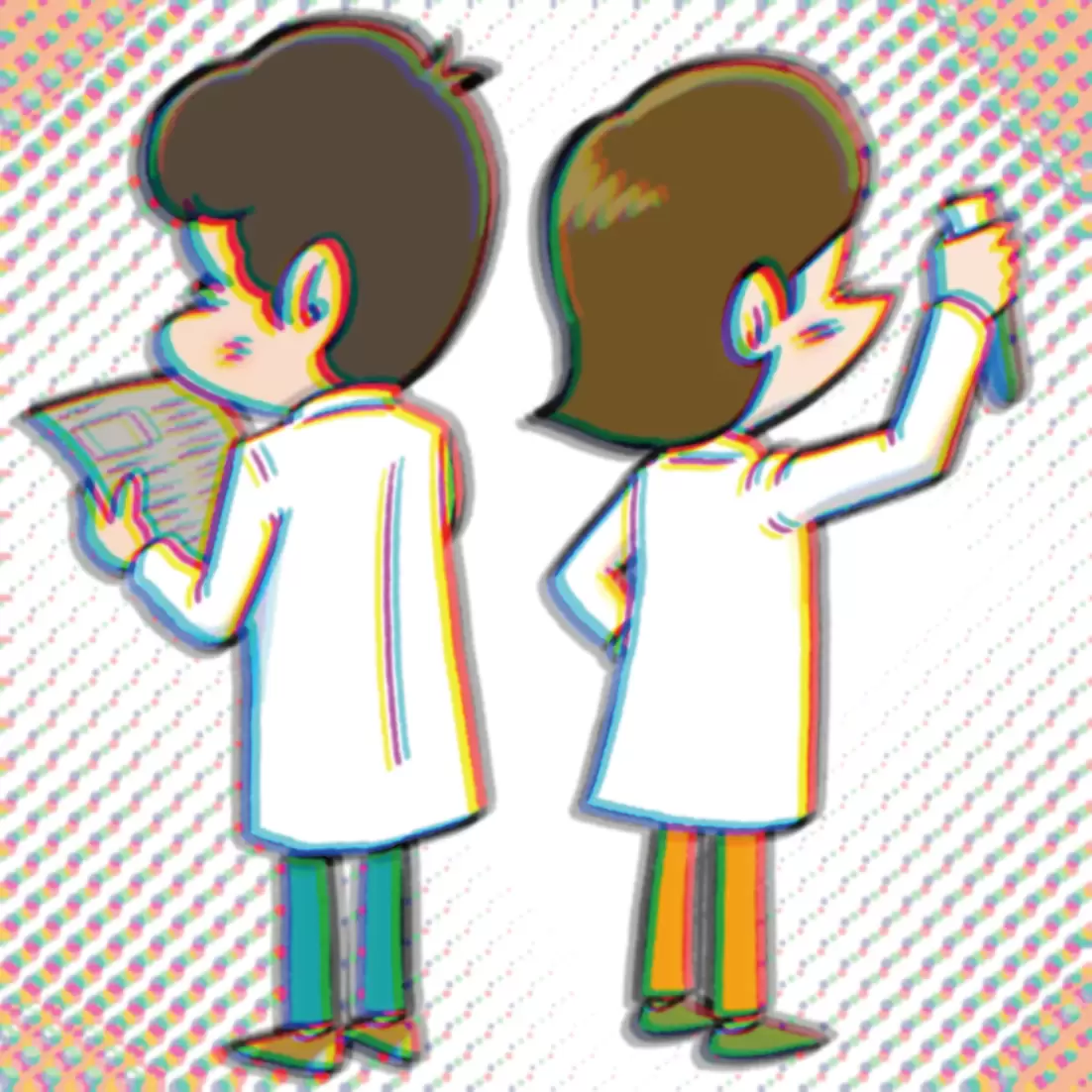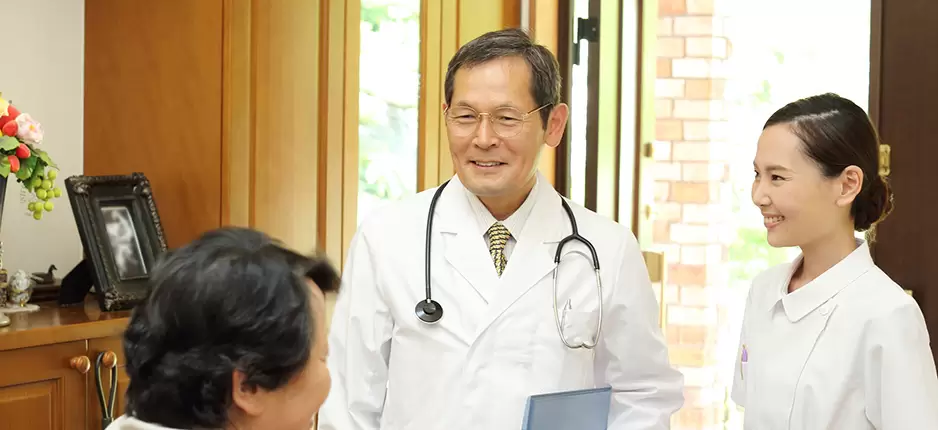この科の医師は――存在を知られていない・全医師の0.17%・超レア!?
イラスト:イケウチリリー
取材・文:マイナビRESIDENT編集部
このコーナーは元々、医学生と初期研修医に将来のことを考える材料にしてもらおうと、『マイナビRESIDENT』用に作りました。2018年に開始した新専門医制度で基本領域になった19診療科の専門医に、その科の魅力やイマイチなところ、どんな人が向いているのか、「あるある」、一日の仕事の流れ、典型的な医師像などを「ぶっちゃけ」で語ってもらった記事です。こういった他科の詳細な情報は、転科や診療領域の追加を考えている医師にとっても有益だと考え、『マイナビDOCTOR』にも掲載することにしました。
山﨑悦子(やまざき・えつこ)さんに聞きました。
インタビューを受けていただいた医師
山﨑悦子(やまざき・えつこ)医師 = 1966年生まれ
- ■所属
- 横浜労災病院(650床)血液内科部長
- ■主な資格
- 臨床検査専門医、総合内科専門医・内科指導医、血液専門医
- ■卒業大学
- 筑波大学、横浜市立大学大学院
* 医師の所属、主な資格は取材当時(2023年10~12月)
インタビュー内容
- Q1.なぜ血液内科に加え、臨床検査を専門に選んだのですか?
- Q2.臨床検査の良いところを教えてください
- Q3.臨床検査のイマイチなところはありますか?
- Q4.臨床検査専門医としての技術や知識を磨くためにやっていることはありますか?
- Q5.臨床検査は何年ぐらいで、自信を持って診療できるようになれますか?
- Q6.臨床検査に向いている人を教えてください
- 臨床検査医として病院に勤務していた時の一日の流れ
- Q7.臨床検査専門医を持っていることは開業にプラスになりますか?
- Q8.もし麻酔科がなかったら、何科を選びますか?
- Q9.臨床検査専門医の「あるある」を教えてください
- Q10.典型的な臨床検査専門医像はありますか?
- 医学生・初期研修医へのメッセージ
Q1.なぜ血液内科に加え、臨床検査を専門に選んだのですか?
きっかけは大学病院の人事でした。当時の臨床検査部の部長が退職したので、その後任として、当時所属していた血液内科から異動したんです。それで、臨床検査部の部長になったので専門医を持っていないといけないということで、日本臨床検査学会に入会して、専門医を取ったというわけです。
臨床検査は大きく二つに分けられます。血液や骨髄、尿や便といった検体から体の状態を調べる「検体検査」。もう一つが「生理機能検査」で、超音波や心電図、脳波など、直接患者に対して行う検査です。検体検査の中では、検査医が関わるものとして血液や骨髄の細胞の形態や数の異常を調べる「スメア」が一定の割合を占めます。当時の臨床検査部には、既に生理機能検査の専門の医師がいたのですが、血液や骨髄の専門家がいなかったんです。それで、病院側の意向で、私が臨床検査部長になったんです。
Q2.臨床検査の良いところを教えてください
臨床検査領域は、自分の担当患者がいません。ですから、夜中や休みの日に呼び出されることがなく、自分で仕事のタイムスケジュールの管理ができるんです。そういった点から、子育て中の医師などにはお勧めしています。実際に、私は8年間、大学病院の臨床検査部長をやり、その間に主治医になったことはありませんでした。
臨床検査専門医としての主な仕事は、臨床検査技師の指導や検査の精度管理です。それが自分の時間管理でできます。なので、研究をしたい人であればその時間は取りやすいですし、厚生労働省から依頼される仕事や外部で行う臨床研究の仕事なども引き受けることができます。私が血液を専門としているように、だいたいみんなバックボーンがあるので、それを主軸とした研究や外部の仕事をやっている人が多いですね。
Q3.臨床検査のイマイチなところはありますか?
臨床検査専門医は日本全国で約600人(2023年2月時点)しかいません。希少過ぎるので、制度としてインセンティブにできないんです。例えば、病院経営の観点から話をすると、外来患者の1検体の検査につき何点付くという「検体検査管理加算」があります。この条件の中に、「臨床検査専門医がいること」という一文がないんですね。これを入れてしまうと、管理加算を取れない病院だらけになってしまうからです。今のところ、病院にとって臨床検査専門医を雇うメリットがなく、専門医を取得した医師にも目に見える得がありません。
ただ、今はゲノム医療が進んでいます。それを支えるのが遺伝子関連検査で、その領域に臨床検査医がどんどん入っていっています。ゲノム医療を実施する場合は臨床検査専門医が必要という方向に進んでいるので、それは良い流れだと思っています。
Q4.臨床検査専門医としての技術や知識を磨くためにやっていることはありますか?
毎年開催される臨床検査医学会にちゃんと出席して、最新の情報をキャッチアップすることです。厚生労働省の方針に左右されやすい領域なので、そういったことは学会で情報収集しないと分かりませんからね。
Q5.臨床検査は何年ぐらいで、自信を持って仕事ができるようになりますか?
臨床検査領域はそれだけを専門にしている医師はほとんどいないんですよ。臨床検査医が個々にやる仕事は、自分のバックボーンに関連したことになります。私は「血液」なので骨髄を読んだり、消化器の医師なら腹部エコーの実施・読影、循環器の医師なら心電図の実施・読影というように。臨床検査専門医だから臨床検査についてオールマイティかというとそうではなく、自分のバックボーンと全然関係ないところは、やはり何年たっても分かりません。
逆にそのバックボーンがどれだけしっかりしているかによって、それに関連した臨床検査についての自信も変わってきます。1年目からバリバリ自信を持ってやれる人もいれば、何年目になっても自信を持って物を言えない人もいます。
Q6.臨床検査に向いている人、また専門医を取るとメリットのある診療科を教えてください
誰でも向いていますよ。向いていない人はいないと思います。ただ、自分で直接患者を診ることがないので、臨床がすごく好きだという人にはお勧めしないです。
「こういう人に勧めたい」というのは、育児などで臨床医を続けられないからといって離職を考えている人です。臨床検査医は休日夜間の呼び出しはほぼないし、時間調整は自分でできるので、離職せずにキャリアを築けますから。
他科で臨床検査専門医を取ると何かプラスになるかというと、あまりないと思います。ただ、臨床検査専門医の試験合格に、血液と感染症の分野がネックになる人が結構いるんです。血液の分野だと、骨髄のスメア(細胞の形態や数の異常の検査)は血液内科にとっては得意中の得意です。でも、他科の医師には、とても難易度が高いんですよ。ですから、血液内科医は臨床検査専門医試験に受かりやすいし、臨床検査医の中には血液内科の医師が多くいます。でも、臨床検査専門医を取ったから、血液内科医としてすごい強みになるかというと、そんなことはないですね。
臨床検査医として病院に勤務していた時の一日の流れ

Q7.臨床検査専門医を持っていることは開業にプラスになりますか?
プラスにはならないですね。開業するなら、何か他に専門分野がないと難しいと思います。標榜(ひょうぼう)はできます。「臨床検査専門医を持っているので、検査の結果を詳しく説明できますよ」というのを売りとして出せますが、それが大きなメリットになるかというと、そうではない気がします。
Q8.他科の医師から一目置かれるのは何科ですか?
他科の人が、どの科をどう見ているのかは分かりません。私の個人的なこと言うと、血液内科に一目置いています(笑)。ずっと血液内科を専門としてきて、とても面白い分野だと思っているんです。何でみんな血液内科に進まないのだろうと思うぐらいです。
悪性疾患の場合、内科が病気を見つけて、外科が手術で治療するという流れが多いですよね。血液内科は、白血病に関しては、診断、治療、看取(みと)りまで全部自分で行うことができるんです。この一連の流れを自分たちだけで完結できるという、そういう診療科はなかなかないですからね。
Q9.臨床検査専門医の「あるある」を教えてください
存在を知られていません(笑)。臨床検査専門医というものがあることを知っている人の方が少ないですよね。市中病院に臨床検査部専従の医師がいた時に、「あの人、何をしているんだろう? よく分からないけど病院にいるよね」という感じだと思います。臨床検査医と臨床検査技師の区別がついていない人もいるぐらいです。
Q10.典型的な臨床検査専門医像はありますか?
みんな、さまざまなバックボーンがあるので、典型像はないです。
医学生・初期研修医へのメッセージ
仕事が長続きするのは、興味があるからなんですよ。時間的に余裕がありそうで、ワーク・ライフ・バランスが実現できそうだとか、そういう理由で進路を選んでしまうと長続きしません。医師免許を取った後1~2年ですぐに、出産や育児や介護で時間がなくなることは通常はないと思います。なので、まず5年ぐらいは自分の興味のあることを一生懸命やってみたらいいのではないでしょうか。それで、本当に時間が足りなくなったら、その時に専門の変更を考えればいいんです。そういう場合には、臨床検査領域は良いアイデアです(笑)。
ただし、いきなり臨床検査専門医になることはお勧めしません。臨床検査専門医になるのであれば、何かバックボーンがあって、それに立脚してやった方が絶対にいいからです。どの領域でもいいので、まずはそこをきちんと学び、身に付けるべきだと思います。