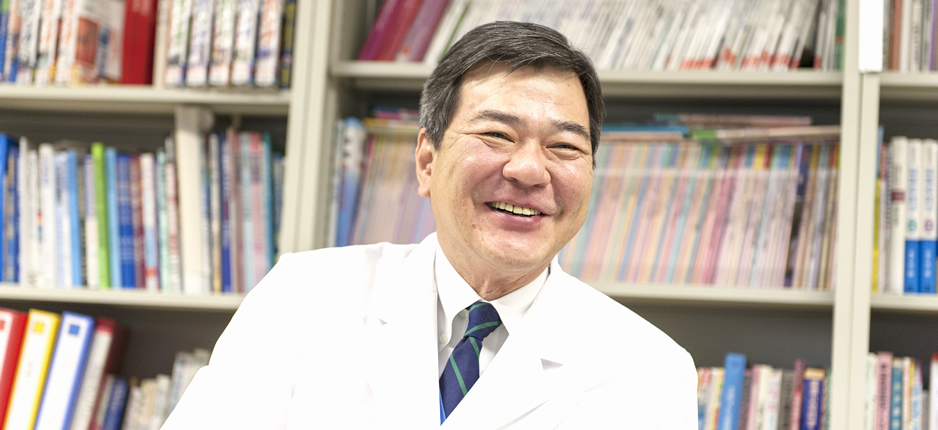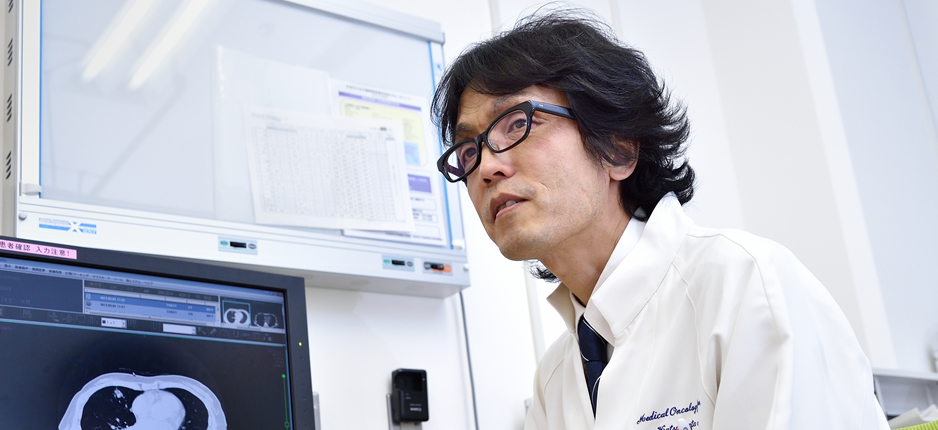すべての人に死は訪れる
ほんのわずかな偶然が生死を分けることを
ヒマラヤ登山が教えてくれた
◆生と死との間をさまよう

がん医療の第一線で、患者の生に寄り添いながら、チャレンジを続けてきた荒井さん。その間には、自らも九死に一生を得た体験がある。その一つはヒマラヤ登山中に雪崩に巻き込まれたことだ。
山岳部に在籍した高校時代から続けている登山は本格的な趣味で、幾度か危険な思いもしてきた。ヒマラヤにも2度挑戦したが、その2度目、1983年の遠征隊でナンガパルパット(8125m)の第1次アタック隊として7200m付近を登っている時、大雪崩に遭遇した。700mほども流され、2000m以上も落差のある絶壁(ルパール壁)の手前で偶然止まった。右手を骨折しながら、再びいつ雪崩が起きるかわからない壁を降りて生還したが、テントで同宿し、当日の朝食も一緒に取った仲間は行方不明となった。25年が経った今も遺体は見つかっていない。
そしてもう一つの体験は、愛知がんセンター勤務時代。肝動注用のカテーテル・リザーバー留置術中に誤って自身に針を刺してしまい、B型肝炎を発症、GOT、GPTの高値から劇症化が疑われた。幸い1カ月の入院で回復したが、一時は「これは助からない」と確信し、「死ぬのなら生まれ故郷の東京に帰りたい」と病院を脱走することばかり考えていたという。
「自分の体験を踏まえて、愛着を感じる土地って大事だな、と強く思います。がんが治るなら、きちんと治した方が良いし、延命できるなら、もちろん、それも悪くない。でもある一線を越えた時、誰がどう治療しても結果はもう変わらないという状況が訪れます。そうなった時、限りある時間をいかに心地よく過ごすかという点で考えると、主治医がその病気のスペシャリストである必要は必ずしもない。むしろ古くからのかかりつけの医師で、家庭の状況まで知っているような信頼関係がある先生が身近にいてくれた方が、患者さんはハッピーかもしれない」
がんにならなくても、またまったくの健康体であっても、ほんのわずかな偶然が人の生と死を分ける。ヒマラヤで、そして自身の勤める病院で、命の危機を体験したことは、荒井さんがどういう死に方をするかを常に考えるきっかけになった。
◆「死生観」を持つ習慣を普及させたい

荒井さんは医師になってまもなく40年を迎える。その間に、日本のがん患者人口は2.5倍以上増加した。がん医療技術は飛躍的な進歩を遂げたものの、その半面、大きな課題が生じていると感じている。
「現在のがん医療には、莫大な費用がかかっています。医療への要求も非常に高くなっています。もちろん、それは当然でもあり、決して悪いこととは言えません。しかし、高齢化が進み、逆三角形の人口構成となった日本では、今後は労働力も経済成長も厳しい状況におかれる。その兼ね合いを考えた場合に、がん医療にどこまで費用を投じるべきなのか……」。荒井さんの問題意識は「いかに死ぬか」という点にある。いわばどんな「死生観」を持つかという問いかけだ。そのことに日本人は「無頓着なことが多い」と感じている。一案として、荒井さんは最近、臓器提供の意思表示のように、生命の危険が迫っていることが判明した時点で、延命のための高額な医療は拒否するという意思表明ツールを作ってはどうかと考えている。
「人は誰でも死にます。その時自分はどこで死にたいか。病院か、自宅か、大自然の中か……。どんな風に死にたいか。本来、皆が考えなければいけないことであり、それぞれに答えをもっているはずなのです。しかし、今の日本人は死に直面する土壇場になってバタバタと慌てているのが現実です。病気になる前から、死生観をもつ習慣を日本の文化的風土の中に加えていきたい。私も65歳になりました。そろそろこういうことを話しはじめてもいいだろうと思っているところです」
小澤征爾をうならせたソプラノからビートルズへ ――
趣味の域を超えた音楽生活
登山と並ぶ荒井さんの趣味が音楽。それも登山と同様、これを趣味の範疇と言っていいものか……という凝りようだ。そのキャリアと思い出を語ってもらった。
× × ×
音楽を始めたのは声変わり前の小学生時代。ボーイソプラノで、合唱団に所属していました。全国の演奏旅行にも行き、また、声変わり直前の中学1年のころは、大人に混じって子役のような形で歌ってもいました。小澤征爾さんのオネゲル作「火刑台上のジャンヌ・ダルク」日本初演の時に、子役の部分をソロで歌わせて頂いたのはいい思い出です。国立がん研究センター中央病院の病院長時代に小澤さんが母校の成城学園のOBの方々とボランティアで病院に来て下さったことがあり、ご挨拶をしたのですが、「50年前に小澤さんの指揮で歌わせて頂いたことがあります」と申し上げると、「おー、あの時の子役かあ」と覚えておられ、うれしかったことがありました。
大学在学中はロックバンドをずっとやっていました。世代から、根底にはビートルズへの傾倒があったように思います。担当はベースギターとボーカル。これは人並みの学生時代のバンド活動です。
医師になってからは、音楽から離れていたのですが、愛知県がんセンターを離れる前くらいに、ピアノを弾きながらビートルズソングを歌うようになりました。ピアノは習ったこともなく、譜面も読めないので苦労していますが、レパートリーは10曲くらいでしょうか。

定年間近となった昨秋にひょんなことで、ビートルズを演奏するプロのバンドの方々と知り合い、以後、時々ジャムをさせていただいています。今年2月の私の退任記念パーティーは、彼らと組んで、ライブパーティーにしてしまいました。私はベースでHello Goodbye、ピアノとボーカルでLady Madonna、Hey Judeなど4曲をやりました。退任記念パーティーはつまらない、という定番の認識をぶち壊そうと企画をしたのですが、お越しいただいた方々には結構楽しんで頂けたようです。400人の出席者が最後までほとんど帰らなかったと、会場のホテルの人に驚かれました。


2015年4月、フランス・ニースで開かれたECIO(欧州腫瘍IVR学会)でhonorary lectureを受賞し、講演を行った。講演タイトルは「Beyond the evidence – the true goal of interventional oncology」。ECIOで欧州出身者以外が表彰されたのはこの時が初めてだという。

2014年、国立がん研究センター中央病院の院長時代。
=この項の写真提供・荒井保明さん